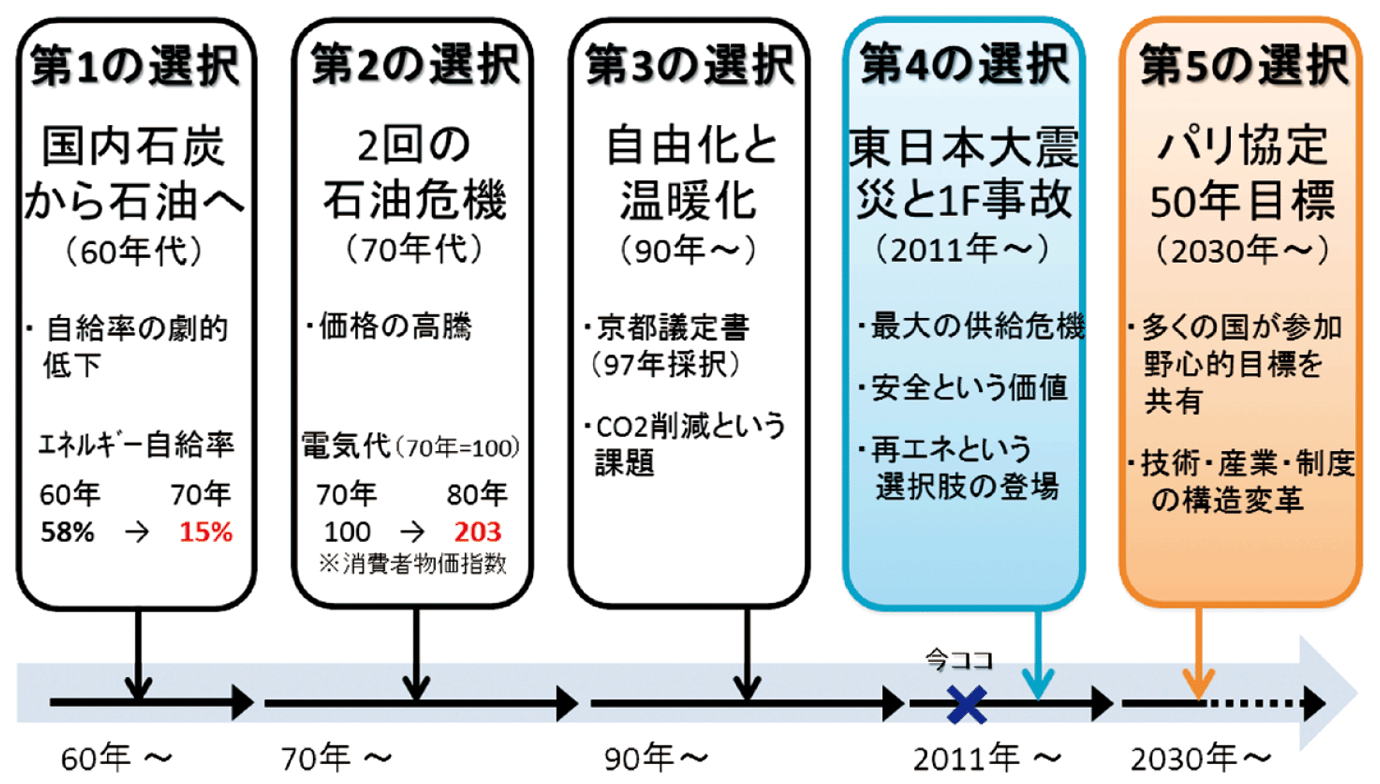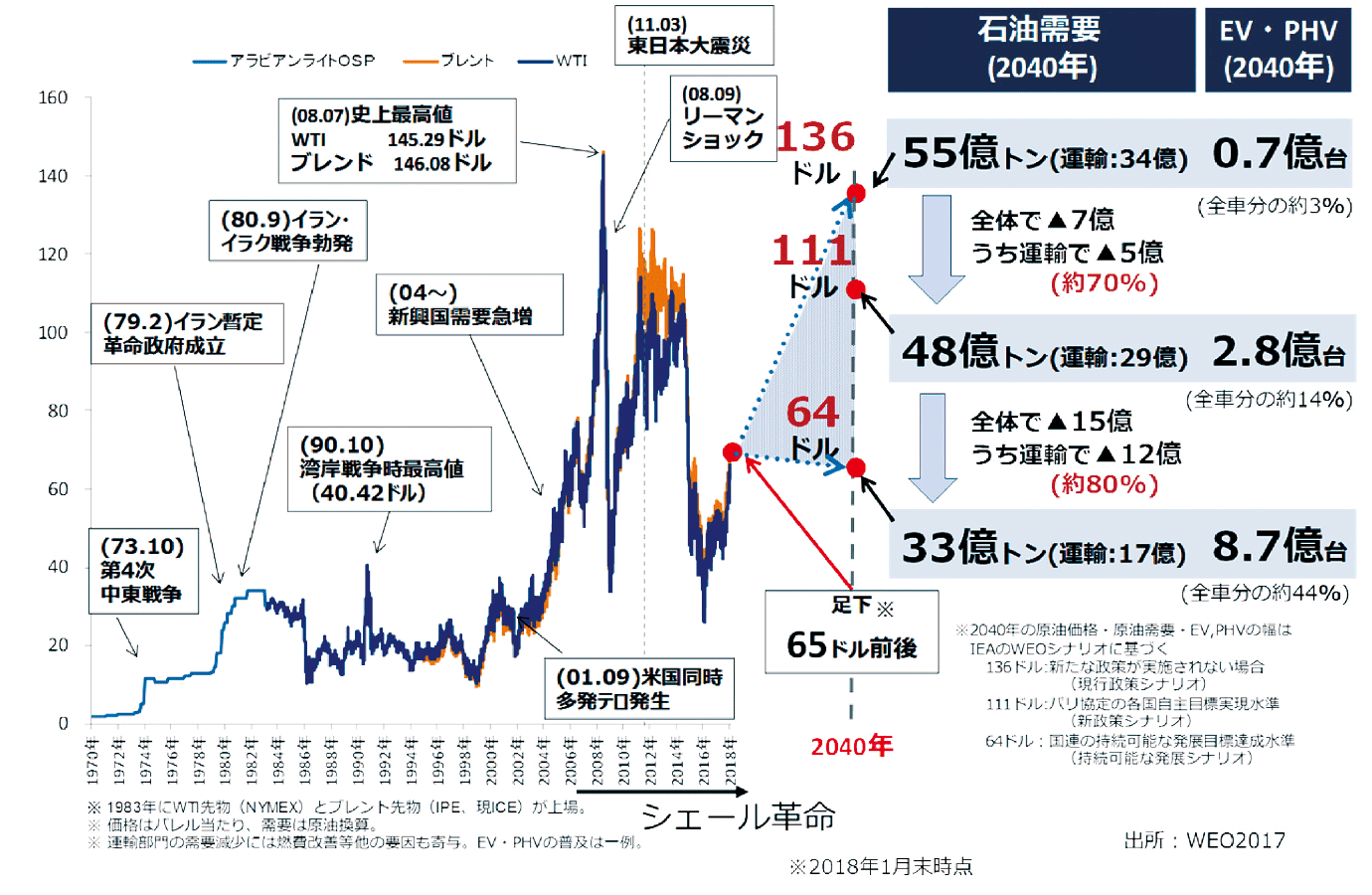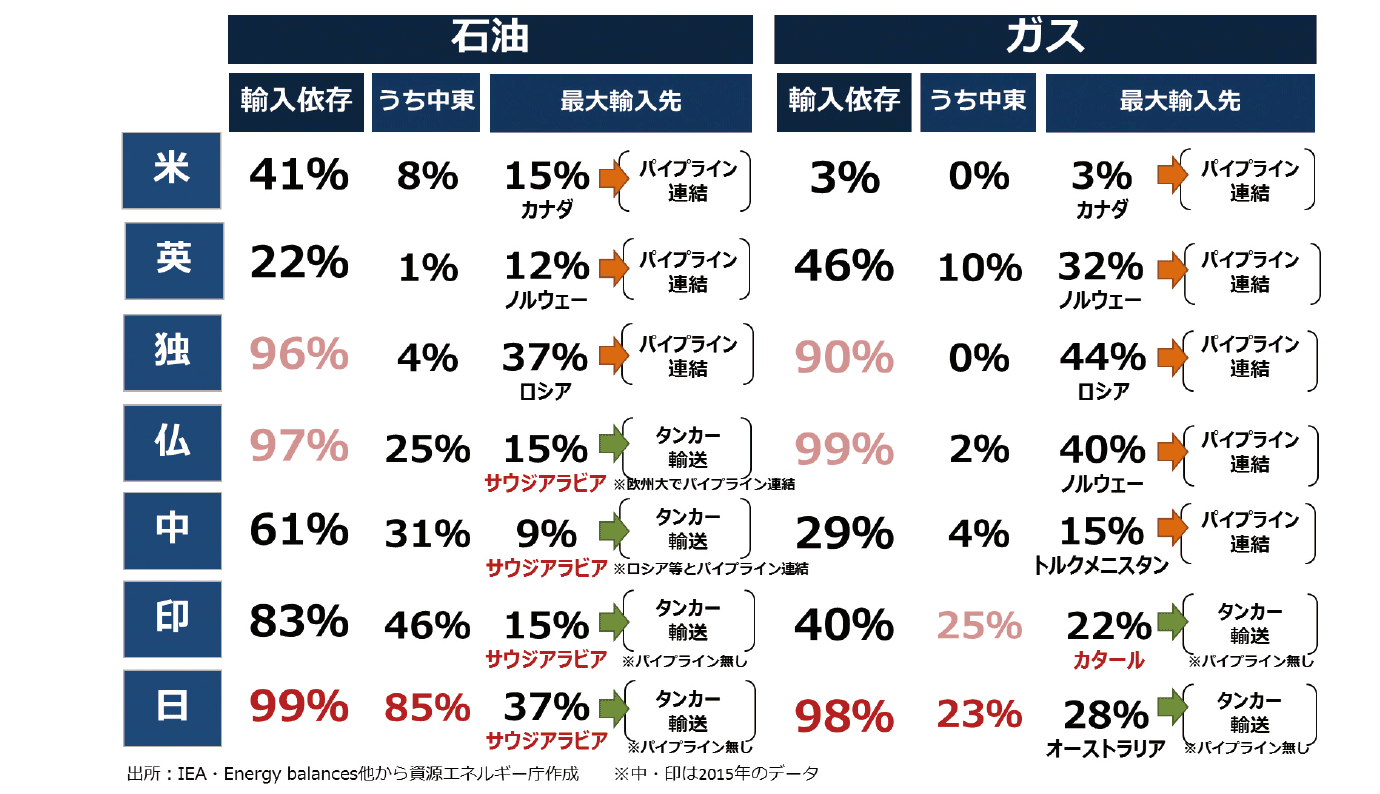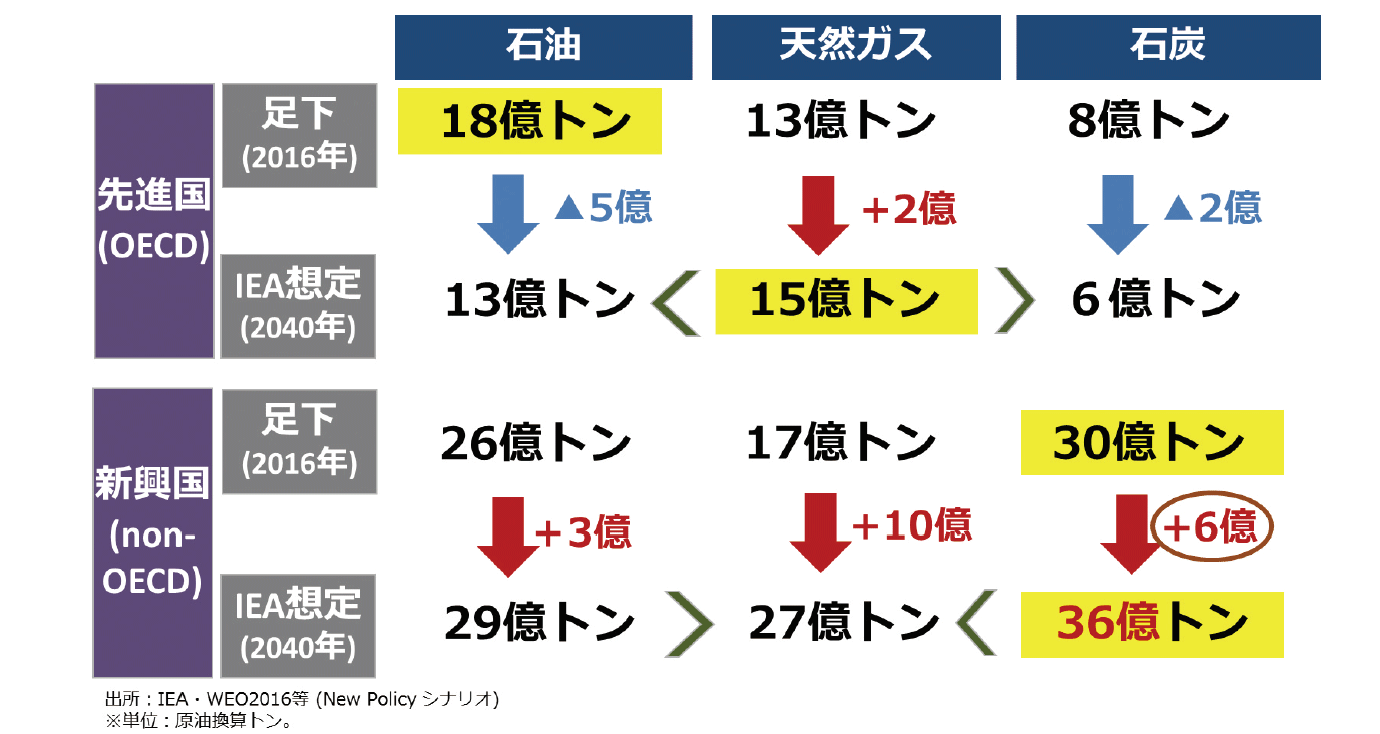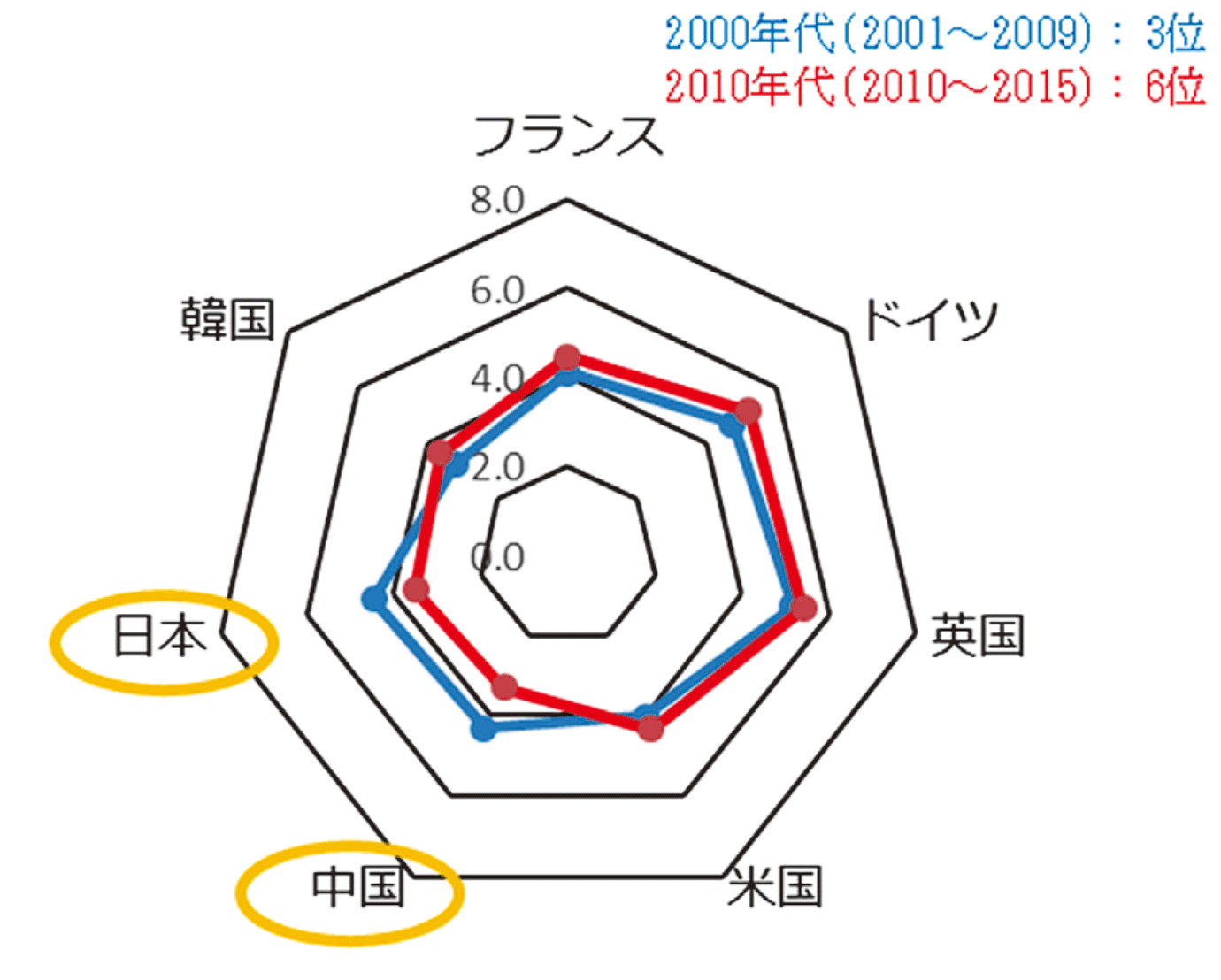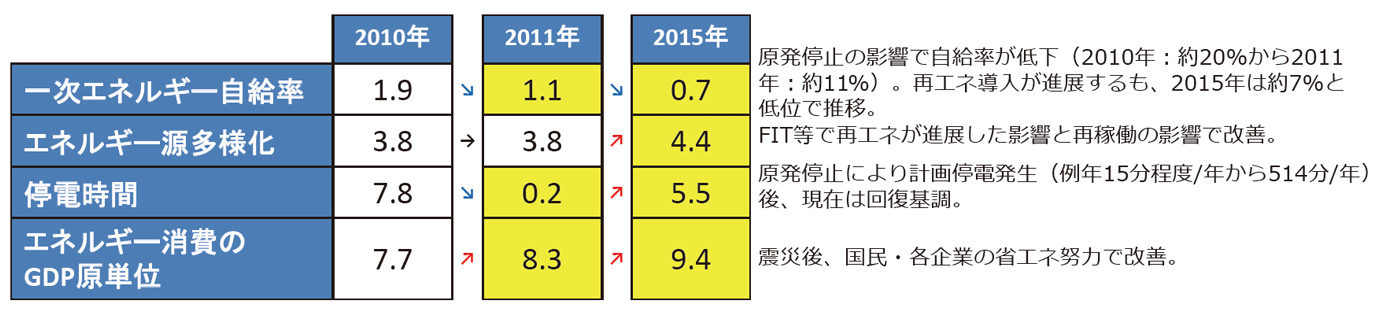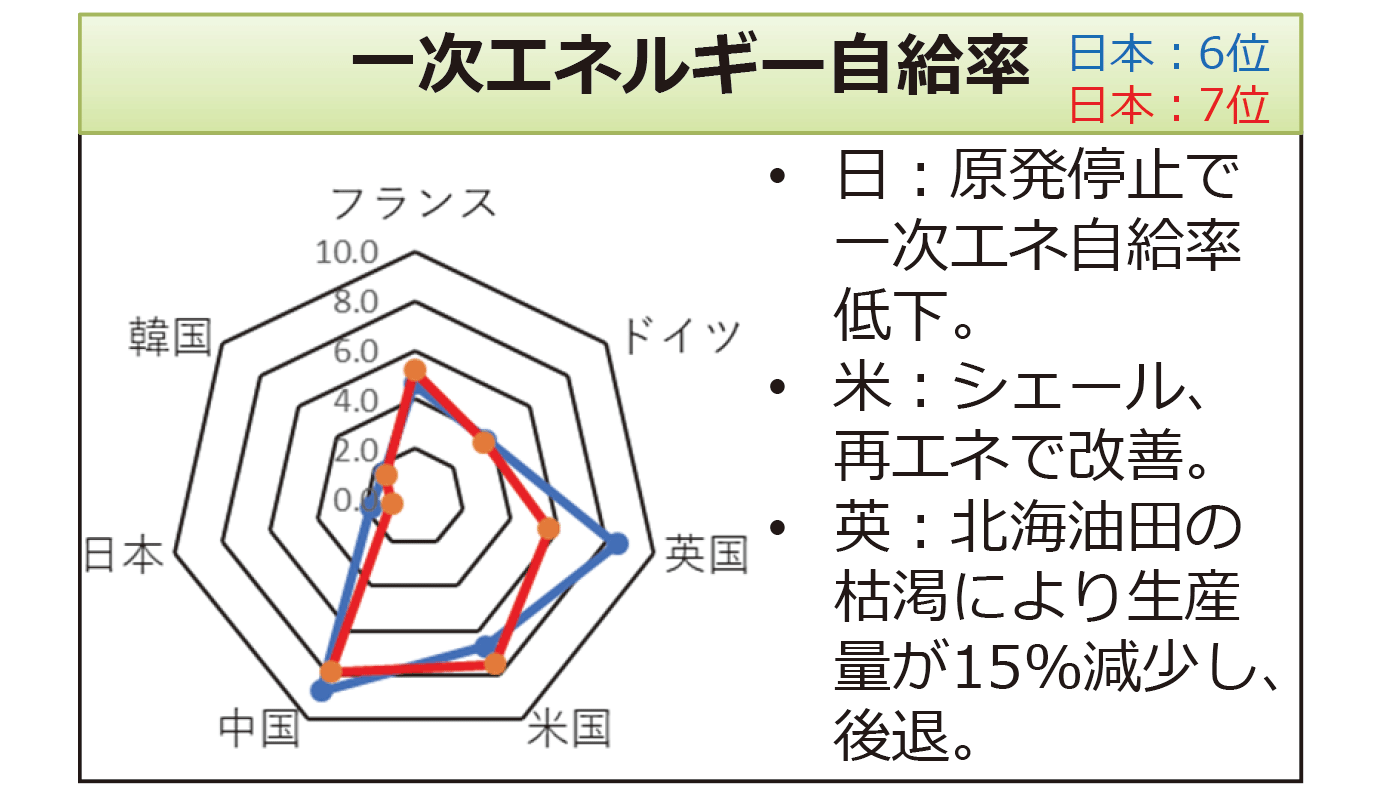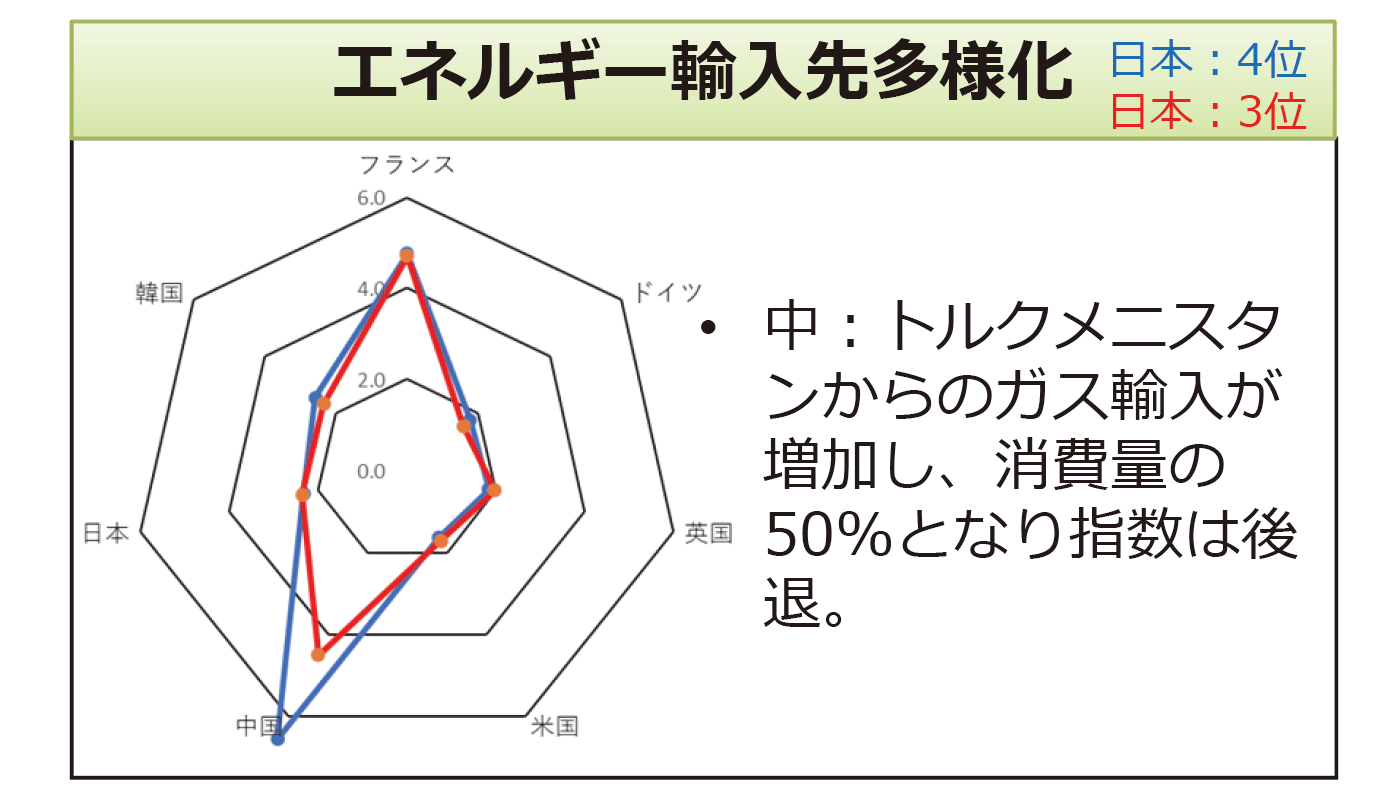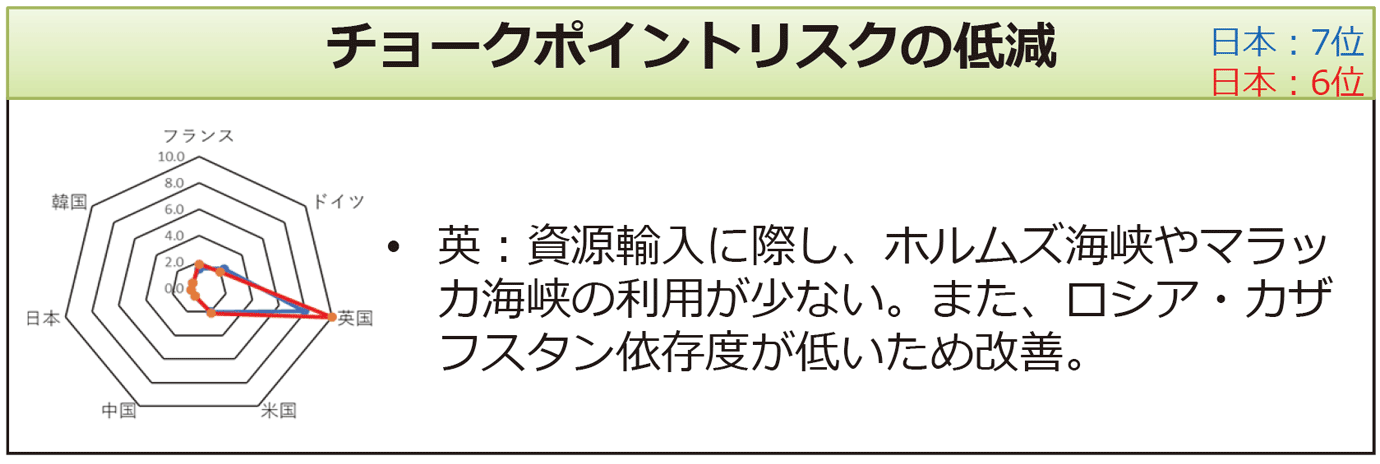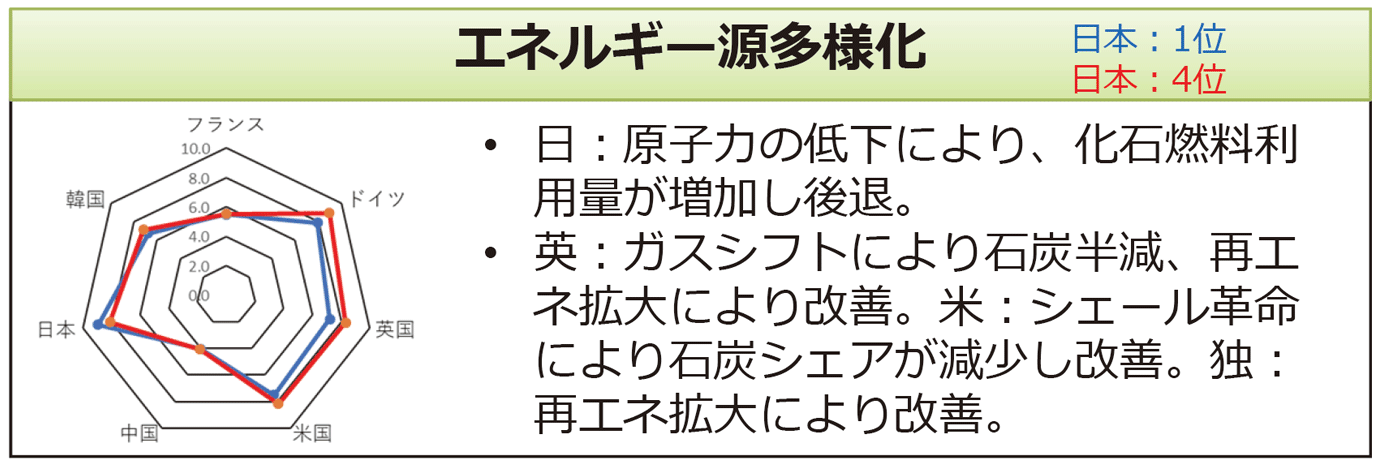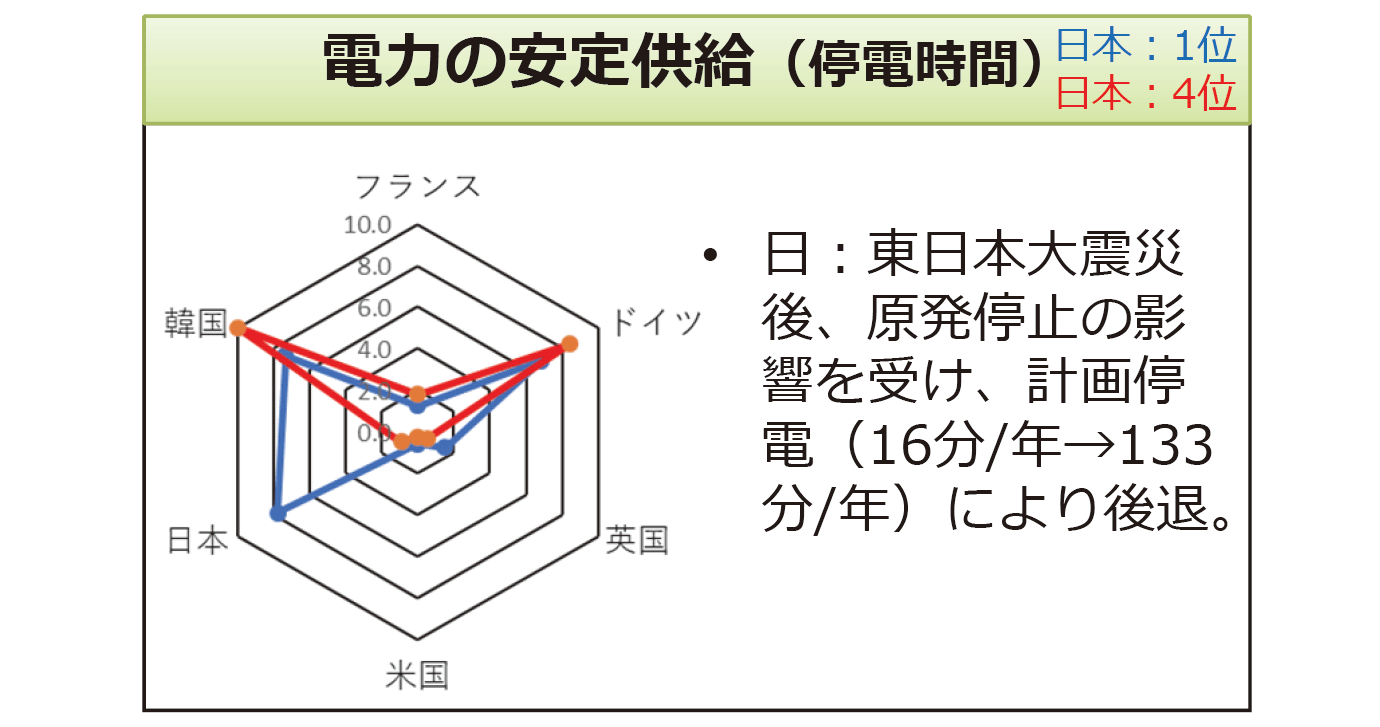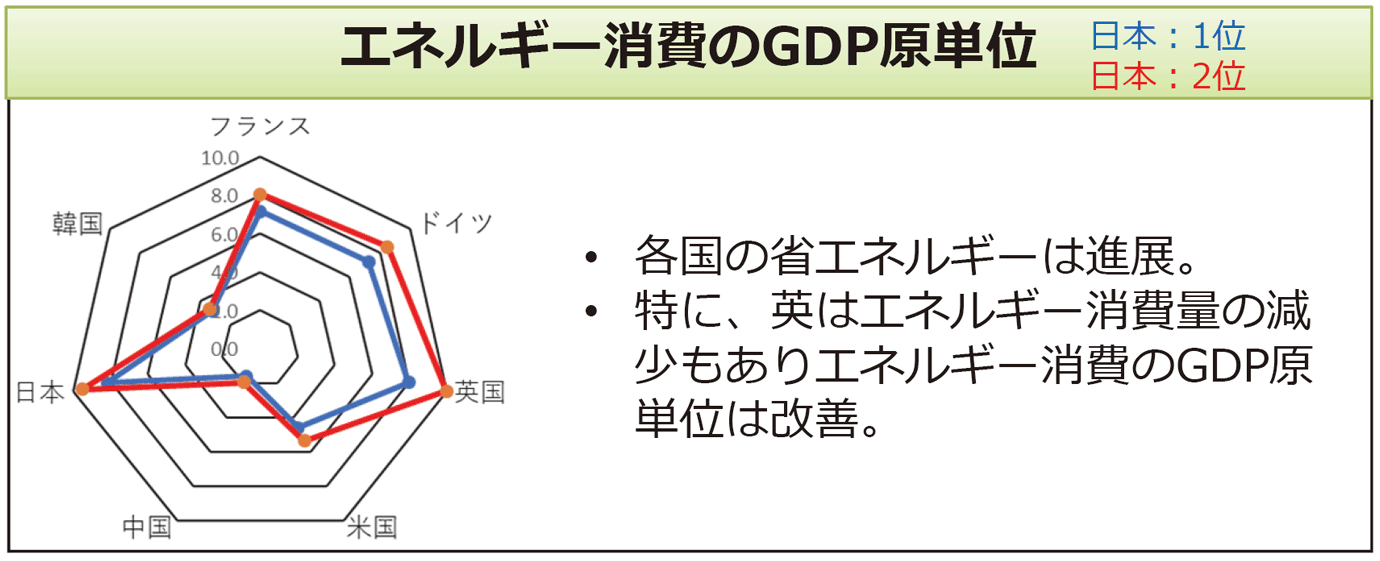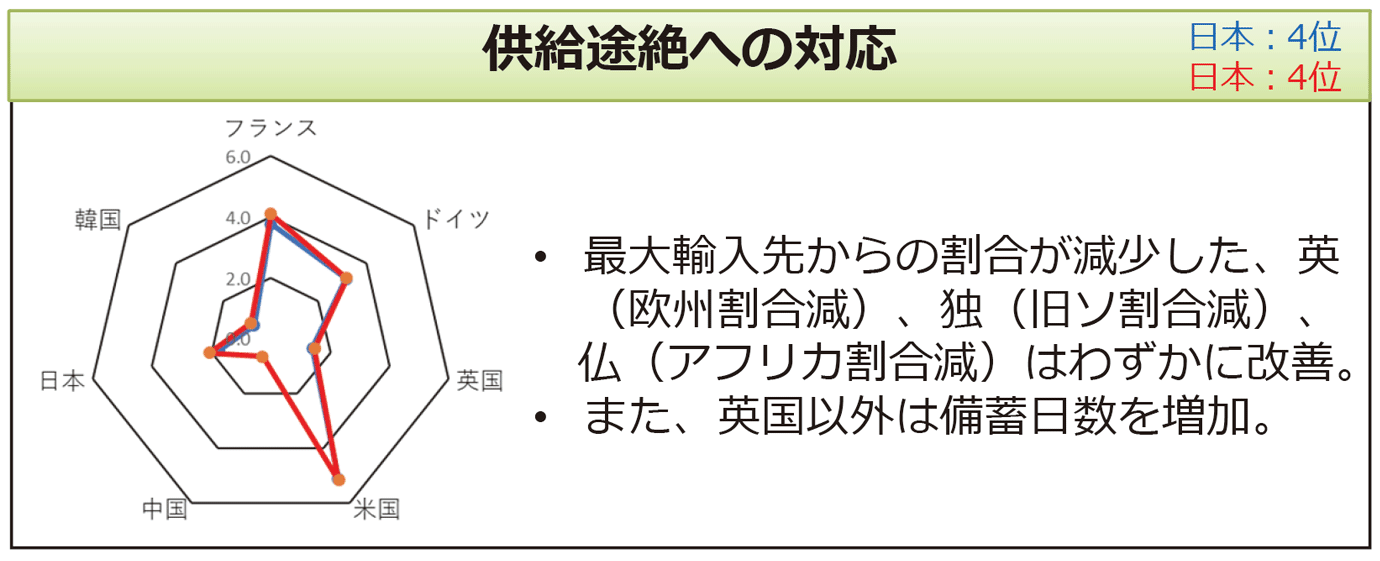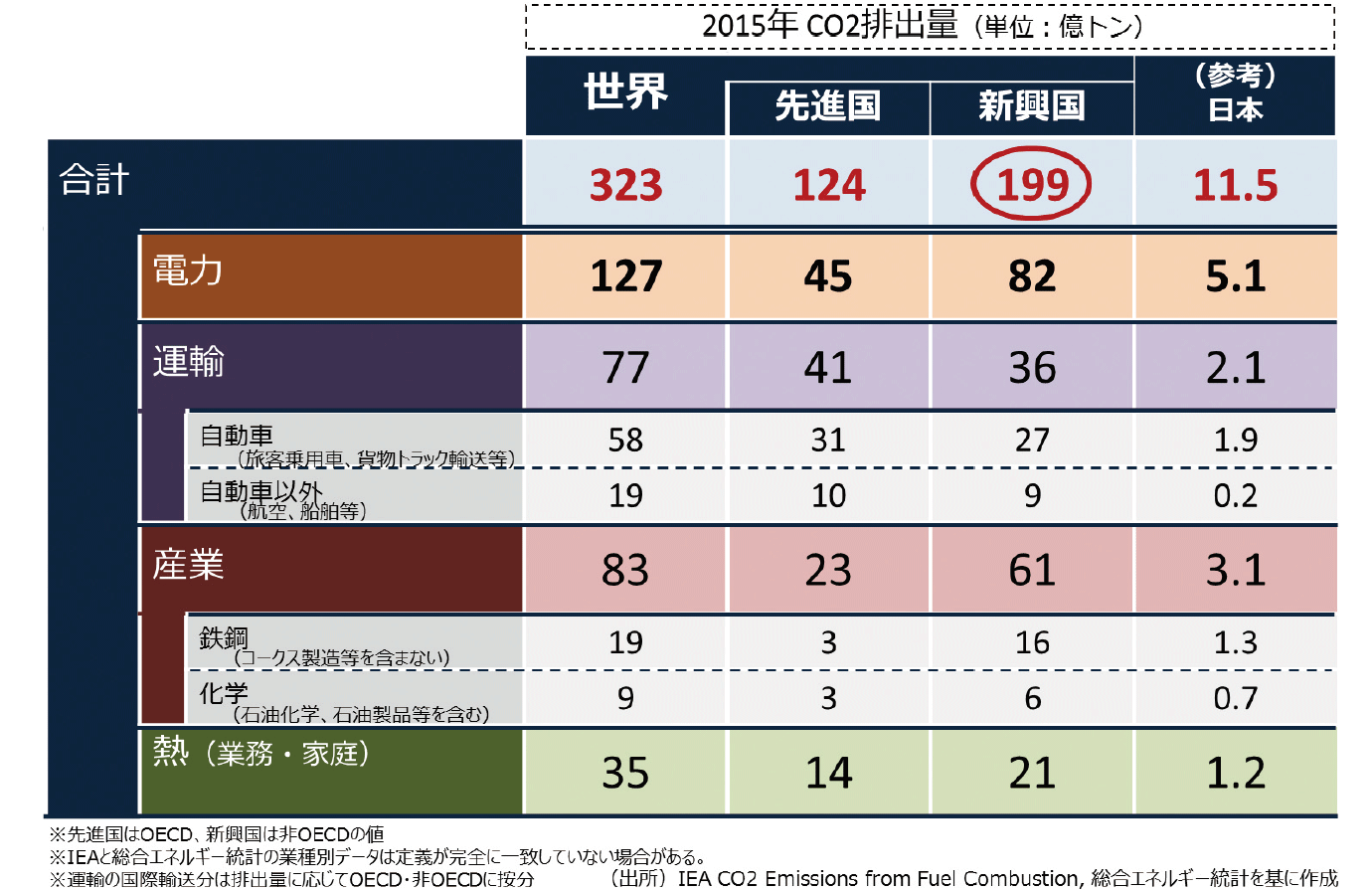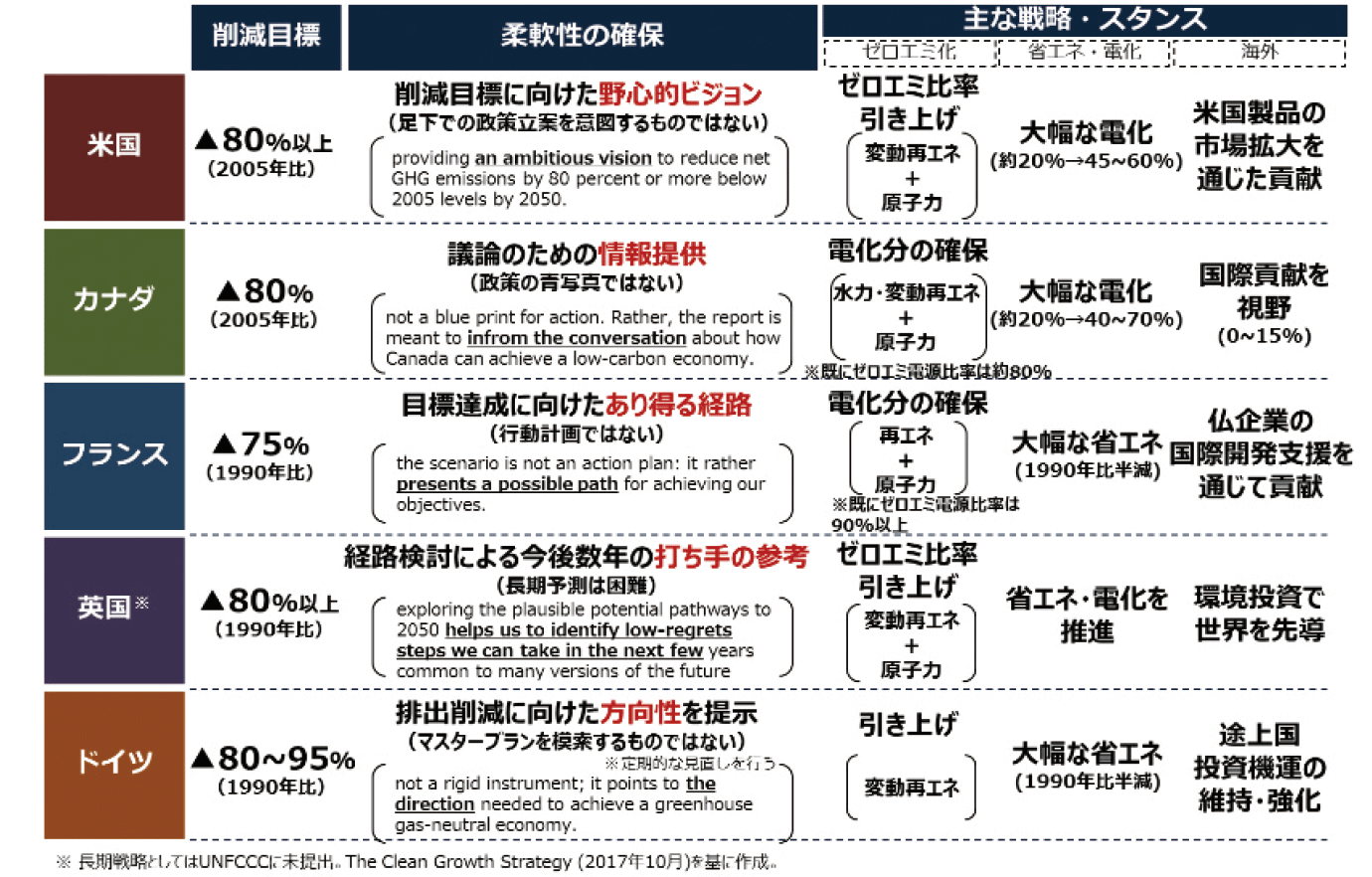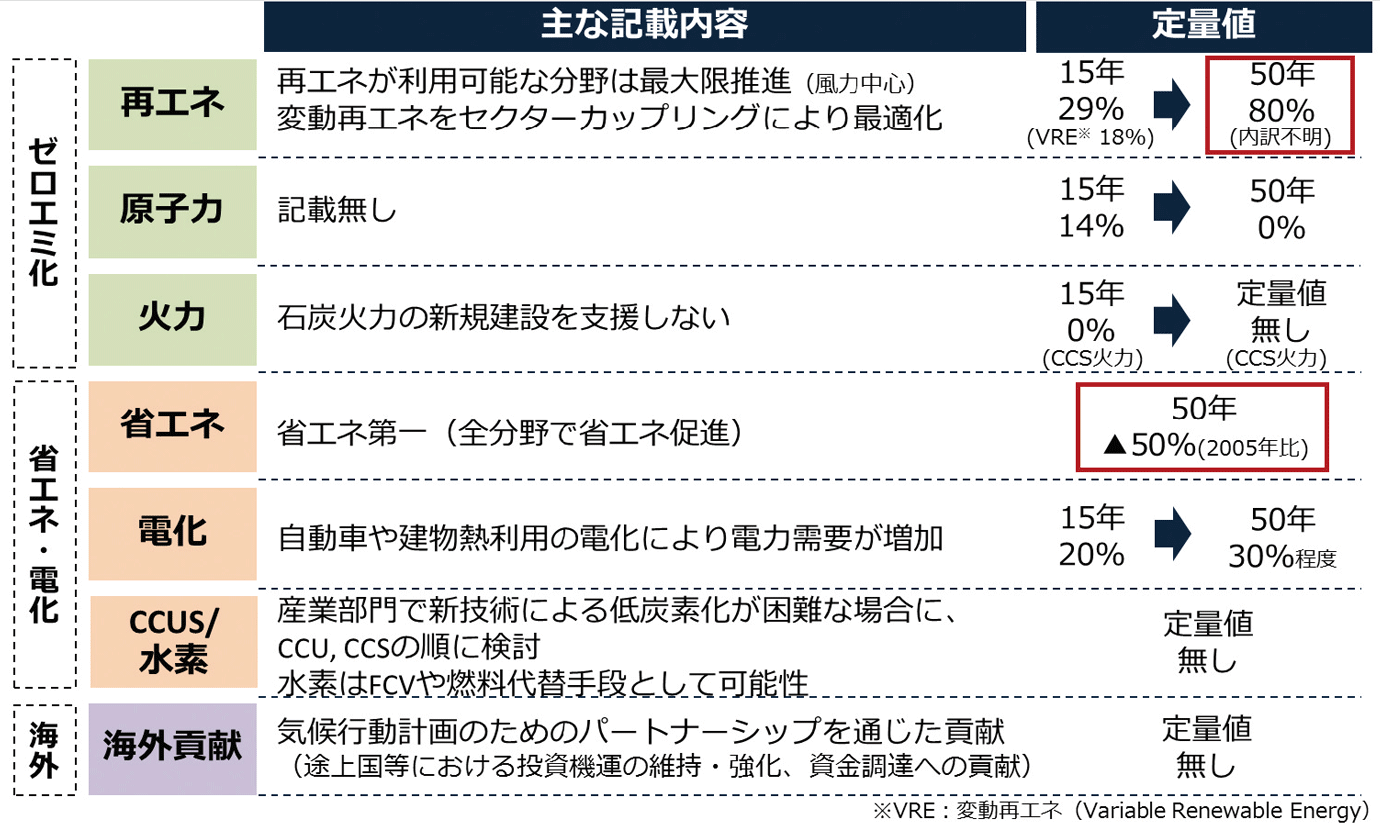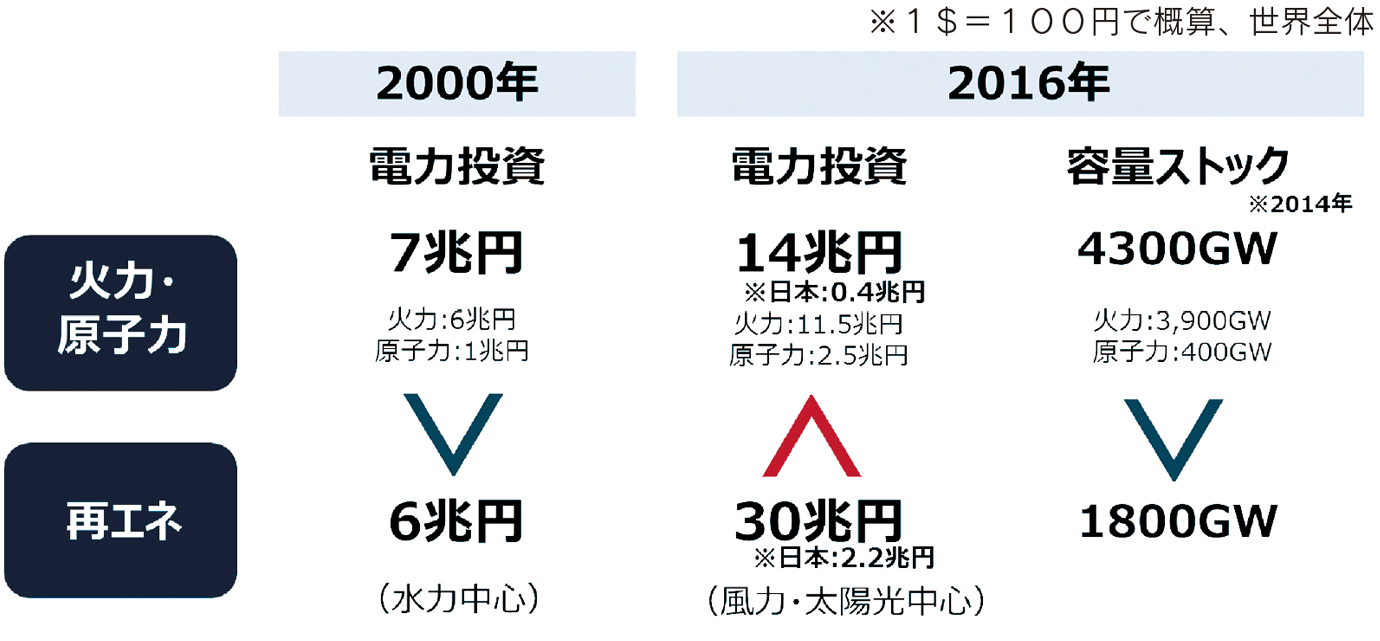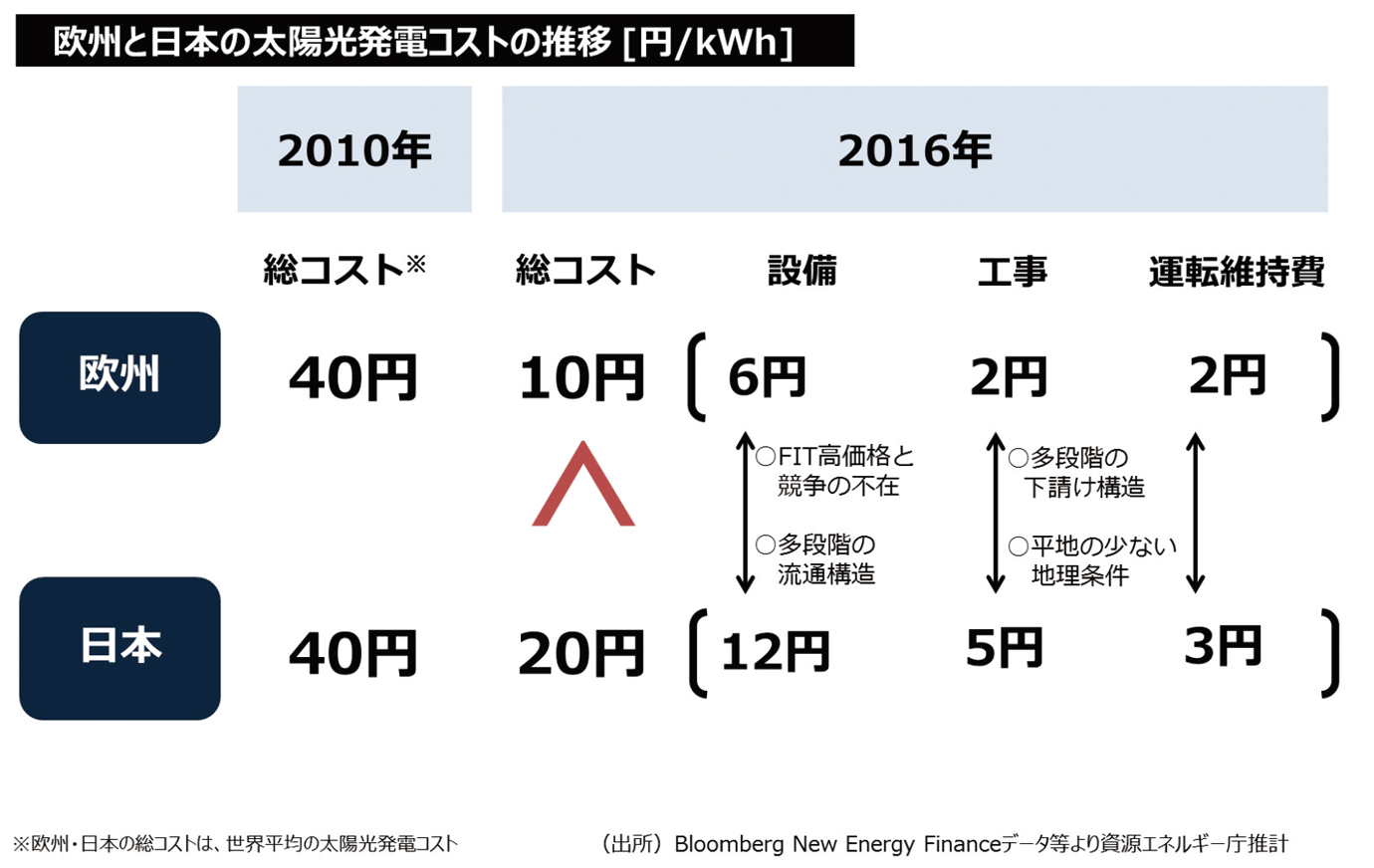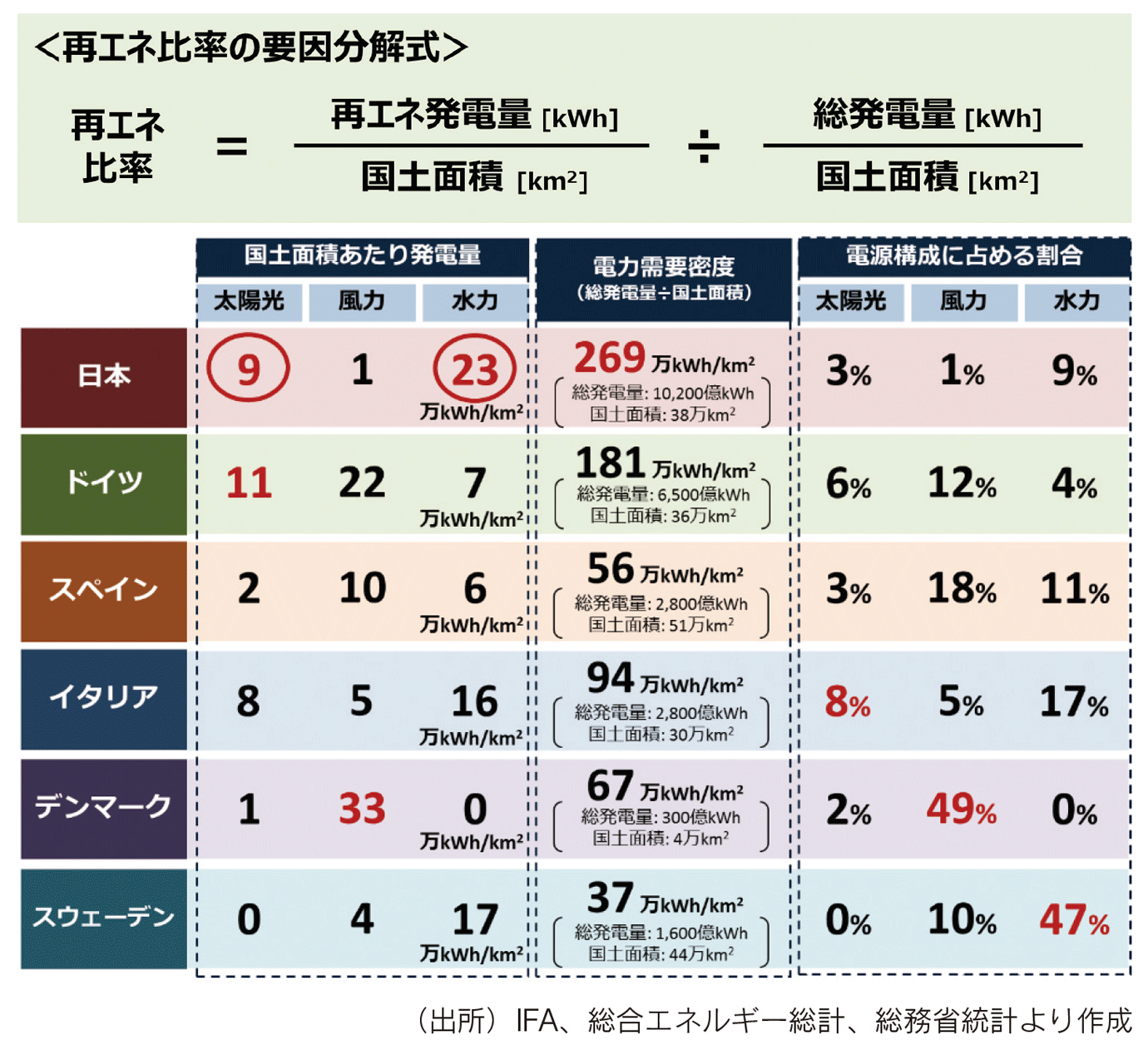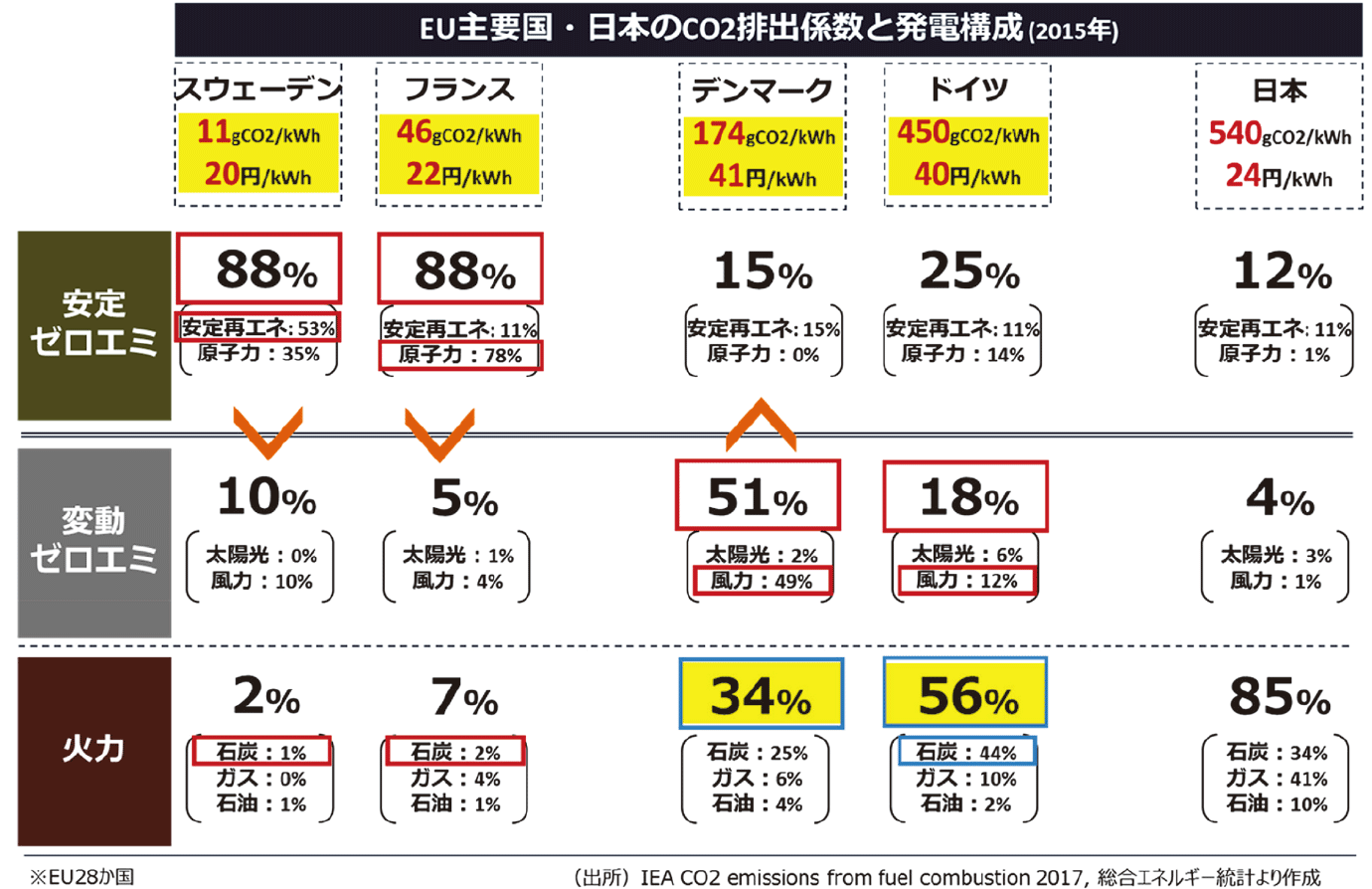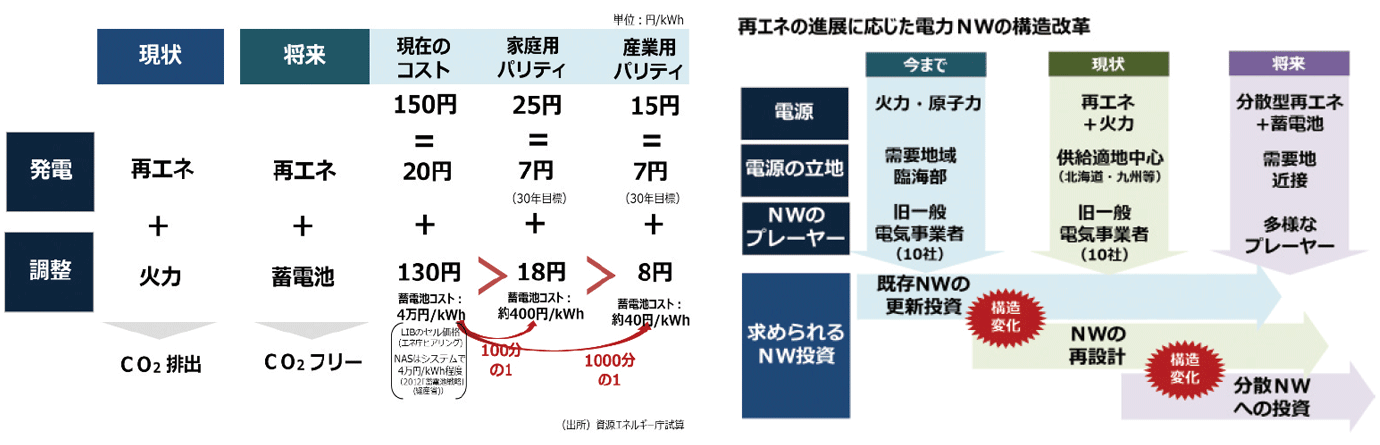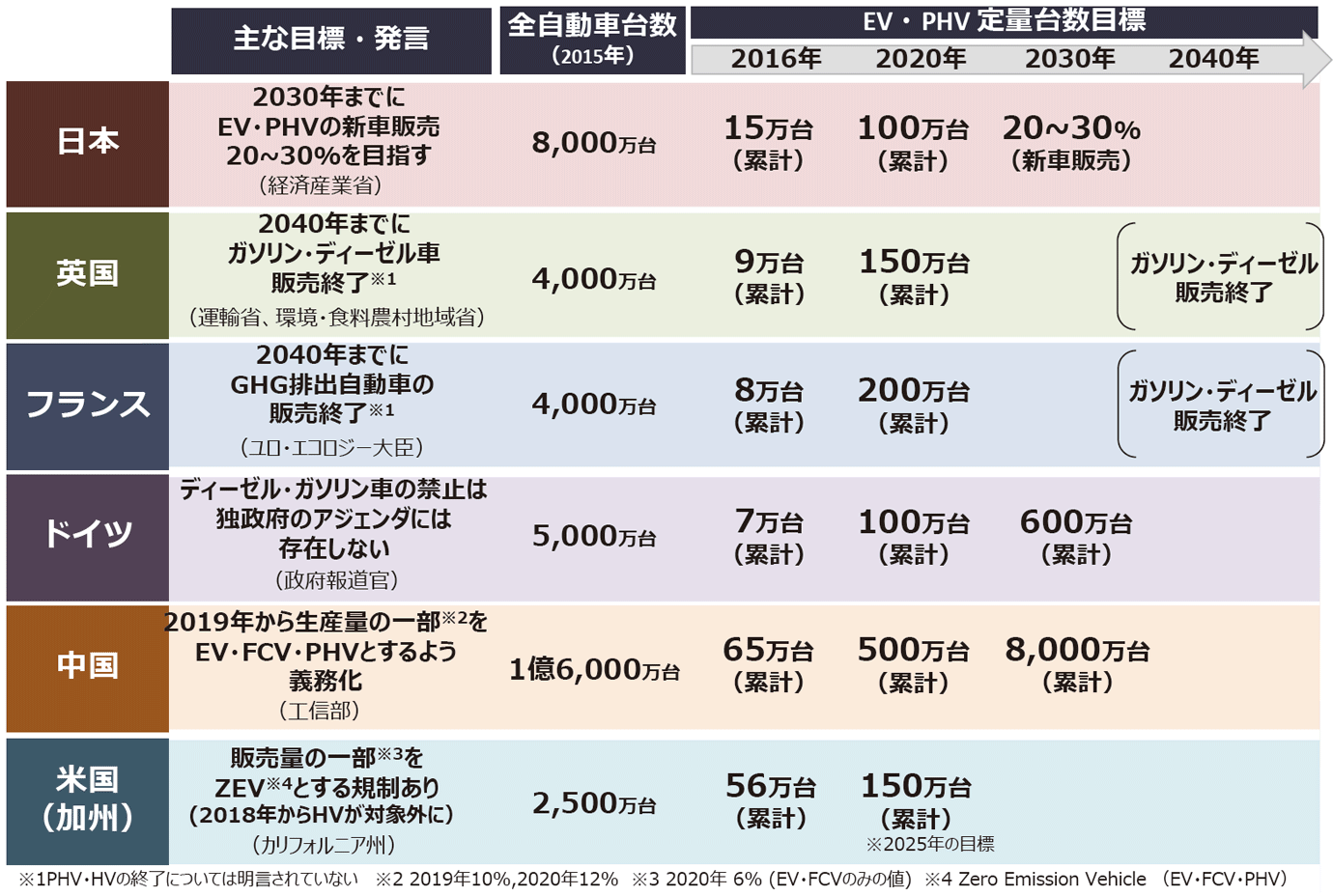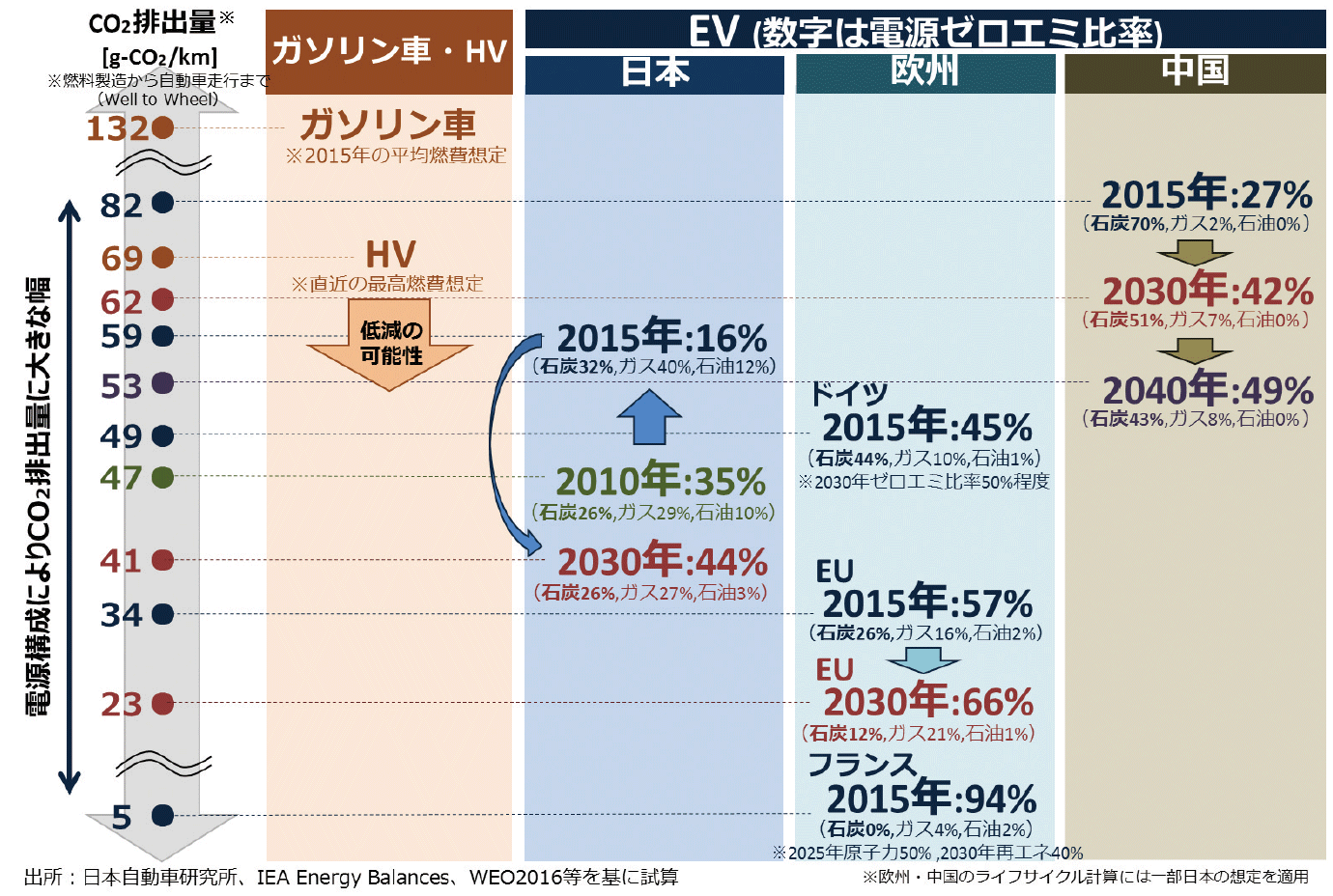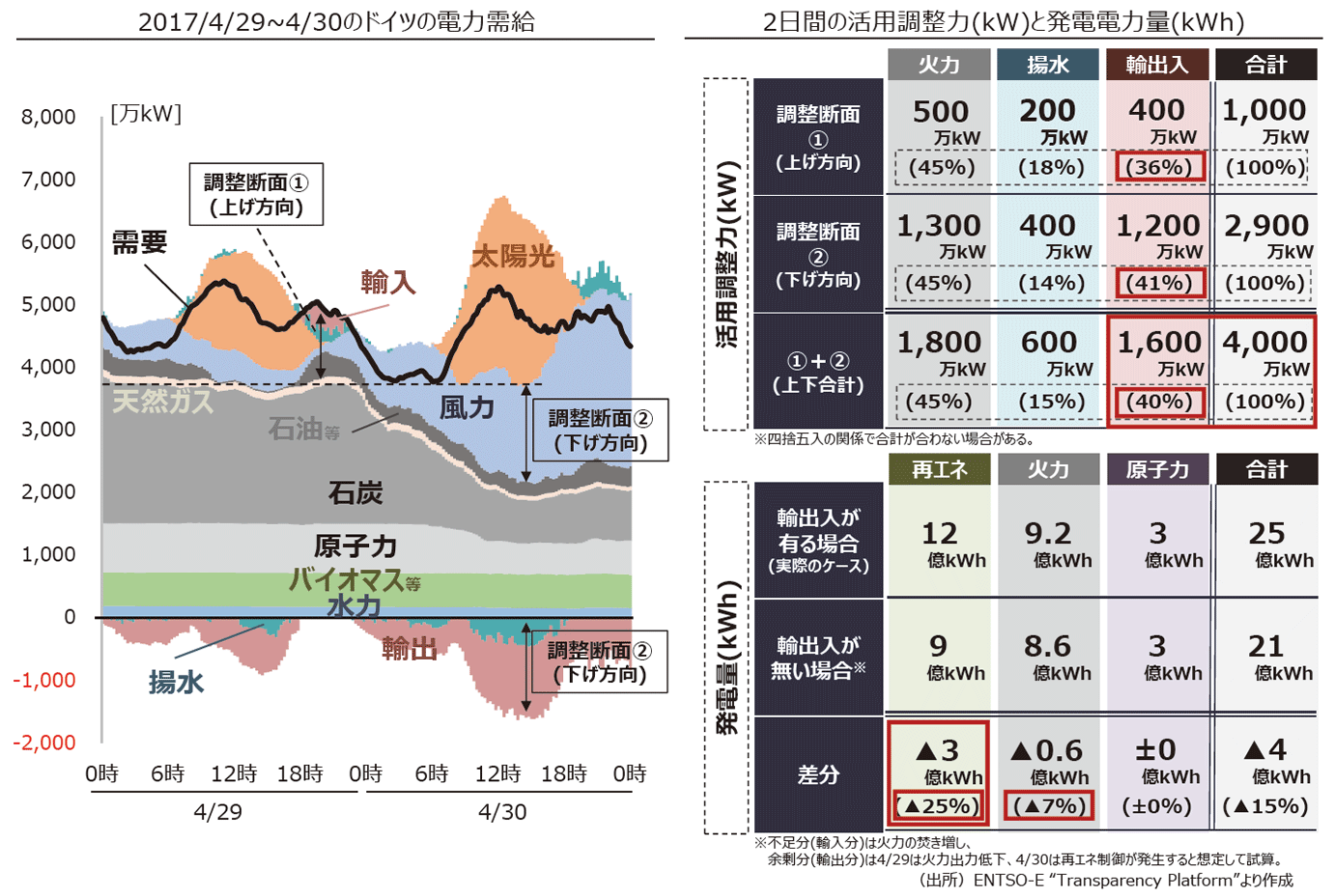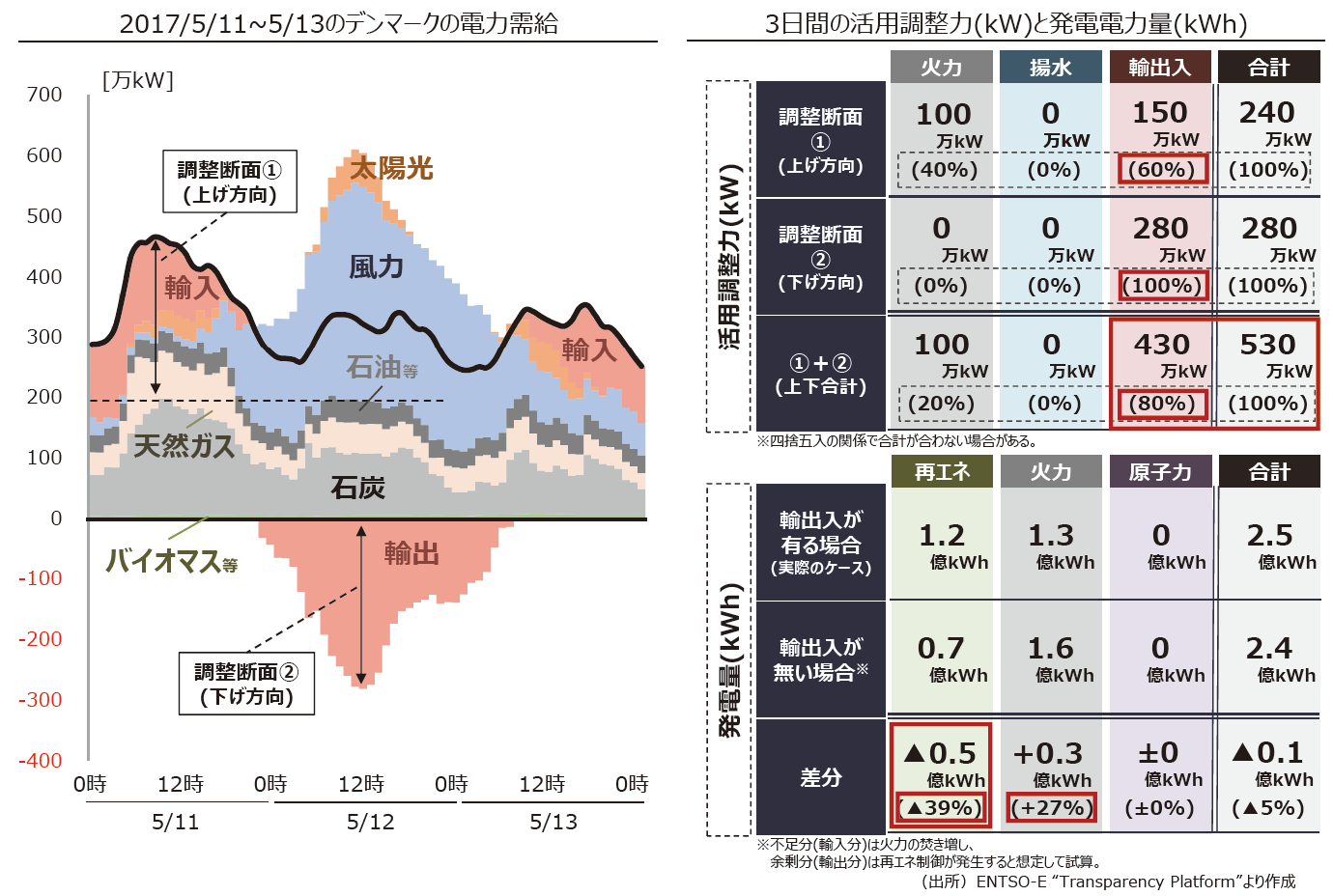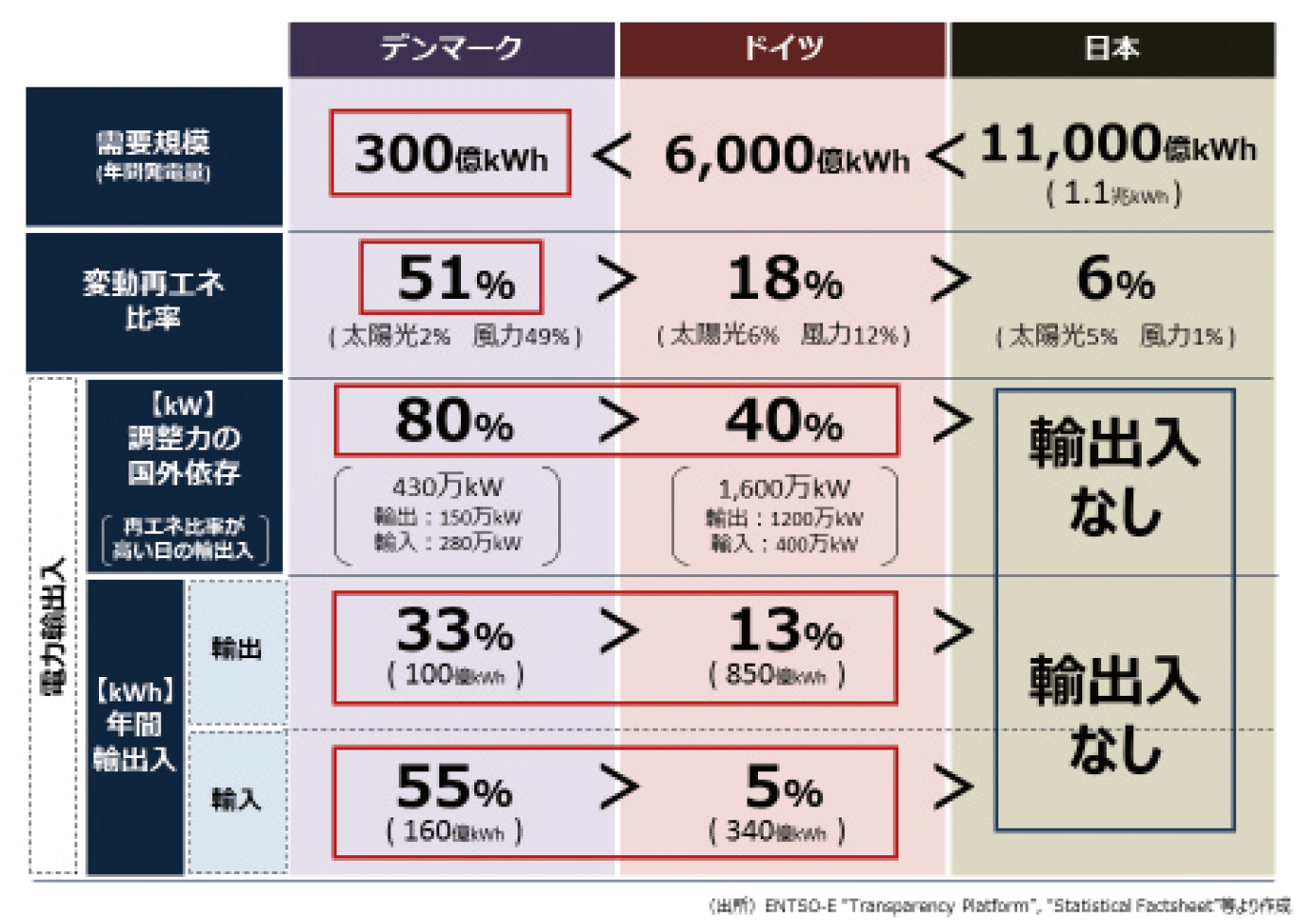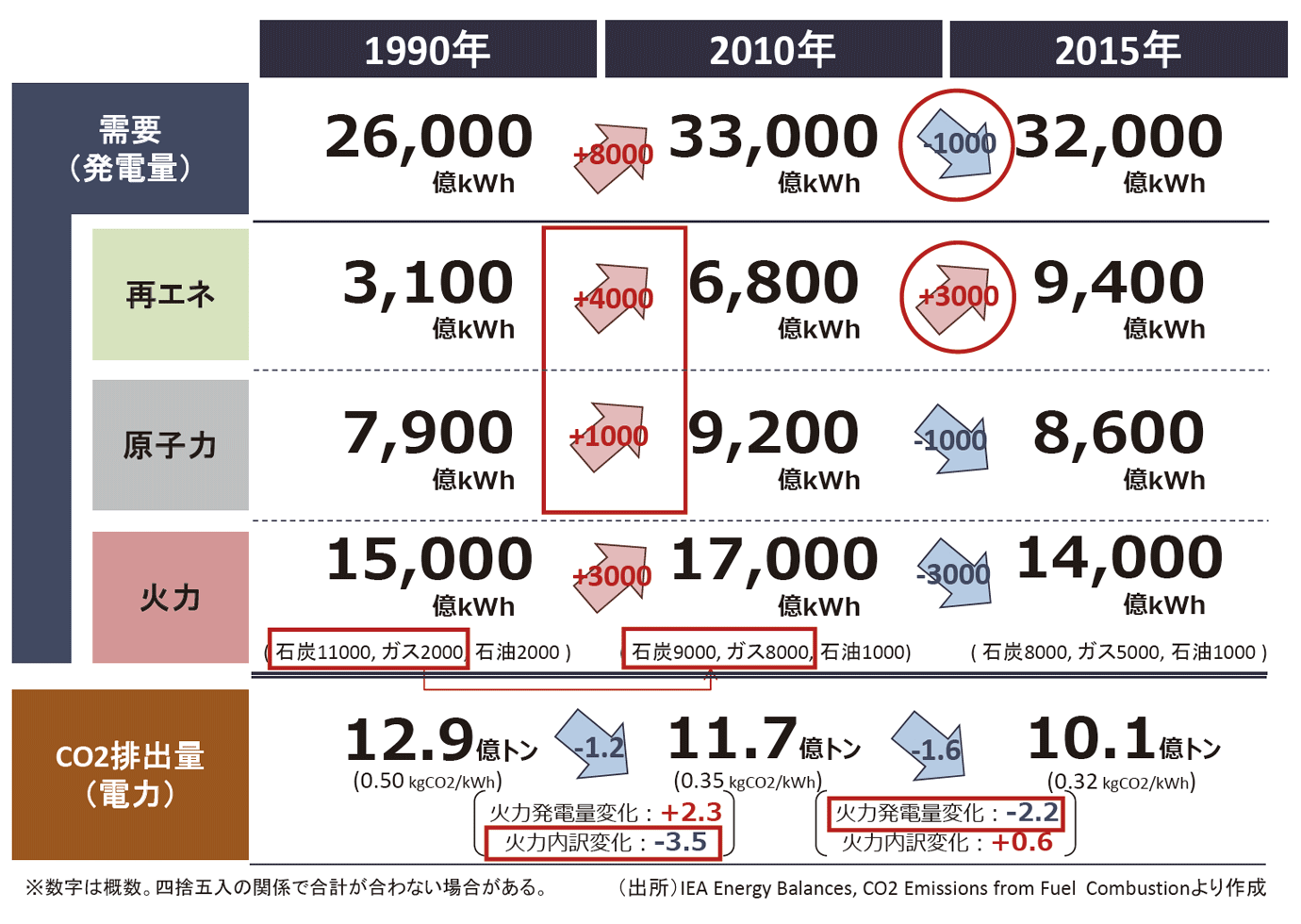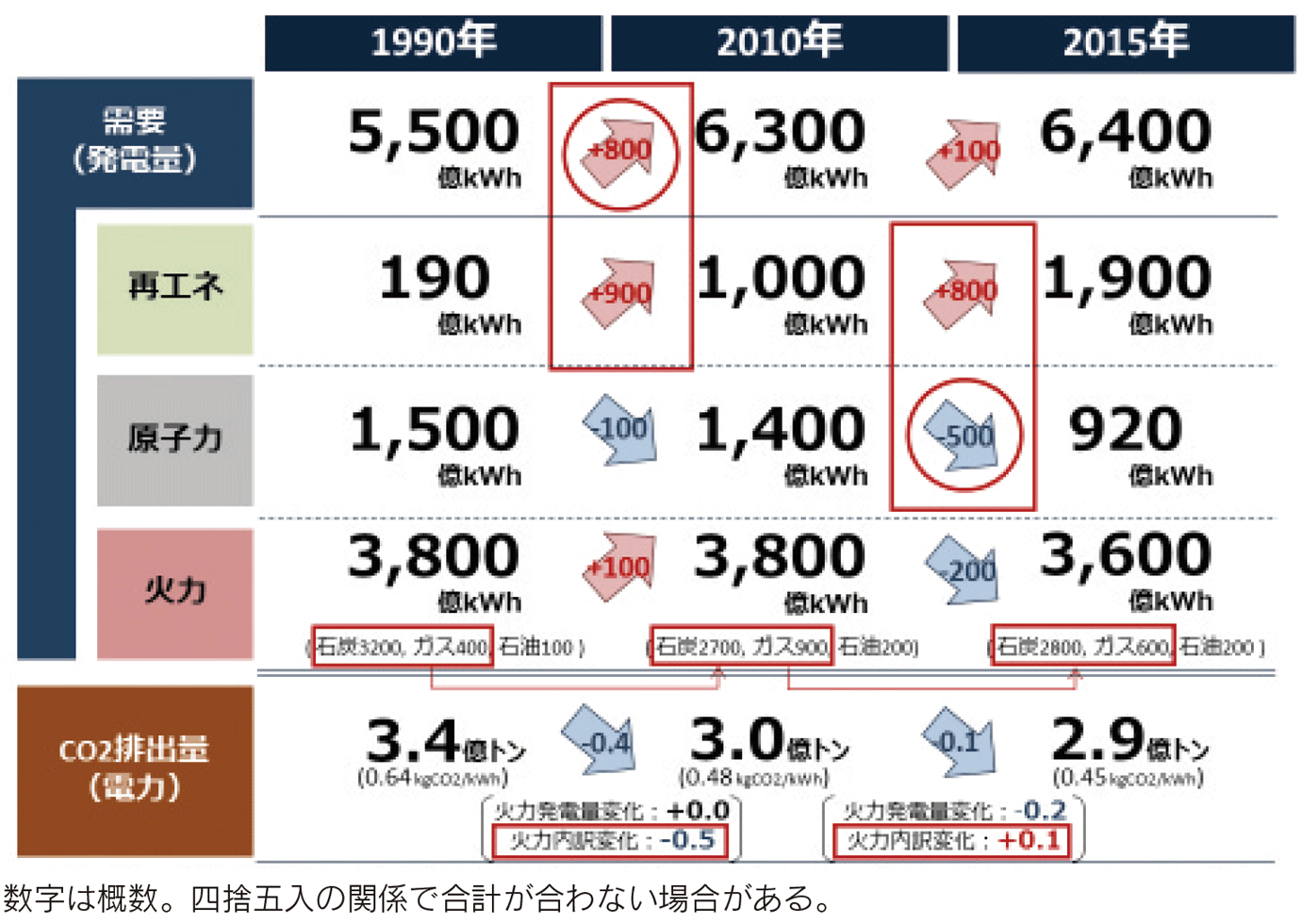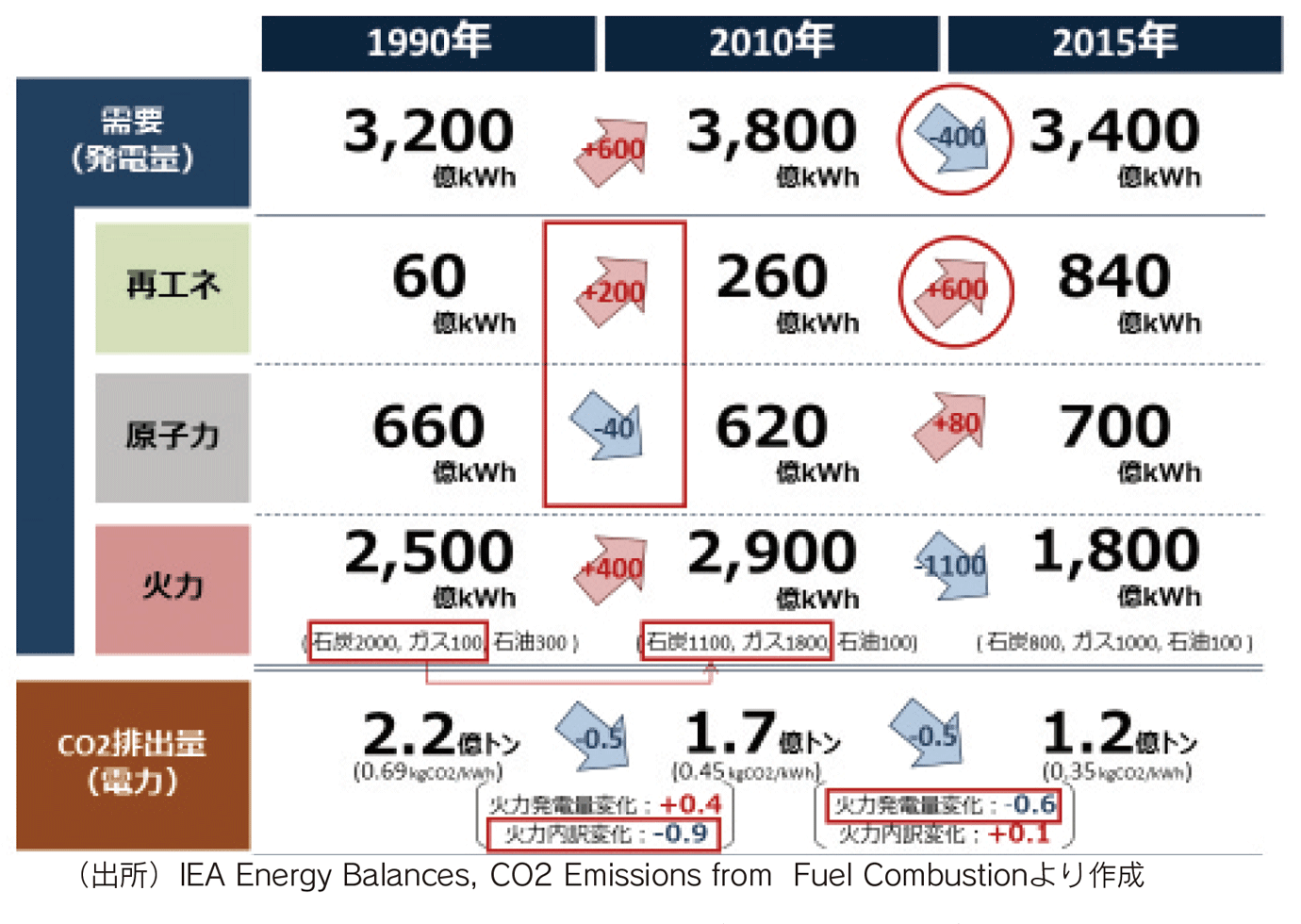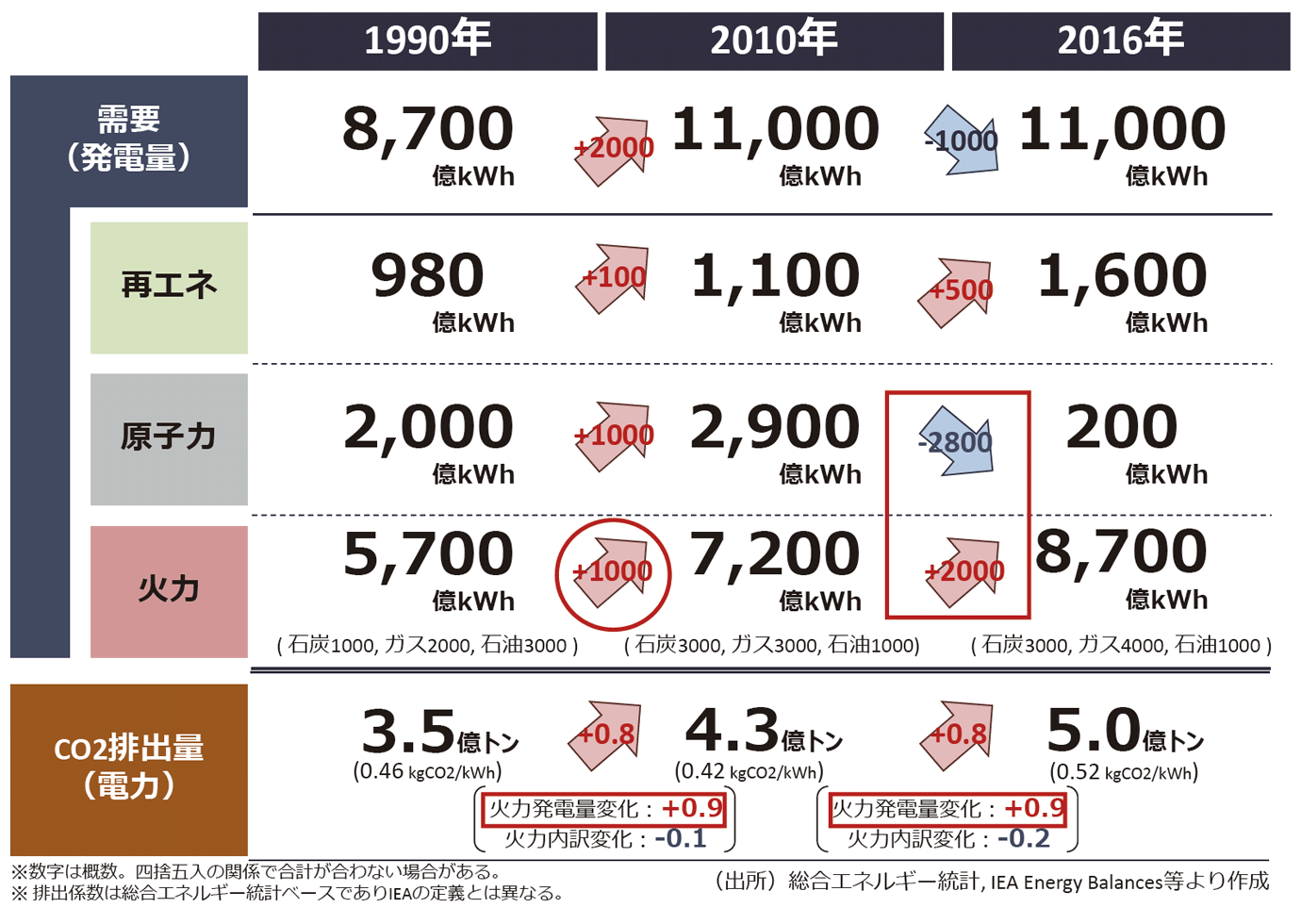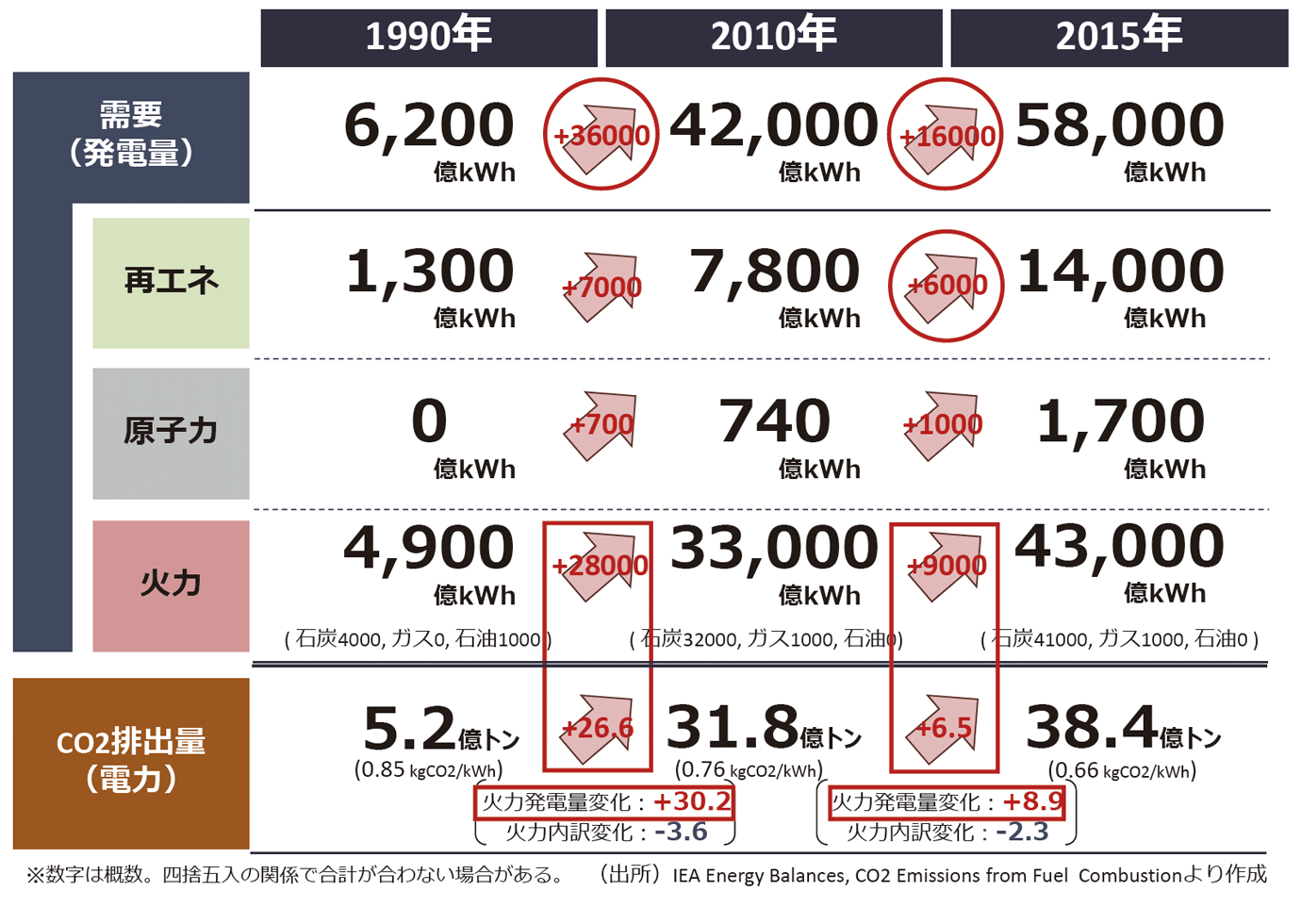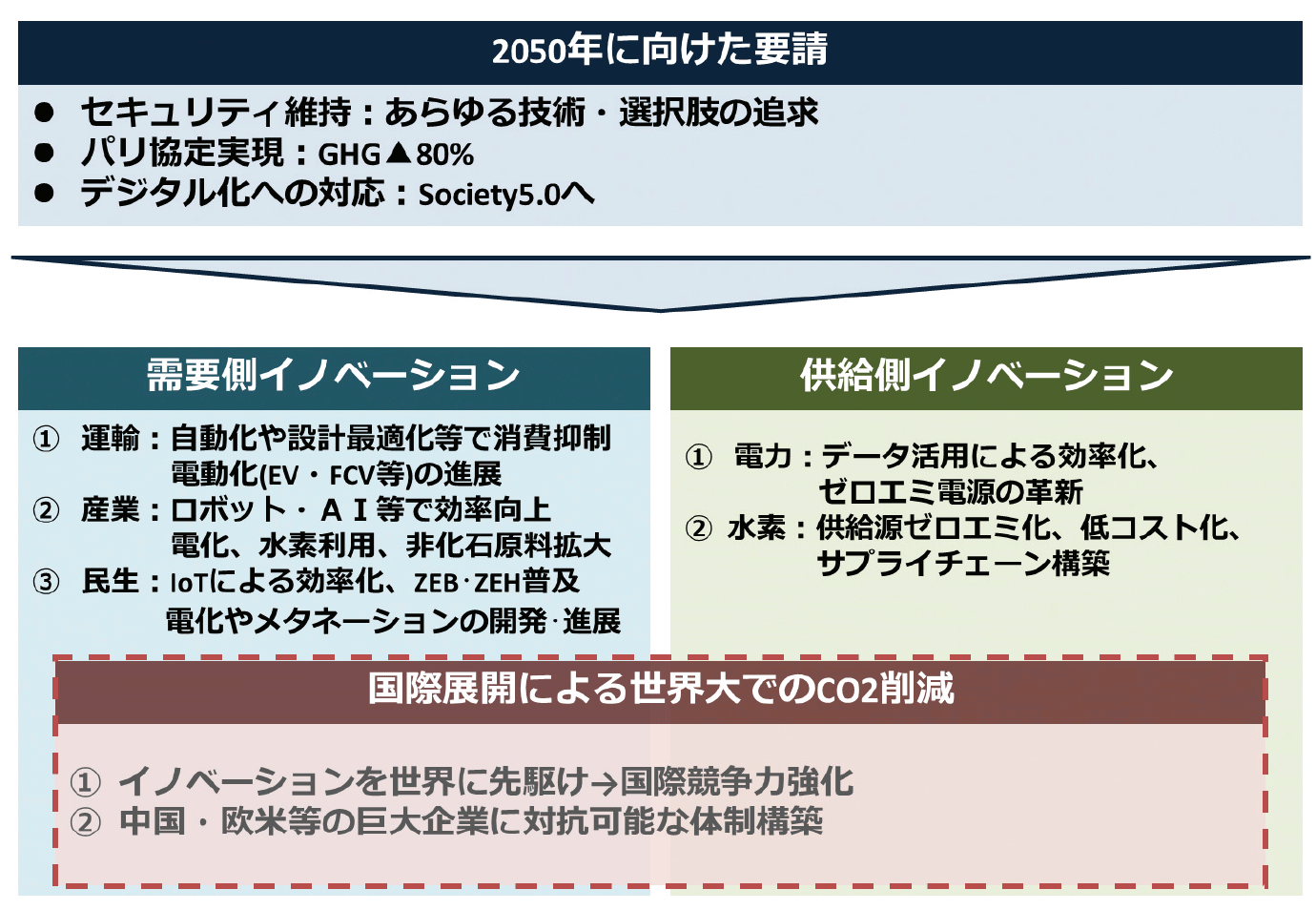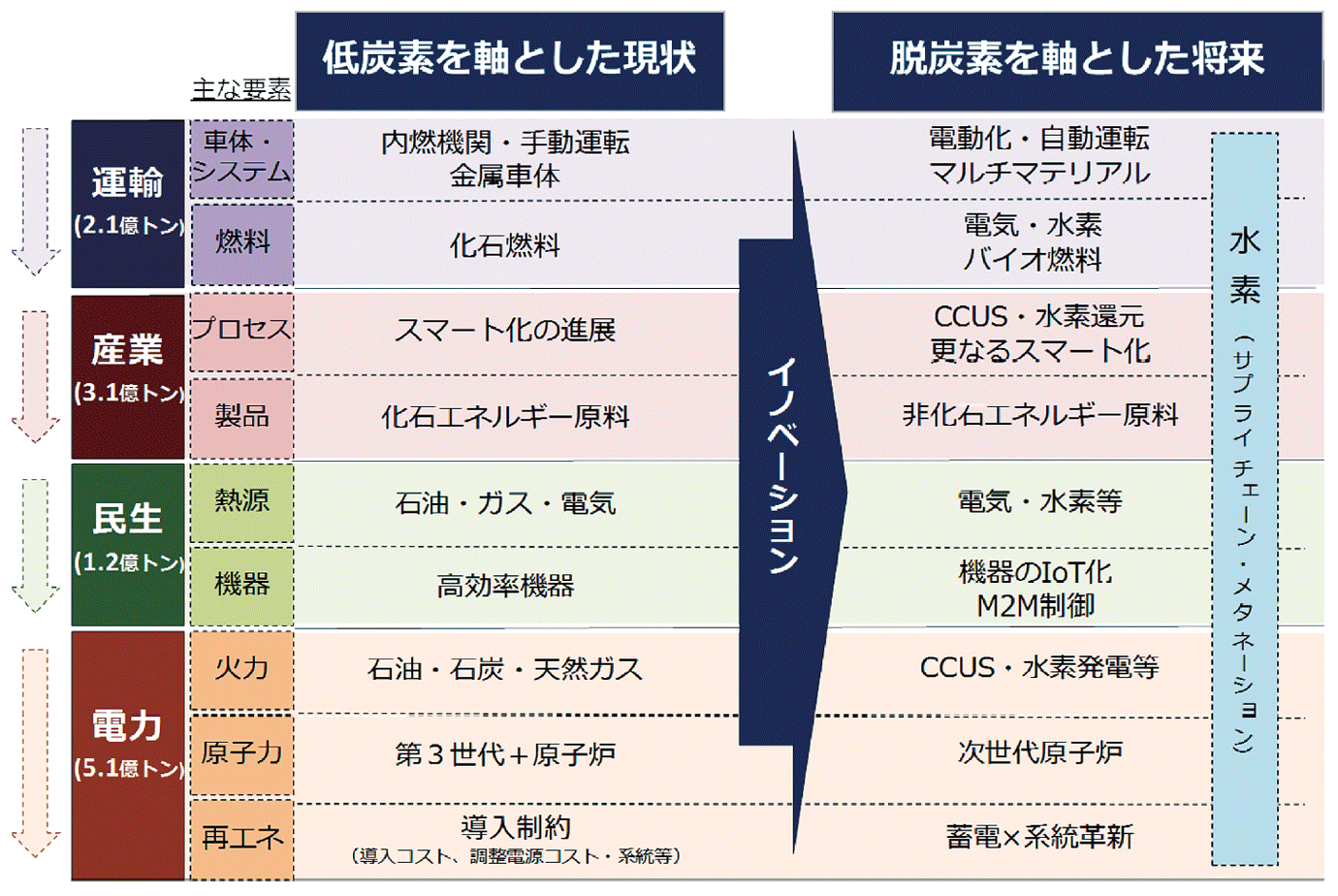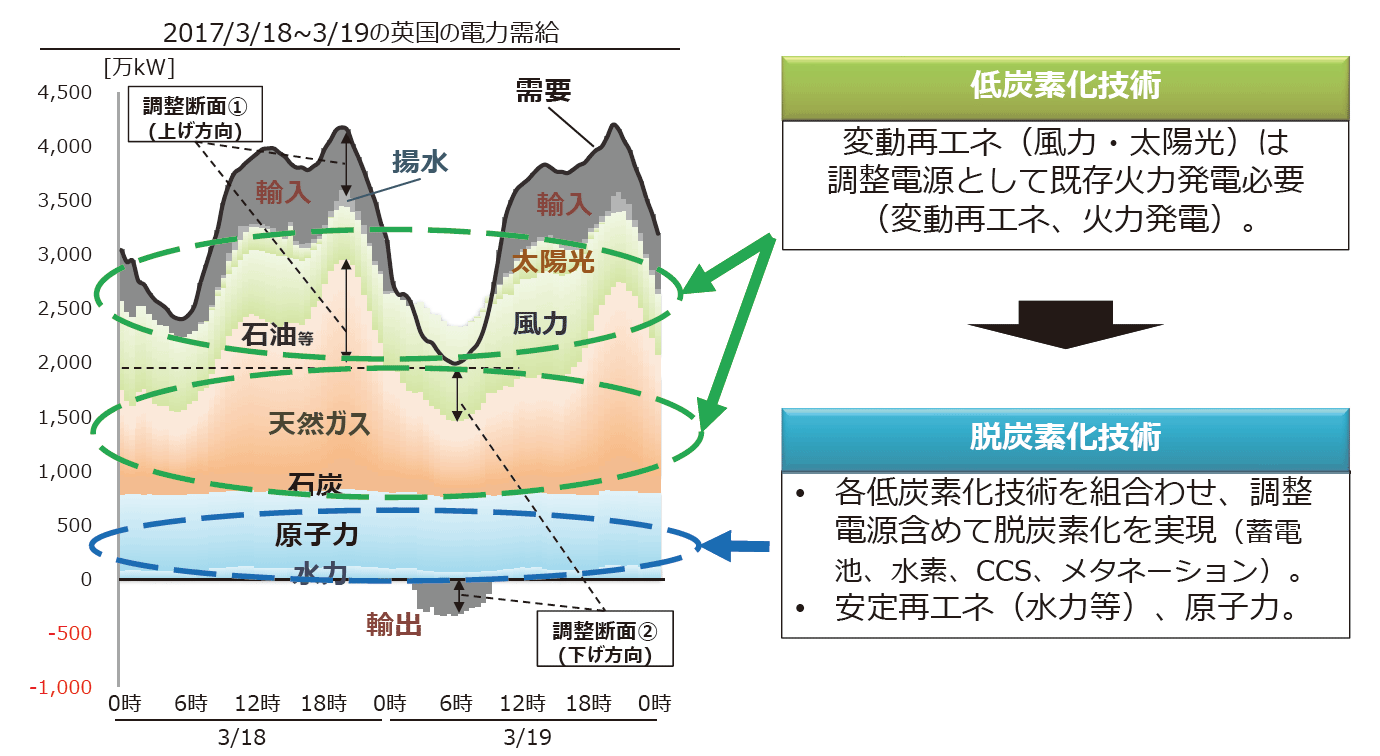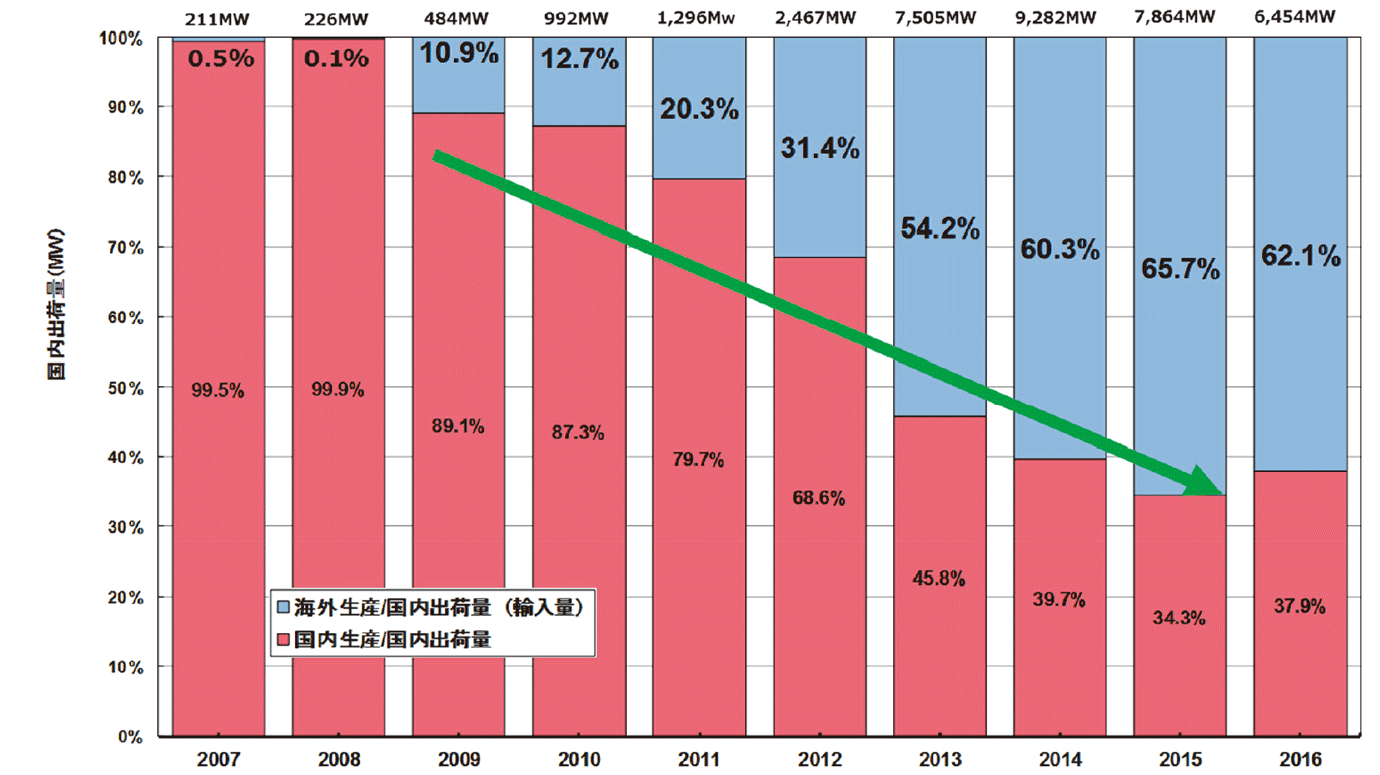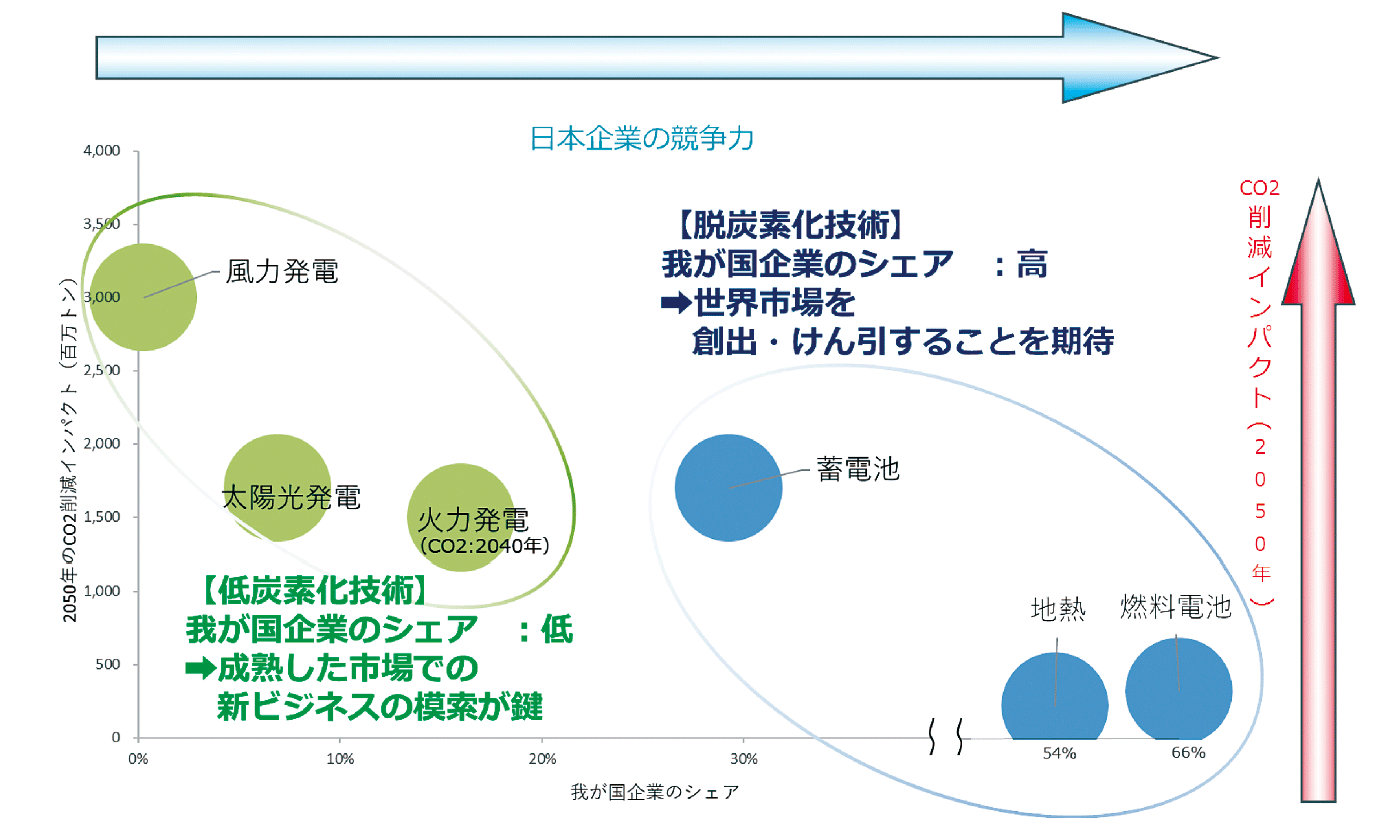第2節 2050年に向けたエネルギー情勢の変化と課題
1.エネルギー政策のメガトレンド
我が国のエネルギーの歴史は、過去からの大きなトレンドの中で、その時々の選択によって、形作られてきました。我が国は、現在まで、4つの大きなエネルギーの転換期において選択をし、現在、5つめの岐路に直面しているといえます。
第1の選択は1960年代です。エネルギー需要の大幅増加によって「国内石炭中心の利用から石油中心の利用」へと大きくシフトしました。この結果、自給率が10年間で58%から15%へと大幅に低下することになります。
第2の選択は、1970年代です。石油に大きくシフトした日本が、2度の石油危機に直面します。その結果としての電気代高騰を受けて、省エネの必要性が広く認識されるとともに、地政学的なリスクが大きく意識されることで、「石油代替・エネルギー源の多様化」が模索されはじめました。
第3の選択は1990年頃です。世界的に「温暖化」が問題視されはじめ、1997年には京都議定書の採択を機に、環境配慮という価値軸が我が国でも強くなってきました。また、地域独占が認められて公共インフラである、都市ガスや電力において、部分的ではありますが「自由化」がこのころから始まりました。
第4の選択は、2011年に発生した東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故です。史上類を見ないエネルギー供給の危機を経て、我が国のエネルギー政策は、安定供給・経済効率性・環境への適合に加え、エネルギーの安全性という大原則を再認識しました。2014年に、震災後はじめての改定となった現行のエネルギー基本計画(以下、「第四次エネルギー基本計画」という。)では、こうした大きな情勢変化を受けて、原子力発電については、可能な限り依存度の低減を目指すことや、再エネの導入加速化という方針が、定められています。
そして、2015年の気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)において、主要排出国を含む全ての国が参加し、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く抑え、1.5℃までに制限する努力をする、としたパリ協定を踏まえ「第5の選択」として2050年に向けエネルギーの将来像を模索するシナリオ等を「エネルギー情勢懇談会2」において議論し、本年4月に提言をとりまとめたところです。
次項では、我が国が2050年に向け「第5の選択」をする際に、踏まえるべき論点や課題について議論した「エネルギー情勢懇談会」の内容を紹介していくことになりますが、まずは、その懇談会のきっかけともいえる問題意識である、2050年の長期エネルギー政策を考えるうえでの「10の変化」を見ていきたいと思います(「10の変化」は情勢懇談会の議論を開始した、2017年時点の情勢認識)。
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
(変化1)原油価格は100ドルから50ドルに
原油価格のトレンドの見極めはエネルギー政策を考える上での基礎ですが、新興国の成長、シェール革命の持続性に加え、EV化の進展度合いなどによって大きく左右されることとなり、見極めが難しくなっています。(【第132-2-1】参照)
(変化2)再エネ価格は日本の外では40円/kWhから10円/kWhに
世界的に再エネ投資は拡大し、発電コストも低下してきています。他方で、日本の再エネのコストは諸外国に比べて高い状況であり、FIT支援後の自立化のために何が必要か、また調整力の確保やネットワークの増強などの課題にどう対応するか、などの問題も顕在化してきています。(【第132-2-8、第132-2-14】参照)
(変化3)自動車産業のEV化競争が激化
自動車の電動化は、エネルギーの需給の構造を変える可能性があります。反対に、自動車の電動化による環境への恩恵は、エネルギーの電源構成によって左右される関係にあります。この点、海外の規制等の政策の動向や、自動車産業、石油メジャー等の戦略に注視が必要です。(【第132-2-15】参照)
(変化4)脱原発を宣言した国がある一方、多くの国が原子力を活用している状況
東京電力福島第一原子力発電所の事故以降、いくつかの国が脱原発宣言を行いました。他方で、多くの国が引き続き原子力発電を推進しています。各国の原子力政策の動向に注視が必要です。(【第132-1-2】参照)
(変化5)全面自由化と再エネ拡大で投資環境に新たな課題
再エネの拡大と自由化が進展し、電力価格の変動が大きくなる中、投資から回収までに長期間を要する電源について、投資の予見性が低下しています。(【第132-2-13】参照)
(変化6)パリ協定をめぐる動向、米国離脱もトレンドは変わらず
パリ協定が発効し、世界的な脱炭素化の潮流の中で、各国が、自ら策定し国連に提出する形で、長期の温室効果ガス排出削減に向けた目標を掲げています。こうした各国の動向を注視する必要があります。(【第132-2-5】参照)
(変化7)拡大する世界のエネルギー・電力市場
我が国のエネルギー・電力市場は量的な拡大が大きく見込みにくい一方で、世界のエネルギー市場・電力市場は今後拡大していく見込みで、ユーティリティ企業やプラントメーカーにとって見逃せない市場になっています。また、化石燃料の消費についても同様で、特に新興国(非OECD)での増加が見込まれています。(【第132-2-3】参照)
(変化8)中国国営企業の台頭、欧米ではエネルギー企業のM&Aが進展
エネルギー分野において、国家電網公司などの中国国営企業の台頭や、欧米ユーティリティ企業の国外進出、M&Aが加速しています。将来の不透明さが増していく時代において、産業のリスク投資能力も重要なポイントとなってきます。(【132-1-3】参照)
(変化9)金融プレーヤーの存在感の高まり
パリ協定、脱炭素化の潮流などを受け、エネルギー分野における世界の投資・金融機関の方針も変化してきています。一部には、化石燃料関連資産から資金を引き揚げるダイベストメントの事例なども生じています。ESG(環境、社会、ガバナンス)を重視する投資の考え方などの動向を注視する必要があります。
(変化10)世界全域での地政学上の緊張関係の高まり
エネルギー源の太宗を海外からの輸入に頼る我が国にとって、地政学を踏まえたエネルギー安全保障の確保は、極めて重要な視点です。シェール革命によって米国の自給率が高まり、その結果、中東における米国の影響力が低下しつつあります。他方で、中国が需要増を背景に中東への関与を強化するなど、地政学を巡るプレーヤーの多極化と変質が生じています。
次項以降は、こうした変化を踏まえて、エネルギーセキュリティや地球温暖化問題への対応、各国の主要企業の動向に関して議論したエネルギー情勢懇親会の内容について記載していきます。
【第132-1-2】世界の原子力の利用実態
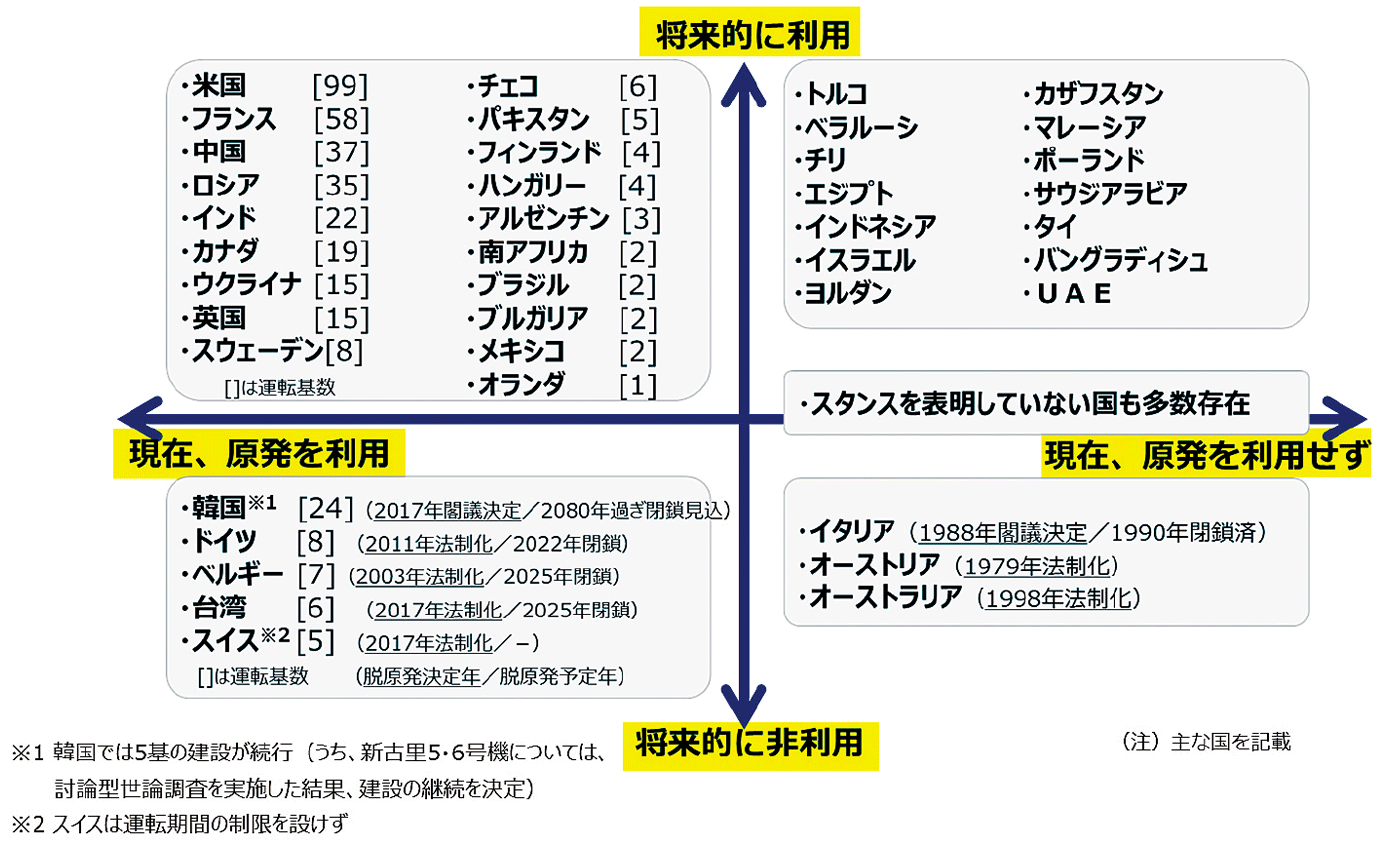
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
【第132-1-3】産業のリスク投資能力の海外との格差(2015年)
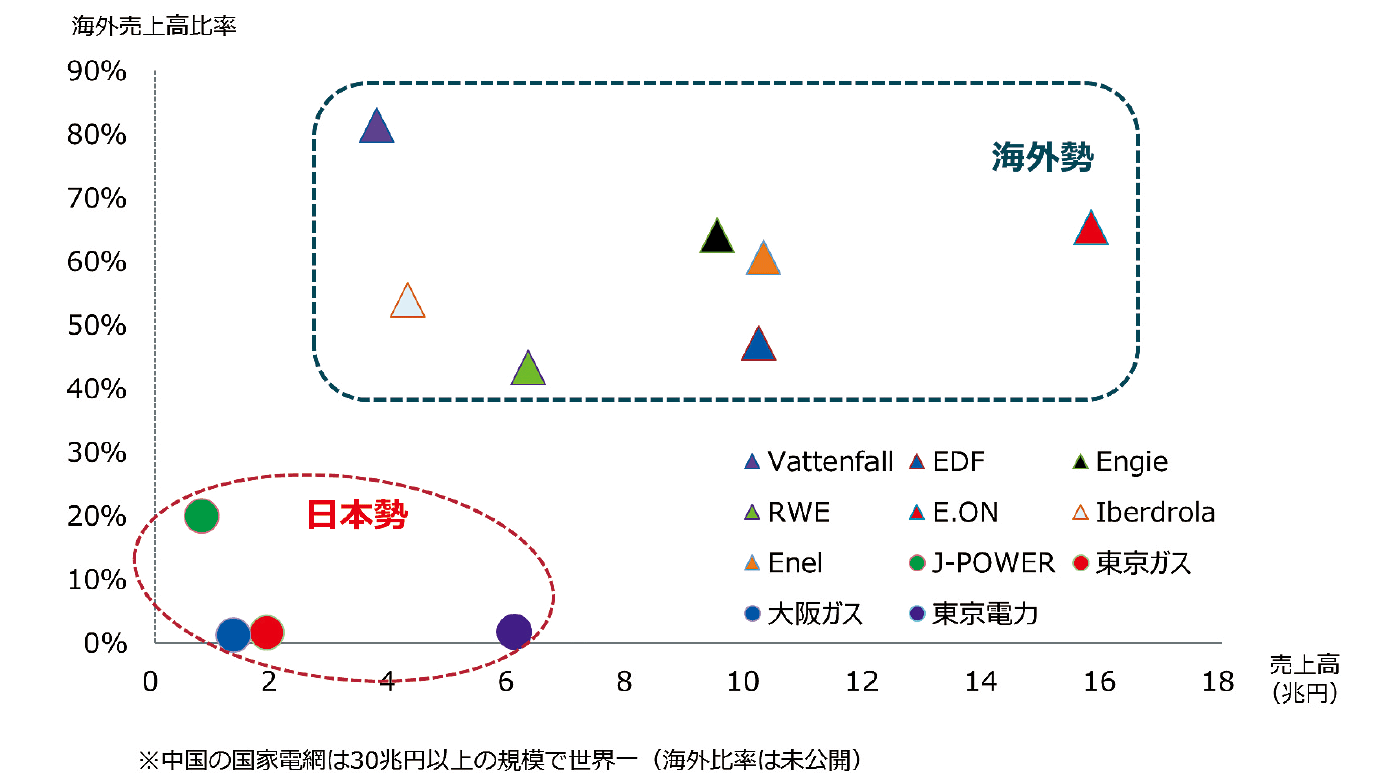
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
2.2050年視点で踏まえるべき論点、課題
(1)エネルギーセキュリティの多極化とリスクの変質
エネルギーセキュリティについては、エネルギー供給国の多極化に伴うリスクの変質が生じており、不確実性が増しています。
国際的な原油価格は、2004年以降は上昇を続け、2008年7月には145.29ドル/バレル(WTI、終値)という史上最高値を付けた後、リーマン・ショックの影響で一旦急落しましたが、中国などの新興国の石油需要の急拡大、中東地域での地政学的リスクなどを背景に再び上昇に転じ、2011年以降は100ドル/バレル前後で高止まりしてきました。しかし、2014年後半以降は、米国のシェールオイル増産等による供給過剰感などから大幅に値下がりし、2016年2月には2003年以来の安値水準となる26.21ドル/バレルまで下落しました。その後は、世界経済の成長による年後半以降の需給引き締まり見通し等を受けて上昇に転じ、11月のOPECの減産合意以降は比較的安定的に推移しています。
また、将来についても、国際エネルギー機関(IEA)のWorld Energy Outlook(WEO)2017では、世界の政策動向に応じて、64ドル/バレル(原油需要33億トン)から136ドル/バレル(原油需要55億トン)と幅のある価格想定(2040年時点)が提示されており、エネルギー効率の向上、中国などの産業構造の変化と温暖化対策、電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHV)の導入拡大などの動向も、注視していく必要があります。
我が国は、石油の85%、ガスの23%を中東から輸入しており、他の主要国と比べても、中東依存度が高いことが特徴です。近年、世界の石油・ガス市場では、シェール革命によって自給率の上がった米国や、輸出国として力を強めているロシアに加え、急激にエネルギー消費を増やしている中国の存在感が増してきており、エネルギー獲得をめぐるプレイヤーの構造が変わってきています。さらに、カタールと中東5か国の断交などの例にも見られるように、中東産油国をめぐる情勢は複雑化しています。
このように、長期のエネルギーの見通しが非常に不透明な状況下で、国内資源が乏しくエネルギー自給率が低い日本は、従来以上に長期的なエネルギー戦略を考えていかなければなりません(自給率は2016年実績でOECD35か国中34位の8.4%)。
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
さらに、世界のエネルギー需要の内容についても転換が起こっており、そのトレンドは加速するとも言われています。IEAの予測では、先進国ではガスシフトが進む一方で(需要は現状13億トンから2040年には15億トンへ)、新興国では石炭への依存が継続する(需要は現状30億トンから2040年には36億トンへ)という見通しもあり、我が国が誇る低炭素化・脱炭素化技術による貢献も期待されます。
上記のように、長期のエネルギー需給について、エネルギーセキュリティの多様化とリスクの変質についてを考えた場合だけでも、その将来は非常に不確実性が高いことがわかります。近年、特にパリ協定以後は、地球温暖化への対策の動向も、エネルギー需給の見通しを考える上で一層重要な視点になっています。次項では、各国の温暖化に対する戦略や対応を中心に見ていきます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
COLUMN
エネルギー安全保障(2000年代と2010年代の比較)
(1)はじめに
エネルギー安全保障という言葉は耳にしますが漠然としたもので、数値で表すことは難しい概念です。しかし、エネルギー白書2010(以下「エネ白2010」という。)では主要7か国を対象に1970年代以降のエネルギー安全保障の強化の取組の定量的評価を試みました(「一次エネルギー自給率」、「各資源(原油・天然ガス・石炭)の輸入相手国の分散度」、「チョークポイントリスクの低減」、「エネルギー源多様化」、「電力の安定供給(停電時間)」、「エネルギー消費のGDP原単位」、「供給途絶対応可能日数」の7項目で評価)。また、エネルギー白書2015(以下「エネ白2015」という。)では、米国の「シェール革命」により主要国のエネルギー安全保障がどのように変化したかを見るために、エネ白2010で使用した「エネルギー安全保障の定量評価指標」を用いて、2000年代の評価値と当時の直近のデータに基づく評価値の比較を行いました。「エネ白2010」が公表されて8年が経過し、エネルギー情勢をめぐる環境も変化しています。今回、最新の統計等を使用し、「2010年代」という評価期間を追加して、主に2000年代と2010年代の比較を行ってみました。調査対象国(以下「各国」という。)はエネ白2010と同じフランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、中国、韓国および日本の7か国です。評価項目および評価手法などは原則として「エネ白2010」を踏襲しました。
使用した統計・資料は国内外の機関等が公表し、広く一般的に使用されているものを使用しましたが、統計上、全ての評価項目にOECD30か国の合計数値が記載されているわけではありません。したがって、OECD合計の記載がない場合は、把握可能なOECD国を選定し、合計したものをOECD合計としてみなしてある評価項目があります。また、評価数値は、評価項目ごとに最大10ポイントで点数化しました。点数化は最も評価数値の高い国を10ポイントとし、その他の国は最も高い評価数値と当該国の評価数値の割合に応じて点数化しました。なお、「エネ白2015」とは、①新たにOECDに仲間入りした国が5か国存在しているため、OECDの定義が異なっていること、②チョークポイントは、最新の米国エネルギー省エネルギー情報局のレポートに基づき、当時のホルムズ海峡、マラッカ海峡、バル・エル・マンデブ海峡、スエズ運河に加えて、トルコ海峡、パナマ運河、デンマーク海峡、喜望峰が追加されていること、などの違いがあります。
(2)全体傾向
2000年代と2010年代の各国のエネルギー安全保障の状態を比較しますと、改善している国がアメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、韓国の5か国、後退した国が日本と中国の2か国になりました。
アメリカはシェールオイル・ガスの増産および石油備蓄量の増加により一次エネルギー自給率と供給途絶対応可能日数が改善しました。イギリスはエネルギー効率の改善が進み、エネルギー消費のGDP原単位が向上しました。ドイツは天然ガスと再エネ拡大およびエネルギー効率改善により、エネルギー源多様化とエネルギー消費のGDP原単位が向上しました。韓国は各国の中で需要家当りの停電時間が最も少なく、電力の安定供給(停電時間)が向上しました。
これら改善した国に対して、日本は東京電力福島第一原子力発電所事故後、全ての原子力発電所の運転が停止したため、一次エネルギー自給率が後退しました。また、東日本大震災後の影響で多くの地域で停電が続いたことにより、需要家1件あたりの停電時間が大きく増加し、電力の安定供給が後退しました。中国はエネルギー消費の増大により、エネルギー輸入量が増加して一次エネルギー自給率が後退するとともに、特定の国からのパイプラインによる輸入シェアが増加することで各資源(原油・天然ガス・石炭)の輸入相手国の分散度が後退しました。
(3)我が国の震災前後の傾向
我が国は2011年に東日本大震災という災害に見舞われました。この災害が我が国のエネルギー安全保障に与えた影響を見てみます。比較は2010年、2011年および2015年の3時点で行いました。
震災前の2010年と震災が発生した2011年を比較しますと、震災後の計画停電により、需要家1件当たりの停電時間が増加し、電力の安定供給が大きく後退しました。また、準国産エネルギーである原子力発電の停止により一次エネルギー自給率が後退しました。
2011年と2015年の比較では、計画停電の終了にともない電力の安定供給が改善するとともに、省エネルギーのさらなる進展により一次エネルギー供給量が減少し、エネルギー消費のGDP原単位が改善しました。さらに、ロシア原油の太平洋側からの供給能力が強化されたため、チョークポイントリスクの低減が見られます。他方で、FIT等で再エネ導入が進展しましたが、原子力発電停止の影響で一次エネルギー自給率は7%と低位で推移しています。
(4)項目別の比較
参考までに、2000年代と2010年代の評価を項目別に比較してみます。図の青の線が2000年代、赤の線が2010年代を示しています。特筆すべきところを見ていきます。
① 一次エネルギー自給率
アメリカはシェール革命により、シェールオイル・ガスの生産が増加しました。さらに再エネも増加したため、一次エネルギー自給率は改善しています。
イギリスは英領北海油田の開発により、かつては一次エネルギー自給率が100%を超えていた時期もありましたが、同油田の枯渇により原油生産量が減少を続け、後退しました。
中国の主要エネルギーは石炭です。中国では国内石炭の生産量は増加しましたが、それ以上にエネルギー消費量が増加したため、自給率が後退しました。
② 各資源(原油・天然ガス・石炭)の輸入相手国の分散度
中国が2000年代、2010年代ともに高い評価になりました。中国が2010年代に多少後退しているのは、2010年からトルクメニスタンからパイプラインによる天然ガスの輸入を開始し、天然ガス輸入に占める同国のシェアが50%に達したため寡占度が上昇したことが主因となっています。
フランスの評価が高いのは、石炭の輸入先の寡占度が低いことが主な要因です。
③ チョークポイントリスクの低減(原油)
チョークポイント3は各国の置かれた地理的位置に左右されます。東アジアに位置する中国、日本、韓国の場合は、チョークポイントを通過しない原油の輸入先は限られてしまいます。したがって、東アジア3か国の評価は低くなっています。
西欧の場合、チョークポイントを通過する原油の輸入先は中東とロシア・カザフスタンです。イギリスは2000年代においてもこの両地域からの輸入量が少ない国でしたが、2010年代にはさらに低下し、一層改善しました。
④ エネルギー源多様化
日本はこれまで各国の中でエネルギー源の多様化が進んだ国でしたが、東京電力福島第一原子力発電所事故後に原子力発電が低下し、化石燃料による発電が増加しました。このため、エネルギー源多様化は後退しました。
イギリスは石炭から北海で生産される天然ガスにシフトしたこと、RPSやFIT政策により再エネが増加したことによりエネルギー源の多様化が進み、改善しました。
アメリカの発電の主流は石炭でしたが、シェール革命により発電に占める天然ガスのシェアが増加し、石炭のシェアが低下しました。また、再エネのシェアも増加しています。これによりアメリカのエネルギー源多様化は改善しました。
ドイツは再エネを増加させましたが、脱原子力政策により原子力発電が減少したため、石炭への依存度はそれほど減少しませんでした。このためドイツは小幅な改善にとどまりました。
⑤ 電力の安定供給(停電時間)
2000年代、日本は韓国と並んで需要家1件あたり停電時間(以下「停電時間」という。)が少ない国でした。しかし、東日本大震災後の計画停電によって、「停電時間」が増加し、電力の安定供給が大きく後退しました。
韓国では、2010年代に電力予備率の目標を高めるとともに、AI・IoT活用による配電システムの効率化により停電時間が改善し、電力の安定供給が最高の評価になりました。
⑥ エネルギー消費のGDP原単位
1970年代に発生した2度の石油危機を受けて、OECD諸国は省エネルギーに注力し、省エネが進展しています。過去、各国の中では日本がエネルギー消費のGDP原単位(以下「GDP原単位」という。)が最も進んだ国でしたが、近年では、フランス、ドイツ、イギリスも改善しています。特に2010年代のイギリスの「GDP原単位」は各国の中で最高の評価になりました。
中国のかつての「GDP原単位」はOECD諸国と比較すると非常に悪い数値でしたが、2000年代から省エネルギーを政策の柱の1つにしてエネルギー効率を高める努力を行っています。また、GDP自体が増加していることも加わり、「GDP原単位」は改善を続けています。
⑦ 供給途絶対応可能日数
供給途絶対応可能日数は最大輸入地域からの石油輸入が停止した場合に、石油備蓄量で持ちこたえることが可能な日数を評価しています。
2000年代よりも最大輸入先からの輸入シェアが減少した国については、供給途絶対応可能日数が改善することとなり(イギリスは欧州地域から、ドイツは旧ソ連地域から、フランスはアフリカ地域から、日本は中東地域からの輸入シェアがそれぞれ減少)、また、イギリスを除いて、各国とも備蓄日数が増加しました。指標は相対評価であるため、各国とも2000年代と2010年代で大きく変わっていませんが、各国ともに実数としては改善をしています(例えば、日本は178日から211日に改善)。なお、アメリカは各国の中で最大輸入地域のシェアが最も低く、備蓄数量も多いため、供給途絶対応可能日数の評価は高くなっています。中国は国家石油備蓄の増強を進めている段階にあります。
- 出典:
- 「平成29年度エネルギー戦略⽴案のための調査・エネルギー教育等の推進事業(国内外のエネルギー動向に関する調査・分析)調査報告書」より資源エネルギー庁作成
(2)地球温暖化対策の変化・潮流
① パリ協定と長期低排出発展戦略
約200の先進国・途上国・地域が参加し締結されたパリ協定では、各国が自ら策定し、国連に提出する形で温室効果ガスの削減目標を掲げています。日本は、「2030年度に、2013年度比で26%削減」を目標として提出しました(2015年エネルギー起源CO2排出量:世界全体で約320億トン、日本は11.5億トンで世界の約3.6%、世界第5位の排出国)。
また、より長期的な視点で低炭素型の発展を目指す「長期低排出発展戦略」を、2020年までに各国提出することが求められています。例えば、G7各国は、技術革新・普及、開発投資促進、海外貢献等を通じ、非常に高い削減目標に挑戦しています(米国80%削減(2005年比)、加80%削減(2005年比)、独80~95%削減(1990年比)、仏75%削減(1990年比))。
他方で、各国の目標や戦略は、2050年という長期視点ということもあり、柔軟性を確保しつつ、目指すべき方向性を示したビジョンとなっています。例えばドイツは、気候変動に関する国際連合枠組条約(UNFCCC)に提出した「長期低排出発展戦略」の中で、目標を「排出削減に向けた方向性を提示したもの(定期的な見直しを行う)」としています。また、目標達成への戦略についても、「全分野での省エネ促進」や「産業分野では、新技術による脱炭素化(CCU及びCCS)を実施」と、非常に多様なものとしていることが特徴です。
我が国も2050年に向けて、温室効果ガスの国内での大幅な排出削減を目指すとともに、世界全体の排出削減に最大限貢献し、世界の経済成長と気候変動対策の両立をリードしながら、世界の脱炭素化をけん引するビジョンを示すことが期待されています。
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
② ゼロエミ電源について
我が国のCO2の排出について、エネルギーを消費しているセクターごとに、電力(発電)部門、運輸部門、産業部門、業務・家庭部門(熱利用)と分けて考えると、特に「電力」の分野のCO2排出量が大きくなっています。この分野における、脱炭素化の動向と意義について見ていきます。
ここでは、太陽光や風力等の再エネと原子力発電等の、発電時にCO2をあまり出さない電源をゼロエミッション(ゼロエミ)電源と呼び、発電量に占めるその比率をゼロエミ比率としています。震災前、日本のゼロエミ比率は35%であり、特にゼロエミ電源の中でも、調整力や系統への負荷が少ない、安定再エネ(水力等)と原子力の比率は、34%と、欧米と比較しても非常に高い位置につけていました。
【第132-2-7】各国のゼロエミ比率とその内訳(変動再エネ・安定再エネ・原子力)
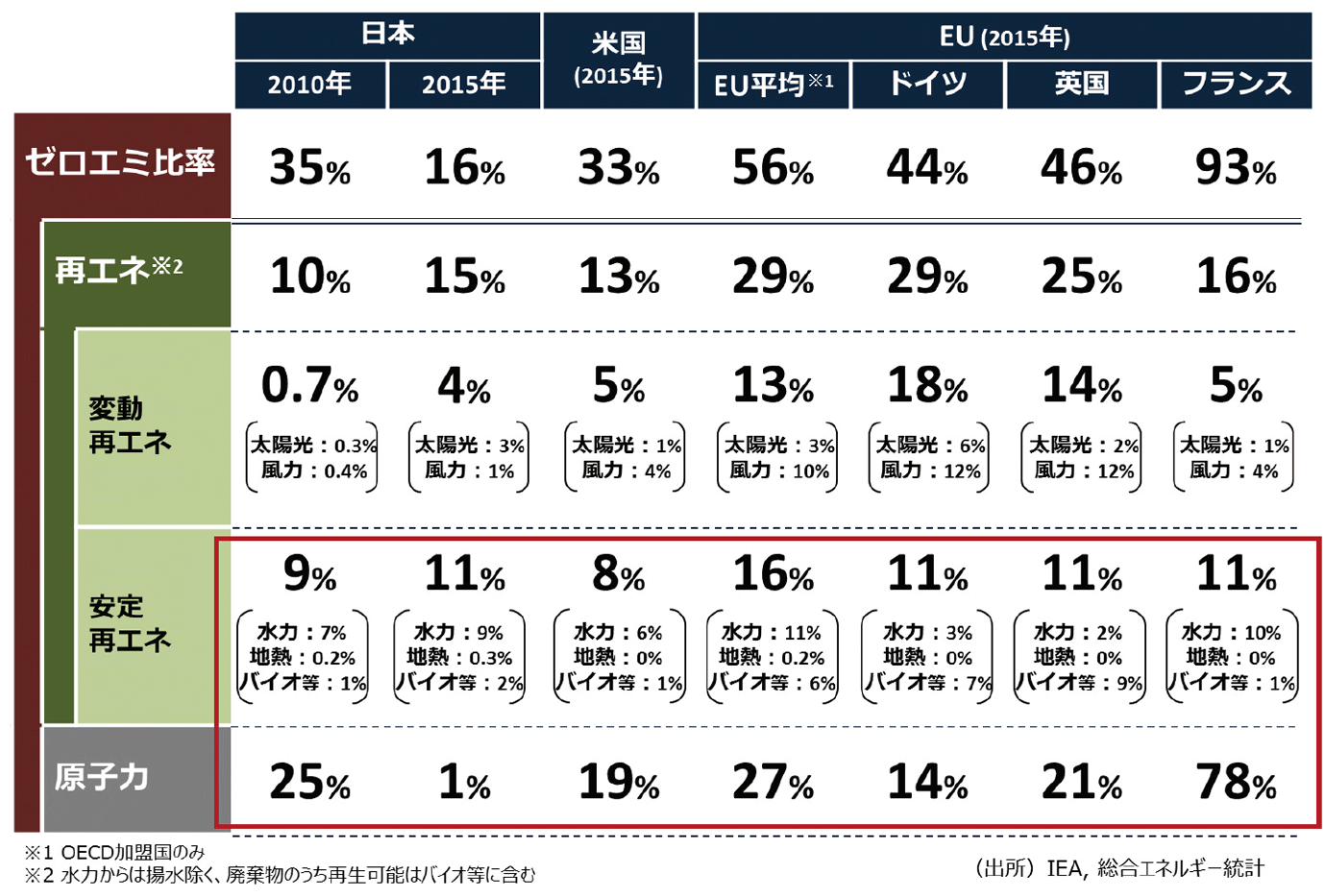
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
特に再エネについては、近年、世界の電力投資の中でも脚光を浴びており、2016年には風力や太陽光を中心に30兆円もの投資がなされています。欧州では大規模な投資の進展などの影響もあり、平均の太陽光発電コストは日本の1/2である10円/kWhと見積もられています。
我が国は、国土面積が小さく、山岳地帯も多いことから、世界的に導入が進展している太陽光や風力の導入において、適地の制約が強い傾向にありますが、そうした中においても、国土面積当たりの再エネ発電量を各国と比較すると、太陽光・水力について高い水準にあります。しかし同時に、総発電量(≒電力需要)を国土面積で除した電力需要密度については、各国よりも相当程度高く、結果、電源構成に占める再エネの比率は低位にとどまっています。こうした事情も踏まえながら、我が国の国情に合わせつつ、再エネを主力電源化するべく、積極的な導入を進めていくことが重要です。
他方で、風力や太陽光などの変動再エネが増加することで各国、様々な課題にも直面しています。
第一に、変動再エネには、気象条件等で発電しない際の調整電源が必要となり、現状多くは火力発電でそれをまかなっています。したがって、デンマーク、ドイツなど変動再エネ比率が高い国では、調整電源としての火力発電比率も相対的に高くなっています。この傾向は米国各州でも同様です。少なくともドイツでは2010年と2015年を比較すると、CO2排出量はほぼ横ばいです。その要因としては、再エネ増加によるCO2削減効果と、原子力の稼働減、石炭火力発電の稼働増、電力需要増によるCO2排出増加効果が相殺しあう関係となっていることが考えられます。また、これらの国々では、限界費用ゼロの再エネが市場に大量普及することで、火力電源の採算性が低下し、本来再エネのバックアップの役割を担うべき火力発電への投資の予見可能性が低下しています。独のE.ONは予見可能性が低くなった火力部門等を新会社Uniperに分離することで、会社全体のポートフォリオの再編を図るなど、各社は、対応を迫られています。
- 出典:
- IEA “World Energy Investment 2017”より資源エネルギー庁作成
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
電源としての火力発電比率も相対的に高くなっています。この傾向は米国各州でも同様です。少なくともドイツでは2010年と2015年を比較すると、CO2排出量はほぼ横ばいです。その要因としては、再エネ増加によるCO2削減効果と、原子力の稼働減、石炭火力発電の稼働増、電力需要増によるCO2排出増加効果が相殺しあう関係となっていることが考えられます。また、これらの国々では、限界費用ゼロの再エネが市場に大量普及することで、火力電源の採算性が低下し、本来再エネのバックアップの役割を担うべき火力発電への投資の予見可能性が低下しています。独のE.ONは予見可能性が低くなった火力部門等を新会社Uniperに分離することで、会社全体のポートフォリオの再編を図るなど、各社は、対応を迫られています。
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料より作成
【第132-2-12】米国のCO2排出係数と発電構成(2015年)
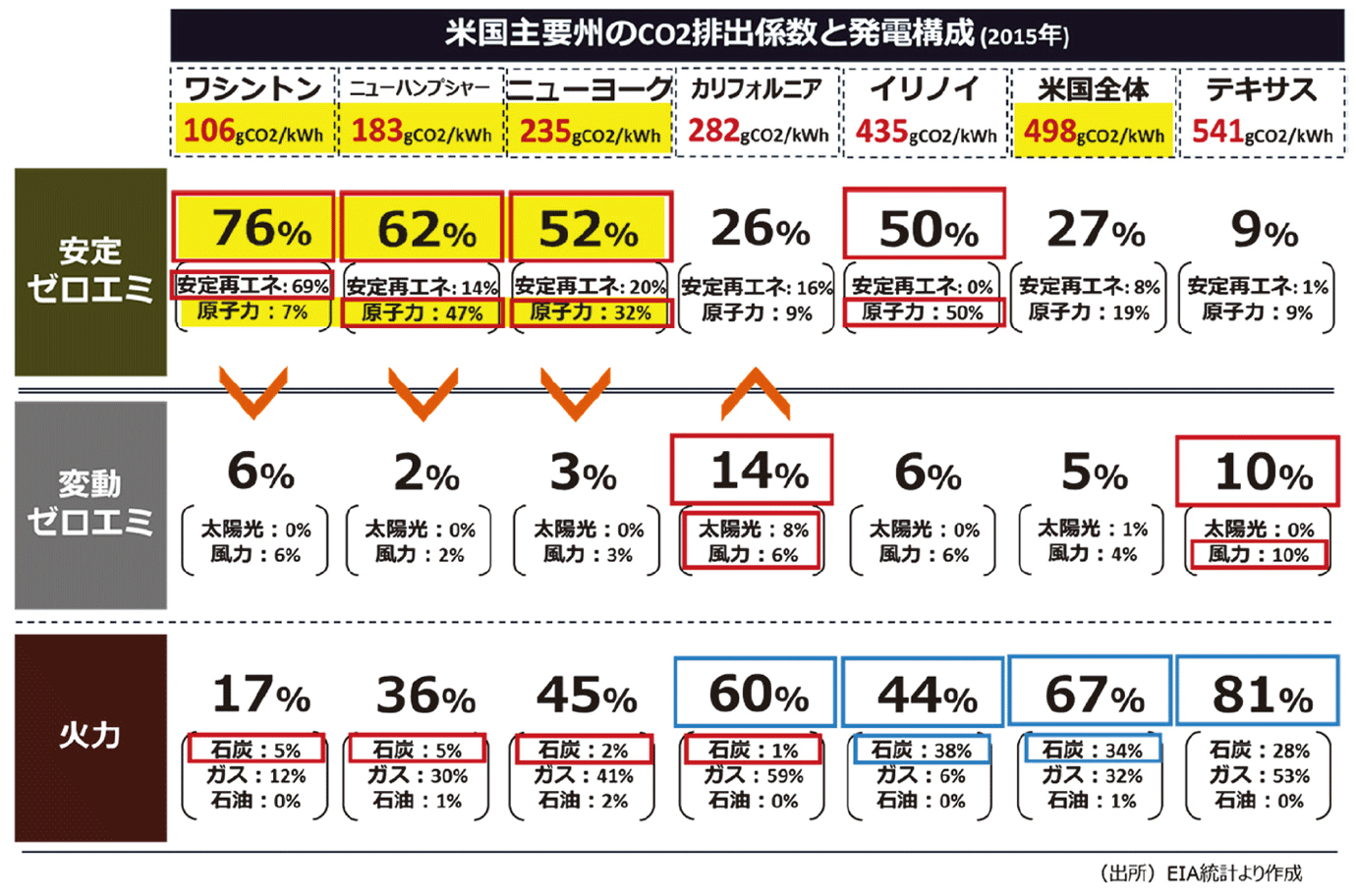
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
【第132-2-13】再エネ比率増加による火力発電所の予見性の低下とE.ON社のスピンオフ事例
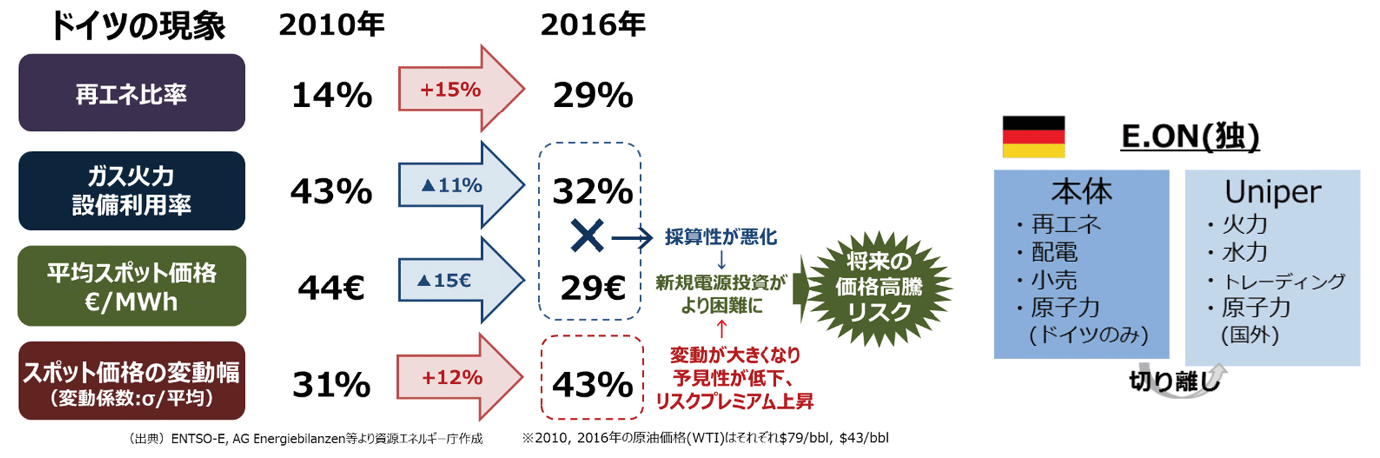
【第132-2-13】再エネ比率増加による火力発電所の予見性の低下とE.ON社のスピンオフ事例(ppt/pptx形式:52KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料、エネルギー白書2017
第二に、再エネ導入が大きく進むと、これまで沿岸部を中心に立地していた大型発電所と消費地とを効率的に結ぶことに最適化されていた既存ネットワークの再設計も必要になる可能性があります。蓄電池による調整という選択肢もありますが、仮に再エネと蓄電池だけで日本全国の電力需要を賄おうとすると、現在の電気料金の水準を維持するためには蓄電池価格が現状の1/100~1/1000になる必要があるという試算もあります。これは再エネと蓄電池だけで全ての需要を賄おうとする極端なケースですが、さらなるコスト低減に向けて官民合同で研究開発等に取り組んでいくことが必要です。
ゼロエミ電源の推進は、需要側の脱炭素化に向けた技術選択にも大きな影響を与えます。例えば、各国・地域が定量的な導入目標を掲げているEVは貯蔵された電気を使用してモーターを駆動するため、利用時点でCO2は排出されず、このように走行段階のみを評価する考え方を「Tank to Wheel」と言います。他方で、そのEVで使用される電気が再エネ由来なのか、石炭火力由来なのかなど、燃料製造から走行段階までを評価する考え方を「Well to Wheel」と言います。EV普及の環境へのインパクトは、EVに充電される電力が何電源由来かにより大きく異なります。具体的には、2030年に累計8,000万台(全自動車数1.6億台)のEV・PHVを計画している中国ですが、2015年時点においては石炭火力等による発電が多いため、EV等が普及しても、そのCO2排出量は82g-CO2/kmと、ハイブリッド車のCO2排出量よりも高いものとなっています。一方で、原子力発電の多いフランスは、すでに5g-CO2/kmと、相当程度低いCO2排出量となっています。各国・各メーカーが環境適合車に舵を切っていく中、そのCO2排出量インパクトは各国の電源構成により大きく影響を受けるため、EVの普及と電源構成は両輪で考えていく必要があります。このように、EV等の需要側の脱炭素化に向けた技術を推進する上でも、電気を供給する電源にも注視していくことが重要です。
- ・ 蓄電池は、バックアップ無しでの成立を前提に、1日の需要全体の3日分の容量が必要と仮定。
- ・ 電力1kWhあたりの蓄電池コストは「蓄電池設備費用(万円/kWh)×蓄電池設備量(kWh)÷償却年数÷総電力需要(kWh)」で計算。
- ・ ここでのパリティは、家庭用・産業用の電気料金水準を想定(系統を通してバックアップ火力も活用した分散型再エネが、系統電力と同コストとなる「グリッドパリティ」等の定義とは異なる点に留意)。
- ・ パリティから再エネ発電費用、抑制費用、系統費用を差し引いた1kWhコストを、パリティ達成のために必要な蓄電池コストと定義。
- ・ 【第132-2-12】図中に記載の蓄電池コストは電池パックのコストを表し、システム全体では5~10倍のコストとなると仮定。
- ・ パリティは人件費・材料費を考慮すると成立しない可能性あり。
- ・ 「調整コスト」には抑制費用、系統費用を含む。
- ・ 以上の前提に基づき、資源エネルギー庁推計。
③ 再エネ先進国に学ぶ再エネ普及社会の現状と課題
ドイツやデンマークは発電比率でみると再エネ比率がドイツ29%(太陽光6%、風力12%、安定再エネ11%)、デンマーク66%(太陽光2%、風力49%、安定再エネ15%)となっており、日本の15%(太陽光3%、風力1%、安定再エネ11%)と比べると再エネ先進国と言えます。将来的に再エネの主力電源化を目指す我が国が、将来直面する課題に対して、先行している各国がどのように対応しているかを学ぶことは大変有意義なことです。本項では、再エネ、特に太陽光や風力などの変動再エネが普及している欧州諸国において、どのように電力需給のバランスを調整しているか紹介します。
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
(ア)国外送電網の利用を通じた電力輸出入による調整
ドイツとデンマーク国内における電力需給の状況と電力輸出入による調整力について紹介します。
(i)ドイツにおける電力需給と調整力
2017年の4月29日から30日における電力需給の構造を例にあげます。
ドイツは、国内の電力需要の増減に対応するため、供給量が変動しない水力、バイオマス、原子力等に加え、変動電源である風力や太陽光の増減に対して、石炭火力や他国との送電網を通じた輸出入で調整している需給構造になっています。特に、昼間12時頃の太陽光の発電量が増えている時間帯では、石炭火力の調整では吸収できず、この余剰電力を国外への輸出により調整しています。一方、18時から24時の時間帯は、国内の電力需要に対して、供給が十分追いつかず、他国より送電網を通じて輸入しています。こういった輸出入を、送電網を介して柔軟に行っているという特徴があります。
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
(ii)デンマークにおける電力需給と調整力
デンマークでは、風力発電の設備容量が非常に伸びています。2017年の5月11日から13日における電力需給の構造を例にあげます。
国内の電力需要の増減に対して、石炭、天然ガス、石油による調整を行っていることがわかります。太陽光に加え、特に風力が大きく発電している5月12日の昼間12時前後の24時間においては、国内の調整電源では吸収できず、大量の余剰電力を国外に輸出することで電力の需給バランスを行っています。
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
(iii)ドイツ・デンマークにおける電力輸出入の状況
ドイツとデンマークのそれぞれの国内需要の規模は違うものの、変動再エネ比率や国外の輸出入による調整状況について、日本と比較しました。デンマークにおいては、変動再エネ比率は51%と高く、調整力の国外依存は、最大で80%を国外との輸出入で調整しています。ドイツにおいては、変動再エネが18%に対して、国外との輸出入による調整は最大で40%を占めています。ドイツとデンマークは、このように海外との送電網を活用することにより、変動再エネを柔軟に導入することができています。
一方、日本は、国外との送電網は連結されていないため、海外との送電網を通じた輸出入による調整は活用することはできない状況です。
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
(イ)国内電源による調整と課題
欧州の変動再エネ比率の高い国の中には、バックアップとして、CO2を排出する火力発電の比率が高い国があります。ドイツでは、2010年と2015年を比較すると、CO2排出量はほぼ横ばいです。その要因としては、再エネ増加によるCO2排出削減効果と、原子力の稼働減、石炭火力発電の稼働増、電力需要増によるCO2排出増加効果が相殺しあう関係になっていることが考えられます。日本が今後、再エネの主力電源化を進めるに当たり、参考となる欧州諸国として、日本と産業構造が類似しているドイツと、日本同様に島国である英国の国内の調整電源の構造とCO2排出量の推移を紹介します。
(i)ドイツにおける調整電源とCO2排出の推移
ドイツの需要は、2010年から2015年にかけて、微増しています。特に、電源構成では、再エネの割合が顕著に伸びており、一方、原子力は大きく減少しています。火力については、全体では微減ですが、その内訳は、石炭が微増、天然ガスが減少となっています。
この結果、CO2の排出量は、2010年から2015年において、全体としてほぼ横ばいとなり、再エネの大幅増加があったものの、そのCO2削減効果は限定されています。
(ii)英国における調整電源とCO2排出の推移
英国における2010年から2015年の電力需要は減少しています。電源構成では、再エネが大幅に増加、原子力が増加、火力は大幅に減少しています。特に、火力の内訳をみると、石炭、天然ガスともに大幅に減少しています。
この結果、CO2の排出量は、2010年から2015年において、大きく減少しており、1990年からのCO2削減量も着実に減少しています。
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
(3)ゼロミッション企業・総合エネルギー企業の経営戦略について
次に、本項では、企業の動向を見ていきます。世界のリーディング・カンパニーは、脱炭素化やデジタル化といったメガトレンドを踏まえ、戦略的な投資や事業構造転換を進めています。その上で、「原子力・再エネ等の脱炭素化を志向する企業」や「コア事業を中心にデジタル化、グローバル化を志向する企業」など手法は様々です。
① ゼロミッション企業の経営戦略について
ここでは、ゼロエミ電源に注力した企業の経営戦略について紹介します。
デンマークDONG社は、化石資源採掘企業を出自とし、DONG Energy社として電力事業に参入、その後、地理的要件や環境意識の観点から、主に洋上風力発電事業で拡大してきました。2017年には、DONGEnergy社からØrsted(オーステッド)社に名称を変更し、石油・ガス上流事業から撤退を発表しました(DONGはDanish Oil and Natural Gasの頭文字)。
同社は、上記の変遷の中で、水力・ガス火力・陸上風力等のノンコア事業の売却を進め、その資金及びリソースを戦略事業である洋上風力に投入することで、洋上風力の開発・建設・所有・運転を一気通貫で実施することを可能にし、他社との差別化を図っています。また、洋上風力のコスト削減のため、風車の大型化や機器・システムの標準化等をグローバル大で推進し、その地位を確立するとともに、各国政府へ、海上利用ルール確立への働きかけも実施することで、市場を自ら創出しているところなどに同社の強みの源泉はあるといえます。
アメリカのエクセロン社は、世界で最も歴史のある原子力発電事業者のうちの1社であり、米国全土で事業展開する大手発電事業者です。同社の競争力の源泉は、エクセロン・ニュークリア・マネジメント・モデル(ENMM)といわれる、原子炉高稼働率ノウハウです(原子炉のプログラム、プロセス、手順、ビジネスツール、ITプラットフォーム等の継続的アップデートにより実現)。エクセロン社は、多くの事業者から様々な条件の原子炉を購入して、運営していますが、ENMMを着実に実践することで、同社の原子炉稼働率は、94.6%(世界平均80%)と高く、競争力の源泉となっています。
また、ENMMを発展させ、原子炉の運転期間を80年まで延長する米国のパイロットプロジェクトの実施にも関心を示しています。
② 総合エネルギー企業の経営戦略について
デジタル化、分散型のトレンドを捉えて顧客重視のビジネスに注力する企業や、グローバルでの脱炭素化エネルギーインフラ(電気・ガス・水素)などに重点投資をする企業、またはその両方を追求する企業があります。これらの企業の特徴は、コア事業を中心にデジタル化やグローバル化で強みを拡大する、というところにあります。
世界のスーパーオイルメジャーであるShell社は、将来のマクロトレンドは、エネルギー転換とデジタル化であると捉えた上で、2070年までの独自シナリオを分析しています。同社は将来の不透明性を踏まえ、あらゆるシナリオへ対応できるよう、ガス、バイオ、再エネ、CCS等新分野への長期的視点での投資を実施するとともに、既存の事業ポートフォリオの組換えについても着実に実施しています。
フランスの大手エネルギー企業であるEDF社やEngie社は、従来のエネルギー販売だけではなく、特に顧客重視の新サービス創出に注力しています。スマートメーターの情報から顧客満足度の高いサービスのビジネス化や、EV等の異分野サービスとの連携など、各社、コモディティ販売ではないエネルギー事業者を志向しています。また、Engie社は、ガス事業出自ということもあり、再エネのバックアップ電源としても重要な天然ガスに着目し、水素やバイオマス由来のガスを用いることで脱炭素化を進める開発や投資も実施しています。
(4)2050年に向けたゼロエミッション技術について
2050年に向け、各国・各企業・有識者が、技術イノベーションの重要性を発信しています。エネルギーの分野においても、従来の枠を超え、AIやIoTなど情報産業との融合により、過去には予測できなかった速度で環境が変化してきており、今後もそのトレンドは加速すると考えられています。ここでは、エネルギー技術の革新について、ゼロエミッションの視点で掘り下げていきます。
① 期待されるエネルギー技術・破壊的イノベーション創出の仕組み
オーストラリアと我が国は、同国ビクトリア州の豊富な石炭資源から水素を製造し、日本に輸送するプロジェクトを実施しています。水素サプライチェーンを構成する技術のうち、①褐炭ガス化技術、②液化水素の長距離大量輸送技術、③液化水素荷役技術を実証中であり、2017年12月に決定した水素基本戦略の中核となるプロジェクトのひとつであるとともに、水素社会実現の選択肢として注目されています。また、水素社会の担い手のひとつであり、我が国を代表する企業のトヨタ自動車は、燃料電池自動車を含む車両の電動化を進めています。各国が、ZEV規制等を導入する中、我が国の運輸分野CO2排出量の約9割を占める自動車分野においても脱炭素化は重要な要素です。同社は、この世界的潮流と顧客ニーズを踏まえ、「車両の電動化」という方針を推進しています(電動化は、EVだけでなく、HV、PHV、FCVを含む広い概念)。
再エネ以外のゼロエミ技術として、SMRについても世界的に注目が高まっています。2026年にSMRを商用化予定のNuScale社によると、既存原子炉と比較し、安全性・経済性・負荷追従可能性という3点が特徴です(安全性:冷却水の自然循環により電源・注水無しで炉心冷却が可能。事故リスクを低減させることにより、緊急時避難計画区域をサイト境界に限定/経済性:設置の簡素化やモジュール工法によりコスト低減・工期圧縮を実現/負荷追従可能性:変動再エネに対する負荷追従が可能)。また、CO2を排出しない水素製造源など多様な用途に活用できる可能性もあり、利用拡大が見込まれます。
米国エネルギー省のエネルギー高等研究計画局(ARPA-E)初代局長であり、Google副社長も務めたスタンフォード大学教授のアルン・マジュマダール氏は、世界のエネルギーシステムは変革期を迎えており、①脱炭素化②デジタル化③多様性をポイントに挙げ、特に、シェール革命、再エネ・蓄電池の低コスト化、デジタル化、水素とCO2によるメタン・エタノール精製等が、世界のエネルギーシステムの変革をけん引するイノベーションであるとしています。さらに、破壊的イノベーションにおいては、基礎研究と(リスクが伴う)商用化の段階における政策的支援の重要性及び、プログラムリーダーへの全権委任と独立した雇用形態の重要性を、同氏のARPA-Eの経験も踏まえて主張しています。
上記のような示唆、さらには2050年に向けた要請を踏まえて、我が国のエネルギー技術については、電力のゼロエミ化や水素などの供給側のイノベーションだけではなく、運輸・産業・民生などの需要側のイノベーションについても、エネルギーの視点から取り組んでいく必要があります。また、世界全体での貢献をするという観点からは、こうした技術を国際的に展開していくことも重要な視点になってきます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
② エネルギー技術の革新によって変容する社会像
2050年の想定されうる社会像について、分野ごとにどのような可能性があるか、考えていきます。
まず、電力分野においては、電力消費等のデータ活用が進展することで省エネが進展し、エネルギー消費が抑制されていきます。また、再エネ技術の進化や蓄電・系統・取引の革新による再エネの最大限活用、さらに安全性が向上した原子力発電の活用、火力発電におけるCCUやCCS、水素利用により、電力のゼロエミッション化が実現する可能性が生まれます。
第二に、運輸分野においては、自動化によるエネルギー消費の大幅な効率化や、マルチマテリアル化などによる素材軽量化といった設計の最適化が進み、電力分野同様にエネルギー消費が抑制されるとともに、電動化による再エネ由来の電気や水素を含むゼロエミッションのエネルギー源の利用や、バイオ燃料等への燃料転換を通じて、運輸全体での排出削減が進んでいく可能性があります。
第三に、産業・ものづくり分野においては、開発・生産プロセスにおけるデータ共有やロボット・AI活用によってエネルギー消費の大幅な高効率化が進むとともに、電化や水素利用の拡大などの非化石エネルギーへの転換に加え、CO2の原料利用といった原料転換の技術の開発・普及などにより、従来では困難であった産業部門においても脱炭素化が進展する可能性があります。
最後に、民生部門として、業務・家庭における熱の使われ方についても、機器等の情報が繋がり、より効率的な機器の使用が可能となることや、ZEB・ZEHの進化・普及により、エネルギー消費が抑制されていき、加えて、電化や水素とCO2からガスを作り出すメタネーションなどの技術の進展により、ゼロエミッションのエネルギー源利用の選択肢が拡大する可能性が生まれます。
さらに、水素については各分野横断的に利活用が期待されます。電力部門では水素発電や脱炭素化LNG発電(カーボンニュートラルメタン)、運輸部門では燃料電池自動車、業務・家庭部門では燃料電池、産業部門では還元剤としての活用など、多くの分野において、脱炭素化への選択肢を提供します。一方で、水素供給源の脱炭素化や水素サプライチェーンの確立など、他のアプローチ同様に課題もあります。
上述の議論を踏まえて、次項では、エネルギー技術への期待と我が国産業の可能性について見ていきます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会資料
(5)各エネルギー技術のCO2削減インパクト、我が国企業の可能性
① エネルギー技術の世界におけるCO2削減インパクト
IEAによれば、世界のCO2排出量は、2015年の約320億トンから、アジア、インド、アフリカを中心とした新興国での排出量が増加し、2040年までに350億トンを超えるといわれています。温室効果ガス削減のため各国・各企業が新たなエネルギー技術の開発・導入に注力しており、特に2050年視点においては、CCS(71億トン/年)、原子力発電(32億トン/年)、風力発電(30億トン/年)などがCO2削減インパクトの大きい技術として注目されています。
② 低炭素化技術と脱炭素化技術
いずれの技術も重要な要素ではありますが、これまで見てきたように、現状、太陽光や風力などの変動再エネは、火力発電のような調整電源が必要であり、それのみでは、本当の意味での脱炭素化を実現することはできません。こうしたことを踏まえれば、個別の技術単体ではなく、複数の技術を組み合わせたシステムとして考えていくことが重要です。本節では、現状の「変動再エネ(風力・太陽光)+調整力(火力)」といった技術を、「低炭素化技術」と呼び、トータルで脱炭素化を実現できる「変動再エネ(風力・太陽光)+調整力(蓄電池、水素、CCS付き火力発電等)」や、「安定ゼロエミ電源(水力、地熱、原子力等)」などの技術を、脱炭素化技術と呼ぶことにします。低炭素化技術については、既に各国の技術競争が過熱しているところであり、この分野の技術での日本の強みを追求していくことも当然重要ですが、脱炭素化技術については、未だ各国が試行錯誤の段階であり、この分野を次なる技術競争のフィールドと捉え、我が国が主導していけるよう努力することが重要です。
③ エネルギー技術に関する期待と我が国産業の可能性
各エネルギー技術に関連する我が国の世界シェアを低炭素化技術や脱炭素化技術の観点から示します。低炭素化技術をみると、高効率火力発電は16%であるものの、太陽光発電は6.9%、風力発電については0.3%と非常に低いものとなっており、国際競争力が高いとは言い難い状況です。他方で、脱炭素化技術をみると、水素関連技術である燃料電池は66%、地熱は54%、蓄電池は29%と比較的高いシェアを誇っています
各技術のCO2削減インパクトと、我が国のシェアの関係を見ると、低炭素化技術については、技術の導入シーンが多く想定されることからCO2削減インパクトが大きく期待されている反面、我が国のシェアは低く、今後は新たなビジネスをどう模索していくかが求められるといえます。他方、脱炭素化のカギとなる技術については、我が国企業のシェアが高く、引き続き競争力を維持するとともに、今後の世界市場を創出・けん引していくことが、日本として求められているといえます。
【第132-2-27】大幅なCO2削減が期待されるエネルギー技術(技術ごとのCO2削減インパクト)
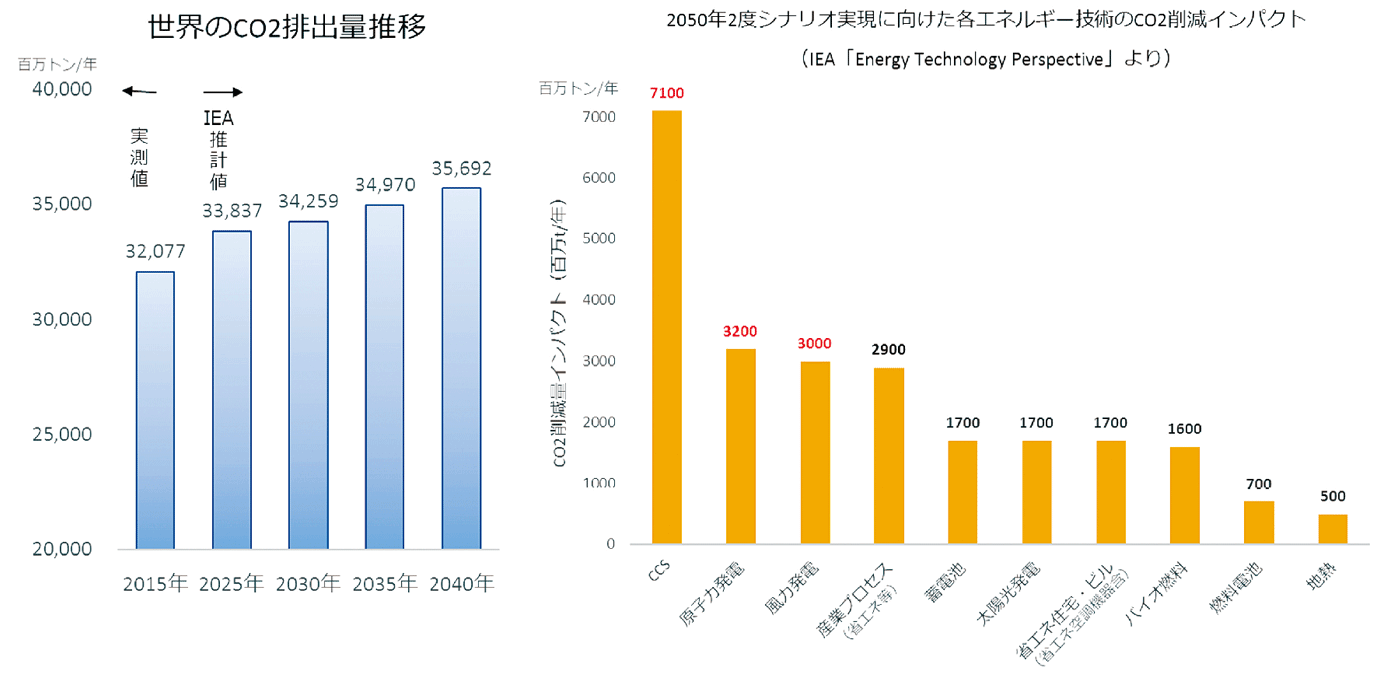
【第132-2-27】大幅なCO2削減が期待されるエネルギー技術(技術ごとのCO2削減インパクト)(ppt/pptx形式:50KB)
- 出典:
- IEA「World Energy Outlook2017」等より資源エネルギー庁作成
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
(6)2050年のエネルギー将来像に向けて
これまで見てきたように、現在我が国のエネルギーを取り巻く情勢は、今まで以上に多くの、そして複雑な変化が起きており、長期的な見通しは一層困難になっています。目指すべき「3E+S」も、脱炭素化への挑戦に加え、安全の革新、多様性と自国技術を重視したエネルギー安全保障、技術革新・競争力強化を踏まえた経済性の向上など、可能性と不確実性のある要素の上に成り立つものとなっていくことが予想されます。
2050年のエネルギーの将来像に向けては、こうした可能性と不確実性に柔軟に対処できるよう、多様な選択肢と複数シナリオを備えることとし、我が国のあらゆるプレーヤーが、あらゆるリソースを投資し、世界中のあらゆる市場で、あらゆる選択肢を追求する総力戦に対応していけるよう、今から準備をしていくことが重要です。
【第132-2-29】エネルギー技術における我が国の優位性(現在の日本企業シェア)
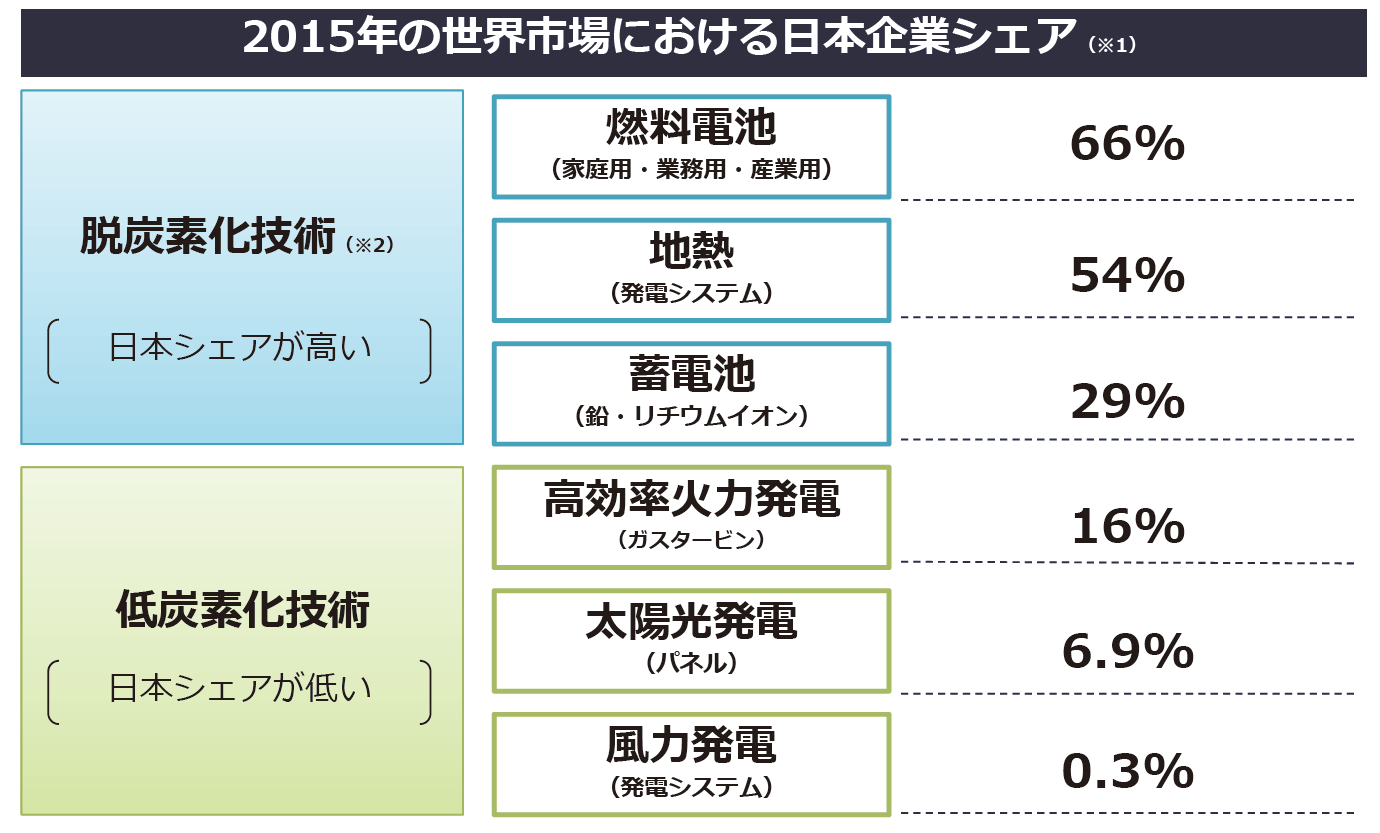
- (※1)
- 高効率火力発電は受注容量シェア、太陽光発電はパネルの出荷量シェア、それ以外は売上シェアにて試算。
- (※2)
- 脱炭素化技術には、原子力、水力、揚水発電(ゼロエミ電源由来の揚水)、バイオマス発電等も含む。
- 出典:
- 「NEDO_平成28年度成果報告書
日系企業のモノとサービス・ソフトウェアの国際競争ポジションに関する情報収集 情報収集項目(1)「モノを中心とした情報収集と評価」」より作成(燃料電池:「家庭用燃料電池(固体高分子形)・家庭用燃料電池(固体酸化物形)・業務・産業用燃料電池(リン酸形)・業務・産業用燃料電池(溶解炭酸塩形)」を引用、地熱:「地熱発電システム(全体)」を引用、蓄電池:「電力貯蔵設備用リチウムイオン二次電池・電力貯蔵設備用鉛二次電池・電力貯蔵設備用電気二重層キャパシター・電力貯蔵設備用リチウムイオンキャパシター」を引用、風力発電:「風力発電(全体)」を引用)、但し、出資比率が50%を超える企業を日本企業とみなす。太陽光発電:「太陽光発電競争力強化研究会 報告書 - 経済産業省」より(2015年太陽光パネル出荷量)。高効率火力発電(ガスタービン):MHI提供資料より資源エネルギー庁作成(出力170MW以上の大規模出力ガスタービンの受注ベース)。
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
- 出典:
- 「CO2削減インパクト」は「【第132-2-27】大幅なCO2削減が期待されるエネルギー技術(技術ごとのCO2削減インパクト)」・高効率火力発電:「経済産業省 次世代火力発電に係る技術ロードマップ」における2040年・非OECDアジアのみデータより。「日本企業の売上シェア」は「【132-2-29】エネルギー技術における我が国の優位性(現在の日本企業シェア)」より資源エネルギー庁作成
COLUMN
産業界によるグローバル・バリューチェーン貢献量の見える化
経済産業省は、2030年以降の長期の温室効果ガス削減に向けて、産官学からなる「長期地球温暖化対策プラットフォーム」を開催しました。2017年4月には報告書をとりまとめ、「国際貢献」、「グローバル・バリューチェーン」、「イノベーション」で我が国全体の排出量を超える地球全体の排出削減に貢献する「地球温暖化対策3本の矢」を基礎とした「地球儀を俯瞰した温暖化対策」を長期戦略の核としていく方針を打ち出しました。今後、温室効果ガスを大幅に削減していくためには、国内における自らの温室効果ガス排出削減を実現していくことは元より、温室効果ガス削減に資する環境性能の優れた製品・サービス等を国内外に展開し、世界全体の大幅削減の実現に貢献していくことが産業界の地球温暖化対策として重要です。
産業界が、自らの強みを認識し、温室効果ガス削減にさらなる貢献を果たしていくためには、自らの製品・サービス等の普及による貢献を見える化し、国際的な普及につなげていくことが大切です。我が国においては、産業界が自らの削減目標を設定し、その目標達成に向けた取組と評価を行う「プレッジ&レビュー方式」で成果をあげてきました。現在、産業界の地球温暖化対策の柱として進められている「低炭素社会実行計画」においても、「低炭素製品・サービス等による他部門での削減」、「海外での削減貢献」が位置付けられ、いくつかの業界において、グローバル・バリューチェーンを通じた削減貢献量の見える化に取り組んでいます。国際的に見ても、化学業界や電機・電子業界、電気通信業界が国際ガイドラインをまとめる等、各業界において削減貢献量の見える化・発信が行われています。一方で、こうした温室効果ガスの削減貢献量の定量化は、各業界や企業等に委ねられていたことから、考え方や根拠の説明には差異がありました。
こうした問題意識の下、グローバル・バリューチェーンを通じた削減貢献の取組の透明性を向上すととともに、産業界による取組をさらに広げていくために、経済産業省は、2017年12月に「グローバル・バリューチェーン貢献研究会」を立ち上げ、産業界の製品・サービス等による温室効果ガス削減貢献を見える化するための基本的な考え方を検討・整理し、2018年3月に「温室効果ガス削減貢献定量化ガイドライン」を策定しました。今後、本ガイドラインに基づいて、産業界は自らの削減貢献量を定量化し、投資家・消費者などのステークホルダーに対する情報発信を通じて、世界全体の排出削減に貢献しつつ、我が国のさらなる経済成長につなげていくことが期待されます。
グローバル・バリューチェーンでの排出削減貢献のポテンシャルを示す興味深い分析(長期的な温室効果ガス排出削減に向けた貢献量分析に関する調査)があります。その分析によると、世界全体で2010年比40%から70%の温室効果ガス削減を実現する対策・技術について、我が国が現行の世界シェア相当の貢献を行ったとすると、世界での排出削減は48.4億トンから62.0億トンに達するとされており、これは我が国の2016年度の温室効果ガス排出量の3.7倍から4.7倍に相当します。また、世界での排出削減貢献における日本の寄与分を達成する際の産業別の投資額から、国内で誘発されるGDPを算定すると、ベースラインGDP比0.7%から3.6%増加すると推計されており、世界全体で強調して排出削減対策が進められれば、温室効果ガス削減に資する環境性能の優れた製品・サービス等を国内外に展開し、世界全体の大幅削減に貢献することで、環境と経済が両立する可能性が示されています。
【第132-0-10】グローバル・バリューチェーンにおける日本の排出削減効果(2050年)
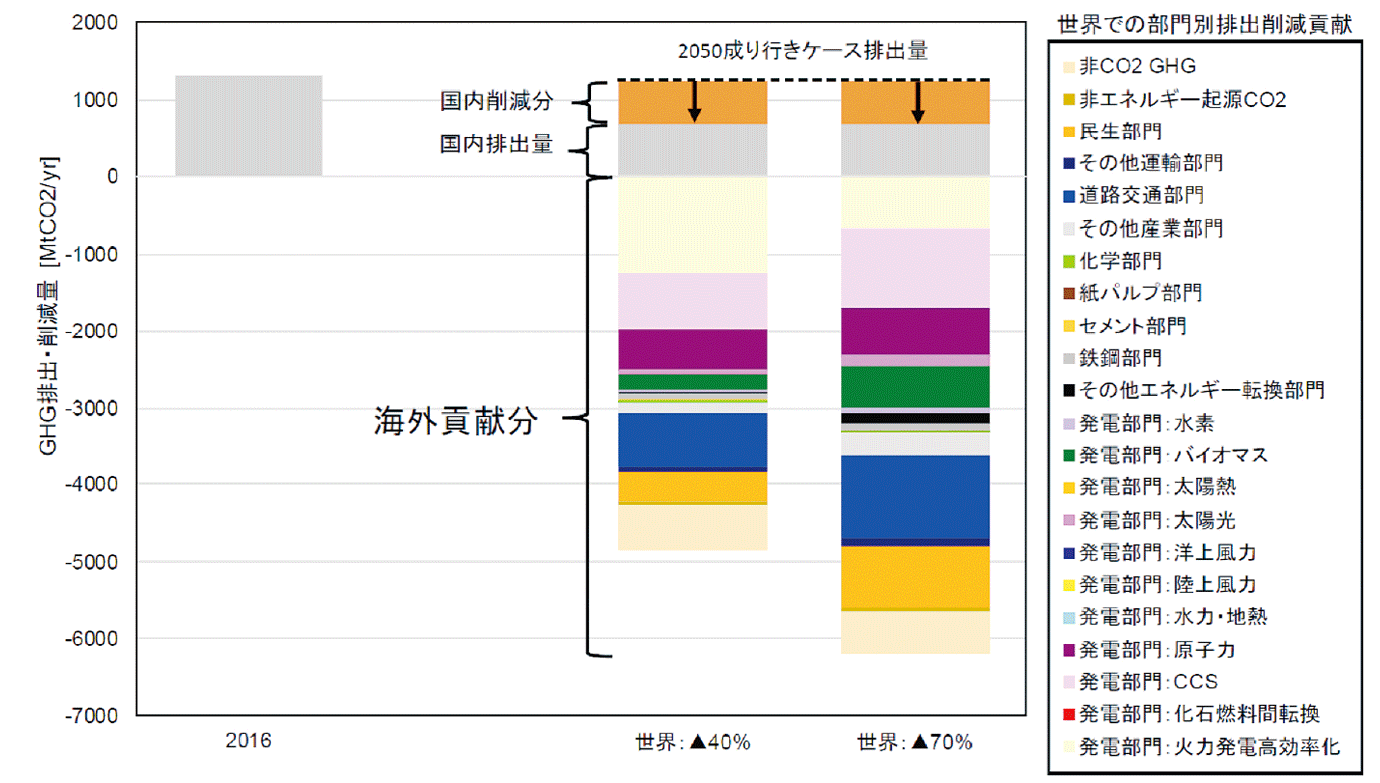
- ※
- 図に示される成り行きケース排出量や国内削減量については、我が国の実際の将来の排出量について予断をあたえるものではない。
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
- 2
- エネルギー情勢懇談会…我が国は、「地球温暖化対策計画」(2016年5月閣議決定)において、「我が国は、パリ協定を踏まえ、全ての主要国が参加する公平かつ実効性ある国際枠組みの下、主要排出国がその能力に応じた排出削減に取り組むよう国際社会を主導し、地球温暖化対策と経済成長を両立させながら、長期的目標として2050年までに80%の温室効果ガスの排出削減を目指す。このような大幅な排出削減は、従来の取組の延長では実現が困難である。したがって、抜本的排出削減を可能とする革新的技術の開発・普及などイノベーションによる解決を最大限に追及するとともに、国内投資を促し、国際競争力を高め、国民に広く知恵を求めつつ、長期的、戦略的な取組の中で大幅な排出削減を目指し、また、世界全体での削減にも貢献していく」こととしています。このため、幅広い意見を集約し、あらゆる選択肢の追求を視野に議論を行っていくため、経済産業大臣主催の「エネルギー情勢懇談会」を新たに設置し、検討を開始しました(第1回は、2017年8月30日)。
- 3
- チョークポイント:ホルムズ海峡、マラッカ海峡、バル・エル・マンデブ海峡(イエメンとアフリカ⼤陸の間にあり、紅海とアデン湾を隔てる海峡)、スエズ運河、トルコ海峡、パナマ運河、デンマーク海峡、喜望峰
- 4
- 「柔軟性の確保」は各国戦略の柔軟性が読み取れる記述の該当箇所を抜粋したもの。