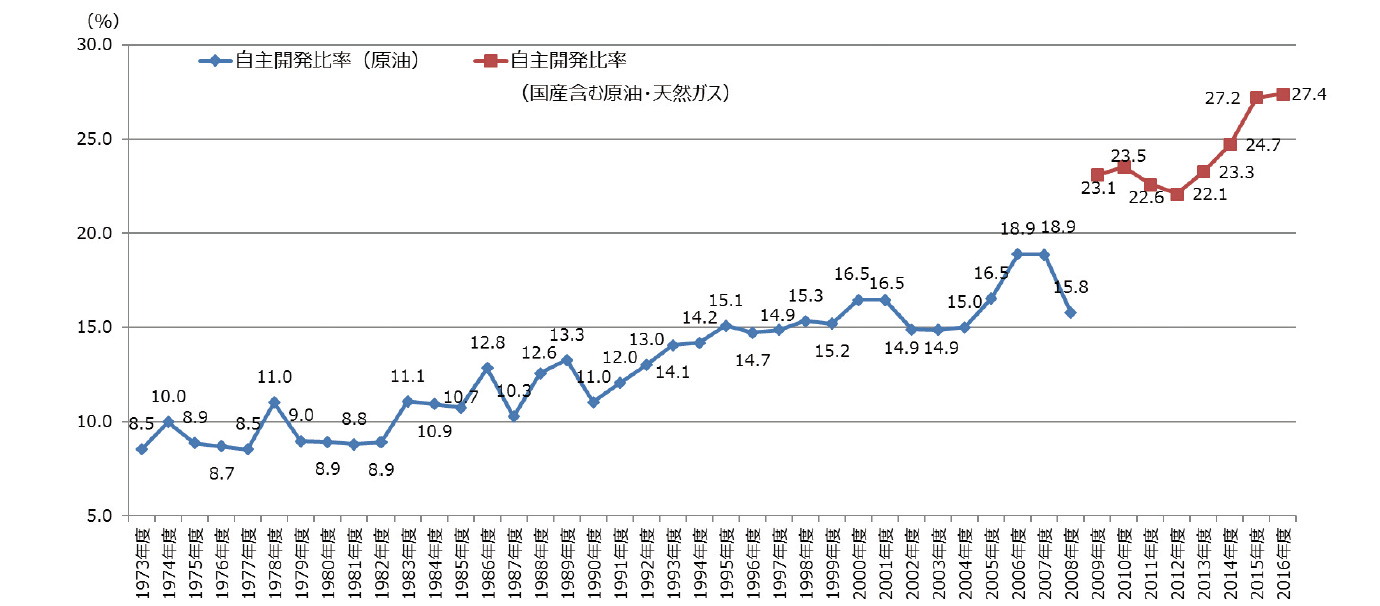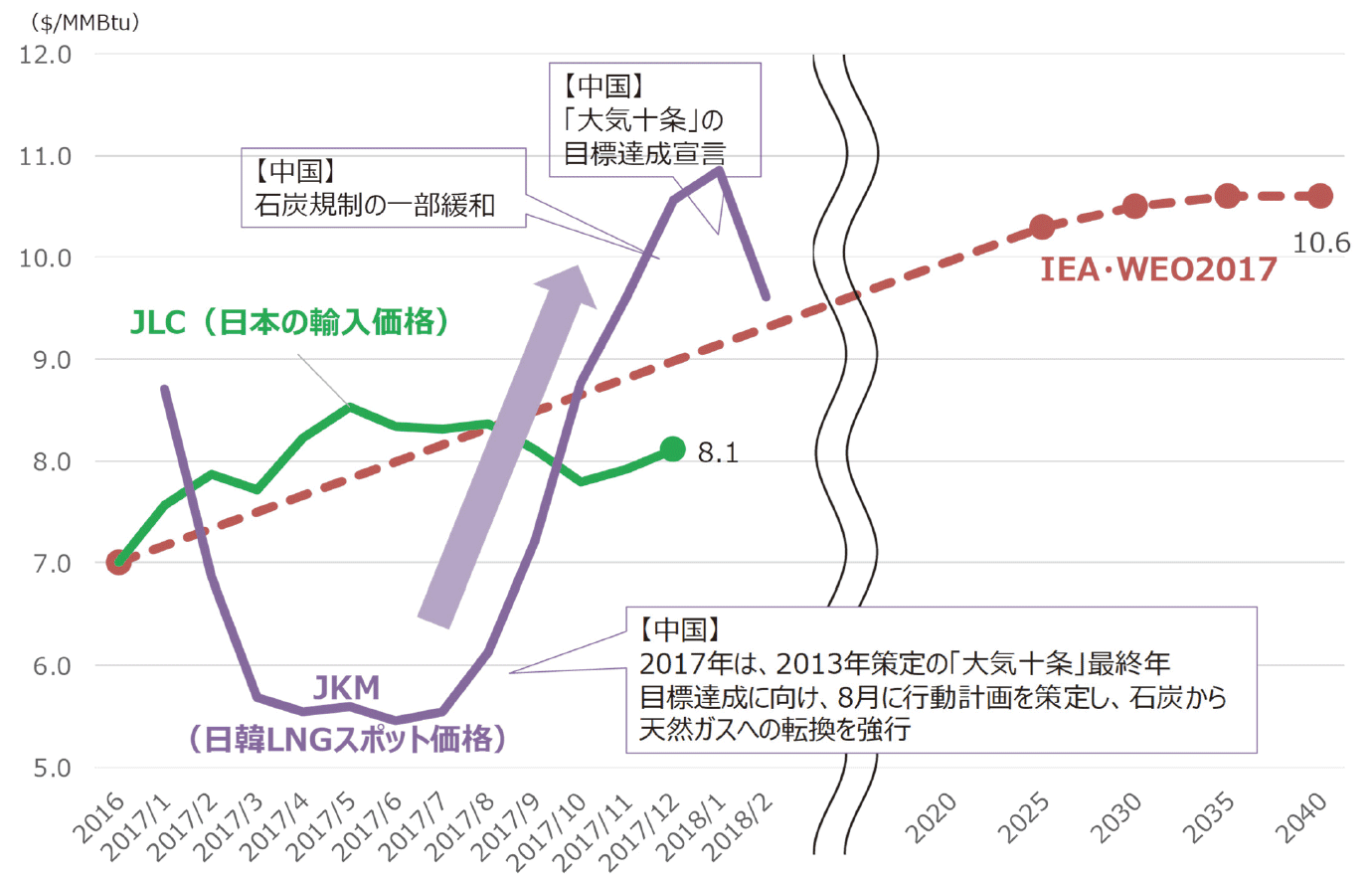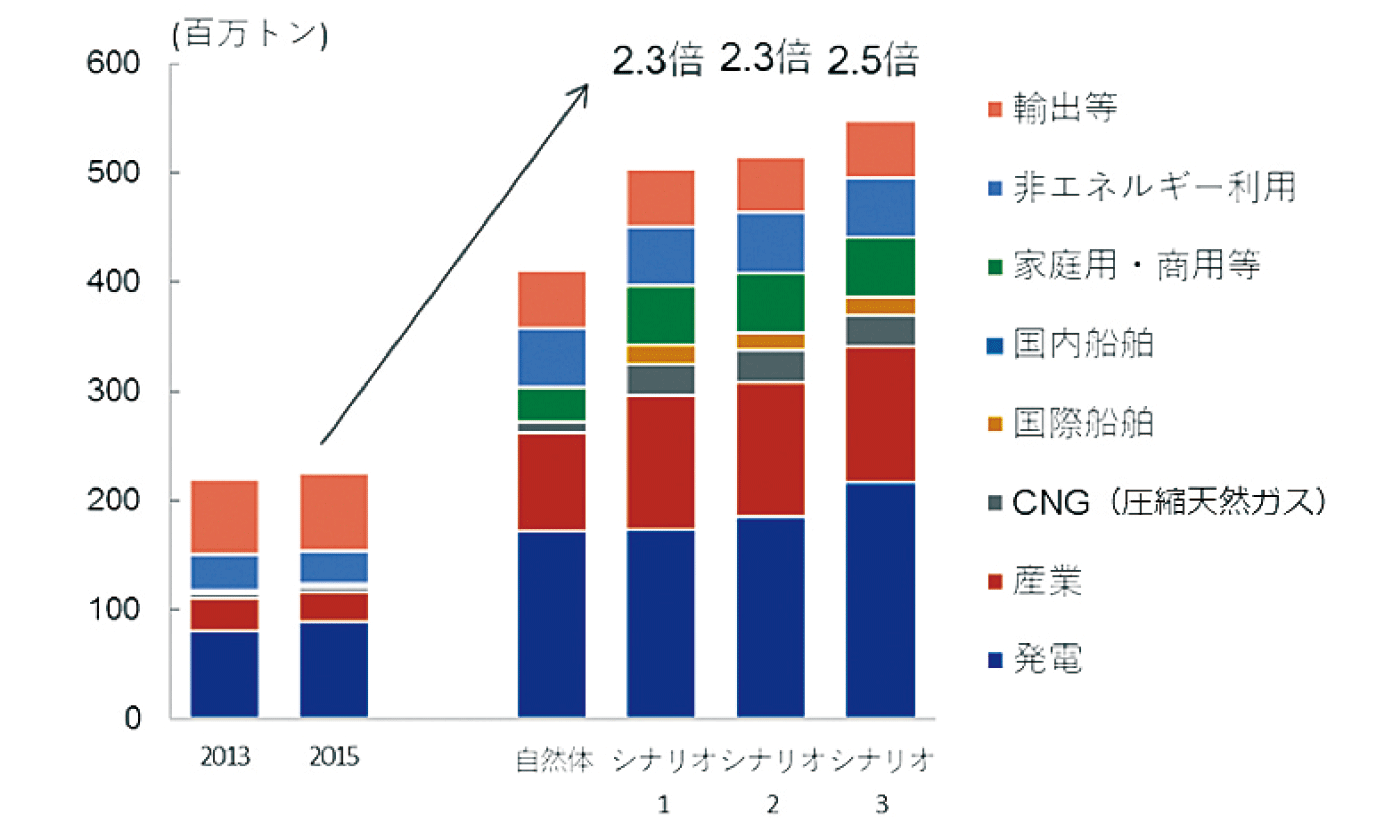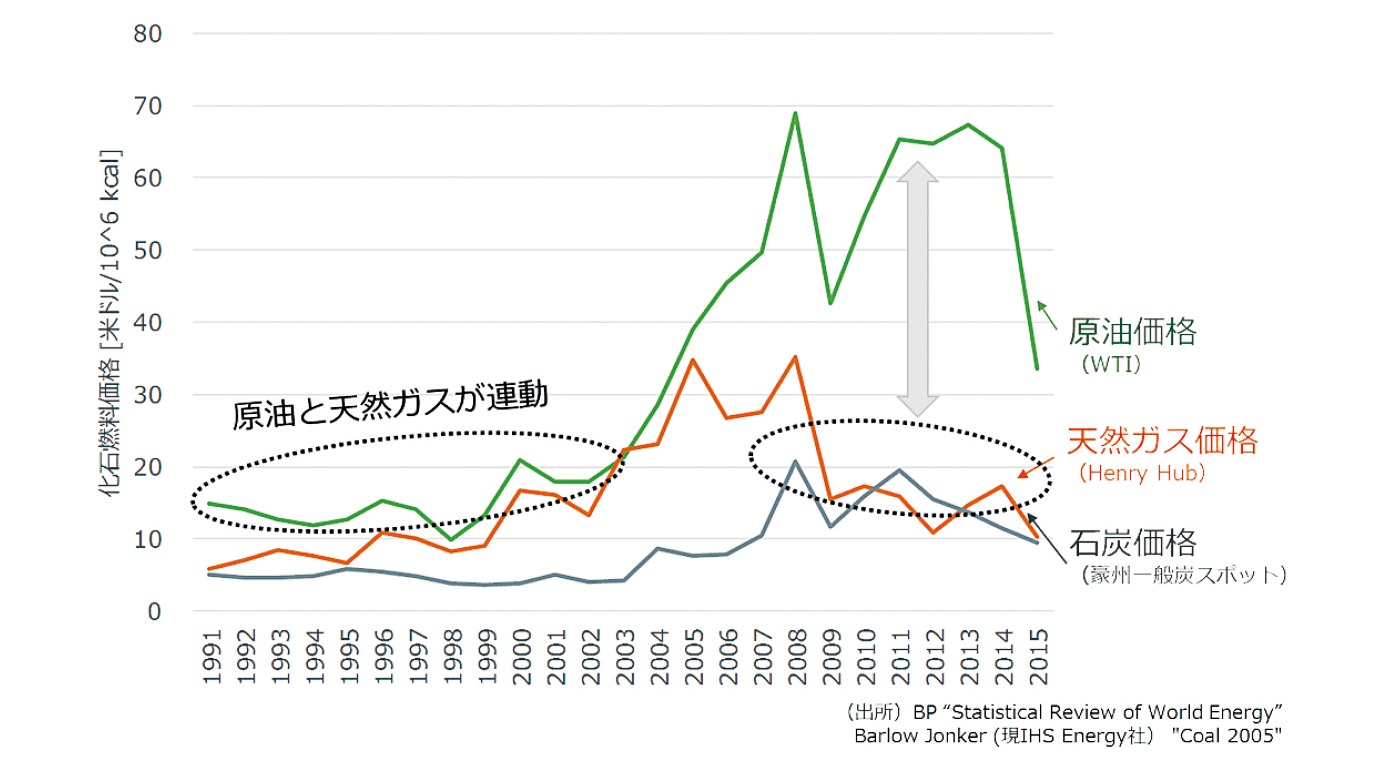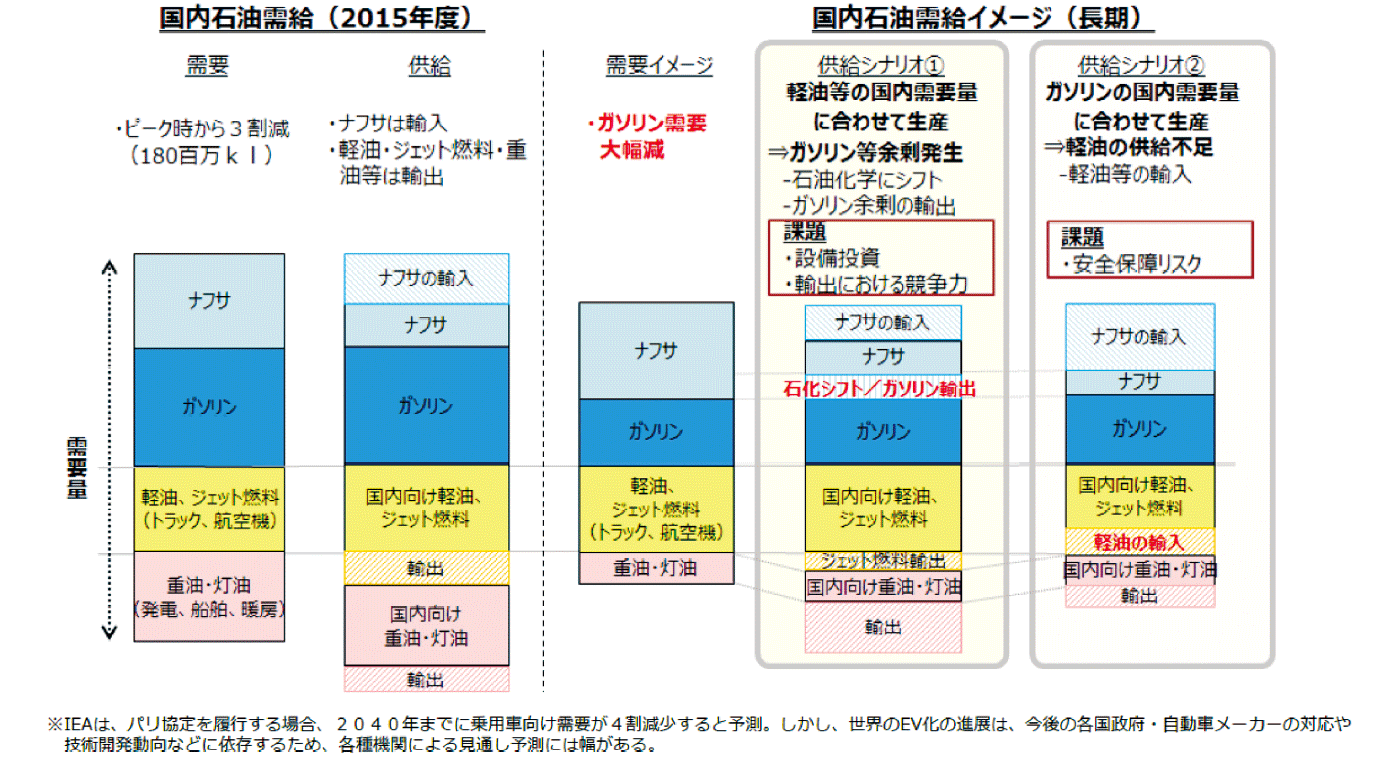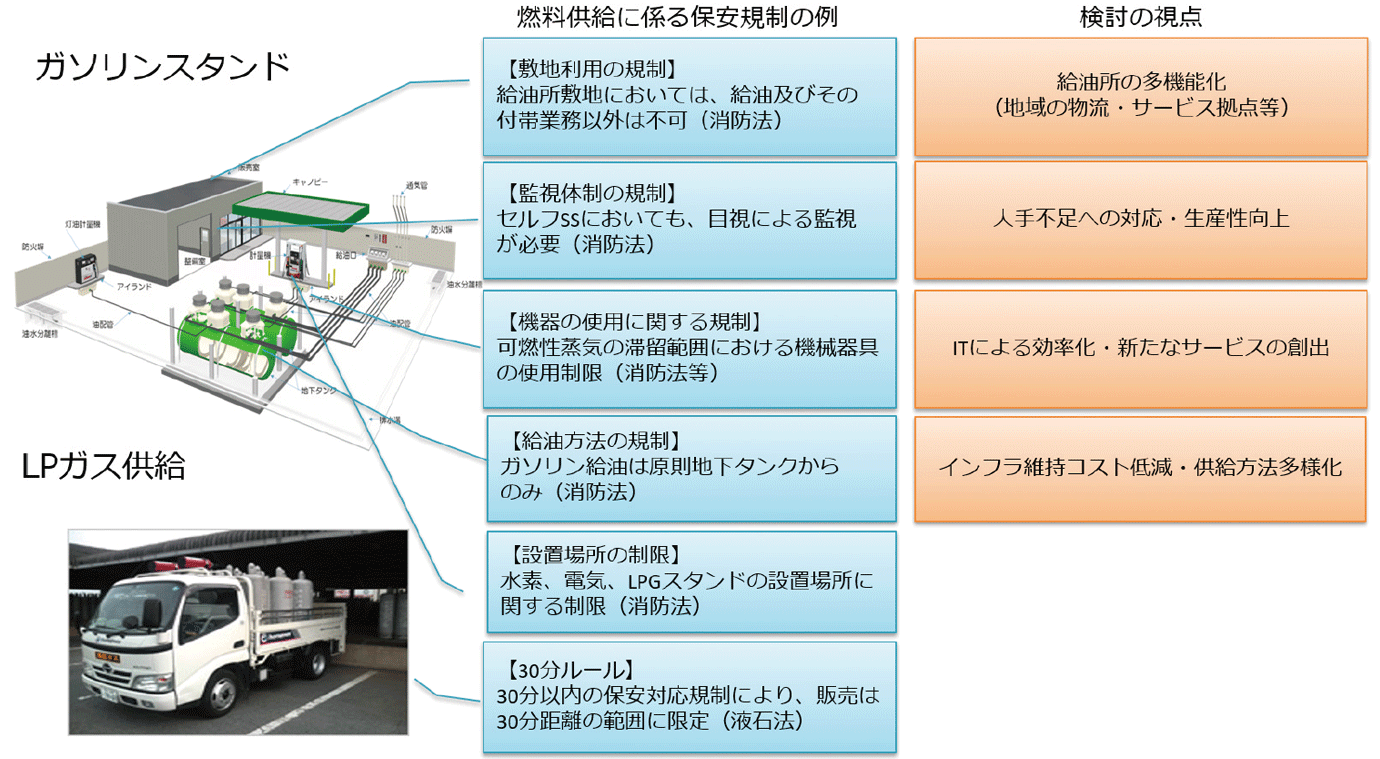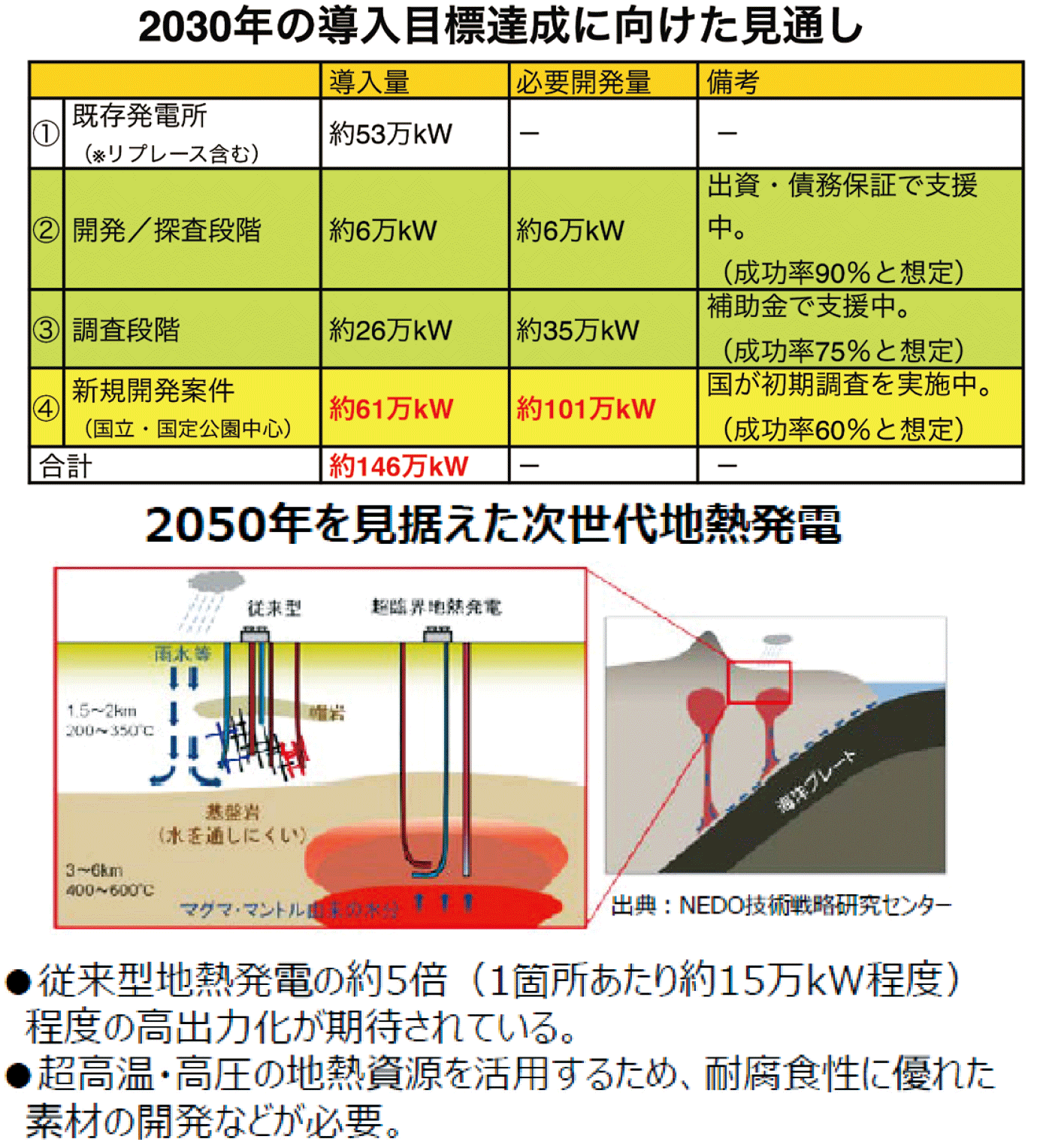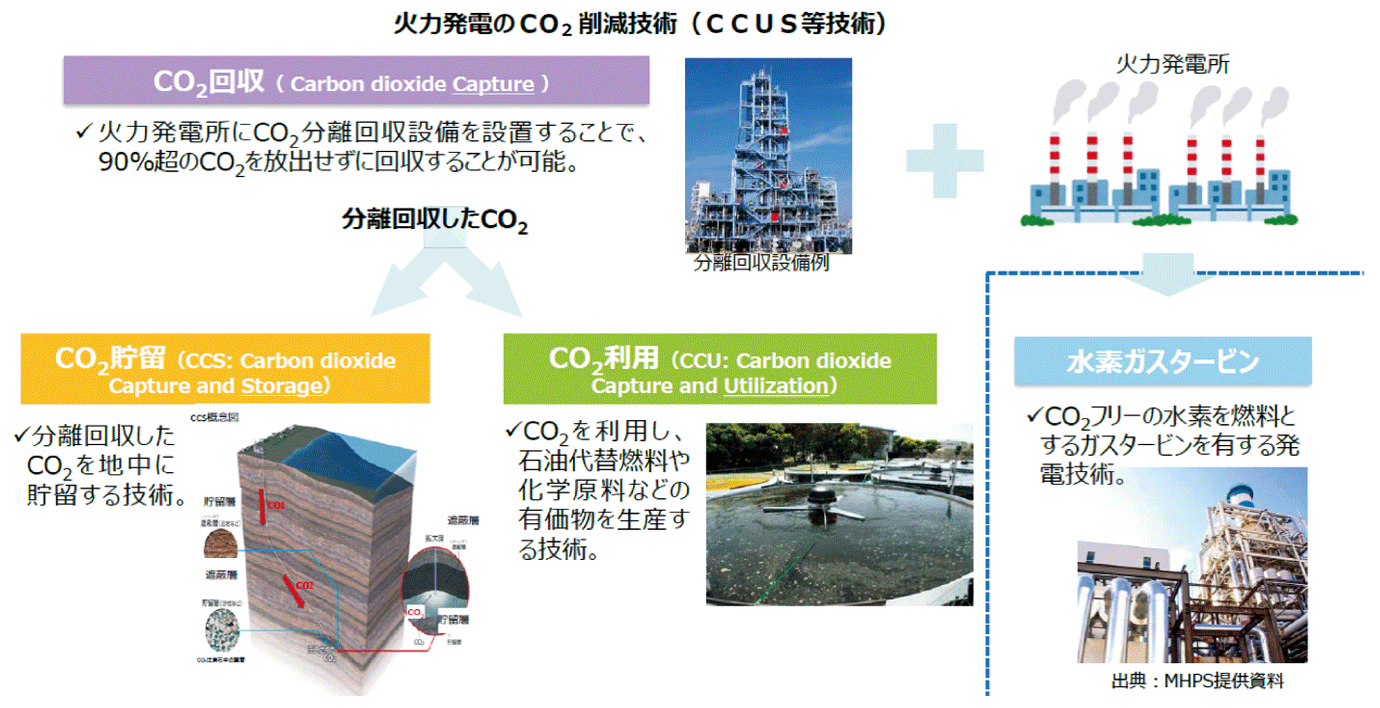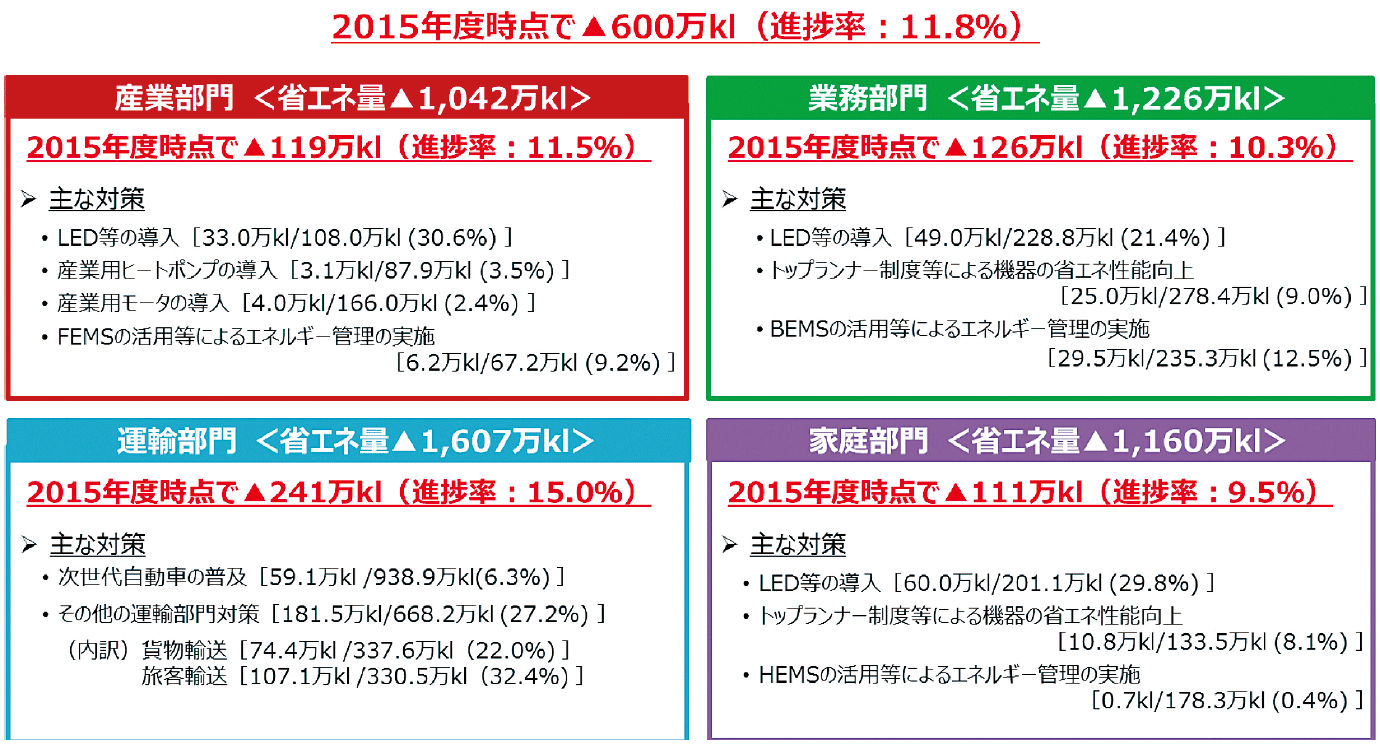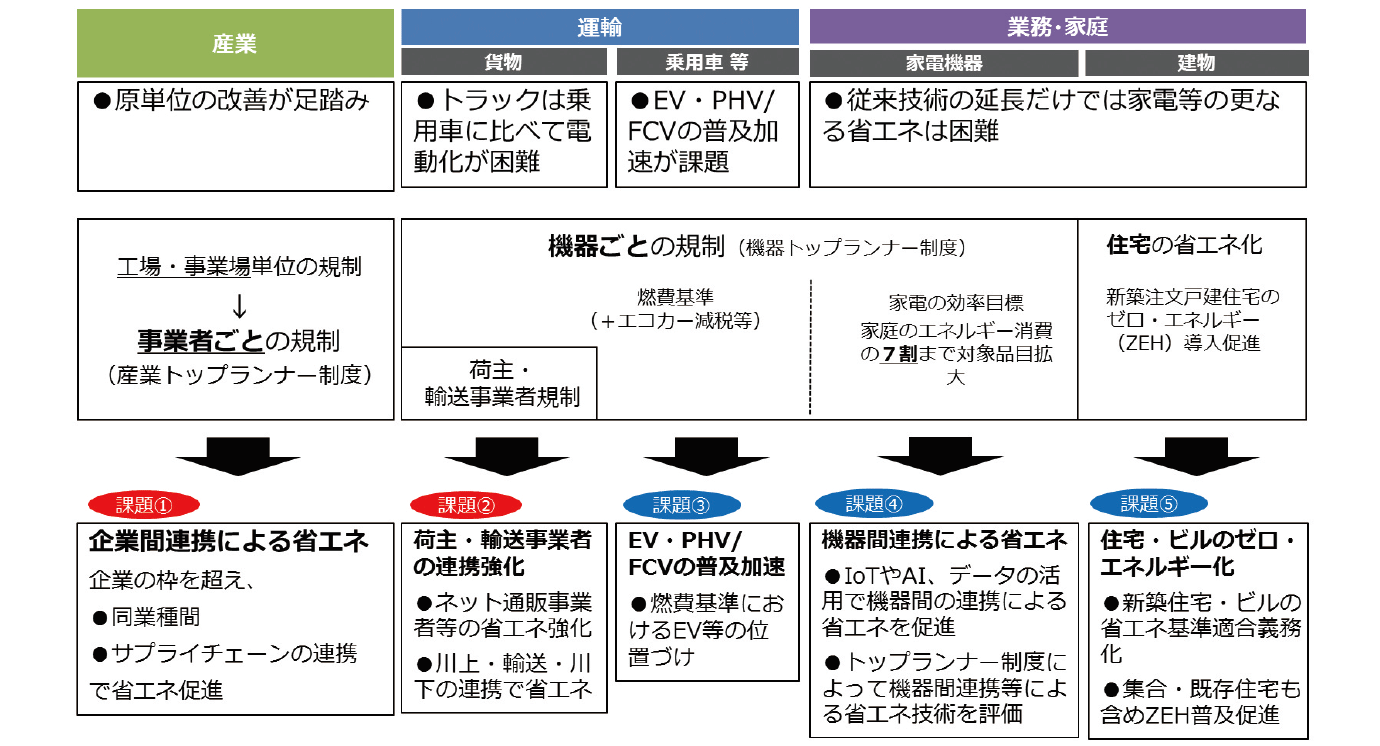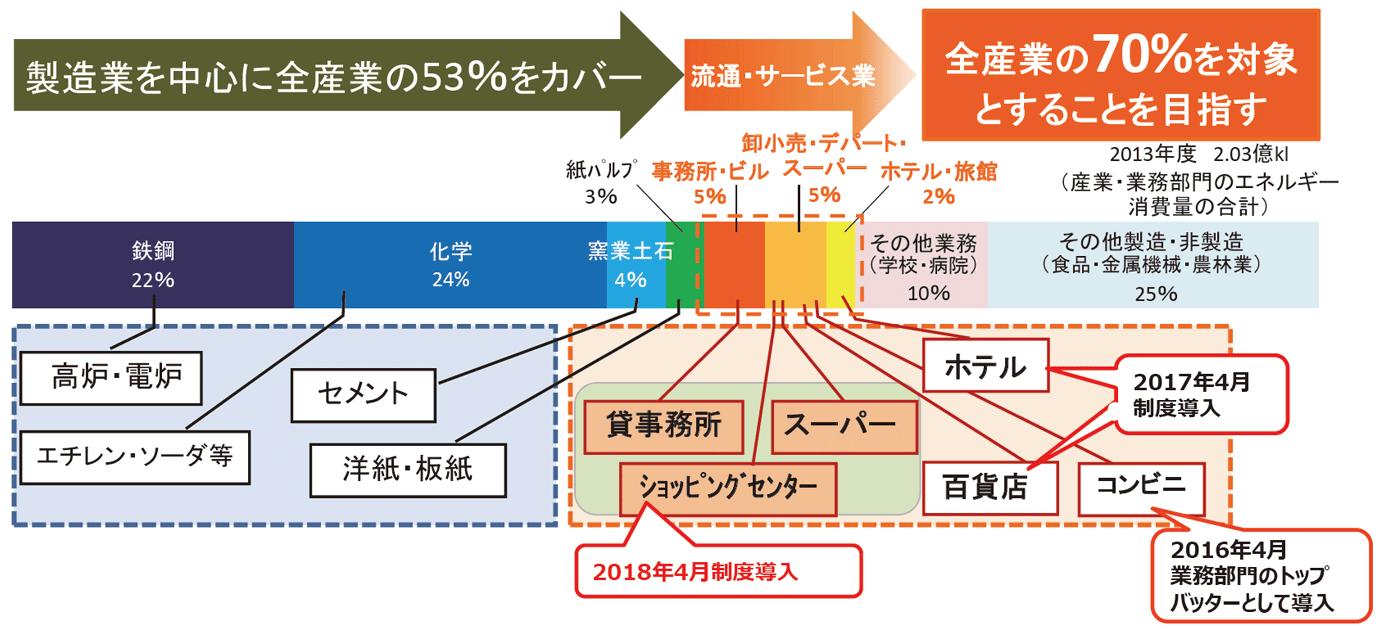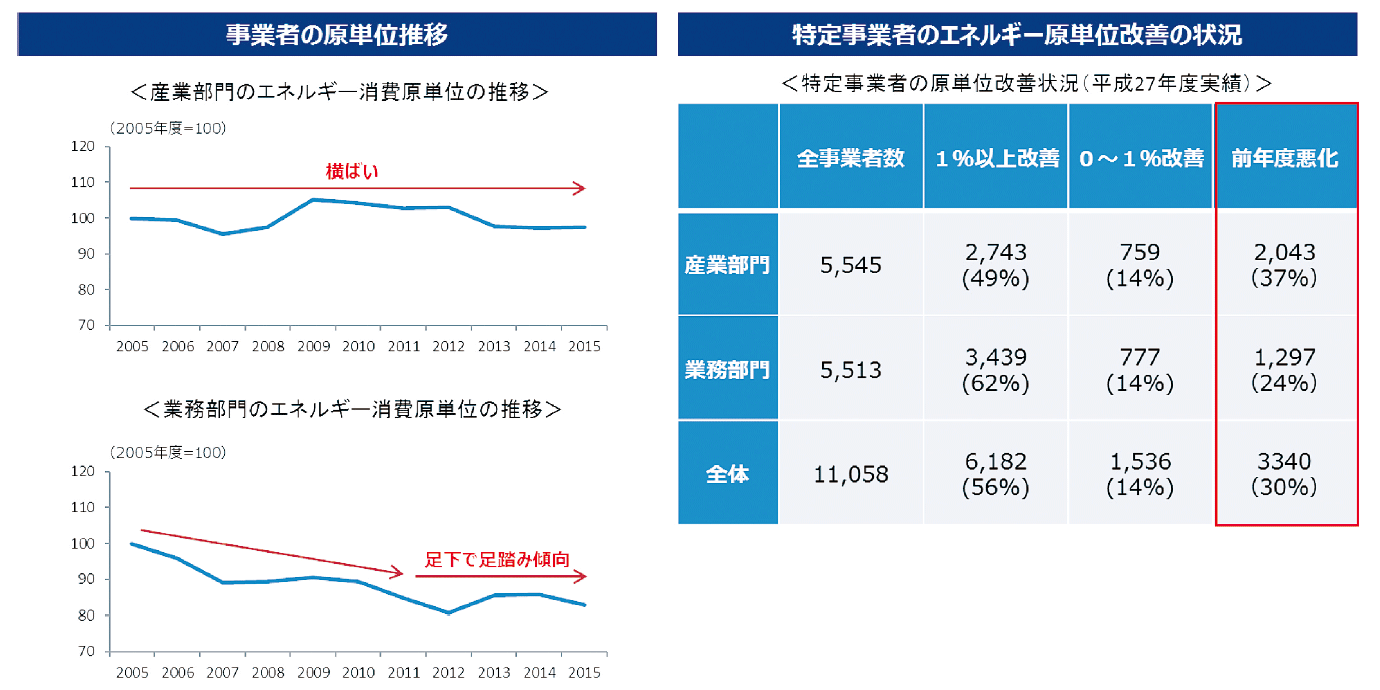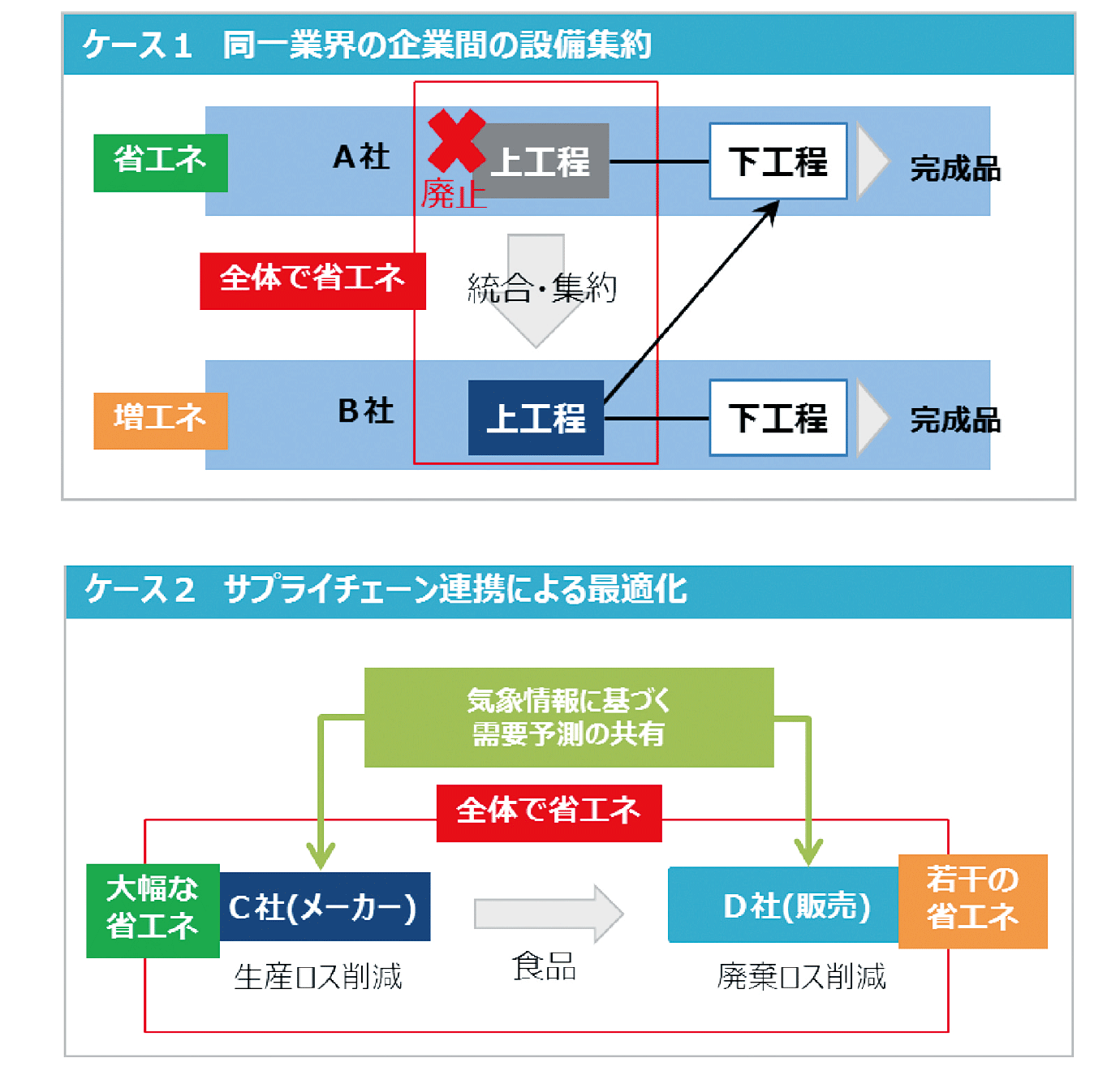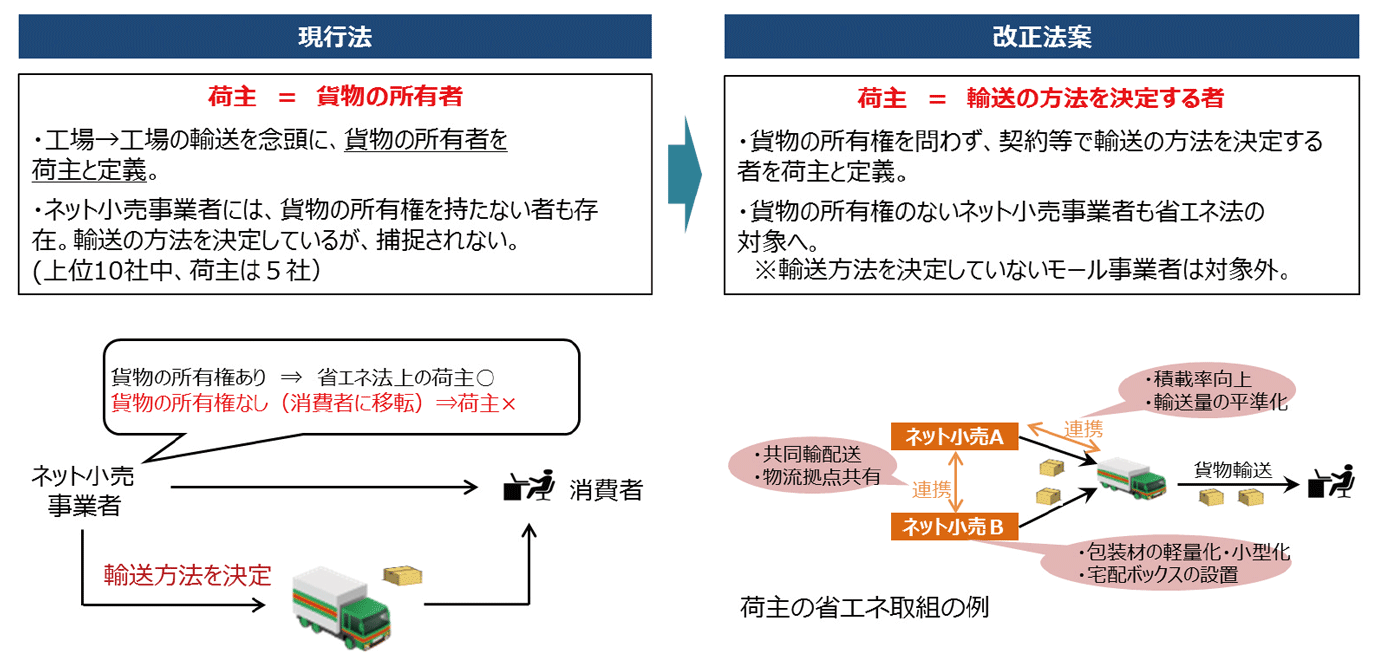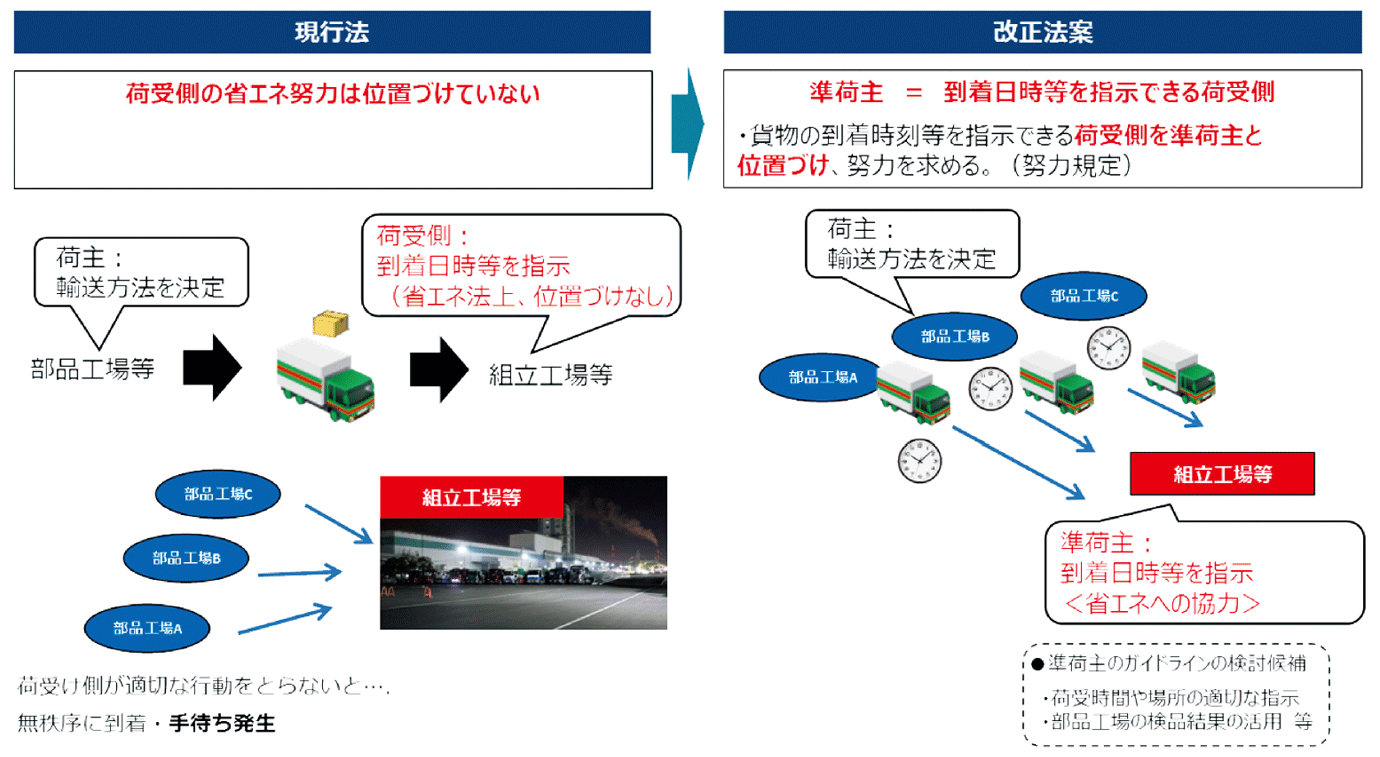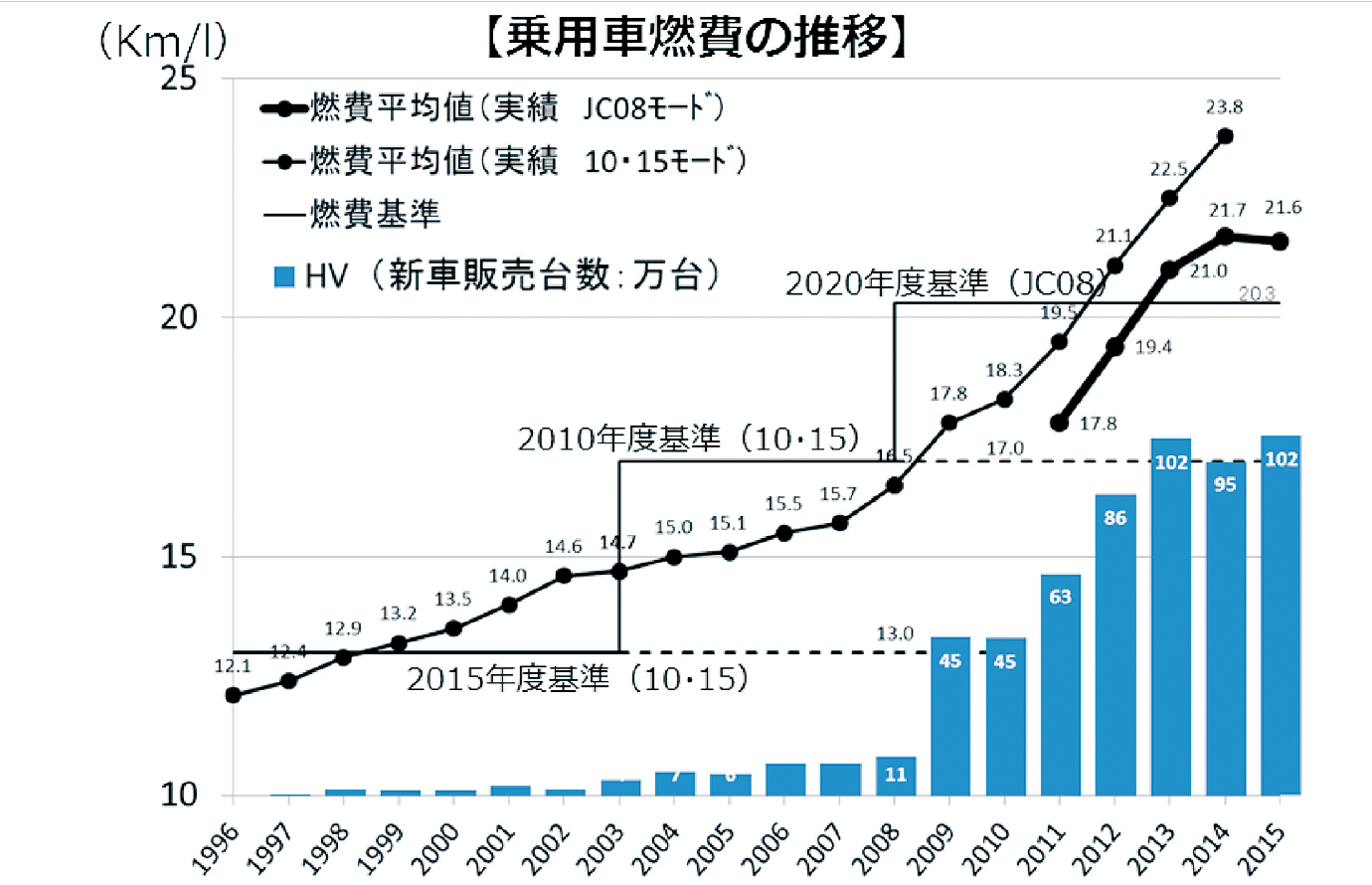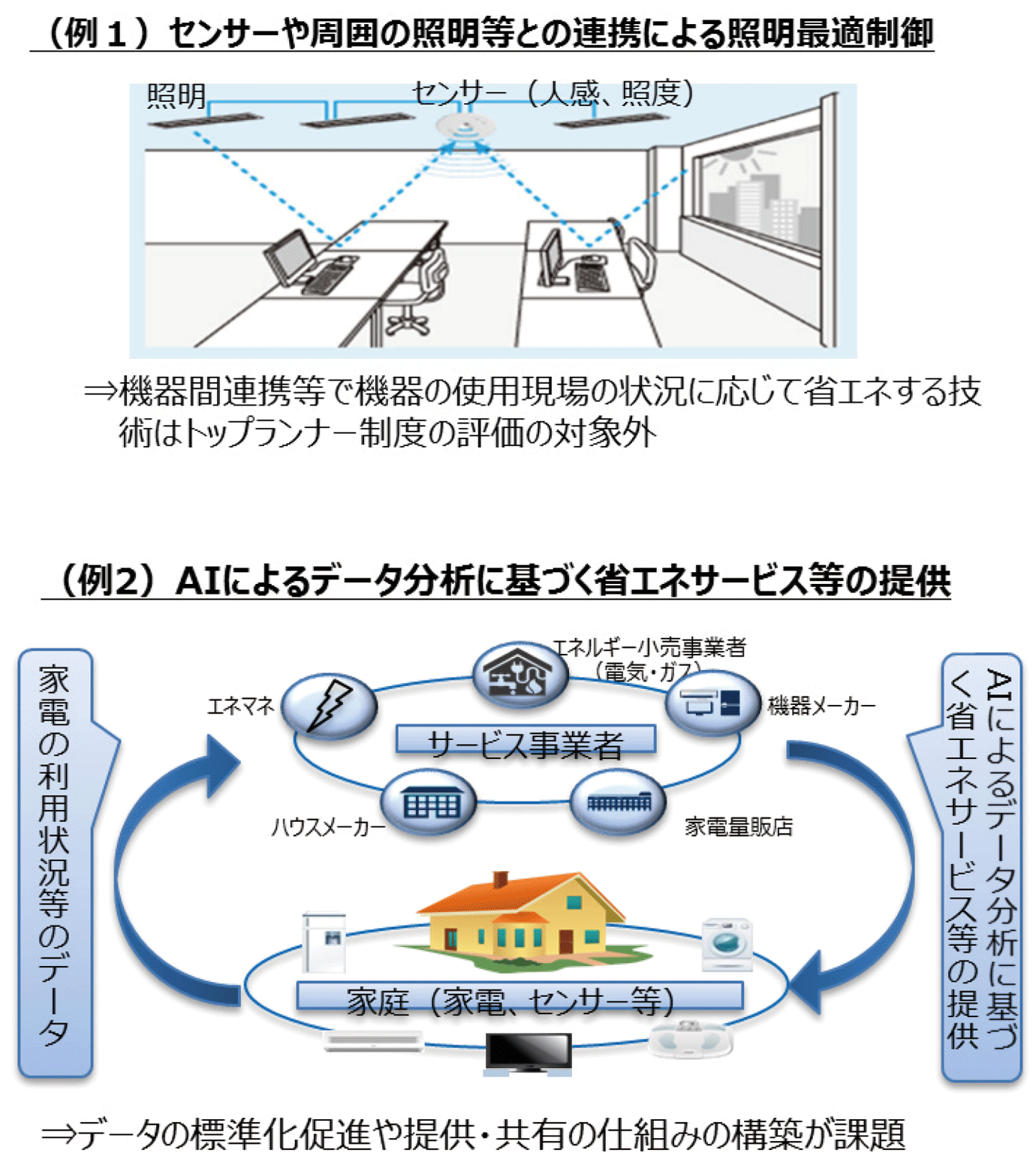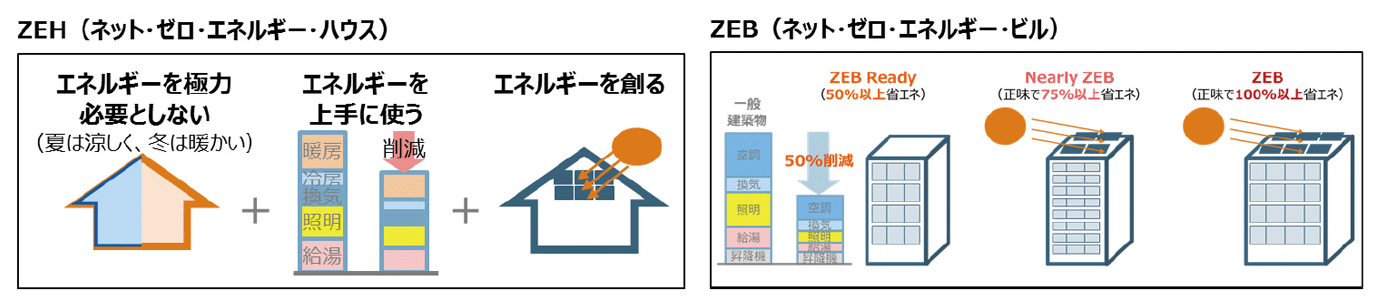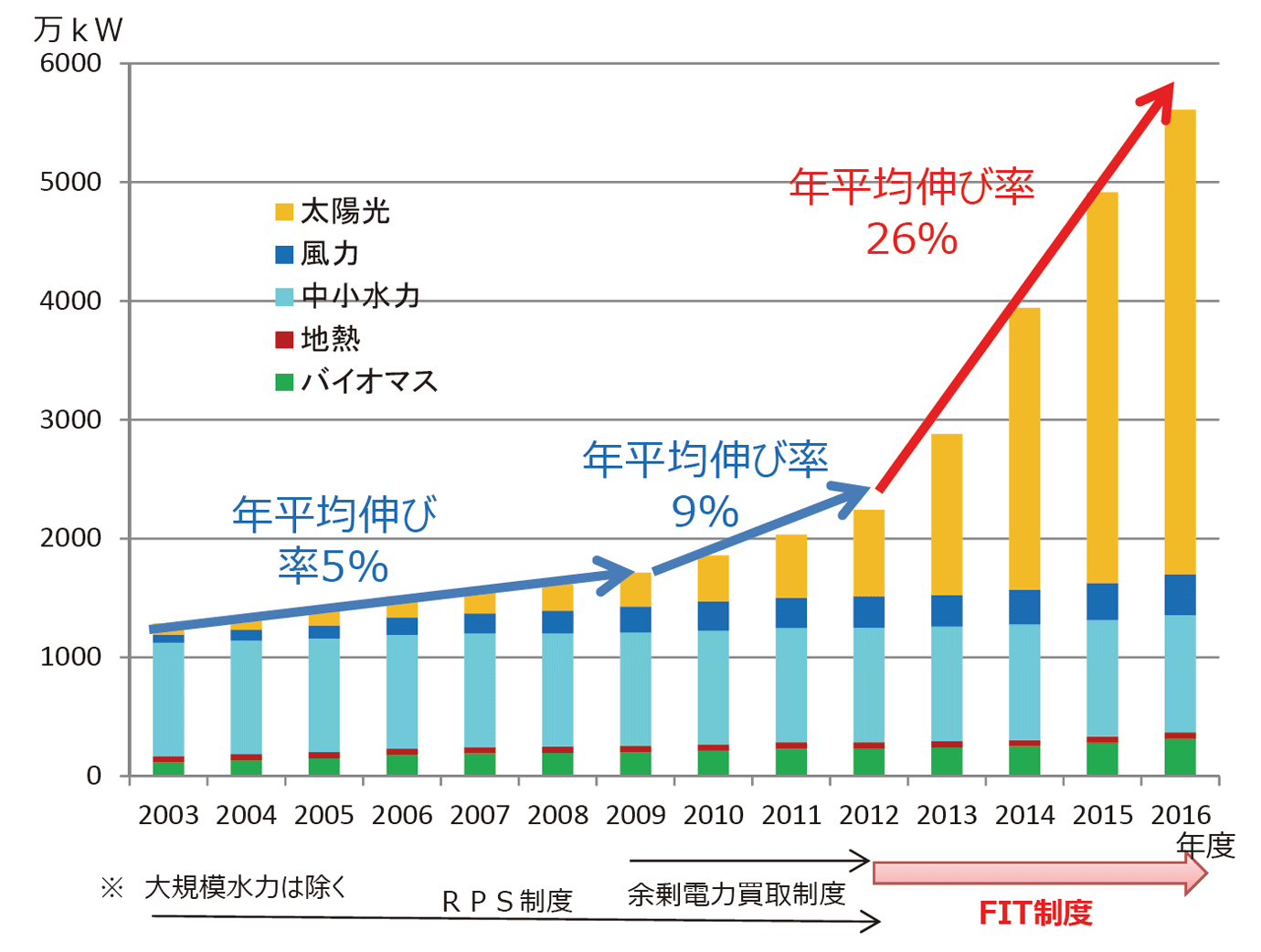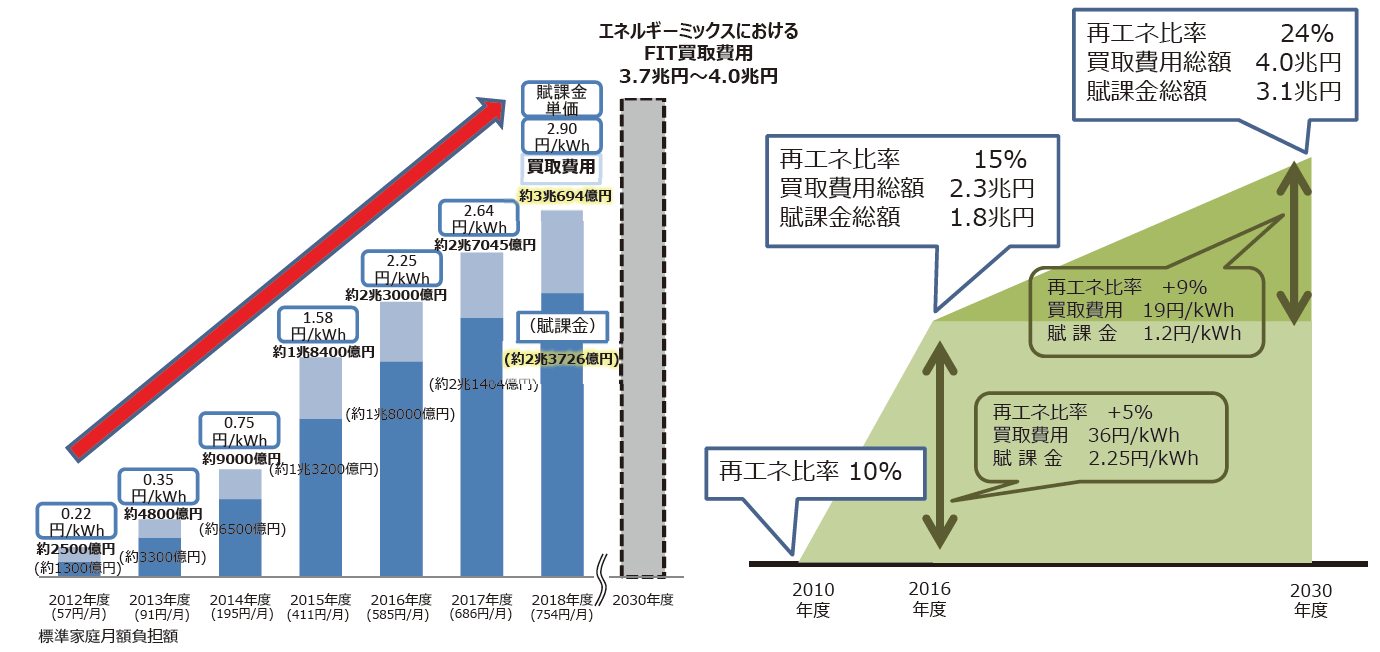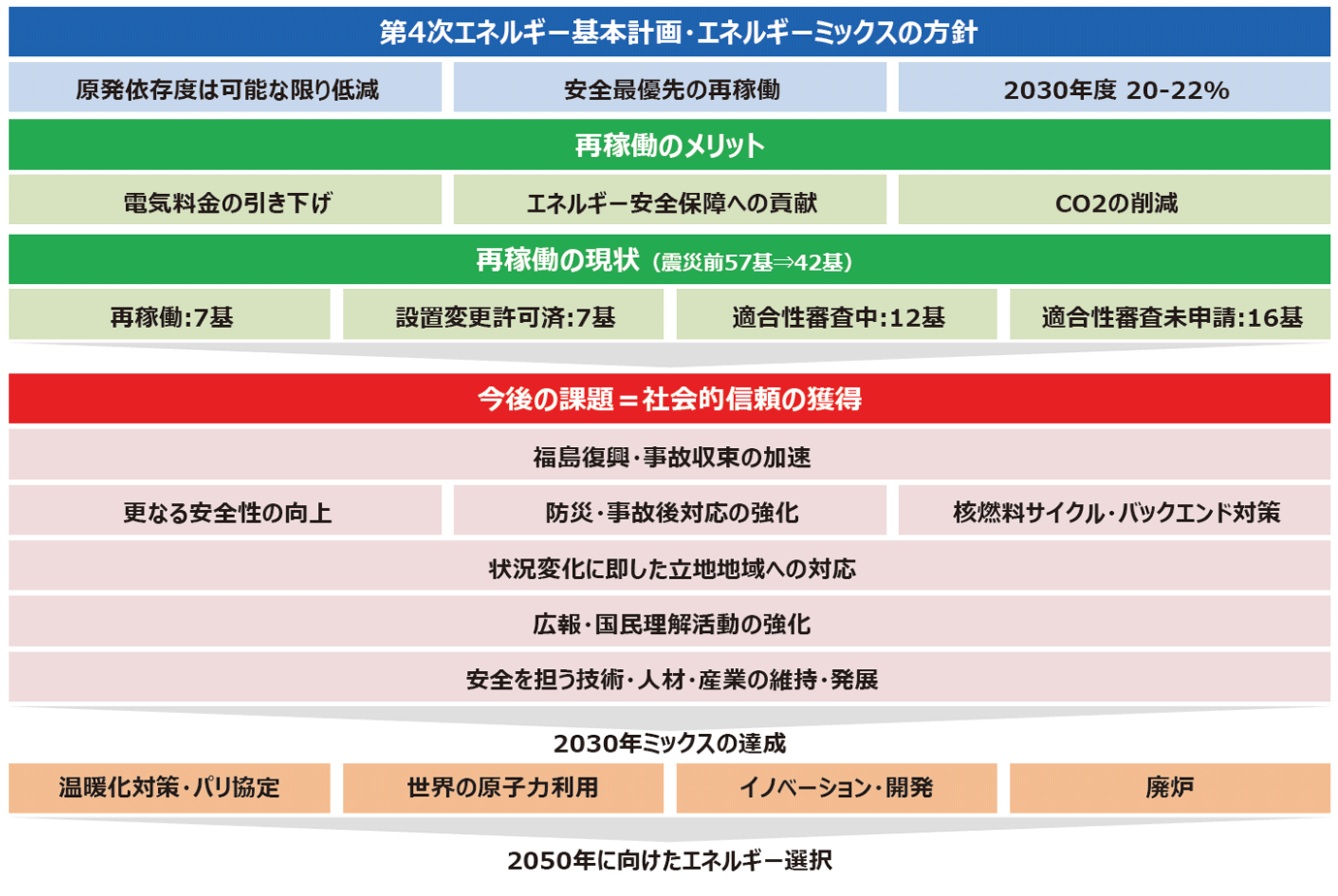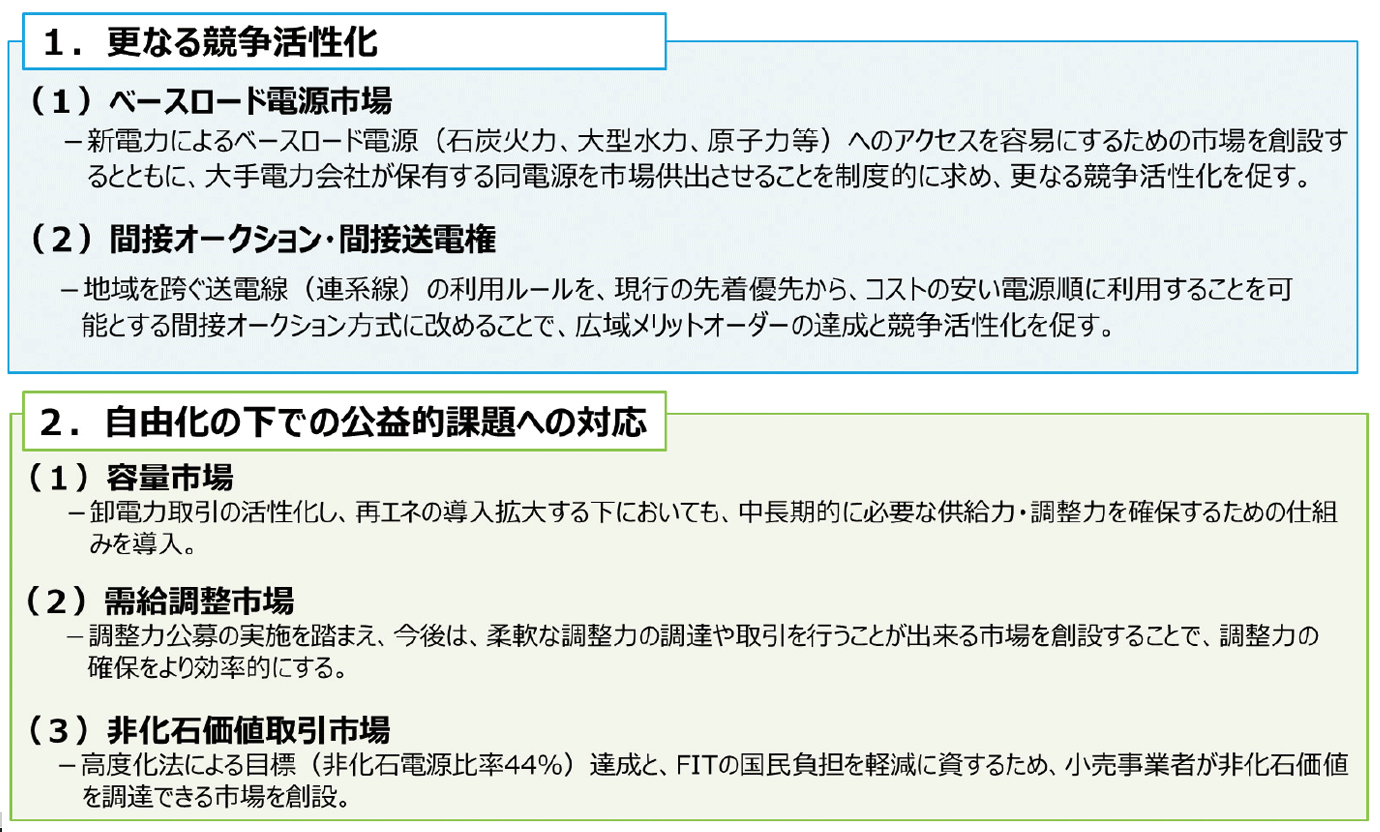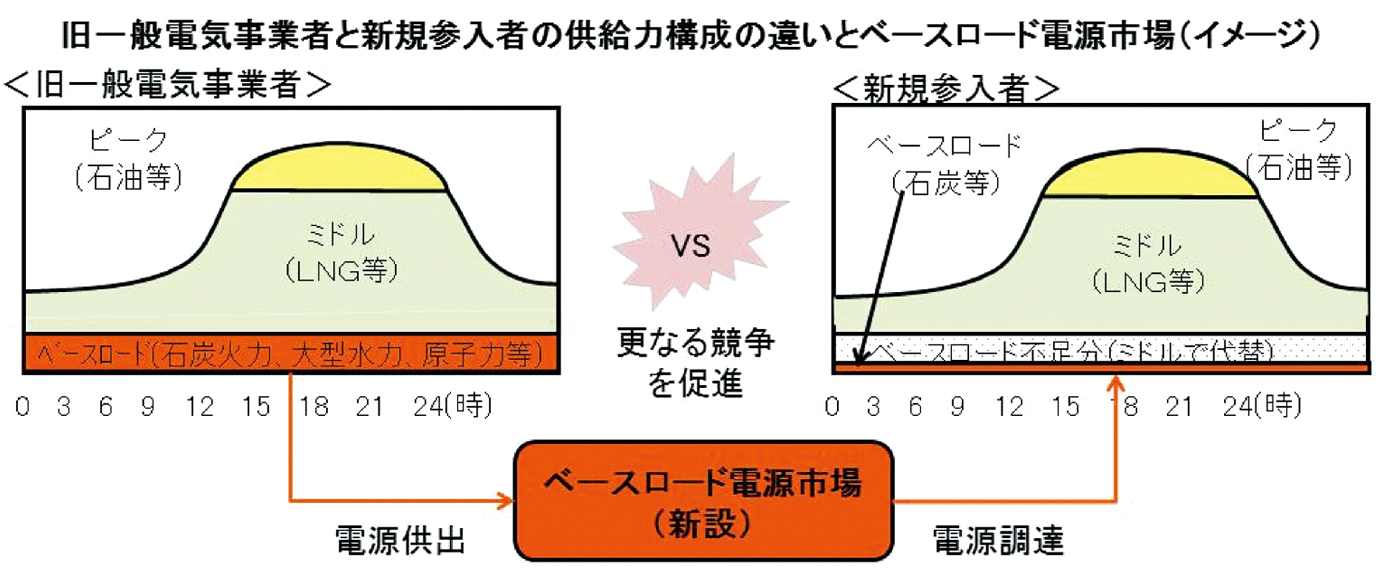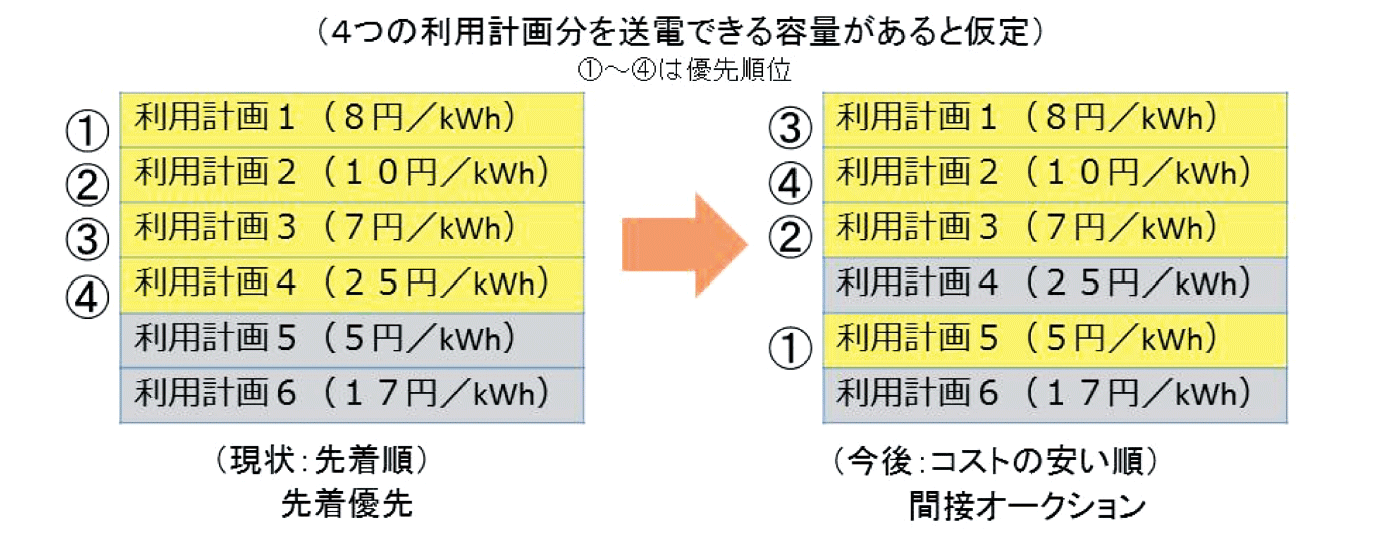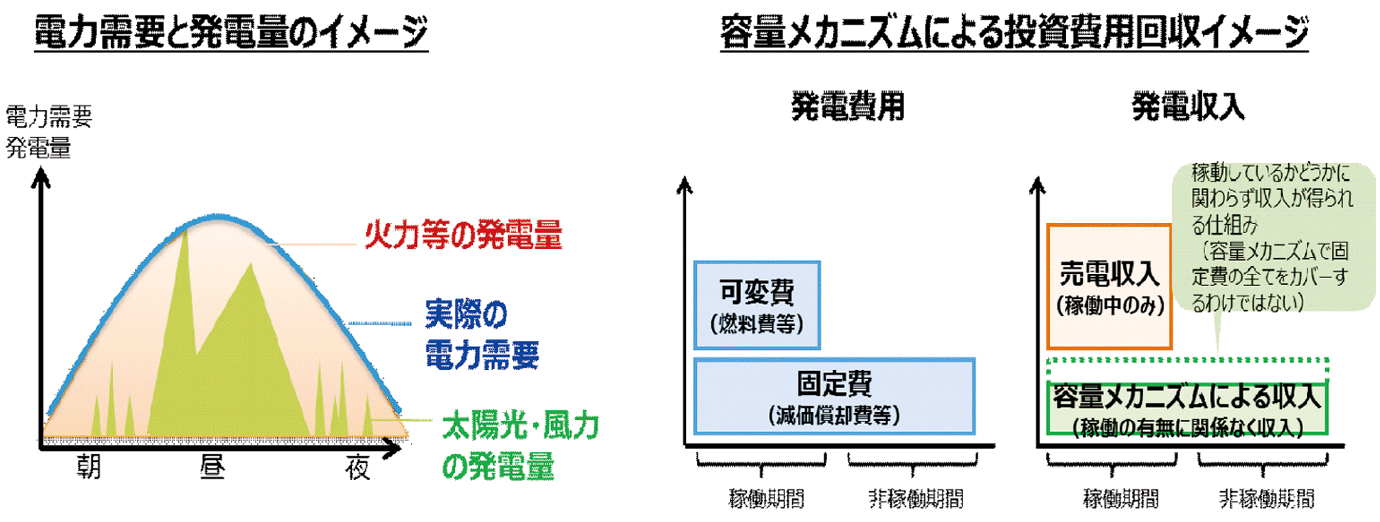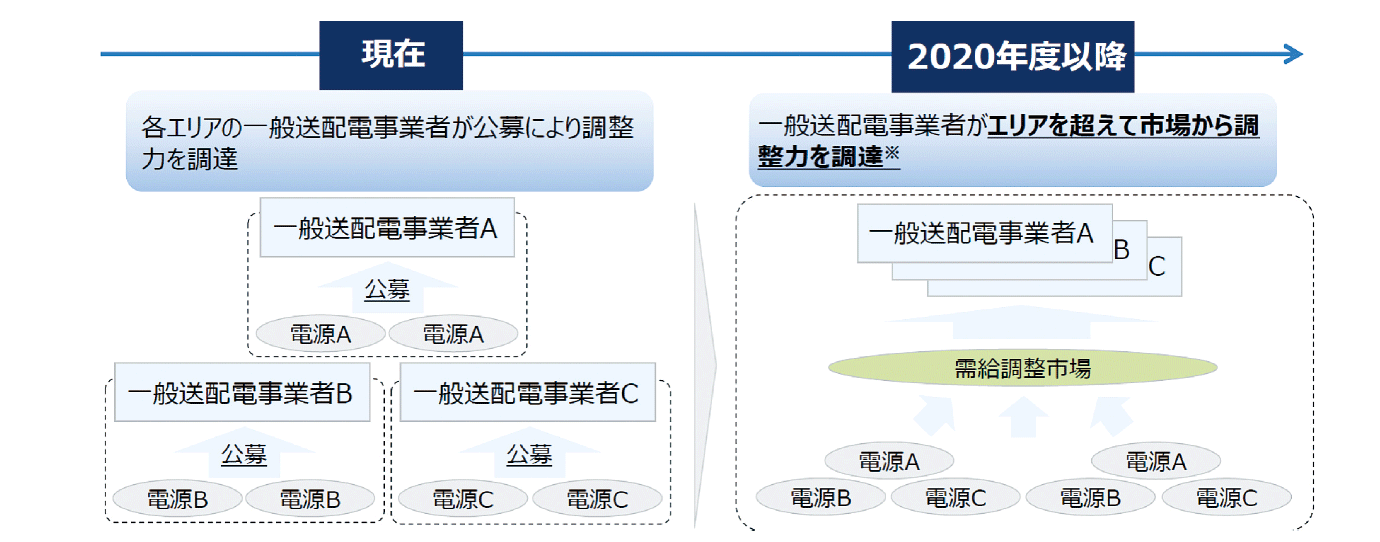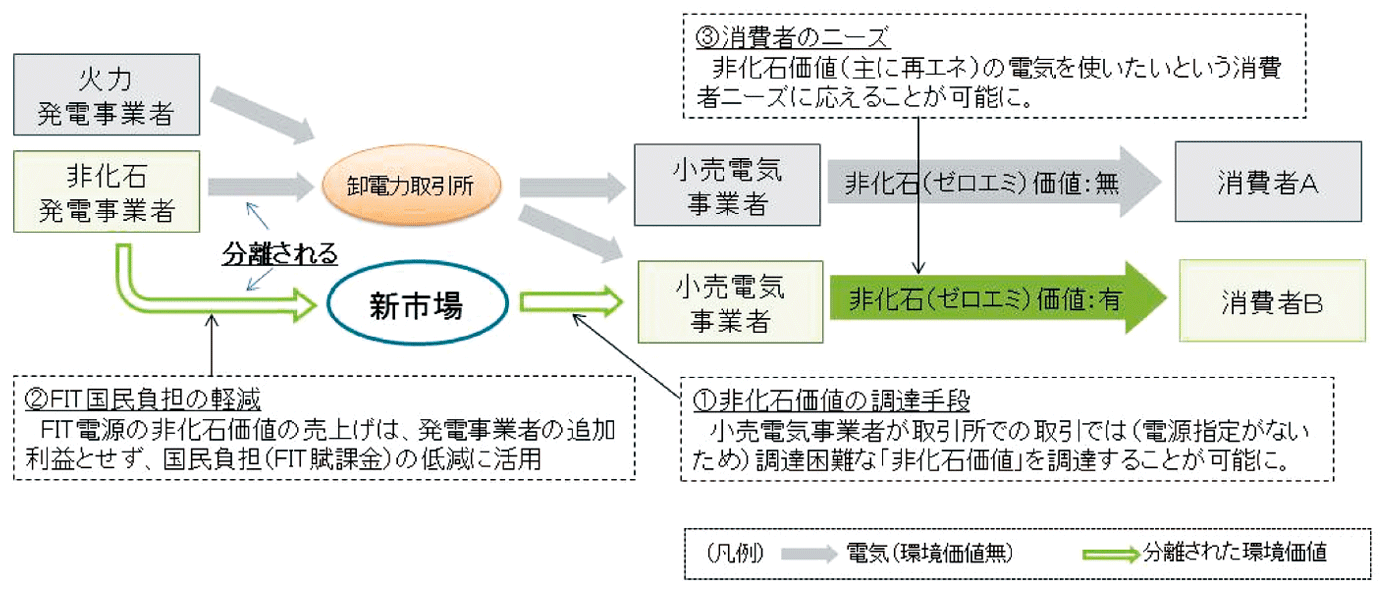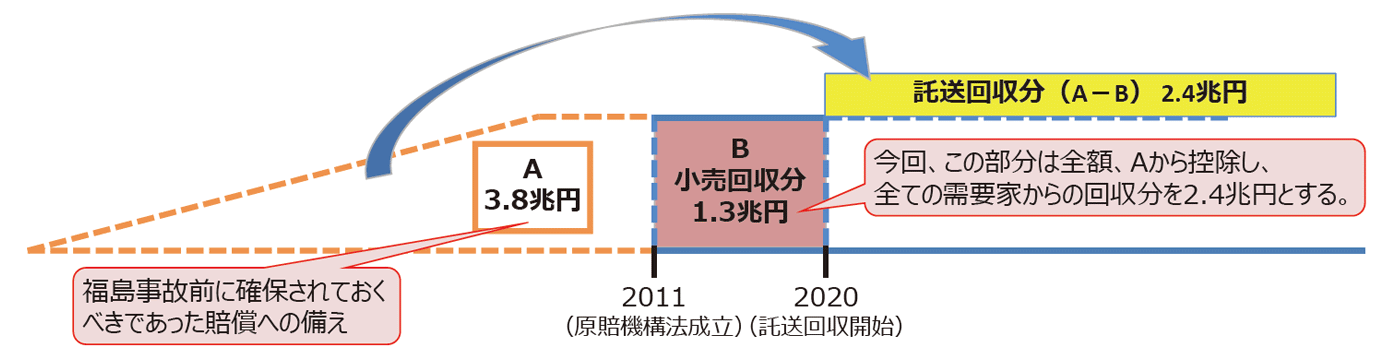第1節 2030年のエネルギーミックスの進捗と課題
1.資源・燃料政策について
今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出量と吸収源による除去量との均衡を達成(脱炭素社会)することを目標とするパリ協定の発効(2016年11月4日)を踏まえ、世界的に脱炭素化(今世紀後半の世界全体での脱炭素社会に向けて、化石燃料利用への依存度を引き下げること等により、炭素排出を低減していくこと)の機運が高まっていますが、脱炭素社会の実現は一足飛びには実現できません。脱炭素社会への移行過程における不確実性に着目すれば、運輸燃料や発電など広範囲で活用できる化石燃料は、依然として重要なエネルギー源であるといえます。海外からの低廉な資源調達と、国内における安定的な燃料供給の二本柱が資源燃料政策の基本理念ですが、現在の我が国をとりまく環境は、大きな変化を迎えています。
海外に目を向けると、シェールオイル増産等による米国のエネルギー自立化がみられ、結果として中東への関心低下など、世界における米国の立ち位置が変化していく可能性があります。また、世界のエネルギー需給において、旺盛な需要を持つ中国・インドの存在感が増し、資源獲得競争は激化しています。さらには、EV・電化の進展による鉱物需要が高まる中、中国資本・資源メジャーによる寡占化も進んでおり、鉱物資源確保が資源調達政策の新たな主戦場となっています。自主権益の確保に加えて、国際資源マーケットの育成・活用、アジア大でのエネルギーセキュリティの追求など、日本のプレゼンスが急速に縮小する局面にあっても、必要な資源を戦略的に確保していくための施策が必要となります。
一方国内では、人口減少・過疎化といった構造的要因による需要減少の中、国内の燃料サプライチェーンをいかに効率的に維持していくかが大きな課題となります。石油・ガスのサプライチェーンについて、災害や海外からの供給途絶などの有事にも対応可能な強靱性の確保は当然のこと、不確実な将来に備え、新事業分野・海外進出の強化等による経営基盤強化や、IoT等を活用した新たなビジネスモデルの追求など、今後起こりうる状況変化にも対応できる供給インフラの整備を今から進めていく必要があります。
これらは現状の取組ですが、将来に向けてはさらなる低炭素化の取組も大前提となります。高効率火力発電設備やCCUS、地熱発電技術など、我が国の強みを持つ先進技術を通じて国内外の低炭素化を追求していくことも忘れてはなりません。
以上のとおり、(1)戦略的な資源確保、(2)将来の情勢変化に対応しうる供給インフラの整備、(3)低炭素化に資する技術開発の3点を基軸に、これからの資源燃料政策を着実に進めていくことが重要です。
(1)資源確保
① 石油・天然ガス自主開発の推進
国内資源に乏しく、石油・天然ガスのほとんどを海外からの輸入に依存する我が国では、石油・天然ガスの自主開発政策を推進しており、特に1970年代の2回の石油危機を契機として、その取組は加速しています。現在は、石油・天然ガスを合わせた自主開発比率を2030年に40%以上とすることを目標としています。こうした目標の下、直近ではUAE・アブダビ首長国における陸上鉱区・海上鉱区の権益獲得、北米におけるシェールオイル・ガス開発への参画、豪州におけるLNGプロジェクトの生産開始等、我が国企業の参画する大型案件が進展するなど、着実に成果を上げてきました。
2015年に策定されたエネルギーミックスでは、2030年においても石油・天然ガスは一次エネルギー供給の約5割を占める見込みであり、エネルギー資源の乏しい我が国において、石油・天然ガスの安定供給の確保は今後も引き続き重要な課題です。再生可能エネルギーの大幅な進展が見られるなど、世界のエネルギー情勢が変革期にある中にあっても、石油・天然ガス権益の確保についてはぶれない取組が必要です。
具体的には、石油・天然ガスの自主開発比率を2030年に40%以上とする政策目標を引き続き堅持し、その着実な達成に向け、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)を通じたリスクマネー供給による支援や、積極的かつ多角的な資源外交の展開など、日本企業による石油・天然ガス権益獲得に向けた総合的な支援を展開していく必要があります。なお、これらの支援に当たっては、我が国のエネルギー安全保障に貢献すべく、戦略的かつ重点的に政策資源を投入していくことが重要です。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
② 資源外交の多角的展開
石油・天然ガスの安定供給の確保に向けては、我が国は戦後、資源国との間で内閣総理大臣を筆頭とするハイレベルによる資源外交を展開してきました。その主眼は石油・天然ガス上流権益の獲得にあり、資源国側の関心が高く、我が国が強みを持つ教育、医療、中小企業等の分野における協力を中心に幅広く実施してきました。
一方で、近年のエネルギー情勢とともに、資源外交のあり方についても、変化を求められています。資源国では、原油価格の低迷に伴う財政逼迫を受け、原油や生ガスを単に販売するだけでなく、より高付加価値である石油製品やLNGとして需要急増が見込まれるアジアに販売する動きや、産業の多角化による資源収入に頼らない経済体制の確立を目指す動きなどがみられます。また、需要国側では、世界的な環境意識の高まりから、エネルギーの低炭素化が課題となっています。このため、発電用化石燃料として最も炭素排出の少ないLNGの調達の重要性が増しており、調達の効率化や最適化につながる柔軟かつ透明性の高い国際市場の確立に加え、その導入に向けたインフラ整備や人材育成が求められています。今後、エネルギー需要の減少が見込まれる我が国において、引き続き石油・天然ガスの安定供給の確保を達成していくためには、こうした資源国・需要国双方のニーズを捉えながら、世界全体、特に今後の成長エンジンでもあるアジア規模のエネルギー安全保障に貢献することで、我が国の石油・天然ガスの安定供給を実現していくことが重要です。
③ アジア規模の市場育成を通じた安定供給
我が国は2016年5月、柔軟かつ透明性の高い国際LNG市場の構築に向け、「LNG市場戦略」を策定しました。中国・インドを始めとするアジアによるLNG需要のけん引、米国・豪州等新たなLNG供給国の台頭、我が国における電力・ガス市場の完全自由化等により柔軟なLNG調達を志向する環境の醸成等、LNGを巡る世界の市場環境が変革期にあることを受け、世界最大のLNG輸入国である我が国が柔軟かつ透明性の高い国際LNG市場の確立をけん引することを目指すものです。
この数年、中国におけるLNG需要の増加が顕著であり、中国の需要増が一因とみられる2017年後半にかけてのアジアのLNGスポット価格の急騰は、LNG市場における中国の存在感の高まりを象徴するものといえます。今後、インドや東南アジアでの需要増加も見込まれる中、こうしたアジアの需要を取り込みつつ、アジア大でのマーケット育成を図っていくことが、我が国へのLNGの安定供給を確保するために重要です。
2017年10月に開催されたLNG産消会議では、世耕経済産業大臣より、アジアでのLNG需要の現実化に向け、LNGの上流・中流・下流のプロジェクトに対する官民で100億ドルのファイナンス供給、及び5年間で500人の人材育成支援の構想を発表しました。また同年、EUとインドそれぞれとの間で、LNG市場形成に向けた消費国間での連携に関する協力覚書(MOC)を締結しました。これらのイニシアチブに基づく取組を、民間企業・関係機関とも連携して今後着実に進めるとともに、新たな国・地域との連携関係も結びながら、柔軟かつ透明性の高い国際LNG市場を構築していきます。
また、引き続きLNG市場の柔軟性・透明性向上に向け、仕向地制限をはじめとする取引流動性を阻害する商慣習の弾力化や、LNGバンカリング等新たな需要の促進、価格報告機関による価格アセスメントの信頼性向上、LNG受入基地等のインフラのアクセス向上を一層進めていきます。
- ※
- シナリオ1:新規火力に占めるガス比率15%、シナリオ2:同30%、シナリオ3:同60%
- 出典:
- ERIA資料を基に資源エネルギー庁作成
- 出典:
- エネルギー情勢懇談会資料
④ 国際競争力あるエネルギー産業
資源に乏しい我が国が持続的に資源の安定供給を実現するためには、海外での国際競争に負けない、自立的なエネルギー企業の育成が不可欠です。特に近年は、石油ガス田開発における技術的難易度の高度化・複雑化に加え、中国・インド等、化石燃料需要の増加が著しい国々の国営石油企業と我が国資源開発企業との競争がますます激化しています。しかしながら、我が国資源開発企業の生産規模や財務基盤は欧米資源メジャーや新興国の国営石油企業と比べて小さく、国際競争力の強化が喫緊の課題となっています。
石油公団の解散及びJOGMEC設立以降、我が国では欧米資源メジャーを目標に、我が国上流開発産業をけん引する「中核的企業」の育成を政策課題としてきました。近年のエネルギー情勢の変化を踏まえれば、この取組を再加速することが大きな課題です。
「中核的企業」と呼びうる企業は、①一定の生産規模(最低でも日量100万バレル程度)、②適正かつ強靱な財務基盤、③優良な資産、及び④マーケティング能力を有していることが必要です。このためには、我が国資源開発企業には、現在取り組んでいる大型プロジェクトを着実に実現させるとともに、将来的な案件を形成し、成長戦略を描いていくことが期待されます。また、保有資産の「量」だけでなく、油価変動への耐性等の「質」の向上も図るため、保有資産のポートフォリオを適切に見直し、入れ替えていくことが重要です。さらに、目まぐるしく変化する資源情勢を捉え、長期的なシナリオを見据えつつ、時代に応じた資源開発技術や人材、マーケティング能力の獲得も必要になります。
政府としては、自主開発比率を向上させると同時に、こうした「中核的企業」の育成を実現するため、JOGMECによるリスクマネー供給資源開発技術の獲得支援、政策金融等骨太な産業構造構築、世界で「勝てる企業」を育成するため、より戦略的な支援策を講じていくことが求められています。
⑤ 国内資源開発の推進
我が国のエネルギー安全保障の観点でいえば、地政学的リスクに左右されず安定的な供給が可能な国内の資源開発を進めることは極めて重要です。加えて、国内での資源開発を促進するということには、我が国の資源開発企業が海外においてより有望かつ難易度の高いフィールドでの開発を行うための人材育成や技術開発などの場を確保するという、産業政策的な観点からも、極めて価値があるものといえます。
国内の有望な資源を決して眠らせることなく、また我が国資源開発産業の発展に向け、民間企業が主体となった国内資源開発を促進することが重要です。このため、鉱業権者の新陳代謝を進めるなど、国内外を問わず真に意欲・能力ある適切な事業者が資源開発に取り組めるよう、事業環境を整備していくことが課題です。特に、我が国は世界で第6位の排他的経済水域の広さを有していることを踏まえ、これを最大限有効活用していくという観点からは、海洋におけるエネルギー・鉱物資源の開発促進のための取組を一層強化していくことが重要です。
在来型石油・天然ガスについては、引き続き三次元物理探査船を使用した国主導での探査を機動的に実施するとともに、より効率的・効果的な探査を実現し、市場での競争力を高めるため、世界水準の機器・技術の導入も含めた体制構築を進め、三次元物理探査船を民間企業による探査にも積極的に活用することを目指します。また、有望な海域への試掘機会を増やすための検討も行います。
砂層型メタンハイドレートについては、2017年に実施した第2回海洋産出試験の結果等を踏まえ、平成30年代後半に民間企業が主導する商業化に向けたプロジェクトが開始されることを目指して、引き続き技術開発を進めます。また、表層型メタンハイドレートについては、2013年度から2015年度にかけて行われた資源量の把握に向けた調査の結果を踏まえ、資源回収・生産技術の調査研究を行うとともに、有望な手法が見つかった場合には研究対象を絞り込み、商業化に向けたさらなる技術開発を推進します。
⑥ 電動化を見据えた既存対策の点検
国内外での自動車の電動化によりリチウムイオン電池や駆動用モーター等に必要な鉱物の需要増加が見込まれる一方、中国をはじめとする新興国企業による確保の取組が旺盛になっています。こうした厳しい鉱物資源の獲得競争の中、日本にとって必要な鉱物資源の安定供給を確保するためには、各鉱物資源の需給や市場特性を十分に踏まえながら、上流対策(資源外交、権益確保、購買力の強化)と中下流対策(省資源化・代替材料開発、備蓄、リサイクル)を複合的に講じていくことが必要です。
(2)供給インフラ
① 国内の燃料サプライチェーンの確保
「2018~2022年度石油製品需要見通し」によれば、我が国の国内の石油需要は毎年度平均1.7%程度減少を続ける見通しである一方、アジア太平洋地域の石油需要・石油化学需要は増大を続ける見通しで、東アジア地域においては、石油化学との統合が進んだ大規模な石油コンビナートの建設が相次いでいます。さらに、北米のシェール革命によって、これまで最大の資源輸入国であった米国が資源輸出国へと変化するとともに、天然ガス由来の安価な原料の調達が可能となったことで新たなエチレンプラントの建設が予定されるなど、世界の石油・石油化学製品の供給量が増加することに伴い、特にアジアの競争環境が激化することが見込まれています。
戦後の高度成長期に運転を開始した我が国の製油所は、東アジアで新たに建設が進んでいる大規模な石油コンビナートと比べ、規模の経済性、エネルギー効率性、石油化学製品生産への弾力的な切り替えなどの生産の柔軟性等の面で見劣りするとの指摘があります。また、2020年1月から予定されている船舶の燃料油中の硫黄分濃度の規制の強化や、長期的には、パリ協定の履行により、国内外の石油需要見通しは予測困難になっていきます。加えて、電気自動車などの次世代自動車の導入拡大によるガソリン需要の大幅な減少の可能性にともない、需要構成が大きく変化する可能性もあります。
こうした状況の中においても、代替困難な軽油などの国内燃料需要は将来的にも存在し続けることが見込まれるため、引き続き、石油製品の安定供給を確保し続ける必要があります。国内の石油産業の経営統合や製油所の再編が進み、次の成長のために必要な事業基盤が整いつつある一方、国内ではガソリンをはじめとする石油需要の減少は依然として継続する見込みです。国内への石油製品の安定供給を確保するためには、今後海外製油所との競争激化が見込まれる中、国内石油精製設備の国内立地を維持していくためには、コンビナート全体で競争力を確保するとともに、縮小する国内需要に対して、他事業分野や海外事業への進出拡大による収益力の向上が重要です。
- 出典:
- 総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会資料
② 燃料供給インフラの効率化・次世代化
消費者に対して石油製品・LPガスの供給を行う下流部門では、需要の減少が収益を圧迫する最大の要因の一つとなっており、自動車をはじめとした燃料効率の大幅な改善の動きも拍車をかけ、事業者の経営環境は厳しい状況が続いています。さらに、人口減少・高齢化の進展により、人手不足の問題も表面化してきています。
今後、人口減少や過疎化の進展により、サービスステーション(SS)をはじめとする燃料供給インフラの維持がますます困難になっていく可能性があります。地域においては、SSだけでなく、郵便局、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、宅配事業者など地域の生活を支えるあらゆるプレーヤーが人手不足や需要減少といった共通の課題を抱えています。そうした中で、SSも含めて、地域における生活サービス拠点の一体化が進む可能性もあります。また、電気自動車(EV)やカーシェアリング、自動運転などの技術革新により、ヒトとクルマの関わり方が大きく変化する可能性もあります。こうした経済社会の変化の中でも、将来にわたって地域の燃料供給拠点を維持していくためには、燃料供給インフラの効率化・次世代化について検討を進めていく必要があります。
- 出典:
- 次世代燃料供給インフラ研究会資料
(3)技術開発
① 地熱発電
国内の地熱発電については、2015年に策定された「長期エネルギー需給見通し」において、設備容量を、2015年現在の約53万kW(電源構成比0.2%)から、2030年度までに約140~150万kW(電源構成比1~1.1%程度)まで増やすことを目指しています。地熱開発を加速化するに当たっては、新規開発地点の開拓と開発期間の短縮などの課題を解決していく必要があります。このため、新規の有望地域におけるポテンシャル調査の集中的な実施や、地熱資源の開発期間の短縮につながる地下の探査や掘削に係る技術開発等の取り組みを進めています。
新規開発地点の開拓について、政府は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)を通じて、新規の有望地点を探索するための地熱ポテンシャル調査を行っています。また、事業者が実施する地熱資源量の把握に向けた地表調査や掘削調査等の開発の難度が高い初期調査に対する補助も行っています。さらに、出資や債務保証による金融支援を通じて、探査・開発段階への移行を促進させています。
技術開発については、事業者にとって足かせとなっている開発期間や開発コストの軽減、さらに稼働率向上に資することを目指しています。具体的には、地下構造の探査精度の向上や掘削期間の短縮などに資する技術開発により、掘削本数を削減することや、掘削期間を短縮することで、開発期間の短縮を可能にします。また、地下の蒸気量の管理技術を確立することで、設備利用率の向上を目指しています。その他、既存の地熱発電よりも大型化が期待されている超臨界地熱発電にも取り組んでいます。2050年頃の実用化を目指し、発電システムの検討や、過酷な条件でも耐えうる材料検討等を含む超臨界地熱発電の実現可能性調査を実施しています。
- 出典:
- 総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会資料 一部修正
② 火力発電の高効率化及び将来を見据えた低炭素化・脱炭素化の展開
火力発電については、石炭火力、LNG火力の高効率化を進めつつ、環境負荷の低減と両立しながら活用することが重要となります。そのために、2016年6月に産学官の有識者で策定した「次世代火力発電に係る技術ロードマップ」に基づき、発電効率を飛躍的に向上させる次世代火力発電技術の早期確立を目指します。
具体的には、石炭をガス化し、燃料電池、ガスタービン、蒸気タービンの3段階で発電を行うことで高効率化を図る石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC)の実証事業やその要素技術開発(大容量燃料電池の開発等)、燃焼温度を高温化することで高効率化を図る1700℃級ガスタービン技術の開発・実証など、我が国の強みを生かした石炭・LNG火力における高効率発電技術の開発を進めています。
また、将来のさらなる地球温暖化対策に向けて、火力発電から排出されるCO2を効率的に分離回収する技術やそのCO2を有効に利用、又は貯留する技術、燃焼時にCO2が発生しない水素・アンモニアによる発電技術、また再生可能エネルギー大量導入に向けた火力発電による負荷変動対応技術等、将来を見据えた低炭素化・脱炭素化に向けた革新技術の開発も進めています。
- 出典:
- 総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会資料
2.さらなる省エネの推進に向けて
(1)エネルギーミックスにおける省エネ対策
2015年7月に策定されたエネルギーミックスにおいて、省エネについては、2013年度実績から2030年度まで年1.7%の経済成長等によるエネルギー需要の増加を見込みながら、具体的な裏付けのある対策・施策、技術の積み上げに基づく徹底した省エネ対策により、年間最終エネルギー消費を対策前に比べ原油換算5,030万kl程度削減することとされています。これは、2013年度から2030年度までに、エネルギー消費効率(=最終エネルギー消費量/実質GDP)を35%程度改善することに相当し、石油危機後の20年間に我が国が実現した省エネと同程度のエネルギー消費効率の改善が必要となります。我が国のエネルギー消費効率は現在で世界最高水準にあり、既に相当の努力がなされてきたことを踏まえると、この見通しは大変野心的なものです。(第1部第1章参照)
(2)エネルギーミックスにおける省エネ対策の進捗
エネルギーミックスにおける省エネ対策(マイナス5,030万kl)の進捗状況を見ると、産業・業務部門における高効率機器の導入・更新は、設備の種類によって進捗に大きな差が見られます。これは、投資回収期間の違いや生産工程への影響、運用に要求される技術水準等に起因して、設備の種類に対する投資判断の難度に差異があるためと考えられます。例えばLED機器のように、生産工程に組み込まれず、投資回収期間が短いため、投資判断が比較的容易な設備の種類の導入は着実に進んでいますが、ヒートポンプやモーターは、生産工程に組み込まれるため、他の生産設備等との調整を要し、投資回収期間も長いため導入は十分には進んでいません。経済成長を前提とするエネルギーミックスの実現に向けて、省エネ設備投資の加速により、産業・業務部門のエネルギー消費効率の改善を図ることが課題です。
また、運輸部門はエネルギーミックスで最大の省エネ量(マイナス1,607万kl)を見込んでいます。貨物輸送分野はトラックの燃費効率だけでは今後大幅な省エネが難しく、今後次世代自動車の普及により効率向上が期待される旅客輸送分野と比較して、現時点で省エネ対策の進捗が遅れており、貨物輸送分野における物流効率化に向けた取組強化が課題です。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
- 出典:
- 資源エネルギー庁
(3)エネルギーミックスにおける省エネ見通し実現に向けた部門別の省エネ政策
このように、エネルギーミックスにおける省エネ見通しに向けて多くの課題が山積しており、経済成長と両立した省エネを進めるため、省エネ法による規制と予算や税制による支援策を両輪に、施策を総動員する必要があります。
省エネポテンシャルを開拓し、エネルギーミックスにおける省エネ見通しの必達に向けて「総合資源エネルギー調査会 省エネルギー小委員会」において検討を行い2017年8月に提言(「省エネルギー小委員会 意見」)が取りまとめられました。
さらなる省エネを実現するには、企業間や機器間の連携促進と新技術の活用が鍵であり、「省エネルギー小委員会」や「基本政策分科会」で議論された、今後の省エネ政策の方向性を部門ごとに紹介していきます。
- 出典:
- (一財)日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧2015」
① 産業部門・業務部門
(ア)省エネ法に基づく事業者単位規制
産業部門・業務部門の省エネ取組を進展させるため、省エネ法では、工場等の設置者に対し、省エネ取組を実施する際の目安となるべき判断基準(設備管理の基準や年1%のエネルギー消費効率改善の目標等)を示すとともに、年度で1,500kl以上エネルギーを使用する「特定事業者」(約12,000者指定)にはエネルギーの使用状況等の報告を義務付け、取組が不十分な場合には指導・助言や合理化計画の作成指示等を措置しています。
また、事業者同士が省エネへの取組を相対的に比較できるようにすることで、事業者の自主的取組を一層促すことを目的として、業種ごとに上位1~2割の事業者が達成しているエネルギー消費効率の水準を目標として設定し、業界ごとに最適な省エネ取組を促す「産業トップランナー制度(ベンチマーク制度)」を2008年に導入しました。
産業トップランナー制度は、これまで製造業を中心に導入が進められており、製造業のエネルギー消費量の約8割、全産業のエネルギー消費の53%をカバーしています。現在、「日本再興戦略2016」(2016年6月閣議決定)に示された、「3年以内(2018年度中)に全産業のエネルギー消費の7割に拡大」するとの方針に沿って、流通・サービス業への導入拡大を進めており、2016年4月にコンビニエンスストア業に、2017年4月にホテル・百貨店に、2018年4月に食料品スーパー、貸事務所、ショッピングセンターにも導入しました。
(イ)複数企業が連携した省エネ取組の促進
石油危機後のたゆまぬ省エネ取組の結果、産業・業務部門のエネルギー消費原単位は相当改善し、世界最高水準となりました。しかし、近年、エネルギー消費原単位の改善は足踏み状況で、特に、省エネ法の特定事業者のうち約3割が対前年度比で悪化しています。
エネルギーミックスの野心的な省エネ見通しの実現に向けて、経済成長と両立する徹底した省エネを進めるには、引き続き企業単位の取組は不可欠です。他方、企業単位の省エネが進展していることを踏まえれば、今後は、複数の企業が連携する新たな省エネ取組を普及することが、消費効率の改善の加速に向けた鍵となります。
近年、例えば個々の企業ごとの省エネ取組の枠を超え、業界、サプライチェーン、グループ単位など、複数の企業が連携した省エネ取組が生まれつつあります。しかし、現行省エネ法は企業単位で最適な省エネ取組を求める体系であり、企業の省エネ評価についても、企業ごとのエネルギー消費量に基づいているため、複数企業が連携する省エネ取組が必ずしも正しく評価されていない場合がありました。
そこで、同業種やサプライチェーン上の複数企業の連携による省エネ取組を認定し、省エネ量を企業間で分配して報告することを認めることで、各企業が適切に評価される措置などを盛り込んだ省エネ法の改正法案(エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律案)を2018年3月9日に閣議決定し、同日、第196回国会に提出しました。改正法案では、これらと同様の措置は、運輸部門についても講じることとしています。
また、2017年12月に閣議決定された「平成30年度税制改正の大綱」には、改正後の省エネ法に基づき認定された「連携省エネルギー計画」の実施に必要な設備投資に対する法人税等の税制措置(特別償却30%、税額控除7%(中小企業のみ))を2018年度から新設することが盛り込まれ、当該税制改正の大綱を踏まえた所得税法等の一部を改正する法律案が2018年3月28日に成立しました。
今般の省エネ法の見直しと、税制措置や補助金等の支援策のパッケージで、企業のエネルギー消費効率の改善を加速していきます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
② 運輸部門
運輸部門の省エネを進めるには、物流効率化と、乗用車・トラック等の燃費改善をともに進めることが重要です。
(ア)貨物輸送の効率化
トラックは乗用車に比べて電動化が難しく、燃費向上だけでは大幅な省エネが難しいため、貨物輸送の省エネを進めるためには、貨物輸送に関係する事業者が連携して物流効率化を進めることが重要です。省エネ法では2005年以降、自らが所有権を有する貨物を貨物輸送事業者に輸送させる企業を「荷主」として規制対象としており、省エネ取組を実施する際の目安となるべき荷主判断基準(省エネに資する輸送方法の選択、貨物輸送事業者との連携、年1%のエネルギー消費効率改善の目標等)を示すとともに、一定規模以上の荷主にはエネルギーの使用状況等の毎年度報告を義務化し、取組が不十分な場合には指導・助言等を行ってきました。
他方、近年のインターネット通信販売市場の成長(5年間で1.8倍)に伴い、小口輸送や再配達によるエネルギー消費の増加が懸念されており、特に、宅配に伴うエネルギー消費の25%が再配達によるものと推計されています(国土交通省調査)。また、企業間物流において、貨物輸送事業者の荷待ち時間は、貨物の発送時点のみならず、貨物の到着時点においても同程度発生しています。
これらの課題に対応し、貨物輸送事業者・荷主・荷物の荷受側の連携強化によって貨物輸送のさらなる省エネを促進するため、3月9日に閣議決定した(前述の)省エネ法の改正法案では、以下の措置も講じることとしています。
(i)貨物の所有権を問わず、契約等で輸送の方法を決定する者を荷主と定義することで、所有権が無いものの輸送方法を決定するネット小売事業者を省エネ法の荷主規制の対象に確実に位置づけ、省エネ取組を促す。
(ii)貨物の到着時点における荷待ちの課題に対応するため、到着日時等を適切に指示できる貨物の荷受側を「準荷主」と位置づけ、荷主の省エネ取組への協力を求める(努力義務)。
今般の省エネ法の見直しと、税制措置や補助金など支援策のパッケージで、物流効率化の取組を促進していきます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
(イ)EV・PHV / FCVの普及加速に向けて
乗用車・トラック等の燃費改善については、省エネ法に基づくトップランナー制度(自動車メーカー等に対し、目標年度までに販売車両の平均燃費値を基準値以上にすること等を求める制度)による規制とエコカー減税等の支援策により、トップランナー制度の基準策定当初の見込みを上回っています。特に乗用車の燃費は大幅に改善してきました。
今後、さらなる省エネに向けては、EV・PHVやFCVの普及加速が課題であり、2030年に新車販売における次世代自動車の割合を50~70%とするとの政府目標の実現に向け、様々なアプローチで取組を進めていきます。現在、省エネ法のトップランナー制度における燃費基準の対象は、現在、ガソリン車・ディーゼル車、LPG車となっており、今後は、燃費規制の対象外であるEV・PHVやFCVの扱い等を含めて検討する必要があります。この点も含め、省エネ法に基づく乗用車の次期燃費基準について、経済産業省と国土交通省の合同会議1において、2018年3月から検討を開始しました。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
- 出典:
- 資源エネルギー庁
- 出典:
- 資源エネルギー庁
③ 業務部門・家庭部門
(ア)機器の省エネ性能向上
オフィスや家庭の省エネを促進するには、個々の機器の省エネ性能の向上を図ることが重要です。省エネ法のトップランナー制度では、特定エネルギー消費機器等(エアコンや冷蔵庫、テレビ等)の製造事業者等(生産量等が一定以上の者)に対して、機器のエネルギー消費効率の目標達成を求めるとともに、エネルギー消費効率等の表示も求めています。対象品目は2013年の法改正で新たに対象となった建材も含めて32品目となり、家庭のエネルギー消費の7割まで対象が拡大しています。トップランナー制度の下、例えば乗用車の平均新車燃費は1996年から2014年までに約97%改善、エアコンの期間消費電力量は2001年から2014年までに約31%改善されました。
さらなる機器の省エネ性能向上には、IoT等を活用し、機器間連携等による新たな省エネ技術の開発・普及の促進が鍵となります。これらの技術を普及させていくため、例えば、現在のトップランナー制度では評価できない、使用現場の状況に応じて機器間連携等によって省エネを実現する技術の評価方法の検討も進めていきます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
(イ)建築物の省エネ化
建築物の省エネを促進するには、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)により新築建築物等の省エネ基準への適合義務化を進めることに加え、住宅・ビルのゼロ・エネルギー化(ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)/ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル))を促進し、2030年に向けて建築物における新たな省エネのモデルを確立・普及させることが重要です。
ZEH/ZEBについて、第四次エネルギー基本計画においては、「2020年までに標準的な新築住宅で、2030年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指す。」「2020年までに新築公共建築物等で、2030年までに新築建築物の平均でZEBを実現することを目指す。」という目標を掲げています。
省エネ性能に限らず知的生産性や快適性を含めて、ZEH/ZEBが持つ多面的な価値の認知を促進するなど、ZEH/ZEBの自立的普及に向けた取組を進めていきます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
- ※
- ZEH/ZEB:高効率機器を導入すること等を通じて大幅に省エネを実現した上で、再エネにより、年間の消費エネルギー量をまかなうことを目指す住宅/ビル
3.再生可能エネルギーの大量導入に向けて
再生可能エネルギーを取り巻く状況は、大きく変貌しています。世界的には、発電コストが低減し、他の電源と比べてもコスト競争力のある電源となってきており、導入量が急増しています。我が国においても、2012年7月の固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の導入以降、急速に再エネの導入が進んでいるものの、その発電コストは国際水準と比較して依然高い状況にあり、国民負担の増大をもたらしています。また、再エネの導入拡大が進むにつれ、従来の系統運用の下で系統制約が顕在化しており、再エネの出力変動を調整するための調整力の確保も含め、再エネを電力系統へ受け入れるコストも増大しています。さらに、地域との共生や発電事業終了後の設備廃棄に対する地元の懸念に加え、小規模電源を中心に将来的な再投資が滞るのではないかといった長期安定的な発電に対する懸念も明らかとなってきています。
こうした中、エネルギーミックスにおいて示された2030年度における再エネの導入水準(22~24%)を着実に達成するためには、再エネをコスト競争力のある電源とし、その大量導入を持続可能なものとしていくことが必要です。このため、以下のような課題を解決していくことが求められます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁(JPEA出荷統計、NEDOの風力発電設備実績統計、包蔵水力調査、地熱発電の現状と動向、PRS制度・固定価格買取制度認定実績等より資源エネルギー庁作成)
(1)発電コストの低減
我が国の再エネの発電コストは、太陽光発電では欧州の約2倍と高い水準にあります。再エネがFITから自立するためには、他の電源と比較して競争力のある水準までコスト低減することが不可欠です。また、FITでは再エネ由来の電気の買取りに要する費用の一部を賦課金として電気料金に上乗せする形で国民が負担することになっており、2016年度の賦課金は年間約1.8兆円でした。エネルギーミックスにおいては、2030年度の再エネの導入水準(22~24%)を達成する場合のFITにおける買取費用総額を3.7~4兆円程度と見込んでおり、現在の賦課金の水準から機械的に計算すると、この場合の国民負担は年間2.9~3.1兆円程度になると想定されます。FIT導入前(2011年度)の再エネ比率は10.8%、2016年度は15.3%なので、再エネ比率を約5%引き上げるために年間約2兆円の国民負担を費やしたことになりますが、今後は、年間約1兆円の追加負担で、再エネ比率を更に7~9%引き上げる必要があることから、発電コストの低減は待ったなしの課題となっています。発電コスト低減に向けて、FIT制度における中長期の価格目標の設定及びその目標に向けたトップランナー方式による太陽光や風力の価格低減、競争を通じてコスト低減を図る入札制度の活用、低コスト化に向けた研究開発などを総合的に進めていきます。
- ※
- 買取費用及び賦課⾦の額は当該年度開始当初の推計値
- (注)
- 2016年度の買取費用総額・賦課金総額は試算ベース。2030年度賦課金総額は、買取費用総額と賦課金総額の割合が2030年度と2016年度が同一と仮定して算出。kWh当たりの買取金額・賦課金は、(1)2016年度については、買取費用と賦課金については実績ベースで算出し、(2)2030年度までの増加分については、追加で発電した再エネが全てFIT対象と仮定して機械的に、①買取費用は総買取費用を総再エネ電力量で除したものとし、②賦課金は賦課金総額を全電力量で除して算出。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
(2)長期安定的な発電を支える事業環境整備
再エネが自立するためには、日本のエネルギー供給の大きな役割を担う責任ある電源として、長期安定的な電源となることも不可欠です。現在は、FITが再エネの導入を支えていますが、熟度が低いままFITの認定を取得して長期間未稼働となったり、メンテナンスや事業終了に備えた準備がおろそかになるなど、適正な発電事業が行われない事態や将来的な太陽光パネルの廃棄等に関する地元の懸念が顕在化してきています。2019年からはFITの買取期間が終了する電源が発生し始めますが、その後も発電が継続され、再投資が行われる環境をいかに整備していくかも重要な課題です。
また、太陽光発電に偏重した導入が進む中、立地制約による事業リスクが高い電源も含め、バランスの取れた導入を促進することも重要です。例えば、欧州では洋上風力発電において我が国よりも大きく先行しており、急速なコストダウンが進んでいます。陸上風力発電の適地が限定的な我が国においても、洋上風力発電は大きな導入ポテンシャルとコスト競争力とが両立し得る重要電源ですが、「海域の占用に関する統一的なルールがない」「海域の先行利用者との調整ルールが不明確」といった課題があります。洋上風力発電の導入促進のため、一般海域の利用について、利害関係者との調整等をルール化し、長期占用を実現するため、「海洋再生可能エネルギー発電設備に係る海域の利用の促進に関する法律案」を2018年3月9日に閣議決定し、同日、第196回国会に提出しました。
(3)系統制約の克服
我が国の系統は、これまで主として大規模電源と需要地を結ぶ形で形成されてきており、再エネ電源の立地ポテンシャルとは必ずしも一致していません。このため、再エネの導入拡大に伴い、系統に制約が生じる例が見られるようになりました。今後、再エネの大量導入に向けて、この「系統制約」が導入の大きなボトルネックとなる可能性があります。
現在の我が国のルールでは、新規に電源を系統に接続する際、まずは系統の空き容量の範囲内で先着順に受入れを行い、空き容量がなくなった場合には系統を増強した上で追加的な受入れを行うこととなっています。再エネの導入量が増えるにつれ、「空き容量がなく、つなげない」「系統増強費用が高い」といった声が発電事業者から上がってくるようになりました。これらの声に応え、国民負担を軽減しながら再生可能エネルギーを最大限導入するためには、まずは既存系統を最大限活用していくことが最優先です。このため、欧州の先進事例も参考にしながら、系統の空き容量を柔軟に活用し、「日本版コネクト&マネージ」の仕組みの具体化に向けた検討に着手しました。「日本版コネクト&マネージ」とは、緊急時用に空けていた容量や、容量を確保している電源が発電していない時間などの「すきま」をうまく活用して、よりたくさんの電気を流せるようにしようというものです。
この「日本版コネクト&マネージ」は多数の再エネ事業者から接続の要望があるところ、スピード感をもって再生可能エネルギーを導入拡大する観点から、関係者間での課題に関する調整が済んだものから実現していく方針で、まずは一般送配電事業者が行う「空き容量の算定方法」を2018年度当初から抜本的に見直しました。これによって、過去の実績を基に、将来の電気の流れをより精緻に想定して空き容量を算出し、より多くの再エネ等新規電源を連系させることが可能となりました。今後も、新たに系統に接続しようとする発電事業者の意見も聞きながら、現行のルールが透明・公平かつ適切なものなのかを確認し、海外の先進的事例を取り入れながら必要な見直しを行うとともに、ルールの明確化を進めてまいります。
(4)適切な調整力の確保
電力では需給バランスを一致させる必要性があるため、自然変動再エネ(太陽光・風力)の導入が拡大することで、出力変動を調整しうる「調整力」を効率的かつ効果的に確保することが、大量の再エネを電力系統に受け入れるための課題になってきています。2017年度よりディマンドリスポンスが新たに電力の需給バランス調整に活用されるようになっていますが、当面は、火力発電や揚水発電による調整が中心となりますので、社会コストを最小化しつつ、いかに広域的かつ柔軟な調整が可能な環境を整備するかが重要となります。
将来的には、蓄電技術の導入によって調整力の脱炭素化を進めていくことも重要であり、それぞれの課題を整理しながら、その道筋を描いていく必要があります。なお、詳細な市場設計やルール整備については、本節「5.エネルギーシステム改革」で後述します。
4.原子力政策の今後
(1)原子力政策の動向
今後の原子力利用に向けた課題
第四次エネルギー基本計画に基づき、原子力については、依存度を可能な限り低減ししていくとともに、安全最優先で利用していくというのが政府の方針です。この方針に基づき、これまでも原子力に関する諸課題について取り組んできましたが、いまだ国民から十分に信頼を得ているとは言いがたい状況であり、原子力利用に対する社会的信頼の獲得に向けた取組を加速・強化していく必要があります。震災から7年経過した今なお、原子力政策の原点は、福島事故への真摯な反省です。こうした反省を忘れることなく、社会的信頼の獲得に向けては、最優先課題としての福島復興・事故収束の加速はもちろんのこと、①さらなる安全性の向上、②防災・事故後対応の強化、③核燃料サイクル・バックエンド対策、④状況変化に即した立地地域への対応、⑤対話・広報の取組強化、⑥原子力の将来課題に向けた技術・人材・産業基盤維持・強化といった様々な観点から取組を進めていくことが求められています。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
(2)社会的信頼の獲得に向けた取組の方向性
① さらなる安全性の向上
原子力の安全性の向上においては、リスクはゼロにならないという考えの下、規制基準における安全対策に加え、産業界が自主的に安全対策を追求していくことが重要です。
今後は、現場から経営に至るすべての関係者の間で、「不断の安全性向上」が実現すべき「価値」として共有され、組織全体で一体的・効果的に改善を積み重ねていくような「組織文化」の確立や、産業全体での知見の結集・共通課題の抽出、それを踏まえた規制当局・社会とのコミュニケーションを行うことが求められます。こうした事業者の取組に加えて、事業者の安全性向上の取組の「見える化」や、社会的評価付け等によるインセンティブ強化など行政によるサポートの強化も重要です。
② 防災・事故後対応の強化
東京電力福島第一原子力発電所事故では、多くの住民が避難を強いられ、財産的・精神的な損害に対して多額の賠償が実施されています。こうした教訓や実態も踏まえて、避難や賠償のための制度が拡充されています。今後は、万が一の事故の際に迅速な対応ができるよう、防災や賠償について平時から取組を進めておくことが重要です。
③ 核燃料サイクル・バックエンド対策
まずは、六ヶ所再処理工場などの核燃料サイクル関連施設の着実な竣工・事業開始や高速炉開発方針の具体化に取り組むとともに、「利用目的のないプルトニウムは持たない」との原則の下、プルサーマルの推進などを通じてプルトニウム・バランスを確保し、国際社会の理解を得ることが重要です。
また、再稼働や廃炉の進展、六ケ所処理工場の竣工の遅れ等により、使用済燃料対策の重要性は一層高まっており、喫緊の課題となっています。使用済燃料対策推進協議会などを通じて、今後とも対策がしっかり進むよう、官民をあげて取組みます。
最終処分の取組について、科学的特性マップの提示は、その長い道のりの最初の一歩です。将来的に複数の地域に処分地選定調査を受け入れていただくことを目指して、国民理解・地域理解を深めていくための取組を一層強化します。また、最終処分に向けた研究成果・人材の継承・発展、国際協力にも取り組みます。
原子力依存度は可能な限り低減するという方針の下、廃炉の重要性は今後一層高まる見通しであり、安全かつ着実な廃炉の実施も求められます。先行する海外企業との連携など、廃炉工程の最適化に向けた国内企業の動きが出てきており、安全を担保しつつ、コスト効率性との両立が図られつつあります。一方、多くの事業者にとって、経験蓄積のための現場や人材育成の機会は限定的であり、廃炉工程で発生する低レベル放射性廃棄物の処分場は現在国内に存在していません。このような中、長期間にわたる廃炉作業を、当初の計画通りに完遂することが極めて重要です。課題に応じた対策を早期に検討し、実行していくことが必要です。
④ 状況に即した立地地域への対応
原子力発電の稼働停止の長期化や廃炉などの環境変化の中で、各地域が抱える課題は様々になってきており、地域ごとの実情に合わせて支援を行っていくことが重要です。
⑤ 対話・広報の取組強化
日本では、国民が知りたい情報にアクセスできるよう根拠情報の整備をするとともに、情報過多にならないようにわかりやすくまとめる工夫も必要です。また一方向の情報発信だけでは「安心」につながらないため、関心・意見を踏まえた、双方向の対話を進める必要があります。さらに、ITやスマートフォンなどの進歩・普及に伴って、国民の情報収集/発信スタイルは大きく変化しているため、より効果的な広報手法を充実化していく必要もあります。
こうした観点から、資源エネルギー庁はホームページで、原子力を含む広くエネルギーに関する話題をわかりやすく発信する「スペシャルコンテンツ」を開始しました。また、「科学的特性マップ」に関する説明会でも、参加者から自らの意見を述べ、理解を深められる双方向での対話を、実施主体担当者が手作りで運営するなど、対話型、Pull型の取組を行っており、引き続き広聴・広報事業に広げていく必要があります。
⑥ 原子力の将来課題に向けた技術・人材・産業の基盤維持・強化
安全かつ効率的な原子力利用の前提となる、原子力技術・人材、高度な研究開発基盤、サプライチェーンの維持・発展を図り、再稼働や国内外建設プロジェクト等を通じて世界水準の技術力を維持することが課題です。
メーカーにおいて、原子力関連業務に従事する従業員数は、震災以降は減少傾向にあり、また原子力関連企業の就職説明会に参加する非原子力系の学生は大きく減少しています。大学における原子力関連の教員、特に若年層が減少し、年齢層が高齢化するとともに、国立研究開発法人として我が国の原子力分野の研究開発を担う日本原子力研究開発機構(JAEA)の人員・予算は減少傾向にあります。原子力の将来を担う人材にとって、魅力的な将来ビジョンを提示できるような状況を構築することが重要です。
5.エネルギーシステム改革
戦後60年余り続いた我が国の電気事業制度は、東日本大震災やその後の電力需給の逼迫を契機に、広域融通の限界や料金水準の高騰といった課題が浮き彫りとなりました。こうした課題を克服しつつ、電力やガス、あるいは供給区域といった市場の垣根を越えた競争が可能となるエネルギー市場を形成すべく、岩盤規制打破に向けたアベノミクスの改革の柱の1つとして、①安定供給の確保、②電気料金の最大限の抑制、③事業者の事業機会及び需要家の選択肢の拡大を目的とする電力システム改革のための電気事業法等の抜本改正が2013年から3段階に分け行われました。
改革の第3弾となる2020年の発送電分離に向けて、さらなる競争の活性化が期待される中で、今後とも競争を通じ、電気料金の抑制や選択肢の拡大を通じて電力システム改革の果実を国民に広く還元するためには、公正・公平な競争環境を整備することが必要不可欠であり、同時に、市場原理のみでは解決が困難な公益的課題の克服を図る必要があります。そこで、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会に「電力システム改革貫徹のための政策小委員会(以下、「貫徹小委」という。)」を2016年9月に設置し、競争活性化の方策と競争の中でも公益的課題への対応を促す仕組みの具体化に向け審議を依頼し、2016年12月に中間とりまとめを行いました。
また、2017年4月1日から、ガスの小売全面自由化が開始されました。これにより、各地域の一般ガス事業者からしかガスの供給を受けることができなかった一般家庭等が、他事業者からもガスの供給を受けることができるようになりました。
今般のガスシステム改革では、電力システム改革同様、①安定供給を確保すること、②ガス料金を最大限抑制すること、③需要家の選択肢や企業の事業機会を拡大すること、の3つを主要な目的に据えました。より具体的には、①安定供給については、一般ガス導管事業者に対して導管網の建設・保守、最終保障サービスを義務付けることや、導管網の整備・相互接続を促進することで、安定供給を確保することを目指すこととしています。②ガス料金については、事業者間の競争や、他業種・他地域からの参入を促し、創意工夫や経営努力を引き出すことで、ガス料金の最大限の抑制を目指すこととしました。③選択肢・事業機会については、新しい発想を持つ事業者の参入を促し、一般家庭や企業を含めた全てのガスの利用者が自由に供給者を選択できるようにするとともに、導管網の整備・相互接続を促進することで選択肢・事業機会を拡大することを目指すこととしています。
本項では、電力システム改革の下における、競争活性化の方策と、競争の中でも公益的課題への対応を促す仕組みの整備について紹介します。
(1)市場・ルールの整備
電力システム改革貫徹のためには、市場メカニズムを有効に活用しつつ、3E+Sの実現を目指すことが重要です。そのため、卸電力市場をはじめとした既存の市場の流動性を高めるとともに、容量市場や非化石価値取引市場など、これまでになかった新たな市場を創設することにより、新たな価値を顕在化・流動化させていくことが適当です。こうした考え方に基づき、貫徹小委の下に「市場整備ワーキンググループ」を設置し、主に①ベースロード電源市場、②連系線利用ルール、③容量メカニズム、④非化石価値取引市場の4つの制度に関して、その意義と基本的な考え方、今後さらなる検討を進める上での留意事項等について議論を行い、結果を取りまとめました。
2017年3月に、貫徹小委中間とりまとめにおいて方向性が示された新たな市場の制度設計等について検討すべく、総合資源エネルギー調査会電力・ガス基本政策小委員会の下に「制度検討作業部会」が設置されました。本作業部会では、実務的な観点を十分に踏まえるべく、新電力等からのヒアリングに加えて意見募集も行った上で、検討を進め、2017年7月には第1次、同年12月には第2次の中間論点整理を行ってきました。
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
① さらなる競争活性化に向けた取り組み
(ア)ベースロード電源市場の創設
石炭火力や大型水力、原子力等の安価なベースロード電源については、大手電力会社が大部分を保有しており、新電力のアクセスは極めて限定的となっています。その結果、新電力はベースロード需要をLNG等のミドルロード電源で対応せざるを得ず、大手電力会社と比して十分な競争力を有しない状況が生じています。
これまでの自主的取組を通じて、旧一般電気事業者は、自社で保有等する限界費用の高い余剰電源(ミドル・ピーク電源)を中心に、卸電力取引所等に投入してきましたが、発電コストが安いベースロード電源については、経済合理的な判断の下、専ら自社で利用してきました。このため、自主的取組の一環である、電源開発株式会社と契約している電源の切出しについては、現在まであまり進んできませんでした。
新電力がベースロード電源にアクセスすることを可能とするためには、旧一般電気事業者等が保有するベースロード電源に関連する取引に対して、一定の制約を課す必要があります。具体的には、実効的な仕組を通じて、発電した電気の一部を適正な価格でベースロード電源市場(以下、「BL市場」という。)に供出することを、旧一般電気事業者等に求めることが必要です。
加えて、貫徹小委の議論においては、新電力のベースロード電源へのアクセスを容易とするための施策として、BL市場を創設し、旧一般電気事業者と新電力のベースロード電源へのアクセス環境のイコールフッティングを図り、さらなる小売競争の活性化を図ることが適当とされました。また、同市場における取引の実効性を確保する観点から、ベースロード電源を保有する旧一般電気事業者等が発電した電気の一部を、適正な価格で市場供出することを、制度的に措置することとされました。
なお、貫徹小委の中間とりまとめにおいて、BL市場及び制度的措置の詳細設計は、遅くとも2020年度から電気の受け渡しを開始できるように、今後検討を行うこととしています。これを受け、関連するその他制度・規制との関係も踏まえつつ、BL市場について論点整理を行ったところであり、今後とも詳細設計を議論していきます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
(イ)間接オークション・間接送電権の導入
地域間(エリア間)連系線の利用については、現在、「先着優先」と「空おさえの禁止」を原則として、広域機関によって利用計画が管理されています。貫徹小委中間とりまとめにおいては、連系線利用ルールを見直すことで、公正な競争環境の下、送電線の利用と広域メリットオーダーの達成を促し、さらなる競争活性化を通して電気料金を最大限抑制し、事業者の事業機会の拡大を実現していくことが適当とされました。また、公平性・公正性を確保するとともに、卸電力市場の取引量増加を図るため、現行連系線利用ルールを「先着優先」から、市場原理に基づきスポット市場を介して行う「間接オークション」へと変更することを軸にルールの見直しを行うこととされました。その後、2017年7月の制度検討作業部会の第一次中間論点整理において、「先着優先」に基づく連系線の利用登録の受付を停止する形で間接オークションが導入されることとされました。なお、間接オークションの導入時期は2018年度とされています。
日本卸電力取引所(JEPX)の前日スポット市場においては、全国の参加者が売り買いの入札をし、売り札についている最も価格の安いものから、買い札については最も価格が高いものから約定するよう約定計算が行われます。こうした約定計算を行う際、連系線をまたぐ取引の量が計算され、全ての取引が連系線の空容量の範囲内で取引を行うことができれば、全国一律の価格(システムプライス)に決定されます。他方で、連系線の空容量の範囲内では取引できない場合、連系線の空容量を勘案し各々の連系線を最大限活用するよう、改めて約定計算が行われます。こうして連系線混雑を考慮し約定計算をした結果、エリアごとに計算されるスポット価格(エリア価格)が異なる場合があり(市場分断)、このエリア間の価格の差異を「エリア間値差」と称します。
貫徹小委や制度検討作業部会においては、先着優先から間接オークションへの移行やBL市場等の卸電力市場活性化策の実施に伴い、エリア間値差がより多くの事業者に影響を及ぼしうることを踏まえ、こうしたリスクを軽減する仕組みが必要との議論が行われてきました。
諸外国においても、例えば、米国のPJMエリア(ペンシルバニア州、ニュージャージー州、メリーランド州、バージニア州及びデラウェア州)においては、地点別の限界価格(LMP)に頻繁に値差が発生することによる事業者のエリア間値差の負担リスクを減少させられるよう、間接送電権の仕組みが整備されています。
上記を踏まえ、我が国においても間接送電権の仕組みを整備することが考えられます。その際、詳細設計の検討にあたっては、①BL市場を含む先渡市場や、前日スポット市場、相対取引等における、エリアをまたぐ広域的取引の環境の整備、②連系線の効率的な利用、③間接送電権の取引の透明性の確保という視点を踏まえながら、取引参加者にとっての利便性や、BL市場を含む先渡市場の活性化にも留意しつつ、検討を進めていくことが求められます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
② 自由化の下での公益的課題への対応
(ア)容量市場の創設
かつての総括原価方式の枠組みの下では、発電投資は規制料金を通じて安定的に回収されてきました。総括原価方式と規制料金の枠組みによる投資回収の枠組みがない中では、原則として、発電投資は市場取引を通じて、または市場価格を指標とした相対取引の中で投資回収されていく仕組みに移行していくと考えられます。このため、固定価格買取制度の対象となる再生可能エネルギー電源を除けば、大部分の電源に係る投資回収の予見性は、従来の総括原価方式下の状況と比較して、低下すると考えられます。
また、固定価格買取制度等を通じて、再エネが拡大することになれば、従来型電源の稼働率が低下するとともに、再エネ電源が市場に投入される時間帯においては市場価格が低下し、全電源にとって売電収入が低下すると考えられます。その結果、電源の将来収入見通しの不確実性が高まり、事業者の適切なタイミングにおける発電投資意欲を更に減退させる可能性があります。
今後、仮に電源投資が適切なタイミングで行われなかった場合、電源の新設やリプレース等が十分になされない状態で、既存発電所が閉鎖されていくこととなります。そのような場合には、中長期的に供給力不足の問題が顕在化し、更に電源開発に一定のリードタイムを要することから、①需給が逼迫する期間にわたり、電気料金が高止まりする問題や、②再エネを更に導入した際の需給調整手段として、必要な調整電源を確保できない問題等が生じると考えられます。
2017年3月に電力広域的運営推進機関が取りまとめた「平成29年度供給計画の取りまとめ」においては、今後10年間を見渡した際に、事業者間競争が激しい中央エリア(東京・中部・関西)において、旧一般電気事業者である発電事業者が経年火力発電所を休止していくなどの要因から、供給予備率が8%を下回る年度があることが示されました。また、発電電力量に占めるLNG火力及び石油火力の比率が低下していく傾向にあることも示されました。
こうした状況を踏まえると、単に卸電力市場(kWh価値の取引)等に供給力の確保・調整機能を委ねるのではなく、一定の投資回収の予見性を確保する施策である容量メカニズムを追加で講じ、電源の新陳代謝が市場原理を通じて適切に行われることを通じて、より効率的に中長期的に必要な供給力・調整力が確保できるようにすることが求められます。
貫徹小委中間とりまとめにおいては、こうした観点から検討を進めた結果、一定量の供給力を確保することができる「容量市場」は、①予め必要な供給力を確実に確保することができること、②卸電力市場価格の安定化を実現することで、電気事業者の安定した事業運営を可能とするとともに、電気料金の安定化により需要家にもメリットがもたらされること、③再エネ拡大等に伴う売電収入の低下は全電源に影響していること等を踏まえると、最も効率的に中長期的に必要な供給力等を確保するための手段であるとされました。
また、こうした措置は、投資回収の予見性を高めるための措置であり、必要な電源投資等のための総コストは変わらない、もしくはリスクプレミアム等の金利分が減少することから、中長期的に見た小売事業者の負担はむしろ抑えられると評価されています。
ほとんどの自由化先進国において、前述した意義に基づき、容量メカニズム等の投資回収の予見性を高める施策が措置されています。一般に、容量メカニズムは供給信頼度確保を目的として導入され、容量市場は、長期的に必要な供給力を確保する観点からは、他の同種の制度よりも、より良いと考えられています。
制度検討作業部会においては、貫徹小委中間とりまとめを受け、容量市場の詳細制度設計について、本作業部会におけるヒアリングや、広域機関における検討も踏まえつつ、検討を行っていきます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
(イ)需給調整市場の創設
一般送配電事業者が電力供給区域の周波数制御、需給バランス調整を行うために必要な調整力を調達するにあたっては、特定電源への優遇や過大なコスト負担を回避しつつ、実運用に必要な量の調整力を確保することが重要となります。
このような観点から、一般送配電事業者による調整力の公募が実施されることとなり、2016年末に行われた初回の調整力公募においては、最大で約4万円/kWという価格で調整力の確保が行われるとともに、エリア間で最大約4倍の価格差(最大は九州電力の約4.2万円/kW、最低は中国電力の約1.0万円/kW)がつくこととなりました。また、調整力として用いられる火力発電所や揚水発電所の大半が、旧一般電気事業者から調達されています。同時に、厳気象対象用の調整力としてはディマンドリスポンス(DR)事業者等の旧一般電気事業者以外の調整力も活用されることとなりました。
貫徹小委中間とりまとめにおいては、今後、公募結果を踏まえつつ、需給調整市場の詳細設計を行い、一般送配電事業者が調整力を市場で調達・取引できる環境を整備することが適当であるとされました。また、電力システム改革専門委員会報告書においても、系統運用者が供給力を市場からの調達や入札等で確保した上で、その価格に基づきリアルタイムでの需給調整・周波数調整に利用するメカニズムを送配電部門の一層の中立化に伴い導入することが適当であると記載されています。
諸外国においても需給調整市場を開設し、調整力を市場の仕組みを活用して前週や直前に調達しています。同時に、欧米においては需給調整の広域化にも取り組んでおり、例えば欧州は卸電力市場の広域統合から、需給調整市場の広域統合へ、ルール整備と実証を加速しています。
我が国においても、再エネの導入が進む中で、調整力を効率的に確保していくことは重要な課題です。他方で、需給調整市場の詳細検討にあたっては、需給調整の実運用とも密接に関わるため、慎重な検討が求められます。また、各一般送配電事業者による需給調整が中央給電指令所のシステムを活用して行われ、連系線の運用も一定のルールの下で広域機関も含めたシステムを用いて行われていることから、市場設計はこうしたシステムの改修が必要となります。他方で、こうしたシステムは、現状において、広域的な調整力の市場調達やその運用を前提として構築されていないのみならず、計画値同時同量制度が開始された今日においても、旧一般電気事業者の発電・小売バランシンググループの電源の最適運用とエリアの需給バランス調整のための調整電源の運用が一体的に行われるシステムが継続的に使用されているという実情があります。こうしたシステムの改修や、実運用の変更を、日々の需給調整に支障を生じさせない形で行うためには、ルール検討やシステム構築のための十分な期間とともに、関係者の多大な努力が必要となります。
制度検討作業部会においては、こうした制約や日々の需給調整に支障を生じさせないことの重要性を認識しつつも、広域化等による需給調整の効率化や、調整力確保に係る市場メカニズムの採用による透明性の向上、DR事業者や新電力等の新規事業者を含めた形での調整力の確保といった諸課題に対応することは、2020年以降の電力システムにとって必須の課題であるとの認識の下、需給調整市場の詳細制度設計を検討していきます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
(ウ)非化石価値取引市場の創設
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(以下、「高度化法」という。)により、小売電気事業者は、自ら調達する電気の非化石電源比率を2030年度に44%以上にすることが求められています。
しかし、卸電力取引所では、非化石電源と化石電源の区別がされないため、非化石電源の持つ価値が埋没し、非化石電源比率を高める手段として活用ができません。結果、取引所取引の割合が比較的高い新規参入者にとっては特に、非化石電源を調達する手段が限定される状況になっており、高度化法の目標達成が困難な面があります。
また、FIT電気(固定価格買取制度に基づき買い取られた電気)の持つ環境価値(非化石価値を含む)については、現状、賦課金負担に応じて全需要家に均等に帰属するものと整理されており、国民負担の軽減を図る観点から、その価値を顕在化するような制度設計のあり方についてのさらなる検討が求められているところです。
このような状況を踏まえ、新たな市場である非化石価値取引市場を創設することによって非化石価値を顕在化し、取引を可能とすることで、小売電気事業者の非化石電源調達目標の達成を後押しするとともに、需要家にとっての選択肢を拡大しつつ、FIT制度による国民負担の軽減を促します。FIT電気に由来する非化石証書の取引については、2018年5月に初回オークションを開始する予定です。
また、本市場の創設に当たっては、上記の制度趣旨を踏まえ、非化石価値を顕在化し、その価値に適切に評価を与えることができるよう、以下のとおり、非化石証書の有する環境価値と、需要家にとっての選択肢拡大という非化石証書の主な役割について基本的な考え方を整理しました。
(i)非化石証書の有する環境価値
電気の持つ環境価値としてはいくつかの概念が考えられますが、(i)非化石価値(高度化法上の非化石比率算定時に非化石電源として計上できる価値)以外に、(ii)ゼロエミ価値(CO2排出係数が0kg-CO2/kWhであることの価値)や③環境表示価値(小売電気事業者が需要家に対しその付加価値を表示・主張する権利)が主なものとして挙げられます。
ゼロエミ価値については、そもそも全ての非化石電源はCO2排出量がゼロであることに鑑み、非化石価値と同時にゼロエミ価値が移転されるものと整理します。
環境表示価値については、非化石証書によって加算された非化石比率やオフセットされた排出係数に関しては、その付加価値を需要家に訴求することは可能とします。ただし、電力の小売営業に関する指針において、電源構成表示に関しては、実際に受電した電源の構成を表示するとの整理がなされており、非化石証書を購入しても電源構成は変わらない点に留意が必要です。他方、同指針において、再エネ由来の証書に関しては、電源構成外にて「実質再エネ100%」等の表示を許容することとしています。
(ii)需要家の選択肢の拡大
証書を購入した小売電気事業者は、非化石価値(再エネ由来の価値)を電気とともに需要家に販売することが可能となります。従って、例えば再エネの推進に貢献したいと考える需要家は、数ある料金メニューから、こうした小売電気事業者が提供する再エネ価値付きのメニューを選択することで、実際に貢献することが可能となります。需要家のニーズが高ければ、非化石価値取引市場が積極的に活用され、小売電気事業者のサービス多様化が図られることが期待されます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
(2)自由化の下での財務会計面での課題解決に向けた取組
2016年4月の小売全面自由化以降、総括原価方式による料金規制の撤廃に伴い、電気事業の財務・会計上の特性にも変化が生じました。このため、電力分野の自由化を進めるに当たっては、これら制度変更に伴う課題として、一般の事業においては問題とならないような、例えば、制度変更により事後的に費用が増大する場合の対応費用をどのように回収するかが課題となり得ます。このため、財務・会計制度や負担のあり方について、具体的な措置の検討・審議を行うため、貫徹小委の下に「財務会計ワーキンググループ」を設置し、小売全面自由化の下での原子力事故に係る賠償への備えに関する負担や廃炉に係る会計制度のあり方に関する議論を行い、2017年2月に結果をとりまとめました。
とりまとめで示された方向性を踏まえ、財務会計面での課題解決に向け、2017年10月、2018年4月に制度改正を実施しました。
① 原子力事故に係る賠償への備えに関する負担のあり方
東京電力福島第一原子力発電所の事故後、原子力事故に係る賠償への備えとして、従前から存在していた原子力損害賠償法に加えて新たに原子力損害賠償・廃炉等支援機構法が制定され、現在、同法に基づき、原子力事業者が毎年一定額の一般負担金を原子力損害賠償・廃炉等支援機構に納付しています。原子力損害賠償法の趣旨に鑑みれば、本来、こうした万一の際の賠償への備えは、東京電力福島第一原子力発電所事故以前から確保されておくべきでしたが、政府は何ら制度的な措置を講じておらず(=制度の不備)、事業者がそうした費用を料金原価に算入することもありませんでした。従来、総括原価方式の下で営まれてきた電気事業においては、一般の事業と異なり、将来的な費用増大リスクを見込んだ自由な価格設定を行うことはできず、料金の算定時点で合理的に見積もられた費用以外を料金原価に算入することは認められていませんでした。これは、規制料金の下では、全ての需要家から均等に費用を回収することとなるため、同じ電気を利用した需要家間では不公平は生じないということを前提として、その電気を利用した時点で現に要した費用(合理的に見積もられた費用)のみ料金原価への算入を認めるという考え方に基づいています。
しかし、2016年4月に小売が全面自由化され、新電力への契約切替えにより一般負担金を負担しない需要家が増加していることを踏まえ、賠償の備えを小売料金のみで回収するとした場合、過去に安価な電気を等しく利用してきたにもかかわらず、原子力事業者から契約を切り替えた需要家は負担せず、引き続き原子力事業者から電気の供給を受ける需要家のみが全てを負担していくことになります。こうした需要家間の格差を解消し、公平性を確保するためには、全需要家が等しく受益していた賠償の備えについて、全ての需要家が公平に負担することが適当であり、また、そうした措置を講ずることが、福島の復興にも資するものとの考えに立ち、負担のあり方について、貫徹小委で検討を進めました。その結果、回収する金額の規模は、現行の一般負担金の算定方法を前提とすることが適当と考えられ、現在の一般負担金の水準をベースに、1kWあたりの単価を算定した上で、これを前提に、2010年度までの我が国の原子力発電所の毎年度の設備容量等を用いて算出した金額から、回収が始まる前の2019年度末時点までに納付した又は納付することになると見込まれる一般負担金の合計額を控除した約2.4兆円としました。回収方法については、電源構成に占める原子力の割合は供給区域ごとに異なる一方で、賠償の備えの負担は、過去の原子力の電気の利用に応じて行うべきものであることや、現状、一般負担金は小売規制料金に含まれ、供給区域ごとに異なる水準となっていること等を踏まえると、賠償の備えを国民全体で負担するに当たっては、特定の供給区域内の全ての需要家に一律に負担を求める託送料金の仕組みを利用することが適当と考えられました。
こうした検討を踏まえ、東京電力福島第一原子力発電所事故以前から確保されておくべきであった賠償の備えを託送料金で回収する仕組みを可能とする制度改正(電気事業法施行規則の改正)を2017年9月に実施しました(施行は2020年4月1日)。
なお、留意点として、本来、発電部門の原価として回収されるべき賠償の備えについて、託送料金の仕組みを通じて広く全需要家に負担を求めるに当たっては、その額の妥当性を担保する措置を講ずるとともに、個々の需要家が自らの負担を明確に認識できるよう、指針等を通じ、小売電気事業者に対し、需要家の負担の内容を料金明細票等に明記する措置を講じることとされました。また、原子力に関する費用について、託送料金の仕組みを通じた回収を認めることは、結果として、原子力事業者に対し、他の事業者に比べて相対的な負担の減少をもたらすものであり、競争上の公平性を確保する観点から、原子力事業者に対しては、例えば、原子力発電から得られる電気の一定量を小売電気事業者が広く調達できるようにするなど、一定の制度的措置を講じることとしています。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
② 福島第一原子力発電所の廃炉の資金管理・確保のあり方
東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に必要な資金については、東京電力が負担することが原則であり、東京電力にグループ全体で総力を挙げて捻出させる必要があるとの考え方の下、「国民負担増とならない形で廃炉に係る資金を東京電力に確保させる制度」について、2016年10月に東電委員会から国に対して検討要請がなされました。
この要請を踏まえ、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉の円滑かつ着実な実施を担保するため、長期間にわたり必要となる巨額の資金の管理を担保する制度として、事故炉の廃炉を行う原子力事業者(事故事業者)に対し、廃炉に必要な資金を機構に積み立てることを義務付ける等の措置を講じることを内容とする廃炉等積立金制度を2017年10月より開始しました。
また、発電・送配電・小売りに分社化されている東京電力において、グループ全体で総力を挙げて捻出する資金が自由化の下でも確実に廃炉に充てられるための制度として、東京電力パワーグリッド(送配電部門、以下「東電PG」という。)が親会社(東京電力ホールディングス)に対して支払う東京電力福島第一原子力発電所の廃炉費用相当分について、超過利潤と扱われないように費用側に整理して取り扱われるようにするとともに、乖離率の計算に際して実績単価の費用の内数として扱われるようにする制度的措置を2018年3月に実施しました。なお、この措置を講ずるに当たっては、東電PGの託送料金の値下げ機会が不当に損なわれないよう、東電PG自体の超過利潤・乖離率の代わりに、他の一般送配電事業者の効率化達成状況によって値下げ命令の要否を判断するとともに、東電グループ全体の中で東電PGの負担が過大なものとならないよう、例えば収益性や資産状況を参考に、グループ各社との負担の程度を比較し、著しく不適当な分担となっていないかどうかを確認する措置についても併せて講じています。
③ 廃炉に関する会計制度の扱い
(ア)廃炉会計制度について
従前の電気事業会計制度の下では、廃炉に伴う資産の残存簿価の減損等により、一時に巨額の費用が生じることで、(i)事業者が合理的な意思決定ができず廃炉判断を躊躇する、(ii)事業者の廃炉の円滑な実施に支障を来す、との懸念がありました。このため、2013年と2015年に、設備の残存簿価等を廃炉後も分割して償却(=負担の総額は変わらないが、負担の水準を平準化)する会計制度が措置されました。こうした制度整備を受けて、2015年に5基、2016年に1基の原子炉について、廃炉決定が行われています。
廃炉会計制度は、計上した資産の償却費が廃炉後も着実に回収される料金上の仕組みが併せて措置されることを前提としており、現在は小売規制料金により費用回収することが認められています。したがって、現在経過的に措置されている小売規制料金が原則2020年に撤廃されることを見据えた場合、今後も制度を継続するには、着実な費用回収を担保する措置を講ずることが不可欠です。この点、2015年3月の廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループ報告書(「原発依存度低減に向けて廃炉を円滑に進めるための会計関連制度について」)においては、競争が進展した環境下においても制度を継続させるためには、「着実な費用回収を担保する仕組み」として、総括原価方式の料金規制が残る送配電部門の託送料金の仕組みを利用することとされていました。
制度創設の経緯・趣旨を踏まえれば、廃炉会計制度は、原発依存度低減というエネルギー政策の基本方針に沿って措置されたものとして、本制度を継続することが適当であるとされました。本制度を継続するために必要となる着実な費用回収の仕組みについては、小売規制料金が原則2020年に撤廃されることから、自由化の下でも規制料金として残る託送料金の仕組みを利用することが妥当と考えられます。
こうした検討を踏まえ、廃炉を行う際の設備の残存簿価等について、引き続き小売料金での償却等を認め、2020年4月以降に託送料金での回収を可能とする制度改正(電気事業会計規則等の改正)を2017年10月に実施しました。なお、発電、送配電、小売の各事業が峻別された自由化の環境下で、発電に係る費用の回収に託送料金の仕組みを利用することは、原発依存度低減や廃炉の円滑な実施等のエネルギー政策の目的を達成するために講ずる例外的な措置と位置付けられるべきと考えられます。
(イ)原子力発電施設解体引当金について
原子炉の運転期間中に廃炉に必要な費用を着実に積み立てるため、原子力事業者は、毎年度、原子力発電所一基ごとの廃止措置に要する総見積額を算定し、経済産業大臣の承認を得た上で、各原子炉の発電実績に応じて原子力発電施設解体引当金として積み立てることが義務付けられています。解体引当金は、東京電力福島第一原子力発電所事故以降、原子力発電所の長期にわたる稼働停止が続き、従来の生産高比例法では引当が進まないといった課題が生じたことから、2013年、引当方法を定額法に、引当期間を運転期間40年に廃炉後の安全貯蔵期間10年を加えた原則50年に変更する制度改正が行われ、今後、競争が進展した環境下でも本制度を継続し、廃炉後の安全貯蔵期間中も引当を継続させるためには、廃炉会計制度と同様、費用回収が着実に行われる仕組みが必要となっています。
その引当期間については、事業者が負担するという原則に立てば、着実な費用回収が前提となる安全貯蔵期間に入る前、すなわち、廃炉前に引当を完了していることが廃炉を円滑に実施する観点からより適切な制度のあり方であり、原則50年としている引当期間を原則40年に短縮することとしました。
引当期間の見直しを行った場合、2013年の制度改正以降に廃炉決定し、解体引当金の残額を10年間に分割した引当を現在行っているものや、今後早期廃炉するものについては、解体引当金の未引当分を一括して引き当てる必要が生じます。しかし、制度の事後的な変更によって、事業者の財務に影響を与えることは適当でないことに加え、こうした費用の発生が早期廃炉を志向する事業者の判断を歪めるようなことがあれば、廃炉会計制度の趣旨にも反するので、2013年の制度改正以降に廃炉決定したものや今後早期廃炉するものに限り、廃炉に伴い一括して計上することが必要となる費用を廃炉会計制度の対象とすることで、一括して発生する費用を分割して計上する仕組みとすることとしました。
解体引当金の基礎となる原発の解体に必要な費用は、1985年及び1999年の総合資源エネルギー調査会原子力部会において示された算定式に基づき、毎年度、物価変動や廃棄物量の変動を加味し、炉ごとに総額(=総見積額)を算定しています。この算定式は、原子力部会において技術的な検討を行った結果として導き出されたものであり、その前提に大きな変更はないことから、現時点で合理的に見積もることできる費用が不足なく含まれているものと評価できます。一方で、この算定式は、モデルとなるプラントの廃炉工程を前提としたものであるため、今後、個々のプラントにおいて廃止措置を実施していく過程等で、例えば、多数の炉が設置されている原子力発電所では、設備の共有等による効率化などにより、総見積額の見直しが必要となり得ます。こうしたことを踏まえ、自由化の下でも廃炉に必要な費用があらかじめ確実に確保されるよう、個別の炉・発電所ごとに固有の事情(規制変更などにより算定式の前提を大幅に変更する必要がある場合を除く)が生じた場合に、当該事象を速やかに総見積額に反映させることが可能な仕組みを導入することが必要と考えられます。ただし、総見積額の妥当性を確保するため、これまでと同様に、総見積額を経済産業大臣が承認する仕組みとすることとしました。
これらの検討を踏まえ、引当期間を原則40年することに加えて、2013年の制度改正以降に廃炉決定したものや今後早期廃炉するものに限り、廃炉に伴い一括して計上することが必要となる費用を廃炉会計制度の対象とする等の制度改正(解体引当金省令の改正)を2018年4月に実施しました。
6.水素基本戦略の策定
水素は、我が国の一次エネルギー供給構造を多様化させ、大幅な低炭素化を実現するポテンシャルを有する手段です。2017年4月に開催された「第1回再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議」において、安倍首相から、政府が一体となって取り組むための基本戦略を策定するよう指示がありました。これを受けて、産学官の有識者から構成される「水素・燃料電池戦略協議会」における議論等を経て関係府省庁が案を取りまとめ、水素基本戦略として、同年12月に開催された「第2回再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議」で決定されました。
水素基本戦略は、個別技術の導入・普及に係る既存の水素・燃料電池戦略ロードマップの内容を内包しつつ、水素をカーボンフリーなエネルギーの新たな選択肢として位置づけ、政府全体として施策を展開していくための方針です。世界に先駆けて水素社会を実現するため、水素基本戦略や水素・燃料電池戦略ロードマップに基づき、供給・利用両面の取組を進めていきます。
水素の本格的な利活用のためには、水素をより安価で大量に調達することが必要となります。水素基本戦略では、本格的な商用利用が始まる2030年に30円/Nm3、2050年には20円/Nm3(現状の1/5)を目標に設定しています(現状コスト:~100円/Nm3(ステーション価格))。このため、海外の褐炭や原油随伴ガス等の未利用エネルギーを水素化し、国内に輸送する国際水素サプライチェーンの実証を進めています。
また、大量に水素を消費する水素発電については、2018年1月より神戸市において、水素をエネルギー源として電気と熱を街区供給する世界初の実証を開始しました。更に、高効率・高濃度な水素ガスタービンの燃焼技術等の開発が進められています。発電コストについても、2030年頃の時点で、17円/kWhを目標としており、また、将来的には環境価値も含め、既存のLNG火力発電と同等のコスト競争力(12円/kWh)を目標に設定しています。
また、2017年8月から福島県浪江町において、再生可能エネルギーの導入拡大や電力系統の安定化に資する技術として、太陽光発電といった自然変動電源の出力変動を吸収し、水素に変換・貯蔵するPower-to-gas技術の実証を開始しました。このほか、未利用となっている国内の地域資源(再生可能エネルギー、副生水素、使用済みプラスチック、家畜ふん尿等)から製造した水素を地域で利用する低炭素な水素サプライチェーン構築の実証等も進めています。
モビリティでの水素利用については、2013年から燃料電池自動車の市場投入に向けた水素ステーションの先行整備が開始され、2018年3月末までに約100か所の水素ステーションが開所しました。また、2014年12月に国内初の燃料電池自動車の市販が開始されたことに続き、2016年3月には2車種目の燃料電池自動車の販売が開始され、我が国では世界に先駆けて市場展開が進んでいます。更に、2016年度には燃料電池バス及び燃料電池フォークリフトが市場投入されました。今後は、燃料電池自動車や水素ステーションの普及に向け、低コスト化に向けた技術開発や、規制の見直し、水素ステーションの戦略的整備を進めるとともに、燃料電池バス及び燃料電池フォークリフトの導入拡大、トラック等の大型車両や船舶、鉄道車両など、他のアプリケーションの燃料電池化に向けた取組が求められます。
また、2009年に世界に先駆けて市場投入された家庭用燃料電池(エネファーム)については、技術開発によるコスト低減や性能向上、導入支援による普及初期の市場の確立などを通じて、2018年1月には約23.3万台が普及しました。2017年に市場投入された業務・産業用燃料電池についても導入支援による普及を図るとともに、発電効率向上に向けた機器開発、実装を進めていくことが重要です。
- 1
- 「総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会自動車判断基準ワーキンググループ」と「交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会 自動車燃費基準小委員会」