第1節 各国における気候変動対策・エネルギー政策の進捗と今後の対応
1.世界全体における温室効果ガス排出量の動向
(1)温室効果ガス排出量の推移
前述のとおり、多くの国が温室効果ガスの排出削減に向けた取組を加速させています。しかし、世界全体における温室効果ガス排出量の推移を見ると、いまだに増加傾向が続いていることがわかります。国連環境計画(UNEP)の報告書によると、2022年の世界全体の温室効果ガス排出量はCO2換算で574億トンであり、過去最高を記録しました。中でも、エネルギー起源CO2の排出増加が、世界全体の温室効果ガス排出量を増加させる主要因となっています。世界全体の温室効果ガス排出量を減らしていくためには、化石エネルギーの消費を世界的に減らしていくことが重要であるといえます(第131-1-1)。
【第131-1-1】世界の温室効果ガス排出量の推移
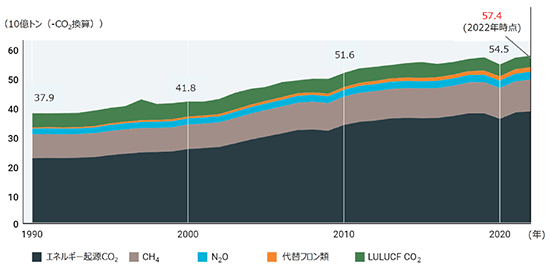
【第131-1-1】世界の温室効果ガス排出量の推移(ppt/pptx形式:134KB)
- 資料:
- UNEP「Emissions Gap Report 2023」を基に経済産業省作成
(2)エネルギー起源CO2排出量の推移
次に、温室効果ガス排出量の増加の主要因となっている、エネルギー起源CO2の排出量の推移について確認していきます。先進国(OECD)における排出量は、2007年をピークに、近年は減少傾向にあり、2021年の排出量は1990年比で2.4%の減少(ピーク時の2007年比では16.5%の減少)となっています。一方で、途上国(非OECD)における排出量は、経済成長に伴うエネルギー需要の増加等に伴い、特に2000年代以降に急増しており、2021年の排出量は1990年の約2.5倍となっています。中でも、中国とインドにおける排出量の増加が顕著であり、中国における2021年の排出量は1990年の約5.0倍に、インドにおける2021年の排出量は1990年の約4.3倍になっています(第131-1-2、第131-1-3)。
【第131-1-2】エネルギー起源CO2排出量の推移(OECD・非OECD別)
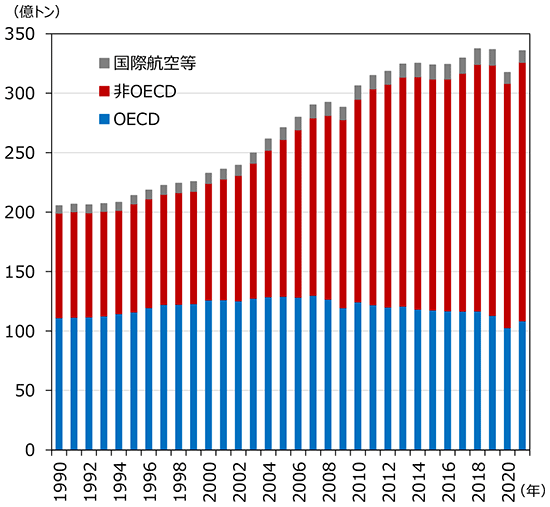
【第131-1-2】エネルギー起源CO2排出量の推移(OECD・非OECD別)(ppt/pptx形式:56KB)
- 資料:
- IEA「CO2 Emissions from Fuel Combustion」を基に経済産業省作成
【第131-1-3】エネルギー起源CO2排出量の推移(国別)
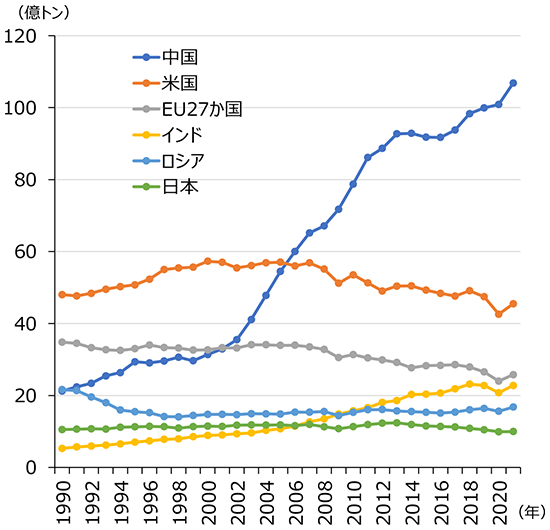
【第131-1-3】エネルギー起源CO2排出量の推移(国別)(ppt/pptx形式:69KB)
- 資料:
- IEA「CO2 Emissions from Fuel Combustion」を基に経済産業省作成
2021年の世界のエネルギー起源CO2排出量を国別に見ると、中国が世界全体の31.8%を占めており、次いで米国が13.6%、インドが6.8%、ロシアが5.0%を占めていることがわかります。また、EUは27か国の合計で7.7%、日本は3.0%を占めています(第131-1-4)。
【第131-1-4】2021年のエネルギー起源CO2排出量(国別)
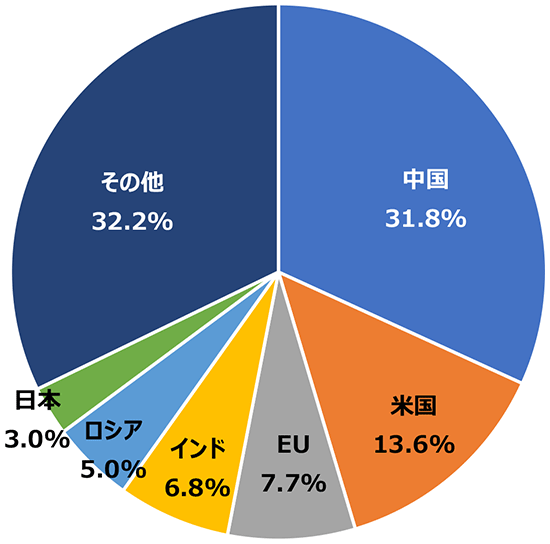
【第131-1-4】2021年のエネルギー起源CO2排出量(国別)(ppt/pptx形式:49KB)
- 資料:
- IEA「CO2 Emissions from Fuel Combustion」を基に経済産業省作成
(3)今後の見通し
エネルギー起源CO2の排出増加が続いている途上国では、今後も経済成長に伴ってエネルギー需要が増えることが予想されています。IEAによる将来見通し2によると、インドや東南アジア、中東、アフリカ等においては、2030年や2050年にかけて、エネルギー需要が大きく増加していくことが見込まれています(第131-1-5)。
【第131-1-5】地域別のエネルギー需要の見通し
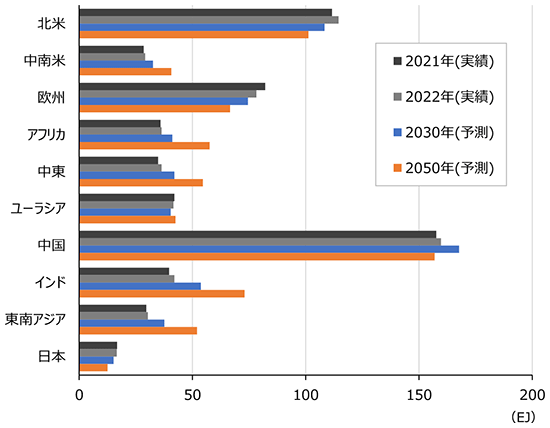
(注)2030年及び2050年の数値は、IEAが想定した将来シナリオであるSTEPS(各国が表明済の具体的政策を反映したシナリオ)における予測値。
【第131-1-5】地域別のエネルギー需要の見通し(ppt/pptx形式:52KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Outlook 2023」を基に経済産業省作成
一般的には、エネルギー需要が増えることで、エネルギー起源CO2の排出量も増加します。そのため、世界全体の排出削減を実現していくためには、今後もエネルギー需要の増加が見込まれる途上国において、排出削減に向けた取組を推進していくことが極めて重要です。そして、日本を含む先進国には、途上国におけるこうした取組を技術面や資金面等でサポートしていくことが求められています。
2.主要国における取組の進捗状況
これまでも各国では、それぞれの事情に応じた政策の下で、温室効果ガスの排出削減に向けた様々な取組が行われてきました。そのうち、エネルギー起源CO2の排出削減に向けては、一般的に、エネルギー供給の脱炭素化(非化石電源の拡大等)と、エネルギー消費効率の改善(省エネの推進等)を進めていく必要があります。本項では、日本を含む主要国(日本・米国・英国・ドイツ・フランス・EU)のNDC等の達成に向けたこれまでの進捗状況を整理するとともに、その要因や背景情報等について、エネルギー供給の脱炭素化(非化石電源比率)とエネルギー消費効率の改善(省エネ)に分解して確認していきます。
(1)日本
①温室効果ガスの削減目標と進捗状況
最初に、日本の状況について確認していきます。日本は、2030年度のNDCとして、2013年度比で温室効果ガスを46%削減する(さらに50%の高みに向けて挑戦を続ける)ことを目指しています。この目標の達成に向けた進捗として、2021年度における温室効果ガスの削減実績は21%となっています3。日本のNDCにおける基準年度である2013年度の温室効果ガス排出量の実績と、2030年度の目標を結んだ直線(基準年における実績値と目標値を結んだ直線のことを、以下「目標ライン」という。)を、実際の温室効果ガス排出・吸収量の実績と比較すると、2021年度時点においては、概ね目標ラインの水準に沿ったペースとなっていることがわかります。日本では、温室効果ガスの削減が着実に進んでいる状況(オントラック)です(第131-2-1)。
【第131-2-1】日本における温室効果ガスの削減状況
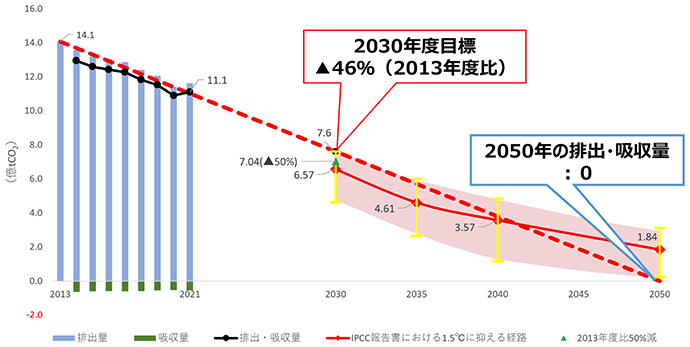
(注)図中の赤い帯の範囲は、2023年3月に公表されたIPCC(気候変動に関する政府間パネル)第6次評価報告書統合報告書において示された「1.5℃に抑える経路における世界全体の温室効果ガス排出削減量」を、仮想的に割り当てたもの。この報告書では、モデルの不確実性等を加味し、1.5℃に抑える経路については幅を持って示されているため、2030年・2035年・2040年・2050年時点における排出量についても、黄色線で幅を持って示している。また、その代表値をつないだものを赤色の実線で示している(以下各国における同種データについて同じ)。
【第131-2-1】日本における温室効果ガスの削減状況(ppt/pptx形式:240KB)
- 資料:
- 環境省作成
なお、日本の温室効果ガス排出量のうち、エネルギー起源CO2が占める割合は85%となっており、これは本項で確認している主要国の中で最も高い数値となっています。日本が温室効果ガス排出量を削減していくためには、徹底した省エネの取組とともに、一次エネルギーの大半を化石エネルギーに依存している現在の日本のエネルギー供給構造を、非化石エネルギー中心の構造へと転換するための取組を進めていくことが極めて重要です。
②エネルギー供給の脱炭素化(非化石電源の拡大等)
日本では、2021年10月に閣議決定された「第6次エネルギー基本計画」において、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」を示しています。これは、2030年度のNDCに向けて、徹底した省エネや非化石エネルギーの拡大を進める上での需給両面における様々な課題の克服を野心的に想定した場合に、どのようなエネルギー需給の見通しとなるかを示したものです。この中では、2030年度の電源構成に占める各発電方式の割合の見通しについても記載しており、その中で、非化石電源である再エネの割合については36%〜38%程度、原子力の割合については20%〜22%程度を見込むとしています。
この2030年度の見通しに対する日本の電源構成の推移を確認すると、再エネの導入拡大や、2011年に発生した東日本大震災後に稼働を停止していた原子力発電所の再稼働の進展等により、近年は非化石電源が着実に拡大していることがわかります。しかし、2021年度時点の非化石電源比率は27%に留まっており、今後、日本が排出削減をより一層進めていくためには、非化石電源の拡大に向けた取組の加速が必要不可欠となっています。2023年7月に閣議決定された「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」(以下「GX推進戦略」という。)の中でも、再エネの主力電源化と原子力の活用に向けた様々な取組の方針を明記していますが、非化石電源の拡大に向けて、こうした取組を着実に進めていくことが求められています。
また日本では、燃焼時のCO2排出が他の化石エネルギーよりも少ない天然ガス火力の導入を過去から進めてきた一方で、電源構成の約3割を燃焼時のCO2排出の多い石炭火力が占めているという特徴も見られます。石炭火力については、電力の安定供給の確保を大前提に、電源構成における比率を低減させることとしています(第131-2-2、第131-2-3)。
【第131-2-2】日本における電源構成の推移
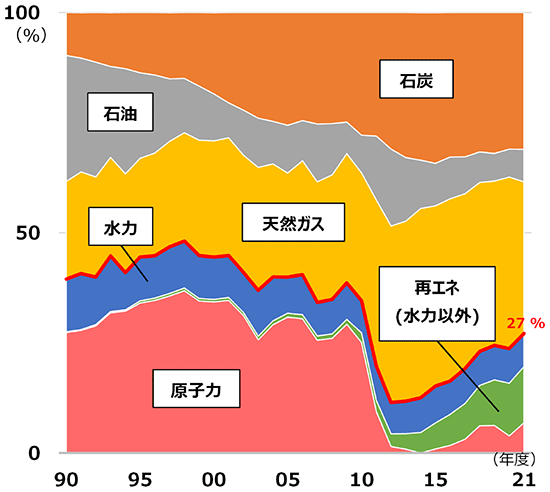
【第131-2-2】日本における電源構成の推移(ppt/pptx形式:211KB)
- 資料:
- 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に経済産業省作成
【第131-2-3】脱炭素成長型経済構造移行推進戦略(GX推進戦略)の概要
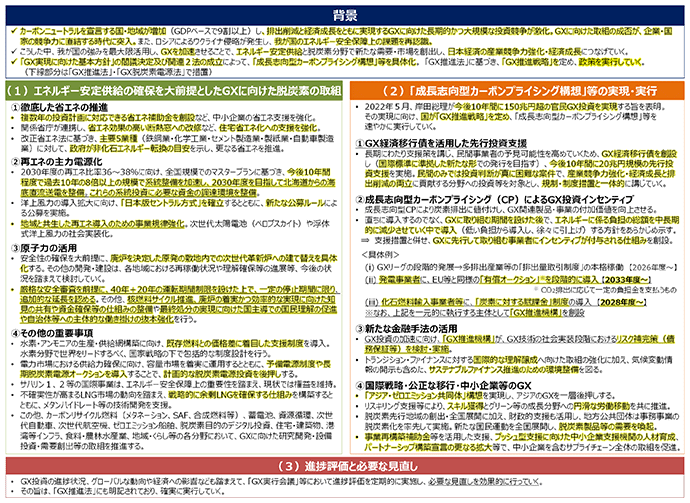
【第131-2-3】脱炭素成長型経済構造移行推進戦略(GX推進戦略)の概要(ppt/pptx形式:7,329KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
③エネルギー消費効率の改善(省エネの推進等)
前項で紹介した「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」では、最終エネルギー消費に関する2030年度の見通しも示しています。この見通しの中で、2013年度に原油換算で約3.6億klであった最終エネルギー消費については、省エネ対策の野心的な深堀りによって、2030年度には2.8億kl程度になるとの見込みを示しています。日本における最終エネルギー消費の推移を確認すると、2021年度の最終エネルギー消費は約3.2億klとなっており、目標ラインの水準と概ね同じペースで削減が進んでいることがわかります。また、最終エネルギー消費の推移を部門別に見ると、産業・運輸・業務・家庭の全部門において削減傾向にあることもわかります(第131-2-4)。
【第131-2-4】日本における最終エネルギー消費の推移
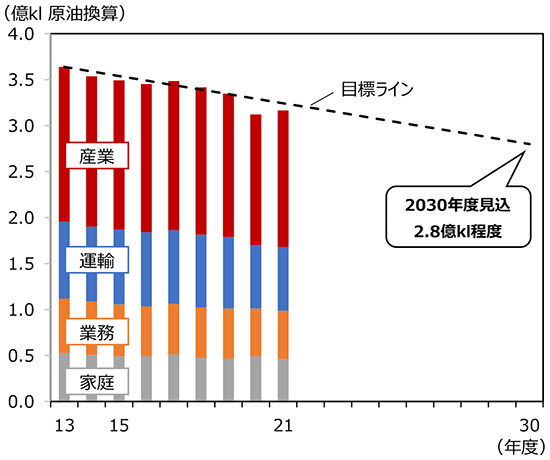
【第131-2-4】日本における最終エネルギー消費の推移(ppt/pptx形式:56KB)
- 資料:
- 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に経済産業省作成
化石エネルギーの資源に乏しい日本は、貴重なエネルギーを大切に活用すべく、過去から省エネの取組に努めてきました。その結果、日本は世界でもトップレベルの省エネ水準を誇る省エネ先進国となっています。2023年7月に閣議決定された「GX推進戦略」でも、引き続き徹底した省エネを推進していくことを明記しており、2023年度補正予算においても、企業向けには省エネ設備への更新支援や中小企業への省エネ診断支援を措置するとともに、家庭向けには断熱窓への改修支援や高効率給湯器の導入支援等の住宅省エネ化支援を行っています(第131-2-5)。
【第131-2-5】省エネ支援パッケージの概要
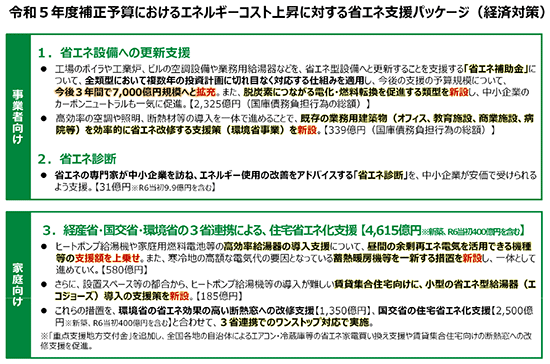
【第131-2-5】省エネ支援パッケージの概要(ppt/pptx形式:1,418KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
(2)米国
①温室効果ガスの削減目標と進捗状況
米国は、石油・石炭・天然ガスといったあらゆる化石エネルギー資源を国内に有しているだけでなく、原子力発電については世界最多の基数を保有しており、さらに再エネに関しても広大な国土等の良好な立地条件を有しています。こうしたこともあり、2021年における米国のエネルギー自給率は100%を超えており、本項で紹介している5か国の中では圧倒的に高い数値となっています。その一方で、国民1人当たりのエネルギー起源CO2排出量については、5か国の中で最も多い状況にあります(第131-3-1参照)。
このような特徴を有する米国は、2030年のNDCとして、2005年比で温室効果ガスを50%〜52%削減するという目標を掲げています。この目標に向けた進捗として、2021年における温室効果ガスの削減実績は17%となっています。2021年の温室効果ガス排出・吸収量の実績を、2021年における目標ラインの水準と比較すると、実績が目標ラインの水準を24%程度超過しています(第131-2-6)。
【第131-2-6】米国における温室効果ガスの削減状況
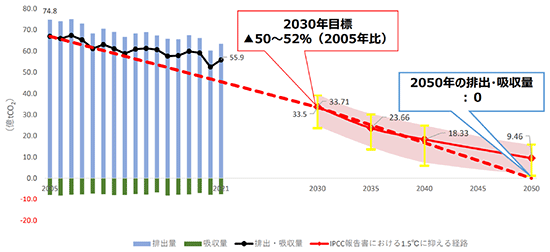
【第131-2-6】米国における温室効果ガスの削減状況(ppt/pptx形式:201KB)
- 資料:
- 環境省「第151回中央環境審議会地球環境部会 資料1」より抜粋(UNFCCC「Greenhouse Gas Inventory Data」を基に作成)
②エネルギー供給の脱炭素化(非化石電源の拡大等)
米国における電源構成の推移を見ると、原子力の割合が20%前後の水準を維持し続けている中、再エネの導入拡大に伴い、非化石電源比率が徐々に高まっていることがわかります。その結果、2021年における米国の非化石電源比率は39%となりましたが、その一方で、電力の半分以上を火力発電に頼る状況が続いています。米国では、その火力発電の内訳にも変化が見られます。2000年代半ば頃までは、火力発電の多くを石炭火力が占めていましたが、その後、シェール革命によって国内で安価な天然ガスが生産されるようになったこともあり、石炭から天然ガスへの燃料転換が進みました。このように、米国では非化石電源の拡大に加えて、火力発電の低炭素化についても進められてきました(第131-2-7)。
【第131-2-7】米国における電源構成の推移
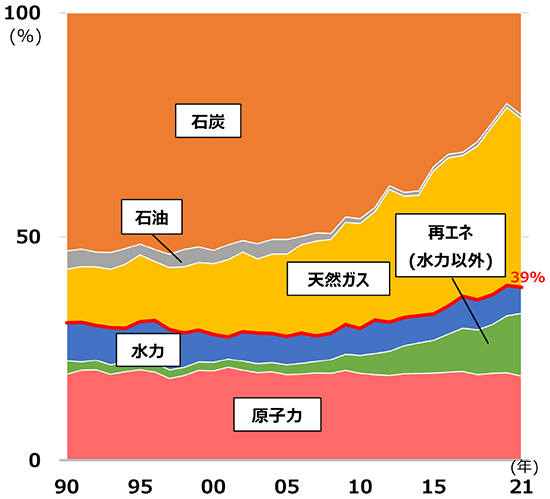
【第131-2-7】米国における電源構成の推移(ppt/pptx形式:169KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023」を基に経済産業省作成
こうした状況の中、米国は、2021年に提出したNDCにおいて、2035年までに電力部門を脱炭素化するとの目標を示しています。2021年時点の非化石電源比率を踏まえれば、この目標の実現のためには、再エネや原子力のさらなる導入拡大に向けた取組が不可欠な状況にあります。取組の一例として、2022年8月には気候変動対策等を盛り込んだ「インフレ削減法4」が成立し、この中では、再エネや原子力といったクリーン電力への移行を促進するための強力な支援策が示されました。具体的には、設備投資に対する投資税額控除や生産税額控除等の支援策が講じられることとなっており、これによって非化石電源の導入を加速させています。
③エネルギー消費効率の改善(省エネの推進等)
2021年における米国の最終エネルギー消費は2005年比で1%の削減となっており、長らく横ばいが続いています。部門別に確認すると、運輸部門におけるエネルギー消費が最も多いという特徴があることから、米国の最終エネルギー消費を削減していくためには、自動車の燃費規制等の取組が重要となります。米国では、運輸省が、各自動車メーカーが販売する全ての自動車の平均燃費である「企業別平均燃費(CAFE)」の基準値を改定する等、燃費規制の強化を進めています(第131-2-8)。
【第131-2-8】米国における最終エネルギー消費の推移
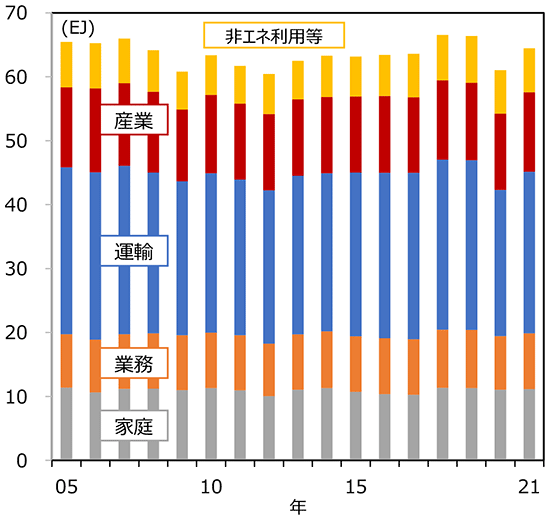
【第131-2-8】米国における最終エネルギー消費の推移(ppt/pptx形式:55KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023」を基に経済産業省作成
(3)英国
①温室効果ガスの削減目標と進捗状況
英国は、2030年のNDCとして、1990年比で温室効果ガスを68%削減するという目標を設定しています。この目標に向けた進捗として、2021年における温室効果ガスの削減実績は47%となっています。2021年の温室効果ガス排出・吸収量の実績を、2021年における目標ラインの水準と比較すると、実績が目標ラインの水準を11%超過しています(第131-2-9)。
【第131-2-9】英国における温室効果ガスの削減状況
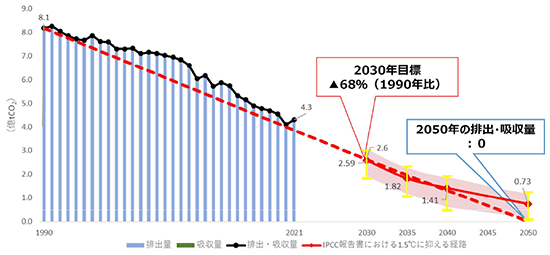
【第131-2-9】英国における温室効果ガスの削減状況(ppt/pptx形式:404KB)
- 資料:
- 環境省「第151回中央環境審議会地球環境部会 資料1」より抜粋(UNFCCC「Greenhouse Gas Inventory Data」を基に作成)
②エネルギー供給の脱炭素化(非化石電源の拡大等)
英国における電源構成の推移を見ると、2010年代の再エネの急速な導入拡大に伴い、非化石電源比率が一気に高まっていることがわかります。その結果、1990年から2010年にかけて25%前後の水準で推移していた非化石電源比率は、2017年に50%を超えることとなりました。また、この非化石電源の拡大に伴い、火力発電の割合は大きく減少しましたが、火力発電の内訳にも大きな変化があったことがわかります。1990年には火力発電の大半を石炭火力が占めており、電源構成に占める石炭火力の割合も65%と高い数値になっていましたが、その後は北海ガス田からも生産される天然ガスへの燃料転換が進み、2021年の電源構成に占める石炭火力の割合は2%にまで下がっています。このように、英国では非化石電源の拡大に加えて、火力発電の低炭素化も着実に進められてきました。なお、英国では、2021年に再エネの割合が前年比で減少し、天然ガス火力の割合が増加しましたが、これは天候不順により風力の発電電力量が低迷したことが一因とされています(第131-2-10)。
【第131-2-10】英国における電源構成の推移
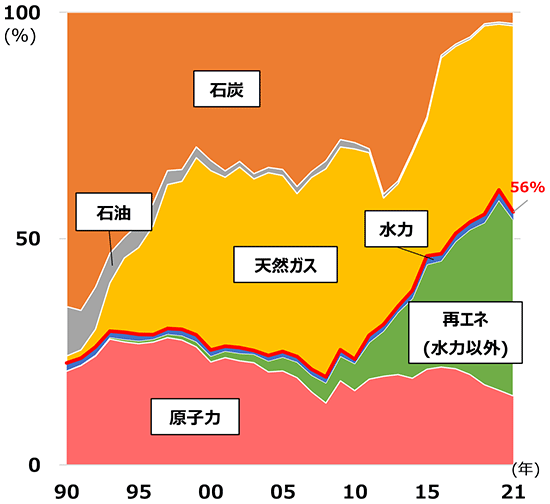
【第131-2-10】英国における電源構成の推移(ppt/pptx形式:55KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023」を基に経済産業省作成
このような状況の中、英国は、2022年4月に発表した「British Energy Security Strategy」において、再エネや原子力、水素等の国産エネルギーの導入を加速させ、2030年までに電源の95%を低炭素化するとの方針を掲げました。この戦略の中で、再エネに関しては、特に洋上風力と太陽光の導入を拡大していく方針が示されています。また、電源構成に占める割合がやや低下傾向にあった原子力に関しても、2030年までに最大8基の原子炉を新設する方針や、2050年までに最大24GWの出力を整備し、電源構成に占める原子力の割合を25%に引き上げる方針等を打ち出しています。この方針に基づく取組が奏功すれば、英国における非化石電源比率はさらに高まることが期待されます。
③エネルギー消費効率の改善(省エネの推進等)
2021年における英国の最終エネルギー消費は1990年比で14%の削減となっており、近年も減少傾向が続いています。部門別に最終エネルギー消費の推移を見ると、特に産業部門において削減が進んできたことがわかります。英国では、1990年代後半から、エネルギーを比較的多く消費する製造業からサービス業等への産業構造の転換が発生しており、産業部門における最終エネルギー消費の減少には、このことが一定程度影響していると考えられます。排出削減を進めていくためには、エネルギー消費効率の改善を進めていくことが重要ですが、その際には、各国における産業構造の違い等にも留意する必要があります(第131-2-11、第131-2-12)。
【第131-2-11】英国における最終エネルギー消費の推移
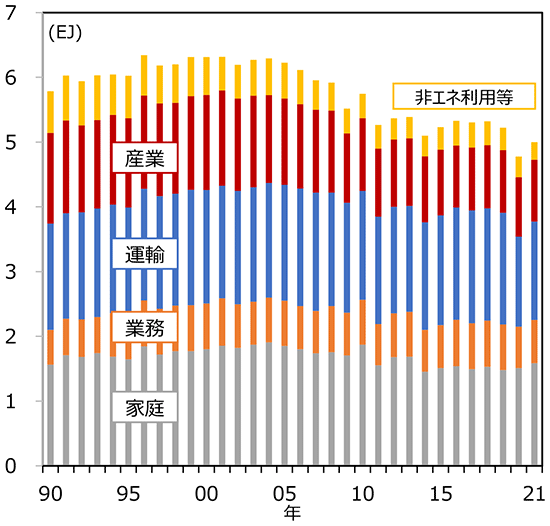
【第131-2-11】英国における最終エネルギー消費の推移(ppt/pptx形式:57KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023」を基に経済産業省作成
【第131-2-12】主要国のGDPに占める製造業の割合の推移
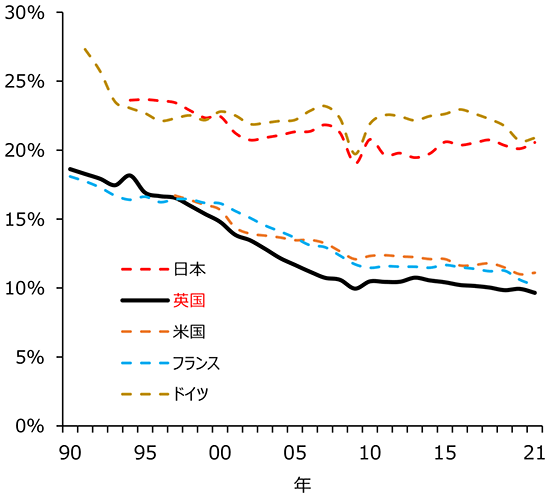
【第131-2-12】主要国のGDPに占める製造業の割合の推移(ppt/pptx形式:65KB)
- 資料:
- OECD. statsを基に経済産業省作成
(4)フランス
①温室効果ガスの削減目標と進捗状況
EU加盟国であるフランスは、2030年のNDCとして、EUとしての目標(1990年比で温室効果ガスを55%削減する)を提出しています。この目標に向けた進捗として、2021年における温室効果ガスの削減実績は23%となっています。2021年の温室効果ガス排出・吸収量の実績を、2021年における目標ラインの水準と比較すると、実績が目標ラインの水準を34%超過しています(第131-2-13)。
【第131-2-13】フランスにおける温室効果ガスの削減状況
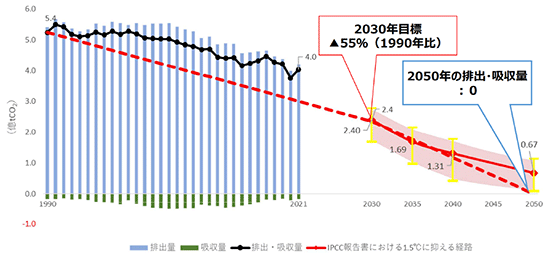
【第131-2-13】フランスにおける温室効果ガスの削減状況(ppt/pptx形式:404KB)
- 資料:
- 環境省「第151回中央環境審議会地球環境部会 資料1」より抜粋(UNFCCC「Greenhouse Gas Inventory Data」を基に作成)
②エネルギー供給の脱炭素化(非化石電源の拡大等)
1970年代のオイルショック以来、エネルギー自給率を高める目的で原子力発電を推進してきたフランスでは、過去から非化石電源比率が極めて高い水準で推移してきました。2021年における非化石電源比率も92%となっています。そうした中でも、近年では再エネの割合が増加しており、その一方で、原子力の割合はやや減少傾向5にあります(第131-2-14)。
【第131-2-14】フランスにおける電源構成の推移
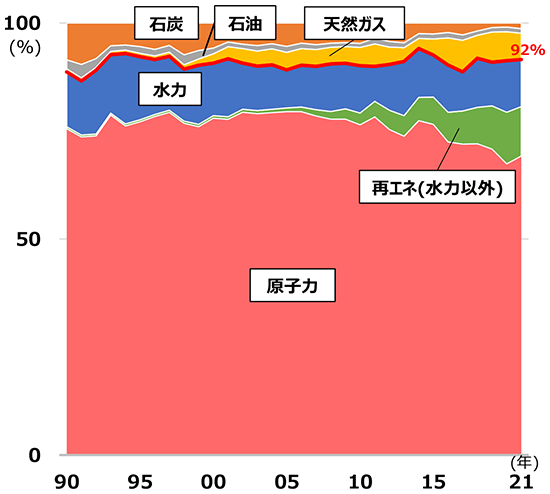
【第131-2-14】フランスにおける電源構成の推移(ppt/pptx形式:54KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023」を基に経済産業省作成
このように、既に非化石電源比率の高いフランスですが、原子力と再エネをさらに拡大させていく方針を掲げています。2023年11月に公表された「エネルギー・気候戦略」は、2050年までのカーボンニュートラルの実現に向け、フランスが化石エネルギーから脱却する最初の先進工業国になることを目指すための戦略であり、この中で、原子力に関しては、6基のEPR2(改良型欧州加圧水型炉)の建設について2024年末に最終意思決定を行う方針や、さらに8基のEPR2の建設に向けた検討を実施していく方針等が示されました。この戦略の中では、再エネに関しても、太陽光や洋上風力、陸上風力の導入量を2035年までに拡大させていく方針等が明記されています。
なお、フランスにおける温室効果ガス排出量の内訳を確認すると、エネルギー起源CO2の占める割合は72%で、そのうち約9割が非電力部門からの排出となっています。非化石電源比率が9割を超えているフランスでは、電力消費に伴うCO2排出は既に少ない状況となっており、フランスが排出削減を進めていくためには、非電力部門における脱炭素化(電化の推進を含む)や、エネルギー消費効率の改善に向けた取組が重要と考えられます。
③エネルギー消費効率の改善(省エネの推進等)
フランスは、前述の「エネルギー・気候戦略」において、2030年における最終エネルギー消費を2012年比で30%削減するという目標を掲げました。具体的には、建築物の省エネ改築や化石エネルギーを利用した暖房システムからの脱却、電気自動車(EV)の普及、製造業における脱炭素化等を支援することを通じて、この目標の達成を目指すとしています。
2021年におけるフランスの最終エネルギー消費は、2012年比で5%の削減(1990年比では7%の増加)となりました。2021年の最終エネルギー消費の実績を、2021年における目標ラインの水準と比較すると、実績が目標ラインの水準を11%超過している状況となっています。「エネルギー・気候戦略」は、2023年11月に公表されて間もない戦略ではありますが、この目標及び2050年までのカーボンニュートラルの達成に向けて、様々な省エネの取組を加速させていく必要があると考えられます(第131-2-15)。
【第131-2-15】フランスにおける最終エネルギー消費の推移
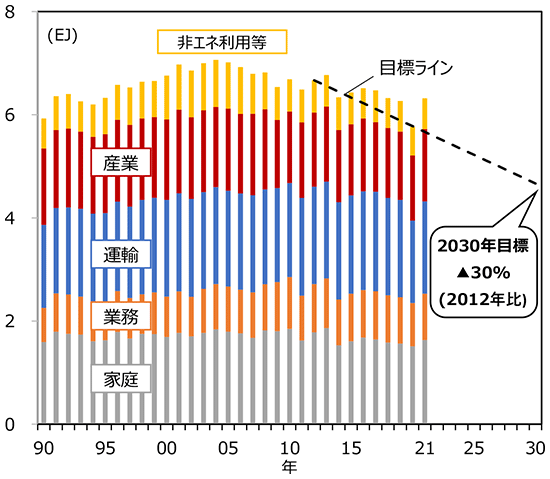
【第131-2-15】フランスにおける最終エネルギー消費の推移(ppt/pptx形式:59KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023」を基に経済産業省作成
(5)ドイツ
①温室効果ガスの削減目標と進捗状況
フランスと同様にEU加盟国であるドイツは、2030年のNDCとして、EUとしての目標(1990年比で温室効果ガスを55%削減する)を提出していますが、これに加え、2021年6月に改正された「気候保護法」では、ドイツ国内における2030年の温室効果ガスの削減目標として、1990年比で65%削減することを掲げています。これらの目標に向けた進捗として、2021年における温室効果ガスの削減実績は41%となっています。2021年の温室効果ガス排出・吸収量の実績を、2021年における目標ライン(2030年に1990年比65%削減)の水準と比較すると、実績が目標ラインの水準を20%超過しています(第131-2-16)。
【第131-2-16】ドイツにおける温室効果ガスの削減状況
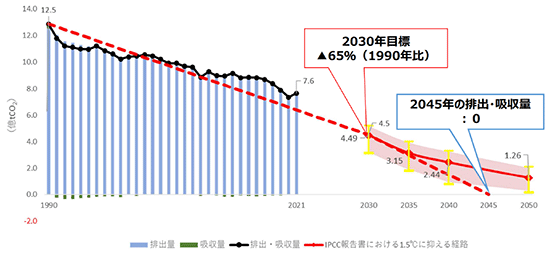
【第131-2-16】ドイツにおける温室効果ガスの削減状況(ppt/pptx形式:364KB)
- 資料:
- 環境省「第151回中央環境審議会地球環境部会 資料1」より抜粋(UNFCCC「Greenhouse Gas Inventory Data」を基に作成)
ドイツは、カーボンニュートラルの実現に関しても高い目標を掲げています。先進国を中心に、多くの国が2050年までのカーボンニュートラルの実現を掲げる中、前述の改正気候保護法では、2045年までのカーボンニュートラルの実現を目標として掲げています。
②エネルギー供給の脱炭素化(非化石電源の拡大等)
ドイツにおける電源構成の推移を見ると、1990年代に30%前後の水準で推移していた原子力の割合が、2000年代以降、減少傾向にあることがわかります。その一方で、原子力と同じ非化石電源である再エネについては、2000年代以降に導入が大幅に拡大しています。ドイツでは、原子力の割合が減少するペースよりも、再エネの割合が増加するペースの方が早かったことから、非化石電源比率が高くなってきており、2019年以降は50%を超えています。こうした中、減少傾向となっているのが石炭火力です。1990年の電源構成に占める石炭火力の割合は59%でしたが、2021年には30%にまで低下しました。なお、ドイツでは、2021年に再エネの割合が前年比で減少していますが、英国と同様に、天候不順による発電電力量の低迷が要因とされています。再エネの減少分については、主に石炭火力がカバーしました(第131-2-17)。
【第131-2-17】ドイツにおける電源構成の推移
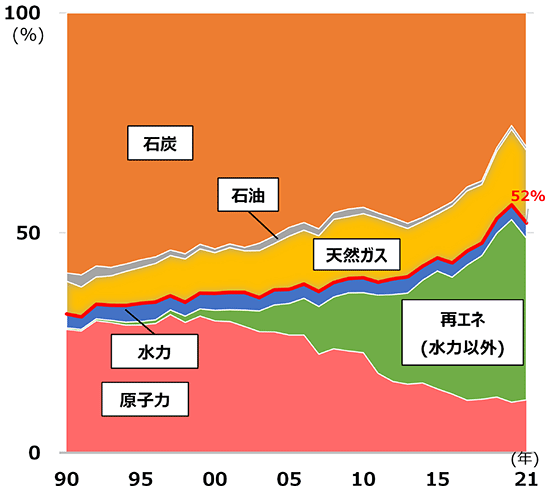
【第131-2-17】ドイツにおける電源構成の推移(ppt/pptx形式:649KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023」を基に経済産業省作成
前述のとおり、温室効果ガスの削減について高い目標を掲げているドイツですが、非化石電源である原子力と再エネに対しては、真逆の方針を取っていることが大きな特徴です。徐々にその割合を減らしてきた原子力については、2002年の原子力法の改正以降、「脱原子力」の方針を取っており、原子力発電所の閉鎖が段階的に進められてきました。2022年2月に発生したロシアによるウクライナ侵略の影響で、エネルギーの需給ひっ迫が生じたことにより、当初の予定よりも延期されましたが、2023年4月には最後まで残っていた3基の原子炉が閉鎖され、これにより、ドイツにおける脱原子力が完了しています。2021年の電源構成に占める原子力の割合は12%でしたが、今後は原子力による発電がゼロとなるため、原子力に代わる電源の確保が求められます。
一方で、2000年代以降、急速に導入が進んできた再エネに関しては、さらに推進していく方針が示されています。ドイツでは、2030年における再エネの割合を65%とする目標が示されていましたが、2023年に改正された再エネ法では、その目標を80%へと引き上げました。2021年における再エネの割合が40%となっている中、この目標の達成に向けて、太陽光や陸上風力を中心とした再エネのさらなる導入拡大が見込まれています。
③エネルギー消費効率の改善(省エネの推進等)
ドイツは、2045年までのカーボンニュートラルの実現という高い目標をクリアするための計画の一環として、2023年9月に連邦議会により可決された「エネルギー効率化法」において、2030年の最終エネルギー消費を2008年比で26.5%削減するという目標を掲げました。
2021年におけるドイツの最終エネルギー消費は、2008年比で3%の削減(1990年比では7%削減)に留まっており、近年では横ばいが続いています。2021年の最終エネルギー消費の実績を、2021年における目標ラインの水準と比較すると、実績が目標ラインの水準を15%超過している状況となっており、「エネルギー効率化法」で示した目標の達成に向けて、様々な省エネの取組を加速させていく必要があると考えられます(第131-2-18)。
【第131-2-18】ドイツにおける最終エネルギー消費の推移
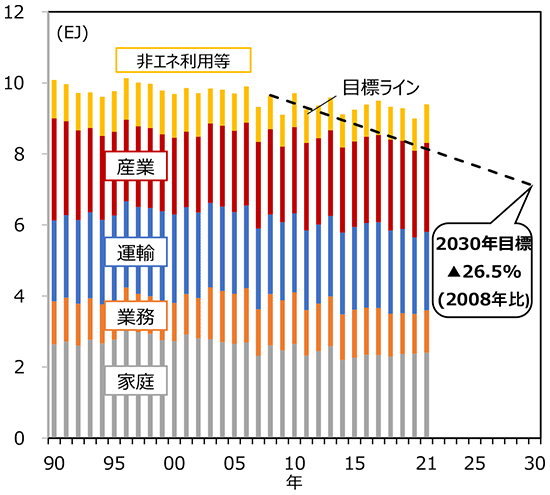
【第131-2-18】ドイツにおける最終エネルギー消費の推移(ppt/pptx形式:58KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023」を基に経済産業省作成
(6)EU(27か国)
①温室効果ガスの削減目標と進捗状況
最後に、EU(27か国)について見ていきます。ここまで見てきたように、原子力発電を推進してきたフランスや、その一方で「脱原子力」を完了させたドイツをはじめ、EUには、エネルギーについて多種多様な政策方針を持っている国々が加盟しています。このようなEUですが、まずはEU全体として、温室効果ガスの排出削減がどのように進んできたのかについて確認していきます。
EUは、2030年の温室効果ガスの削減目標として、1990年比で55%削減することを設定しています。この目標に向けた進捗として、2021年における温室効果ガスの削減実績は30%となっています。2021年の温室効果ガス排出・吸収量の実績を、2021年における目標ラインの水準と比較すると、実績が目標ラインの水準を21%超過しています(第131-2-19)。
【第131-2-19】EUにおける温室効果ガスの削減状況
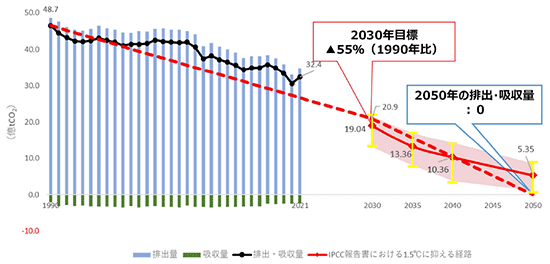
【第131-2-19】EUにおける温室効果ガスの削減状況(ppt/pptx形式:440KB)
- 資料:
- 環境省「第151回中央環境審議会地球環境部会 資料1」より抜粋(UNFCCC「Greenhouse Gas Inventory Data」を基に作成)
②エネルギー供給の脱炭素化(非化石電源の拡大等)
EU全体の電源構成の推移を見ると、2000年代半ばまで30%以上の水準で推移していた原子力の割合が、近年ではやや減少傾向となっていることがわかります。一方で、原子力と同じ非化石電源である再エネについては、2000年代以降に導入が拡大しています。原子力の割合が減少するペースよりも、再エネの割合が増加するペースの方が早いことから、非化石電源比率が高くなってきており、2019年以降は60%を超えている状況となっています。2022年に発表され、太陽光の導入拡大目標を掲げた「EU太陽光戦略」をはじめ、EUでは再エネのさらなる拡大に向けた方針6が示されており、今後も再エネの割合が拡大していくことが予想されています。また、減少傾向の続く火力発電の中では、石炭火力及び石油火力から天然ガス火力への燃料転換が徐々に進んでおり、非化石電源の拡大に加えて、火力発電の低炭素化についても着実に進展していることが確認できます(第131-2-20)。
【第131-2-20】EUにおける電源構成の推移
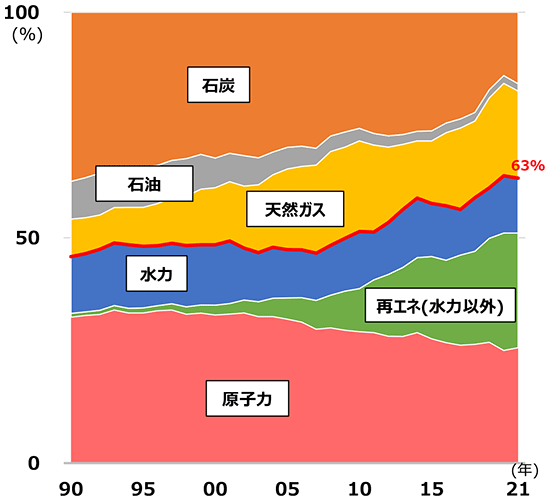
【第131-2-20】EUにおける電源構成の推移(ppt/pptx形式:55KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023」を基に経済産業省作成
③エネルギー消費効率の改善(省エネの推進等)
EUでは、2023年7月に、2030年の温室効果ガスの削減目標(1990年比55%削減)の達成に向けた政策パッケージ「Fit for 55」の一環である「エネルギー効率化指令」の改正案が採択されました。この中では、2030年における最終エネルギー消費を、2020年に予測された2030年の最終エネルギー消費から、さらに11.7%削減するという目標が示されました。これは、2005年比で約25%削減する水準に相当するとされています。
2021年におけるEUの最終エネルギー消費は、2005年比で6%の削減(1990年比では3%の増加)となっています。2021年の最終エネルギー消費の実績を、2021年における目標ライン(2030年に2005年比25%削減)の水準と比較すると、実績が目標ラインの水準を11%超過している状況となっています。この目標の達成に向けて、様々な省エネの取組を加速させていく必要があると考えられます(第131-2-21)。
【第131-2-21】EUにおける最終エネルギー消費の推移
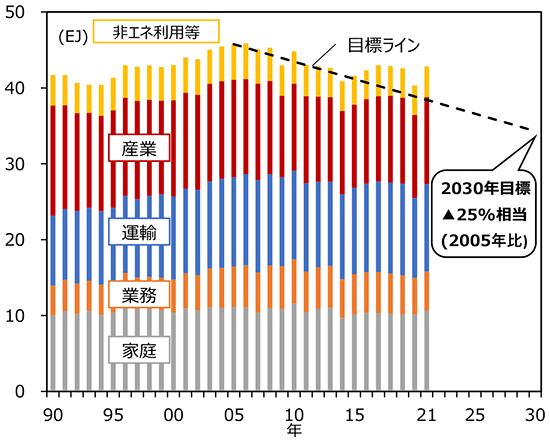
【第131-2-21】EUにおける最終エネルギー消費の推移(ppt/pptx形式:61KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023」を基に経済産業省作成
3.各国における取組の進捗比較
前項では、日本・米国・英国・フランス・ドイツ・EUにおける温室効果ガスの排出削減目標に向けた進捗状況等について、それぞれ確認を行いました。本項では、先進国(OECDに加盟している38か国)を対象に、カーボンニュートラルの実現に向けた現在の状況について、比較を行っていきます。ここでは、先進国が排出する温室効果ガスの大半を占めているエネルギー起源CO2を対象に、まず2021年における国民1人当たりのCO2排出量という観点で比較を行った上で、その多寡を左右している要因について分析を行っていきます。
(1)国民1人当たりのエネルギー起源CO2排出量
各国における国民1人当たりのエネルギー起源CO2排出量を見ていくと、OECDに加盟している38か国の中でも、かなり大きな差があることがわかります。38か国の国民1人当たり排出量の平均は、2021年時点で6.26トンでした。「パリ協定」が採択された2015年における当該38か国7の平均が7.14トンであったため、6年間で0.88トン(12%)の削減が行われたことになります。
国別に見ていくと、前項でも取り上げた主要5か国の中では、フランスが38か国中10位、英国が16位となっており、OECDの平均を下回っていることがわかります。他方で、ドイツは29位、日本は32位、そして米国は下から2番目となる37位となっており、5か国の中でも大きな開きが生じています。この5か国における国民1人当たり排出量について、2015年時点の数値と比較すると、2015年の時点で既に1人当たり排出量の少なかったフランスでは、この6年間の削減量が0.29トン(6%)と限定的であったものの、他の4か国においては、英国が1.28トン(21%)の削減、ドイツが1.43トン(16%)の削減、日本が1.11トン(12%)の削減、米国が1.60トン(10%)の削減となっており、削減が一定程度進んだことが確認できます(第131-3-1、第131-3-2)。
【第131-3-1】OECD加盟国(38か国)における1人当たりのエネルギー起源CO2排出量(2021年)
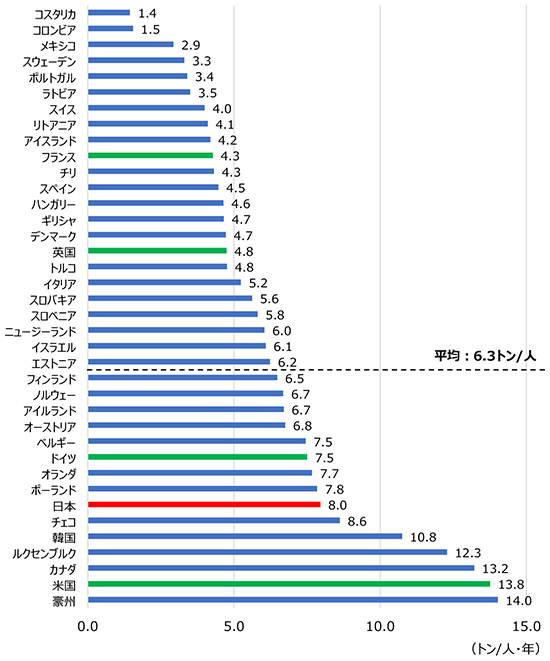
【第131-3-1】OECD加盟国(38か国)における1人当たりのエネルギー起源CO2排出量(2021年)(ppt/pptx形式:55KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023」、「CO2 Emissions from Fuel Combustion」を基に経済産業省作成
【第131-3-2】主要国における1人当たりのエネルギー起源CO2排出量の推移
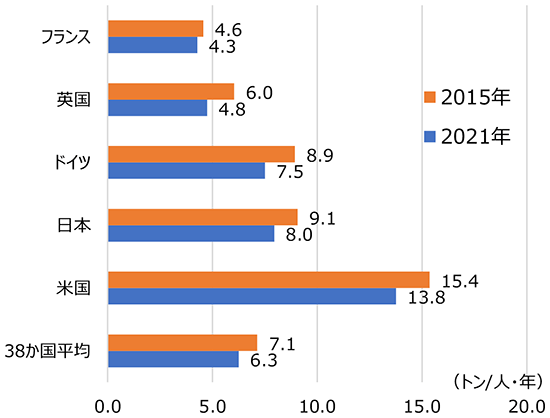
(注)端数処理(四捨五入)の関係で、グラフ内の数値と本文中の数値が合わないこと等がある。
【第131-3-2】主要国における1人当たりのエネルギー起源CO2排出量の推移(ppt/pptx形式:51KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023」、「CO2 Emissions from Fuel Combustion」を基に経済産業省作成
なお、国民1人当たりCO2排出量の多寡を決める要因には、後述のとおり様々な要因があり、各国の事情等によって大きく影響される側面もあるため、このデータだけで単純に評価を行うことはできません。しかし、カーボンニュートラルの実現に向けた取組を進めていく上で、特に排出量が相対的に多くなっている国においては、排出削減に向けた改善の余地がどこに大きく存在しているのかを確認することが重要です。
次項では、1人当たりCO2排出量の多寡を左右している要因について、分解して確認を行っていきます。
(2)CO2排出の因数分解による分析
CO2排出の要因分析には様々な方法や切り口がありますが、例えば、国民1人当たりのエネルギー起源CO2排出量は、国民1人当たりの活動量(GDP等)、1単位の活動を行うために要するエネルギー消費量(エネルギー消費効率)、1単位のエネルギー消費に対して行われるエネルギー供給に伴うCO2の排出量(エネルギーの低炭素度)の3つに因数分解することができます。このうち、国民1人当たりの活動量(GDP等)は、経済の動向等によって変動するものであるため、政策的にCO2の排出削減を進めるに当たっては、エネルギーの消費効率の向上(消費サイドの改善)とエネルギーの低炭素化(供給サイドの改善)の2つを進めていくことが重要となります(第131-3-3)。
【第131-3-3】エネルギー起源CO2排出の要因分解式
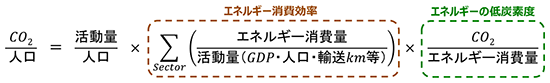
【第131-3-3】エネルギー起源CO2排出の要因分解式(ppt/pptx形式:79KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
ここでは、前項でも紹介した5か国(日本・米国・英国・フランス・ドイツ)における国民1人当たりのエネルギー起源CO2排出量を、「エネルギーの低炭素度」と「エネルギーの消費効率」に分解することで、その多寡の要因を確認します。前者のエネルギーの低炭素度については、電力部門と非電力部門の2項目に分けて確認し、後者のエネルギーの消費効率については、家庭部門・産業部門・運輸部門の3項目に分けて確認していきます(計5項目について確認)。そして、各国における各項目のパフォーマンスを偏差値に変換して整理しました。スコアについては、38か国の平均を「50」とし、50よりも大きいほどカーボンニュートラル実現に向けた進捗状況が相対的に良い(エネルギーの低炭素化が進んでいる、エネルギーの消費効率が良い)ことを表しており、50よりも小さいほどカーボンニュートラル実現に向けた進捗状況が相対的に悪い(エネルギーの低炭素化が進んでいない、エネルギーの消費効率が悪い)ことを表しています。
2021年における5か国のスコアを見ると、国によって特徴が大きく異なっていることがわかります。5か国について、1人当たり排出量の少ない順に見ていくと、まずフランスについては、供給サイドの2項目と需要サイドの1項目の計3項目においてトップとなっており、こうした状況が、1人当たり排出量が5か国の中で最も少ないという結果につながっているものと考えられます。フランスに次いで、英国も比較的良いスコアを出しており、産業部門におけるエネルギーの消費効率ではトップとなっています。ドイツについては、OECD平均値を下回る項目が多くなっています。日本は家庭部門におけるエネルギーの消費効率でトップとなる等、需要サイドの項目では良いスコアを記録していますが、供給サイドでは2項目とも低いスコアとなっています。米国については、全体的にOECDの平均を下回る結果となっています(第131-3-4)。
【第131-3-4】主要5か国におけるCO2排出要因の分解状況(2021年)
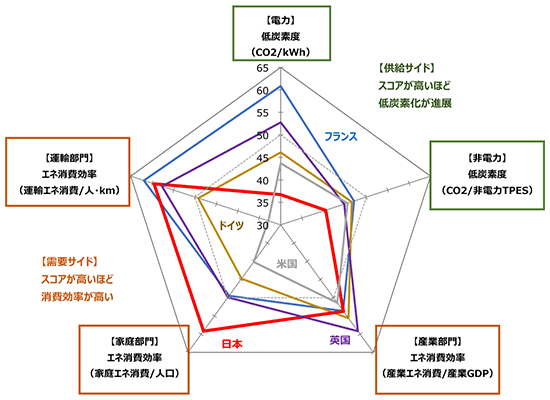
【第131-3-4】主要5か国におけるCO2排出要因の分解状況(2021年)(ppt/pptx形式:64KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023」、「CO2 Emissions from Fuel Combustion」、OECD. Stats等を基に経済産業省作成
なお、それぞれの項目のスコアには、各国が置かれている構造的な事情等も大きく影響しています。例えば、日本の場合、すぐに使えるエネルギー資源に乏しいことに加え、山地が多く、四方を深い海に囲まれているといった地理的な環境や、製造業の割合が高い産業構造である等の特徴を有しており、こうした状況下において、エネルギーを安定的に供給し続けるためには、多様なエネルギー源を活用する必要があります。したがって、それぞれのデータに関して各国比較を行う際には、こうした各国の事情について注意深く考慮する必要があります。
(3)エネルギーの低炭素度
①電力の低炭素度
電力の低炭素度については、フランスのスコアが最も高く、次いで英国、ドイツ、米国、日本の順となりました。この順番は、各国の電源構成における非化石電源比率の高さと比例しています。過去から原子力発電を推進してきたフランスでは、既に電源構成の9割以上を非化石電源が占めており、電力部門におけるCO2排出は限定的なものになっています。フランスに次いで高いスコアとなった英国では、再エネ・原子力といった非化石電源が約6割を占めていることに加え、残る火力発電についても、その大半を燃焼時のCO2排出が相対的に少ない天然ガス火力が占めています。ドイツにおける非化石電源比率は英国に近い水準ですが、火力発電の多くを燃焼時のCO2排出が相対的に多い石炭火力が占めており、このことが英国との差を生んだと考えられます。電力の低炭素度のスコアが相対的に低くなった米国・日本は、他の3か国と比べると非化石電源比率が低く、また石炭火力の割合も高い水準となっています(第131-3-5)。
【第131-3-5】主要5か国の電源構成(2021年)
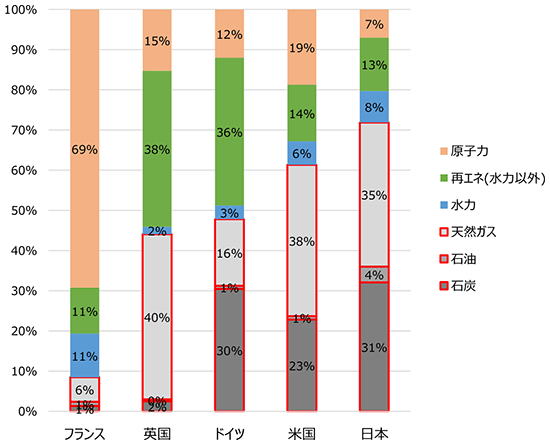
【第131-3-5】主要5か国の電源構成(2021年)(ppt/pptx形式:51KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023」を基に経済産業省作成
日本は、国土面積の約3割しか平地がないことに加え、四方を深い海に囲まれている等の地理的条件を有しています。また、太陽光や風力といった再エネは、季節や天候によって発電量が変動する特徴があります。このため、日本としては、再エネ、原子力、脱炭素火力等、あらゆる選択肢を確保しながら、電力の安定供給と脱炭素の両立を実現していくことが重要です。
前述のとおり、各国においては再エネや原子力の拡大に向けた取組が急速に拡大しています。そのため、今後は電力の低炭素度のさらなる向上が期待されます。
②非電力部門の低炭素度
日本は、熱需要等の非電力部門における低炭素度についても、他国と比べ、低いスコアとなっています。その要因として、製造業の割合が高い産業構造となっていること、中でも、原料炭を消費する鉄鋼業や、産業用ボイラー等でエネルギーを多く消費する化学工業・窯業等を国内に多く有していること等が考えられます。こうした産業は、日本の主要産業である自動車工業や、昨今、投資が加速している半導体産業等の機能性化学品を必要とする産業を支える分野として、重要な役割を担っており、こうした分野における脱炭素化については、安定供給や国際競争力等への影響も考慮しなければなりません。このように、カーボンニュートラルの実現に向けた各国の状況を比較する際には、各国における産業構造の違い等にも留意する必要があります。
なお、電力部門の脱炭素化が再エネや原子力等の非化石電源の導入拡大によって進んでいくことを踏まえ、非電力部門の脱炭素化に向けた方策の1つとして、電化の推進が考えられています。しかし、高温の熱需要等、電化による対応が困難な分野も存在しており、こうした分野においては、水素や合成メタン(e-methane)、バイオマス等のエネルギーを活用しながら脱炭素化を進めていくことが期待されています。
(4)エネルギーの消費効率
①家庭部門におけるエネルギー消費効率
次に、需要サイドの状況について見ていきます。家庭部門におけるエネルギー消費効率では、日本がトップとなりました。これには、様々な省エネ機器の普及等の要因が挙げられますが、各国における習慣の違いも結果に大きく影響していると考えられます。各国における世帯当たりエネルギー消費量のデータを見ると、欧米諸国では暖房用途でのエネルギー消費が非常に多くなっているのに対し、日本では暖房用途でのエネルギー消費が少ないことがわかります。欧米諸国では、暖房システムの集中化等により、長時間にわたって全館暖房を行う住宅が多い一方で、日本では、居室ごとに暖房システムを設置し、その居室にいるときに、その居室だけを暖房することが主流となっています。各国の気候等による違いもありますが、こうした習慣の違いも、日本と欧米諸国の差を生んだ要因の1つと考えられます(第131-3-6)。
【第131-3-6】主要5か国の世帯当たりエネルギー消費量
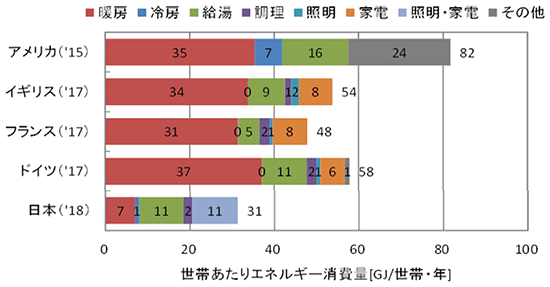
【第131-3-6】主要5か国の世帯当たりエネルギー消費量(ppt/pptx形式:95KB)
- 資料:
- 住環境計画研究所
②産業部門におけるエネルギー消費効率
産業部門8におけるエネルギー消費効率については、家庭部門や運輸部門と比べると、5か国の中であまり大きな差が生じていません。いずれの国もOECDの平均値を上回るスコアとなっており、各国においてエネルギー消費効率の改善に向けた取組が進んできたことが窺えますが、一般的には、産業部門の中でもエネルギーを多く消費する傾向のある製造業の占める割合が高いほど、本項目のスコアは悪化すると考えられます。5か国の産業部門のGDPに占める製造業の割合を見ると、日本とドイツではその割合が高いことが確認でき、この2か国については、国内に製造業を多く抱える中でも、他の3か国と同水準のエネルギー消費効率を実現していると評価できます(第131-3-7)。
【第131-3-7】主要5か国のGDPに占める産業部門の割合(2021年)
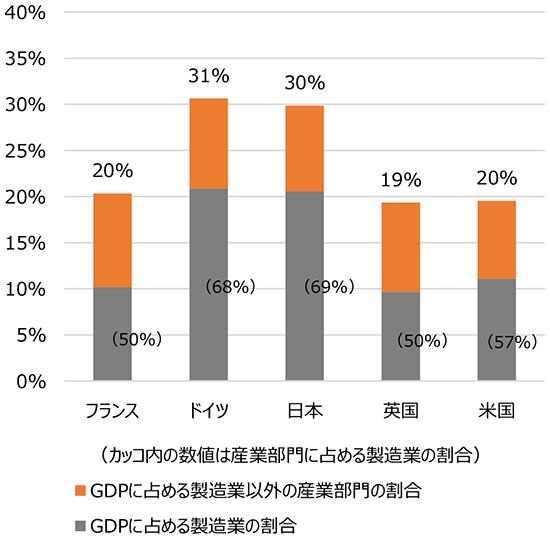
【第131-3-7】主要5か国のGDPに占める産業部門の割合(2021年)(ppt/pptx形式:48KB)
- 資料:
- OECD. Statsを基に経済産業省作成
本項目では、産業部門におけるGDP1単位の生産のために消費されたエネルギー量(消費効率)について評価を行っていますが、エネルギー消費の多い製造業が多ければ多いほど、その消費効率の高さにかかわらず、最終的なエネルギー消費及びCO2排出の絶対量は増えることになります(逆に、製造業が少ない国ほど少なくなる)。カーボンニュートラルの実現に向けた各国の状況を比較する際には、各国における産業構造の違い等にも留意する必要があります。また、本項目については、米ドル基準のGDPで除してスコアを算出しているため、為替の影響を受けてしまう点についても注意が必要です。
③運輸部門におけるエネルギー消費効率
運輸部門におけるエネルギー消費効率については、フランス、日本、英国が高いスコアを記録した一方で、米国のスコアが極めて低い水準となりました。運輸部門における各国の1人当たりエネルギー消費量を確認すると、米国が他の4か国の約3倍になっていることがわかります。広大な国土を有し、長距離移動が必要とされる米国ならではの事情が窺えます。また、このデータを輸送機関別に分解すると、どの国においても自動車が大半のシェアを占めており、運輸部門におけるエネルギー消費効率の改善には自動車の燃費・電費の改善が最も重要であることがわかります。また、米国では航空機(国内線)による消費も多くなっています(第131-3-8)。
【第131-3-8】運輸部門における主要5か国の1人当たりエネルギー消費(機関別、2021年)
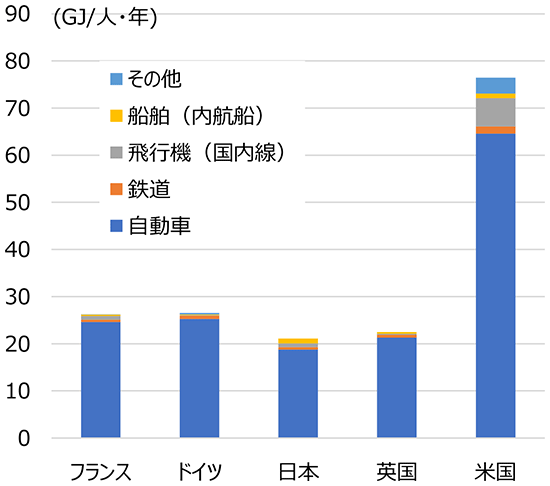
【第131-3-8】運輸部門における主要5か国の1人当たりエネルギー消費(機関別、2021年)(ppt/pptx形式:52KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023」、「CO2 Emissions from Fuel Combustion」を基に経済産業省作成
ここまで見てきたように、日本がカーボンニュートラルを実現していくためには、特に供給サイドの脱炭素化に向けた取組の加速が必要となっています。引き続き、家庭・産業・運輸の各部門における徹底した省エネの取組とともに、再エネ・原子力といった非化石電源の導入拡大に向けた取組等をより一層進めることで、化石エネルギーの消費を減らしていくことが重要です。
4.COP28における動向
気候変動問題という国境のない問題に対応していくためには、世界各国が足並みを揃えて取組を進めていく必要があります。そうした中、世界中の国々が集まり、気候変動に関する様々な問題や取組について議論を行う場が、「国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)」です。COPは、「気候変動に関する国際連合枠組条約9」が発効した1994年の翌年である1995年に初めて開催されて以降、新型コロナ禍の影響により開催されなかった2020年を除いて、毎年開催されています。
2023年11月30日から12月13日にかけて、アラブ首長国連邦(以下「UAE」という。)のドバイにおいて開催された国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(以下「COP28」という。)では、パリ協定の長期目標の達成に向けた世界全体の進捗状況を評価する「グローバル・ストックテイク」(以下「GST」という。)の完結に焦点が当てられました。このGSTは、パリ協定の第14条において5年ごとの実施が定められているものであり、今回が初めての実施となりました。
COP28での議論・交渉の末に採択されたGSTの決定文書では、気候変動問題に対する世界全体の進捗状況の評価として、パリ協定の目標達成に向けて一定の進捗はあったものの、1.5℃目標の達成には隔たりがあること、そして、目標達成に向けて緊急的な行動が必要であることが強調されました。この1.5℃目標の達成のためには、2025年までに温室効果ガスの排出をピークアウトさせる必要があるとされており、各国ごとの異なる状況・道筋・アプローチを考慮した上で、分野別の貢献として、2030年までに再エネの発電容量を世界全体で3倍にすること、エネルギー効率改善率を世界平均で2倍にすることが盛り込まれました。その他にも、排出削減対策が講じられていない石炭火力発電のフェーズダウンに向けた取組の加速や、2050年までにネット・ゼロを達成するための化石燃料からの移行、再エネ・原子力・CCUS・低炭素水素等のゼロ・低排出技術の加速、道路交通部門からの排出削減の加速等が盛り込まれています。なお、この決定文書では、「ゼロ・低排出技術」の1つとして原子力が明記されましたが、世界原子力協会(WNA)によれば、COPの決定文書において「原子力」が気候変動に対する解決策として正式に明記されたのは、今回が初めてのことでした。
その他にも、COP28の期間中に、日本は気候変動に関する様々な国際イニシアティブへの参加を表明し、関連会合において、日本の政策や取組について海外に広く発信を行いました。具体的には、議長国であるUAE及びEUが主導する「世界全体での再生可能エネルギー3倍・エネルギー効率改善率2倍宣言」や、UAE及び米国等による「各国の国内事情の相違を認識しつつ、2050年までに2020年比で世界全体の原子力発電容量を3倍にする」との野心的な目標に向けた協力方針を含む「原子力3倍宣言10」等に対して、賛同を表明しました。なお、「原子力3倍宣言」について、日本は、第三国への革新炉の導入支援や同志国と連携したサプライチェーンの強靱化等の取組を通じて、世界全体での原子力発電容量の増加に貢献する観点から、賛同を表明しました(第131-4-1)。
【第131-4-1】原子力3倍宣言

【第131-4-1】原子力3倍宣言(ppt/pptx形式:469KB)
COP28で採択されたGSTの決定文書において確認されたように、現在の気候変動問題に対する世界全体の取組の進捗状況では、1.5℃目標の達成に向けた軌道に乗っていません(オフトラック)。これを軌道に乗せていく(オントラック)ためには、気候変動対策を世界全体でさらに加速させていくことが不可欠となっています。そのためには、まず各国における固有の事情等を踏まえた多様な道筋の下で、自国における排出削減を着実に進めていくことが重要です。その上で、特に先進国については、それぞれが有する強みを活かしながら、途上国に対する様々な支援等を通じて、世界全体の排出削減に貢献していくことが求められています。
- 2
- 各国が表明済の具体的政策を反映したシナリオ(STEPS)における見通し。
- 3
- 本項では、他国との比較を行う観点から2021年度における実績を紹介していますが、最新の実績である2022年度の日本の温室効果ガス排出・吸収量の実績は10.85億トン(CO2換算)となっており、2021年度比では2.3%の削減、2013年度比では22.9%の削減となりました。過去最低値を記録し、オントラックを継続しています。
- 4
- 「Inflation Reduction Act(IRA)」のことで、インフレ抑制法とも呼ばれています。
- 5
- フランスにおいて原子力の割合が減少傾向となった理由として、再エネの導入が進んだことに加え、2012年に発足したオランド大統領率いる社会党政権が、原子力の割合を2025年までに50%まで引き下げる等の方針の下、原子力政策を進めたことが挙げられます。なお、原子力の割合を引き下げるための規定等は既に撤廃されています。
- 6
- 一例として、2023年9月に欧州議会で採択された再エネ指令の改正案では、2030年までに最終エネルギー消費における再エネの割合を42.5%に引き上げる目標が掲げられており、さらに45%まで高めるための努力を行うことも示されています。
- 7
- 2015年時点のOECD加盟国は34か国でしたが、その後、2016年にラトビアが、2018年にリトアニアが、2020年にコロンビアが、そして2021年にコスタリカが加盟したことで、2023年末時点のOECD加盟国は38か国となっています。そのため、2015年において、これら4か国はOECD加盟国ではありませんでしたが、本項における2015年のデータについては、2021年のデータと比較するために、これら4か国も含めた38か国のデータを用いて算出しています。
- 8
- 製造業、鉱業、建設業、農林水産業を対象としています。
- 9
- 1992年5月に採択され、1994年3月に発効した条約で、大気中の温室効果ガスの濃度を安定させることを目的に、地球温暖化がもたらす様々な悪影響を防止するための国際的な枠組みを定めています。COP28の開催時点(2023年11月)で、計198か国・地域が締約しています。
- 10
- 「原子力3倍宣言」には、2024年1月時点で、計25か国(UAE、米国、フランス、日本、英国、カナダ、韓国、フィンランド、スウェーデン、ベルギー、ルーマニア、ポーランド、ブルガリア、チェコ、ウクライナ、スロベニア、スロバキア、ガーナ、カザフスタン、モロッコ、モルドバ、オランダ、アルメニア、ジャマイカ、クロアチア)が賛同を表明しています。