第2節 GXの実現に向けた日本及び各国の対応
前節に記載のとおり、人類共通の課題である気候変動問題に対応すべく、世界各国では、温室効果ガスの削減に向けた様々な取組が推進されています。そうした中、一般的に、温室効果ガスを減らすための取組には追加のコストが必要となってしまうことから、こうした取組の「負担」の面がしばしばフォーカスされがちとなっています。しかし、日本や欧米諸国等、世界各国においては、この排出削減に向けた取組を、「排出削減」だけでなく、「エネルギー安定供給の確保」や「経済成長・産業競争力の強化」へもつなげていく、すなわち「GX」の実現に向けた取組が急速に進められています。
本節では、世界及び日本におけるGXの実現に向けた取組等について、確認していきます。
1.各国で進むGXの実現に向けた取組
GXを実現していくべく、欧米諸国を中心に、世界各国では、再エネや水素、CCS11、電気自動車、蓄電池、半導体等に対し、官民が連携した投資促進策が次々に打ち出されています。各国における投資促進策は決して同じスキームによるものではなく、各国固有の事情等を踏まえながら、より一層効果的なものとするために、様々な工夫が講じられています。具体的には、中長期にわたる政府支援へのコミットによる投資の予見可能性の確保や、初期投資への支援だけではなく生産量に比例した形での支援、サプライチェーン上の各段階に対するきめ細かな支援、排出量取引制度等の規制・制度的措置の有効活用等、それぞれの国における投資促進策には、様々な特徴が見られます(第132-1-1)。
【第132-1-1】各国におけるGX投資促進策の例
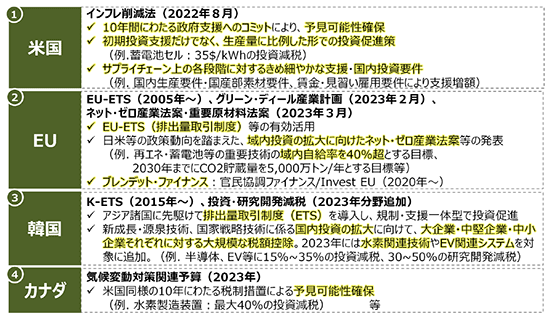
【第132-1-1】各国におけるGX投資促進策の例(ppt/pptx形式:2,338KB)
- 資料:
- 各国政府資料等を基に経済産業省作成
例えば、米国では、2022年8月に成立した「インフレ削減法12」において、エネルギー安全保障や気候変動関連分野への投資促進策が示されました。インフレ削減法の中では、10年間で3,690億ドル(1ドル140円換算で約52兆円)の政府による支援が打ち出されており、その中でも、特に強力な支援が措置されているのが、再エネや原子力を中心としたクリーン電力の分野です。具体的には、再エネに対する投資税額控除や生産税額控除、原子力に対する生産税額控除等、10年間で1,603億ドル(約22兆円)の支援が措置されています。その他にも、インフレ削減法では、クリーン水素やバイオ燃料等のクリーン燃料の分野や、クリーン自動車やクリーン製造業等の分野に対する支援が措置されています(第132-1-2)。
【第132-1-2】米国のインフレ削減法におけるエネルギー安全保障・気候変動関連投資
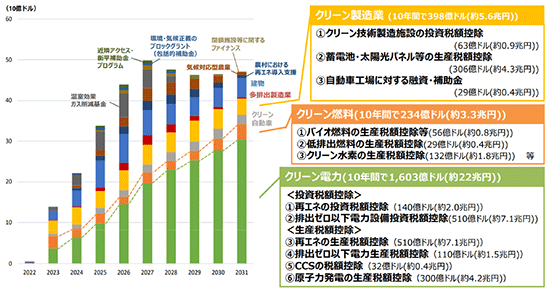
(注)円については、1ドル140円換算で計算している。
【第132-1-2】米国のインフレ削減法におけるエネルギー安全保障・気候変動関連投資(ppt/pptx形式:513KB)
- 資料:
- Congressional Budget Office、電力中央研究所資料を基に経済産業省作成
2.水素・CCSの推進に向けた取組
世界各国による様々な工夫を凝らした投資促進策等により、世界中でGXの実現に向けた取組が着実に進んでいます。そうした中、脱炭素に資する技術として従来から着目されてきた省エネや再エネ等の分野に加えて、脱炭素化が難しい分野における切り札として、燃焼時にCO2を出さない脱炭素燃料である「水素」や、CO2を分離回収して地中に貯留する「CCS」といった新たな脱炭素技術の推進・商用化に向けた取組が世界的に加速しており、各国における官民が連携した投資促進策等の中でも、こうした分野への支援等が多く見られるようになっています。世界中がカーボンニュートラルの実現に向けた取組を加速させていく中、水素やCCSが担う役割は、今後より一層重要なものになっていくことが予想されています。また、水素やCCSを取り巻くマーケットの成長・拡大についても、世界的に期待が高まっています。
本項では、今後のエネルギーを考えていく上で欠かすことのできない分野となっている水素やCCSに関して、今後の需要見通しや世界の動向等について概観していきます。
(1)水素を巡る世界の動向
①水素を巡る状況
まず、水素を巡る動向について確認していきます。水素(H2)は、様々なエネルギーから製造することができ、また、炭素(C)を含んでいないことから、燃焼時にCO2を排出しない脱炭素燃料です。そのため、カーボンニュートラルの実現に向けて、発電部門の脱炭素化のみならず、産業部門や運輸部門等の脱炭素化が難しい様々な分野の脱炭素化への貢献が期待されており、その利活用に向けた取組が世界中で急速に進んでいます。
IEAのレポートによれば、2050年における世界の水素等13の需要は、足元における需要の約5倍(年間約4.3億トン)へと急増することが想定されています。水素還元製鉄や熱等といった産業部門での利用や、自動車やトラック等における運輸部門での利用、そして発電部門での利用等、様々な分野での利活用が想定されています(第132-2-1)。
【第132-2-1】世界の水素等の需要見通し
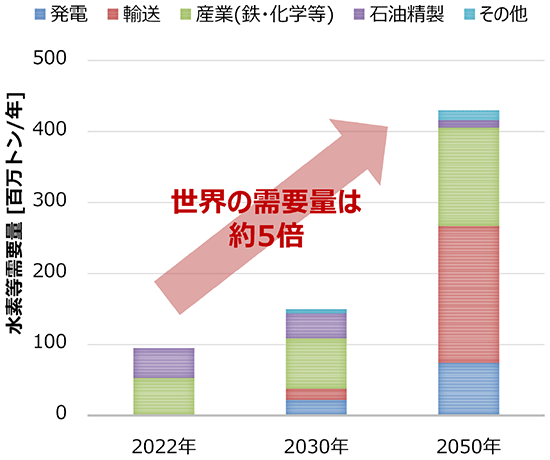
(注)2030年及び2050年の数値は、IEAが想定した将来シナリオであるNZE(2050年世界ネットゼロを達成するためのシナリオ)における予測値。
【第132-2-1】世界の水素等の需要見通し(ppt/pptx形式:687KB)
- 資料:
- IEA「Net Zero Roadmap」を基に経済産業省作成
②各国における水素政策の動向
カーボンニュートラルの実現に向けた取組が進んでいく中、水素の需要は世界的に拡大していくことが予想されていますが、その一方で、水素の利活用が進む社会の実現のためには、水素サプライチェーンの構築や、水素製造等に係るコストの低減、水素関連技術の研究開発等の課題も存在しています。各国は、カーボンニュートラルの実現という観点とともに、これから世界的に拡大していくことが見込まれている水素マーケットを見越して、自国の水素産業を成長させていくという観点からも、水素の利活用を推し進めていくための戦略等を策定しており、こうした課題の解決に向けて、規制と支援の両輪で様々な取組を実施しています(第132-2-2)。
【第132-2-2】各国における水素政策の例
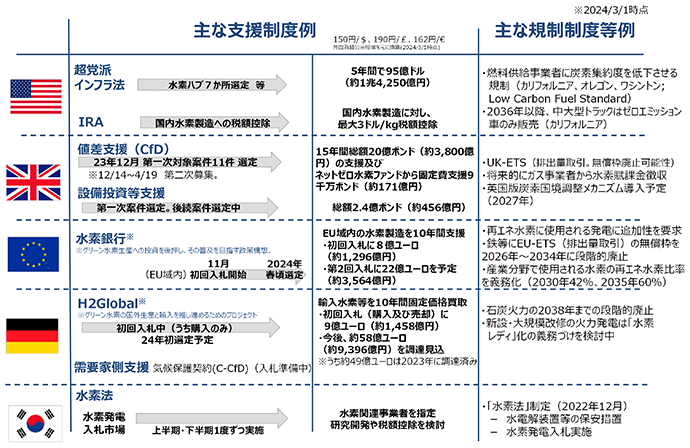
【第132-2-2】各国における水素政策の例(ppt/pptx形式:91KB)
- 資料:
- 各国政府資料等を基に経済産業省作成
(ア)米国
米国は、2021年6月に発表した「Hydrogen Shot」において、クリーン水素の価格を10年以内に1kg当たり1ドルにするとの目標を掲げました。また、2023年6月に公表した「U.S. National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap」では、クリーン水素の年間生産量を、2030年までに1,000万トン、2040年までに2,000万トン、2050年までに5,000万トンへと拡大するとの目標を掲げました。
こうした目標の達成に向けて、2021年に成立した超党派による「インフラ投資雇用法」では、クリーン水素関連のプロジェクトに対して5年間で95億ドルの支援策が打ち出され、クリーン水素に係る研究開発や、利用促進のための拠点となるクリーン水素ハブの整備等への支援が行われています。また、2022年8月に成立した「インフレ削減法」では、国内でのクリーン水素の製造に対する10年間の生産税額控除(最大で1kg当たり3ドルを控除)等の支援策が打ち出されています。
(イ)英国
英国は、2022年4月に発表した「British Energy Security Strategy」において、2030年までに国内で10GWの低炭素水素の製造能力を確保するとともに、そのうち5GW以上を水電解装置由来の水素とすることを目標として掲げました。
こうした目標の達成に向けて、英国では、差額決済契約(CfD14)制度による低炭素水素と化石エネルギーの価格差支援や、最大2.4億ポンドの「ネットゼロ水素ファンド(NZHF)」を通じた低炭素水素の製造能力の拡大に向けた設備投資等への支援を実施していくこととしています。2023年12月には、ネットゼロ水素ファンドによるグリーン水素プロジェクトへの資金支援の第一弾の結果が発表され、計11のプロジェクトが選定されました。
(ウ)EU
EUは、ロシアによるウクライナ侵略が発生した直後の2022年3月に、ロシア産エネルギーからの脱却等を目指した計画である「REPowerEU」を発表しました。この計画では、水素について、2030年にEU域内で年間1,000万トンのグリーン水素を製造するとともに、EU域外から同じく年間1,000万トンのグリーン水素を輸入するとの目標を掲げました。この目標が実現することで、2030年には年間2,000万トンものグリーン水素がEU内に供給されることになります。
こうした目標の達成に向けて、各EU加盟国において取組が進められていますが、EUとしても様々な取組を実施しています。2023年にEUが発表した「グリーンディール産業計画」では、その政策メニューの1つとして、「欧州水素銀行」が創設されました。欧州水素銀行は、EU域内でのグリーン水素の製造を支援する仕組みであり、製造したグリーン水素1kg当たりの固定額プレミアムを10年間にわたって補助するために、競争入札が開始されています。
(エ)ドイツ
ドイツは、2020年に発表した「国家水素戦略」において、2030年までに国内で5GWの水素製造能力を確保するという目標を掲げましたが、2023年7月に国家水素戦略を初めて改定し、この目標を、少なくとも10GWに倍増させました。また、ドイツは国外からの輸入拡大に向けた取組にも力を入れています。改定後の国家水素戦略では、国内における水素需要の増加が見込まれる中、国内製造だけでは需要が賄えないことや、経済性等の観点から、2030年における国内の水素需要のうち、50%〜70%を国外から輸入するという目標も掲げています。
こうした目標の達成に向けて、ドイツは、非EU加盟国であるアフリカ等のグリーン水素の製造に適した国や地域と提携して、グリーン水素等の国外製造と輸入を推進するため、「H2Global」プロジェクトを進めています。具体的には、取引仲介会社が、入札を通じて10年間にわたって固定価格で全量を購入するとともに、入札を通じて需要家に販売(1年等の短期契約)することとしており、供給側からの購入価格と需要家への販売価格の価格差を、政府が支援しています。
(オ)その他の国々
欧米以外の国々でも、水素の活用に向けた戦略が策定されるとともに、その実現に向けた様々な取組が進められています。
例えば、韓国は、2021年10月に発表した「水素先導国家ビジョン」において、クリーン水素の製造量を2030年に年間100万トン(うちグリーン水素25万トン、ブルー水素75万トン)とし、2050年には年間500万トン(うちグリーン水素300万トン、ブルー水素200万トン)へと拡大するという目標を掲げています。2023年6月には、水素やアンモニア等を燃料にして発電された電気を購入・供給する「水素発電入札市場」を世界で初めて開設すると発表しました。
その他にも、中国やインド、豪州、シンガポール、チリ等、多くの国において、水素の活用に向けた戦略が策定されており、その実現に向けて、研究開発やインフラ整備等への支援策等が講じられています。
(2)CCSを巡る世界の動向
①CCSを巡る状況
次に、CCSを巡る動向について確認していきます。世界中の多くの国々がカーボンニュートラルの実現を目指し、省エネの推進や、再エネ・原子力等の非化石電源の導入拡大、水素の活用等の取組を進めていますが、その一方で、CO2の排出が避けられない分野も存在しています。カーボンニュートラルを実現するためには、こうした分野から排出されるCO2を抑制する必要がある中、CO2を回収して地中に貯留するCCSは、この問題を解決するための重要なオプションとなっています。
②各国におけるCCS政策の動向
カーボンニュートラルの実現に不可欠な取組として、CCSが世界的に推進されていくことが想定されていますが、CCSの導入を進めていくためには、CCS適地の開発や事業コストの低減、関連技術の研究開発、事業化に向けた環境整備等、様々な課題が存在しています。そのため、各国においては、こうした課題を解決し、CCSの導入を進めていくための法制度や支援策の整備が積極的に進められています。さらに、鉄鋼業界や化学業界等のCO2を多く排出する民間企業によるCCSに向けた取組についても、盛んに行われるようになってきています(第132-2-3、第132-2-4)。
【第132-2-3】世界各国におけるCCS政策
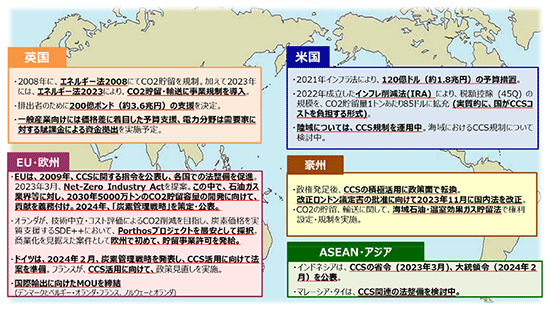
【第132-2-3】世界各国におけるCCS政策(ppt/pptx形式:824KB)
- 資料:
- 各国政府資料等を基に経済産業省作成
【第132-2-4】世界のCO2多排出企業におけるCCSに向けた取組
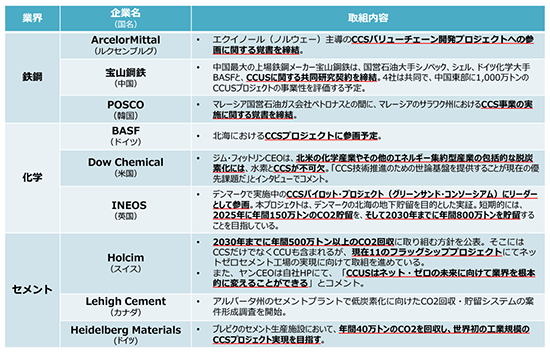
【第132-2-4】世界のCO2多排出企業におけるCCSに向けた取組(ppt/pptx形式:68KB)
- 資料:
- 各社資料等を基に経済産業省作成
(ア)米国
米国は、CCSに対する支援策として、CO2の貯留量等に応じた生産税額控除(セクション45Q)を2008年に導入しました。2022年8月に成立した「インフレ削減法」では、その内容が改定され、税額控除の金額が大きく引き上げられました。具体的には、CO2の地中貯留に対する税額控除が、1トン当たり50ドルから85ドルへと引き上げられました。このことにより、CCSのコストを国が実質的に負担する形となっており、米国におけるCCSプロジェクトが今後大きく加速することが見込まれています。
その他にも、2021年に成立した超党派による「インフラ投資雇用法」では、CO2の分離・回収や輸送、利用、貯留等に関する技術開発や実証等に対して、2022年から2026年の5年間で計120億ドルの予算措置が講じられています。
(イ)EU
EUは、2024年2月にEU理事会と欧州議会の間で暫定的な政治合意がなされた「ネットゼロ産業法案」において、CCSに関して、2030年までに年間5,000万トンの貯留能力の開発を目指すとの目標を掲げました。そして、この目標を達成するため、EU域内の石油・ガスの生産事業者に対して、生産量に応じた貢献を義務づけています。
また、ネットゼロ産業法案の暫定合意と同日には、欧州委員会が、CCUS15技術とCO2の輸送に関する「炭素管理戦略」を発表しました。ネットゼロ産業法案で掲げた目標等を目指していく中で必要となる技術の開発や、規制や投資の枠組みの構築に向けた今後の取組が示されています。
(ウ)英国
英国は、2030年までに年間2,000万トン〜3,000万トン、2035年までに年間5,000万トンのCO2を貯留するとの目標を掲げており、こうした目標の達成に向けた取組として、2023年3月には、今後20年間で最大200億ポンドの支援を行うことを発表しました。
また、同年12月には、英国のエネルギー安全保障・ネットゼロ省が、英国におけるCCUSの拡大と競争市場の確立に向けた計画である「CCUSビジョン」を発表しました。この計画において、英国は、島国ならではの地質や技術等を有するため、他国よりも戦略的優位性を持っており、北海沖には最大で780億トンのCO2を貯留できるスペースがあると分析しています。そして、CCUSビジョンでは、英国が2035年までにCCUSに関して競争力のある市場に移行していくための取組が示されており、これによって、2050年までに年間50億ポンドもの経済成長をもたらすとしています。
(エ)その他の国々
欧米以外の国々においても、CCSの導入に向けた動きが加速しています。
世界全体のCO2排出量の3割以上を排出している中国では、2023年6月に、国有石油会社である中国海洋石油集団(CNOOC)が、中国で初めてとなる沖合でのCCS実証プロジェクトを開始したと発表しています。
また、経済成長に伴いCO2の排出増加が続くASEANでも、CCSに関する取組が加速しています。インドネシアでは、2023年3月に、石油・天然ガスの上流部門におけるCCS及びCCUSの実施に関する省令が制定されました。この省令は、排出削減を実現しながら、石油と天然ガスの増産を促進するものとされています。また、マレーシアやタイにおいても、CCSに関する法整備が検討されています。
さらに、多くの化石エネルギーを生産している豪州や中東地域等においても、CCSを積極的に進めるべく、様々な取組が行われています。
3.日本におけるGX実現に向けたエネルギー政策
(1)GX実現に向けた日本の政策動向
世界中でGXの実現に向けた投資促進策やルールメイキングの議論等が積極的に進められていますが、日本も同様に、国際ビジネスで勝てる企業群を生み出すための市場創造の議論や、研究開発・実証、規制・標準化等の制度整備等、GXの実現に向けた政策を積極的に推進しています。
日本では、2022年7月に、産業革命以来の化石エネルギー中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心のものに移行させ、経済社会システム全体の変革である「GX」を実行するべく、必要な施策を検討する目的で、官邸に「GX実行会議」を設置しました。このGX実行会議では、大きな論点として、日本のエネルギーの安定供給の再構築に必要となる方策と、それを前提とした脱炭素に向けた経済・社会、産業構造変革への今後10年のロードマップについて、議論が重ねられました。そして、2023年2月10日には、GXの実現を通じて、2030年度の温室効果ガス46%削減(2013年度比)や2050年カーボンニュートラルといった国際公約の達成を目指すとともに、安定的で安価なエネルギー供給につながるエネルギー需給構造の転換を実現し、さらには、日本の産業構造・社会構造を変革し、将来世代を含む全ての国民が希望を持って暮らせる社会を実現するための今後10年を見据えた取組の方針をとりまとめた「GX実現に向けた基本方針」(以下「GX基本方針」という。)が閣議決定されました。
2023年度は、GXの実現に向けて必要となる法整備が進みました。GX基本方針では、世界規模でGXの実現に向けた官民の投資競争や新たな市場・ルールの形成の取組が加速する中、日本でも、脱炭素分野において新たな需要・市場を創出し、2050年カーボンニュートラル等の国際公約と産業競争力強化・経済成長を同時に実現していくためには、今後10年間で150兆円を超える官民のGX投資が必要であると示されています。そのため、GX基本方針に基づき、「GX推進戦略」の策定・実行や脱炭素成長型経済構造移行債(以下「GX経済移行債」という。)の発行、成長志向型カーボンプライシングの導入や脱炭素成長型経済構造移行推進機構(GX推進機構)の設立、そして進捗評価と必要な見直しを法定する「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和5年法律第32号)」(以下「GX推進法」という。)が、2023年5月12日に成立しました。また、ロシアによるウクライナ侵略に起因する国際エネルギー市場の混乱や国内における電力需給ひっ迫等への対応に加え、GXの実現に向けて、脱炭素電源の利用促進を図りつつ、電気の安定供給を確保するための制度整備が必要であることから、GX基本方針に基づき、地域と共生した再エネの最大限の導入促進と、安全性の確保を大前提とした原子力の活用に向けて、所要の関連法16を改正する「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第44号)」(GX脱炭素電源法)が、同年5月31日に成立しました。その後、GXの実現に向けた政策を実行していくため、GX推進法に基づき、GX基本方針の内容を踏まえて、同年7月28日に「GX推進戦略」を策定(閣議決定)しました(第132-3-1、第132-3-2)。
【第132-3-1】脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)の概要
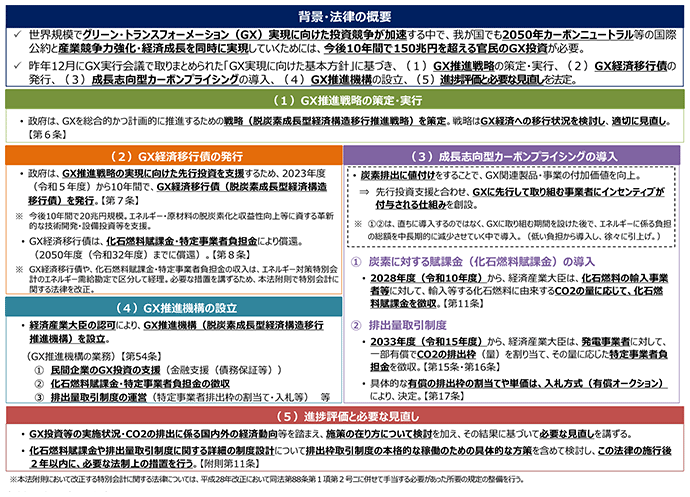
【第132-3-1】脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)の概要(ppt/pptx形式:82KB)
- 資料:
- 内閣官房作成
【第132-3-2】脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(GX脱炭素電源法)の概要
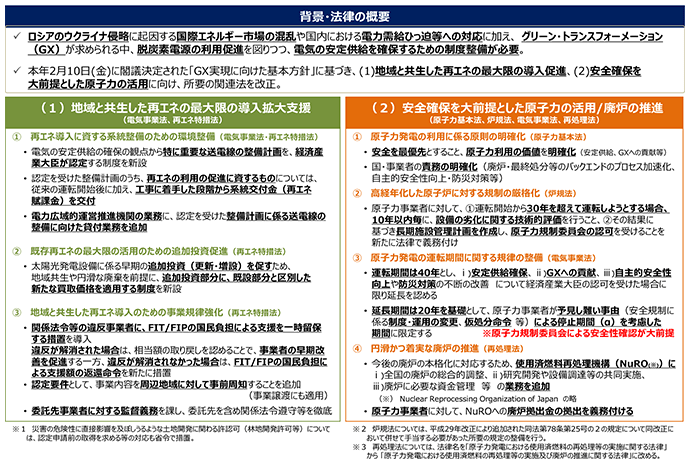
【第132-3-2】脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(GX脱炭素電源法)の概要(ppt/pptx形式:79KB)
- 資料:
- 内閣官房作成
2023年10月からは、GX経済移行債を活用した投資促進策の具体化に向けて、技術開発動向を踏まえた排出削減効果や、市場動向を踏まえた経済効果等に照らした検討を進めるため、「GX実現に向けた専門家ワーキンググループ」を開催し、重点分野ごとのGXの方向性や投資促進策等について議論を行いました。そして、同年12月のGX実行会議において、「分野別投資戦略」としてとりまとめました。分野別投資戦略では、支援策の対象となる事業者に対してGXに関する相応のコミットを求めることとしており、そうした観点から「投資促進策の執行原則」の中では、「海外市場の獲得(物売りにとどまらず、制度・システム売りを含む)を見据え、海外でポジションを取るためのルールメイキングもセットで進める(GXリーグでの民間のルールメイキングの取組サポート等)」こと等が記載されています。今後は、この分野別投資戦略の遂行により、各重点分野での官民によるGX投資を促進していくことで、日本のGXの実現を加速させていきます。
(2)分野別投資戦略
分野別投資戦略では、16の重点分野について、GXの方向性や投資促進策等がとりまとめられました。16分野とは、鉄鋼、化学、紙パルプ、セメント、自動車、蓄電池、航空機、SAF、船舶、くらし、資源循環、半導体、水素等17、次世代再エネ(次世代型太陽電池・浮体式等洋上風力)、原子力、CCSを指します。本項では、その概要について確認していきます。
①製造業(鉄鋼・化学・紙パルプ・セメント)
最初に、日本全体のCO2排出量の4割弱を占める製造業関連の分野別投資戦略について見ていきます。製造業では、主に製造プロセスの転換に向けた設備投資や技術開発への支援等を進めていくことが示されています。
例えば、4分野(鉄鋼・化学・紙パルプ・セメント)の中で最もCO2排出の多い鉄鋼については、GXの方向性として、大型革新電炉・直接還元等による高付加価値鋼板製造の生産を拡大していくこと等が示されました。そして、そのための投資促進策として、大型革新電炉転換や還元鉄の確保・活用等のプロセス転換投資への支援等を進めつつ、同時に、GX価値の見える化や導入補助時のGX価値評価等のインセンティブ設計、国際的に調和されたルール形成の追求等を通じた市場創造等も進めていくことが示されました(第132-3-3)。
【第132-3-3】分野別投資戦略の概要(製造業関連)
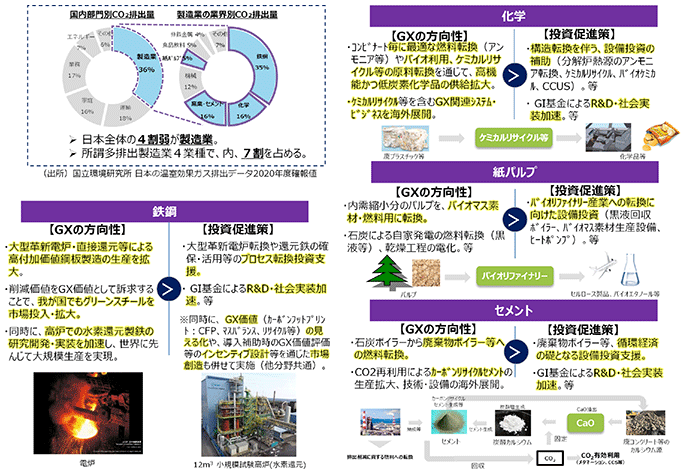
【第132-3-3】分野別投資戦略の概要(製造業関連)(ppt/pptx形式:4,558KB)
- 資料:
- 「分野別投資戦略」より抜粋
②運輸(自動車・蓄電池・航空機・SAF・船舶)
次に、運輸関連の分野別投資戦略について見ていきます。運輸部門から排出されるCO2の大半を排出している自動車については、GXの方向性として、電動車の開発・性能向上への投資促進と市場拡大を一体的に実施していくことや、世界の蓄電池の開発・生産をリードする拠点として成長していくことが示されました。そして、そのための投資促進策として、電動車の購入支援に加え、蓄電池の生産能力拡大に向けた設備投資への補助、全固体電池等の次世代電池の研究開発への支援等を進めつつ、国際ルールの形成等も行っていくことが示されました。
また、航空機、SAF、船舶についても、脱炭素化に向けた技術開発や設備投資への支援等を進めていくことが示されました。(第132-3-4)。
【第132-3-4】分野別投資戦略の概要(運輸関連)
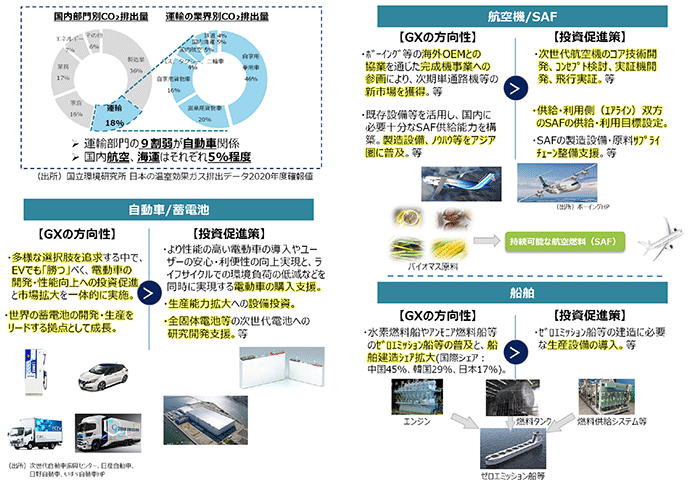
【第132-3-4】分野別投資戦略の概要(運輸関連)(ppt/pptx形式:7,969KB)
- 資料:
- 「分野別投資戦略」より抜粋
③くらし・資源循環・半導体
国民のくらしに深く関連する家庭部門、ビル等の業務部門、自家用乗用車等の運輸部門から排出されるCO2は、日本全体のCO2排出量の過半を占めており、くらしのGXを進めていくことが重要です。家庭部門や業務部門におけるGXの方向性として、断熱窓への改修や高効率給湯器の導入に対する支援を強化していくことや、トップランナー規制により市場に普及する機器・設備の高効率化を図っていくことが示されました。そして、そのための投資促進策として、家庭における断熱窓への改修や高効率給湯器の導入に加え、商業・教育施設等の建築物の改修への支援等を進めていくことが示されました。
資源循環については、GXの方向性として、産官学連携での資源循環市場の創出・確立を進めていくこと等が示されました。そして、そのための投資促進策として、循環型ビジネスモデルの構築に向けて、研究開発から実証・実装までの戦略的かつシームレスな支援等を進めつつ、循環価値(カーボンフットプリント、マテリアルフットプリント等)についての算定・表示ルールの形成等も行っていくことが示されました。
半導体については、GXの方向性として、省エネ・低消費電力化のキーパーツであるパワー半導体の製造基盤の確保に努めていくことや、AI半導体等の次世代技術を確立していくことが示されました。そして、そのための投資促進策として、パワー半導体やガラス基板の生産基盤整備への支援や、AI半導体等の次世代技術の開発への支援等を進めていくことが示されました(第132-3-5)。
【第132-3-5】分野別投資戦略の概要(くらし・資源循環・半導体)
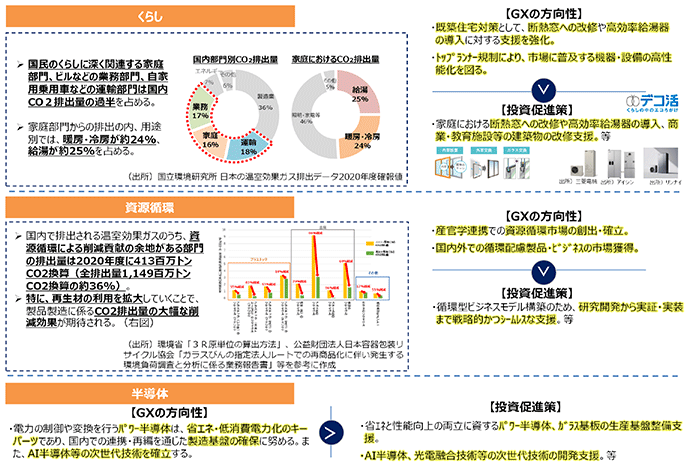
【第132-3-5】分野別投資戦略の概要(くらし・資源循環・半導体)(ppt/pptx形式:1,739KB)
- 資料:
- 「分野別投資戦略」より抜粋
④エネルギー(水素等・次世代再エネ・原子力・CCS)
エネルギー関連では、水素等18・次世代再エネ(次世代型太陽電池、浮体式等洋上風力)・原子力・CCSの分野別投資戦略がとりまとめられました(第132-3-6)。
【第132-3-6】分野別投資戦略の概要(エネルギー関連)
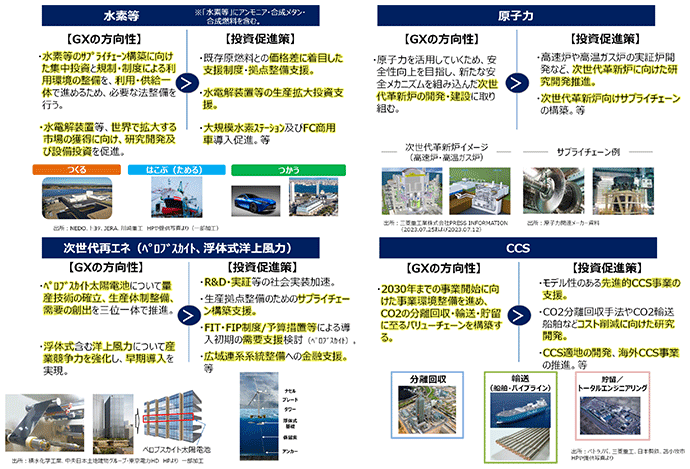
【第132-3-6】分野別投資戦略の概要(エネルギー関連)(ppt/pptx形式:7,606KB)
- 資料:
- 「分野別投資戦略」より抜粋
(ア)水素等
水素等については、GXの方向性として、水素等のサプライチェーン構築に向けた集中投資と規制・制度による利用環境の整備を利用・供給一体で進めるために必要な法整備を行っていくことや、水電解装置等の世界で拡大する市場の獲得に向けて研究開発及び設備投資を促進していくことが示されました。そして、そのための投資促進策として、既存原燃料との価格差に着目した支援制度や拠点整備支援制度の整備、水電解装置等の生産拡大投資への支援、大規模水素ステーション及び燃料電池商用車の導入促進等を進めつつ、クリーン水素等の環境価値評価の基盤構築等も行っていくことが示されました。
(イ)次世代再エネ
次世代再エネについては、次世代型太陽電池(ペロブスカイト太陽電池)と浮体式等洋上風力に関するGXの方向性や投資促進策等が示されました。GXの方向性として、ペロブスカイト太陽電池については、量産技術の確立・生産体制の整備・需要の創出を三位一体で推進していくことが示され、浮体式を含む洋上風力については、日本の産業競争力を強化し、早期導入を実現していくことが示されました。そして、そのための投資促進策として、グリーンイノベーション基金による研究開発・実証等の社会実装の加速や、生産拠点整備のためのサプライチェーン構築への支援、FIT・FIP制度や予算措置等によるペロブスカイト太陽電池の初期需要の創出、広域連系系統整備への金融支援等を進めつつ、欧米等とも連携した評価手法等の国際標準化等も行っていくことが示されました。
(ウ)原子力
原子力については、GXの方向性として、原子力を活用していくため、安全性の向上を目指し、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設に取り組んでいくことが示されました。そして、そのための投資促進策として、高速炉や高温ガス炉の実証炉開発等の次世代革新炉に向けた研究開発の推進、次世代革新炉向けサプライチェーンの構築等を進めていくことが示されました。
(エ)CCS
CCSについては、GXの方向性として、2030年までの事業開始に向けた事業環境整備を進め、CO2の分離回収・輸送・貯留に至るバリューチェーンを構築していくことが示されました。そして、そのための投資促進策として、モデル性のある先進的CCS事業への支援、CO2分離回収手法やCO2輸送船舶等のコスト削減に向けた研究開発、CCS適地の開発、海外CCS事業の推進等を進めていくことが示されました。
⑤日本のGX実現に向けた取組
このように、2023年12月にとりまとめられた「分野別投資戦略」では、重点分野ごとの具体的なGXの方向性や投資促進策等が示されました。GX経済移行債による投資促進策についても、それぞれの分野において、既に始まりつつあります。まさに、日本におけるGXの実現に向けた取組は、検討フェーズから「実行」フェーズへと突入したといえます(第132-3-7)。
【第132-3-7】GX経済移行債による投資促進策(案)
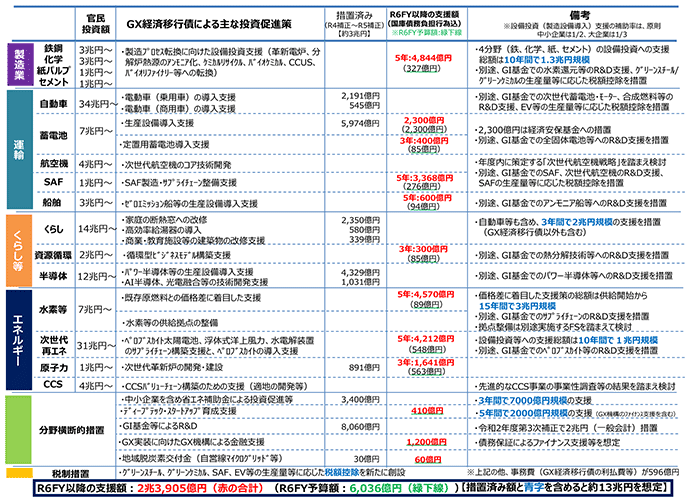
【第132-3-7】GX経済移行債による投資促進策(案)(ppt/pptx形式:104KB)
- 資料:
- 「分野別投資戦略」より抜粋
また、前章でも紹介したとおり、日本では「GX」とともに、生成AIの普及をはじめとした「DX」のさらなる進展も予測されています。GXに加えて、DXの進展によるデータ処理量の増大に伴い、今後の電力需要に関しては、増加する可能性についての指摘もあり、不確実性が一層高まっている状況です(第122-2-1参照)。日本では、こうした動向・変化にも注意を払いつつ、GXの実現に向けた様々な取組を通じて、今後もエネルギーの安定供給を確保しながら、カーボンニュートラルの実現に向けた歩みを着実に進めていきます。
(3)水素社会推進法案・CCS事業法案
日本が掲げている2050年カーボンニュートラルという目標の実現に向けては、徹底した省エネの推進や、再エネ・原子力といった脱炭素電源の導入拡大等の取組が重要ですが、それらとともに、脱炭素化が難しい分野におけるGXの推進が不可欠となっています。そうした中、その解決策として期待が高まっているのが、水素等やCCSです。前述のとおり、世界中で水素等やCCSの活用に向けた取組が進んでいますが、日本においても、活用に向けた法整備を進めています。2024年2月13日には、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案」(以下「水素社会推進法案」という。)及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律案」(以下「CCS事業法案」という。)の2法案が閣議決定され、第213回国会に提出されました19。この2つの法案は、鉄鋼・化学等の産業やモビリティといった脱炭素化が難しい分野・用途でのGXを推進するため、こうした分野における①低炭素水素等の供給・利用の促進を図るとともに、②CCSに関する事業環境整備を行うものであり、GX推進戦略に基づいて、所要の措置を講じるものとなっています。
①水素社会推進法案
2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、脱炭素化が難しい分野においてもGXを推進し、エネルギー安定供給・脱炭素・経済成長を同時に実現していくことが課題となっています。そうした中、脱炭素化が難しい分野におけるGXを進めるためのカギとなるエネルギー・原材料として、安全性を確保しながら、低炭素水素等の活用を促進することが不可欠です。このため、水素社会推進法案では、国が前面に立って、低炭素水素等の供給・利用を早期に促進するため、基本方針の策定、需給両面の計画認定制度の創設、計画認定を受けた事業者に対する支援措置(価格差に着目した支援・拠点整備支援等)や規制の特例措置を講じるとともに、低炭素水素等の供給拡大に向けて、水素等の供給を行う事業者が取り組むべき判断基準の策定等の措置を講じています(第132-3-8)。
【第132-3-8】水素社会推進法案の概要

【第132-3-8】水素社会推進法案の概要(ppt/pptx形式:1,167KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
②CCS事業法案
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、脱炭素化が難しい分野におけるGXを実現するためには、こうした分野における化石燃料・原料の利用後の脱炭素化を進める手段として、CO2を回収して地下に貯留するCCSの導入が不可欠となっています。このため、CCS事業法案では、2030年までに民間事業者が国内におけるCCS事業を開始するための事業環境を整備するため、試掘・貯留事業の許可制度の創設、貯留事業に係る事業規制・保安規制の整備とともに、CO2の導管輸送事業に係る事業規制・保安規制を整備しています(第132-3-9)。
【第132-3-9】CCS事業法案の概要
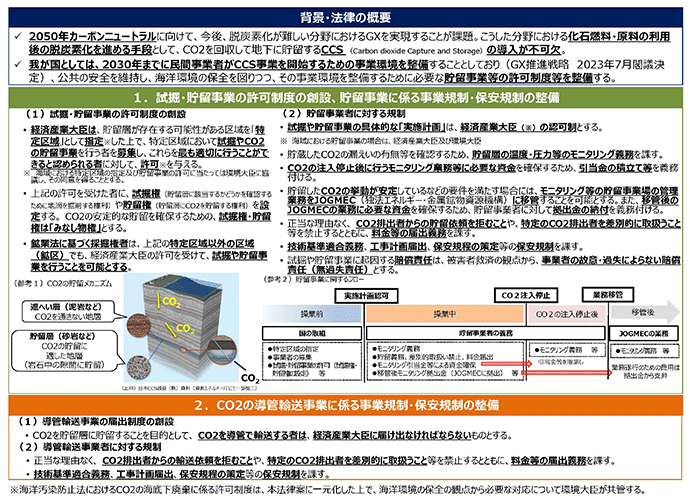
【第132-3-9】CCS事業法案の概要(ppt/pptx形式:1,048KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
4.アジアのGXに向けた日本の貢献
前項のとおり、日本におけるGXの実現に向けた取組は、検討フェーズから「実行」フェーズへと突入しています。こうした取組を進めることにより、日本では、エネルギー安定供給の確保や経済成長を実現していくとともに、2030年度の温室効果ガス46%削減(2013年度比)や2050年カーボンニュートラルといった目標の達成に向け、気候変動問題への対応についても加速させていきます。
しかし、気候変動問題という国境のない問題に対応していくためには、世界全体の温室効果ガス排出量を減らしていくことが不可欠である中、前節でも確認したように、経済成長を続ける途上国、特にアジア諸国からの排出量が急増していることから、世界全体の排出量は依然として増加傾向が続いています。世界全体の排出量を減らしていくためには、途上国、特にアジア諸国における排出削減・GXを進めることが重要となっており、日本では、こうした国々のGXに貢献するための取組も推進しています。本項では、こうした日本の取組等について確認していきます。
(1)成長著しいアジアの状況と課題
中国やインドをはじめ、急速に経済成長を遂げている国を多く抱えるアジアでは、エネルギー需要の増加に伴い、エネルギー起源CO2の排出量も急増しており、2021年における世界全体の排出量の6割近くは、アジアによる排出が占める状況となっています。中国やインド以外では、ASEANの排出量も増加しており、2021年におけるASEANの排出量は、日本の排出量の約1.6倍となりました。こうした状況から、世界全体でカーボンニュートラルを実現していくためには、アジアにおける排出をどう減らすかという点が極めて重要なポイントとなっており、換言すれば、アジアにおけるカーボンニュートラルなくして、世界のカーボンニュートラルは実現できないといっても過言ではない状況です(第132-4-1)。
【第132-4-1】エネルギー起源CO2排出量の推移(主要国・エリア別)
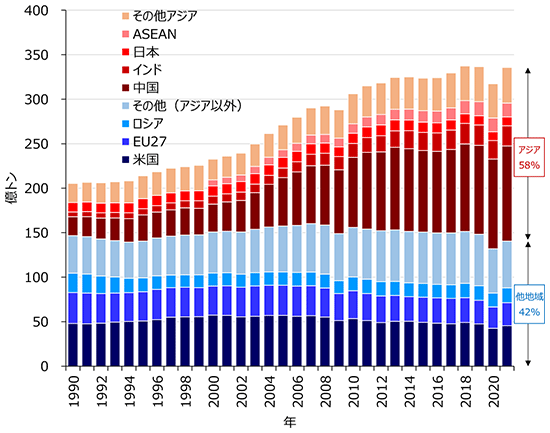
(注)1999年以前の「その他アジア」には、「ASEAN」を含む。
【第132-4-1】エネルギー起源CO2排出量の推移(主要国・エリア別)(ppt/pptx形式:64KB)
- 資料:
- IEA「CO2 Emissions from Fuel Combustion」を基に経済産業省作成
こうした中、アジアでは、今後もエネルギー需要が堅調に伸びていくことが予測されています。例えば、IEAが策定した将来見通し20において、ASEANの電力需要については、2021年から2050年にかけて2.8倍に増加していくと見込まれています。この2050年におけるASEANの電力需要の予測値は、現在の日本の電力需要の約3倍に相当するものとなっています(第132-4-2)。
【第132-4-2】アジア各国における電力需要の予測
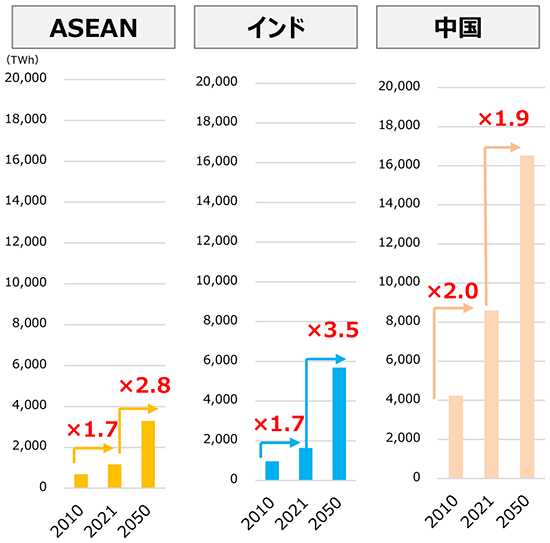
(注)2050年の数値は、IEAが想定した将来シナリオであるSTEPS(各国が表明済の具体的政策を反映したシナリオ)における予測値。
【第132-4-2】アジア各国における電力需要の予測(ppt/pptx形式:67KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Outlook 2023」を基に経済産業省作成
このように、成長著しいASEANですが、2050年までのカーボンニュートラルを掲げるベトナムやマレーシア、2060年までのカーボンニュートラルを掲げるインドネシアのように、カーボンニュートラルという目標を掲げる国も多く登場しており、各国では、カーボンニュートラルの実現に向けた取組が進められています。しかしその一方で、ASEANの多くの国では、日本と同様に、電力の大半を石炭火力や天然ガス火力に依存している状況となっています(第132-4-3)。
【第132-4-3】主要なASEAN諸国における発電電力量と電源構成(2021年)
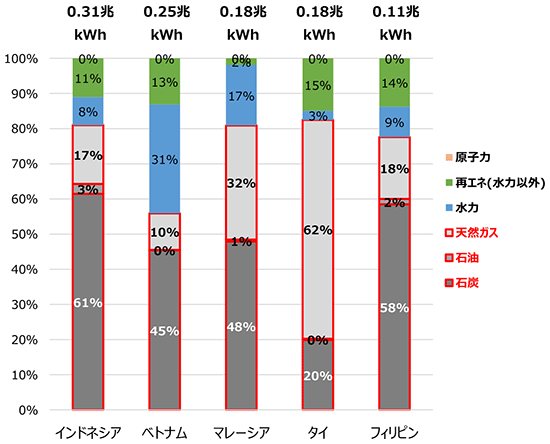
【第132-4-3】主要なASEAN諸国における発電電力量と電源構成(2021年)(ppt/pptx形式:55KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023」を基に経済産業省作成
一般的に、カーボンニュートラルの実現に向けては、非化石電源を拡大させ、石炭火力等の火力発電の割合を減らしていくことが必要とされていますが、今後も経済成長に伴う電力需要の大幅な増加が予測されているASEANにおいて、一足飛びに石炭火力等を廃止していくことは現実的ではありません。ASEANは、電力需要の増加が予測される中、エネルギーの安定供給を損なうことなく、同時に脱炭素化を果たしていかなければならないという非常に難しい課題を抱えており、そのための解決策を必要としています。
(2)アジアのGXへの日本の貢献(AZEC)
世界全体のカーボンニュートラルの実現のためには、各国固有の事情に応じた多様な道筋の下、様々な技術を活用しながら、同じゴールに向かって、それぞれの取組を着実に進めていくことが重要です。例えば、ASEAN等のアジアにおいては、今後も経済成長に伴うエネルギー需要の増加が見込まれる中、現実的な形で着実に取組を進めていくことが必要とされており、そのことが世界全体のカーボンニュートラルの実現に向けても不可欠となります。
こうした中、日本では、「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」の枠組みの下、様々な取組を加速させています。AZECには、日本の他に、豪州、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム(計11か国)がパートナー国として参画しており、日本は、このAZECの枠組みの下、日本が有する脱炭素技術やファイナンス等を通じて、アジアにおけるGXの実現にも貢献していくべく、様々な取組を進めています。前述のとおり、日本は様々な分野においてGXの実現に向けた取組を進めていますが、電源の多くを火力発電に頼っている、GDPに占める製造業の割合が高い等、日本の置かれている状況は、アジア各国を取り巻く状況とも共通点が多くあります。そのため、日本のGXの実現に向けた取組は、アジアにおけるGXにもつながりうると考えられます。AZECは、エネルギーの需給構造が類似したアジアの国々が、脱炭素に必要な技術や情報、ノウハウ、資金、人材、市場、資源を共有し、ルールや標準、制度を共通化することで、日本のGXの実現に向けた取組と、アジアにおけるGXをつなぐ「架け橋」となるものです。その一例として、日本では、脱炭素燃料である水素等を燃料とした発電やCCS事業等の推進に向けて、技術開発や法整備等の取組を加速させていますが、既存の火力発電の設備を活用しながら、段階的かつ着実に排出削減を進めることができるこうした技術は、電力需要が今後も大幅に増加し、当面の間は火力発電を活用せざるを得ないASEAN等の国々にとっても、極めて重要なオプションです。日本では、こうした脱炭素に資する様々な技術や知見等を、日本のGXの実現につなげるだけでなく、AZECの取組を通じて、アジアにおけるGXの実現にもつなげていくことを目指しています。
2023年12月18日には、初となる「AZEC首脳会合」が東京で開催され、日本からは岸田総理、齋藤経済産業大臣等が参加したほか、AZECパートナー国からも首脳が参加し、AZECの考え方や活動に係る議論が行われました。この首脳会合では、岸田総理から、「多様な道筋による、ネットゼロ」という共通目標の達成や、「脱炭素・経済成長・エネルギー安全保障」の同時実現という3つのブレークスルーの重要性を発信しました。その上で、次世代のGX技術の開発や導入加速に向けた日本の取組に触れつつ、AZEC構想を通じて、日本の技術や経験を各国へ共有していく意思を表明しています(第132-4-4)。
【第132-4-4】アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)構想の概要
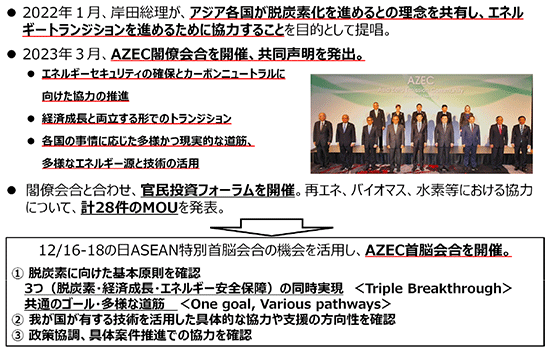
【第132-4-4】アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)構想の概要(ppt/pptx形式:485KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
今後も日本では、日本国内におけるGXの実現に向けた取組を着実に進めていくとともに、日本が有する様々な技術や知見等の強みを活用しながら、アジアのGX、そして世界のGXの実現にも貢献していきます。
- 11
- CCS:Carbon dioxide Capture and Storageの略で、CO2の回収・貯留のこと。
- 12
- 「Inflation Reduction Act(IRA)」のことで、インフレ抑制法とも呼ばれています。
- 13
- ここでのデータには、アンモニアや合成燃料等の水素化合物を含んでいます。
- 14
- CfD:Contract for Differenceの略。CfD制度とは、投資回収が可能な水準で基準価格を設定し、その価格と需要家への販売価格(参照価格)との価格差を長期間にわたって支援することで、事業の予見可能性や事業安定性を確保する仕組みのこと。
- 15
- CCUS:Carbon dioxide Capture, Utilization and Storageの略で、CO2の回収・有効利用・貯留のこと。
- 16
- 関連法とは、「電気事業法」、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)」、「原子力基本法」、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規法)」、「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(再処理法)」のこと。
- 17
- 「水素等」には、アンモニア、合成メタン、合成燃料が含まれます。
- 18
- 「水素等」には、アンモニア、合成メタン、合成燃料が含まれます。
- 19
- その後、2法案は2024年5月に成立しています。
- 20
- 各国が表明済の具体的政策を反映したシナリオ(STEPS)における見通し。