第2節 エネルギーセキュリティに関する日本の課題と対応
日本のエネルギー政策における基本的な方向性を示すものが、「エネルギー基本計画」です。このエネルギー基本計画は、これまで約3年から4年に一度の頻度で見直されており、最新の「第6次エネルギー基本計画」は、2021年10月22日に閣議決定されています。この第6次エネルギー基本計画において、エネルギー政策を進める上では、安全性(Safety)を前提とした上で、エネルギーの安定供給(Energy Security)を第一とし、経済効率性の向上(Economic Efficiency)による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、環境への適合(Environment)を図る視点が重要であるとしています。なお、この考え方のことを、それぞれの頭文字を取って「S+3E」と呼んでいます。その上で、この第6次エネルギー基本計画では、2050年カーボンニュートラルや2030年度の温室効果ガスの排出削減目標(2013年度比で46%削減、さらに50%の高みに向けて挑戦を続ける)の実現に向けたエネルギー政策の道筋を示すこと、そして、気候変動対策を進めながら、日本のエネルギー需給構造が抱える課題の克服に向けて、安全性の確保を大前提に安定供給の確保やエネルギーコストの低減に向けた取組を示すこと、の2つを重要なテーマとしています。
そうした中、2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略は、それまでのエネルギーを取り巻く環境を大きく変化させることとなりました。その後も、前節でも記載したように、イスラエル・パレスチナ情勢の悪化やパナマ運河における通航制限等、エネルギーを取り巻く環境に影響を与える事象は世界各地で数多く発生しており、世界各国は、カーボンニュートラルの実現に向けた取組とともに、エネルギーセキュリティの確保に向けた取組を進めています。
前節では、こうした対応状況等について、主に他国の動向について記載してきましたが、本節では、日本のエネルギーセキュリティを巡る状況や課題等について確認していきます。
1.日本のエネルギーが抱え続ける構造的課題
(1)日本におけるエネルギー価格の高騰
①日本のエネルギー供給構造
四方を海に囲まれており、エネルギー資源に乏しい日本では、過去から現在に至るまで、一次エネルギーの大半を海外から輸入する化石エネルギーに頼ってきました。再エネの導入拡大や原子力の再稼働といった取組を進めているものの、2022年度のエネルギー自給率は、わずか12.6%に留まっています(第122-1-1)。
【第122-1-1】一次エネルギー国内供給の構成及びエネルギー自給率の推移
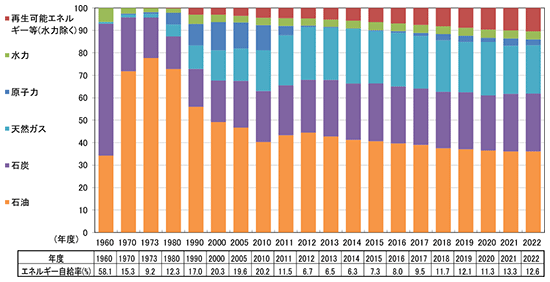
(注1)IEAは原子力を国産エネルギーとしている。
(注2)エネルギー自給率(%)=国内産出/一次エネルギー供給×100。
(注3)端数処理(四捨五入)の関係で、グラフ内の構成比の合計が100%とならないこと等がある(以下同様)。
【第122-1-1】一次エネルギー国内供給の構成及びエネルギー自給率の推移(ppt/pptx形式:147KB)
- 資料:
- 1989年度以前のデータはIEA「World Energy Balances 2023 Edition」、1990年度以降のデータは資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に経済産業省作成
②世界的なエネルギー価格の高騰・高止まり
国際情勢の変化等に伴い、エネルギーを巡る不確実性が一層高まる中、エネルギーの大半を海外から輸入する化石エネルギーに頼っている日本も、様々な影響を受けることとなっています。その1つが、価格面への影響です。
前節にも記載のとおり、世界の化石エネルギーの価格は、2021年頃から上昇傾向となっていましたが、2022年2月に発生したロシアによるウクライナ侵略の影響を受け、さらに急騰しました。その後の化石エネルギーの価格は下落傾向へと転じましたが、2010年代後半の価格水準と比べると、依然としてその水準は高いままの状態が続いています。例えば、アジアのLNGスポット価格であるJKMについては、2019年の平均価格が5ドル/MMBtu程度の水準であった一方、2023年の平均価格は、その3倍近い14ドル/MMBtu程度の水準となりました。石炭に関しても、豪州産一般炭の価格は、2019年の平均が78ドル/トン程度の水準であった一方、2023年の平均は、その2倍以上となる173ドル/トン程度の水準となりました(第121-1-7参照、第121-1-8参照、第121-1-9参照)。
③円安方向への為替の変動
さらに、日本では、こうした化石エネルギー価格の高騰・高止まりに加えて、特に2022年以降、為替変動による影響も強く受けています。2021年に1ドル110円前後の水準で推移していた為替レートは、その後、日本と米国の金利差等の影響を受けて円安の傾向が強まり、2022年10月から2024年3月に至るまで、たびたび一時1ドル150円の水準にまで達しました。日本が海外から化石エネルギーを調達する際、こうした円安方面への為替変動は、円建ての輸入金額の増加につながることとなります(第122-1-2)。
【第122-1-2】ドル・円の為替レートの推移(長期・短期)
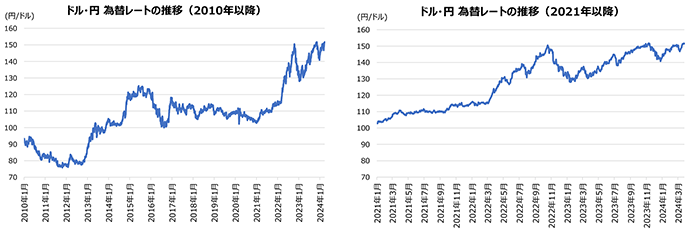
【第122-1-2】ドル・円の為替レートの推移(長期・短期)(ppt/pptx形式:94KB)
- 資料:
- 日本銀行「時系列統計データ(東京市場ドル・円 スポット 17時時点)」を基に経済産業省作成
④日本のエネルギー輸入金額への影響
近年の世界的な化石エネルギー価格の高騰・高止まりや、円安の進展等が、日本にどのような影響を与えたのかについて、日本の貿易統計のデータから確認していきます。これまでも、日本では、多くの化石エネルギーを輸入してきたため、多くの国富が海外へと流出していましたが、今回の化石エネルギー価格の高騰や円安等の影響によって、さらに多額の国富が流出することとなりました。2020年から2022年にかけてのデータを見ると、化石エネルギーの輸入量については、あまり大きな変化が見られない一方で、化石エネルギーの輸入金額については、2020年の11.3兆円から、2022年には33.7兆円へと、約3倍(2020年比で22.4兆円の増加)に急増していることがわかります。この2022年の輸入金額は、原油価格が1バレル100ドルを超えていた2010年代前半の水準と比較しても、5兆円以上多い金額となっています。その後、化石エネルギーの価格が2022年の水準から相対的に低下した2023年においては、化石エネルギーの輸入金額も27.3兆円へと減少しましたが、2020年の輸入金額と比較すると、なおも2.4倍の水準となっています(第122-1-3)。
【第122-1-3】日本の化石エネルギーの輸入金額・輸入量の推移
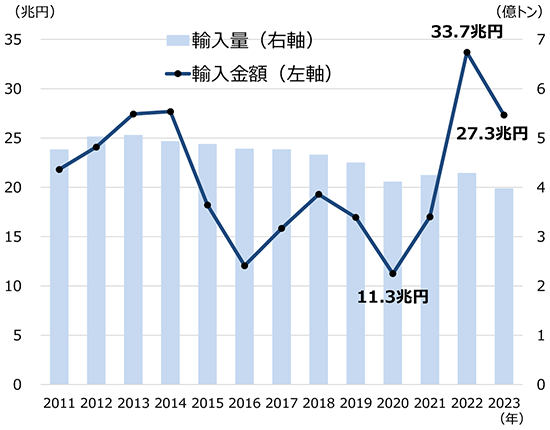
(注)数値は、「石炭及びコークス及び練炭」、「石油及び石油製品」、「天然ガス及び製造ガス」の合計値。
【第122-1-3】日本の化石エネルギーの輸入金額・輸入量の推移(ppt/pptx形式:55KB)
- 資料:
- 財務省「貿易統計」を基に経済産業省作成
日本の化石エネルギーの輸入金額の急増は、日本全体の貿易収支にも大きな影響を与えています。2020年に0.4兆円の黒字を記録した日本の貿易収支は、2021年に赤字となり、2022年には過去最大の赤字(20.3兆円)を記録することとなりましたが、その主要因は、化石エネルギーの輸入金額の増加でした。2022年と比べ、化石エネルギーの輸入金額が減少した2023年についても、依然として、化石エネルギーが日本の貿易赤字の主要因となっています(第122-1-4)。
【第122-1-4】日本の貿易収支の推移
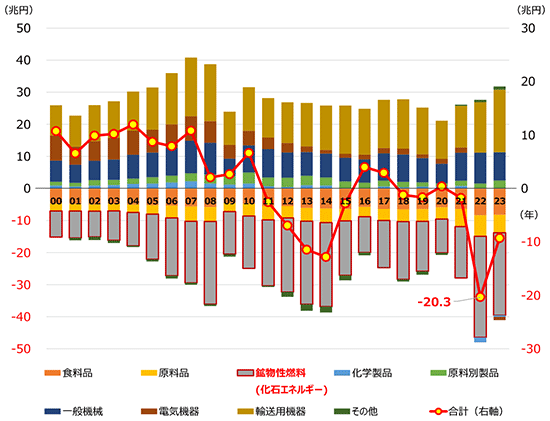
(注)「鉱物性燃料」は、「石炭及びコークス及び練炭」、「石油及び石油製品」、「天然ガス及び製造ガス」の合計値であり、化石エネルギーに相当する。
【第122-1-4】日本の貿易収支の推移(ppt/pptx形式:62KB)
- 資料:
- 財務省「貿易統計」を基に経済産業省作成
(2)エネルギー価格高騰への対応
日本における化石エネルギーの輸入金額の増加は、国富の流出や貿易収支の悪化を招くだけでなく、化石エネルギーを燃料・原料としている電気やガス、ガソリン等の価格上昇、ひいては、あらゆる財やサービスの価格上昇につながることとなります。日常生活や企業活動に欠かすことのできない電気やガス、ガソリン等の価格が上がってしまうことは、当然のことながら、家庭や企業等にとって大きな負担となります。こうした中、日本では、エネルギー価格の高騰の影響を受ける家庭や企業等の負担を軽減するための措置を講じてきました。
①燃料油価格激変緩和対策事業
政府では、燃料油(ガソリン・軽油・灯油・重油・航空機燃料)の卸売価格の抑制のための措置を講じることで、小売価格の急騰を抑制し、家庭や企業等の消費者の負担を低減することを目的に、2022年1月より、「燃料油価格激変緩和対策事業」を実施しました。この事業は、全国平均ガソリン小売価格が一定額以上となった場合に、政府が石油精製業者や石油輸入業者に対し、価格上昇を抑えるための原資を支給することにより、ガソリン等の卸売価格の上昇を抑え、ひいては小売価格の急騰を抑えるものです(第122-1-5)。
【第122-1-5】燃料油価格激変緩和対策事業のスキーム
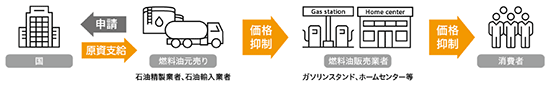
【第122-1-5】燃料油価格激変緩和対策事業のスキーム(ppt/pptx形式:83KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
本事業は、新型コロナ禍からの経済回復や一部の産油国における生産停滞等により、世界的に石油の需給がタイトになったこと等を背景としたガソリン価格の上昇を受け、2022年1月より原資の支給を開始しました。事業開始当初は、レギュラーガソリンの全国平均価格が170円を超えた際に発動し、対象の油種についてはガソリン・軽油・灯油・重油の4種類、補助の上限額については1リットル当たり5円としていました。しかし、同年2月にロシアによるウクライナ侵略が発生し、地政学的な変化が、世界の原油価格や需給動向に大きな影響を与える可能性が生じたこと、さらに、その後の長引く原油価格の高騰や乱高下が、新型コロナ禍からの経済回復や国民生活へ悪影響を与えることを防ぐ観点から、同年中には、補助を拡大させる方向に事業内容を見直すとともに、対象油種に航空機燃料も追加し、燃料油の急激な価格上昇を抑制しました。
2023年1月以降は、段階的に補助の枠組みを縮減しながら、引き続き措置を講じていましたが、同年夏頃からは、世界的な原油価格の上昇や為替動向の影響も重なって、レギュラーガソリンの全国平均価格が上昇し、過去最高額12を記録することとなりました。こうした状況を踏まえて、同年9月からは、補助額や補助率を見直した新たな激変緩和措置を講じており、同年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」では、「緊迫化する国際情勢及び原油価格の動向など経済やエネルギーをめぐる情勢等を見極め、柔軟かつ機動的に運用しつつ、措置を2024年4月末まで講ずる」こととされました。その後、中東情勢の緊迫化等を背景とした今後の価格高騰リスクや様々な経済情勢を見極めるため、2024年4月末までとしていた激変緩和措置を一定期間延長することとしました(第122-1-6)。
【第122-1-6】燃料油価格激変緩和対策事業の推移
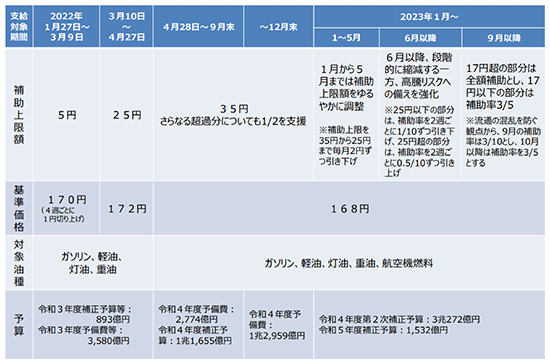
【第122-1-6】燃料油価格激変緩和対策事業の推移(ppt/pptx形式:271KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
レギュラーガソリンの全国平均価格の推移を、仮に本事業による措置がなかった場合の価格の推移と比較することで、本事業による効果を確認することができます。本事業による措置がなかった場合には、2022年4月〜11月や2023年9月〜11月のレギュラーガソリンの全国平均価格が、1リットル当たり200円を大きく超えていたことがわかります(第122-1-7)。
【第122-1-7】レギュラーガソリンの全国平均価格の推移
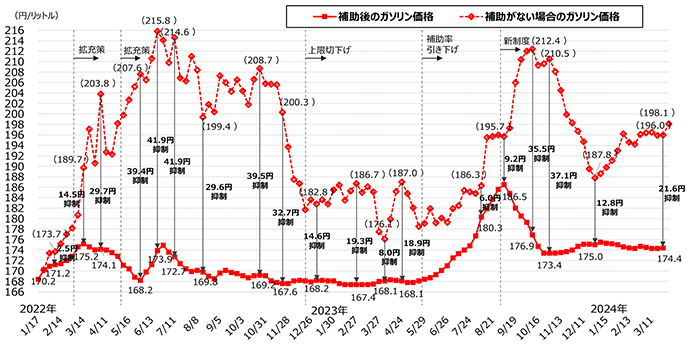
【第122-1-7】レギュラーガソリンの全国平均価格の推移(ppt/pptx形式:177KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
②電気・ガス価格激変緩和対策事業
政府では、電気・都市ガス料金の値上がりによって影響を受ける家計や企業の負担を軽減することを目的に、小売事業者等を通じて電気・都市ガスの使用量に応じた料金の値引きを行う「電気・ガス価格激変緩和対策事業」を実施しました。
具体的には、2022年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に基づき、2023年1月〜8月使用分まで、電気料金については、低圧契約の家庭等に対して1kWh当たり7円、高圧契約の企業等に対して1kWh当たり3.5円、都市ガス料金については、年間契約量が1,000万㎥未満の家庭や企業等に対して1㎥当たり30円の値引きを実施し、同年9月使用分については、電気の低圧契約は1kWh当たり3.5円、高圧契約は1kWh当たり1.8円、都市ガスは1㎥当たり15円の値引きを実施しました。2023年8月30日には、岸田総理から「物価高に対する経済対策を策定し、実行するまでの間は、9月末まで行うこととしております支援を、その後も継続する」旨の発表がなされ、同年10月〜12月使用分について、同年9月使用分と同じ単価で値引きを実施しました。2023年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」では、本事業における措置について、「2024年春まで継続する。具体的には、国際的な燃料価格の動向等を見極めつつ、現在の措置を2024年4月末まで講じ、同年5月は激変緩和の幅を縮小する」こととされたことを踏まえ、2024年1月〜4月使用分について、2023年9月〜12月使用分と同じ単価で値引きを実施しました。さらに、2024年3月29日には、齋藤経済産業大臣から「LNGや石炭の輸入価格がロシアのウクライナ侵略前と同程度に低下した状況等を踏まえ、措置を5月末まで講じることとし、5月は低圧で1kWhあたり1.8円の支援とする等、幅を縮小します。その上で、予期せぬ国際情勢の変化等により価格急騰が生じ、国民生活への過大な影響を回避するため、緊急対応が必要となった場合には、もちろん迅速かつ機動的に対応」する旨の発表がなされ、同年5月使用分については、電気の低圧契約は1kWh当たり1.8円、高圧契約は1kWh当たり0.9円、都市ガスは1㎥当たり7.5円の値引きを実施しました(第122-1-8)。
【第122-1-8】電気・ガス価格激変緩和対策事業のスキーム
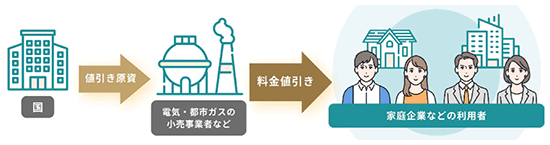
【第122-1-8】電気・ガス価格激変緩和対策事業のスキーム(ppt/pptx形式:288KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
なお、「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の対象となっていない「特別高圧」の電気や「LPガス」については、地方公共団体が地域の実情にあわせて必要な支援をきめ細やかに実施できる「地方創生臨時交付金」において、支援を行いました。
(3)日本のエネルギーが抱え続ける課題
ここまで確認してきた激変緩和対策事業等の効果によって、家庭や企業等における負担を一定程度抑えることができました。他方で、こうした対策は多くの予算によって実施されているという側面もあり、こうした対策を長い期間にわたって実施し続けることは現実的ではありません。今回の対策に措置された予算の合計額を確認すると、2022年1月から発動することとなった「燃料油価格激変緩和対策事業」には、合計で約6.4兆円の予算13が措置されており、また、2023年1月以降の使用分を対象として始まった「電気・ガス価格激変緩和対策事業」には、合計で約3.7兆円の予算14が措置されていることがわかります。
エネルギーの大半を海外に頼り続ける現在のエネルギー供給構造が続く限り、日本はこれからも、今回のようなエネルギー価格の高騰リスクに晒され続けることとなります。また、国際情勢によっては、より一層の価格高騰に陥ってしまうリスクや、さらには、エネルギーの安定供給に大きな支障が出るといったリスクについても、十分に考えられる状況です。こうした状況を克服すべく、今回のようなエネルギーを取り巻く国際情勢の変化にも強い、強靱なエネルギー需給構造への転換を着実に進めていくことが、日本にとって極めて重要であると改めて認識されました。そのためには「GX15」、すなわち、化石エネルギーへの過度な依存から脱却し、クリーンエネルギー中心の産業構造・社会構造への転換を進めていくことが重要です。エネルギーの効率的な利用に向けた徹底した省エネルギー(以下「省エネ」という。)の取組や、再エネのさらなる導入拡大や原子力の最大限の活用等のエネルギー自給率向上に向けた取組等を、一歩一歩、進めていくことが求められています(GXについては次章にて記載)。
COLUMN
化石エネルギーの価格動向と電力会社の収支動向
前述のとおり、世界の化石エネルギーの価格は、2021年頃から急激に上昇しました。さらに日本では、同じ時期に為替レートが円安方向に推移したことも重なって、化石エネルギーの輸入金額が増加し、ひいては、国内における電気料金等のエネルギー価格の上昇につながることとなりました。本コラムでは、こうした化石エネルギーの価格動向が、日本の電力会社の経営や電気料金の算定にどのような影響を与えるのかについて、確認していきます。
(1)近年の大手電力会社の収支動向
まず、大手電力会社10社について、2019年度以降の四半期ごとの決算データの推移を確認していきます16。本業で稼いだ利益を示す営業利益の推移を見ていくと、激しく乱高下していることがわかります。2021年度の営業利益については、第2四半期までは黒字となっていたものの、第3四半期からは赤字へと転じており、その後、2022年度の第4四半期に黒字転換するまで、赤字が続きました。その後は黒字が続いています(第122-1-9)。
【第122-1-9】大手電力会社10社合計の営業利益の推移
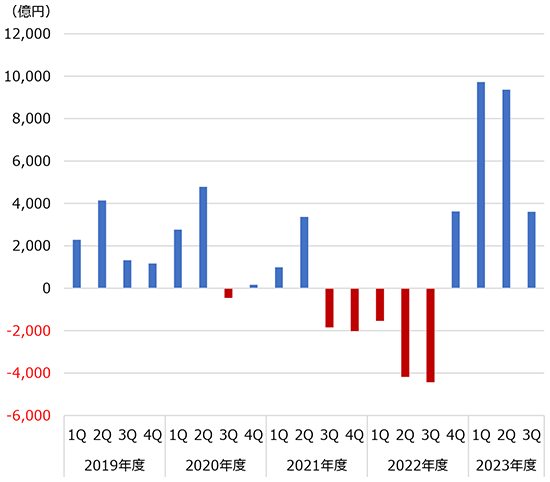
(注)数値は大手電力会社10社における営業利益の合計額。
【第122-1-9】大手電力会社10社合計の営業利益の推移(ppt/pptx形式:49KB)
- 資料:
- SPEEDAを基に経済産業省作成
こうした短期間における変動には様々な要因が存在していますが、中でも大きな要因の1つとなっているのが、電力会社にとっての主な収入源である電気料金の算定方法です。次項以降、このことについて確認していきます。
(2)電気料金の内訳
一般的に、家庭等が毎月支払う電気料金17は、アンペア数等に応じた「基本料金」に、毎月の使用電力量(kWh)に応じた「従量料金」を加算することで算出されます。
従量料金には、「電力量料金」と「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」があり、これらは、それぞれの単価に対して毎月の使用電力量を乗じることで算出されています。このうち、電力量料金の単価については、火力発電の燃料である原油・LNG・石炭の価格変動に伴って、毎月自動的に変動することになっています(後述の「燃料費調整制度」)。また、再エネ賦課金単価については、各年度の開始前に所定の算定方法に則って算出されることとなっており、例えば2023年度の単価は1kWh当たり1.40円でした(第122-1-10)。
【第122-1-10】電気料金の内訳
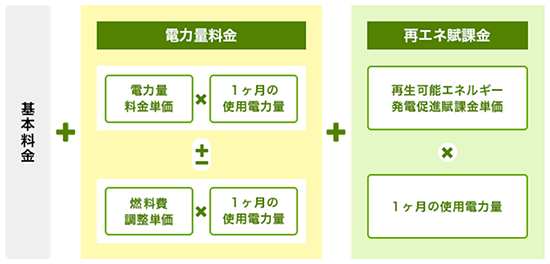
【第122-1-10】電気料金の内訳(ppt/pptx形式:78KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
(3)燃料費調整制度
燃料費調整制度18とは、火力発電の燃料である原油・LNG・石炭の価格(為替も反映した円建ての日本着ベースの価格)の変動に応じて、電力量料金単価を毎月自動で調整する仕組みです。この制度により、燃料価格が上がると電気料金も自動的に上がり、燃料価格が下がると電気料金も自動的に下がることとなります。電力会社が毎月プレスリリースを行い、時にはニュース等で報道されることもある毎月の電気料金の「値上がり」や「値下がり」については、基本的にこの燃料費調整制度による自動調整の結果です。
具体的には、各社の火力発電における燃料構成比等を加味してあらかじめ定められた「基準燃料価格19」と、各月の3〜5か月前における実際の燃料価格に基づいた「実績燃料価格20」の差を、燃料費調整単価に換算し、月々の電気料金に反映しています。例えば、1月〜3月における燃料価格の変動は、同年6月分の電気料金に自動で反映され、2月〜4月における燃料価格の変動は、同年7月分の電気料金に自動で反映されることになります。このように、燃料費調整制度においては、燃料価格の変動が実際の電気料金へと反映されるまでに、数か月程度のタイムラグが発生することになります(第122-1-11)。
【第122-1-11】燃料費調整制度のイメージ
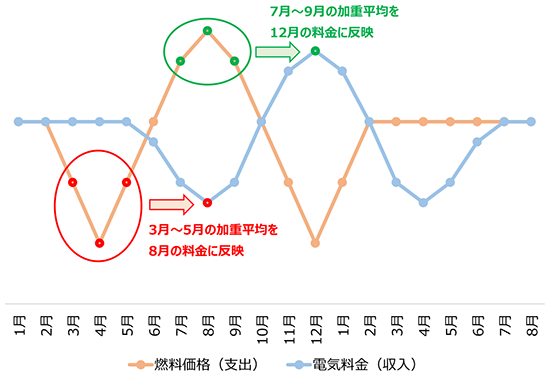
【第122-1-11】燃料費調整制度のイメージ(ppt/pptx形式:55KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
なお、燃料費調整制度は、大手電力会社(みなし小売電気事業者)の規制料金(経過措置料金)に設定が義務づけられています。さらに、燃料価格が大幅に上昇した際の需要家への影響を緩和する目的で、調整可能な料金の幅に上限を設けており21、基準燃料価格の1.5倍までしか反映されない仕組みとしています22(第122-1-12)。
【第122-1-12】燃料費調整制度における上限到達時のイメージ
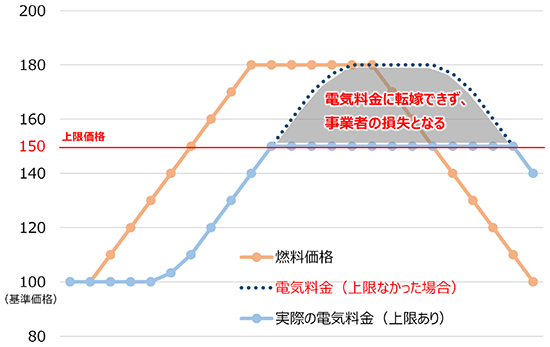
【第122-1-12】燃料費調整制度における上限到達時のイメージ(ppt/pptx形式:205KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
(4)電力会社の決算における燃料費調整制度の影響
前項のとおり、燃料費調整制度では、燃料価格の変動が実際の電気料金へと反映されるまでに、数か月程度のタイムラグが発生しますが、このタイムラグが、電力会社の決算に大きな影響を及ぼすことになります。
例えば、燃料価格が上昇した場合、電力会社にとっての支出が増加することになりますが、電力会社にとっての収入である電気料金へ反映される(燃料費調整制度による自動反映(値上がり))のは、その数か月先のこととなります。このように、燃料費調整制度では、支出が変動するタイミングと収入が変動するタイミングがずれることになりますが、このタイミングのずれのことを、一般的に「期ずれ」と呼んでいます。そのため、燃料価格が上昇傾向にある期間を切り取って、電力会社の収支を確認すると、当該期間中においては支出が収入を上回ることから、この期ずれの影響による損失(差損)が多くなってしまいます(第122-1-13のパターン①)。逆に、燃料価格の下落期においては、期ずれによる利益(差益)が多くなります(第122-1-13のパターン②)。
【第122-1-13】燃料費調整制度による期ずれのイメージ
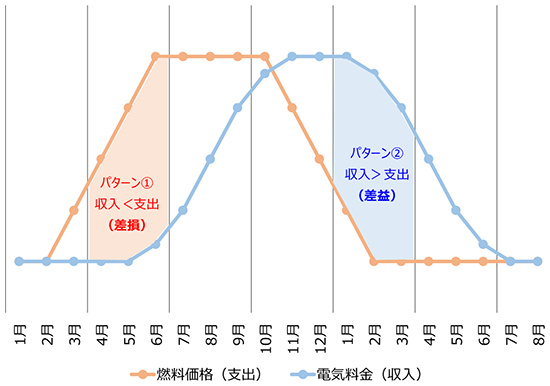
【第122-1-13】燃料費調整制度による期ずれのイメージ(ppt/pptx形式:54KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
通常、燃料費調整制度においては、実績燃料価格の上昇幅が基準燃料価格の1.5倍までに収まっている限り、長い期間で見れば、収入と支出は一致していくことになります(第122-1-14)。しかし、特に対象期間の短い四半期決算においては、燃料費調整制度による期ずれの影響(差益・差損)が強く表れる傾向にあります。本コラムの冒頭で確認したとおり、電力会社の四半期ごとの営業利益は近年大きく変動していますが、燃料価格が大きく上昇することになった2021年から2022年にかけては期ずれによる差損が、燃料価格が下落傾向に転じた2023年からは期ずれによる差益が、それぞれ大きく影響したものと考えられます。
【第122-1-14】燃料費調整制度による収入と支出の一致のイメージ
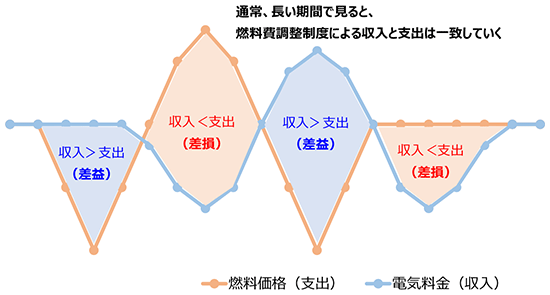
【第122-1-14】燃料費調整制度による収入と支出の一致のイメージ(ppt/pptx形式:54KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
また、2022年以降の電力会社の収支悪化に関しては、この「期ずれによる差損」以外にも、燃料費調整制度による大きな要因がありました。
前述のとおり、規制料金における燃料費調整制度には、燃料価格が大幅に上昇した際の需要家への影響を緩和する目的で、調整可能な料金の幅に上限(基準燃料価格の1.5倍)を設けており、その上限を超える分については、電気料金に反映されない仕組みとしています。そうした中、2021年から高騰を始めた燃料価格は、2022年に、規制料金を有する10社全てにおいて、この上限に到達することとなりました。そして、上限を超過した分の費用については、電気料金に反映することができないことから、電力会社が負担(赤字供給)することとなり、このことが、電力会社の損失を増やす大きな要因となりました23(第122-1-15)。
【第122-1-15】規制料金の推移(400kWh/月の一般家庭の場合)
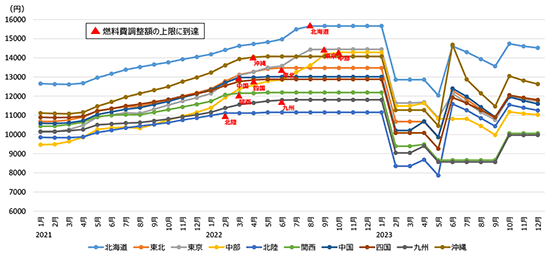
(注1)2023年2月の値下げは、「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の開始によるもの。
(注2)2023年4月の東京・中部・北陸・関西・中国・九州の値上げは、託送料金の値上げによるもの。
(注3)2023年5月の値下げは、再エネ賦課金単価の見直し(3.45円/kWh→1.40円/kWh)によるもの。
(注4)2023年6月の北海道・東北・東京・北陸・四国・中国・沖縄の値上げは、後述する規制料金の改定によるもの。
(注5)2023年10月の値上げは、「電気・ガス価格激変緩和対策事業」における値引き単価の変更(7.0円/kWh→3.5円/kWh)によるもの。
【第122-1-15】規制料金の推移(400kWh/月の一般家庭の場合)(ppt/pptx形式:90KB)
- 資料:
- 財務省「貿易統計」等を基に経済産業省試算
(5)2023年6月の規制料金の改定(値上げ)
実績燃料価格が、燃料費調整制度における上限に到達し、電力会社が「赤字供給」を続けることは、電力会社の財務状況の悪化へとつながります。電力会社の財務状況が悪化することは、発電設備等の修繕やリプレースを含む各種投資の減少等にもつながりかねず、最終的には、電力の安定供給にも悪影響を及ぼす可能性があります。こうした状況の中、2022年11月から2023年1月にかけて、規制料金を有する電力会社7社24が、規制料金の改定の認可申請を行いました。
この認可申請に対しては、電力・ガス取引監視等委員会が、中立的・客観的・専門的な観点から厳格で丁寧な審査25を行い、2023年5月に、当初の認可申請の内容から値上げ幅を圧縮26した形で、規制料金の改定を認可しました(同年6月より適用)。改定を行った7社のうち6社の規制料金においては、「電気・ガス価格激変緩和対策事業」等の効果もあり、改定後の電気料金(2023年7月請求分)の水準が、認可申請前の水準(2022年11月請求分)よりも安価になりました(第122-1-15参照)。また、改定を行った7社の規制料金では、燃料費調整制度における基準燃料価格の水準が上がったことに伴い、その1.5倍となる「上限」の水準も上がったため、足元における燃料価格では、上限に到達することがなくなりました27。
電力会社の収支動向は、様々な要素によって左右されますが、その中でも、燃料価格の動向、そして、燃料費調整制度の仕組みによって大きな影響を受ける傾向にあります。電力会社の決算等を確認・評価する際には、燃料費調整制度の仕組みについて理解した上で、直近の燃料価格の動向等も確認しつつ、「期ずれ」による影響等がどの程度含まれているのか、「期ずれ」がなければどうだったのか、中長期的な電力の安定供給に与える影響がないか等の視点を持つことが重要といえます。
2.エネルギー安全保障における新たな課題と対応
(1)エネルギー安全保障を巡る新たな課題
2022年2月から始まったロシアによるウクライナ侵略や、2023年10月からのイスラエル・パレスチナ情勢の悪化等、世界の情勢はより一層緊迫感の増す方向へと変化を続けており、世界は「分断」や「対立」の様相を深めているといっても過言ではありません。また、エネルギーに関しては、化石エネルギーからクリーンエネルギーへの移行等、カーボンニュートラルの実現に向けた様々な取組が世界中で加速しています。さらには、GXの進展に加えて、生成AIの普及をはじめとした「DX28」の進展によるデータ処理量の増大に伴い、今後の電力需要が増加する可能性についての指摘もある状況です。未来のことを全て予測することはできませんが、例えば、2024年1月に電力広域的運営推進機関が公表した今後10年の電力需要の想定では、人口減少や節電・省エネ等により家庭部門の電力需要は減少することが予測されていますが、データセンターや半導体工場の新増設等により、産業部門の電力需要については大幅な増加が予測されています。この結果、前回(1年前)の同機関の想定では電力需要の減少が予測されていた一方、今回の想定では、全体として電力需要が増加していくと予測されています(第122-2-1)。
【第122-2-1】DXの進展による電力需要増大
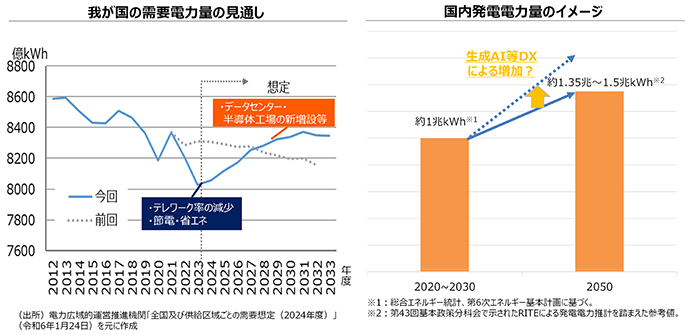
【第122-2-1】DXの進展による電力需要増大(ppt/pptx形式:111KB)
- 資料:
- 「第11回GX実行会議 資料1」より抜粋
こうした様々な情勢の変化は、エネルギーを取り巻く環境にも大きく影響を与えており、いわば「エネルギー安全保障」を毀損しうるリスクの多角化にもつながっていると考えられます。
過去からエネルギーの大半を海外から輸入する化石エネルギーに頼ってきた日本では、特に半世紀前に発生した第一次オイルショック以来、エネルギー安全保障を確保していくため、エネルギー利用効率の改善に向けた省エネの推進に加え、エネルギー源の多角化や調達先の多角化等の取組を推進してきました。こうした取組を進めていくことは、今後においても極めて重要です。しかし、世界情勢が様々な面において変化していく中、日本がこれからもエネルギー安全保障を確保し続けていくためには、官民の連携の下、サプライチェーン全体の観点から、新しい様々なリスクを想定及び把握すること、そして、それらを踏まえた制度設計や新たな投資等を積極的に進めていくことが求められています。
次項では、2021年10月に閣議決定された第6次エネルギー基本計画において、「現状において安定供給性や経済性に優れた重要なエネルギー源である」とされている「石炭」をテーマに、取り巻く環境の変化や新たに生じつつあるリスク等について確認を行っていきます。
(2)「石炭」のセキュリティを巡る課題と対応
①石炭というエネルギー
石炭は、2022年度において、日本の一次エネルギー供給の25.7%を占めるエネルギーであり、電源構成に占める石炭火力の割合についても30.8%と、高いシェアを占めています。このように、石炭は現在の日本を支えている重要なエネルギー源となっています(第122-1-1参照、第214-1-6参照)。
また、世界全体で見ても、同様の傾向が確認できます。石炭は、2022年における世界全体のエネルギー消費の26.7%を占めており、石炭火力による発電は、2021年における世界全体の発電電力量の36.1%を占めています(第221-1-3参照、第223-1-6参照)。
このように、現在の日本及び世界のエネルギーを支えているといっても過言ではない石炭は、その用途から、一般炭と原料炭の2つに分類されます。一般炭は発電用の燃料のほか、ボイラー用途やセメント製造用途、化学工業用途といった産業用途としても用いられており、原料炭は主に製鉄用のコークス原料として用いられています。また、石炭は、石炭の根源植物が石炭に変質する過程である石炭化作用の進行度合い(石炭化度)に応じて、無煙炭、瀝青炭、亜瀝青炭、褐炭、亜炭、泥炭に分類されます29。一般的に、石炭化度が比較的高い無煙炭及び瀝青炭は高品位炭と呼ばれ、亜瀝青炭や褐炭等は低品位炭と呼ばれています。なお、日本では、主に高品位炭を消費しています。
さらに、石炭には、他の化石エネルギーと比べると、可採年数が長く、賦存地域も分散しているという特徴があります。日本が化石エネルギーを海外から輸入するに当たって、石炭は、中東依存度が極めて低いこともあり、調達に係る地政学的リスクが相対的に低いともいえます。加えて、熱量当たりの価格についても、他の化石エネルギーより低い水準で推移してきました(第222-1-31参照、第222-1-41参照)。
他方で、石炭には、燃焼時のCO2排出が化石エネルギーの中で最も多いという特徴もあります。気候変動問題への関心が世界的に高まり、各国がカーボンニュートラルの実現に向けた取組を加速させていく中、こうした特徴から、石炭火力の廃止等の方針を掲げる国も増えつつあります。
次項以降、このような様々な特徴を有している石炭について、その需給や貿易の動向、石炭を取り巻く環境変化等について概観していきます。
②世界の石炭生産と輸出の動向
まず、世界の石炭生産について見ていきます。2022年における世界の石炭生産は、過去最高となる約86億トンとなりましたが、それを国別に見ると、その半分以上を中国による生産が占めています。次いで、インド、インドネシア、米国、豪州等による生産が多くなっています(第122-2-2、第222-1-32参照)。
【第122-2-2】世界の石炭生産(2022年)
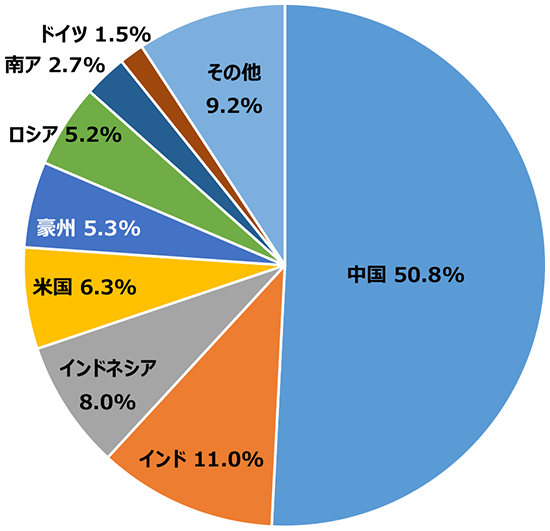
【第122-2-2】世界の石炭生産(2022年)(ppt/pptx形式:47KB)
- 資料:
- IEA「Coal Information 2023」を基に経済産業省作成
また、石炭には、その多くが生産国の中で消費され、他国に輸出される割合が小さいという特徴もあります。例えば、世界の半分以上の石炭を生産している中国や、それに次ぐ世界第2位のインドにおいて生産される石炭は、ほぼ全量が自国内で消費されており、中国やインドから他国へ輸出される石炭は、極めて少なくなっています。前述のとおり、2022年における世界全体の石炭生産は約86億トンですが、同年に他国へ輸出された石炭は世界全体で約14億トンであり、その割合はわずか16%ほどとなっています。なお、中国とインドについては、自国産の石炭を消費しているだけでなく、他国からの石炭輸入においても世界第1位と第2位を占めており、石炭市場において極めて大きな影響力を有しているといえます(第122-2-3、第222-1-36参照、第222-1-37参照)。
【第122-2-3】世界の主要な石炭生産国における自国での消費及び他国への輸出(2022年)
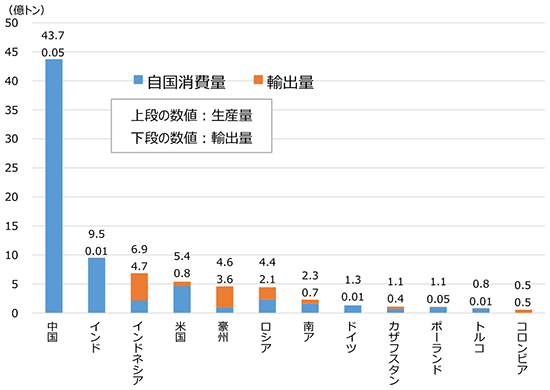
(注)「自国消費量」は「生産量」から「輸出量」を引いて算出している。
【第122-2-3】世界の主要な石炭生産国における自国での消費及び他国への輸出(2022年)(ppt/pptx形式:50KB)
- 資料:
- IEA「Coal Information 2023」を基に経済産業省作成
世界のエネルギーを支えている石炭ですが、こうした背景から、石炭の主要な輸出国は、石炭生産に比して国内での石炭消費の少ないインドネシアや米国、豪州、ロシア、南アフリカ等の国々に限られています。日本では、国内で消費する石炭のほぼ全量を海外からの輸入に頼っていますが、その輸入元についても、豪州やインドネシア等、こうした国々が大半を占めています(第213-1-21参照)。
なお、それぞれの国において生産される石炭は、その種類に違いがある(低品位炭の生産が多い一方、高品位炭の生産が極めて少ない等)ため、例えば、「高品位の一般炭」を調達したい場合には、調達先の選択肢がさらに限られていくことになります。
③世界の石炭消費の動向
次に、世界全体の石炭消費の動向を見ていきます。世界全体の石炭消費は、主要な石炭生産国である中国やインドにおける発電用途での消費を中心に、近年に至るまで増加傾向にあり、2022年には過去最高を記録しています。また、急速に経済成長を遂げているASEAN諸国においても、経済成長に伴う電力需要の急増に対し、主に石炭火力による発電を増やすことで対応してきたため、石炭消費が増加の一途を辿っています。その一方で、欧米諸国においては、CO2排出削減対策の進展等に伴い、石炭消費は減少傾向にあります。2023年12月にIEAが発表したレポートから、今後の石炭消費の見通しを確認すると、2026年にかけて、世界全体の石炭消費は概ね横ばいとなっていることがわかります。今後も経済成長が見込まれるインドネシアやベトナム等を中心としたASEAN諸国やインドでは、電力需要の拡大等に伴い、石炭消費の増加が予測されており、最大の石炭消費国である中国における消費も、横ばいで推移することが見込まれています(第122-2-4、第122-2-5、第122-2-6)。
【第122-2-4】世界の石炭消費の推移と見通し
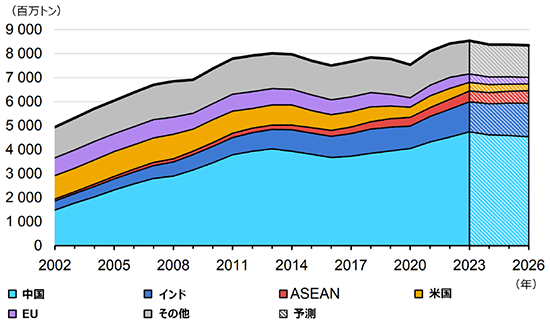
(注)2022年のデータは速報値、2023年のデータは推計値。
【第122-2-4】世界の石炭消費の推移と見通し(ppt/pptx形式:307KB)
- 資料:
- IEA「Coal 2023」を基に経済産業省作成
【第122-2-5】ASEAN諸国の発電電力量の推移
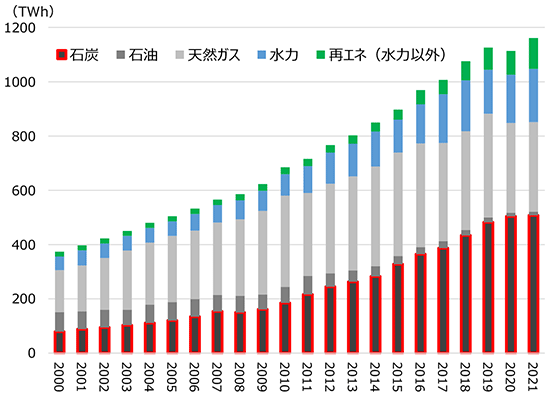
【第122-2-5】ASEAN諸国の発電電力量の推移(ppt/pptx形式:55KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023」を基に経済産業省作成
【第122-2-6】ASEAN諸国における石炭消費
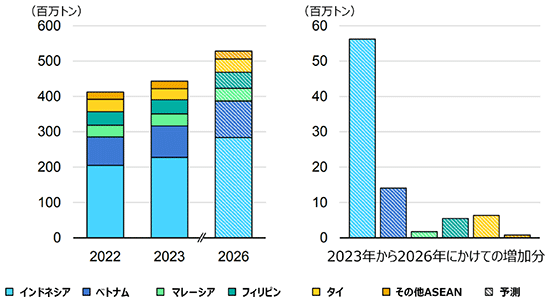
【第122-2-6】ASEAN諸国における石炭消費(ppt/pptx形式:203KB)
- 資料:
- IEA「Coal 2023」を基に経済産業省作成
④石炭を巡る新たなリスク等
前節でも確認したとおり、2022年2月に発生したロシアによるウクライナ侵略等の影響を受け、他の化石エネルギーと同様に、石炭の価格も高騰を経験してきました(第121-1-9参照)。また、世界的に気候変動対策のさらなる強化が求められていますが、このことは、石炭関連事業を取り巻く環境に大きな変化をもたらしています。本項では、石炭を巡るこうした変化に伴う新たなリスクや影響等について確認していきます。
(ア)石炭大国である中国の動向
石炭を含む化石エネルギーの価格は、2021年半ば頃から上昇傾向となりましたが、こうした状況に対して、石炭の生産及び消費において世界第1位の中国は、国内での石炭生産を大きく増加させる対応を取りました。石炭価格がさらに高騰することとなった2022年に入ってからは、国内での石炭生産を増加させたこともあり、特に一般炭の輸入を大きく減らしました。その後、石炭価格は下落傾向へと転じましたが、こうした状況の中で中国は、国内における石炭生産をさらに増やすとともに、一般炭の輸入を一転して大きく増やす対応を取りました。この結果、2023年における中国の石炭輸入量は、過去最高を記録しました30。中国の石炭調達の方針に影響を与える要素として、国内における石炭需要の動向等、様々なことが考えられますが、今回の中国の動きからは、国際的な石炭価格の動向によっても、国内での石炭生産量と他国からの石炭輸入量を臨機応変に調整しうる、ということが改めて確認できたといえます(第122-2-7、第122-2-8)。
【第122-2-7】中国における石炭生産の推移
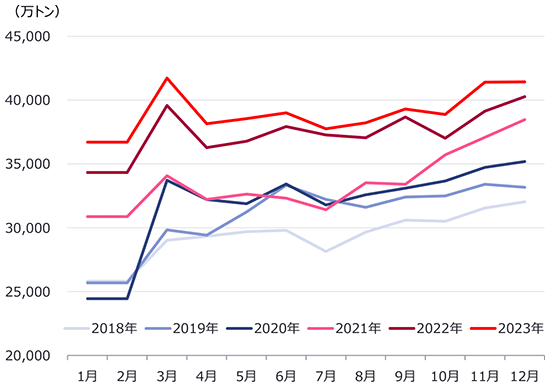
(注1)中国国家統計局が公表している石炭生産に係るデータには、一般炭・原料炭等の分類がない。
(注2)中国国家統計局は、1月と2月の石炭生産に係るデータを毎年合算して公表しているため、本表における1月及び2月のデータには、その合算値の半分の数値を記載している。
【第122-2-7】中国における石炭生産の推移(ppt/pptx形式:52KB)
- 資料:
- 中国国家統計局公表資料を基にエネルギー経済社会研究所作成
【第122-2-8】中国の石炭輸入の推移
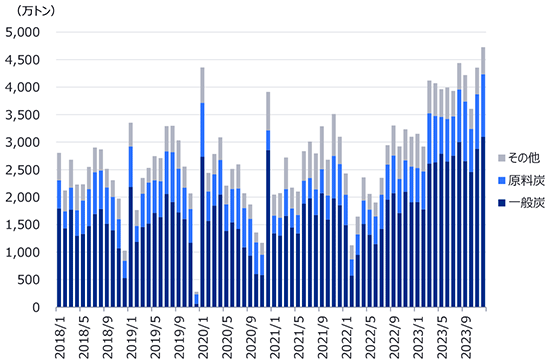
【第122-2-8】中国の石炭輸入の推移(ppt/pptx形式:58KB)
- 資料:
- 中国海関総署公表資料を基にエネルギー経済社会研究所作成
前節で紹介したIEAによる今後の化石エネルギーの価格見通しにおいては、気候変動対策が世界的に進展することで、石炭需要が中長期的に減少すると見込まれることから、石炭の価格は下落していくと予測されています。しかし、石炭価格が低い水準となった場合には、今回のように、中国が石炭輸入を大きく増やすということも考えられます。世界の石炭市場における中国の影響力が圧倒的に大きい中、このことは、中国が今後の石炭価格の下支えとなる可能性を示唆しています。
なお、中国では、国内で大量に生産される低品位炭が主に消費されているため、輸入においても低品位炭の輸入が主流となっていますが、2023年以降は、高品位炭の輸入が増えていることも確認できます31。前述のとおり、日本は主に高品位炭を調達・消費していますが、今後の中国における高品位炭の輸入動向によっては、日本の高品位炭の調達にも影響が生じうると考えられるため、こうした観点からも、中国の動向を注視していく必要があります(第122-2-9)。
【第122-2-9】中国の一般炭輸入の推移
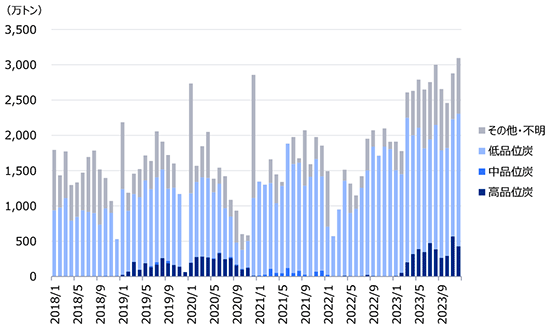
【第122-2-9】中国の一般炭輸入の推移(ppt/pptx形式:57KB)
- 資料:
- 中国海関総署公表資料、Kplerを基にエネルギー経済社会研究所推計
(イ)石炭関連事業からのダイベストメント等の動向
ここまで見てきたように、近年においても石炭消費が増加傾向にある中国やインド、ASEAN諸国等では、今後も石炭消費が一定程度継続又は増加することが見込まれています。しかしその一方で、気候変動対策の観点から、石炭関連事業からのダイベストメント(投融資の撤退)の動きも世界的に進んでいます。先進国を中心に、「原則として一般炭の新規採掘事業や拡張事業へのファイナンスを提供しない」といった方針を掲げる金融機関が増加する等、石炭関連事業(特に主として発電用・産業用燃料として用いられる一般炭関連事業)を取り巻く環境は、一層厳しさを増しています。
主に高品位炭を消費している日本では、輸入する石炭の多くを豪州産の高品位炭に長らく依存してきましたが、その豪州においても、新規の高品位炭開発のための上流投資が減少傾向にあります。また、石炭事業を縮小させる企業や石炭事業から撤退する企業も登場し、その結果、特定の企業による寡占化が進行しています。加えて、石炭事業に関する豪州国内における環境規制の強化や、豪州から中国への石炭輸出の増加(高品位炭の輸出を含む)等の変化も生じています。今後も、炭鉱の閉鎖(生産量・輸出量の減少)を含め、様々な変化が起きることが考えられます。石炭を豪州からの輸入に頼ってきた日本ですが、中長期的には、石炭(特に高品位の一般炭)の安定的な確保が難しくなっていく可能性があることを、認識しておく必要があると考えられます(第122-2-10)。
【第122-2-10】豪州における石炭を取り巻く状況
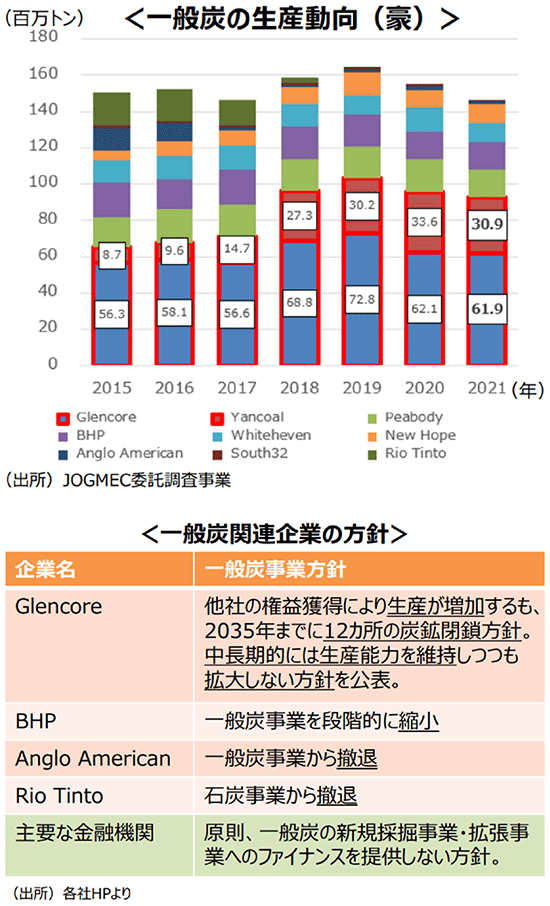
【第122-2-10】豪州における石炭を取り巻く状況(ppt/pptx形式:289KB)
- 資料:
- 資源エネルギー庁「GXを見据えた資源外交の指針」より抜粋
また、気候変動対策の進展は、石炭のサプライチェーンのうち、上流開発や生産を取り巻く環境を厳しいものにしているだけではなく、石炭の消費、特に石炭火力発電を取り巻く環境にも大きな影響を与えています。先進国を中心に、CO2の排出削減対策の一環として、発電時におけるCO2排出の多い石炭火力発電を廃止していく方針を掲げる国が増加しており、2023年5月に広島で開催されたG7サミットにおいて採択された首脳コミュニケでも、「国内の排出削減対策が講じられていない石炭火力発電のフェーズアウトを加速するという目標に向けた、具体的かつ適時の取組を重点的に行うというコミットメントを再確認し、他の国に対して我々に加わるよう要請する」ことが明記されました。こうしたトレンドは今後も加速していくことが想定される中、日本においても、電力の安定供給を大前提に、電源構成における石炭火力発電の比率を引き下げていくとともに、後述のとおり、脱炭素型の火力発電への置き換えに向けて取り組んでいく必要があります。
⑤石炭を巡る環境変化への日本の対応
現在の日本は、エネルギーの多くを石炭に頼っています。特に電力の分野においては、太陽光発電や風力発電といった出力変動の大きい再エネの導入量が増加している中、石炭火力を含む火力発電が、供給力や調整力といった面で、日本の電力の安定供給において極めて重要な役割を果たしている状況です。しかし、前述のとおり、世界の石炭を取り巻く環境には様々な変化が生じており、日本のエネルギー安全保障に関しても、新たなリスクが表出しつつある状況となっています。
その1つが、石炭の安定的な確保に係るリスクです。世界の石炭市場において極めて大きな影響力を有する中国の動向(高品位炭の調達動向等)に加え、主要な石炭輸出国である豪州等において、石炭からのダイベストメントや環境規制が炭鉱開発及び石炭供給に与える影響等によっては、日本がこれまでのようには石炭を安定的に確保できなくなる可能性も考えられます。日本が今後も石炭を安定的に確保していくためには、まず、南アフリカやコロンビア等の調達先の多角化に向けた取組を引き続き行っていくことが重要です。現在の日本は主に高品位炭を輸入して消費している状況ですが、中・低品位炭の利用に向けた取組を進めることも、調達先を多角化していくための方策の1つとして考えられます。日本において、中・低品位炭を利用していくためには様々な課題32が存在していますが、高品位炭よりも多くの国で生産される中・低品位炭の利用が進んだ場合には、石炭の調達先の多角化による調達構造の強靱化につながるため、日本のエネルギー安全保障に寄与することとなります。
次に、石炭火力発電については、2050年カーボンニュートラル等の目標に向け、電力の安定供給の確保を大前提に、電源構成に占める比率をできる限り引き下げていくこととしています。しかし、現在の日本において、石炭火力発電が電力の安定供給のために重要な役割を担っている中、カーボンニュートラルの実現と電力の安定供給の確保をいかに両立させていくかという点は、日本にとって非常に大きな課題です。日本では、この課題の解決に向けた様々な取組を行っていますが、その1つが、燃焼時にCO2を排出しない脱炭素燃料である「アンモニア(NH3)」を活用した、石炭火力発電の脱炭素化です。既存の石炭火力発電の燃料として、石炭とアンモニアを同時に燃焼させる「アンモニア混焼」の実証事業が着実に進展しており、石炭の代わりにアンモニアを燃焼させることで、その分、燃焼時のCO2の排出を削減することができます。また、アンモニアのみを燃料とした「アンモニア専焼」の将来的な実現を目指した研究開発等の取組についても進められています。アンモニアの大規模供給に向けたサプライチェーンの構築や技術開発、コストの低減等の様々な課題がありますが、カーボンニュートラルの実現とエネルギー安全保障の確保を両立していくために、新規投資や技術開発等の取組を推進していく必要があります。
その他にも、日本では、石炭火力発電の脱炭素化を見据えつつ、石炭をガス化し、ガスタービンと蒸気タービンによるコンバインドサイクル方式で発電する石炭火力である「石炭ガス化複合発電(IGCC)」や、IGCCに燃料電池を組み込んだトリプルコンバインドサイクル方式の石炭火力である「石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC)」等の技術開発や実証等の取組も進めています。また、バイオ燃料の混焼といった取組も行っています。
日本では、こうした取組を通じて、電力の安定供給に必要な設備を維持しつつ、火力発電由来のCO2排出量の削減や、脱炭素型の火力発電への置き換えを進めていきます。
また、こうした石炭火力発電の脱炭素化に向けた取組は、日本と同様に、電源構成において石炭火力発電の占める割合の高い国が多いアジアにとっても、極めて重要です。経済成長に伴い、今後も電力需要の増加が見込まれるアジアでは、増加する電力需要に対応していくための取組(発電所の新設等)とともに、CO2の排出削減に向けた取組も進めていかなければならないといった、非常に難しい課題を抱えています。その際、日本が推進しているこうした取組は、この難解な課題に対する解決策の1つになることが期待されます。詳細については次章にて記載していますが、日本では、こうした脱炭素技術等を、「アジア・ゼロエミッション共同体」(以下「AZEC」という。)の枠組み等も用いながら、アジアへも展開し、アジアにおけるGXの実現にも貢献していくことを目指しています。
(3)エネルギー安全保障の確保に向けて
本項では、石炭のサプライチェーンを事例として挙げながら、日本のエネルギー安全保障を毀損しうる新たなリスクやその対応について確認しましたが、石炭に限らず、あらゆる分野において、様々なリスクが生まれつつあります。その一例として、電力の分野では、省エネの進展等に伴い、近年の日本の電力需要は減少傾向にありますが、今後は生成AIの普及をはじめとした「DX」のさらなる進展が予測されています。GXの進展に加えて、DXの進展によるデータ処理量の増大に伴い、今後の電力需要の見通しに関しては、増加する可能性についての指摘もある等、不確実性がより一層高まっており、今後も電力の安定供給を確保し続けていくためには、こうした動向・変化にも注意を払い、必要な対応をしっかりと講じていくことが重要となっています(第122-2-1参照)。
このように、エネルギーを巡る不確実性が一層高まり、日本のエネルギーに影響を与えうる「変数」がますます増加している中、これからも日本がエネルギー安全保障を確保し続けていくためには、エネルギーの上流(どのように調達するか等)、中流(どのように供給・輸送するか等)、下流(どのように消費するか等)、そして、サプライチェーン全体を通じた動向をタイムリーに把握するとともに、様々なリスクを想定して、新規投資の促進、技術開発の推進、制度設計等、必要な取組を着実に実行していく必要があります。また、エネルギー事業者自身の健全性の確保等についても、エネルギー安全保障を確保していくためには欠かせない視点です。
COLUMN
世界的に需要の高まる鉱物資源
世界各国がカーボンニュートラルの実現を目指す中、ますます重要となっているのが「鉱物資源」です。鉱物資源とは、地下に埋蔵されていて、人間にとって有益な鉱物全般のことを指しており、その種類は非常に多く、鉱物によって様々な特性を有しています。鉱物資源のうち、埋蔵量・産出量がともに多く、精錬が比較的簡単な鉄やアルミニウム、銅、鉛、亜鉛等の金属は「ベースメタル」と呼ばれており、他方で、産出量が少ない、あるいは、抽出することが難しい希少な金属は「レアメタル」と呼ばれています。具体的には、リチウムやニッケル、コバルト等があります。さらに、レアメタルの一部である希土類17元素は「レアアース」とも呼ばれています(第122-2-11)。
【第122-2-11】鉱物資源(元素記号表)
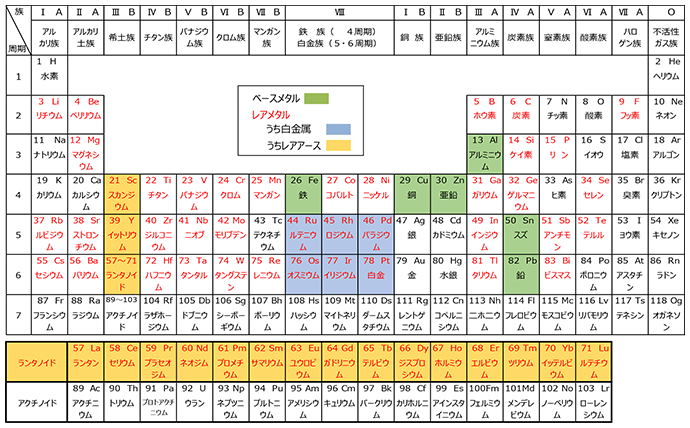
【第122-2-11】鉱物資源(元素記号表)(ppt/pptx形式:83KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
こうした鉱物資源は、あらゆる工業製品の原材料となっており、国民生活や経済活動を支える極めて重要な資源です。カーボンニュートラルの実現に向け、世界中で再エネや電動車(EV、FCV等)の導入が急速に進んでいますが、こうした分野においても鉱物資源は欠かすことのできない資源となっています。例えば、風力発電機器においては、強力な永久磁石を使用することで高効率化を実現していますが、この永久磁石の製造には、レアメタルが不可欠となっています。また、電動車の製造に不可欠な部品であるワイヤーハーネスやバッテリー、駆動モーターには、銅やリチウム、ニッケル、コバルト、レアアース(ネオジム等)が使われており、電動車には、従来型の自動車よりも多くの鉱物資源が用いられています(第122-2-12)。
【第122-2-12】カーボンニュートラルの実現に必要な鉱物資源の例
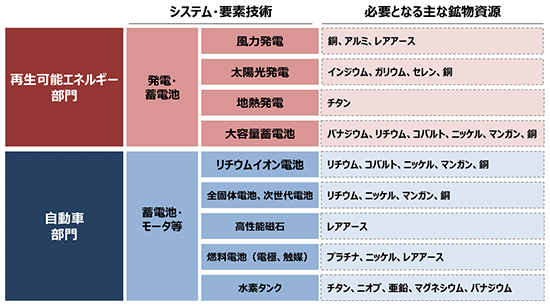
【第122-2-12】カーボンニュートラルの実現に必要な鉱物資源の例(ppt/pptx形式:65KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
このように、世界中がカーボンニュートラルの実現に向けた取組を進める中、様々な工業製品の原材料として、鉱物資源の需要はますます高まりを見せています。IEAの需要見通し33によると、2040年における需要は、2020年比で銅が1.7倍、コバルトが6.4倍、リチウムが12.8倍、ニッケルが6.5倍、レアアースが3.4倍へと増加することが予測されています(第122-2-13)。
【第122-2-13】鉱物資源の需要見通し
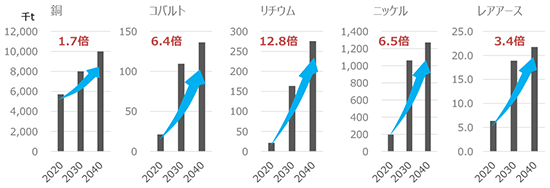
【第122-2-13】鉱物資源の需要見通し(ppt/pptx形式:66KB)
- 資料:
- IEA「The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions」を基に経済産業省作成
鉱物資源需要の高まりにより、国際的な資源獲得競争がますます激しくなっていくことが予測されますが、日本は、ベースメタル、レアメタルのいずれについても、ほぼ全量を海外からの輸入に頼っている状況です。2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、日本においても、今後さらに鉱物資源の需要が高まっていくと考えられる中で、日本では、鉱物資源を安定的に確保するための取組がより一層必要となっています。
しかし、鉱物資源の安定供給の確保に向けては、様々な課題があります。特に、多くの鉱物資源のサプライチェーンが特定の国に依存していることは、日本が強靱なサプライチェーンを構築していくための大きな課題となっています。生産国の偏りだけでなく、製錬工程についても特定の国に偏っていることが、サプライチェーン上の大きな特徴となっており、日本としては、粘り強く、サプライチェーンの各工程において、鉱物資源の安定供給上のリスクがないか検証するとともに、各工程の多様化を進めていくことが必要となっています(第122-2-14)。
【第122-2-14】鉱物資源の生産・製錬・輸入に関する国・地域別の割合
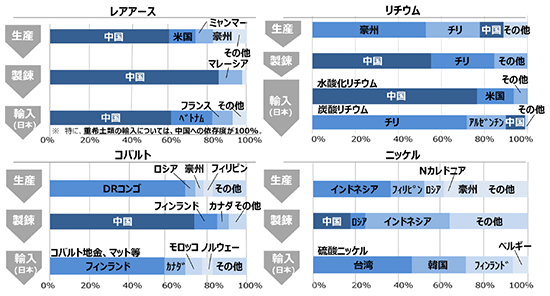
【第122-2-14】鉱物資源の生産・製錬・輸入に関する国・地域別の割合(ppt/pptx形式:88KB)
- 資料:
- IEA、ITC、JOGMECのデータベース等を基に経済産業省作成
こうしたサプライチェーンの強靱化・多様化に向けた取組の一環として、2023年8月に、西村経済産業大臣は、鉱物資源国として国際的に関心の高まっているナミビア、コンゴ民主共和国、ザンビア、マダガスカル等のアフリカ諸国を訪問し、鉱物資源の確保のための政府間の関係強化及びビジネス関係の強化を図りました。
また、日本では、鉱物資源の安定供給を確保するため、強靱なサプライチェーンの構築に向けた取組以外にも、リサイクルを含む精錬技術の開発支援や、重要鉱物の備蓄、省資源・代替技術の開発支援等の様々な取組を行っています(第122-2-15)。
【第122-2-15】日本の鉱物資源政策の概要
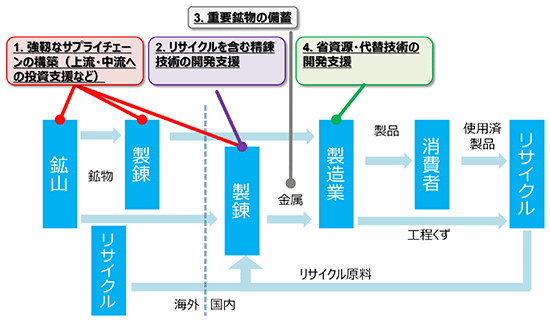
【第122-2-15】日本の鉱物資源政策の概要(ppt/pptx形式:1,145KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
鉱物資源の安定供給の確保に向けた取組については、日本だけでなく国際的にも議論が加速しています。その一例として、2023年4月に札幌で行われた「G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合」においては、世界中で需要が増加している重要鉱物に関する課題を克服していくための「重要鉱物セキュリティのための5ポイントプラン」が合意されました。5ポイントプランとは、「長期的な需給予測」、「責任ある資源・サプライチェーンの開発」、「更なるリサイクルと能力の共有」、「技術革新による省資源」、「供給障害への備え」のことを指しており、今後はこれらを実行に移していくことが求められています(第122-2-16)。
【第122-2-16】重要鉱物セキュリティのための5ポイントプラン
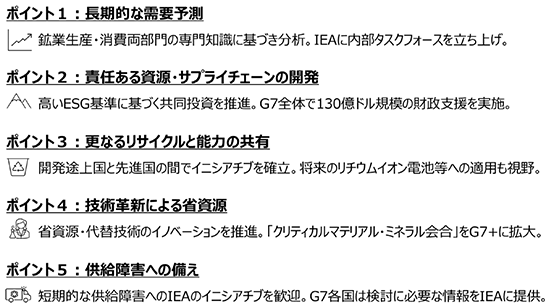
【第122-2-16】重要鉱物セキュリティのための5ポイントプラン(ppt/pptx形式:187KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
その後、同年10月には、IEAとして初となる重要鉱物とクリーンエネルギー移行に関する会議である「IEA重要鉱物・クリーンエネルギーサミット」が開催されました。その中では、エネルギー・トランジションを推進する上で、特定国に依存しない形で、重要鉱物の安定供給を確保し、そのサプライチェーンの強靱化を図ることが急務であるとの共通認識が形成されました。
3.能登半島地震における被害と対応
本章では、ここまで、主に国際情勢に関連した内容について確認を行ってきましたが、その他にも、日本のエネルギーに甚大な影響を与える事象として、地震や台風、豪雨、豪雪等の「自然災害」があります。2024年の元日には、石川県能登地方を震源とする「令和6年能登半島地震」(以下「能登半島地震」という。)が発生し、石川県を中心に甚大な被害が出ることとなりました。エネルギーに関しても、広範囲で停電が発生する等、様々な被害・影響が発生し、自然災害の多い日本において、災害発生時のエネルギーの安定供給やレジリエンスの重要性が改めて認識される年明けとなりました。
本項では、エネルギーに関して、能登半島地震による被害状況や、復旧対応の状況等について整理します。
(1)能登半島地震の概要
2024年1月1日16時10分頃、石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6(暫定値)の地震が発生し、石川県輪島市・志賀町で震度7、石川県七尾市・珠洲市・穴水町・能登町で震度6強を観測する等、石川県を中心に、強い揺れを観測しました(第122-3-1)。
【第122-3-1】能登半島地震の震度
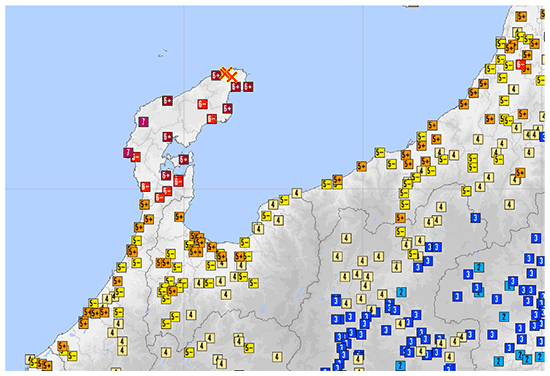
(注)数値は各地における震度。「×」印は震央。
【第122-3-1】能登半島地震の震度(ppt/pptx形式:225KB)
- 資料:
- 気象庁「震度データベース」
この地震により、死者245名、負傷者1,300名の人的被害、そして、住家被害については、全壊が8,695棟、半壊が18,986棟等の被害が発生しました(いずれも2024年4月2日時点34)。ライフラインに関しても、水道において、石川県内を中心に最大約13.7万戸で断水が発生し、電気においても、北陸電力管内を中心に最大約4万戸で停電が発生する等、住民生活に大きな影響を及ぼしました。
(2)エネルギー供給への影響と復旧対応
①電力
発災当初、北陸電力管内では、最大約4万戸の停電が発生しました。北陸電力送配電は、災害時連携計画に基づき、他の電力会社や協力会社等から作業員や電源車等の広域的な応援も受け、連日千人規模で復旧作業を実施しました。その結果、地震発生から1か月後の1月末時点では、停電戸数が約2,500戸まで減少し、石川県全体では99%以上の送電率、被害が甚大であった輪島市と珠洲市においても約9割の送電率となり、全体として概ね復旧しました。その後も、現場へのアクセスの改善状況に応じて、順次復旧作業を進め、3月末時点では、北陸電力送配電が保安上の措置(屋内配線の不具合による漏電等が発生する恐れがある箇所)を実施している約350戸を除き、復旧しています。
なお、産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会において、今回の停電復旧対応に関する検証を開始しています。
②都市ガス
発災当初、都市ガスの供給については、液状化や差し水等により導管が被害を受けたため、石川県金沢市及び富山県富山市において計148戸の供給支障が生じましたが、その後の事業者の復旧対応により、1月4日までに供給を再開しました。
都市ガスの製造については、新潟県上越市に所在するLNG基地において、地震発生に伴いプラントを停止した後、製造再開のために実施していた安全確認作業が津波警報により中断したことで、製造支障が発生しましたが、国産ガスプラントからの供給やパイプライン内湛ガス35による供給に加え、他事業者からのバックアップ供給を受けたことにより、供給への影響はありませんでした。なお、当該基地における都市ガスの製造及び送ガスについては、1月2日に再開しました。
また、コミュニティーガス(旧簡易ガス)については、石川県内の7団地において計509戸の供給支障が生じましたが、その後の事業者の復旧対応により、建物の崩落等により復旧が困難なものを除き、1月10日までに供給を再開しました。
③LPガス
発災当初、石川県七尾市にある北陸地域のLPガス供給の拠点「七尾ガスターミナル」では、LPガスの受入及び出荷設備の損傷により、部分的な出荷制限が生じましたが、業界団体において災害対策本部を設置し、元売事業者間で情報共有を行い、基地間で連携して代替出荷を実施するとともに、さらには道路や港湾等を担当する行政機関の協力もあり、3月1日には通常の出荷体制へと移行しました。
また、LPガス販売事業者の事業所や充塡所等においても設備の損傷が生じましたが、各家庭の軒下に既に設置されているLPガスボンベや充塡済の在庫ボンベの出荷等により、供給を継続しました。具体的には、奥能登4市町(石川県輪島市・珠洲市・穴水町・能登町)における3つの充塡所のうち、2つの充塡所が地震により使用停止となりましたが、それらの充塡所において在庫となっていた充塡済のLPガスボンベを出荷するとともに、業界団体・事業者間の連携の下、石川県内の別の充塡所で充塡したLPガスを現地に配送することで、不足なく対応しました。また、政府、地方公共団体、業界団体の連携の下、被災地域におけるLPガス供給体制を把握しつつ、避難所等への「プッシュ型」によるLPガス供給支援を実施しました。なお、業界団体や販売事業者において、流出したLPガスボンベの全数回収や需要家宅のLPガス設備の安全点検を早期に全数実施したことで、家屋の倒壊等の場合を除き、2月中旬にはLPガスの使用に支障のない状況となりました。
④燃料油(ガソリン等)
発災当初、能登6市町(石川県輪島市・珠洲市・穴水町・能登町・七尾市・志賀町)では、道路の損傷により大型タンクローリーによる燃料供給が困難な地域が発生しました。サービスステーション(以下「SS」という。)においては、給油のための長蛇の列が発生し、給油制限が行われました。早期の復旧に向けて、1月4日以降、道路啓開の進捗とともに、平時を上回る台数のタンクローリーによる輸送が行われたことで、1月9日頃には、給油待ちの行列はほぼ解消されました。
能登6市町では、政府、地方公共団体、業界団体の連携の下、被災地域における燃料供給インフラの状況を把握しつつ、燃料供給支援を実施しました。具体的には、暖房を必要とする避難所や停電が発生した病院等に対して、「プッシュ型」で灯油及び軽油等の燃料を供給するとともに、中核SS36を中心に、自衛隊・警察・消防等の緊急車両や電源車・通信・医薬・バキュームカー等の車両に対して、優先給油を実施しました。さらに、住民の生活需要に応えるため、入浴施設やランドリーカーへの燃料供給にも対応しました。これらの燃料供給に当たっては、地元のSSが大きな役割を果たしました。
- 12
- それまでのレギュラーガソリンの全国平均価格の過去最高額は、2008年8月に記録した185.1円でした。
- 13
- 2021年度補正等893億円、2021年度予備費等3,580億円、2022年度予備費2,774億円、2022年度第1次補正11,655億円、2022年度予備費12,959億円、2022年度第2次補正30,272億円、2023年度補正1,532億円。
- 14
- 2022年度第2次補正31,074億円、2023年度補正6,416億円。
- 15
- GX:Green Transformation(グリーントランスフォーメーション)の略。
- 16
- ここでの大手電力会社10社とは、北海道電力・東北電力・東京電力ホールディングス・中部電力・北陸電力・関西電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力を指します。また、10社の連結決算の合計について記載しています。
- 17
- 本コラムにおける電気料金とは、特段の記載のない限り、みなし小売電気事業者10社(北海道電力・東北電力・東京電力エナジーパートナー・中部電力ミライズ・北陸電力・関西電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力)が提供している規制料金(経過措置料金)のことを指します。なお、自由料金の中には、基本料金がない料金メニューや、電力量料金の部分が「電力市場連動型」(日本卸電力取引所(JEPX)のスポット市場価格等に連動)となっている料金メニュー等も登場しています。
- 18
- 事業者の効率化努力の及ばない燃料価格や為替レートの変動による影響を外部化することにより、事業者の経営効率化の成果を明確にし、経済情勢の変化を可能な限り迅速に料金に反映させると同時に、事業者の経営環境の安定化を図ることを目的に、1996年1月から導入されている制度です。
- 19
- 各事業者が料金改定申請を行った際の直近3か月における原油・LNG・石炭の貿易統計価格の加重平均値であり、各事業者の火力発電における燃料の熱量構成比を加味して算出しています。
- 20
- 各月の3〜5か月前の原油・LNG・石炭の貿易統計価格の加重平均値(3か月平均)のこと。
- 21
- 下限はありません。
- 22
- 自由料金の中には、燃料費調整を設定していない料金メニューも見られます。また、燃料費調整を設定している場合でも、上限設定のないものが多く見られます。
- 23
- 他方、こうした仕組みにより、日本の電気料金(規制料金)の上昇については、一定程度抑制されました。今回の世界的な燃料価格の高騰に伴う日本の電気料金の上昇率は、英国やイタリア等の上昇率と比べ、限定的なものとなっています(資源エネルギー庁「令和4年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2023)」より)。
- 24
- 北海道電力・東北電力・東京電力エナジーパートナー・北陸電力・中国電力・四国電力・沖縄電力の7社。
- 25
- 例えば、燃料費については、より安価に燃料を調達している事業者の価格を基準として調達の効率化を求める「トップランナー査定」を行いました。また、修繕費等の固定費についても、経営効率化の深掘り等、厳格な査定を行いました。
- 26
- 当初、規制料金改定の認可申請を行った7社は、28%〜48%の値上げを申請しましたが、下落傾向にあった燃料価格を踏まえて再算定することを含め、前述のとおり厳格な査定を行った結果、標準家庭における値上げ率は、14%〜42%に圧縮されました。
- 27
- 改定後の規制料金においても、引き続き、燃料費調整制度における調整可能な料金の幅には上限(基準燃料価格の1.5倍)を設定しており、下限の設定はありません。改定後も改定前と同様に、燃料費調整制度に基づき、燃料価格が上がると規制料金も上がり、燃料価格が下がると規制料金も下がることとなります。
- 28
- DX:Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)の略。
- 29
- 日本では、無煙炭から褐炭までを一般的に石炭と呼んでいます。
- 30
- 2020年後半より、中国は豪州からの石炭輸入を減らし、その後は輸入停止の状態が続いていました(両国間の関係悪化が要因とされています)が、2023年より豪州からの石炭輸入を再開しました。このことも、2023年における中国の石炭輸入の増加の一因となっています。
- 31
- 中国が高品位炭の輸入を増加させた要因として、中国国内における高効率な石炭火力発電である「超々臨界圧石炭火力発電(USC)」の導入拡大等が考えられます。
- 32
- 中・低品位炭の利用に際しては、環境面、安全面、設備面、制度面等に関する様々な課題があります。
- 33
- 各国が表明済の具体的政策を反映したシナリオ(STEPS)における見通し。
- 34
- 内閣府「令和6年能登半島地震による被害状況等について(令和6年4月2日14:00現在)」より。
- 35
- パイプライン内に備蓄しているガスのこと。
- 36
- 緊急通行車両等への優先給油や医療機関・避難所等に対する燃料供給を行うSSのこと。