第1節 エネルギーを巡る不確実性と各国における対応
エネルギー政策を考える上では、安全性を大前提として、エネルギーの安定的な供給、経済性の確保(エネルギーコストの抑制)、環境との調和等が重要な要素となっています。そうした中、2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵略や、2023年10月からのイスラエル・パレスチナ情勢の悪化をはじめ、世界のエネルギー情勢に大きな影響を与える事象が世界各地で立て続けに発生しています。エネルギーを取り巻く情勢は、大きく変化しているとともに、ますます混迷したものになっているといえます。昨今のこうした状況により、エネルギー情勢について今後の見通しを立てることが一層困難なものになりつつある中、世界各国には、様々なリスクやシナリオに備えながら、中長期的な目線で、エネルギーセキュリティを確保するための取組を進めていくことが求められています。
1.エネルギーを巡る不確実性の増大
1973年に発生した第一次オイルショックをはじめ、世界のエネルギー情勢は、これまでも様々な要因によって影響を受けてきました。本項ではまず、世界のエネルギー情勢に影響を与え、エネルギーを巡る不確実性を高めている近年の事象について概観していきます。
(1)ロシアによるウクライナ侵略
2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略は、発生から2年以上が経過した今もなお、世界のエネルギー情勢に強い影響を与えています。ロシアによるウクライナ侵略の発生後、欧米諸国等はロシアへの経済制裁を実施しました。エネルギーの分野においても、侵略開始直後に米国政府が全てのロシア産エネルギーの輸入禁止の方針を示す等、各国は、ロシア産エネルギーからの脱却を目指していくこととなりました。しかし、その一方で、特にそれまでエネルギーの多くをロシアに依存していたドイツやイタリア等の欧州諸国においては、ロシア産エネルギーに代わるエネルギーの確保が喫緊の課題となりました。このことが、世界のエネルギーの需給構造を大きく変化させ、世界的なエネルギーの需給ひっ迫やエネルギー価格の高騰を引き起こし、世界経済や人々の暮らしにも大きな影響を与えることとなりました。
ロシアによるウクライナ侵略が長期化する中、2023年以降も、欧米諸国によるロシアに対する経済制裁は、継続・強化されています。2023年11月に米国政府が発表したロシアに対する追加の経済制裁では、制裁の対象として、日本企業も参画するロシア北極圏でのLNGプロジェクト「アークティックLNG2」の事業会社が加えられました。
なお、ロシアのサハリン島における日本の原油及びLNGプロジェクトである「サハリン1」及び「サハリン2」について、サハリン1に関しては、原油輸入の9割超を中東地域に依存している日本にとって貴重な中東地域以外からの原油調達先であり、また、サハリン2に関しては、2023年に日本が輸入したLNGの約9.3%を供給し、総発電量の約3%に相当する等、いずれも日本のエネルギー安全保障上、極めて重要なプロジェクトです。そのため、中長期的なエネルギー安定供給の確保の観点から、現状、日本としてはサハリン1及びサハリン2の権益を維持する方針です。
(2)イスラエル・パレスチナ情勢(中東情勢)
石油や天然ガスの一大生産地であり、日本が原油の9割以上を調達している中東地域1においても、エネルギーを巡る不確実性を高める事象が発生しています。具体的には、2023年10月7日にパレスチナ武装勢力がイスラエルを攻撃して以降、イスラエル・パレスチナ武装勢力間で戦闘が発生しており、パレスチナのガザ地区を中心に情勢が悪化しています。また、このイスラエル・パレスチナ情勢の悪化等をきっかけに、イエメンの武装組織である「フーシ派」が、アラビア半島とアフリカ大陸の間に位置する紅海周辺の海域を通る船舶に対して、ドローン等で攻撃を繰り返すという事象も発生しています。2024年3月末時点では、日本における原油や天然ガスの安定供給に影響を及ぼしていないものの、他の中東地域の情勢悪化へと広がっていく可能性等、今後の状況を注視していく必要があります。
特に、前述のフーシ派による紅海周辺の海域を通る船舶への攻撃を受け、日本を含む世界の多くの海運事業者が、紅海を通るルートから、主に南アフリカの喜望峰を経由するルートへの変更を余儀なくされました。紅海北部に位置するスエズ運河を通航した船舶隻数の推移を確認すると、2023年12月頃から大きく減少していることがわかります。それまでは、1日に70隻〜80隻前後の船舶がスエズ運河を通航していましたが、2024年1月下旬頃からは、その半分程度となる30隻台にまで急減しています。紅海南部に位置するバブ・エル・マンデブ海峡を通航した船舶隻数の推移を見ても、同様の傾向を確認できます。一方、南アフリカの喜望峰を通航した船舶隻数の推移を確認すると、スエズ運河やバブ・エル・マンデブ海峡とは概ね真逆の状況になっていることがわかります。喜望峰を通航する船舶隻数は、2023年12月頃まで1日に50隻前後の水準で推移していましたが、その後に大きく増加し、2024年2月以降は一時90隻台にまで達しました(第121-1-1)。
【第121-1-1】紅海(スエズ運河、バブ・エル・マンデブ海峡)及び喜望峰を通航する船舶隻数の推移
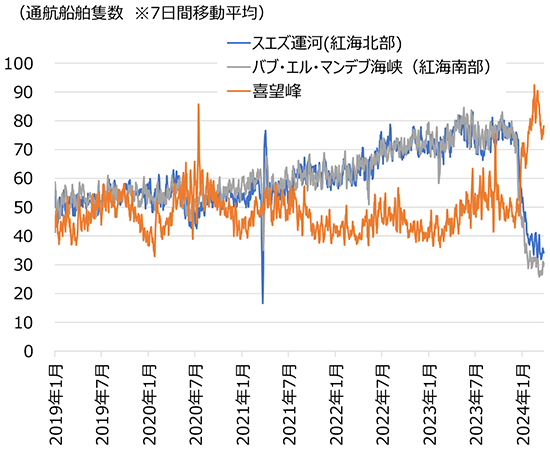
(注)数値は7日間の移動平均。
【第121-1-1】紅海(スエズ運河、バブ・エル・マンデブ海峡)及び喜望峰を通航する船舶隻数の推移(ppt/pptx形式:98KB)
- 資料:
- IMF・University of Oxford「PortWatch」を基に経済産業省作成
紅海は、アジアと欧州を結ぶ重要な航路であり、紅海を通るルートから喜望峰を経由するルートへの変更は、エネルギーに限らず、様々な物資の輸送・サプライチェーンに対して大きな影響を与えることになります。具体的には、喜望峰を経由するルートへ変更することにより、航海距離が約7,000km、航海日数が約10日増えるため、輸送コストの上昇や輸送量の低下等につながることになります。例えば、アジア(中国・上海)から欧州(オランダ・ロッテルダム)へ向かう40フィートコンテナの海上輸送の運賃の推移2を確認すると、紅海周辺における情勢が悪化し始めた2023年11月から上昇しており、2024年1月には前月比で2.5倍以上にまで急騰していることがわかります(第121-1-2、第121-1-3)。
【第121-1-2】紅海ルートと喜望峰ルート
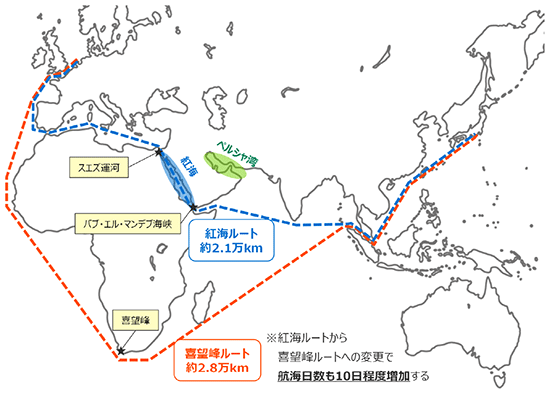
【第121-1-2】紅海ルートと喜望峰ルート(ppt/pptx形式:280KB)
- 資料:
- 各種情報を基に経済産業省作成
【第121-1-3】40フィートコンテナの海上運賃の推移(上海発/ロッテルダム着)
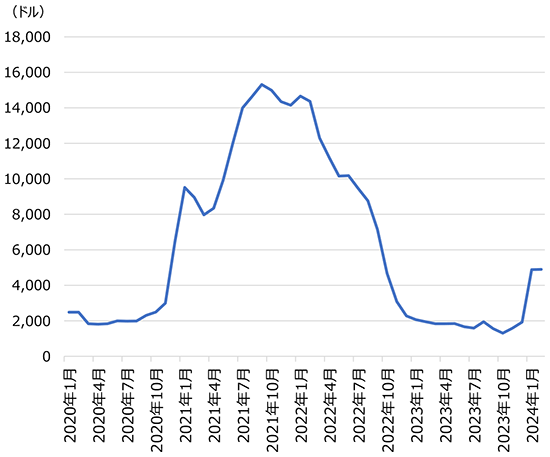
【第121-1-3】40フィートコンテナの海上運賃の推移(上海発/ロッテルダム着)(ppt/pptx形式:52KB)
- 資料:
- 日本海事センター「主要航路コンテナ運賃動向」を基に経済産業省作成
エネルギーに関しても、紅海は石油やLNGの輸送における大動脈の1つとなっています。米国のエネルギー情報局(以下「EIA」という。)によると、2023年の上半期において、紅海を経由する石油の輸送量は、世界全体の石油の海上輸送量の12%を占め、LNGの輸送量については、世界全体のLNG貿易量の8%を占めていました。この紅海周辺における情勢の悪化により、英国の石油大手事業者であるBPやシェル等も紅海を経由するルートでの航行を全て停止すると発表しており、輸送の面から、世界のエネルギー情勢を巡る不確実性が高まっているといえます。
エネルギーの多くを中東地域に頼っている日本としては、こうした情勢の悪化が他の海域等にも波及し、エネルギー安定供給への影響やエネルギー価格の上昇につながるリスク等を考慮しながら、状況を引き続き注視していく必要があります。
(3)パナマ運河の干ばつ・水位低下
前項では、紅海周辺の海域で発生したエネルギーの輸送面におけるリスクについて記載しましたが、2023年は、エネルギーの輸送に影響を与える事象が他にも発生しました。それが、記録的な干ばつによる、パナマ運河の通航船舶隻数の制限・減少です。
パナマ運河は、全長約80kmの太平洋と大西洋をつなぐ海上交通の要衝であり、人造湖であるガトゥン湖を主たる水源として運用されています。しかし、2023年はパナマ運河周辺における降雨量が少なく、深刻な干ばつに見舞われたことから、ガトゥン湖の水位が大きく低下し、貯水量が減少するという事態に陥りました。これを受け、パナマ運河を管理するパナマ運河庁は、喫水制限の強化に加え、通航できる船舶隻数を減らす対応を取ることとなり、その結果、パナマ運河の通航を予定していた多くの船舶が、通航に際して長時間の待機を余儀なくされ、あるいは、南アフリカの喜望峰経由のルートや南米大陸のマゼラン海峡経由のルート等への変更を強いられることとなりました。こうした対応は、航海距離や航海日数の増加等につながり、輸送コストの上昇や輸送量の低下等を引き起こすことになります。実際に、パナマ運河を通航した船舶隻数の推移を確認すると、2023年11月頃から大きく減少していることがわかります。それまでは、1日に35隻前後の船舶がパナマ運河を通航していましたが、2024年1月以降は20隻台前半にまで減少しています。また、中国・上海から米国の東海岸にあるニューヨークへ向かう40フィートコンテナの海上輸送の運賃については、パナマ運河の通航船舶隻数が減少し始めた2023年11月から上昇傾向となりました(第121-1-4、第121-1-5)。
【第121-1-4】パナマ運河を通航する船舶隻数の推移
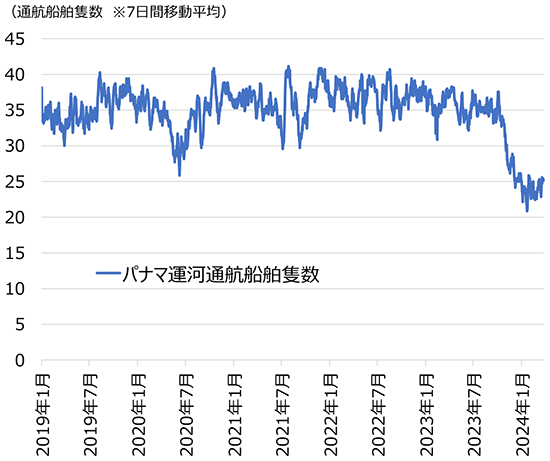
(注)数値は7日間の移動平均。
【第121-1-4】パナマ運河を通航する船舶隻数の推移(ppt/pptx形式:67KB)
- 資料:
- IMF・University of Oxford「PortWatch」を基に経済産業省作成
【第121-1-5】40フィートコンテナの海上運賃の推移(上海発/ニューヨーク着)
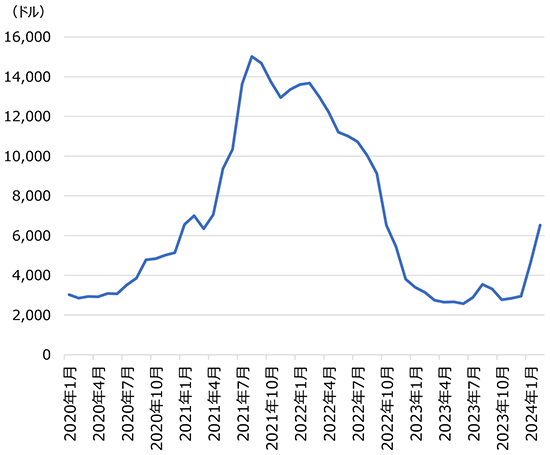
【第121-1-5】40フィートコンテナの海上運賃の推移(上海発/ニューヨーク着)(ppt/pptx形式:53KB)
- 資料:
- 日本海事センター「主要航路コンテナ運賃動向」を基に経済産業省作成
なお、日本は、米国から輸入するLNG等を主にパナマ運河経由のルートで調達してきましたが、輸送ルートの変更やLNGのスワップ(交換)等の対応もあり、2024年3月末時点では、日本のエネルギー安定供給やエネルギー価格への影響は限定的なものとなっています。
紅海と同様に、チョークポイントにおけるこうした動向は、エネルギーに限らず、様々な物資の輸送・サプライチェーンに極めて大きな影響を与えます。エネルギーをはじめ、多くの物資を海外に頼る日本としては、今後も輸送・サプライチェーン上のリスク等に十分な注意を払っていくことが極めて重要です。
(4)その他の動向
ここまでに確認してきた事象以外にも、世界のエネルギー情勢に影響を与える事象は、様々な要因、様々な場所において発生しています。
例えば、世界有数の天然ガスの生産国であり、日本にとって最大のLNG輸入先3でもある豪州では、2023年9月に、JERA等の日本企業もLNGの調達を行っている大規模なLNGプラント4においてストライキの実施が予告され、LNGの安定供給に対する懸念が一時的に高まるといった事象が発生しました。このストライキについては、豪州政府の介入もあり、労使双方が合意したことで終結することとなりましたが、政情が比較的安定しており、日本を含め世界各国のエネルギーを支えている豪州においても、エネルギーセキュリティに関して様々なリスクがあることが再認識されました。
また欧州では、2023年10月に、フィンランドとエストニアを結び、フィンランド側からエストニア側に天然ガスを供給する海底パイプラインである「バルチックコネクター」においてガス漏れが発生し、バルチックコネクターの運用が緊急停止される事態が発生しました。その後、エストニアはラトビア経由でガスの供給を確保したと発表していますが、2022年に発生した「ノルドストリーム15」の稼働停止に続き、欧州における天然ガスの輸送面でのリスクが再度浮かび上がることとなりました。
その他にも、ノルウェーのガス関連設備における相次ぐトラブル等、2023年以降も世界各地でエネルギー需給に影響を与える様々な事象が発生しました(第121-1-6)。
【第121-1-6】近年発生したエネルギーに影響を与える事象例
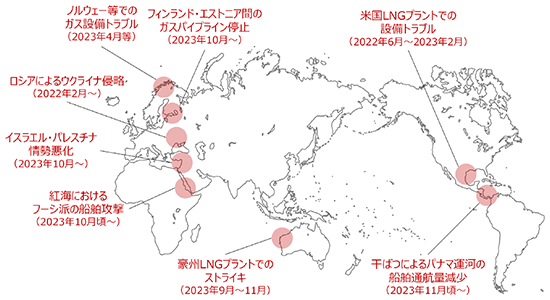
【第121-1-6】近年発生したエネルギーに影響を与える事象例(ppt/pptx形式:313KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
(5)化石エネルギーの価格動向
2023年以降も、世界のエネルギー情勢に影響を与える様々な事象が発生しましたが、ロシアによるウクライナ侵略が発生し、世界中でエネルギーの需給ひっ迫やエネルギー価格の高騰が発生することとなった2022年の水準と比べると、2023年以降のエネルギー価格は、比較的落ち着きを取り戻しています。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行前である2010年代後半頃の価格水準と比較すると、2023年以降のエネルギー価格は、引き続き高い水準で推移していることがわかります。例えば、ロシアによるウクライナ侵略を受けて世界的に需要の高まったLNGに関して、アジアのLNGスポット価格であるJKM6の推移を見ていくと、2019年の平均価格が5ドル/MMBtu程度の水準であった一方、2023年の平均価格は、その3倍近い14ドル/MMBtu程度の水準となっていることがわかります(第121-1-7、第121-1-8、第121-1-9)。
【第121-1-7】天然ガス・LNG市場価格の推移
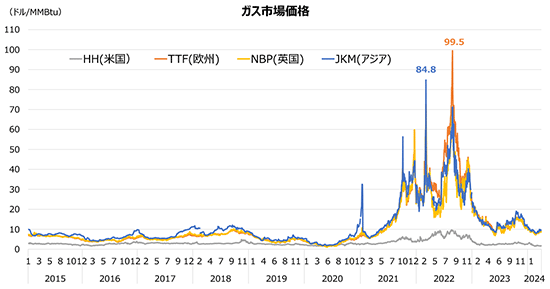
【第121-1-7】天然ガス・LNG市場価格の推移(ppt/pptx形式:123KB)
- 資料:
- S&P Global Platts等を基に経済産業省作成
【第121-1-8】原油市場価格の推移
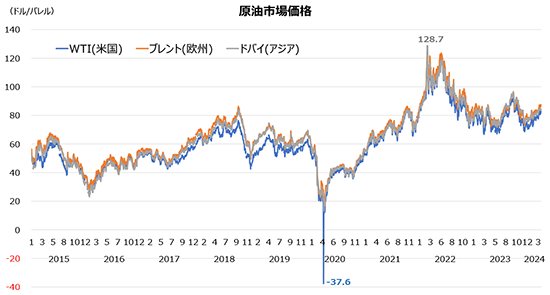
【第121-1-8】原油市場価格の推移(ppt/pptx形式:113KB)
- 資料:
- Chicago Mercantile Exchangeを基に経済産業省作成
【第121-1-9】石炭市場価格の推移
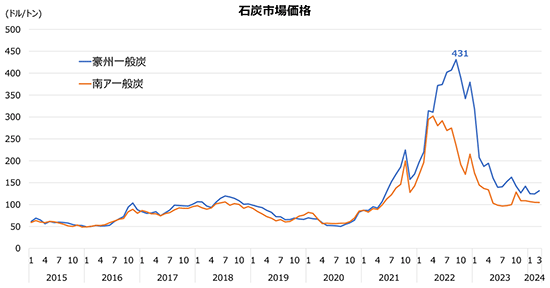
【第121-1-9】石炭市場価格の推移(ppt/pptx形式:56KB)
- 資料:
- The World Bank「Commodity Markets」を基に経済産業省作成
(6)エネルギーセキュリティの確保に向けた対応
ここまで見てきたように、特にロシアによるウクライナ侵略やイスラエル・パレスチナ情勢の動向については、いまだ予断を許さない状況が続いています。また、エネルギーを巡る不確実性が高まる中、世界のエネルギー情勢やエネルギー価格に影響を与えうる事象が、今後も様々な要因で発生すると考えられます。さらに、それ単独では大きな影響を引き起こすには至らないような事象でも、複数の事象が重なり影響し合うことで、大きな影響を引き起こす可能性もあります。もちろん、未来のことを全て予測することはできませんが、エネルギーに関するあらゆるリスクを想定した上で、最新の国際情勢も注視しながら、サプライチェーン全体の観点で、エネルギーセキュリティの確保に向けた取組を不断に続けていくことが重要です。
2.世界的なエネルギー需給構造の変化
前述のとおり、2022年2月に発生したロシアによるウクライナ侵略を受け、欧米諸国等はロシアに対する経済制裁を実施し、ロシア産エネルギーからの脱却を目指していくこととなりました。このことによって、世界のエネルギーを取り巻く状況は大きく変化しています。本項では、天然ガス・LNG、石油、石炭の貿易構造がどのように変わったのかについて、Energy Institute7や国際エネルギー機関(以下「IEA」という。)の年次データ等を用いながら、確認を行っていきます。
(1)天然ガス・LNG貿易の動向
最初に、ロシアによるウクライナ侵略によって、最も大きな影響を受けたと考えられる天然ガス貿易の動向について見ていきます。天然ガスの輸送方法は、気体のままパイプラインで輸送する方法と、マイナス162℃まで冷却し、液体のLNGにしてから船舶(LNG船)等で輸送する方法の2つに大別されます。ノルウェーから欧州諸国への輸送や米国とカナダ間の輸送等、同じ大陸内かつ比較的近傍への輸送には、主としてパイプラインが用いられ、豪州や米国からアジア諸国への輸送等、海上輸送が必要な場合等には、LNGとして輸送されています。
パイプラインを用いた貿易及びLNGの貿易について、2021年から2022年にかけての動向を見ていくと、まず、ロシアから欧州へのパイプラインによる輸出が大きく減少していることが目を引きます。これについては、ロシアからドイツ経由で欧州に天然ガスを供給していた海底パイプラインである「ノルドストリーム1」が、2022年8月末から稼働を停止した影響が大きいと考えられます。欧州では、この減少分について、米国やカタール等からのLNG輸入を増やすことで対応しました。なお、欧州の米国からのLNG輸入については、2022年以前から増加傾向にあり、2019年からの3年間で約4倍にまで急増しています。また、詳細については後述していますが、欧州ではカタールの国営会社であるカタールエナジーとLNGの長期契約を結ぶ動きも近年相次いでいます。一方で、パイプラインを用いた欧州向けの輸出が減少したロシアは、中国向けの輸出を増やしていることもわかります。中国については、ロシアからの輸入を増やすとともに、中東地域からのLNG輸入も増やしていますが、その一方で、米国からのLNG輸入を大きく減らしています。中国と同様に、日本や韓国においても米国からのLNG輸入が減少しており、米国産LNGについては、アジア向けに輸出される割合が減少し、欧州向けに輸出される割合が高まったことが確認できます(第121-2-1)。
【第121-2-1】天然ガス・LNGの主な貿易動向(2021年→2022年)
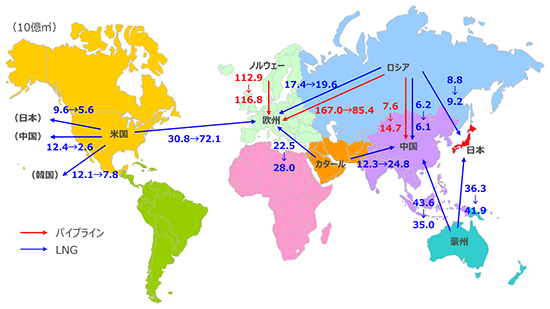
(注1)数値は2021年の貿易量と2022年の貿易量を表している。
(注2)本図には、2021年から2022年にかけて大きな変化等のあった貿易ルートのみを表している。2022年における世界全体の天然ガス・LNGの貿易動向については、第222-1-21を参照。
【第121-2-1】天然ガス・LNGの主な貿易動向(2021年→2022年)(ppt/pptx形式:99KB)
- 資料:
- Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2023」等を基に経済産業省作成
米国から他国へのLNG輸出の状況について、月次データを用いてさらに詳しく確認していくと、LNG輸出量が右肩上がりに増加していることがわかります。特に、ロシアによるウクライナ侵略が発生した2022年以降、欧州向けの輸出が多くなっており、こうした傾向は2024年3月に至るまで継続しています。アジア向けの輸出については、欧州向けの輸出が急増した2022年に一時減少しましたが、その後は回復傾向にあります。また、欧州のLNG輸入に関する月次データを確認すると、2022年に米国からの輸入を中心にLNG輸入が急増した後、概ね横ばいの水準で推移していることがわかります(第121-2-2、第121-2-3)。
【第121-2-2】米国のLNG輸出の推移
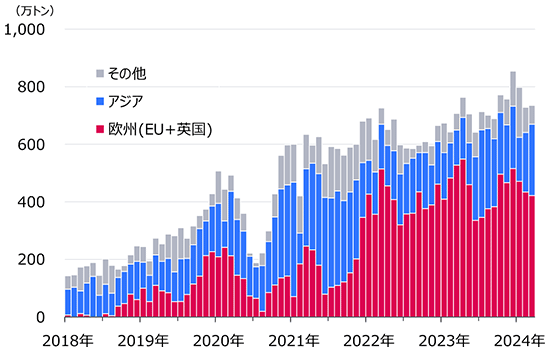
【第121-2-2】米国のLNG輸出の推移(ppt/pptx形式:58KB)
- 資料:
- Kplerを基にエネルギー経済社会研究所作成
【第121-2-3】欧州(EU+英国)のLNG輸入の推移
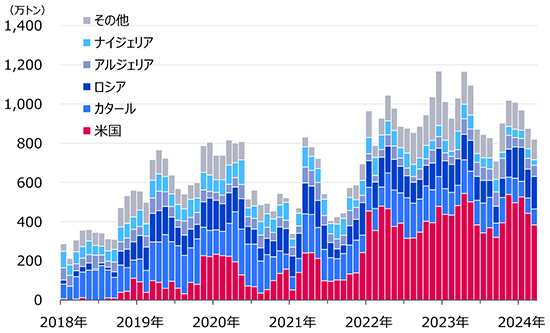
【第121-2-3】欧州(EU+英国)のLNG輸入の推移(ppt/pptx形式:65KB)
- 資料:
- Kplerを基にエネルギー経済社会研究所作成
このように、特に欧州へのLNG輸出を拡大させてきた米国では、近年、新規のLNGプロジェクトが続々と運用を開始しています。EIAによると、今後も2028年頃にかけて、LNGの輸出能力がさらに拡大していく見通しとなっており、世界のLNG市場における米国の存在感がますます大きくなっていくことが予想されています(第121-2-4)。
【第121-2-4】米国を含む北米地域におけるLNG輸出能力の見通し
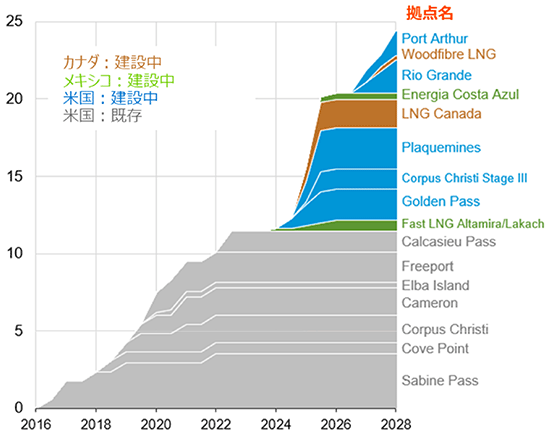
【第121-2-4】米国を含む北米地域におけるLNG輸出能力の見通し(ppt/pptx形式:132KB)
- 資料:
- EIA「LNG export capacity from North America is likely to more than double through 2027」を基に経済産業省作成
その一方で、米国では、2024年1月に、非FTA締結国へのLNG輸出認可の一時停止が発表されました。既に認可済のプロジェクトへの影響は見込まれていませんが、これから認可を取得予定のプロジェクトについては、LNGの生産開始が遅れるということが懸念されます。
また、LNG輸入事業者の国際グループである「GIIGNL」が公表しているレポートを基に、日本・中国・欧州の事業者が長期契約で確保したLNGの量を契約締結年別に見ていくと、近年、中国や欧州の事業者が積極的に長期契約を締結し、LNGを確保していることがわかります。他方、日本の事業者が近年締結した長期契約で確保したLNGの量については、中国や欧州の確保量と比べると少ない状況となっています(第121-2-5)。
【第121-2-5】日本・中国・欧州の事業者が締結した長期契約でのLNG確保量(契約締結年別)
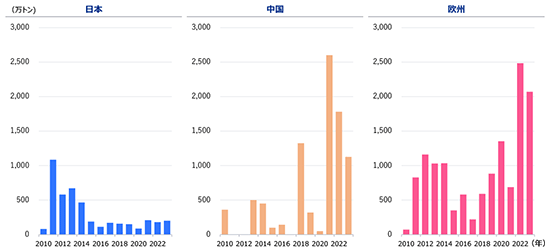
【第121-2-5】日本・中国・欧州の事業者が締結した長期契約でのLNG確保量(契約締結年別)(ppt/pptx形式:53KB)
- 資料:
- GIIGNL「Annual Report」を基にエネルギー経済社会研究所作成
(2)石油貿易の動向
次に、2021年から2022年にかけての石油貿易の動向について見ていくと、天然ガスと概ね同じような傾向を確認することができます。まず、ロシアから欧州への輸出については、EUや英国におけるロシア産エネルギーからの脱却の方針に伴い減少しており、欧州はその代替として、米国や中東地域からの輸入を増やして対応しました。欧州への輸出を減らしたロシアは、中国やインドへの輸出を増やしていることも確認できます。なお、過去から石油の中東依存度が極めて高かった日本にとって、ロシアは数少ない中東地域以外の石油調達先でしたが、2022年にはロシアからの輸入を大きく減らしており、その結果、石油の中東依存度がさらに高まることとなっています(第121-2-6、第213-1-4参照)。
【第121-2-6】石油の主な貿易動向(2021年→2022年)
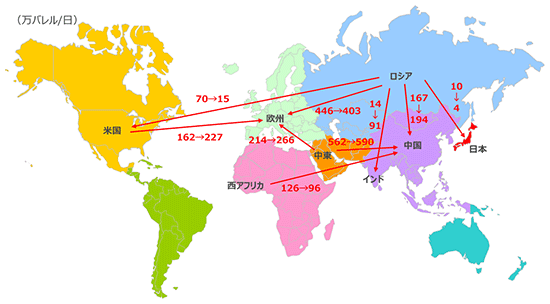
(注1)数値は原油及び石油製品の合計であり、2021年の貿易量と2022年の貿易量を表している。
(注2)本図には、2021年から2022年にかけて大きな変化等のあった貿易ルートのみを表している。2022年における世界全体の石油の貿易動向については、第222-1-9を参照。
【第121-2-6】石油の主な貿易動向(2021年→2022年)(ppt/pptx形式:94KB)
- 資料:
- Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2023」等を基にEnergy Instituteの換算係数を使用して経済産業省作成
また、世界のエネルギー需給に影響を与える要素の1つとなっている石油・天然ガスの上流部門に対する投資額の推移を見ていくと、近年は投資額が増加傾向にあり、2010年代後半の水準まで回復していることがわかります。一方、2014年以降の石油・天然ガス価格の急落を契機として、世界的に脱炭素投資へのシフトが進む等、化石エネルギーを取り巻く情勢(需要動向・政策動向等)が不透明となったこと等により、上流部門に対する投資額は、過去と比較すると減少したことも確認できます。2023年における投資額についても、依然として2015年の投資額の約7割に留まっている状況です(第121-2-7)。
【第121-2-7】石油・天然ガスの上流部門に対する投資額の推移
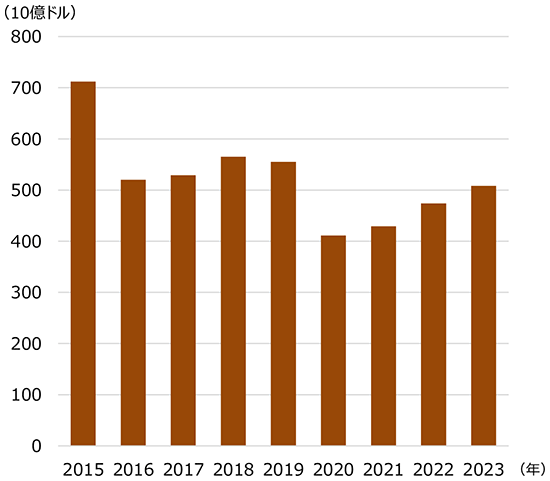
【第121-2-7】石油・天然ガスの上流部門に対する投資額の推移(ppt/pptx形式:50KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Investment 2023」を基に経済産業省作成
油田・ガス田の開発等、上流部門に関するプロジェクトでは、投資決定から運用開始までに多くの時間を必要とするため、足元で投資決定を行ったとしても、即座に石油や天然ガスの生産を開始することはできません。換言すれば、「過去の上流部門に対する投資動向が、現時点における生産・供給力を左右する」ということができ、場合によっては、需給のひっ迫や価格の高騰等にもつながることが考えられます。カーボンニュートラルの実現のためには、化石エネルギーの消費を減らしていくことが重要ですが、日本を含め、世界中の多くの国々が化石エネルギーに依存している現在の状況を踏まえれば、トランジション期において上流投資を一定程度維持し続けていくことは、世界全体のエネルギー安定供給の確保の観点から極めて重要であると考えられ、2023年5月に開催された「G7広島サミット」においても、天然ガス・LNGの必要性が確認されました。そうした中で、2016年以降の上流部門に対する投資額の減少の影響については、引き続き注意を払っていく必要があります。
(3)石炭貿易の動向
最後に、石炭について見ていきます。石炭には、一般炭と原料炭、高品位炭と低品位炭等、多くの種類があり、また天然ガスや石油とは異なり、生産された国においてその多くが消費されているという特徴があります(詳細は次節にて記載)。
石炭の貿易について、2021年から2022年にかけての動向を確認していくと、ロシアから欧州や日本への輸出が大きく減少していることがわかります。欧州では、ロシア産石炭の代替として、米国やコロンビア、南アフリカからの輸入を増やして対応しました。その一方で、石炭消費が世界で最も多い中国と、それに次ぐインドでは、ロシアからの輸入を大きく増やしたことも確認できます。インドについては、インドネシアからの輸入も大きく増やしています(第121-2-8)。
【第121-2-8】石炭の主な貿易動向(2021年→2022年)
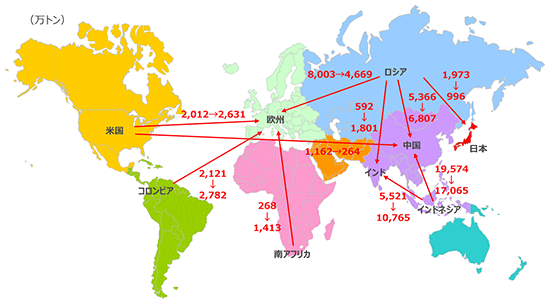
(注1)数値は2021年の貿易量と2022年の貿易量を表している。
(注2)本図には、2021年から2022年にかけて大きな変化等のあった貿易ルートのみを表している。2022年における世界全体の石炭の貿易動向については、第222-1-38を参照。
【第121-2-8】石炭の主な貿易動向(2021年→2022年)(ppt/pptx形式:95KB)
- 資料:
- IEA「Coal Information 2023」、貿易統計等を基に経済産業省推計
(4)全体概況
これまでエネルギーの多くをロシアから調達していた欧州諸国では、ロシア産エネルギーからの脱却を図っていくに当たり、エネルギーの調達先を主に米国、そして中東地域へとシフトしていることが窺えます。他方でロシアは、主に中国やインドに対してエネルギーを多く輸出しつつあるという状況も見て取れます。
ロシアによるウクライナ侵略等の影響で、このように大きく変化することとなった世界のエネルギー需給構造は、仮にロシアによるウクライナ侵略が終息したとしても、以前のように戻るとは考えづらく、このまま一定程度固定化される、あるいは、さらに変化していくことが考えられます。欧州諸国がエネルギーの調達を増やしている米国や中東地域は、日本にとっても極めて重要なエネルギーの調達先です。現在、エネルギーの9割近くを海外から輸入する化石エネルギーに頼っている日本が、今後もエネルギーを安定的かつ安価に調達していくためには、こうした世界のエネルギー需給構造の変化をタイムリーに把握するとともに、必要な対応を着実に講じていくことが極めて重要です。
COLUMN
化石エネルギー価格の見通し
ここまで見てきたとおり、化石エネルギーの価格は近年激しく変動しており、世界経済や人々の暮らしに大きな影響を与えています。化石エネルギーの価格は様々な要因から影響を受けて形成されるものであり、エネルギーを巡る不確実性がますます高まっている中、化石エネルギーの価格について、長期的な見通しを立てることは非常に難しいものになっています。
しかし、そうした中でも、IEA等においては、エネルギー情勢に影響を与える様々な要素を踏まえながら、複数の将来シナリオを策定し、それぞれのシナリオにおける2030年や2050年の化石エネルギー価格の見通しを紹介しています。当然のことながら、将来は不確実なものであり、今後のことを全て予測することはできませんが、将来のエネルギーのことを考えていく上では、それぞれのシナリオにおいてどのような見通しになっているのかについて、その傾向を確認しておくことは重要であると考えられます。本コラムでは、IEAや日本エネルギー経済研究所(以下「IEEJ」という。)が策定している複数の将来シナリオにおける今後の化石エネルギー価格の見通しについて見ていきます。
(1)IEAによる化石エネルギー価格の見通し
IEAは、毎年公開している「World Energy Outlook」において、前提条件の異なる3つのシナリオを策定し、それぞれのシナリオにおけるエネルギー需給や価格の見通し等について紹介しています。1つ目の公表政策シナリオ(以下「STEPS8」という。)は、各国が表明済の具体的政策を反映したシナリオ、2つ目の表明公約シナリオ(以下「APS9」という。)は、有志国が宣言した野心を反映したシナリオ、3つ目のネット・ゼロ・エミッション2050年実現シナリオ(以下「NZE10」という。)は、2050年世界ネットゼロを達成するためのシナリオとなっています。これらの3つのシナリオは、STEPS、APS、NZEの順に気候変動対策が強くなり、脱炭素化に資するエネルギーや技術が多く利用されるシナリオとなっています。
2023年10月に公開された最新の「World Energy Outlook 2023」から、2030年や2050年の化石エネルギー価格の見通しを見ていくと、いずれのシナリオにおいても、2022年の価格水準からは下落していく見通しとなっていることがわかります。これは、各シナリオにおいて、気候変動対策の進展に伴い化石エネルギーの需要減少が見込まれる中、需要に対する供給量については十分に確保されると仮定して分析を行っていることが要因となっています(第121-2-9)。
【第121-2-9】IEAによる化石エネルギー価格の見通し
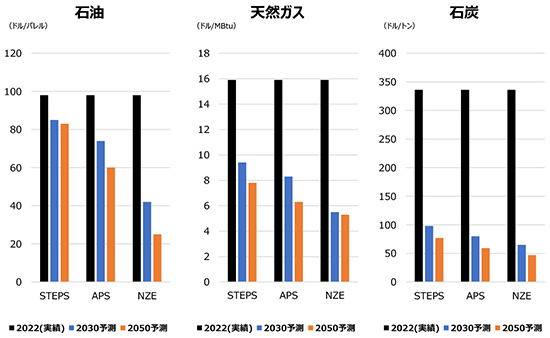
【第121-2-9】IEAによる化石エネルギー価格の見通し(ppt/pptx形式:58KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Outlook 2023」を基に経済産業省作成
(2)IEEJによる化石エネルギー価格の見通し
続いて、IEEJによる化石エネルギー価格の見通しについて確認していきます。IEEJも、「IEEJ Outlook」を毎年公表しており、この中では前提条件の異なる2つのシナリオを策定し、それぞれのシナリオにおけるエネルギー需給や価格の見通し等について紹介しています。1つ目の「レファレンスシナリオ」は、現在までのエネルギー・環境に係る政策や技術等を背景に、これまでの趨勢的な変化が今後も継続するとした場合のシナリオであり、2つ目の「技術進展シナリオ」は、エネルギーの安定供給の確保や気候変動対策の強化に向けた政策等が強力に実施され、最大限奏功した場合のシナリオとなっています。
2023年10月に公開された最新の「IEEJ Outlook 2024」から、2030年の化石エネルギー価格の見通しを見ていくと、IEAによる見通しと同様に、いずれのシナリオにおいても、2022年の価格水準からは下落していくことが見込まれています。しかし、2050年における化石エネルギー価格の見通しについては、IEAによる見通しとは少し異なる傾向が見られます。レファレンスシナリオにおける2050年の価格は、2030年における価格と概ね同水準になると見込まれており、中には、2030年よりも価格が上昇する見通しとなっている化石エネルギーも見られます。また、技術進展シナリオにおける2050年の価格は、2030年における価格から下落していくことが想定されていますが、その下落幅は限定的なものとなっています。IEAによる見通しと同様に、気候変動対策の進展等によって、化石エネルギーの需要は減少していくことが見込まれていますが、その際、化石エネルギーの市場自体も縮小していくこと等が影響し、化石エネルギーの価格低下が抑えられる、あるいは、価格が上昇しうるとの予測になっています(第121-2-10)。
【第121-2-10】IEEJによる化石エネルギー価格の見通し
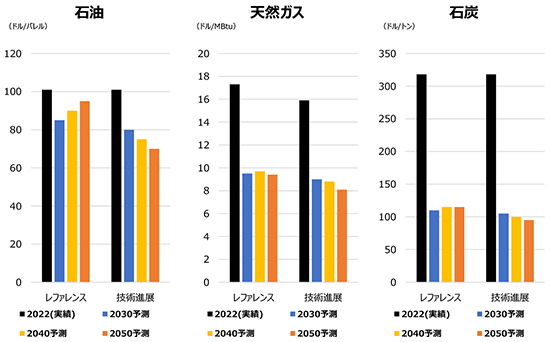
【第121-2-10】IEEJによる化石エネルギー価格の見通し(ppt/pptx形式:57KB)
- 資料:
- 日本エネルギー経済研究所「IEEJ Outlook 2024」を基に経済産業省作成
(3)さいごに
IEAとIEEJがそれぞれ策定した各シナリオでは、カーボンニュートラルの実現に向けた取組が世界各国において進められることで、化石エネルギーの需要が徐々に減少していくことが見込まれています。一般論として、化石エネルギーの需要が減少していく場合には、化石エネルギーの価格も低下していくことが想定されます。しかし、気候変動対策のさらなる強化が強く求められていることもあり、化石エネルギーの上流部門への投資減少や油田等の閉鎖等、化石エネルギーの供給についても減少していくことが想定されます。その際、化石エネルギーの供給減少の状況によっては、化石エネルギーの需要が減少したとしても、価格が下落しない可能性や、あるいは上昇するという可能性もあると考えられます。また、化石エネルギーの価格が下落した場合は、化石エネルギーの価格競争力が相対的に向上することになるため、需要の減少が想定よりも抑制されるといった可能性も考えられます。本コラムの冒頭で記載したとおり、化石エネルギーの価格は様々な要因から影響を受けて形成されるものですが、カーボンニュートラルの実現に向けた取組が世界中で進むといった大きな変化が予測される中、今後の見通しを立てることは、より一層難しいものになっています。
現在、日本を含む多くの国では、エネルギーの多くを化石エネルギーに頼っていますが、カーボンニュートラルの実現のためには、化石エネルギーへの依存度を徐々に減らしていくことが重要です。また、化石エネルギーへの依存度を逓減していくことは、カーボンニュートラルだけでなく、不確実性の高いエネルギー情勢の変化にも強い、強靱なエネルギー需給構造の実現にもつながると考えられます。しかしその際、化石エネルギーの供給側の減少が、需要側の減少速度に見合わないようなスピードで行われてしまうと、世界中でエネルギーの需給ひっ迫やエネルギー価格の高騰が発生し、ひいては世界経済の混乱等にもつながりかねません。エネルギーセキュリティの確保とカーボンニュートラルの実現は、どちらも極めて重要な課題です。これらを両立するためには、それぞれの取組を、どちらかだけに偏ることなく、両輪でバランスよく着実に進めていくことが求められています。
3.カーボンニュートラルと両立したエネルギーセキュリティ確保に向けた各国の対応
世界中でカーボンニュートラルの実現に向けた取組が進められる中、ロシアによるウクライナ侵略をはじめ、エネルギーセキュリティの確保に大きな影響を与える事象が数多く発生しています。これらを受け、世界各国では、再エネや原子力といった脱炭素電源の導入拡大に向けた投資促進策をはじめ、官民が連携しながら、カーボンニュートラルの実現とエネルギーセキュリティの確保の両立に向けた様々な取組が進められています。また、詳細については次章にて記載していますが、こうした観点から、水素やCCSの活用に向けた取組も加速しています。
本項では、こうした状況下における各国の対応や政策動向等について概観していきます。
(1)英国
英国では、2022年2月に発生したロシアによるウクライナ侵略と、それに伴うエネルギー価格の高騰を受け、同年4月に「British Energy Security Strategy」を発表し、中長期的にエネルギーセキュリティを強化していく方針を示しました。この中では、再エネや原子力、水素等の国産エネルギーへ移行していくことが重要視されており、再エネに関しては、洋上風力や太陽光を中心にさらなる導入拡大に向けた新たな目標が掲げられ、原子力に関しては、2030年までに最大8基の原子炉の新設に対する投資決定を行うことや、2050年までに現状の3倍以上となる最大24GWの出力を整備し、電力需要の25%を賄うこと等が示されました。また、この戦略では、石油やガスについても言及されており、英国内で生産することは、海外から輸入するよりもCO2の排出が少なくなることを踏まえ、新規の北海石油・ガスプロジェクトの認可プロセスを開始していくことが示されています。
その後、2023年3月には、エネルギーセキュリティの向上と電気料金の低減、排出削減の両立を目指した野心的な計画「Powering Up Britain」を公表しました。この中では、安価でクリーンな国産電力を拡大していくことの必要性が掲げられており、洋上風力やグリーン水素等のプロジェクトへの支援策等が記載されています。さらに、2024年1月には、2050年に向けた民生用原子力のロードマップが示されました。このロードマップには、原子力なしではネットゼロの達成もエネルギーセキュリティの確保も困難であるとの考えの下、大規模な原子力発電所の新設プロジェクトの検討を進めていくことや、次世代原子炉で使用する燃料の国産化に向けた支援を行っていくこと等が盛り込まれています。
(2)フランス
過去からエネルギーの多くを原子力により確保してきたフランスでは、エネルギーセキュリティの確保とカーボンニュートラルの実現に向けて、再エネと原子力の活用が進められてきましたが、2023年11月に発表された「エネルギー・気候戦略」においても、こうした方針が反映されています。この戦略の中で、再エネに関しては、太陽光や風力、バイオガス等を中心に導入をさらに拡大していくことが示され、それぞれの導入目標についても掲げられました。また、フランスで推進されてきた原子力に関しては、既存の原子力発電所の運転期間延長の検討等に加え、2022年2月に打ち出されていたEPR2(改良型欧州加圧水型炉)の建設に向けた取組を進めていくための具体的なスケジュール等が示されました。この戦略の中で、2024年末に最終決定を行うことが示された6基のEPR2の建設については、2023年7月に建設予定地(計3か所)も決定される等、具体的な動きが既に加速しています。
また、フランスでは、エネルギーセキュリティの確保に向けて、エネルギー産業への政府の関与を強化する目的で進められてきた、フランス最大の電力会社である「フランス電力(EDF)」の国有化についても、2023年6月に完了しています。このことにより、再エネや原子力の導入拡大に向けた取組をはじめ、エネルギーセキュリティの確保等に向けた様々な取組が、政府主導の下で一層強力に推進されることが想定されています。
さらに、2023年3月には、フランスと英国間において、両国のエネルギーセキュリティの向上を促進するための新たな協定(パートナーシップ)も締結されました。この中では、化石エネルギーから再エネと原子力への移行を促進していくことが掲げられており、具体的には、ウランの供給源や核燃料の生産能力の多様化に関する協力や、両国をつなぐ国際連系線の増強に関する協力等を強化していく旨が示されています。
このように、フランスでは、主に再エネ及び原子力の導入を拡大させることで、エネルギーセキュリティの確保に努めていますが、化石エネルギーの安定的な確保に向けた取組も進められています。2023年10月に、カタールの国営会社であるカタールエナジーは、フランスのトタルエナジーズとLNGの長期契約を結んだことを発表しました。この長期契約は、2026年から27年間にわたるものとされています。
(3)その他欧州諸国
その他の欧州諸国においても、エネルギーセキュリティの確保に向けた取組が盛んに行われています。前述のとおり、フランスのトタルエナジーズはカタールエナジーとLNGの長期契約を締結しましたが、これと同時期に、イタリアのエニもカタールエナジーとLNGの長期契約を締結しました。なお、2022年11月には、カタールエナジーからドイツへのLNG供給に関する長期契約も締結されています。ドイツでは、2024年2月に、燃料を将来的に脱炭素燃料である水素に変更可能(水素レディ)な天然ガス火力発電の新設(計10GW分)への支援を行うことも発表されています。2023年4月に「脱原子力」が完了し、再エネの導入拡大が急速に進むドイツでは、電力の安定供給の確保に向けて、天然ガス火力が再エネの出力変動をカバーする「調整力」として期待されています。
また、欧州では、原子力政策の方針を、推進の方向へと見直す国も登場しています。スウェーデンでは、2022年10月に、新たなサイトでの原子炉の建設を禁止する規制や運転中の原子炉の数を10基までに制限する規制等を撤廃し、原子力発電所の新規建設を推進していく等の方針が示されました。2023年には、こうした規制を撤廃するための改正法案が議会において承認されるとともに、2035年までに少なくとも大型原子炉2基分の原子力発電設備を建設し、2045年までに新たに大型原子炉10基分の設備を追加することを想定したロードマップも公表されており、原子力の導入拡大に向けた取組が急速に進められています。また、スウェーデンと同じ北欧のノルウェーでは、国内初の商業用原子力発電所となる小型モジュール炉(以下「SMR」という。)の建設に向けた動きが見られており、さらに、原子力の活用に慎重な方針であったイタリアにおいても、原子力利用の可能性に関する議論が2023年9月から開始されています。
(4)米国
国内に化石エネルギー資源があり、エネルギー自給率も100%を超えていることから、欧州諸国等と比べると、ロシアによるウクライナ侵略等の影響が小さかったとされる米国ですが、他国と同様に、エネルギーセキュリティの確保と排出削減を目的に、再エネや原子力等の拡大に向けた動きが進んでいます。2022年8月に成立した「インフレ削減法11」では、エネルギーセキュリティと気候変動対策に関する分野に対して、10年間で3,690億ドル(1ドル140円換算で約52兆円)の国による支援策が打ち出されました。この中で、特に大きく掲げられているのは、太陽光・風力・地熱・バイオマス等の再エネや原子力といったクリーン電力への移行を促進するための支援策です。再エネの導入を加速するために、再エネ関連の設備投資に対する投資税額控除や生産税額控除等の支援策が講じられており、原子力に関しても、生産税額控除等の支援策が設けられています。その他にも、インフレ削減法では、バイオ燃料やクリーン水素等のクリーン燃料、蓄電池や太陽光パネル等のクリーン製造業等に対する支援策が講じられています。
2023年12月には、ホワイトハウスからこうした取組の進捗と効果が発表されました。この中では、インフレ削減法の成立以降、特に太陽光発電と風力発電の生産能力の拡大に向けた取組に顕著な進展が見られることが紹介されており、この結果、2030年における太陽光発電の設備容量の見通しが、2021年に予測した数値の約2倍に増加しており、さらに風力発電の設備容量の見通しについても、2021年の予測から43%増加していると示されました。また、太陽光発電や風力発電の導入加速に伴い、さらに重要性の高まる系統用蓄電池に関しても、直近の1年間で貯蔵容量が2倍以上に増加しており、2024年にはさらに2倍に増加する見込みであること等が紹介されました。
(5)韓国
日本と同様に、化石エネルギー資源に乏しい韓国では、かつて原子力の割合を減らしていく方針が示されていましたが、2022年5月に発足した尹錫悦(ユン・ソンニョル)政権では、エネルギーセキュリティの確保とカーボンニュートラルの実現の両立を目的に、その方針を撤回しています。2023年1月に公表された「第10次電力需給基本計画」においては、既存の原子力発電所の運転継続や建設計画が止まっていた新規の原子力発電所の建設再開等を通じて、原子力の割合を約35%に高めていくとともに、再エネの割合についても、太陽光や風力等のそれぞれの特性を考慮しながら、約31%へと高めていく方針が示されています。
(6)その他アジア諸国
エネルギーの多くを化石エネルギーに依存しており、近年の化石エネルギー価格の高騰の影響を受けたアジア諸国においても、エネルギーセキュリティの確保と排出削減の観点から、再エネの導入拡大に向けた取組とともに、原子力の導入に向けた検討が進んでいます。インドネシアでは、国内初となる原子力発電所の建設に向けた取組が行われており、2023年3月には、米国がインドネシアのSMRの建設を支援することも発表されています。フィリピンにおいても、2032年に原子力発電所を国内で初めて稼働させることを目標に、様々な取組が進められています。2023年11月には、フィリピンと米国が原子力協定を締結しました。これにより、SMR等に関する米国の先進的な技術等も活用しながら、フィリピンにおける原子力の導入に向けた取組が進められていくと考えられます。
4.まとめ
第一次オイルショックが発生した50年前の状況と、今の状況を比べると、エネルギーを取り巻く環境には様々な変化が見られます。しかし、そうした中でも、「エネルギーセキュリティの確保」という課題が、世界各国にとって最重要の課題であることは通底しています。世界的にカーボンニュートラルの実現に向けた取組の強化が求められていることもあり、エネルギーセキュリティの確保という課題は、ますます解決するのが難しい課題になっていますが、本節において見てきたように、世界各国においては、その解決に向けた様々な取組が進められています。
次節では、エネルギーセキュリティに関する日本の状況等について確認していきます。
- 1
- 2022年度の日本の原油輸入のうち、約95%が中東地域からの輸入です(第213-1-3参照)。
- 2
- コンテナの海上輸送の運賃は、新型コロナ禍からの経済回復等による世界的な海上輸送の需給ひっ迫や原油価格の高騰等を背景に、2020年末頃から急騰しましたが、2022年半ば以降、海上輸送の需給の緩和等の影響で下落傾向に転じました。
- 3
- 2022年度の日本のLNG輸入のうち、約43%が豪州からの輸入であり、最大のシェアを占めています(第213-1-10参照)。
- 4
- ストライキの対象プロジェクトとなった「ゴーゴン」・「ウィートストーン」は、合計で年間2,450万トンのLNG生産能力を有しています。なお、これを2022年に世界全体で取引されたLNG貿易量(38,920万トン)で割ると、その割合は約6%となります。
- 5
- ロシアからドイツ経由で欧州に天然ガスを供給していた海底パイプライン。
- 6
- JKM:Japan Korea Markerの略。
- 7
- Energy Instituteの「Statistical Review of World Energy」の各年版を用いています。なお、「Statistical Review of World Energy」は、2022年版までBPより公表されていましたが、2023年版からEnergy Instituteより公表されています。
- 8
- STEPS:Stated Policies Scenarioの略。
- 9
- APS:Announced Pledges Scenarioの略。
- 10
- NZE:Net Zero Emission by 2050 Scenarioの略。
- 11
- 「Inflation Reduction Act(IRA)」のことで、インフレ抑制法とも呼ばれています。