第2節 一次エネルギーの動向
1.化石エネルギーの動向
(1)石油
①資源の分布
世界の石油確認埋蔵量は、2020年末時点で約1.7兆バレルであり、これを2020年の石油生産量で除した可採年数は53.5年となりました。1970年代には石油資源の枯渇が懸念されましたが、回収率の向上や新たな石油資源の発見・確認により、1980年代以降は40年程度の可採年数を維持し続けてきました。近年は、米国のシェールオイルや、ベネズエラやカナダにおける超重質油の埋蔵量が確認され、可採年数は増加傾向となっています。
2020年末時点で世界最大の確認埋蔵量を有するのはベネズエラであり、そのシェアは17.5%でした。長年1位であったサウジアラビアは2010年以降2位となっており、そのシェアは17.2%でした。3位はカナダですが、その後はイラン、イラク、ロシア、クウェート、アラブ首長国連邦の順となっており、主に中東諸国が続きます。中東諸国だけで、世界全体の確認埋蔵量の約半分を占めています(第22-1-1)。
【第22-1-1】世界の石油確認埋蔵量(2020年末)
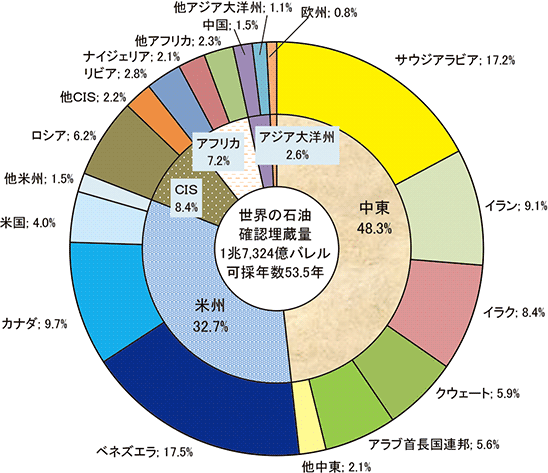
【第22-1-1】世界の石油確認埋蔵量(2020年末)(xlsx形式:27KB)
- 資料:
- Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2024」を基に作成(埋蔵量データは2022年版から更新なし)
近年では、在来型石油とは異なる生産手法を用いて生産されるシェールオイル(タイトオイル)が注目されています。2015年の米国エネルギー情報局(EIA)による発表では、世界のシェールオイルの可採資源量1は4,189億バレルと推定されており、主なシェールオイル資源保有国は、米国、ロシア、中国、アルゼンチン、リビア等となっています(第22-1-2)。
【第22-1-2】EIAによるシェールオイル・シェールガス資源量評価マップ(2015年)
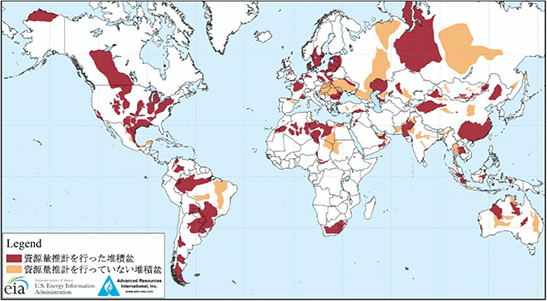
【第22-1-2】EIAによるシェールオイル・シェールガス資源量評価マップ(2015年)(pptx形式:1,120KB)
- 資料:
- EIA「World Shale Resource Assessments」(2015年9月)を基に作成
②生産の動向
世界の原油生産は、第一次オイルショックが発生した1973年から2023年にかけて約1.6倍に拡大しました。地域別に見ると、2000年以降、中東や北米等で生産が拡大しました(第22-1-3)。
【第22-1-3】世界の原油生産の推移(地域別)
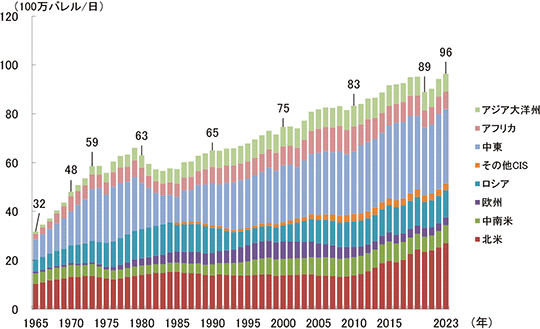
(注)1984年以前の「ロシア」には、その他旧ソ連邦諸国を含む。
【第22-1-3】世界の原油生産の推移(地域別)(xlsx形式:37KB)
- 資料:
- Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2024」を基に作成
OPEC産油国(サウジアラビア、イラン、イラク、クウェート、アラブ首長国連邦、ベネズエラ等)の生産は、1970年代までの大幅増産後、高い原油価格を背景とする非OPEC産油国の増産や世界の石油消費の低迷を受け、1980年代前半に減少しましたが、1980年代後半から回復しました。この結果、世界全体の原油生産に占めるOPECのシェアは、1973年の50%から低下し、1980年代半ばには30%を一時割り込んだものの、その後は再び上昇し、1990年代以降は40%前後の水準で推移しています。
非OPEC産油国(旧ソビエト連邦諸国(CIS)、米国、メキシコ、カナダ、英国、ノルウェー、中国、マレーシア等)の生産量は、1965年に1,809万バレル/日でしたが、2023年には6,233万バレル/日にまで達しています。近年では、シェールオイル生産の技術革新(シェール革命)により、急速に生産を拡大させている米国の動向が注目されています(第22-1-4)。
【第22-1-4】世界の原油生産の推移(OPEC・非OPEC別)
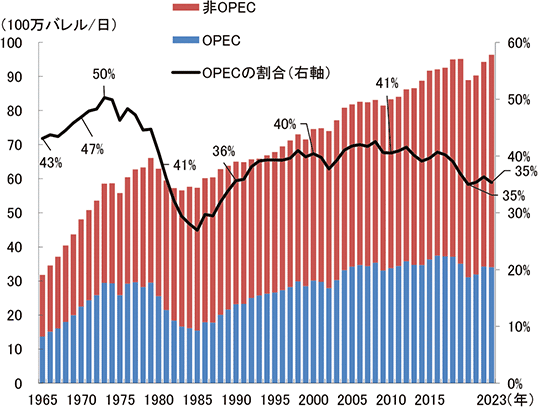
(注)「非OPEC」には、ロシア等の旧ソ連邦諸国を含む。
【第22-1-4】世界の原油生産の推移(OPEC・非OPEC別)(xlsx形式:28KB)
- 資料:
- Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2024」を基に作成
米国における原油生産は、原油価格が高水準であった2010年代前半に急拡大しました。その後は原油価格の下落に伴い、生産が一時減少しましたが、シェールオイルの開発・生産コストの低下も進んだことで、2010年代後半には再び増加しました。2023年は2021年ころからの原油価格の上昇もあり、生産量は過去最高となりました(第22-1-5)。
【第22-1-5】米国のシェールオイル生産の推移
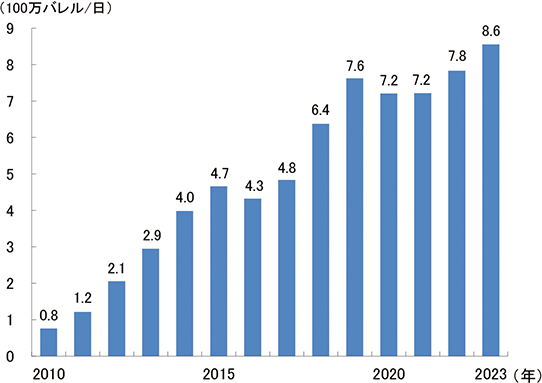
【第22-1-5】米国のシェールオイル生産の推移(xlsx形式:19KB)
- 資料:
- EIA「Tight oil production estimates」を基に作成
2010年代前半のシェールオイルの増産に対して、OPEC産油国は当初、市場シェアの確保を重視して増産で対抗したため、世界では供給過剰の状態が続き、その後の原油価格の低迷を招くことになりました。こうした中、OPEC2と非OPEC産油国は、長引く価格低迷を打開するため、2016年11月から12月に開催された第171回OPEC総会及び第1回OPEC・非OPEC閣僚会議において、15年ぶりの協調減産に合意しました。これを契機に、協調減産に参加したOPEC・非OPEC産油国は「OPECプラス3」と呼ばれるようになりました。
その後もOPECプラスは、原油価格を一定の範囲内に収めることを目的に、市場環境(原油の需給動向、在庫状況等)にあわせて、参加国間で生産調整を続けました。しかし、世界中で新型コロナ禍の影響が顕著になり始めた2020年3月のOPECプラス閣僚会議では、協調減産量の拡大について議論されたものの合意に至らず、協調減産は同月末で終了することになりました。直後に、サウジアラビアやアラブ首長国連邦は同年4月からの増産を打ち出したものの、その後の原油価格の急落を受け、同年4月に再びOPECプラス閣僚会議が開催されました。そして、二度の会議を経て、新型コロナ禍の影響による原油需要の急減への対応のため、OPECプラスで970万バレル/日という、かつてない規模の減産を行うことで合意しました。この減産合意は同年7月末まで維持されましたが、世界経済が徐々に回復傾向にあるとの見方から、OPECプラスはその後、徐々に減産幅を縮小し、2022年8月には減産幅がゼロになりました。
その後、OPECプラスは、世界的な景気減速への懸念により、同年11月から200万バレル/日の大幅協調減産を行うことで合意し、2024年1月からはこれを291万バレル/日に拡大しました。
加えて、2023年4月には、サウジアラビア、ロシアを含む一部の産油国が協調減産に加えて166万バレル/日の自主減産を実施する旨を発表しました。その後、2023年11月のOPECプラス閣僚会合において、2024年第1四半期にサウジアラビア、ロシアを含む一部の産油国が220万バレル/日の追加の自主減産を実施する方針を発表しました。自主減産は需要の回復を待って解除する目算でしたが、需要の低迷が続いたことを受けて2024年3月、6月、9月、11月にこの追加の自主減産の方針が延長され、2024年12月まで延長する旨を発表しました(第22-1-6)。
【第22-1-6】OPEC/非OPECの減産目標値の推移
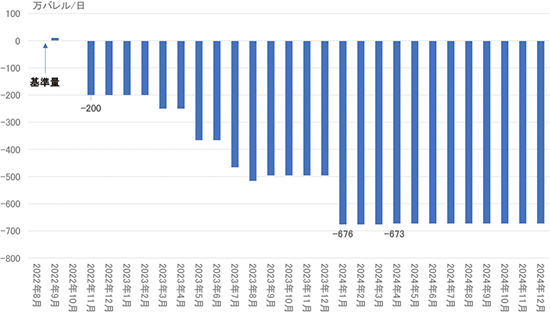
(注1)2022年8月を基準量としている。
(注2)2024年1月1日にアンゴラがOPECを脱退したため、2024年1月以降のデータについては、アンゴラを集計の対象外としている。
【第22-1-6】OPEC/非OPECの減産目標値の推移(xlsx形式:19KB)
- 資料:
- OPECプレスリリースを基に作成
③消費の動向
世界の石油消費は経済成長とともに増加し、1973年の5,606万バレル/日から、2023年には10,022万バレル/日となりました。
1973年に4,185万バレル/日であったOECD諸国の石油消費は、2023年には4,473万バレル/日となりました。1980年代半ば以降、経済成長とともに緩やかに増加しましたが、自動車の燃費改善や世界的な気候変動対策の高まり等を背景として、2005年をピークに減少傾向にあります。
一方、非OECD諸国では石油消費が著しく増加しています。堅調な経済成長に伴い、1973年の1,421万バレル/日から、2023年には5,549万バレル/日となりました。その結果、世界の石油消費に占める非OECD諸国のシェアは、1973年の25%から2023年には55%まで拡大しました(第22-1-7)。
【第22-1-7】世界の石油消費の推移(地域別)
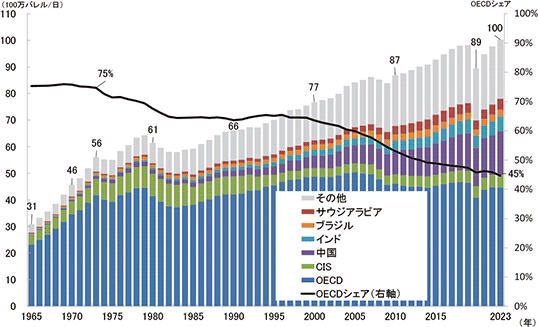
【第22-1-7】世界の石油消費の推移(地域別)(xlsx形式:239KB)
- 資料:
- Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2024」を基に作成
石油は様々な用途で消費されますが、輸送用としての消費が大きな割合を占めており、2022年における世界の石油消費のうち、63%が輸送用となっています。輸送用の消費は自動車保有台数の増加に伴って増えており、世界の石油消費の増加の主要因となっています。また、石油化学原料用としての消費も堅調に増加しています(第22-1-8)。
【第22-1-8】世界の石油消費の推移(用途別)
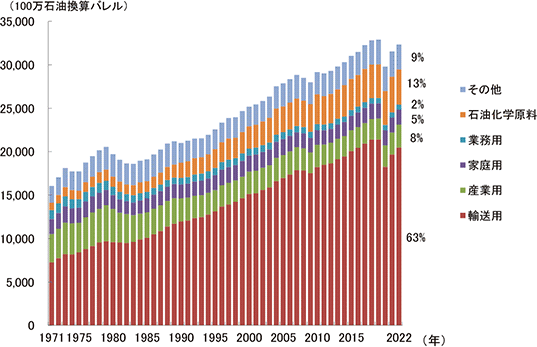
【第22-1-8】世界の石油消費の推移(用途別)(xlsx形式:282KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2024」を基に作成
④貿易の動向
世界の石油貿易は、石油消費の増加とともに拡大してきました。2023年の世界全体の石油貿易量は6,955万バレル/日であり、そのうち日米欧による輸入が38%を占めました。
輸出面では、中東からの輸出が2,362万バレル/日と最大のシェアを誇っており、全体の34%を占めました。中東からの輸出のうち、74%がアジア大洋州向けであり、中東にとってアジア大洋州が最大の市場となっています。中東以外では、北米、欧州、アフリカ、等が主要な輸出地域となっています(第22-1-9)。
【第22-1-9】世界の主な石油貿易(2023年)
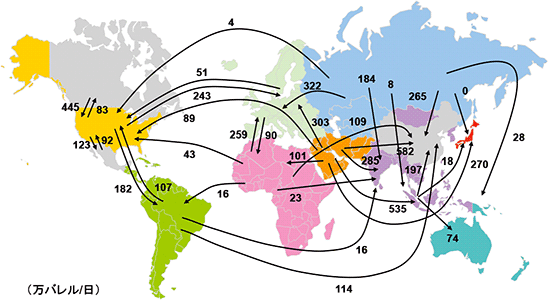
(注)数値は原油及び石油製品の貿易量を表す。
【第22-1-9】世界の主な石油貿易(2023年)(pptx形式:203KB)
- 資料:
- Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2024」を基にEnergy Instituteの換算係数を使用して作成
また、石油が輸送される際の安全確保は、エネルギー安全保障上、非常に重要です。海上輸送ルートとして世界的に広く使われる狭い海峡のことを「チョークポイント」と呼びます。本項でのチョークポイントについては、EIAが示したレポートにあるチョークポイント8か所(ホルムズ海峡、マラッカ海峡、バブ・エル・マンデブ海峡、スエズ運河、トルコ海峡、パナマ運河、デンマーク海峡4、喜望峰)を使用します。
各国の輸入する原油がこれらのチョークポイントを通過することをリスクと捉え、チョークポイント比率を算出しました。例えば、欧州諸国の場合、チョークポイントを通過するのは中東から輸入する原油にほぼ限られるため、チョークポイント比率が比較的低くなります。他方で、日本を含む東アジア諸国の場合、中東から輸入する原油の大半は、ホルムズ海峡とマラッカ海峡の二つを通過することになります。複数のチョークポイントを通過することになるため、東アジア諸国のチョークポイント比率は高くなっています(第22-1-10)。
【第22-1-10】チョークポイントリスクの推移(推計)
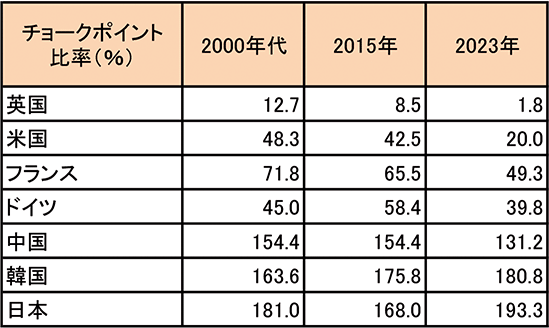
(注1)チョークポイントを通過する各国の輸入原油の数量を合計した上で、総輸入量に対する比率をチョークポイント比率として算出している。チョークポイントを複数回通過する場合は、数量を都度計上するため、チョークポイント比率は100%を超えることもある。
(注2)チョークポイント比率が低いほど、チョークポイントを通過せずに輸入できる原油が多いため、リスクが低いという評価になる。
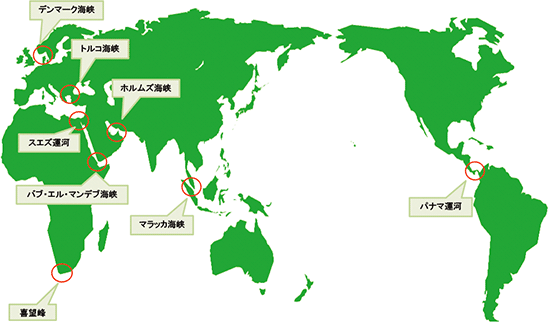
- 資料:
- IEA「Oil information 2024 database」、中国輸入統計を基に作成
【第22-1-10】チョークポイントリスクの推移(推計)(xlsx形式:55KB)
⑤価格の動向
原油価格は、これまで大きな変動を繰り返してきました。2000年代半ば以降、中国等の非OECD諸国において石油需要が急増したことを受けて上昇した原油価格は、2008年に発生した世界金融危機に伴い急落しました。2000年代半ば以降、中国等の非OECD諸国において石油需要が急増したことを受けて上昇した原油価格は、2008年に発生した世界金融危機に伴い石油需要の急減に伴い急落しました。しかしその後は、世界経済の回復やOPEC産油国の減産等により、原油価格は上昇に転じ、2010年代前半は高い水準で推移しました。2014年の夏以降は、米国を筆頭とする非OPEC産油国による生産増加と、これに対抗する形でOPECが市場シェアの確保を重視して増産したこと、そして非OECD諸国の経済成長の減速に伴う石油需要の伸びの鈍化等を受け、原油価格は再び急落しました。その後は、2017年からのOPECプラスの協調減産の効果もあり、原油価格は回復しました。
しかし、2020年に入り、世界中で新型コロナ禍の影響が顕著になる中、徐々にOPECプラスの足並みが揃わなくなり、同年3月末に協調減産体制は終了しました。これに伴い、サウジアラビアやアラブ首長国連邦は同年4月からの増産を打ち出したものの、新型コロナ禍による移動制限や経済活動の停滞に伴い、世界の原油需要が急減したことで、原油価格は大幅に下落し、同月にはWTI原油で一時マイナス価格5を記録しました。これを受け、OPECプラスは再び協議を行い、970万バレル/日というかつてない規模の減産に合意しました。その後、世界経済が徐々に回復傾向にあるとの見方から、同年8月以降、OPECプラスは協調減産幅を段階的に縮小し、同年秋以降には、経済活動が徐々に再開される中で、石油需要が増加するとともに減産の効果も見られ、原油価格は上昇していきました。その後、2022年2月に発生したロシアによるウクライナ侵略等の影響により、原油価格は同年3月に急上昇しましたが、中国の一部都市におけるロックダウンや消費国による備蓄石油の放出等により下落しました。
2023年に入ってからは、同年4月にOPECプラス参加国の一部が自主減産の実施を発表したことで、需給ひっ迫の懸念が高まり、原油価格が一時上昇しましたが、米国の景気後退への懸念等により下落しました。その後、サウジアラビアとロシアが石油の自主的な供給削減を同年末まで延長すると表明したことや、イスラエル・パレスチナ情勢が悪化したこと等を受け、原油価格は再び上昇しましたが、その後は、米国と中国における需要減退への懸念や、中東情勢が緊迫化しているものの原油生産に直接的な影響が出ていないこと等により、原油価格は下落傾向へと転じました(第22-1-11)。
【第22-1-11】国際原油価格の推移
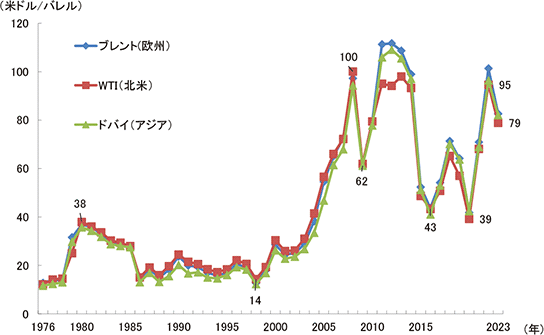
(注)数値はWTIの価格。
【第22-1-11】国際原油価格の推移(xlsx形式:26KB)
- 資料:
- Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2024」を基に作成
2024年に入ると、ウクライナによるロシアの製油所に対する攻撃や、イスラエルとイラン・イエメンのフーシー派・レバノンのヒズボラ間の情勢の緊迫化、OPECプラス参加国による自主減産の延長等の影響による短期的な原油価格の上昇局面はあるものの、4月以降は中国やインドなどの需要の弱さを背景に、原油価格は概ね下落傾向となっています。
(2)ガス体エネルギー
①天然ガス
(ア)資源の分布
世界の天然ガスの確認埋蔵量は、2020年末時点で188.1兆㎥でした。中東のシェアが40.3%と高く、欧州・ロシア・その他旧ソ連邦諸国が31.8%で続きます。石油埋蔵量の分布と比べると、天然ガス埋蔵量の地域的な偏りは比較的小さいといえます。また、2020年末時点の確認埋蔵量を2020年の生産量で除した天然ガスの可採年数は、48.8年でした(第22-1-12)。
【第22-1-12】世界の天然ガス確認埋蔵量(2020年末)
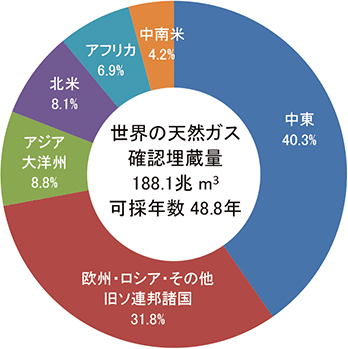
【第22-1-12】世界の天然ガス確認埋蔵量(2020年末)(xlsx形式:20KB)
- 資料:
- Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2024」を基に作成(埋蔵量データは2020年末が最新)
近年は、シェールガスや炭層メタンガス(CBM)といった非在来型天然ガスの開発が進展しており、特にシェールガスは多くの資源量が見込まれています。2015年のEIAの発表によると、シェールガスの技術的回収可能資源量は、評価対象国の合計で214.4兆㎥とされており、在来型天然ガスの確認埋蔵量よりも多いと推計されています。
(イ)生産の動向
天然ガスの生産は増加傾向にあり、1990年から2023年にかけて2.1倍となっています。2023年における世界の天然ガスの生産を地域別に見ると、北米が世界全体の31%、欧州・ロシア・その他旧ソ連邦諸国が24%を占めていることがわかります。シェール革命により生産が増加している米国を中心とした北米や、国内の天然ガス需要が急増している中国やLNGプロジェクトの開発が相次いだ豪州を抱えるアジア大洋州、世界最大級の構造性ガス田を有し、石油に依存した経済からの脱却を図る中東等において、天然ガスの生産が増加傾向にあります(第22-1-13)。
【第22-1-13】世界の天然ガス生産の推移(地域別)
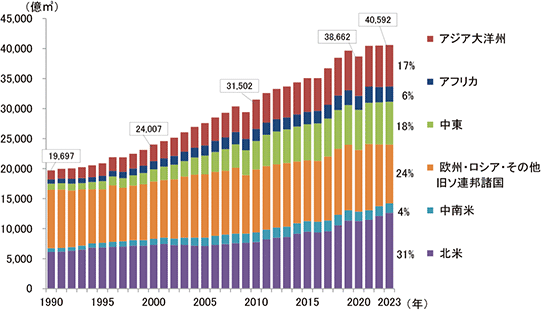
【第22-1-13】世界の天然ガス生産の推移(地域別)(xlsx形式:30KB)
- 資料:
- Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2024」を基に作成
世界的な天然ガスの需要増加に対応するため、大規模な天然ガスの資源開発が進められています。また、豪州や米国での新規LNGプロジェクトの稼働開始により、LNGの供給も増加しています。堅調なLNG需要に対応していくためには、今後も新規プロジェクトへの投資が必要と考えられます(第22-1-14)。
【第22-1-14】日本企業が参画する近年の主要なLNGプロジェクトの例
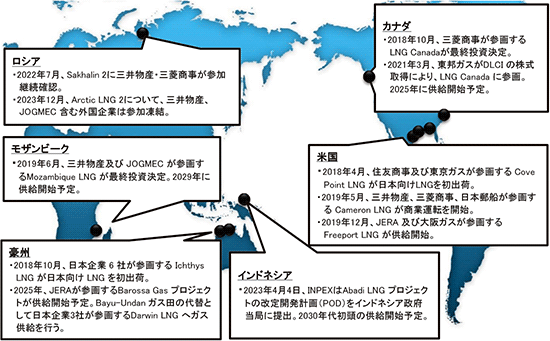
【第22-1-14】日本企業が参画する近年の主要なLNGプロジェクトの例(pptx形式:1,301KB)
- 資料:
- 各種資料を基に作成
さらに、脱炭素燃料として注目される水素やアンモニアの原料とする技術等、天然ガスの新たな利用可能性を広げる技術についても研究開発が進展しており、一部では既に商業生産が行われています。
また、世界各地でシェールガスやCBM等の非在来型天然ガスの開発計画が立てられており、特に米国でのシェールガスの増産が顕著です。EIAによると、米国のシェールガス生産は2007年から急増しており、2023年には9,824億㎥に達しています(第22-1-15)。
【第22-1-15】米国の在来型ガス・シェールガス等の生産の推移
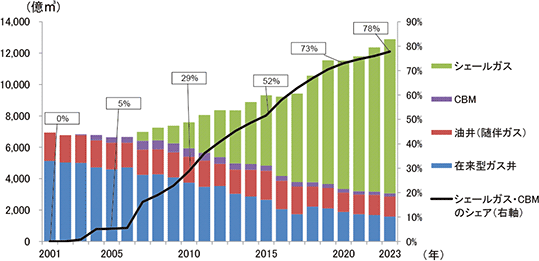
(注)在来型ガスは、ガス層を目指して掘削したガス生産専用井により回収している。
【第22-1-15】米国の在来型ガス・シェールガス等の生産の推移(xlsx形式:27KB)
- 資料:
- EIA「Natural Gas Data」を基に作成
(ウ)消費の動向
世界の天然ガス消費は、1990年から2023年にかけて2.1倍に増加しています。天然ガスは、石炭や石油に比べて環境負荷が低いことに加え、コンバインドサイクル発電6等の技術進展等もあり、その利用が拡大してきました。
天然ガス消費の推移を地域別に見ると、北米と欧州・ロシア及びその他旧ソ連邦諸国における消費が過去から多いことがわかります。その背景として、地域内で天然ガスが豊富に生産されることから、早くから産業用や暖房用等への天然ガスの利用が進んできたことや、パイプライン等のインフラが整備されており、天然ガスを気体のまま大量に輸送して安価に利用できる環境にあること等が挙げられます(第22-1-16)。
【第22-1-16】世界の天然ガス消費の推移(地域別)
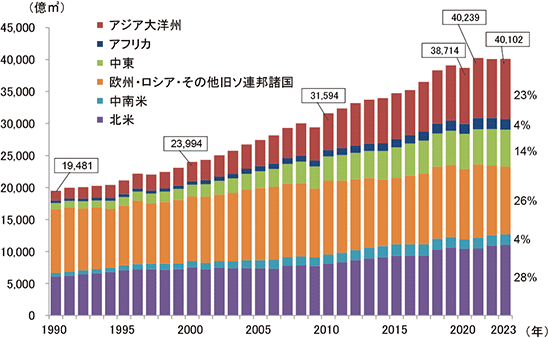
【第22-1-16】世界の天然ガス消費の推移(地域別)(xlsx形式:42KB)
- 資料:
- Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2024」を基に作成
日本・米国・OECD欧州における、2022年の一次エネルギー供給に占める天然ガスの割合を見ると、米国は35%、OECD欧州は24%となっていることがわかります。日本は21%であり、OECD欧州との差は3%です(第22-1-17)。
【第22-1-17】日本・米国・OECD欧州の一次エネルギー構成(2022年)
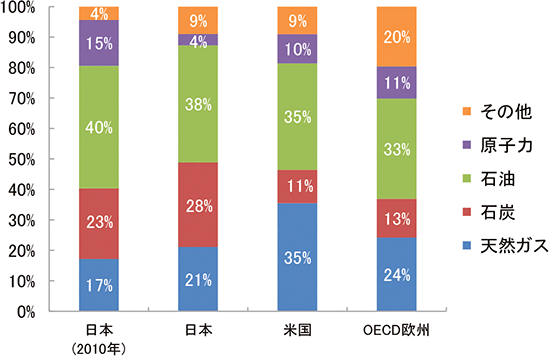
【第22-1-17】日本・米国・OECD欧州の一次エネルギー構成(2022年)(xlsx形式:29KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2024」を基に作成
しかし、天然ガスの用途を見ると、日本と欧米とでは大きな差異があることがわかります。日本では発電用の割合が全体の67%を占めていますが、米国やOECD欧州では発電用の割合がそれぞれ39%、30%と日本よりも低く、民生・その他用や産業用の割合が高くなっています(第22-1-18)。
【第22-1-18】日本・米国・OECD欧州の天然ガス利用状況(2022年)
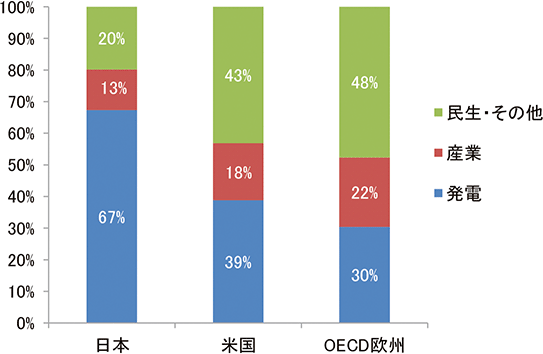
【第22-1-18】日本・米国・OECD欧州の天然ガス利用状況(2022年)(xlsx形式:18KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2024」を基に作成
日本では、LNGという形態でしか天然ガスを輸入できなかったため、需要が集積しやすい発電用や、一定規模以上の大手都市ガス会社による利用を中心に導入が進んできました。この結果、天然ガスの需要がある地域にLNG基地が順次立地し、LNG基地からパイプラインが需要に応じて徐々に延伸するという日本特有のインフラ形態となりました。そのため、発電用と比べて需要が地理的に分散している民生用や産業用では、天然ガスの利用が相対的に遅れています。
(エ)貿易の動向
2023年に取引された天然ガスのうち、パイプラインによる取引は55%、LNGによる取引は45%でした。LNGによる取引の割合は年々増加傾向にあります(第22-1-19)。
【第22-1-19】世界の天然ガス貿易量の推移(輸送方式別)
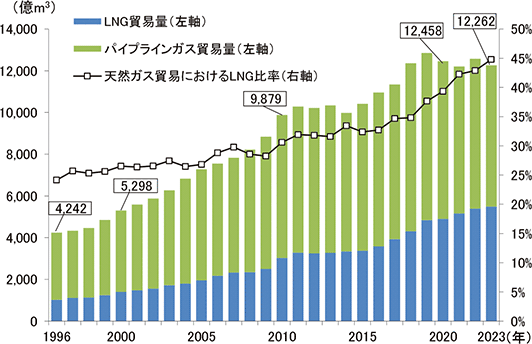
(注)2008年以前のデータには、旧ソ連域内における貿易量を含んでいない。
【第22-1-19】世界の天然ガス貿易量の推移(輸送方式別)(xlsx形式:26KB)
- 資料:
- Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2024」を基に作成
また、2023年に世界全体で生産された天然ガスのうち、30.2%が生産国では消費されずに、他国へ輸出されました。その割合は、生産量の70.7%が他国へ輸出される石油とは大きく異なっています(第22-1-20)。
【第22-1-20】石油・天然ガスの貿易比率(2023年)
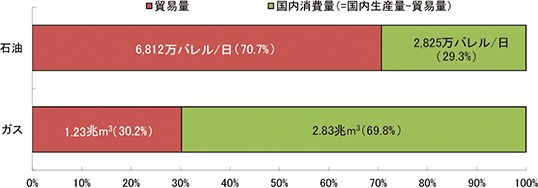
【第22-1-20】石油・天然ガスの貿易比率(2023年)(xlsx形式:22KB)
- 資料:
- Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2024」を基に作成
天然ガスの主な輸入地域は欧州と北東アジアであり、その他は地域内での輸出入が主となっています。2023年の世界の天然ガスの貿易を輸送方式別に見ていくと、パイプラインによる貿易については、ロシアやノルウェー、カナダ等が主な輸出国となっており、主な輸入国は米国7、ドイツ等でした。また、LNGによる貿易については、アジア向けの輸出が中心となっており、2023年の世界全体のLNG貿易の64%はアジア向けでした。なお、日本向けの輸出は世界全体の16%を占めており、2023年は日本が世界第2位のLNG輸入国でした。LNGの輸出国については、カタール、豪州、米国が中心でした(第22-1-21、第22-1-22)。
【第22-1-21】世界の主な天然ガス貿易(2023年)
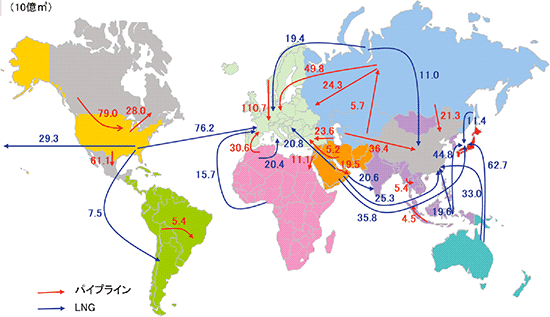
(注)日本付近を指している青色の矢印に記載されている数値は、日本・韓国・台湾によるLNG輸入の合計値。
【第22-1-21】世界の主な天然ガス貿易(2023年)(pptx形式:291KB)
- 資料:
- Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2024」を基に作成
【第22-1-22】世界のLNG輸入(2023年)
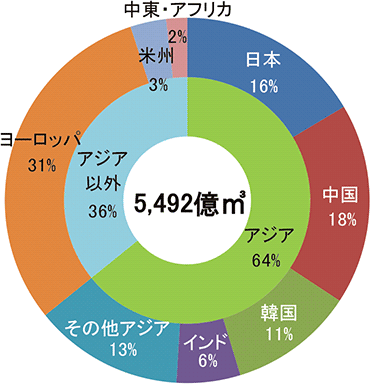
【第22-1-22】世界のLNG輸入(2023年)(xlsx形式:25KB)
- 資料:
- Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2024」を基に作成
(オ)価格の動向
日本向けの天然ガス(LNG)CIF価格8(年平均)は、1990年代には3~4ドル/MMBTU(百万BTU)(以下「ドル」という。)、2000年代前半には4~6ドルの水準で推移しましたが、その後は原油価格に連動して上昇し、2014年にかけて高い水準が続きました。2014年は約16ドルとなり、米国の天然ガス価格(Henry Hub9スポット価格)や英国、オランダの天然ガス価格と比べて割高でした。これは、アジア市場においてLNGの需給がひっ迫していたことに加え、日本向けのLNG価格は原油価格を参照して決められるものが多く、原油価格の上昇の影響を大きく受けたことが原因です。しかし、その後は原油価格の下落及びLNGの需給緩和に伴い、日本と欧米の価格差は縮小しました。
そうした中、2021年より上昇傾向となっていた天然ガス価格は、ロシアによるウクライナ侵略が発生した2022年2月以降の地政学的な緊張の中で、さらに不安定な状態となりました。日本向けのLNG価格は、原油価格に連動する長期契約が7~8割を占めていたこともあり、欧州ほどの急激な変動はなかったものの、原油価格の高い状態が続いたことから、2022年には年平均で史上最高値となる約17ドルに達しました(第22-1-23)。
【第22-1-23】天然ガス・LNG価格の推移
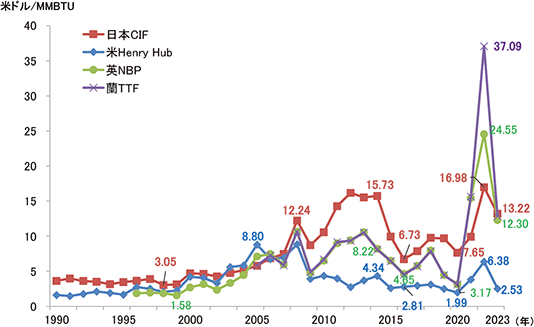
【第22-1-23】天然ガス・LNG価格の推移(xlsx形式:29KB)
- 資料:
- Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2024」を基に作成
なお、2023年の世界のLNG取引全体に占めるスポット及び短期取引の割合は、約39%とされています(第22-1-24)。
【第22-1-24】世界のLNG取引全体に占めるスポット及び短期取引の割合(2023年)
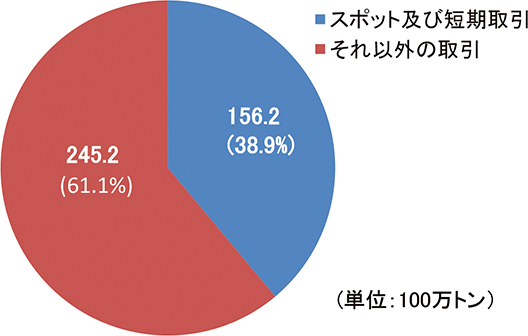
(注)「スポット取引」は1年未満の取引、「短期取引」は契約期間が4年未満の取引を指す。
【第22-1-24】世界のLNG取引全体に占めるスポット及び短期取引の割合(2023年)(xlsx形式:18KB)
- 資料:
- GIIGNL「The LNG Industry GIIGNL Annual Report 2024」を基に作成
②LPガス
(ア)生産の動向
世界のLPガス生産は、2011年から2023年にかけて年平均3.0%で増加しました。2023年に生産されたLPガスのうち、65%がガス田及び油田の随伴ガスから、35%が製油所から生産されました。地域別に見ると、シェールガス由来のLPガス生産が増えている北米が最大のシェアを占めました。次いで、アジア大洋州、中東の順となっています(第22-1-25)。
【第22-1-25】世界のLPガス生産の推移(地域別)
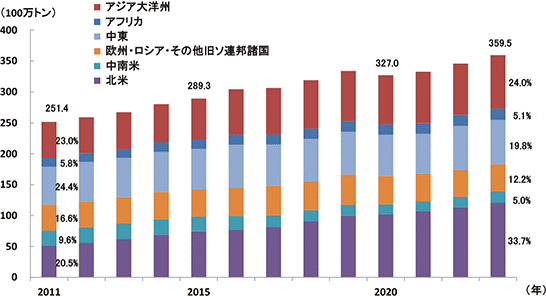
【第22-1-25】世界のLPガス生産の推移(地域別)(pptx形式:1,301KB)
- 資料:
- Argus Media Group「Statistical Review of Global LPG 2024」を基に作成
(イ)消費の動向
世界のLPガス消費も増加傾向にあります。地域別に見ると、最大消費地域であるアジア大洋州における消費が大きく増加しており、2011年から2023年にかけて1.9倍になりました(第22-1-26)。
【第22-1-26】世界のLPガス消費の推移(地域別)
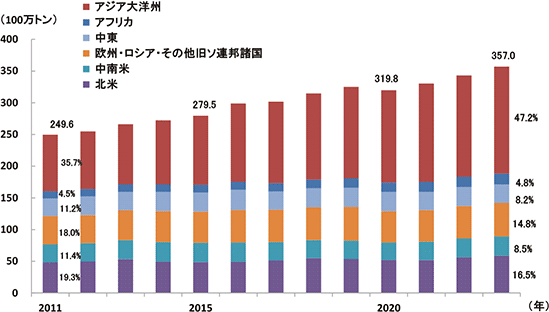
【第22-1-26】世界のLPガス消費の推移(地域別)(pptx形式:1,301KB)
- 資料:
- Argus Media Group「Statistical Review of Global LPG 2024」を基に作成
2023年における世界のLPガス消費を用途別に見ると、家庭・業務用が43.6%と最も多く、次いで化学原料用、精製用、輸送用、工業用が続きました。なお、LPガスは地域によって主な用途が異なっているという特徴があります(第22-1-27)。
【第22-1-27】世界のLPガス消費(用途別、2023年)
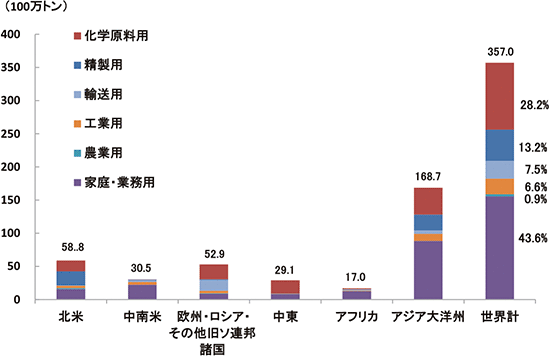
【第22-1-27】世界のLPガス消費(用途別、2023年)(pptx形式:1,301KB)
- 資料:
- Argus Media Group「Statistical Review of Global LPG 2024」を基に作成
(ウ)価格の動向
LPガスの価格は、原油価格の動向に大きく影響されます。価格形成は、①米州(米国・テキサス州のモント・ベルビュー市場を中核にした地域)、②欧州(北海のArgus価格指標(ANSI:Argus North Sea Index)及びアルジェリア・ソナトラック公定価格をベースにした北西欧・地中海等を中核にした地域)、③スエズ以東(サウジアラビア・アラムコの公定契約価格(CP)をベースにした中東・アジア大洋州を中核にした地域)の3つの市場地域に大別されており、各市場地域の価格差を埋めるように裁定取引が行われ、需給調整がなされています。長らく日本のLPガス輸入価格の決定に支配力を持ってきたサウジアラビアの公定契約価格は、スポット市場の値動きが一定程度反映されているものの、基本的にはサウジアラビア側から一方的に通告される価格であり、日本を含む消費国からは価格決定プロセスの不透明性が指摘されてきました。近年では、米国からのLPガスの輸入が増加していることから、米国のプロパンガス取引価格(モント・ベルビュー市場価格)も、日本のLPガス輸入価格の決定に影響力を持ちつつあります。
サウジアラビア産(サウジアラムコCP)のプロパン価格(FOB価格10)は、2009年1月に380ドル/トン(以下「ドル」という。)でしたが、その後は原油価格の高騰の影響を受けて上昇し、2012年3月には1,230ドルとなりました。2014年からは下落し、2015年以降は概ね300~600ドル前後の水準で推移しました。その後、2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵略等の影響で原油価格が上昇したことを受け、同年4月には約8年ぶりの高値となる940ドルにまで達しました。以降は、中国やインドにおけるLPガス需要の低迷や世界的な景気後退への懸念等により、価格は下落しましたが、その後、アジアにおける厳冬や中東からの供給減少の影響等により再び上昇し、2025年3月時点で615ドルとなっています。2024年は米国のプロパンガス取引価格を150ドル以上上回って推移しています(第22-1-28)。
【第22-1-28】プロパン価格の推移
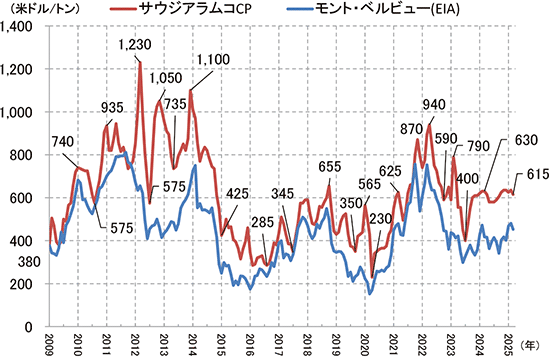
(注)数値はサウジアラムコCPの価格。
【第22-1-28】プロパン価格の推移(xlsx形式:37KB)
- 資料:
- サウジアラムコCPは石油情報センター「LPG価格の動向」、モント・ベルビューはEIA「Mont Belvieu, TX Propane Spot Price」を基に作成
(エ)貿易の動向
2023年にLPガスを最も輸出した地域は北米でした。中でも米国は、世界最大の輸出国となっています。北米に続くのは中東で、カタールやアラブ首長国連邦、サウジアラビア、イラン等の産油国が輸出を行っています(第22-1-29)。
【第22-1-29】世界のLPガス輸出(2023年)
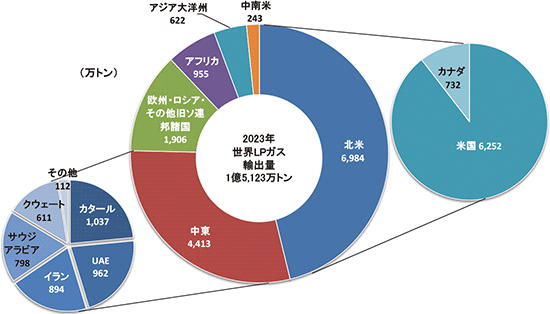
【第22-1-29】世界のLPガス輸出(2023年)(pptx形式:1,301KB)
- 資料:
- Argus Media Group「Statistical Review of Global LPG 2024」を基に作成
一方、輸入面ではアジア大洋州が最大の輸入地域でした。その中で最大の輸入国は中国で、次いでインド、日本、韓国、インドネシアとなりました。アジア大洋州に続く輸入地域は、欧州・ロシア・その他旧ソ連邦諸国でした(第22-1-30)。
【第22-1-30】世界のLPガス輸入(2023年)
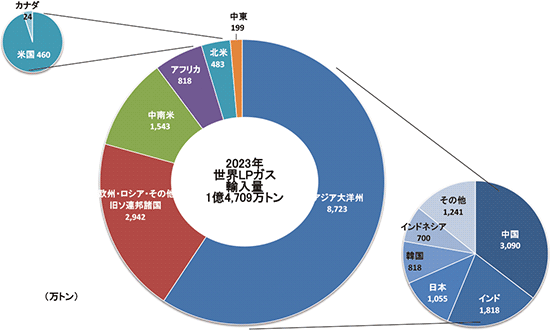
【第22-1-30】世界のLPガス輸入(2023年)(pptx形式:1,301KB)
- 資料:
- Argus Media Group「Statistical Review of Global LPG 2024」を基に作成
前述のとおり、世界のLPガス市場は大きく3地域(米州、欧州、アジア)に分割されており、かつては基本的に、各地域内で貿易取引が行われていました。しかし1999年を境に、それまでは供給余剰であったアジア市場が一転して供給不足状態となり、大西洋地域からアジア市場にLPガスが流入するようになりました。近年では、特に米国からアジアや欧州への輸出が増加しています。米国におけるシェールガス田由来のLPガス生産の増加や、2016年のパナマ運河拡張等が大きな要因となっています。
(3)石炭
①資源の分布
石炭の確認埋蔵量は2020年末時点で10,741億トンであり、これを2020年の石炭生産量で除した可採年数は139年でした。石炭は、米国、ロシア、豪州、中国、インド等に多く埋蔵されており、石油や天然ガスと比べて地域的な偏りが少なく、世界に広く賦存しているという特徴があります。炭種別11の確認埋蔵量は、無煙炭と瀝青炭が7,536億トン、亜瀝青炭と褐炭が3,205億トンでした(第22-1-31)。
【第22-1-31】世界の石炭確認埋蔵量(2020年末)
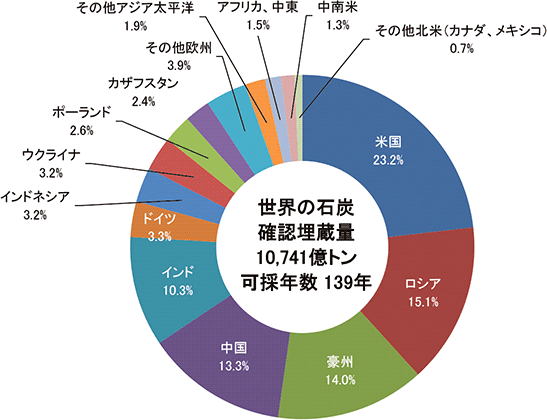
【第22-1-31】世界の石炭確認埋蔵量(2020年末)(xlsx形式:20KB)
- 資料:
- Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2024」を基に作成(埋蔵量データは2022年版から更新なし)
②生産の動向
世界の石炭生産は、2000年代に大きく増加しました。2000年の石炭生産は46.4億トンでしたが、2013年には79.9億トンに達しました。その後は、中国を中心とした世界の石炭需要の動向に伴って増減を繰り返し、2023年の石炭生産は過去最高となる89.6億トン(2023年のデータは推計値、以下同じ。)となりました。
2023年の石炭生産を国別に見ると、中国が世界全体の半分以上を占めていることがわかります。次いでインド、インドネシア、米国、豪州が続いており、これら上位5か国のシェアは約8割となりました。この5か国について、2010年と2023年を比較すると、石炭生産が減少したのは米国のみであり、他の4か国では増加したことがわかります。米国の生産減少については、気候変動対策の高まりに加え、国内でのシェールガスの生産増加で天然ガスの価格が低下し、ガス火力発電の経済性が向上したことにより、電力分野での石炭消費が減少したこと等が要因と考えられます。他方、世界の石炭生産の半分以上を占める中国は、2000年代以降、電力分野を中心に急拡大する国内需要に応えるため、生産を大幅に拡大してきました。2010年代半ばには、大気汚染対策等により石炭消費が減少したことで生産も一時減少しましたが、2017年以降は再び増加に転じています。中国に次ぐ石炭生産国であるインドも同様に、国内需要の拡大に伴い、石炭生産が拡大傾向にあります(第22-1-32)。
【第22-1-32】世界の石炭生産の推移(国別)
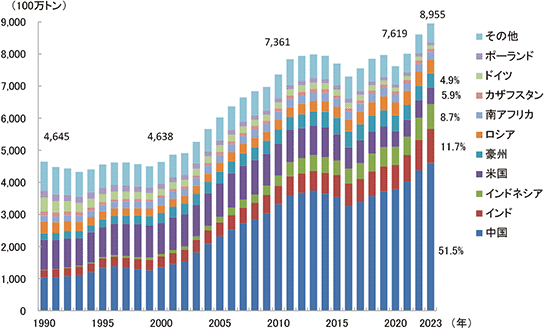
(注)2023年のデータは推計値。
【第22-1-32】世界の石炭生産の推移(国別)(xlsx形式:29KB)
- 資料:
- IEA「Coal Information 2024」を基に作成
炭種別に見ると、2023年の世界全体の石炭生産のうち、81.2%が主に発電用燃料として利用される一般炭となっており、その生産は2000年代に入って急速に増加しました。また、主にコークス製造に用いられる原料炭の生産も2000年代に入って倍増しました。一方で、熱量が低く、生産地での発電用燃料等の用途に限られる褐炭の生産は、近年減少傾向にあります(第22-1-33)。
【第22-1-33】世界の石炭生産の推移(炭種別)
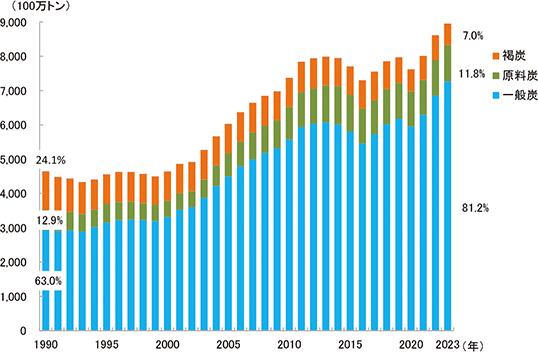
(注)2023年のデータは推計値。
【第22-1-33】世界の石炭生産の推移(炭種別)(xlsx形式:26KB)
- 資料:
- IEA「Coal Information 2024」を基に作成
③消費の動向
世界の石炭消費は、2013年にかけて中国やインドを中心に増加しました。その後は増減を繰り返しましたが、2023年の石炭消費は過去最高となる86.9億トンとなりました。
2023年の石炭消費を国別に見ると、中国だけで世界全体の半分以上を消費していることがわかります。なお、前述のとおり、中国は石炭生産においても世界全体の半分以上を占めています。中国の石炭消費は、2000年代に入って急増しました。2010年代半ばには、大気汚染対策等を背景に一時的に減少しましたが、2017年以降は再び増加に転じています。中国に次いで石炭を消費しているのはインドであり、2023年には世界全体の14.6%を消費しました。なお、日本の2023年の石炭消費は世界第7位で、世界全体に占める割合は1.9%となっています(第22-1-34)。
【第22-1-34】世界の石炭消費の推移(国別)
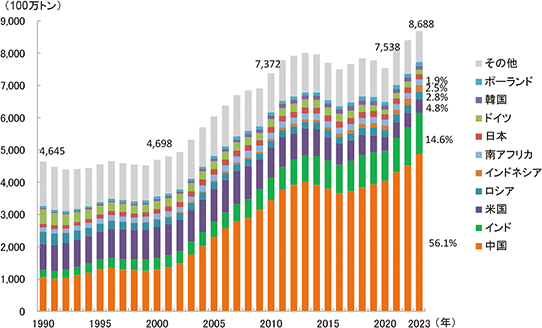
(注)2023年のデータは推計値。
【第22-1-34】世界の石炭消費の推移(国別)(xlsx形式:30KB)
- 資料:
- IEA「Coal Information 2024」を基に作成
2022年の世界の石炭消費を用途別に見ると、発電用に66.9%、鉄鋼生産に用いるコークス製造用に12.0%、製紙・パルプや窯業等の産業用に11.3%が消費されたことがわかります(第22-1-35)。
【第22-1-35】世界の石炭消費の推移(用途別)
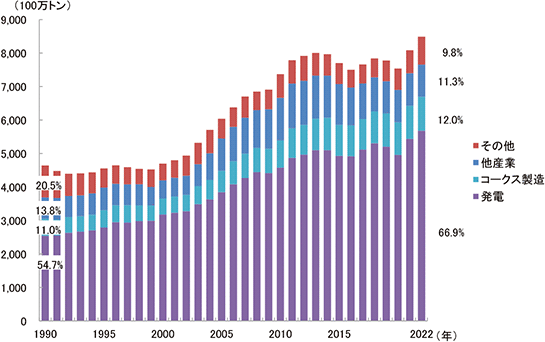
(注1)その他には統計誤差を含む。
(注2)用途別の内訳については2022年のデータが最新。
【第22-1-35】世界の石炭消費の推移(用途別)(xlsx形式:22KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Statistics 2024」を基に作成
④貿易の動向
2023年の世界最大の石炭輸出国はインドネシアで、世界全体の36.6%を占めました。インドネシアは2011年に豪州を抜き、世界最大の石炭輸出国になりました。第2位の豪州は世界全体の23.9%を占め、次いでロシア、米国、南アフリカが続いています。
インドネシアからの石炭輸出が増加した理由としては、石炭需要が拡大しているインドや東南アジア諸国に加え、中国や韓国等の東アジアにも地理的に近いこと、開発しやすい海岸線沿いや河川沿いに賦存する石炭の開発が進み、発熱量が低い石炭が多いものの、安価に生産できること等が挙げられます。また、豪州が多くの石炭を輸出している理由としては、アジア市場に近いことや、高品質の石炭が豊富に賦存していること、石炭の生産地が海岸近くにあることから開発が進み、鉄道や石炭ターミナル等の輸送インフラが他国よりも早くから整備されたこと等が挙げられます。
炭種別に見ると、2023年の一般炭の輸出は10.6億トン、原料炭の輸出は3.3億トンと報告されています。国別に見ると、一般炭の最大の輸出国はインドネシアで、次いで豪州、ロシア、南アフリカ、コロンビアが続きました。原料炭の最大の輸出国は豪州で、次いでモンゴル、米国、ロシア、カナダとなりました(第22-1-36)。2023年のモンゴルの原料炭の輸出量は、前年比で2倍以上に増加しました。
【第22-1-36】世界の石炭輸出(2023年)
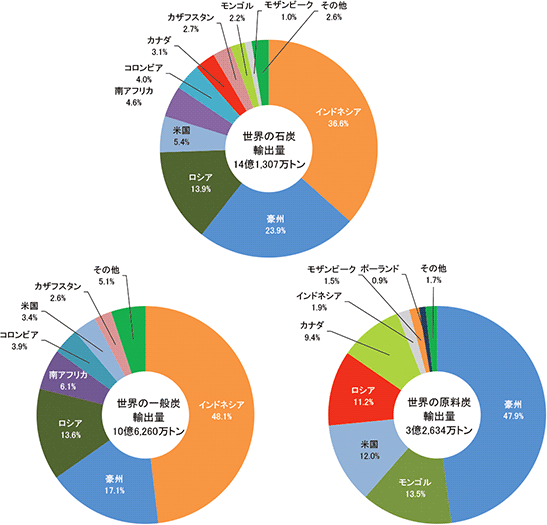
(注1)データは推計値。
(注2)各国・地域の輸出量を積み上げたもので、第22-1-37の輸入量合計と一致しない。
【第22-1-36】世界の石炭輸出(2023年)(xlsx形式:38KB)
- 資料:
- IEA「Coal Information 2024」を基に作成
輸入側について確認すると、2023年の世界最大の石炭輸入国は中国となっており、そのシェアは31.9%でした。次いでインド、日本、韓国、台湾となっており、アジア勢が続いています。長らく世界最大の石炭輸入国は日本でしたが、2011年に中国が日本を抜いて世界最大の石炭輸入国になりました。中国やインド等のアジア諸国では、電力需要の増加に伴って石炭火力発電所での石炭消費が増加しており、石炭の輸入も増えています。
炭種別に2023年の輸入国を見ると、一般炭は中国が最大の輸入国で、その後はインド、日本、韓国、台湾が続きました。原料炭も中国が最大の輸入国で、次いでインド、日本、韓国、インドネシアの順となりました(第22-1-37)。
【第22-1-37】世界の石炭輸入(2023年)
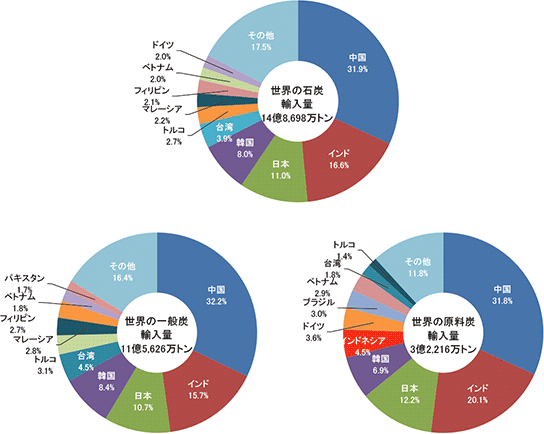
(注1)データは推計値。
(注2)各国・地域の輸入量を積み上げたもので、第22-1-36の輸出量合計と一致しない。
【第22-1-37】世界の石炭輸入(2023年)(xlsx形式:36KB)
- 資料:
- IEA「Coal Information 2024」を基に作成
2023年における世界の主な石炭貿易フロー(褐炭を除く。)を見ると、石炭の貿易は、中国、インド及び日本等を中心とするアジア市場と欧州市場に大きく分かれていることがわかります。アジア市場は中国、インド、東南アジア諸国等の需要増加により拡大傾向にありますが、欧州市場は気候変動対策(脱石炭)の進展等により縮小傾向にあります。2022年はロシアからの天然ガスの輸入が減少した影響等により、欧州の石炭輸入は前年比で増加しましたが、2023年には再び減少しました(第22-1-38)。
【第22-1-38】世界の主な石炭貿易(2023年見込み)
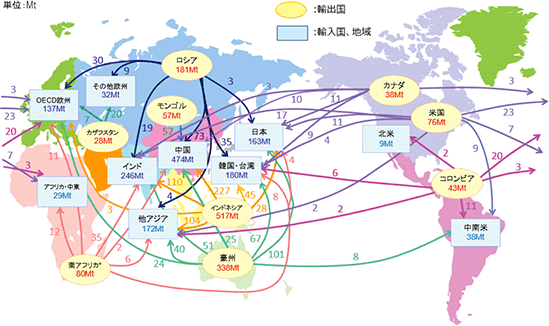
(注)褐炭を除く。200万トン以上のフローを記載。南アフリカにはモザンビークを含む。
【第22-1-38】世界の主な石炭貿易(2023年見込み)(pptx形式:199KB)
- 資料:
- IEA「Coal Information 2024」及び貿易統計等を基に推計
⑤価格の動向
石炭価格は世界の石炭需給の動向等を反映して変動していますが、2000年代半ばから変動幅が大きくなりました。一般的に日本の石炭輸入価格は、長期契約をベースに、国際的な市場価格(スポット価格)の動向を勘案して決定されます。
日本の豪州産一般炭の輸入CIF価格(年平均)は、2000年代半ばから、アジア等での需要拡大や生産国における供給障害等を背景に上昇し、2011年には140ドル/トン(以下「ドル」という。)を超える高値を記録しました。その後は、輸出国で供給力の拡大が進んだ一方、需要の伸びが鈍化したことから供給過剰となり、価格は下落傾向となりました。その後、2017年に価格は上昇に転じましたが、2019年には需給の緩みを背景に再び下落し、2020年は新型コロナ禍の影響で需要が減少したことにより、価格はさらに下落しました。2022年は、ロシアによるウクライナ侵略や供給国での豪雨等により国際市場価格が高騰したことから、価格は332ドルまで高騰しました。その後は供給過剰と需要の鈍化により下落傾向となり、2024年の価格は160ドルとなっています。
原料炭の価格も、2000年代半ば以降、急激な変動を見せています。日本の豪州産原料炭(強粘結炭)の輸入CIF価格(年平均)は、2011年に需要が増加する中、供給側の豪州・クイーンズランド州を記録的な豪雨が襲い、生産や出荷が滞ったこと等を背景に上昇し、当時の最高値となる282ドルを記録しました。その後は欧州の経済不安や、中国、インドの経済成長の減速等を背景に供給過剰となり、価格は下落しましたが、2017年には中国の輸入増加等を背景に、200ドル超まで上昇しました。その後、2020年には一般炭と同様に、新型コロナ禍の影響で価格は下落しました。2022年の価格は、ロシアによるウクライナ侵略や供給国での豪雨等により国際市場価格が高騰したことから、352ドルまで高騰しました。その後は需給が緩和したため、2024年の価格はやや下落して270ドルとなっています(第22-1-39)。
【第22-1-39】日本の豪州炭輸入CIF価格の推移
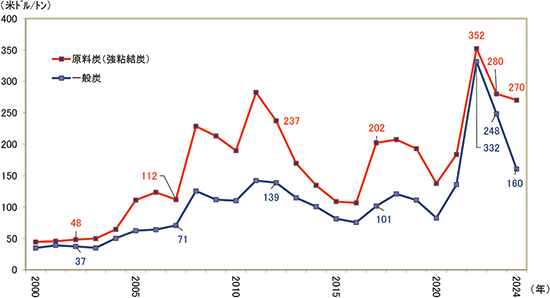
(注)2023年までのデータは確定値。
【第22-1-39】日本の豪州炭輸入CIF価格の推移(xlsx形式:20KB)
- 資料:
- 財務省「日本貿易統計」を基に作成
日本の石炭輸入価格に影響を与える国際市場価格も、近年は大きく変動しています。豪州一般炭のスポット価格(豪州のニューキャッスル港出し一般炭スポットFOB価格(月平均))は、2016年初頭に50ドルを割り込みましたが、その後は上昇し、同年11月には100ドル超まで高騰しました。中国の石炭需要が増加に転じると同時に、中国政府が国内の石炭生産を政策的に抑制したこと等により、中国国内の石炭需給がタイトになり、中国による石炭輸入が増加したことに加え、石炭輸出国において、長引く価格低迷により不採算炭鉱の閉山や休山が進んでいたこと等が価格高騰の要因として挙げられます。その後、中国の生産調整の緩和等により価格は一時下落しましたが、インドによる輸入増加等もあり、2018年7月には120ドル付近まで上昇しました。その後は主要な需要国による輸入が停滞したことから、価格は再び下落しました。2020年には、新型コロナ禍による石炭需要の落ち込みから、同年8月には50ドル付近まで価格が下落しました。その後は石炭需要の回復に伴って価格も持ち直し、2021年に入ってからも上昇しました。2022年1月には、需要期の冬期であることに加えて、インドネシアが国内の発電用石炭の不足を受けて石炭輸出を一時禁止したことも重なり、価格は200ドル近くまで上昇していました。そうした中、同年2月にロシアによるウクライナ侵略が発生しました。同年4月にはEUと日本がロシア炭の禁輸を発表し、加えて同年7月には豪州・ニューサウスウェールズ州での大雨の影響もあり、同年9月には価格が430ドルを上回るまでに急騰しました。その後は下落し、2024年9月時点では139ドルとなっています。
また、豪州高品位原料炭の輸出価格(四半期平均価格)も、概ね一般炭と同様の理由により大きく変動しています。2016年第1四半期には80ドルを割り込んでいましたが、一般炭と同様の要因により、同年第4四半期には200ドル近くまで上昇しました。その後は2019年第3四半期にかけて、価格は170~200ドル前後の水準で推移しました。その後、中国等の需要国による輸入が停滞したことで価格は下落し、さらに新型コロナ禍の影響も重なって、2020年第3四半期には100ドル付近まで下落しました。2021年に入り、中国国内の市場動向等の影響で価格は上昇し、同年第4四半期には300ドル以上にまで急騰しました。そうした中、2022年2月にロシアによるウクライナ侵略が発生したことによって価格はさらに上昇し、同年第2四半期には450ドル近い価格となりました。その後は下落し、2024年第4四半期では183ドルとなっています(第22-1-40)。
【第22-1-40】豪州一般炭・高品位原料炭価格の推移
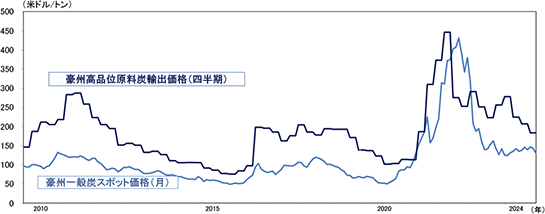
(注1)豪州一般炭スポット価格:World Bankが公表する豪州ニューキャッスル港出し一般炭スポットFOB価格(月平均)。
(注2)豪州高品位原料炭輸出価格:豪州DISRが公表する豪州高品位原料炭輸出FOB価格(四半期平均)。
【第22-1-40】豪州一般炭・高品位原料炭価格の推移(xlsx形式:54KB)
- 資料:
- World Bank及び豪州DISR「Resources and Energy Quarterly」を基に作成
なお、石炭(一般炭)と他の化石エネルギー(原油、LNG)を同一の発熱量(1,000kcal)当たりのCIF価格で比較すると、石炭の価格が基本的に他の化石エネルギーよりも低廉であることがわかります。1980年代前半の石炭は、他の化石エネルギーに対して高い価格優位性を有していましたが、1986年度以降は原油やLNGの価格が低下したことから、その価格差が縮小しました。2000年代半ば以降、原油やLNGの価格は急激な変動を繰り返しましたが、発熱量当たりのCIF価格を見ると、石炭の価格変動幅は比較的小さく、また他の化石エネルギーに対する価格優位性も維持してきました。しかし、2021年度以降は石炭の価格変動幅も大きくなっています(第22-1-41)。
【第22-1-41】化石エネルギーの単位熱量当たりCIF価格の推移
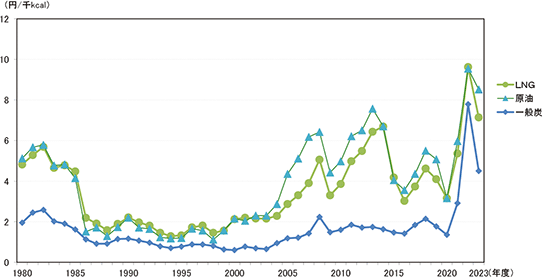
【第22-1-41】化石エネルギーの単位熱量当たりCIF価格の推移(xlsx形式:21KB)
- 資料:
- 日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」を基に作成
2.非化石エネルギーの動向
(1)再生可能エネルギー
近年、世界中で再エネの利用拡大に向けた取組が進んでいます。再エネの導入促進策としては、研究開発・実証や設備導入補助に加え、FIT制度やFIP制度、RPS制度12、入札等があります。
一般的にFIT制度とは、再エネから発電された電力を優遇的な固定価格で長期にわたって買い取ることを国が保証する制度のことで、日本では2012年から正式に導入されています。近年では、このFIT制度に代わって、FIP制度を導入する国が多くなっています。FIP制度とは、再エネから発電された電力を発電事業者が自ら卸電力市場や相対取引で販売することを前提として、その販売電力量当たり一定額のプレミアムを補助する制度です。再エネの自立化を促しつつ、投資インセンティブが確保されるように支援を行う制度となっています。日本でも、大型太陽光発電等に対しては、2022年からFIT制度に代わってFIP制度が適用されており、導入促進策の中心となっています。なお、2022年時点では、63か国においてFIT制度又はFIP制度が導入されています13。また近年では、買取価格等を競争入札によって決定する仕組みを多くの国が取り入れています。前述のとおり、日本ではFIT制度が2012年から正式に導入されていますが、2017年からは太陽光発電等の一部の買取価格が競争入札によって決定されるようになっており、その後も対象が風力発電等に拡大しています。また、2022年4月にはFIP制度が始まり、小規模発電等の一部を除くFITの大部分がFIPに置き換わりました。
こうした施策によって、再エネへの投資は飛躍的に増加しており、2023年には世界全体で6,000億ドルを超える投資が行われました(大型水力発電を除く)。地域別に見ると、欧州や米国の投資額が増加した一方、中国の投資額が前年比で減少しています(第22-2-1)。
【第22-2-1】再生可能エネルギーへの投資の推移(地域別)
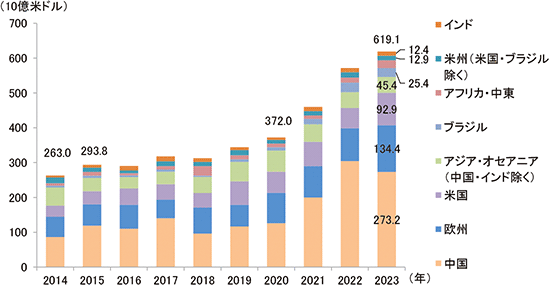
(注)大型水力発電を除く。
【第22-2-1】再生可能エネルギーへの投資の推移(地域別)(xlsx形式:18KB)
- 資料:
- REN21「Renewables 2024 Global Status Report-Energy Supply」を基に作成
また、再エネへの投資を発電方式別に見ると、太陽エネルギーと風力に投資が集中していることがわかります(第22-2-2)。
【第22-2-2】再生可能エネルギーへの投資の推移(発電方式別)
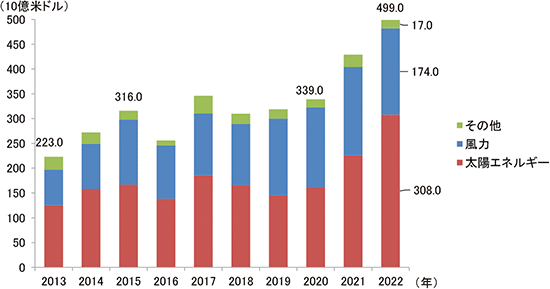
(注)発電方式別の内訳は、2022年のデータが最新の値。
【第22-2-2】再生可能エネルギーへの投資の推移(発電方式別)(xlsx形式:19KB)
- 資料:
- IRENA「Global Landscape of Renewable Energy Finance 2023」を基に作成
①太陽光発電
世界における太陽光発電の導入は、特に2000年代後半から加速しており、2023年の累積導入量は16.4億kWに達しました。2000年代後半からの導入拡大の背景には、2000年前後に欧州諸国で導入されたFIT制度があります。太陽光発電の買取価格が比較的高額に設定されたこと等により、ドイツやイタリアでは他国に先駆けて顕著な伸びを示しました。日本でも、FIT制度が2012年に導入されたことにより、導入が大幅に拡大しました。2023年の累積導入量を見ると、日本は中国、米国に次いで世界第3位となっています。また、太陽光発電市場が大きく拡大したことで発電設備の導入コストが低下しており、近年では新興国を含めた世界中で導入が広がっています。特に中国は、2015年に当時世界第1位だったドイツを抜き、世界第1位となりました(第22-2-3)。
【第22-2-3】世界の太陽光発電の累積導入量の推移(国別)
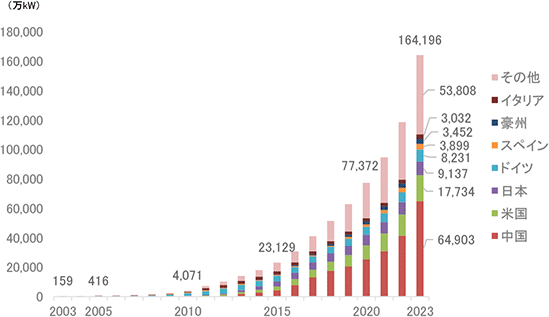
【第22-2-3】世界の太陽光発電の累積導入量の推移(国別)(xlsx形式:24KB)
- 資料:
- IEA「PVPS TRENDS 2024」を基に作成
太陽光発電の導入拡大による波及効果として雇用の創出等が期待されますが、その一方で、FIT制度による買取費用は最終的に賦課金として消費者に転嫁される仕組みとなっていることから、費用負担の増大も懸念されています。2024年度の日本のFIT制度による賦課金は3.49円/kWhとなっており、1か月の電力使用量が400kWhの需要家モデルの場合、月額負担は1,396円と推計されています14。
②風力発電
世界における風力発電の導入量は右肩上がりに増加しており、2023年の累積導入量は10.0億kWに達しました。導入量が最も多いのは、世界全体の約4割を占める中国で、これに米国、ドイツ、インド、スペインが続きます(第22-2-4)。
【第22-2-4】世界の風力発電の導入状況の推移(国別)
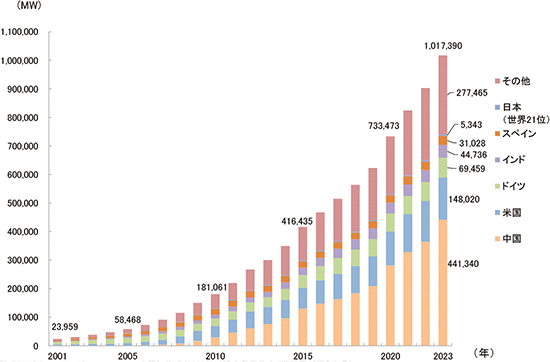
【第22-2-4】世界の風力発電の導入状況の推移(国別)(xlsx形式:24KB)
- 資料:
- IRENA「Query Tool(online version)」を基に作成
風力発電のうち、洋上風力発電の市場も急速に拡大しており、2023年末時点では、世界全体で7,318万kWが導入されています。特に導入が進んでいるのが中国で、2023年には683万kWの設備が追加され、累積導入量は世界全体の約半分となる3,729万kWになりました15。
③地熱
世界の地熱発電設備は、2023年時点で1,503万kWが導入されています。最も多く導入されているのは米国で、次いでインドネシア、フィリピン、トルコが続きます。インドネシア、トルコ、ニュージーランド、ケニアといった国々では、2010年代にも設備容量が増加しました。特にケニアでは、国内の総発電量に占める地熱発電の割合が4割を超えています(2022年)16。日本では、2023年時点で43万kWが導入されており、世界第10位となっています。なお、欧州大陸では地熱発電を利用できる地域が少なく、地熱を活用しているのはイタリア等に限られています(第22-2-5)。
【第22-2-5】世界の地熱発電の導入状況の推移(国別)
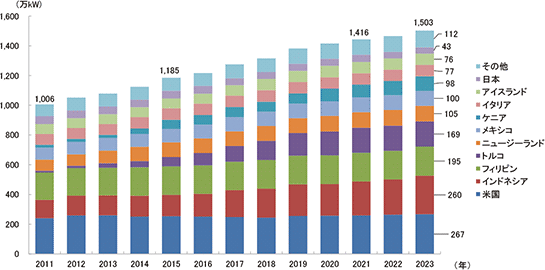
【第22-2-5】世界の地熱発電の導入状況の推移(国別)(xlsx形式:21KB)
- 資料:
- IRENA「Renewable Capacity Statistics 2024」等を基に作成
④水力
世界の水力発電設備は、2023年時点で12.6億kWとなっています。水力発電設備が最も多い国は中国で、世界全体の約3割を占めています。先進国における大規模ダム開発が頭打ちとなっている一方で、中国の水力発電の設備容量は近年も増加傾向にあります。中国の揚子江中流に建設された三峡ダム発電所は、2012年に全32基のうち最後の発電ユニットを完成させ、世界最大規模の水力発電所(2,250万kW)となっています(第22-2-6)。
【第22-2-6】世界の水力発電の導入状況の推移(国別)
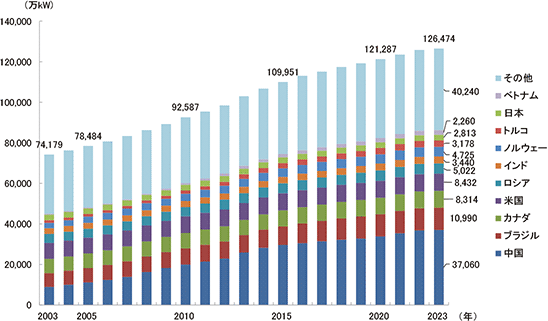
【第22-2-6】世界の水力発電の導入状況の推移(国別)(xlsx形式:24KB)
- 資料:
- IRENA「Query Tool(online version)」を基に作成
2022年の国内の総発電量に占める水力発電の割合は、中国が15%、日本が8%、米国が6%となっていますが、水力発電が88%を占めるノルウェーのように極めて高いシェアを持つ国もあります17。
⑤バイオマス
バイオマスは、発電用の燃料としての利用に加え、輸送用や暖房・厨房用の燃料としても用いられています。開発途上国では、従来から薪や炭といった伝統的なバイオマス利用が行われていますが、一般的には、経済成長に伴って灯油や電気等の利用が増え、こうしたバイオマス利用は減少すると考えられます。また、欧米等の先進国では、持続可能なバイオマスの利活用基準を設定した上で、活用を進めている国が多く存在します。2022年時点でバイオマスは、世界全体の一次エネルギー総供給の8.4%を占めており、先進国(OECD)平均では6.0%、開発途上国(非OECD)平均では10.1%でした(第22-2-7)。
【第22-2-7】世界のバイオマス利用状況(2022年)
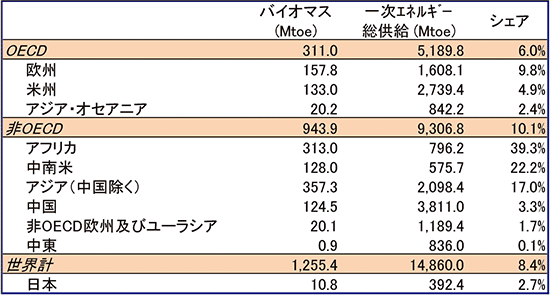
(注1)「中国」の数値には香港を含む。
(注2)「世界計」の数値には国際航空及び海運の数値が含まれており、「OECD」と「非OECD」の合計値と「世界計」の数値は一致しない。
【第22-2-7】世界のバイオマス利用状況(2022年)(pptx形式:60KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2024」を基に作成
バイオマスの利用に関しては、特に運輸部門における石油依存の低減や温室効果ガスの排出削減を目指した政策が打ち出されています。また、廃油や植物を原料とした持続可能な航空燃料(SAF)への注目も高まっています。2021年には、SAFの導入促進を目指す世界経済フォーラムの「Clean Skies for Tomorrow Coalition」に参画している企業60社が、世界の航空業界で使用される燃料におけるSAFの割合を、2030年までに10%に増加させる方針を示しました18。2022年には日本政府も国内航空会社の燃料使用におけるSAFの割合を2030年までに10%とする目標を示しました19。
しかし、バイオ燃料の主たる原料は、サトウキビやトウモロコシ等の食料であるため、バイオ燃料の急激な利用拡大は、食料価格の高騰等を招く可能性があると指摘されています。また、バイオ燃料の生産のために森林を伐採し、耕地とする動きが拡大しかねないとの見方もあります。このため、バイオ燃料の生産・消費による食料市場や自然環境への影響を抑えるための持続可能性基準について、各国での検討が進められています。また、食料以外の原料(稲わらや木材等のセルロース系原料、藻類、廃棄物等)を用いた次世代型バイオ燃料の開発も進められています。
⑥再生可能エネルギーのコスト動向
再エネの発電コストは、世界的に低下傾向となっています20。発電コストの低減は、主に技術革新や再エネを推進する政策によって支えられてきました。日々進歩する技術によって製造コストの削減や保守管理の効率化が図られたことに加え、大規模な導入によって「規模の経済」が働いたことも大きな要因と考えられます。さらに、多くの国で導入されている競争入札制度で買取価格が決められることも、競争を促し、発電コストを抑制させる方向へと導きました。
再エネの中でも、太陽光及び陸上風力の発電コストが著しく低下しています。2023年に運転を開始した太陽光の平均発電コストは0.05ドル/kWhとなっており、2010年の0.46ドル/kWhから大きく低下しました。2000年代後半から低下している太陽電池モジュール価格が発電コストを引き下げたと考えられます。陸上風力も同様に、タービン価格の低下等に伴って平均発電コストも低下しており、2010年の0.11ドル/kWhから、2023年には0.03ドル/kWhへと下がりました。地熱、水力、バイオマスは、資源が豊富な場所では太陽光や風力よりも安価な電源ですが、平均発電コストにはあまり変化がありません。水力発電は、高度な技術が求められる遠隔地での開発等が増えており、コストアップの要因となっています。また、地熱発電については、高い初期投資コストや開発リスクが投資の障壁となっています(第22-2-8)。
【第22-2-8】世界の再生可能エネルギー発電コストの推移
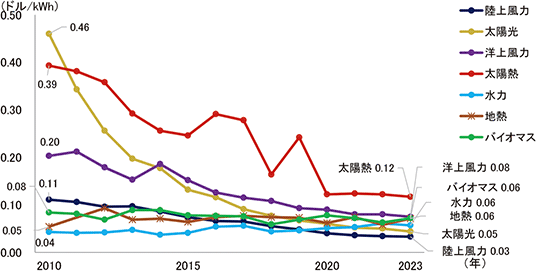
(注)地熱の2011年のデータなし。
【第22-2-8】世界の再生可能エネルギー発電コストの推移(xlsx形式:24KB)
- 資料:
- IRENA「Renewable Power Generation Costs in 2023」を基に作成
(2)原子力
①世界の原子力発電の推移
1951年に米国において世界初の原子力発電が開始されて以来、二度のオイルショックを契機に、世界各国で原子力発電の開発が積極的に進められてきましたが、1980年代後半以降は原子力発電設備容量の伸びが緩やかになりました。しかし、エネルギー需要の増加が著しいアジアでは、近年に至るまで原子力発電設備容量が増加しています(第22-2-9)。
【第22-2-9】世界の運転中の原子力発電設備容量の推移(地域別)
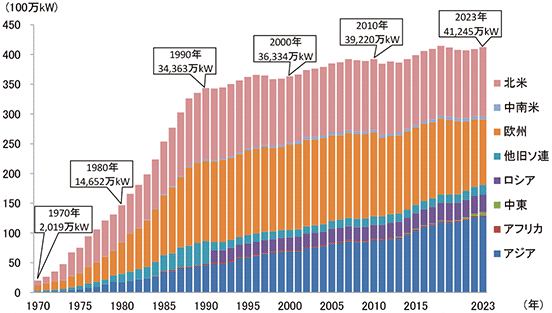
【第22-2-9】世界の運転中の原子力発電設備容量の推移(地域別)(xlsx形式:27KB)
- 資料:
- 日本原子力産業協会「世界の原子力発電開発の動向2024年版」を基に作成
また、エネルギー需要が急増している新興国を中心に、原子力発電所の新規導入又は増設の検討が進められています。
世界の原子力発電電力量は、原子力発電の開発に伴い、2000年代にかけて増加傾向でしたが、2011年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて日本の原子力発電電力量が減ったため、2010年代前半に減少しました。その後、2013年からは再び増加傾向に転じています(第22-2-10)。
【第22-2-10】世界の原子力発電電力量の推移(地域別)
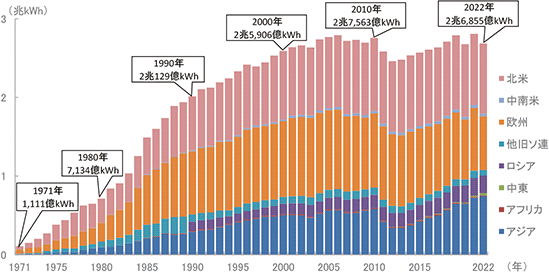
【第22-2-10】世界の原子力発電電力量の推移(地域別)(xlsx形式:29KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2024」を基に作成
欧米では、原子力発電所の新規建設が少ないものの、出力増強や設備利用率の向上に取り組んできました。例えば、米国では、1979年のスリーマイル島事故後の自主的な安全性向上の取組によって官民による設備利用率向上を進めた結果、近年の設備利用率は90%以上で推移しています。日本では、2011年3月の東日本大震災後、原子力発電所は長期稼働停止することとなりました。その後、2015年8月に新規制基準の施行後初めて再稼働した九州電力川内原子力発電所1号機をはじめ、2025年3月までに14基が再稼働したものの、設備利用率は低いままです(第22-2-11)。
【第22-2-11】主要原子力発電国における設備利用率の推移
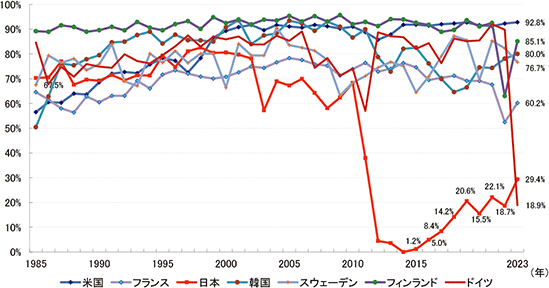
【第22-2-11】主要原子力発電国における設備利用率の推移(xlsx形式:26KB)
- 資料:
- IAEA「Power Reactor Information System(PRIS)」を基に作成
②各国の原子力発電の現状
本項では、各国・地域の原子力発電を巡る状況について概観します(第22-2-12)。
【第22-2-12】各国・地域の現状一覧
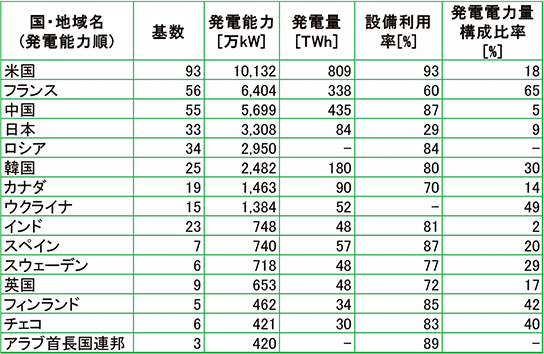
(注1)「基数」・「発電能力」は2024年1月1日時点のデータ。「発電量」・「設備利用率」・「発電電力量構成比率」は2023年時点のデータ。
(注2)「‐」はデータなし。
【第22-2-12】各国・地域の現状一覧(pptx形式:62KB)
- 資料:
- 基数・発電能力は日本原子力産業協会「世界の原子力発電開発の動向2024年版」、発電量・発電電力量構成比率はIEA「World Energy Balances 2024」、設備利用率はIAEA「Power Reactor Information System (PRIS)」を基に作成
(ア)米国
米国は、原子力発電の規模が世界一であり、設備利用率も高い状況となっています。2025年3月時点で91基の原子力発電所について、運転期間(認可)の60年への延長が認められており、さらに4基が審査中、1基が延長を申請予定となっています。また、2017年7月には、原子力規制委員会(以下「NRC」という。)が80年運転に向けたガイダンスを確定しており、これにより、認可を受けた原子力発電所については80年運転が可能となっています。これまでに計22基が80年運転に向けた2回目の運転期間の延長を申請しており、NRCはこのうち、ターキーポイント3、4号機、ピーチボトム2、3号機、サリー1、2号機に対して運転期間延長の認可を発給しました。
また、2005年8月に成立した、原子力発電所の新規建設を支援するプログラムを含む「2005年エネルギー政策法」に基づき、建設遅延に対する補償や、発電量に応じた一定の税額控除、政府による融資保証制度が整備されました。こうしたインセンティブの導入を踏まえ、2007年以降、原子力発電所の新規建設に向けて、19件の建設・運転一体認可申請がNRCに提出されました(2025年3月時点で認可8件、審査一時停止2件、申請取下げ8件、申請却下1件)。
東京電力福島第一原子力発電所事故直後の2011年3月14日、米国のエネルギー省(DOE)は、前月に発表した原子力発電所の新設支援のための融資保証枠は変更しないと発表し、原子力政策の維持を表明しました。その後、2013年には、ボーグル3、4号機の建設が開始されました。これは、米国内で約35年ぶりとなる原子力発電所の新規着工でした。原子力発電を重視する姿勢は、2017年1月のトランプ大統領の就任後も変わりなく、同年9月には建設費用の増加が見込まれるボーグル3、4号機に対し、DOEが建設継続のために追加融資保証の適用を提案しました。また、2021年1月に発足した前バイデン政権も気候変動対策の観点から原子力を重視する方針を示しました。その後、当初予定よりも大幅に遅延したものの、2023年7月にはボーグル3号機が、2024年4月にはボーグル4号機が営業運転を開始しました。
他方で、米国内でシェールガス開発が進み、天然ガスの価格が下落していることもあり、経済性の観点から、原子力発電所の閉鎖も発表されています。2015年から2024年までの10年間に計8基が閉鎖されました。新設についても費用の大幅な増加に伴い、ボーグル3、4号機及びV.C.サマー2、3号機の建設工事を請け負うウエスチングハウス社の米国連邦倒産法に基づく再生手続の申立て(2017年3月)を受け、同年7月にV.C.サマー発電所の建設中止が決定されました。
原子力発電所の閉鎖が相次ぐ状況に鑑み、温室効果ガス削減や雇用等の地元経済への影響の観点から、複数の州で原子力発電所の運転継続を支援する制度が導入されています。2016年8月にはニューヨーク州で、原子力発電所に対する補助金プログラムを盛り込んだ包括的な地球温暖化防止策である「クリーン・エネルギー基準」が承認され、同年12月にはイリノイ州で、州内の原子力発電所に対する財政支援措置を盛り込んだ包括的エネルギー法が成立しました。その後も、2017年10月にはコネチカット州で、2018年5月にはニュージャージー州で、2019年7月には、オハイオ州で、それぞれ同様の法律が成立しています。2021年9月にはイリノイ州で新たな低炭素電源支援法が成立したことにより、経済的な問題から閉鎖が予告されていたバイロン1、2号機とドレスデン2、3号機の運転が継続されることとなりました。2022年9月には、カリフォルニア州で、閉鎖が決定されていたディアブロキャニオン1、2号機の運転期間延長を支援する法案が成立しました。さらに、2024年9月には2022年に成立したインフレ抑制法(IRA)のエネルギーインフラ再投資(EIR)に基づき、パリセード原子力発電所の復旧と再稼働に係る資金調達支援を決定しました。同じく2024年9月には、データセンター向けに原子力による電力を供給するため、スリーマイル・アイランド1号機を再稼働させる方針を明らかにしています。
また米国では、DOEが2015年より実施している「原子力の技術革新を加速するゲートウェイプログラム」や、2020年5月に立ち上げられた「革新炉実証プログラム(ARDP)」を中心に、政府が革新炉の開発支援を積極的に行っています。米国議会でも、革新炉開発を促進するための立法活動が進められており、2018年9月には「原子エネルギー能力法」が、2019年1月には「原子力イノベーション革新・近代化法」が成立しました。2021年11月に成立した「インフラ雇用投資法」では、革新炉実証プログラムへの予算支援の承認とともに、経済的に困難な既設炉へのクレジット付与が盛り込まれ、2022年8月に成立した「インフレ削減法」では、既設炉及び新規革新炉に対する生産税額控除並びに新規革新炉に対する投資税額控除が盛り込まれました。さらに、2024年6月に成立したクリーンエネルギーの多用途かつ先進的な原子力展開の加速化法(ADVANCE法)では、新たな原子力技術の開発と展開を支援します。
(イ)欧州
(ⅰ)英国
英国は、2007年7月に発表したエネルギー白書の中で、原子力発電所の新規建設に向けた政策支援を行う方針を表明しました。2011年7月には、英国下院において8か所の新設候補サイトが示された原子力に関する国家政策声明書が承認されました。2013年12月に成立した「エネルギー法」では、原子力発電への適用を含んだ差額決済方式を用いた低炭素発電電力の固定価格買取制度(FIT-CfD)を実施することが規定されました。このFIT-CfDはヒンクリー・ポイントC発電所新設計画に適用されることとなりました。また、2015年10月には、フランス電力(EDF)と中国広核集団有限公司(CGN)の間で、同計画に対してEDFが66.5%、CGNが33.5%を出資することで合意に至ったと発表され、2017年3月には、原子炉建屋外施設のコンクリート打設が開始されました。また、EDFは2018年11月に、サイズウェルC発電所の2021年末の建設開始を目指すと発表しましたが、2024年5月に英原子力規制庁(ONR)よりサイト許可(NSL)が発給されるも2025年3月時点では未着工となっています。ヒンクリー・ポイントC発電所、サイズウェルC発電所のほか、2025年3月現在、英国内ではEDFとCGNによるブラッドウェルB発電所の新設計画が進められています。
また、英国は2017年11月に「Industrial Strategy」を、2018年6月には「Nuclear Sector Deal」を公表しました。これらの中では、先進的モジュール炉の研究開発、新設、廃炉コストの削減、将来の原子力輸出等への支援策が示され、英国内の民生用原子力産業に対し、総額2億ポンドを投じるとされています。その後、2020年11月には「グリーン産業革命に向けた10ポイント計画(10 Point Plan)」を発表し、原子力の分野では、大型原子炉や小型モジュール炉、先進的モジュール炉に対し最大3.85億ポンドを投資する方針を示しました。2022年9月には「先進的モジュール炉研究開発・実証プログラム」の予備調査を行う実施事業者として、JAEAが参加するチームを採択しました。
2021年10月には、「Net Zero Strategy: Build Back Greener」が公表され、新たに1.2億ポンドの「未来の原子力実現基金」を新設することが発表されました。同月には、原子力発電所の新設に対する新たな支援制度として、規制資産ベース(RAB)モデルの導入が発表されました。RABモデルとは、設備に対する投資コストに見合った適切なリターンを規制機関が評価し、利用料を通じてそれを消費者から回収することを認める仕組みです。従来の支援制度と比較して事業の不確実性が低減されるとともに、最終的な消費者負担も軽くすることができると期待されており、RABモデルはサイズウェルC発電所に適用される予定となっています。
2022年4月には、「British Energy Security Strategy」が公表され、2030年までに最大8基の原子炉を新設し、2050年までに電力需要の最大25%を原子力で賄うという目標が示されました。また、同戦略で発表された新設のための組織である「大英原子力推進機関(Great British Nuclear)」が2023年7月に設立されました。2024年2月には「民生用原子力ロードマップ2050」が政府より発表され、前述した「British energy security strategy」で示された2050年までに電力需要の最大25%を原子力で賄う目標に対して具体策が示されました。
(ⅱ)フランス
フランスは米国に次ぐ世界第2位の原子力発電規模を有しています。発電設備が国内需要を上回っているという状況から、1990年代前半以降、原子力発電所の新規建設は行われてきませんでした。しかし、2005年7月に制定された「エネルギー政策指針法」において、2015年頃までに既存原子力発電所の代替となる新規原子力発電所を利用可能とするため、原子力発電オプションの維持が明記されたこともあり、EDFは2006年5月、新たな原子力発電所としてフラマンビル3号機の建設を決定しました。その後、2007年12月に着工しましたが、この建設には大幅な遅延が生じるも、2024年9月にフランスの原子力安全規制当局(ASN)の承認を受け、起動操作を開始し、その翌日には初臨界に達しました。
2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所事故後も、フランスは原子力政策堅持の姿勢を崩しませんでしたが、2015年8月、オランド大統領率いる社会党政権が、原子力発電による発電割合を、2025年までに50%(2015年時点では約76%)まで引き下げ発電容量についても現行の容量(63.2GW)を上限とすることを規定した「グリーン成長のためのエネルギー転換法」を成立させました。2025年までに原子力の割合を50%まで引き下げるという目標については、送電系統運用者のRTEから、計画どおり実施した場合、2020年以降の電力供給の不足やCO2の削減目標の未達が生じるとの懸念が示され、2017年5月に就任したマクロン大統領政権下の閣僚からも、非現実的であるとの見解が示されました。その結果、2017年11月に原子力の割合を50%に引き下げる目標年次の延期が決定され、2019年11月に公布した「エネルギー・気候法」では、原子力比率を50%まで引き下げる目標年が2035年と記されました。しかし、2015年に成立した「グリーン成長のためのエネルギー転換法」の規定により、新たな原子力発電所を完成させる前に古い原子力発電所を閉鎖しなければならなくなったこともあり、フェッセンハイム1、2号機が早期閉鎖されました。
2021年2月、規制当局であるASNは、運転開始から40年を迎える90万kW級原子炉について、EDFが計画している安全性向上策とASNが要求する追加措置の実施を条件に、50年運転を認める決定を発表しました。これは、1978年から1987年に営業運転を開始した32基が対象とされています。フランスでは、規制による運転年数の制限は特に設けられておらず、10年ごとに実施される各原子炉の定期安全レビューにおいて合格した場合に、その後の10年間の運転許可が付与されることとなっています。この決定により、90万kW級原子炉の全般的評価フェーズが完了し、今後は順次個別レビューが行われ、2031年までには全ての定期安全レビューが完了する予定です。
また、2022年2月にマクロン大統領は、排出削減目標の達成のため、全ての既設炉の運転期間を延長するとともに、6基のEPR2(改良型の欧州加圧水型原子炉)の新設に着手し、さらに最大で8基の新設の可能性に関する調査を開始する方針を示しました。この方針に従い、2023年6月に新たな法律が制定され、既設炉の近傍での新規建設に係る手続きが短縮されたことに加え、2035年までに原子力の割合を50%まで引き下げる目標や発電容量の上限を63.2GWとする規定が撤廃されました。また、2023年6月には、気候変動対策やエネルギー安全保障に係る施策を政府主導で進めていくことを目的として、EDFが完全国有化されています。
(ⅲ)ドイツ
ドイツでは、2002年2月に成立した改正原子力法に基づき、当時運転中であった19基の原子炉を2020年頃までに全廃する予定としていましたが、2009年9月の連邦議会総選挙においてこの「脱原子力政策」が見直され、2010年9月に原子力発電所の運転延長を認める法案が閣議決定されました。しかし、東京電力福島第一原子力発電所事故直後の2011年3月27日に行われた州議会選挙で、脱原子力発電を公約とした緑の党が躍進したことや、大都市で原子力発電所の運転停止を求めるデモが相次いだこと等により、同年4月には、連立政権も脱原子力を推進する立場へと転換しました。2011年時点でドイツ国内17基の原子炉がありましたが、それらを段階的に廃止し、再エネとエネルギー効率改善により代替していくための法律が同年8月から施行されました。これにより、8基の原子炉が即時閉鎖となりました。また、残り9基の原子炉についても2022年までに順次閉鎖されることになり、2015年から2021年にかけて6基の原子炉が閉鎖となりました。これにより、ドイツの運転中の原子力発電所は3基のみとなり、これらも2022年末に廃止される予定でしたが、2022年10月にドイツ政府は、先立って実施した電力供給と系統運用の安定性に関するストレステストの結果を踏まえ、この3基を最長で2023年4月15日まで稼働させる方針を示しました。そして同日に、残っていた3基が全て閉鎖され、これによりドイツにおける脱原子力が完了しました。
(ⅳ)その他の欧州
その他の欧州では、スペイン、スウェーデン、ベルギー、チェコ、スイス、フィンランド、ブルガリア、ハンガリー、スロバキア、ルーマニア、オランダ等において原子力発電所が運転中です。
スウェーデンでは、1980年の国民投票の結果を踏まえて、原子力発電所を段階的に廃止していくこととなり、1997年には新設禁止を定めた原子力法が制定されました。しかしその後、廃止の方針を見直す機運が高まり、2010年6月には新設禁止を定めた原子力法を改正し、当時運転中であった10基に限り、既設サイトでのリプレースを可能とする法案が議会で可決されました。その後、2012年7月には、電気事業者がよりリプレースのための調査を行うとの発表があり、規制当局に対してリプレース計画が申請されました。他方で、2019年及び2020年には、経済性の悪化を理由にリングハルス2号機及び1号機が閉鎖されました。その後、2022年10月に発足したクリステション首相率いる新政権は、原子力発電所の新規建設や、閉鎖したリングハルス原子力発電所の再稼働を推進する方針を示しました。この方針に基づき、2023年11月には、既存サイト以外での原子炉の新設を禁止する規定及び運転中の原子炉数を10基までに制限する規定を撤廃する法案が議会で可決されました。さらに、同年11月には、2035年までに大型炉2基分、2045年までに最大で大型炉10基分の新設を目指すロードマップも公表されました。
ベルギーでは、2003年1月に脱原子力発電法が成立し、これに基づき、国内にある7基の原子炉は、建設から40年経たものから順次閉鎖される予定となりました。2012年7月、ベルギー政府はこの方針を踏襲し、ドール1、2号機を2015年に廃炉にすることを決定した一方で、国内最古の原子力発電所の1つであるチアンジュ1号機については、10年間の運転延長(2025年まで運転)を決定しました。しかし、2014年10月に発足した新政権は、ドール1、2号機についても運転延長を認める方針を表明しました。その後、2018年3月に発表されたエネルギー戦略では、2025年までに全ての原子力発電所を停止することとなっていましたが、2022年3月には、ドール4号機とチアンジュ3号機の運転を10年間延長することを決定しました。他方で、同年9月にはドール3号機が、2023年1月にチアンジュ2号機が、40年の運転を経て閉鎖しました。
チェコでは、2015年5月に、2040年における原子力の割合を約49%にまで高める目標を掲げました。2019年11月には、ドコバニ原子力発電所における新規原子炉を2036年までに完成させる方針が示され、2021年3月には、規制当局がドコバニ原子力発電所の2基増設の立地許可を発行しました。2024年1月、チェコ政府は増設に係る入札について、1基ではなく最大4基の拘束力のある入札へ変更し、フランスのEDFと韓国水力・原子力会社(KHNP)を入札に招聘しました。2024年7月には価格を含む評価基準のほとんどで、より良い条件を提示していた韓国水力・原子力会社(KHNP)に優先権を与えると発表しました。
フィンランドでは、同国5基目の原子炉となるオルキルオト3号機の建設が2005年12月から行われ、工期が長引いたものの、2022年3月から電力供給を開始しています。また、2010年7月には、議会が電力事業者であるTVOとフェンノボイマの新規建設(各1基)を議会が承認しました。フェンノボイマは2012年1月にピュハヨキ(ハンヒキビ)1号機の建設の入札を行い、2013年12月に建設事業者としてロシアのロスアトムが選ばれました。しかし2022年5月、フェンノボイマは、ロスアトムの作業の遅れやロシアのウクライナへの侵略等を理由に、ロスアトムとの契約を破棄しました。なお、運転中の原子力発電所については、オルキルオト1、2号機が2038年末まで、ロビーサ1、2号機が2050年末までの運転延長を承認されています。2023年11月、TVOはクリーン・エネルギーへの移行にともない電力需要の大幅な増加が予想されているフィンランドにおいて、天候に左右されず常に発電可能な原子力発電がこの需要を満たす上で有効と考え、運転中のオルキルオト1、2号機の運転期間を少なくとも10年間延長とする可能性の分析調査を開始しました。
リトアニアでは、2011年7月、ビサギナス原子力発電所の建設のために、日立が戦略的投資家(発電所建設の出資者)として優先交渉企業に選定されました。2012年10月には、国政選挙とあわせて実施された国民投票で6割強が原子力発電建設に反対し、政権も交代したためプロジェクトは停滞しましたが、2014年3月にはウクライナ情勢を受けてエネルギー安全保障への関心が高まり、与野党間で再度プロジェクト推進の合意がなされました。2014年7月には、リトアニア・エネルギー省と日立の間で、事業会社の設立に向けたMOUが署名されました。しかし、2016年11月、政府は費用対効果が悪化する中、エネルギー安全保障上必要となるまで計画を凍結すると発表しました。
他にも、原子力発電を導入していないポーランドでは、気候変動対策やエネルギー安全保障などの観点から、原子力発電所の新規導入が検討されています。2020年10月に閣議決定された「原子力発電プログラム」、及び2021年2月に閣議決定された「2040年までのエネルギー政策」では、2033年に初号機の運転を開始し、2043年までに計6基の原子力発電所を建設する目標が示されました。初号機には米国ウエスチングハウスの加圧水型原子炉(AP1000)が選定されており、2023年7月には建設計画に対して「原則決定」が発給されました。建設サイトは同国北部のポモージェ県が予定されており、2024年8月には同県に対してAP1000の導入実施主体である国営電力会社(PEJ)が建設準備作業の許可申請を行っています。
(ウ)アジア地域
(ⅰ)中国
中国では、2014年11月に公表された「エネルギー発展戦略行動計画2014-2020」では2020年の原子力発電設備容量を5,800万kWへと拡大させる目標が示されました。その後、2018年に新たに7基が営業運転を開始したことにより、世界第3位の原子力発電大国となりました。また、2020年から2024年にかけて、中国が開発を進めてきた第3世代原子炉「華龍一号」を含む計9基が営業運転を開始し、直近では、2022年3月に公表された「第14次5ヵ年計画」において、2025年の原子力発電設備容量を7,000万kWとする目標が示されました。2025年3月時点で、中国製第3世代原子炉「CAP1000」を含む計29基の建設が進められています。
(ⅱ)台湾
台湾では、2005年の「全国エネルギー会議」において、既存の3か所のサイトでの原子力発電の運転と、龍門原子力発電所の建設プロジェクトの継続が確認されましたが、その後は原子力発電所の新規建設は行わず、既設炉を40年間運転させた後、2018年から2024年の間に廃炉にするとの方針が示されました。東京電力福島第一原子力発電所事故後の2011年11月に明らかにされた原子力政策の方向性でも、その方針に変更はありませんでした。
しかし、2014年4月、野党や住民による原子力発電への反対の声が高まったことを受け、台湾当局は、龍門原子力発電所の建設を凍結し、当該原子力発電所の稼働の可否については、必ず公民投票を通じて決定しなければならないこととなりました。さらに2017年1月には、2025年までに全ての原子力発電所の運転を停止することを含んだ電気事業法の改正案が可決されました。しかし、同年8月には台湾各地で大規模な停電が発生し、産業界が安定的な電力供給を求めてエネルギー政策の見直しを当局に要請しました。2018年11月には公民投票の結果を受け、「2025年までに全ての原子力発電所の運転を停止する」との条文が削除されました。一方で、2018年から2023年にかけて計4基が廃止されました。2021年12月には、凍結されている龍門原子力発電所の建設の再開是非を問う公民投票が実施されましたが、これは反対多数で否決されました。直近では、40年の運転期間を満了したとして、2023年3月に國聖2号機が、2024年8月には馬鞍山1号機が閉鎖となりました。これにより台湾で運転中の原子力発電所は馬鞍山2号機のみとなっています。
(ⅲ)韓国
韓国は、2014年1月に、「第2次国家エネルギー基本計画」を閣議決定し、2035年の原子力発電の割合を29%とすることを決定しました。
しかし、2017年5月に発足した文政権は、「脱原子力政策」への転換を宣言し、同年10月には、原子力発電所の段階的削減と再エネの拡大を中心とするエネルギー転換政策のロードマップを閣議決定しました。このロードマップにおいて、既に建設許可が下りていたセウル3、4号機(新古里5、6号機)については、建設準備作業を再開するとした一方で、これら2基以降の新設原子力発電所の建設計画については全面白紙化し、原子力発電所の運転期間の延長も認めない方針が示されました。同年12月には、このロードマップに沿った「第8次電力需給基本計画」が閣議決定され、段階的に原子力を縮小し、2030年の発電電力量に対する原子力の割合を23.9%まで減らすこととしました。この方針に基づき、2018年6月、既設炉1基の早期閉鎖と4基の建設計画の中止が決定されました。また、2020年12月に発表された「第9次電力供給基本計画」では、2034年の発電設備容量に対する原子力の割合を10.1%まで減らす方針が示されました。
しかし、2022年5月に発足した尹政権は、これまでの脱原子力政策を撤回し、原子力を推進する立場へと転換しました。2023年1月には「第10次電力需給基本計画」を採択し、2030年の発電電力量に対する原子力の割合を30%以上に高めることや、中止が決定していた新ハヌル3、4号機の建設を再開すること等を表明しました。2025年2月、韓国政府は「第11次電力需給基本計画」を発表し、2038年までに大型炉2基、小型モジュール炉(SMR)1基の合計3基の原子力発電所を新たに建設するとしています。
(ⅳ)インド
インドでは、電力需要が増加する中、原子力に対する期待が高まっています。2005年7月、インドと米国の両政府は民生用原子力協力に関する合意に至り、2007年7月には両国間の民生用原子力協力に関する二国間協定交渉が実質合意に至りました。この協定は、原子力供給国グループ(NSG: Nuclear Suppliers Group)におけるインドへの原子力協力の例外化(インドによる核実験モラトリアム等の「約束と行動」を前提に、核兵器不拡散条約非締約国のインドと例外的に原子力協力を行うこと)の決定やIAEAによる保障措置協定の承認、両国議会による承認等を経て、2008年10月に発効しました。この原子力供給国グループによる例外化の決定以降、インドは米国とだけでなく、ロシア、フランス、カザフスタン、ナミビア、アルゼンチン、カナダ、英国、韓国といった国々とも民生分野で原子力協力協定を締結しています。2017年7月には、日印原子力協定が発効しました。
電力需給のひっ迫が続くインドでは、東京電力福島第一原子力発電所事故以降も、原子力発電の利用を拡大するとの方針に変化はなく、2023年5月に発表された「国家電力計画2022-2032」では、2032年までに原子力発電設備容量を1,968万kWへ拡大させる見通しを示しました。2024年7月、インドのN.シタラマン財務大臣は2024年度の予算を発表するとともに原子力発電シェアの拡大に向け、民間部門と提携し国産小型モジュール炉の研究開発等を支援していくと発表しました。
(エ)ロシア
ロシアでは、1986年のチョルノービリ原子力発電所(現在のウクライナに所在)事故以降、原子力発電所の新規建設が途絶えていましたが、近年は積極的に推進するようになっています。
2007年にロシア政府は、連邦原子力庁であったロスアトムを国営公社へと再編し、ロスアトムがロシアにおける原子力の平和利用と軍事利用を一体的に運営することになりました。この結果、ウラン探鉱・採掘、燃料加工、発電、国内外での原子炉建設等、民生用の原子力利用に関して国が経営権を握っていたアトムエネルゴプロムも、ロスアトムの傘下に入ることとなりました。
2009年11月ロシア政府が承認した「2030年までを対象期間とする長期エネルギー戦略」では、総発電量に占める原子力の割合を2008年の16%弱から2030年には20%近くまで引き上げること等が掲げられました。2019年10月には、「2035年までのロシア連邦のエネルギー戦略」を公表し、2035年の原子力による発電電力量が、低位ケースで227TWh、高位ケースで245TWh(2019年時点では209TWh)まで増加するという見通しを示しました。同年12月には、ロシアの浮体式原子力発電所が初めて系統に接続され、2021年3月には、レニングラードII-2号機が営業運転を開始しました。また、ロシアは国内での原子力発電所の開発のみならず、原子力の輸出も積極的に進めています。
③核燃料サイクルの現状
(ア)ウラン資源
ウラン資源は世界に広く分布しており、カザフスタン、カナダ、ナミビア、豪州等が生産量、資源量ともに上位を占めています(第22-2-13、第22-2-14)。
【第22-2-13】世界のウラン生産(2022年)
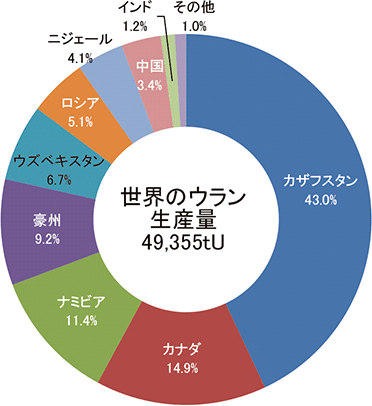
【第22-2-13】世界のウラン生産(2022年)(xlsx形式:18KB)
- 資料:
- 世界原子力協会(WNA)ホームページを基に作成
【第22-2-14】世界のウラン既知資源量(2021年)
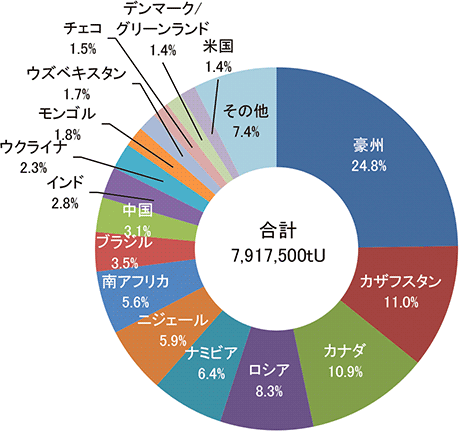
(注1)ウラン既知資源量とは260米ドル/kgU以下のコストで回収可能な埋蔵量(2021年1月1日時点)。
(注2)2020年のウラン需要量は6.01万トンU。
【第22-2-14】世界のウラン既知資源量(2021年)(xlsx形式:19KB)
- 資料:
- IAEA・OECD/NEA「Uranium 2022: Resources, Production and Demand」を基に作成
ウラン価格(スポット価格)は、第一次オイルショック後の原子力発電の拡大に伴い、1970年代に上昇しましたが、1979年のスリーマイル島事故や1986年のチョルノービリ事故を受けて新規建設が低迷したことから下落し、その後は低い水準で推移してきました。そうした中、2000年代半ば頃からは価格が上昇傾向となり、2007年には一時136ドル/ポンドU3O821(以下「ドル」という。)にまで急騰しました。その後、2008年の世界金融危機の影響で価格は急落しましたが、2011年3月にも一時60ドルを超える高値となりました。これは、解体核高濃縮ウランや民間在庫取崩し等の二次供給の減少や、中国等によるウラン精鉱の大量購入等から需給ひっ迫が懸念され、世界的にウラン獲得競争が激化したことと、投機的資金の一部がウランスポット取引市場に流入したことによるものと考えられています。その後は、東京電力福島第一原子力発電所事故等の影響により価格が下落し、一時20ドル以下となりました。しかし近年では、CO2の排出削減に資する安定電源としての原子力への注目の高まりや、2022年2月に発生したロシアによるウクライナ侵略以降のロシア産ウランの供給途絶の懸念の高まり等から、価格は上昇傾向が、足下では下落も見られます(第22-2-15)。
【第22-2-15】ウラン価格(U3O8)の推移
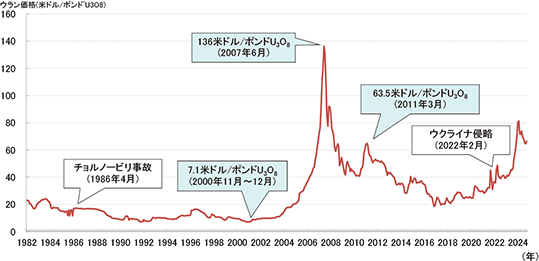
【第22-2-15】ウラン価格(U3O8)の推移(xlsx形式:38KB)
- 資料:
- IMF「IMF Primary Commodity Prices」を基に作成
(イ)ウラン濃縮
世界のウラン濃縮事業は、2022年時点で、ロシアのロスアトム、フランスのオラノ、米国・英国・オランダ・ドイツの共同事業体URENCOの3社合計で年間53,800tSWU22の生産能力を有し、世界全体の約9割のシェアを占めています23。ロスアトムは世界全体の生産能力の4割以上を占めていますが、2022年2月にロシアがウクライナに侵略したことを受け、米国等の西側諸国ではロシア産濃縮ウランの輸入禁止を検討する等、ロシア産濃縮ウランの供給途絶が懸念されています。また、オラノは2028年までに年間250トンSWU、URENCOは2025年から順次年間1,450トンSWUの生産能力拡張を行う方針です。オラノは2024年10月にフランス南部のトリカスタン・サイトにあるジョルジュ・ベスⅡ濃縮工場の拡張工事を開始し、URENCOは米ニューメキシコ州ユーニスにある同社の濃縮プラントの拡張プロジェクトの一環として、最初の新型遠心分離機を設置しました。
日本のウラン濃縮事業は遠心分離法を採用しており、日本原燃は、1992年3月に年間150トンSWUの規模で操業を開始し、1998年末には年間1,050トンSWU規模に到達しました。その後、一部の遠心分離機の新型機への更新や生産機能の停止によって、2025年3月時点の施設規模は年間450トンSWUになっています。今後、段階的に新型遠心機の更新工事等を行い、最終的には年間1,500トンSWU規模を達成する計画です。
(ウ)再処理
フランス及び英国では、自国内で発生する使用済燃料の再処理を実施するとともに、海外からの委託再処理も実施してきました。フランスのオラノは、海外からの委託再処理を行うためのUP3(処理能力:1,000トン・ウラン/年、操業開始:1990年)及びフランス国内の使用済燃料の再処理を受け持つUP2-800(処理能力:1,000トン・ウラン/年、操業開始:1994年)の再処理工場をラ・アーグに有しています24。
英国原子力廃止措置機関(NDA)は、セラフィールド施設及び海外からの委託再処理を行うためTHORP(処理能力:900トン・ウラン/年、操業開始:1994年)再処理工場をセラフィールドに有していましたが、2018年11月に操業を終了しました。
(エ)プルサーマル
使用済燃料から再処理によって分離されたプルトニウムをウランと混ぜた混合酸化物燃料である「MOX燃料」の使用については、海外で既に相当数の実績があります。1970年代から2021年末までに、フランスやドイツ、スイス、ベルギー等の9か国の約50基の発電プラントにおいて、MOX燃料約6,300体が使用されました。例えばフランスでは3,500体、ドイツでは2,474体のMOX燃料が軽水炉で利用されました(2021年末時点)。また、軽水炉用のMOX燃料加工施設は、フランスで稼働しています。
(オ)高レベル放射性廃棄物の処分
高レベル放射性廃棄物の処分については、各国の政策により、使用済燃料を直接処分する国と、使用済燃料の再処理を実施してガラス固化体として処分する国があります。高レベル放射性廃棄物の処分方法を決定している国では、全て地層処分を行う方針が採られており、処分の実施主体の設立、処分のための資金確保等の法制度が整備されるとともに、処分地の選定、必要な研究開発等が積極的に進められてきました(第22-2-16)。
【第22-2-16】高レベル放射性廃棄物処分に関する各国の状況
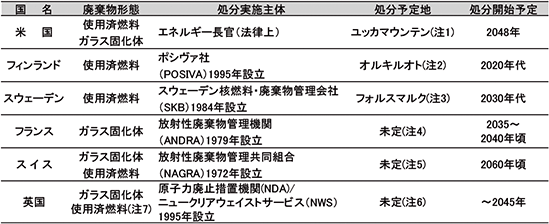
(注1)ネバダ州のユッカマウンテンは安全審査段階だが、現在は安全審査が中断している状況。
(注2)2001年5月に処分地として決定。2016年12月に処分場の建設を開始。2021年12月に操業許可を申請。
(注3)2009年6月に処分地として決定。2022年1月に政府が事業許可を発給。
(注4)ビュール地下研究所近傍において法律に基づいた検討プロセスが進んでおり、2023年1月に設置許可を申請。
(注5)処分場のサイト選定は、原子力令に従って策定された特別計画に基づいて3段階で進められている。その第1段階として、2011年11月に、高レベル放射性廃棄物の処分場の「地質学的候補エリア」3か所が正式に選定された。その後、第2段階として「地質学的候補エリア」の検討が行われ、2018年11月に、「ジュラ東部」、「チューリッヒ北東部」、「北部レゲレン」が、第3段階に進む候補エリアに決定された。第3段階として放射性廃棄物管理共同組合(NAGRA)は各候補エリアにおいてボーリング調査等を実施し、2022年9月に「北部レイゲン」を処分場サイトとして政府に提案した。2024年に概要承認申請が実施される予定。
(注6)カンブリア州とカンブリア州内の2市がサイト選定プロセスへの関心表明を行っていたが、2013年1月にカンブリア州議会がプロセスからの撤退を議決した。2市の議会についてはプロセスへの継続参加に賛成していたが、州と市の両方の合意を必要としていたため、1州2市はプロセスから撤退することとなった。その後、2014年7月に、英国政府は地層処分施設の新たなサイト選定プロセス等を示し、2018年からは新しいサイト選定プロセスを実施している。2020年11月以降、カンブリア州のコープランド市とアラデール市、リンカンシャー州の計3自治体が、調査エリアの特定に向けたワーキンググループを設置しており、それぞれ、コープランド市の2地域、アラデール市、リンカンシャー州の計4地域において、コミュニティーパートナーシップが設置された。
(注7)施設の操業計画によっては再処理しない使用済燃料が残る可能性があり、それらを地層処分する可能性も考慮している。
【第22-2-16】高レベル放射性廃棄物処分に関する各国の状況(pptx形式:57KB)
- 資料:
- 資源エネルギー庁「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について(2024年版)」(2024年2月)を基に作成
(ⅰ)米国
1987年の放射性廃棄物政策修正法により、ネバダ州のユッカマウンテンが唯一の処分候補地として選定されました。その後、処分場に適しているかどうかを判断するための調査を経て、2002年に、DOEがユッカマウンテンを処分サイトとして大統領に推薦しました。
2009年に発足したオバマ政権は、ユッカマウンテン計画を中止し、高レベル放射性廃棄物処分に関する代替策を検討する方針を示しました。これに伴い、NRCは2011年9月に、ユッカマウンテン処分場の建設認可に係る許認可申請書の審査手続の一時停止を決定しました。
DOEは、2010年1月に米国の原子力の将来に関するブルーリボン委員会を設置して代替策の検討を行い、2012年1月には最終報告書が公表されました。2013年1月には、DOEが公表した「使用済燃料及び高レベル放射性廃棄物の管理・処分戦略」において2021年までにパイロット規模の使用済燃料の中間貯蔵施設の操業を開始し、2025年までにより大規模な中間貯蔵施設を建設、2048年までに処分場を操業開始できるように処分場のサイト選定とサイト特性調査を進めるという枠組が示されました。
2017年4月には、連邦議会下院でユッカマウンテン計画の維持を目的とする議論が開始される等、放射性廃棄物管理政策に関連する取組は活発化しました。しかし、ユッカマウンテンに関連するネバダ州の反対で膠着状態となったことから、2020年2月に、トランプ政権は代替となる解決策を開発する方針を表明しました。2021年1月に発足したバイデン政権は、オバマ政権時に示されたブルーリボン委員会の勧告に基づき、同意に基づくサイト選定によって使用済燃料の中間貯蔵を進める方針としていました。
(ⅱ)フィンランド
フィンランドでは、1983年よりサイト選定が開始され、1999年に処分実施主体であるポシヴァがオルキルオトを処分予定地として選定し、法律に基づく「原則決定」の申請書をフィンランド政府に提出しました。その後、2000年に地元が最終処分地の受入を承認したことを受け、フィンランド政府がオルキルオトを処分地とする原則決定を行い、2001年に国会がそれを承認しました。
2012年12月、ポシヴァはフィンランド政府へ最終処分場の建設許可申請書を提出しました。放射線・原子力安全センターは、建設許可申請書に係る安全審査を行い、2015年2月に、キャニスタ封入施設及び地層処分場を安全に建設することができるとする審査意見書を雇用経済省に提出しました。同年11月に、フィンランド政府はポシヴァに対して建設許可を発給し、2016年12月にポシヴァは処分場の建設を開始しました。その後、2021年12月にはポシヴァが処分場の操業許可を政府に対して申請しました。2024年8月には実際の最終処分作業に先立つ、安全性確認のための試験操業を開始しました。処分開始は、操業許可の発給後、2020年代半ばの予定とされています。
(ⅲ)スウェーデン
スウェーデンでは、スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(以下「SKB」という。)が、1993年からの調査結果を受けて、2009年6月は、地質条件を主たる理由としてエストハンマル自治体のフォルスマルクを最終処分場予定地として選定しました。2020年10月のエストハンマル自治体議会は使用済燃料処分場の受入意思を議決し、これを受け、スウェーデン政府は2022年1月に事業許可を発給しました。2024年10月には、SKBは土地・環境裁判所よりフォルスマルクに使用済燃料の最終処分場およびオスカーシャム自治体に地上の使用済燃料封入プラントを建設・操業を可能にする許可を取得しました。
また、スウェーデンのオスカーシャム自治体には、使用済燃料の集中中間貯蔵施設(以下「CLAB」という。)があり、SKBが1985年から操業しています。2021年9月には、貯蔵容量が11,000トンに引き上げることが決定されました。
(ⅳ)フランス
フランスでは、1991年に「放射性廃棄物管理研究法」が制定され、地層処分、核種分離・変換、長期地上貯蔵の3つの高レベル放射性廃棄物に関する管理方法の研究が15年間を期限に実施されました。地層処分については、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)が、カロボ・オックスフォーディアン粘土層のあるビュールにおいて、2000年8月から立坑の掘削を開始して地下研究所を建設し、研究を行いました。その後、法律に基づいて設置された国家評価委員会は、2006年に、3つの管理方法に関する研究成果を総合的に評価しました。これらを基に2006年6月には可逆性のある地層処分の実施に向けて「放射性廃棄物等管理計画法」が制定されました。この中では、2015年に処分場の設置許可申請を行い、2025年に処分場の操業を開始すること、設置許可申請は地下研究所による研究対象となった地層に限定することが定められました。また、環境法典が改正され、ANDRAによる地層処分場の操業は、可逆性と安全性の立証を目的とする「パイロット操業フェーズ」から始めることとなりました。
その後、ANDRAは、ビュール地下研究所周辺の候補サイト区域をフランス政府に提案し、2010年3月のフランス政府の了承を経て、同区域の詳細調査を実施しました。2013年5月から2014年2月にかけて地層処分の設置に関する公開討論会及び市民会議が実施され、これらの総括報告書及び市民会議の見解書が2014年2月に公開されました。この報告書等を受けて、ANDRAは地層処分場プロジェクトの継続に関する方針を決定し、2014年5月には、今後のプロジェクト継続計画を公表しました。2020年8月には、工事の許認可に必要となる地層処分場の設置に関する公益宣言が申請され、2022年7月に、フランス政府は公益宣言を発出しました。その後、2023年1月にはANDRAが地層処分場の設置許可申請を行いました。
- 1
- 「可採資源量」とは、技術的に生産することができる石油資源量を表したもので、経済性やその存在の確からしさ等を厳密に考慮していないという点で、「確認埋蔵量」より広い範囲の資源量を表しています。
- 2
- OPEC加盟国のうち、内戦等の特殊事情により減産状態にあるベネズエラ、リビア、イランは減産の対象外とされました。
- 3
- 当初は計25か国でしたが、2019年1月にカタール、2020年1月にエクアドル、2024年1月にアンゴラがOPECを脱退したことにより、2024年3月末時点では計22か国となっています。
- 4
- デンマークとスウェーデンの間にある、バルト海と北海を結ぶ海峡の総称のこと(Danish Straits)。
- 5
- 売主がお金を支払い、買主がお金を受取ることを意味します。
- 6
- ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせた発電方式のこと。
- 7
- 米国は世界有数のパイプラインによる天然ガス輸出国でもあります。
- 8
- CIF:Cost, Insurance and Freightの略で、CIF価格とは、積出地での価格に運賃や船荷保険料を加えた価格のこと。
- 9
- 米国国内のガス取引価格の指標となっている、ルイジアナ州にある天然ガスのパイプラインの接続地点(ハブ)の呼び名。Henry Hub価格と日本のLNG輸入価格を比較する場合には、天然ガスの液化・気化コストやLNG船での輸送コスト等を考慮する必要があります。
- 10
- FOB:Free On Boardの略で、FOB価格とは積地引渡し価格のこと。
- 11
- 石炭の根源植物が石炭に変質する過程を石炭化作用と呼び、この進行度合いのことを石炭化度といいます。石炭は、石炭化度によって無煙炭、瀝青炭、亜瀝青炭、褐炭、亜炭、泥炭に分類されますが、日本では無煙炭から褐炭までを一般的に石炭と呼んでいます。
- 12
- 政府が電気事業者等に対し、再エネから発電された電力の調達量を義務的に割り当てる制度です。
- 13
- 21世紀のための再生可能エネルギー政策ネットワーク(REN21)「Renewables 2024 Global Status Report-Energy Supply」より。
- 14
- 資源エネルギー庁の発表より。
- 15
- IRENA「Renewable Capacity Statistics 2024」より。
- 16
- IEA「World Energy Balances 2024」より。
- 17
- IEA「World Energy Balances 2024」より。
- 18
- Clean Skies for Tomorrow Coalition「2030 Ambition Statement」より。
- 19
- 国土交通省「第1回SAFの導入促進に向けた官民協議会」説明資料より。
- 20
- ここでの発電コストは均等化発電単価(LCOE)を指しますが、将来、再エネの大量導入が進んだ社会を考えると、LCOEのみでは必ずしもコストの全体像を捉えられないとの考え方も広がってきており、社会全体での統合コストに着目する必要もあります。
- 21
- U3O8(八酸化三ウラン):ウラン鉱石を精錬したもので、ウラン精鉱やイエローケーキとも呼ばれます。
- 22
- SWU(Separative Work Unit=分離作業量)は、ウランを濃縮する際に必要となる仕事量を表す単位です。例えば、濃度約0.7%の天然ウランから約3%に濃縮されたウランを1kg生成するためには、約4.3kgSWUの分離作業量が必要です。
- 23
- World Nuclear Association「Uranium Enrichment」(2022年10月更新)より。
- 24
- UP3及びUP2-800における処理能力の合計は、1,700トンHM/年に制限されています