第1節 世界的なエネルギーの需給ひっ迫と資源燃料価格の高騰
エネルギー政策を考える上では、安全性を大前提として、まずはエネルギーの安定的な供給、そして、経済性の確保(エネルギーコストの抑制)、環境との調和等が重要な要素とされています。しかし、2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナへの侵略を契機に、世界のエネルギーを取り巻く情勢は混迷を深めるとともに大きく変化し、特にエネルギーの安定供給やエネルギーコストの面で、世界各国に大きな影響を与えることとなりました。
2021年から上昇傾向にあったエネルギー価格でしたが、2022年には、さらに高騰することとなり、世界各地の天然ガス市場では過去最高値を記録しました(第121-1-1)。ロシアのウクライナ侵略等を起因とする、こうした世界のエネルギー情勢の変化は、短期的なエネルギーの需給ひっ迫や価格高騰を引き起こしただけでなく、中長期的にもエネルギー市場への影響を及ぼすことが予想されています。
【第121-1-1】エネルギー市場価格の推移
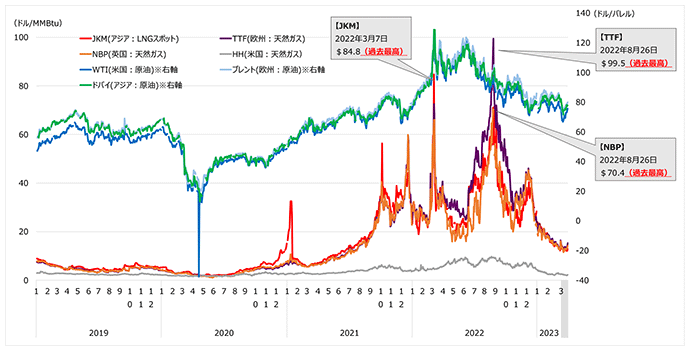
【第121-1-1】エネルギー市場価格の推移(ppt/pptx形式:115KB)
- 資料:
- S&P Global Platts等を基に経済産業省作成
本節では、まずロシアによるウクライナ侵略等を起因として生じた世界のエネルギーの需給ひっ迫やエネルギー価格高騰の状況、そしてその背景等を概観した上で、こうした危機に対して世界各国で取られた対応や政策の動向等について整理を行います。
1.世界的なエネルギーの需給ひっ迫の背景
2021年は世界全体で新型コロナ禍からの経済回復や、寒波の到来等によるエネルギー需要の増加に加えて、LNGプラントでのトラブル等も重なったことで、エネルギーの需給ひっ迫が発生していました。それに伴い、2021年から原油や天然ガス等のエネルギー価格も上昇を始めていました。そうした状況の中、2022年2月にロシアによるウクライナ侵略が発生したことで、エネルギー市場における混迷が一層拡大することとなりました。
(1)ロシアのウクライナ侵略
ロシアによるウクライナ侵略を受け、EUやG7を始めとする欧米諸国を中心にロシアに対する大規模な経済制裁が行われることとなりました。その中で、エネルギーの分野においてもロシア産エネルギーからの脱却へと舵を切っていくことになりましたが、このことは世界のエネルギーの需給構造を大きく変化させる一因となりました。以降では、世界のエネルギー市場におけるウクライナ侵略前のロシアの存在や、欧米諸国が実施した経済制裁の内容等について整理していきます。
①世界のエネルギー市場におけるロシアの存在
本項ではまず、欧米諸国等によるロシアへの経済制裁の影響が表れていない2020年における、ロシアの天然ガス・原油・石炭の生産量を見ていきます(第121-1-2)。いずれのエネルギーについても、世界全体の生産量の中でロシアが占める割合は大きく、天然ガスはシェア率17%で世界第2位、原油はシェア率12%で世界第3位、石炭はシェア率5%で世界第6位の生産国となっていました。これらのデータから、ロシアが世界のエネルギー市場にとって大きな存在であるということがわかります。
【第121-1-2】世界の化石エネルギー生産に占めるロシアの割合(2020年)
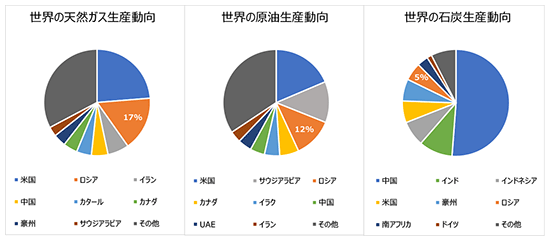
【第121-1-2】世界の化石エネルギー生産に占めるロシアの割合(2020年)(ppt/pptx形式:50KB)
- 資料:
- BP「bp Statistical Review of World Energy 2021」等を基に経済産業省作成
その上で、ロシアのウクライナ侵略が各国のエネルギー情勢に与えた影響は、それぞれの国の一次エネルギー自給率や、石油・天然ガス・石炭のロシアへの依存度によって大きく異なります。そこで次に、G7各国の一次エネルギー自給率や、各エネルギーのロシア依存度を見ていきます(第121-1-3)。
【第121-1-3】ロシアによるウクライナ侵略前のG7各国の一次エネルギー自給率とロシアへの依存度
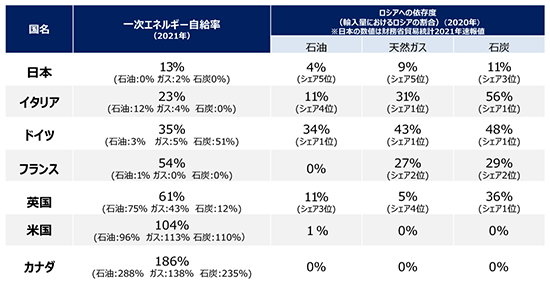
【第121-1-3】ロシアによるウクライナ侵略前のG7各国の一次エネルギー自給率とロシアへの依存度(ppt/pptx形式:53KB)
- 資料:
- World Energy Balances 2022(自給率)、BP統計、EIA、Oil Information、Cedigaz統計、Coal Information(依存度)、貿易統計(日本)を基に経済産業省作成
欧州諸国は、ロシアと地続きであることもあり、ロシアへのエネルギー依存度が高くなっていたことがわかります。ドイツやイタリアではパイプラインを用いてロシアから天然ガスを輸入していたこともあり、天然ガスのロシア依存度がそれぞれ43%、31%となっていました。その他のエネルギーに関しても、欧州諸国は、ロシアに依存している割合が高くなっており、次項で記載するロシアに対する経済制裁によってロシア産エネルギーから脱却していくに当たって、足元で代替となるエネルギーの確保が迫られることとなりました。
他方で米国やカナダは、一次エネルギー自給率が100%を超えていることもあり、欧州諸国と比べるとエネルギーのロシア依存度は著しく低くなっており、ロシア産エネルギーから脱却するに当たっての影響は比較的小さかったことが想定されます。
②世界各国によるロシアへの経済制裁
こうした状況の中、2022年2月にロシアがウクライナに侵略したことを受け、欧米諸国を中心にロシアに対する様々な経済制裁が実施されました。この経済制裁の対象にはエネルギー分野も含まれており、その結果、エネルギーの多くをロシアに依存してきた欧州を始め、世界全体のエネルギーの需給構造と価格にも大きな影響を及ぼすこととなりました(第121-1-4)。
【第121-1-4】ロシア産エネルギーを巡る動向
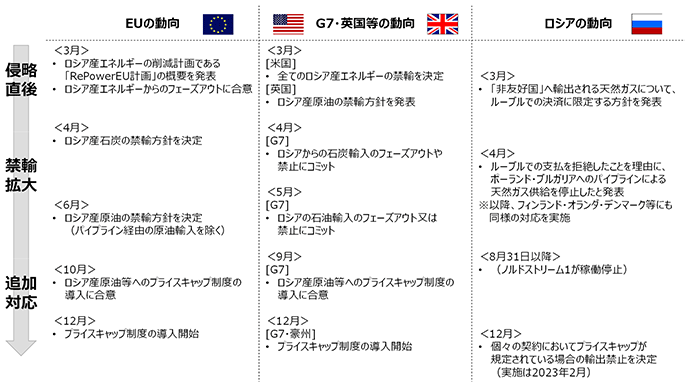
【第121-1-4】ロシア産エネルギーを巡る動向(ppt/pptx形式:140KB)
- 資料:
- 各国政府資料等を基に経済産業省作成
具体的な制裁として、ロシアによるウクライナ侵略が発生してから2週間以内に、米国では全てのロシア産エネルギーの輸入禁止の方針が示され、英国でもロシア産原油の段階的な輸入禁止の方針が示されました。またEUでも、2022年3月8日にはロシア産エネルギーからの脱却の方針を示した「REPowerEU計画1」が発表されました。
その後もロシアによるウクライナ侵略の長期化により、制裁の内容は順次拡大されていきました。EU第5弾制裁パッケージ(2022年4月採択)では石炭、EU第6弾制裁パッケージ(同年6月採択)でパイプラインを除く原油の禁輸の方針等が決定されています。また、G7は、「ロシアの石油の輸入のフェーズアウト又は禁止等を通じて、ロシアのエネルギーへの依存状態をフェーズアウトすることをコミットする。我々は、適時にかつ秩序立った形で、また、世界が代替供給を確保するための時間を提供する形で、これを行うことを確保する」ことに合意しました。
さらに、ロシアの石油収入を減少させつつ、国際原油市場の混乱を回避しながら原油価格の上昇圧力を緩和させるという目的で、2022年9月にG7財務大臣会合においてプライスキャップ制度の導入が合意され、プライスキャップ当初導入国であるG7各国と豪州では、ロシア産原油については同年12月から、ロシア産石油製品については2023年2月から、プライスキャップ制度を開始しました。このプライスキャップ制度とは、一定の価格を超えるロシア産原油・石油製品の海上輸送等に関連するサービス(船舶保険等)を禁止2するものです。
一方で、ロシア側でもエネルギーの供給に関して動きがありました。2022年3月23日には、「非友好国」へ輸出される天然ガスの支払貨幣をルーブルに限定することを発表し、同年4月27日にはルーブルでの支払を拒絶したことを理由に、ポーランドとブルガリアへのパイプラインでの天然ガスの供給を停止しました。その後も同様の理由でフィンランドやオランダ、デンマーク、フランス等への天然ガスの供給を停止しています。
さらに、ロシアからドイツ経由で欧州に天然ガスを供給している海底パイプライン「ノルドストリーム1」については、ロシアの国営天然ガス企業であるガスプロム社が2022年8月31日から9月2日の3日間、点検のためにガス供給を停止していましたが、その際、技術的な問題が見つかった、として再稼働が無期限に延期されることとなりました。その後、同年9月26日にノルドストリーム1が損傷し、ガス漏れが発覚したこともあり、供給が再開される見通しは立っていません。
また、ロシアは2023年2月以降、個々の契約においてプライスキャップが規定されている場合に輸出を禁止する等の措置も取っています。
③ロシアへの制裁と供給停止による影響
ロシア産エネルギーからの脱却を目指す欧米諸国、特にロシア依存度の高い欧州諸国では、ロシア産エネルギーに変わるエネルギーの確保が早急に求められることとなりました。詳細は後述しますが、欧州ではロシアからパイプラインを用いて輸入していた天然ガスの代替エネルギーとして、特にLNGへの需要が急激に高まり、世界中のLNGの市場価格が急騰しました。その結果、これまでも主要なエネルギー源としてLNGを輸入していたアジア諸国等、ロシアへのエネルギー依存度がそれほど高くなかった国でも、LNGの需給ひっ迫やエネルギー価格高騰等の影響を受けることとなりました。
同様に原油や石炭市場においても、ロシアへの経済制裁の影響が生じました。制裁によりロシア産の原油や石炭が禁輸の対象になったことや、ロシア産エネルギーの供給途絶リスクが高まったこと等により、市場価格が高騰しました。
(2)その他の供給減・需要増の要因
ロシア以外のエネルギー輸出国では、LNG関連設備のトラブル等も発生しており、このこともLNGの供給力不足、ひいては需給ひっ迫の一因となっています。
マレーシアでは国営石油・ガス会社であるペトロナス社が、2022年9月21日に発生した土砂崩れによって生産設備の主要なパイプラインの機能不全が生じたとして、同年10月4日にLNGの供給に対して、不可抗力による供給停止(フォース・マジュール)を宣言しました。この宣言によりペトロナス社は供給義務を免れることとなり、マレーシア産のLNGに頼っていたアジアのLNG市場において、大きな混乱をもたらす一因となりました。
さらに、日本企業もLNG調達契約を結んでいる米国のフリーポートLNGプロジェクトにおいても、2022年6月8日に設備火災が発生し、操業を停止しました。その後、復旧を進めて一部操業を再開し、2023年2月11日には出荷を行いましたが、今回の世界的なLNGの需給ひっ迫を助長する一因となりました。
また、2022年7月には豪州において、豪州国内が「ガス不足」と判断された場合、LNGの輸出を制限し、原料ガスの一部を豪州国内向けに優先供給する「豪州国内ガス安全保障メカニズム(ADGSM)」を2030年まで延長することが決定されました。同年9月に、2023年の発動は当面のガス供給にめどが立ったとして見送られましたが、今後の状況によっては発動する可能性も残っています。これによって、豪州国外への供給に対して、不測の影響を及ぼす可能性があります。
さらに過去数年を見返すと、LNG設備のトラブルによる供給停止だけでなく、2020年に発生したパナマ運河の大渋滞等、世界全体のエネルギー需給に影響を及ぼす事例はたびたび発生しており、短期的にエネルギーの安定供給を脅かす要因は数多く存在しているといえます。
またLNGの需要を増加させる要因としては、他の電源との兼ね合いが挙げられます。2021年度は欧州における天候不順や風力不足への対応として天然ガス火力への需要が高まりましたが、2022年度においても、フランスで原子力発電所が停止した際には、天然ガス火力への需要が高まりました。
このように世界のLNG需給バランスは国内外の様々な要因により、大きな影響を受けていることがわかります。
(3)化石エネルギーの上流投資の減少
エネルギーの需給ひっ迫が生じた背景には、ここまで述べてきた短期的な要因だけではなく、長期的・構造的な要因もあります。その1つとして、2015年のパリ協定を契機に、化石エネルギーに対する政策や需要動向が不透明となったことを受け、ガス田や油田といった上流部門への投資額が、大きく減少し続けている傾向にあることが挙げられます(第121-1-5)。こうした過去の投資額の減少が、現在のエネルギー供給力の不足の一因にもなっていると考えられます。さらに過去の投資額の減少による影響は、今後も続く可能性が指摘されています。例えば、国際エネルギー機関(IEA)が2022年に発表したガス・マーケットレポート3において、2020年・2021年に天然ガスの上流部門へ投資された金額は、新型コロナ禍の影響もあり、Net Zero Emissionシナリオ4で想定されている水準にも満たず、12%不足していると分析されています。
【第121-1-5】新規・既存の天然ガス・石油田における上流投資額の推移
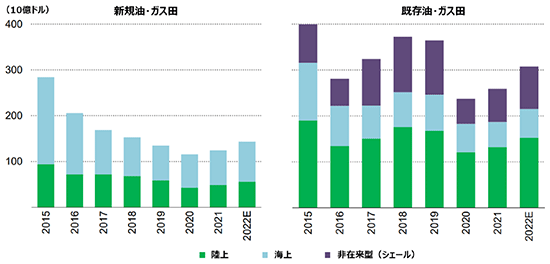
【第121-1-5】新規・既存の天然ガス・石油田における上流投資額の推移(ppt/pptx形式:129KB)
- 資料:
- IEA「World energy investment 2022」を基に経済産業省作成
こうした上流部門に関するプロジェクトでは、投資決定から運用開始までには多くの時間を要し、足元で投資決定を行ったとしても供給力不足に即座に対応できないという性質があります。こうした性質を理解した上で、長期的なエネルギー政策を考えていく必要があることが、改めて世界中で再認識されたといえます。
2.世界的なエネルギー価格の高騰
以降では、まず世界のエネルギー市場の価格推移を確認した上で、その影響を受ける各国のエネルギーの輸入物価や消費者物価についても整理していきます。
(1)化石エネルギーの市場価格の推移【天然ガス・LNG/原油/石炭】
はじめに、今回のエネルギーを巡る混乱において、最も大きな影響を受けたと考えられる天然ガス・LNGの市場価格の推移を見ていきます。アジアのLNGスポット価格であるJKM(Japan Korea Marker)は2021年から上昇傾向にあり、たびたび急騰していましたが、ロシアによるウクライナ侵略を受け、2022年3月7日に史上最高値である約85ドル/MMBtuとなりました。これは1年前の価格(約6ドル/MMBtu)と比較すると、14倍ほどの価格となります。また、欧州の天然ガス価格指標であるTTF(Title Transfer Facility)やNBP(National Balancing Point)についても2022年8月26日に史上最高値に達しています。これは、ロシアから欧州に向けて天然ガスを供給しているノルドストリームの供給停止の懸念が高まったことが要因と考えられます。その後、JKM・TTF・NBPの価格は下落しましたが、今後もロシアによるウクライナ侵略の動向や、世界のエネルギー需給状況等に影響を受けることが想定され、見通しは不透明なままとなっています。
原油価格についても前述の禁輸等の影響を受けて、大きな変動がありました。2022年3月8日には欧州の指標価格であるブレント価格で約128ドル/バレルとなり、1年前の価格(約68ドル/バレル)と比較して2倍近い価格となりました。その後、原油価格は低下したものの、80ドル/バレル付近での推移が続いており、2021年以前の水準と比較すると高値の水準となっています。
石炭価格(豪州一般炭)に関しても同様に価格の高騰が顕著になっています。ロシア産石炭の輸入を段階的に禁止した影響に加えて、天然ガスの価格が高騰したことで欧州を中心に火力発電用の燃料としての石炭需要が増加したことも、価格高騰の要因の1つです。さらに、主要な石炭輸出国である豪州においては、2022年2〜3月や7月に大雨により石炭生産・輸送に障害が発生し、石炭の生産量が落ち込んでおり、このことも石炭価格の高騰につながりました。また、同じく主要な石炭輸出国の1つであるインドネシアにおいても、今回の天然ガス価格の高騰を受けて、国内における発電用燃料として石炭への需要が高まったことで、石炭の輸出を一時停止する等の措置を講じており、世界的な石炭価格高騰の一因となりました。その後、2023年に入って以降は、欧州での暖冬の影響や風力設備の稼働等を踏まえて価格が下落傾向にあります(第121-2-1)。
【第121-2-1】天然ガス・LNG、原油、石炭(豪州一般炭)の市場価格の推移
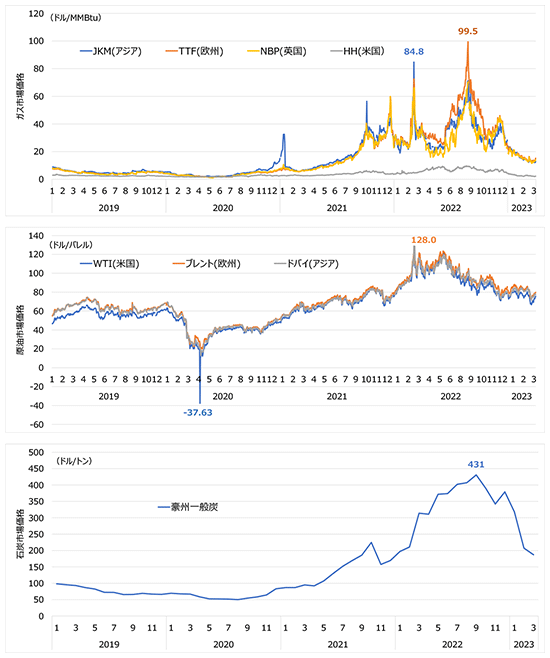
【第121-2-1】天然ガス・LNG、原油、石炭(豪州一般炭)の市場価格の推移(ppt/pptx形式:115KB)
- 資料:
- S&P Global Platts, ICE, CME (天然ガス・LNG)、Chicago Mercantile Exchange(原油)、The World Bank「Commodity Markets」(豪州一般炭)を基に経済産業省作成
(2)各国のエネルギー輸入物価の推移【天然ガス/原油/石炭】
次に、主要国が輸入した天然ガス・原油・石炭の1単位当たりの価格(輸入物価)の推移を各国の貿易統計に基づき集計・整理していきます(以下、2020年1月の数値を基準(100)として、グラフデータの計算をしています)(第121-2-2)。いずれの国でもエネルギーの輸入物価は高騰していますが、高騰の状況は国によって大きく異なっていることがわかります。国によっては、エネルギーの輸出国と価格変動リスクをヘッジできるようなフォーミュラで長期契約を結ぶといった対応を取っており、そうした国ではエネルギーの市場価格が高騰しても、そのことがそのまま即座に輸入価格の高騰につながるわけではありません。
【第121-2-2】天然ガス&LNG、原油、石炭の輸入物価の推移(2020年1月の数値を基準(100)としている)
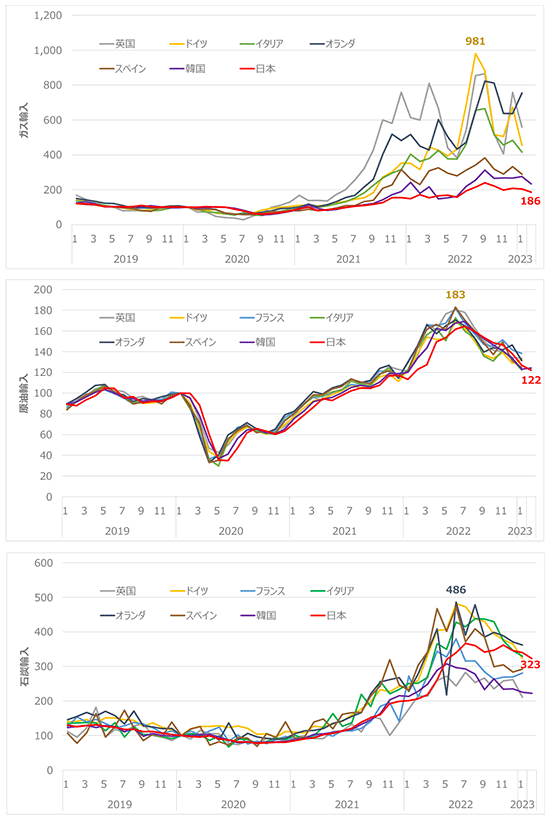
【第121-2-2】天然ガス&LNG、原油、石炭の輸入物価の推移(2020年1月の数値を基準(100)としている)(ppt/pptx形式:62KB)
- 資料:
- Global Trade Atlasを基に経済産業省作成
エネルギーごとの輸入物価の推移を見ていくと、特に天然ガスでは、国によって高騰の状況が大きく異なっていることがわかります。2022年9月のドイツの輸入物価は981となっており、2020年1月の輸入物価の約10倍にまで急騰しました。日本や韓国等と比較すると、欧州諸国の輸入物価の高騰が目立ちますが、これはこれまで欧州諸国がエネルギーの多くをロシアに依存しており、ロシアによるウクライナ侵略の後、急遽スポット市場で多くのLNGを調達せざるを得なくなったこと等が影響していると考えられます。
次に石炭の輸入物価を見ていきます。石炭についても、国によって高騰の状況は大きく異なっており、いくつかの国では500近い数値にまで高騰していることがわかります。しかし天然ガスと比べると、欧州、アジアといった地域による傾向はあまり見られないことも読み取れます。また原油については、天然ガスや石炭と比べると上昇率が低く、国による違いも小さい状況となっています。
(3)各国のエネルギー価格(消費者物価)の推移【電気・ガス・ガソリン等】
最後に、主要国における電気料金、ガス料金、ガソリン等料金5の推移について、消費者物価指数を用いて見ていきます(以下、2020年1月の数値を基準(100)として、グラフデータの計算をしています)(第121-2-3)。
【第121-2-3】消費者物価指数(電気料金、ガス料金、ガソリン等料金)の推移(2020年1月の数値を基準(100)としている)
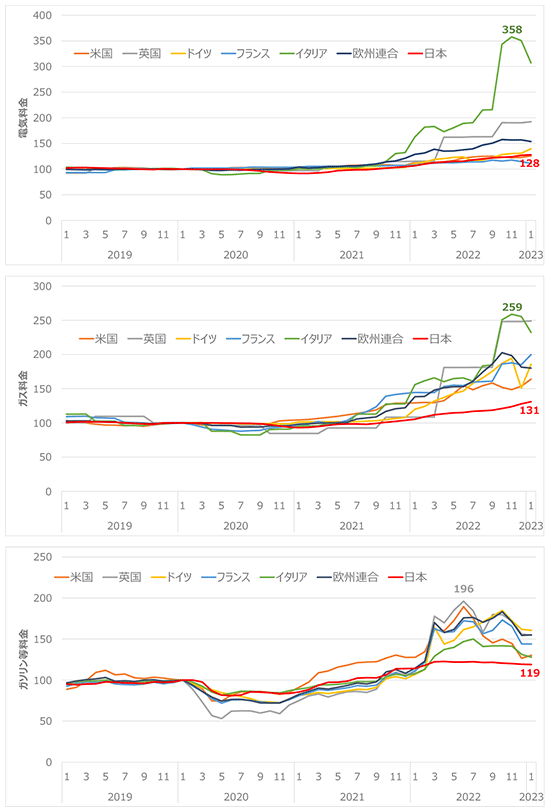
【第121-2-3】消費者物価指数(電気料金、ガス料金、ガソリン等料金)の推移(2020年1月の数値を基準(100)としている)(ppt/pptx形式:61KB)
- 資料:
- 各国政府統計より経済産業省作成
これまでに見てきたデータと同様に、各国で電気料金等が上昇していることがわかります。2022年11月に電気料金が358、ガス料金が259となっているイタリア等、急激に高騰している国もあります。しかし、これまで紹介してきたエネルギーの市場価格や輸入物価の推移と比べると、全体的に上昇幅が小さいということもわかります。国によって電気料金制度等は異なるため一概にはいえませんが、家庭や企業への影響の大きい電気料金等については、今回のエネルギー価格の高騰を受けて各国政府が様々な支援策を講じています。こうした支援策の内容については後述するため、ここでは省略しますが、この電気料金等の推移データについては、そういった支援策の効果等も一定程度反映されていると考えられます。
なお、天然ガスの輸入物価や電気料金等の消費者物価の推移を見ると、日本は他の主要国に比べ、価格の上昇幅が小さく抑えられていることがわかります。次章にも記載しますが、これは欧州諸国と比べると、ロシア産エネルギーへの依存度が低かったことに加えて、日本はLNGの多くを長期契約・油価連動で調達していたこと、電気料金等の急騰を抑える制度上の仕組み(燃料費調整制度等)があったこと等が要因と考えられます。
(4)エネルギー価格の高騰に伴うアジア諸国への影響
世界的なエネルギー価格の高騰は、アジアの国々にも大きな影響を及ぼしました。欧州諸国がLNGを買い求めたこと等が影響し、アジア向けのLNGのスポット価格も高騰することとなりました。以前よりLNGスポット市場からの調達比率が高かったアジアの国々では、高騰するLNGの購入を断念するといった事態も起きています。
バングラデシュでは、LNGのスポット市場の高騰により外貨準備高が急減したことも踏まえて、2022年7月・8月にLNGの購入を見送りました。それに伴い、国内の燃料消費を抑制するために、労働時間の短縮等を実施しましたが、同年7月には国内で稼働しているディーゼル炊きの火力発電所の稼働を停止し、全国的な計画停電を実施しました。
またパキスタンでも、エネルギー価格の高騰に伴う外貨準備高の急減への対応策として、LNG輸入を大幅に減らし、燃料節約のため計画停電を行う等の対応を取りました。
COLUMN
エネルギー自給率の内訳
石油危機以来、エネルギー自給率はたびたび注目されるテーマです。直近ではロシアによるウクライナ侵略の影響もあり、エネルギー自給率の重要性が再認識されています。エネルギー自給率とは、国内のエネルギー消費量に対して、国内のエネルギー生産量の占める割合を数値化したものであり、例えば自国で化石エネルギーを生産できる国は高い数字を示す傾向にありますが、日本のように海外から輸入するエネルギーに頼る国では低い数字を示す傾向にあります。
最初に、2000年以降の各国のエネルギー自給率の推移を見てみます(第121-2-4)。自国内での化石エネルギーの生産量の増加を受けて、豪州・インドネシア・米国では自給率が上昇し、化石エネルギーの生産量を減らしている英国では自給率が減少する結果となっています。同じく自給率が減少傾向にある中国・インドにおいては、その要因は旺盛な国内エネルギー消費の高まりを受けたエネルギー輸入量の増加であり、結果的に自給率は低下しているものの、国内での化石エネルギーの生産量は横ばいもしくは増産傾向にあります。日本は東日本大震災を受けて、原子力発電所からのエネルギー供給量が減少し、2015年には7%まで自給率が落ち込んだものの、原子力発電所の再稼働や再エネの普及促進等の結果、2020年には11%まで自給率が改善しています。
【第121-2-4】主要国におけるエネルギー自給率の推移
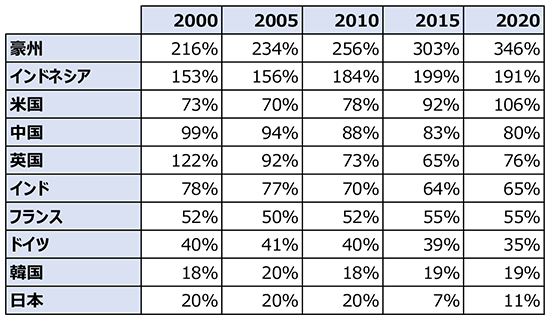
【第121-2-4】主要国におけるエネルギー自給率の推移(ppt/pptx形式:47KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2022」より経済産業省作成
次に、2020年の各国のエネルギー自給率の構成を見ていきます(第121-2-5)。自給率が100%を超える豪州・インドネシア・米国については、石炭・原油・天然ガスといった化石エネルギーの国内生産が自給率を牽引していることがわかります。フランスやドイツは日本と同様に、化石エネルギーの自国生産量が少ない国ですが、ドイツでは再エネ、フランスでは原子力発電の活用によって一定程度の自給率が担保されています。
【第121-2-5】2020年の主要国のエネルギー自給率の構成
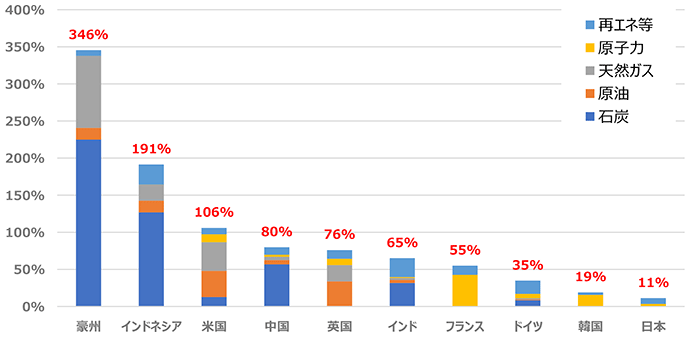
【第121-2-5】2020年の主要国のエネルギー自給率の構成(ppt/pptx形式:44KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2022」より経済産業省作成
次に、化石エネルギーごとの自給率を見ていきます。例えば石炭自給率の場合、国内の石炭生産量を、国内の石炭消費量で割って算出します。
最初に、石炭自給率を見ていきます(第121-2-6)。石炭自給率が100%を超えているのは豪州・インドネシア・米国の3か国ですが、各国で事情は異なっています。豪州・米国は自国内の石炭消費量が減少傾向にあり、他エネルギーへのシフトが進んでいる状況ですが、諸外国への輸出分を含め、国内生産量は堅調に推移しているため、結果的に自給率が上昇しています。対して、インドネシアでは石炭火力等の用途で近年も石炭消費量が増加傾向にあり、自給率が2015年比で低下しています。
【第121-2-6】主要国における石炭自給率の推移
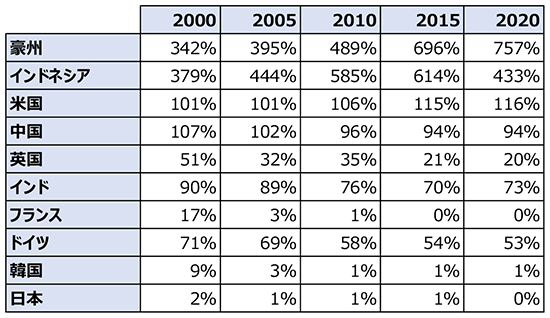
【第121-2-6】主要国における石炭自給率の推移(ppt/pptx形式:49KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2022」より経済産業省作成
石炭輸出量の多い豪州とインドネシアですが、石炭消費量の多い電力産業を中心に直近の動向を確認すると、それぞれに国内の状況は異なります。豪州では、国内最大級の石炭火力発電所であるエラリング発電所が当初計画から7年前倒しの2025年に廃止されると発表されています。一方、インドネシアでは増加する電力需要に対し、石炭火力発電所の設備容量拡大が計画されています。これらの政策動向から、豪州は石炭消費量を減らすことで石炭自給率がさらに上昇するものと想定され、インドネシアの石炭自給率は、国内の石炭生産量が増加しない限り、低下する方向に推移することが想定されます。
次に、天然ガス自給率です(第121-2-7)。天然ガスはフランス・日本を除く全ての国で消費量が増加傾向を示しており、豪州・米国といった生産量の増加が続く国を除いては、総じて自給率が減少傾向にあります。石油や石炭と比べ、燃焼時のCO2排出量が少なく、相対的にクリーンとされる天然ガスの需要は今後も高まっていくことが想定されています。このように、世界中で天然ガスの需要が高まる中、輸入に頼らざるを得ない国は安定的・安価に調達していくための長期的な計画が必要です。
【第121-2-7】主要国における天然ガス自給率の推移
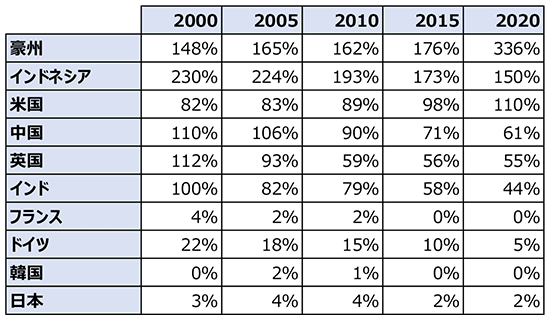
【第121-2-7】主要国における天然ガス自給率の推移(ppt/pptx形式:49KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2022」より経済産業省作成
最後に原油自給率です(第121-2-8)。原油消費量は、産業需要が堅調である米国・中国・インド・インドネシアの4か国が増加傾向にあるものの、その他諸国では減少傾向にあります。豪州や英国は、生産と消費量ともに減少傾向にありますが、消費量の減少スピードのほうが速く、自給率は改善傾向にあります。
【第121-2-8】主要国における原油自給率の推移
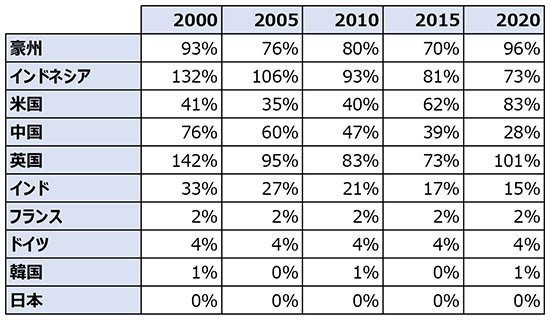
【第121-2-8】主要国における原油自給率の推移(ppt/pptx形式:48KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2022」より経済産業省作成
エネルギー自給率は、国内エネルギー総消費量を自国で生産するエネルギーの総量で割り戻して計算するため、自国で生産するエネルギーの総量を増加させるか、もしくは国内のエネルギー総消費量を抑えることで向上します。
現在は化石エネルギーの生産状況や原子力の活用状況等が各国のエネルギー自給率に大きく影響を与えていますが、今後は水素・アンモニアといった代替燃料もエネルギー自給率に影響を与えることになる可能性があります。既に足元では水素・アンモニアの活用に向けて国際的に取組が進んでおり、今後エネルギー自給率を議論する際の重要な要素となっていくことも想定されます(第121-2-9)。
【第121-2-9】水素に係る海外動向
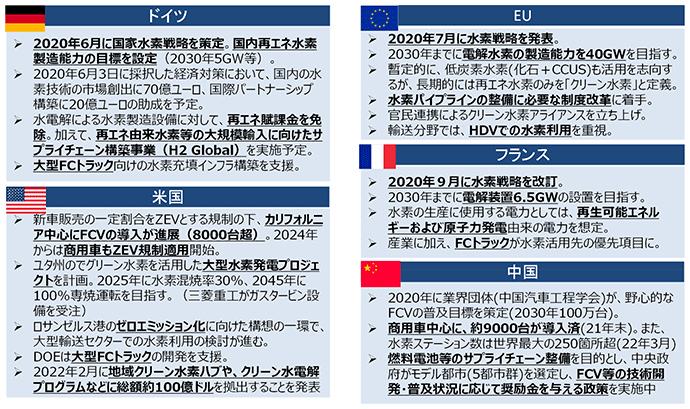
【第121-2-9】水素に係る海外動向(ppt/pptx形式:69KB)
- 資料:
- 総合資源エネルギー調査会第1回省エネルギー・新エネルギー分科会水素政策小委員会/資源・燃料分科会アンモニア等脱炭素燃料政策小委員会合同会議資料3(2022年3月29日)
化石エネルギー資源を保有しない国において、一次エネルギー自給率を向上させるためには、自国で生産するエネルギーの総量を増加させる観点から、化石エネルギーによらないエネルギーの構成比率を高める必要があります。例えば、フランスや韓国では原子力、ドイツでは再エネの活用によって、日本よりも高い自給率を維持しています。また、国内エネルギー総消費量を抑える観点からは、産業・家庭における省エネルギー(以下「省エネ」という。)の推進が有効です。特に化石エネルギーを用いる分野における省エネの推進によって、自給率の改善が期待されます。
コラム冒頭で示したとおり、現在の日本の一次エネルギー自給率は10%強に留まっていますが、2021年10月に閣議決定された「第6次エネルギー基本計画」では、2030年度の一次エネルギー供給の構成として再エネの比率を22〜23%、原子力の比率を9〜10%としており、その場合、一次エネルギー自給率は30%程度の水準まで向上することとなります(第121-2-10)。
【第121-2-10】日本のエネルギー需要・一次エネルギー供給(2013年度実績・2030年度計画)
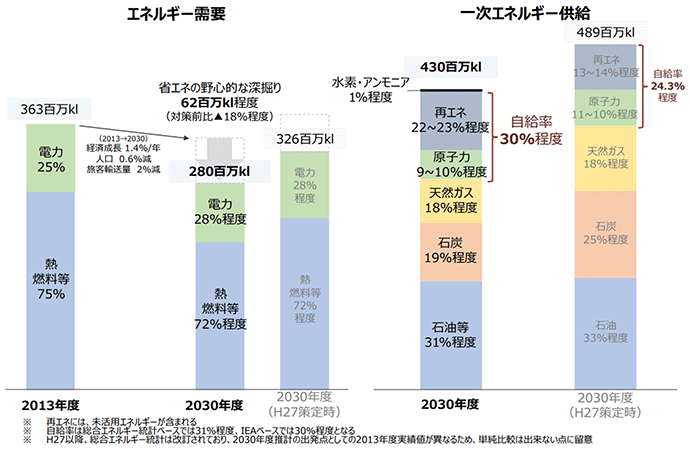
【第121-2-10】日本のエネルギー需要・一次エネルギー供給(2013年度実績・2030年度計画)(ppt/pptx形式:422KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
3.エネルギーの需給ひっ迫に対する各国の対応(LNG争奪戦)
ロシアによるウクライナ侵略以前、エネルギーの多くをロシアに依存し、特に天然ガスをパイプライン経由でロシアから輸入していた欧州では、ロシア産エネルギーからの脱却を進めていく中で、代替エネルギーの確保が求められました。本項では、ロシアのウクライナ侵略以降、代替エネルギーとして需要が高まったLNGを巡る世界の動向を整理します。
(1)欧州におけるロシア産天然ガスの代替先
欧州諸国は、ロシアからパイプラインで供給を受けていた天然ガスの代替となるエネルギーを確保する必要性に迫られました。各国では省エネが推進されるとともに、ノルウェー等の他国からの天然ガス輸入量の拡大、原子力等の他のエネルギーを用いる発電所の活用等も実施されましたが、ロシア産天然ガスの代替エネルギーとして、大きな役割を担ったのが、天然ガスを液化したLNGでした(第121-3-1、第121-3-2)。2022年、欧州ではLNGの輸入量を増やすことにより、需給バランスを維持しました。日本も、2022年冬期に、日本国内の安定供給の確保を大前提とした上で、一部のLNGを欧州向けに融通する等、欧州のLNG確保に協力しました。しかしながら、この欧州のLNG輸入量の拡大は、世界全体のLNGの需給構造に大きな影響を及ぼしました。
【第121-3-1】2021-2022年の欧州の天然ガス需給の構造
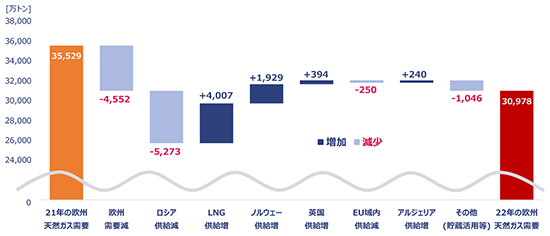
【第121-3-1】2021-2022年の欧州の天然ガス需給の構造(ppt/pptx形式:44KB)
- 資料:
- Department for Business, Energy & Industrial Strategy “Energy Trends: UK gas”、Eurostat、ENTSOG Transparency Platform、Kplerよりエネルギー経済社会研究所作成
【第121-3-2】主要地域のLNG輸入量の推移
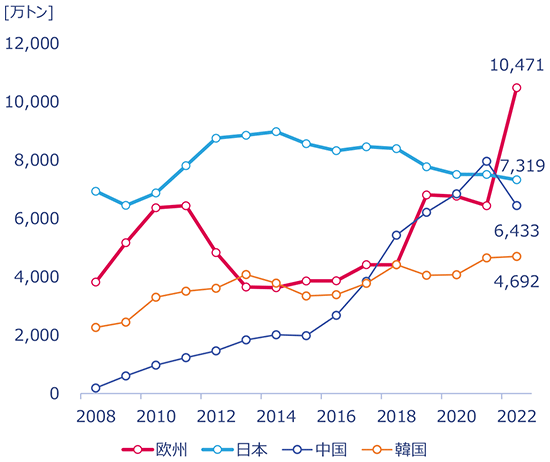
【第121-3-2】主要地域のLNG輸入量の推移(ppt/pptx形式:47KB)
- 資料:
- Kplerを基にエネルギー経済社会研究所作成
(2)2022年の世界のLNG需給構造
ある地域でLNG輸入量を拡大させるためには、世界全体におけるLNGの供給量を増やすか、あるいは他の地域においてLNGの輸入量を減らす必要があります。今回、欧州がLNGの輸入量を拡大させましたが、同時に米国からのLNG輸出量の増加と、中国を中心としたアジア諸国でのLNG輸入量の減少も起きていました(第121-3-3)。
【第121-3-3】2021-2022年の世界LNG需給バランス
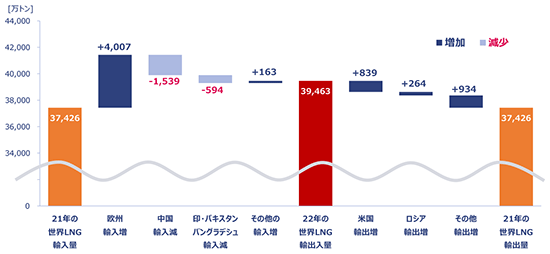
【第121-3-3】2021-2022年の世界LNG需給バランス(ppt/pptx形式:45KB)
- 資料:
- Kplerを基にエネルギー経済社会研究所作成
①欧州におけるLNGの輸入状況
欧州のLNG輸入状況の内訳を確認していくと、ロシアによるウクライナ侵略が始まる直前から、急激にLNGの輸入量が増えていることがわかります。また、その増加分のLNGを輸出している国が主に米国であることが輸入状況のデータからわかります(第121-3-4)。
【第121-3-4】欧州(EU+英国)の月次LNG輸入状況
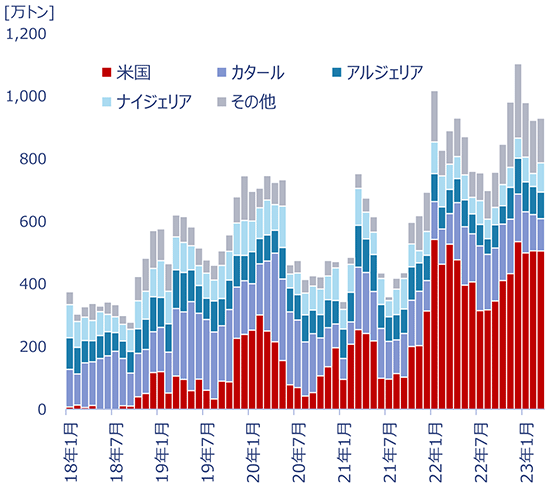
【第121-3-4】欧州(EU+英国)の月次LNG輸入状況(ppt/pptx形式:53KB)
- 資料:
- Kplerを基にエネルギー経済社会研究所作成
②米国におけるLNGの輸出状況
次に、米国のLNG輸出状況の内訳を確認していきます(第121-3-5)。前述の欧州のLNG輸入状況のデータとも連動しますが、2022年に入って以降、欧州向けのLNG輸出量が大きく増加していることがわかります。他方で、これまで米国産LNGの主な輸出先となっていたアジアへの輸出量が減っており、それまでアジアのプレイヤーが引き取っていた米国産LNGが、欧州へと売却され、LNGの流れが変わっている状況を見ることができます。
【第121-3-5】米国産LNGの輸出状況
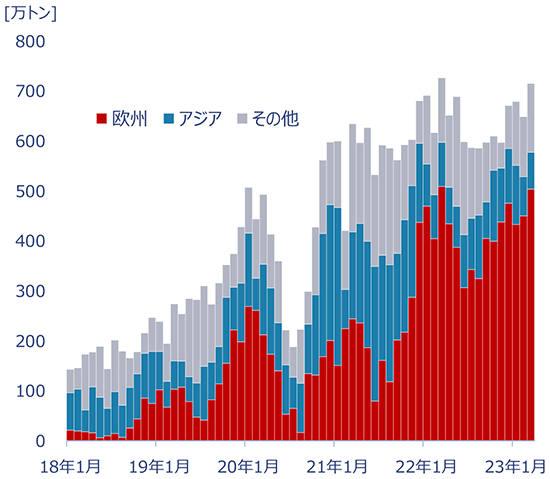
【第121-3-5】米国産LNGの輸出状況(ppt/pptx形式:48KB)
- 資料:
- Kplerを基にエネルギー経済社会研究所作成
③アジアにおけるLNGの輸入状況
前述のとおり、欧州諸国がLNGの輸入量を拡大させた一方で、アジア諸国ではLNGの輸入量を減少させることとなりました。中でも特に中国のLNG輸入量が大きく減少していました。中国がLNG輸入量を減らした背景としては、天然ガスや石炭の国内生産量を増やしたこと、パイプラインを用いたロシアからの天然ガス輸入量を増やしたこと等が挙げられます。
また、中国以外のアジア諸国におけるLNG輸入量の減少要因としては、前述のとおり、バングラデシュやパキスタン等の国において、高騰するLNGスポット市場からのLNG調達を見送ったこと等が挙げられます。
(3)今後のLNGを取り巻く世界の情勢
①アジアにおけるLNG市場の構造変化
前項で概観したとおり、欧州がロシア産天然ガスの代替エネルギーとしてLNGの輸入量を拡大させたことによる影響は、欧州だけでなく世界全体へと広がっています。
LNG需要の要所の1つであるアジアのLNG市場にも大きな影響を及ぼしています。これまで極東のLNGスポット価格指標であったJKMは、主に中国の経済動向や生産状況に連動して変動していましたが、2022年以降は中国の動向ではなく、欧州における天然ガス価格指標であるTTFとの連動性が高まっています(第121-3-6)。
【第121-3-6】LNGスポット価格(JKM/TTF)と中国のLNG需要
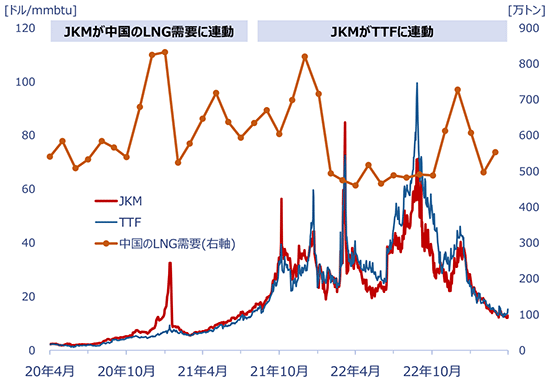
【第121-3-6】LNGスポット価格(JKM/TTF)と中国のLNG需要(ppt/pptx形式:64KB)
- 資料:
- Kpler、S&P Global Platts等を基にエネルギー経済社会研究所作成
気体の天然ガスとして取引を行ってきた欧州のガス価格と、LNGとして取引を行ってきたアジアのLNG価格とでは、価格の変動要因が異なることから別々の値動きをすることもありましたが、今回の世界的なLNG需要の高まりを受けて、アジアのLNG市場が欧州の影響を強く受けたことがわかります。
②中長期的なLNGの需給バランスの見通し
次に、中長期的なLNGの需給バランスの見通しについて概観していきます。ロシアによるウクライナ侵略以降、LNG需要が急増したことでLNG需給は急激にひっ迫しましたが、JOGMECのレポート6によると、需要量に対して供給量が不足する傾向は短期的な現象ではなく、今後も一定程度この傾向が続いていくと予想されています(第121-3-7)。
【第121-3-7】世界のLNG供給余力(ピーク月(1月)ベース)
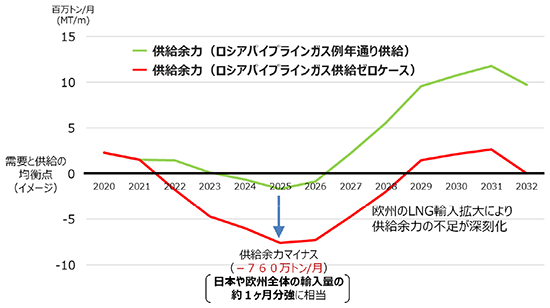
【第121-3-7】世界のLNG供給余力(ピーク月(1月)ベース)(ppt/pptx形式:81KB)
- 資料:
- 各種資料よりJOGMEC作成
今後も欧州諸国には、ロシア産天然ガスの代替となるエネルギーを継続的に確保していくことが求められます。そうした中、省エネの推進や他のエネルギーの活用等の取組と並行して、欧州では浮体式LNG貯蔵再ガス化設備(以下「FSRU」7という。)を中心にLNG受入基地の建設が急ピッチで進められています。今後、LNG受入基地の建設が進み、LNGの受入能力が増加するにつれて、欧州諸国はますます多くのLNGを輸入することが見込まれています。
このように、特に欧州におけるLNG需要が今後も伸び続けることが想定される一方で、LNGの供給側、つまり生産能力については、2015年頃から続いた上流部門への投資減少の影響等もあって、こうした旺盛なLNG需要にすぐには追い付けないことが想定されています。
その結果、現在、運用開始に向けて建設等が進んでいる天然ガスの液化プロジェクト等が順調に立ち上がったとしても、2025年頃までは、LNGの生産能力の伸びは需要の伸びに追い付けず、世界全体のLNGの供給余力は2025年頃に向かってさらに低下、すなわち需給がひっ迫していくことが想定されています。その後、各種プロジェクトが新たに運用開始できれば、それに伴い世界全体のLNGの供給量は増加していくことが見込まれますが、今回始まった世界的な「LNG争奪戦」は短期間で終わることはなく、今後も一定程度この傾向が続いていくことが予測されています。こうした状況下においてLNGを輸入に頼る国には、LNGの安定的な確保に向けた長期的な戦略の立案と実行が一層求められることになります。
③中長期的なLNG価格の見通し
次に、中長期的なLNG価格の見通しについて概観していきます。前項のとおり、LNGの需給がひっ迫する状況が今後も続くという見通しを踏まえ、前述のJOGMECのレポートではLNGの価格についてもしばらくは高値で推移し続けるという見通しを立てています(第121-3-8)。スポットLNG価格は2020年代後半まで長期契約のLNG価格を上回る可能性が示唆されており、欧州のガス需要が大きく変わらなければ、LNGや天然ガスの価格が今回のエネルギーの需給ひっ迫前の通常時の水準に戻るのは、2030年以降になる可能性も想定されています。
【第121-3-8】LNGの価格予測
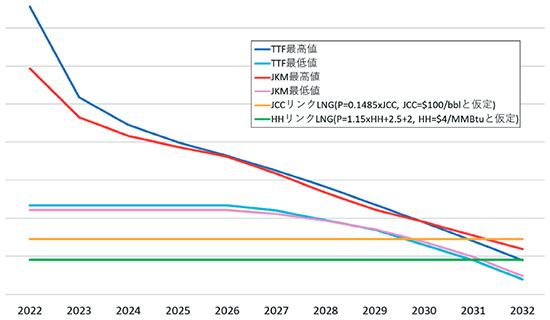
【第121-3-8】LNGの価格予測(ppt/pptx形式:333KB)
- 資料:
- 各種資料よりJOGMEC作成
④LNG確保に向けた各国の動向
ここまで見てきたように、長期戦の様相を呈している「LNG争奪戦」に対し、LNGを輸入している世界各国では、LNGの安定的な確保に向けて政府が積極的に関与しています。今回、LNGの輸入量を大きく増やした欧州諸国だけでなく、アジアでも中国や韓国は脱炭素社会の実現に向けた取組と並行し、エネルギー安定供給のための国家戦略に基づき、国営企業を中心にLNGの長期契約の交渉・締結を進めています(第121-3-9)。
【第121-3-9】各国のLNG確保に向けた状況
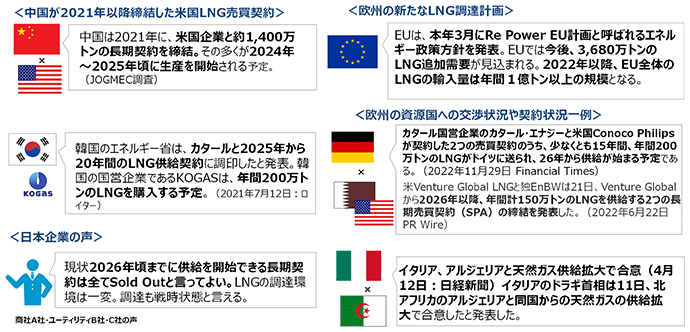
【第121-3-9】各国のLNG確保に向けた状況(ppt/pptx形式:201KB)
- 資料:
- 第19回石油・天然ガス小委員会資料3(2022年12月5日)
なお、2021年時点における日本・中国・韓国の事業者が締結済のLNG長期契約におけるLNGの確保量を見てみると、それぞれの状況が大きく異なっていることがわかります。中国では、締結済の長期契約におけるLNGの確保量が2020年代後半にかけて大幅に増加していく見通しとなっています。韓国は、2024年頃までは横ばいが続き、その後は減少していく見通しとなっています。日本は、これまでLNGの長期契約を推進してきたこともあり、2020年頃にかけて長期契約での確保量が右肩上がりで増加していました。しかし、既存のLNG長期契約の更新や新規契約の締結がなされなければ、今後は急激に確保量が減少していく見通しとなっています(第121-3-10)。
【第121-3-10】日本・中国・韓国の事業者が長期契約で確保済のLNG量(2021年時点)
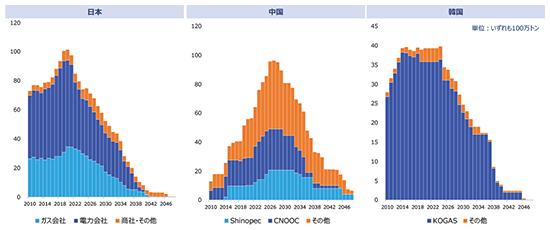
【第121-3-10】日本・中国・韓国の事業者が長期契約で確保済のLNG量(2021年時点)(ppt/pptx形式:54KB)
- 資料:
- GIIGNL Annual Reportを基にエネルギー経済社会研究所作成
ロシアによるウクライナ侵略の今後の動向を始め、国際情勢の先行きが一層不透明になっていく中、エネルギー政策を考えていく上では、足元の課題への対応を積み重ねていくだけではなく、長期的な視点に立って取組を進めていくことも重要です。エネルギーの安定供給の確保や最適なエネルギー構成の構築等の課題に対して、資源外交の展開等、国家を挙げて取り組んでいかなければならないことが、今回のLNGを巡る動向からも、改めて認識されました。
2023年4月に、G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合に先んじて発表されたIEAの分析では、既存ガス田の減衰等を要因に、追加の天然ガスの上流投資が世界的に必要であることが明示されており(第121-3-11)、同年4月15日、16日に開催されたG7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合でも、天然ガス・LNG分野に関する議論が行われ、閣僚声明では、天然ガス・LNGの必要性が示されました。具体的には、ロシアによるウクライナ侵略が世界的な資源確保競争を激化させたことによるエネルギー危機が、特にガス需要の増加が見込まれるアジアを中心とするグローバルサウスの国々に対して、環境・経済・社会的な悪影響を及ぼしていることを認識した上で、「このような特別な状況において、エネルギーの節減とガス需要の削減を通じてクリーンエネルギー移行を加速させることの主要な必要性を認識しつつ、明確に規定される各国の状況に応じて、例えば低炭素及び再生可能エネルギー由来の水素の開発のための国家戦略にプロジェクトが統合されることを確保することにより、ガス部門への投資が、我々の気候目標と合致した形で、ロックイン効果を創出することなく実施されるなら、この危機により引き起こされる将来的なガス市場の不足に対応するため適切でありうる」とされました。また、G7諸国は「ガス生産国と消費国の間の対話を通じて、より長期的な展望を考慮しながら、ガスセキュリティにおけるIEAの機能と役割が、さらに強化されることを期待する」ともされています。同会合での議論や、天然ガス・LNG市場の大きな動乱を踏まえ、今後、日本政府として、産消国間の対話の機会であるLNG産消会議をIEAと共同で開催し、天然ガス・LNGに関するセキュリティ強化に向けた必要な政策や各国間の連携を議論していく予定です。
【第121-3-11】STEPSとAPSにおける2030年にかけて必要なガスの追加供給量
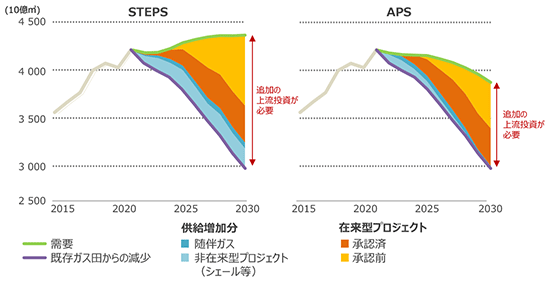
【第121-3-11】STEPSとAPSにおける2030年にかけて必要なガスの追加供給量(ppt/pptx形式:116KB)
- (注)
- STEPSは各国が表明済の具体的政策を反映した公表政策シナリオ、APSは有志国が宣言した野心を反映した表明公約シナリオ(いずれもIEAが想定した将来シナリオ)
- 資料:
- IEA「Outlooks for gas markets and investment」より経済産業省作成
4.諸外国で講じられた対応策
世界的なエネルギーの需給ひっ迫とそれに伴うエネルギー価格の高騰により、家庭や企業等の需要家は大きな影響を受けています。さらにエネルギー価格の高騰は需要家に対してだけなく、エネルギー事業者等の経営に対しても甚大な影響を与えています。上昇する燃料価格(原価)が、小売価格(電気料金等)を上回り、経営を圧迫するといった事例も各地で発生しています。
こうしたエネルギー価格高騰への対応として、各国では様々な対策が取られています。需要家に対しては、エネルギー価格に対する上限金額の設定や料金支援等の対策が実施された国もあります。また中長期的な対策として、エネルギー市場全体に対する制度改革やエネルギー事業者に対する公的資金による救済や国有化等の政策も実施されています。
さらに、エネルギー価格高騰への対応だけではなく、エネルギーの確保・安定供給に対しても、各国は対応策を取っています。欧州では、前項で記載したLNGと同様に石炭輸入量も増やす対応も行いました(第121-4-1)。石炭火力発電所の再稼働や原子力発電所の稼働期間延長等、各国では多岐にわたる緊急対応策を導入しています。
【第121-4-1】欧州の船舶輸送における石炭輸入量の推移
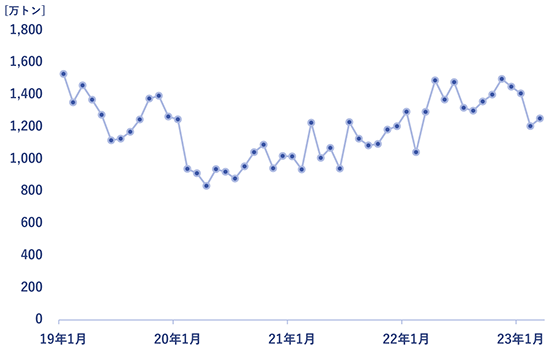
【第121-4-1】欧州の船舶輸送における石炭輸入量の推移(ppt/pptx形式:45KB)
- 資料:
- Kplerを基にエネルギー経済社会研究所作成
以降ではエネルギーの需給ひっ迫やエネルギー価格の高騰に対する主要国の政策動向に関して記載していきます。
(1)英国
英国では、エネルギー部門の規制機関であるガス・電力市場局(Ofgem)が、エネルギー価格の上限の見直しを四半期ごと8に実施していますが、今回の世界的なエネルギー価格の高騰に伴い、英国内のエネルギー価格の上限も大幅に上昇することとなりました。標準的な家庭のガス・電力使用量の場合、2021年10月から2022年3月までのガス・電力価格の上限は、年間で1,277ポンドとなる水準でしたが、その後の複数回にわたる上限の見直しにより、2023年1月から3月の期間のガス・電力価格の上限は、年間で4,279ポンドとなる水準にまで高騰しています(第121-4-2)。
【第121-4-2】英国の標準的な家庭のエネルギー価格の上限の推移
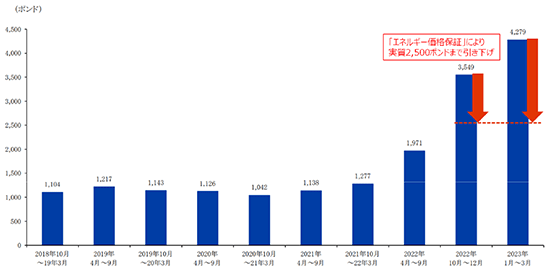
【第121-4-2】英国の標準的な家庭のエネルギー価格の上限の推移(ppt/pptx形式:121KB)
- 資料:
- Ofgem
Ofgemは、こうしたエネルギー価格の高騰に対する需要家保護のための施策として、「エネルギー価格保証」と称する家計支援措置を2022年10月より実施しています。この措置は、標準的な家庭のガス・電力使用量の場合、年間支払額が2,500ポンドに制限される9というものです。また企業向けの対策も行われており、2023年4月から「エネルギー料金割引スキーム(Energy Bills Discount Scheme)」として、エネルギー使用量に応じた補助を行っています。
また、足元の電源確保を目的とした対策も講じられました。2022年7月、当初は同年9月末での閉鎖が予定されていた2つの石炭火力発電所について、2023年3月までの稼働延長を決定しました。2023年1月には寒波による電力需要の増加と風力発電からの発電量の減少が重なりましたが、稼働延長していた石炭火力発電所の緊急利用準備等を行うことで対応しました。なお、この措置はあくまでも2021年から続くガス価格の高騰と、ロシアによるウクライナ侵略によるエネルギー市場の混乱に対応するための緊急策であり、電力部門からの温室効果ガスの排出削減を目的に、石炭火力発電を段階的に廃止し、2024年に全廃するという従来の計画については、方針を変えないとしています。
また、2022年4月には「エネルギー安全保障戦略10」を発表し、長期的にエネルギー安全保障の強化に向け、多様な国産エネルギー源を増強するための様々な取組方針が示されました。この中で、原子力発電については2030年までに最大8基の原子炉新設を目指す方針となっており、2050年までに現在の3倍超となる最大24GWの出力を整備した上で、電力需要の最大約25%を賄う(現在は約15%)ことを目指し、先進的な原子力技術開発も加速させるために、1億2,000万ポンドの政府基金も設立されています。また、このエネルギー安全保障戦略では、石油やガスについても方針が挙げられています。ロシア産エネルギーからの脱却に加え、英国内でガスを生産することは、海外から輸入する場合に比べて温室効果ガスの排出量が少ないこともあり、新規の北海石油・ガスプロジェクトの認可プロセスを開始する予定となっています。
また英国は、電力市場レビュー(REMA:Review of Electricity Market Arrangements)を開始しており、数年に及ぶ制度改革も見越して、卸市場における再エネと火力発電の価格分離や地域別市場、再エネ支援制度の見直し等、様々な案についてレビューを実施しています。今回のエネルギー価格の高騰の経験も踏まえて、価格高騰対策とエネルギーセキュリティの両面を踏まえた市場改革が見込まれています。
(2)ドイツ
ここまでに記載してきたとおり、国内で消費する天然ガスの多くをパイプライン経由でロシアから輸入していたドイツでは、LNGを始めとする代替エネルギーの確保が迫られることとなり、その結果、国内のエネルギー価格も高騰することとなりました。エネルギー価格の高騰に対する需要家保護の対応としては、2022年7月より、再エネ賦課金を廃止しています。また、エネルギーの節約を促す仕組み11を組み込んだ電力・ガス等の上限価格設定も、2023年より導入されています。
また、ドイツではロシア産エネルギーに代わるエネルギーの確保についても喫緊の課題となりました。足元の短期的な対応策としては、より多くのLNGを輸入するため、2022年〜2023年にかけてFSRUを導入するとしており、2022年12月には初のFSRUがドイツ北部のウィルヘルムスハーフェン市で稼働を開始しています。LNGの調達以外にも代替エネルギーの確保に向けた取組が行われました。まず、当初2022年末で廃止を予定していた3基の原子力発電所を2023年4月15日まで稼働可能な状態を維持するといった対応が取られました。さらに、発電部門での天然ガスの消費を節約するために、停止中の石炭(褐炭含む)火力発電所の再稼働のための法改正が進められ、停止していた石炭火力発電所が再稼働を果たす等もしています。
また、ドイツのエネルギー企業であるUniper社は、ロシアからの天然ガス供給が停止し、高騰する代替ガスの調達が必要となったこと等で財務状況が悪化したため、2022年7月にドイツ政府に救済措置を申請することとなりました。その後、ドイツ政府はUniper社の国有化に合意しています。
他にもドイツでは、エネルギーの安定供給を確保するために、中東のカタールからLNGの供給を受ける長期契約を締結したと発表しています。
(3)フランス
フランスでは、エネルギー価格の高騰への需要家保護の対策として、家庭等の需要家を対象に、電力料金については規制料金の上昇率を制限し、ガス料金については規制料金を2021年10月の水準で凍結するといった対応を一時的に実施しました。さらに、エネルギー価格高騰による影響の大きい企業12に対する支援を行うことで、産業支援も行いました。
直近のエネルギーの需給ひっ迫への対応としては、節電要請の実施に加えて、2022年3月に運転が停止され、同年内に廃止予定であった石炭火力発電所の再稼働を決定するとともに、冬季の需要対策として同年11月から稼働を再開しています。
さらにフランス政府は、総額97億ユーロにて、フランス電力(EDF)の株式を100%取得し、完全国有化を実施すると発表しています。EDFを国有化し、政府が大規模な発電プロジェクトの実現に向けてEDFを全面的に支援することで、フランスでは長期的なエネルギーセキュリティの確保を進めていく方針です。
またこのことにより、2022年に発表された原子炉建設再開計画を政府主導で進めていける状態となります。エネルギーセキュリティの確保や脱炭素社会の実現に向けた原子力発電所の建設が検討されており、2050年までに最大14基の原子力発電所が新設される可能性があります。
(4)EU
EUではロシアによるウクライナ侵略を受けて「REPowerEU計画」を発表しました。この中では、省エネの推進に加えて、天然ガス等のエネルギー輸入元の多角化と再エネへの移行によって、エネルギーの安全保障の確保を目指すという方針を示しています。特にロシア産エネルギー依存からの脱却のための方策として、短期的にはガス貯蔵量の確保や需要減少を目的とした省エネ促進、新たなLNG輸入先の確保等の取組が示されています。その他にも、電力価格の規制や需要家である企業への支援等についても記載されています。
(5)米国
欧州の各国と比較すると、ロシア産エネルギーへの依存度が低く、ロシア産エネルギーからの脱却の影響が比較的少ないとされる米国でも、世界的なエネルギー価格の高騰により、電気料金等が上昇しました。米国では、石油備蓄の放出を行うとともに、原油・天然ガス等の国内生産量の拡大を容認する等、エネルギーの供給量を増やす対策を取っています。
(6)その他
その他の国でも、ロシア産エネルギーからの脱却の影響が大きい欧州を中心に、様々な対応策が取られています。スペインとポルトガルでは、発電用の天然ガス価格に上限を設ける制度が2022年6月から始まっています。
また、欧州の中でもロシア産エネルギーへの依存度の高かったイタリアでは、アルジェリアと天然ガスの追加調達について合意する等の対策に加えて、エネルギー価格の高騰を緩和させるための対策も行っています。具体的には、ガス代に課税される付加価値税(VAT)の引き下げ等が行われています。
また欧州以外でも、豪州ではエネルギー価格高騰に対する家庭や企業への支援策に関する法案が2022年12月に可決され、「エネルギー価格救済支援策(Energy Price Relief Plan)」が政府から発表されました。ガスや石炭の国内卸売価格への上限額の設定や、一部の世帯や中小企業を対象とした電力料金支援策が発表されています。
- 1
- European Commission 「REPowerEU: Joint European Action for more affordable, secure and sustainable energy」(2022年3月8日発表)
- 2
- プライスキャップ制度導入国の海上輸送・船舶保険等を行うサービス事業者は、上限価格を超えるロシア産原油・石油製品の海上輸送に関連したサービス提供ができません。
- 3
- IEA「Gas Market Report Q1 2022 including Gas Market Highlights 2021」(2022年1月発表)
- 4
- IEAが想定している将来シナリオの1つで、2050 年に世界でネットゼロを達成するためのシナリオのこと。
- 5
- 他に軽油・灯油等を含みます。
- 6
- JOGMEC「石油・天然ガスレビューVol.56 No.5」(2022年9月刊行)
- 7
- Floating Storage and Regasification Unitの略で、浮体式LNG貯蔵再ガス化設備のこと。陸上にLNG基地をつくらず、貯蔵・再ガス化設備を加えた専用船を洋上に係留するもの。
- 8
- 2022年9月までは、エネルギー価格の上限の見直しを半年に一度の頻度で実施していましたが、2022年10月以降は四半期ごとに見直すこととなっています。
- 9
- 2,500ポンドという水準は2023年3月まで継続され、2023年4月からは3,000ポンドへと変更。
- 10
- 英国政府「British energy security strategy」(2022年4月7日発表)
- 11
- 実際の年間消費量が予測年間消費量の80%より節約できた場合、80%を下回った部分についてはそのガス不使用分を契約上のガス価格で計算した金額相当が返金される仕組み。
- 12
- 電気・ガスの燃料費が2021年の売上高の3%以上に達しており、対象期間の電気・ガスの燃料費が2021年の平均価格の2倍になった企業が支援措置の対象。