第2節 日本の経済・社会に与える影響
2021年10月に、日本のエネルギー政策の基本的な方向性を示す「第6次エネルギー基本計画」が閣議決定されました。この第6次エネルギー基本計画において、エネルギー政策を考える上では、安全性(Safety)を大前提とした上で、エネルギーの安定供給(Energy Security)を第一とし、経済効率性の向上(Economic Efficiency)による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に環境への適合(Environment)を図る、いわゆる「S+3E」の視点が重要であるとしています。そしてその上で、第6次エネルギー基本計画では、2050年カーボンニュートラルや2030年度の温室効果ガスの排出削減目標(2013年度比で46%削減、さらに50%の高みに向けて挑戦を続ける)の実現に向けたエネルギー政策の道筋を示すこと、そして、気候変動対策を進めながら日本のエネルギー需給構造が抱える課題の克服に向けて安全性の確保を大前提に安定供給の確保やエネルギーコストの低減に向けた取組を示すこと、の2つを重要なテーマとしています。
そうした中、この第6次エネルギー基本計画の閣議決定からおよそ4か月後の2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵略は、エネルギーを取り巻く世界の情勢を一変させることとなりました。前節で記載したとおり、世界各国のエネルギーの安定供給に大きな影響を与えただけでなく、エネルギー価格を高騰させることにもつながりましたが、こうした事象は、エネルギーの多くを海外からの輸入に頼っている日本にとっても例外ではなく、他国と同じ様にエネルギーの確保や高騰するエネルギー価格への対応が急がれることとなりました。また、エネルギーの安定供給に関しては、2022年3月と同年6月に東京電力管内を中心に、電力の需給がひっ迫するという事象も発生しています。冒頭で示した日本のエネルギー政策における重要な視点である「S+3E」のうち、特にエネルギーの安定供給とコストの面が大きく揺らぐこととなった1年であったといえます。
前節では、エネルギーの需給ひっ迫と価格高騰、そしてそれらへの対応策について、主に欧米諸国を中心とした他国の動向を記載しましたが、本節では日本国内に焦点を絞って整理していきます。具体的には、ロシアによるウクライナ侵略等が日本へもたらした影響や、国内で発生した電力需給のひっ迫、そしてそれらへの対応策等について概観していきます。
1.日本におけるロシアによるウクライナ侵略の影響とその対応
(1)日本におけるエネルギーの輸入物価の推移
周囲を海で囲まれ、すぐに使える資源に乏しい日本は、一次エネルギーの大半を石油や石炭、天然ガスといった化石エネルギーが占めており、その化石エネルギーのほぼ全量を海外から輸入していることから、2021年の一次エネルギー自給率は13.3%に留まっています(第122-1-1)13。これはOECD38か国の中でも下から2番目の低さとなっています。
【第122-1-1】日本の一次エネルギー供給の構成及び自給率の推移
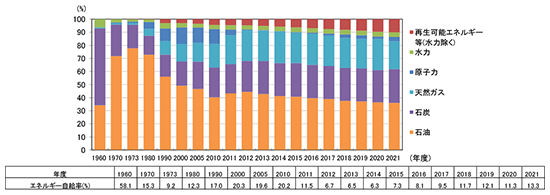
【第122-1-1】日本の一次エネルギー供給の構成及び自給率の推移(ppt/pptx形式:104KB)
- (注1)
- IEAは原子力を国産エネルギーとしている。
- (注2)
- エネルギー自給率(%)=国内産出/一次エネルギー供給×100。
- 資料:
- 1989年度以前はIEA「World Energy Balances 2022 Edition」、1990年度以降は資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成
そうした中、ロシアによるウクライナ侵略や海外のLNGプラントでのトラブル、2015年頃から続いている上流投資の減少等の影響で、世界のエネルギー需給はひっ迫し、エネルギーの価格も急騰することとなりましたが、エネルギーの多くを海外からの化石エネルギーに頼る日本もその影響を大きく受けることとなりました。各国が輸入した天然ガスや原油、石炭の1単位当たりの価格(輸入物価)の推移については前節で取り上げていますが、日本における輸入物価も諸外国と同様に上昇していることがわかります(第121-2-2参照)。
しかし、今回のエネルギーを巡る混乱の中、世界中で焦点が集まることとなった天然ガスの輸入物価の推移を見ると、日本の特徴を確認することもできます(第122-1-2)14。例えばドイツでは、2020年1月と比較すると、天然ガスの輸入物価が一時10倍近くにまで跳ね上がっており、輸入物価の高騰が顕著でしたが、そうした欧州等の国々と比べると、日本の輸入物価の上昇幅は相対的に小さい、ということがわかります。
【第122-1-2】天然ガスの輸入物価の推移(2020年1月の数値を基準(100)としている)
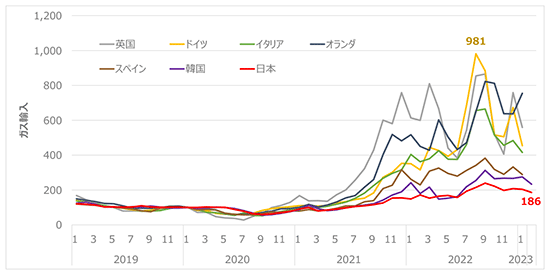
【第122-1-2】天然ガスの輸入物価の推移(2020年1月の数値を基準(100)としている)(ppt/pptx形式:47KB)
- 資料:
- Global Trade Atlasを基に経済産業省作成
ドイツ等の欧州諸国と日本とで天然ガスの輸入物価の上昇幅が大きく異なることになった理由としては、まず、ロシアによるウクライナ侵略以前のエネルギーのロシア依存度の違いが挙げられます。エネルギーのロシア依存度が高かった欧州では、ロシア産エネルギーからの脱却を目指すに当たって、急遽スポット市場でLNGの大量調達を余儀なくされたため、そのことが輸入物価の急騰の一因となったと考えられます。
また、ロシアによるウクライナ侵略の前から、天然ガスやLNGを調達するに当たって締結していた既存の長期契約の内容も、欧州諸国と日本における輸入物価の上昇幅の違いを生む結果につながったと考えられます。日本では安定的にLNGを確保する目的で、一定の範囲内で価格を維持しやすい長期契約を中心にLNGを調達しており、さらにその価格の算定式は大半が原油価格に連動するものとなっています。今回のエネルギーを巡る混乱の中で、①日本はそもそも価格を安定させる効果がある長期契約を中心にLNGを調達していたことに加え、さらに、②天然ガスやLNGの価格上昇の状況と比べて原油の価格上昇の状況が比較的落ち着いていたことも影響した結果、日本が締結していた長期契約は、量だけでなく価格についてもリスクを一定程度ヘッジできていたと考えられ、こうしたことが日本の輸入物価の抑制に寄与した要因となっていると考えられます。
一方の欧州では、過去にLNGスポット市場の市場価格が低下したことを受けて、原油価格連動の長期契約をリスクと捉えていたため、ガス市場価格連動の長期契約や、スポット市場からの調達等へとシフトを進めていました。今回のエネルギーを巡る情勢の中で、欧州の輸入物価が急騰した背景には、欧州がスポット市場からのLNG調達を増やしてきたことに加え、過去に締結済の長期契約により調達したLNGの価格がガス市場価格に連動していたこともあると考えられます。
COLUMN
サハリン1・2プロジェクト
日本は、原油及びLNGの輸入のほぼ全量を海外からの輸入に依存しており、エネルギー安定供給の観点から供給源の多角化を進めてきました。特に、原油は94.1%を中東に依存しており、LNGも豪州やマレーシアといった特定の産ガス国の依存度が高いことから、調達先の多角化が急務となっています(第122-1-3)。
【第122-1-3】日本の原油・LNG・石炭輸入におけるシェア(2022年速報値)
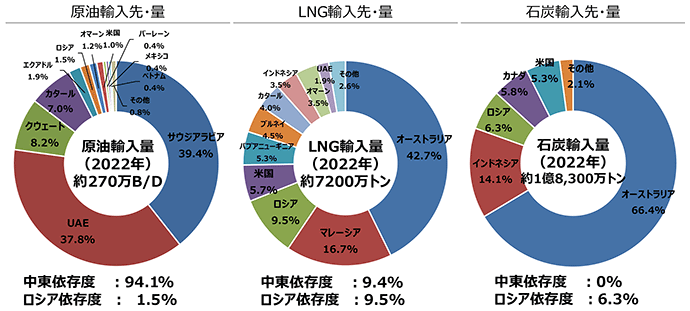
【第122-1-3】日本の原油・LNG・石炭輸入におけるシェア(2022年速報値)(ppt/pptx形式:58KB)
- 資料:
- 財務省貿易統計
ロシアのサハリン島における石油・天然ガス開発プロジェクトである「サハリン1」及び「サハリン2」は、中東を始めとする他の国や地域と比べて、日本との距離が非常に近く、輸送日数やコストを低く抑えられ、またマラッカ海峡やホルムズ海峡といった、いわゆるチョークポイントを通過する必要がないことから、安全かつ安定的な供給が可能となっています。さらに近年は、サハリン地域の開発に加えて、ロシアにおける北極圏開発も進められており、NSR(北極海航路)を経由したLNG調達といった、さらなる多角化を目指した開発が進められてきました。
しかしながら、今般のロシアによるウクライナ侵略を受けて、前節でも記載したとおり、G7等の各国においては、ロシアに対し、エネルギー分野でも様々な制裁措置を講じてきました。他方で、国によってロシア産エネルギーに対する依存度は大きく異なっており、例えば、ドイツやイタリアはロシアに対するエネルギー依存度が高いことから、ロシア産エネルギーへの依存度を低減させる影響は大きいと考えられます(第122-1-4)。
【第122-1-4】G7各国の一次エネルギー自給率とロシアへの依存度
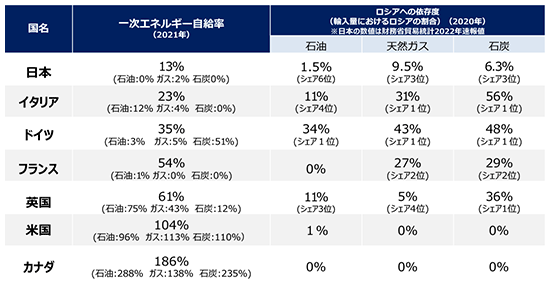
【第122-1-4】G7各国の一次エネルギー自給率とロシアへの依存度(ppt/pptx形式:52KB)
- 資料:
- World Economy Balances2022(自給率)、BP統計、EIA Oil Information、Cedigaz統計、Coal Information(依存度)、貿易統計(日本)を基に経済産業省作成
こうした中、2022年5月8日のG7首脳共同声明では、「我々は、ロシアの石油の輸入のフェーズアウト又は禁止等を通じて、ロシアのエネルギーへの依存状態をフェーズアウトすることをコミットする。我々は、適時にかつ秩序立った形で、また、世界が代替供給を確保するための時間を提供する形で、これを行うことを確保する。」と記載されました。日本としても、G7首脳声明も踏まえ、持続可能な代替エネルギーの供給を確保するための時間を確保しながら、石油や石炭を含め、ロシアのエネルギーへの依存状態から徐々に脱却していくこととしています。
一方で、ロシアにおける日本の原油及びLNGプロジェクトであるサハリン1・2について、サハリン1は、原油輸入の9割超を中東に依存する日本にとって貴重な中東以外からの原油調達先であり、また、サハリン2は、日本のLNG輸入の約9.5%を供給し、総発電量の約3%に相当する等、日本の電力・ガス供給に不可欠なエネルギー源となっています。そのため、いずれもエネルギー安全保障上、極めて重要なプロジェクトです。
その上で、仮に日本がサハリン1・2から撤退し、日本の権益をロシアや第三国が取得する場合、ロシアを逆に利したり、日本のエネルギー安全保障を害したりすることとなり、有効な制裁とならない可能性があります。具体的には、仮にロシアに権益が渡ることになった場合、ロシアはその権益からの生産物をより高い価格で第三国や市場で売却することで、より多くの外貨を稼ぐことになります。一方、日本企業は、足元では代替エネルギーをより高い価格で市場から調達せざるを得なくなる、あるいは、代替調達先が確保できなければ、国民生活や経済活動が、多大な犠牲を強いられるおそれがあります。こうした、ロシアに対する制裁の実効性及び長期的なエネルギー安定供給確保の観点から、現状、日本としてはサハリン1・2の権益を維持する方針です。
ロシアの大統領令に基づき、2022年8月にサハリン2、同年10月にサハリン1の新会社が設立されました。サハリン1・2に参画する日本企業は、新会社への参画を申請し、その申請を承認する旨のロシア政府令が公表されたところです。このことは、日本のエネルギー安全保障の観点から非常に意義があることと考えています。
(2)日本におけるエネルギーの消費者物価の推移
私たちが日々生活する上で負担している電気料金やガス料金、ガソリン料金等ですが、基本的にはその燃料や原料の価格動向等が反映される仕組みとなっています。例えば電気料金の多くに適用されている「燃料費調整制度15」では、1〜3月の燃料価格が同年6月の電気料金に反映されるといった仕組みになっており、燃料価格が下がっている場合は電気料金も下がり、燃料価格が上がっている場合は電気料金も上がる16ことになっています。
そのため、今回のエネルギー価格高騰は、日本の電気料金、ガス料金、ガソリン料金の上昇にもつながっています。実際に、電気料金の月別平均単価の推移を見ると、2022年12月時点では1年前と比べ家庭向けが約3割、産業向けが約6割上昇しました(第122-1-5)。また都市ガス料金についても同様に、家庭向けが約4割、産業向けに関しては約2倍に上昇しました(第122-1-6)。
【第122-1-5】電気料金の月別平均単価の推移
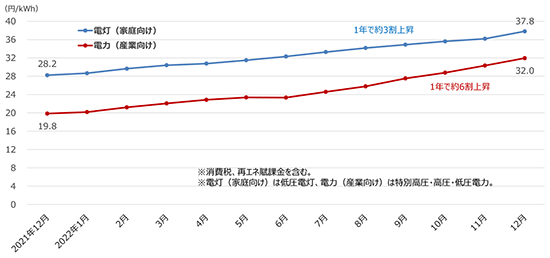
【第122-1-5】電気料金の月別平均単価の推移(ppt/pptx形式:59KB)
- 資料:
- 電力取引報を基に経済産業省作成
【第122-1-6】都市ガス料金の月別平均単価の推移
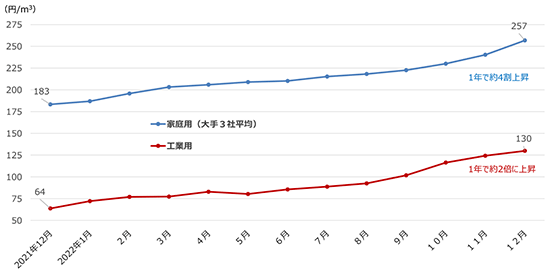
【第122-1-6】都市ガス料金の月別平均単価の推移(ppt/pptx形式:59KB)
- 資料:
- 家庭用は大手3社の標準家庭の料金の平均を元に原料費調整の上限がない前提で経済産業省作成。工業用はガス取引報を基に経済産業省作成
このように、世界のエネルギー価格の高騰を受けて日本国内における電気料金やガス料金等も上昇しましたが、前節にも掲載した消費者物価指数を用いて、改めて世界各国の状況と比較すると、輸入物価と同様に、ここでも日本の特徴を見ることができます。欧州では、2020年1月と比較すると、電気やガスの消費者物価が2倍や3倍以上になっている国もありますが、その一方、日本の電気やガスの消費者物価の上昇幅は相対的に小さいことがわかります(第122-1-7)17。
【第122-1-7】消費者物価指数(電気料金、ガス料金)の推移(2020年1月の数値を基準(100)としている)
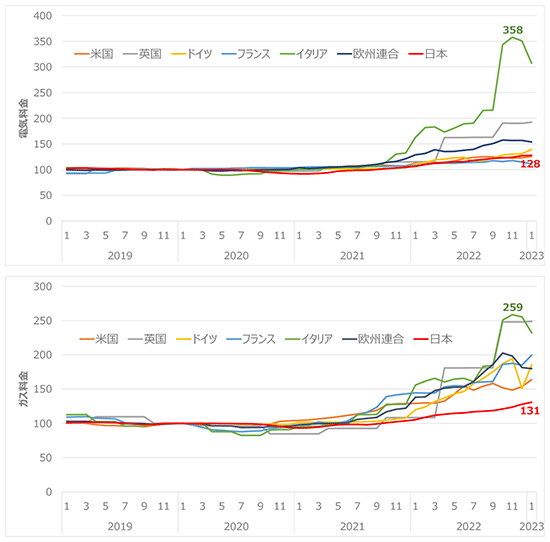
【第122-1-7】消費者物価指数(電気料金、ガス料金)の推移(2020年1月の数値を基準(100)としている)(ppt/pptx形式:53KB)
- 資料:
- 各国政府統計より経済産業省作成
その要因としては、前項に記載したとおり、天然ガスの輸入物価の上昇幅が相対的に小さいことに加え、燃料費調整制度・原料費調整制度における上限設定の影響で、電力会社やガス会社が燃料費・原料費の上昇分を小売料金に転嫁できていない、といったこと等の複合的な要因が考えられます。
(3)エネルギー価格の高騰への日本の対応
電気料金やガス料金、ガソリン料金等の上昇は、家計や企業の経営等にとって大きな負担となっています。こうした中、政府はエネルギー価格の高騰の影響を受ける家庭や企業等の負担を軽減するため、次のような措置を実施しました。
①燃料油価格激変緩和対策事業
政府では、燃料油(ガソリン・軽油・灯油・重油・航空機燃料)の卸価格の急騰を抑制することにより、消費者の負担を低減することを目的に、「燃料油価格激変緩和対策事業」を行っています。この制度は、全国平均ガソリン小売価格が1リットル当たり168円程度よりも上がらないように、石油元売・輸入事業者に価格上昇を抑える原資を政府が支給することにより、ガソリン等の卸価格の上昇を抑え、小売価格の急騰を抑えるものです(第122-1-8)。
【第122-1-8】燃料油価格激変緩和対策事業のスキーム
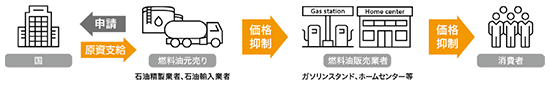
【第122-1-8】燃料油価格激変緩和対策事業のスキーム(ppt/pptx形式:74KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
ガソリン価格の上昇に伴い2022年1月より支給が開始されており、事業開始当初は、レギュラーガソリンの全国平均価格が170円を超えた際に、ガソリン、軽油、灯油、重油を対象に、補助の上限額を1リットル当たり5円としていました。その後、ロシアによるウクライナ侵略等の地政学的な変化が、世界の原油価格や需給に大きな影響を与える可能性があったことから、同年3月には、補助上限額を25円にするとともに基準価格を172円にすることで、急激な価格上昇を抑制しました。また、同年4月には、長引く原油価格の高騰・乱高下が、新型コロナ禍からの経済回復や国民生活への悪影響を与えることを防ぐ観点から、基準価格を168円に引き下げ、補助上限額を35円とするとともに、さらなる超過分についても2分の1を支援する制度を設けました。あわせて、航空機燃料も対象に追加しています。その後、2023年1月からは、補助上限額を緩やかに調整しています(第122-1-9)。その結果、レギュラーガソリンの全国平均価格は2022年度末に至るまで1リットル当たり170円前後の水準を維持しています。なお、仮にこの補助制度がなかった場合の全国平均価格を見てみると、2022年4月から11月にかけて1リットル当たり200円を超えている時期があったことがわかります(第122-1-10)。
【第122-1-9】燃料油価格激変緩和対策事業の推移
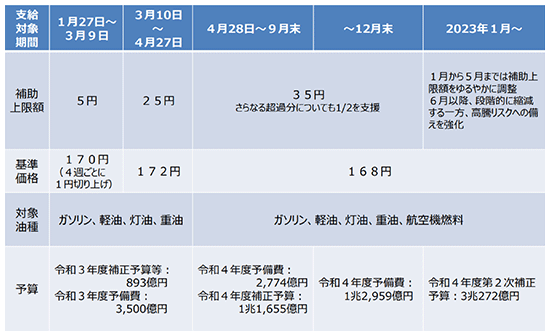
【第122-1-9】燃料油価格激変緩和対策事業の推移(ppt/pptx形式:219KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
【第122-1-10】レギュラーガソリンの全国平均価格の推移
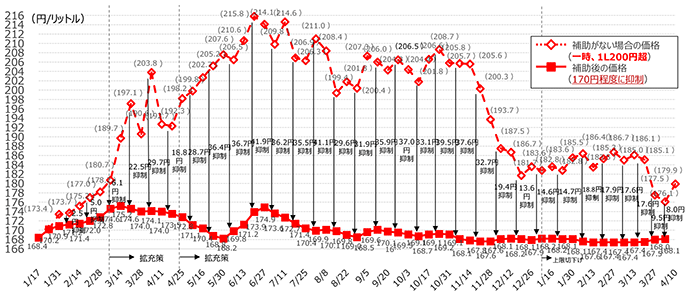
【第122-1-10】レギュラーガソリンの全国平均価格の推移(ppt/pptx形式:148KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
②電気・ガス価格激変緩和対策事業
「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(2022年10月28日閣議決定)に基づき、各小売事業者等を通じて、電気・都市ガスの使用量に応じた料金の値引きを行い、電気料金・都市ガス料金の急激な上昇によって影響を受ける家庭や企業等の負担を軽減する事業を実施しています。
具体的には、電気料金については、低圧契約の家庭等に対して7円/kWh(9月使用分は3.5円/kWh)、高圧契約の企業等に対して3.5円/kWh(9月使用分は1.8円/kWh)、また、都市ガス料金については、年間契約量が1,000万㎥未満の家庭や企業等に対して30円/㎥(9月使用分は15円/㎥)を値引きすることとし、2023年1月使用分(同年2月請求分)から値下げを開始しました(第122-1-11)。
【第122-1-11】電気・ガス価格激変緩和対策事業のスキーム
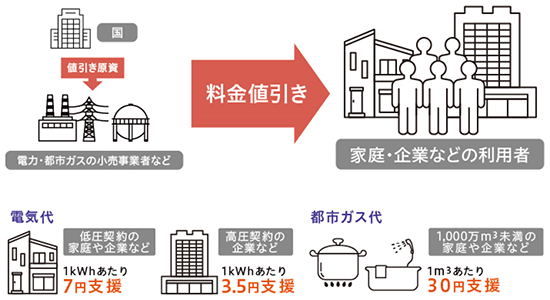
【第122-1-11】電気・ガス価格激変緩和対策事業のスキーム(ppt/pptx形式:171KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
これにより、標準的な世帯18では、電気料金で月額2,800円、都市ガス料金で月額900円の負担軽減となっています。
③エネルギー価格高騰へのその他の対応
これまでに紹介してきた激変緩和対策事業に加えて、多くの地方公共団体においてもエネルギー価格高騰への対応策が実施されました。2022年9月20日及び2023年3月28日に、足元の物価高騰に対する追加対策等を目的として、コロナ物価予備費の使用が閣議決定されました。その中に、地方創生臨時交付金(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金)が盛り込まれ、各地方公共団体が、推奨事業メニューに応じて電力・ガス・食料品等の価格高騰への対応を地域の実情に応じて重点的・効果的に活用できるよう、総額1兆3,000億円が措置されました。この地方創生臨時交付金を活用して、各地方公共団体ではそれぞれの地域の実情にあわせて、必要な支援をきめ細やかに実施しています(第122-1-12)。
【第122-1-12】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金の推奨事業
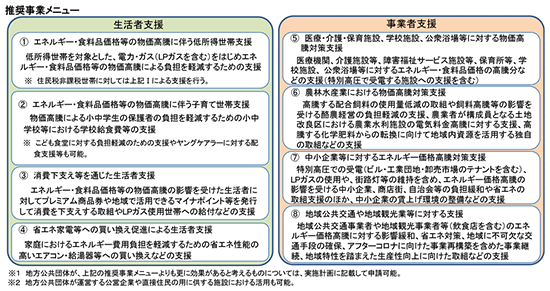
【第122-1-12】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金の推奨事業(ppt/pptx形式:56KB)
- 資料:
- 第8回物価・賃金・生活総合対策本部(2023年3月22日)より抜粋
2.電力の供給力不足に伴う需給ひっ迫
エネルギーの安定供給に関して国内では、ロシアによるウクライナ侵略による影響とは別に、電力の需給ひっ迫19という事象も発生しました。2022年の3月には、東京電力管内(以下「東京エリア」という。)・東北電力管内(以下「東北エリア」という。)で電力需給ひっ迫警報が発令され、同年6月にも東京エリアで電力需給ひっ迫注意報が発令されました。
2022年3月の需給ひっ迫は、福島県沖地震20等による発電所の停止、真冬並みの寒さによる需要増加、悪天候による太陽光の出力減少、冬の高需要期を過ぎたことによる発電所の計画的な補修点検等が重なったことにより発生しました。また、同年6月の需給ひっ迫は、真夏並みの暑さによる需要増加、夏の高需要期を前にした計画的な補修点検等が重なったことにより発生しました。
これらの状況を受けて、政府、電力広域的運営推進機関(以下「電力広域機関」という。)及び事業者においては、発電所の出力増加、地域間での機動的な電力融通、ディマンド・リスポンス(以下「DR」という。)等、電力需給を緩和させるためにあらゆる取組を行いました。また、二度の電力需給ひっ迫を踏まえ、2022年度の冬季に向けて様々な対策を実施してきました。
本項では、2022年3月と6月に発生した電力需給ひっ迫の背景・要因・対応、そして2022年度冬季に向けた電力需給対策について記載します。
(1)2022年3月の東日本における需給ひっ迫
2022年3月22日に東京・東北エリアで発生した電力需給ひっ迫では、2012年の制度整備後、初となる「電力需給ひっ迫警報」が東京・東北エリアに発令されました。また、官民双方において各種媒体を通じて広く国民に節電を要請し、その結果、多くの需要家の方々の協力により、合計約4,400万kWhの需要抑制がなされ、大規模停電は回避されました(第122-2-1)。
【第122-2-1】2022年3月22日 東京及び東北エリアにおける需給ひっ迫
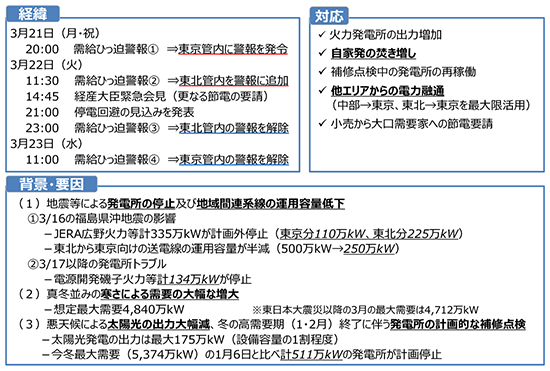
【第122-2-1】2022年3月22日 東京及び東北エリアにおける需給ひっ迫(ppt/pptx形式:54KB)
- 資料:
- 資源エネルギー庁「2022年3月の東日本における電力需給ひっ迫に係る検証取りまとめ」
(1)需給ひっ迫発生の背景・要因
(ア)地震等による発電所の停止及び地域間連系線の運用容量低下
2022年3月16日に発生した福島沖を震源とする地震により停止した火力発電所のうち、一部は復旧に時間がかかり、3月22日の需給ひっ迫の際には計6基(約335万kW)が停止していました。また、通常であれば約500万kWの送電が可能な東北東京間連系線も、地震の影響で運用容量が約半分にまで減少しました。これにより、東北エリアから東京エリアへと送電可能な電力にも制約が生じることとなりました。
加えて、3月17日以降に地震とは関係なく、火力発電所3基(約134万kW)が3月20日までの間にトラブルで停止していました。これらにより、需給ひっ迫当日の電力の供給力が大きく低下していました。
(イ)真冬並みの寒さによる需要の大幅な増大
3月22日の電力需給ひっ迫当日、東京及び東北エリアにおいて、3月としては記録的な寒さにより電力需要が大きく増加していました。前日の3月21日夜時点における3月22日の東京エリアにおける想定最大需要は約4,840万kWとなり、「10年で一度の厳しい寒さ」を想定した場合の3月の東京エリアの最大需要である4,536万kWを約300万kW上回る、極めて高い水準となっていました。
(ウ)悪天候による太陽光の出力大幅減
3月22日は1日を通じて日差しが少なく、東京エリアの太陽光発電の1日の発電量は約1,189万kWhと低い状態に留まりました。前年の同時期である2021年3月16日〜31日の16日間の平均発電量は約7,208万kWhであり、3月22日は太陽光発電の出力が大幅に低下していたことがわかります。
(エ)冬の高需要期終了に伴う発電所の計画的な補修点検
3月は一般的に高需要期ではないため、例年、発電所の補修点検のための計画停止が1月や2月よりも多くなっていますが、このことも電力需給ひっ迫の要因の1つとして挙げることができます(第122-2-2)。3月22日に計画停止をしていた火力発電所は約570万kWとなっていました。これは、同様に厳しい寒さが襲った同年1月6日(計画停止していた火力発電所は約230万kW)と比べても、約340万kWの供給力が低下していたこととなります。
【第122-2-2】2021年度の発電事業者の供給計画における全国の発電所の月別補修量の分布
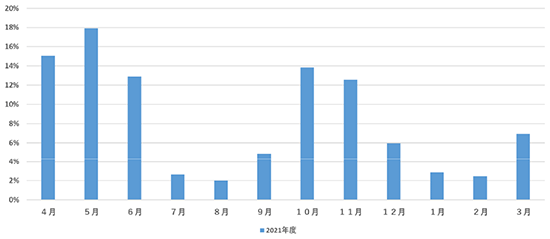
【第122-2-2】2021年度の発電事業者の供給計画における全国の発電所の月別補修量の分布(ppt/pptx形式:69KB)
- 資料:
- 資源エネルギー庁「2022年3月の東日本における電力需給ひっ迫に係る検証取りまとめ」
(2)需給ひっ迫への対応
(ア)火力発電所の出力増加・自家発の焚き増し・補修点検中の発電所の再稼働
東京エリアにおいて、火力発電所の増出力運転(定格出力を上回る出力での運転)を実施し、計26.5万kWの供給力を確保しました。また、東北エリアにおいても増出力運転により計9.8万kWの供給力を確保しました。
さらに、東京電力パワーグリッド及び東北電力ネットワークは、小売電気事業者及び自家発事業者に対して、発電余力の焚き増しの要請を行いました。東京エリアでは3月22日〜23日で、約207万kWhの発電量が得られました。
加えて、東京エリアにおいては、一部の発電事業者が火力発電所の補修作業の実施時期を調整し、計171.2万kWの出力を確保しました。
(イ)他エリアからの電力融通
需給ひっ迫前日の3月21日時点で、東京エリアにおける節電効果を織り込まない実質の予備率はマイナス7.8%となっており、他エリアから東京エリアへの最大限の電力融通が不可欠となっていました。その後、3月22日の東北エリアの予備率は8.4%の見通しであったため、東北エリアから東京エリアへの電力融通指示が電力広域機関から出されました。さらにその後、東北エリアの需要が低気温により想定以上に増加し、東北エリアにおいて需給ひっ迫のおそれが生じたため、北海道エリア(北海道電力管内)から東北エリアへの電力融通指示も出されました。
(ウ)需要家への節電要請
政府による電力需給ひっ迫警報の発令に加えて、官民双方において各種媒体を通じ、広く国民に節電を要請しました。その結果、多くの需要家の方々の協力により、東京エリアにおいては1日の総電力需要の6%に当たる約4,400万kWhの需要抑制がなされました。
(2)2022年6月の東京電力管内における需給ひっ迫
2022年3月の電力需給ひっ迫から3か月後の同年6月27日から30日にも、東京エリアを中心に電力の需給ひっ迫が発生し、東京エリアには「電力需給ひっ迫注意報」が発令されました。3月の需給ひっ迫時と同様に、官民双方において各種媒体を通じて広く国民に節電を要請する等、電力需給を緩和させるためのあらゆる取組を行い、当日は節電効果による需要の減少や、供給力の増加等により、大規模停電は回避されました(第122-2-3)。
【第122-2-3】2022年6月 東京エリアにおける需給ひっ迫
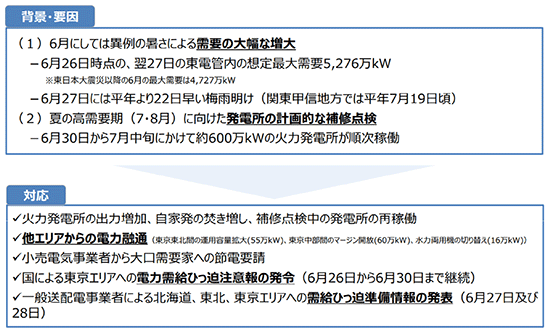
【第122-2-3】2022年6月 東京エリアにおける需給ひっ迫(ppt/pptx形式:343KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
①需給ひっ迫発生の背景・要因
3月の需給ひっ迫では、真冬並みの寒さによる需要増加がその一因となりましたが、6月の需給ひっ迫では、真夏並みの暑さによる需要増加が一因となりました。需給ひっ迫の期間、東京エリア内は過去に例を見ない記録的な猛暑となり、6月30日の最大需要電力は5,487万kWを記録しましたが、これは過去10年の6月の最大需要電力である4,727万kWを1割以上も上回っていました。
また、6月は3月と同様に、夏の高需要期(7月・8月)に向けて、補修点検を行うために計画停止している発電所が多くなっている時期であり、このことも電力需給ひっ迫の要因となりました。
②需給ひっ迫への対応
3月の需給ひっ迫時と同様に、火力発電所の出力増加や自家発の焚き増し、補修点検中の発電所の再稼働、他エリアからの電力融通、節電要請等を実施することで、電力需要の減少と電力供給力の増加を図りました。
6月26日(日)から6月30日(木)までの電力需給ひっ迫に対する対応は以下のとおりです(第122-2-4)。
【第122-2-4】6月26日〜6月30日 需給ひっ迫時の対応
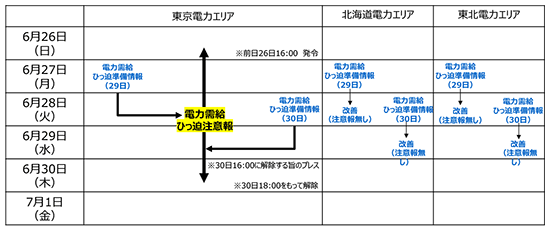
【第122-2-4】6月26日〜6月30日 需給ひっ迫時の対応(ppt/pptx形式:47KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
- 6月26日(日)夕方、翌27日(月)の東京エリアの広域予備率が5%を下回る見込みとなったため、資源エネルギー庁が「電力需給ひっ迫注意報」を発令しました。
- その後、東京エリアにおいては30日(木)まで注意報を継続し、電力需給のひっ迫のおそれがなくなった30日18時をもって注意報を解除しました。
- 北海道、東北エリアについては、29日(水)、30日(木)の前々日時点でエリア予備率が5%を下回る見通しであったため、各エリアの一般送配電事業者が「電力需給ひっ迫準備情報」を発出しました。その後、前日段階で広域予備率の回復が見られたため、電力需給ひっ迫注意報の発令はありませんでした。
③需給ひっ迫への対応の検証
資源エネルギー庁では6月の電力需給ひっ迫の後、今回の電力需給ひっ迫の検証や今後の施策の参考とするため、節電対応の個別事例を把握することを目的として、所管団体を通じてアンケートを行い、東京エリアの製造業や小売業等、801社から回答を得ました。アンケート結果によれば、国から「電力需給ひっ迫注意報」が発令されていることについて、6月26日の段階で約6割、27日の午前中までには9割の事業者が認識していました。それを受けて、約6割が事前に節電行動を検討し、うち約9割が普段と行動を変化させたと回答しています。また、具体的な取組内容としては「節電の呼びかけ」「消灯」「冷房の温度調整」といった身近な取組が大宗を占めていたことがわかりました(第122-2-5)。
【第122-2-5】今回の電力需給ひっ迫における節電対策に係るアンケートについて
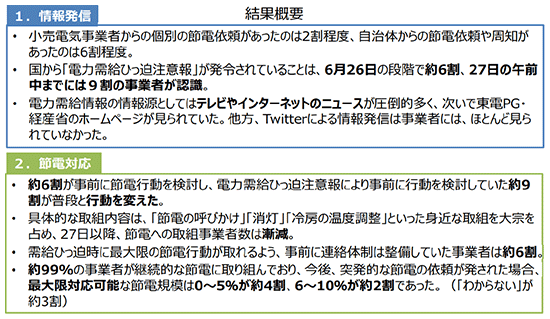
【第122-2-5】今回の電力需給ひっ迫における節電対策に係るアンケートについて(ppt/pptx形式:659KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
(3)2022年度冬季の電力需給対策
2022年3月、6月に二度の電力需給ひっ迫を経験し、2022年度冬季にも厳しい電力需給となることが想定されたことから、2022年11月1日に2022年度2回目の電力需給に関する検討会合が開催されました。そして、いかなる事態においても国民生活や経済活動に支障が生じることがないよう、電力需給の安定に万全を期すべく、「2022年度冬季の電力需給対策」が決定されました。休止電源の稼働や非化石電源の最大限の活用等の供給側の対策、無理のない範囲での節電協力の呼びかけや省エネ対策の強化、DRの普及拡大等の需要側の対策、予備電源の確保や新規投資促進策の具体化等の構造的対策が、電力需給対策として取りまとめられました(第122-2-6)。
【第122-2-6】2022年度冬季の電力需給対策
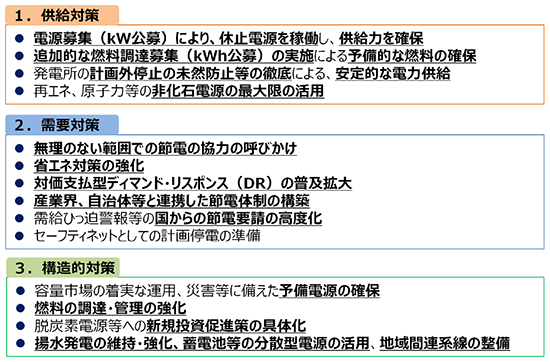
【第122-2-6】2022年度冬季の電力需給対策(ppt/pptx形式:82KB)
- 資料:
- 資源エネルギー庁「2022年度冬季の電力需給対策」
2022年度冬季は、無理のない範囲での節電の呼びかけ(2022年12月1日〜2023年3月31日)や、追加供給力対策等の電力需給対策を講じたこともあり、2023年1月下旬に10年に一度程度の厳しい寒波に見舞われたものの、安定供給に特に大きな支障は生じませんでした。
COLUMN
ディマンド・リスポンス(DR)/節電プログラム促進事業
生活に欠かせない電気を安定して供給するためには、電気をつくる量(供給)と電気の消費量(需要)が常に同じでなければなりません。その量が常に一致していないと、バランスが崩れ、大規模な停電につながるおそれがあります。これをいわゆる「同時同量」の原則といいます。また電気は、急な需要の増加に備えてあらかじめ蓄えておくことはできず、電気が必要となったタイミングで、必要な量の電気をつくり、供給しなければなりません(開発が進む蓄電池でも、大量の電気を蓄えるには相当量の蓄電池を確保する必要があります)。そのため、電力会社は電力の需給バランスを一定にするために、あらかじめ作成した発電計画をベースに、刻々と変動する電力需給にあわせて発電量を変え、供給する電力量を需要量と一致させ続ける努力をしています。
さらに供給側には、電力の需給バランスに急激な変動をもたらすリスク要因が存在しています。例えば、太陽光や風力等の再エネ電源からの電力供給量は、天候等の様々な条件によって変動しますが、近年の再エネの導入量が拡大していることによってこの変動量が増加しています。また、電力需要が多い時期には需給がひっ迫する一方で、電力需要が少ない時期には供給過剰となり、再エネ由来の電気が余るという事象も起きています。
こうした状況を背景に、電力の需要側である消費者が、電力の供給状況に応じて、電気を使う量や時間といった消費パターンを変化させるDRの重要性が高まっています。電力は、冷房や暖房、照明等の利用が多くなる時間帯に需要が高まるのが一般的です(第122-2-7)。電力消費者が、電力の使用量や使用時間を変えることで、この需要のパターンを変えることができます。
【第122-2-7】夏季と冬季の電力需要パターンとピーク時間帯(イメージ)
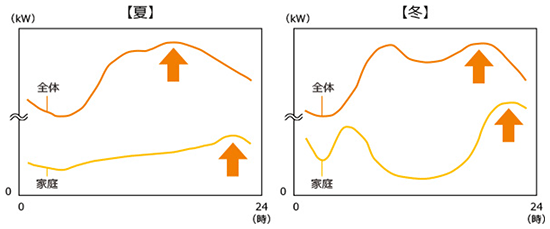
【第122-2-7】夏季と冬季の電力需要パターンとピーク時間帯(イメージ)(ppt/pptx形式:101KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
例えば、多くの電力が消費される時間帯や、太陽光発電の発電量が少なくなり、需給がひっ迫しやすい時間帯(夕方15時〜18時頃)に、消費者が電気を使う量を減らせば、ピークの山の高さを低くすることができます。こうした需要量を減らす取組を「下げDR」と呼びます。また、自宅の蓄電池に貯めていた電気や、コージェネレーションシステム等の自家発電設備を使うことで、電力会社からの電力供給を抑制することも「下げDR」の一種です。
「上げDR」は、春季や秋季の昼間のように、再エネ(太陽光)の発電量が多い一方で電力需要は比較的小さい場合等、電力の供給量が需要量を上回る際に必要となります。余りそうな電力を有効活用するために、例えば夕方から夜の時間帯ではなく、昼の時間帯に電気自動車(EV)のバッテリーや蓄電池の充電をする等、時間をずらして電力を消費することで、電力の需給バランス確保に役立てる方法があります。こうした「上げDR」が機能すれば、ときに需要以上に発電してしまう再エネの電力を、余すところなく活用することができます。このように、DRはエネルギーを効率よく使うこと(省エネ)にも貢献するため、気候変動問題への対応にも役立ちます(第122-2-8)。
【第122-2-8】上げDR・下げDRのイメージ
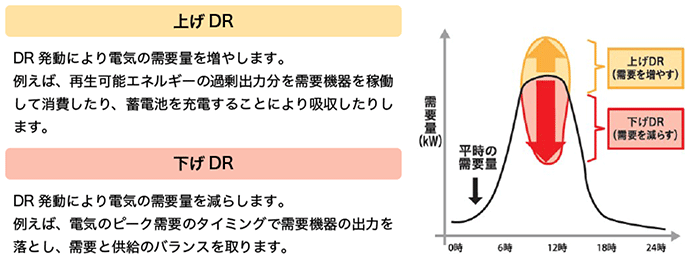
【第122-2-8】上げDR・下げDRのイメージ(ppt/pptx形式:123KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
こうした電力需給ひっ迫に備えるため、需要側の対策の1つとして「対価支払型DR」が促進されました。対価支払型DRとは、需要家が電力需要のピーク時等に節電を行うことをあらかじめ電力会社と契約しておき、その上で電力会社からの依頼に応じて節電を行った場合に対価を得られるという仕組みです。これを促すため、2022年度、政府は電気利用効率化促進対策事業として、節電プログラム促進事業を行いました。これは、本事業に採択された小売電気事業者等が実施する節電プログラムへの参加表明を行った需要家の方々に、節電への取組に対する電力会社による特典等に加えて、国による「参加特典」や「節電達成特典」を付与する(小売電気事業者等を通じて需要家の方々に付与)もので、需要家の方々が節電を行うインセンティブを高めました(第122-2-9)。
【第122-2-9】節電プログラム促進事業の概要
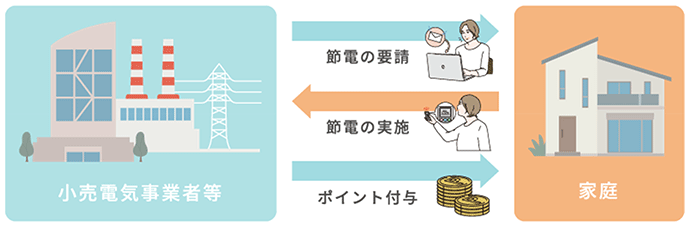
【第122-2-9】節電プログラム促進事業の概要(ppt/pptx形式:84KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
本節で見てきたとおり、この1年はエネルギー価格の高騰や電力需給のひっ迫の発生等、日本のエネルギー需給構造の脆弱性が顕在化した1年となりました。国民生活や社会・経済活動の根幹である安定的で安価なエネルギー供給は日本の最優先課題であり、気候変動問題への対応を進めるとともに、エネルギー危機にも耐えうる強靱なエネルギー需給構造へと転換していく必要性が高まっています。
そうした中、エネルギー安定供給の確保・産業競争力の強化・脱炭素を同時に実現するための取組の方針が「GX21実現に向けた基本方針」として取りまとめられ、2023年2月10日に閣議決定されました。本方針の内容については次章の第2節で記載しますが、エネルギー安定供給の確保に向け、徹底した省エネに加え、再エネや原子力等のエネルギー自給率の向上に資する脱炭素電源への転換等、GXに向けた脱炭素の取組を進めること等が記載されています。
- 13
- 第211-4-1と同一のデータ。
- 14
- 第121-2-2のガスの輸入物価の推移データと同一のデータ。
- 15
- 燃料費調整制度は、事業者の効率化努力のおよばない燃料価格や為替レートの影響を外部化することにより、事業者の経営効率化の成果を明確にし、経済情勢の変化を出来る限り迅速に料金に反映させると同時に、事業者の経営環境の安定を図ることを目的とし、1996年1月に導入されました。2016年4月以降は、旧一般電気事業者の小売部門(みなし小売電気事業者)の特定小売供給約款における契約種別ごとの料金に適用することとなっています。
- 16
- 燃料の価格が大幅に上昇した際の需要家への大きな影響を和らげるため、自動的に調整される料金の幅に一定の上限が設けられているメニューもあります。
- 17
- 第121-2-3の電気・ガスの消費者物価の推移データと同一のデータ。
- 18
- 標準的な世帯:月間で電気を400kWh、都市ガスを30㎥使用する2人以上の世帯を指します。
- 19
- 電力需要に対して供給力にどの程度の余裕があるかを示したものを電力の予備率といいます。電力需要には3%程度のぶれがあることから、電力の安定供給には予備率3%が最低限必要とされています(予備率が低くなるほど電力需給はひっ迫することとなります)。
- 20
- 2022年3月16日23:36に福島沖を震源に発生した最大震度6強の地震。
- 21
- GX:Green Transformation(グリーントランスフォーメーション)のこと。