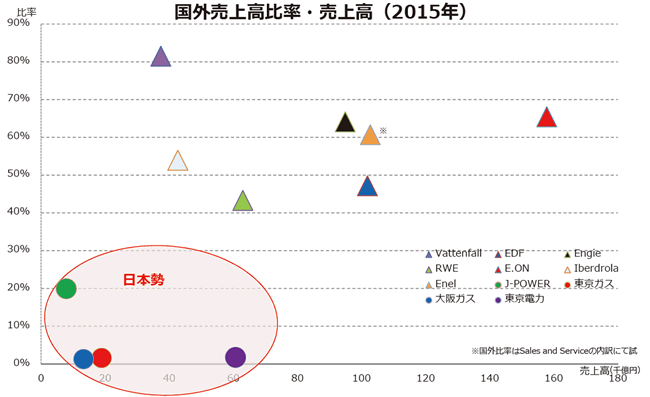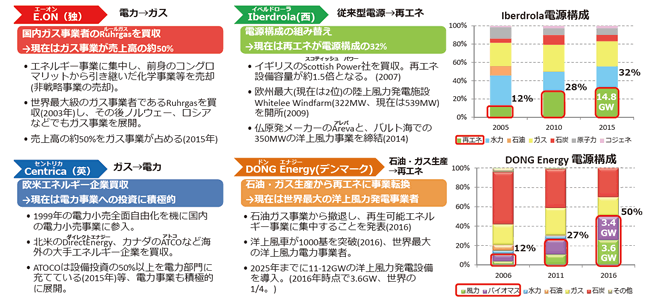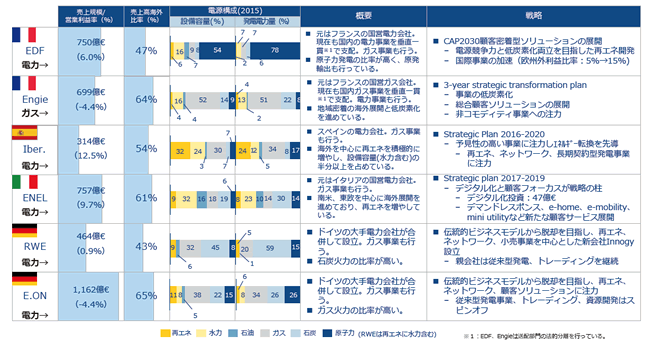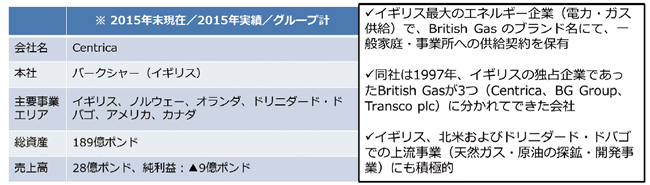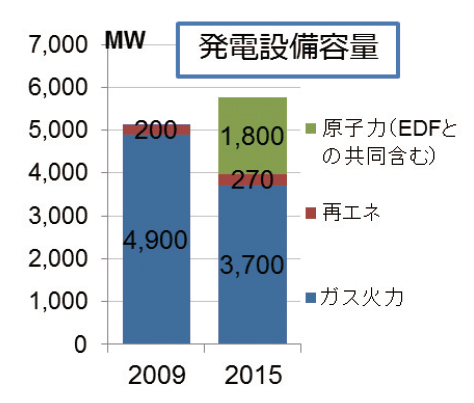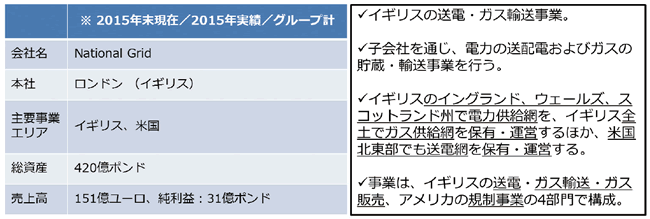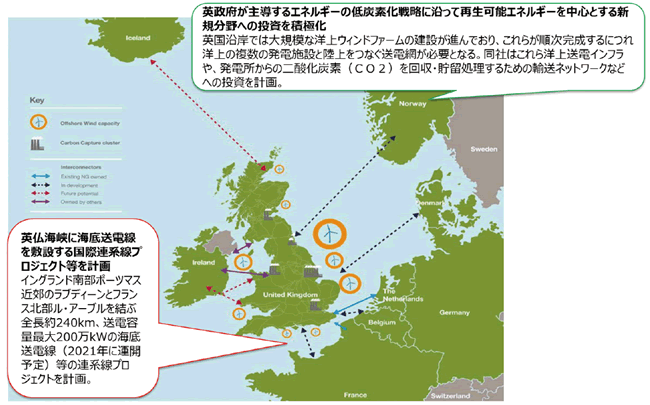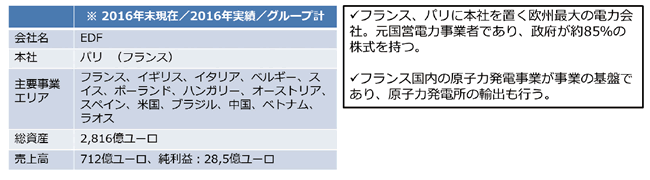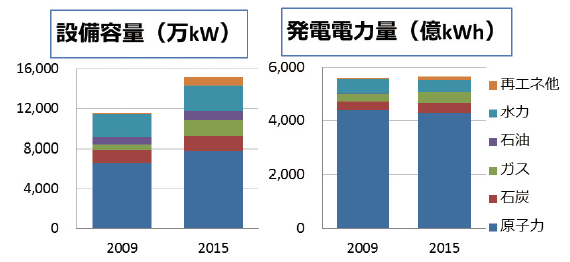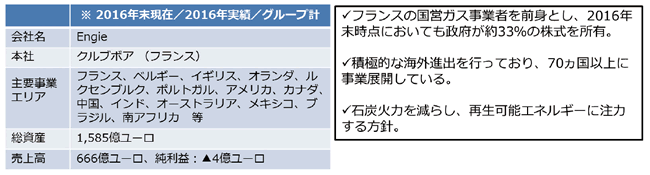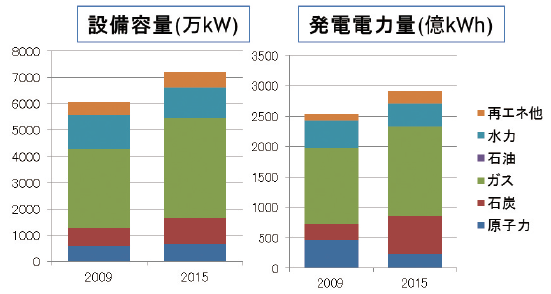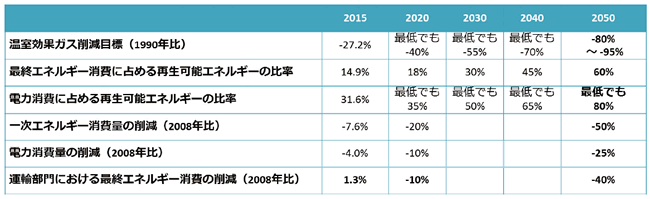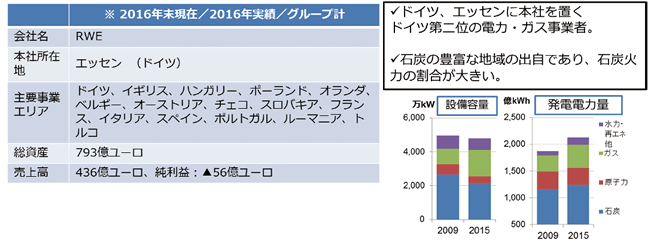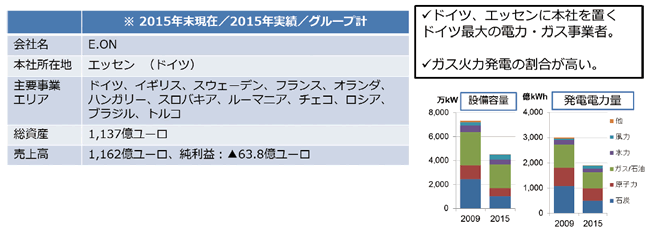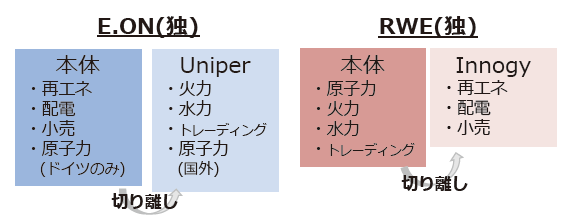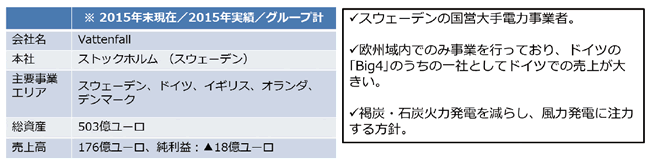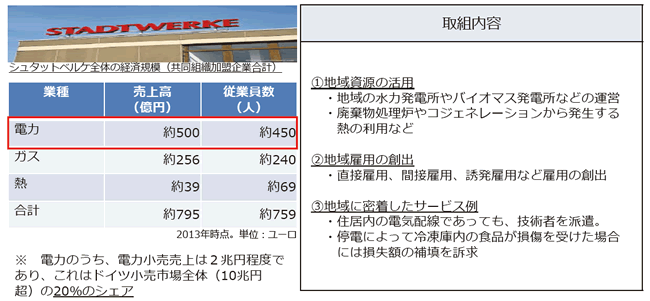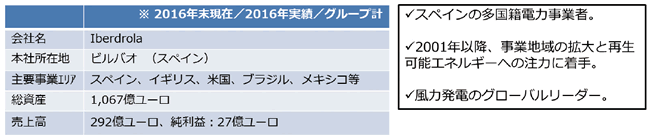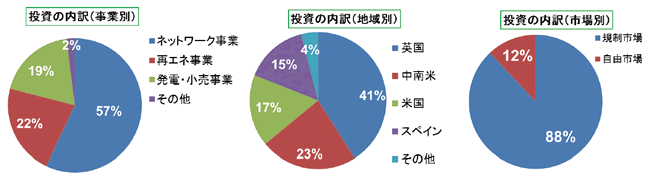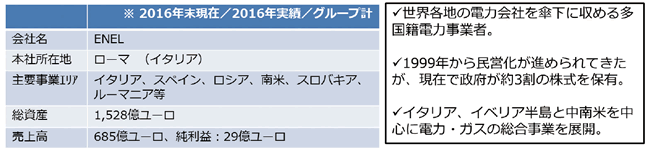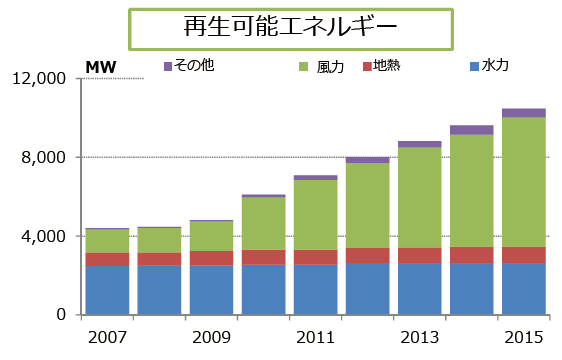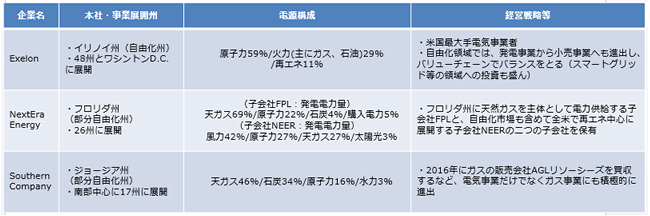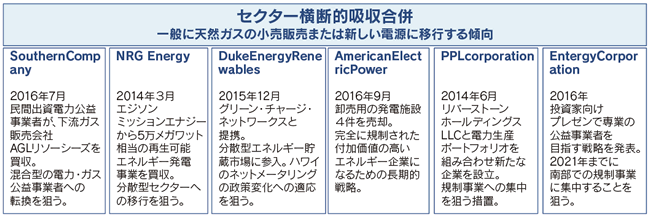第1節 国外電力・ガス産業の動向
1. 欧米における事業環境の変化と企業の対応(総論)
欧米では、2000年前後から電力・ガスの小売全面自由化や再エネの導入が進められており、制度の面で大きな事業環境の変化がありました。
とりわけ欧州では、欧州委員会が1996年、2003年、2009年に3段階の欧州電力指令とガス指令(以下「エネルギーパッケージ」という。)を出し、それを受けた各国は電力・ガス市場の自由化、及び垂直一貫型企業の分割などを推進しました。また、欧州委員会は、環境への適合や再エネ導入の拡大を目的として、2008年及び2014年に、それぞれ2020年、2030年の温室効果ガス削減・省エネ達成・再エネ導入率の枠組みを提示し、各国はそれを踏まえた再エネ支援策等を整備するなど、制度面で事業環境が大きく変化してきました。
また米国では、連邦政府と州政府で規制権限が分かれていることもあり、自由化の進捗や再エネの導入には州ごとに濃淡があり、制度面では欧州のように一律に議論することは困難ですが、技術面では、カリフォルニアのスタートアップ企業などを中心に、再エネ関連技術など、新しい技術とビジネスモデルが生まれ、企業の選択肢の幅を拡げるような動きも出てきています。
こうした制度面や技術面での事業環境変化に加え、先進国における経済成長の鈍化等に起因する国内エネルギー需要の伸びの低下と、反対に新興国における大きな需要の伸びも相まって、欧米のエネルギー企業では、新たな需要を求めた国外展開、電力・ガス分野の相互参入や電源構成の見直しといった従来事業から異分野への進出、また中長期的に新たな価値やサービスを創出していくための技術の発掘・取り込み(ベンチャー投資による次世代エネルギー技術の発掘や、M&Aを通じた取り込み)などの動きが見られています。
2000年前後から自由化が本格化した欧州では、国内市場での競争が激化する一方で、新たに開かれた国外市場でシェアを拡大する機会が増加しています。こうした事業環境変化を受け、欧州のエネルギー企業各社は、企業規模の大小にかかわらず、積極的に国外展開を行いました。
中でも、フランスの国営ガス企業であるGDFを出自として電気事業にも参入したEngieは、地域密着のサービスを提供するために24のビジネスユニットを編成するなど、EU域外にも積極的に展開する戦略を打ち出しています。また、スペインのIberdrolaやイタリアのENELは、国内市場のみでの成長に限界があることもあり、中南米等をはじめとしたEU域外への積極的な進出を行っています。
自由化の進展に伴って、同一業界内での競争だけでなく、電力・ガス等の相互参入も促進されています。例えば、ドイツの電力会社であるE.ONは同じくドイツのガス会社であるRuhrgasを買収することでガス事業にも進出し、今ではガスが電力と同程度の売上を占めるまでに成長しています。また、イギリスのガス会社のCentricaは、電力自由化を契機に電気事業に参入し、国外のエネルギー企業を買収しつつ、世界規模で電気事業を展開しています。
エネルギー企業の中では、その電源構成を変えてきている企業も存在します。スペインのIberdrolaは、その中でも顕著な例で、固定価格買取制度(以下「FIT」という。)等の再エネ導入支援策に後押しされて、風力発電を中心に再エネ電源に大きくシフトをしています。2015年時点で、保有する設備容量に対する再エネの比率は、32%と、欧州主要エネルギー企業の中でも最大級となっています。対照的に、石炭火力については、そのほとんどを手放していくとしています。DONG Energyは、政府が株式の過半を保有するデンマークの企業ですが、元々は北海の石油・ガス田の開発を行う企業であったところ、電気事業に進出し、その後再エネへのシフトを強めながら、現在では洋上風力発電の世界有数のプレーヤーとなっています。
再エネの急速な導入が進んだドイツにおいては、支援策を前提とした再エネに対して、火力が相対的に競争力を失っており、ドイツの電力会社であるRWEや、前述のE.ONなど、従来火力発電に競争力を有していた企業は厳しい経営状況となっています。このため、2016年に、両社とも、火力を中心とした従来型の事業と、再エネやネットワークなどの事業を切り分け、分社化を行うなどの大きな事業の転換を図っています。
このように、事業環境の変化に対して、地域の拡大や異分野への参入など、各社それぞれの戦略に基づいた対応をしています。また、欧米の主要企業は、今後も絶え間なく続くであろう事業環境の変化に備えて、その対応の選択肢を増やすため、新しい技術の発掘・取り込みにも力を入れています。
- 出典:
- Annual Report等を基に資源エネルギー庁作成
- 出典:
- Annual Report等を基に資源エネルギー庁作成
【第131-1-3】新サービス創出(技術革新)への動き
※エネルギー企業からベンチャーキャピタル等への出資額。括弧内はベンチャーキャピタル等の資金枠に占める割合を示す。
1 €=120円、1 $=110円で換算。
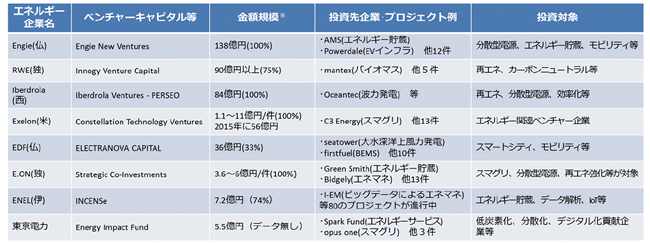
- 出典:
- 各社Annual Report、HP及び、報道等を基に資源エネルギー庁作成
企業としての研究開発へ力の入れ方として、売上高に占める研究開発費の割合などを比較すると、欧米の企業と日本企業とで大きな差は見られません。しかし、欧米の企業は、自ら内製するのみならず、シリコンバレー等のベンチャー企業への投資や、技術を所有する企業のM&Aなどにより、他社の技術・サービス・人材を効率的に発掘し、取り込もうとしています。近年では、再エネ関連技術、蓄電技術、分散型電源等の制御技術、ビッグデータ解析など、新たな付加価値を生み出すビジネスを実現する上で重要となる技術に投資が集まっています。
2.各国の状況について
(1)欧州全体の動きについて
欧州では、電力・ガス市場の自由化前は、国営や独占企業による電気・ガス事業の運営が一般的でしたが、1990年頃にイギリスを皮切りとして自由化が始まりました。また、同時期に欧州委員会は「欧州単一市場」創出を目的とした電力・ガス分野の自由化を狙い、エネルギーパッケージを3度にわたり発しています(1996年「第1次エネルギーパッケージ」、2003年「第2次エネルギーパッケージ」、2009年「第3次エネルギーパッケージ」)。当パッケージ内では、発電やガス生産分野での競争導入、2007年7月までの小売全面自由化への移行、独占的な垂直事業の分離等が規定され、各国はこの指令に基づいて国内制度を整備しました。
【第131-2-1】EUにおける再エネの導入量
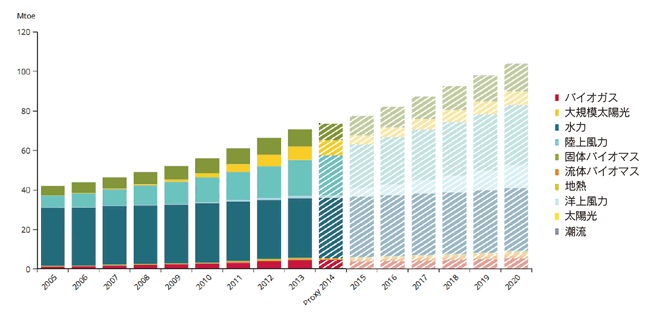
- 出典:
- European Commission
また、再エネ導入についても、2009年、欧州委員会では、EU圏のエネルギー消費量に占める再エネの割合を、2020年に20%以上とする目標を制定しました。これに加えて2014年には、再エネの割合を2030年に27%以上とする目標を制定しており、この目標達成に向けて加盟各国が政策を推進することとしています。この欧州指令を背景に、EU各国においてFIT等の導入促進施策が取り入れられ、EU28か国内での再エネ導入量は、2004年から2015年までの約10年間で2倍に増加しています。
このように、FIT等の導入促進施策により再エネの拡大が進む一方で、電気料金に占める再エネの賦課金の割合が増大し、各国においてその国民負担が課題となっています。そのため、2014年4月に欧州委員会はガイドラインを制定し、2017年以降は、再エネの支援策が原則として競争入札に基づき決定されることとするなど、各国における再エネ導入支援策についても、EUのルールと整合的なものとなることが求められることになりました。また、2016年11月には、新設される再エネ容量の優先給電について、一部見直す方針が出されています。
こうした欧州での環境変化に対して各国のエネルギー企業は柔軟に企業行動を変容させ、順応してきました。次のセクションでは、こうした動きの経緯について、各国ごとに、より詳細に見ていきます。
【第131-2-2】各国の家庭用電気料金
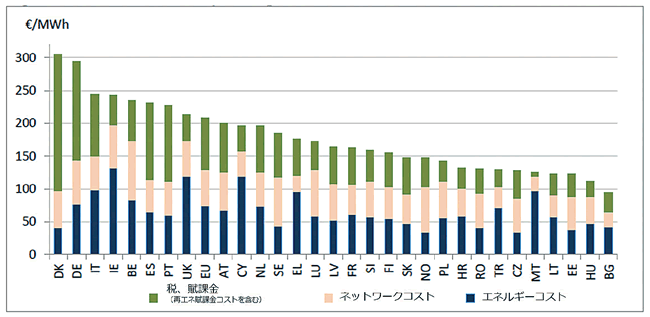
※DK:デンマーク、DE:ドイツ、IT:イタリア、IE:アイルランド、BE:ベルギー、ES:スペイン、PT:ポルトガル、UK:イギリス、EU:EU28か国平均、AT:オーストリア、CY:キプロス、NL:オランダ、SE:スウェーデン、EL:ギリシャ、LU:ルクセンブルク、LV:ラトビア、FR:フランス、SI:スロベニア、FI:フィンランド、SK:スロバキア、NO:ノルウェー、PL:ポーランド、HR:クロアチア、RO:ルーマニア、TR:トルコ、CZ:チェコ、MT:マルタ、LT:リトアニア、EE:エストニア、HU:ハンガリー、BG:ブルガリア
- 出典:
- European Commission
(2)欧州エネルギー企業について
欧州では自由化の進展による企業の再編が起こったのち、制度面で再エネ導入の推進がはかられ、再エネに大きく舵をきるイタリアのENELやスペインのIberdrola、また、火力発電の相対的な競争力喪失により足下の業績が落ち込み、火力などの従来事業や再エネ事業を分社化により切り分けたドイツのE.ON、RWEのような企業が存在しています。
総じて言えば、欧州のエネルギー企業は、再エネ導入等による電力卸価格の低下等を背景に、安定した収益を上げることが難しい事業(上流開発・火力)について非注力化・撤退を図る傾向が見られるとともに、規制や制度的支援の残る事業である再エネ、送配電、小売等に対して注力している傾向が見られます。
ここからは、それぞれの国ごとに制度変化等に触れつつ、欧米エネルギー企業の具体的な対応について見ていきます。
- 出典:
- 第1回「電力・ガス分野から考えるグローバルエネルギーサービス研究会」Arthur D Little 資料を一部改編
【第131-2-4】電力・ガス企業の時価総額の推移
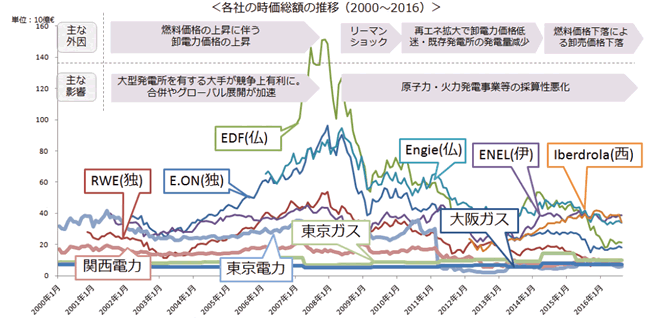
- 出典:
- 各社Annual Reportを基に資源エネルギー庁作成
①イギリス
【第131-2-5】イギリスにおける電気・ガス事業者の変遷
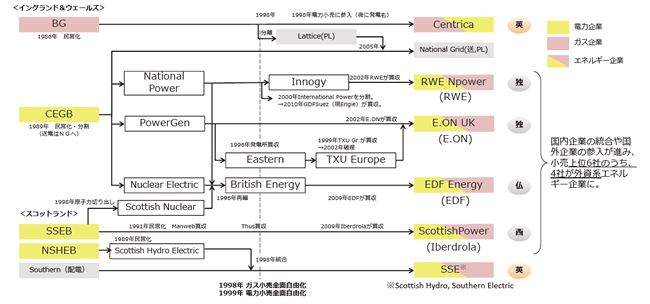
※代表的な企業を抜粋しており、電気・ガス事業者を網羅するものではない。
- 出典:
- 日本エネルギー経済研究所資料等を基に資源エネルギー庁作成
【第131-2-6】イギリスにおける電力・ガスの販売量シェア(2015年実績)
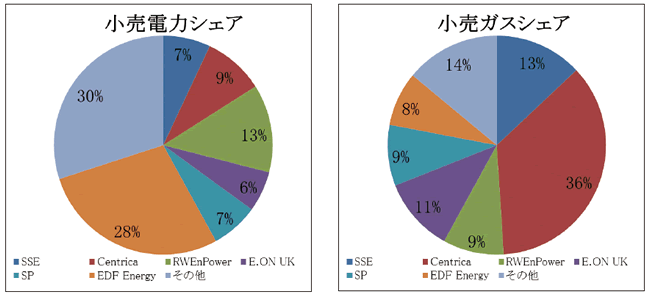
- 出典:
- ofgemを基に資源エネルギー庁作成
イギリスは、欧州委員会が発した1996年の第1次エネルギーパッケージに先行して、1990年から段階的に自由化がはじまり1999年には全面自由化し、現在でも年間平均スイッチング率が20%と最も競争が激しい市場といわれています。
中央発電公社であったCentral Electricity Generating Board(CEGB) が民営化され、Nationl Power、PowerGen、Nuclear Electricの3つの発電会社と、送電会社であるNational Gridに分割されました。
ガスについてはBritish Gas(BG)による輸送・配給・小売まで含めた垂直一貫による国営体制でした。自由化後、小売事業はCentricaが、ネットワーク(輸送)事業はBGGroupへ分割され、ガス配給網は、8つの地域に分けられました。
その後、欧州の他国の企業がイギリスの企業を買収することで、イギリス市場への参入をはかり、現在ではCentrica(イギリス)、RWE nPower(ドイツ)、E.ON UK(ドイツ)、EDF Energy(フランス)、Scottish Power(スペイン)、Scottish Hydro,Southern Electric(SSE)(イギリス)の「Big6」といわれる小売事業者による寡占状態となりました。また、イギリスの特徴として、「Big6」のうち、4社が外資系企業であるという点が挙げられます。近年でも、エネルギーの安定供給や環境への適合のため、外資系企業の資本力や技術力を有効に利用しています。イギリス国内では、2020年代に多くの既設発電所が廃止される予定であることに加え、温室効果ガス削減等の観点から、現在6サイトで原子力発電の新設計画が進捗しています。計画が進展しているヒンクリーポイントCでは、2016年9月にイギリス政府、EDF、中国広核集団公司(CGN)の3者が最終合意文書を調印しました。
特に、積極的に事業ポートフォリオの多様化を図っているCentricaと、イギリスの送電・輸送部門の運営を独占しているNational Gridについて、説明します。
(ア) Centrica
- 出典:
- 日本エネルギー経済研究所資料を基に資源エネルギー庁作成
Centricaの事業は、大きく5つに区分され、British Gas(イギリス内の下流ビジネス)、Direct Energy(北米での上流・下流ビジネス)、Bord Gais Energy(アイルランド国内での下流ビジネス)、Centrica Energy(上流事業中心で探鉱・開発等実施)、Centrica Strage(イギリスでのガス貯蔵所オペレーション)となっています。
Centricaは、ガス国営企業のBGを出自とし、1998年には輸送部門をLattice(後に、National Gridと統合)とし分割しています。2000年にはDirect Energy(アメリカ)を、2001年にはLuminus(ベルギー)を、2004年にはATCO(カナダ)を買収し、それ以降も積極的に国外展開を実施しており、特に北米を中心に展開している子会社のDirect Energyの2015年の売上は約106億ポンドと、Centricaの全売上のうち約4割を占めています。
ネットワーク部門を所有していないエネルギー企業のため、前述した国外展開のみならず、エネルギー事業、家庭への暖房・ガス機器の設置、上下水道の配管、通信、セキュリティなどの多様な分野への進出を実施し、収益を確保していると言われています。近年では、ConnectedHomeを合言葉に、イギリス、アメリカにおいて、人の生活と住宅・家電等をデジタルでつなぐサービスを展開すべく、累積5億ポンドの投資を計画しています。
- 出典:
- Centrica Annual Report and Accounts 2015を基に資源エネルギー庁作成
また、欧州一般に言われているように、Centricaも再エネ電源の優先給電等の影響を受け、風力発電の利益は2014年から2015年の2年間で約2倍に増加しましたが、ガス火力発電所の発電量は10TWhから6.3TWhと4割抑制され、発電単価に占める固定費用が相対的に高まり、発電単価は9ユーロ/MWhから12.4ユーロ/MWhと3割上昇し、火力電源の赤字は継続しています。こういった事業環境の変化を受け、2017年2月に、再エネにかかわらず、イノベーションやテクノロジーを、企業を越えて発掘するという理念の下、Centrica Innovation(CI)を設立しました。CIの目標は①鍵となる技術の集積地での人材獲得(シアトル、ヒューストン、ロンドン、ケンブリッジ、テル・アヴィヴ)、②ベンチャー企業への投資を通じて更なる投資を呼ぶ、③社内外のイノベーションを育て、成長させる、④Centrica全体にイノベーション文化を根付かせる、としており、今後の活動が着目されています。
(イ)National Grid
National Gridは1989年のCEGB民営化により誕生したネットワーク部門専業の事業者で、イギリス内の運用を一手に引き受けており、自国事業の安定的収益をベースとし、事業拡大のために国外展開を志向してきました。例えば、2000年、ニューイングランドで2番目の電力会社で130万人の顧客を持つNew England Electric Systemを、ボストンを中心に30万人に送配電サービスを手がけるEastern UtilitiesAssociatesを取得しています。さらに2002年には、ニューヨークを中心に展開し全米で9番目の送電会社のNiagara Mohawkを取得しました。その結果、現在では、保有資産の割合の35%がアメリカと、国外比率が高い企業となっています。
National Gridが、イギリス国内で安定的なキャッシュフローを実現しているにもかかわらず、積極的に国外展開を行う背景として、株主への高い配当等を確保しようという企業の方針があると言われています。その為、National Gridは既存事業領域の安定収益のみに安住せず、積極的に事業ポートフォリオの組み替えを行っています。例えば、2016年8月にNational Gridの子会社であるナショナル・グリッド・トランスコ(NGT)は、(2015年収入が10億5,200万ポンドであった)イギリス内のガス供給網の半分を総額58億ポンドで売却しました。(イギリス北部の供給網は、中国のインフラ事業会社である長江基建(チョンコン・インフラストラクチャー)を中心とする企業連合が14億ポンドで、ウェールズとイギリス西部はオーストラリアマクウォーリー銀行グループ系の企業連合が12億ポンドで、イギリス南部とスコットランドはスコティッシュ・アンド・サザン・エナジーなどで構成する企業連合が32億ポンドで買収)
一方で、大型の投資案件も計画・実行しています。2015年実績で、イギリスの電気送電網に約11億ポンド、ガス輸送網に約2億ポンド、ガス配給網に約5億ポンド、アメリカの規制部門に約19億ポンド投資しており、さらに株主価値を高めるため、今後5年間で、7~9億ポンド/年の設備投資を予定しています。直近では、オーストラリアのビクトリア州とタスマニアを結ぶ60万kW連系線プロジェクトへの参入も表明しています。
また、イギリスとフランスの海峡に全長約240kmに及ぶ海底送電線を敷設する国家間プロジェクト(2021年運転予定)にも参画しており、国内のエネルギーセキュリティを高める事業も積極的に展開しています。
- 出典:
- 日本エネルギー経済研究所資料を基に資源エネルギー庁作成
【第131-2-10】National Gridの保有資産
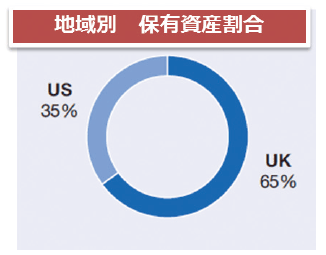
- 出典:
- 日本エネルギー経済研究所資料
- 出典:
- 日本エネルギー経済研究所資料
②フランス
フランスでは、1946年の「電気・ガス事業国有化法」によって国内の電気・ガス事業の国有化が行われ、電気事業についてはEDF、ガス事業についてはGDFという国営企業が、各事業を垂直一貫で担う体制となりました。長らく続いた国営企業の独占体制でしたが、1996年の欧州委員会の「第1次エネルギーパッケージ」を受けて、自由化に舵を切ることとなり、1999年には電力の小売自由化が、2000年にはガスの小売自由化が開始され、2004年には「EDF・GDF株式会社法」によってEDFとGDFの株式公開が行われ、2007年には電力・ガスの小売全面自由化が完了しました。
自由化の過程において、送電部門・輸送部門と配電部門・配給部門の法的分離も行われましたが、電気事業についてはEDFの子会社であるRTEが送電部門、Enedisが配電部門を支配しており、ガス事業についてはEngie(旧GDF Suez)の子会社であるGRT Gazが輸送部門、GRDFが配給部門を支配しており、電気・ガス事業の自由化以降も、元国営企業の支配的な構造は変化していません。EDFとEngieは各々の事業に加えて電気・ガス事業に相互に参入することで、両者がフランスにおける2大エネルギー企業となっています。
【第131-2-12】フランスにおける電気・ガス事業者の変遷
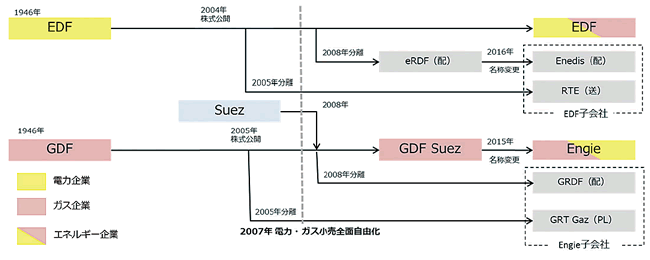
※代表的な企業を抜粋しており、電気・ガス事業者を網羅するものではない。
- 出典:
- 日本エネルギー経済研究所資料等を基に資源エネルギー庁作成
(ア) EDF
EDFは元フランス国営の電気事業者であり、2015年末時点においても政府が約85%の株式を所有しています。EDFは世界の原子力発電設備の約18%を所有する世界最大の原子力発電事業者であり、発電電力量の78%を原子力発電による電力が占めています。この背景として、第一次石油危機以降、輸入石油への依存を軽減させることを目的として、政府が原子力の開発に傾注してきたことが挙げられます。
EDFの戦略は、盤石なフランス国内事業を後ろ盾に、事業の多角化と、原子力発電輸出を含む国外進出を行うことにあります。1990年代には欧州域内のみならず、南米、中国などへの広域的な事業展開を開始しました。2000年代後半には全方位展開の戦略に批判を受け、南米、アジアの一部事業を残しながらも、電気・ガス事業の自由化や市場の統一が進みつつある欧州への事業の集中を行いました。それと同時に、イタリアのガス事業者であるEdison社の買収や、イタリアENELのガスパイプライン事業への参画など、ガス事業の強化も行いました。2009年にはイギリスのBritish Energyを買収することによりイギリスに本格参入し、現在ではイギリスの6大エネルギー企業である「Big6」の一つとなっています。欧州域内で電気・ガス事業を強化する一方で、同時期に原子力発電についても国外事業展開を行いました。中国では、台山核電合有限公司という合弁会社を設立して原子力発電所の新設計画を進め、アメリカではCENG(Constellation Energy Nuclear Group)という合弁会社を設立して米国の原子力発電所の運営を行いました(2013年に撤退を決定し、2016~2022年の間に当該合弁会社の株式の売却を予定。)。
2015年に発表した「CAP2030」という経営戦略の中で、低炭素成長のチャンピオンになることを宣言しており、従来から積極的に展開してきた原子力発電に加えて、再エネにも注力するとともに、2030年までに国外事業を2015年の3倍に増やす方針を打ち出しています。
原子力発電についてはフランス国内で1基、中国で2基、イギリスで2基の新設計画を進めています。2015年に成立した「エネルギー移行法」において、国内の原子力発電比率を約75%から2025年に50%とすることが規定されましたが、電力需要全体を底上げすることで相対的に原発比率を減らす方針であり、EDFは国内原子力発電所の運転期間延長や国外展開を通じて、今後も原子力発電事業を推し進めていく考えです。
- 出典:
- 日本エネルギー経済研究所資料を基に資源エネルギー庁作成
- 出典:
- 日本エネルギー経済研究所資料
再エネについては、設備容量を2014年の28GWから2030年には50GWにすることを目標としています。近年は欧州域外において再エネ関連の展開を活発化しており、2014年にはブラジルにEDF EN do Brazilを、2015年にはチリにEDF EN chileを立ち上げ、水力・太陽光・風力などを積極的に推進しています。
国外事業の観点では、既に25か国に事業を展開しています。2014年にはハンガリーのガス子会社やオーストリアのエネルギー子会社を売却した一方で、前述の通り南米をはじめとした需要が見込める地域に再エネ投資を行うなど、ポートフォリオを変更しながら、国内の支配的地位に安住することなく、国外展開を積極的に行っています。
(イ) Engie
フランス国営のガス事業者であったGDFは、2008年に国際的に電力、ガス、水道事業を展開していたエネルギー企業であるSuezと合併してGDF Suezとなり、2015年に名称変更が行われEngieとなりました。2015年末時点においても政府がEngieの株式の約33%を所有しています。出自であるガス事業のみならず、電気事業も行うエネルギー企業であり、2010年以降は特に再エネを中心とした国外展開に注力しており、2016年現在、70か国以上に進出しています。
EngieもEDF同様に、支配的な国内事業を基盤として国外への展開を行ってきました。大きな転機となった出来事の一つが、2008年に行われたSuezとの合併でした。イタリアの電気事業者であるENELによるSuezの敵対的買収に対し、フランス政府が対抗策として行った合併とされていますが、これにより、GDFはSuezが支配的に行っていたベルギーの電気・ガス事業を獲得することとなりました。また、2011年には、欧州外の新興国において勢力を拡大していたイギリスの独立系発電事業者であるInternational Powerを買収することによって、所有設備容量を倍増させるとともに、中東・アジア・オーストラリア・北米市場への参入の足がかりとしました。
このように、ガス事業のみならず電気事業にも力を入れてきたEngieですが、特に2016年以降はエネルギー事業環境の変化に対応するグローバルリーダーとなることを戦略として掲げています。Engieは、エネルギー産業の潮流として、電源の分散化、低炭素化、デジタル化、効率化という4つを挙げ、これに対応するため、変革の象徴として社名をGDF SuezからEngieに変更するとともに、2016年には大規模な事業再編を行いました。この事業再編において、従来の欧州エネルギー、国際エネルギーなどの大きな事業分野を細分化し、24のビジネスユニットを設けることで顧客密着のサービスを提供する体制を整えました。中でも欧州域外に10の地域ユニットを設けており、アフリカ、北米、アジア太平洋、ラテンアメリカなどそれぞれの事業地域に密着した体制となっています。
- 出典:
- 日本エネルギー経済研究所資料を基に資源エネルギー庁作成
- 出典:
- Annual Reportを基に資源エネルギー庁作成
また、事業転換の数値目標については、①2018年までに低炭素な事業(ここでは、ガス火力、再エネ、原子力等の低炭素電源による発電及びガス事業等を指す。)によるEBITDA(営業利益と減価償却費の和。国によって異なる税率、減価償却費等の影響を抑え、国際的な企業の収益力比較に用いられる指標。)の割合を80%以上とすること、②顧客ソリューション事業のEBITDAを2018年までに50%増加させること、③コモディティ価格変動の影響を受けない規制事業等のEBITDAを2018年までに85%以上とすること、の3つを掲げています。特に、低炭素化を進める動きとして、石炭火力からの撤退を進めており、欧州のみならず米国やインドでも石炭火力からの撤退を発表しています。その一方で2016年にはフランスの風力発電事業者であるMAIA EOLISを買収し、設備容量においてフランス最大の風力発電事業者となっています。このように、ガス事業者としての出自を活かしたガス火力発電は残しつつ、再エネに積極的に投資することで、低炭素化を進めています。
Engieの特徴として、デジタル化をはじめとするイノベーション関連への積極的な投資も挙げられます。多くの欧州エネルギー企業がベンチャーキャピタル等を通してデジタル技術等のベンチャー企業への投資を行っていますが、Engieはグループで所有するベンチャーキャピタルファンドであるEngie New Venturesにおいて、約138億円の投資枠を設けています。EDFが同様にベンチャー出資に充てている約36億円と比較すると、Engieがイノベーションを重要視する姿勢が見てとれます。
③ドイツ
ドイツの電気・ガス事業は、従来、市場を地理的に分け合い、それぞれの地域で独占的な企業が電力・ガス産業を担っていました。自由化前は、「Big8」と呼ばれる地域独占の8社が、電気事業において支配的役割を果たしていました。1996年の欧州委員会の「第1次エネルギーパッケージ」を受けて、1998年に電力・ガスの小売全面自由化が行われると、電力・ガスの相互参入と統合が進み、2000年代後半には「Big4」と呼ばれる4大エネルギー企業(E.ON、RWE、Vattenfall、EnBW)に集約されました。
自由化後におけるドイツの電気事業の特徴として、欧米諸国と比べて電気料金が高く、特に託送料金が高かったことが挙げられます。当時、「Big4」はネットワーク部門を有する垂直一貫体制を取っており、独占性の強い送電事業の利益を原資として、発電・小売分野において競争排他的な価格設定(不当廉売)を行うことで、新規参入者を締め出す動きがあったと、連邦カルテル庁は指摘しています。このような不当に高い託送料金の設定を防ぐため、2005年には独立規制機関である「連邦規制ネットワーク庁(BNetzA)」を設置して託送料金を同庁の規制下に置き、2009年からは効率化のインセンティブを働かせるために送配電料金に対するレベニューキャップ規制を設けました。2010年以降には、公平な競争環境を醸成するためにネットワーク部門の分離を求める欧州委員会の圧力等を理由に、ネットワーク部門を分離する動きが加速しました。その結果、送電部門においてはEnBWを除いて所有権分離を行っています。
ドイツ国内で支配的な地位を確立した「Big4」ですが、総じて火力発電の比率が高く、近年はドイツ国内の電気事業の環境変化によって戦略の変更を迫られています。ドイツ政府はエネルギー転換政策(Energiewende)を掲げており、2022年までの原子力発電所の全廃を決定すると同時に、2050年までの温室効果ガス排出量、電力消費量の削減目標や再エネ比率の目標などの長期戦略を定めています。2016年からは、褐炭火力発電所の発電シェアを下げるための容量リザーブ制度(Capacity Reserve)が開始され、褐炭火力発電所は一定期間予備力として待機したのち、順次閉鎖されることとなりました(実際の入札は2018/19年分より開始予定)。また、FITを通じて、限界費用が低く、優先給電ルールの下では抑制されにくい再エネの導入が拡大したことにより、火力電源の設備利用率が低下し、火力発電設備を多く持つ企業の収益低下につながっています。こうした国内の環境変化を受けて、E.ON、RWE、Vattenfallは大きな戦略の変更を行いました。以下ではこれら3社の戦略についてそれぞれ説明します。
【第131-2-17】ドイツにおける電気・ガス事業者の変遷
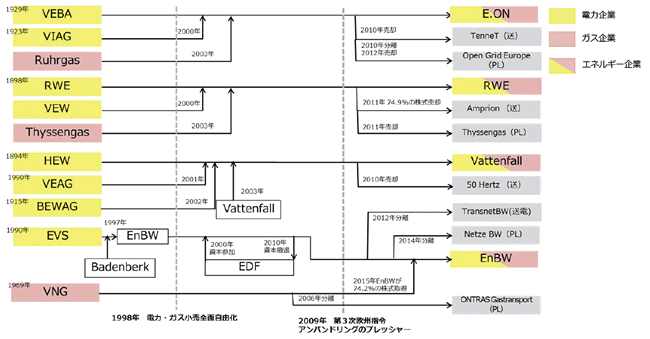
※代表的な企業を抜粋しており、電気・ガス事業者を網羅するものではない。
- 出典:
- 日本エネルギー経済研究所資料等を基に資源エネルギー庁作成
- 出典:
- BMWi情報を基に資源エネルギー庁作成
【第131-2-19】ドイツにおける再エネの導入量推移
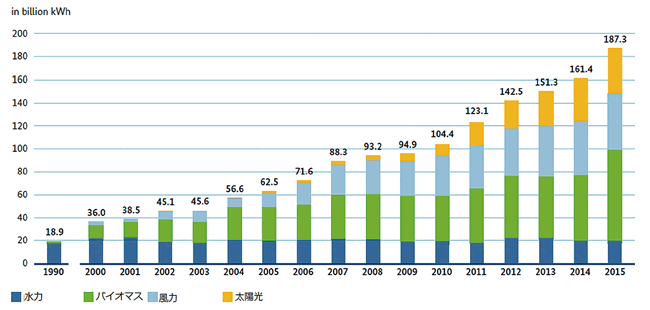
- 出典:
- BMWi
- 出典:
- 日本エネルギー経済研究所資料を基に資源エネルギー庁作成
(ア) RWE
RWEは石炭が豊富なルール地方の発電・小売事業者として設立されました。地方自治体と強い結びつきを持ち、この地方の石炭資源を基盤に発展してきたため、現在も石炭火力発電の比率が高いことが特徴です。1988年にTexaco(ガス事業者)、1996年にThyssengas(ガス事業者)を買収し、ガス事業にも本格的に参入しました。1997年には通信事業、2000年代には水道事業にも事業領域を広げ、いわゆるマルチユーティリティ企業を指向しましたが、シナジー効果は現れず撤退し、エネルギー事業に集中する方針に回帰しています。事業展開は欧州を中心に行っており、2002年にInnogyを買収して参入したイギリスにおいては「Big6」の一つとなっています。2010年以降、再エネ事業に注力する方針を打ち出しながらも、従来型の発電事業の不振による資金的な制約により、新規の投資が難しい状況が続きました。こうした状況を打開するため、2016年には再エネやネットワーク部門などの、現在の事業環境下において収益性が高い、あるいは成長が見込める分野を分離し、Innogyという名称で子会社化しました。これにより、Innogyに対して市場からの投資を集め、積極的に再エネ事業等を進めて行くことで、従来型事業である火力発電や原子力発電を引き続き担うRWE本体にも利益を還元することを目指しています。なお、従来型電源についても、再エネの導入における調整力として、その拡大を補助する重要な役割をもつ存在として位置付け、柔軟に活用していく方針です。
(イ)E.ON
E.ONは2000年にドイツのコングロマリットであるVEBAとVIAGを前身として設立されたため、設立当初はエネルギー以外にも通信や化学事業など附帯的な業務を行っていました。2000年代には、エネルギー事業以外の分野を売却することによって得た資金を用いて、欧州において積極的なM&Aを行い規模を拡大しました。例えば2001年にはPowergen(イギリス)の買収によりイギリスや北米市場へ進出し、同年Sydkraft(スウェーデン)を買収して北欧に進出しました。2003年にはドイツのガス部門の支配的事業者であったRuhrgasを買収したことによりガス事業にも本格参入し、E.ONは巨大エネルギー企業となりました。2016年時点において、ガス事業の売上高と電気事業の売上高は同程度となっています。
自由化後、2010年頃まではM&Aを活発に行っていましたが、E.ONはガス火力発電の比率が高いため、再エネの拡大に伴って収益が低下し、2011年の赤字を受けて資産の入れ替えを加速しています。2014年にはRWE同様に、従来型事業と再エネやネットワーク事業などの収益性の高い事業の分割を発表し、2016年に子会社のUniperを設立しました。事業分割の構図はRWEとは反対に、E.ON本体に再エネやネットワーク部門を残し、従来型事業の火力発電や原子力発電を子会社のUniperに分割する形としています。この分割に関する経営戦略として、E.ONは2つのエネルギー世界への対応を掲げています。一方を「顧客が中心となる世界」と定義し、需要家の電源に対しての興味を踏まえ、持続可能性や電源の分散化、再エネなどに重点を置き、E.ON本体が対応する分野です。そして、もう一方を「設備を中心とした世界」と定義し、欧州市場が統一され、再エネが拡大していく中で、従来型電源が供給信頼性の確保に必要であると位置付け、Uniperが対応する分野です。
- 出典:
- 日本エネルギー経済研究所資料を基に資源エネルギー庁作成
- 出典:
- 各社HP等を基に資源エネルギー庁作成
(ウ)Vattenfall
Vattenfallはスウェーデンの国営電力会社であり、ドイツの3つの電気事業者との資本提携と買収をすることによってドイツに進出しました。ドイツ以外にはイギリス、デンマーク、スウェーデン、オランダを中心に事業展開しており、欧州域外での事業は行っていません。RWE、E.ONと同様に電源構成に占める火力発電の割合が高いVattenfallも、現在のドイツにおける再エネの導入拡大によって収益が悪化しており、事業の転換を図っています。
2016年には「持続可能性」をキーコンセプトとした新たな経営戦略を発表し、その中で、石炭・褐炭火力発電を非戦略的事業として位置付け、これらの発電所を閉鎖するかバイオマス発電で置き換えるという方向性を示しています。この方針を裏付けるように、同年中に、ドイツの褐炭発電事業と採掘事業の売却を行いました。Vattenfallは、褐炭・石炭発電からの脱却を図る一方で、風力発電を中心とした再エネへの注力も戦略の柱としています。同年6月には、デンマーク最大の洋上風力発電施設の建設に着手したことも発表しました。2020年までに合計で4GWの風力発電設備を導入することを目標としています。
このような、FIT等を通じた再エネの急激な拡大と、それに伴う従来型電源の収益性の低下は、ドイツのみならず欧州域内における事業環境変化の潮流となっており、その対応によってエネルギー企業の足下の経営を左右するという状況が生じています。
- 出典:
- Vattenfall HPを基に資源エネルギー庁作成
【第131-2-24】Vattenfallの電源構成(発電電力量)と褐炭火力発電売却による変化
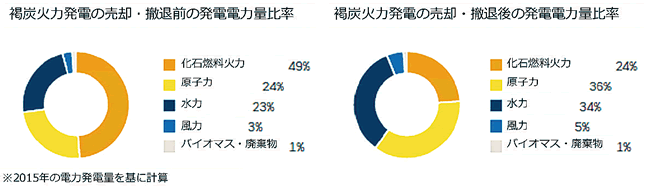
- 出典:
- Vattenfall HP
C O L U M N
ドイツにおける地域事業者(シュタットベルケ)について
ドイツにおいては、「シュタットベルケ」と呼ばれる電力・ガスを含む地域事業者が重要な位置を占めています。シュタットベルケとは、19世紀後半以降、水道、交通、ガス供給、電気事業(発電・配電・小売)など、ドイツ国内のインフラ整備・運営を行うために発達してきた、自治体出資による事業者です。※シュタットベルケの数は、ドイツ全体で約1,400に上り、電気事業を手がけるシュタットベルケは900を超える。
2000年前後のドイツの電力・ガス自由化後も、大手電力・ガスが再編する中、地域密着のサービス提供と一定以上のコスト力により、大手に負けない競争力を維持し、地域顧客を獲得してきました。
- 出典:
- 総合資源エネルギー調査会 電気・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会(第1回)資料
④スペイン
○Iberdrola
Iberdrolaは1992年にIberdueroとHidroeléctrica Española(ともに電気事業者)の合併によって設立されました。1990年代には、言語のつながりを活かしてブラジルやメキシコへの国外展開を開始し、2000年代になると、国内事業の不振により国外を事業の中心とする方針転換を行い、一層の国外展開を進めてきました。国内事業が不振となった理由として、スペイン国内で規制料金と自由料金を需要家が選択できる仕組みとなっており、政府が規制料金の大幅な値上げを認めないため、エネルギー企業が採算の取れる金額での小売り販売が出来なかったことが挙げられます。
また、再エネをめぐる動きに対しても、機動的に対応している姿が見られます。スペインでは、1997年に改正された「電気事業法」に基づき1998年には固定価格買取価格の算出方法を規定するとともに、1999年には「再エネ促進計画」によって2010年までの風力発電設備の導入目標を閣議決定するなど、国内において再エネ導入の機運が高まっていました。また、スペインのみならず再エネの導入支援策は多くの国で導入が始まっており、例えばアメリカにおいても、1990年代に連邦政府による税控除や、州ごとのRPS制度(Renewable Portfolio Standard:電力会社に一定割合の再生可能エネルギーの活用を義務づける制度)の導入が進むなど、国外においても再エネ発電による事業を行うインセンティブが高まりを見せました。
こうした事業環境を背景に、2001年には先述の国外展開戦略とともに、再エネ需要の高まりに対応していく方針を打ち出しました。国内でも風力発電所をはじめとした再エネの導入を進め、2005年には当時スペイン最大の風力発電所を開設しました。2007年にはイギリスの大手電気事業者であるScottish Powerを、2008年にはアメリカのEnergy Eastを買収することで、本格的に米国、イギリスへの進出を行いました。リーマン・ショック以降は、引き続き再エネ投資を拡大するとともに、安定的に投資回収が見込める送配電の規制事業への注力も掲げ、2011年にはブラジルの配電会社であるElektroを買収しています。
スペイン本国では、2007年にFITの太陽光発電の買取価格を2倍に引き上げた結果、太陽光発電の導入量が急激に拡大し、それに伴って賦課金が急増したため、2012年にはFITを中止し、2016年には再エネの買取コストを抑制するため入札制度を導入しました。しかし、国外での積極的な事業展開の結果、2015年において、Iberdrolaの所有する設備容量は、約14.8GWであり、再エネの割合は32%と、欧州主要エネルギー企業の中で最も高くなっています。2016年から2020年までの事業計画によると、88%は規制市場に投資する予定です。再エネには95億ユーロを投資する計画であり、その内訳はアメリカが40%、イギリスが45%です。また、2015年から2020年に向けて再エネやCCGT(Combined Cycle Gas Turbine)を6,900万kW増やす予定である一方で、石炭火力発電は、保有する電力容量全体に対して1%ほどを残して縮小していく予定としています。
このように、IberdrolaはE.ON、Engie、EDFなどの欧州大手事業者と比して規模の小さい事業者ですが、その小ささを活かして機動的に事業環境の変化に合わせた方針転換を行うことにより、安定した成長を実現しています。
- 出典:
- 日本エネルギー経済研究所資料を基に資源エネルギー庁作成
【第131-2-27】スペインの賦課金総額の推移
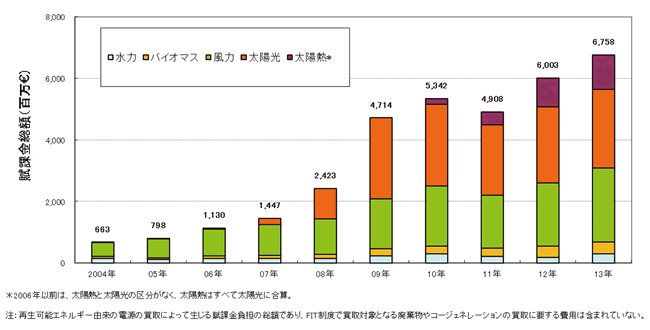
- 出典:
- 国家市場・競争委員会資料を基に資源エネルギー庁作成
- 出典:
- 日本エネルギー経済研究所資料
⑤イタリア
○ENEL
ENELは1962年にイタリアの電気事業者のほぼ全てを統合する形で、国営企業として設立されました。その後、1999年にベルサーニ政令により民営化されましたが、2016年3月末時点においても、政府は約24%の株式を所有しています。また、同政令で、同社の市場シェアにおける上限(2003年に50%)が設けられることとなりました。国内電気事業におけるシェア上限を設けられたENELは、2000年代初頭にはマルチユーティリティ戦略による多角化を行いました。水道、通信、不動産事業に参入という戦略は、本来事業であるエネルギー事業とのシナジーが現れず、2000年代半ばには各事業からの撤退、エネルギー事業への回帰と集中が行われることとなりました。エネルギー以外の事業への多角化に失敗したENELは、その後、国外市場に成長を求め、2006年にブルガリア、スロバキア、ルーマニアの電力会社を買収し、2007年にはスペインの大手電気事業者であるEndesaを買収しました。
Endesaの買収以降、主力事業地域はイタリア国内とスペインをはじめとするイベリア半島となりましたが、2008年に開始されたイタリアでのロビンフッド課税(エネルギー事業者に対して法人税率を上乗せするもの。2008年に5.5%、2010年に6.5%、2011年から2013年に10.5%の上乗せに変更。)や、スペインでの規制料金の報酬削減といった主要地域での事業環境の変化を踏まえて、2010年頃からは、特に中南米を中心とした国外への再エネ進出を活発に行っています。
- 出典:
- 日本エネルギー経済研究所資料を基に資源エネルギー庁作成
- 出典:
- 日本エネルギー経済研究所資料
- 出典:
- Annual Reportを基に資源エネルギー庁作成
こうした方針は投資額に顕著に現れており、投資の対象としては再エネの金額が大きく伸びており、国内外別で見れば国内向けが大きく縮小し、国外が増加しています。2016年に発表された、2017年から2019年に向けた事業戦略においては、総投資額の209億ユーロのうち60%を成長事業投資に充てることとし、このうち、90%は再エネやネットワーク事業といった低リスク事業に充てることとしています。このように、現在の事業の中心地域での収益悪化を背景に、欧州域外への進出や低リスク事業への集中により成長の機会を求める動きを見せています。
(3)アメリカにおけるエネルギー企業について
アメリカでは1990年代から電力・ガスの自由化が始まりました。しかし、州際取引を中心とした発送電・生産輸送部門に対する権限が連邦エネルギー規制委員会(Federal Energy Regulatory Commission:FERC)にあり、小売を中心とした事業規制が州ごとの公益事業委員会(Public Utilities Commission:PUC)にあるため、連邦と州がそれぞれが規制権限を持つという構造となっています。そのため、欧州と異なり、FERCが発送電・ガス輸送部門改革を進め、PUCが小売自由化を行うという、複雑な構造の下、自由化が進展しました。
その後、2000年代のカリフォルニア州の電力危機などを契機に、自由化の流れが中断され、電力小売全面自由化を検討していた州は24州ありましたが(2州は小売自由化に関する州法を成立させたものの、実施に至らず法律自体を廃止。もう2州は小売自由化の実施を無期限延期)、現在13州+ワシントンD.C.が小売全面自由化を実施しているに留まっています(2016年1月時点)。アメリカにおけるエネルギー企業は、電気事業者だけでも登録ベースで3,300社を越えていますが、大手の事業者であるExelon、NextEra Energyなどのように自由化州、規制州の双方にまたがって事業を行っている事業者では、規制州と自由化州を別な事業として経営を行っているところも見られます。
また、米国の電気事業者でも、自由化州での競争や、再エネなどの分散型電源の導入を促進する州での事業展開にあたり、M&A等を通じた設備容量の拡大やガス小売部門への進出などの動きも出始めています。
- 出典:
- 各種資料を基に資源エネルギー庁作成
- 出典:
- 平成28年度エネルギー環境総合戦略調査(エネルギー制度改革と我が国のエネルギー産業)より資源エネルギー庁作成
再エネの導入という面でも、州によって制度による支援の度合いに濃淡はありますが、電力危機を経験したカリフォルニアなどでは自由化の中断とあわせて、独立電源の推進も行っており、これにシリコンバレーをはじめとした企業群が呼応する形で、多くの再エネや分散型電源を進める技術、ビジネスを核とした企業が生まれています。
3. エネルギー関連技術を巡る動向とベンチャー投資等の動き
これまで見てきたように、エネルギー産業をとりまく事業環境はたえず変化しており、企業は都度、自らの事業を見直すことで成長を続けています。この企業の選択肢を増やすことができるのが「技術」であり、例えば再エネ分野でも太陽光発電、風力発電、蓄電技術の進化や、それらに伴う第三者保有などの新サービスの創出がなされています。さらに、近年では、より機動的にこういった新技術を発掘・ビジネス化する為、内製化という手段だけでなく、ベンチャー企業への投資や、M&Aによる買収といった取組を進める欧米のエネルギー企業が多く見られます。
欧米を中心としたエネルギー企業は、ベンチャーファンドを設立し、有望なエネルギー関連のベンチャー企業に中長期的に投資する仕組みを2010年代頃から実行しています。また、自由化前よりも、一層スピーディな経営判断や結果が求められていることもあり、M&Aを積極的に活用することで、技術についても短期に獲得し、成長を志向しています。
Engieは2014年にEngie New Venturesという投資ファンドを設立し、シリコンバレーを中心にAdvanced Microgrid Solutions(エネルギー貯蔵管理)、Powerdale(EVの充電インフラ)、Tendril (エネルギー需要マネジメント)、kWh Analytics (太陽光発電プロジェクトのリスクマネジメント)など、既に14のスタートアップ企業へ投資しています。
一方で、RWEはInnogy Venture Capitalというベンチャーファンドを設立し、ヨーロッパのベンチャー企業のみを支援するという方針を掲げています。RWEが投資した企業としては、mantex(バイオマス発電の高効率化)、enercast(再エネの稼働予測をするシステム構築)などが挙げられます。
また、近年のM&A事例としては、例えばEngieによるEV-Box(オランダ)の買収が挙げられます。輸送は、世界のCO2排出量の23%(EUでは30%)を占めており、2050年までに、より環境に優しく、より流動性の高い自動車への転換が不可欠と言われています。それらを解決する為にEngieは、信号システムなど交通流動性を改善するサービスを提供していました。これを強化するため2017年3月、世界26か国・4万か所に遠隔制御が可能な電気自動車スタンドを展開している、EV-Boxを買収しました。
日本でも2017年3月に東京電力が、低炭素化、分散化、デジタル化等のベンチャーへ投資するEnergy Impact Fundに出資を行いましたが、日本企業によるベンチャーキャピタル等を通じた技術の発掘・取込に向けた動きはまだ緒についたばかりといえるでしょう。
(再掲)【第131-3-1】新サービス創出(技術革新)への動き
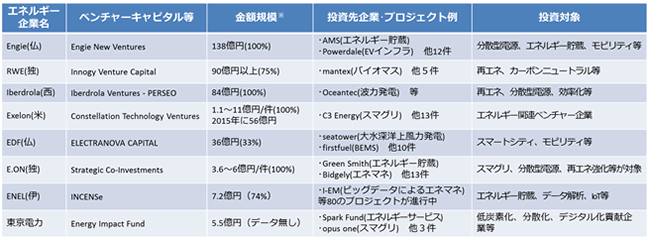
※エネルギー企業からベンチャーキャピタル等への出資額。括弧内はベンチャーキャピタル等の資金枠に占める割合を示す。
1 €=120円、1 $=110円で換算。
- 出典:
- 各社Annual Report、HP及び、報道等を基に資源エネルギー庁作成
【第131-3-2】エネルギー企業におけるM&Aの動き
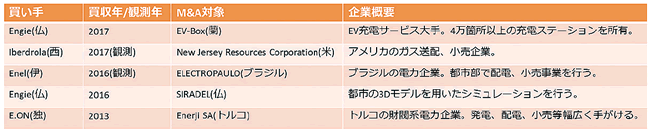
※観測は、確認できる限りにおいて当該案件が初めて公にされた場合であって、案件情報はニュース、企業のプレスリリース、あるいはその他ソースに基づく。情報源としてアナリストやブローカーの憶測も含まれる。
- 出典:
- 各社Annual Report、HP及び、報道等を基に資源エネルギー庁作成
【第131-3-3】各企業のM&A件数(2010/1~2017/3)
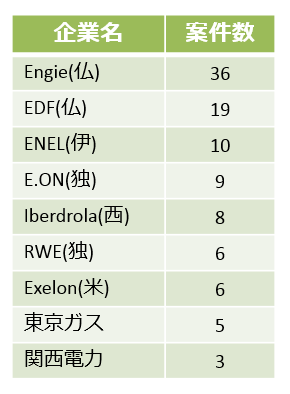
※期間:2010年1月1日~ 2017年3月1日 / 案件:上記期間に買収を公表、完了した案件、及び報道されたものを含む。ジョイントベンチャー、対等合併などは含まない。買い手がターゲットの株主資本50%以上を取得し、ターゲットの支配権を有する取引を買収と分類している。取得比率が少ない場合においても、最終保有比率が50%以上となる場合は買収として分類される。
- 出典:
- SPEEDA情報を基に資源エネルギー庁作成
C O L U M N
エネルギー産業の周辺領域まで含めた、技術革新・新サービス創出の事例
ここでは、エネルギー産業における新しい技術やビジネスモデルについて、エネルギー産業の周辺産業(たとえば太陽光パネルメーカーや風車メーカー等)も含めて、最近の動向を記載します。
太陽光発電については2009年以降のシリコン価格の低減等によるモジュール価格の低減、これと平行した導入量の拡大とFITの買取価格の引き下げや入札制度導入等により、事業者間の競争と集約化・効率化(設計・調達・建設の専業化、流通構造改革等)が進展した結果、世界では太陽光発電の導入コストの大幅削減と、これを可能とする産業の形成が実現されてきています。
【第131-3-4】太陽光発電の発電コスト・買取価格の国際比較(2016年)
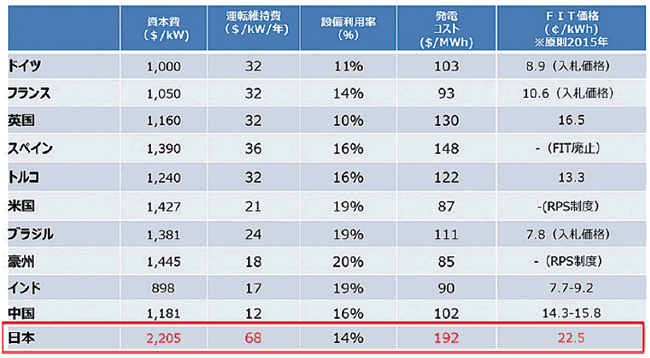
- 出典:
- Bloomberg 資料を基に資源エネルギー庁作成(FIT価格は資源エネルギー庁調べ)
また、風力発電については、世界では1980年代以降風車技術の大幅な進展と市場の拡大に伴う量産化などによるコスト低減により、発電コストが大幅に低下してきました。2000年代に技術進展の鈍化や資材の供給不足により価格は下げ止まりしましたが、2010年頃からはさらなる大型化や、製造コスト低減などにより、発電コストは再度低減傾向にあります。
【第131-3-5】世界の風力発電コストの推移
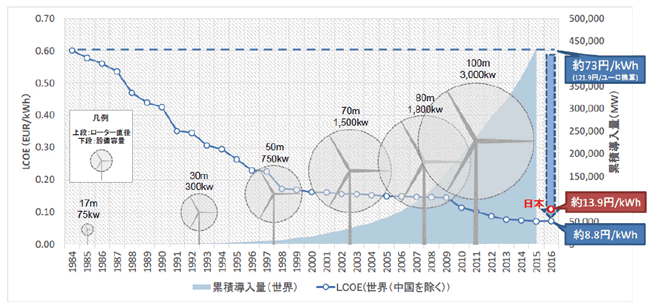
- 出典:
- The future cost of onshore wind( Bloomberg New Energy Finance, 2015)、 IEA Wind Task 26 “The Past and Future Cost of Wind Energy(IEA, 2012)を基にNEDO技術戦略研究センター作成
※LCOE:均等化発電原価。ライフタイムに要するコストの総計を現在価値に割引き、年間発電量に基づいて均等化して算出したコスト
太陽光パネルについて
First Solar(アメリカ) ~太陽光発電コストの低減~
【第131-3-6】First Solarの太陽光パネルの発電コスト(同社試算による)
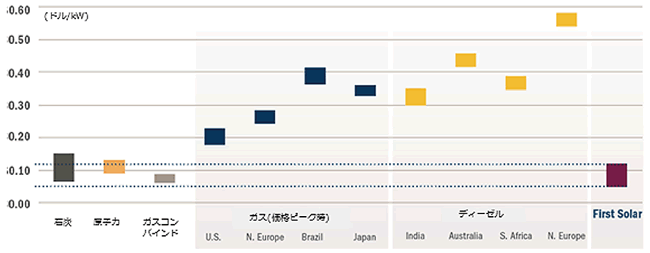
- 出典:
- First Solar Sustainability Report
First Solarは、光を吸収する力が大きいCdTe(カドミウムテルル)を用いた太陽光パネルの薄膜化により、材料を少量化することで工期の短縮と大量生産を可能にし、コスト面での強みを有しています。有害物質であるCdを使用する点、レアメタルであるTeを使用する点、シリコン製のパネル比べて変換効率が低いという点、がデメリットとして挙げられますが、中国企業にも負けないコスト競争力を有していると言われています。またパネルの製造のみならず、エンジニアリング、プロジェクト開発、発電事業など太陽光バリューチェーンの多くに関わることにより、コストの効率化とリスク分散を図っています。さらに事業機会の拡大を目指して積極的な資産買収等も行っており、例えば2007年にTurner Renewable EnergyのIPPノウハウ、2009年にOptisolarのプロジェクト開発能力、2010年にNextLight太陽光発電所施行技術、2013年にGEの太陽光発電技術を獲得し、運営管理による利益比率を高めています。
Sun Power(アメリカ) ~技術革新による発電効率の上昇~
Sun Powerの強みは、太陽光パネルの変換効率の高さにあります。太陽光パネルメーカーとしての歴史は長く、1970年代から石油危機に対処する方法を模索する中で研究が進展してきました。政府の資金援助やベンチャーキャピタル投資を受けながら、NASAへのパネル提供などを通じて実績を重ねた同社は、2016年時点においてバックコンタクト方式(受光面の電極をなくす技術)により、従来品が15%程度であった変換効率について、20%を超えるという世界最高水準を達成しています。
2007年には太陽光発電所の製造を行うPower Lightの買収により、太陽光パネルの製造のみならず発電事業も行う、太陽光の垂直一貫企業となりました。2011年にはフランスTOTAL SunPowerの株式の約60%を取得したことで、TOTALの世界的なネットワークも活用した、より積極的な国外展開を模索しています。近年では大規模太陽光発電所の開発にも注力しています。
【第131-3-7】Sun Power製の太陽光パネルの発電効率
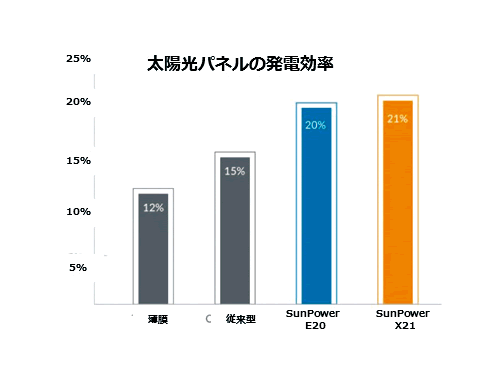
- 出典:
- Sun Power HP
Solar City(アメリカ) ~太陽光パネルの第三者保有モデル~
Solar Cityは太陽光パネルの新たなサービスの形態として、第三者保有モデルによるビジネスを展開しています。太陽光発電設備の普及には、初期費用の高さが壁となる場合も見受けられますが、同社が主体とするビジネスモデルは、太陽光発電システムを無料で家庭の屋根に設置し、太陽光発電で発電した電気を従来の電力会社の電気料金単価より低い値段で顧客に提供するというものです。このビジネスモデルが広く受け入れられ、建物の所有者名義の発電設備を抜いて、米国住宅用太陽光発電市場の72%を占めるまでに成長しています。(2014年には第三者保有の設置容量が890MWに達し、非住宅用(産業用のメガソーラー)を市場規模で上回りました。)
しかし、太陽光発電の普及によりコストが下がり、一般消費者も低い金利で銀行からローン貸し付けが可能になったことで、当ビジネスモデルの前提が崩れ、2016年には第三者保有モデルでの導入がやや鈍化しています。また、2016年にはTeslaがSolar Cityを買収しました。
風車製造について Vestas(デンマーク) ~データ分析を活用した稼働率向上~
欧州における陸上風力の新規導入が飽和しつつある中、世界最大の風車メーカーであるVestas等は、保有する膨大な風車稼働データを活用し、高い稼動率を保証するメンテナンスサービスを提供しています。こうした風車メーカーは稼働率保証を顧客に提供しています。風車メーカー独自にメンテナンスを実施することで、顧客のビッグデータを蓄積し、そのビッグデータを活用したモニタリングにより、風車のトラブルを事前に予測することで停止時間を減らし、それが稼働率保証に繋がるというビジネスモデルです。プロジェクト自体が巨大である洋上風力発電の開発が増える中で、メーカーの統合による大規模化・寡占化が進んでおり、2013年にはVestasと三菱重工の洋上風力発電部門の統合が発表され、2014年に洋上風力発電設備専業の新会社を発足しました。
【第131-3-8】風力発電の業界構造
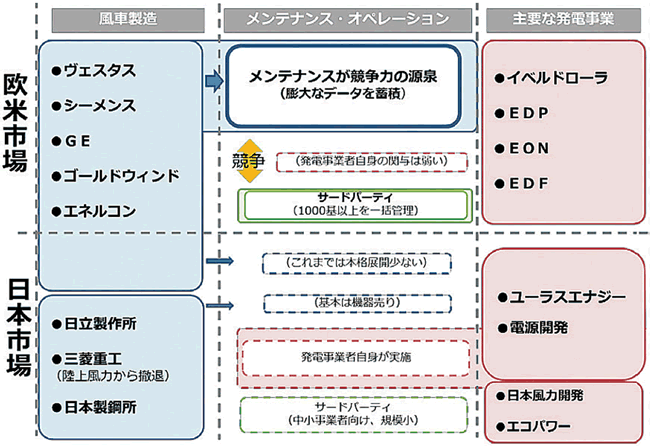
- 出典:
- 平成28年10月 風力発電競争力研究会 報告書
蓄電技術について
AES Energy Strage(アメリカ) ~拡張性の高い蓄電システムの構築~
【第131-3-9】AESのバッテリーユニットイメージ

- 出典:
- AES Energy Strage HP
AES Energy Strageは40kWを一単位として、数十万kWまでフレキシブルに拡張できるバッテリーユニットを開発し、従来は困難であった蓄電池導入後の容量変更が可能になり、発電側、送電側、需要側の幅広い用途に対応することを可能としています。ピーク時とオフピーク時の電力価格差を利用した電力量取引に加え、自動制御で周波数制御を行える設計を活かして、周波数安定化の市場での利益を得ることも戦略としています。
Stem(アメリカ) ~ ICTと蓄電地を活用したエネルギーマネジメント、ディマンドレスポンス~
Stemは、情報通信技術と蓄電地を用いて、電力の需要予測やリアルタイム管理を行うことで、電力使用を最適化するサービスを提供し、需要家の省エネを補助すると同時に、再エネ導入拡大に伴うグリッドへの負担を低減しています。例えば、商業施設に蓄電池を設置し、需要家向けにピークカットによる契約料金の引き下げに加えて、それらの蓄電池数百台を集約(アグリゲート)して電力会社向けに調整力としても提供する取組を行っています。同社はIberdrola、RWE、Exelon等、世界の大手エネルギー事業者からベンチャーキャピタルを通じた出資を受け、注目を集めています。
ディマンドレスポンスについて Energy Pool(フランス)
Energy Poolは、主に製紙、鉄鋼、化学などの大口産業需要家にDR Boxというゲートウェイを設置し、そのゲートウェイに対してDR信号を発することにより、需要家の生産ラインを制御してDRを実施しています。実績として、2016年6月に原子力発電所の計画外停止等により需給がひっ迫した際、一般送配電事業者から要請を受けたEnergy Poolが、DRにより56.1万kWの需要削減に成功しています。
SMR(Small Modular Reactor)について NuScale(アメリカ)
近年では小型原子炉(SMR:Small Modular Reactor)について、日本を含む世界中のエネルギー企業・ベンチャー企業が研究しています。従来の100万kW超の原子力発電所と異なり、1基ごとの出力を小さくすることで冷却を容易にし、安全性を高めています。また、あらかじめ工場で製造したユニットを現場で組み立てることで、工期短縮や製造コストの削減も実現します。
例えば、アメリカのベンチャー企業であるNuScaleは、直径約4.5m、高さ約23m、1基あたり5万kWの出力の小型原子炉を開発中です。SMRを12基組み合わせることで60万kWの出力を予定しています。NuScaleは2026年の商用運転開始を目指しています。
【第131-3-10】従来原子炉とSMRの大きさ比較
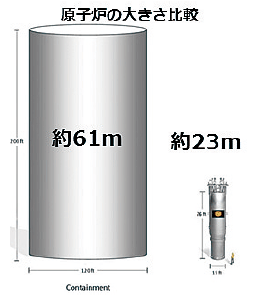
- 出典:
- NuScale HP
中国における電気事業の動向
中国では、1997年に誕生した国有企業である国家電力公司が垂直一貫でほぼ独占的に事業を展開していましたが、2002年に送配電はエリアごとに2企業に、発電分野は5企業に分割され、同時に4つのIPP企業が設立されています。
(送配電会社:国家電網公司と南方電網有限責任公司の2社、発電会社:中国華能集団公司、中国大唐集団公司、中国国電集団公司、中国華電集団公司、中国電力投資集団公司の5社)
【第131-3-11】2002年の中国の電気事業者分割
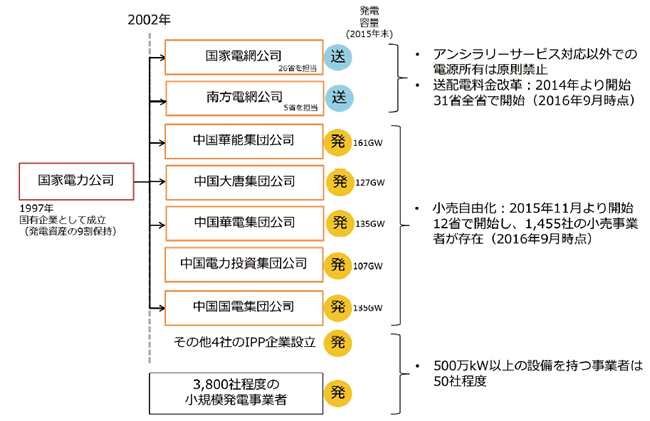
- 出典:
- 中国電力工業発展報告2016等を基に資源エネルギー庁作成
中国では、国有企業という特性上、政府の5カ年計画(現在は、2017年3月公表の2016年~2020年計画である13次5カ年計画)に従い、各企業が事業展開を実施しています。本計画での電力需要の伸び率は、年率3.6%~ 4.8%とこれまでのような急速な伸びが見込まれないことを背景とし、5カ年計画には、電気事業の国際展開という方針が随所に掲げられており、従来にも増して我が国企業の国外展開などに当たって、強力な競合相手になる可能性があります。
【第131-3-12】発電能力と電力需要量の推移
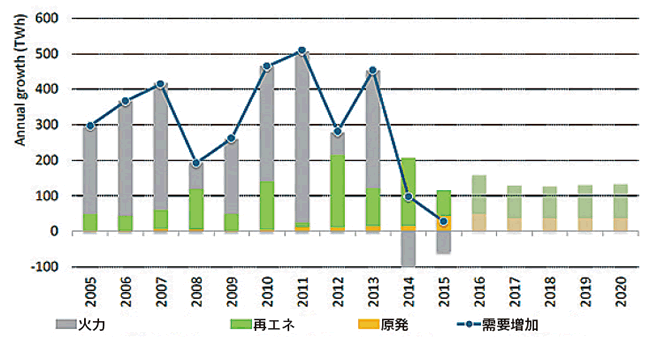
- 出典:
- WEI2016
例えば国家電網公司は、2010年からブラジルに進出し、総延長6,000キロ近くの送電ネットワークを保有していましたが、2017年2月にブラジルのCPFLエネルジアの株式23.6%を約2,100億円で追加取得したと発表しました(国家電網公司のCPFLエネルジアの持株比率は54.64%に)。CPFLエネルジアは送電子会社9社を擁するブラジル送電市場シェア13.4%(7,000億kWh)の企業であり、容量ベースでも民営2位に位置付けられる発電所を運営しています。
すでに国家電網は、香港やフィリピン、ブラジル、ポルトガル、オーストラリア、イタリア、ギリシャでも送電資産を取得しており、保有する国外電力関連資産は、総額で400億米ドルを超えています。
一方で、2015年には、オーストラリアの電力・通信サービスを供給する電力公社オースグリッドの売却入札(99年間にわたり50%超の株式を貸与)において、国家安全保障上の問題を理由にオーストラリア政府から応札を拒否されるといった案件も生じています。
また、中国は再エネ分野においても世界的に大きな規模を占めており、2015年には中国の全発電設備への投資のうち風力発電と太陽光発電で3分の1以上が再エネへの投資となるなど、中国国内でも再エネ投資は活発に行われています。世界の太陽電池メーカー上位6社のうち中国が4社を占め、世界最大の風力発電タービンメーカーなども中国企業となっています。
【第131-3-13】世界の再エネ投資額の推移
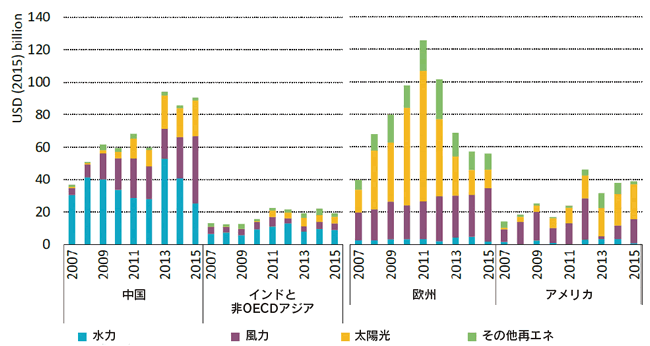
- 出典:
- WEI2016
1987年にパキスタンに参入した中国電力建設集団は、2016年9月、単一事業としてはパキスタン最大の風力発電事業であるTricon Boston風力発電事業について、設計(engineering)・調達(procurement)・建設(construction)を含むEPC包括請負契約を締結しました。総設備規模150MWで、同国での中国電力建設集団の設備容量は480MWとなります。
さらに、原子力発電所の輸出については、第3世代原子力発電所と同等の能力と言われている、「華龍一号」の輸出を推進しています。既に、中国核工業集団公司がパキスタン、南米、イギリスで、中国広核集団がルーマニアなどで契約を進めており、近隣国にとどまらず国際的な影響力を強めています。特に、技術協力という観点だけでなく、人員や資金等の協力も含めて官民共同で推進しているといわれています。
【第131-3-14】世界に進出する中国の原子力発電
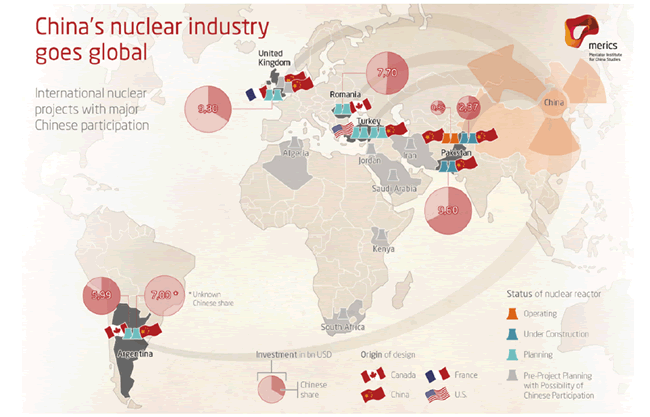
- 出典:
- 独merics中国研究所 2016