第1節 2018年に発生した主な災害の概要
2018年は、2月に起きた福井県の豪雪に始まり、夏以降も大阪府北部地震、平成30年7月豪雨、平成30年台風第21号・台風第24号、平成30年北海道胆振東部地震等の自然災害が続発し、これに伴う大規模停電など、災害発生時のエネルギーの安定供給の重要性が再認識されるとともに、過酷な災害時における安定供給に係る課題が明らかとなった年となりました。
そして近年、こうした顕著な自然現象の発生回数は増加傾向にあると言えます。例えば地震について、震度5以上の地震の回数は近年増加傾向にあることが見て取れます。また、大雨の発生状況についても、1時間当たり降水量が50mmを超える降雨の回数も逓増傾向にあります。こうした背景もあり、過去の地震や風水災等による保険金の支払額を見ても、近年は大規模災害が相次いでいることが確認できます。
本節では、2018年に起こった主な災害について、発災と被害の状況、復旧までの取り組みを振り返ります。
【第131-0-1】2018年に発生した主な災害の概要

【第131-0-1】2018年に発生した主な災害の概要(ppt/pptx形式:1,080KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
【第131-0-2】近年の自然災害について
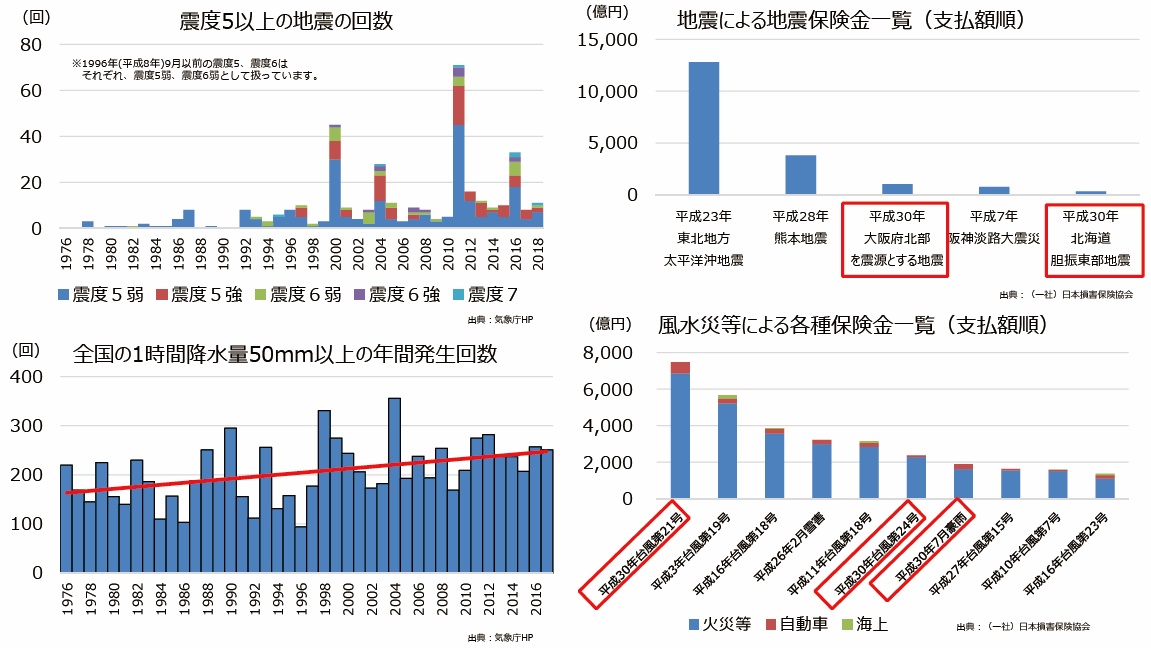
【第131-0-2】近年の自然災害について(ppt/pptx形式:203KB)
- 出典:
- 気象庁、日本損害保険協会の統計データを基に資源エネルギー庁作成
1.平成30年2月福井県の記録的な大雪(2018年2月上旬)
(1)概要
2018年2月3日から8日にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置が続き、上空5,000m付近で、平年より10℃以上低いマイナス30℃以下の強い寒気に広く覆われました。この影響で北日本から西日本にかけての日本海側を中心に断続的に雪が降り、福井県福井市では昭和56年(1981年)の豪雪(196センチ)以来37年ぶりに積雪が140センチを超えるなど大雪となりました。
この大雪により、除雪中の事故や転倒等が発生し、2018年2月16日時点で、死者22名、重傷者102名のほか、家屋の全半壊等が生じました。また、この大雪に伴い道路の通行止めや鉄道の運休等の交通障害が生じました。特に、福井県の国道8号線の坂井市~あわら市間で、6日から数日間にわたり約1,500台の車両が立ち往生する事態となりました。このように交通網が麻痺状態となったことから、学校の休校、企業の休業、灯油やガソリン等の生活物資の不足等、地域住民の生活や経済活動全般に多大な影響を及ぼしました。
(2)エネルギー供給への影響と復旧対応
電力インフラ、都市ガスインフラには大きな被害はなかったものの、除雪作業の遅延等による道路閉鎖・渋滞などの影響が生じ、石油配送には大幅な遅延が発生しました。坂井市三国町の石油出荷基地(油槽所)と幹線道路を結ぶ国道・県道等でも、6~10日の間、通行不能となったため、除雪車用の軽油、暖房用の灯油、自家用車用のガソリンを供給するサービスステーション(以下、「SS」と呼ぶ。)の在庫が不足する事態となりました。
資源エネルギー庁は、「県内のすべての地域において燃料にアクセスできる状況を確保する」という方針のもと、福井県、地元の石油商業組合、大手石油元売会社など幅広い関係者と連携し、燃料不足の解消に努めました。具体的には、例えば嶺北地域において、
- -大手石油元売会社に対し、県外の近隣製油所・油槽所からの応援配送を含め、被災地への供給について万全の体制を敷くよう要請しました。石油元売各社は県外からの応援配送を実施し、12日から14日にかけては、平年の6~8割増しで供給しました。
- -油槽所周辺など燃料輸送のための道路について、県は重点的な除雪を実施しました。また、積雪により大型ローリーの通行に困難があったため、石油元売からの要請に応じて、中核SS(災害時に、警察・消防等の緊急車両や災害復旧車両に対して優先的に燃料供給を行う拠点として整備したSS)等に繋がる道路の優先除雪や警察による誘導を実施しました。
- -前述の中核SSに対し、在庫状況を確認しました。加えて、中核SSや、県が除雪車の燃料供給拠点としたSSに対し、継続供給を実施しました。
- -SSの稼動状況を確認するため、福井県嶺北地域の全SSを対象に営業状況、販売制限の有無、油種別在庫状況などの情報を収集しました(初回は資源エネルギー庁が実施し、以後県において情報を更新しました。)。
【第131-1-1】福井豪雪による災害状況
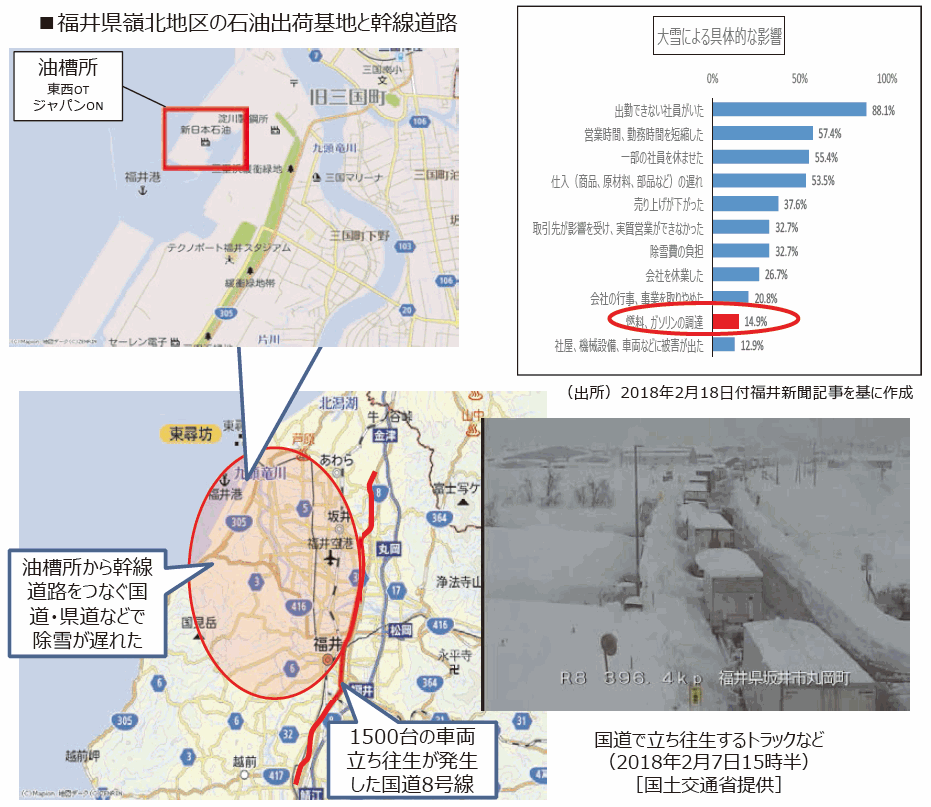
【第131-1-1】福井豪雪による災害状況(ppt/pptx形式:279KB)
- 出典:
- 災害時の燃料供給の強靭化に向けた有識者会議 全国石油商業組合連合会資料 一部修正
2.大阪府北部地震(2018年6月18日発生)
(1)概要
2018年6月18日7時58分、大阪府北部の深さ13kmでマグニチュード6.1の地震が発生し、大阪府大阪市北区等で震度6弱、京都府京都市等で震度5強を観測する等、近畿地方を中心に強い揺れを観測しました。
この地震により、死者6名、負傷者462名の人的被害、住家全壊21棟、半壊454棟等の住家被害が生じました(2019年2月12日現在)。ライフラインでは、約17万戸(最大)で停電が発生し、約11万戸(最大)で都市ガスの供給支障が発生する等、住民生活に大きな影響を及ぼしました。
(2)エネルギー供給への影響と復旧対応
①電力
発災後、関西電力北豊中変電所における設備被害等により、大阪府・兵庫県内で最大約17万戸が停電しました。
これを受けて関西電力が復旧にあたり、変電所及び電線等のインフラ設備を確認のうえ、約3時間後には復旧を完了しました。
②都市ガス
発災直後、二次災害防止と早期復旧を図るため、大阪ガスにより約11万戸の供給が停止されました。
翌19日には大阪ガスが1,000名体制で復旧作業に着手しました。20日には日本ガス協会(870名)が復旧作業に着手するとともに、21日には同協会の応援隊が2,300名規模に拡大しました。大阪ガスグループとその他の事業者をあわせて約5,100名で作業にあたり、発災から7日目の24日にすべての世帯で復旧が完了しました。
また、移動式ガス発生設備により、21ヵ所の災害拠点病院等について、ガスの臨時供給が行われました。
【第131-2-1】大阪府北部地震の概要
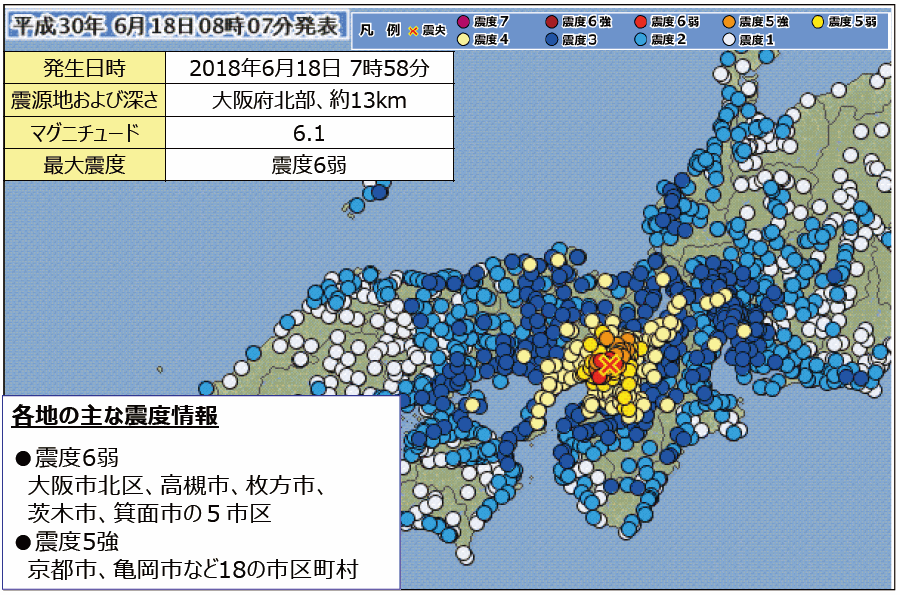
【第131-2-1】大阪府北部地震の概要(ppt/pptx形式:349KB)
- 出典:
- ガス安全小委員会 大阪ガス資料 一部修正
【第131-2-2】大阪府北部地震によるガス供給の停止エリア
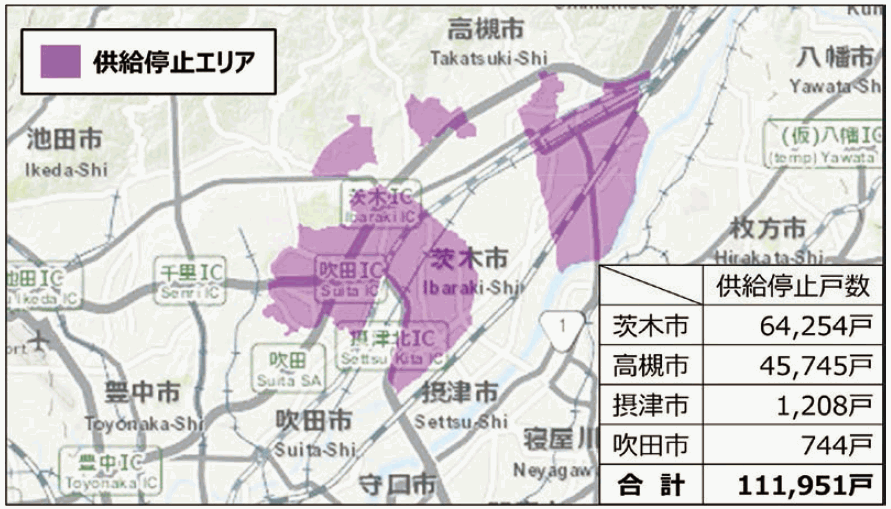
【第131-2-2】大阪府北部地震によるガス供給の停止エリア(ppt/pptx形式:1,247KB)
- 出典:
- ガス安全小委員会 大阪ガス資料
【第131-2-3】大阪府北部地震における導管網と都市ガス供給の復旧作業の進捗
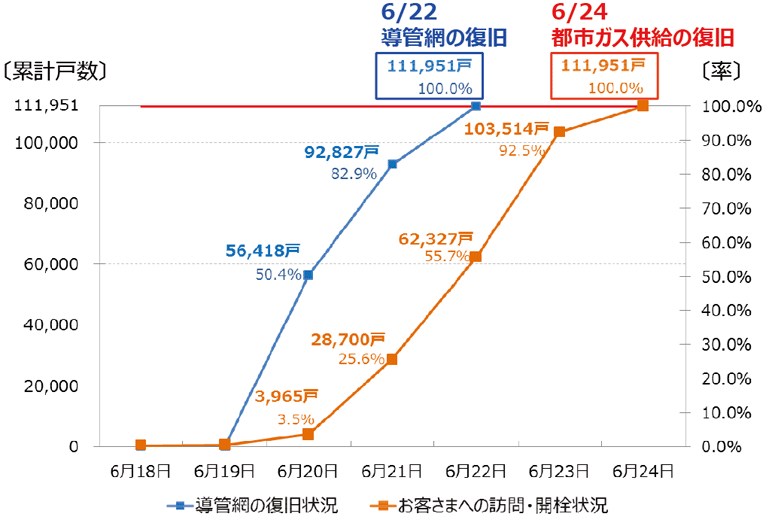
【第131-2-3】大阪府北部地震における導管網と都市ガス供給の復旧作業の進捗(ppt/pptx形式:110KB)
- 出典:
- ガス安全小委員会 大阪ガス資料
③燃料
大阪国際石油精製大阪製油所(高石市)の設備の一部が運転を停止しましたが、製品在庫からの出荷や融通等により地域の供給に支障はなく、24日15時をもって通常運転を再開しました。
その他製油所、油槽所、SSについては、大きな被害はありませんでした。
3.平成30年7月豪雨“西日本豪雨”(2018年6月28日~7月8日)
(1)概要
6月28日以降、北日本に停滞していた前線は7月4日にかけ北海道付近に北上した後、7月5日には西日本まで南下してその後停滞しました。また、6月29日に日本の南で発生した台風第7号は東シナ海を北上し、対馬海峡付近で進路を北東に変えた後、7月4日15時に日本海で温帯低気圧に変わりました。
この前線や台風第7号の影響により、日本付近に暖かく非常に湿った空気が供給され続け、西日本を中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨となりました。6月28日から7月8日までの総降水量は、四国地方で1,800mm、東海地方で1,200mmを超えるところがあるなど、7月の月降水量平年値の2 ~4倍となる大雨となったところがあった他、九州北部、四国、中国、近畿、東海、北海道地方の多くの観測地点で24、48、72時間降水量の値が観測史上第1位となるなど、広い範囲で長時間の記録的な大雨となりました。
この豪雨により、岡山県、広島県、愛媛県等で河川の氾濫や土砂災害が相次ぎ、死者237名、行方不明者8名等の人的被害のほか、全壊6,767棟、半壊11,243棟、床上浸水7,173棟、床下浸水21,296棟の住家被害が発生しました(2019年1月9日時点)。また、停電が約8万戸(最大)で発生する等、ライフラインにも大きな被害が生じました。
【第131-3-1】平成30年7月豪雨“西日本豪雨”の降水分布(2018/6/28~7/8)
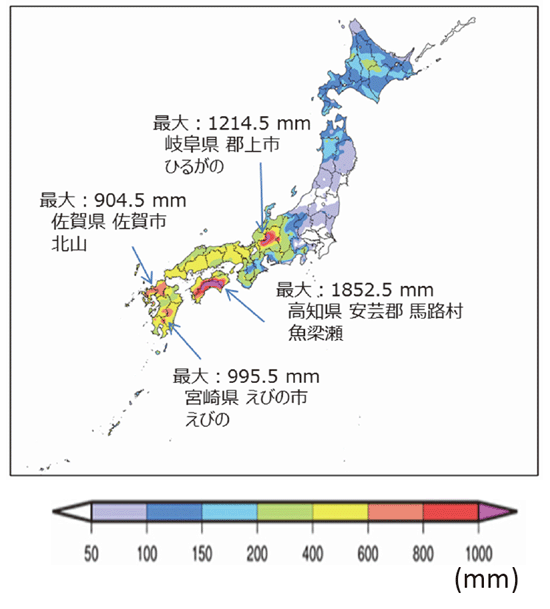
【第131-3-1】平成30年7月豪雨“西日本豪雨”の降水分布(2018/6/28~7/8)(ppt/pptx形式:152KB)
- 出典:
- 気象庁
(2)エネルギー供給への影響と復旧対応
①電力
中国、四国地方を中心に土砂崩れや河川氾濫及びそれらに伴う停電被害が発生し、最大約8万戸が停電しました。中でも中国電力管内では約6万戸の停電を記録しました。
これを受け、中国電力では、他電力を含む復旧要員を最大2,400人動員し、72時間後には約9割の停電を解消しました。1週間後の7月13日には、土砂崩れ等で倒壊・流出した家屋等を除きすべての世帯で停電が解消されました。
電気設備への影響も大きく、沼田西変電所(広島県三原市)への浸水被害により、同変電所からの全ての送電が停止されました。電源車による応急送電を実施しつつ変電所の仮復旧を行った結果、同じく13日には、発電所からの送電が再開されました。
【第131-3-2】平成30年7月豪雨による被害状況と復旧作業の様子(1)
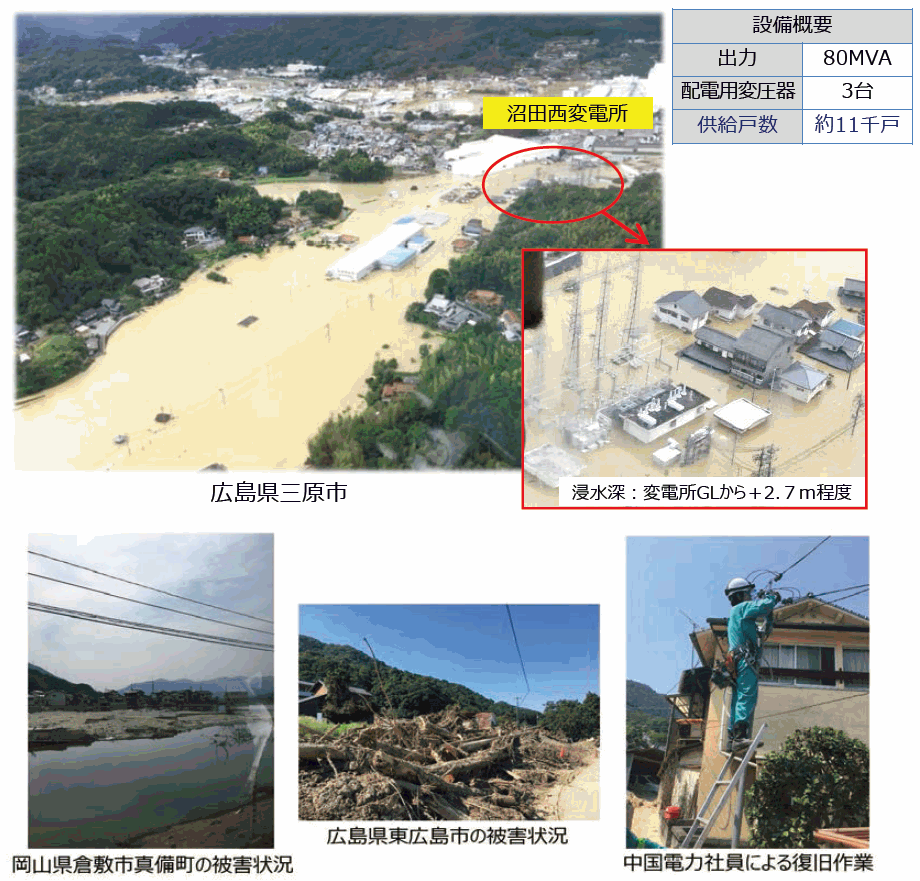
【第131-3-2】平成30年7月豪雨による被害状況と復旧作業の様子(1)(ppt/pptx形式:1,819KB)
- 出典:
- 電力安全小委員会 中国電力資料、電力レジリエンスワーキンググループ資料
経済産業省においては、
- -電力会社に対し、自治体や道路管理者等、地元行政機関との連携体制構築および記者会見やSNS(Twitter等)を活用した情報発信を指示しました。
- -また、多くの住民が避難を余儀なくされる中、冷房設備のない避難所において、熱中症を防止するため、岡山、広島及び愛媛の3県・40ヵ所の避難所で、計541台の冷房設備(スポットクーラー325台、業務用クーラー216台)を搬入しました。設置にあたっては、メーカー、物流企業、電力会社、電気工事事業者と連携しました。
- -国土交通省と連携し、ダムの放流情報の電力会社への共有や復旧の妨げとなる道路の優先啓開を要請しました。
- -被災電力会社に対し、各行政機関との橋渡し役として、職員をリエゾンとして派遣しました。
- -電源車への燃料供給の確保について、中国電力から広島県石油商業組合への協力要請と並行し、全国石油商業組合連合会に対しても要請しました。
- -中国電力と並行して、Twitterで停電情報を発信しました。
②都市ガス
土砂崩れや家屋倒壊による供給管、内管の損傷、長雨による差し水により、約290戸において供給不良が発生しました。また、ガス供給に支障はなかったものの、道路法面崩落により中圧導管が露出し、さらに、岡山県倉敷市において旧簡易ガス団地3ヵ所が冠水しました。
これを受け、政府においては、日本ガス協会、日本コミュニティーガス協会に対し被災需要家一戸一戸の被害状況、復旧支障要因、復旧見通し等の報告及び復旧の促進を要請するとともに、日本コミュニティーガス協会に対しては臨時のガス供給を実施できる体制を早急に整えるよう要請しました。
この結果、住民が居住する地域については、7月8日に復旧を完了しました。また、、簡易ガス団地については、住民が戻り次第供給開始できるよう臨時供給の準備を整えました。
③燃料
岡山県真備町、愛媛県大洲市や宇和島市においては、一部のSSが水没するなど甚大な被害を受けました。こうした中でも、自家発電機を稼働して緊急車両等に対する燃料供給を行い、移動電源車への燃料供給等に貢献したSSもありました。
【第131-3-3】平成30年7月豪雨による被害状況と復旧作業の様子(2)
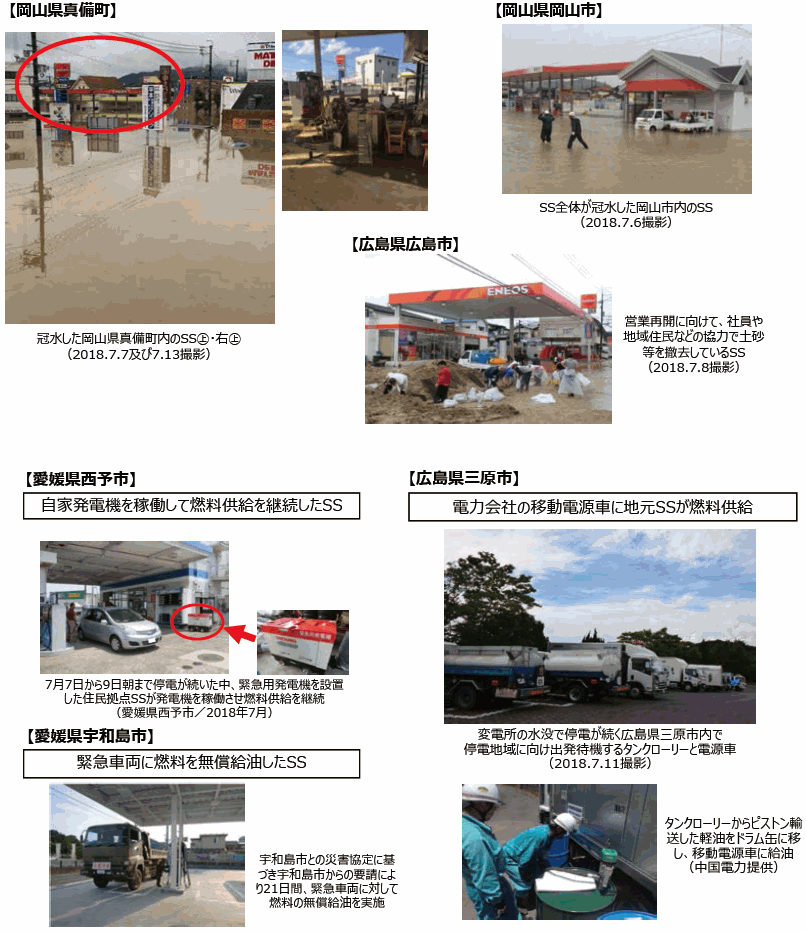
【第131-3-3】平成30年7月豪雨による被害状況と復旧作業の様子(2)(ppt/pptx形式:881KB)
- 出典:
- 災害時の燃料供給の強靭化に向けた有識者会議 全国石油商業組合連合会資料 一部修正
4.平成30年台風第21号(2018年9月4日日本上陸)
(1)概要
8月28日に南鳥島近海で発生した台風第21号は、9月4日12時前に非常に強い勢力で徳島県南部に上陸しました。4日14時前には兵庫県神戸市に再び上陸し、速度を上げながら近畿地方を縦断し、日本海を北上、5日には間宮海峡で温帯低気圧に変わりました。
台風の接近・通過に伴って、西日本から北日本にかけて非常に強い風が吹き、非常に激しい雨が降りました。特に四国や近畿地方では、猛烈な風雨をもたらし、顕著な高潮となったところがありました。
この台風により、死者14名、重傷者46名等の人的被害のほか、住家被害として全壊59棟、半壊627棟、床上浸水64棟、床下浸水452棟等の住家被害がありました(2019年2月12日時点)。また、強風や土砂崩れによる電柱の倒壊等により、関西電力管内で約170万戸が停電し復旧まで2週間以上を要したほか、大阪湾での記録的な高潮により関西国際空港が浸水し運用ができなくなる等、住民生活や中小企業、農林漁業や観光業等の経済活動に大きな影響を及ぼしました。
(2)エネルギー供給への影響と復旧対応
①電力
台風第21号により、近畿地方を中心に大規模な停電被害が発生しました。ピーク時には全国で約240万戸、関西電力管内では約170万戸の停電を記録し、配電設備では約6,700ヵ所に損傷がみられました。他にも、電柱倒壊等、多くの設備被害が発生し、復旧までに2週間以上を要する事態となりました。関西電力では当初の約8,000名から増強し、約12,000名体制で復旧作業を実施しました。自治体と連携するとともに、ニーズに応じて被災者にポータブル発電機を提供し、他の電力会社に対しては発電機車の派遣を要請しました(中国電力20台、四国電力5台、九州電力15台)。
また、発災直後に関西電力の停電情報システムがダウンしたため、停電情報を1時間ごとにプレス発表するとともに、SNSやHPでも発信したものの、被災者に対する情報提供の面で大きな支障が生じました。
【第131-4-1】平成30年台風第21号による停電状況
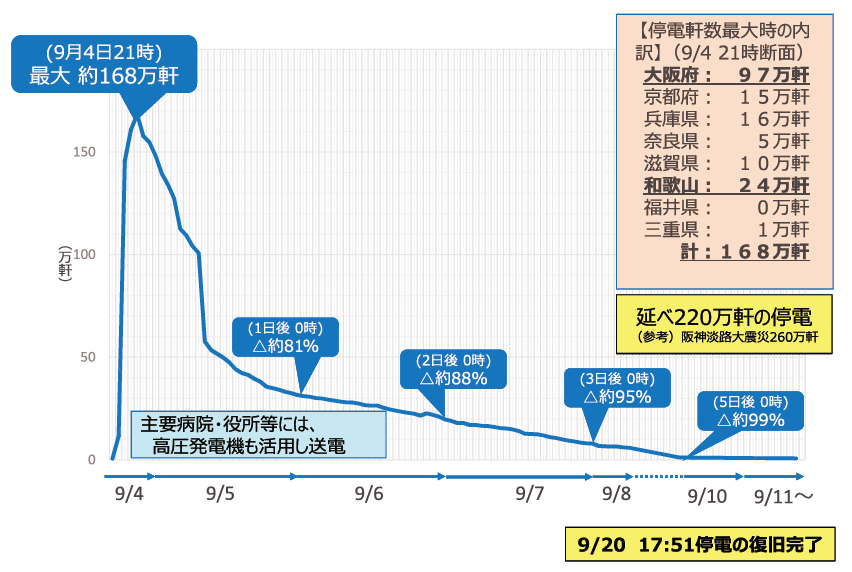
【第131-4-1】平成30年台風第21号による停電状況(ppt/pptx形式:397KB)
- 出典:
- 電力安全小委員会 関西電力資料
【第131-4-2】平成30年台風第21号による停電被害
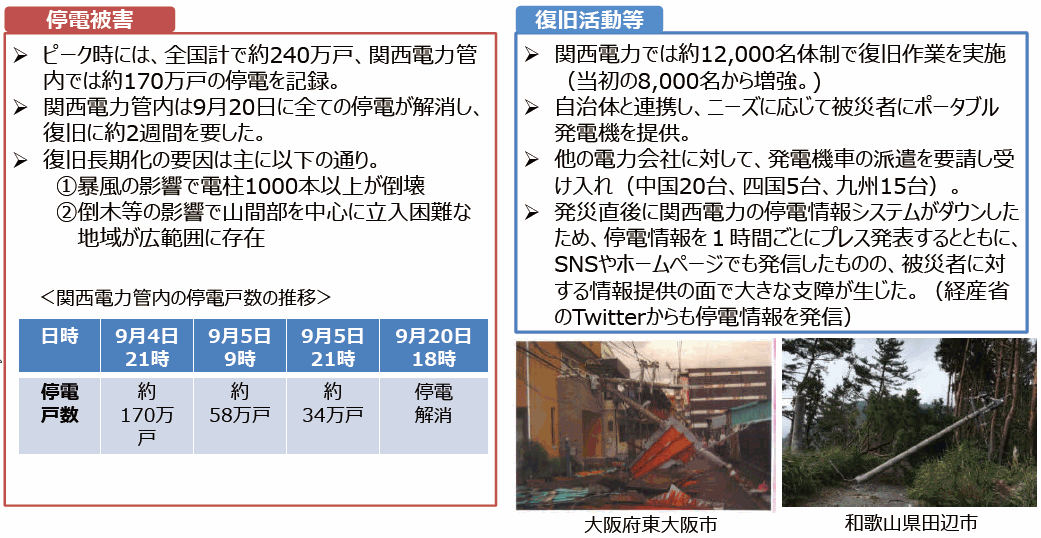
【第131-4-2】平成30年台風第21号による停電被害(ppt/pptx形式:226KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
経済産業省においては、
- -発災前、電気事業連合会及び台風の接近が予想されるエリアの電力会社に対し、(A)電力業界大での発電機車等の資機材や人員の融通をはじめとした広域連携の準備、(B)TwitterやFacebook等のSNSを活用した迅速かつ正確な情報の発信、(C)自治体や道路管理者等地元行政機関との密接な連携体制構築、を指示しました。
- -発災当日は、(A)厚生労働省と連携して病院等の停電状況を把握するとともに、緊急性がある場合は被災電力会社に連絡、(B)産業保安監督部(経済産業省の地方部局)職員を各行政機関との橋渡し役として被災電力会社に派遣、(C)経済産業省のTwitterも活用して、停電状況等を随時発信しました。
- -発災2日目は、(A)停電が大規模に残るエリアについて、電源車や人員の派遣等の広域連携を加速させるため、電気事業連合会とも連携して周辺電力会社に働きかけを実施、(B)監督部では現地調査を実施し、自治体や住民の声を収集することで住民ニーズ把握を支援しました。
- -発災3日目以降は、停電長期化エリアへの対応を実施しました。具体的には、(A)停電が長期化している被災自治体に電話調査を行い、被災電力会社との連絡体制の状況や自治体ニーズの把握、(B)国土交通省・道路管理者と連携して、復旧作業加速化のため、優先的に障害物等を除去すべき道路の整理を行いました。
②都市ガス
ジェット燃料を運送する内航タンカーが大阪湾に停泊していたところ、4日午後、強風に流され関西国際空港の連絡橋に衝突しました。これに伴い橋に敷設されていた中圧導管が損傷しガス漏れが発生しました。同日中には、バルブを閉止して安全な現場状況にあることを確認しましたが、バルブ閉止による供給支障が77戸で発生しました。
これを受け、大阪ガスを中心に約100名体制で現場対応にあたり、関西国際空港内の低圧導管の健全性を確認した上で、空港側と調整しながら開栓作業をすすめ、ガス供給を順次再開しました。その結果、事故から12日後の16日に全戸のガス供給を再開しました。
また、神戸市東灘区においては、高潮により敷地外に高圧ガス容器(酸素、窒素)約100本が流出しました。神戸市消防局が対応にあたり、一部は海上に流出したものの、14日には流出容器をほぼすべて回収しました。
【第131-4-3】平成30年台風第21号によるSSの被災状況
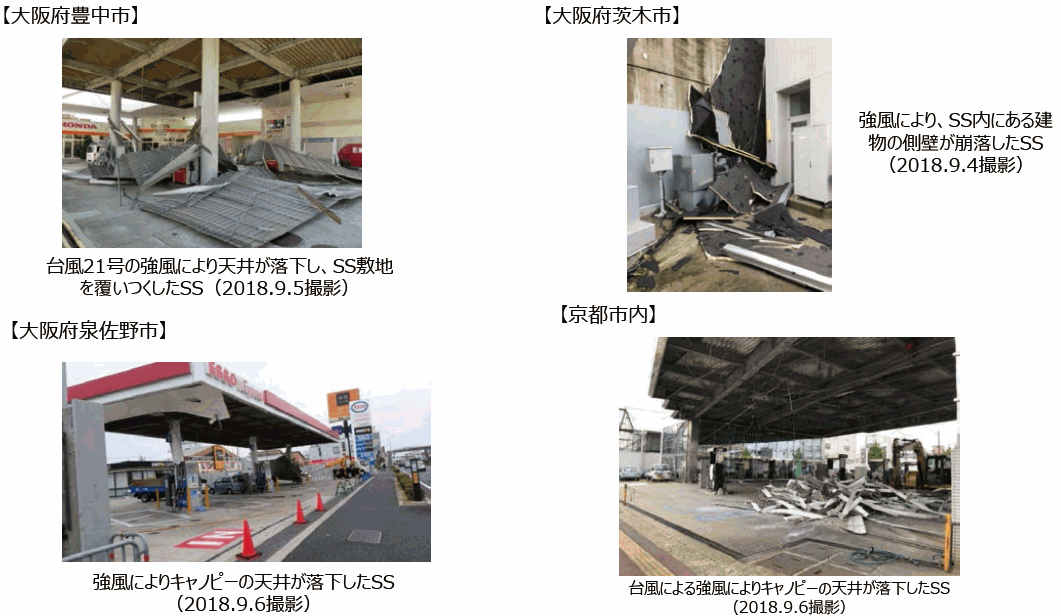
【第131-4-3】平成30年台風第21号によるSSの被災状況(ppt/pptx形式:425KB)
- 出典:
- 災害時の燃料供給の強靭化に向けた有識者会議資料 全国石油商業組合連合会資料 一部修正
③燃料
出光興産岸和田油槽所(大阪府)においては、停電のため電源確保ができず一時的に出荷ができない状態になりましたが、5日朝の停電復旧により同日昼には通常出荷を再開しました。
また、SSにおいても、近畿地方を中心にキャノピーの天井が落下してSS敷地を覆い隠すなど、大きな被害を受けました。
なお、前述の通り、ジェット燃料を運送する内航タンカーが強風に流され関西国際空港の連絡橋に衝突しましたが、ジェット燃料の積み込み前であったため燃料の漏洩はなく、乗組員11名の無事も確認できました。5日未明には、海上保安部の指導の下、タグボートでタンカーを牽引し、連絡橋との引きはがし作業も完了しました。
5.平成30年北海道胆振東部地震(2018年9月6日発生)
(1)概要
2018年9月6日3時7分、北海道胆振地方中東部の深さ37kmでマグニチュード6.7の地震が発生し、胆振地方中東部で震度7、石狩地方中部、石狩地方南部、日高地方西部で震度6弱を観測しました。
この地震により、死者42名、負傷者762名等の人的被害のほか、住家全壊462棟、半壊1,570棟等の被害が発生しました(2019年1月28日時点)。
地震そのものの大きさもさることながら、地震発生から約20分後の3時25分には北海道全域が停電となる“ブラックアウト”が発生したこともあり、住民生活のほか物流等の企業活動、農林水産業や観光業等、道内の経済活動に大きな影響及ぼしました。
(2)エネルギー供給への影響と復旧対応
①電力
(ア)ブラックアウトからの復旧
3時7分の地震発生にともない、3時25分には北海道エリアにおいて日本で初めてとなるエリア全域におよぶ大規模停電(ブラックアウト)が発生し、北海道全域において約295万戸の電力供給が停止しました。
9月6日時点で停電戸数は約295万戸に上りましたが、地震による被害のなかった火力発電所を順次再稼働させることで、8日時点では約4,000戸にまで停電戸数は減少しました。その後、更に道路の復旧作業と並行して順次作業が進んだことで、発災約1ヶ月後の10月4日に停電は解消しました。
その間(地震発生~9月19日までの間)、他の電力会社から約1,700人、高圧移動発電機車151台が応援にかけつけました。
経済産業省においては、
- -地震前から定められていたルールに基づき、その時点で得られた客観的データを元に定量的な分析を行った上で、確認された事実・見通し等をその都度、公表するとともに、復旧情報等、国民が必要とする情報・見通しは、期限を設けて目途を示すよう、電力会社等に指示を行いました。
- -加えて、電力供給が安定するまでの間、電力需給のギャップによって大規模停電が再び発生することを回避するために、道内の一定規模の自家発電機保有者に対して、個別に電話等で自家用発電機の系統への送電を要請しました。また、電力需要が増加する平日8:30~20:30の時間帯には、道内全域で平常時よりも「1割」程度の需要減が必要となったため、当該時間帯を「節電タイム」と位置づけ、さらに今年度中に廃止予定の老朽火力発電設備の故障等のリスクや、病院・上下水道といった節電困難な施設があることも踏まえつつ、9月8日より、道内全域の家庭・業務・産業の各部門に対して、平時よりも「2割」の節電要請を行いました。
また、効果的な節電を実現するため、
- -業務部門向けの「節電ステッカー」のほか、家庭部門向けの「節電呼びかけポスター」を作成しました。
- -資源エネルギー庁のHPにおいて、2割節電に取り組む事業者を「節電サポーター」として募集し、協力いただいた事業者の事業者名と写真を公開しました。
- -業界への節電協力要請を経済産業省Twitterで発信しました。
- -地方公共団体の防災無線を用いた節電への呼びかけの依頼を行いました。
- -節電を要請する中、Twitterを通じて1時間毎に「節電率」を発表するとともに、プレスブリーフィングも継続的に実施しました。
【第131-5-1】9月10日の週の需給ギャップと対応方針
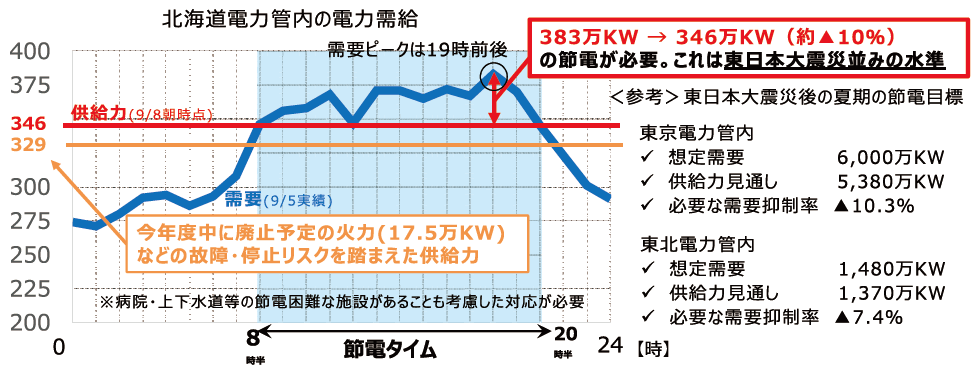
【第131-5-1】9月10日の週の需給ギャップと対応方針(ppt/pptx形式:187KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
【第131-5-2】節電の呼びかけ
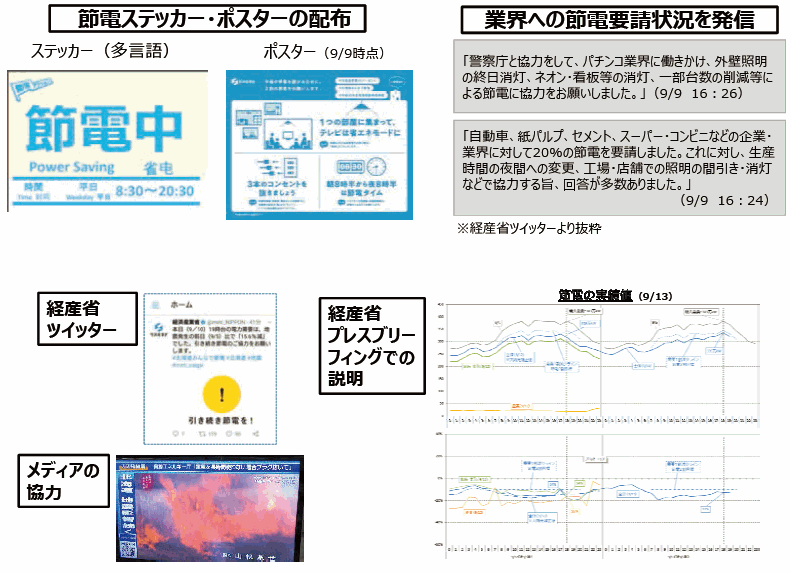
【第131-5-2】節電の呼びかけ(ppt/pptx形式:3,560KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
なお、節電要請については、9月14日に京極揚水発電所の2機目が起動し、供給力に一定の上積みを図ることができたことを踏まえ、数値目標付き節電要請を解除、9月19日には、苫東厚真発電所1号機が予定を前倒して復旧したことに伴い需要減1割の目標も解除しました。その後、苫東厚真発電所4号機が9月25日に、同2号機が10月10日に復旧し、石狩湾新港LNG火力発電所1号機も10月5日に試運転を開始しました。これらの復旧に伴い、電力需給は安定したものの、電力需要が最も大きくなる冬の時期に向けて無理のない範囲での節電の取組を要請しました。
【第131-5-3】当時の北海道エリアの需給バランスの推移見通し
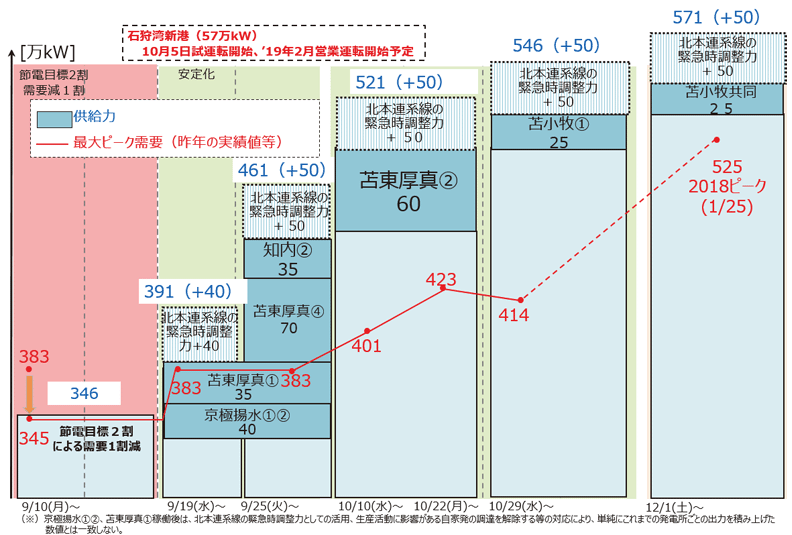
【第131-5-3】当時の北海道エリアの需給バランスの推移見通し(ppt/pptx形式:158KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
【第131-5-4】北海道エリアにおいて大規模な計画外停止が生じた場合の需給見通し
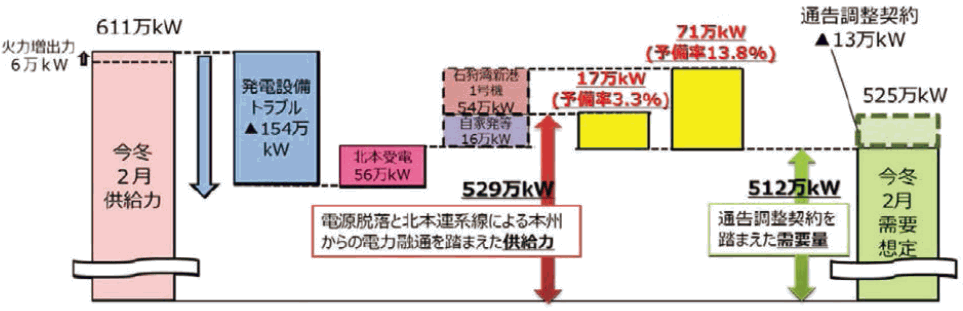
【第131-5-4】北海道エリアにおいて大規模な計画外停止が生じた場合の需給見通し(ppt/pptx形式:572KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
また、11月8日、総合資源エネルギー調査会電力・ガス基本政策小委員会において、2018年度冬期の需給見通しについて検証を行うとともに、必要となる対策についても議論、取りまとめが行われました。具体的には、北海道においては、厳気象時における最大需要(H1需要)が生じた際にも電力の安定供給に最低限必要とされる予備率3%が確保されていることが確認されました。発電所で大規模な計画外停止(▲154万kW)が生じた場合にも、北海道胆振東部地震発生後と同様に自家発電機の焚き増し等を行うことで、予備率3%以上の確保を図る事ができる見通しであることが確認されました。
(イ)ブラックアウトに至った原因
“ブラックアウト”とは、大手電力会社の管轄する地域のほぼすべてで停電が起こる現象(全域停電)のことを意味しています。これまでも大きな自然災害にともなって大規模停電が発生することはありましたが、今回のような各電力会社の供給エリア全域で起こったケースは国内では初めてのことでした。
今回のブラックアウトの原因究明にあたっては、国の認可機関である「電力広域的運営推進機関」(以下、「広域機関」と呼ぶ。)に第三者による検証委員会(以下、「検証委員会」と呼ぶ。)が設置され、ブラックアウトに至った経緯、及びブラックアウト後、一定の供給力確保(約300万kW)に至るまでの復旧経緯について、技術的な観点から、データに基づいた事象の解明が行われました。その結果、今回のブラックアウトに至る事象は主として、苫東厚真発電所1、2、4号機の停止(N-3)に加え、地震の揺れによる送電線4回線(N-4)事故に伴う道東の複数の水力発電所の停止等が発生した複合的な事象であったことが確認されました。
【第131-5-5】地震からブラックアウトに至る経緯
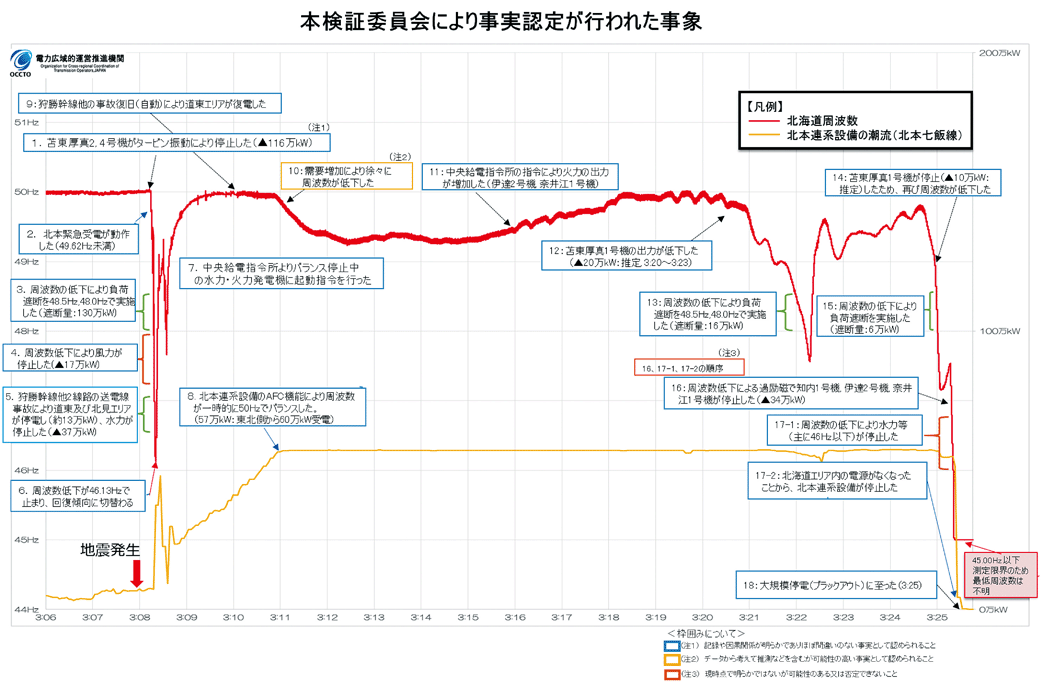
【第131-5-5】地震からブラックアウトに至る経緯(ppt/pptx形式:1,022KB)
- 出典:
- 電力広域的運営推進機関
(ウ)再生可能エネルギーへの影響
事業用の太陽光・風力発電設備には、北海道電力の系統連系技術要件に基づき周波数低下リレー(UFR)が設置されており、系統事故等により、系統全体の周波数が一定の値を下回る場合に、自動的に解列する機能が具備されています。今般の地震発生直後も、当該機能により運転中の風力発電設備のほぼ全てが自動的に解列されました。
太陽光や風力発電については、天候や日照条件によって発電量が変動し、安定的に運用するには出力変動に対応する調整力が必要不可欠なため、調整力の確保状況と並行して9月8日から9月14日にかけて段階的に、北海道電力において系統への接続復帰が可能との判断が行われ、供給力として活用されました。なお、住宅用の太陽光発電等については、停電解消後に順次発電が開始されていました。
また、再生可能エネルギーが非常電源として活用された事案も存在しました。例えば、稚内市が所有していた蓄電池付き太陽光は、地震発災直後に系統から自動解列したものの、すぐに系統から独立して、自営線で連系した公園、球場等に電力を供給し、非常用電源として活用されました。また、家庭用太陽光発電は、自立運転機能の利用により、非常電源として活用され、停電時においても電力利用を継続できた家庭が約85%存在したとの業界団体による調査結果も報告されました。
水力、バイオマス、地熱発電などの発電量の変動が少なく安定的に発電が可能な再生可能エネルギーについては、発災直後より、接続が可能になったものからすぐに系統に接続し発電が行われており、発電量の変動はほぼなく、一定割合で発電し、供給力として貢献していました。
発災時、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、家庭用太陽光設備の自立運転モードへの切り替え、コージェネレーションの活用等により冷蔵庫、テレビ、携帯電話の充電などが可能となり、生活環境の維持に貢献した事例も見られました。
【第131-5-6】風力・太陽光発電の接続復帰経緯
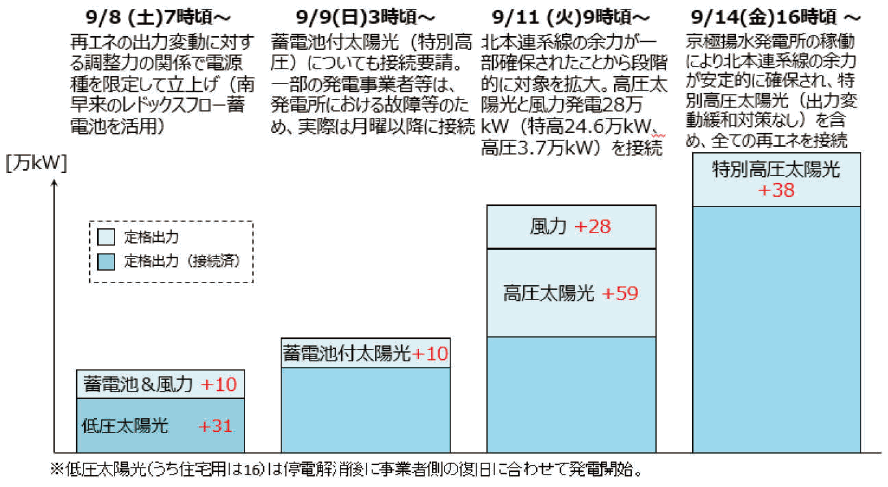
【第131-5-6】風力・太陽光発電の接続復帰経緯(ppt/pptx形式:366KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
【第131-5-7】災害時における家庭用太陽光発電設備の稼働状況について
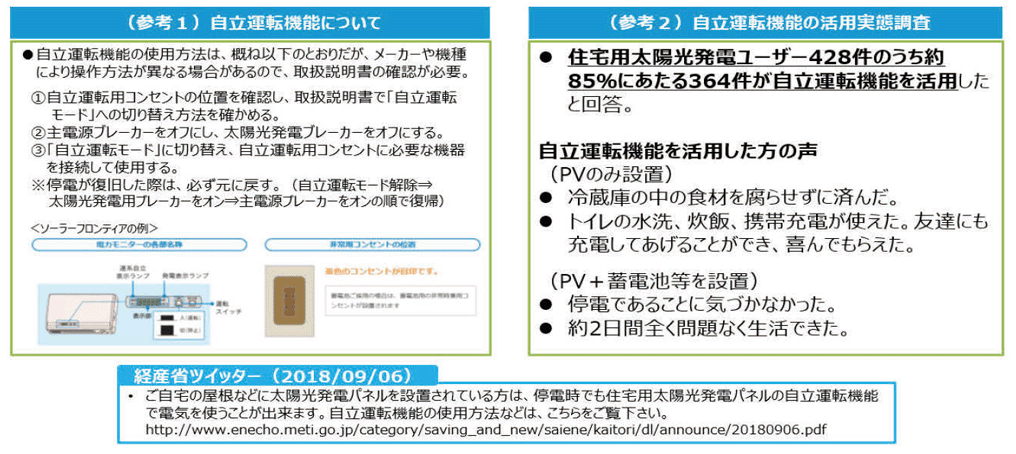
【第131-5-7】災害時における家庭用太陽光発電設備の稼働状況について(ppt/pptx形式:790KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
【第131-5-8】風力・太陽光発電の出力の推移
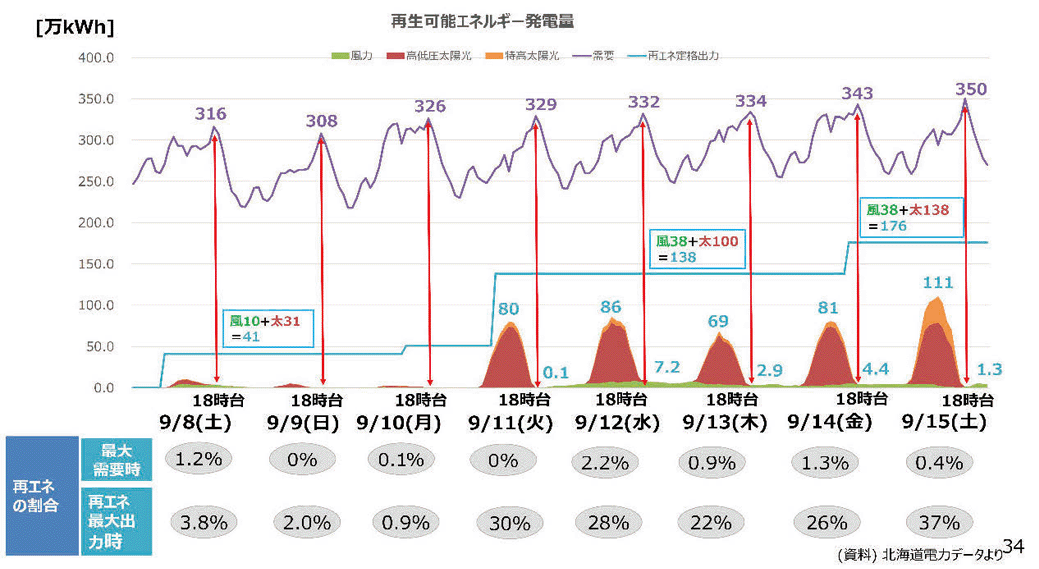
【第131-5-8】風力・太陽光発電の出力の推移(ppt/pptx形式:611KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
【第131-5-9】バイオマス・地熱の出力の推移
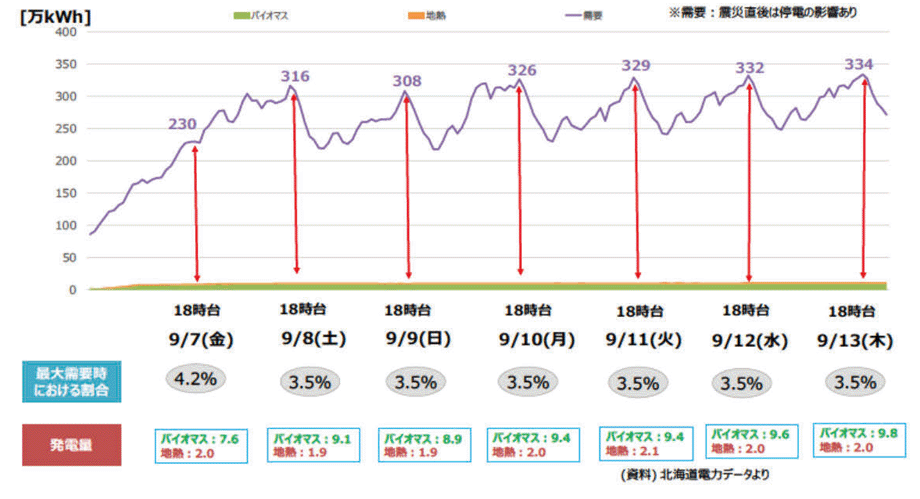
【第131-5-9】バイオマス・地熱の出力の推移(ppt/pptx形式:404KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
②都市ガス
地震発生直後、停電により一部のガス製造所において製造が停止しましたが、保安電力用の非常用発電設備が自動起動し、保安上必要な設備への電力供給が開始されたことから、地震発生から1時間後には、3製造所(石狩LNG基地・函館みなと工場・北見工場)からのガスの供給が再開されました。
都市ガスは全域において大きな被害はありませんでした。札幌市清田区里塚では液状化による道路陥没・土砂流出が発生するも、ガス導管には影響はなく、大きな被害は発生しませんでした。
北海道ガス以外の事業者においても、非常用発電設備により都市ガス製造を継続しました。停電の長期化を想定し、「非常用電源車の配備」、「非常用電源の燃料調達」、「LNG・LPGローリー輸送ルートの安全確保、優先走行」について、日本ガス協会を通じて政府に要望がありました。
熱供給については停電の影響から、札幌市では都心地域、光星地域、厚別地域、真駒内地域を中心に約9,000戸、苫小牧市では中心街南地域、西部地域、日新団地地域を中心に約4,000戸が供給停止になりました。いずれも設備被害はなく、9月9日時点で復旧が完了しました。
【第131-5-10】北海道ガスグループによる地震発生後の対応状況
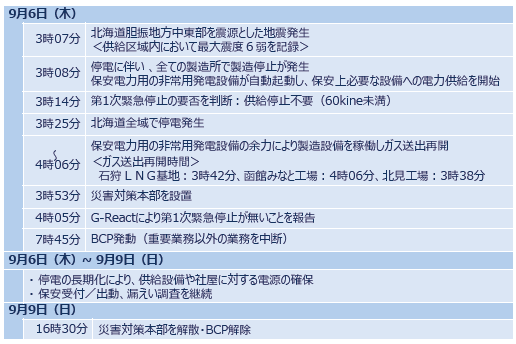
【第131-5-10】北海道ガスグループによる地震発生後の対応状況(ppt/pptx形式:56KB)
- 出典:
- ガス安全小委員会 北海道ガス資料
【第131-5-11】ガス導管への被害の概要
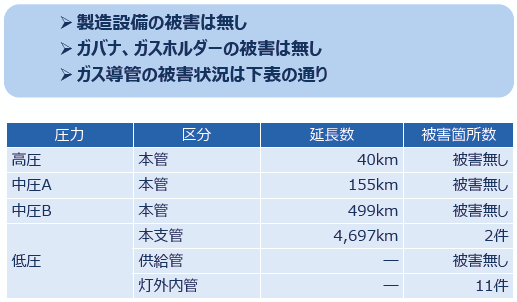
【第131-5-11】ガス導管への被害の概要(ppt/pptx形式:49KB)
- 出典:
- ガス安全小委員会 北海道ガス資料
【第131-5-12】道内ガス事業者の被害の状況
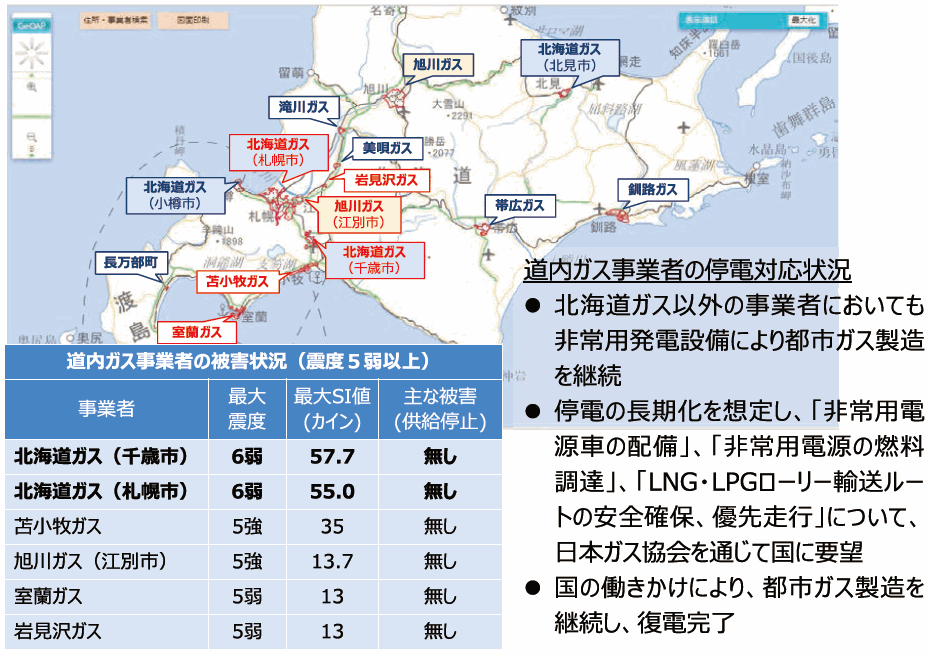
【第131-5-12】道内ガス事業者の被害の状況(ppt/pptx形式:409KB)
- 出典:
- ガス安全小委員会 北海道ガス資料
③燃料
北海道内には約1,800ヵ所のSSがあるも、停電により地下タンクからガソリン・軽油をくみ上げるポンプや計量器などの機器が作動せず、自家発電機を持つ場所以外の営業が停止しました。加えて、災害直後の需要増加により営業中のSSに顧客が殺到したことで、札幌市内を中心に道内の広範囲にわたり給油制限や在庫切れが発生しました。
しかし、電力が復旧していくに従い、営業可能なSSは増加していきました。道内にはガソリン(11日分)、軽油(7日分)などの在庫が保持されており、それらが500台近いローリーで順次配送され、延べ数で6日は447件、7日は770件、8日には1,577件が営業を再開し、12日には1,743件(約9割)が営業を再開しました。
また特に被害の大きい3地域(安平町、厚真町、むかわ町)の17ヵ所のSSにおいては、ガソリンの給油制限も実施しましたが、9日以降、重点的な配送を行い、11日に供給制限・在庫不足が解消しました。
地震発生以降、電力が回復するまでの約2日間、病院・通信施設・上下水道等の重要施設では非常用発電機が稼働しており、発電機を連続稼働させるために必要な燃料(ディーゼル(軽油)・A重油等)の備蓄が不足していたことから、6日未明から約300件の緊急供給要請があり(病院:161件、通信施設:86件、上下水道:36件)、関係各省、北海道庁、石油元売各社、北海道石油商業組合が連携し、燃料供給要請に対応しました。
【第131-5-13】燃料供給における被害の状況
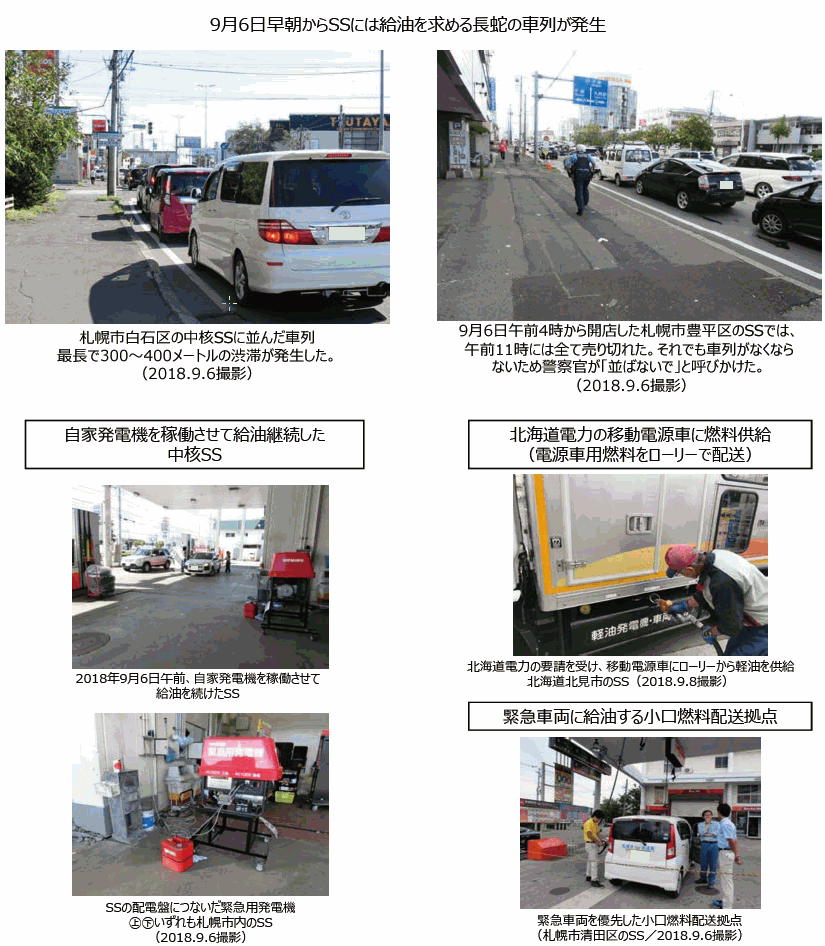
【第131-5-13】燃料供給における被害の状況(ppt/pptx形式:832KB)
- 出典:
- 災害時の燃料供給の強靭化に向けた有識者会議資料 全国石油商業組合連合会資料 一部修正
6.平成30年台風第24号(2018年9月30日日本上陸)
(1)概要
9月21日にマリアナ諸島近海で発生した台風第24号は、9月28日から30日明け方にかけて、非常に強い勢力で沖縄地方に接近した後、30日20時頃に和歌山県田辺市付近に上陸しました。その後、東日本から北日本を縦断し、10月1日9時までに日本の東で温帯低気圧に変わりました。
台風の接近・通過に伴って、広い範囲で暴風、大雨、高波、高潮となり、特に南西諸島及び西日本・東日本の太平洋側を中心に、これまでの観測記録を更新する猛烈な風または非常に強い風を観測しました。また、紀伊半島等では過去の最高潮位を超える高潮を観測した所がありました。
この台風により、死者4名、重傷者26名等の人的被害のほか、住家被害として全壊53棟、半壊384棟、床上浸水316棟、床下浸水1,909棟等の住家被害がありました(2019年2月12日時点)。また、全国計で最大約180万戸の停電が発生する等、ライフラインにも大きな被害が生じました。
【第131-6-1】平成30年台風第24号による停電被害
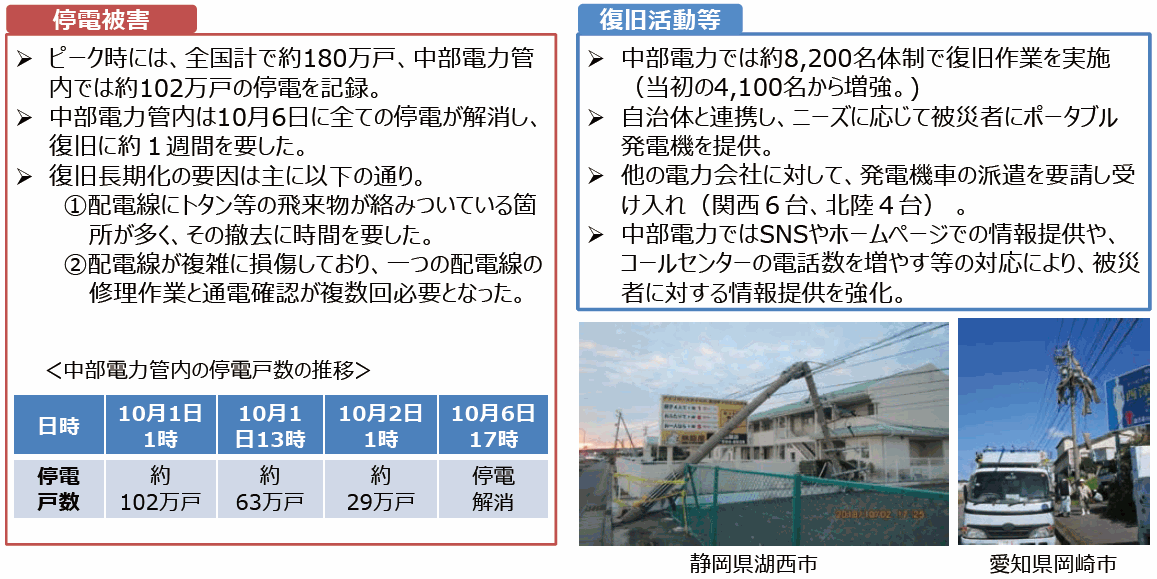
【第131-6-1】平成30年台風第24号による停電被害(ppt/pptx形式:218KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁