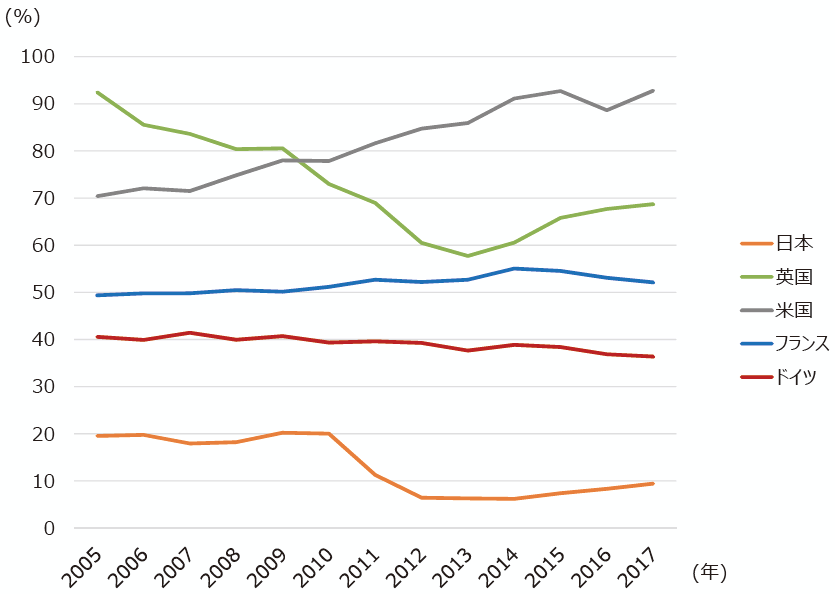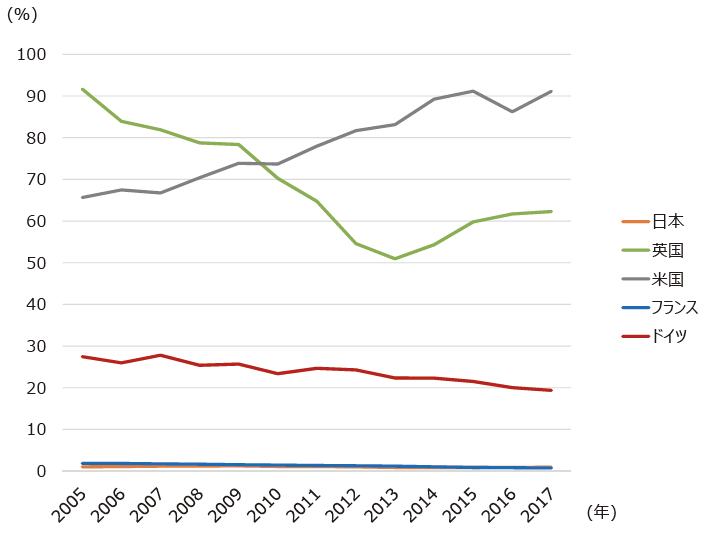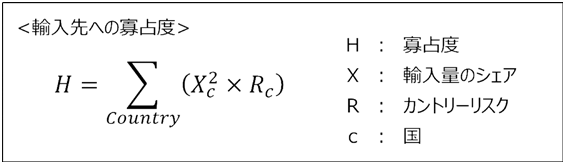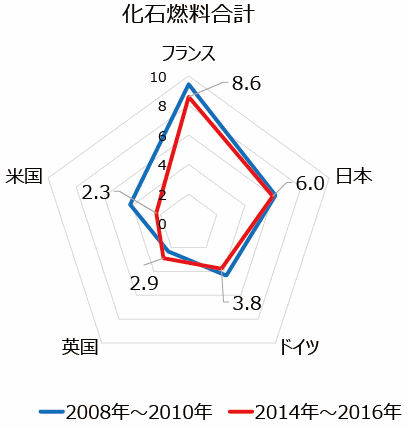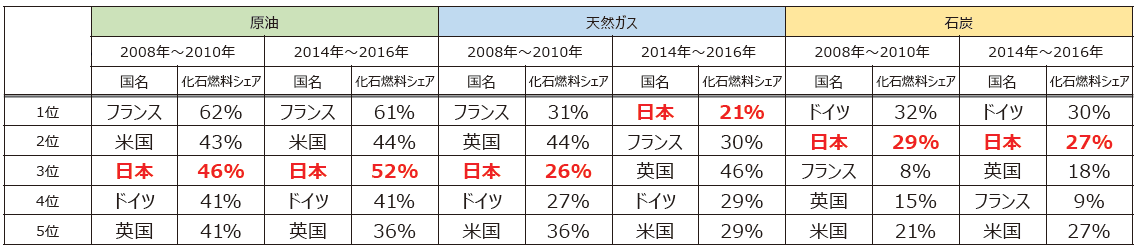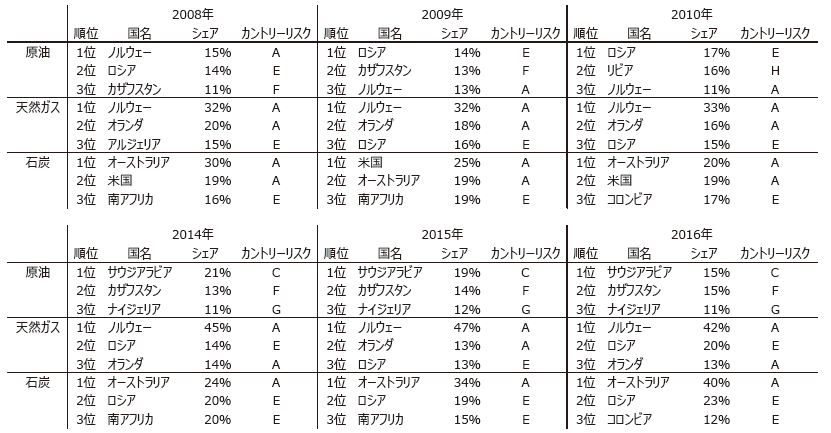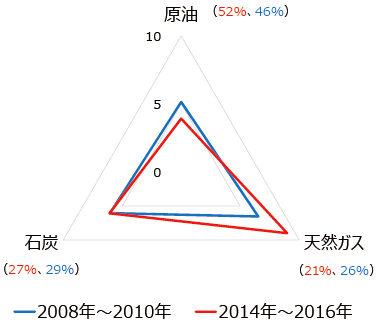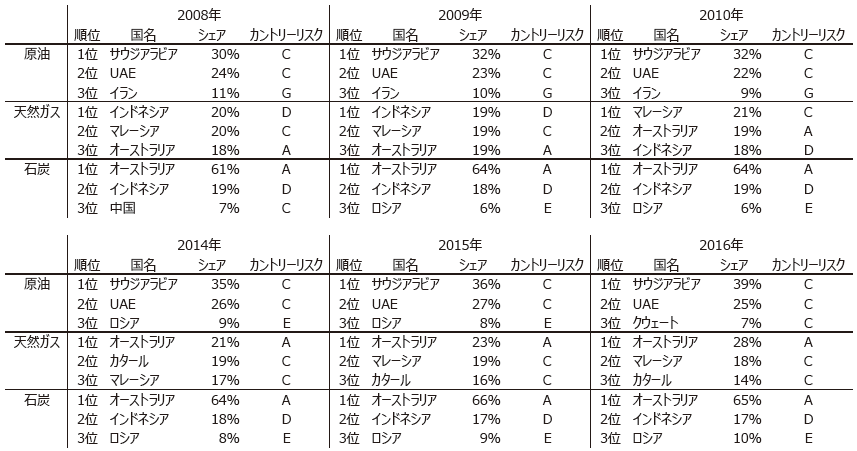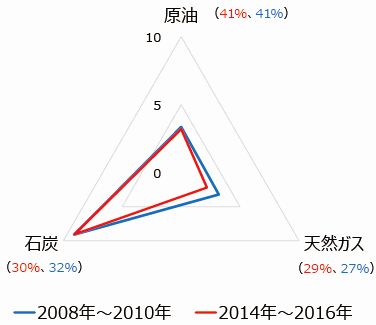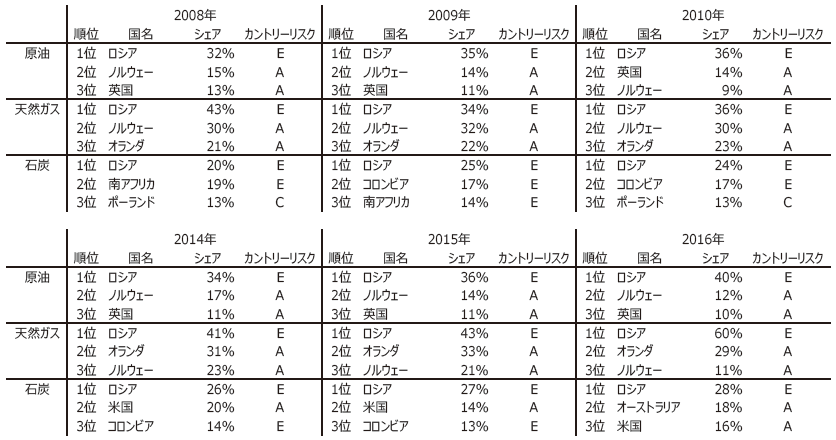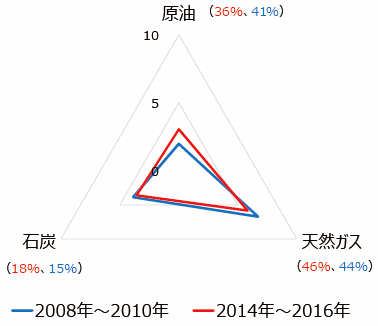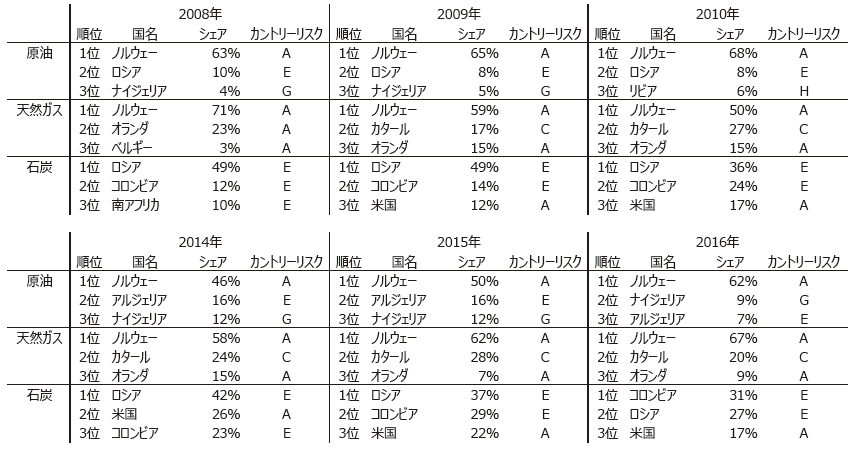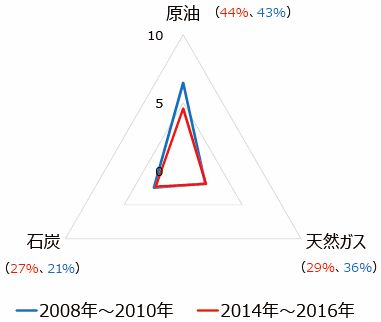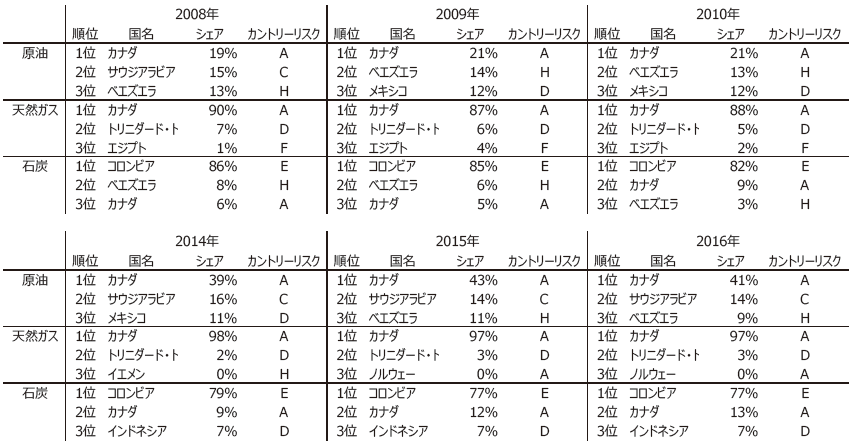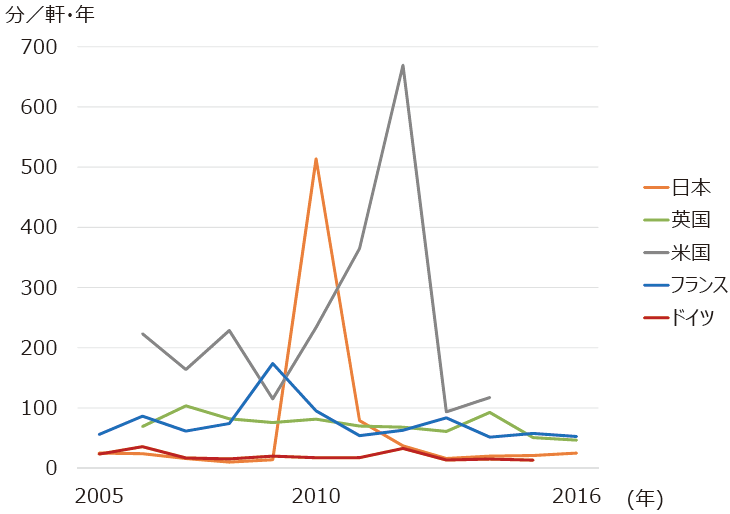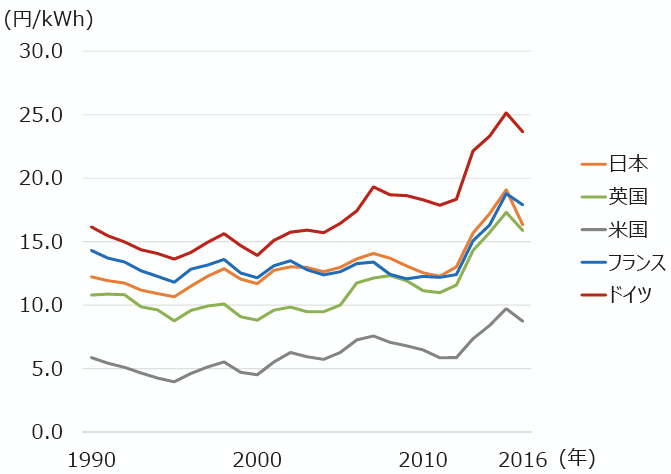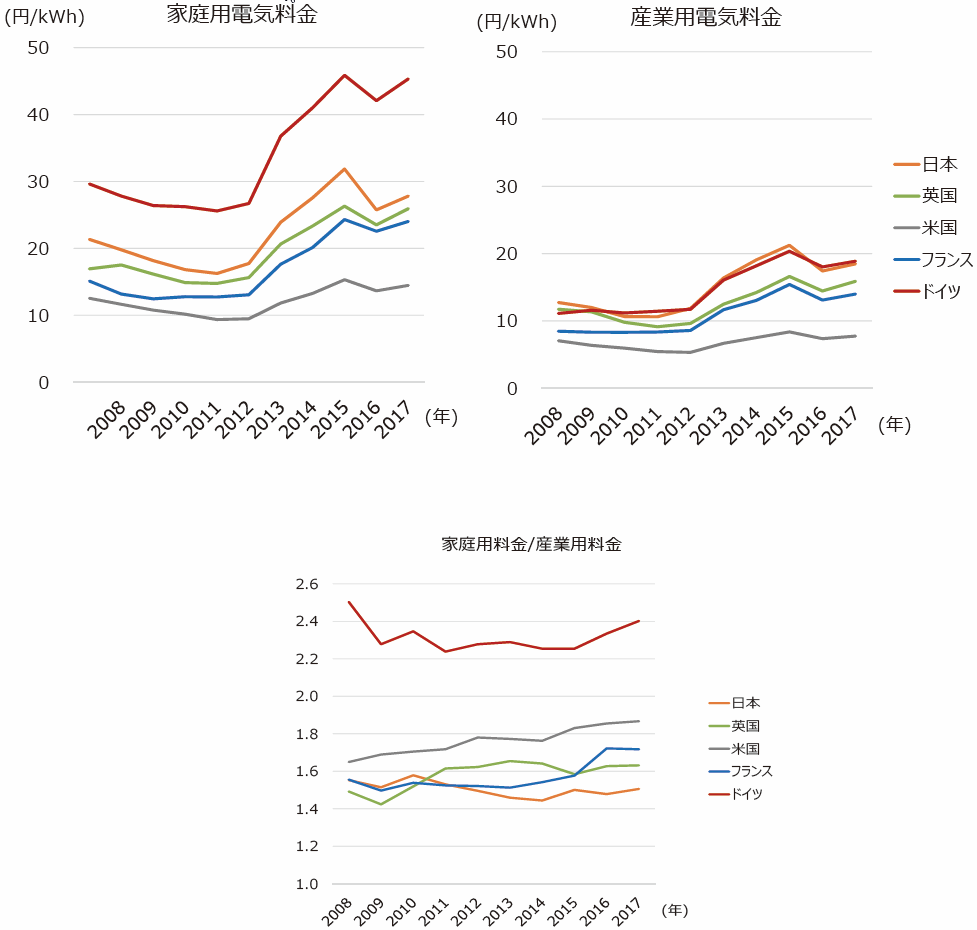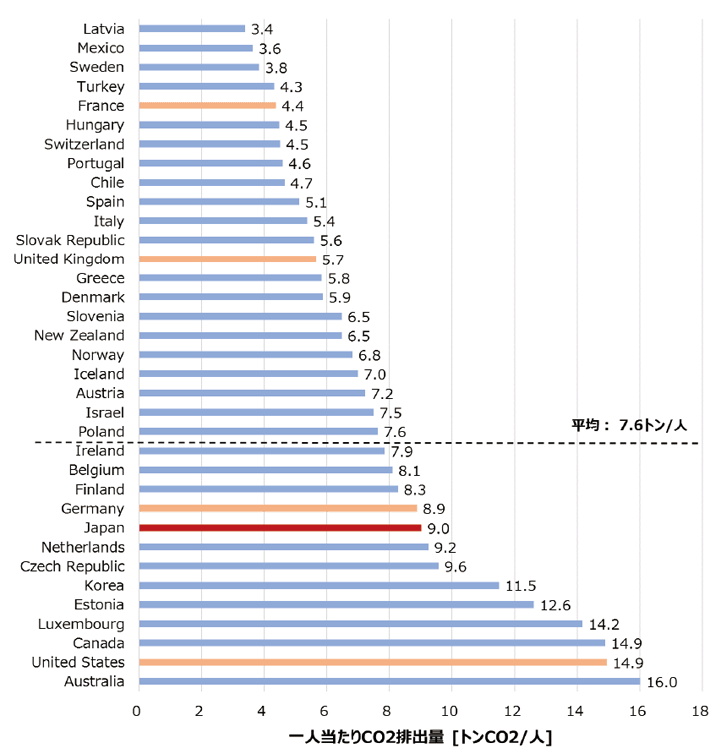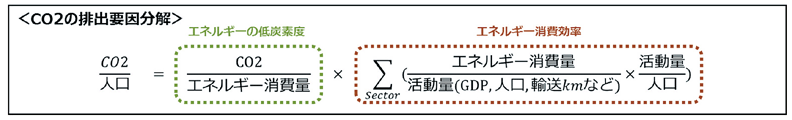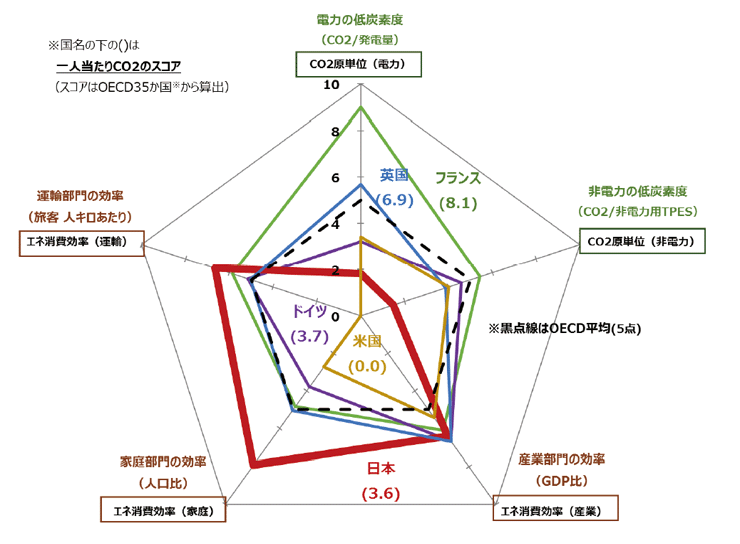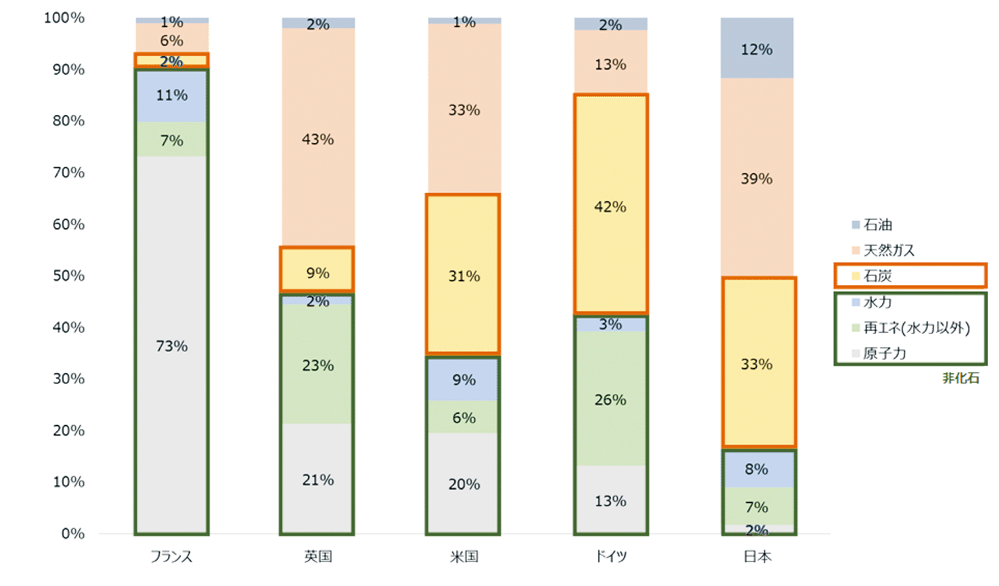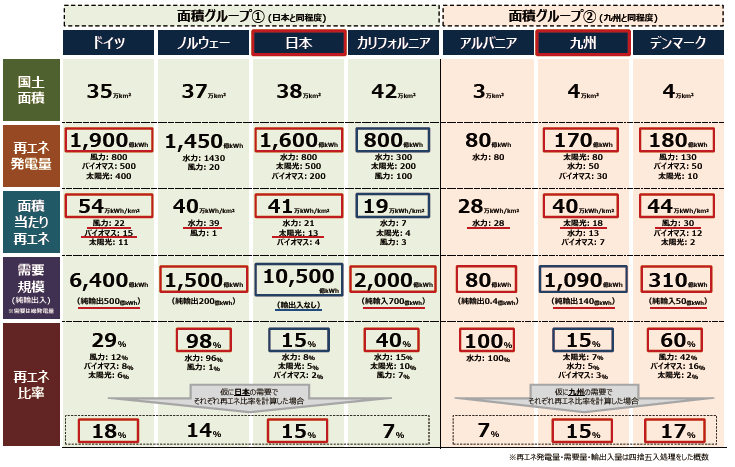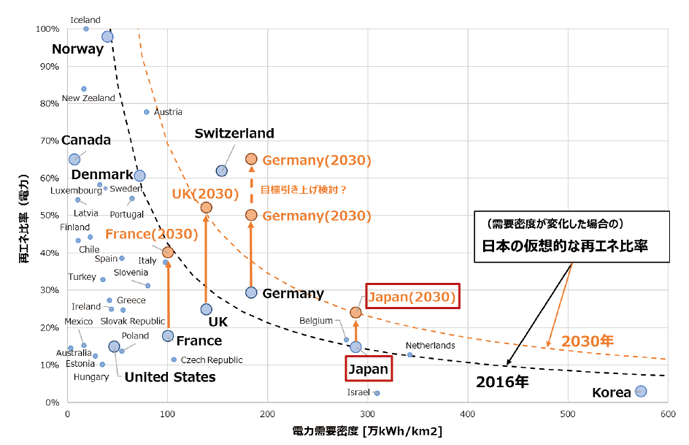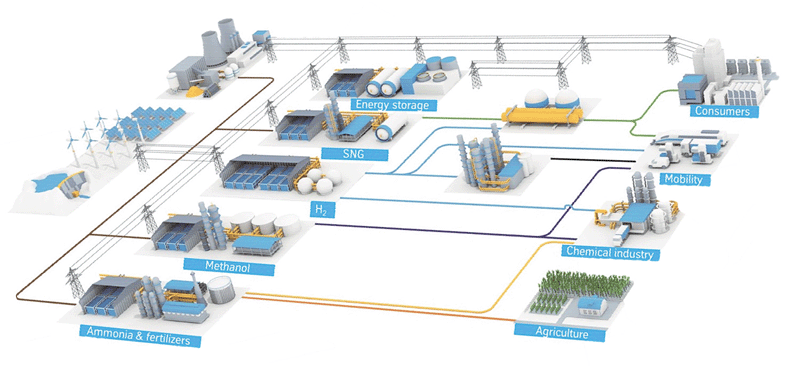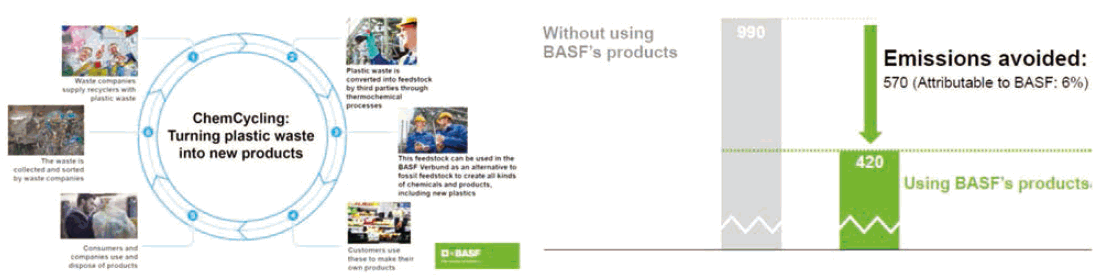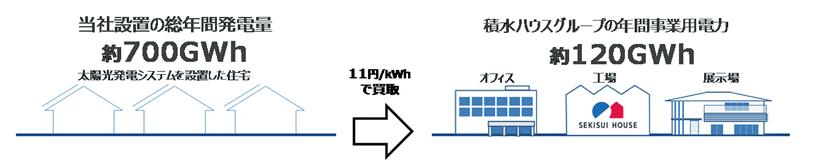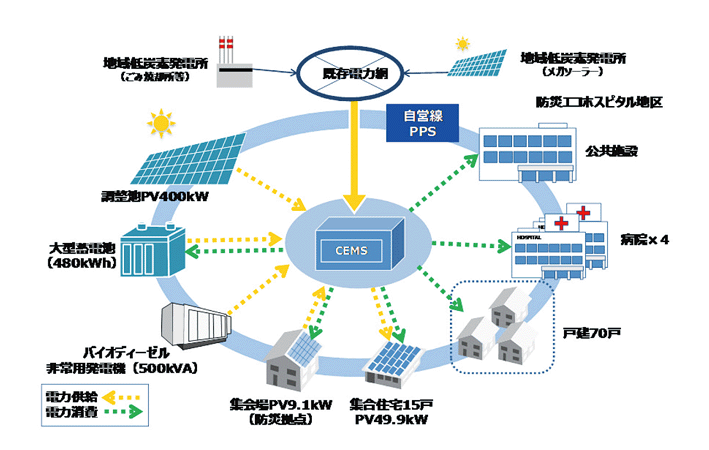第3節 データで見る各国エネルギー事情
これまで、主に地球温暖化問題に対する各国のコミットメントの内容とその進捗、およびその実現に向けたエネルギー政策の観点からの取組状況についてみてきました。
他方、エネルギー政策自体として達成すべき政策目標において、環境適合はその目標の一つに過ぎません。
エネルギー政策の要諦は、安全性(Safety)を前提とした上で、エネルギーの安定供給(EnergySecurity)を第一とし、経済効率性の向上(Economic Efficiency)による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に環境への適合(Environment)を図るため、最大限の取組を行うことです。こうした複数の価値の同時実現が求められるという点において、各国のエネルギー政策は共通しています。
このため、本節では、第2節で分析した英国・米国・フランス・ドイツを比較対象として、この3Eの観点から、我が国を含む各国のエネルギー情勢の横断比較をデータに基づき行います。
1.エネルギーの安定供給(Energy Security)
我が国は、現状ほとんどのエネルギー源を海外からの輸入に頼っているため、海外においてエネルギー供給上の何らかの問題が発生した場合、我が国が自律的に資源を確保することが難しいという根本的な脆弱性を有しています。
こうした脆弱性は、エネルギー消費の抑制のみで解決されるものではないことから、我が国は石油の代替を進め、リスクを分散するとともに、国産エネルギー源を確保すべく努力を重ねてきました。
また、このようなエネルギー源の安定調達に加え、継続的なエネルギー供給の確保という観点も重要です。近年、頻発する自然災害によるエネルギーインフラの毀損も増えていますが、ひとたび国内のエネルギー供給システムに問題が生じた場合には、経済活動や国民生活に多大な影響が及びます。
本節では、エネルギー源の安定調達の観点について「エネルギー自給率」及び「エネルギー輸入先の多様化度」の指標、継続的なエネルギー供給の確保の観点について「停電時間」の指標を用いて、国際比較を行います。
(1)エネルギー自給率
エネルギー自給率が低いということは、エネルギー資源を他国に依存しているということです。つまり、エネルギー資源の確保の際に国際情勢の影響を受けやすくなり、安定したエネルギー供給に懸念が生じる可能性が高まります。
自国内の化石資源が豊富であれば、化石燃料の依存度の如何はエネルギー自給率に中立的ですが、自国内の化石資源が乏しい国は、省エネの取組や非化石エネルギーの活用が進めば自給率は上昇します。
化石資源の有無は国によって状況が大きく異なることから、一律に水準を評価することはできませんが、ある程度のエネルギーの自給を実現することがエネルギーの安定供給に資すると考えられます。
主要国のエネルギー自給率を俯瞰すると、いずれも4~5割以上と高く、自国資源に乏しい日本の自給率の低さが際立っています。
米国はシェール革命により化石燃料(原油と天然ガス)の生産量が大きく増加し、さらに再生可能エネルギーも増加したことにより、エネルギー自給率は直近10年間で約20%上昇しており、この高い自給率傾向は当面継続すると考えられます。
英国は英領北海油田の開発により、かつては一次エネルギー自給率が100%を超え、エネルギー輸出国であったこともありましたが、英領北海油田の枯渇により原油生産量が減少を続け、自給率を下げてきているものの、現在でも自給率は約7割程度となっています。
フランスは電力供給の8割を原子力によって供給する構造となっています。原子力は、仮に海外からの調達が途絶した場合でも数年にわたって国内保有燃料だけで生産が維持できるため、化石に比してエネルギーセキュリティの改善に貢献することもあり、IEAにおいても自給率の計算において原子力を算入しています。このため、フランスの自給率は50%前後で安定して推移しています。
ドイツは、国内で産出される石炭の利用と原子力により4割程度の自給率でした。近年では、再生可能エネルギー導入促進政策により、再生可能エネルギーによる発電量の増加が自給率増加に寄与しているものの、他方で、原子力発電所の稼働停止を進めているため、結果として自給率は漸減傾向となっています。今後は、石炭火力からのフェーズアウトやロシアからの天然ガス調達の増加などが予定されており、自給率は更に低下していく可能性があります。
日本の自給率は、東日本大震災前は20%前後の水準でしたが、震災以降、原子力の発電量が減少したため、一次は6%まで悪化しました。近年は、固定価格買取制度の導入による再生可能エネルギーの発電量の増加や原子力発電所の再稼働、省エネルギーの進展などにより漸増傾向にありますが、未だ10%程度にとどまっています。
- 出典:
- IEA World Energy Balances を基に資源エネルギー庁作成
- 出典:
- IEA World Energy Balances を基に資源エネルギー庁作成
(2)化石燃料の輸入先の多様化度
(1)で示したとおり、我が国の自給率は先進国の中でも低い水準にあります。このような中、特定の国・地域に偏らずエネルギー資源の調達先を分散させることは、エネルギーセキュリティの強化に資すると考えられます。
他方、原油・天然ガス・石炭の3種のエネルギー源それぞれについて、評価対象国における輸入先の寡占度をHerfindahl-Hirschman Indexの手法を用いて算出しました。
加えて、当該寡占度を0から10の点数に換算23して評価しました(数値が大きいほど輸入先が多様化し、リスク量が少ない)。
なお、評価対象国の総合的なリスク評価は、原油・天然ガス・石炭のそれぞれで求められた点数に、化石燃料輸入に占めるそれぞれの燃料の輸入量のシェア(エネルギー量ベース)を乗じたものを合計して算出しました。
その結果、2014~2016年の評価において、評価の高い順からフランス、日本、ドイツ、英国、米国となりました。以降、その要因について見ていきます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
- 出典:
- IEA, Oil/Natutal gas/Coal Information database等より資源エネルギー庁作成
- 出典:
- OECDカントリーリスク評価等を基に資源エネルギー庁作成
フランスは2014~2016年において、輸入している化石燃料の6割を原油が、3割を天然ガスが、1割を石炭が占めています。原油については輸入先トップ3を合わせても約40%程度を占めるシェアに留まり、輸入先の多様化が図れているため高得点となっています。天然ガスについてはカントリーリスクの少ないノルウェー・オランダからの輸入が50%程度を超えているものの、輸入先の多様化という面で評価が下がりました。石炭においてはカントリーリスクの高いロシアや南アフリカなどのシェアが増加したため評価は低くなっていますが、石炭自身のシェアが10%程度と低く影響力が少ないため、総合評価は最も高くなっています。
【第123-1-6】フランスのカントリーリスク評価24
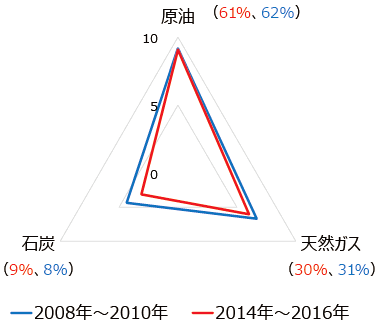
- (括弧内は化石燃料輸入量に占める当該燃料のシェア)
【第123-1-6】フランスのカントリーリスク評価(ppt/pptx形式:104KB)
- 出典:
- IEA, Oil/Natutal gas/Coal Information database等より資源エネルギー庁作成
- 出典:
- OECDカントリーリスク評価等を基に資源エネルギー庁作成
日本は2014~2016年において、輸入している化石燃料の5割を原油が、2割を天然ガスが、3割を石炭が占めています。原油については輸入先トップ3のカントリーリスクがすべてC以下となり、かつ輸入先トップ3のシェアが約70%と高く、評価点は相対的に低くなっています。また、2014~2016年にかけては、上位2か国(サウジアラビア・UAE)からの輸入量が60%を超え、依存度が高まっています。天然ガスについてはカントリーリスクの少ないオーストラリアからの輸入量を増やしており、かつ輸入先国が約20か国に上り、輸入先の多様化の面からも高い評価となっています。石炭についてはカントリーリスクの少ないオーストラリアからの輸入量が70%弱を占めておりますが、輸入先の多様化が図れておらず低い評価となりました。結果として総合評価はフランスに次ぐ2位となっています。
- 出典:
- IEA, Oil/Natutal gas/Coal Information database等より資源エネルギー庁作成
- 出典:
- OECDカントリーリスク評価等を基に資源エネルギー庁作成
ドイツは2014~2016年において、輸入している化石燃料の4割を原油が、3割を天然ガスが、3割を石炭が占めています。原油についてはカントリーリスクの高いロシアへの依存度が高いため、輸入先国が約30か国に上るものの評価点は低くなっています。天然ガスについても原油と同様にロシアの依存度が高く評価が低くなっております。石炭についてはカントリーリスクの低い米国からの輸入が増加したものの、ロシア依存度が上昇したため、評価は若干下がりました。結果として総合評価は3位となっています。
- 出典:
- IEA, Oil/Natutal gas/Coal Information database等より資源エネルギー庁作成
- 出典:
- OECDカントリーリスク評価等を基に資源エネルギー庁作成
英国は2014~2016年において、輸入している化石燃料の4割弱を原油が、5割弱を天然ガスが、2割を石炭が占めています。原油についてはノルウェーへの依存度が7割弱を占めていたものの、2014年・2015年にはアルジェリアやナイジェリアなどへの輸入多角化を進め、評価は改善しています。天然ガスについても原油と同様にノルウェーへの依存度が高く評価が低くなっております。石炭については輸入先トップ3が約75%を占めており、輸入先の多様化が図れておらず低い評価となりました。結果として総合評価は4位となっています。
- 出典:
- IEA, Oil/Natutal gas/Coal Information database等より資源エネルギー庁作成
- 出典:
- OECDカントリーリスク評価等を基に資源エネルギー庁作成
米国は2014~2016年において、輸入している化石燃料の4割強を原油が、3割を天然ガスが、3割弱を石炭が占めています。原油については2008~2010年にかけては輸入先トップ3のシェアが合わせて50%に満たず、輸入先の多様化が図れていましたが、2014~2016年にかけてカナダへの依存度が高まっており、評価は若干下がりました。天然ガスについては輸入量のほぼ全量をカナダに依存しており、輸入先多様化の面から評価は低くなりました。石炭についても8割弱をコロンビアのみから輸入しており、輸入先多様化の面から評価は低くなりました。結果として総合評価は5位となっています。
- 出典:
- IEA, Oil/Natutal gas/Coal Information database等より資源エネルギー庁作成
- 出典:
- OECDカントリーリスク評価等を基に資源エネルギー庁作成
(3)停電時間
1年間の需要家1軒あたりの平均停電時間(以下を「年間停電時間」という。)を見てみると、大規模な自然災害等による一時的な数値の上昇を除くと、日本とドイツが最も短くて10~20分程度、フランス及び英国が60~70分程度、米国はバラツキが大きいもののいずれも100分超という状況です。エネルギーの利用者から見た安定供給の質は、日本は世界的に見ても高いことが伺えます。
米国は2012年に大きな停電を経験しています。これはハリケーン・サンディによる地下変電施設の浸水及び送電線の倒壊で、東部一帯で800万世帯・事業所が停電したためです。また、次に大きな停電となっている2011年では、送電網で発生したトラブルによりカリフォルニア州南部とアリゾナ州、メキシコにまたがる広範囲で140万世帯に停電が発生しました。
日本では、2010年度に東日本大震災が起こり、その余震による停電(計画停電を含む)が発生しました。他方、2010年度と2011年度以外の年間停電時間の平均は約20分であり、ほとんど停電が起きていないことがわかります。
フランスでは2009年に暴風雨に見舞われ南部で100万世帯以上が停電しました。2009年以外の年間停電時間の平均は67分であり、日本の約3倍となっています。
英国では、大きな停電は近年起きていませんが、年間停電時間の平均は73分となっており、フランスと同程度となっています。
ドイツは日本と同様、年間停電時間が平均で約20分と安定的に供給されています。
- 出典:
- 海外電気事業統計2017, 海外電力調査会, 電気事業のデータベースより資源エネルギー庁作成
2.経済効率性(Economic Efficiency)
ここでは、小売全面自由化から3年が経過し競争が進展している電気料金の状況を通じて、経済効率性見ていきます。
(1)電気料金(全体)
各国の電気料金(全体平均)を比較すると、ドイツでは1990年代からすでに高い価格水準でしたが、近年では突出して高くなっています。英国は2000年代中頃までは日本やフランスに比べ安い価格でしたが、近年では同水準となっています。また米国は、1990年代から一貫して低い価格を維持しています。なお、本節では購買力評価を用いて価格水準を比較しています。
- 出典:
- IEA Energy Prices and taxes を基に資源エネルギー庁作成
(2)電気料金(家庭用と産業用の比較)
家庭用電気料金に関しては、長期的にも短期的にもドイツが最も高く、近年では日本より6割高い価格となっています。また、直近では日本、英国、フランスが同水準の価格であり、米国は日本の約半分と最も安くなっています。
産業用電気料金では、日本とドイツが同水準で最も高くなっています。続いて英国、フランスの順に安く、家庭用電気料金と同様、最も安いのは米国となっており、日本とドイツの約半分の価格となっています。
- 出典:
- IEA Energy Prices and taxesを基に資源エネルギー庁作成
【第123-2-3】主要国の電気料金の違いと消費比率の違い(2016年)
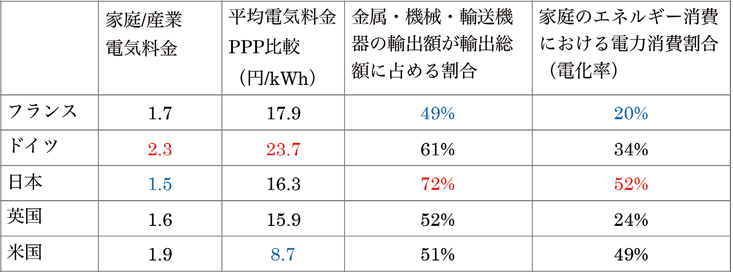
- 出典:
- IEA Energy Prices and taxes、OECDstatを基に資源エネルギー庁作成
家庭用電気料金と産業用電気料金を比べると、どの国においても家庭用電気料金の方が高くなっています。
また、家庭用電気料金が産業用電気料金に比べ、どのくらい高い水準かを見てみると、ドイツが2.3倍と最も高くなっており、続いて米国が1.9倍、最も低いのは1.5倍の日本となっています。
日本では、電力を多く消費する製造業(金属・機械・輸送機器)が輸出額に占める割合が5か国中最も高くなっているため、産業用電気料金を抑えることが国際競争力の観点からも重要となります。一方で、家庭の電化率が5か国中で最も高く、家庭用電力料金を抑えることも重要であり、電気料金全体を下げていくことが大切となります。
3.環境適合(Environment)
パリ協定では、各国は、温暖化対策についての自国の貢献をNDCとしてコミットし、ここで自ら設定した目標の達成に向けた政策措置を実施していきながら、削減目標の進捗を評価していく「プレッジ&レビュー」方式が採用されています。
第2節では、こうしたパリ協定の性質を踏まえ、各国の誓約(プレッジ)に向けたGHGの削減の進捗と各国の政策的な取組状況について見てきました。
他方、各国のプレッジの水準をどのように設定するかは各国の主体性に委ねられているため、プレッジ&レビューの進捗を確認するだけでは、各国の間の脱炭素化の進展度合いを横断的に比較することはできません。
そこで、ここでは先進国が排出するGHGの大半を占めるエネルギー起源CO2について、2016年を対象に、国民1人当たりのCO2排出量という観点で比較を行うとともに、その多寡を左右する要因の分析を行うこととします。
(1)国民1人当たりCO2排出量
OECD加盟諸国26の国民1人当たりCO2排出量について、排出の少ない国から並べてみると、今回取り上げた先進主要国の中では、OECD35ヶ国の中、フランスが5位でトップ、続いて13位に英国と比較的排出量が少なく、ドイツと日本は排出量水準がほぼ同じでフランスの約2倍、米国は35か国中34位と低迷しており排出量はフランスの約3倍と、先進諸国の中でも大きな開きがあることが見て取れます。
なお、35か国の平均値は7.6トン/人・年であり、日本、ドイツ、米国は当該平均値を下回っています。国民1人当たりCO2排出量の多寡を決める要因は、後述するとおり複数の要因があること、当該複数要因は国情によって左右されることもあるため、当該順位のみをもって単純な評価はできませんが、排出量の相対的に多い国において、何処に改善の余地が大きいのかを確認することは、以後のGHG削減に向けた政策措置において重点を置くべきポイントを見極めるのに有用です。
次項では、当該排出量の多寡を左右する要因を分解して、より詳細に見ていきます。
- 出典:
- IEA CO2 Emissions from Fuel Combustion, World Energy Balances、OECD stat等より資源エネルギー庁作成
(2)需要サイドと供給サイドからみたCO2排出
国民1人当たりのCO2排出量は、国民1人当たりの活動量(GDP等)、当該活動1単位を行う為に要するエネルギー消費量(エネルギー消費効率)、および1単位のエネルギー消費に対してなされるエネルギー供給に伴い生じるCO2の排出量(エネルギー供給の低炭素度)に分解できます。
このうち、国民1人当たりの活動量は、経済発展の進展度合い等によって決定されるため、GHG削減にあたっては、他の2つ、即ちエネルギー消費効率とエネルギー供給の低炭素度の2点を如何に改善していくかが重要となります。
日米英独仏の5か国の国民1人当たりCO2排出量を、エネルギーの低炭素度、エネルギーの消費効率、1人当たり活動量に分解し、前者について、エネルギー低炭素度は更に電力と非電力に分解、エネルギーの消費効率については更に運輸・家庭・産業の各部門に分解して、それぞれの項目のパフォーマンスを他国と水準比較し、これを0から10のスコアに変換して分析を行いました(スコアは10がもっとも効率が良い/CO2排出量が少ない。5が全体平均。)。
フランスは、エネルギー供給の低炭素度、中でも電力部門の低炭素度が他国に比べて抜きんでて高く、結果として総合スコアを大きく引き上げています。これは、電力供給の9割が非化石電源(原子力約7割、再生可能エネルギー約2割)であることが主な要因です。また、フランスの特徴は、エネルギー低炭素度及びエネルギー消費効率のすべての項目に亘ってスコアがよく、バランスが取れているということです。こうしたバランスが、OECD諸国の中でもフランスの総合パフォーマンスを高いものとしていると言えます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
- 出典:
- IEA CO2 Emissions from Fuel Combustion, World Energy Balances、OECD stat等より資源エネルギー庁作成
供給サイドと需要サイドのバランスの良さという点で、英国も共通しています。
ドイツは需要サイドの産業・運輸部門の効率の良さに強みがありますが、他方、家庭部門(建築)の効率や、石炭に依存(約4割)している電力部門の低炭素度の低さに課題があります。
日本は、家庭・産業・運輸いずれの需要部門においてもエネルギー消費効率は世界トップクラスであり、総合スコアを大幅に引き上げています。他方、供給側のエネルギーの低炭素度は各国に比して低い水準となっており、日本の課題はこのエネルギー低炭素度の改善にあることがわかります。なお、非電力の低炭素度は、GDPに占める製造業の比率や、製造業の中でも原料炭を使う鉄鋼業やエネルギー多消費の化学・窯業などの比率が高いほど低スコアになることから、こうした点を考慮したうえで評価する必要があります。
米国は全体的にOECD諸国の平均以下となっていますが、特に家庭部門と運輸部門のスコアが悪く、エネルギー消費効率の改善が米国の課題であることが見て取れます。
(3)電源構成
前項では、日本のエネルギー低炭素度、中でも電力部門の低炭素度の改善が、国民1人当たりCO2削減にあたって重要であることがわかりました。ここでは、電力部門の低炭素度を左右する電源構成について、各国との比較を行います。
フランスの電源構成は原子力発電の比率が73%と太宗を占め、火力発電への依存度が10%以下と、最も低炭素化が進んでいます。
英国では、再生可能エネルギーと原子力がそれぞれ2割強であり、この結果、非化石電源が約半分を占めています。また、残りは火力発電で供給していますが、火力発電のほとんどは天然ガスによるものであり、石炭火力の比率が低い(9%)ことも低炭素化に貢献しています。
米国は、原子力が20%、再生可能エネルギーが15%であり、非化石電源比率は35%と5か国中2番目に低くなっていますが、火力発電に占める石炭火力とガス火力の比率がそれぞれ約半分ずつとなっており、ドイツよりもガス化が進んでおり、結果として電力の低炭素度は5か国中3番目となっています。
ドイツでは、再生可能エネルギーの比率は水力も含め29%と5か国の中で最も多くなっていますが、原子力が13%であるため、非化石電源比率は42%となっています。また、57%を占める火力発電の約7割が石炭火力となっているため、電力供給の低炭素度は5か国中4位にとどまっています。
日本では、再生可能エネルギーの導入促進策を受けて、再生可能エネルギーの比率は拡大傾向にありますが、東日本大震災以降、原子力発電の大半が停止しており、非化石電源比率が最も低く、電力供給の低炭素度が5か国中最低となっています。今後、再生可能エネルギーの更なる大量導入と原子力発電の再稼働が進展していくことによって、非化石電源比率を高めていくことが、CO2削減の観点から極めて重要であることがわかります。
- 出典:
- IEA World Energy Balancesより資源エネルギー庁作成
COLUMN
再生可能エネルギー27の導入に係る状況
再生可能エネルギーの導入可能量は自然条件・土地条件に大きく左右されます。例えば、国土面積が大きく、未利用地が豊富な国の方が、太陽光パネルなどを大規模に設置しやすいということがいえます。
各国の再生可能エネルギー導入量を機械的に国土面積で除して比較すると、日本は世界第8位の導入量であり、比較的高い順位となっています。
【第124-0-1】面積あたりの再生可能エネルギー導入量(上位30か国:2016年)
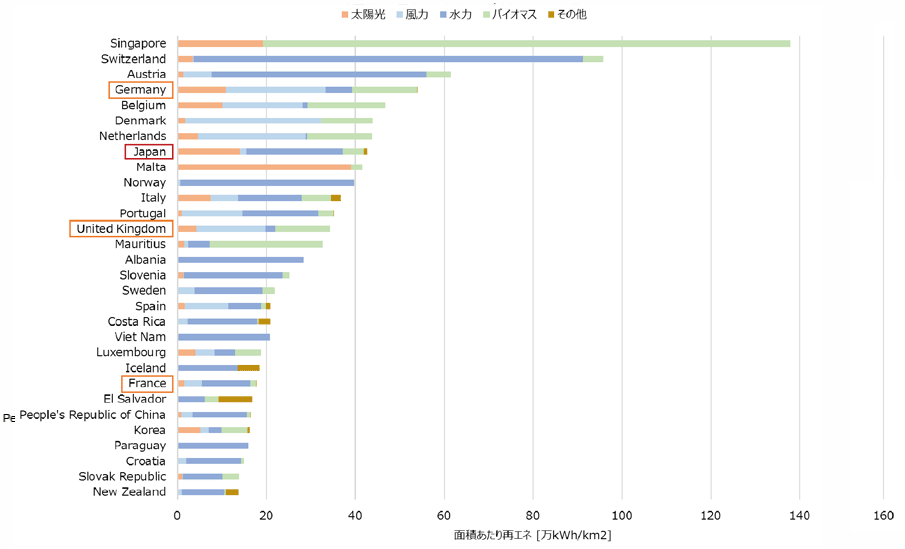
- 出典:
- IEA CO2 Emissions from Fuel Combustion等より資源エネルギー庁作成
【第124-0-2】同様の国土面積あたりの電力需要と再生可能エネルギー比率のイメージ
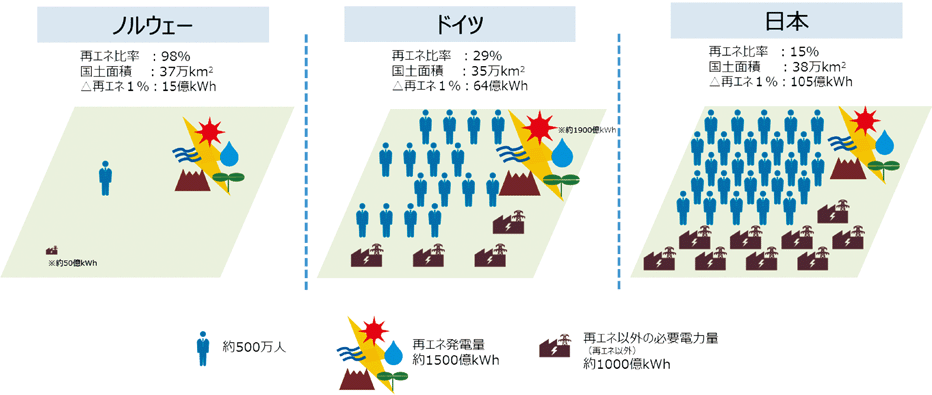
- 出典:
- IEA, World Bank, 総務省統計等各種データより資源エネルギー庁作成
このように、単位面積当たりの再生可能エネルギーの導入量は世界的に見ても高い水準にある日本ですが、再生可能エネルギーの電源構成に占める比率は相対的に低い水準にあります。これは、再生可能エネルギーの単位面積当たりの導入量が同じ水準であったとしても、単位面積当たりの電力需要が多ければ、結果として再生可能エネルギー比率が低く出てしまうことが原因です(第124-0-2)。
例えば、ノルウェーやドイツ、カリフォルニアは日本と同様の土地面積を有していますが、人口密度や産業活動量の違いから単位面積当たりの電力の需要量が大きく異なります。このため、単位面積当たりの再生可能エネルギー導入量は、日本はドイツに次ぐ高い水準であり、カリフォルニアは日本の約半分にとどまっていますが、日本の単位面積当たりの電力需要の多さ(ドイツの約1.6倍、カリフォルニアの約5倍、ノルウェーの約7倍)のため、結果として日本の再生可能エネルギー比率は相対的に低い水準となります。
見方を変えると、再生可能エネルギー比率を1%増やすにためには、日本はノルウェーの7倍の量の再生可能エネルギーを導入しなければならないということであり、電力の需要密度(以下、「需要密度」という。)の高い日本において再生可能エネルギー比率を高めることの難しさがわかります。
- 出典:
- IEA、EIA、World Bank、総務省統計等各種データより資源エネルギー庁作成
同様の観点で、太陽光発電の導入が進んでいる九州地方について見てみると、土地面積が近似し、かつ、非常に高い再生可能エネルギー比率を実現しているアルバニア(100%)やデンマーク(60%)と比べて、単位面積当たりの再生可能エネルギー発電量は決して遜色がない水準となっています。
他方、九州地方の再生可能エネルギー比率が15%と相対的に低い水準となっているのは、単位面積当たりの需要密度がアルバニアの約14倍、デンマークの約3.5倍と極めて高いことが原因です。
- 出典:
- IEA World Energy Balances, 総務省統計等より資源エネルギー庁作成
以上のように、電力供給における再生可能エネルギー比率は、再生可能エネルギーの導入量が国土面積による制約を受けること、需要密度の違いによって再生可能エネルギー導入量に対する感応度が異なることから、こうした国情を踏まえずに単純に再生可能エネルギー比率を各国と横断的に比較することは、エネルギーの脱炭素化に向けた取組への評価をミスリードする恐れがあります。
このような観点から、需要密度の違いを勘案しながら、各国との再生可能エネルギー比率の横断比較ができるよう分析したのが(第124-0-4)です。
黒の破線は、日本の面積当たりの再生可能エネルギー導入量を固定して、仮に日本の需要密度が異なった場合の再生可能エネルギー比率を示したものです。
これを見ると、需要密度が均等化された後の日本の再生可能エネルギー比率より高い再生可能エネルギー比率の国は、スイスやドイツといった少数の国に限られることがわかります。
【第124-0-5】日本の需要密度で補正した再生可能エネルギー比率(OECD諸国)
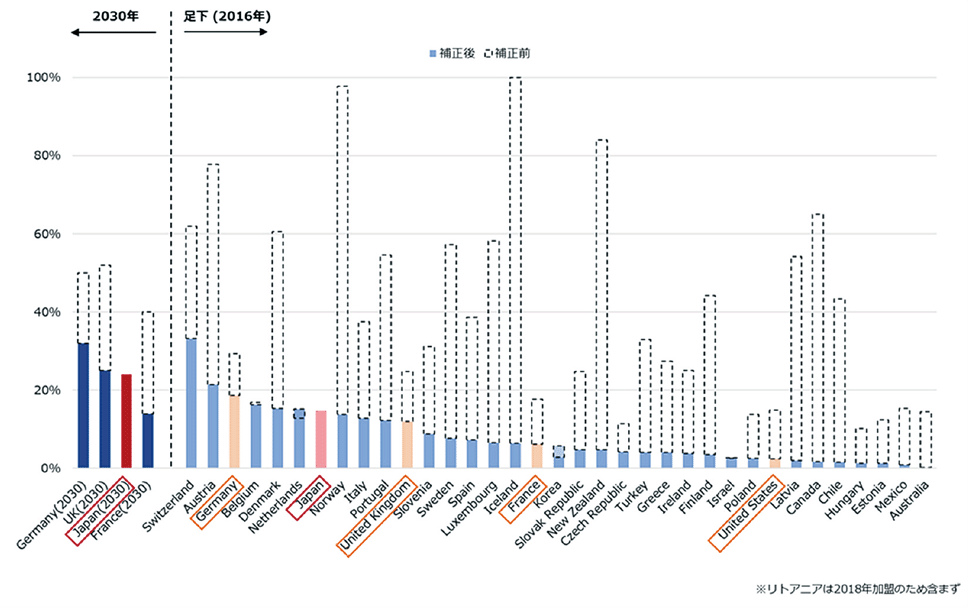
- 出典:
- IEA World Energy Balances, 総務省統計等より資源エネルギー庁作成
また、日本が示しているエネルギーミックスにおける2030年度の再生可能エネルギー比率22~24%という水準を同様に見てみると、英独仏の2030年の再生可能エネルギー比率目標と比較しても遜色ない水準となっています。
他方、逆に各国が日本と同様の需要密度であったと仮定した場合の再生可能エネルギー比率で比較すると、OECD諸国内で日本の再生可能エネルギー比率は第7位となります。
【第124-0-6】OECD諸国の再生可能エネルギー比率(日本の需要密度での補正前後)
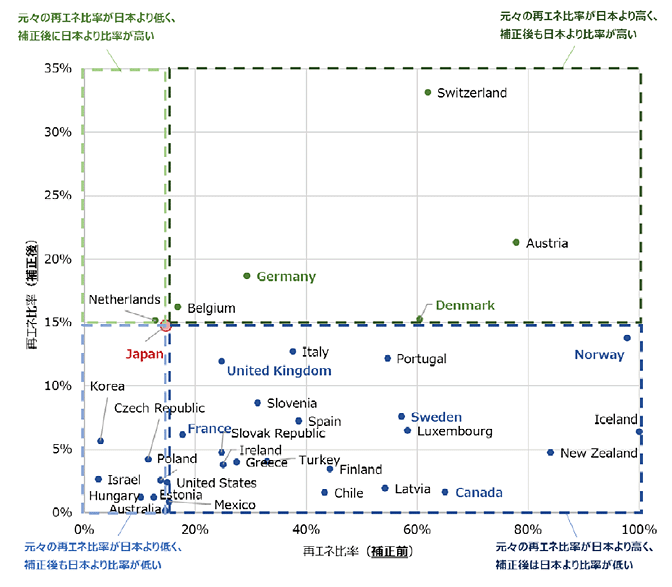
【第124-0-6】OECD諸国の再生可能エネルギー比率(日本の需要密度での補正前後)(ppt/pptx形式:289KB)
- 出典:
- IEA World Energy Balances, 総務省統計等より資源エネルギー庁作成
以上をまとめると、再生可能エネルギーの導入量はいずれの国も自然環境(土地面積等)の制約を受けるのに対して、各国の土地面積あたりの需要密度は大きくことなるため、再生可能エネルギー比率を各国比較するにあたっては、こうした国情の違いを踏まえて行うことが重要です。
土地面積当たりの再生可能エネルギー導入量が相対的に多いものの、需要密度が各国に比して極めて高い日本においては、再生可能エネルギー比率を引き上げるには再生可能エネルギーの大量導入が必要となりますが、大量導入が進むほど、系統制約や調整力の確保といった課題が生じてきています。
パリ協定を踏まえたエネルギー転換・脱炭素化を実現するためには、こうした再生可能エネルギー導入にあたっての諸課題に引き続き正面から取り組むとともに、再生可能エネルギーのみならず、水素やカーボンリサイクル、原子力などのあらゆる脱炭素化の選択肢に取り組んでいくことが重要と言えます。
COLUMN
グローバル企業のGHG削減に向けた様々な取組
需要側の企業においても、それぞれの事業形態や状況に応じた形でGHG排出削減を進めています。再生可能エネルギー由来の電力の調達、水素の利活用、CO2の再利用といった様々な取組が挙げられ、ここではグローバル企業の取組の一例を紹介します
鉄鋼:ティッセンクルップ社(ドイツ):再生可能エネルギー由来の水素、コークス炉のCO2から化学原料を組成
自社の風力発電・太陽光発電から水素を組成。当該水素を活用して、コークス炉から発生するCO2を化学原料(メタン、アンモニア等)に転換する実証事業を進めています。
- 出典:
- ティッセンクルップ・ウーデ・クロリンエンジニアズ
化学:BASF社(ドイツ):自社製品の世界市場への展開、化学原料のリサイクルを通じたCO2削減
自社製品の世界市場への展開、プラスチック廃棄物から新製品を組成するケミカルリサイクルを通じて、排出削減に貢献するプロジェクトを進めています。
- 出典:
- BASF社
家電:Signify社(オランダ):カーボンニュートラルと廃棄物ゼロに向けた取組
2020年までにカーボンニュートラルと廃棄物ゼロに向けた取組を進めています。電力については、中東での太陽光発電、米国での風力発電の建設などを通じ2020年に再生可能エネルギーからの100%調達を目指しています。また、2020年までに廃棄物ゼロを目指しています。こうした環境の下で製造されるLEDの普及を通じて、世界のエネルギー消費の削減に貢献することとしています。
- 出典:
- Signify社
不動産:積水ハウス(日本)
2050年までに住宅のライフサイクルでの脱炭素を目指しネット・ゼロエネルギーハウスの普及を進めています。また、自社が販売した太陽光発電を設置した住宅からFIT終了後の電力を買取り、自社の事業用電力として利用することで2040年までにRE100を目指しています。(第124-0-10)。
日本では防災も重要となり、自営線を設置し、太陽光発電、大型蓄電池、非常用発電機を組み合わせ、普段は再生可能エネルギーの地産地消、非常時にも停電しない街を実現しています(第124-0-11)。
- 出典:
- 積水ハウス
- 出典:
- 積水ハウス
- 23
- カントリーリスクのウェイト値は、(株)日本貿易保険が海外投資保険の保険料率(各国のリスクをAからGまで評価・分類するOECDカントリーリスク専門家会合が定める国カテゴリーごとに設定されたもの)を利用。点数換算は、数値を偏差値に変換し、偏差値30が0、偏差値70が10となるように正規化して点数を算出。点数が10に近づくほどリスクが少なく、輸入先が多様化していることを示しています。
- 24
- 各エネルギー源の横にある数字は、化石燃料の輸入量を100%とした時に、各エネルギー源の輸入量がどれだけを占めているのかを示しています。赤字は2014年〜2016年の平均値を、青字は2008年〜2010年の平均値を算出しています。他国についても同様です。
- 25
- カントリーリスクはA〜Hまでの8段階で設定され、Aに近づくほどリスクが少ないとされています。
- 26
- 本節では、データ取得の関係から2018年に加盟したリトアニアを除く35ヶ国を扱うこととしています。
- 27
- 本コラムにおける再生可能エネルギーは、再生可能エネルギー電気を示しています。