第2節 重要インフラの緊急点検とその対策パッケージ
前節の通り、平成30年7月豪雨、平成30年台風第21号、平成30年北海道胆振東部地震をはじめとする自然災害により、ブラックアウトの発生、空港ターミナルの閉鎖など、国民の生活・経済に欠かせない重要なインフラがその機能を喪失し、国民の生活や経済活動に大きな影響を及ぼす事態が発生しました。これらの教訓を踏まえ、重要インフラが、自然災害時にその機能を維持できるよう、平時から万全の備えを行うことが重要です。
本節では、前節の災害を踏まえた重要インフラの緊急点検とその対策パッケージについてまとめます。
1.重要インフラの緊急点検
(1)政府における重要インフラの緊急点検
今般の災害による国民生活や経済活動への影響に鑑み、電力等の生活を支える重要なインフラが、あらゆる災害に対し、その機能を維持できるよう、2018年9月21日に開催された「重要インフラの緊急点検に関する関係閣僚会議」において、全国で緊急に点検を行うことが決定されました。
この決定を踏まえ、政府は、全国で132項目の緊急点検を実施し、点検結果と対応方策をとりまとめました。
【第132-1-1】政府における重要インフラの緊急点検の実施概要
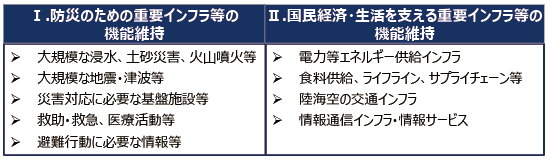
【第132-1-1】政府における重要インフラの緊急点検の実施概要(ppt/pptx形式:48KB)
- 出典:
- 重要インフラの緊急点検に関する関係会議資料を基に資源エネルギー庁作成
(2)インフラの総点検結果について
前述の132項目の点検項目のうち、電力と燃料分野に関する項目については、経済産業省において以下の通り点検を行いました。
【第132-1-2】重要インフラの緊急点検の結果及び対応方策一覧(※電力、燃料分野)
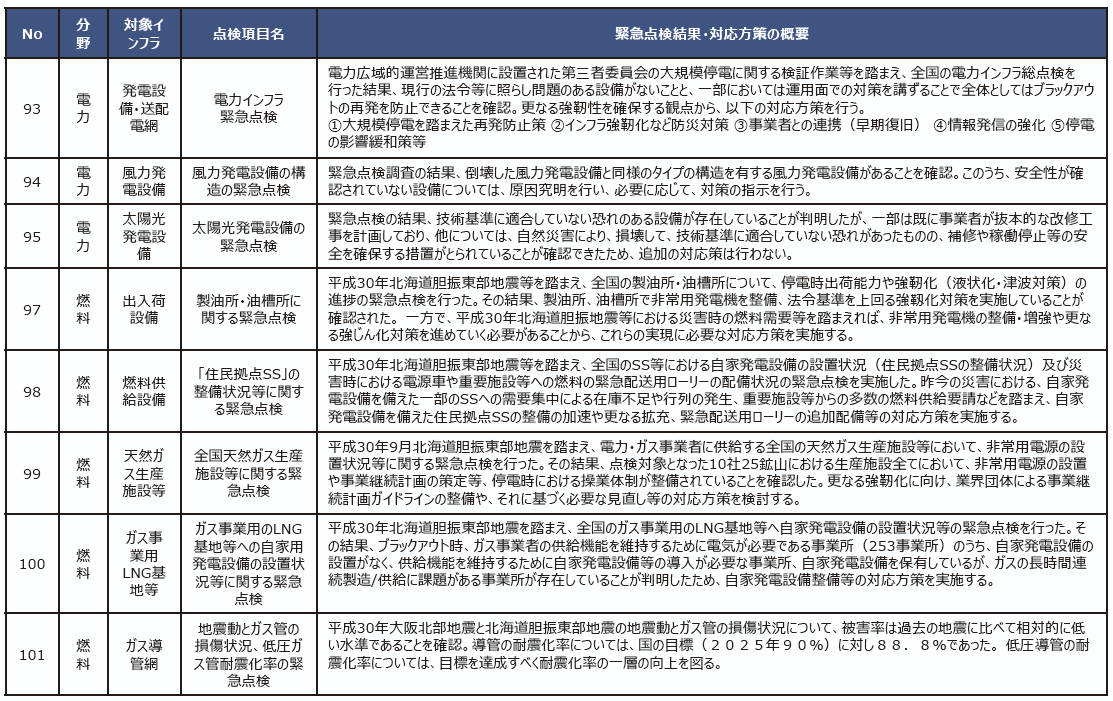
【第132-1-2】重要インフラの緊急点検の結果及び対応方策一覧(※電力、燃料分野)(ppt/pptx形式:63KB)
- 出典:
- 重要インフラの緊急点検に関する関係会議資料を基に資源エネルギー庁作成
【第132-1-3】インフラの総点検結果の概要
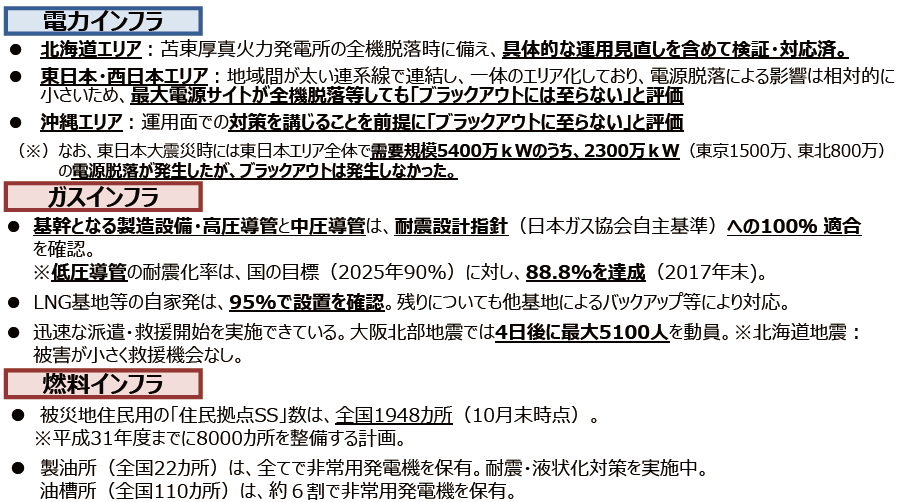
【第132-1-3】インフラの総点検結果の概要(ppt/pptx形式:58KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
その結果、一定条件下において、東日本・西日本エリアでブラックアウトに至らないことが確認されました。電力、ガス、燃料インフラにおける点検結果は以下の通りです。
①電力インフラ
前述の「重要インフラの緊急点検に関する関係閣僚会議」での決定を受け、電力インフラのレジリエンスを強化し、停電の早期復旧に向けた取組や国民への迅速かつ正確な情報発信等、災害に強い電力供給体制を構築するための課題・対策を議論するべく、2018年10月9日に総合資源エネルギー調査会 電力・ガス基本政策小委員会と、産業構造審議会 電力安全小委員会の下に、合同ワーキンググループとして「電力レジリエンスワーキンググループ」が設置されました。
【第132-1-4】電力レジリエンスワーキンググループの目的及び概要
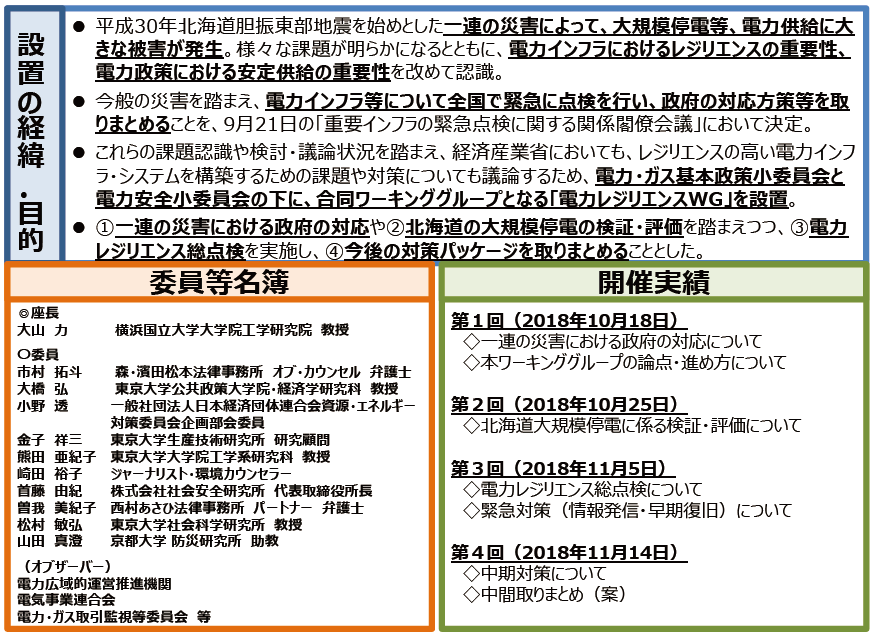
【第132-1-4】電力レジリエンスワーキンググループの目的及び概要(ppt/pptx形式:64KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
電力インフラの総点検については、電力レジリエンスワーキンググループにおいて、電力会社等からの報告を受け、審議・評価を行いました。その内容は以下の通りです。
(ア)各エリアにおける最大電源サイト脱落の点検
検証の結果、東日本エリア、中西日本エリア、沖縄エリアについて、年間を通じた最過酷断面で最大電源サイトが脱落した場合においても、必要に応じて運用対策等を実施することにより、今般の事案のような周波数低下による「ブラックアウトには至らない」ことが確認されました。
各エリアにおける具体的な検証結果は以下の通りです。
- (A)北海道エリア
- 広域機関の検証委員会において、現在稼働中の最大サイトである苫東厚真発電所の全機脱落時に備え、2018年度冬季に関し、具体的な運用の在り方を含めてブラックアウトの再発防止策を検証済みです。また、2019年2~3月の石狩湾新港LNG火力発電所や新北本連系設備の運転開始後に、苫東厚真発電所が全機脱落した場合に加え、泊原子力発電所の全機脱落ケースについても、検証を実施しました。殆どの過酷断面でブラックアウトしないことが確認されましたが、泊原子力発電所の全機脱落時の一部のケースにおいてブラックアウト防止のための追加的な対策が必要であることが確認されました。このことから、泊原子力発電所の再稼働時期の目途が実際に立った時点で、改めてシミュレーションを行いつつ、必要な対策の検討を行い、所要の措置を講ずることが必要不可欠であると検証委員会が提言を行いました。
- (B)東日本・中西日本エリア
- それぞれのエリアについて、最過酷断面において最大電源サイト(東日本:富津火力発電所、中西日本:川越火力発電所)が脱落した場合においても、地域間連系線による緊急融通や周波数低下リレー(UFR)による負荷遮断等の周波数維持装置の動作により、「ブラックアウトには至らない」ことが確認されました。
- (C)沖縄エリア
- 最過酷断面において最大規模の発電所が脱落した場合には、対策が無いとブラックアウトに至ることが否定できないものの、運用面での対策(安定化装置/周波数低下リレー(UFR)の整定値(負荷遮断量及び時限)の見直し、太陽光最大出力時には最大火力サイトの出力を電源持ち替えにより抑制)を講じることを前提に「ブラックアウトに至らない」と評価できることが確認されました。なお、運用面での対策については既に実施済みです。
(イ)大規模電源サイト等に近接する4回線事故の点検
平成30年北海道胆振東部地震における送電線4回線(N-4)事故は、全て、地震による揺れで送電線と鉄塔が接近し、設備を通じて地面に電流が流れたことで遮断機が作動し、一時的に電力供給が停止したことが原因であることが検証委員会で確認されているところ、北海道エリアについては必要な対策を講ずることで「ブラックアウトに至らない」と評価されました。
【第132-1-5】道東エリアにおける送電線事故の状況
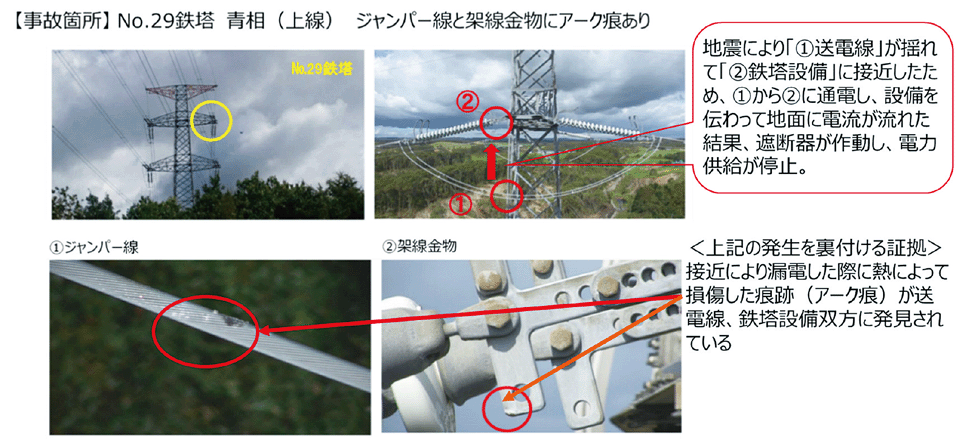
【第132-1-5】道東エリアにおける送電線事故の状況(ppt/pptx形式:1,386KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
また、同ワーキンググループの第3回において、東日本エリア、中西日本エリア、沖縄エリアにおいて同様の事象が発生した場合においても「ブラックアウトに至らない」ことが確認されています。各エリアにおける検証結果は以下の通りです。
- (A)北海道エリア
- 平成30年北海道胆振東部地震の際、27.5万V以下の電圧領域においてN-4事故が発生したことを踏まえ、検証委員会や第2回電力レジリエンスワーキンググループの検証・議論において、北海道電力により、重要変電所の近傍における送電線の稠密地帯等において、適切な再発防止策を検討する必要があるとされており、エリア内の他の重要変電所と隣接する送電線も含めて必要な対策を講じることで「ブラックアウトに至らない」と評価されました。
- (B)東日本・中西日本エリア
- 両エリアにおいては、最上位の基幹送電線の電圧が、北海道エリアが27.5万Vなのに対し、50万Vで構成されています。50万V送電線は、(a)送電線と鉄塔設備までの距離が約2倍であること、(b)送電線の重さが約3~7倍であることから、同様の縦揺れが生じても裕度があると考えられるため、N-4事故が発生する蓋然性が低いと評価されました。その上で、仮に50万Vの主要送電線でN-4事故が発生した場合でもブラックアウトが発生しないことも確認済みです。
- (C)沖縄エリア
- 主要送電線でN-4事故が発生しても、代替ルートが確保されており、「ブラックアウトに至らない」と評価されました。
(ウ)電気設備に関する点検
- (A)火力発電設備
- 火力発電所の耐震設計規程(JEAC3605)等への準拠状況を点検した結果、火力発電設備が確保すべき耐震性である、「一般的な地震動に際し個々の設備毎に機能に重大な支障が生じないこと」が確認されました。
- (B)送電設備・配電設備・変電設備
- 災害発生地域等における設備の健全性や、浸水可能性のあるエリアに設置された設備の有無及び対応状況の点検を行い、健全性に問題のある設備がないことや適切な対応がとられていることが確認されました。
②都市ガスインフラ
前述の「重要インフラの緊急点検に関する関係閣僚会議」を受け、都市ガスインフラについては、経済産業省の「産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 ガス安全小委員会」において、緊急点検が実施されました。
具体的には、停電時のLNG基地等における自家発電設備の設置状況に関する全国273社への調査や、情報発信の状況調査を行いました。
(ア)設備
基幹となる製造設備・高圧導管と中圧導管は、耐震設計指針(JGA自主基準)への100%適合が確認されました。
ガス事業用のLNG基地等への自家発電設備の設置状況等については、平成30年10月15日~10月26日までの間、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者、ガス製造事業者、ガス小売事業者の合計273社にアンケートを実施しました。その結果、都市ガスの供給継続に電気が必要である事業所253ヵ所のうち240ヵ所(95%)で自家発電設備の設置が確認されました。残り13ヵ所のうち11ヵ所は他基地によるバックアップにより対応、2ヵ所自家発電設備等を導入する方針です。また、自家発電設備を保有している事業所240ヵ所のうち、ガスを長時間連続して製造・供給することに課題がある事業所は22ヵ所あることが確認され、自家発電設備等の更新等により対応する方針です。
低圧導管の耐震化率は、ガス安全高度化計画等の目標(2025年90%)に対し、2017年末時点で88.8%を達成しており、前倒し達成は確実な状況であることが分かりました。
第17回ガス安全小委員会(2018年3月6日)において導入された、新たな緊急停止判断基準の有効性の確認を目的に、大阪府北部地震及び北海道胆振東部地震における揺れの大きさ(SI値)と被害率の相関を点検したところ、大阪・北海道の各地震とも、被害率は、過去の地震に比べて相対的に低い水準であったことが確認されました。
【第132-1-6】地震動とガス導管の損傷状況
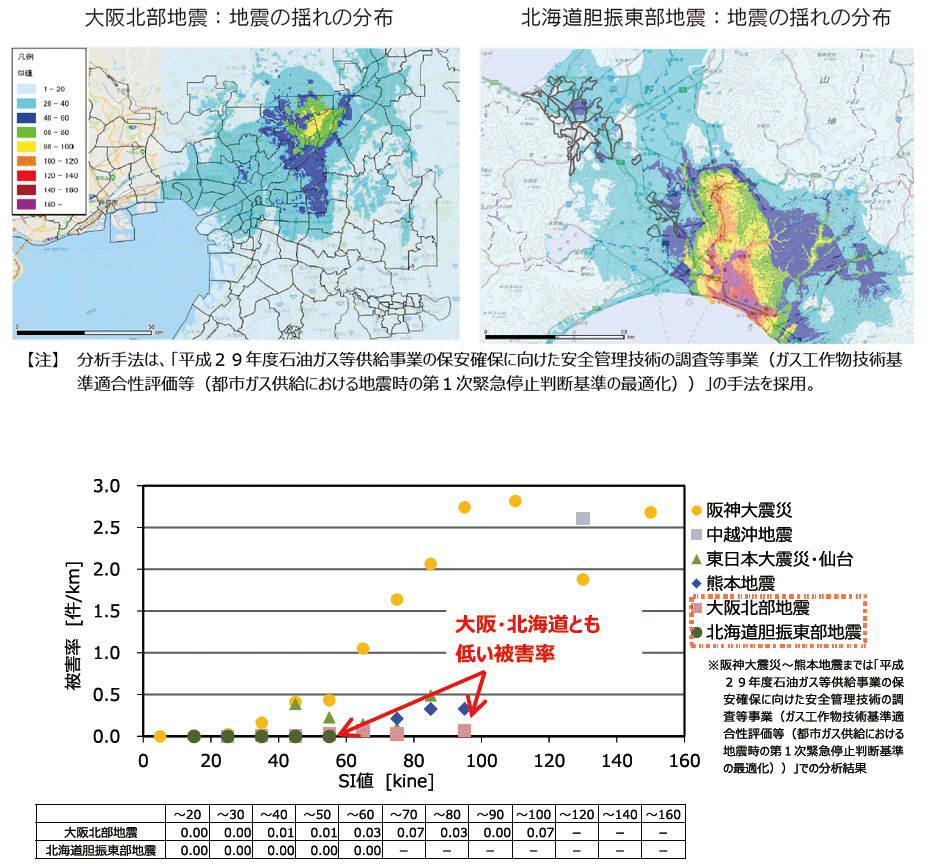
【第132-1-6】地震動とガス導管の損傷状況(ppt/pptx形式:2,943KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
(イ)連携
2016年4月14日に発生した熊本地震では、他ガス会社の連携に際し、最大4,600人集まるのに10日間を要しましたが、大阪北部地震では、4日間で最大5,100人が集まりました。このことから、迅速な派遣、救援開始を実施できていることが分かりました。
(ウ)情報発信
例えば大阪ガスでは、「復旧見える化システム」等、被災地域の復旧進捗をわかりやすく表示する様々な工夫が行われています。
他にも、企業は概ねHP、SNS、TV等による情報発信を実施していますが、手法には改善余地があることが分かりました。
③燃料インフラ
前述の「重要インフラの緊急点検に関する関係閣僚会議」を受け、主に石油、天然ガス等の燃料については、経済産業省において「災害時の燃料供給の強靭化に向けた有識者会議」を開催しました。同会議では、燃料供給インフラの緊急点検を実施するとともに、今後の対応について検討を行いました。
石油、ガス等の燃料については、主に出荷拠点(製油所・油槽所)、販売拠点(SS)・輸送、エネルギー生産施設(天然ガス生産施設・石炭炭鉱)について点検を行いました。その結果は次の通りです。
【第132-1-7】災害時の燃料供給の強靭化に向けた有識者会議の目的及び概要
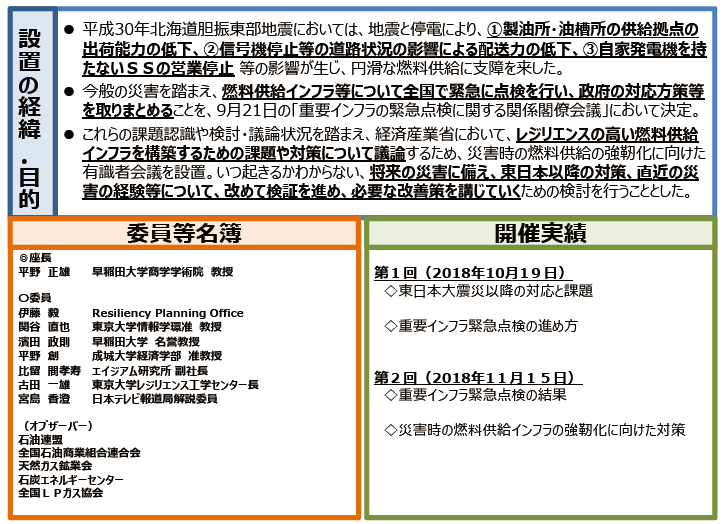
【第132-1-7】災害時の燃料供給の強靭化に向けた有識者会議の目的及び概要(ppt/pptx形式:60KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
(ア)出荷拠点(製油所・油槽所)
北海道胆振東部地震においては、製油所・油槽所等の出荷拠点について、停電により地域の石油製品の供給拠点である油槽所の出荷能力が大幅に減少しました。また、出荷設備の被害はなかったものの、一部の精製設備では被害が発生する事態となりました。
そこで、大規模な災害が頻繁に生じている中、出荷拠点の強靭化対策の状況確認のため、全国の製油所・油槽所について、(A)停電時の出荷能力、および(B)強靭化対策の状況を点検しました。
製油所、油槽所における非常用発電機の整備状況を点検したところ、すべての製油所では整備がされている一方、油槽所においては65%に留まることが確認されました。
また、東日本大震災以降の強靭化対策の実施状況を確認したところ、製油所については全ての製油所で法令基準を上回る強靭化対策が実施されていたものの、油槽所においては約37%に留まる結果となりました。
以上の点検結果から、主に油槽所において、非常用発電機の整備・増強及び強靭化対策の強化の必要性が示唆されました。
【第132-1-8】緊急点検の結果概要(製油所・油槽所)
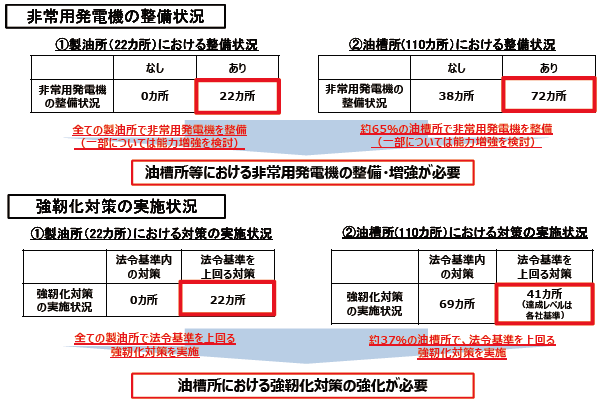
【第132-1-8】緊急点検の結果概要(製油所・油槽所)(ppt/pptx形式:57KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
(イ)販売拠点(SS・輸送)
北海道胆振東部地震においては、道内全域の停電により自家発電機を持たない一般のSSが営業を停止し、自家発電機を有するSS(中核SS・住民拠点SS等)に需要が集中しました。その結果、自家発電機を有するSSに行列が発生し、平常通りの営業状況に回復するまでに1週間程度を要する事態となりました。
また、道内全域の停電等により、電源車や病院等の重要施設等の非常用発電機の燃料が不足し、多方面への燃料の緊急配送が必要となりました。
そこで、全国のSSにおける自家発電機の設置状況(住民拠点SSの整備状況)及び緊急配送用ローリーの配備状況を点検しました。
「住民拠点SS」については、緊急点検により、2018年10月末時点で全国計1,948ヵ所の整備済み(目標達成率24%)、2018年度末までに全国計3,553ヵ所の整備見込みを確認しましたが、今般の経験を踏まえ、更に目標を引き上げ(8,000ヵ所から10,000ヵ所へ)、早急に整備を行うことが必要であることが示唆されました。
緊急配送用ローリーについては、緊急点検により、各都道府県石油組合において、電源車や重要施設等への緊急配送用(小型)ローリーとして全国計5,678台あることが確認されたものの、より機動的な燃料供給体制を確保できるよう、緊急配送用ローリーの追加配備(1,500台)を目指すこととしました。
【第132-1-9】緊急点検の結果概要(SS)
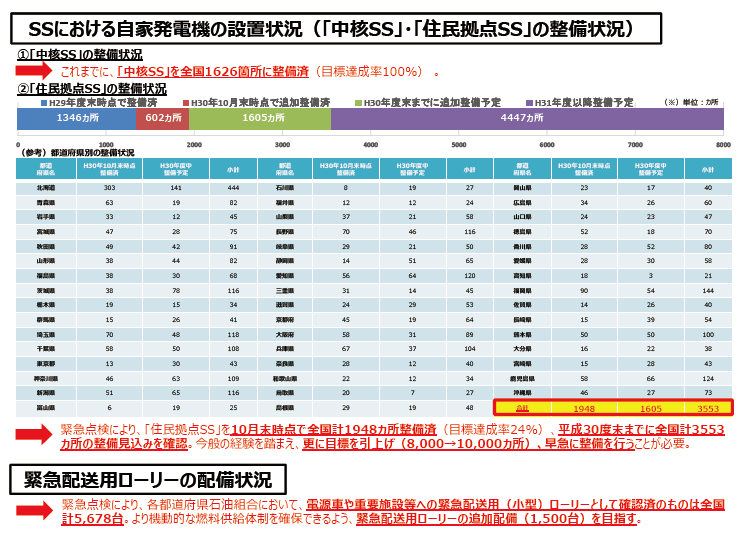
【第132-1-9】緊急点検の結果概要(SS)(ppt/pptx形式:74KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
(ウ)エネルギー生産施設(天然ガス生産施設・石炭炭鉱)
天然ガス生産施設においては、地震や停電等が発生した際の適正な操業体制の維持や、電力事業者等へ供給する生産施設における生産の継続といった課題が確認されました。
また、石炭炭鉱においては、停電により、坑内掘炭鉱の排水や通気を行うポンプが停止しました。もし、この停電が長引けば、坑道が完全に水没し、操業不能になる恐れもありました。
そこで、電力・ガス事業者等へ供給する天然ガス生産施設について、地震や停電等が発生した際の適正な操業体制・継続が可能か点検するとともに、全国の坑内掘炭鉱について、停電時の出荷能力の点検を行いました。
天然ガス生産施設においては、全25鉱山について、非常用発電機の設置やBCPの策定等、非常時における操業体制の構築状況が確認されました。一方、石炭炭鉱においては、国内に一ヵ所ある坑内掘炭鉱において、非常用発電機が整備されていないことが確認されました。これにより、災害時のエネルギー安定供給を確保するため、更なる体制構築が必要であることが示唆されました。
【第132-1-10】緊急点検の結果概要(エネルギー生産施設)
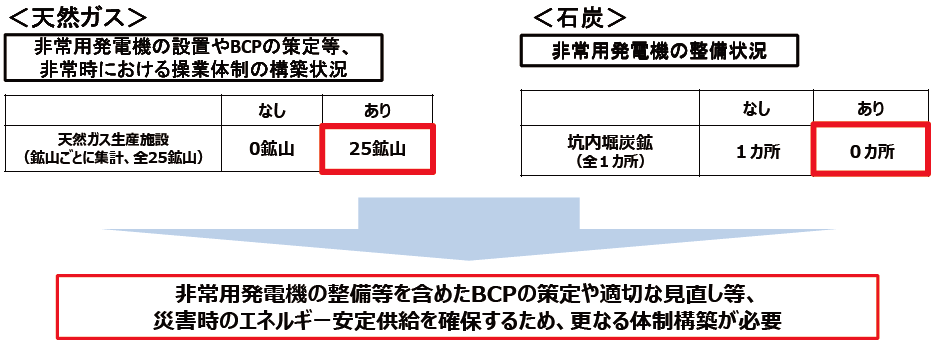
【第132-1-10】緊急点検の結果概要(エネルギー生産施設)(ppt/pptx形式:48KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
2.対策パッケージ
以下では、電力、ガス、燃料の各エネルギー源について、今般の災害を踏まえ、エネルギーの安定供給を確保するためのレジリエンス強化に向けた取組について記載します。
(1)電力レジリエンス対策パッケージ
前述の電力レジリエンスワーキンググループでは、一連の災害に係る事実関係の整理と電力インフラの総点検を行うとともに、検証委員会の中間報告で提言された再発防止策を踏まえ、今後取り組むべき対策パッケージをとりまとめました。
【第132-2-1】電力レジリエンス対策パッケージ
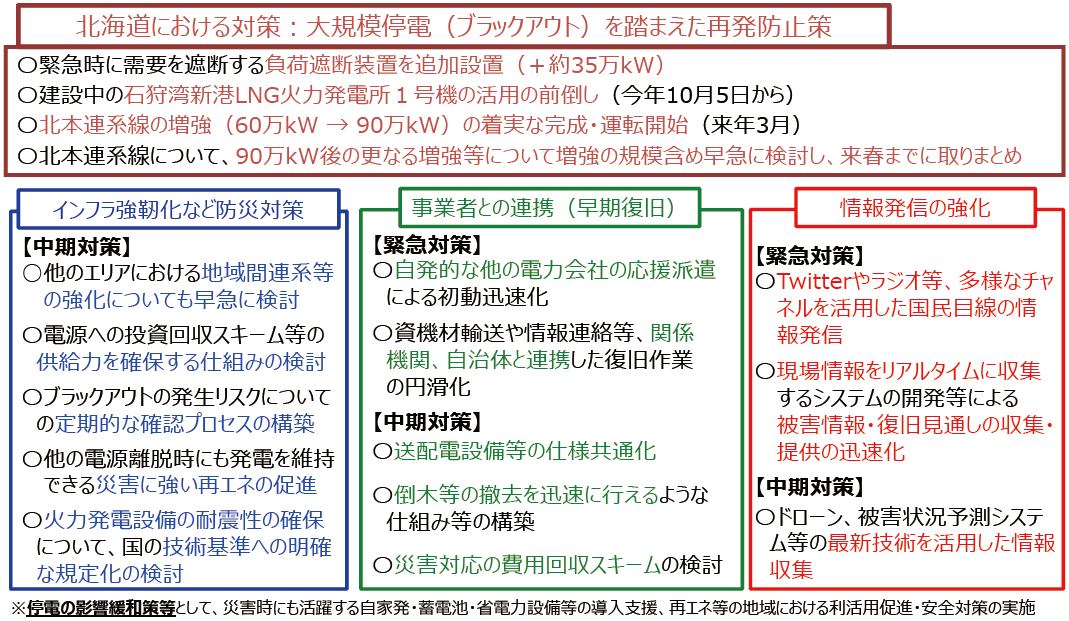
【第132-2-1】電力レジリエンス対策パッケージ(ppt/pptx形式:62KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
①北海道における対策:大規模停電(ブラックアウト)を踏まえた再発防止策
今般の北海道における大規模停電において、北本連系線が地震後、ブラックアウトまでの間に期待されていた機能を果たしたものの、結果としてブラックアウトを防止できなかったこと、北海道エリアの電源構成は老朽火力発電所を多く抱えていることなどに鑑み、北海道エリアの今後の再生可能エネルギーの導入拡大と中長期的な供給力及び調整力の安定的な確保を両立させるため、ひいては中長期的観点から北海道におけるブラックアウト等の発生リスクを低減させるため、検証委員会の中間報告の提言も踏まえ、北本連系線については、新北本連系線整備後(合計連系容量60万kWから90万kWに増強後)の更なる増強について、広域機関において速やかに検討に着手することとされました。また、新北本連系線整備後の更なる増強については、ルートや増強の規模含め、2019年春までを目途に具体化を図ることとされました。この対策パッケージを踏まえ、広域機関では、2018年12月18日に北本連系線の更なる増強等の検討等、電力レジリエンスに関する検討事項全般を審議する「電力レジリエンス等に関する小委員会」を立ち上げました。
また、検証委員会において検証されたシミュレーション結果を踏まえた最終報告書が取りまとめられ、UFR整定の見直しや高速負荷遮断を行う安定化装置による対策が必要であるとし、電力会社に対策の検討を求めることとしました。
②インフラ強靭化などの防災対策
(ア)中期対策
- (A)更なる供給力等の対応力の確保策
- ブラックアウト等を最大限回避し、早期に需給を安定化させるために必要な供給力等の対応力の確保を図るため、電源への投資回収スキーム等の対策を講じます。
- 具体的には、早期に需給を安定化させるために必要な対応力の確保及び供給力の更なる確保を図るため、供給信頼度基準の考え方等について検討を引き続き行っていく中で、調整力公募における調整力(稀頻度リスク対応調整力を含む)の必要量の見直しを検討します。加えて、現在、詳細設計中の容量市場について、災害対応を含む稀頻度リスク等への対応強化を図るため、取引される供給力の範囲拡大等を含め、政府及び広域機関において検討を行います。
- こうした取組を含め、不確実性が高まる中で、投資判断の予見性を向上させ、過少投資を回避するため、電源等に対する投資が促進される仕組みの整備が求められます。また、同ワーキンググループにおける議論において、経年化した火力発電所等について委員より寄せられた意見も踏まえ、老朽火力発電所等の適切な活用を図るための方策についても、国民負担とのバランスも加味しながら、中長期的な視野に立って検討します。
- さらに、同ワーキンググループにおいては、電力インフラの総点検(ネットワーク全体)を行い、前述のとおりの評価を行いましたが、設備構成等は随時変化するため、従来の需給検証プロセスに加え、電力インフラ総点検の方法をベースとしつつ、より精度を高めた形で、ブラックアウトのリスクを定期的に確認するプロセスを構築します。
- (B)レジリエンスと再生可能エネルギー拡大の両立に資する地域間連系線等の増強・活用拡大策等の検討
- 災害時等に電源脱落等が発生した場合に備え、レジリエンスを高めるとともに、再生可能エネルギーの大量導入に資するため、各地域間を結ぶ連系線等について、東日本大震災後に講じられている各種の地域間連系線強化対策の現状も踏まえつつ、需給の状況等を見極めながら、増強・活用拡大策について検討します。
- その際、北本連系線の新北本連系線整備後の更なる増強等も含めて、これらの検討にあたって、レジリエンス強化と再生可能エネルギー大量導入を両立させる費用負担方式やネットワーク投資の確保の在り方(託送制度改革含む)についても検討に着手します。
- また、「需給調整市場」の構築の着実な実施など、調整力の広域的な最適調達・運用を可能とするための制度整備について検討を行っていきます。
- (C)災害に強い再生可能エネルギーの導入促進
- 今般の北海道における大規模停電において、ほぼ全ての風力発電所は地震発生直後に解列したことも踏まえ、主力電源化に向けて大量導入が見込まれる変動再エネ(太陽光、風力)について、周波数変動への耐性を高めるため、周波数変動に伴う解列の整定値等の見直しを行います。
- また、太陽光や風力といった再エネの出力変動への迅速かつ効率的な対応等を可能とするネットワークのIoT化を推進する方策について検討するとともに、大規模停電等の災害時にも蓄電池等を組み合わせて地域の再生可能エネルギーを利活用するモデルの構築を進めます。
- 併せて、家庭用太陽光を災害時に利用できるよう、まずは家庭向けに自立運転機能の周知徹底や情報提供に向けた取組を速やかに実施するとともに、メーカーによって仕様が一部異なっている点も踏まえて、自立運転機能の更なる利用容易化に向けた検討を進めます。
- (D)火力発電設備の耐震性確保の技術基準への明確な規定化
- 火力発電設備の耐震性確保の基準について、これまでの政府の基本的な考え方を法令上で明確化するため、火力発電設備が確保すべき耐震性(一般的な地震動に際し個々の設備毎に機能に重大な支障が生じないこと)を電気事業法に基づく技術基準に規定することを検討します。
【第132-2-2】地域間連系線の増強計画
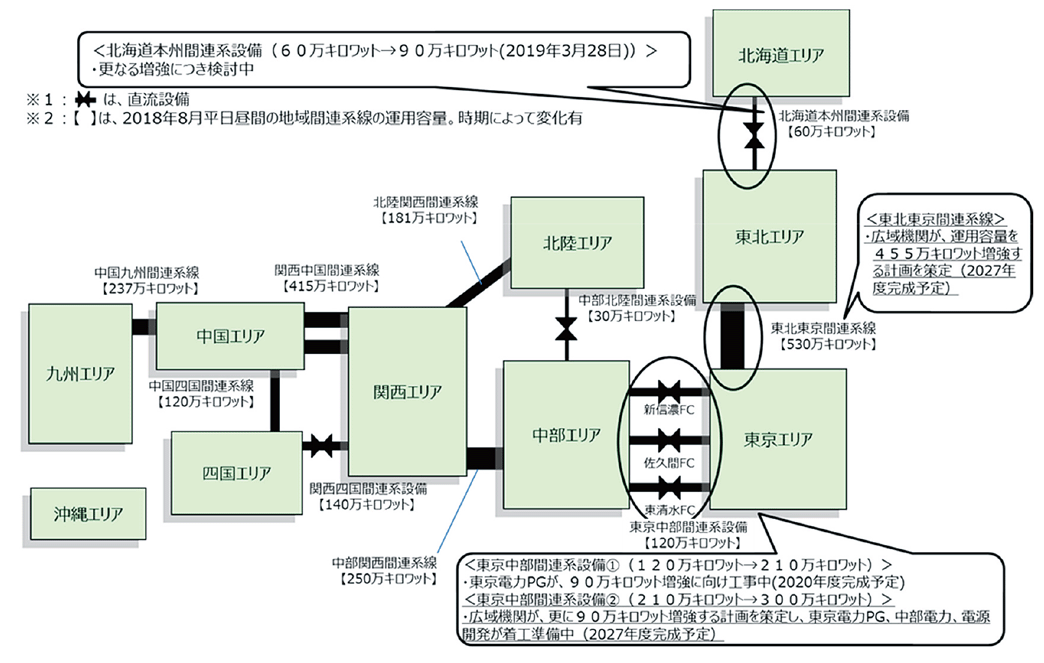
【第132-2-2】地域間連系線の増強計画(ppt/pptx形式:790KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
③事業者との連携(早期復旧)
(ア)緊急対策
自然災害が大規模化・激甚化する傾向にある中において、復旧の早期化を実現するためには、電力会社間、さらには電力会社と関係機関の連携強化が重要となります。
電力会社間の連携については、現在、エリア毎(東地域、中地域、西地域)に幹事会社を置き、電力会社間で連携するスキームを構築済みです。これにより、被災した電力会社は速やかに必要な資機材・人材の応援派遣等を要請することができています。今後、更なる迅速化を図るため、電力会社各社が自発的に応援派遣できるよう当該スキームを発展させ、より円滑な連携体制を整えることが必要となります。
また、電力会社と行政機関や他の重要インフラ事業者等の連携に時間がかかる場合、現場情報や地元ニーズの把握が円滑に行われないおそれがあるとともに、電力会社の復旧作業の障壁(道路への倒木等)が早期に取り除かれず停電が長期化するおそれがあります。今後発生する可能性がある大規模災害に備えるため、それぞれの繋がりを強化して復旧作業の迅速化を図るとともに、関係機関等と一体となった災害復旧体制を検討すべきであると考えられます。
以上の視点に基づく具体的な緊急対策は以下のとおりです。
- (A)他の電力会社の自発的な応援派遣による初動迅速化
- 被災電力会社からの要請を待つことなく、隣接電力会社が電源車等を近傍まで自発的に派遣するよう運用の見直しを実施します。また、応援準備状況を被災電力会社に逐次共有するなど、より速やかに広域的な応援体制を構築できるよう、支援する側と受入れ側双方の連携体制を改善します。
- 電力会社間の応援の円滑化を目的とした共同訓練等を実施します。併せて、ブラックスタートを含む復旧作業のノウハウを共有するため、マニュアル等の作成や充実化について検討を行います。
- (B)関係機関と連携した復旧作業の円滑化
- 停電復旧作業に従事する車両を多数遠方に派遣する際に、フェリーへの優先搭乗や、関係省庁による復旧車両の輸送支援(公共性・緊急性がある場合等)を速やかに要請できるスキームを構築します。
- 高速道路の優先通行や復旧に必要な道路の優先開通等を実現するため、道路関係機関(地方整備局等)や重要インフラ事業者(通信事業者等)等との連絡窓口の整理や協定の締結等を行います。
- (C)自治体との災害時の情報連絡体制の構築
- 自治体との連携によって停電復旧作業の障害を速やかに取り除けるように、災害時の連絡窓口やリエゾン派遣ルールの構築・確認等を行います。
- 迅速かつ正確な情報発信や停電復旧早期化を実現するためには、電力会社のみならず、政府の後押しも非常に重要となります。例えば、関係省庁間でマクロな視点から災害対応について議論し、復旧活動に資する協定等を事前に締結することで、現場ベースで必要な連携体制を構築しやすくなり、情報収集・発信、復旧活動の円滑化・早期化を図ることが可能となります。電力会社の緊急対策をより充実したものとするために、政府としてもサポートできるよう必要な施策を着実に実施する必要があります。
(イ)中期対策
- (A)送配電設備の仕様等の共通化
- 設備仕様の共通化は、電気料金の低減や新規接続を希望する再エネ事業者の負担軽減といった観点で検討されてきましたが、他の電力会社からの応援作業員による復旧作業の円滑化等に資する可能性もあるため、この検討を更に加速化させます。
- (B)復旧の妨げとなる倒木等の撤去の円滑化に資する仕組み等の構築
- 2018年夏以降の度重なる台風被害に伴う停電において、一部エリアでは倒木、飛来物、倒壊家屋等の撤去に長時間を要し、停電が数週間に渡って長期化したケースがありました。原因の一つとして、撤去すべき倒木・飛来物等の所有者への確認・協議や、道路管理者との調整等に時間を要したことが挙げられます。関係法令を整理した上で、電力会社がより迅速に設備の復旧を実施できるよう、復旧の妨げとなる倒木等の撤去の円滑化に資する仕組み等の構築を検討していきます。
- (C)災害時における多様な電力事業者の円滑な連携体制の構築
- システム改革等が進展し、新電力(発電・小売)や再エネ事業者含め電力事業者の多様化が進む中、災害時にはこれらの事業者が円滑に連携し、必要な役割を果たすこと(適切な費用分担を含む)で停電からの早期復旧を実現する体制を強化する方策を検討します。
- 加えて、2020年に発送電分離となることも見据えた際、災害時には、送配電部門の中立性を担保する前提で、旧一般電気事業者の各部門が有機的な連携を維持・担保する仕組みについても検討を行います。
- (D)早期復旧を促す災害対応の費用回収スキームの検討
- 今回の一連の災害・大規模停電からの復旧において、一般送配電事業者を中心に、早期復旧を第一とした様々な取組がなされました。発送電分離・自由化の進展等のシステム改革がなされた後においても、引き続き災害時においては、災害・停電からの最大限の早期復旧を実現していくことを可能とする環境を整備するという観点から、災害対応時に係る合理的な費用について回収することを可能とするスキームの構築について検討を行います。
- (E)需給ひっ迫フェーズにおける卸電力取引市場の取引停止に係る扱いの検討
- 今回の北海道における大規模停電時の経験も踏まえ、需給バランスが大きく崩れた場合等における卸電力取引市場における取引停止に係る取扱いを今後検討します。あわせて、卸電力取引市場が停止した際のインバランス料金に関する制度設計を今後検討します。
④情報発信の強化
(ア)緊急対策
下図に示すとおり、国民が求める情報は主に「停電戸数・停電地域」、「復旧見込み」、「エリア毎の停電原因・復旧進捗状況」の3パターンに大別されます。停電発生エリアの国民は、まず現状把握のために「停電戸数・停電地域」等の基本的な情報を求めると考えられます。その後、避難等を含め、取るべき行動を素早く決定する必要が生じることから、停電後1日(24 時間)以内に一定の「復旧見込み」が必要となると考えられます。停電が長期化する場合には、より詳しい状況を把握するため、遅くとも数日以内には「エリア毎の停電原因・復旧進捗状況」等の情報が求められることとなるほか、停電エリア以外でも、電力需給ひっ迫に伴う地域的な節電の必要性等の情報が求められると考えられます。また、それぞれのタイミングで必要な情報提供を行うため、現場で復旧作業に従事する作業員に過度な負担を与えないことを前提に、現場の情報をリアルタイムに収集・集約・発信することが不可欠となります。
【第132-2-3】国民が求める情報とタイミング
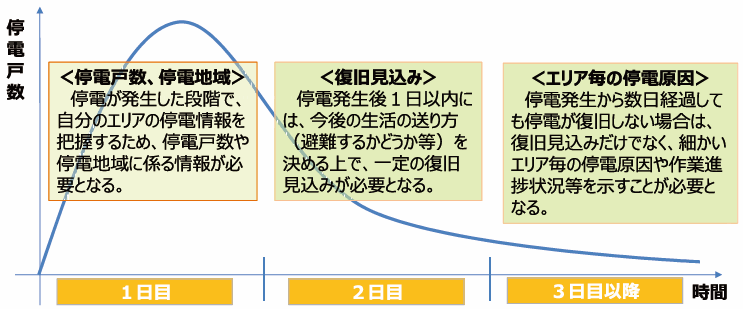
【第132-2-3】国民が求める情報とタイミング(ppt/pptx形式:194KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
【第132-2-4】各主体が求める情報のニーズとタイミング
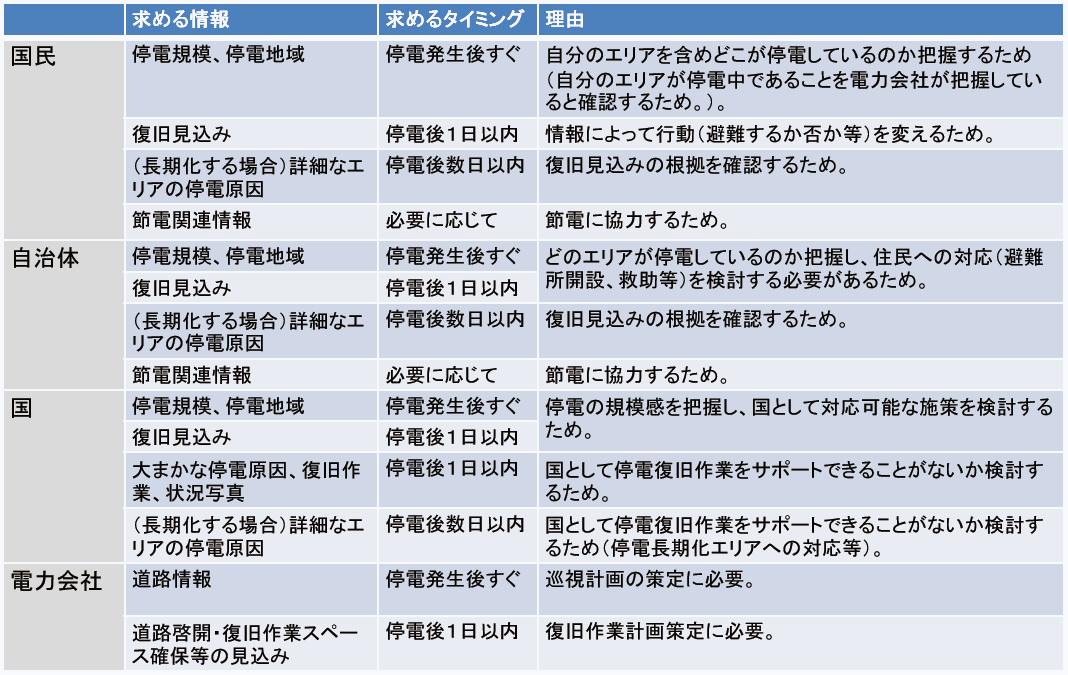
【第132-2-4】各主体が求める情報のニーズとタイミング(ppt/pptx形式:57KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
以上の視点に基づく具体的な緊急対策は、以下のとおりです。
- (A)SNS等を活用した国民目線の情報発信
- 全ての電力会社が Twitter等のアカウントを開設し、災害時に復旧見込み、節電情報等を迅速に発信します。また、政府も情報発信のサポートを積極的に行います。
- 災害時、電力会社各社のHPがアクセス集中により閲覧しづらくなることを防ぐため、電気事業連合会が大手ポータルサイトと連携して、キャッシュサイトを開設します。さらに、システムがダウンした場合、Twitter等を活用してバックアップを行います。
- (B)多様なチャネルの活用による幅広い国民層への情報周知
- インターネットを使うことが出来ない国民に対しても、災害時、停電情報、復旧見込み、復旧進捗状況等の周知を徹底するため、停電時も情報を発信できるようラジオ局等との連携体制を強化するとともに、電力会社各社所有の広報車の活用や、避難所等への貼り紙やチラシの配布等についても積極的に実施します。
- 災害時、情報のハブとなる地方自治体に対し、迅速かつ正確に情報を伝達できる関係を築くため、災害時の連絡窓口や被災自治体へのリエゾン派遣ルールの構築・確認等、電力会社と自治体の連絡体制を強化します。
- 電力会社各社は、自社グループの小売部門や他の電力会社等のコールセンターと連携することで、災害時における電話対応の体制を通常時よりも強化し、国民ニーズに応える体制を整えます。加えて、自動応答の整備についても検討します。
- (C)現場情報収集の迅速化
- 電力会社各社は、災害時、基本的に紙ベースで行われている被害状況・復旧進捗等の現場情報集約をシステム化等で迅速化することで、リアルタイムに把握することができる仕組みの構築を検討します。
- 停電が起こっているエリアの住民から生の情報を拾い上げ、住民ニーズや被害状況を迅速に把握することを目的として、電力会社各社のHPへの情報収集フォームの開設やアプリ等の情報収集ツールの整備を行います。また、文字情報だけでなく、画像データの収集も検討します。
(イ)中期対策
- (A)電力会社のHP上の停電情報システムの精緻化
- 現在HP上で公開されている電力会社の停電エリア、復旧見込み、復旧進捗状況等の情報について、国民に対して分かりやすく詳細に情報発信を行うという観点から、より一層の精緻化を図ります。
- (B)関係省庁の連携による重要インフラに係る情報の共同管理・見える化
- 現在、内閣府を中心に検討が進められている「災害情報ハブ」への参画を念頭に、電力会社が提供可能な情報と災害復旧時に必要となる情報を整理し、道路や通信等重要インフラ情報と共に有効活用できるシステムの設計について検討を行います。
- (C)ドローン、被害状況を予測するシステム等の最新技術を活用した情報収集
- ドローンを活用した立ち入り困難な区域における現場情報の収集や、被害状況を予測するシステムの活用による設備被害予測の高度化等、最新技術を活用した情報収集の方策について検討を行います。
(2)ガスレジリエンス対策パッケージ
前述の「産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 ガス安全小委員会」では、直近の地震対応における教訓を踏まえ、ガスインフラの更なる強化・改善に向けて、以下の通り対策をとりまとめました。
【第132-2-5】ガスレジリエンス対策パッケージ
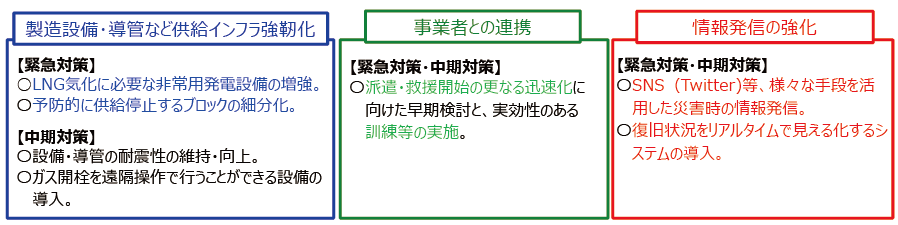
【第132-2-5】ガスレジリエンス対策パッケージ(ppt/pptx形式:48KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
【第132-2-6】供給停止ブロックの細分化
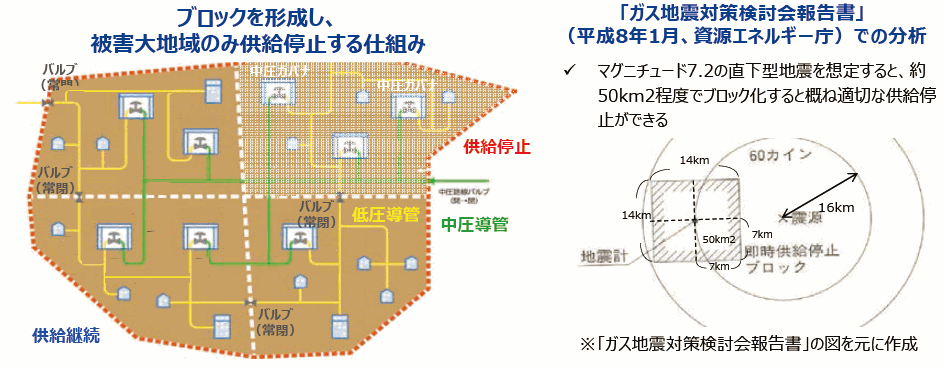
【第132-2-6】供給停止ブロックの細分化(ppt/pptx形式:1,230KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
①製造設備・導管など供給インフラ強靭化
(ア)緊急対策
ガス事業者は、二次災害の防止と供給停止の極小化のバランスを考慮し、導管網を適切な規模で分割(ブロック化)しています。阪神大震災後の「ガス地震対策検討会」では、供給停止を要する大きな揺れの面積等の分析を踏まえ、50km2程度で供給停止できるブロックを形成すること、必要に応じてブロックの細分化を図ることとされました。
他方、過度な細分化は、ネットワークの冗長性を低減させ、サンドブラストや他工事、差水等での供給支障リスクを高めるため、供給安定性を阻害する部分もあります。このため、ガス事業者は、「平時の供給安定性」と「地震時の供給停止範囲の極小化」の両立を考慮した、ブロックの形成と細分化を検討することとしています。
また、現在の復旧手法は、阪神淡路大震災から確立された手法がベースとなっていますが、耐震化率が大幅に向上し、マイコンメーターがほぼ100%設置された状況を踏まえると、マイコンメーターが備える保安機能の活用等を通じた合理的な復旧手法の検討が重要となります。例えば東京ガス(日立地区)では、供給停止後のガバナの圧力保持状態や緊急巡回点検からガス導管・建物の被害は軽微と判断できたため、開閉栓作業をマイコンメーターによる保安機能で代替し、早期復旧を実現することができました。
(イ)中期対策
製造設備・高中圧導管は過去の大地震においても高い耐震性が確認されていますが、低圧ガス導管は接合部を中心に被害が発生したケースがありました。したがって、低圧ガス導管の耐震対策を進め、ネットワーク全体で強靭性を高めます。
また、地震時にも有効なスマートメーターの導入を検討します。
【第132-2-7】事業者間の連携
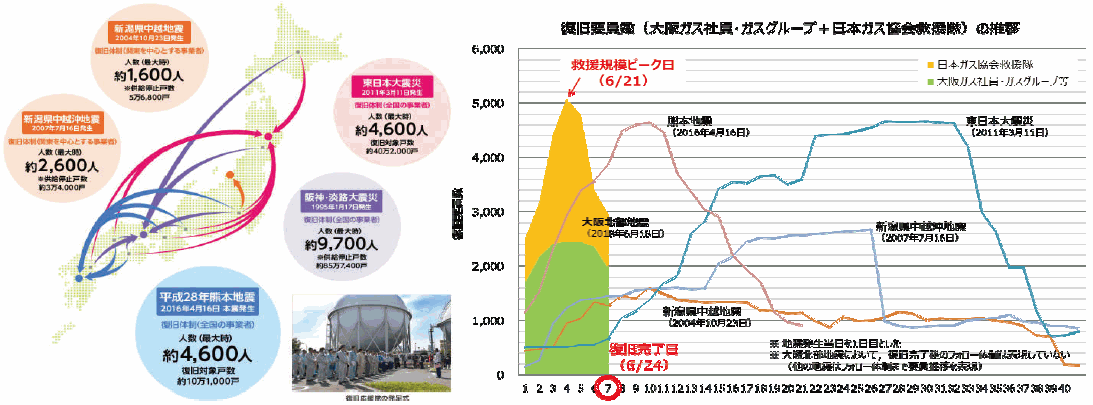
【第132-2-7】事業者間の連携(ppt/pptx形式:899KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
②事業者との連携
緊急対策・中期対策
都市ガス協会の相互連携の枠組みは、災害の経験を活かしながら改善を重ねつつ、復旧に重要な役割を発揮してきました。こうした枠組みは維持・継続しつつ、より確実・迅速な対応へ高度化していきます。
例えば、被災事業者は救援要請をできる限り早く行うこと、救援事業者は要請をける前から準備を進めること、実効性のある訓練を実施すること等、より円滑な救援体制の立ち上げに資する取り組みを検討していくことが望まれます。
③情報発信の強化
緊急対策・中期対策
都市ガスでは、これまでも多様な災害時の情報発信が試みられていますが、需要家・社会に対し、一層分かりやすく、幅広い情報発信が重要です。
復旧見通しのできるだけ早期の情報発信に向けては、過去の熊本地震を踏まえた提言内容に基づき、的確な復旧完了見込みの算出に向けた技術的検討の更なる深堀を行います。
また、大阪地震での好事例を参考に「復旧見える化システム」の横展開やホームページ・TV・ラジオ・新聞・SNS(Twitter)等の幅広い広報活動の仕組みづくりを進めていきます。
【第132-2-8】災害時の情報発信
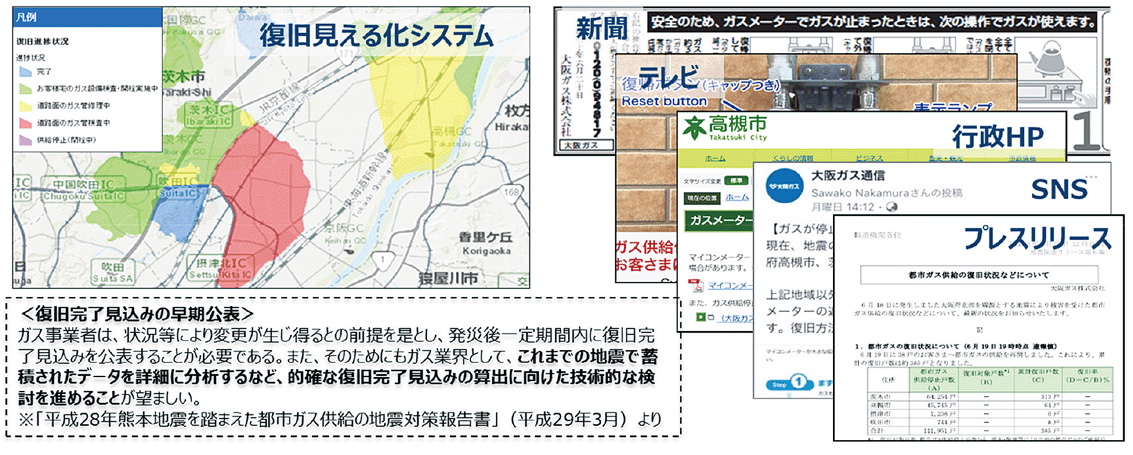
【第132-2-8】災害時の情報発信(ppt/pptx形式:1,841KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
(3)燃料供給レジリエンス対策パッケージ
前述の「災害時の燃料供給の強靭化に向けた有識者会議」では、災害時の燃料供給の強靭化のための対策として、今後の対策パッケージをとりまとめました。具体的には、「即着手し、年度内に実現する対策」と、「即検討に着手し、3年以内に実現する対策」として、以下の通り対策をとりまとめました。
【第132-2-9】燃料供給レジリエンス対策パッケージ
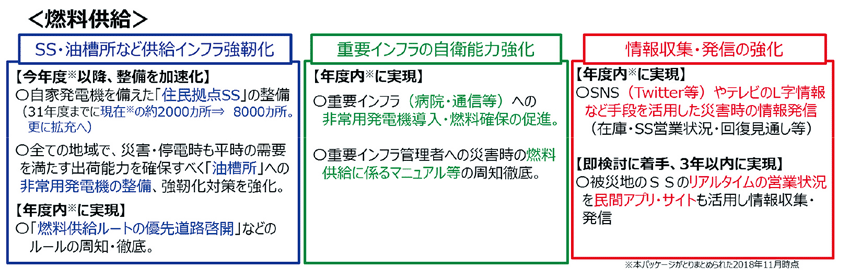
【第132-2-9】燃料供給レジリエンス対策パッケージ(ppt/pptx形式:731KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
①SS・油槽所など供給インフラ強靭化
(ア)今年度以降、整備を加速化する対策
全ての地域で、災害時にも平時と同程度の出荷能力を維持するため、製油所・油槽所の非常用発電機の整備・増強を実施します。また、油槽所については、大規模災害を想定した耐震化等の点検を2019年度に実施し、それを踏まえた強靭化対策を実施します。
燃料輸送路が優先啓開対象でない都道府県への働きかけ・フォローアップを行い、全地域の防災計画等における燃料輸送路の優先啓開を目指します。また、タンクローリーの緊急通行車両の事前届出が進んでいない地域の届出・届出の受理促進を働きかけ、各地域で関東並み(約7割)の届出率を目指します。
自家発電機を有する「住民拠点SS」の全国8,000ヵ所への整備を加速し、将来的に全国10,000ヵ所の整備を目指します。また、緊急配送用ローリーの追加配備(1,500台)を目指します。加えて、災害時専用の臨時の移動式給油設備の全国的な運用体制の構築を検討します。
災害時の効果検証及びそれを踏まえた検討内容について、各社の系列BCPへの反映を進めるとともに、定期的な格付け審査の実施により、その状況のフォローアップを継続していきます。
病院、避難所等における石油やLPガスの燃料タンク・自家発電機の整備に係る支援を拡充します。また、地方公共団体を対象とする会議等において、災害時燃料供給に関する情報提供を行い、理解・取組を促進します。
エネルギー生産事業者において、ガイドラインを基に、非常用発電機の整備等も含めたBCPの策定や必要に応じた見直しを検討します。
(イ)年度内に実現する対策
燃料輸送路を把握していない、または優先啓開の対象としていない都道府県等に対し、燃料輸送路に関する情報提供・優先啓開を働きかけます。また、タンクローリーの緊急通行車両の事前届出の実施状況を確認し、石油元売各社から都道府県公安委員会への届出を促進するとともに、都道府県に対しても、届出の迅速な受理を促します。
「住民拠点SS」を全国約3,500カ所へ整備します。(2018年10月末時点で1,948ヵ所整備済み。)また、大規模災害時にSSの営業を継続するための手順・対応等に係るBCPを各都道府県の石油組合が策定します。
これまでの石油精製・元売会社の系列BCPに基づく取組について、災害時に機能していたか検証を行うとともに、必要な見直しを検討します。
SS地下タンクの大型化の支援を継続するとともに、SS地下タンクの流通在庫を活用した燃料備蓄確保の取組の更なる推進に向けて、各都道府県へ働きかけを行います。
②重要インフラの自衛能力強靭化
(ア)年度内に実現する対策
病院、避難所、通信施設、上下水道、地方自治体の庁舎などの重要施設、自家用車における燃料備蓄の意識向上に向けた普及啓発活動を実施します。
具体的には、病院、避難所、通信施設、上下水道、地方自治体の庁舎などの重要施設の所管省庁を通じて、重要施設における災害時の燃料供給に関する理解促進(自衛措置の必要性等)や燃料備蓄等の状況把握を実施します。これを基に関係省庁に働きかけを行い、毎年度、状況をとりまとめます。
③情報収集・発信の強化
(ア)年度内に実現する対策
SS・LPガス中核充填所の営業情報・在庫情報等の迅速な把握のため、常時連絡可能な各石油組合等の連絡体制を整備します。また、中核SS・住民拠点SSの「災害時情報収集システム」における報告訓練を徹底します。
災害時に石油連盟等から収集する情報(被災状況、出荷実績、在庫情報、配送計画等)を見直し、災害情報発信専用ページやSNSを活用した発信内容(配送状況、配送計画等)を整理します。加えて、災害時の情報発信に関するマスコミとの情報交換による連携を強化します。
(イ)即検討に着手、3年以内に実現する対策
全国のSSの営業情報・在庫情報等をタイムリーに収集し、消費者が必要とする情報の発信を可能とするシステムの整備につき、民間サービスとの連携も視野に入れ検討します。
全国のLPガス中核充填所の営業情報・在庫情報等をタイムリーに収集できるシステムを整備します。
以上