第3節 一次エネルギーの動向
1.化石エネルギーの動向
(1)石油
①供給の動向
日本の一次エネルギー供給における石油供給量は、石油危機を契機とした石油代替政策や省エネ政策の推進により減少しましたが、1980年代後半には、取り組みやすい省エネの一巡や、原油価格の下落に伴って増加に転じました。1990年代半ば以降は、石油代替エネルギー利用の進展や自動車の燃費向上等により再び減少基調で推移し、2021年度の供給量は熱量ベースで6,735PJとなりました(第213-1-1)。
【第213-1-1】日本の石油供給量の推移
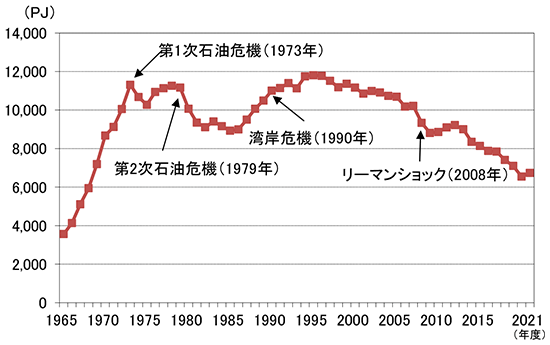
(注)石油(原油+石油製品)の一次エネルギー国内供給量。
【第213-1-1】日本の石油供給量の推移(xls/xlsx形式27KB)
- 資料:
- 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成
日本の原油自給率10は、1970年頃から2021年度に至るまで継続して0.5%未満の水準にあります(第213-1-2)。エネルギー資源の大部分を海外に依存する供給構造は、2021年10月に閣議決定された「第6次エネルギー基本計画」においても、日本のエネルギー需給における構造的課題として明記されています。
【第213-1-2】国産と輸入原油供給量の推移
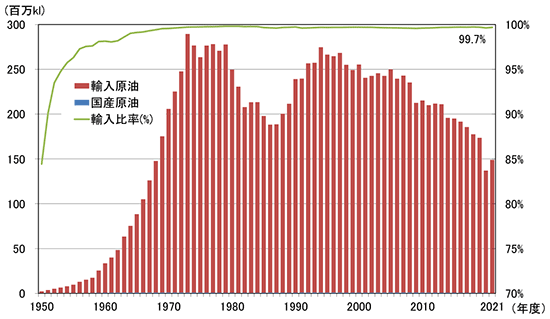
【第213-1-2】国産と輸入原油供給量の推移(xls/xlsx形式34KB)
- 資料:
- 経済産業省「資源・エネルギー統計年報・月報」を基に作成
日本は主にサウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、カタール等の中東地域から原油を輸入しており、2021年度の原油輸入量に占める中東地域の割合(中東依存度)は92.5%でした。特に輸入量が多いのはサウジアラビアとアラブ首長国連邦です(第213-1-3)。なお、中東依存度を諸外国と比較すると、2020年の米国の中東依存度11は9.0%、欧州OECDは14.0%であり、日本の中東依存度は諸外国と比べて高い水準となっています。
【第213-1-3】原油の輸入先(2021年度)
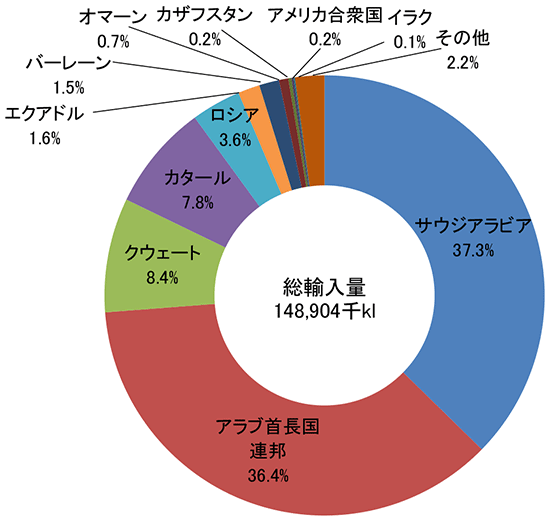
【第213-1-3】原油の輸入先(2021年度)(xls/xlsx形式22KB)
- 資料:
- 経済産業省「資源・エネルギー統計年報」を基に作成
日本は、二度の石油危機の経験から原油輸入先の多角化を図りました。中国やインドネシアからの原油輸入を増やすことで、1967年度に91.2%であった中東依存度を1987年度には67.9%まで低下させました。しかしその後、中国や東南アジア諸国での原油需要の増加に伴い、同地域からの原油輸入量が減少したことで中東依存度は再び上昇し、2009年度には89.5%に達しました。2010年代に入ると、サハリンや東シベリアといったロシアからの原油輸入の増加等で、中東依存度は2009年度と比べ低下傾向にありましたが、2016年度にはロシア等からの輸入が減少したことで中東依存度は再び増大し、2021年度では92.5%となりました(第213-1-4)。
【第213-1-4】原油の輸入量と中東依存度の推移
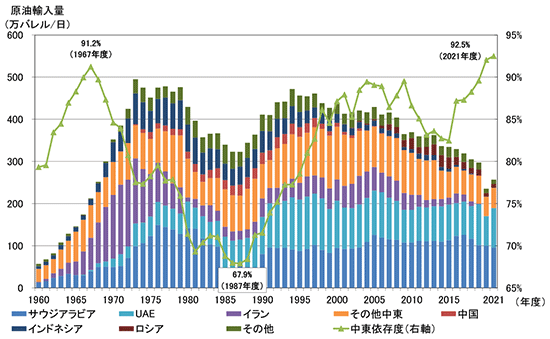
【第213-1-4】原油の輸入量と中東依存度の推移(xls/xlsx形式40KB)
- 資料:
- 経済産業省「資源・エネルギー統計年報・月報」を基に作成
アジアの産油国の原油需給の動向を見ると、国内の原油需要が増加したことを受け、これまで輸出していた原油を国内向けに振り向け、1990年に比べて輸出向けの割合が減少傾向にあることがわかります(第213-1-5)。
【第213-1-5】原油生産に占める国内向け原油、輸出向け原油の割合
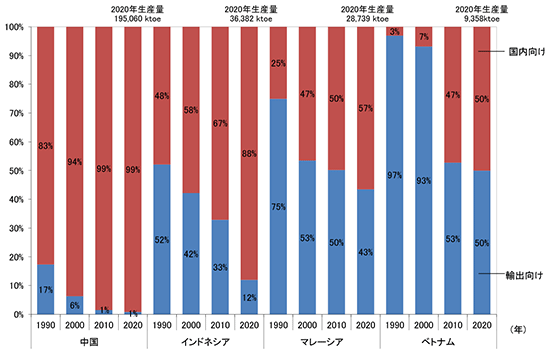
【第213-1-5】原油生産に占める国内向け原油、輸出向け原油の割合(xls/xlsx形式21KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2022 Edition」を基に作成
なお、国際エネルギー機関(IEA)は各加盟国に対して、石油純輸入量の90日分以上の緊急時備蓄を維持するよう勧告していますが、日本は2022年8月時点で219日分の石油備蓄を保有しています。これは、備蓄義務を負う石油純輸入国28か国のうち、産油量があり純輸入量が少ないため備蓄日数が多く算出されるエストニア、デンマーク、米国、オランダを除く24か国中2番目の日数であり、24か国の平均である145日より74日多い日数の備蓄を有していることになります(第213-1-6)。
【第213-1-6】日本及びIEA加盟国の石油備蓄日数比較(2022年8月時点)
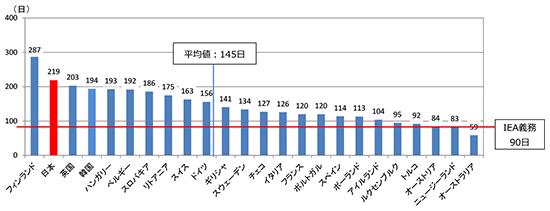
(注)備蓄義務を負う石油純輸入国28か国のうち、産油量があり純輸入量が少ないため備蓄日数が多く算出されるデンマーク、エストニア、米国、オランダを除く24か国を比較した。
【第213-1-6】日本及びIEA加盟国の石油備蓄日数比較(2022年8月時点)(xls/xlsx形式28KB)
- 資料:
- IEA「Oil Stocks of IEA Countries」を基に作成
②消費の動向
日本では原油の殆どが蒸留・精製により石油製品に転換され、それらの石油製品は国内で販売又は輸出されています。これに加え、国内消費向けに石油製品の輸入も行っています。2021年度の石油製品販売量は、燃料油合計で1億5,349万klであり、2000年代に入り減少傾向となっています。油種別販売構成を見ると、第一次石油危機以前の1971年度まではB・C重油12の販売量が5割以上を占めていましたが、その後はガソリン、ナフサ、軽油等より軽質な石油製品の消費が増加しています。2021年度のガソリン、ナフサ及び軽油の油種別販売量のシェアは、それぞれ、29.0%、27.1%及び20.9%となりました。逆にB・C重油は5.4%まで減少しました(第214-4-1参照)。
③原油価格の推移
本項では、2008年の米国の投資銀行リーマン・ブラザース社の破綻に端を発した世界金融危機以降の原油輸入CIF価格13の動きを見ていきます。円建て輸入CIF価格は、2008年8月に約9.2万円/klの高値を付けた後に、2009年1月に約2.5万円/klの水準にまで急落しました。その後、各国による景気刺激策の影響を受け、原油需要の回復期待が高まる中、2009年5月に3万円台/klまで上昇し、2011年3月には5万円台/klへと上昇しました。2011年度以降も上昇傾向を継続し、2014年1月には約7.5万円/klまで上昇し、原油価格の高い状態が概ね2014年末まで続きました。しかしその後、様相が大きく変化しました。当時、高い原油価格を背景に米国のシェールオイルが増産され続ける一方、欧州や中国の景気は減速傾向にあり、石油市場には供給過剰感が生じました。こうした環境にも関わらずOPECは2014年11月の総会で減産を見送りましたが、これが契機となって原油価格は下落に転じ、2016年初頭には約2.2万円/klとなりました。それ以降は世界経済の緩やかな回復に加え、2016年9月のOPEC総会で8年ぶりの減産の方向性が打ち出され、ロシア等の非OPEC産油国も減産に協力をしたことや、2016年11月の米国大統領選後の円下落等もあり、再び上昇に転じました。その後原油価格は上下を繰り返しながらも、OPEC及び非OPEC産油国からなるOPECプラスによる着実な減産により需給が引き締まり、2018年秋まで上昇基調を続けました。その後、原油価格は5万円/kl前後の価格を維持していましたが、米国によるイラン原油禁輸の適用除外措置の発表や、米国のシェールオイル増産等により、需給が緩みつつありました。そういった環境下で、OPECプラスはさらなる追加減産に合意し、2020年1月からの減産強化を決めました。
その矢先に起こったのが、新型コロナ禍です。世界の経済が減速し、石油需要が短期間のうちに大幅に減少しました。OPECはこの状況に対処しようと2020年3月に非OPECに追加減産を提案しましたが、ロシアがこれを拒否したことで協調減産が決裂しました。この結果を受けたサウジアラビアは、これまで協調減産をリードしてきた態度を一変させ、増産に踏み切ることを表明しましたが、その結果、原油価格が急落しました。原油価格の急落を受けて2020年4月にOPECプラスは再び協調減産に合意しましたが、世界中で都市封鎖(ロックダウン)が行われる等で世界の石油需要は急減し、また原油の貯蔵能力の限界を超えるとの見方から、米国の指標原油であるWTI原油は一時マイナス価格14を記録するという前代未聞の状況を経験しました。その後は、OPECプラスが合意した過去に例のない規模での協調減産の効果や、新型コロナ禍から世界経済が徐々に回復したこと等により価格は上昇しました。
その後、2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵略の影響で原油価格は高騰し、2022年7月には約10万円/klとなりました。以降は米国政策金利の上昇や世界経済の減速懸念により、価格は下落傾向となっています(第213-1-7)。
【第213-1-7】原油の円建て輸入CIF価格とドル建て輸入CIF価格の推移
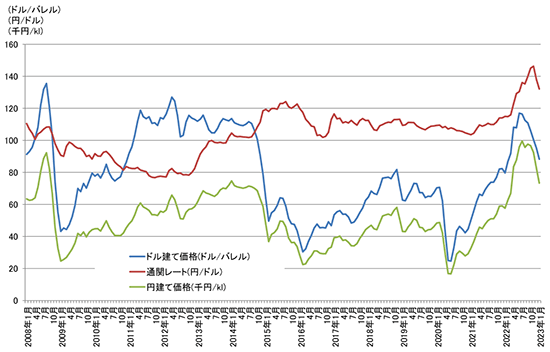
(注)WTI(West Texas Intermediate)原油は米国の代表的な指標原油。オクラホマ州クッシングの原油集積基地渡し価格。2020年4月のマイナス価格は、売主がお金を支払い、買主はお金を受取ることを意味する。
【第213-1-7】原油の円建て輸入CIF価格とドル建て輸入CIF価格の推移(xls/xlsx形式41KB)
- 資料:
- 財務省「日本貿易統計」、米国エネルギー情報局のデータを基に作成
原油の輸入金額は、かつて日本にとって無視できない負担となっており、第二次石油危機後には日本の総輸入金額に占める原油輸入金額15の割合は30%を超えていました。しかし、1986年度以降は概ね10%〜15%程度で推移してきました。背景には、原油価格が低下したこととともに、石油危機以後の石油代替政策、省エネ政策等が功を奏したことがあります。輸入金額に占める原油の割合が低下したことで、原油価格の高騰が日本経済に与える影響は石油危機時と比べると小さくなったと考えられます。2020年度は新型コロナ禍の影響による石油需要の減少から原油の輸入量が減少し、また、原油の輸入CIF価格が低下したことにより、原油輸入金額の占める割合は1965年度以降で最低の5.9%となりました。しかし、2021年度は新型コロナ禍からの経済回復による石油需要の増加から原油の輸入量が増加したこと、原油の輸入CIF価格が上昇したことにより、原油輸入金額の占める割合は8.8%となりました(第213-1-8)。
【第213-1-8】原油の輸入価格と原油輸入額が輸入全体に占める割合
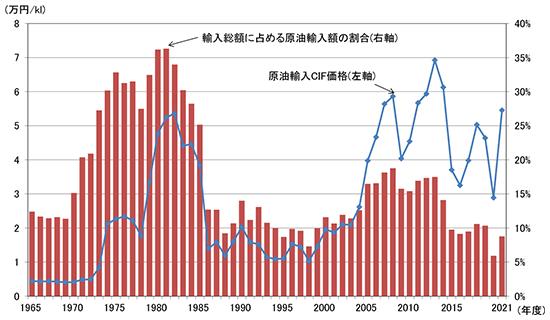
【第213-1-8】原油の輸入価格と原油輸入額が輸入全体に占める割合(xls/xlsx形式31KB)
- 資料:
- 財務省「日本貿易統計」を基に作成
(2)ガス体エネルギー
ガス体エネルギーの主なものとしては天然ガスとLPガスがあります。天然ガスは、油田の随伴ガスや単独のガス田から生産され、メタンを主成分としています。常温・常圧では気体であるため、輸送に当たっては、気体のままパイプラインでの輸送、あるいは、マイナス162℃まで冷却して液体にし、液化天然ガス(LNG:Liquefied Natural Gas)としてタンカー等での輸送のいずれかの方法がとられています。天然ガスは、化石エネルギーの中では燃焼時のCO2の排出量が少なく、相対的にクリーンであるために利用が増えました。
また、LPガスは液化石油ガス(Liquefied Petroleum Gas)のことで、油田や天然ガス田の随伴ガス、石油精製設備等の副生ガスから取り出したブタン・プロパン等を主成分としています。簡単な圧縮装置を使って常温で容易に液化できる気体燃料であるため、液体の状態で輸送、貯蔵、配送が行われています。
①天然ガス
(ア)供給の動向
日本では、1969年のLNG導入以前の天然ガス利用は国産天然ガスに限られ、一次エネルギー供給に占める割合は1.1%に過ぎませんでした。しかし、1969年の米国・アラスカからのLNG輸入を皮切りに東南アジア、中東等からも輸入が開始され、日本におけるLNGの導入が進み、一次エネルギー供給に占める天然ガスの割合は2014年度に過去最高の24.5%に達し、2021年度は21.4%となりました(第211-3-1参照)。
2021年度における天然ガス供給の輸入割合は、石油と同様に極めて高い97.8%であり、輸入分は全量(7,146万トン)がLNGとして輸入されました。一方、主に新潟県、千葉県、北海道等で産出されている国産天然ガスの割合は2.2%でした。国産天然ガスの生産量は、2021年度において約22.6億㎥(LNG換算で約159万トン)となりました(第213-1-9)。
【第213-1-9】天然ガスの国産、輸入別の供給量
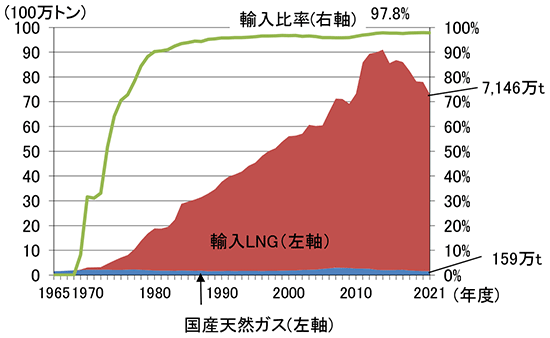
【第213-1-9】天然ガスの国産、輸入別の供給量(xls/xlsx形式28KB)
- 資料:
- 経済産業省「エネルギー生産・需給統計年報」、「資源・エネルギー統計」、「電力調査統計月報」、「ガス事業統計月報」、財務省「日本貿易統計」を基に作成
2021年度の日本に対するLNGの輸入供給源を見ると、豪州、マレーシア等の割合が高い状況であることがわかります。中東依存度は14.9%と石油と比べて低く、地政学的リスクも相対的に低いといえます。特に、2012年度から最大のLNG輸入先となっている豪州では、新規LNG生産プロジェクトからの輸入が順次開始されており、豪州が占める割合は2012年度の19.6%から2021年度には38.3%に拡大しています。一方、インドネシアは1980年代半ば、マレーシアは2000年代半ばをピークとして、年々割合を減らしています。また、2014年度にはパプアニューギニアからの輸入が、2017年1月にはシェールガス生産が急増した米国本土からのLNG輸入が開始される等、供給源の多角化がさらに進展しています(第213-1-10、第213-1-11)。
【第213-1-10】LNGの輸入国(2021年度)
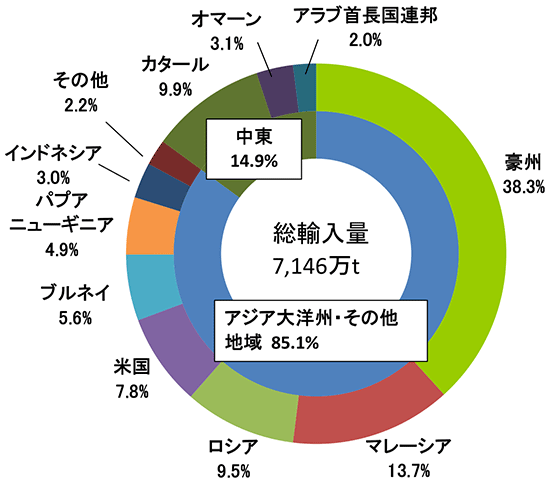
【第213-1-10】LNGの輸入国(2021年度)(xls/xlsx形式30KB)
- 資料:
- 財務省「日本貿易統計」を基に作成
【第213-1-11】LNGの供給国別輸入量の推移
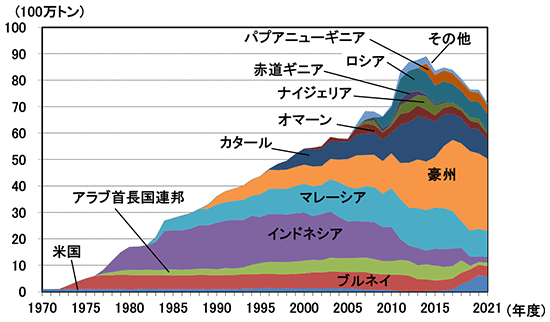
【第213-1-11】LNGの供給国別輸入量の推移(xls/xlsx形式32KB)
- 資料:
- 財務省「日本貿易統計」を基に作成
なお、2021年において、世界のLNG貿易の19.6%を日本の輸入が占めました(第222-1-23参照)。
(イ)消費の動向
2021年度の日本の天然ガスの消費動向を見ると、電力用として約57%、都市ガス用として約36%が使われていることがわかります。天然ガスは、一次エネルギーの供給源多様化政策の一環として、その利用が増加してきました。特に2011年3月の東日本大震災以降、原子力発電所の稼動停止を受け、発電用を中心に増加しました。2014年度に消費量が過去最高となった後は、原子力発電所の再稼動や再エネの普及等により、発電用需要が減少しており、天然ガスの消費量も減少傾向にあります(第213-1-12)。
【第213-1-12】天然ガスの用途別消費量の推移
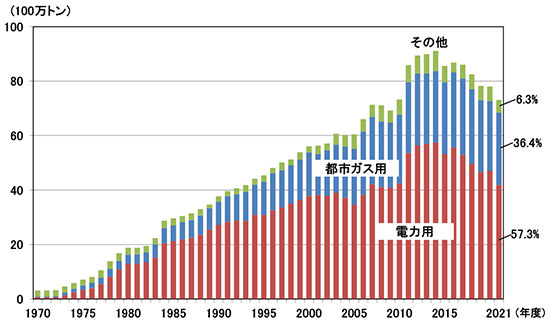
【第213-1-12】天然ガスの用途別消費量の推移(xls/xlsx形式114KB)
- 資料:
- 経済産業省「エネルギー生産・需給統計年報」、「資源・エネルギー統計」、「電力調査統計月報」、「ガス事業統計月報」、財務省「日本貿易統計」を基に作成
なお、都市ガスの用途別販売量としては、2000年頃までは家庭用が最大のシェアを占めていましたが、近年は工業用が増加しており、最大のシェアを占めています(第214-2-2参照)。
(ウ)LNG価格の動向
日本のLNG輸入価格は、1969年の輸入開始以来、基本的に原油価格に連動してきました。1970年代の二度の石油危機で原油価格が高騰すると、LNG輸入価格も上昇し、1980年代に原油価格が下落すると、LNG輸入価格も低下しました。
日本のLNG輸入量の大半を占める長期契約におけるLNG輸入価格は、その多くが日本向け原油の輸入平均CIF価格に連動しています。ただし、連動率は概ね65%〜90%であり、また一部の日本向けLNG輸入価格は、原油価格変動の影響を緩和するために、Sカーブといわれる調整システムを織り込んだ価格フォーミュラにより決定されています。その結果、2004年度以降の原油価格急騰の環境下でも、LNG輸入価格の変化は原油価格の変化に比べると緩やかになっています。なお、2016年度にはシェールガス生産が増加した米国本土からのLNG輸入が開始されましたが、同国からのLNG輸入は、米国国内のガス市場価格(ヘンリーハブ価格)に連動するものが多く、価格決定方式の多様化につながっています。さらに2010年代以降に増加しているスポット調達では、原油価格、他のガス価格等の動向を参照しながらも、相対交渉により独自の価格設定がなされるようになっています。
2010年代に入って以降は、原油輸入CIF価格の上昇に伴い、LNG輸入CIF価格も上昇し、2014年度には1トン当たり約8.7万円となりました。その後、国際原油価格の下落に伴い、LNG輸入価格は低下していきました。2017年度からは国際原油価格が上昇に転じたことに伴い、2018年度のLNG輸入価格も再度上昇しましたが、2019年度からは再び原油価格が下落に転じたこと、また原油価格に連動しない米国産LNGやスポットLNGの増加の影響もあり、2020年度は1トン当たり約4.1万円台に低下しました。2021年には原油輸入CIF価格が上昇に転じたこともあり、1トン当たり7.0万円台となりました(第213-1-13)。
【第213-1-13】LNG輸入CIF価格の推移
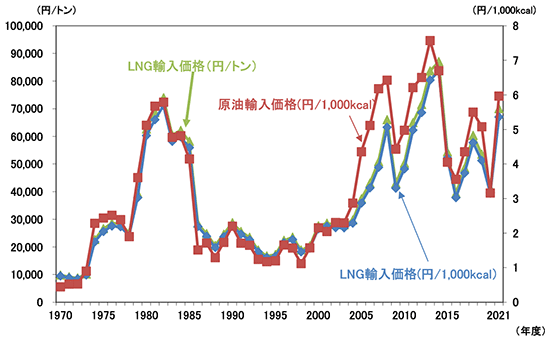
【第213-1-13】LNG輸入CIF価格の推移(xls/xlsx形式28KB)
- 資料:
- 財務省「日本貿易統計」を基に作成
日本の総輸入金額に占めるLNG輸入金額の割合を見ると、1980年代の後半からはLNG輸入価格の低下に伴い、4%を下回る水準で推移してきました。しかし、2000年代後半以降は原油価格の上昇によりLNG輸入価格も上昇したことに加え、特に、2011年3月の東日本大震災以降の原子力発電所稼動停止に伴い、発電用途のLNG輸入量が増加しました。これにより、LNG輸入金額の割合は上昇し、2014年度には過去最高となる9.3%に達しました。その後は原油価格の低下によるLNG輸入価格の低下等からLNG輸入金額の割合は低下しました。その後、LNG輸入金額の割合はLNG輸入価格に連動しながら4〜6%前後で推移しています(第213-1-14)。
【第213-1-14】LNGの輸入価格とLNG輸入額が輸入全体に占める割合
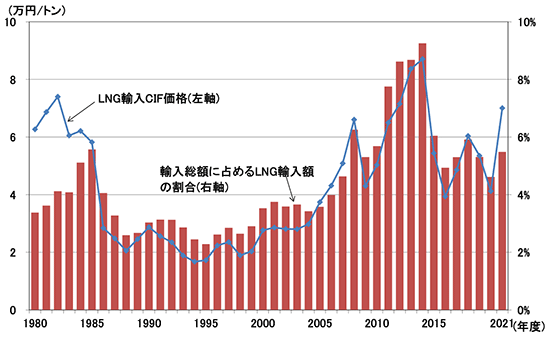
【第213-1-14】LNGの輸入価格とLNG輸入額が輸入全体に占める割合(xls/xlsx形式24KB)
- 資料:
- 財務省「日本貿易統計」を基に作成
②LPガス
(ア)供給の動向
LPガスは、天然ガス生産からの随伴ガス、原油生産からの随伴ガス、さらに石油精製過程等からの分離ガスとして生産されています。LPガスの供給は1960年代までは、国内の石油精製の分離ガスが中心でしたが、1980年代まで年々輸入比率が高まり、1993年度には輸入比率が最大となる77.1%(1,534万トン)まで拡大しました。その後、輸入比率は横ばいで推移し、2021年度の輸入比率は供給量の76.3%(1,008万トン)となりました(第213-1-15)。
【第213-1-15】LPガスの国産、輸入別の供給量
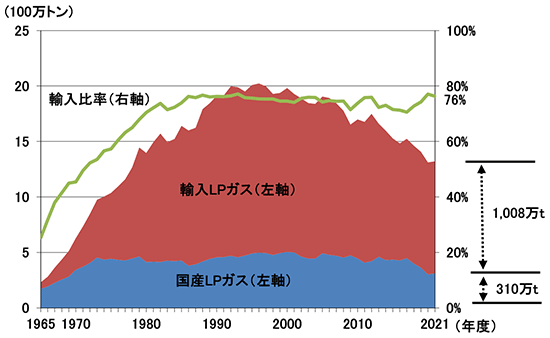
(注)「国産LPガス」は、製油所の数値。
【第213-1-15】LPガスの国産、輸入別の供給量(xls/xlsx形式29KB)
- 資料:
- 経済産業省「資源・エネルギー統計」、財務省「日本貿易統計」を基に作成
2021年度における日本のLPガスの主な輸入国は、米国、カナダ、豪州及び、クウェート、アラブ首長国連邦、カタール等の中東諸国でした。米国のシェールガス・シェールオイル開発に随伴して生産されるLPガスの輸入が2013年に開始されたことにより、LPガス全体の輸入量が減少傾向にある中で、米国は2015年度に最大の輸入先となり、2019年度には統計開始後最大となる72.6%のシェアを記録し、2021年度も66.6%と高いシェアを維持しました。シェール革命に加え、2016年6月にパナマ運河拡張が完了し、大型LPG船の通航が可能になったことも追い風となっています。その結果、LPガス輸入の中東依存度は2011年度の86.6%から、2021年度には9.9%へと低下し、逆に米国への一極集中が進んでいます(第213-1-16)。
【第213-1-16】LPガスの輸入国(2021年度)
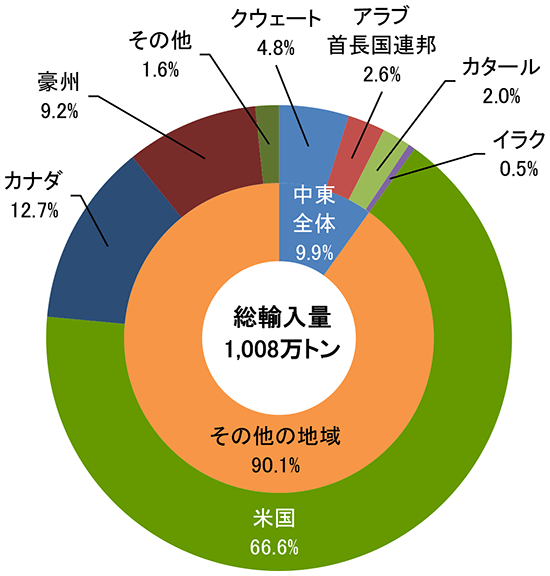
【第213-1-16】LPガスの輸入国(2021年度)(xls/xlsx形式22KB)
- 資料:
- 財務省「日本貿易統計」を基に作成
(イ)消費の動向
LPガスの消費は、1996年度に過去最高の1,970万トンとなった後、燃料転換等により減少傾向が続きました。2017年度には厳冬により給湯・暖房需要が増加したことで5年ぶりに増加したものの、2018年度から再び減少に転じ、2021年度の消費量は1,254万トンとなっています。1996年度と比較すると36%減少しており、1978年度並みの水準になっています。また、2021年度のLPガスの消費を用途別に見ると、家庭業務用の消費が全体の48.6%を占めました。次いで一般工業用が20.7%、化学原料用が15.1%と大きなシェアを持ち、都市ガス用(10.5%)、自動車用(4.4%)と続きます(第213-1-17)。
【第213-1-17】LPガスの用途別消費量の推移
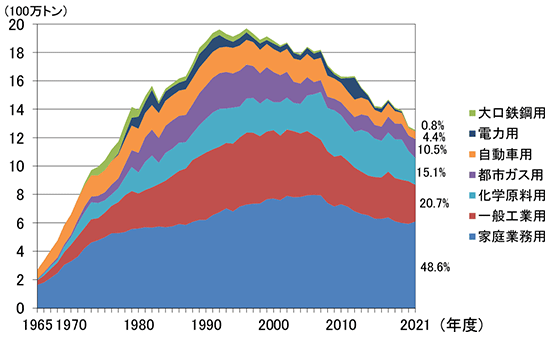
【第213-1-17】LPガスの用途別消費量の推移(xls/xlsx形式28KB)
- 資料:
- 日本LPガス協会資料を基に作成
(ウ)LPガス輸入価格の動向
日本のLPガス輸入価格は、サウジアラビアのサウジアラムコ社が決定する通告価格16に大きく左右される構造となっていました。しかし、2013年度頃からは、価格指標の多様化を目的とし、米国プロパンガス取引価格17を価格指標とするLPガスの輸入も活発化しています。
2010年度以降の原油価格高騰とともに、2013年度のLPガス輸入(CIF)価格(年度平均)は過去最高の93,177円/トンとなりました。その後、国際原油価格の下落や相対的に低価格である米国とカナダ産のLPガス輸入シェアの拡大により、LPガス輸入価格が低下し、2020年度には47,273円/トンとなりました。2021年度は国際原油価格の高騰により82,209円/トンに上昇し、2014年以来の8万円台を記録しました(第213-1-18)。
【第213-1-18】LPガス輸入CIF価格の推移
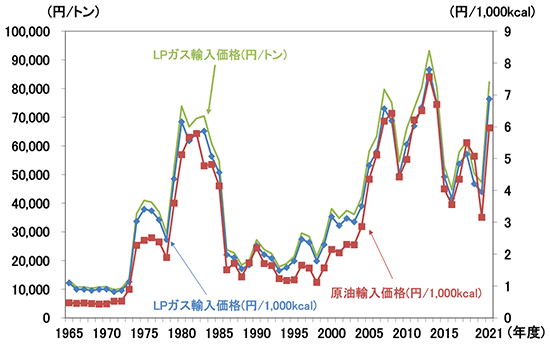
【第213-1-18】LPガス輸入CIF価格の推移(xls/xlsx形式26KB)
- 資料:
- 財務省「日本貿易統計」を基に作成
また、日本の総輸入金額に占めるLPガスの輸入金額の割合を見ると、二度の石油危機を契機に1980年代には2%を上回る水準にまで上昇しました。その後は下落し、1980年代後半からは約1%の水準で推移していましたが、2016年度にはLPガス輸入価格の低下と輸入量の減少に伴い、1971年度以来の低水準となる0.7%まで低下しました。以降も1%を下回る水準が続き、2021年度は0.9%となりました(第213-1-19)。
【第213-1-19】LPガスの輸入価格とLPガス輸入額が輸入全体に占める割合
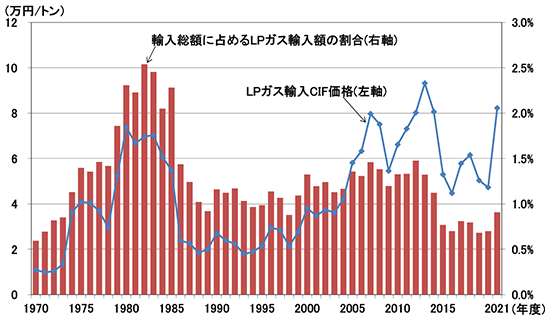
【第213-1-19】LPガスの輸入価格とLPガス輸入額が輸入全体に占める割合(xls/xlsx形式25KB)
- 資料:
- 財務省「日本貿易統計」、日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」を基に作成
(3)石炭
①供給の動向
2021年度、日本は石炭の国内供給のほぼ全量(99.6%)を海外からの輸入に依存しました。国内の石炭生産量は、1960年代には石油への転換の影響、1980年代以降には、割安な輸入炭の影響を受けて減少を続けました。1990年度から国内原料炭18の生産がなくなり、国内一般炭19の生産量は減少で推移しました。2002年から2017年にかけて、国内一般炭の生産量は、年間120〜130万トン前後で推移しましたが、2018年に100万トンを割り込み、2021年度は66万トンまで減少しました。一方で、海外炭の輸入量は1970年度に国内炭の生産量を上回り、1988年度には1億トンを超え、その後も一般炭を中心に増加し、近年では1.7億トンから1.9億トンの水準となっています(第213-1-20)。
【第213-1-20】国内炭・輸入炭供給量の推移
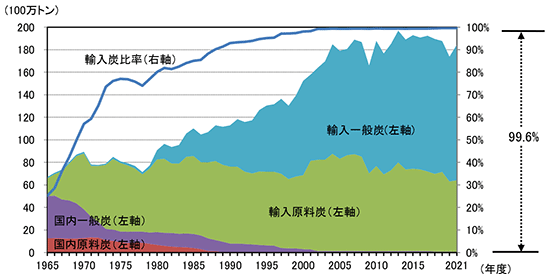
(注)国内一般炭には国内無煙炭、輸入一般炭には輸入無煙炭をそれぞれ含む。
【第213-1-20】国内炭・輸入炭供給量の推移(xls/xlsx形式28KB)
- 資料:
- 2000年度までは経済産業省「エネルギー生産・需給統計年報」、2001年度より財務省「日本貿易統計」、石炭フロンティア機構「コールデータバンク」を基に作成
2021年度は輸入一般炭が1億1,421万トン、輸入原料炭が6,338万トンとなり、無煙炭20をあわせた石炭輸入量合計は1億8,382万トンとなりました。同年度の一般炭の輸入先は、豪州が72.3%を占めており、次いでロシア(11.2%)、インドネシア(9.5%)、米国(3.6%)、カナダ(2.7%)からの輸入がこれに続きました。原料炭の輸入先は、豪州が54.5%を占めており、次いでインドネシア(18.3%)、米国(9.1%)、カナダ(8.0%)、ロシア(7.2%)からの輸入がこれに続きました(第213-1-21)。
【第213-1-21】石炭の輸入先(2021年度)
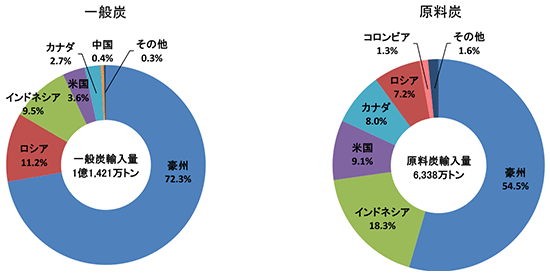
【第213-1-21】石炭の輸入先(2021年度)(xls/xlsx形式25KB)
- 資料:
- 財務省「日本貿易統計」を基に作成
②消費の動向
日本の2021年度の石炭消費を用途別に見ると、電気業が1億1,161万トンと最も多く21、次いで鉄鋼業が5,959万トンとなっています。
電気業における石炭消費量は、1960年代後半は2,000万トンを上回っていましたが、石炭火力発電の他電源への転換が進んだことから1979年度には701万トンにまで低下しました。しかし、第二次石油危機以降は、石油代替政策の一環としての石炭火力発電所の新設及び増設に伴って石炭消費量は増加に転じ、2007年度には約8,700万トンに達しました。2003年度からは電気業が最大の石炭消費部門となっています。2009年度以降は、世界的な不景気や、「みなし措置」22満了で以前から卸電気事業にかかわる許可を受けていた共同火力が電気事業者から外れたこと、さらに2011年度は東日本大震災で一部の石炭火力発電所が被災したことから、発電用石炭消費は減少しました。2012年度以降は、被災した石炭火力発電所の復旧や発電設備の新設等により石炭消費量が増加しました。2016年度から調査対象事業者が変更となっていることに注意が必要ですが、近年は1.1億トン前後で推移しており、2021年度は1億1,161万トンと前年比3.7%増となりました。
鉄鋼業における石炭消費量は、1960年代後半から1970年代前半にかけて、経済成長に伴い2,000万トン台から1974年の6,800万トンまで増加しました。その後、1970年代後半は減少が続きましたが、1980年代以降は6,000万〜7,000万トン前後で推移しました。近年では、新型コロナ禍の影響を受けた2020年度は5,300万トン台まで減少しましたが、2021年度は5,959万トンと前年度比11.8%増となりました(第213-1-22)。
【第213-1-22】石炭の用途別消費量の推移
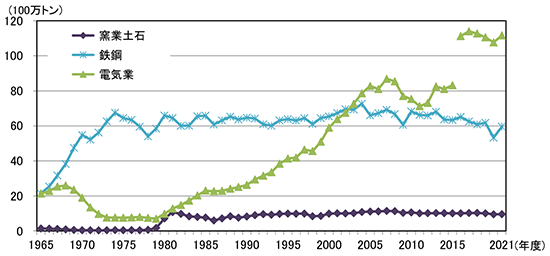
(注)2016年度以降の電気業は、小売業参入の全面自由化に伴う電気事業類型の見直しにより、調査対象事業者が変更されている。
【第213-1-22】石炭の用途別消費量の推移(xls/xlsx形式33KB)
- 資料:
- 2000年度までは経済産業省「エネルギー生産・需給統計年報」、2001年度以降同「石油等消費動態統計年報」、「電力調査統計年報」を基に作成
③石炭価格の動向
日本の輸入石炭価格(CIF価格)は、1990年代から2000年代半ばにかけて、原料炭が4,000〜10,000円/トンの価格帯で、一般炭は3,500〜8,000円/トンの価格帯で推移してきました。2000年代半ば以降は原油価格の上昇を受けて、石炭の採炭コスト・輸送コストも上昇し、さらには世界的な石炭需要の増大も重なって石炭価格が急騰しましたが、2009年に世界的な金融危機によって急落しました。中国等の需要増加により、2011年まで石炭価格が再び上昇しましたが、その後、欧米における脱石炭化の進展、中国の需要低迷等が原因で、2016年夏まで石炭価格は低下傾向が続きました。2016年夏以降、中国における需給のひっ迫等により、石炭価格は原料炭、一般炭ともに急騰しました。
原料炭の輸入価格は2017年3月には5年ぶりに20,000円/トン付近まで上昇し、その後は2019年5月まで17,000〜18,000円/トン台で推移しました。しかし、生産、輸出が順調である中、需要の伸びが鈍化したことを受け下落し始め、そこに新型コロナ禍による経済活動の低迷が加わり、2020年7月以降は10,000円/トン台で推移しました。その後、鉄鋼需要の回復や中国での需給ひっ迫から2021年12月には28,000円/トンまで上昇しました。そうした中、2022年2月にロシアによるウクライナ侵略が発生し、4月のEUと日本によるロシア炭の輸入禁止表明等もあり、5月には50,000円/トンまで上昇し、7月まで50,000円/トンを上回って推移しましたが、輸入需要が停滞する中で供給が追い付き、7月をピークに下落基調となり、2023年1月には40,000円/トン台まで下落しました。
一般炭の輸入価格は、2018年10月には14,000円/トン超まで上昇しましたが、以後は下落が続き、2020年8月以降は7,000円/トン台で推移しました。2021年に入り、一般炭も原料炭と同様にアジアでの需要の回復から上昇基調となり、2021年12月には22,000円/トン付近まで上昇しました。その後、2022年は2月のロシアによるウクライナ侵略、4月のEUと日本のロシア炭輸入禁止表明、豪州での天候不順により価格が急騰し、7月に50,000円/トンを上回り、11月には59,000円/トン台まで上昇しましたが、2023年1月には49,000円/トン台まで下落しました(第213-1-23)。
【第213-1-23】国内炭価格・輸入炭価格(CIF)の推移
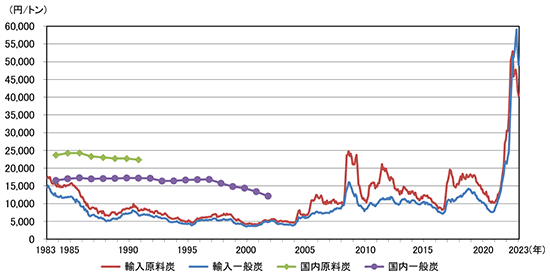
(注)輸入炭は月次平均データ、国内原料炭、国内一般炭は年度価格。国内原料炭は1990年度で生産が終了。国内一般炭の価格は、2002年度以降公表されていない。
【第213-1-23】国内炭価格・輸入炭価格(CIF)の推移(xls/xlsx形式70KB)
- 資料:
- 輸入炭については財務省「日本貿易統計」、国内炭については資源エネルギー庁「コール・ノート2003年版」を基に作成
また、日本の総輸入金額に占める石炭の輸入金額の割合は、1970年度に7%を超えていましたが、1980年代後半からは3%を下回る水準で推移してきました。2008年度には価格上昇のため4%を上回りましたが、その後は再び3%前後で推移し、2021年度は3.7%となりました(第213-1-24)。
【第213-1-24】石炭の輸入額と石炭輸入額が輸入全体に占める割合
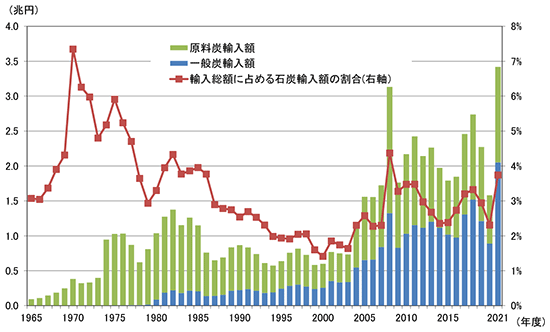
【第213-1-24】石炭の輸入額と石炭輸入額が輸入全体に占める割合(xls/xlsx形式80KB)
- 資料:
- 財務省「日本貿易統計」を基に作成
2.非化石エネルギーの動向
(1)原子力
①原子力発電の現状
原子力は、エネルギー資源に乏しい日本にとって、技術で獲得できる事実上の国産エネルギーとして、1954年5月の内閣諮問機関「原子力利用準備調査会」発足以降、電気事業者による原子力発電所の建設が相次いで行われました。2011年2月末時点で、日本国内では54基の商業用原子力発電所が運転されていました。しかし、2011年3月に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故後の同発電所1〜6号機の廃止に伴い、原子力発電所数は48基となりました。2015年4月には、民間事業者が適切かつ円滑な廃炉判断を行うことができるよう、政府として財務・会計上の措置を講じたことを踏まえ、運転開始後40年以上が経過した高経年炉7基のうち、日本原子力発電敦賀発電所1号機、関西電力美浜発電所1、2号機、中国電力島根原子力発電所1号機、九州電力玄海原子力発電所1号機について、さらに2016年5月には四国電力伊方発電所1号機について、各事業者が廃炉の判断を行い、運転を終了しました。また、2018年3月には関西電力大飯発電所1、2号機が、5月には四国電力伊方発電所2号機が、12月には東北電力女川原子力発電所1号機が運転を終了しました。さらに、2019年4月には九州電力玄海原子力発電所2号機が、9月には東京電力福島第二原子力発電所1〜4号機が運転を終了しました。
日本は、米国、フランス、中国に次ぎ、世界で4番目の設備能力を有しており(2022年1月現在の原子力発電設備容量)、ロシア、韓国、カナダがこれに続いています(第213-2-1)。
【第213-2-1】世界の原子力発電設備容量(2022年1月現在)
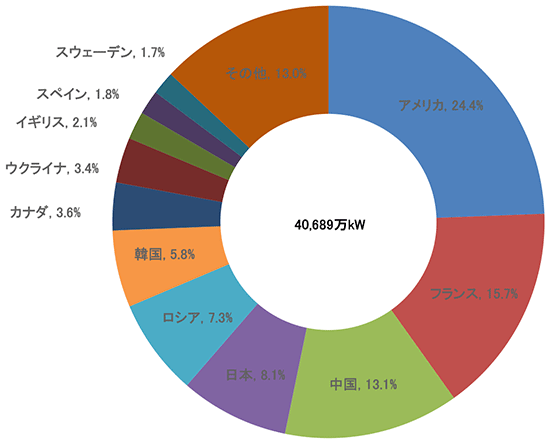
【第213-2-1】世界の原子力発電設備容量(2022年1月現在)(xls/xlsx形式21KB)
- 資料:
- 日本原子力産業協会「世界の原子力発電開発の動向2022年版」を基に作成
日本の発電電力量に占める原子力発電のシェアは、2010年度に25.1%でしたが、2011年度に9.3%、2012年度に1.5%、2013年度に0.9%となり、2014年度は原子力発電所の稼動基数がゼロになったことに伴い0%となりました。その後は再稼動が進んだため、2021年度に6.9%となりました(第214-1-6参照)。
また、原子力発電所の設備利用率(東京電力福島第一原子力発電所の事故後に運転を停止し、その後再稼働に至らず停止中の発電所も含め、運転を終了した炉を除く全ての発電所を基に計算)は2010年度時点で67.3%でしたが、2013年度に2.3%、2014年度に0%まで低下した後、再稼働が進むにしたがって回復しており、2015年度に2.6%、2016年度に5.0%、2017年度に9.1%、2018年度に19.3%、2019年度に20.8%、2020年度に13.5%、2021年度に24.5%となりました(第213-2-2)。
【第213-2-2】日本の原子力発電設備利用率の推移
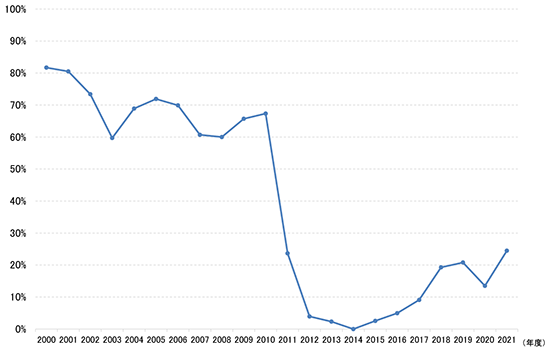
【第213-2-2】日本の原子力発電設備利用率の推移(xls/xlsx形式19KB)
- 資料:
- 原子力安全基盤機構「原子力施設運転管理年報」、原子力規制庁「実用発電用原子炉施設、研究開発段階発電用原子炉施設、加工施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設における放射性廃棄物の管理状況及び放射線業務従事者の線量管理状況について」、経済産業省「電力調査統計」、「総合エネルギー統計補足調査」を基に作成
日本で主として採用されている原子炉は、軽水炉と呼ばれるものであり、軽水23を減速材・冷却材24に兼用し、燃料には低濃縮ウランを用います。軽水炉は、世界の原子力発電の中心となっており、沸騰水型(BWR)と加圧水型(PWR)の2種類に分類されます。このうち、BWRは原子炉の中で蒸気を発生させ、それにより直接タービンを回す方式であり、PWRは原子炉で発生した高温高圧の水を蒸気発生器に送り、そこで蒸気を作ってタービンを回す方式です(第213-2-3)。
【第213-2-3】BWRとPWR
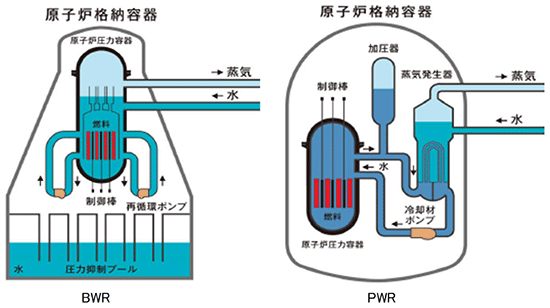
【第213-2-3】BWRとPWR(ppt/pptx形式:181KB)
- 資料:
- 日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」を基に作成
②核燃料サイクル
核燃料サイクルは、原子力発電所から出る使用済燃料を再処理し、未使用のウランや新たに生まれたプルトニウム等の有用資源を回収して、再び燃料として利用するものです。具体的には、再処理工場で回収されたプルトニウムを既存の原子力発電所(軽水炉)で利用するプルサーマルが挙げられ、回収されたプルトニウムをウランと混ぜて加工される混合酸化物燃料(MOX燃料)が、プルサーマルに使用されています。
日本は、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減等の観点から、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイクルの推進を基本的方針としています(第213-2-4)。
【第213-2-4】核燃料サイクル
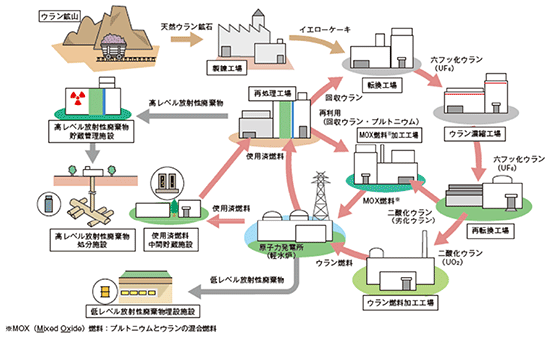
【第213-2-4】核燃料サイクル(ppt/pptx形式:95KB)
- 資料:
- 日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」
(ア)使用済燃料問題の解決に向けた取組
日本では、原子力利用に伴い確実に発生する使用済燃料について、将来世代に負担を先送りしないように対策を総合的に推進しており、高レベル放射性廃棄物についても、国が前面に立ち、最終処分に向けた取組を進めています。また、使用済燃料については、再処理工場への搬出を前提とし、その搬出までの間、各原子力発電所等において、安全を確保しながら計画的に貯蔵するための対策を進めており、引き続き、発電所の敷地内外を問わず、中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設等の建設・活用を進めることにより、使用済燃料の貯蔵能力の拡大に向けた取組を進めています。あわせて、将来の幅広い選択肢を確保するため、放射性廃棄物の減容化・有害度低減等の技術開発を進めています。
(ⅰ)放射性廃棄物の処分
原子力発電所で発生した低レベル放射性廃棄物の処分については、発生者責任に基づき、原子力事業者等が処分に向けた取組を進めることとしています。放射能レベルに応じて、処分する深さや放射性物質の漏出を抑制するためのバリアの違いにより、人工構造物を設けない浅地中埋設処分(浅地中(トレンチ)処分)、コンクリートピットを設けた浅地中への処分(浅地中(ピット)処分)、一般的な地下利用に対して十分余裕を持った深度(地下70m以上)への処分(中深度処分)、地下300m以上深い地層中への処分(地層処分)のいずれかの方法により処分することとしています(第213-2-5)。
【第213-2-5】放射性廃棄物の種類と概要
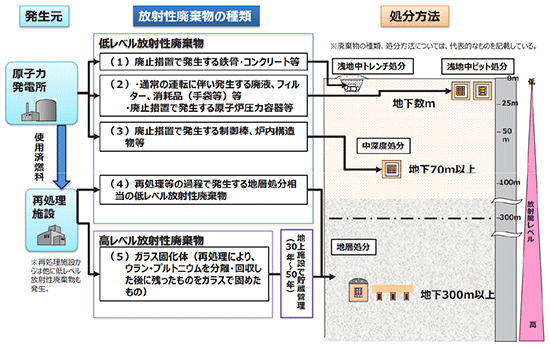
【第213-2-5】放射性廃棄物の種類と概要(ppt/pptx形式:505KB)
- 資料:
- 資源エネルギー庁
2021年3月末時点の各原子力施設の運転及び解体により発生する低レベル放射性廃棄物の保管量は、全国の原子力施設(原子炉施設、加工施設、再処理施設、廃棄物埋設・管理施設、核燃料物質使用施設)において、容量200Lドラム缶に換算して約118万本分の貯蔵となりました。また、使用済燃料プール、サイトバンカ、タンク等には、使用済制御棒、チャンネルボックス、使用済樹脂、シュラウド取替により発生した放射性廃棄物の一部等が保管されています。日本原燃は、青森県六ヶ所村において1992年12月に低レベル放射性廃棄物埋設施設の操業を開始し、2022年3月末時点で、約34万本のドラム缶を埋設処分しています。加えて、日本原子力研究所(現日本原子力研究開発機構)動力試験炉(JPDR)の解体に伴い発生したものについては、茨城県東海村の同機構敷地内の廃棄物埋設実地試験施設において、約1,670トンの浅地中トレンチ処分が行われています。
一方、発電によって発生した使用済燃料は、高レベル放射性廃棄物としてガラス固化され、冷却のため30年〜50年間程度貯蔵した後、地下300m以上深い地層に処分されます。国内では日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所の再処理施設において、国外ではフランス、英国の再処理施設において再処理が行われてきました。使用済燃料の再処理に伴って発生する高レベル放射性廃棄物は、ガラス固化体として、2022年3月末時点で、国内で処理されたもの、海外から返還されたものをあわせて2,505本が国内(青森県六ヶ所村、茨城県東海村)で貯蔵されています。また、同月末までの原子力発電の運転により生じた使用済燃料を、全て再処理しガラス固化体にした本数に換算すると、約26,000本相当が発生しています。
この高レベル放射性廃棄物及び一部のTRU廃棄物については、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)」(以下「最終処分法」という。)に基づき、地層処分を行うべく、原子力発電環境整備機構(NUMO)が、2002年から文献調査の受入自治体の公募を開始しました。経済産業省は、2015年5月、最終処分法に基づく基本方針を改定(閣議決定)し、科学的に適性が高いと考えられる地域を国から提示する等、国が前面に立って取組を進め、2017年7月の最終処分関係閣僚会議を経て、火山や断層等といった、処分地選定で考慮すべき科学的特性を全国地図の形で示した「科学的特性マップ」を公表しました。科学的特性マップ公表後は、地層処分という処分方法の仕組みや日本の地下環境等に関する国民の皆さまの理解を深めていただくため、マップを活用した全国各地での説明会を実施する等、全国的な対話活動に取り組んでいます。また、2019年に取りまとめた「複数地域での文献調査に向けた当面の取組方針」に沿って対話活動を進めていく中で、地層処分事業をより深く知りたいと考える経済団体、大学・教育関係者、NPO等、関心のあるグループが、2022年12月末時点において全国で約160団体に増えており、勉強会や情報発信等の多様な取組が活発に行われてきています。
その中で2020年10月、立地選定の第1段階である文献調査に応募した北海道寿都町及び国からの文献調査申入れを受託した北海道神恵内村の2町村において、同年11月17日より文献調査を開始し、2021年4月に両町村で「対話の場」を立ち上げました。引き続き、この事業に関心を持つ全国のできるだけ多くの地域で、文献調査を通じて、対話の場等も活用しながら、調査の進捗状況の説明や地域の将来ビジョンについての議論等を、積極的・継続的に積み重ねていきます。
(ⅱ)使用済燃料の中間貯蔵
使用済燃料の中間貯蔵とは、使用済燃料が再処理されるまでの間、一時的に貯蔵・管理することをいいます。
日本では青森県むつ市において、使用済燃料を貯蔵・管理する法人であるリサイクル燃料貯蔵の中間貯蔵施設1棟目について、2010年8月に貯蔵建屋の建設工事が着工され、2013年8月に完成しました。
2014年1月、リサイクル燃料貯蔵は、新規制基準(2013年12月施行)への適合性審査を原子力規制委員会に申請し、2020年11月に許可されました。安全審査の進捗を踏まえ、追加工事の工程見直しが行われ、事業開始時期は2023年度になっています。
(ⅲ)放射性廃棄物の減容化・有害度低減に向けた取組
原子力利用に伴い発生する放射性廃棄物の問題は、世界共通の課題であり、将来世代に負担を先送りしないよう、その対策を着実に進めることが不可欠です。
高速炉は、マイナーアクチノイド等の長寿命核種を燃焼させることができる等、放射性廃棄物の減容化・有害度の低減を可能とする有用な技術であり、フランス、米国、ロシアや中国等の諸外国においても、その開発が進められています。
このような国際動向の下、フランス及び米国と、二国間の国際協力を実施しています。フランスとは、2014年5月に安倍総理が訪仏した際に、日本側の経済産業省と文部科学省、フランス側の原子力・代替エネルギー庁(CEA)が、フランスのナトリウム冷却高速炉の実証炉開発計画である第4世代ナトリウム冷却高速炉実証炉(ASTRID)計画及びナトリウム冷却炉の開発に関する一般取決めに署名し、日仏間の研究開発協力を開始しました。その後、2019年6月に、2020年から2024年までの研究開発協力の枠組みについて定めた新たな取決めを締結(日本:経済産業省、文部科学省、フランス:原子力・代替エネルギー庁)し、2020年1月から、本取決めの下で、シミュレーションや実験に基づく協力を実施しています。米国とは、米国が建設を検討するVTR(多目的試験炉)計画への研究協力に関する覚書に2019年6月に署名し、安全に関する研究開発等を開始しました。また、多国間協力としては、高い安全性を実現することを狙いとして、国際的な枠組み(第4世代原子力システムに関する国際フォーラム(GIF))において、ナトリウム冷却高速炉に関する安全設計の基準の構築を進めると同時に、その基準を国際的な標準とするべく専門家間での議論を実施しています。
(イ)核燃料サイクルの工程(プルサーマルの場合)
原子力発電の燃料となるウランは、最初、ウラン鉱石の形で鉱山から採掘されます。ウランは、様々な工程(製錬→転換→濃縮→再転換→成型加工)を経て燃料集合体に加工された後、原子炉に装荷され発電を行います。発電後には、使用済燃料を再処理することにより、有用資源であるプルトニウム等を回収します。
(ⅰ)製錬
ウラン鉱山からウラン鉱石を採掘して、ウラン鉱石を化学処理してウラン(イエローケーキ、U3O8)を取り出す工程です。日本では、ウラン鉱石をカナダ、豪州、カザフスタン等から調達してきました。現在、国内ではこの工程は行われていません。
(ⅱ)転換
イエローケーキを次の濃縮工程のためにガス状(UF6)にする工程であり、日本ではこの工程を海外にある転換会社に委託してきました。
(ⅲ)濃縮
ウラン濃縮とは、核分裂性物質であるウラン235の濃縮度を、天然の状態の約0.7%から軽水炉による原子力発電に適した3%〜5%に高めることを意味し、日本では、日本原燃が青森県六ヶ所村のウラン濃縮施設において遠心分離法という濃縮技術を採用しました。
日本原燃は、1992年3月から年間150トンSWU25の規模で操業を開始し、1998年末には年間1,050トンSWU規模に到達しました。その後、遠心分離機を順次新型に置き換えるため、2010年3月から導入初期分である年間75トンSWUの更新工事を行い、前半分は2012年3月に、後半分は2013年5月に、それぞれ年間37.5トンSWU規模で生産運転を開始しました。
2014年1月、日本原燃はウラン濃縮工場の新規制基準(2013年12月施行)への適合性審査を原子力規制委員会に申請し、2015年8月の認可によって暫定的に全工程の稼動が可能となった後、2017年5月に正式に審査が完了しました。既設遠心機の一部の生産機能停止によって、現在の施設規模は年間450トンSWUとなっていますが、今後、段階的に新型遠心分離機への更新工事等を行い、最終的には年間1,500トンSWU規模を達成する計画です。
(ⅳ)再転換
成型加工工程のためにUF6をパウダー状のUO2にする工程であり、日本では、三菱原子燃料(茨城県東海村)のみが再転換事業を行っています。なお、それ以外の分については、海外の再転換工場に委託してきました。
(ⅴ)成型加工
UO2粉末を焼き固めたペレットにした後、燃料集合体に加工する工程で、日本ではこの工程の大半を国内の成型加工工場で行ってきました。
(ⅵ)再処理
使用済燃料の再処理とは、原子力発電所で発生した使用済燃料から、まだ燃料として使うことのできるウランと新たに生成されたプルトニウムを取り出すことをいいます。青森県六ヶ所村に建設中の日本原燃再処理事業所再処理施設(年間最大処理能力:800トン)では、2006年3月から実際の使用済燃料を用いた最終試験であるアクティブ試験を実施してきました。
使用済燃料からプルトニウム・ウランを抽出する工程等の試験は既に完了しており、高レベル放射性廃液をガラス固化する工程の確立に時間を要していましたが、2012年6月から試験を再開し、安定運転に向けた最終段階の試験を実施しました。最大処理能力での性能確認等を実施し、2013年5月に使用前事業者検査を除く全ての試験を終了しました。
その後、2014年1月に日本原燃は、六ヶ所再処理工場の新規制基準(2013年12月施行)への適合性審査を原子力規制委員会に申請し、2020年7月に許可されました。2024年度上期のできるだけ早期の竣工に向けて、最終的な安全機能や機器設備の性能を確認しています。
(ⅶ)MOX燃料加工
MOX燃料加工は、再処理工場で回収されたプルトニウムをウランと混ぜて、プルサーマルに使用されるMOX燃料に加工することをいいます。日本では、日本原燃が青森県六ヶ所村においてMOX燃料工場の工事を2010年10月に着工しました。その後、東日本大震災の影響により一時中断していましたが、2012年4月から建設を再開しました。2014年1月、日本原燃はMOX燃料工場の新規制基準(2013年12月施行)への適合性審査を原子力規制委員会に申請し、2020年12月に許可されました。2024年度上期の竣工を目指し建設工事を進めています。
(ⅷ)プルトニウムの適切な管理と利用
日本は、プルトニウム利用の透明性向上のため、1994年から毎年「我が国のプルトニウム管理状況」を公表しており、内閣府が取りまとめを行っています。また、1998年からはプルトニウム管理に関する指針に基づき、国際原子力機関(IAEA)を通じて、日本のプルトニウム保有量を公表しています。その上で、利用目的のないプルトニウムは持たないとの原則を引き続き堅持し、プルトニウム保有量の削減に取り組む方針としており、再処理によって回収されたプルトニウムを既存の原子力発電所(軽水炉)で利用するプルサーマルに取り組んでいます。
電気事業連合会は、2020年12月に、基本的なプルサーマル導入の方針を示すプルサーマル計画を公表し、地元理解を前提に、稼働する全ての原子炉を対象に1基でも多くプルサーマル導入を検討するとともに、当面の目標として、2030年度までに少なくとも12基でのプルサーマルの実施を目指す旨を表明しました。さらに電気事業連合会は、2021年2月に、より具体的なプルトニウムの利用見通しを示すプルトニウム利用計画も公表しました。
これらを踏まえ、再処理事業の実施主体である使用済燃料再処理機構が中期計画を策定、2021年3月に経済産業省が原子力委員会の意見も聴取した上で認可し、プルトニウムバランスの確保に向けた具体的な取組方針が示されました。その後、2022年2月に公表された日本原燃による六ヶ所再処理施設及びMOX燃料加工施設の暫定操業計画、電気事業者によるプルトニウム利用計画を踏まえ、再処理機構は同年3月に、具体的な再処理量等を実施中期計画に記載し、経済産業大臣に対して変更の認可申請を行いました。原子力委員会の意見を踏まえ、同年3月に経済産業大臣は実施中期計画の変更を認可しました。
また、プルトニウム利用に関する日米の取組として、2014年3月、日本と米国は日本原子力研究開発機構の高速炉臨界実験装置から高濃縮ウラン(HEU)と分離プルトニウムを全量撤去し処分することで合意し、両国の声明により、「この取組は、数百キロの核物質の撤廃を含んでおり、世界規模で高濃縮ウラン及び分離プルトニウムの保有量を最小化するという共通の目標を推し進めるものであり、これはそのような核物質を権限のない者や犯罪者、テロリストらが入手することを防ぐのに役立つ」と説明しました。また、同月にオランダ・ハーグで開催された第3回核セキュリティ・サミットにおいて、安倍総理は「利用目的のないプルトニウムは持たない」との原則を引き続き堅持する旨を表明するとともに、プルトニウムの回収と利用のバランスを十分に考慮すること、プルトニウムの適切な管理を引き続き徹底することを表明しました。また、日米首脳間の共同声明では、日本原子力研究開発機構の高速炉臨界実験装置(FCA)からHEUとプルトニウムを全量撤去することを表明しました。2016年4月には、米国・ワシントンD.C.で開催された第4回核セキュリティ・サミットにおいて、安倍総理は、FCAからの燃料の撤去予定を大幅に前倒しして完了したこと、さらに現在HEU燃料を利用している京都大学臨界集合体実験装置(KUCA)を低濃縮ウラン(LEU)燃料利用の原子炉に転換し、全てのHEU燃料を米国に移送すること等を発表し、その後、2022年8月に完了しました。
③原子力施設の廃止措置
廃止が決定された原子力発電所の廃止措置は、事業者が作成し規制機関の認可を受けた廃止措置計画に基づき実施されます。廃止措置の主な手順としては、「原子炉の解体」を中心として4つのステップがあります(第213-2-6)。
【第213-2-6】原子力発電所廃止措置の流れ
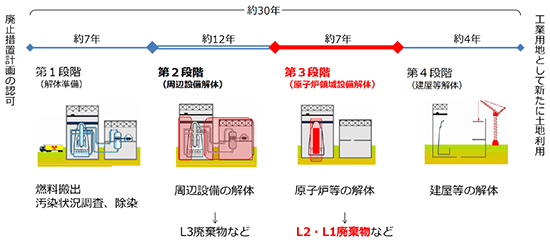
【第213-2-6】原子力発電所廃止措置の流れ(ppt/pptx形式:155KB)
- 資料:
- 2019年4月23日「総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会」
使用済燃料の搬出のほか、放射性物質を多く含むものは放射線を出す能力が徐々に減る性質を利用して、時間を置いてその量を減らしたり(安全貯蔵)、一部の放射性物質を先に取り除いたり(汚染の除去)して、規制に基づいて解体を進め、丁寧に放射性物質を取り除いていきます。
1950年代に始まった日本の原子力利用から既に50年以上が経過し、一部の原子力施設では施設の廃止や解体が行われ、所要の安全確保の実績が積み上げられてきました。一方、これらの経験を踏まえ、安全確保のための制度上の手続面の明確化や、原子力施設の廃止や解体に伴って発生する様々な種類の廃棄物等から、放射性物質として管理する必要のあるものと、汚染のレベルが自然界の放射性物質の放射線レベルと比べても極めて低く、管理すべき放射性物質として扱う必要のないものを区分するための制度(クリアランス制度)の創設が必要とされていました。こうした状況を踏まえ、2005年5月に原子炉等規制法を改正して、廃止措置及びクリアランス制度等の導入が行われました。
原子力発電所の廃止措置に伴い発生する解体廃棄物の総量は、110万kW級の軽水炉の場合、約50万トンとなり、これらの廃棄物を適正に処分していくことが重要です。
運転中・解体中に発生する廃棄物の中には、安全上「放射性物質として扱う必要のないもの」も含まれています。これらは、放射能を測定し安全であることを確認し、国のチェックを受けた後、再利用できるものはリサイクルし、できないものは産業廃棄物として処分することとしています。国によるチェックが行われた後、放射性廃棄物として適切に処理処分する必要がある低レベル放射性廃棄物の量は、各電力会社が2020年4月時点で公表している「廃止措置実施方針」によると、51プラント合計で約48万トン(総廃棄物重量の約2%)と試算されました。この中には炉内構造物等の「放射能レベルの比較的高いもの」が約8,000トン(総廃棄物重量の約0.04%)、コンクリートピットを設けた浅地中への処分が可能な「放射能レベルの比較的低いもの」が約8万トン(総廃棄物重量の約0.3%)、また、堀削した土壌中への埋設処分(浅地中トレンチ処分)が可能な「放射能レベルの極めて低いもの」が約40万トン(総廃棄物重量の約1.8%)含まれていると試算されました。
日本では1998年に日本原子力発電東海発電所が営業運転を停止し、廃止措置段階に入っており、試験研究炉では、日本原子力研究所(現・日本原子力研究開発機構)の動力試験炉(JPDR)の解体撤去が、1996年3月に計画どおり完了し、2002年10月に廃止届が届けられました。また、研究開発段階にある発電用原子炉では、2003年に運転を終了した日本原子力研究開発機構の新型転換炉ふげん発電所の廃止措置計画の認可が2008年2月に行われました。同発電所は、原子炉廃止措置研究開発センターに改組され、廃止措置のための技術開発を進めてきました。
2009年1月、中部電力は浜岡原子力発電所1号機と2号機を廃止し、11月に廃止措置計画の認可が行われました。また、2011年3月に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故後、同発電所1〜6号機が廃止となる等、2023年3月時点で、各事業者の判断により24基の商業用原子力発電所の廃炉が決定されています。
(2)再生可能エネルギー
①全般
再エネは、化石エネルギー以外のエネルギー源のうち、永続的に利用することができるものを利用したエネルギーであり、代表的なものとしては太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等が挙げられます。
日本の再エネの導入拡大に向けた取組は、「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号)」(以下「石油代替エネルギー法」という。)に基づく石油代替政策に端を発しており、1970年代の二度の石油危機を契機に、日本は石油から石炭、天然ガス、原子力、再エネ等の石油代替エネルギーへのシフトを進めました。
石油代替エネルギーの技術開発については、1974年に通商産業省工業技術院(現・産業技術総合研究所)が「サンシャイン計画」を開始しました。この計画は、将来的にエネルギー需要の相当部分を賄いうるエネルギーの供給を目標として、太陽、地熱、石炭、水素エネルギーの4つの石油代替エネルギー技術について重点的に研究開発を進めるものでした。また、1980年に設立された新エネルギー総合開発機構(現・新エネルギー・産業技術総合開発機構:以下「NEDO」という。)において、石炭液化技術開発、大規模深部地熱開発のための探査・掘削技術開発、太陽光発電技術開発等が重点プロジェクトとして推進されました。その後、1993年に「サンシャイン計画」は、「ムーンライト計画」と統合され、「ニューサンシャイン計画」として再スタートすることとなりました。「ニューサンシャイン計画」は、従来独立して推進されていた新エネルギー、省エネ及び地球環境の3分野に関する技術開発を総合的に推進するものでしたが、2001年の中央省庁再編に伴い、「ニューサンシャイン計画」の研究開発テーマは、以後「研究開発プログラム方式」によって実施されることとなりました。
さらに、石油代替エネルギーのうち、経済性における制約から普及が十分でない新エネルギーの普及促進を目的として、1997年に「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)」が制定されました。同法は、国や地方公共団体、事業者、国民等の各主体の役割を明確化する基本方針の策定や、新エネルギー利用等を行う事業者に対する財政面の支援措置等を定めたものです。
こうした取組の結果、日本の一次エネルギー供給に占める石油の割合は、1973年度の75.5%から、2021年度には36.3%にまで低下しました。しかし、天然ガス、石炭等も含めた化石エネルギー全体の依存度は、2021年度には83.2%となっています。
一方、近年の世界のエネルギー需要の急増等を背景に、今後は従来どおりの質・量の化石エネルギーを確保していくことが困難となることが懸念されています。このような事態に対応し、また、低炭素社会の実現にも寄与すべく、2009年7月に、石油への依存の脱却を図るというこれまでの石油代替施策の抜本的な見直しが行われました。この結果、研究開発や導入を促進する対象を「石油代替エネルギー」から、再エネや原子力等を対象とした「非化石エネルギー」とすることを骨子とした石油代替エネルギー法の改正が行われ、同法の名称も「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に改められました。また、あわせて「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号)」(以下「高度化法」という。)が制定され、エネルギー供給事業者に対して再エネ等の非化石エネルギーの利用を一層促進する枠組みが構築されました。
また、2003年からは、「電気事業者による新エネルギー電気等の利用に関する特別措置法(平成14年法律第62号)」(以下「RPS法」という。)に基づき、RPS(Renewables Portfolio Standard)制度26を開始し、電気分野における再エネの導入拡大を進めました。さらに2012年7月からは、このRPS制度に替えて、固定価格買取(FIT)27制度(以下「FIT制度」という。)を導入し、再エネの大幅な導入拡大を進めています。2017年4月にはこのFIT制度が改正され、設備に代わり事業計画を確認する制度となったことで、適切なメンテナンス等を事業者に課すようになりました。FIT制度の導入により、再エネに対する投資回収の見込みが安定化したこともあり、制度開始後、2021年度末までに運転を開始した再エネ発電設備は制度開始前と比較して約3.3倍に増加しました。2022年4月からは、再エネ発電事業者の投資予見可能性を確保しつつ、市場を意識した行動を促すため、FIT制度に加えて、新たに、市場価格を踏まえて一定のプレミアムを交付する制度(FIP制度)28が創設されました。
②太陽光発電
太陽光発電は、シリコン半導体等に光が当たると電気が発生する現象を利用し、太陽の光エネルギーを太陽電池(半導体素子)により直接電気に変換する発電方法です。日本における導入量は、近年着実に伸びており、2021年度末累積で6,935万kWに達しました。企業による技術開発や、国内で堅調に太陽光発電の導入が進んだことにより、太陽光発電設備のコストも着実に低下しています(第213-2-7)。
【第213-2-7】太陽光発電の国内導入量とシステム価格の推移
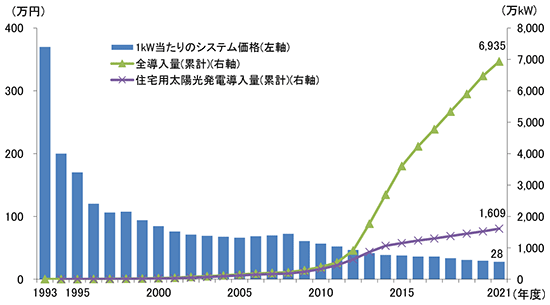
(注)システム価格は住宅用(10kW未満)の平均値(設置年別の推移)。
【第213-2-7】太陽光発電の国内導入量とシステム価格の推移(xls/xlsx形式25KB)
- 資料:
- システム価格は経済産業省資源エネルギー庁資料を基に作成、国内導入量は2014年度まで太陽光発電普及拡大センター資料、2015年度以降は資源エネルギー庁「固定価格買取制度 情報公開用ウェブサイト」を基に作成
太陽電池の国内出荷量は、住宅用太陽光発電設備に対する政府の補助制度が一時打ち切られた2005年度をピークに伸び悩んでいましたが、2009年1月に補助制度が再度導入され、地方自治体による独自の補助制度もあわせると設置費用が低減したことや、2009年11月に太陽光発電の余剰電力買取制度が開始されたこと等を受けて、2009年度から増加基調に転じています。また、2012年に開始したFIT制度の効果により、非住宅分野での太陽光発電の導入が急拡大し、2014年度に太陽電池の国内出荷量は過去最高を記録しました。その後、太陽光発電の買取価格が引き下げられていること等により、2015年度以降の出荷量は減少傾向となりました(第213-2-8)。
【第213-2-8】太陽電池の国内出荷量の推移
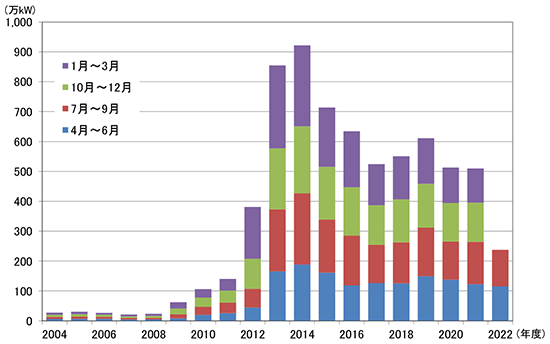
(注)2022年度は4月から9月まで。
【第213-2-8】太陽電池の国内出荷量の推移(xls/xlsx形式21KB)
- 資料:
- 太陽光発電協会資料を基に作成
世界的に見ると、日本は2003年末まで太陽光発電の累積導入量が世界第1位でしたが、ドイツの導入量が急速に増加した結果、2004年にはドイツに次ぐ世界第2位となりました。その後、ドイツの累積導入量を再び上回ったものの、近年、中国や米国の年間導入量が急速に増加しており、2021年末の累積導入量では世界第3位となっています(第213-2-9)。
【第213-2-9】世界の累積太陽光発電設備容量(2021年)
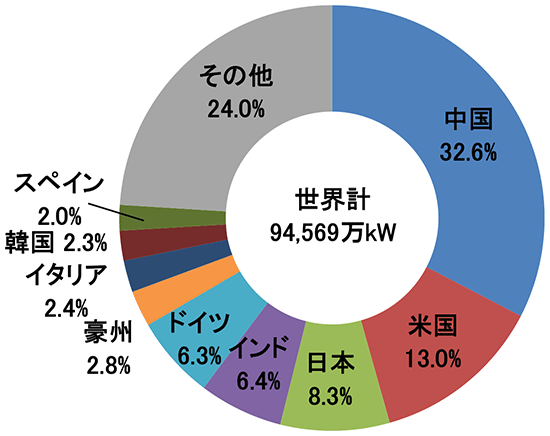
【第213-2-9】世界の累積太陽光発電設備容量(2021年)(xls/xlsx形式21KB)
- 資料:
- IEA Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS)「Trends in Photovlotanic Applications 2022」、「2022 Snapshot of Global PV Markets」を基に作成
また、日本は太陽電池の生産量でも2007年まで世界でトップでしたが、2013年をピークに減少傾向となり、中国を始めとするアジアの企業が生産を拡大した結果、2021年時点では世界の太陽電池(モジュール)生産量に占める日本の割合は0.9%にまで落ち込み、その一方で中国(75%)の寡占化が進みました(第213-2-10)。日本における太陽電池の国内出荷量に占める国内生産品の割合を見ると、2008年度まではほぼ100%でしたが、国内出荷量が大幅な増加基調に転じた2009年度から低下し、2021年度では12%でした(第213-2-11)。
【第213-2-10】世界の太陽電池(モジュール)生産量(2021年)
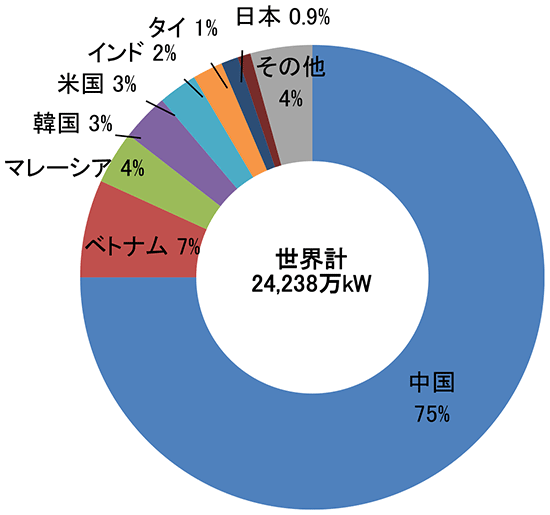
【第213-2-10】世界の太陽電池(モジュール)生産量(2021年)(xls/xlsx形式21KB)
- 資料:
- IEA Photovoltaic Power Systems Programme(PVPS)「Trends in Photovoltaic Applications 2022」を基に作成
【第213-2-11】太陽電池国内出荷量の生産地構成の推移
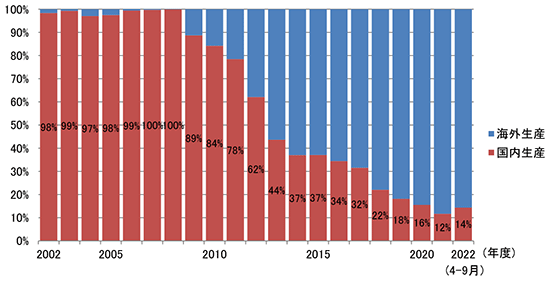
【第213-2-11】太陽電池国内出荷量の生産地構成の推移(xls/xlsx形式21KB)
- 資料:
- 太陽光発電協会資料を基に作成
太陽光発電には、天候や日照条件等により出力が不安定であるという課題が残されています(第213-2-12)。特に九州エリアでは需要に比して大規模な導入が進んでおり(第213-2-13)、近年では太陽光発電のピーク時に、エリア内電力需要(1時間値)の8割以上を太陽光発電が占めることもあります。導入が進展する地域においては、午前の残余需要29の減少及び夕方の残余需要の増加の程度が以前より急激になっており、系統運用上の課題となっています。太陽光導入量が多い九州エリアではこの問題が特に顕著であり、太陽光の出力変動に対し、火力、揚水等だけでは調整が困難になり始めたため、2018年10月には計4日、離島を除いて国内で初めてとなる、太陽光の出力抑制を実施しました。2019年度以降も九州エリアでは、太陽光の出力制御が実施されています(第213-2-14)。2022年度は、北海道・東北・中国・四国エリアでも初めて出力制御が行われました。太陽光発電の導入拡大のためには、コスト低減に向けた技術開発とともに、出力変動への対応を進めることが重要になります。
【第213-2-12】太陽光発電の天候別発電電力量の推移
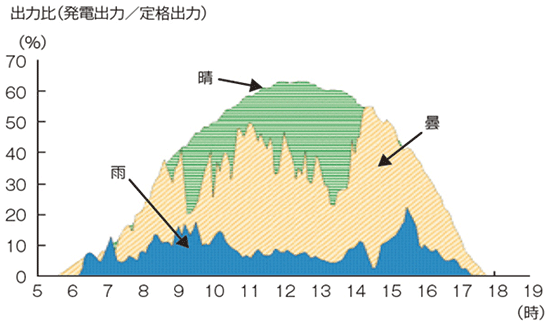
【第213-2-12】太陽光発電の天候別発電電力量の推移(ppt/pptx形式:94KB)
- 資料:
- 資源エネルギー庁調べ
【第213-2-13】FIT制度による太陽光発電の認定量・導入量(2021年度末)
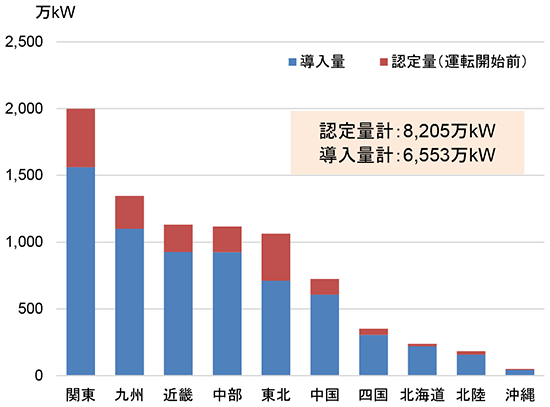
(注)「認定量」は「導入量」と既認定未稼働設備容量(「認定量(運転開始前)」)の合計値である。
【第213-2-13】FIT制度による太陽光発電の認定量・導入量(2021年度末)(xls/xlsx形式24KB)
- 資料:
- 資源エネルギー庁 固定価格買取制度 情報公開用ウェブサイトを基に作成
【第213-2-14】九州エリア需給実績と出力抑制の状況(2020年4月30日)
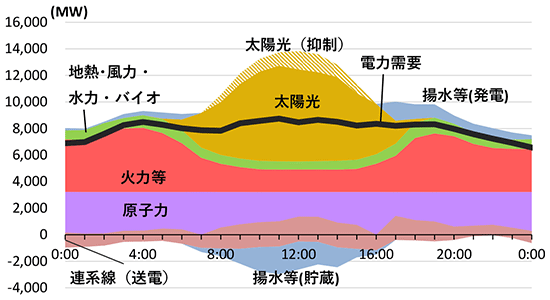
(注)太陽光発電の自家消費分は、「太陽光」には含まれず、「電力需要」の減少分として表れている。
【第213-2-14】九州エリア需給実績と出力抑制の状況(2020年4月30日)(xls/xlsx形式28KB)
- 資料:
- 九州電力送配電Webサイトを基に作成
③太陽熱利用
太陽エネルギーによる熱利用は、古くは太陽光を室内に取り入れることから始まっていますが、積極的に利用され始めたのは、太陽熱を集めて温水を作る温水器の登場からです。太陽熱利用機器はエネルギー変換効率が高く、新エネルギーの中でも設備費用が比較的安価で費用対効果の面でも有効であり、現在までの技術開発により、用途を給湯に加え暖房や冷房にまで広げた高性能なソーラーシステムが開発されました。
太陽熱利用機器の普及は、1979年の第二次石油危機を経て、1980年代前半にピークを迎えました。1990年代中期以降は石油価格が低く推移していたことや、競合する他の製品の台頭等を背景に、新規設置台数が年々減少してきました(第213-2-15)。
【第213-2-15】太陽熱温水器(ソーラーシステムを含む)の新規設置台数
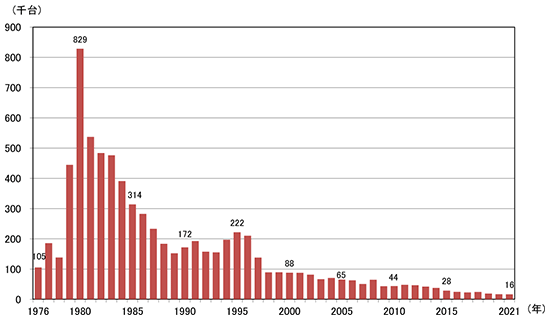
【第213-2-15】太陽熱温水器(ソーラーシステムを含む)の新規設置台数(xls/xlsx形式26KB)
- 資料:
- ソーラーシステム振興協会資料、経済産業省生産動態統計年報を基に作成
④風力発電
風力発電は風の力で風車を回し、その回転運動を発電機に伝えて電気を起こす発電方法です。
1997年度に開始された設備導入支援を始め、1998年度に行われた電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインの整備や2003年度のRPS法の施行、2012年に開始したFIT制度等により、風力発電の導入が図られました。2021年末時点での導入量は、2,574基、出力約458万kW(第213-2-16)であるとともに、未稼動分を含めたFIT制度による認定量は合計で1,571万kWとなっており、そのうち約4割は東北に集中しています(第213-2-17)。未稼働の案件が順次稼動すれば、太陽光発電と同様に出力変動の問題がより大きくなり、電力系統への影響緩和のため、出力変動に応じた調整力の確保や系統の強化が課題となっています。
【第213-2-16】日本における風力発電導入の推移
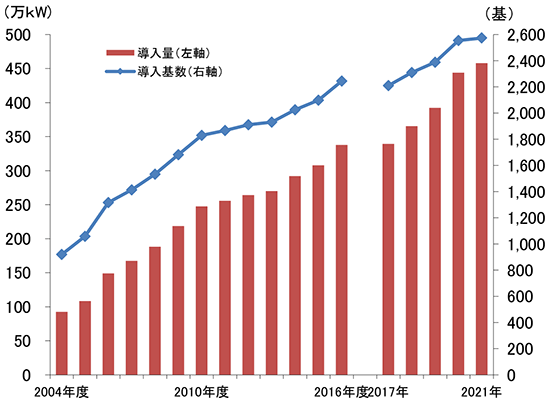
(注)2016年までは年度単位、2017年からは暦年単位の累計導入実績。
【第213-2-16】日本における風力発電導入の推移(xls/xlsx形式22KB)
- 資料:
- 一般社団法人日本風力発電協会(JWPA)統計を基に作成
【第213-2-17】FIT制度による風力発電の認定量・導入量(2021年度末)
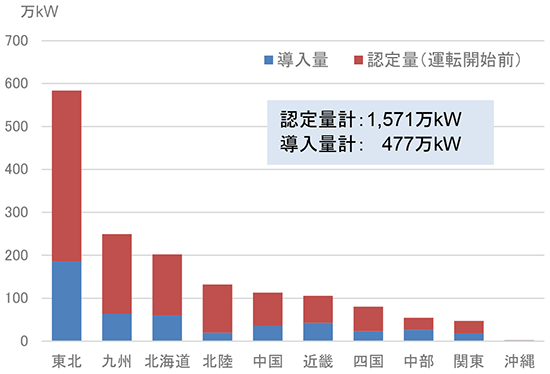
(注)「認定量」は「導入量」と既認定未稼働設備容量(「認定量(運転開始前)」)の合計値である。
【第213-2-17】FIT制度による風力発電の認定量・導入量(2021年度末)(xls/xlsx形式26KB)
- 資料:
- 資源エネルギー庁固定価格買取制度 情報公開用ウェブサイトを基に作成
他方、日本の風力発電設備容量は、2021年末時点で世界第21位となっています(第213-2-18)。これには、日本が諸外国に比べて平地が少なく地形も複雑なこと、電力会社の系統に余裕がない場合があること等の理由から、風力発電の設置が進みにくいといった事情があります。
【第213-2-18】風力発電導入量の国際比較(2021年末時点)
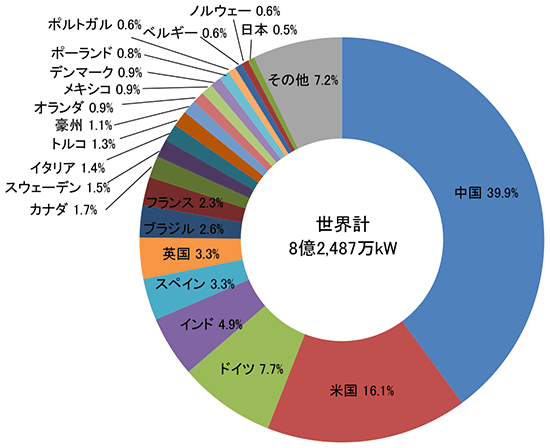
【第213-2-18】風力発電導入量の国際比較(2021年末時点)(xls/xlsx形式31KB)
- 資料:
- The International Renewable Energy Agency (IRENA)「Renewable Capacity Statistics 2022」を基に作成
そのような課題に直面しつつも、再エネの中でも相対的にコストの低い風力発電の導入を推進するため、電力会社の系統受入容量の拡大や、広域的な運用による調整力の確保に向けた対策が行われています。さらに、開発期間の短縮のため、通常は3、4年程度を要するとされる環境アセスメントの手続期間を半減させることを目標に、地方公共団体の協力を得て審査期間の短縮を図るとともに、環境調査を前倒しして他の手続と同時並行で進める手法の実証事業を行い、「環境アセスメント迅速化手法のガイド─前倒環境調査の方法論を中心に─」(2018年3月、NEDO)を取りまとめ、「発電所に係る環境影響評価の手引」に前倒し手法を反映しました(2019年3月)。
⑤バイオマスエネルギー
バイオマス(生物起源)エネルギーとは、化石資源を除く、動植物に由来する有機物で、エネルギー源として利用可能なものを指します。特に植物由来のバイオマスは、その生育過程で大気中のCO2を吸収しながら成長するため、これらを燃焼させたとしても追加的なCO2は排出されないことから、「カーボンニュートラル」なエネルギーとされています。
バイオマスエネルギーは、原料の性状や取扱形態等から廃棄物系と未利用系に大別されます。利用方法については、直接燃焼のほか、エタノール発酵等の生物化学的変換、炭化等の熱化学的変換による燃料化等があります(第213-2-19)。
【第213-2-19】バイオマスの分類及び主要なエネルギー利用形態
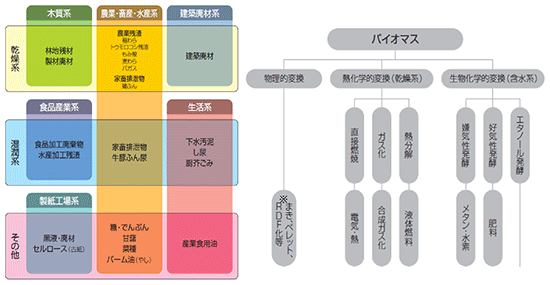
(注)RDF:Refuse Derived Fuelの略で、廃棄物(ごみ)から生成された固形燃料。
【第213-2-19】バイオマスの分類及び主要なエネルギー利用形態(ppt/pptx形式:233KB)
- 資料:
- 資源エネルギー庁「新エネルギー導入ガイド企業のためのAtoZ バイオマス導入」
日本において利用されているバイオマスエネルギーは、廃棄物の焼却によるエネルギーが主であり、製紙業等のパルプ化工程で排出される黒液や、製材工程から排出される木質廃材、農林・畜産業の過程で排出される木くずや農作物残さ、家庭や事務所等から出るゴミ等を燃焼させることによって得られる電力・熱を利用するもの等があります。特に、黒液や廃材等を直接燃焼させる形態を中心に導入が進展してきました。
生物化学的変換のうち、メタン発酵について、家畜排せつ物や食品廃棄物からメタンガスを生成する技術は確立されているものの、原料の収集・輸送やメタン発酵後の残さ処理等が普及に向けた課題となっています。下水汚泥については下水処理場における収集が容易なことから、大規模な下水処理場を中心にメタン生成を行いエネルギーとして利用を進めてきました。
バイオマス発電については、2012年に開始したFIT制度により、導入が進んでいます。また、2015年度から新たに2,000kW未満の未利用木質バイオマス発電についての買取区分が別途設けられ、より小さい事業規模でも木質バイオマス発電に取り組めるようになりました。2021年度末のFIT制度によるバイオマス発電導入設備容量は、473万kW(RPS制度からの移行導入量を含む。)に達しました(第213-2-20)。
【第213-2-20】FIT制度によるバイオマス発電導入設備容量の推移
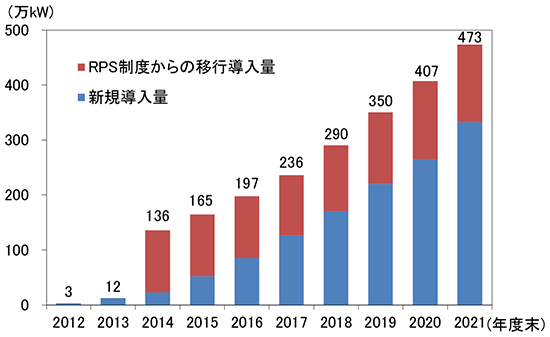
(注)「RPS制度からの移行導入量」は2014年度以降の数値のみ掲載している。
【第213-2-20】FIT制度によるバイオマス発電導入設備容量の推移(xls/xlsx形式23KB)
- 資料:
- 資源エネルギー庁「固定価格買取制度 情報公開用ウェブサイト」を基に作成
いずれの類型・原料種についても、原料バイオマスを長期的かつ安定的に確保することが共通の課題となっています。また、持続可能な形で生産された燃料であることも重要な要素です。
また、輸送用燃料であるバイオエタノールやバイオディーゼルは、生物化学的変換により、その大部分が製造されています。バイオエタノールは、これまで一般的にサトウキビ等の糖質やトウモロコシ等のでん粉質等で製造されてきましたが、日本では食料競合を避けるため、稲わらや木材等のセルロース系バイオマスを原料として商業的に生産できるよう、研究開発を推進しています。利用方式としては、ガソリンに直接混合する方式と、添加剤(ETBE30)として利用する方式があります。一方、バイオディーゼルは、ナタネやパーム等の植物油をメチルエステル化して、そのままもしくは軽油に混合した状態でディーゼル車の燃料として利用されています。欧米等では大規模な原料栽培から商業的に取り組まれていますが、日本では、使用済みの植物油(廃食用油等)を回収・再利用する形でのバイオディーゼル製造が主流です。
また、近年では、新たなバイオ燃料製造技術として、ATJ技術(触媒によりバイオエタノールからジェット燃料等を製造する技術)や、木材や廃棄物のガス化・液化技術(これら原料をH2とCOのガスに変換し、触媒によりガスからジェット燃料等を製造する技術)、炭化水素等を生産する微細藻類を活用したジェット燃料等の製造技術に関する技術開発が活発に行われており、軽油代替・ジェット燃料油代替の製造技術として実用化が期待されています。さらに、近年では航空機運航分野の脱炭素化推進のため、持続可能な航空燃料(SAF)が注目され、技術開発が進められています。日本は、2030年までに国内航空会社の燃料使用量の10%をSAFに置き換えることを目標としています。
⑥水力
水力発電は、高いところにある河川等の水を低いところに落とすことで、水の持つ位置エネルギーを利用して水車を回し、発電を行うものです。利用面から流れ込み式(水路式)、調整池式、貯水池式、揚水式に分けられ、揚水式以外を特に「一般水力」と呼んでいます。揚水式とは、電力需要が供給より小さい時間帯に下部にある水を上部に汲み上げておき、電力が必要となった際に放流して発電する方式であり、他とは区別されています。
2021年3月末時点で、日本の一般水力発電所は、既存発電所数が計2,028か所、新規建設中のものが92か所に上りました。また、未開発地点は2,660か所(既存・建設中の合計値の約1.3倍)となっています。しかし、未開発の一般水力の平均発電能力(包蔵水力)は7,203kWであり、既存や建設中の発電所の平均出力(既存13,554kW、建設中11,180KW)よりも小さなものとなっています。開発地点の小規模化が進んだことに加えて、開発地点の奥地化も進んでいることから、発電コストが他の電源と比べて割高となり、開発の大きな阻害要因となっています。
今後は、農業用水等を活用した小水力発電のポテンシャルを活かしていくことが重要になります。小水力発電は、地域におけるエネルギーの地産地消の取組を推進していくことにもつながります。2012年に開始したFIT制度の効果により、2022年3月時点で82万kWの中小水力発電が新たに運転開始しており、今後も開発が進むことが見込まれます。
なお、日本の水力発電の設備容量(揚水を含む)は、2021年度末で5,001万kWに達しており、年間発電電力量は876億kWhとなりました(第213-2-21)。
【第213-2-21】日本の水力発電設備容量及び発電電力量の推移
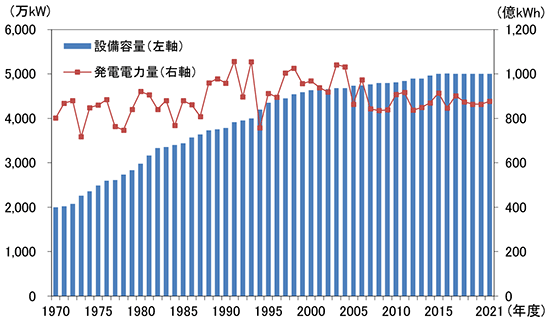
【第213-2-21】日本の水力発電設備容量及び発電電力量の推移(xls/xlsx形式24KB)
- 資料:
- 2015年度までは電気事業連合会「電気事業便覧」、2016年度以降は資源エネルギー庁「電力調査統計」を基に作成
世界と比較すると、世界の水力発電設備容量における日本のシェアは約4%となっています(第213-2-22)。
【第213-2-22】水力発電導入量の国際比較(2021年末)
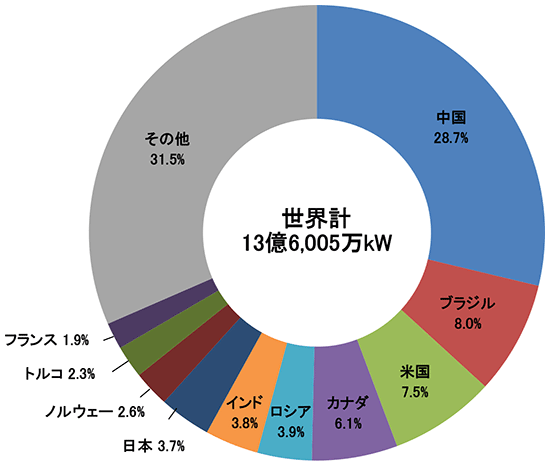
【第213-2-22】水力発電導入量の国際比較(2021年末)(xls/xlsx形式21KB)
- 資料:
- IRENA「Renewable Capacity Statistics 2022」を基に作成
⑦地熱
地熱発電は、地表から地下深部に浸透した雨水等が地熱によって加熱され、高温の熱水として貯えられている地熱貯留層から、坑井により地上に熱水・蒸気を取り出し、タービンを回して電気を起こす発電方式です。CO2の排出量がほぼゼロで環境適合性に優れ、長期間にわたって安定的な発電が可能なベースロード電源である地熱発電は、日本が世界第3位の資源量(2,347万kW)を有する電源として注目を集めています(第213-2-23)。
【第213-2-23】主要国における地熱資源量及び地熱発電設備容量
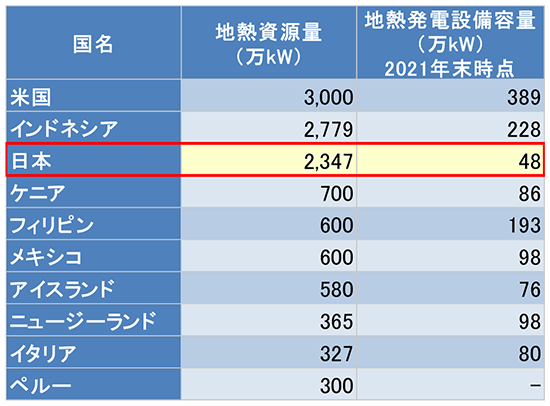
【第213-2-23】主要国における地熱資源量及び地熱発電設備容量(ppt/pptx形式:45KB)
- 資料:
- 地熱資源量は国際協力機構作成資料(2010年)及び産業総合技術研究所作成資料(2008年)より、地熱発電設備容量はIRENA「Renewable Capacity Statistics 2022」を基に作成
地熱発電の導入に当たっては、地下の開発に係る高いリスクやコスト、温泉事業者を始めとする地域の方々等の地元理解、そして、開発から発電所の稼動に至るまでに10年を超える期間を要するといった課題が存在しています。
こうした課題を解決するために、様々な支援措置が講じられています。例えば、開発リスクが特に高い初期調査段階におけるコストを低減するため、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「JOGMEC」という。)を通じ、資源量の把握に向けた地表調査や掘削調査等に対する支援を行っています。また、JOGMEC自らが、地熱資源の8割が存在する国立・国定公園を中心に、新規開発地点を開拓するための先導的資源量調査を行っているほか、地域の理解促進を目的としたセミナーや見学会の開催等についても支援を行っています。開発の初期段階で必要となる地表調査・掘削調査への支援は、2021年末時点で、国内35か所において行われており、着実に地熱開発が進んでいます(第213-2-24)。
【第213-2-24】地熱発電開発プロセス
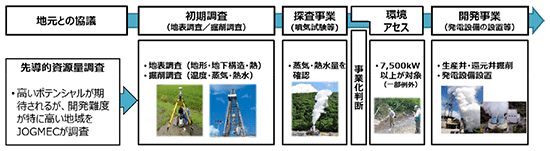
【第213-2-24】地熱発電開発プロセス(ppt/pptx形式:445KB)
- 資料:
- 資源エネルギー庁作成
また、開発リードタイムを短縮するため、高性能の探査・掘削機材の技術開発に加え、通常は3、4年程度を要するとされる環境アセスメントの手続期間を半減させることを目標に、2014年度から、NEDOが、実地での環境影響調査を前倒しで進める場合の課題の特定・解決を図るための実証事業を実施し、そこで得られた知見を「前倒環境調査のガイド」として2016年、2017年に公表しました。さらに、環境省が2021年4月に発表した「地熱開発加速化プラン」では、自然公園法や温泉法の運用見直し及び地域との合意形成を通じて、地熱発電案件開発の加速化が図られます。
なお、国際的に見ると、世界の地熱発電設備容量に占める日本のシェアは約3%となっており、世界第10位の規模となります(第213-2-25)。
【第213-2-25】地熱発電導入量の国際比較(2021年末時点)
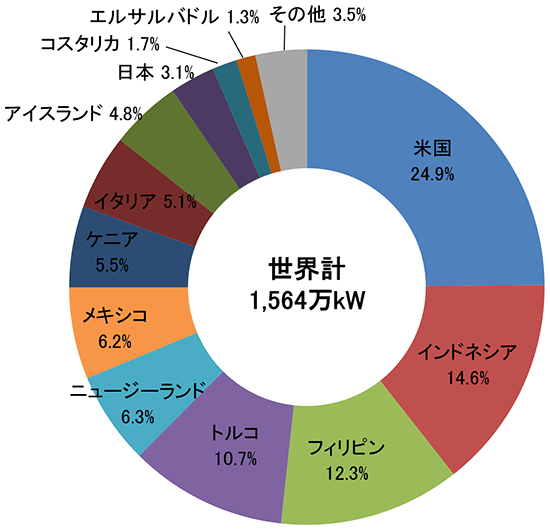
【第213-2-25】地熱発電導入量の国際比較(2021年末時点)(xls/xlsx形式21KB)
- 資料:
- IRENA「Renewable Capacity Statistics 2022」を基に作成
⑧未利用エネルギー
「未利用エネルギー」とは、夏は大気よりも冷たく、冬は大気よりも温かい河川水・下水等の温度差エネルギーや、工場等の排熱といった、今まで利用されていなかったエネルギーのことを意味します。
具体的な未利用エネルギーの種類としては、①生活排水や中・下水・下水処理水の熱、②清掃工場の排熱、③変電所の排熱、④河川水・海水・地下水の熱、⑤工場排熱、⑥地下鉄や地下街の冷暖房排熱、⑦雪氷熱等があります。
特に、雪氷熱利用については、古くから北海道、東北地方、日本海沿岸部を中心とした降雪量の多い地域において、生活上の障害であった雪氷を夏季まで保存し、雪室や氷室として農産物等の冷蔵用に利用してきました。近年、地方自治体等が中心となった雪氷熱利用の取組が活発化しており、農作物保存用の農業用低温貯蔵施設、病院、介護老人保健施設、公共施設、集合住宅等での冷房用の冷熱源に利用されています。
また、清掃工場の排熱の利用や下水・河川水・海水・地下水の温度差エネルギーの利用は、利用可能量が非常に多く、また、比較的消費地に近いところにあること等から、今後さらなる有効活用が期待されており、エネルギー供給システムとして、環境政策、エネルギー政策、都市政策への貢献が期待されている地域熱供給を始めとしたエネルギーの面的利用とあわせて、さらに導入効果が発揮できるエネルギーです(第213-2-26)。
【第213-2-26】未利用エネルギーの活用概念
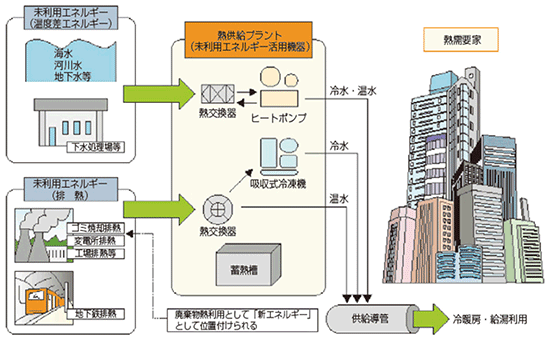
【第213-2-26】未利用エネルギーの活用概念(ppt/pptx形式:124KB)
3.エネルギーの高度利用
(1)次世代自動車
次世代自動車には、燃料電池自動車、電気自動車、ハイブリッド自動車等があります。2021年1月には、菅総理が第204回国会の施政方針演説において、脱炭素社会実現に向け、2035年までに新車販売における電動車31100%の実現を表明しました。
日本において、運輸部門のエネルギー消費の大半は、ガソリンや軽油の使用を前提とする自動車によるものであり、これらの燃料を消費しない、あるいは消費量を抑制する次世代自動車の導入は、環境面への対応等の観点から非常に有効な手段です。次世代自動車は、その導入について価格面を中心に様々な課題がありますが、いわゆるエコカー補助金・減税等の効果等もあり、ハイブリッド自動車を中心に普及台数が拡大しています。さらに、2009年には電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の市販が開始され、2014年には燃料電池自動車の市販も開始されました。
2021年度末時点の日本における保有台数は、ハイブリッド自動車が約1,087.8万台(プラグインハイブリッド自動車約17.4万台を含む)、プラグインハイブリッド自動車が約17.4万台、電気自動車が約14.0万台、燃料電池自動車が約0.7万台となりました(第213-3-1)。
【第213-3-1】次世代自動車の保有台数の推移
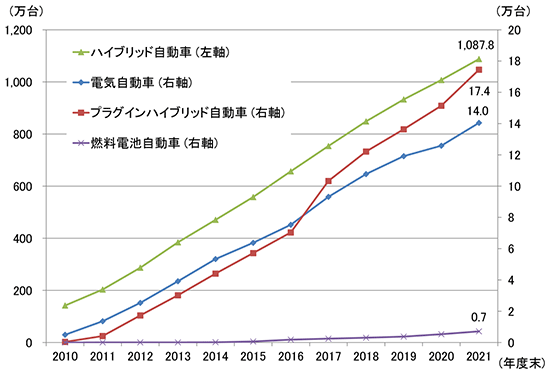
【第213-3-1】次世代自動車の保有台数の推移(xls/xlsx形式22KB)
- 資料:
- 自動車検査登録情報協会「自動車保有車両数」を基に作成
(2)燃料電池
燃料電池は、水素等の燃料と空気中の酸素を化学的に反応させることによって直接電気を発生させる装置です(第213-3-2)。燃料電池は、以下の3点から、エネルギー安定供給の確保の観点のみならず、地球環境問題の観点からも重要なエネルギーシステムであると考えられます。
【第213-3-2】燃料電池の原理
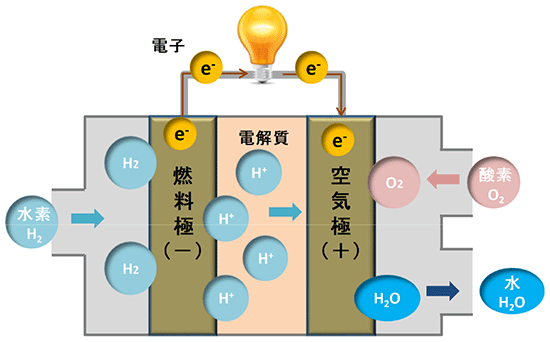
【第213-3-2】燃料電池の原理(ppt/pptx形式:95KB)
①燃料となる水素は製造原料の代替性が高く、副生水素、原油随伴ガス、褐炭といった未利用エネルギーや、再エネを含む多様な一次エネルギー源から様々な方法で製造可能なこと。
②発電効率が30〜60%と高く、また反応時に生じる熱を活用し、コージェネレーションシステム(熱電併給システム)として利用した場合には総合効率が90%以上になり、エネルギー効率が非常に高いシステムであること。
③発電過程でCO2や窒素酸化物、硫黄酸化物を排出せず、環境特性に優れるクリーンなエネルギーシステムであること。
日本では、世界に先駆けて2009年5月から一般消費者向けの家庭用燃料電池の本格的な販売が開始されており、2022年3月末時点までに約43.3万台が導入されています(第213-3-3)。
【第213-3-3】家庭用燃料電池の累積導入台数の推移
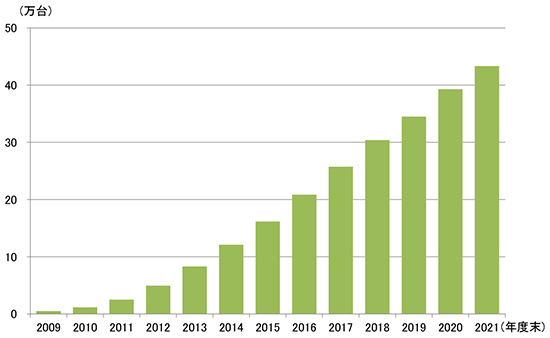
【第213-3-3】家庭用燃料電池の累積導入台数の推移(xls/xlsx形式23KB)
- 資料:
- コージェネレーション・エネルギー高度利用センター「コージェネ導入実績報告」を基に作成
(3)ヒートポンプ
ヒートポンプは冷媒を強制的に膨張・蒸発、圧縮・凝縮させながら循環させ、熱交換を行うことにより、水や空気等の低温の物体から熱を吸収し高温部へ汲み上げるシステムであり、従来のシステムに比べてエネルギー利用効率が非常に高いことが特長です(第213-3-4)。そのため、民生部門でのCO2排出削減に大きく貢献することが期待されています。
【第213-3-4】ヒートポンプ(CO2冷媒)の原理
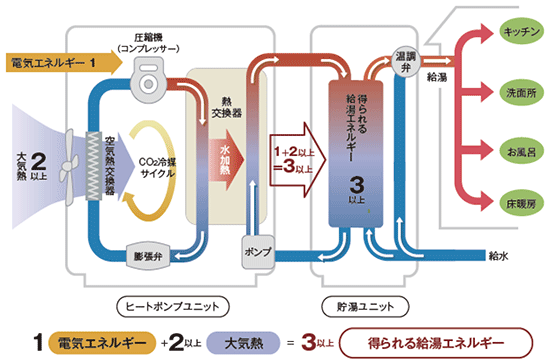
【第213-3-4】ヒートポンプ(CO2冷媒)の原理(ppt/pptx形式:213KB)
- 資料:
- 日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集2016」
また、欧米ではヒートポンプによる熱利用を再エネとして評価する動きもあります。高度化法施行令では、「大気中の熱その他の自然界に存在する熱」が再エネ源として位置づけられました。高効率ヒートポンプの初期費用は比較的高くなることから、市場化・普及までの期間を短縮することが必要です。
日本のヒートポンプは、家庭部門でエアコンの空調に多く導入されていますが、給湯機器や冷蔵・冷凍庫等、様々な製品にも使用されています。また、高効率で大規模施設にも対応できるヒートポンプは、オフィスビルの空調や病院・ホテルの給湯等に利用されていますが、今後は工場や農場等でも普及拡大が期待されています。
(4)コージェネレーション
コージェネレーション(Cogeneration)とは、熱と電気(又は動力)を同時に供給するシステムです。消費地に近いところに発電施設を設置できるため、送電によるロスが少なく、また、発電に伴う冷却水や排気ガス等の排熱を回収利用できるため、エネルギーを有効利用することができます。排熱を有効に利用した場合には、エネルギーの総合効率が最大で90%以上に達し、省エネやCO2の排出削減に貢献できます。
日本におけるコージェネレーションの設備容量は、産業用を中心として着実に増加してきました。民生用では病院、ホテル等の熱・電力需要の大きい業種、産業用では化学、食品等の熱多消費型の業種を中心に導入されてきました。2021年度末におけるコージェネレーションの累計設置容量は、1,351万kWとなりました(第213-3-5)。
【第213-3-5】日本におけるコージェネレーション設備容量の推移
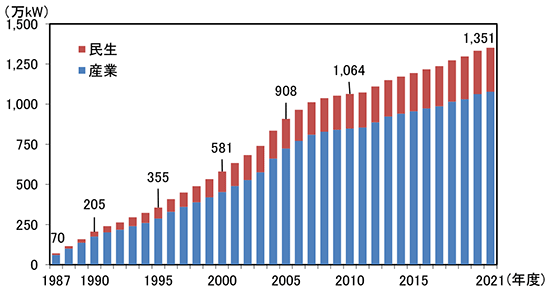
(注)民生用には、戸別設置型の家庭用燃料電池やガスエンジン等を含まない。
四捨五入による誤差を含む。
【第213-3-5】日本におけるコージェネレーション設備容量の推移(xls/xlsx形式24KB)
- 資料:
- コージェネレーション・エネルギー高度利用センター「コージェネ導入実績報告」を基に作成
(5)廃棄物エネルギー
廃棄物エネルギーとは、再利用及び再生利用がされない廃棄物を廃棄物発電等の熱回収により有効利用したり、木質チップの製造等廃棄物から燃料を製造したりすることができるものです。再エネの1つであるバイオマス系の廃棄物エネルギーだけでなく、化石エネルギーに由来する廃棄物エネルギーについても有効活用を行う意義があります。
廃棄物エネルギーの利用方法としては、廃棄物発電、廃棄物熱供給、廃棄物燃料製造が挙げられます。2021年度末における日本の廃棄物発電(一般廃棄物に限る)の施設数は396で、1,028に上る全一般廃棄物焼却施設の38.5%を占めました。また、発電設備容量は合計で214.9万kWに達しました32。
- 10
- ここでの原油自給率は、日本の海外における自主開発原油は含まれず、日本の原油供給のうち国内で産出された原油の割合を示します。
- 11
- 米国及び欧州OECDの中東依存度については、天然ガス液(Natural gas liquids)を含まない原油(Crude oil)のみの数値を示します。資料:IEA「Oil Information (2022)」
- 12
- 重油は動粘度の違いにより、A重油、B重油とC重油に分類されています。同じ種類の中ではさらに硫黄分により品質が分類されています。A重油は重油の中では最も動粘度が低く、茶褐色の製品です。用途は、工場の小型ボイラ類を始め、ビル暖房、農耕用ハウス加温器、陶器窯焼き用の他に、漁船等船舶用燃料等としても使われています。C重油は、A重油に比べて粘度が高く、黒褐色の製品です。その用途は、火力発電や工場の大型ボイラ、大型船舶のディーゼルエンジン用の燃料等に用いられています。B重油はA重油とC重油の中間の動粘度の製品ですが、現在殆ど生産されていません。燃焼用の燃料としては、取り扱い面から、引火点、動粘度、流動点等、燃焼面からは発熱量、硫黄分、水分、水泥分、燃焼後の管理のための灰分等が重要な品質管理項目になっています。
- 13
- Cost, Insurance and Freightの略で、引渡し地までの保険料、運送料を含む価格を意味しています。
- 14
- 売主がお金を支払い、買主はお金を受取ることを意味します。
- 15
- 原油輸入金額は、「原油」の輸入額の合計を示しています。
- 16
- サウジアラムコ社の通告価格とはコントラクトプライス(CP)と呼ばれ、サウジアラムコ社が、原油価格やマーケット情報を参考にしながら総合的に判断し、決定します。日本を含めた極東地域に輸入されるLPガスについては、サウジアラビア以外の産ガス国も多くがこのCPにリンクしています。
- 17
- 米国テキサス州Mont Bellevueにあるプロパンガス基地における取引価格はMB(Mont Bellevue)と呼ばれています。Mont Bellevueでの取引価格は世界の3大取引価格の1つになっています。
- 18
- 原料炭は、主に高炉製鉄用コークス製造のための原料として用いられています。
- 19
- 一般炭は、主に発電所用及び産業用のボイラ燃料として用いられています。
- 20
- 無煙炭は、石炭の中でも最も石炭化が進んだ石炭で、燃焼の際に殆ど煙を出さず、また、火力が強いという特徴があります。
- 21
- ただし、小売業参入の全面自由化に伴う電気事業類型の見直しにより、2016年度以降は電気業以外の消費量との重複を一部含みます。
- 22
- 1995年の「電気事業法(昭和39年法第170号)」改正を受けて、共同火力及び公営電気事業は、卸電気事業から卸供給へ移行することとなりましたが、経過措置により2010年3月までは「みなし卸電気事業者」として位置づけられていました。
- 23
- 軽水とは普通の水のことを指し、軽水炉の減速材、冷却材等に用いられます。これに対し、重水素(水素原子に中性子が加わったもの)に酸素が結合したものが重水であり、重水炉に用いられます。
- 24
- 核分裂によって新しく発生する中性子は非常に高速であり、これを高速中性子と呼びます。このままでも核分裂を引き起こすことは可能ですが、この速度を遅くすると次の核分裂を引き起こしやすくなります。この速度の遅い中性子を熱中性子と呼び、高速中性子を減速し熱中性子にするものを減速材と呼びます。軽水炉では、熱中性子で核分裂連鎖反応を維持するために減速能力の高い軽水(水)を減速材として用います。また、核分裂によって発生した熱を炉心から外部に取り出すものを冷却材と呼びます。軽水炉では水を冷却材として用いるので、冷却材が減速材を兼ねています。
- 25
- SWU(Separative Work Unit=分離作業量)は、ウランを濃縮する際に必要となる仕事量を表す単位です。例えば、濃度約0.7%の天然ウランから約3%に濃縮されたウランを1kg生成するためには、約4.3kgSWUの分離作業量が必要です。
- 26
- 電気事業者に毎年度、一定量以上の再エネの発電や調達を義務付ける制度。
- 27
- 再エネで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度。
- 28
- 発電事業者が卸電力取引市場等で売電した時、その売電価格に対して一定のプレミアムを交付する制度。
- 29
- 需要電力(太陽光発電の自家消費分を除いたもの)から、太陽光発電(自家消費分を除く)及び風力発電の出力を控除した需要。
- 30
- ETBEとは、Ethyl Tertiary-Butyl Etherの略で、エタノールとイソブテンにより合成され、ガソリンの添加剤として利用されています。
- 31
- 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車。
- 32
- 環境省「一般廃棄物処理実態調査結果(令和3年度)」