【インタビュー】「風力発電は大型化や広域利用も可能な再エネ、政策として産業育成を」―加藤仁 氏(後編)
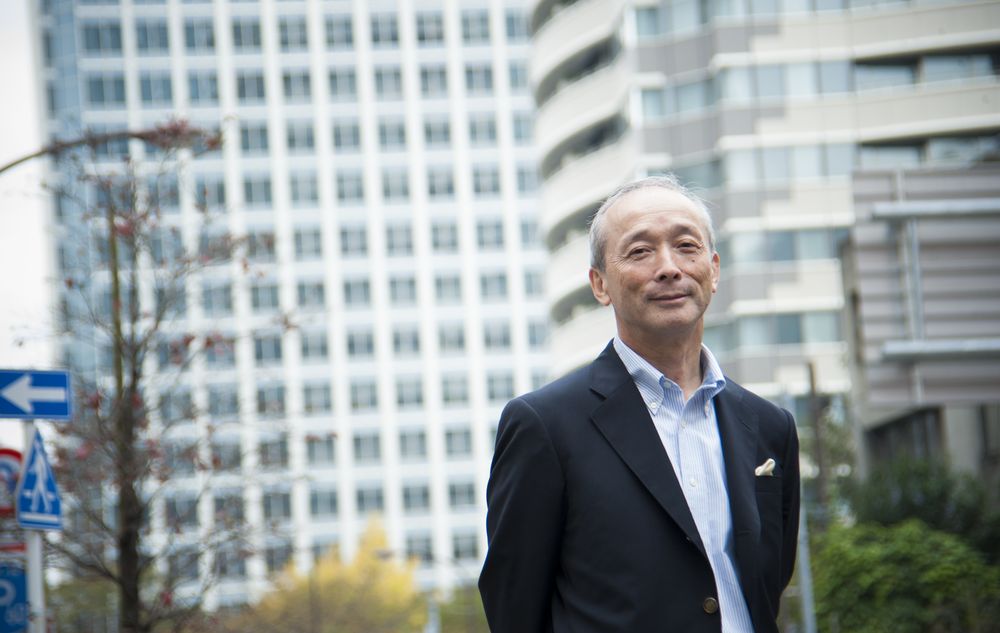
前編「将来はヨーロッパで最大の電源に~拡大する風力発電」では、ヨーロッパの風力発電の現状や普及拡大の背景をお聞きしました。後編は、日本で風力発電を普及するための課題や、事業者の視点から見た、再生可能エネルギー(再エネ)の大量導入を図るために必要な政策などについてうかがいます。
発電コストの面でもじゅうぶん戦える風力発電
―前編では、日本の自然条件は決して風力発電に向いていないわけではないというお話をうかがいました。発電コストについてはいかがでしょうか?オランダではkWhあたり6円を実現しているということでしたが、日本でも実現可能なのでしょうか。
加藤 風力発電が陸上に設置される場合は、土地の値段が発電コストに影響してきます。日本のように土地が高い国では、発電コストも高くなってしまいます。しかし洋上風力発電であれば、ヨーロッパと日本ではコスト差はさほど出ないでしょう。
また、現在日本には風車メーカーは1社しかないため、洋上風力発電用の風車は当面は経験と技術を持つヨーロッパで製造されたものを輸入することが主体になるでしょうが、風車自体の価格は日本とヨーロッパ間で大きな差異は生じないでしょう。さらに、洋上風力発電の建設工事は、オランダやベルギーの業者が中心であり、経験は別としてコスト的には国内業者とほとんど同じレベルでしょう。お話したように、洋上風力発電の保守には特別に訓練された技術者がたずさわるため、資格をもった日本人を中心にメンテナンスを任せることになるでしょう。従って、ヨーロッパと日本では、保守に掛かる人件費の面でも大きな差はつかないと考えられます。
このように、洋上風力発電に関していえば、ヨーロッパと日本でコストに大きく差が生じることはほとんどないと考えています。コスト差が生じる要素は、風況くらいでしょう。設備費は同額でも風が強い方が発電量が増えるため、kWhあたりの発電コストは割安になります 。ヨーロッパより平均風速が弱い日本は、ヨーロッパより洋上風力発電による発電コストは風が弱い分だけは高くなるので、日本風力発電協会としては日本における風力の発電コスト8-9円/kWhを達成可能な目標としています。
また、将来的に風車を建て替える際は、海底ケーブルなどはそのまま使用可能ですし、環境への影響や風況などの調査費なども不要となるため、これらを活用した「建て替え」を実施すれば更に発電コストは下がります。 また、現在、スコットランド沖などで、風車を海上に浮かべる「浮体式」の洋上風力発電に関する大規模な実証試験がはじまっています。海底に風車の基礎を固定する「着床式」の洋上風力発電では、海底のさまざまな形状や地質に合わせて基礎をつくることが必要となりますが、浮体式であれば海底がどのような形状や地質でも同じ浮体を活用することができ、量産が可能となり、コスト削減にも役立つと考えられます。
このようなことを考えあわせれば、海洋国家である日本における風力発電は、自前のエネルギーを利用した主要な「電源」(電気をつくる方法)になり得ると考えています。
風力発電推進には政策の後押しが必要
―前編では、ヨーロッパの風力発電が進んだ要因の一つとして、EUの再エネ推進政策による効果が大きいというお話もありました。日本では、2018年に「エネルギー基本計画(第5次)」が閣議決定され、再エネの主力電源化が明確に打ち出されました(「新しくなった『エネルギー基本計画』、2050年に向けたエネルギー政策とは?」参照)。これをどのように評価なさっていますか。
加藤 エネルギー基本計画に「再エネの主力電源化」が盛り込まれたことは、一歩先へと踏み出したと捉えています。風力発電もようやく本格的にスタートできるでしょう。
陸上風力発電も着実に伸びてはいくはずですが、陸上は土地の制約があることから、将来的には、洋上風力発電が大きく伸びる可能性があると我々はとらえています。
―洋上風力発電を促進する法案が可決されました。これをどのようにとらえていらっしゃいますか。

加藤 我々はこの法案を「洋上新法」と呼んでいますが、たいへん期待しています。というのも、ヨーロッパなどで洋上風力発電が大量導入されているのは一般海域なのですが、日本には一般海域の利用についてのルールがなく、それが洋上風力発電導入の制約となっていたためです。
たとえば、洋上で、ある程度の規模があって効率のよい50万kWの風力発電所を建設するとなると、現状では3,000億円ほどのコストがかかります。しかし現行のルールでは、一般海域を利用するには県知事による3〜5年ほどの期間の認可しか得られません。しかし、大型プロジェクトである洋上風力発電は、最低30年は海域を利用できるという目算がなければ、コスト回収に不安を覚えて、誰も手を出さないでしょう。
洋上新法ができて、初めてそこがクリアすることが出来ます。固定価格買取制度(FIT)に加えてこのルールができることで、車の両輪が揃った状態になり、風力発電はやっと走り出すことができます(「日本でも、海の上の風力発電を拡大するために」参照)。
ただし、それで万事解決ということではありません。車の両輪が揃っても、どの道路を通ってどこに行けばよいか、インターチェンジは?、給油所は?という車が走れる環境の整備はこれから実施していく必要があります。
―具体的には、どのような課題が残されているのでしょうか。
加藤 私は、日本の電力需給のしくみに多くの課題が残されていると考えています。先日、九州電力では、電力供給が需要を上回る恐れがあるということで、太陽光発電と風力発電の出力抑制がおこなわれました。これは日本の電力インフラ政策の欠点の現われだと思います。
太陽光発電設備の認定をおこなった段階でこのような事態は予想出来ていたはずです。余った電気を九州の外に融通し、広域で運用する対策が出来ていれば、このような問題は回避できたはずです。しかし日本の場合、各地域の電力会社が地域ごとに独立した経営を行って来ているために、送電・配電をおこなう電力系統が、地域ごとに閉じた形になっていて、なかなか他の地域への融通ができません。北海道のブラックアウトも、電力網が他の地域と十分な容量の系統で繋がっていなかったこともアクシデントが起きた要因の一つでしょう。広域で系統を運用するということなしでは、どうしても限界は来てしまいます。電力が逼迫したときに需要家に使用を抑えてもらうディマンドリスポンス、蓄電池の活用などのエネルギーマネジメントにしても、広域的に系統が繋がってこそ効果があるのです。
加えて、再エネは規模が小さいうちは地産地消で良いのですが、発電量が増えれば、広域消費を考えなくてはなりません。大型の洋上風力発電などは、まさに広域消費をおこなうべきもので、その実現のためには、電力系統への接続をスムーズに進めていかなくてはなりません。今後、再エネの主力電源化を進めるにあたっては、国がこうした根本的な課題に取り組む必要があります。風力発電に関連してさまざまな政策のピースが整いつつありますが、グランドデザインがあってこそ、それらのピースが活かされるようになるのです。国が本腰を入れて導入を促進しない限り、再エネの主力電源化の実現は難しいでしょう。
―再エネは、地産地消と広域利用の両面で考えなければならないというのは、目が見開かれるようなお話ですね。

加藤 風力発電などの再エネについては、電源が電力系統から遠く、送電線が長くなるのが問題だともいわれます。しかし、たとえば関西電力がつくった黒部ダムは、中部電力管内にある。原子力発電所にいたっては、東京に電力を供給するためのものが青森県に計画されている。それは国の政策として、適した立地を求めたところそうなったということです。ですから、重要なのはまず政策なのです。
また、そのような長い送電線ができている場所はあるのですから、送電線を新たに一から引く必要はありません。現在電力系統について議論されている「コネクト&マネージ」の発想のベースも同じようなものであって、あとどれだけ、どこに引かなくてはならないか?という議論が必要でしょう。
目指すべきは、風力発電の国内での産業化
加藤 先ほど、日本に洋上風力発電所を建設する場合は当面はヨーロッパの製品(風車)の導入が中心になるだろうと申し上げましたが、建設や据付作業は国内で日本の企業がになう必要があります。これも課題のひとつです。洋上風力発電の場合、海の上でゼロから建設作業をおこなうと非効率であるため、風車はできるだけ陸上で組み立て、組み立てた状態のまま船に乗せて海上へ運び、海上で基礎の上に設置します。そのためには「プレアッセンブル(仮組み立て)ポート:基地港」といわれる港湾にある工場や専門の船が必要となり、初期投資は相当な額になるでしょう。
しかし、日本の潜在的な技術からすれば、洋上風力発電所の建設は難しいことではありません。重要なことは、国内に産業をおこすことです。我々は、日本国内に洋上風力発電所を2030年までに10GW(1,000万kW)建設することで関連する産業が創出され、新たな洋上風力発電産業が形成されると考えています。工事を日本でおこなうという前提で、2030年までに1,000万kWの洋上風力発電所が建設されるとすると、そこから得られる経済波及効果は累計で12兆円ほど、雇用は新規で9万人ほどが生まれるものと試算しています。
ところが政策によっては、国内で産業をおこせず、海外の企業が利益を得るだけだったり、単なる一過性で終わってしまったりする恐れもあります。カギとなるのは国がつくる長期目標であり、グランドデザインです。せっかく洋上新法をつくったのですから、日本で新しい産業をおこすことを目標にしてほしいですね。
日本は後発ですが、利点はあります。まずはヨーロッパの経験に学びながら実績をつみ、その間に港湾施設など追いつけるだけのインフラを整備すればいい。日本にも洋上風力発電の産業が形成されるころには、現在実証試験が進められている浮体式の洋上風力発電の結果も出てくるでしょうから、そちらに移行することも可能になるでしょう。そうすれば、洋上風力発電は日本でも発電の大きな柱になっていくはずです。日本がアジアで先んじれば、周辺国に輸出していくこともできるようになるでしょう。
―風力発電の普及は、日本の産業にも大きなインパクトをもたらすわけですね。

加藤 洋上風力発電は大規模に電気を供給でき、火力発電の代替としても有望です。価格についても、ヨーロッパではすでにkWhあたり6円という発電コストの実績がある。なおかつクリーンな電気であり、さらに自国の技術で自国のエネルギーをになっていくことができる、エネルギー安全保障上も重要な電源だと思います。国として、社会として、洋上風力発電を推進し、新しい産業を育ててほしいものです。
―風力発電の重要性と可能性を再認識いたしました。ありがとうございました。
1953年生まれ。1977年、三菱重工業株式会社入社。2008年にエネルギー・環境統括戦略室長、2013年に執行役員原動機事業本部副事業本部長 兼 風車事業部長。2014年、MHI Vestas Offshore Wind A/S:のCo-CEO。2017年、日本風力開発株式会社副会長。2018年から一般社団法人 日本風力発電協会代表理事に就任。
お問合せ先
長官官房 総務課 調査広報室
※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。
あなたにオススメの記事
-

【インタビュー】「まだまだ残っている、省エネのポテンシャル」―奥村 和夫氏(後編)
-

【インタビュー】「省エネは、快適な暮らしと合理的な生産方法を実現する手段」―奥村 和夫氏(前編)
-

【インタビュー】「先進技術で石炭のゼロエミッション化を目指し、次世代のエネルギーに」−北村 雅良氏(後編)
-

【インタビュー】「安定的で安価な石炭は今も重要なエネルギー源、技術革新でよりクリーンに」−北村 雅良氏(前編)
-

【インタビュー】「日本のノウハウを生かし、LNGの国際市場をリードする存在に」-広瀬 道明氏(後編)
-

【インタビュー】「LNGは環境性・供給安定性・経済合理性のバランスのとれたエネルギー」-広瀬 道明氏(前編)
-

【インタビュー】「国際競争力を高めつつ、安定供給を維持するために 」-月岡 隆氏(後編)
-
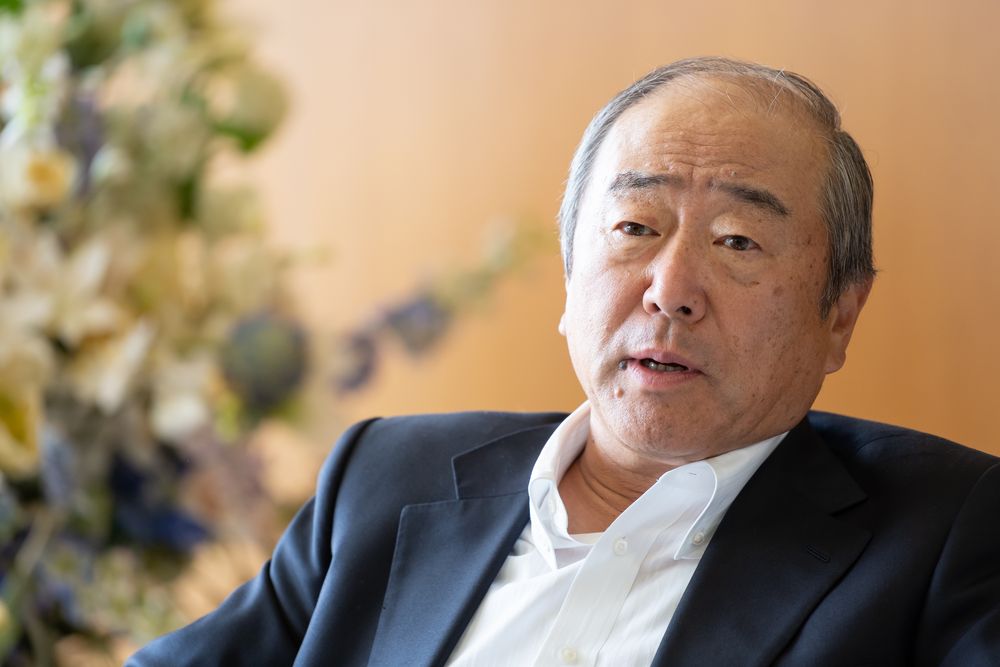
【インタビュー】「可搬性・貯蔵性に優れた石油は、エネルギー供給の“最後の砦”」-月岡 隆氏(前編)
最新記事
-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用
-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?
-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革
-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目
-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!
-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)
-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)
-

ガソリンの暫定税率(当分の間税率)の廃止でガソリン代はどうなるの?よくいただく質問に、資源エネルギー庁がお答えします!




