【インタビュー】「安定的で安価な石炭は今も重要なエネルギー源、技術革新でよりクリーンに」−北村 雅良氏(前編)

安定的で安価に電気を作り出すことができる火力発電は、エネルギーの安定供給に欠かせないもの。その一翼を担っているのが石炭火力です。一方で、石炭は燃焼時のCO2排出量が多く、地球温暖化への懸念から、批判の声も聞かれます。こうした現状のもとで、私たちは石炭利用をどのようにとらえればいいのでしょうか。石炭利用の現在と将来像を、石炭エネルギーセンター(JCOAL)会長の北村雅良氏にうかがいました。前後編にわたってお届けします。
生活に欠かせない石炭をよりクリーンに
―石炭というとすぐに思い浮かぶのは蒸気機関車など古いモノのイメージで、現在の私たちにとっては、あまり身近な燃料ではないように思えます。しかし、実は石炭は今でも日本に欠かせないものだそうですね。まずは、石炭が今の日本でどのような役割を果たしているのかを解説していただけますか。
北村 日本において、石炭は現在でもとても重要なエネルギー源のひとつです。たとえば、製鉄やセメント製造、製紙業などの産業では、原料や熱源として、石炭を多量に必要としています。また、石炭を燃料として発電する石炭火力発電所は、日本の全発電量の約3割を担っており、電源(電気をつくる方法)として非常に重要な役割を果たしています。2011年に起こった福島第一原子力発電所の事故の後、火力発電の燃料としては天然ガスが急速に増えましたが、それでも石炭は引き続きベース電源を担っています。
私のように長く石炭に関わり、石炭が今もなお生活や産業に密接なものとして使われていることを知っていると、もし石炭がなくなったらどうするのだろうと心配になるほど、石炭は現在でも人々の生活の根っこを支えているのです。
では、石炭の強みとはなんでしょうか。それは供給の安定性と価格の安さです。日本は現在、ほとんどの石炭を輸入に頼っていますが、主な輸入先はオーストラリアやアジアなどで、中東に依存していないため、石油のような地政学的リスクはありません。また、熱量あたり(カロリーあたり)の価格は液化天然ガス(LNG)の約半分で、価格の推移も、原油やLNGより安定的です。

私が電源開発株式会社(J-POWER)で働きはじめて最初に託された仕事は、英文レポートの翻訳作業でした。その内容は、「1000キロの鉄道を敷くと1kmあたりの敷設コストは何ドルになるか」などというもの。発電と関係のない内容を不思議に思ったものですが、実は、当時の社内では「オーストラリアの内陸部の炭鉱を開発して港まで鉄道を敷き、石炭を日本に輸入する」という構想を練っており、そのレポートは「鉄道の敷設計画のフィジビリティスタディ(実行可能性調査)」だったのです。電源開発株式会社は1972年当時、国内炭の火力発電所を建設・稼働させていたのですが、当時の火力発電は石油が95%を占め、石炭火力は当時は事業の中心ではありませんでしたので、国内炭の先行きに危機感を持った先輩たちが輸入炭の利活用を進めようとしていたのです。
その翌年、1973年に第1次オイルショックが起こり、1979年の第2次オイルショック後には石炭の本格的な輸入が始まりました。石油火力の発電コストが跳ね上がったこと、また資源の確保が特定の国や地域に偏らないようにすることがエネルギー・セキュリティの観点から望ましいと考えられるようになったことが理由でした。先輩たちには先見の明があったのですね。
各国事情を考慮したエネルギー政策が必要
―石炭はエネルギーの安定供給には欠かせない燃料なのですね。
北村 石炭は燃焼時に、ぜんそくなどの健康被害を引き起こす、ばいじん、窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)が排出されるという問題がありますが、これらについては日本の高度な環境対策技術により解決が図られています。その一方で、「CO2の排出量が多い」という、地球環境レベルの問題があります。
CO2については、2018年のCOP24でパリ協定の実施ルールが採択され、すべての締結国が、透明性のある共通ルールで、CO2削減の目標や量の検証をおこなうこととなっています。こうした世界的な潮流を背景に、「CO2を排出する石炭は使わない方がいい」という声が強まり、近年では「脱石炭」という主張も聞かれるようになっています。電源についても、石炭火力にたよらず、「もっと再生可能エネルギー(再エネ)を増やせばいい」とおっしゃる方もいます。現在の石炭火力発電所は、従来のものとはまったく異なり、クリーン化が進んでいるのですが、石炭はカーボン(炭素)を燃やしているわけですから、燃焼後にどうしてもCO2が残ってしまいます。天然ガス火力発電はCO2の排出量が石炭の半分ほどですので、この点は天然ガスの方が優れています。
しかし、電源にはそれぞれに一長一短があり、すべてが良いところばかりというエネルギーは存在しませんから、エネルギーミックスを図ることが重要なのです。また、考え方を転じれば、現在の石炭火力発電の主な課題は、CO2に絞られるととらえることができます。だとすれば、同じ量の石炭からより多くの電気をつくれるよう発電効率を上げるとともに、CO2の排出を抑制する技術をさらに向上させればよい。そのため、私たちは技術的なチャレンジを進めています。
―海外では、CO2削減の観点から、石炭火力を止めることを打ち出している国もあります。今後の石炭利用について、世界はどのような方向に向かっているとお考えでしょうか。

北村 そうですね。確かに、ドイツは政府の諮問委員会で、「2038年までに石炭火力をすべて止めるべく努力する」と明言しました。イギリスやカナダなどは、「脱石炭連合」を設立しました。ただ、どのように温暖化対策に取り組むかということには、それぞれの国のエネルギー事情が影響をおよぼすということを忘れてはなりません。
たとえばヨーロッパは、EU全体でエネルギー政策を考えることができるという、他国にはない利点があります。EU内では国を越えて送配電網が繋がっているため、フランスの原子力、北欧諸国の水力、現在ヨーロッパ中で広がる風力など、広域で電力を融通することが可能なのです。EU全体でやりくりすることでエネルギーのバランスを調整できるため、思い切った政策が打ち出せるということもあるのです。
しかし、日本にはそうした国を越えた電力系統はありません。一方で、近年増加している再エネで電気をすべてまかなうことは、太陽光などの再エネ由来発電が天候に左右され不安定であることや国土面積の狭さを考えれば、難しい。であれば、現在、日本の全発電量の3割を担っている石炭火力を止めることよりも、石炭火力からのCO2の排出を抑えながら、もっと効率よく使っていくことを考えるべきではないでしょうか。
また、世界には、電気そのものにアクセスできない人々が9~10億人いると言われており、いまだに薪(たきぎ)で煮炊きしているような地域があることも考えなくてはなりません。そのため、2015年に国際連合のサミットで採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」では、エネルギーについての目標が設けられています。2030年までに、「アフォーダブル(手ごろな値段で入手できる)」で「リライアブル(信頼できる)」、「サスティナブル(持続可能)」で「モダン(近代的)」なエネルギーに、すべての人々がアクセスできるようにしようという目標です。この目標を実現し、人類すべてに安価なエネルギーを安定的に供給するためには、熱源や動力源としての石炭をエネルギーミックスから除外することはできないはずです。
さらに、自国に石炭資源がある国は、安定的で安価なエネルギー源として、今後もそれを使い続けるでしょう。たとえばポーランドは石炭の一種である「褐炭」の上に国土があるような国で、石炭火力が電源の8割を占めます。褐炭をリキッド化して利用したり、ガス化してアンモニアを製造したりということもおこなっていて、石炭を化学原料としても活用しています。こうした国が「石炭利用を止めろ」と言われたら、産業や生活が立ちゆかなくなってしまう。エネルギー消費が急激に高まる中国やインド、インドネシアも同様です。ドイツは石炭資源が豊富で、安全保障上の観点からも、石炭を利用しています。
このように、地球規模で見れば、国や地域によって、石炭は今後も重要なエネルギーであり続けるでしょう。ですから私は、「脱炭素」「ノーコール」という表現は、問題の本質を正しく表現していないと思っています。温暖化を防ぐために問題となるのはあくまでもCO2であり、目指すべきは「脱CO2」なのではないでしょうか。そのために、「石炭利用のゼロエミッション化(排出されたものを回収して再利用するなどして実質ゼロにすること)」を目指すというのが的確な表現ではないかと思います。それには時間がかかるでしょうが、それを目指して絶え間なくがんばろう、その努力を加速しよう、というのが私たちの思いです。
―後編では、石炭のゼロエミッション化に向けて、日本の役割や技術の進化などについてうかがいます。
1947年、長野県で生まれる。東京大学経済学部卒業後、電源開発株式会社(J-POWER)に入社。企画部長、常務、副社長を経て、2009年6月、代表取締役社長に就任。2016年より、同社代表取締役会長。2015年、石炭エネルギーセンター(JCOAL)会長に就任。
お問合せ先
長官官房 総務課 調査広報室
※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。
あなたにオススメの記事
-

【インタビュー】「まだまだ残っている、省エネのポテンシャル」―奥村 和夫氏(後編)
-

【インタビュー】「省エネは、快適な暮らしと合理的な生産方法を実現する手段」―奥村 和夫氏(前編)
-

【インタビュー】「先進技術で石炭のゼロエミッション化を目指し、次世代のエネルギーに」−北村 雅良氏(後編)
-

【インタビュー】「日本のノウハウを生かし、LNGの国際市場をリードする存在に」-広瀬 道明氏(後編)
-

【インタビュー】「LNGは環境性・供給安定性・経済合理性のバランスのとれたエネルギー」-広瀬 道明氏(前編)
-

【インタビュー】「国際競争力を高めつつ、安定供給を維持するために 」-月岡 隆氏(後編)
-
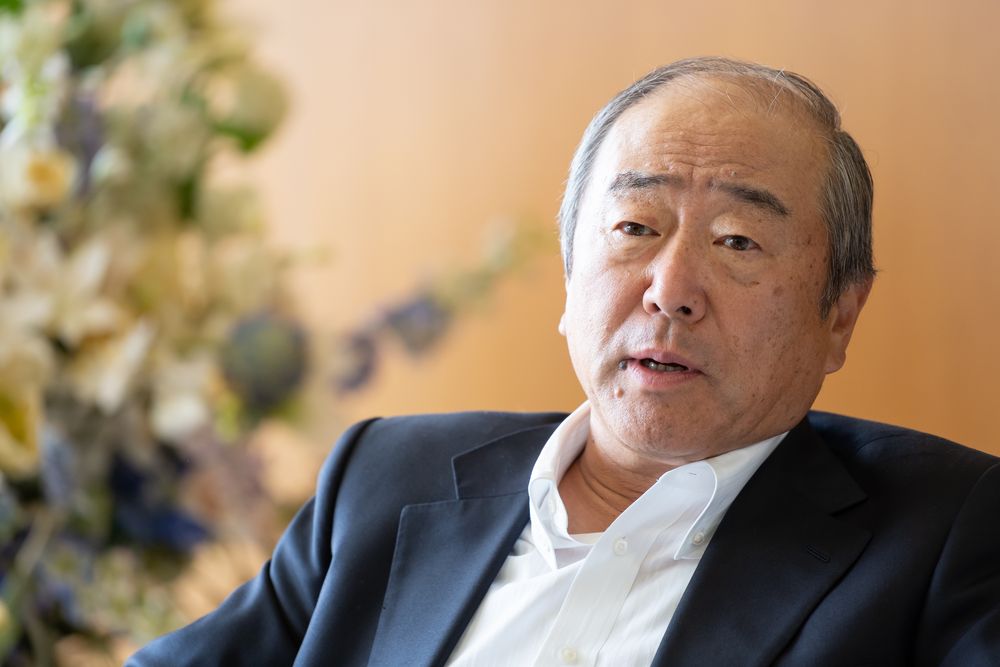
【インタビュー】「可搬性・貯蔵性に優れた石油は、エネルギー供給の“最後の砦”」-月岡 隆氏(前編)
-
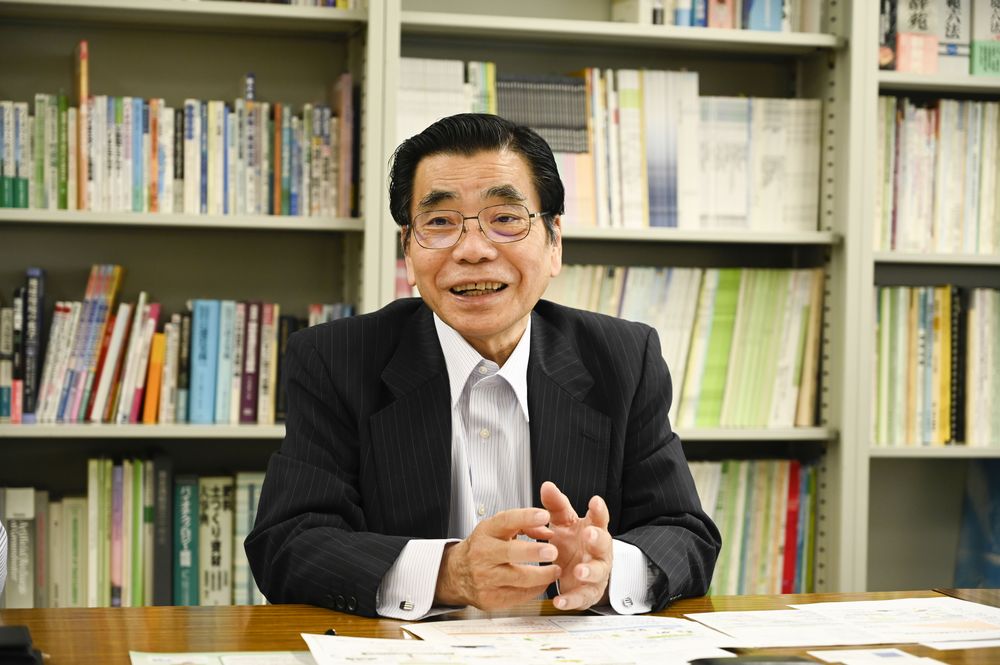
【インタビュー】「バイオマスエネルギーで循環型社会の形成を」—牛久保 明邦氏(後編)
最新記事
-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用
-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?
-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革
-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目
-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!
-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)
-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)
-

ガソリンの暫定税率(当分の間税率)の廃止でガソリン代はどうなるの?よくいただく質問に、資源エネルギー庁がお答えします!




