【インタビュー】「コスト競争力のある原発で、持続可能な世界を実現」―山本隆三 氏(後編)
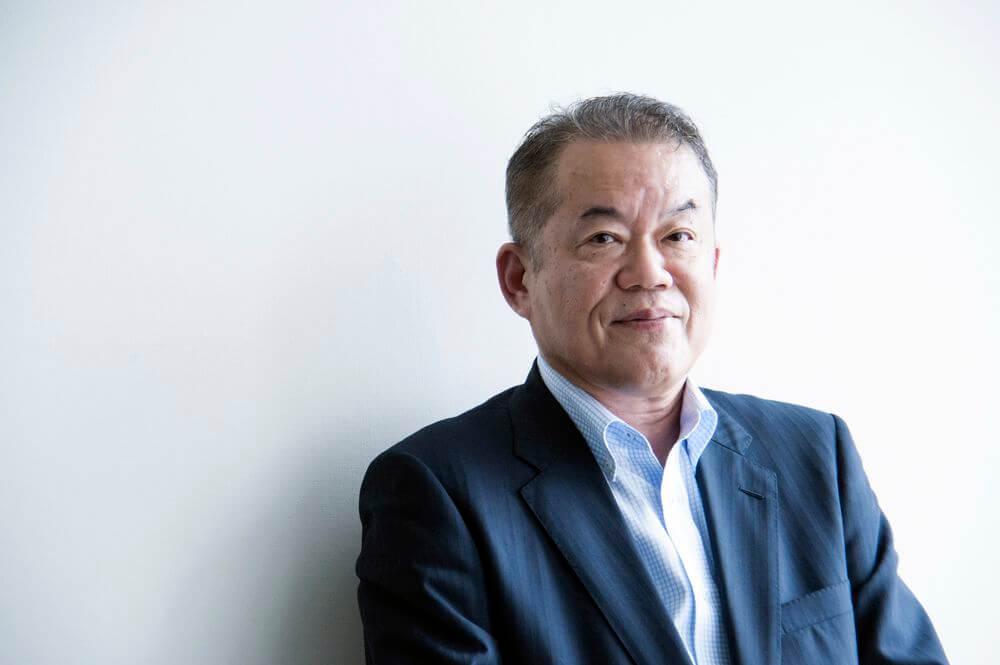
燃料供給の現場に身を置いた経験や、海外事情に精通する立場から、エネルギー問題を経済性や政治状況の観点で検証してきた山本隆三氏のインタビュー。前編「エネルギー安全保障の観点から考える、原発の意味」に続き、後編ではコストを抑制した温暖化対策としての原子力の有用性、また、世界の原子力発電(原発)の状況などについてもうかがいました。
環境と経済性の両立を図るためには原発が有用
-エネルギーでは、温暖化対策や経済性といった点も大きな課題です。これらの観点から見ると、原発はどのようなエネルギーだと言えるのでしょうか。
山本 温暖化対策について考える時には、エネルギーに限らず、対策のためにかかるコストについても合わせて考える必要があります。温暖化対策は継続的におこなわれるべきものであり、温暖化対策を重視するあまり経済性を無視するということになっては対策を継続できません。
原発は、再生可能エネルギー(再エネ)と同様、発電時にCO2を排出しない電源(電気をつくる方法)であり、温暖化対策として有効です。ただ、コストの面で見れば原発には競争力があります。

山本 再エネでは、風力、太陽光発電が火力並みのコストに下がった国も一部にはありますが、多くの国では、ほかの電源に比べまだまだ発電コストが高いのが実態です。ドイツは2018年1月、メルケル首相の所属するドイツキリスト教民主同盟とドイツ社会民主党(社民党)とが連立交渉をおこない、「2020年の温室効果ガスの排出目標を放棄する」ことで合意しました。そこには、再エネのコスト問題が関係しています。
ドイツの電源は現在約40%が褐炭・石炭火力で、発電コストが非常に安価です。しかし2020年の温暖化目標を必達とするならば、全廃して再エネに置き換えることが必要となります。キリスト教民主同盟が当初連立を模索していた緑の党は、これを要求していました。しかし、再エネへの置き換えは、電気代の値上がりにつながる恐れがあります。しかも、電力供給の不安定化にもつながります。そこでキリスト教民主同盟は連立を断念し、労働組合に近く、炭鉱関連労働者の雇用を重視する社民党と連立を組むこととなったのです。
一方で原発は、発電コストの安価な電源です。米国などでは設備利用率が90%に達しているなど、再エネとの比較では送電線の利用率が高く、より無駄のない電源だともいえます。つまり原発は、コストを抑制しながら温暖化対策を進めるために有用なものなのです。
電気料金安定化のカギは原発に、新設を進める多くの国
-ドイツは「2022年に全原発を閉鎖する」という方針を打ち出しているため原発に頼ることができず、かといって再エネでは電気代が高騰するため、温室効果ガス排出目標の放棄という判断をせざるを得なかったのですね。
山本 そうですね。ただ、ドイツがこの先原発をどうするつもりなのかは不透明です。コストと供給の安定化の問題を考慮して、原発廃止を撤回することもありうるのではないかと思っています。
脱原発の方針を掲げながら撤回した国には前例があります。それはスウェーデンです。1980年に「2010年までに脱原発する」と決定したものの、1990年代になって撤回しました。理由は2つあります。ひとつは、ドイツの問題と同様、電気代が高騰するということ。もうひとつは温暖化問題です。IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)が設置されたのが1988年ですから、スウェーデンが脱原発を掲げた1980年には温暖化問題はあまり注目されていなかったのですね。そこで、原発を利用せず温暖化対策を進めることが可能かどうかを改めて検討したところ、難しいという結論に達したのです。2017年には、現在利用している原発10基を、電気代のさらなる抑制と温暖化対策のためにすべて建て替えるということも発表しており、方針を180度転換したと言えます。
ヨーロッパではほかにも、ブルガリア、ハンガリー、アルメニア、ポーランドなども原発新設や建て替えに乗り出しています(「世界の原発利用の歴史と今」参照)。イギリスも原発を新設中ですが、その理由はエネルギー安全保障と、電気料金の安定化を図ることにあります。イギリスは1990年代に電力自由化に踏み切り、不採算な火力発電や炭鉱が次々と閉鎖しました。一方で、将来的なビジネスの予測がしづらいという理由から発電所の新設は進まず、近年のイギリスは発電設備の数が減少し、最大需要に対して供給力にどの程度余裕があるかを示す「電力供給予備率」がどんどん落ちていました。2017年の冬には予備率の見込みが1.1%と、万が一のことがあれば停電するというところまで追い込まれたこともありました(※2016年末に発表された見通し)。
加えて、かつては輸出もおこなっていた国産の天然ガスは、国内需要をまかなえないほどに生産量が激減しており、価格が変動しやすい輸入天然ガスに頼っています。これらの要因が、電気代の不安定さにつながってしまっています。そうした中、発電コストがある程度予想でき、さらに40年〜50年安定的に運転を継続できる原発は、非常に重要な電源ということになります。
そこでイギリスは、原発運転開始後の一定期間は国が電気を買い取るという、将来の事業の安定性を保障する制度を設けた上で、原発の建設を促しているのです。建設中の原発が稼働すれば、全電力の8%がまかなえると言われています。
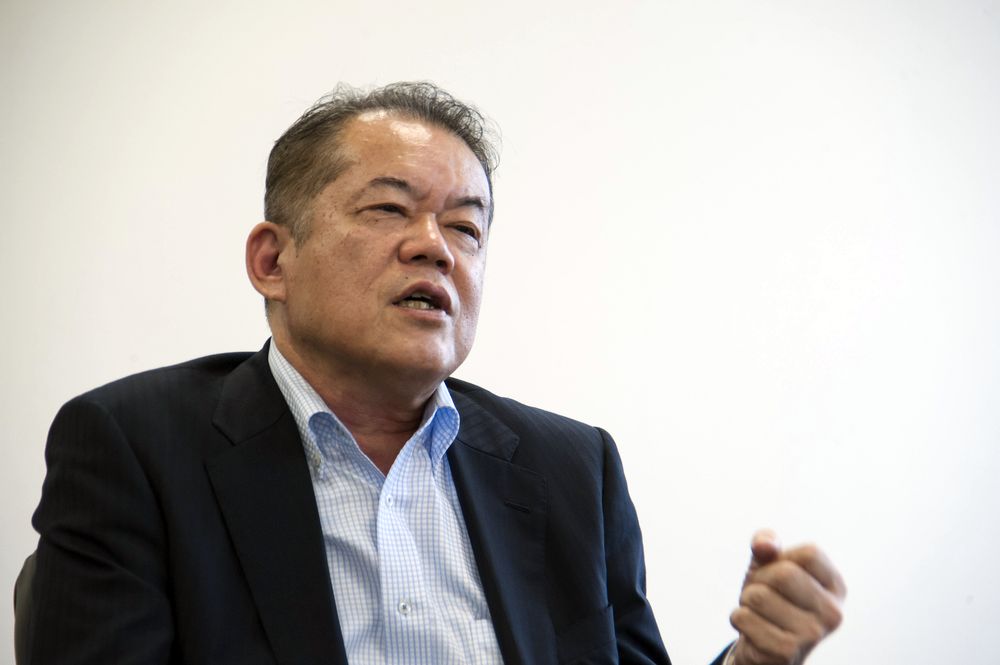
原発回避で失われる最新技術 中国とロシア頼みの懸念
-海外では原発の有用性が見直されているのですね。
山本 ただ、僕が懸念しているのは、現在世界の原発の新設や建て替えを請け負っているのは、ほとんどが中国かロシアだということです。イギリスの原発も当初はフランスが単独で参入していましたが、中国も参加することになりました。潤沢な資金を中国が提供したということだと思います。
実際、前編でお話した米国のボーグル原発は、米国が30年ぶりに新設する原発ですが、国内では十分なエンジニアが集まらず、中国のエンジニアを招聘しました。中国では2018年10月時点で、原発を14基同時に建設していますから、最新技術の蓄積ができているというわけです。
ですが、世界中の原発をロシアと中国がつくることになれば、日本、米国、フランスが持つ原子力の技術は急速に失われてしまうのではないでしょうか。それは大きな問題です。また、政治体制が異なる国にエネルギーの技術をおさえられるということは、非常に強く懸念される事態にほかなりません。
そういう意味でも、日本は、原発のメリットに目を向けて、研究を継続していく必要があると思います。そもそも日本は、経済が停滞していた20年の間に、多くの技術力を失っています。特許申請件数で見ても、かつては米国と世界一を争うほどでしたが、現在の日本はその座を中国に奪われています。それでも日本は原子力分野では世界で優位に立っていましたが、ここにきて危うくなっていると感じます。
-確かに、建設の機会がなければ技術を磨く機会も得られませんね。世界の原子力分野では、どのような最新技術が登場しているのでしょうか。

山本 いま、世界の原子力の最新技術は、小型炉、つまりスモールモジュラーリアクターへと移りつつあります。発電量10万kwほどという少ない発電量のモジュールを工場でつくり、それを現地に運んで組み立てるという形が基本です。中国、ロシア、米国、イギリスが研究中で、日本も研究をおこなっています。現在、世界には50ほど設計段階のものがあり、まだ実用化はされていません。
米国で今もっとも研究が進んでいる小型炉は、最大で12基のモジュールを連結でき、合計で60万kwほどの発電量を持っています。大型の原子炉は、発電量100万kwを越えるものが普通ですので、60万kwというとずいぶん小さいように思いますが、場所を取らないというメリットがあります。また小型炉であれば、万が一電力供給が途絶えても自然対流で燃料の冷却を継続できるといったように、過酷事故のリスクが少ないというメリットもあります。原発の有用性を考える際には、こうした最新技術も視野に入れておく必要があります。
最近よく「持続可能な世界」という言葉を耳にします。ただ、「持続可能な世界とは環境に優しい世界のこと」という認識は誤りです。温暖化対策を無理に推し進め、電気代が高騰して産業が継続できなくなるとすれば、それは「持続可能な世界」とはいえません。「持続可能な世界」とは、「将来世代が今の世代より良い生活ができるということ」であり、産業や企業もまた持続しなくてはなりません。そのためには、温暖化対策はコストをできるだけ抑制しながら進め、電気代の安定化を図らなくてはならないのです。
その観点から見れば、原発の役割は非常に大きいものです。持続可能な社会を目指すためにこそ、最新の原子力技術を活用しながら、各電源のベストな構成を考えていくべきでしょう。
1951年、⾹川県⽣まれ。京都⼤学⼯学部卒業後、住友商事株式会社に⼊社。⽯炭部副部⻑、地球環境部⻑ を務める。2013年より常葉⼤学経営学部教授。国⽴研究開発法⼈新エネルギー・産業技術総合開発機構「民間主導による低炭素技術普及促進事業採択審査委員会」委員長代理、⽇本商工会議所、東京商工会議所エネルギー・環境委員会学識委員などを務める。
お問合せ先
長官官房 総務課 調査広報室
※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。
あなたにオススメの記事
-

【インタビュー】「まだまだ残っている、省エネのポテンシャル」―奥村 和夫氏(後編)
-

【インタビュー】「省エネは、快適な暮らしと合理的な生産方法を実現する手段」―奥村 和夫氏(前編)
-

【インタビュー】「先進技術で石炭のゼロエミッション化を目指し、次世代のエネルギーに」−北村 雅良氏(後編)
-

【インタビュー】「安定的で安価な石炭は今も重要なエネルギー源、技術革新でよりクリーンに」−北村 雅良氏(前編)
-

【インタビュー】「日本のノウハウを生かし、LNGの国際市場をリードする存在に」-広瀬 道明氏(後編)
-

【インタビュー】「LNGは環境性・供給安定性・経済合理性のバランスのとれたエネルギー」-広瀬 道明氏(前編)
-

【インタビュー】「国際競争力を高めつつ、安定供給を維持するために 」-月岡 隆氏(後編)
-
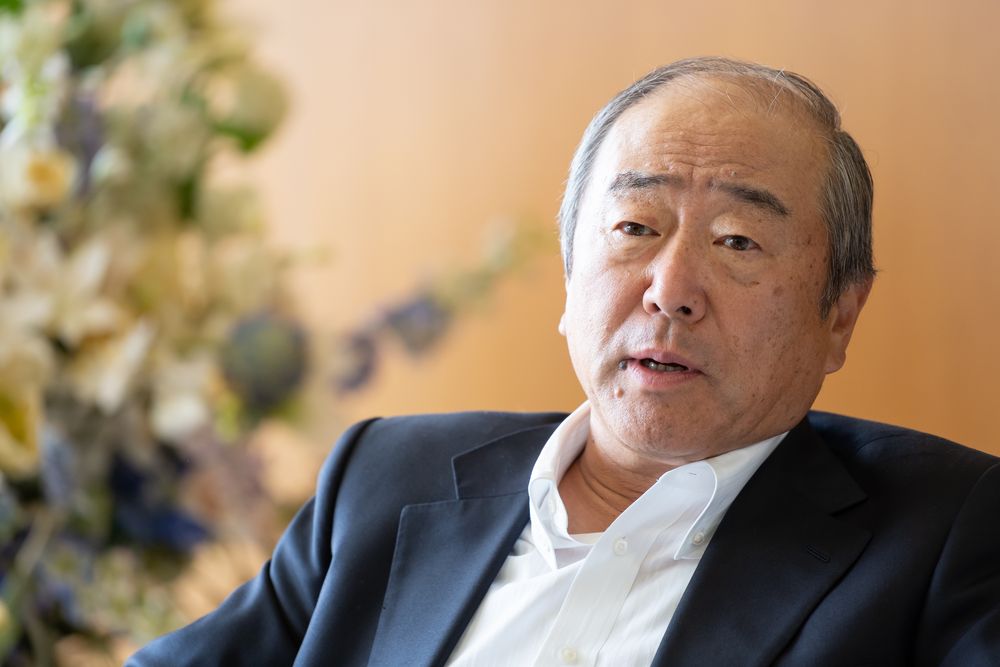
【インタビュー】「可搬性・貯蔵性に優れた石油は、エネルギー供給の“最後の砦”」-月岡 隆氏(前編)
最新記事
-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用
-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?
-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革
-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目
-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!
-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)
-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)
-

ガソリンの暫定税率(当分の間税率)の廃止でガソリン代はどうなるの?よくいただく質問に、資源エネルギー庁がお答えします!




