【インタビュー】「電力・ガスシステム改革の評価とこれからの課題」―山内弘隆 氏(後編)
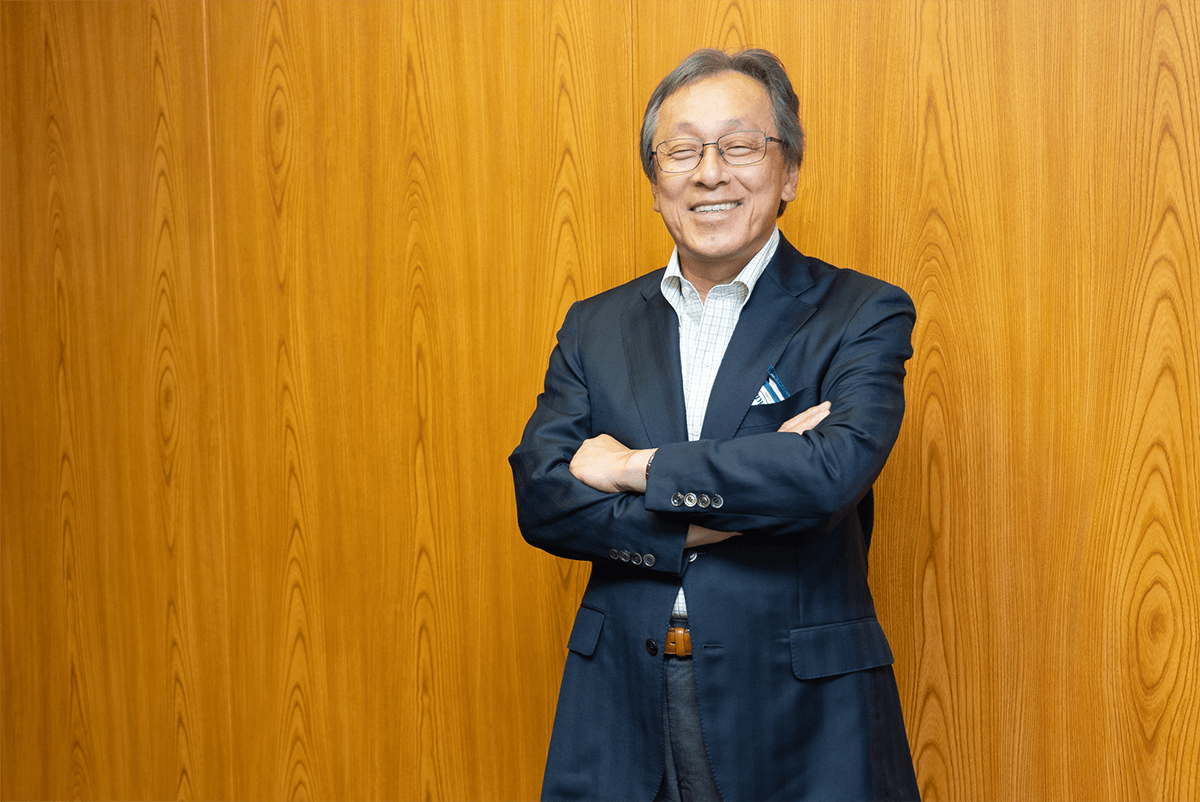
公共経済学や公益事業論を専門とし、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(以下、電力・ガス基本政策小委員会)でも委員長を務める山内弘隆氏のインタビュー。前編「エネルギーの自由化はなぜ必要なのか?」に続いて後編では、電力・ガスシステム改革の現状についての評価、残された課題や今後必要となる施策などについてうかがいました。
電力システム改革後、スイッチング率はフランスを上回り評価すべき数字
―電力・ガスシステム改革の現状をどのようにご覧になっていますか。
山内 電力については2016年4月に小売全面自由化が、都市ガスについては2017年4月小売全面自由化がおこなわれました。電力では、いわゆるスイッチング率を指標として見ると、まだまだじゅうぶんではないという議論もあります。しかし、市場全体の13%ほど(家庭用8.4%、産業用5.6%)という現在のスイッチング率は、電力自由化後に徹底的な競争促進策を採った英国に比べれば低いものの、フランスと比較すれば上回っています。これは評価すべき数字だと思います。
日本では、急進的な政策は一般的に好まれず、改革も慎重を期す傾向があると思います。そのような慎重な施策で10%超というのは、妥当な数字ではないでしょうか。企業で考えてみれば、売上高が10%減少するというのは大きな数字です。それだけの契約が旧電力会社から新電力会社へと移行したのです。旧電力会社は市場の圧力をかなり感じているのではないでしょうか。
もうひとつ指標となるのは、事業者の新規参入状況です。電力の場合、市場が大きいこともあり、新規参入事業者はかなり多く、新しいビジネスが育っていると言えるでしょう。全面自由化から1年半が経過し、撤退する事業者も出始めてはいますが、これは市場を見通すことが可能になってきたということです。今後は、きわめて新しいアイデアを持つ事業者や、イノベイティブな経営や販売手法を採っている事業者が伸びる段階に入るのでしょう。
―新規参入の電力会社でシェアを獲得しているのは、どういった企業なのでしょう。
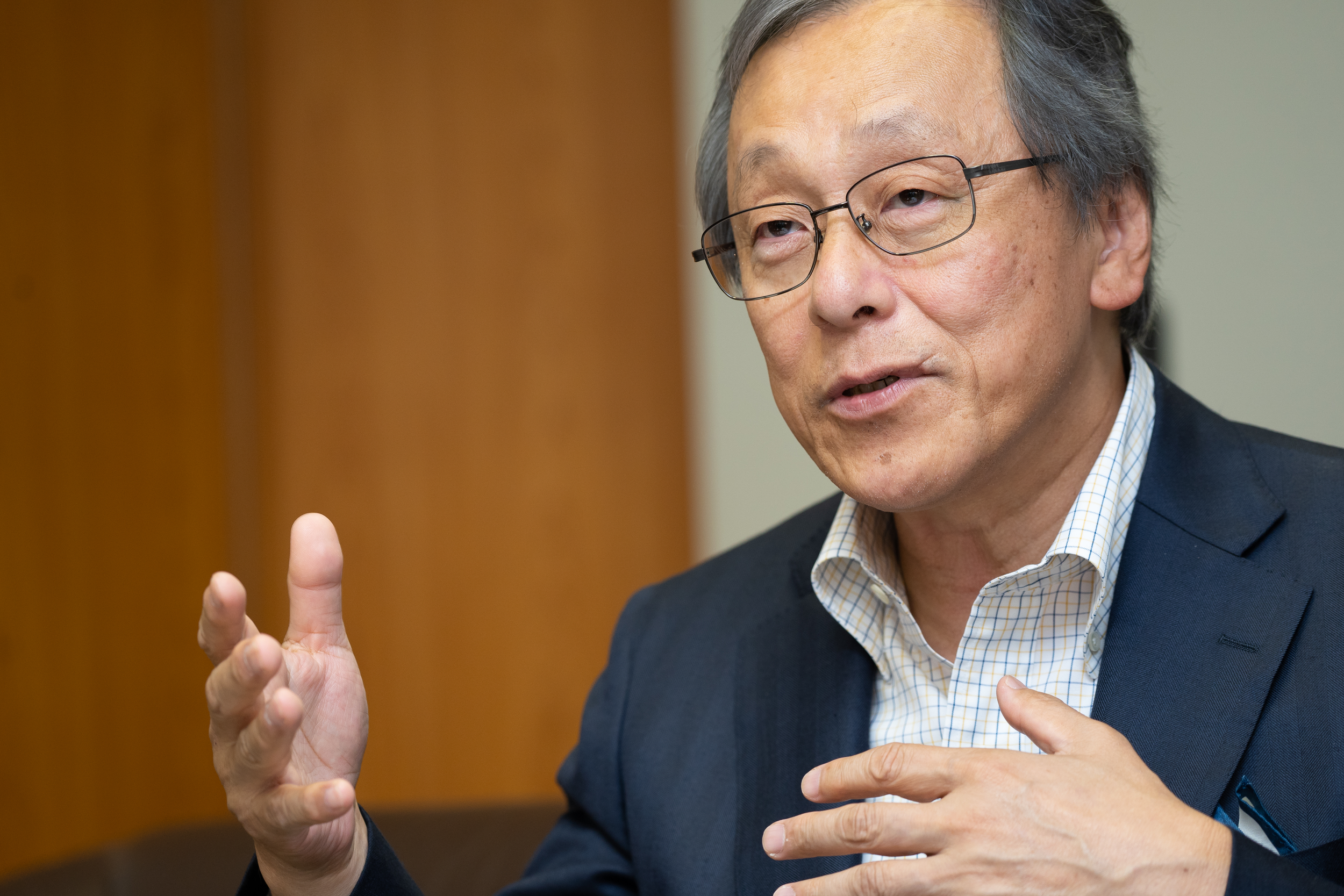
山内 まず、顧客とのチャンネル、コンタクトポイントを元々持っている企業です。たとえば低圧部門の新電力会社として多くのシェアを獲得しているKDDIは、携帯電話の機種交換などでショップを訪れた顧客に対し、待ち時間に電力の営業をしているそうです。ガス大手各社も電力分野に参入していますが、これらの企業も、保安検査で顧客宅を訪問するというコンタクトポイントを持っています。
実は、ガスシステム改革を議論する際、実際の現場を見る必要があると考え、東京ガスの子会社ライフバルの保安検査に同行したことがあります。一人暮らしの高齢者などにとっては、自宅にやって来る保安検査のスタッフは何でも頼める相手という認識で、壊れたものの修理や電球交換なども相談するのです。その様子を見た時、電力自由化が実施された暁にはガス会社は多くのシェアを獲得できるのではないかと予想しましたが、実際にそうなりました。
さらに最近は、対面販売だけでなく、インターネットを通じた顧客への営業も盛んになりつつあるようです。それだけ需要家が「電力自由化」とは何かを理解し、スイッチングの方法が分かるようになったということです。KDDIはこの動きを重視し、自社サイト内に電力に関するコンサルティングサイトを開設して電気の使い方と電気料金のアドバイスをおこなっています。また、電気と他のサービスをバンドリングしたプランもかなり顧客を獲得していますね。
ガスシステム改革がもたらすのは最も効率的な供給方法と技術革新
―ガスについてはいかがでしょうか。
山内 ガスについては、数字を見てもまだ新規参入事業者の数がじゅうぶんではないとの見方もあると思います。ただ、ガス機器の販売や機器のメンテナンスを安価にする事業者の登場など、競争の効果は現れつつあると感じます。
―電力とガスは性質の異なるものですから、一口に「自由化」と言ってもなかなかパラレルには進まないということでしょうか。

山内 そうですね。まず、全国に送配電網が張り巡らされている電力と、極めてローカルなネットワークしか存在しないガスでは、売り方や新規事業者の参入方法も当然異なってきます。
2つ目は供給工程の違いです。たとえば都市ガスの場合、上流工程には海外のガス田があり、ガス事業者はそこで採掘したガスを自社の船で日本まで輸送して、ネットワークを経由して供給します。特に日本のガス事業者のガス専用船の運用などは、海外の有名大学でケーススタディとして研究されるほど特徴的な仕組みです。さらに現在では、日本のガス事業者はガス田への投資もおこなっています。非常に垂直統合が進んだ産業ではないかと思いますし、その意味では、調達から輸送・蓄積・供給というガス産業の一連の流れは、電力より参入ハードルが高いのかもしれません。現在、ガスの輸入基地を他企業へと開放する制度改革を進めていますが、ガス輸入基地は各企業の私的財産でもあり、どのように開放するかという点は議論の分かれるところです。また、電力のような卸売市場が存在しておらず、今後、市場の開設をおこなう必要も生じるかもしれません。
ただ、ガスは都市ガスとプロパンガス(LPガス)の競争、またオール電化との競争をおこなっており、その観点ではすでに競争が起こっているとも言えます。そうした実態についても評価すべきです。
今後、ガスのシステム改革を通じて、最も効率的なガスの供給方法が模索されていくでしょう。ガス管というネットワークを敷いて集中的に供給する都市ガスのシステムは、人口が集中している地域でしか成立し得ないものです。将来的には、人口減少によって人口密度が下がった地域では、シリンダーでガスを輸送するプロパンガスの方が効率的だとして、ガス管による供給が廃止されるとことも起こるかもしれません。
もうひとつ、ガスシステム改革において抑えておくべきポイントは、ガスでも技術革新が起こっているということです。先日発表された第5次エネルギー基本計画では、水素を将来の主力エネルギー源のひとつにしていくことが明記されましたが(「新しくなった『エネルギー基本計画』、2050年に向けたエネルギー政策とは?」参照)、ガスは水素と高い親和性を持ちます。そこで、たとえば再生可能エネルギーで電気を作りすぎた時に、その電気を使って水素を作りガス管を通じて供給するという実験もおこなわれています。また、ガスから水素を作る動きもあります。こうした技術革新も、自由化の中で進んでいくことを期待しています。
細やかなチューニングをおこないながら、少しずつエネルギーシステム改革を進めるべき
―現在残っている課題は何でしょうか。
山内 適切な競争を成立させるための制度設計です。先ほどお話したガスの卸売市場もそうですが、市場をうまく利用しながら適切な競争ができるよう、議論を進めています。
たとえば、市場の競争が激しくなりすぎてしまうと、設備への投資インセンティブが削がれてしまい、長期的なエネルギーの安定供給ができなくなってしまいます。特に電力については、日本では節電が進んで電力使用量がだんだん減っていることもあり、投資へのインセンティブが働きづらくなってしまいます。しかし、将来に向けて、大規模な電源への投資は継続される必要がある。どのようにして投資インセンティブを確保していくか、考えていく必要があるでしょう。
電力では、ネットワークに関しても同様の問題があります。前編で申し上げたように、日本や主要国では一社がネットワークを独占するという設計になっています。そのため、たとえ発電側に再生可能エネルギーなどの分散電源が増えたり、電力広域的運営推進機関(通称:広域機関)が「あるべきネットワークの姿」を定義したとしても、ネットワーク事業者がそれに応えてネットワークを構築する必要は基本的にはありません。そこで、ネットワーク事業者にインフラ投資をするインセンティブを与え、維持していくことが重要になります。これはEUで問題になっている点で、日本でも何らかの形で取り組む必要が出てくるでしょう。
さらに、作り置きができないという特性を持つ電気を市場に載せた上で、発電と消費の同時同量を実現し、安定供給を担保する必要があります。そのためには、どの時点でどれだけの電気が必要か、あるいはどれだけの需要があるのかといったことを効率的に組み合わせる、さまざまな装置や仕組みが必要です。そこで現在「容量市場」や「需給調整市場」、「環境価値市場」などの市場を作ることで補完をしようとしています。まるで金融分野のようですが、実は、電力取引はほぼ金融取引に近づいています。英国のOvo Energyは小売のプライシングとサービスで勝負している電力会社ですが、経営者は金融出身とのことで、おそらく金融分野で培った調達ノウハウを活かしているのでしょう。
とはいえ、全体的に見れば、日本の電力・ガスシステム改革は極端に振れることなく、うまく調整して進めることができていると捉えています。今後も、細やかなチューニングを行いながら、電気の特性や技術に通じた専門家と知恵を出し合って制度設計をしていくことが必要になるでしょう。そのような専門家は旧電力会社内にいることが多く、電力システムをトータルで見ることができます。そうした人材と、制度設計や市場構築ができる人材がきちんとタッグを組まないと、電力市場の構築は成功しません。日本の政策は慎重だと先ほど申し上げましたが、それでいいのではないかと私が考えるのは、エネルギーにはこのような難しさがあるためです。エネルギーシステム改革は、段階的に少しずつ進めるという方法が適しているのではないかと思います。

―エネルギーシステム改革は技術的ノウハウも絡む分野であるだけに、慎重さと細やかさが求められるということがよく分かりました。ありがとうございました。
1955年、千葉県生まれ。慶應義塾大学商学部卒業、同大学院商学研究科博士課程単位取得満期退学。専門は公共経済学、交通経済学、公益事業論。資源エネルギー庁調達価格等算定委員会委員などを歴任。現在、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会委員長。一橋大学大学院経営管理研究科教授、一般財団法人運輸総合研究所長。
お問合せ先
長官官房 総務課 調査広報室
※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。
あなたにオススメの記事
-

【インタビュー】「まだまだ残っている、省エネのポテンシャル」―奥村 和夫氏(後編)
-

【インタビュー】「省エネは、快適な暮らしと合理的な生産方法を実現する手段」―奥村 和夫氏(前編)
-

【インタビュー】「先進技術で石炭のゼロエミッション化を目指し、次世代のエネルギーに」−北村 雅良氏(後編)
-

【インタビュー】「安定的で安価な石炭は今も重要なエネルギー源、技術革新でよりクリーンに」−北村 雅良氏(前編)
-

【インタビュー】「日本のノウハウを生かし、LNGの国際市場をリードする存在に」-広瀬 道明氏(後編)
-

【インタビュー】「LNGは環境性・供給安定性・経済合理性のバランスのとれたエネルギー」-広瀬 道明氏(前編)
-

【インタビュー】「国際競争力を高めつつ、安定供給を維持するために 」-月岡 隆氏(後編)
-
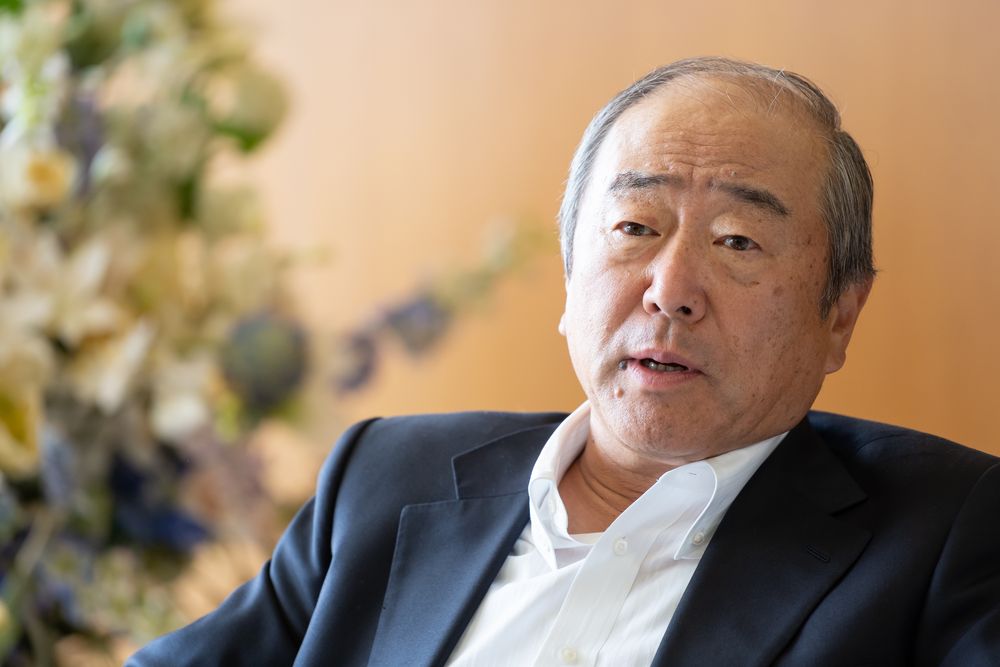
【インタビュー】「可搬性・貯蔵性に優れた石油は、エネルギー供給の“最後の砦”」-月岡 隆氏(前編)
最新記事
-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用
-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?
-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革
-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目
-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!
-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)
-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)
-

ガソリンの暫定税率(当分の間税率)の廃止でガソリン代はどうなるの?よくいただく質問に、資源エネルギー庁がお答えします!




