【インタビュー】「エネルギーの自由化はなぜ必要なのか?」―山内弘隆 氏(前編)
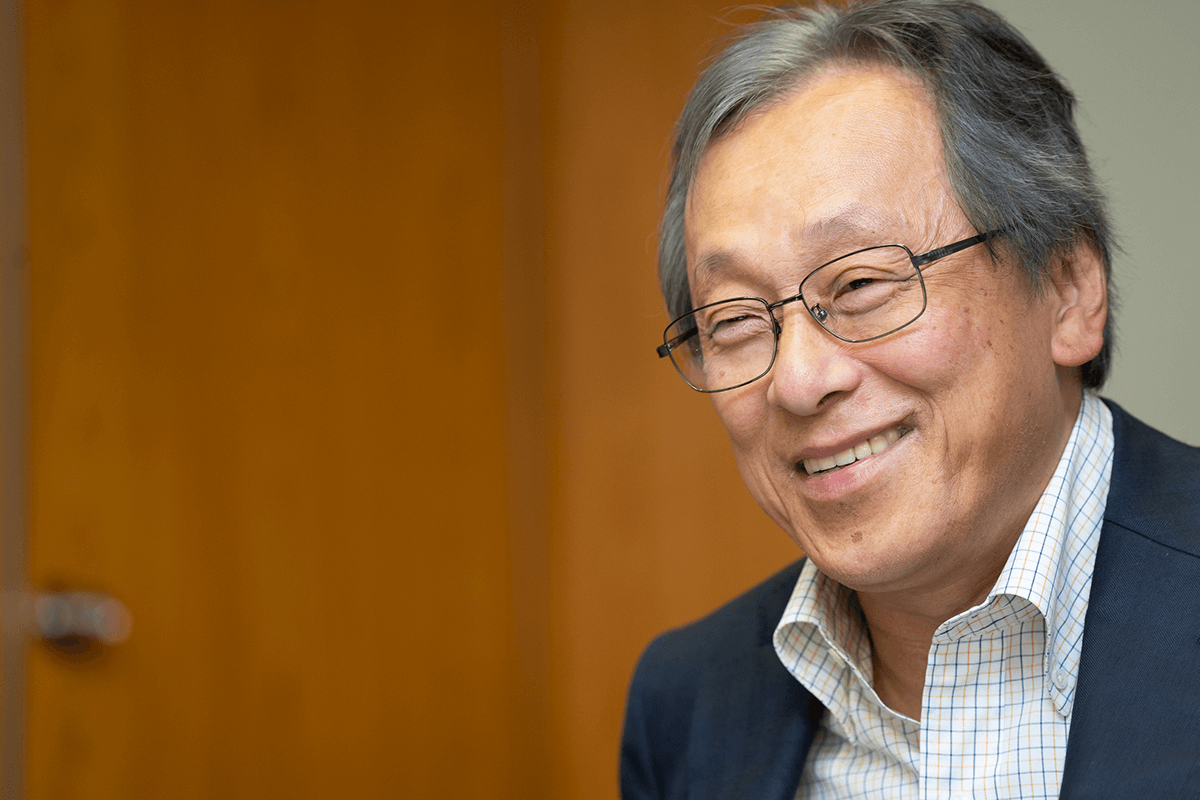
公共経済学や公共事業論を専門とし、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(以下、電力・ガス基本政策小委員会)でも委員長を務める山内弘隆氏。電力・ガスシステム改革の持つ意義や、得られた成果、見えてきた課題と今後必要な施策などについて、山内氏にお聞きました。前後編の2回に分けてお届けします。
進むインフラの自由化、その波が電力・ガスシステムにも
―2016年4月の電力小売全面自由化、2017年4月の都市ガス小売全面自由化によって、電力・ガスシステム改革は、ひとつの山を越えたように思います。こうしたエネルギーの自由化の意義は、どのような点にあるのでしょうか。
山内 そもそも近年、電力・ガスに限らず世界のインフラ分野は、自由化をおこない市場を開放して競争を生み出そうとする大きな流れの中にあります。1978年に米国で実施された航空の規制緩和を皮切りに、通信の自由化などさまざまなインフラの自由化が実施されてきました。かつては、インフラのような公益事業は市場に任せてしまうとうまく運営されないと考えられてきました。しかし1970年代頃から、技術の進歩などを背景に、その様相は大きく変化します。
1983年、ポール・ジョスコウ&リチャード・シュマレンシーが執筆した『Market for Power』がマサチューセッツ工科大学から発行されました。彼らはその著作の中で、インフラを支えるネットワークの部分は規制が必要かもしれないが、市場に参加する企業すべてがネットワークを公平に利用できるようにすれば、インフラ事業を市場に任せても適正な競争が成り立つ可能性があると主張したのです。実際に、米国では、北東部地域で卸電力市場を形成していた「PJM」という機関のように、大規模な電力市場が早くから存在し、さまざまな事業者がそこで電力取引をおこなってきました(PJMは、現在は卸電力市場運営に加えて送電線運用もおこなうPJM-ISOとなっている)。
また、インフラを独占的に運営することで生じる、非効率性やコストの高止まりといった問題が顕在化していました。さらに、市場への新規参入が起こらないことは、産業のダイナミズムの喪失にも繋がっていました。そうした問題意識もあって、1980年代から1990年代にかけ、米国・欧州・日本において、インフラ事業の自由化の流れが動き始めました。こうしたインフラ自由化の流れが、エネルギーに到来したのが現在なのです。
―エネルギーの自由化は世界でも進んでいるのですか。
山内 たとえば英国では、1990年のサッチャー政権下で、電力の民営化が実施され、自由化が進められています。欧州でも、1993年に欧州連合(EU)ができたことから状況が一変します。EUは、産業や貿易の自由化といったいわゆるマーケット志向の政策を原則的に採用する傾向があります。その政策はエネルギーにも適用されました。最も大きな転換点は、1996年に公布された「EU電力自由化指令」でしょう。これにより、EUが主導して各国の電力自由化を進めることとなりました。もちろん、原子力発電中心のフランス、「シュタットベルケ」と呼ばれる地域独占型のエネルギー供給企業が存在するドイツなど、EU各国のエネルギー事情にはそれぞれの特性があるものの、大枠としては、エネルギーシステム改革を実施し競争を促すという方向に動いています。
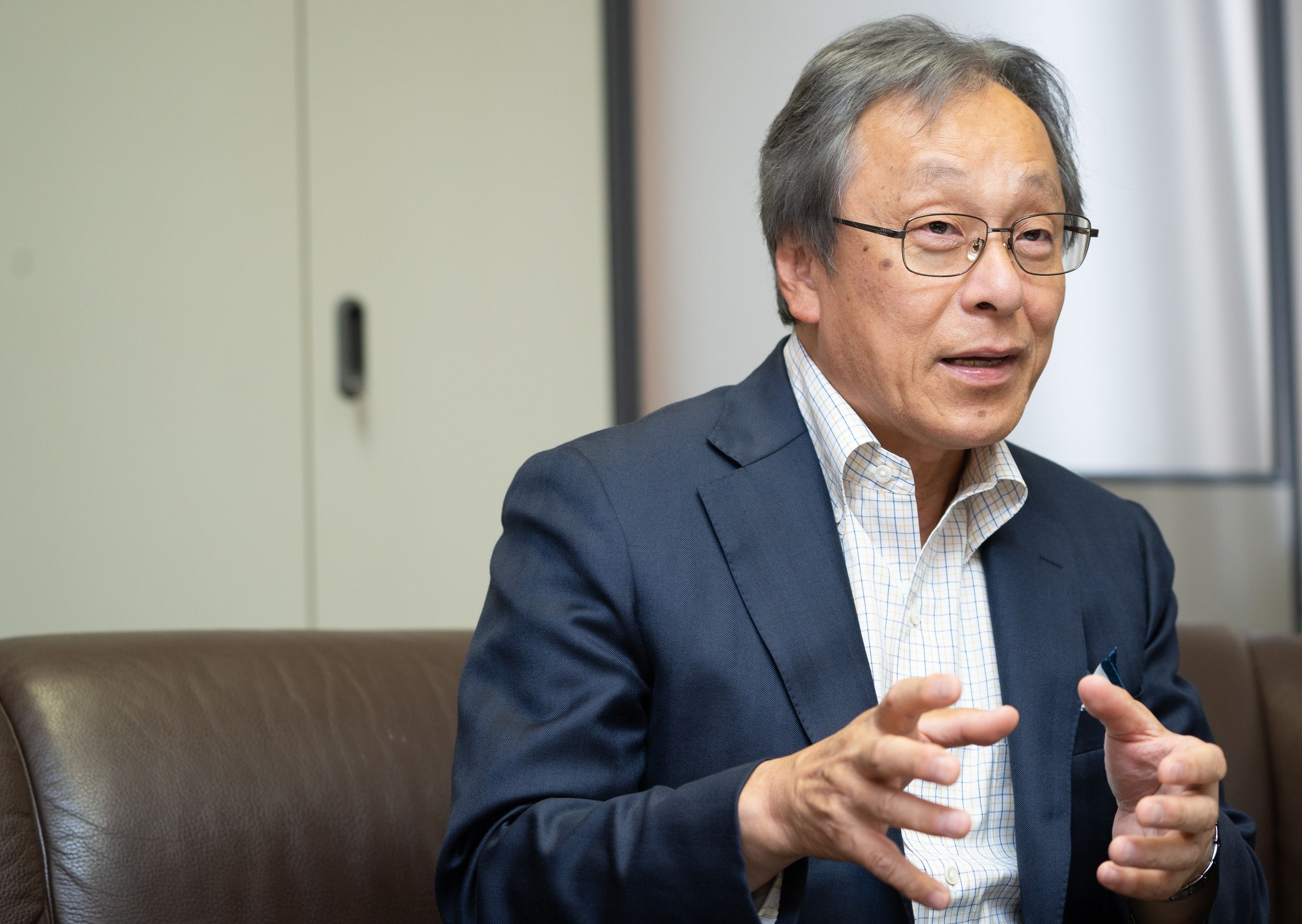
日本の電力・ガスシステム改革の目的とは
―そのような中で、日本の電力・ガスシステム改革はどのような特徴を持っているのでしょうか。
山内 日本で電力・ガスに関するさまざまな改革が始まったのは1995年からのことです。日本の電力システムは以前から民営で、民間企業が発電・小売・送配電のすべてを担っている、どちらかと言えば欧州より米国に近いものでした。ただ、日本は米国と異なり国土が狭いこともあって、地域独占型の一般電気事業者(発電から送配電まで担う従来型の電気事業者)が存在していました。
この電力・ガスシステム改革の最大の目的は、競争が可能な分野については競争を促すことで、効率性向上やコスト削減を目指すことです。ただ、改革開始当初は、企業や工場など大規模なエネルギーが利用される分野では競争が可能だが、家庭向けエネルギー分野では事業者間の競争を起こすのは難しいのではないかと考えられていました。
ところが、家庭向けエネルギーの自由化は当面見送るという方向に進みつつあった2011年、東日本大震災が起こり、それに伴って東京電力福島第一原子力発電所の事故が発生しました。このことによって、電力・ガスシステム改革に新たな観点が加わりました。
それはまず、社会的リスクをできるだけ小さく抑えるため、大規模集中型のエネルギー供給システムから、分散型や地産池消の供給システムへと移行することが望ましいのではないかといった観点です。また、さまざまなリスクをはらむ原子力発電やCO2を多く排出する化石燃料よりも、再生可能エネルギーを利用すべきではないかという議論も広がりました。つまり、東日本大震災とそれに伴う原子力発電の事故から得た反省を、電力・ガスシステム改革の中で活かそうという気運が高まったのです。
時を同じくして電力分野では、「スマートメーター」や「HEMS・BEMS」、「スマートグリッド」などのさまざまなイノベーションが登場してきました。これらは、エネルギー消費面でのデジタル化、スマート化を促進するものです。また、電力に必要とされる「同時同量性」(需要の量と供給の量を一致させること)を制御できる技術を発展し、活用すれば、発電事業・小売事業・送配電事業を分割しても適切な電力の運用が可能になることが明らかとなりました。こうした革新的な技術を電力・ガスシステム改革に活用することで、さらなるイノベーションの誕生を促すべきであるという議論も高まりました。このような観点も加わって、現在の電力・ガスシステム改革が進められています。
適正な競争を促し、従前の組織が持っていた良さを引き継ぐための制度作り
―インフラ事業を市場に任せてしまうと、過当競争が起こるのではないかというような懸念があると思いますが、大丈夫なのでしょうか。

山内 歴史的に見ると、日本の電力会社では、過去に激しい競争がおこなわれた時代がありました。「電撃戦」と呼ばれた過当競争で、およそ3回起こっています。まず、大正時代に起こった火力発電の競争。3つの電力会社が苛烈な競争を繰り広げ、当時の東京市長だった奥田義人氏が仲介に入りました。その後、今度は水力発電で競争が起こります。さらに送配電技術が発達すると、今度は中部地域や関西地域で事業を営んでいた電力会社が関東へと進出し、関東の電力会社と競争することとなりました。鉄道においても、同一区間で複数企業が並行して自社の線路を敷く、運賃をどんどん割引いて最後は粗品も付けるなどの過当競争が起こったことがあります。
しかし、近年のインフラ事業の自由化は、ネットワークには競争をさせず、従来の独占を維持させておくという方法を採っています。日本の電力システム改革でも、ネットワークにあたる送配電網は従来の地域独占型を維持させ、そのネットワークを経由して電気を販売する事業や発電する事業で競争をさせるという設計になっています。これはジョスコウ&シュマレンシーの理論にも合致するものです。
英国は鉄道でも同様の方法を採っており、ネットワークに当たる線路網は一社が独占し(2002年までレールトラック社、現在はネットワーク・レール社)、その上を各社の列車が運行するという仕組みになっています。英国のその試みはなかなか上手くいってはいないようですが、エネルギーについては、前述したような運用に役立つ技術が発達していることから、適正な競争環境を構築できるのではないでしょうか。
―災害時の対応に関してはいかがでしょう。自由化は影響してくるのでしょうか。
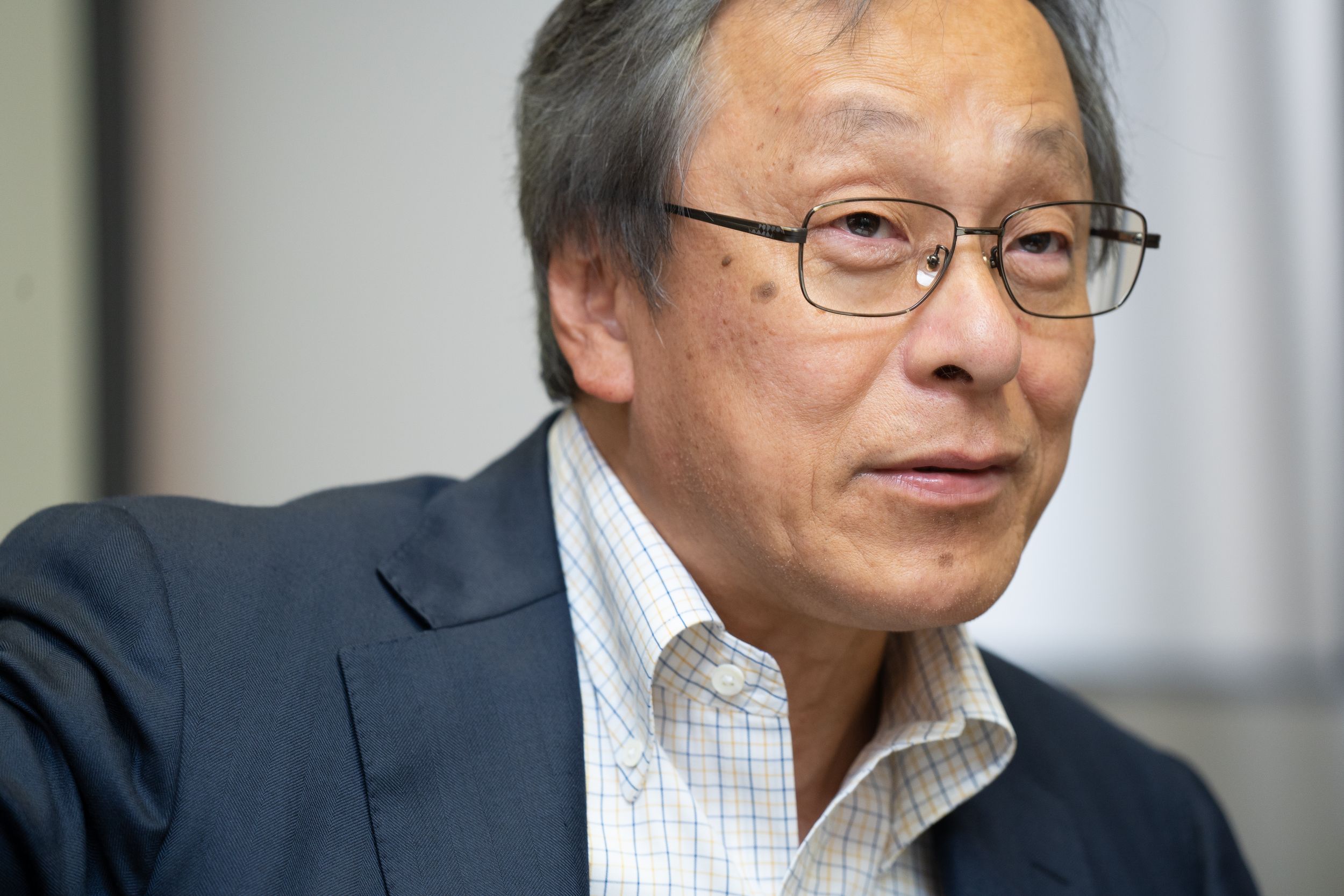
山内 そうですね。たとえば電力システムの改革では、これまで同一組織内で垂直的に統合していた業務を、発電・小売・送配電に分割しました。かつての垂直統合的な業務の進め方は、経済学では「組織の経済学」と言いますが、組織内の別部署と共に業務を進めることで、摺り合わせを容易におこなうことができます。たとえば自動車メーカーが新しい自動車を作りたいと考えた時、望む強度と形状のフロントガラスが市場にすでにあるとは限りません。そこで組織内の別部署と共にフロントガラスを開発すれば、安いコストで製造でき、うまく摺り合わせることもできます。しかし、組織を分割したことで新しい事業者と協業することが必要となれば、摺り合わせがうまく行くとは限りません。
今年の冬、東京電⼒圏内では積雪で太陽光発電の出力が低下し、さらに火⼒発電が故障して、電⼒不⾜のリスクが⾼まりました。あの時は電力広域的運営推進機関(通称:広域機関)が他地域の電⼒会社へ電⼒融通を指示して事なきを得ましたが、あれこそ摺り合わせが必要な場面です。同⼀組織内ではなくなったことで、そうした摺り合わせがいつも上手くいくだろうかという懸念はあります。特に、今後さらに競争が進み、さまざまな事業者が新しく参⼊してくればどうなるでしょうか。
そのためにも、太陽光発電など変動性の高い電源の予測値を発電計画に取り入れるタイミングや手法についてなど、スムーズな摺り合わせを促すための制度を現在議論しています。2018年6月に起こった大阪府北部地震の際は、全国からガス技術者が関西に集まり、復旧に尽力しました。市場の競争を進めつつも、あのようなスムーズな摺り合わせができる関係をどこまで残していけるかということが自由化の課題になっていくでしょう。
―後半では、電力、ガスそれぞれの改革の現状と今後取り組むべき課題についてお話をうかがいます。
1955年、千葉県生まれ。慶應義塾大学商学部卒業、同大学院商学研究科博士課程単位取得満期退学。専門は公共経済学、交通経済学、公益事業論。資源エネルギー庁調達価格等算定委員会委員などを歴任。現在、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会委員長。一橋大学大学院経営管理研究科教授、一般財団法人運輸総合研究所長。
お問合せ先
長官官房 総務課 調査広報室
※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。
あなたにオススメの記事
-

【インタビュー】「まだまだ残っている、省エネのポテンシャル」―奥村 和夫氏(後編)
-

【インタビュー】「省エネは、快適な暮らしと合理的な生産方法を実現する手段」―奥村 和夫氏(前編)
-

【インタビュー】「先進技術で石炭のゼロエミッション化を目指し、次世代のエネルギーに」−北村 雅良氏(後編)
-

【インタビュー】「安定的で安価な石炭は今も重要なエネルギー源、技術革新でよりクリーンに」−北村 雅良氏(前編)
-

【インタビュー】「日本のノウハウを生かし、LNGの国際市場をリードする存在に」-広瀬 道明氏(後編)
-

【インタビュー】「LNGは環境性・供給安定性・経済合理性のバランスのとれたエネルギー」-広瀬 道明氏(前編)
-

【インタビュー】「国際競争力を高めつつ、安定供給を維持するために 」-月岡 隆氏(後編)
-
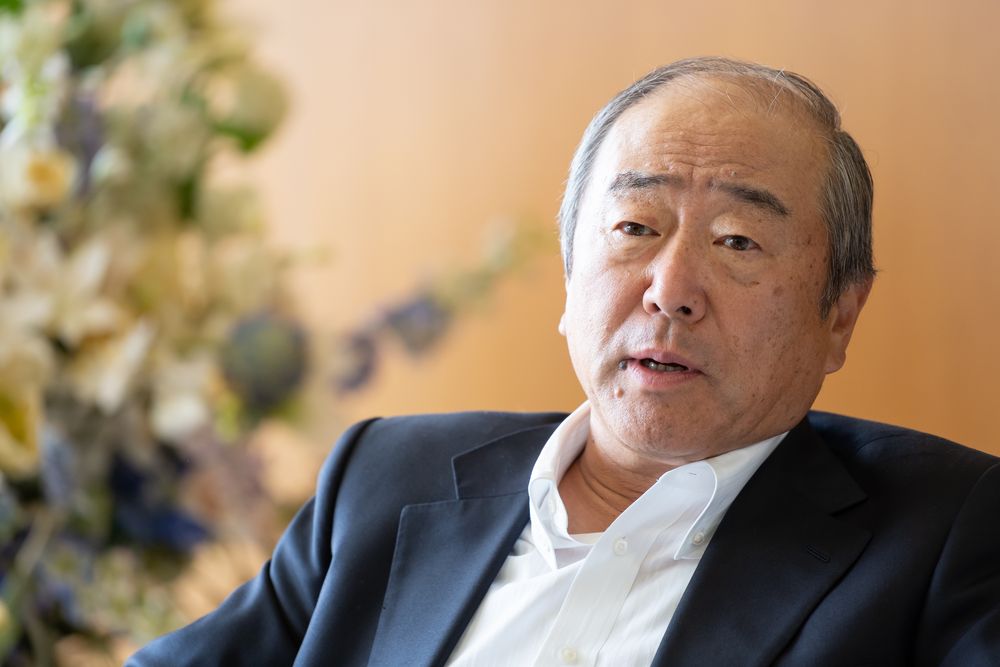
【インタビュー】「可搬性・貯蔵性に優れた石油は、エネルギー供給の“最後の砦”」-月岡 隆氏(前編)
最新記事
-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用
-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?
-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革
-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目
-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!
-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)
-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)
-

ガソリンの暫定税率(当分の間税率)の廃止でガソリン代はどうなるの?よくいただく質問に、資源エネルギー庁がお答えします!




