【インタビュー】「AIやIoTの活用で省エネは加速する」―中上英俊 氏(前編)

エネルギー問題や地球環境問題を専門とし、総合資源エネルギー調査会省エネルギー小委員会(以下、省エネルギー小委員会)の委員長を務めている中上英俊氏。2018年5月におこなわれた省エネ法改正に関する国会の審議では、社会の実態に合わせた省エネの必要性について意見を述べられました。オイルショック以来、日本が取り組む省エネ政策に長きにわたって関わってきた中上氏へのインタビューを、前後編の2回に分けてお届けします。
「エネルギーを合理的に使う」という省エネの原点を見失ってはいけない
―2016年からの審議を経て省エネルギー小委員会がまとめた提言を受け、2018年6月に省エネ法が改正されました(「時代にあわせて変わっていく『省エネ法』」 参照)。長年にわたって関連委員会にたずさわり、省エネ政策を見てこられた立場として、現代における省エネの課題をどのようにとらえていますか?
中上 はじめに、「省エネ」の言葉の定義を明確にしておきましょう。「省エネ法」の正式名称「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」という表現がまさに的確で、エネルギーを「合理的に」使うということが省エネの原点です。ところが、人によって省エネの考え方には差異があり、中にはやみくもにエネルギー使用を制限しようとするあまり、「必要なエネルギーまでもセーブすべき」ととらえる意見もあるため、議論がかみ合わないことがあります。
しかし、必要なときにはエネルギーは使うべきです。ただ、使うのであれば合理的に効率よく使うべきという考え方に立つことが重要なのです。たとえば、昔はぜいたくとされていた冷房も、近年では猛暑・酷暑による熱中症から身を守るため、その使用が推奨されています。このような価値観の変化に省エネは柔軟に対応すべきなのです。
オイルショックを契機に省エネ法が制定された1979年当時と比べ、エネルギー消費量は増えています。その理由に対策の生ぬるさを挙げる見方もありますが、当時と比べ生活水準が格段に上がっているのですから、エネルギー消費が増えるのは当然のこと。増えること自体が悪いのではなく、使い方をいかに合理的にしていくかということを省エネのテーマにすべきなのです。

需要実態の把握を通じて省エネが可能な分野を探ることが重要
中上 以上を前提としたうえで、現代における省エネの課題は大きく2つあります。
1つめは、省エネを評価する際に必要な“ベースライン”が定まっていないこと。2030年のエネルギーのあり方を定めたエネルギーミックス(長期エネルギー需給見通し)では、2013年度を基準年として、2030年度のエネルギー需要を原油換算で5,030万kl程度削減すると示されています。5,030万klの内訳として、産業部門で1,042万kl、業務部門で1,227万kl、家庭部門1,160万kl、運輸部門1,607万klという数字も示されています。これは各部門における省エネ対策として明確な算定根拠がある施策の積み上げでしかありません。個別のエネルギー需要の実態が把握できていないため、どこを合理化すればどれだけ効率的に総合的な省エネが図れるか判断ができないのです。
具体的な例でお話ししましょう。たとえば、「最新の冷蔵庫は10年前の製品と比べ、消費電力が半分だ」というように、ピンポイントでのエネルギー使用量の比較は可能です。ですが、日本国内で使用されている冷蔵庫の製造年と台数の内訳を把握できていないため、最新の冷蔵庫を何台導入したらどれだけエネルギー使用量が減るのかを計算することができません。つまり、省エネを考える場合には、「仮に、国内にある10年前の冷蔵庫100万台を最新の冷蔵庫に入れ替えた場合」といったように、限定した条件をつけた場合の数字になるわけですが、実際には国内に10年前の冷蔵庫が何台普及しているかがわかっていないので、それが実現することができるかどうかもわからない、という状況なのです。
私は、より緻密な省エネ施策を打つためにも需要実態調査が必要だと長年主張してきましたが、未だ実現していません。全国の家庭を対象にエネルギー消費量を調査するには、現状では2~3年の歳月と数億円にのぼる費用がかかるため、難しいのが現状なのです。

―2つめは、どういった課題でしょうか?
中上 日本では、かれこれ40年にわたり省エネ対策がおこなわれてきました。オイルショック当時はムダを省く余地がたくさん残っていましたが、もう手を尽くしているため、1つの施策で大幅なエネルギー削減が期待できるような分野はありません。「砂取りゲーム」をイメージしていただくとわかりやすいでしょう。砂山に棒を立て、棒を倒さないように砂を取っていくゲームでは、最初はたくさんの砂を一気に取れますが、そのうちいろいろな方向から少しずつ砂を取るしかなくなってきます。現代の日本の省エネはそういうステージに入っているのです。
今後省エネを進めるには、こまかく丁寧にまだ削減の余地が残る分野を見つけ出して深掘りし、1%の削減ができる施策を10個積み上げて10%削減を達成する、というやり方をしていかなければなりません。1つめの課題とも重なりますが、深掘りできる部分を精査するためにも実態調査が必要です。
私が現時点で削減の余地がありそうだとみているのは、待機電力が大きい家電や情報機器です。たとえば、一般の家庭にもある衛星放送チューナーのセットトップボックスの待機電力は、10~12W程度消費されていると想定されます。この他にもWi-Fiルーターやモデム等の待機電力は無視できないオーダーに達しているのではないでしょうか。これらの待機電力を削減することができれば大幅な省エネが実現するのではないかと考えられます。また、中小ビルに普及しているマルチパッケージ型HP空調機の待機電力は10Wで、親機のコンプレッサーにいたっては100Wあります。エアコンを使わない春秋シーズンの待機電力を合理化できれば、全国で約50億kWhの省エネが可能になる計算です。
また、産業用機械についても注目しています。産業部門について、今回の省エネ法改正や新たに創設した税制措置では、大規模投資をともなう省エネ設備の導入促進を対策の1つとして盛り込んでいますが、現状の設備についても、アイドリングを制御するだけで数%単位での待機電力の削減が見込めます。このように、こまかい点に着目していくと、まだまだ省エネの余地はあるのです。

パーソナライズされた情報が人々の意識や行動を変える
―そのほかに、課題を解決していくための糸口として期待しているものはありますか?
中上 実は、需要実態調査が簡単に、そしてコストをかけずに可能になる時代がもう目の前まで来ています。AIやIoTの活用です。スマートメーターの普及などによって、今後は膨大なデータが労力をかけずに入手できるようになります。これを分析することでより緻密な施策を打つことができるようになり、省エネも一段と加速するでしょう。また、個々人に対して、ライフスタイルや家族構成などに応じてパーソナライズした省エネ指導をおこなえるようにもなります。AIやIoTによってガラリと様相が変わるであろう次世代の省エネに非常に期待しています。
パーソナライズされた情報は、一般的な情報と比べてどれだけ威力を発揮するでしょうか。飲食店に向けた省エネ施策を想像してみると非常にわかりやすいでしょう。たとえば、中華料理店とお寿司屋さんでは使う調理器具や熱源が異なりますから、本来はそれぞれに見合った省エネ施策があるわけです。それを「飲食店の省エネ対策」と情報をひとくくりにして発信しても、自分ごととして受け入れられないのは当然です。
パーソナライズされた情報の効果は、当社が2015年から2016年にかけておこなった調査でも確認されています。北陸電力管内にて、各家庭に配付する請求書に、近隣のよく似たご家庭の電力消費量の平均値や、電力消費量がもっとも少ない世帯の事例、節電のヒントを載せたところ、短期間で1~2%の削減効果がありました。1~2%という数字は少ないように見えるかもしれませんが、4割程度の世帯が一斉に冷蔵庫を最新式に買い替えたのに相当する効果です。パーソナライズされた情報が人を動かす力は大きいのです。
―AIやIoTが普及するとより情報のパーソナライズが進み、省エネもこれまでとは別次元に進むわけですね。
後半では、eコマースの普及やテレワークの導入といったITの普及によるライフスタイルの変化とエネルギー消費との関係や、省エネを世の中で加速させる意外なきっかけについてお話しがおよびました。
1945年、岡山県生まれ。横浜国立大学工学部建築学科卒業、横浜国立大学大学院工学研究科建築学専攻修士課程終了、東京大学大学院工学系研究科建築学専門課程博士課程所定の単位取得退学、東京大学博士(工学)。1973年にエネルギー関連の調査研究やコンサルティングをおこなう株式会社住環境計画研究所を創設。2013年より同社代表取締役会長。エネルギー・地球環境問題、地域問題を専門とし、日本学術会議連携会員、早稲田大学招聘研究員、東京工業大学大学院非常勤講師、経済産業省総合資源エネルギー調査会省エネルギー小委員会委員長、環境省中央環境審議会専門委員、国土交通省社会資本整備審議会臨時委員ほかを務める。
お問合せ先
長官官房 総務課 調査広報室
※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。
あなたにオススメの記事
-

【インタビュー】「まだまだ残っている、省エネのポテンシャル」―奥村 和夫氏(後編)
-

【インタビュー】「省エネは、快適な暮らしと合理的な生産方法を実現する手段」―奥村 和夫氏(前編)
-

【インタビュー】「先進技術で石炭のゼロエミッション化を目指し、次世代のエネルギーに」−北村 雅良氏(後編)
-

【インタビュー】「安定的で安価な石炭は今も重要なエネルギー源、技術革新でよりクリーンに」−北村 雅良氏(前編)
-

【インタビュー】「日本のノウハウを生かし、LNGの国際市場をリードする存在に」-広瀬 道明氏(後編)
-

【インタビュー】「LNGは環境性・供給安定性・経済合理性のバランスのとれたエネルギー」-広瀬 道明氏(前編)
-

【インタビュー】「国際競争力を高めつつ、安定供給を維持するために 」-月岡 隆氏(後編)
-
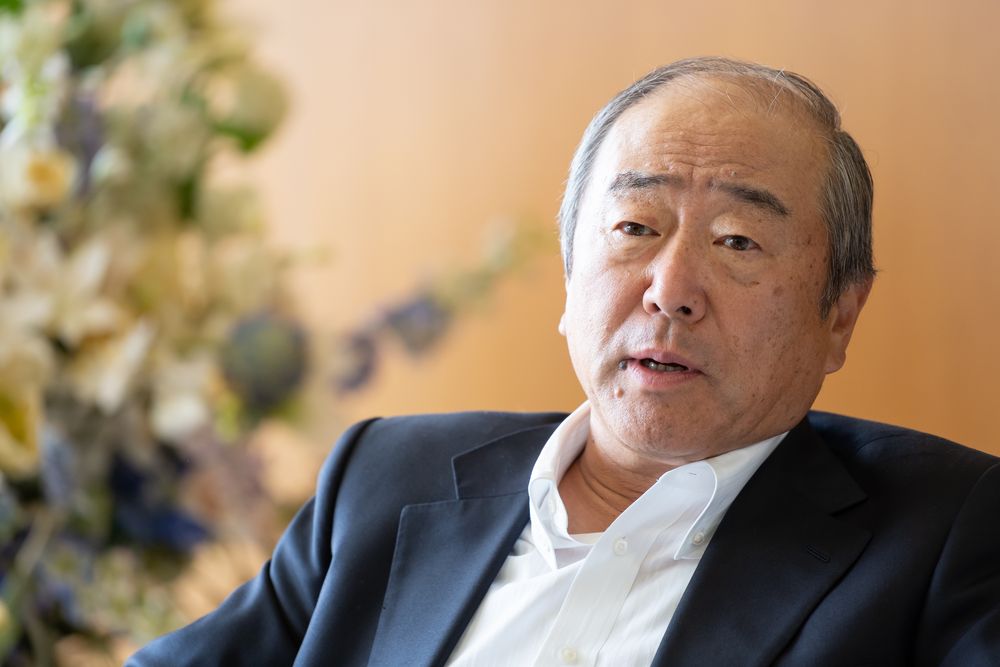
【インタビュー】「可搬性・貯蔵性に優れた石油は、エネルギー供給の“最後の砦”」-月岡 隆氏(前編)
最新記事
-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用
-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?
-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革
-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目
-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!
-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)
-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)
-

ガソリンの暫定税率(当分の間税率)の廃止でガソリン代はどうなるの?よくいただく質問に、資源エネルギー庁がお答えします!




