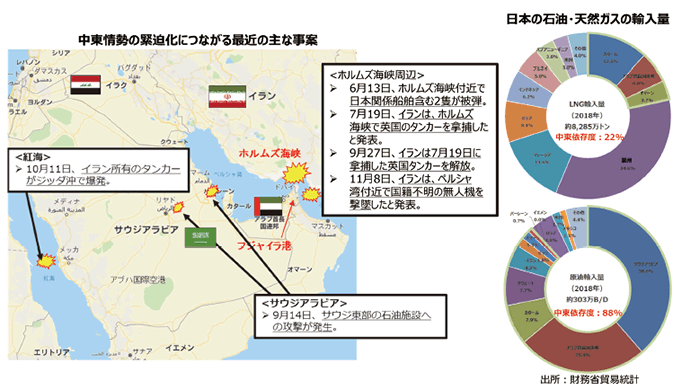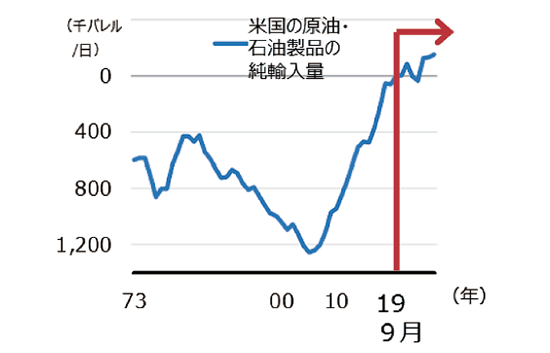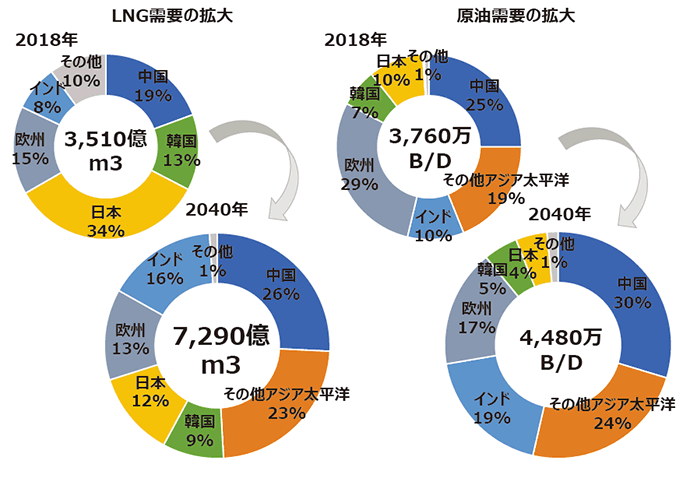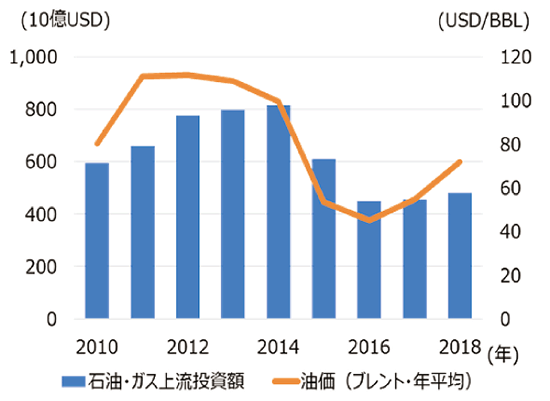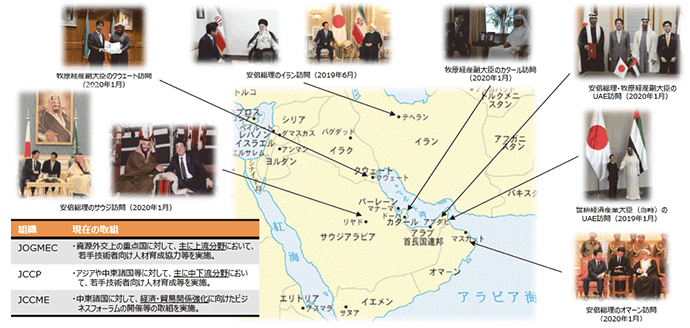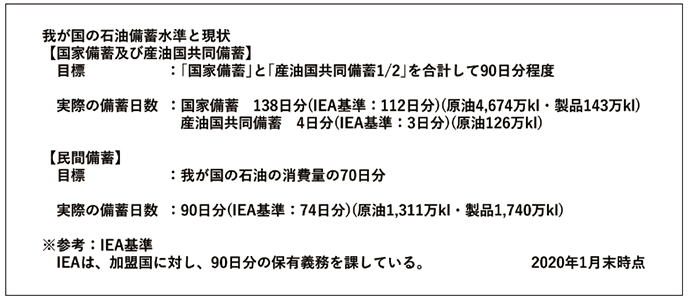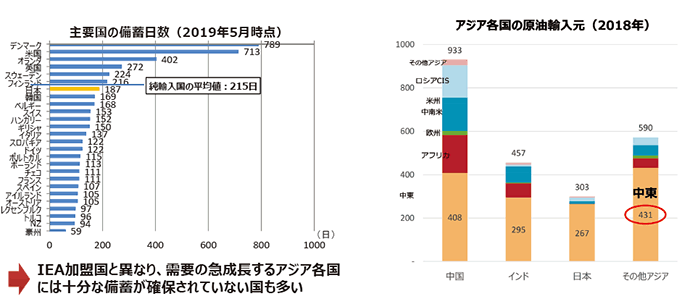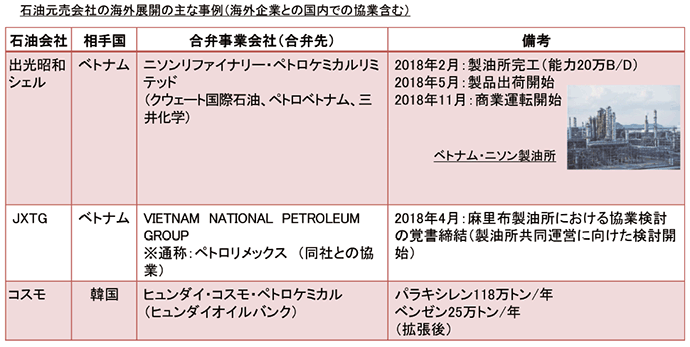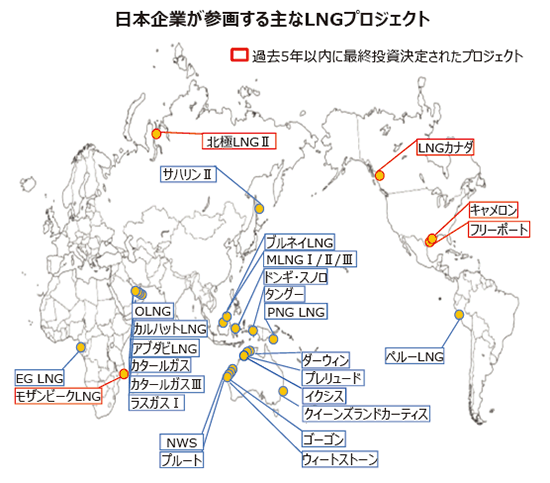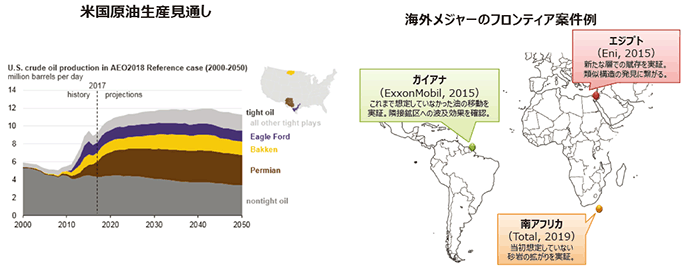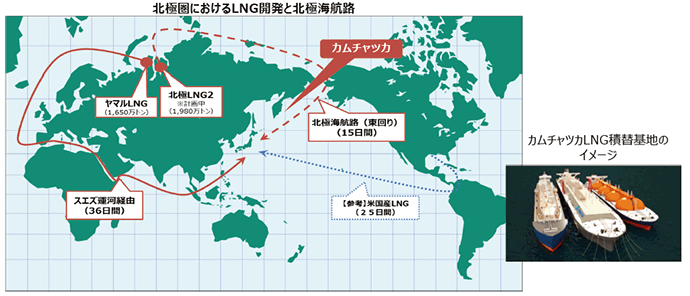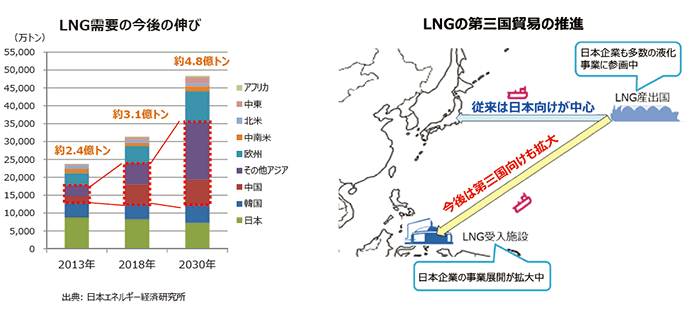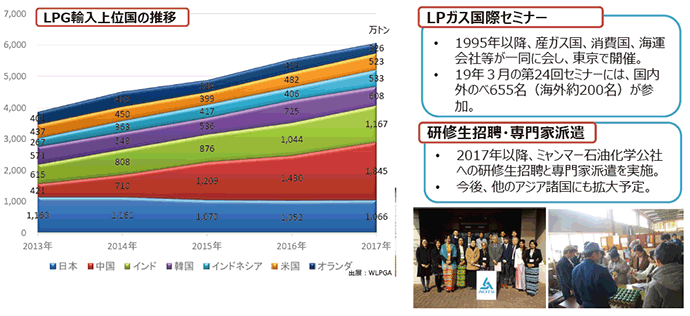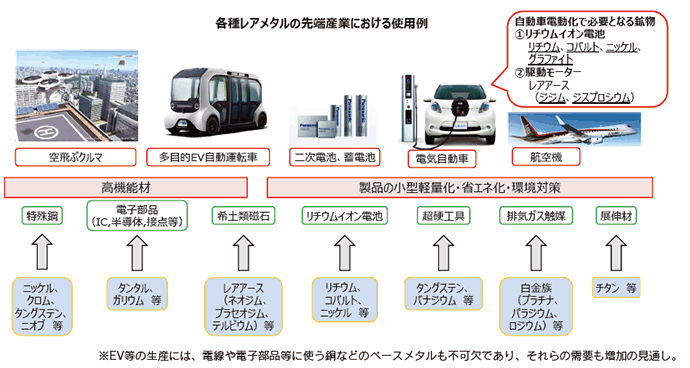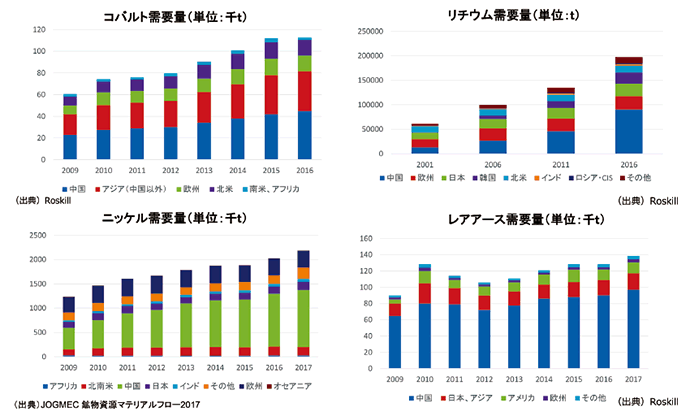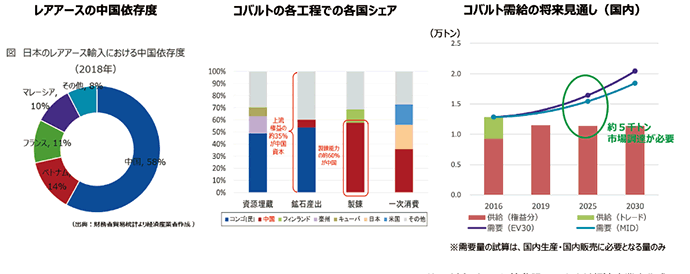第1節 災害・地政学リスクを踏まえた国際資源戦略
日本は一次エネルギーの9割を占める化石燃料を輸入に依存しています。日本の資源・燃料需要が長期的に減少する一方、アジアでの需要が増大するなど、世界の需給構造が変化する中でも、国際資源・燃料市場で存在感や購買力を維持し、日本のエネルギー安全保障を実現していくには、日本に閉じない「アジア大」の視点から、資源・燃料政策を展開していくことが必要です。
地球温暖化への関心が高まる中、国際機関の長期予測で化石燃料の見通しにバラつきが生じるなどエネルギーの長期的な将来像は不確実になっています。2014年以降、化石燃料への投資は小規模化・短期化の傾向もあります。一方で、2040年を見通しても、成長著しい新興国を始め世界にとって化石燃料が引き続き重要なエネルギー源であり、化石燃料の開発には巨額の長期投資が必要ですが、投資予見性が低い現状は、企業にとって判断が難しい状況でもあります。
こうした現状を踏まえ、アジアや産油国との共同備蓄、国際LNG市場の取引量拡大による流動性・柔軟性確保を通じたエネルギー安定供給の強化等、大きく変化する国際資源情勢をにらんだ資源戦略の強化が必要です。また、世界最高水準の高効率火力発電技術やカーボンリサイクル技術など、環境負荷の低い日本のエネルギー技術の国際展開による世界への貢献を進めることも重要です。
本節では、大きく変化する国際資源情勢の中で、日本の資源・燃料の安定供給を実現する方策について論じます。1
1.地政学リスクを踏まえた石油・天然ガス等のセキュリティ強化
(1)背景
二度にわたる石油ショックの経験から、石油に変わるエネルギーとして、原子力、天然ガス、石炭の導入が促進された結果、一次エネルギー国内供給に占める石油の割合は、1973年度の75.5%から2010年度には40.3%まで大幅に低下するなど、日本はリスクの分散を図ってきましたが、国内外の資源・燃料情勢が大きく変化する中、エネルギーの安定供給をどう確保していくかは、引き続き大きな課題です。
①国内のエネルギー需要の減少
日本の最終エネルギー消費は、2004年度をピークに減少を続けており、人口減少や高齢化等の社会構造の変化に伴い、運輸部門・家庭部門を中心に今後も減少する見通しです。2023年までの石油製品需要の見通しについても、2017年度から全体で約6.4%減少見込みであり、市場のさらなる縮小が見込まれます。
石油や天然ガスの国内需要の減少が続けば、国際資源・燃料市場における日本のシェアが低下し、ひいては購買力の低下にもつながりかねません。また災害時はもとより、平時における国民生活や企業の経済活動を支える国内燃料サプライチェーンを維持・強化するための再投資をどのように進めていけるのかが課題です。
②国際需給構造の変化と地政学リスクの高まり
世界の供給側での動きに着目すると、中東情勢の構造的な不安定さは、さらに増しています。2019年6月、ホルムズ海峡周辺のオマーン湾で、日本関係船舶を含む2隻のタンカーが攻撃を受ける事案や、同年9月にはサウジアラビア東部の2つの石油施設が攻撃を受ける事案が発生しました。
こうした地政学リスクの高まりは、原油の88%を中東に依存する日本にとって、エネルギー安全保障上の大きな課題と言えます。
従来は世界の石油・天然ガス等の供給の大半を中東の資源国が担っていましたが、近年、米国のシェールオイル・ガス開発やロシア・北極圏でのガス開発など、新たな資源供給源が出現したことにより、世界全体における中東からの原油輸出量の割合は1970年代後半の約60%から、足元では約40%まで低減しています。例えば2009年に中国と逆転するまで世界最大のエネルギー消費国で、多くの化石燃料を輸入していた米国は、シェール革命の進展により、2019年9月に月次統計上初めて原油・石油製品の純輸出国となり、2020年中にもエネルギー純輸出国に転じる可能性があるとの見通しが示されています。2
需要側について見てみましょう。世界の石油・天然ガス等の需要は引き続き拡大傾向であり、特に、LNGの需要は2040年までに倍増する見通しです。その内訳を見てみると、2009年に米国に代わって世界最大のエネルギー消費国となった中国や、同じく世界第3位のインドが、人口増加や経済成長等を背景として資源需要を急速に拡大し、エネルギー市場における存在感を日増しに高めていく見通しです。一方で、日本の相対的な市場シェアは縮小し、今後、国際市場における日本の地位は相対的に低下していくものと見られます。
これらの国の需要動向や政策動向は、国際マーケットにおける価格形成にも大きな影響を及ぼすようになってきています。
資源・燃料を取り巻く地経学的バランスが大きく変化し、国際資源・燃料市場での相対的な地位の低下が予想される日本にとって、石油・天然ガスなどの一次エネルギーを引き続き安定的に確保するためには、自国の市場シェア等に頼る従来の調達方法とは異なる取組が必要になってきます。
- 出典:
- 経済産業省「新・国際資源戦略の方向性」より抜粋
- 出典:
- EIA「February 2020 Monthly Energy Review」より経済産業省作成
- 出典:
- IEA「World Energy Outlook 2019」より経済産業省作成
③エネルギーの将来像の不確実性の高まり
地球温暖化への関心が高まる中、国際エネルギー機関(IEA)等の長期予測において、化石燃料の見通しについて、シナリオによって大きな差が生じるなど、エネルギーの長期的な将来像は不確実性を増しています。また、前述の国際需給構造の変化や地政学リスクの高まり等に応じ、エネルギー市場の不安定さが増しています。例えば、中国経済の先行き不透明感や北米シェールオイルの堅調な生産などにより、2014年以降、それまで高止まりしていた原油価格は急落しました。これに伴い、石油・天然ガスの上流開発投資は、縮小し、低迷しています。また、2020年3月には、OPECプラス会合における協調減産の見送りにより、再び原油価格は急落し、上流開発投資への影響が懸念されます。
他方で、2040年を見通しても成長著しい新興国を始め世界にとって、化石燃料は引き続き必要です。そして、化石燃料の開発には巨額の長期投資が必要です。世界のエネルギー需要を満たすためには、今後30年で約3,000兆円もの燃料分野への投資が必要との試算もあります3。こうした中、投資の予見性が低い現状は、企業の投資判断を極めて難しいものにしています。エネルギーの将来像に関する不確実性を低減し、投資の予見可能性を高めることが必要です。
【第121-1-4】世界の一次エネルギー需要に占める化石燃料比率の見通し
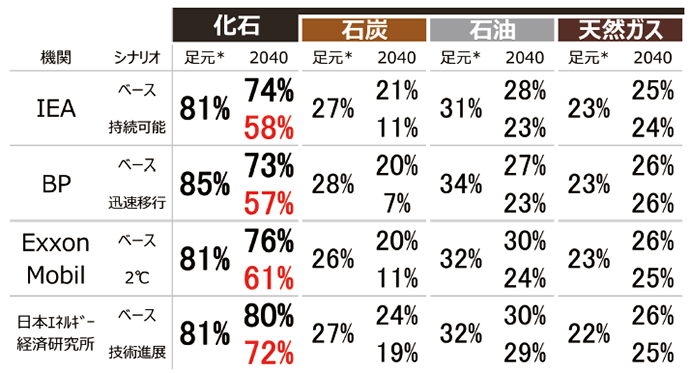
(注)IEAのみ2018年データであり、その他は2017年データ。
- 出典:
- 各国際機関等の長期予測資料から経済産業省作成
- 出典:
- IEA「World Energy Investment 2019」より経済産業省作成
(2)対応の方向性
①産油国との関係強化や備蓄政策、企業支援の強化
(ア)中東諸国との資源外交の強化
中東の資源国は、豊富な資源埋蔵量等を背景に、2018年時点で、世界における石油純輸出量の約40%を占めており、米国のシェールオイルの普及を加味しても、2040年時点で石油純輸出量の約35%は中東が占めると予測されています。日本においても、原油価格や輸送コストなどの経済性を考慮すると、引き続き相当程度の石油を中東から輸入せざるを得ない状況が続くと考えられます。したがって、今後とも、中東地域からの石油供給の安定性を高めていく必要があります。
日本は、これまで内閣総理大臣を筆頭に、積極的な資源外交を展開し、例えば、アラブ首長国連邦(UAE)での自主開発油田権益の確保等の成果を上げてきました。今後とも、中東地域の各資源国との間で、こうした取組を続けていきます。
- 出典:
- 経済産業省「新・国際資源戦略の方向性」より抜粋・一部修正
(イ)中東以外の資源国との関係強化
供給源の一層の多角化に向け、米国やロシアを始め、カザフスタン、アゼルバイジャン、アフリカ、中南米など、中東以外の産油国・地域との関係を強化していくことも重要です。また、今後は、上流開発にとどまらない幅広い分野での協力や、国営企業等との協業などにより、包括的かつ互恵的な関係の構築を進めることも重要です。
(ウ)日本国内の石油備蓄の充実
日本の石油備蓄は、(A)国が保有する「国家備蓄」、(B)「石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)」に基づき石油精製事業者などが保有する「民間備蓄」、(C)UAE及びサウジアラビアとの間で2009年以降開始された「産油国共同備蓄」の3つで構成されており、現在、国内消費量の200日分超(IEA基準;約190日分)に相当する量が確保されています。
昨今、中東地域においては、ドローンなどの新技術により低コストでの攻撃が可能になるなど、地政学的リスクが増大しており、石油の供給制約が長期にわたって発生する懸念や、これらが多発的・連続的に発生する蓋然性が高まっています。
こうした状況を踏まえれば、効率的な備蓄管理の下、現在の備蓄数量はおおむね維持しつつ、緊急事態が発生した場合においても、原油及び石油製品の安定供給の確保に向けて円滑に必要な対応を取ることができるような備えが重要です。そのため、石油備蓄の機動的かつ効果的な活用に向け、平時より、石油精製・元売会社との連携強化、必要に応じた油種の入れ替え、総合的・実践的なシミュレーションや訓練を行う等、官民が連携して体制を整えておくことが必要です。
- 出典:
- 経済産業省「新・国際資源戦略の方向性」より抜粋・一部修正
- 出典:
- 経済産業省「新・国際資源戦略の方向性」より抜粋
(エ)日本の石油備蓄を活用したアジアとの関係強化
成長著しいアジアでは、引き続き石油需要が急速に拡大していくと見込まれています。一方、アジアの国々には、日本と同じく原油の中東依存度が高い一方、緊急時に備えた十分な備蓄を有さない国も多く、中東情勢の変化により石油の供給途絶につながりかねないなどの脆弱性があることは否定できません。
アジアの国々は、今後、国際資源・燃料市場において、需給両面でその存在感を増していくと見込まれています。国内需要が縮む日本にとって、需要が拡大するアジアとの連携強化を進めることは、国際資源・燃料市場における将来の存在感の確保につながるものです。
石油備蓄の構築・運用に関する長年にわたる豊富な経験や専門知識、さらには原油、タンク等の備蓄資産を有する日本は、アジア地域におけるセキュリティ向上のハブとして貢献できます。アジアの国々との間で、緊急時の原油等の相互融通など、各国の事情に応じた備蓄協力を積極的に進めるほか、平時の石油供給の安定化に資する産油国共同備蓄の拡大等も進めていくことが必要です。
COLUMN
新型コロナウイルス感染拡大等の国際原油市場への影響と生産国・消費国の取組
ここでは、2020年1月以降の国際原油市場の動きと、産油国及び消費国の取組を振り返りながら、国際原油市場の安定化の重要性について考えてみます。
新型コロナウイルスの感染拡大とOPECプラスによる協調減産交渉決裂
2012年頃から、米国でのシェールオイルの生産が活発化したこともあり、2014年以降、原油価格は下落しました。そこで、OPEC加盟国とロシア等を含めた「OPECプラス」は、2017年より協調減産を実施してきました。
2020年1月から2月にかけて、新型コロナウイルス感染拡大による需要減少で原油価格が下落する中、3月上旬に協調減産の見直しの時期を迎えました。しかし、3月6日のOPECプラス閣僚会合では、各国の意見が鋭く対立し協調減産の交渉は決裂しました。さらに、その直後に一部産油国は大幅な増産を表明し、価格競争が激化する状況となりました。
新型コロナウイルスのさらなる感染拡大とOPECプラスによる協調減産再合意
3月中旬から新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による経済減速懸念が強まり、世界規模での大幅な原油の需要減少が指摘されるようになりました。3月下旬になり、原油価格の低迷が続き、世界の原油価格市場における主要な指標であるブレント原油の先物価格(以下、「ブレント原油価格」という。)は25ドル前後を推移する中、各産油国の首脳レベルでの減産に向けた調整も行われ、4月に入り、減産への期待が高まり、一時原油価格は1バレル10ドル程度上昇し、ブレント原油価格は34ドル台になりました。
4月10日には、国際原油・ガス市場の安定化及び世界経済の強化に向けた協力を促進するため、G20臨時エネルギー大臣会合がテレビ会議形式で開催され、梶山経済産業大臣も参加しました。同会合では、不安定な国際原油・ガス市場が実態経済に多大なる悪影響を与えていること、経済活動にとっての礎としてのエネルギー安全保障が重要であることなどを認識し、市場安定化、エネルギー安全保障強化の観点からG20として連携を強化していくことを確認しました。
その後、4月12日のOPECプラス閣僚会合において、5月及び6月に日量970万バレルの減産を実施することを含め、原油の大幅な減産に合意しました。
協調減産再合意後の原油価格の推移
しかしながら、4月中旬、原油需要が一層減少する中、原油価格は再び下落し、ブレント原油価格は一時20ドルを割りました。その後、欧米諸国による経済活動再開の動きなどが見られ、5月初旬には、ブレント原油価格は30ドルまで上昇しています。
また、米国の代表的な原油価格指標であるWT(Iウェスト・テキサス・インターミディエイト)の先物価格については、4月20日の終値がマイナス37.63ドルとなり、史上最安値を更新しました。これは、原油需要の減少に伴い、米国において、原油在庫が拡大し、貯蔵容量不足の懸念が広がる中、現物の原油を引取らなければならなくなる投資家による先物の売却が発生し、買い手も少なかったことにより生じたものです。なお、4月21日にはプラスの価格に戻っています。
安定した原油市場の重要性
さて、このように、原油価格が乱高下し、原油市場が不安定となっていることについて、どのように考えるべきでしょうか。原油価格が低いことは、日本のような原油消費国にとって、貿易収支を改善させるほか、燃料価格の低下につながるなどの良い面があります。他方、原油価格の急激な下落や上昇を繰り返す状況が続くと、石油や天然ガスに関係しているエネルギー企業の収益や産油国経済に悪影響を及ぼすほか、計画的なエネルギーインフラへの投資を困難にする可能性があり、石油やガスの安定供給に影響が出る可能性も否定できません。
新型コロナウイルスの影響により世界規模で経済が悪化している中では、経済回復のためには、エネルギーの安定供給が欠かせません。そのため、原油の生産国・消費国双方にとって、原油市場の安定が非常に重要です。生産国・消費国がこの認識を共有し、協力していくことが必要と考えられます。
【第121-1-9】2020年1月以降の原油価格の動き
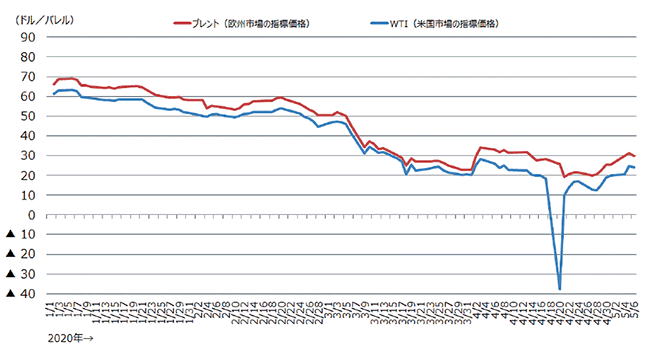
- 出典:
- 「Chicago Mercantile Exchange」ウェブサイトより経済産業省作成
- 出典:
- 経済産業省「新・国際資源戦略の方向性」より抜粋
(オ)石油精製・元売会社のアジア地域への展開
今後、国内の石油需要が減少していく中でも、引き続き石油を安定的に供給できる基盤を維持・確保していくためには、石油精製・元売産業の基盤を維持することが不可欠です。このため、石油精製・元売各社が、国内製油所の競争力強化に加え、アジア等の拡大する海外市場において石油精製・販売事業といったビジネスを拡大し、ネットワークを構築していくことが有効です。
このため、政府としても、石油精製・元売会社の海外展開について、資源外交等の活用や海外の情報収集・提供等により、引き続き支援をしていくことが必要です。
②液化天然ガス(LNG)に関する資源外交の強化
(ア)調達先の多角化によるLNG安定供給の実現
LNGは、発電に用いた場合、石炭や石油に比べ発電電力量あたりの温室効果ガス排出量が半分ほどで済むクリーンなエネルギーとして、今後もその役割と需要が拡大していく見込みです。一方、液化して輸入したLNGはマイナス162度以下に保ち続けなければならないため、備蓄に不向きです。このため、調達先の多角化や、国際LNG市場の拡大を図ることによって、必要な時に、必要な量を入手できる環境を実現することが重要です。
現在、世界のLNG供給の半分以上を中東と豪州が担っていますが、2040年には、シェール革命が進む米国、北極圏に潜在的な資源を有するロシア、新たな探鉱概念に基づき油ガス田が発見されている中南米・アフリカなどが、LNGの供給国としてその存在感を増していく見通しです。こうした国々と連携を深めることは、調達先の多角化と、LNGの安定供給につながるものです。
こうした国々のLNG供給におけるビジネスモデルの変化等を踏まえ、従来、上流投資に限定されていた石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)の単独権利取得業務の対象を液化事業に拡大していく等、業務範囲を拡充していくことで、世界の資源開発に幅広く日本企業が参画できる環境づくりを進めることが必要です。
- 出典:
- 経済産業省「新・国際資源戦略の方向性」より抜粋
- 出典:
- 経済産業省「新・国際資源戦略の方向性」より抜粋
- 出典:
- 経済産業省「新・国際資源戦略の方向性」より抜粋
(イ)柔軟な国際LNG市場の形成と拡大するアジア需要の取り込み
(A)ファイナンスに関する取組
国際LNG市場における日本の影響力を維持するためには、アジア全体で日本が関与するLNG取引量を増加させ、厚みのある国際LNG市場を形成することが重要です。
こうした観点から、従来はLNGが日本に輸入されることに着目して日本企業の参画を支援してきましたが、今後は、LNGの生産から受入までバリューチェーン全体を視野に入れ、第三国向けも含めて日本企業がLNGをオフテイク・コントロールすることに注目し、第三国向けに供給される「外・外取引」についても、日本企業の関与を後押しする方向にLNG政策を転換し、必要な取組を進めていきます。
そのため、2030年度に日本企業の「外・外取引」を含むLNG取扱量が1億トンとなることを目指す、との目標を設定しました。また、JOGMEC出資・債務保証への受入基地事業の追加を通じて、JOGMECによるリスクマネー供給を中心としたファイナンス支援強化を図ります。
(B)人材育成に関する取組
国際LNG市場の拡大は、近年、急速に進展しており、LNG受入基地事業の立上げに加え、オペレーションに関する技術等を有するLNG事業を担う人材の育成が重要な課題です。こうした課題に対し、日本は、国際LNG市場拡大への関与を確保すべく、具体的には、「LNG人材研修実施団体協議会」の開催等を通じて、政府を中心に関係機関と有機的に連携しつつ、人材育成等の取組を進めていきます。
- 出典:
- 経済産業省「新・国際資源戦略の方向性」より抜粋
【第121-1-15】柔軟な国際LNG市場の形成と拡大するアジア需要の取り込み(人材育成)
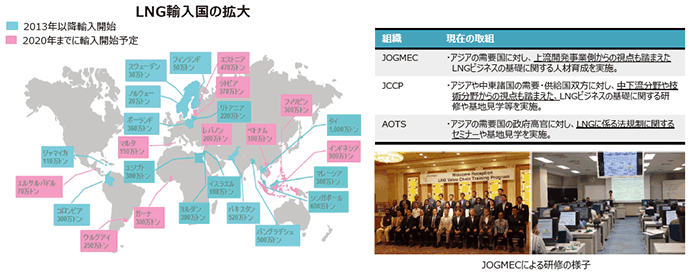
【第121-1-15】柔軟な国際LNG市場の形成と拡大するアジア需要の取り込み(人材育成)(ppt/pptx形式:257KB)
- 出典:
- (左)⽇本エネルギー経済研究所
(右)経済産業省「新・国際資源戦略の方向性」より抜粋
③液化石油ガス(LPG)の市場拡大による調達力の強化
LPGは、常温でも圧縮することで液化でき、容器に充填したガスを各戸に届ける「分散型」供給のため可搬性に優れるなど、平時のみならず災害時にも有効な燃料です。世界のLPG海上輸送量のうち、4分の1を日本企業が扱っており、これは世界最大規模です。こうした市場シェアの高さを活かした購買力をさらに強化するために、取扱量の増加につながり得る国際セミナーの開催や研修生の招聘・専門家派遣を実施し、我が国の優れた技術による機器や保安システムの国際展開も推進することが有効です。
- 出典:
- 経済産業省「新・国際資源戦略の方向性」より抜粋
COLUMN
アジアにおけるエネルギーアクセスの重要性
一般財団法人日本エネルギー経済研究所の報告書によれば、世界の最終エネルギー需要は2050年までに1.3倍に拡大し、他方で先進国の需要は減少に転じるとされています。また、新興国では、1人当たりのエネルギー消費量が2050年でも先進国に比べ半分以下に留まる一方、電力需要は増加し続け、最終エネルギー需要に占める電化率は大きく上昇するとされています。
また、APECの報告書によれば、化石燃料に由来する電源構成比率は2016年の69%から、2050年に57%と、長期的に低減するとされています。ただし、経済成長を考慮すると電力需要そのものが増加するため、化石燃料に由来する発電量は、2016年の10.9兆kWhから、2050年時点で13.0兆kWhに増加するとされています。
【第121-1-17】世界のエネルギー消費量の長期予測
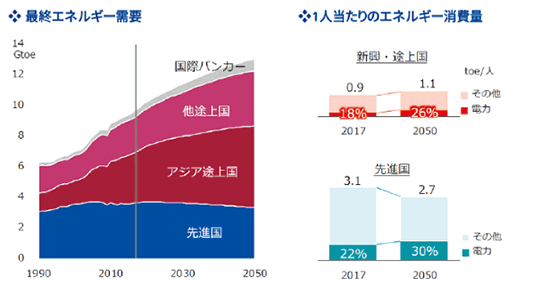
- 出典:
- (一財)日本エネルギー経済研究所「IEEJ Outlook 2020」より
【第121-1-18】APEC加盟国・地域の電源構成と化石比率の推移予測
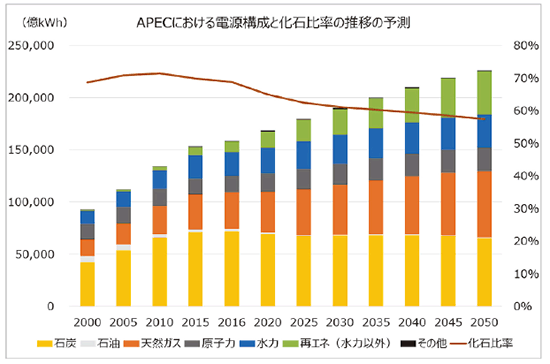
- 出典:
- APEC「Energy Demand and Supply Outlook 2019」より経済産業省作成
2.産業競争力の要となるレアメタル等の鉱物資源のセキュリティ強化
(1)背景
①先端産業において重要性を増す多様なレアメタル
レアメタルには34種類の鉱種が存在しており、物理的・化学的特性や市場規模・価格・主要生産国等も鉱種によって様々であるため、鉱種に合わせた資源確保が求められます。
また、レアメタルは、EVや蓄電池、航空機等の先端産業において、製品の高機能化を実現する上で重要な電池・モーター・半導体等の部品の生産に必要不可欠なものとなっています。
今後、欧米、中国や新興国との間で資源獲得競争の激化が見込まれ、安定供給の確保が一層重要な課題となります。例えば、コバルトの需要量を見てみますと、北米と欧州、中国の需要量はそれぞれ世界全体の需要量の約25%、約35%を占めています。
※EV等の生産には、電線や電子部品等に使う銅などのベースメタルも不可欠であり、それらの需要も増加の見通し。
- 出典:
- 経済産業省「新・国際資源戦略の方向性」より抜粋
- 出典:
- Roskill・JOCMEC参照データより経済産業省作成
- 出典:
- 財務省・Wood Mackenzie等参照データより経済産業省作成
②寡占化の進展と需給ギャップの懸念
我が国の産業活動に重要な一部のレアメタル等については、EVや再エネ機器等の普及、脱炭素化社会の実現に伴って今後も需要が増える見通しです。
例えば、コバルトについては、将来的に約5,000トンの需給ギャップが生じる可能性が指摘されています。もし我が国の鉱山開発企業が現在権益を持つ鉱山からのコバルト供給量が現状のまま変わらない場合、世界的な需給逼迫の状況下で市場調達等を図っていかねばならなくなり、その確保が極めて困難になるとの懸念があります。
しかし、コバルト鉱石生産の約6割はコンゴ民主主義共和国に偏在していることに加え、中流の製錬工程については中国が製錬能力の約6割を占めるなど、寡占化が進展しています。他鉱種でも、タングステン鉱石は9割以上、蛍石鉱石は6割以上が中国で生産されており、日本もその大半を中国から輸入している状況です。
また、2019年には米国の貿易制限的措置への対抗措置として、中国がレアアース輸出制限等を検討する動きを見せたこともあります4。今後EV等の普及で磁石用途等のレアアース需要が大きく伸びることが見込まれる一方で、未だ輸入の約6割を中国に依存しているリスクが改めて顕在化しています。
さらに、銅についても、最大の地金生産国である中国が質的・量的に生産能力を増強させている状況に加え、日本への鉱石の最大供給国であり、これまでカントリーリスクが低いとされてきたチリでさえ政治的な混乱が発生している状況です。レアメタルに限らずベースメタルについても安定供給へのリスクは高まっています。過去に発生したレアアースショック等の経験も踏まえ、現在のような特定国による寡占化状況が日本のサプライチェーンに与えうる影響を踏まえた対応策を講じることが必要です。
(2)対応の方向性
我が国として、ベースメタル、レアメタルなど各鉱種を取り巻く状況に応じた戦略的な資源確保策を講じることが必要であるため、資源の偏在性、カントリーリスク、需要の見通し等の観点から鉱種ごとのリスクを定量的に把握して類型化するとともに、それぞれの特性を踏まえて重点を置くべき政策ツール(上流権益確保の支援、適確な備蓄、リサイクル推進等)等を整理し、戦略的な資源確保策を推進することが必要です。
また、JOGMECのリスクマネー供給機能の強化を通じた供給源多角化の促進や、レアメタル備蓄制度の抜本的な見直し等によるセキュリティ強化、鉱山開発や製錬、製品製造等、サプライチェーンの各段階に関係する各国との環境面での技術支援や雇用創出への貢献を含めた国際協力の強化等に取り組みます。
- 1
- 本節は、「総合エネルギー調査会 資源・燃料分科会 報告書」(2019年7月)及び「新国際資源戦略」(2020年3月)の内容を踏まえたものとなっている。
- 2
- 米国エネルギー省情報局「Annual Energy Outlook 2019」
- 3
- (一財)日本エネルギー経済研究所「IEEJ Outlook 2019」
- 4
- 中国新華社通信の2019年6月4日付報道によると、国家発展改革委員会がレアアース専門家との会合を開催し、輸出に至る生産から加工までの全工程をさかのぼって審査するシステムを設けて輸出管理を強化すべきだと専門家が提言し、国家発展改革委員会は、提言を盛り込んだ措置を早期に打ち出す方針を示したとされています。