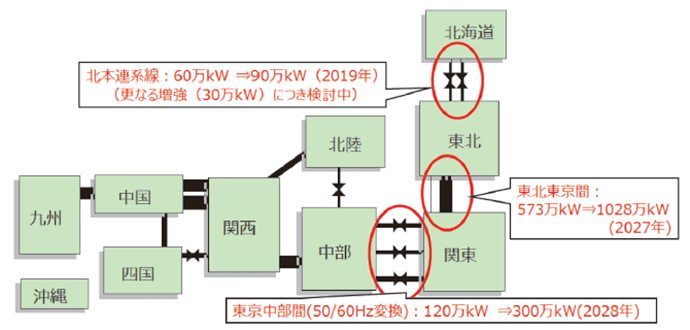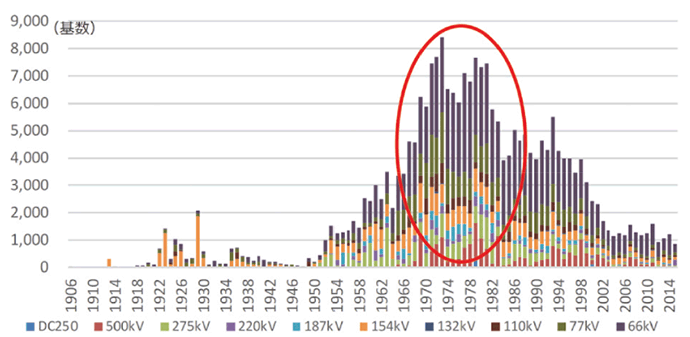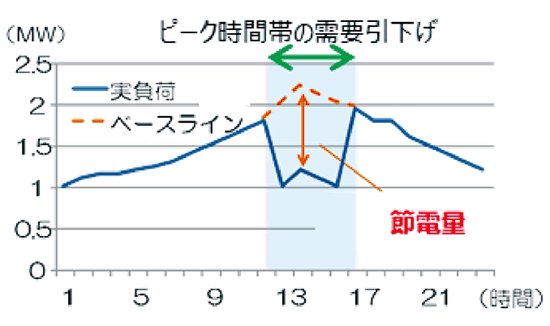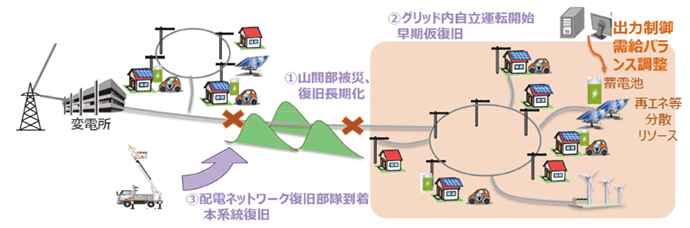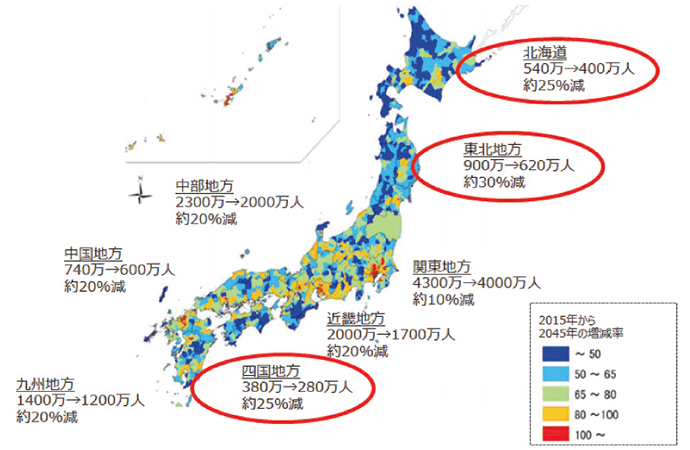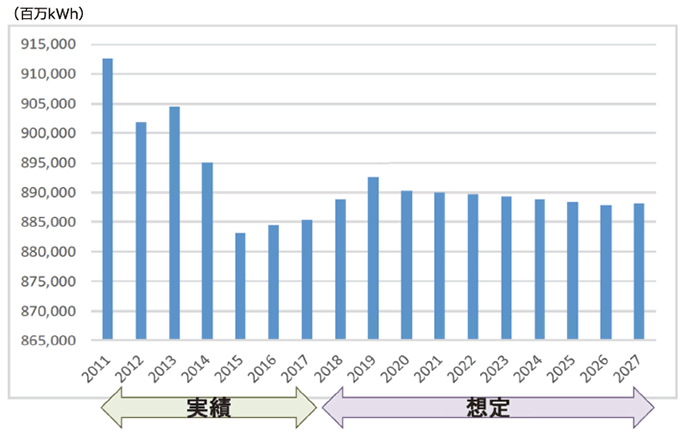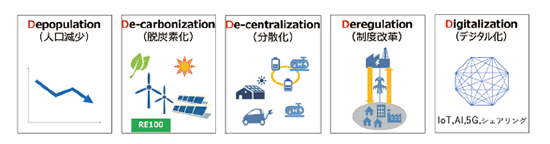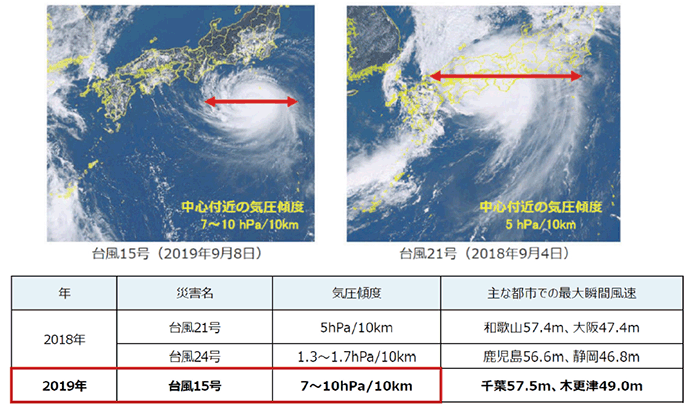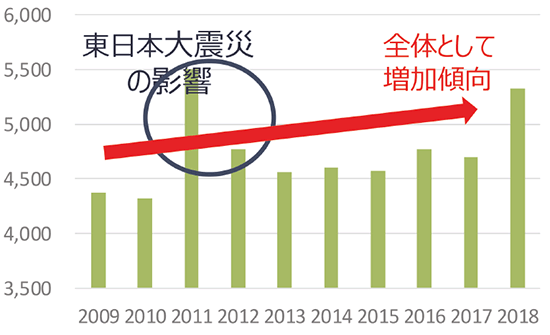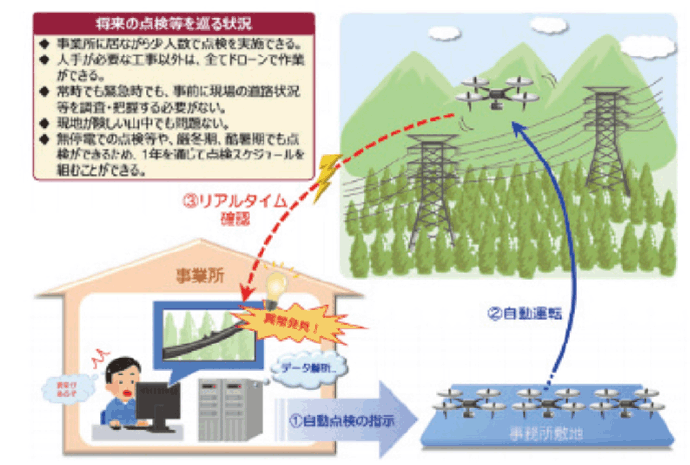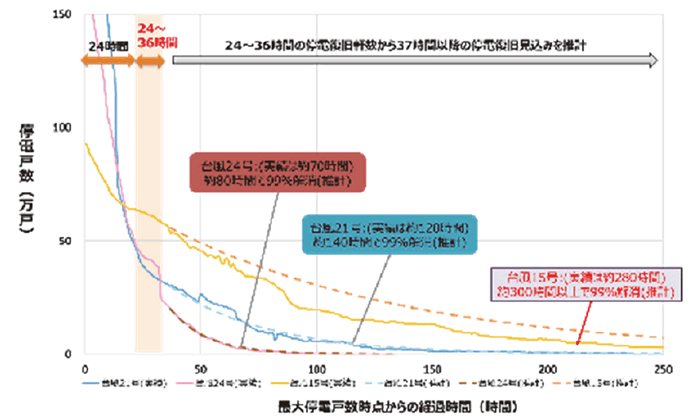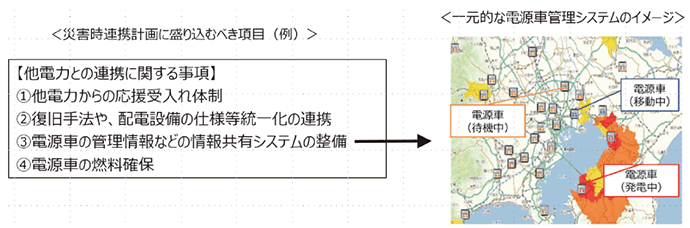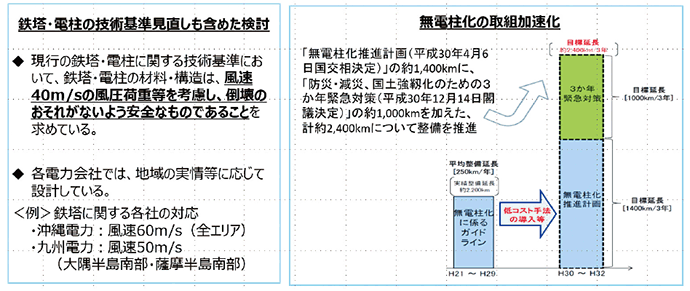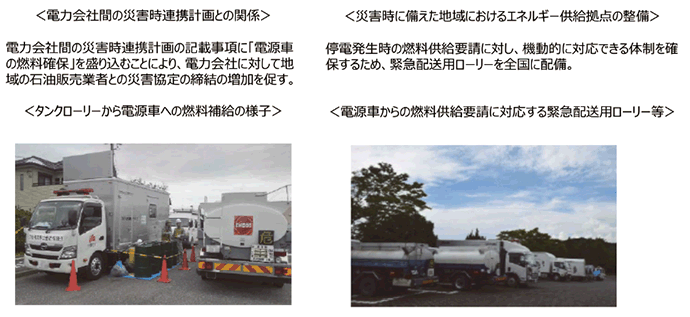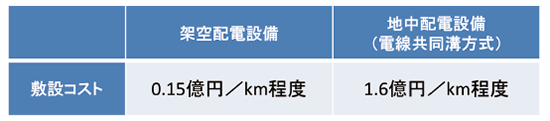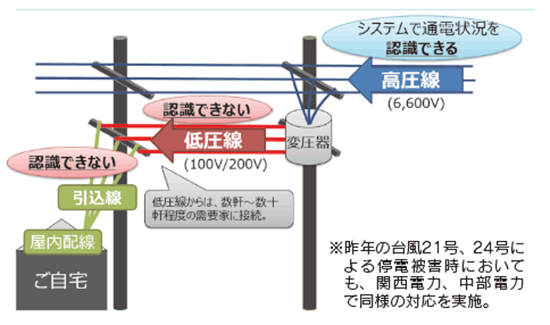第2節 持続可能な電力システム構築
総合資源エネルギー調査会の各分科会・小委員会・WG等では、2018年の北海道胆振東部地震による北海道大規模停電(ブラックアウト)や、2019年の台風15号、19号等の自然災害の教訓も踏まえながら、電力の安定供給に向けた強靱性(レジリエンス)の向上、持続可能な電力システムの構築、さらに再生可能エネルギー(再エネ)の主力電源化のために必要となる具体的な施策の検討が重ねられてきました。
本節では、検討の背景となる事実関係やデータに触れながら、各分科会・小委員会・WG等の議論を概観することで、持続可能な電力システム構築に向けた議論の流れと全体像を紹介します。
1. 脱炭素化と電力レジリエンスの向上への対応
(1)「 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」における議論
パリ協定締結を契機とした地球温暖化対策のさらなる深化の必要性も背景に、2018年7月に閣議決定された第5次エネルギー基本計画において、エネルギー転換に向けたあらゆる選択肢を追求し、再生可能エネルギーを「主力電源化」することとされました。
エネルギー基本計画の決定に先立ち、2017年12月に設置された「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」では、特に再生可能エネルギーの大量導入の実現に向けた課題である「系統制約」を克服するため、「既存系統の最大限の活用」を中心とした対策が議論されてきました。系統制約が課題となった北海道胆振東部地震を始め、一連の自然災害で、再エネの大量導入を図りながら、電力インフラのレジリエンスを高めることで、持続的な安定供給体制を構築していくことの重要性について改めて認識される契機となりました。
(2)「電力レジリエンスワーキンググループ」における議論
2018年9月の北海道胆振東部地震では、日本初の大規模停電(ブラックアウト)が生じるに至り、電力インフラのレジリエンス(強靱性)向上の重要性、電力の安定供給の重要性が改めて認識されました。経済産業省では2018年10月に産業構造審議会と総合資源エネルギー調査会が合同で「電力レジリエンスワーキンググループ」(以下、「レジリエンスWG」という。)を設置し、北海道胆振東部地震について4回の検証を行い、2018年11月に「中間取りまとめ」を公表しました。
この中で、①再発防止策として北本連系線の着実な増強とさらなる強化(60万kWから90万kW)等、②緊急対策として自発的な他電力会社や自治体との連携による初動の迅速化や復旧作業の円滑化等、③中期対策として、地域間連系線の強化や電力供給力を確保するための仕組みの検討、ブラックアウト発生リスクの定期的確認、災害に強い再エネの導入促進、火力発電設備の耐震性確保の技術基準明確化といった防災対策、さらに電力会社間や関係行政機関との情報共有の在り方や、送配電設備等の仕様の共通化、災害対応にかかる費用回収スキームの検討などから成る施策の方向性等がまとめられました。特に、中期対策については、災害に強い再エネの導入促進や費用負担、地域間連系線の在り方などについて即座に検討に着手し、スピード感を持って検討を進め、2019年春を目途に一定の結論を得る方針が示されました。
- 出典:
- 経済産業省「電力システムのレジリエンス強化に向けた背景」より抜粋・加工
【第122-1-2】北海道大規模停電を踏まえた再発防止策、緊急対策、中期対策の概要
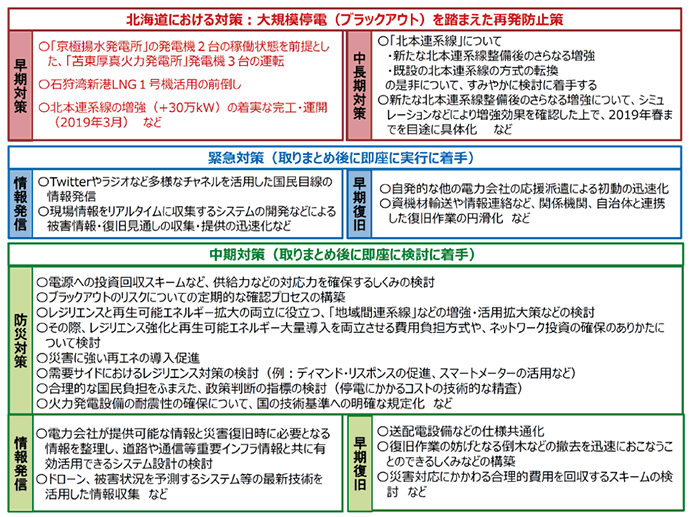
- 出典:
- 経済産業省「電力レジリエンスワーキンググループ中間取りまとめ」より抜粋
(3)「脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会」における議論
①議論の概要
レジリエンスWGで示された方向性を受けて、電力政策を取り巻く環境変化への対応と脱炭素化の実現につなげていくことを目的に、電力インフラのレジリエンス向上と持続的な安定供給体制を構築していくための具体的な方策を検討する場として、2019年2月に「脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会」(以下、「電力レジリエンス小委員会」という。)が総合資源エネルギー調査会に設置されました。
電力レジリエンス小委員会では、AIやIoT等のデジタル技術の進展により、電力コストのさらなる抑制等の実現可能性が出てきた一方で、人口需要減等による電力需要見通しの不透明化等によって、投資の回収予見性は低下しており、電力インフラに対する事業者の投資意欲の減退が深刻化しつつあるという課題も指摘されました。
電力レジリエンス小委員会では、2019年8月に「中間整理」を取りまとめました。この中で、電力政策として、(a)再エネ政策のパラダイムシフト、(b)過少投資問題への対応、(c)分散型エネルギーの推進、またネットワーク政策として、(d)ネットワークの広域化・強靱化ニーズの拡大を踏まえたネットワーク政策の再構築、(e)次世代ネットワークへの転換に向けた託送制度改革という、5つの方向性が打ち出されました。
以下では、電力レジリエンス小委員会の議論を詳しく紹介していきます。
【第122-1-3】持続的な電源・ネットワーク投資による3Eの高度化
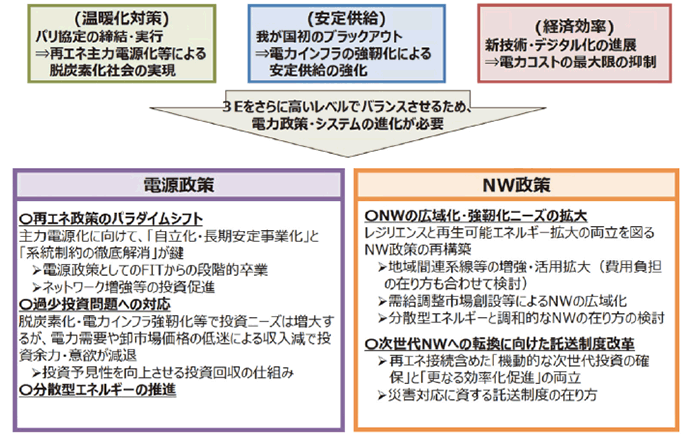
- 出典:
- 経済産業省「総合エネルギー調査会 基本政策分科会(第28回)」より抜粋
②電力ネットワークを取り巻く5つの構造変化
(ア)再エネの主力電源化のための系統増強の必要性
第5次エネルギー基本計画では再エネの「主力電源化」の方針が打ち出されました。天候の影響で発電量が大きく上下する再エネを電力ネットワークに組み込むには、円滑な系統接続を実現するための系統増強が必要になります。再エネのポテンシャルが地域ごとに偏在していることに留意しつつ、検討を進めていくことが必要との考え方が示されました。
(イ)電力インフラのレジリエンス向上の必要性
2018年9月の北海道胆振東部地震によるブラックアウト等、災害の教訓を踏まえたレジリエンス強化が重要との認識の下、ブラックアウトの防止や、停電からの早期復旧のため地域間連系線の意義が電力レジリエンス小委員会でも改めて確認されるとともに、円滑な復旧のため、災害時における事業者間の役割分担の明確化も必要との考え方が示されました。
(ウ)既存の送配電設備の更新投資の必要性
既存の送電線設備の投資のピークは1970年代であり、設備の老朽化が進展しています。将来の電力安定供給を維持するために、計画的に更新投資を順次行っていくことが必要であるとの考え方が示されました。
- 出典:
- 経済産業省「電力システムのレジリエンス強化に向けた背景」より抜粋・加工
(エ)デジタル化の進展と対応の必要性
現在、電気は、発電所から需要家に対し一方向に流れていますが、将来は、太陽光やEV等の分散型電源の普及に伴って、電気の流れが双方向化していくことが見込まれます。今後はIoTやAIといったデジタル技術を活用し、分散電源を束ねて大規模発電所のように運用する「バーチャル・パワー・プラント」(VPP)や、需要に応じて電力価格を変えることで需要家の行動変容を促す「ディマンドリスポンス」(DR)等を通じて、電気の流れを全体最適化していくことが必要になります。こうした変化に対応するために、関連する制度改革の検討も必要であるとの考え方が示されました。
(オ)電力需要見通しの不透明化
今後、多くの地域で人口減少に伴う電力需要減が予想される一方で、一部の都市などでは人口流入が進んだり、電化が一層進展することなどにより電力需要が増大する要素も見られます。このため電力需要の動向を予測することが非常に難しくなっているとの認識が示されました。
- 出典:
- 経済産業省作成
- 出典:
- 関西電力株式会社送配電カンパニー
- 出典:
- 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来 推計人口」(平成30(2018)年推計)より抜粋
- 出典:
- 電力広域的運営推進機関「2018年度 全国及び供給区域ごとの需要想定」より抜粋
③電力ネットワーク改革に向けて必要となる検討事項
電力ネットワークを取り巻く環境の5つの環境変化を踏まえ、電力レジリエンス小委員会で検討を進めた結果、今後のネットワーク改革に向けて必要となる検討事項として、①ネットワーク形成の在り方の改革、②費用の抑制と公平な負担、③託送料金制度改革、④次世代型の送配電への転換、⑤レジリエンス・災害対応強化の5つの方向性をまとめました。
以下では、電力レジリエンス小委員会の示した5つの方向性について、それぞれ詳しく紹介していきます。
【第122-1-9】脱炭素化に向けた電力レジリエンス小委員会 中間整理概要(2019年8月20日)
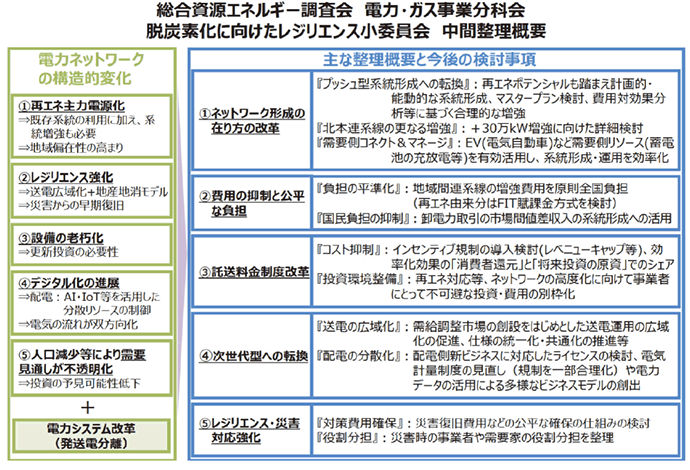
- 出典:
- 経済産業省「脱炭素化に向けたレジリエンス小委員会 中間整理概要」より抜粋
(ア)電力ネットワーク形成の在り方
第3節で紹介する「再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会」における議論を踏まえ、再エネの大量導入を促しつつ、国民負担を抑制していく観点から、電力ネットワーク形成の方向性が示されました。具体的には、これまで、個別の要請に対してその都度電源とネットワークを接続する「プル型」の系統形成が進められてきましたが、今後は、電力広域的運用推進機関(広域機関)や一般送配電事業者が主体的に電源のポテンシャルを考慮し、計画的にネットワークを形成していく「プッシュ型」の系統形成を進めるべきとの考え方が示されました。
そのためには、中長期的な系統形成(マスタープランの検討)、中長期で最適な設備形成・迅速な系統連系を実現するための一括検討プロセスの導入、洋上風力等再エネの規模・特性に応じた系統形成、基幹系統の増強について合理的な設備形成とするための規律の整備や、電気自動車(EV)等の需要側リソース(蓄電池の充放電等)を有効活用し、最大消費電力を抑えるいわゆる「需要側でのコネクト&マネージ」などを推進することが重要であるとの考え方が示されました。
【第122-1-10】最大電力を抑える需要側でのコネクト&マネージの例
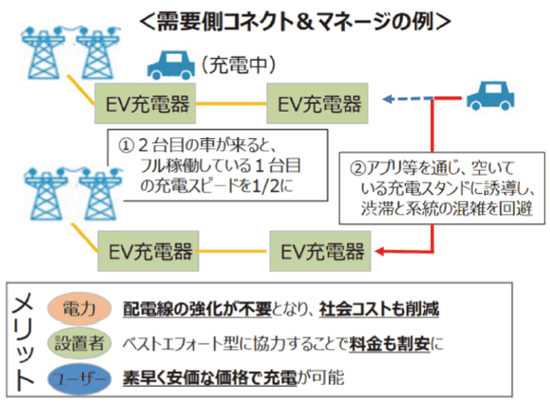
- 出典:
- 経済産業省「脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会 中間整理」より抜粋
(イ)電力ネットワーク費用の負担の在り方
電力ネットワークの形成と再構築には多額の費用がかかります。費用の抑制と負担の平準化を図る観点から、各主体が得られる便益に応じた負担をしていくことが、再エネの大量導入に欠かせないとの考え方が示されました。地域間連系線の増強による3E(安定供給、経済効率性、環境適合)への寄与は、それぞれ①安定供給の強化(停電率の減少等)、②広域メリットオーダーによる取引の活性化(価格低下等)、③再エネ大量導入の促進(CO2削減等)が想定されます。連系線増強に伴う便益のうち、②広域メリットオーダーによりもたらされる便益分(経済性の便益)は、受益者負担の観点から原則全国負担とすることが適切である一方、③再エネ大量導入によりもたらされる便益分(環境適合の便益)は、FIT賦課金が沖縄を含む全国で電力使用量に応じた負担となっていることにも鑑み、いずれもFIT賦課金方式を選択肢の一つとして検討していくべきであるとの考え方が示されました。他方、①安定供給の強化によりもたらされる便益分については、直接便益を受ける各地域の電力会社(一般送配電事業者)が負担する託送料金として回収することが適切との考え方が示され、それぞれ検討を進めていくこととされました。
【第122-1-11】電力系統増強の在り方と費用負担の考え方
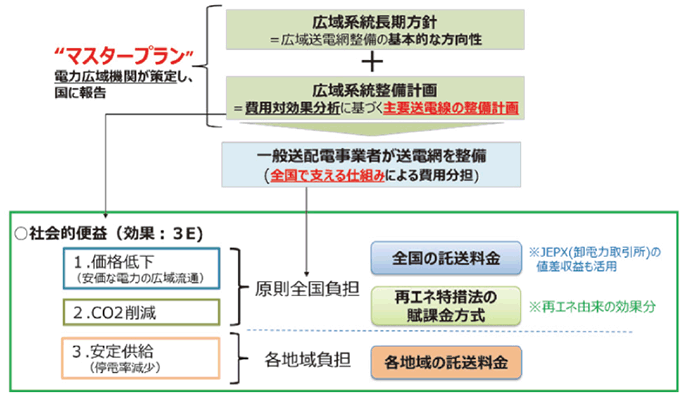
- 出典:
- 経済産業省「持続可能な電力システム構築小委員会 中間とりまとめ」より抜粋
(ウ)電力ネットワーク形成のための投資環境整備
電力ネットワーク形成のために適切な投資がなされるためには、一般送配電事業者が様々な環境変化に的確かつ機動的に対応し、費用を回収できるシステムが必要です。公益事業の規制料金の基本設計には、大別して①「総括原価方式」、②「インセンティブ規制方式」が存在し、後者は「プライスキャップ制度」と「レベニューキャップ制度」に分かれます。
日本では、送配電設備の高経年化や、電力需要見通しの不透明化で、投資回収の予見可能性が低下する一方で、再エネの主力電源化や電力インフラのレジリエンス強化、デジタル化への対応等の様々な環境変化に機動的に対応する必要があります。このため、一般送配電事業者が機動的に費用を回収できる合理的なシステムが必要であり、託送料金制度及び査定の見直しが必要であり、レベニューキャップ等のインセンティブ規制の導入を検討すること等が必要であるとの考え方が示されました。
【第122-1-12】託送料金(規制料金)の基本構造
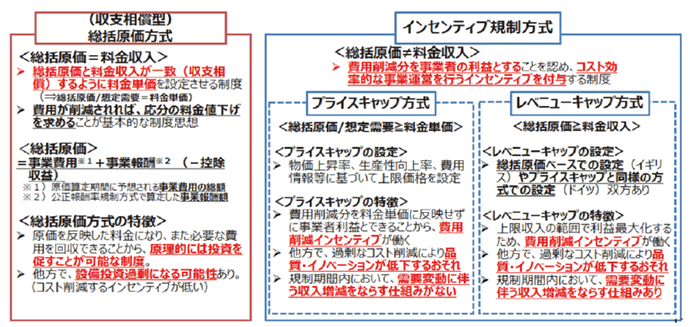
- 出典:
- 経済産業省「脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会 中間整理」より抜粋
(エ)次世代型ネットワークへの転換とそれに対応する制度の在り方
現在、発電所から需要家に対し一方向に流れている電気を、将来は、太陽光やEV等の分散型電源をデジタル技術でまとめて制御する等によって、双方向化し、電気の流れを全体最適化していく社会になっていくことが予想されます。
その結果、ネットワークが次世代型へ転換し、①電力ネットワーク事業の「価値」の中心が「kWh」(発電量)から「kW」(供給力)や「⊿kW」(調整力)に転換し、②送電と配電が「広域化する送電」と「分散化する配電」に機能分化し、③EVなどの外部電源を取り込むことでネットワーク全体としてさらなるコスト低減が可能となっていきます。
次世代型のネットワークへの転換が実現し、全国一体的な取引が行われるであろう将来にむけて、効率的な市場運営が可能となるように、需給調整市場に係る組織形態や契約形態の見直しを含めた制度改革を、改めて検討することが必要との考え方が示されました。その際、各一般送配電事業者の業務・責任の分担や、新たな組織形態・契約形態を想定した法的・制度的な位置づけの整理や、「送電の広域化」と「配電の分散化」を促す方策の検討も必要との考え方が示されました。
- 出典:
- 経済産業省「脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会中間整理」より抜粋
【第122-1-14】分散化・デジタル化に対応した制度の在り方
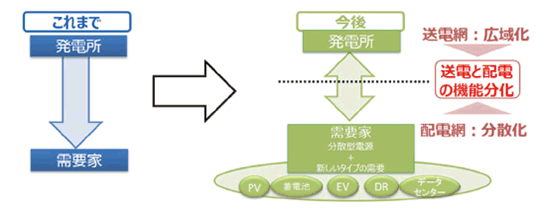
- 出典:
- 経済産業省「脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会中間整理」より抜粋
【第122-1-15】需給調整市場創設に伴う今後の広域的な調整力の調達・運用について
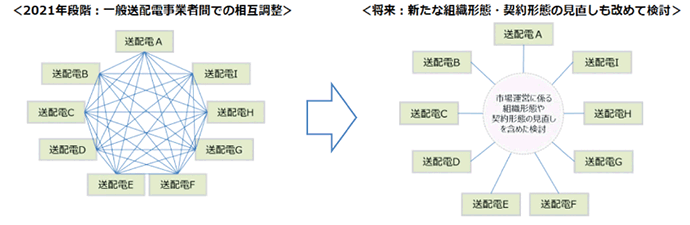
- 出典:
- 経済産業省「脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会 中間整理」より抜粋
(オ)電力ネットワークのレジリエンス向上
北海道胆振東部地震に起因するブラックアウトを踏まえ、2018年11月には電力インフラの総点検が行われました。電気を安定的に供給するためには、電気の消費量(需要)と電気をつくる量(供給力)を一致させ、周波数を一定に保つ必要があります。特に、需要が少ない時期(軽負荷期等)に、供給が減少すると、周波数低下に与える影響が大きくなります。総点検の中では、東日本・中西日本・沖縄エリアにおいて、軽負荷期等に、北海道胆振東部地震と同様の事象である①最大電源サイトが脱落し、②大規模電源サイト等に近接する4回線事故が発生した場合でも、必要な運用対策等を実施することにより「ブラックアウトには至らない」ことが確認されました。
2.令和元年台風第15号等への対応を踏まえたさらなるレジリエンス強化策の検討
(1)令和元年台風第15号等を踏まえた検討の概要
北海道胆振東部地震に起因するブラックアウトの教訓を踏まえた電力インフラのレジリエンス向上については、電力レジリエンス小委員会及びレジリエンスWGの議論を経て、2019年8月に一定の方向性が示され、これを踏まえた詳細な検討が進められていましたが、ここに新たな課題を提起したのが、2019年9月9日早朝に上陸し、関東を直撃する台風としては過去最大規模の勢力となった、令和元年台風第15号(以下、「台風15号」という。)です。
台風15号は、東京湾から千葉市付近に上陸し、千葉県内を縦断して19地点で観測史上1位の最大瞬間風速を記録するなど、千葉県を中心とした広域に甚大な被害を与えました。9月9日7時50分には関東広域で最大約93万戸の停電が発生し、東京、神奈川、埼玉、茨城、栃木、静岡の各都県では、9月11日までに概ね停電が復旧した一方で、千葉県内では送配電設備の被害が大きく、復旧作業に時間を要しました。具体的には、停電発生から10日以上経過した9月21日にようやく停電件数が1万戸以下となり、大規模な倒木や土砂崩れ等により、復旧作業が長期化している地域や低圧線や引込線上の障害が残っている一部の家庭以外の復旧が完了したのは、台風発生から15日後の9月24日でした。台風15号によって、停電復旧の長期化や復旧プロセスの在り方など、電力インフラのレジリエンスに関する新たな課題が浮き彫りになりました。
多くの国民に多大な影響を与えた台風15号への対応について検証を行うため、2019年10月に内閣官房に「令和元年台風15号に係る検証チーム」が発足しました。特に、電力分野について検証するため、産業構造審議会と総合資源エネルギー調査会が2018年10月に合同で設置した「レジリエンスWG」を再開し、台風15号と10月12日に日本に上陸した台風19号について、停電復旧の長期化原因や復旧プロセスにおける課題等について、客観的な事実関係やデータに基づいた検証や、レジリエンスWGでとりまとめられた対策の取組状況のフォローアップを行い、2019年11月6日に「中間論点整理」がとりまとめられました。
また、台風15号により、鉄塔や電柱の損壊事故が多数発生したことを受け、原因の技術的な調査分析や事故による影響を検証し、今後の対策や技術基準の見直しの必要性について、検討を行うため、産業構造審議会電力安全小委員会に「令和元年台風15号における鉄塔及び電柱損壊事故調査検討ワーキンググループ」が設置されました。
これらの検証・検討の結果は、2020年1月10日に、総合資源エネルギー調査会電力・ガス基本政策小委員会、産業構造審議会電力安全小委員会及びレジリエンスWGの連名で「台風15号の停電復旧対応等に係る検証結果取りまとめ」(以下、「台風15号検証結果」という。)として公表されました。
以下では、台風15号の特徴を概観した上で、レジリエンスWGの「中間論点整理」と「台風15号検証結果」の内容を詳しく紹介していきます。
(2)台風15号の特徴
2018年に近畿地方で大規模停電を引き起こした台風21号と比べ、台風15号はコンパクトでしたが風速が大きいことが特徴で、強風となった要因は非常に大きい気圧傾度にあったと考えられています。実際、台風21号の気圧傾度が5hPa/10kmであったのに対し、台風15号の気圧傾度は最大27~10hPa/10kmと観測されました。これにより、千葉市において最大風速35.9メートル、最大瞬間風速57.5メートルを観測するなど、記録的な暴風となったと推定されています。
台風15号については、千葉県内を中心に倒木・飛来物による電柱の折損や倒壊、断線が広範囲かつ多数発生し、近年の類似の災害と比較しても大規模な配電設備の被害が生じたこと(電柱の折損、倒壊数は2018年の台風21号の約1.5倍)に加え、倒木の影響により山間部を中心とした立ち入り困難な地域での巡視が十分に行えず、被害状況の全容把握に時間を要した結果、地域別の復旧見通しの公表が遅れ、復旧が長期化しました。概ね停電が復旧(停電件数がピーク時と比較して99%解消)するまで約280時間を要し、平成30年台風第21号及び台風第24号と比較しても長い期間を要することとなりました。
- 出典:
- 経済産業省「台風15号・19号に伴う停電復旧プロセス等に係る個別論点について」より抜粋
【第122-2-2】台風15号による電柱の被害発生状況
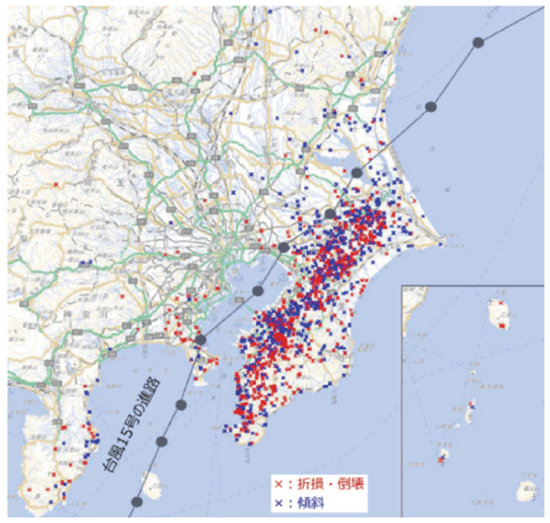
- 提供:
- 東京電力パワーグリッド株式会社より
【第122-2-3】2018年及び2019年の台風等被害における停電戸数の推移
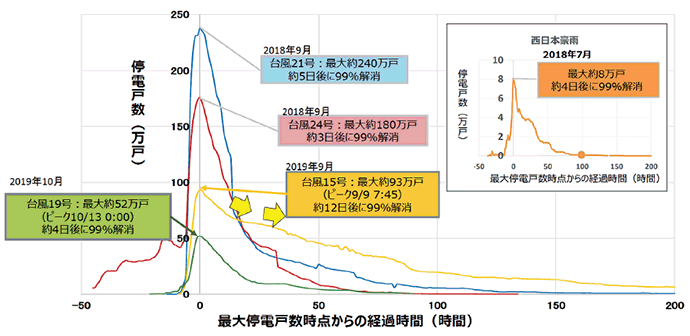
- 出典:
- 経済産業省「台風15号の停電復旧対応等に係る検証結果取りまとめ」より抜粋
【第122-2-4】停電戸数ピーク時から99%の停電が復旧するまでの時間の近年の類似災害との比較

【第122-2-4】停電戸数ピーク時から99%の停電が復旧するまでの時間の近年の類似災害との比較(ppt/pptx形式:37KB)
- 出典:
- 経済産業省「台風15号に伴う停電復旧プロセス等に係る検証について」より抜粋・一部修正
【第122-2-5】台風15号による被害状況
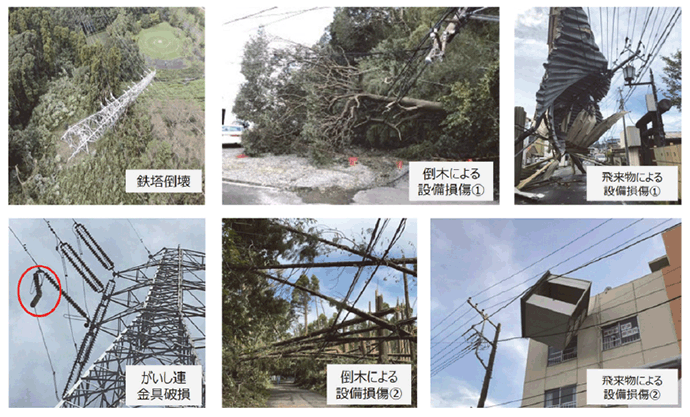
- 提供:
- 東京電力ホールディングス株式会社・東京電力パワーグリッド株式会社より
COLUMN
世界全体の自然災害の状況
昨今、世界全体で大規模な自然災害による被害が拡大しているとの報告が増えています。例えば、国連国際防災戦略事務局(UNISDR)が2018年10月に発表した報告書では、「1998年~2018年の20年間での自然災害による世界全体での経済損失額は2兆9,080億ドル(約330兆円)に上った。このうち大半の77%の2兆2,450億ドルは気候変動に起因する災害で、その前の20年間と比べると、2.5倍に増加している。」(国連国際防災戦略事務局(UNISDR)報告書”Economic Losses, Poverty & Disasters 1998−2017”)とされています。
日本においても同様に自然災害による被害が拡大しており、日本損害保険協会によると、頻発する自然災害の影響で、2018年の自然災害(風水害)の保険金支払額が、過去最高の1兆5,694億円になりました。愛知・大阪・京都・兵庫などで被害が出た2018年9月の台風21号(支払い保険金1兆678億円)、東京・神奈川・静岡などを襲った台風24号(同3,061億円)、2018年7月の豪雨の影響が大きかったとされています。支払保険金総額については、増加傾向にあり、2018年には5兆3,241億円に上りました。
- 出典:
- (一社)日本損害保険協会提供データより経済産業省作成
(3)レジリエンスWG「中間論点整理」の概要
2019年11月に取りまとめられたレジリエンスWGの「中間論点整理」では、オペレーション改善等として、①迅速な情報収集・発信を通じた初動の迅速化、国民生活の見通しの明確化、②被害発生時の関係者の連携強化による早期復旧、インフラ投資として、③電力ネットワークの強靱化によるレジリエンス強化、④復旧までの代替供給・燃料の確保、⑤電力ネットワークの強靱化、電源等の分散化によるレジリエンス強化など5つの論点が示されました。
以下、概要を紹介していきます。
①迅速な情報収集・発信を通じた初動の迅速化、国民生活の見通しの明確化
災害時に最初に重要となるのが、現場の被害情報を正確にかつ迅速に把握することです。そのため、要員を投入せず、初動から現場確認が出来るカメラ付きドローンやヘリコプターの活用の拡大や、それらから集まる画像やデータを一元管理するためのシステムが必要となります。こうして収集された画像や情報は、ビッグデータとしてAI等を用いて迅速な被害予測や復旧見通しに活用されることが期待されます。
- 出典:
- 経済産業省「台風15号・19号に伴う停電復旧プロセス等に係る個別論点について」より抜粋
- 出典:
- 経済産業省「台風15号・19号に伴う停電復旧プロセス等に係る個別論点について」より抜粋
②被害発生時の関係者の連携強化による早期復旧
災害時の復旧活動を円滑に実施するに当たっては、効率的な応援の受入れや他組織との連携が欠かせません。このため、電力事業者間での電源車の効率的な派遣や復旧手法・設備仕様の統一化、早期の停電解消を最優先する「仮復旧」方式の徹底することのみならず、平時からの電力供給事業者間での協力にむけた仕組みづくりが重要です。さらに電力会社から自治体等への情報提供、電力会社・自治体・自衛隊との連携による倒木処理・伐採の迅速化なども必要であることが明らかになりました。こうした災害を全国大の課題として捉え、災害復旧のための費用負担について、電力会社間で相互扶助する仕組みも必要です。
【第122-2-9】被害情報等が落とし込まれた配電線地図(電力会社と自治体の情報共有の例)
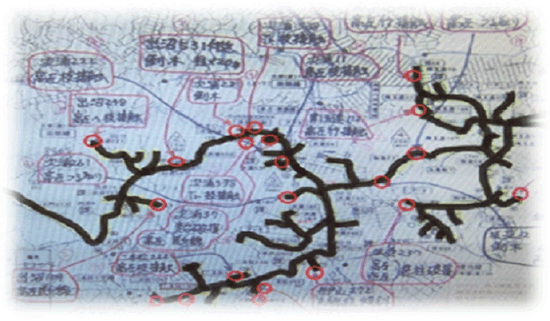
【第122-2-9】被害情報等が落とし込まれた配電線地図(電力会社と自治体の情報共有の例)(ppt/pptx形式:401KB)
- 出典:
- 経済産業省「台風15号・19号に伴う停電復旧プロセス等に係る個別論点について」より抜粋
- 出典:
- 経済産業省「台風15号・19号に伴う停電復旧プロセス等に係る個別論点について」より抜粋・一部修正
③電力ネットワークの強靱化によるレジリエンス強化
台風15号により千葉県の送電鉄塔2基の倒壊や広範囲にわたる電柱の損壊事故が発生したことを踏まえ、鉄塔・電柱の技術基準見直しを含めた検討、レジリエンス強化のための無電柱化、災害に強い分散型グリッドの推進等を一層図っていかなくてはなりません。その際、送配電網の老朽化と将来の電力需給を見据えた次世代型ネットワークの強靱化・スマート化、そのための計画的な更新投資とコスト効率化の両立が求められます。
- 出典:
- 経済産業省「鉄塔・電柱に係る技術基準をめぐる現状について」及び国土交通省「無電柱化の推進に関する最近の取組」より作成
④復旧までの代替供給・燃料の確保
今後の広域災害発生のリスクを考えると、電力会社とタンクローリーを運用している石油業界等との連携の強化や電源車の燃料供給を担うタンクローリー配備の強化は重要です。また、中東情勢の不安定化等を踏まえた調達先の多角化や緊急時の調達確保等、燃料の安定的かつ低廉な調達の確保の在り方が求められます。
- 出典:
- 経済産業省「電力レジリエンスワーキンググループ中間論点整理」
⑤電力ネットワークの強靱化、電源等の分散化によるレジリエンス強化
2018年の北海道胆振東部地震による北海道全域にわたる大規模停電(ブラックアウト)により、緊急時の電力融通のための地域間連系線の強化の重要性が改めて認識されました。さらに災害時に自立運転可能な再エネ等分散型電源の地域への導入拡大、送配電設備の老朽化や再エネ大量導入も踏まえた最新の電源の導入、電源の多様化・分散化の促進が求められています。将来は分散電源やデジタル技術の活用により、電気の流れが従来の一方向から双方向へ変化してくることが予想されています。
【第122-2-13】デジタル技術を活用した電源の多様化・分散化・最適化
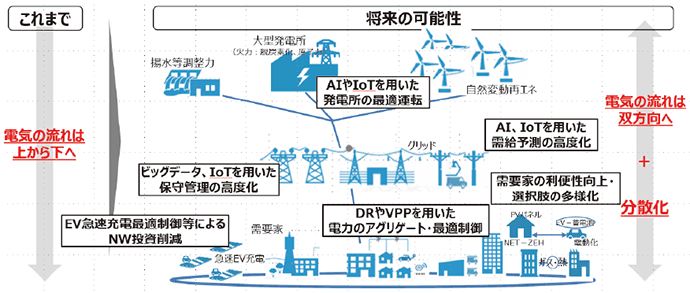
- 出典:
- 経済産業省「再生可能エネルギーの大量導入を支える次世代電力ネットワークの構築について」より抜粋
(ア)鉄塔等の電気設備の損壊事故の原因究明・検証
台風15号の影響により、千葉県君津市の送電鉄塔2基の倒壊や広範囲にわたる電柱の損壊事故が発生し、また、千葉県市原市の山倉ダムに設置された水上設置型太陽光発電所においてはパネルなどの破損事故も発生しました。
鉄塔及び電柱の損壊事故を踏まえ、産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会「令和元年台風15号における鉄塔及び電柱損壊事故調査検討ワーキンググループ」において、その原因の技術的な調査分析に加え、事故による影響も含めて検証し、今後の対策や技術基準の見直しの必要性について、費用対効果に留意しながら検討が行われました。
2020年1月、台風15号による鉄塔・電柱の倒壊・損傷等の原因究明や風速に関する地域の実情等を踏まえ、鉄塔・電柱の技術基準の見直しの方向性等について、「中間報告書」が示されました。
【第122-2-14】台風15号による電気設備の被害状況(千葉県内)
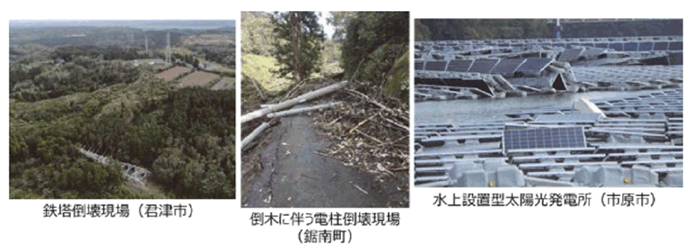
- 出典:
- 経済産業省「台風15号の停電復旧対応等に係る検証結果取りまとめ」より抜粋
【第122-2-15】鉄塔・電柱の技術基準見直しと対応の方向性
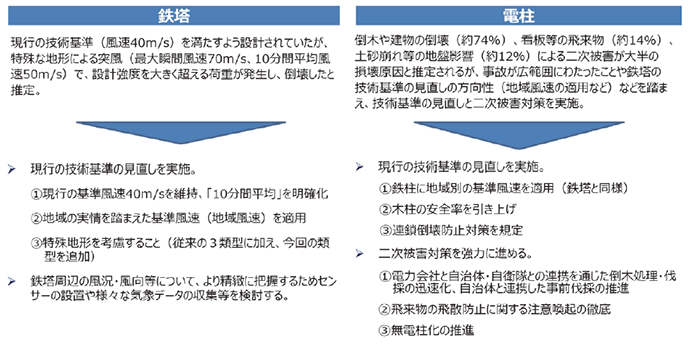
- 出典:
- 経済産業省「令和元年台風15号における鉄塔及び電柱損壊事故調査検討ワーキンググループ中間報告書」より作成
(イ)飛来物等による停電被害を回避・軽減するための無電柱化の推進
台風15号による台風被害においては、飛来物等によって電柱が倒壊するなど、電力ネットワークの末端の配電設備に広域的な被害が生じました。こうした被害を事前に回避・軽減する観点からは、無電柱化の推進は重要です。
これまでに道路防災、安全・円滑な交通確保や景観振興・観光振興の観点からの「無電柱化推進計画」の策定(2018年4月6日)や、2018年の台風21号の電柱倒壊を踏まえ道路閉塞等を防止する目的の「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策(2018年12月14日閣議決定)」により、整備距離について、これまでにない高い目標が掲げられていました。しかし、無電柱化は、「敷設コストが高い(総工事費約5.3億円/km)」「工期が長い(設計から工事完了まで約7年)」「水害(冠水等)による設備被害リスクが高い」といった課題や、復旧には架空線と比較して約2倍の時間を要するといった課題も存在しています。
検証結果では、レジリエンス強化に向けて、費用対効果も考慮しながら、無電柱化の取組を加速化していく必要性が示されました。
- 出典:
- 電気事業連合会より
【第122-2-17】電柱と地上機器における設備単体での復旧時間の比較
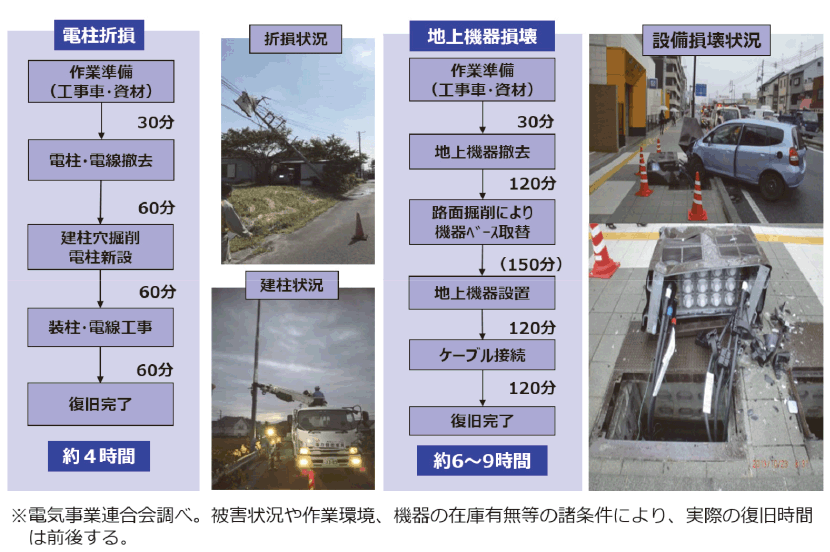
- 出典:
- 電気事業連合会
(ウ)災害に強い分散型グリッドの活用
2019年の台風15号や台風19号、2018年の台風21号による被害では、山間部等で配電線に飛来物が衝突し設備が被害を受ける場合や、被害箇所までの要路確保が倒木等により困難な場合があり、復旧に時間を要した事例が報告されました。電力レジリエンス小委員会では、送配電等の設備の合理化という観点から、太陽光発電や蓄電池といった分散リソースを活用することで需要密度が低い地域の系統のスリム化・独立化の可能性についても議論が行われていましたが、台風被害での教訓を踏まえれば、主要な電力系統から長距離の送配電設備等を経由して電力供給を受けるのではなく、遠隔分散型グリッドとして独立した系統での電力供給を行った方が、レジリエンスが高まる地域が存在すると考えられます。
こうした観点から、災害発生時においても独立した系統での円滑な電力供給を可能とする制度整備の必要性が改めて示されました。
また、今回の台風15号では、特に停電情報システムに低圧線以下の停電情報が反映されないなど、正確な情報収集・発信に一部問題がありました。こういった課題の解決のため、分散リソースやIoT等の制御技術の活用を図り地域に密着した配電運用を行うことで、正確な情報発信や電力供給のみならず地域の防災・減災に資するシステムを実現することが必要であることも明らかにされました。
さらに、現在、実証事業において、一般送配電事業者、地方自治体を含むコンソーシアム体制を前提とした、マイクログリッド構築の検討が進められているところですが、規制の適用関係を明確化することによって、新たな地域で、新たなプレーヤーが配電事業に参入していくことが期待されます。また、分散型エネルギーの近隣間の融通など、地域における自立した電気の取引を促進するための環境整備も併せて検討することが必要とされました。
【第122-2-18】災害に強い遠隔分散型グリッドイメージ
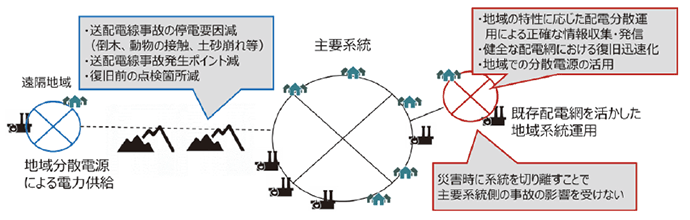
- 出典:
- 経済産業省「台風15号の停電復旧対応等に係る検証結果取りまとめ概要」より抜粋
- 出典:
- 経済産業省「台風15号の停電復旧対応等に係る検証結果取りまとめ」より抜粋
【第122-2-20】AIやIoT等の技術活用による地域の防災・減災に資するシステム
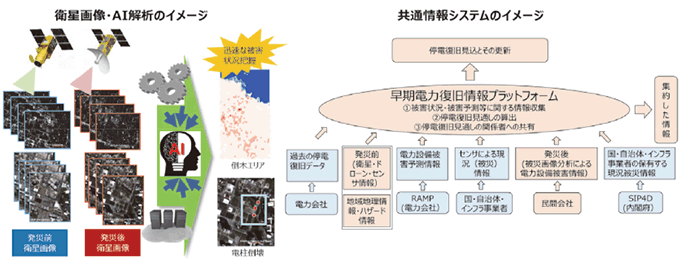
- 出典:
- 経済産業省「台風15号の停電復旧対応等に係る検証結果取りまとめ」より抜粋
【第122-2-21】地域マイクログリッドの構築
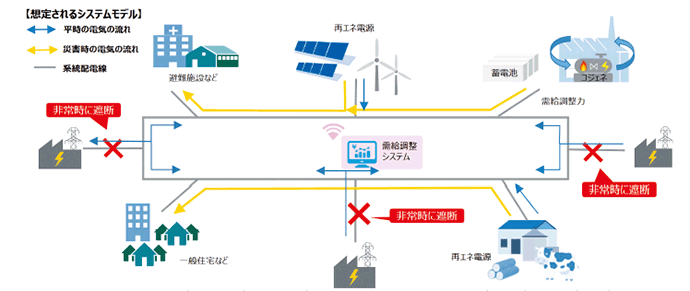
- 出典:
- 経済産業省「地域分散型電源活用モデルの確立に向けた支援制度について」より抜粋
(4)レジリエンスWG等合同委員会による「台風15号検証結果」の概要
レジリエンスWGの「中間論点整理」で示された5つの論点の検討を深め、総合資源エネルギー調査会電力・ガス分科会電力・ガス基本政策小委員会と産業構造審議会保安・消費生活製品安全分科会電力安全小委員会及びレジリエンスWGの連名で、2020年1月10日に「台風15号の停電復旧対応等に係る検証結果」を公表しました。
この中で、①迅速な情報収集・発信を通じた初動の迅速化、国民生活の見通しの明確化、②被害発生時の関係者の連携強化による早期復旧、③電力ネットワークの強靱化によるレジリエンス強化については、政府として対応すべき事項と電力会社として対応すべき事項にわけて整理するとともに、官民や業種を超えて対応する必要がある④復旧までの代替供給・燃料の確保と⑤電力ネットワークの強靱化・電源等の分散化によるレジリエンス強化に必要な事項が取りまとめられました。併せて、電力会社自身による台風15号への対応検証結果も取りまとめられました。
【第122-2-22】台風15号の停電復旧対応等に係る検証結果(2020年1月10日)
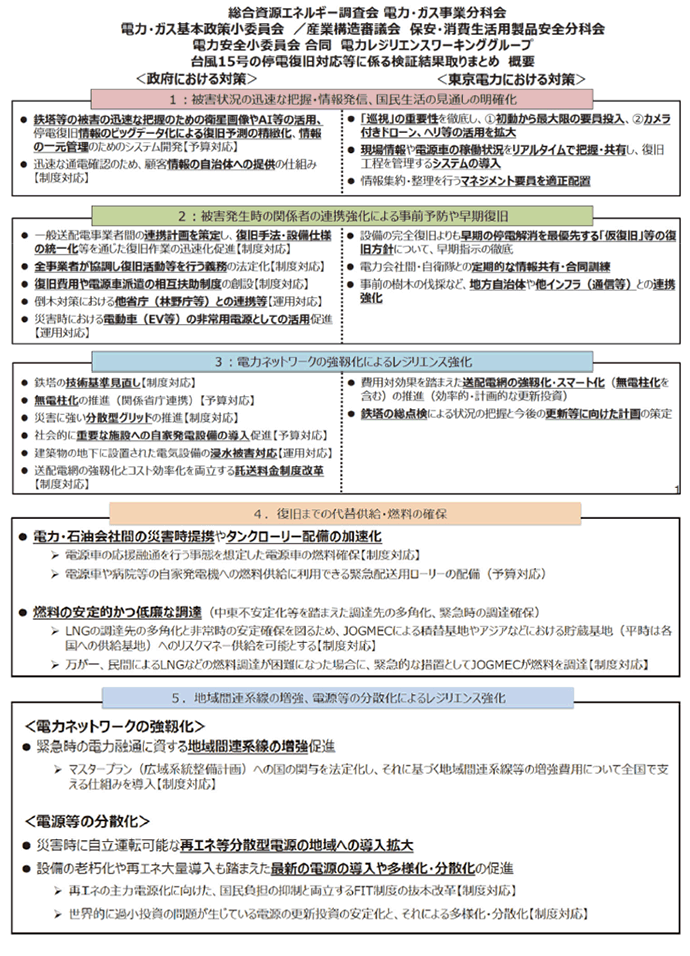
- 出典:
- 経済産業省「台風15号の停電復旧対応等に係る検証結果取りまとめ概要」より抜粋
【第122-2-23】台風15号踏まえた電力会社としての課題認識と対応策(2020年1月10日)
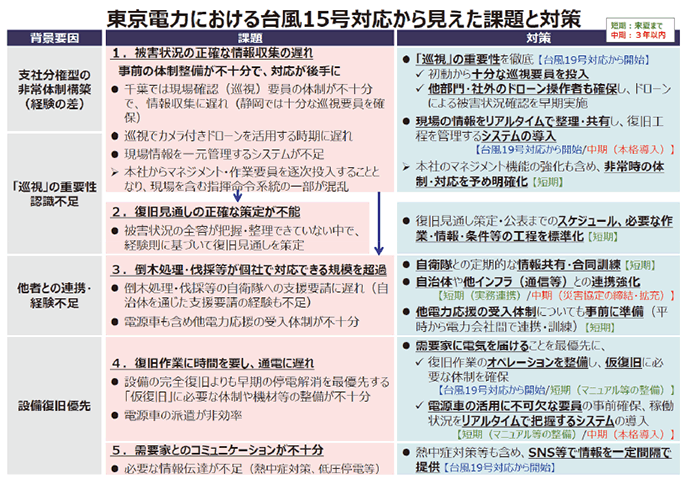
- 出典:
- 出典:経済産業省「台風15号の停電復旧対応等に係る検証結果取りまとめ概要」より抜粋
3.「持続可能な電力システム構築小委員会」における議論
北海道胆振東部地震や台風15号等を踏まえた検討をさらに深め、電力インフラのレジリエンスを向上させ、新技術を取り込んだ形で持続的な安定供給体制を構築するために必要となる電力システム制度改革等を議論するため、2019年11月に、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の下に「持続可能な電力システム構築小委員会」を設置しました。
その後、さらに議論を進め、2020年2月に「持続可能な電力システム構築小委員会 中間取りまとめ」を公表し、(1)災害時における早期の災害復旧のための関係者の連携強化、(2)強靱な電力ネットワークの形成、(3)電力システムの分散化と電源投資といった論点について、課題と対応の方向性を整理しました。
以下では、それぞれの論点について、紹介していきます。
(1)災害時における早期の災害復旧のための関係者の連携強化
災害時の電力復旧活動の円滑な実施に向け、他のエリアからの効率的な応援の受入れや他組織との連携を行うべく、多様な関係機関の連携についての体制や運用等の詳細を事前に整理・共有しておくことが必要であること、また電力会社の持つ情報が関係機関に迅速に共有されることが必要であること等の考え方が示されました。
災害の大規模化に伴い、電力復旧に係る応援人員・設備の規模・期間が大規模・長期化し、その費用負担も増大する傾向にあります。災害はいつ、どこで起きるか予想することは困難であるため、こうした費用負担を、被災地域だけに負わせるのではなく、日本全体の課題として災害を捉えた費用負担の在り方についても検討が必要であるとの考え方が示されました。こうした観点から、取り組むべき事項として、以下の①、②、③が示されています。
①災害時連携計画の整備による復旧作業の迅速化
昨今の停電復旧において一般送配電事業者間の効率的な連携が重要になっていることを踏まえて、あらかじめ、一般送配電事業者間の連携に関する計画(災害時連携計画)を作成することを制度上求めるべきであるとされました。提言された災害時連携計画の盛り込むべき事項は以下の通りです。
- 一般送配電事業者間の共同災害対応に関する事項
- 復旧方法、設備仕様等の統一化に関する事項
- 各種被害情報や電源車の管理情報等を共有する情報共有システムの整備に関する事項
- 電源車の地域間融通を想定した電源車の燃料確保に関する事項
- 電力需給及び系統の運用に関する事項
- 関係機関(地方公共団体・自衛隊等)との連携に関する事項
- 共同訓練に関する事項
②災害復旧費用の相互扶助制度の創設
災害時は事業の公益性、対象となる事業範囲に鑑み、被災電力事業者は一定の基準を満たした場合、災害時に発生した(ア)他電力等からの応援に係る費用、(イ)本復旧と比較して迅速な停電の解消が期待される仮復旧作業に関し、それぞれ要した費用について、相互扶助制度の適用を受けることができるよう制度を設計すべきであるとの提言がなされました。この際、(イ)の仮復旧費用については、要した費用だけを切り分けて算出することが困難であり、その算出のために停電復旧対応が遅れるといった事態を防止する観点などから、送配電設備の損壊時に発生する仮復旧・本復旧費用の試算結果等を基に、一定の基準で算出した費用を仮復旧に要した費用とみなすことが可能とされるべきとの考え方が示されました。
【第122-3-1】災害復旧費用の相互扶助制度のイメージ
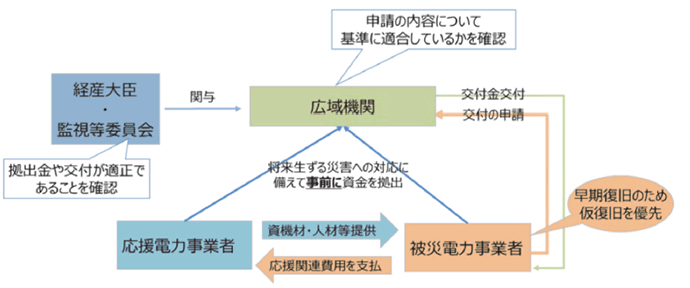
- 出典:
- 経済産業省「持続可能な電力システム構築小委員会中間とりまとめ」より抜粋
【第122-3-2】中立的な組織を通じた電力データ活用のイメージ
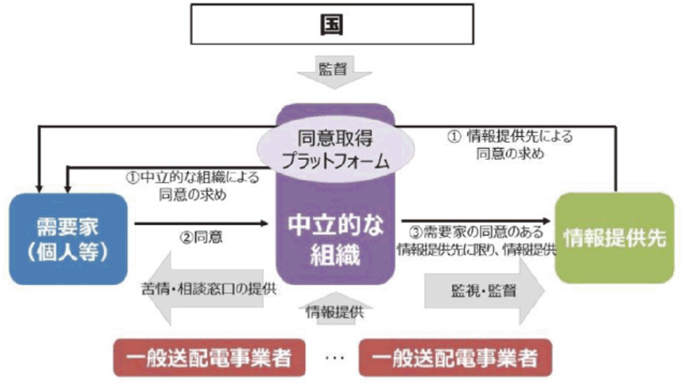
- 出典:
- 経済産業省「持続可能な電力システム構築小委員会中間とりまとめ」より抜粋
③電力会社による個別情報の自治体等への提供
(ア)災害対応のための自治体等への情報提供
電力会社と地方公共団体等が、災害復旧時に円滑に連携して対応するため、事前の防災段階から、発災時のデータ受渡しの手続などの連携体制を確認しておく必要があることから、個人情報保護の観点も適切に踏まえた上で、「電気事業法(昭和39年法律第170号)」に基づき、一般送配電事業者に対し、関係行政機関等への情報提供の必要性が認められる場合には、個人情報を含む電力データの提供を求める制度整備を進めるべきとの考えが示されました。
(イ)社会的課題解決等のための電力データの活用
また、個人情報を含む電力データについては、上記のような災害復旧対応の目的だけにとどまらず、(i)地方公共団体等による防災計画の高度化などの社会的課題の解決や、(ii)銀行口座開設に当たっての不正防止などの事業者による社会的課題の解決や新たな価値の創造など、様々な活用ニーズがあることから、今後、個人情報保護委員会など関係行政機関や消費者団体をはじめとする関係者と密接に連携しつつ、データ活用の在り方の検討を進めていくことの必要性が示されました。
(2)強靱な電力ネットワークの形成
台風15号では、電力ネットワークの末端の配電設備の被害が広範囲で発生しました。大規模な災害時にも停電の発生を可能な限り防止し、電力供給の信頼度を維持・向上させるためには、強靱かつ持続的な電力ネットワークの形成が不可欠となります。そのため、送配電網についても、老朽化や将来の需給動向等を踏まえて、送配電網の強靱化とコスト効率化を両立する託送料金改革の中で、電力会社が強靱化やスマート化を計画的かつコスト効率的に実施する必要があります。さらに、緊急時の電力融通に資するとともに、再生可能エネルギーの大量導入を進めていく中で系統強化の観点から必要となる地域間連系線の増強も進めていくことが必要とされました。
①地域間連系線の増強を促進するための制度整備
地域間連系線の増強は、エリア間の相互融通を可能にすることで、電源が脱落した場合などにおける停電リスクを低下させることが確認されました。また同時に、地域間連系線の増強は、短期的には既存の再生可能エネルギーの稼働率を高め、その最大限の活用を促す効果があります。これに加え中長期的には、より安価なコストの再生可能エネルギー導入が進み、同じkW(供給力)、kWh(発電量)を達成するための再生可能エネルギー支援策に係るコストを低減させる可能性もあることから、地域間の連系線の増強は、再生可能エネルギー推進にも資するものであると整理されました。これを踏まえ、レジリエンス強化を目指しながら、さらなる再生可能エネルギーの導入も見据えて、地域間連系線の増強を促進するための制度整備が求められています。
【第122-3-3】地域間連系線の増強計画(再掲)
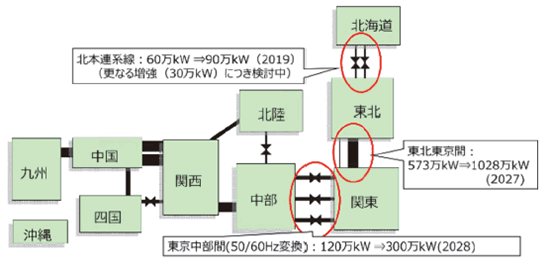
- 出典:
- 経済産業省「持続可能な電力システム構築小委員会中間とりまとめ」より抜粋
【第122-3-4】「必要なネットワーク投資の確保」と「国民負担抑制」を両立する託送制度改革
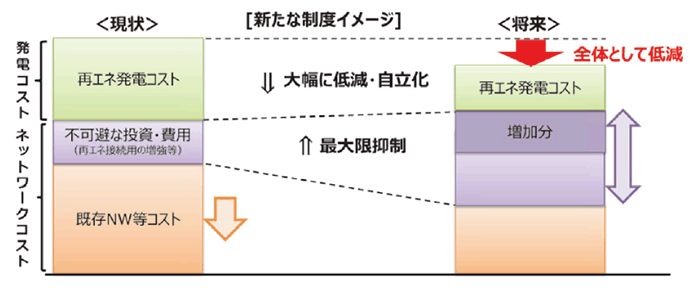
- 出典:
- 経済産業省「持続可能な電力システム構築小委員会中間とりまとめ」より抜粋
②送配電網の強靱化とコスト効率化を両立する託送
料金改革
託送料金改革については、電力レジリエンス小委員会の中間整理(2019年8月)において、「託送料金制度の見直しに当たっては、「国民負担抑制」と「必要な投資確保」の両立が大原則であり、このための基本コンセプトは「『単価』の最大限の抑制」×「必要な投資『量』の確保」であるとの方向性が示されました。
このため、一般送配電事業者に、必要な送配電投資の着実な実施を促すとともに、コスト効率化を促す観点から、欧州の制度も参考に、国が、一定期間ごとに、収入上限(レベニューキャップ)を承認することにより、一般送配電事業の適切性や効率性を定期的に厳格に審査するとともに、一般送配電事業者自らの効率化インセンティブを促し、併せて、新規電源接続のための送配電設備の増設や調整力の変動などの外生的要因による費用増や費用減については、機動的に収入上限に反映する仕組みを基本とした託送料金制度を導入すべきとされました。
(3)電力システムの分散化と電源投資
山間部等、地理的制約により事前の防災対策が困難なケースに、あらかじめ分散型電源(再生可能エネルギー、蓄電池、コージェネレーション、電動車等)を活用することにより、災害時・緊急時のレジリエンスを向上させる方策について検討が必要です。北海道全域にわたる大規模停電(ブラックアウト)等も踏まえ、最新の電源の導入や多様化・分散化を促進するための仕組みや、住民の生活維持や事業活動の継続に不可欠な社会的重要施設への自家発電設備等の導入拡大の必要性も示されました。
【第122-3-5】遠隔分散型グリッドのイメージ
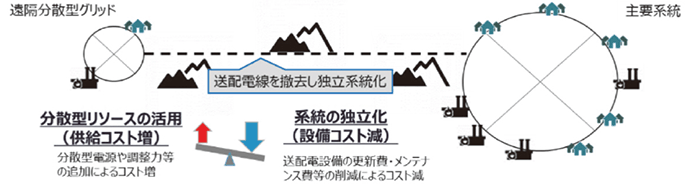
- 出典:
- 経済産業省「持続可能な電力システム構築小委員会中間とりまとめ」より抜粋
①災害に強い分散型グリッドの推進のための環境整備
山間地などの一部においては、今後、長距離の送配電線を維持することより、特定の区域を独立系統化して地域分散電源による電力供給を行う方が、送配電網の維持コストの削減に伴い電力システム全体のコストは下がり、同時に災害への耐性(レジリエンス)も高まるエリアが出てくることが想定されます。このような主要系統から切り離された独立系統(遠隔分散型グリッド)を通じた供給を行うため、一般送配電事業者が系統運用と小売供給を一体的に行う新たな仕組みの導入を進めることが必要とされました。また、コスト効率化や災害時のレジリエンス向上の観点から、特定の区域において、一般送配電事業者の送配電網を活用して、新規参入者自ら面的な系統運用を行うニーズも高まっていることを踏まえ、新たな事業者の参画を促すため、配電系統を維持・運用し、託送供給及び電力量調整供給を行う事業者を、配電事業者として制度上位置付けるべきとの考え方が示されました。
【第122-3-6】新規参入者による配電事業のイメージ
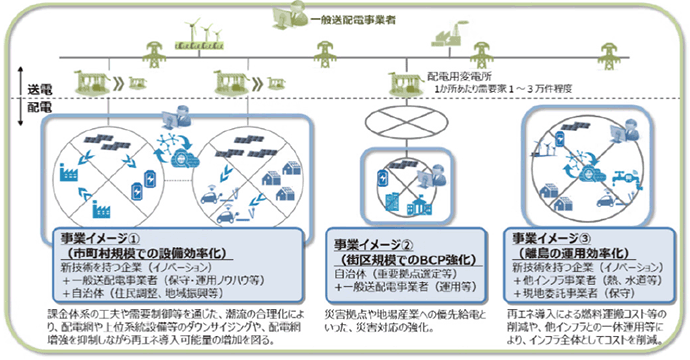
- 出典:
- 経済産業省「持続可能な電力システム構築小委員会中間とりまとめ」より抜粋
②分散型電源のための新たな制度
(ア)アグリゲーターライセンスの導入
今後、再生可能エネルギー等の分散リソースの供給力を束ねて仲介する事業者(いわゆる「アグリゲーター」)を介して、これらの供給力にまとめてアプローチできれば、天候や設備の被災状況等も考慮する必要はありますが、平常時の需給調整に貢献するのみならず、災害時に電力需給がひっ迫した場合においても、効率的に対応できることが期待されます。また、アグリゲーターを適切な義務や規制の対象とすることにより、規制の適用関係が明確化されるとともに、事業の信頼性を高め、ビジネス環境の向上につながり、ひいては自家発電設備や、小規模再生可能エネルギー発電施設、蓄電池などの分散リソースのさらなる普及が期待されます。このため、自家発電設備等の分散リソースを広く供給力として国が把握するとともに、分散リソースを束ねて供給力や調整力として活用するビジネス環境を整える観点から、アグリゲーターを電気事業法に位置付けるべきとの考え方が示されました。
【第122-3-7】分散リソースを活用した新たな取引イメージ
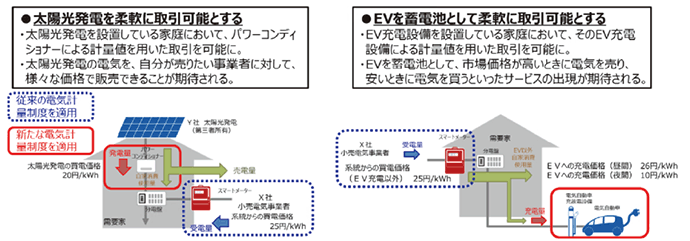
- 出典:
- 経済産業省「持続可能な電力システム構築小委員会中間とりまとめ」より抜粋
(イ)電気計量制度の合理化
今後、アグリゲーター等がEV、蓄電池、住宅用太陽光等の分散リソースを束ねて供給力や調整力として活用するなど、電気の流れが双方向になっていくと、リソースごとに電気計量を行うニーズが増えていきますが、現在の制度は必ずしもこのような計量による取引に適した仕組みになっていません。具体的には、現行の電気計量制度では、全ての取引に係る電力量の計量について、「計量法(平成4年法律第51号)」に基づく型式承認または検定を受けた計量器を使用することが求められているところ、中間とりまとめでは、計量器の精度の確保や需要家への説明を求めることなどを前提に、このような取引に限って、計量法の規定について適用除外とする必要性が示されました。
③設備の老朽化や再エネ大量導入も踏まえた電源投資の確保の在り方
北海道では全域にわたるブラックアウトが発生しました。その復旧段階においては、火力発電所のみならず、道内各所の水力、バイオマス、地熱といった発電量の変動が少なく安定的に発電が可能な再生可能エネルギーが、発災直後から安定的な供給力として貢献していました。また、老朽火力発電所も復旧段階で供給力の積み増しに役割を果たしており、様々な特徴・役割を有する発電設備が存在することが安定供給にとって有用であることが確認されました。一方で、設備年齢が高経年化する中で、こうした老朽電源に依存し続けることは困難です。再生可能エネルギーの大量導入の中で安定供給を持続的なものとしていくためには、中長期的に適切な供給力・調整力のための投資を確保し、最新の電源の導入や多様化・分散化を促進していくことが必要です。
こうした必要な電源への投資を確保するため、既に国内では、発電能力容量(kW)に応じて、稼働していない期間(kWh=0の期間)でも一定の収入を得られる仕組み(容量市場)の導入が2020年夏に予定されています。しかし、容量市場は、(ア)4年後の1年間の供給力を評価する市場であるため長期的な収入の見通しが困難であること、(イ)出力が自然変動する再生可能エネルギーは供給信頼度が低く相対的に容量収入が少ないことなどの課題があるため、容量市場単独では、電源投資を行う者に対して、最新の電源への投資のために必要な長期的な予見可能性を付与することは困難です。
こうしたことから、再生可能エネルギーを含めた電源全体の投資を安定的に確保するため、電源特性等も踏まえつつ、長期的な予見可能性を与える制度措置が必要との考え方が示されました。