第2節 脱炭素実現に向けた日本の対応
2021年10月に、日本のエネルギー政策の基本的な方向性を示す第6次「エネルギー基本計画」が閣議決定されました。今回の「エネルギー基本計画」では、2つの重要テーマに基づき、政策をまとめています。
第一に、2050年カーボンニュートラルや2030年度の野心的な温室効果ガス削減目標18の実現に向けたエネルギー政策の道筋を示すことです。世界的な脱炭素に向けた動きの中で、国際的なルール形成を主導することや、これまで培ってきた脱炭素技術、新たな脱炭素に資するイノベーションにより国際的な競争力を高めることについても言及しています。
第二に、日本のエネルギー需給構造が抱える課題の克服に向けた政策の展開を示すことです。そのために、安全性の確保を大前提に、気候変動対策を進める中でも、安定供給の確保やエネルギーコストの低減に向けた取組を進めるという、S+3E(Safety、Energy security、Economic efficency、Environment)の大原則をこれまで以上に追求することとしています。
政府では、「エネルギー基本計画」を踏まえ、第208回国会に「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案」を提出したほか、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定・国会提出する等、各分野で政策の具体化を進めています。また、この一環として、エネルギー供給のみならず、需要側のイノベーションや設備投資等、需給両面を一体的に捉えた「クリーンエネルギー戦略」の策定に向けた議論を進めており、どのような分野で、いつまでに、どういう仕掛けで、どれくらいの投資を引き出すのかといった経済社会変革の道筋の全体像を示すこととしています。
本項では、まず「エネルギー基本計画」を踏まえ、エネルギーに関する国民の関心がどのように推移してきているのか、定量的な把握を試みます。その上で、クリーンエネルギー戦略の検討を踏まえて、注目すべき点を紹介します。
1.エネルギーに関連する国民の関心度の推移
「エネルギー基本計画」を始めとするエネルギー政策全般の議論や、電力やガス、省エネ等の各分野における制度の施行、資源・燃料や電力の価格変動、COP等の気候変動に関する国際会議等が開催された時に、国民がどのような点に関心を有していたかを整理することは、今後のエネルギー政策を検討するに当たっても重要です。資源エネルギー庁では、総合資源エネルギー調査会における議論を全てオンラインで中継・公開し、「エネルギー基本計画」を始めとした政策を決定する際にはWeb上の「意見箱」の開設やパブリックコメントの募集を通じて、多様なご意見を取り入れるよう努めていますが、エネルギー政策に対して積極的に意見をいただく方々はもちろん、エネルギー政策に対して積極的に意見を述べることのない方々の意見をも幅広く把握しながら政策を検討することも非常に重要です。
このような国民の関心の一つの表れとして、インターネットでどのようなワードが多く検索されたのかのデータを用いて、エネルギー情勢への国民の関心度の定量的な把握を試みます。具体的には、エネルギー関連のワードや複数ワードの組合せを一定の塊として分類し、そのワードを検索した人数を時系列で示した後、検索人数や、その増減の大きな分野ごとにワードごとに詳細に分析します。また、エネルギー政策における3Eのそれぞれについて世代ごとの動向を整理します。
(1)全体の動向
インターネット検索されているエネルギー関連のワードについて、Yahoo!検索の統計データを用いて調査を実施しました。検索結果の分析に当たっては、ワードの分類を行い、Yahoo!検索のデータを取得できる2014年以降の推移を示すこととしました。日本のエネルギー政策の根幹である「S+3E」の考え方を基本に、個々のワードを内容の関連性から、大きく15分野19に分類しました。Yahoo! JAPANで検索したユーザーを標本に日本のインターネット利用者の推定検索人数を算出しています。また、ワードの選定に当たっては、第4、5、6次「エネルギー基本計画」内で出現頻度が高かった「エネルギー関連ワード」を抽出し、これらのワードを検索している人が他に特徴的に検索している拡張エネルギー関連ワード20を抽出しました。その中でも、一定以上の検索人数がいるワードに絞り込み、各ジャンルへ振り分けを行うことをベースに整理し、検索数を確認した上で、一定量の検索数がないワードは採用しないこととしています21(検索データ出典:ヤフー・データソリューション)。
分野別の検索数における分析結果を時系列で見ると、政策変更や災害等があったタイミングで、対応する分野が伸びていることが分かります。例えば、電力小売全面自由化があった2016年4月には「電力自由化」(電力・ガスの制度・市場)の検索人数が大きく増えました。また、2018年9月の北海道胆振東部地震により北海道全域が停電した際や、2019年9月に令和2年台風15号により千葉で大規模停電が発生した時には「停電」(エネルギーレジリエンス)の検索人数が増えました。新型コロナウイルス感染症の影響で原油価格が大幅に下落し、米国のWTI原油先物が史上初めてマイナスを記録した2020年4月には、「エネルギー価格」の検索人数が増えました。直近では、菅内閣総理大臣(当時)が2020年10月に所信表明演説で2050年カーボンニュートラルを宣言して以降、「気候変動対応」の検索人数が継続的に増えています。特に、2021年10月末から11月中旬にかけて開催されたCOP26の影響で、2021年11月の検索人数が伸びています(第122-1-1)。
【第122-1-1】エネルギー政策に関するワードを検索した人数の推移

【第122-1-1】エネルギー政策に関するワードを検索した人数の推移(xls/xlsx形式71KB)
(2)分野別の動向
ここでは、今回整理した15分野のうち、特に検索人数や、その増減が大きかった分野を4つ選定し、その内訳を紹介します。
①気候変動対応
「気候変動対応」は、2020年まではCOPやパリ協定、ESG関連のワードが検索され、緩やかな増加傾向にありましたが、2020年10月以降、「カーボンニュートラル」の検索人数が急増しました。また、COP26が開催された2021年11月には「COP」の検索人数も大きく伸び、2020年末以降、国民が気候変動に関する関心を高めたことが定量的に示されています(第122-1-2)。
【第122-1-2】気候変動関連に関する検索人数の推移
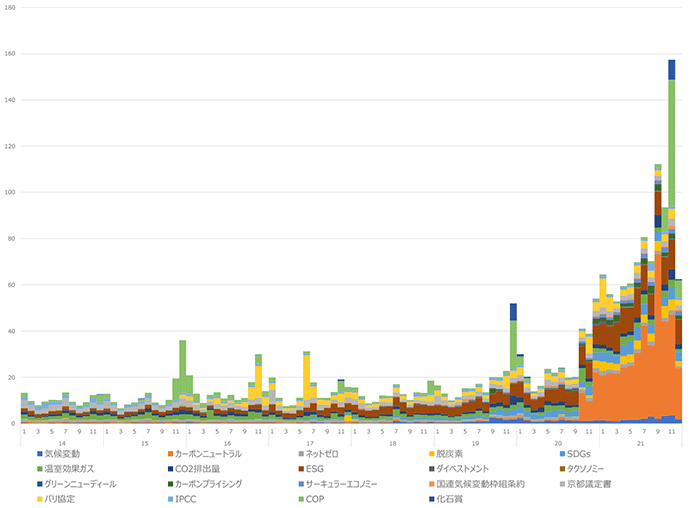
【第122-1-2】気候変動関連に関する検索人数の推移(xls/xlsx形式79KB)
②エネルギーイノベーション
「エネルギーイノベーション」は、2017年まではCO2回収・貯留(CCS)や核融合に関連するワードの検索が大多数でしたが、2017年以降「全固体電池」の検索人数が、またグリーン成長戦略の発表された2020年12月以降はエネルギーイノベーションの分野全体の検索人数が伸びました(第122-1-3)。
【第122-1-3】エネルギーイノベーションに関する検索人数の推移
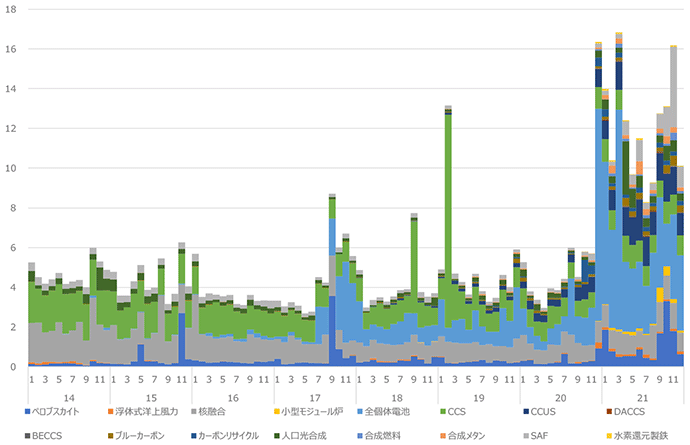
【第122-1-3】エネルギーイノベーションに関する検索人数の推移(xls/xlsx形式59KB)
③エネルギー価格
「エネルギー価格」は、その時々の原油・天然ガス・ガソリン価格に連動して検索数も上下する傾向にあります。特に直近では資源高の影響で、ガソリン価格に関連するワードの検索数が特に増加しています(第122-1-4)。
【第122-1-4】エネルギー価格に関する検索人数の推移
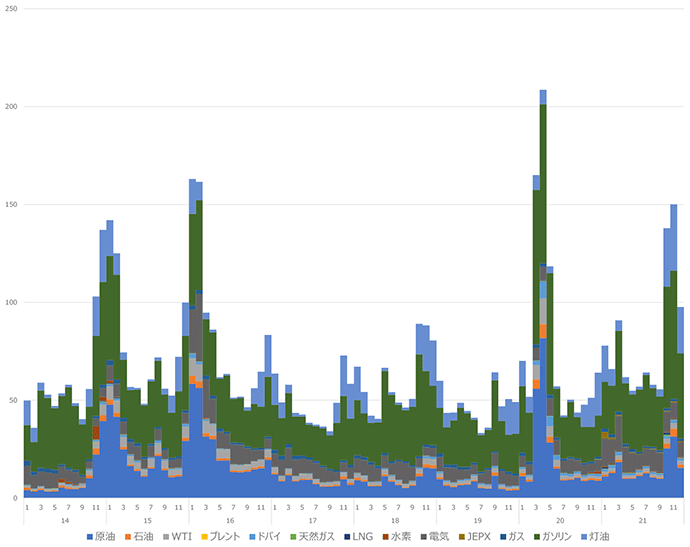
【第122-1-4】エネルギー価格に関する検索人数の推移(xls/xlsx形式63KB)
④発電方法
「発電方法」は、一貫して太陽光発電に関する検索人数が一番多く、次いで、原子力発電の検索人数が多くなっています。また、近年では風力発電関連やアンモニア発電についての検索人数が増加しており、再生可能エネルギーや新燃料による発電方法への関心が高まっていることが分かります(第122-1-5)。
【第122-1-5】発電方法に関する検索人数の推移
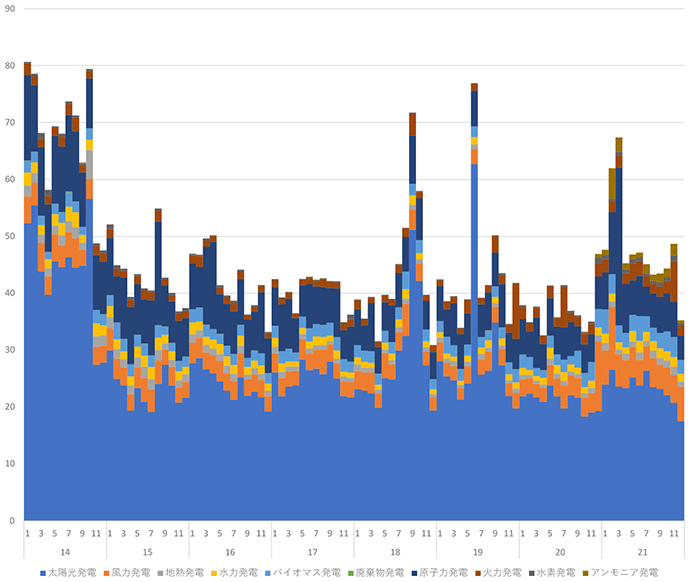
【第122-1-5】発電方法に関する検索人数の推移(xls/xlsx形式53KB)
(2)世代別の傾向
①全体の動向
各分野について、全世代平均を100とした場合に、各世代でどの分野の検索数が多いのかを見ると、10代と20代では、多くの分野で全世代平均である100を下回っており、エネルギーに関する関心が相対的に低いことが見て取れます。特に「エネルギー価格」と太陽光発電や風力発電を含む「発電方法(再エネ・新燃料)」分野では、10代と20代の検索数が、30代以上の検索数と比べ大きく下回っていることが特徴的です。大まかな傾向としては、30代、40代、50代の検索数が他の世代に比べ多くなっており、特に、仕事(エネルギーイノベーション、電力・ガスの制度・市場等)や生活(省エネルギー関連、エネルギー価格等)に関連する分野で検索数が特徴的に多い傾向が見受けられました(第122-1-6)。
【第122-1-6】世代別のエネルギーに関するワードの検索傾向(2021年)
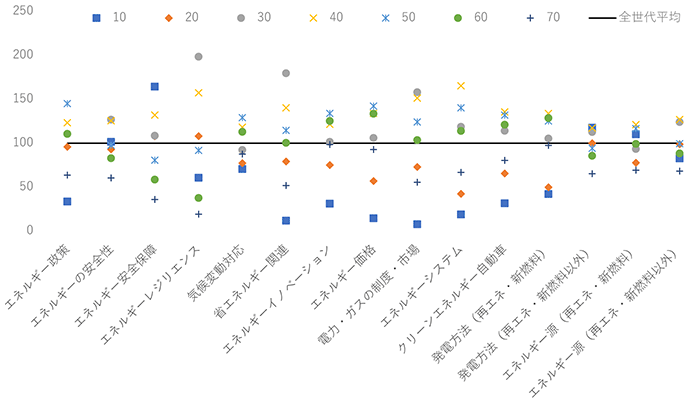
【第122-1-6】世代別のエネルギーに関するワードの検索傾向(2021年)(xls/xlsx形式27KB)
②3E(Energy security、Economic efficency、Environment)の視点における世代別の検索動向
ここからは、3Eの視点から、世代別の検索動向の推移を見ていきます。世代ごとに人数が異なることから、インターネット人口1万人あたりで基準化して、人数を示しています。
(ア)Energy security(「エネルギー安全保障」+「エネルギーレジリエンス」)における世代別の検索人数の推移
「エネルギー安全保障」と「エネルギーレジリエンス」の2分野の検索数を合算した値を、年代別に見ると、60代以上は検索人数が少なく、相対的な関心が低いと考えられる一方、20代以下と30代〜50代では検索数が多く、相対的な関心が高いと考えられます。また災害があったタイミング等に検索数が大きく伸びる一方、過去8年で検索数が伸びていく傾向は見られず、一過性の関心にとどまっています(第122-1-7)。
【第122-1-7】世代別検索人数の推移(エネルギー安全保障+エネルギーレジリエンス)(1万人あたり)
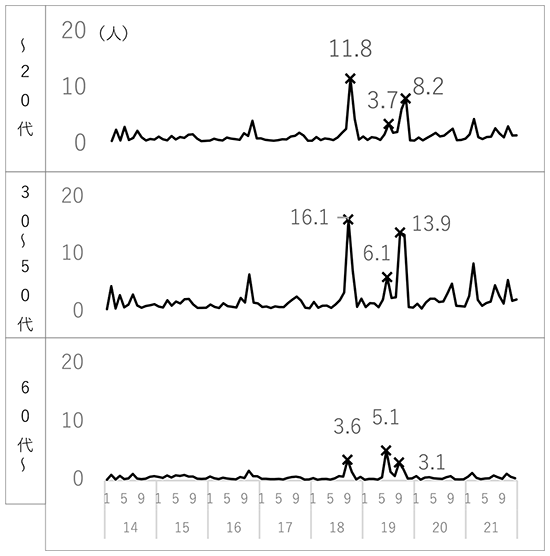
【第122-1-7】世代別検索人数の推移(エネルギー安全保障+エネルギーレジリエンス)(1万人あたり)(ppt/pptx形式:186KB)
【第122-1-7】世代別検索人数の推移(エネルギー安全保障+エネルギーレジリエンス)(1万人あたり)(xls/xlsx形式133KB)
(イ)Economic efficency(「エネルギー価格」+「電力・ガスの制度・市場」)における世代別の検索数の推移
「エネルギー価格」と「電力・ガスの制度・市場」の2分野の検索数を合算した値を、年代別に見ると、電力小売全面自由化があった2016年4月には30代以上において検索数が大きく伸びましたが、10代、20代では検索数の伸びは大きくなく、相対的な関心が低かったと考えられます。これは、10代を中心に家族と同居していることから、自らの収入から電力料金を支払っていない層が一定程度おり、相対的な関心が低いためだと考えられます。また、新型コロナウイルス感染症の影響で、WTI原油先物価格が史上初めてマイナスを記録した2020年4月には、職業に就いている層の多い30代〜50代で特に検索数が伸びました。また、制度変更や国際的な事象があったタイミングで検索数が大きく伸びる一方、過去8年で検索数が伸びていく傾向は見られず、一過性の関心にとどまっています(第122-1-8)。
【第122-1-8】世代別検索人数の推移(エネルギー価格+電力・ガスの制度・市場)(1万人あたり)
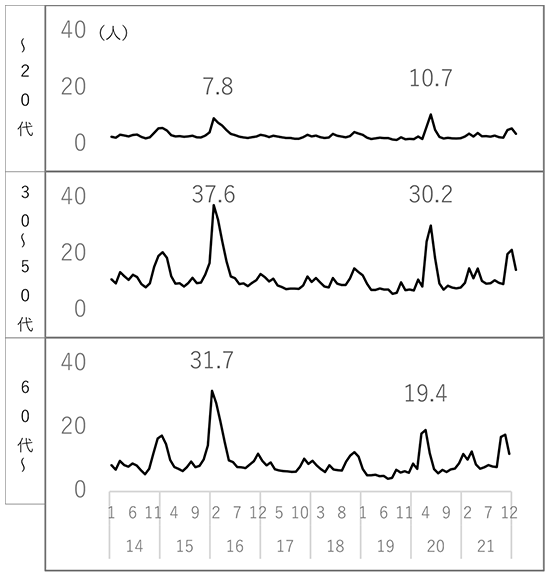
【第122-1-8】世代別検索人数の推移(エネルギー価格+電力・ガスの制度・市場)(1万人あたり)(ppt/pptx形式:50KB)
【第122-1-8】世代別検索人数の推移(エネルギー価格+電力・ガスの制度・市場)(1万人あたり)(xls/xlsx形式133KB)
(ウ)Environment(「気候変動対応」)における世代別の検索数の推移
「気候変動対応」については、時系列で見ると、2020年秋以降、右肩上がりで検索数が伸びる傾向が見てとれます。特に60代以上において第6次「エネルギー基本計画」におけるパブリックコメントが募集されていた9月の検索数が多い一方で、30〜50代、20代と年代が若くなるにつれて検索人数が減少する傾向にあります。また、COP26が開催された11月には、各年代で満遍なく多くの検索がされていたことが分かります(第122-1-9)。
【第122-1-9】世代別検索人数の推移(気候変動対応)(1万人あたり)
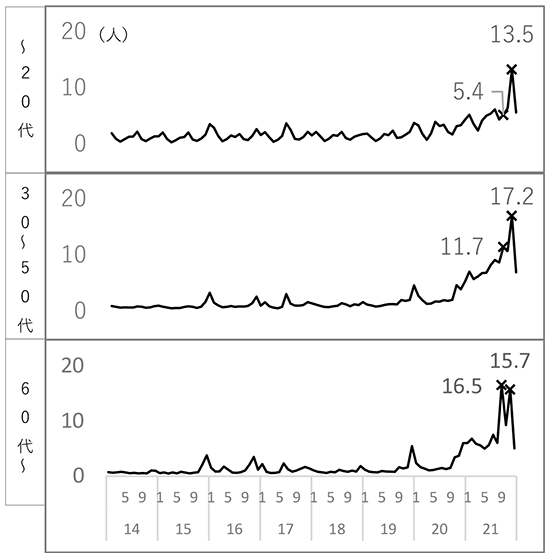
【第122-1-9】世代別検索人数の推移(気候変動対応)(1万人あたり)(ppt/pptx形式:49KB)
【第122-1-9】世代別検索人数の推移(気候変動対応)(1万人あたり)(xls/xlsx形式132KB)
今回の分析は、エネルギー政策やエネルギー情勢への国民の関心度合いとその動向について、あくまで一面ですが、定量的な把握を試みました。こうしたデータも踏まえて、日本のエネルギー事情の全体像について国民各層が理解を更に深めていけるよう、政府としても、資源エネルギー庁ホームページの「スペシャルコンテンツ」やパンフレットなどの各種媒体を始めとして、科学的知見やデータに基づいた客観的で多様な情報提供を続けるとともに、エネルギーに関する基礎用語、最新の動向やトピックなど政策に関連する情報をできる限り分かりやすく丁寧に発信していきます。
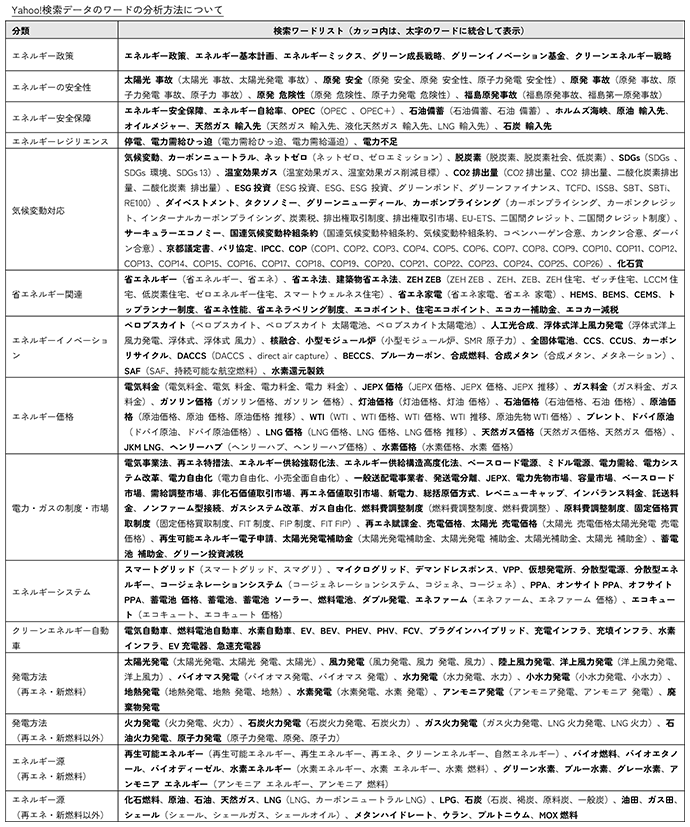
各ワードは、同じものを意味する軽微な違いを一つにまとめるグループ化を行っています。第122-1-1から第122-1-9までのグラフは、内包される各ワードの完全一致検索人数を足し上げたり、複数分類の人数を足したのべ人数を用いてグラフ化しています。(検索データ出典:ヤフー・データソリューション)
2.クリーンエネルギー戦略の検討状況
岸田内閣総理大臣は、2021年12月6日の所信表明演説で、エネルギーの供給側のみならず、需要側のイノベーションや設備投資等、需給両面を一体的に捉えた「クリーンエネルギー戦略」の策定を表明しました。また、2022年1月18日の「クリーンエネルギー戦略」に関する有識者懇談会では、「クリーンエネルギー戦略」の策定について、具体的な指示がありました。
取りまとめを担う経済産業省22では、クリーンエネルギー戦略検討合同会議23を開催し、検討を進めています。また、環境省、金融庁、国土交通省、農林水産省、文部科学省、外務省、内閣府等の各府省においてもそれぞれの担当分野から検討を進めています。
これまで政府は、2021年6月に「グリーン成長戦略」を策定、2021年10月には第6次「エネルギー基本計画」を閣議決定しました。その中で、2050年カーボンニュートラルや2030年度の野心的な温室効果ガス削減目標の実現に向けた産業政策やエネルギー政策を示してきました。こうした野心的な削減目標に向けて、着実な移行(トランジション)を行うための具体的な筋道を示すことが、「クリーンエネルギー戦略」の目的の一つです。そのために、単にエネルギーの供給構造のみならず、産業構造、国民の暮らし、地域のあり方全般にわたる幅広い取組が必要であり、多くの論点に方向性を見出すべく検討を進めています。
ここでは、「クリーンエネルギー戦略」で重点を置いているエネルギーの需要側について、検討の視座を紹介します。
【第122-2-1】「クリーンエネルギー戦略」の概念図
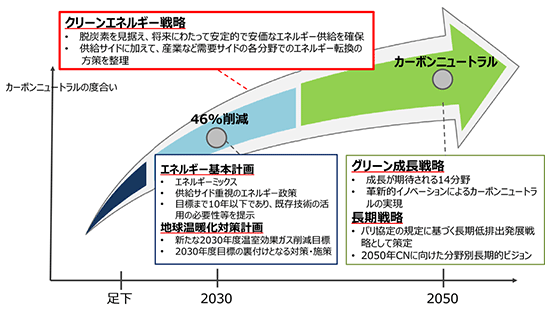
【第122-2-1】「クリーンエネルギー戦略」の概念図(ppt/pptx形式:76KB)
(1)エネルギーの需要側の動向
①産業部門
産業部門は、日本の最終エネルギー消費全体の61.9%を占め、うち製造業は全体の42.1%を占めています24。製造業の中では、化学工業(含 石油石炭製品)、鉄鋼、窯業土石(セメント等、紙・パルプで多くのエネルギーを消費しています(第122-2-2)。
【第122-2-2】産業別のエネルギー消費量(2020年)
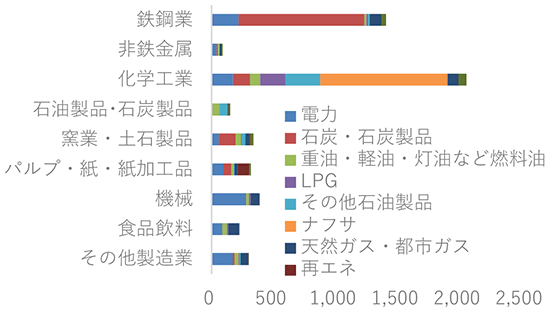
【第122-2-2】産業別のエネルギー消費量(2020年)(xls/xlsx形式32KB)
日本のGDPに占める製造業の産出量の割合は、国際比較可能な2019年で23%と主要国の中では高い水準にあるため、製造業の脱炭素化は日本経済全体の脱炭素化にとっても大きな課題であることが分かります(第122-2-3)。
【第122-2-3】主要国の製造業比率とエネルギー消費量(2019年)

製造業のエネルギー消費は大きく電力と熱の2つに分けられます。電力については、電力事業者が電源の脱炭素化を進めれば、系統から電力を購入している製造業の脱炭素化も反射的に進みます。また、個々の企業が工場等に自家発電の太陽光発電を導入したり、再エネ由来J-クレジットや非化石証書等を購入することでも進展します。
製造業の中でも、製造プロセスの特質上、大量の電力と熱を利用する鉄鋼、化学等では、自家発電の量が相当程度を占めており、これを低炭素化・脱炭素化していくことも重要です。石炭火力発電を比較的CO2排出量の少ないガス火力発電にリプレースすること、今は単純に焼却されているエネルギーである廃棄物を利用した発電を利用すること、水素・アンモニアを混焼すること等が挙げられます。ゆくゆくは、排出されたCO2に対してCCUSを行うこと、水素・アンモニア・合成メタンを専焼で利用すること等も選択肢に入ってきます。
熱については、各企業の脱炭素化に向けた取組が重要になります。ただし、熱といってもそのありようは多様です。鉄鋼では、鉄鉱石を溶解するために高炉で石炭を燃焼させて約2,000℃の高温を活用する一方で、食品飲料では、冷凍保存のため氷点下の温度が必要です。熱源が化石燃料である場合は、水素・アンモニアといった脱炭素燃料に置き換えていくことが必要になります。また、電化困難な高温部分以外は、電力が脱炭素化されていくことを前提に、電化していくことも有効です。
2020年の産業部門の最終エネルギー消費ベースでの電力の比率は21%であり(第122-2-3)、更なる電化の余地は大きいと考えられます。具体的には、200℃以下の熱需要をヒートポンプで賄ったり、製鉄手段を高炉から電炉に切り替えていく、といったことがあります。
国内における低炭素化・脱炭素化に技術的な限界がある場合、それでも脱炭素を徹底していくならば、エネルギー多排出産業のうち特にエネルギー効率が低く、しかも低付加価値な汎用品製造業を、再エネやCCSを安価に利用できる外国に移転させることも選択肢となり得ます。ただし、これは良質な雇用の維持の観点や、日本国内にサプライチェーンを有することによる技術・イノベーション力維持の観点からの熟慮が必要です。また海外との分業が深まるため、製品の消費地まで運ぶ必要が生じ、運輸部門の脱炭素化が進まなければ温暖化の観点でもデメリットが生じる可能性もあります。さらに、CO2排出規制が日本より緩い外国に産業が移転することで、低炭素化の取組が遅れ、かえって世界全体のCO2排出量が増加してしまうという、いわゆる「カーボンリーケージ」を引き起こしては本末転倒です。エネルギー政策の立案においては、このような点も含め、総合的な検討が求められます。
②家庭部門
家庭部門についても触れておきます。家庭部門の最終エネルギー消費は、全体の17.3%を占めます。地域別に最終エネルギー消費の内訳を見ると、北海道では冬季の暖房需要で灯油・軽油が57%を占める、南関東や近畿では都市ガスが30%台半ばを占める、沖縄では電力(63%)とLPガス(24%)の消費が多い等、地域ごとにエネルギー消費に特色があることが分かります(第122-2-4)。
【第122-2-4】地域別の家庭のエネルギー消費(2019年度)
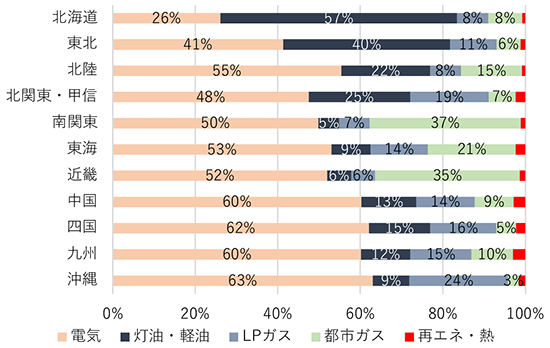
【第122-2-4】地域別の家庭のエネルギー消費(2019年度)(xls/xlsx形式38KB)
- 資料:
- 都道府県別エネルギー消費統計より経済産業省作成
(2)国際的なエネルギーコストの動向(RUEC)
①理論的背景
脱炭素に向け、エネルギー源を転換させていくタイミングでは、大規模な投資が必要となり、世界全体でエネルギーコストが高まる可能性があります。脱炭素に向けて官民を挙げて積極的な行動をとり、「経済と環境の好循環」を実現するためには、脱炭素を単にコストとしてのみ捉えるべきではありません。しかし、GHG排出という外部性を内部化していく過程では生産性が低下しますが、その要因を分解して整理し、その推移に応じて政策措置を講じていくことで、脱炭素と国際的な産業競争力とを両立することも可能になります。
具体的には、実質単位エネルギーコスト(英語では「Real Unit Energy Cost」。以下「RUEC」という。)という概念を用い、長期的なデータで、エネルギー価格の上昇に対する日本経済の脆弱性を、米国と比較しながら見ていきます25。なお、RUECは、2014年に欧州委員会が1995年以降のエネルギーコストの上昇に対する対応を検討するために用いた概念です。2014年の欧州委員会のレポートでは、欧州、米国、日本、ロシア、中国のRUECを比較しています26。
RUECの概念を理解するため、コストの概念を3つの段階で分けて見ていきます。
まず第1段階として、日米の「名目エネルギー価格(PE)」の推移を確認します(第122-2-5)。このグラフでは、2011年の米国を1と基準化して表示しています。日本の名目エネルギー価格は米国と比べ一貫して高く、2012年にピークとなる2.1倍を記録して以降、やや下落しましたが、足下では上昇傾向です。日本の名目エネルギー価格を対米国比で見ると、1995年までは差が拡大する傾向にありましたが、同年にピークとなる3.3倍を記録して以降、縮小する傾向に転じています。
【第122-2-5】名目エネルギー価格の推移の日米比較
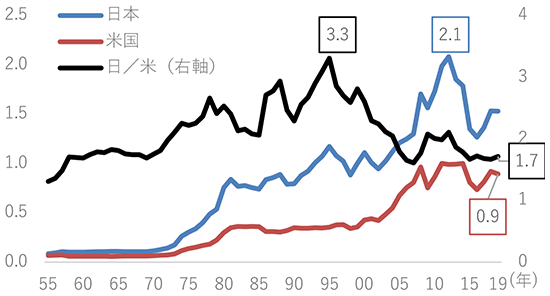
【第122-2-5】名目エネルギー価格の推移の日米比較(xls/xlsx形式52KB)
第2段階として、名目エネルギー価格を一般物価(経済全体の物価)で除した「実質エネルギー価格(PE/PX)」の推移を見ていきます(第122-2-6)。名目エネルギー価格が上昇しても、一般物価が上がっていれば、各国経済にとってエネルギーコストの問題は相対的に小さくなります。また、一般物価が上がっているときには、大まかに見て名目エネルギー価格の上昇を転嫁できている、という解釈も可能でしょう。日本の実質エネルギー価格の関係を見ると、2011年まで長期的に差が縮小していきましたが、同年に底となる1.5倍を記録してからは拡大に転じています。
【第122-2-6】実質エネルギー価格の推移の日米比較
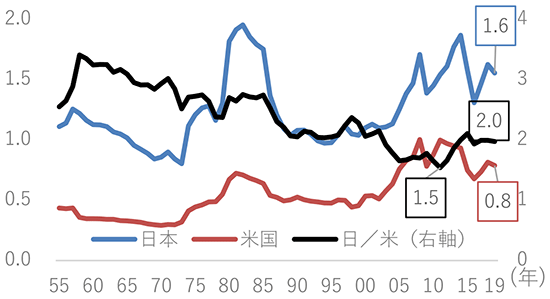
【第122-2-6】実質エネルギー価格の推移の日米比較(xls/xlsx形式52KB)
第3段階として、実質エネルギー価格をエネルギー生産性で除したもの((PE/PX)/(X/E))、すなわちRUEC27の推移を見ていきます(第122-2-7)。このグラフでは、2011年の米国を1と基準化して表示しています。実質エネルギー価格が高くなっても、エネルギー生産性が高ければ、つまり少ないエネルギーで多くの付加価値を生み出せれば、各国経済にとってエネルギーコストの問題は更に相対的に小さくなります。このため、エネルギーコストの上昇に対する経済全体の耐性を評価するには、名目エネルギー価格の変動だけでなく、一般物価、エネルギー生産性を考慮したRUECで評価することが適切です。日本のRUECを対米国比で見ると、1980年代以2011年までは米国に遜色ない水準を維持していましたが、2012年以降は米国に差を広げられ、戦後最も格差が広がった1960年代の水準に近づいています。
【第122-2-7】RUECの推移の日米比較
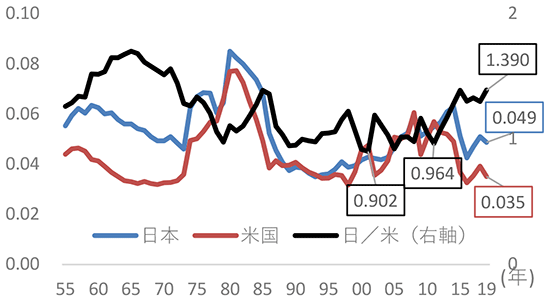
【第122-2-7】RUECの推移の日米比較(xls/xlsx形式52KB)
②エネルギーコストの要因分解
RUECの対米国比を実質エネルギー価格とエネルギー生産性に分解することで、RUECの動きの背景を分析します(第122-2-8)。まず、日本の実質エネルギー価格は、2012年から上昇し、原油価格の下落などで2014〜2016年には低下しましたが、足下では再び上昇傾向となり、高止まりしています。この要因の一つとして、日本で同年、FIT制度が導入され、設備容量の急速な伸びに伴って買取費用の総額が伸びたこと等により電力料金が上昇したことや、物価上昇が引き続き鈍いこと等により、実質エネルギー価格が高くなったことが考えられます。一方、米国では、2005年以降本格化したシェールガスの増産によって燃料価格が低下したことや、物価水準がエネルギー価格と比べ相対的に上昇していること等から、実質エネルギー価格が低くなったことが考えられます。
【第122-2-8】RUECの日米比較の要因分解
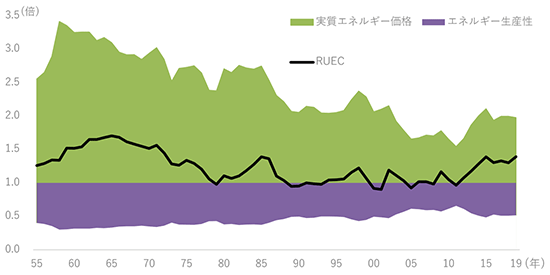
【第122-2-8】RUECの日米比較の要因分解(xls/xlsx形式40KB)
次に、日本のエネルギー生産性は、一貫して日本の方が優位にあり、1980年代までは米国の2倍以上の生産性を見せましたが、2000年代以降はその優位性が縮小し、足下では約1.4倍となっています。この要因としては、シェールガス等により米国ではエネルギーコストの上昇が日本よりも抑えられていたことがあります。また、日本ではオイルショックを契機に省エネ政策を強力に進め、過去50年で約4割のエネルギー効率改善を実現したものの、1980年代後半以降は効率が伸び悩んできたこともあります。さらには省エネ余地が日本より大きかった米国でエネルギー効率の改善が近年大きく進んできたこと等も考えられます。なお、ここで言うエネルギー生産性は、産業構造の差異を考慮していません。つまり、エネルギー多消費産業の海外移転が生じると、ここでのエネルギー生産性の指標は改善したかのように見えてしまうため、それが高いことが必ずしも良いとは限りません。実際、製造業の海外移転が進んでいる日本の優位性の実態は、縮小してなお過大に見えている、とも言えます。
③政策的な含意
脱炭素に向け、エネルギー源を転換させていくタイミングでは、大規模な投資が必要となり、日本においてもエネルギーコストが高まる可能性がありますが、国際的な産業競争力を損なわないよう配慮する必要があり、これを把握する定量的な手法の一つとしてRUECによる分析を紹介しました。
RUECを改善するためには、①エネルギー価格を低く抑えていくことと、②エネルギー生産性を高めることの2つの方法がありますが、日本のRUECの絶対値だけにとらわれず、海外のRUECと比較し、①、②のどちらにより大きな課題があるのかを見極めながら取り組むことが重要です。
なお、②エネルギー生産性については、2050年カーボンニュートラルを実現するには、特に産業部門においてさらなる省エネを実現していかねばならない一方で(第3章第1節参照)、日本は石油危機以降省エネの取組を強力に進めた結果、その余地が国際的に見て相対的に小さくなっている可能性を考えると、更なる省エネの実現に向けてどのような取組が効果的なのか、継続的に検討を深めていく必要があります。
COLUMN
GXリーグの設立
「2050年カーボンニュートラルと整合的で、野心的な目標として、2030年度に、温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指し、更に50%の高みに向けて挑戦を続ける。世界全体のカーボンニュートラル達成に向けて日本が掲げるこの目標は、並大抵の努力で達成できるものではありません。製品・サービスの脱炭素化や大胆な投資によるイノベーションの創出といった企業の行動変容だけでなく、生活者の意識・行動の変容まで含めて、社会経済全体が大きく変わっていく、グリーントランスフォーメーション(GX)の実行が求められます。
気候変動対策を企業にとっての成長に着実につなげるためには、企業による炭素削減の取組が正当に評価されるためのルールが必要です。例えばEUでは、十分な削減努力が行われていない国からの輸入品に対し、課徴金を賦課する規制(国境調整措置)を導入する検討が進んでいますが、そういった欧州政府による規制だけでなく、海外のNGO/NPO、民間企業連合によるルール形成も先行し、「デファクト→デジュール」の更なる流れも加速しています。
こうしたルールは、国際的にビジネスを行う日本企業にも無関係ではありません。それらのルールが先行して適用され、これを受け入れた場合、日本企業がこれまでと同じ競争条件でビジネスを続けられるとは限りません。
国際的にルールが定まってからの「受け身」では、日本企業の持つ強み(削減貢献効果の高い製品等)が活かされない懸念があります。日本からも、世界に対してルールを提案していくような、カーボンニュートラルに向けた新たなリーダーシップが求められています。
こうした背景の下で、経済産業省は、2050年カーボンニュートラル実現と社会変革を見据えて、GXへの挑戦を行い、現在及び未来社会における持続的な成長実現を目指す企業が同様の取組を行う企業群や官・学と共に協働する場として、2023年度に「GXリーグ」を立ち上げるための準備を進めています。
本年2月1日公表した「GXリーグ基本構想」に対しては、CO2を多く排出する産業も含め、幅広い業種から440社が賛同の立場を表明しています。これらの企業の排出量の合計を試算すると、日本全体の排出量の約28%をカバーする規模になります28。
GXリーグは、三つの場の提供と参画企業のリーダーシップを通じて、カーボンニュートラルに向けた社会構造の変革のための価値を提供することを目指します。その三つの場とは、①カーボンニュートラルとビジネス機会の創出ととらえる業界を超えた対話を行う「未来社会像対話の場」、②将来の健全な市場を民と官で創造するための共創を行う「市場形成ルールの場」、③GX投資とGHG削減を社会に対して開示するために実践する「自主的な排出量取引の場」です。
①「未来社会像対話の場」では、2050年カーボンニュートラルの未来像及びそこに至る移行像を「対話」を通じて創造します。業種を超えた自由な対話・ワークショップ形式での議論を通じ、2050CNにおけるGX企業にとってのビジネス機会やGX企業としてのリーダシップ(行動指針)といった項目を提示します。
②「市場形成ルールの場」では、①における議論も踏まえつつ、そういった未来像・ビジネス機会も踏まえた新たな市場創造のための官民によるルール形成に挑戦するものです。これらの取組を通じて得た議論の成果は、国内外へのイニシアチブとしての発信や国際標準化、政府による国内制度化等を目指します。
③「自主的な排出量取引の場」では、企業が自ら2030年に向けた野心的な排出量削減目標を掲げ、その達成に向けた毎年の取組状況の開示を行い、目標に達しない場合はカーボンクレジット市場を通じた自主的なクレジットの取引を行います。この場を通じて、GX企業による削減に向けた取組と投資を開示することで、資本市場・労働市場・消費市場からGX企業が評価される環境の構築を目指します。
「GXリーグ」の立ち上げに向けて、これらの場の構築を進めていくべく、2022年度を準備期間と位置づけて、4月から賛同企業の皆さまと共に、具体的なコミュニケーションと議論を開始しています。
- 18
- 温室効果ガス46%削減(2013年度比)を目指すこと、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けることを表明しています。
- 19
- エネルギー政策、エネルギーの安全性、エネルギー安全保障、エネルギーレジリエンス、気候変動対応、省エネルギー関連、エネルギーイノベーション、エネルギー価格、電力・ガスの制度・市場、エネルギーシステム、クリーンエネルギー自動車、発電方法(再エネ・新燃料)、発電方法(再エネ・新燃料以外)、エネルギー源(再エネ・新燃料)、エネルギー源(再エネ・新燃料以外)の15分野。
- 20
- Yahoo! JAPANで検索した全ユーザーと、エネルギー関連ワードを検索したユーザーを同数と考えた場合、エネルギー関連ワードを検索したユーザーの方がより多く検索しているワード群を指します。
- 21
- 詳細な分析方法は、本節末にて解説しています。
- 22
- 令和4年1月18日「クリーンエネルギー戦略に関する有識者懇談会」における岸田総理大臣指示。
- 23
- 正式名称は、「産業構造審議会 産業技術環境分科会グリーントランスフォーメーション推進小委員会/総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 2050年カーボンニュートラルを見据えた次世代エネルギー需給構造検討小委員会合同会合」。
- 24
- 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計(速報)」。
- 25
- 本稿のRUECの分析(第122-2-5から第122-2-8)は、野村浩二氏の著書(「日本の経済成長絵とエネルギー経済と環境の両立はいかに可能か」(慶應義塾大学出版会、2021年))、野村浩二氏がクリーンエネルギー戦略検討合同会合(第5回、2022年3月23日)で説明した資料及び同氏から提供を受けたデータに基づいています。なお、データの解釈は、経済産業省によるものです。
- 26
- European Commission(2014)“Energy Economic Developments in Europe” European Economy 1. January 2014
- 27
- 単位エネルギーコスト(E/X)を名目表示したものが名目単位エネルギーコスト(英語では「Nominal Unit Energy Cost」。以下「NUEC」という。)で、PEE/Xであり、これを実質化したものが、RUEC=NUEC/PX=(PEE/X)/PXであります。これを式変形すると、(PE/PX)/(X/E)になります。
- 28
- 温対法に基づく数値は、電力等の2次エネルギー消費に伴う排出量が計上されている一方で、他社に2次エネルギーを供給した分の排出量については除いた数値となっています。そのため、賛同企業から一般家庭・賛同外企業に供給された2次エネルギーに伴う排出量を含まない値となっており、家庭部門等への電力供給に伴う排出を加味すると日本全体の排出量に占める割合は4割以上と見込まれます。