第1節 新型コロナウイルス感染症がエネルギー需給に与えた影響
新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)は、経済活動や国民生活に大きな影響を及ぼしています。2020年1月に日本で初めての感染者が報告され、3月に世界保健機関(WHO)が世界的流行を宣言した後、4月7日に日本で初めての緊急事態宣言による行動制限が始まると、テレワークやオンライン授業など外出を伴わない生活様式が拡大し、人や物の移動が制限されたことで、外食、旅行、娯楽等を中心とした需要面での落ち込みや、生産拠点の閉鎖等の供給面での停滞に伴い、経済全体が大きなダメージを受けました。
エネルギーについても、世界的な行動制限や渡航制限に伴ってガソリンや航空燃料等の急激な需要減が生じ、産油国間の協調減産の決裂等から、2020年4月には原油先物価格が史上初めてマイナス価格を記録しました。2020年のエネルギー需要は2019年に比べ4%下落しましたが、2020年後半以降は、ワクチン接種の拡大や各国政府による経済刺激策を通じた経済活動の拡大により世界のエネルギー需要は急激な回復を見せました。しかし、天然ガスや石炭等の価格は過去最高水準に達し、エネルギー分野に大きな混乱を生じさせています。
本稿では、いまだに影響が続く新型コロナがエネルギー面でどのような影響を与えたのか、新型コロナ前の2019年、新型コロナの影響が大きかった2020年、回復の傾向が見られる2021年の比較を中心に整理します。
1.新型コロナが世界のエネルギー動向に与えた影響
(1)エネルギー需要全体の動向1
2020年の世界のエネルギー需要は2019年に比べ4%減少し、第二次世界大戦以降最大の下落幅を記録しました。2021年には世界的な経済活動の回復に伴ってエネルギー需要も全体として2019年の水準を2%超えることが見込まれていますが、運輸部門では旅客用航空機燃料の需要回復が鈍いこと等から2019年の水準には届かない見通しです。CO2排出量は、2020年に2019年比で5.8%減少した後、2021年には化石燃料の需要増により4.8%増える見通しですが、過去最高となった2019年に比べると1.2%低い水準にとどまる見通しです。
【第131-1-1】世界の実質GDP、エネルギー需要、CO2排出量の推移(2019年比)
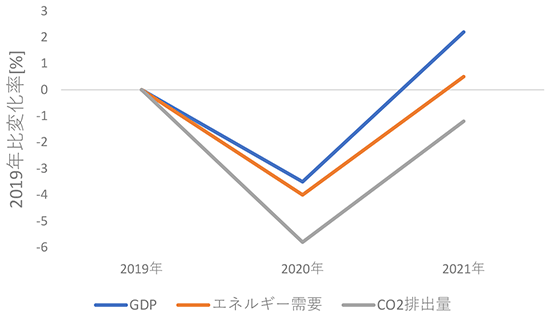
【第131-1-1】世界の実質GDP、エネルギー需要、CO2排出量の推移(2019年比)(xls/xlsx形式27KB)
- 資料:
- IEA「Global Energy Review 2021」より経済産業省作成
(2)エネルギー源ごとの動向
世界のエネルギー需要をエネルギー源ごとに見ると、2020年と2021年でそれぞれの燃料と電力が以下のような影響を受けたことが分かります。
①原油
原油需要は、2020年に2019年比で8.8%減少しました。特に、原油需要の60%を占める運輸部門の需要動向が大きな影響を与えています。2020年の航空用燃料の需要は、旅客数が2019年比66%減したことに伴い41%減少し、ガソリン需要は12%減少、船用燃料油需要は国際貿易の減少で8%減少しました。
移動制限の緩和等に伴い、2021年の原油需要は2020年に比べ6%回復する見込みですが、それでも2019年に比べ3.2%減と、新型コロナ前の水準には届かない見通しです。国際航空以外の燃料需要は2021年12月には2019年の水準に戻りましたが、国際航空燃料需要は2019年に比べ20%減となったことが影響しました。国別に見ると、2020年に主要国が軒並み原油需要を減らす中で、唯一2019年の原油需要を上回った国は、中国でした。
②石炭
石炭需要は、2020年に2019年比で4%減少し、第二次大戦以降で最大の落ち幅となりました。石炭需要の減少の4割は電力部門が占めており、経済停滞に伴う電力需要の減退のほか、ガス価格の下落で欧州と米国で石炭火力のガス転換が発生し、それぞれ20%、21%の石炭使用が減少したことが影響しました。そのほか、経済停滞に伴う鉄鋼やセメントの原料炭需要の減少も影響しました。
一方、2021年には石炭需要が2020年比で4.5%増となり、2019年水準を超える見通しです。その4分の3は電力部門の需要増によるもので、2021年後半以降のガス価格の上昇によって欧米でガスから石炭への燃料転換が発生したことが要因とされています。
国別に見ると、石炭需要が2020年、2021年とも続けた伸びた唯一の主要国は中国でした。石炭の世界需要の3分の1は中国が占めており、中国の動向が世界需要に大きな影響を与えます。
③ガス
ガス需要は、2020年に2019年比で1.9%減となりましたが、その減少幅は石炭、石油ほど大きくはありませんでした。その一因は米国、欧州で見られた燃料転換です。米国では、電力全体の需要は減る一方、ガス発電需要は年2%減少し、欧州でもガス価格の下落と炭素価格の上昇により、比較的GHG排出量の少ないガス火力への需要が増えました。国別に見ると、2020年には中国、韓国、インドでは需要が増加する一方、ロシアや中東では減少しており、国・地域によって傾向が異なりました。
2021年のガス需要は、2020年比で3.2%増加し、2019年水準を超える見通しです。国別に見ると、欧州は2019年水準に戻りますが、米国は2019年水準に届かない見通しです。一方、アジアは2021年には2020年比で7%増、2019年比では8.5%増となる見通しです。アジアでは中国の影響が大きく、2021年には2019年比で14%増となる見通しです。
ガスの用途別内訳の動向を見ると、2021年には産業用需要が貿易回復に伴って5%増え、建築物の暖房用需要も低い気温に伴い5%伸びる見通しです。一方、発電用ガス需要は、電力需要全体が伸びていないことや、再エネや石炭との代替の影響で、1%成長にとどまる見通しです。
④再生可能エネルギー
他の燃料種がすべて減少となる中、再エネは2020年に2019年比で3%増となりました。これは、電力部門における再エネ需要が7%増加したことが影響しています。
2021年には、電力部門の再エネ需要は2020年比で8%増が見込まれており、1年当たりで見ると、1970年代以降最も大きな増加幅となる見通しです。その増分のほぼ半分は中国におけるものであり、米国、欧州、インドがこれに続く見通しです。
2021年の再エネ電力のうち、最も大きく伸びるのは風力であり、2020年比で17%増が見込まれています。これは、中国と米国で2020年末を政策的な期限として記録的な量の風力発電設備の増強に取り組んでいることが要因となっています。太陽光も2020年比で18%増が見込まれているほか、水力についても中国やアジアで大きく伸びる見通しです。
⑤電力
電力需要は、2020年前半の都市封鎖に伴う行動制限に伴う需要減により、2019年比で1%減となりました。都市封鎖による影響を見るため、気象条件の差を考慮した比較をすると、2019年同月に比べ、2020年2月には中国や米国で約10%の電力需要が減少しました。3〜4月には、ドイツ、フランス、米国で15%減、スペインとイタリアは25%以上の減少となりました。インドについては、3月半ば〜4月末で2019年比で20%減、日本と韓国は5月に8%減となりました。
【第131-1-2】世界全体の電力需要における新型コロナの影響
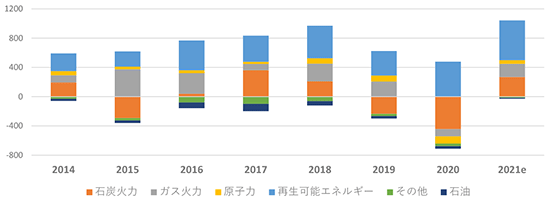
【第131-1-2】世界全体の電力需要における新型コロナの影響(xls/xlsx形式30KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Outlook 2021」より経済産業省作成
2021年の電力需要は、経済活動の回復に伴い2020年比で4.5%増となる見通しです。主に新興国が主導しており、中国は2021年に2019年比で12%増、東南アジアは同3%増となる見通しです。先進国についても2020年比で2.5%増、2019年比でも1%増と需要が回復する見通しです。国別に見ると、米国では2021年に2020年比で約2%増え、2019年の水準を1.6%超える見通しです。ドイツ、フランス、イタリア、スペインでは2021年に2020年比で3%増となりますが、2020年に2019年比で4〜6%減少していることから、2019年水準には達しない見通しです。日本も2021年は1%成長していますが、2020年に4%減しており、2019年水準を回復するには至らない見通しです。
電力供給の内訳を見ると、2020年は石炭が4.4%減と最も落ち込んでおり、このうちの半分は安いガス価格による米国のガス転換、残り23%は欧州の燃料転換で説明できます。安価なガスにより、米国では石炭火力発電が20%減少する中で、ガスは2%減にとどまりました。一方、2021年には、石炭が最大の増加となる見通しです。2021年後半のガス価格の上昇に伴ってガスは2020年比で1%増にとどまる一方、米国では2020年に減少した石炭火力の半分が戻ることや、中国で2020年比8%の電力需要増が生じる中でその約半分を石炭火力で賄うこと、インドでも電力需要増の7割を石炭火力で賄うことが影響しています。原子力は、2020年に2019年比で4%減となりました。その内訳は、欧州で11%減、日本で33%減、米国で2%減、中国で5%増、ロシアで3%増等となっています。一方、2021年には2020年比2%増の見通しであり、これは2019年をやや下回る水準となる見通しです。
2.新型コロナが日本のエネルギー動向に与えた影響
(1)エネルギー需要全体の動向
2020年度の日本の最終エネルギー消費は2019年に比べ1,100PJ以上も減少し、単年度で見れば2008年9月のリーマンショックによる落ち込みを超える大きな下落幅となりました。
【第131-2-1】前年度からの日本の最終エネルギー消費の変化
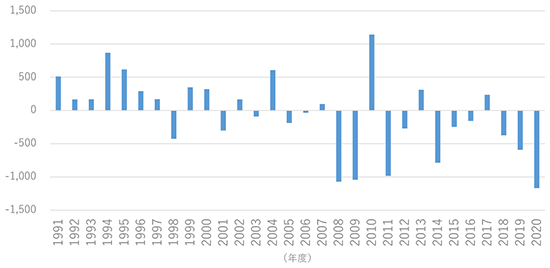
【第131-2-1】前年度からの日本の最終エネルギー消費の変化(xls/xlsx形式34KB)
- 資料:
- 総合エネルギー統計2020年度確報より経済産業省作成
(2)部門別のエネルギー消費の動向
部門別の最終エネルギー消費について、2019年度と2020年度を比べると、産業部門のうち7割を占める製造業分野で約10%、業務他(第三次産業)で約5%、運輸で約10%の減少が生じましたが、家庭部門では逆に約5%の増加となりました。これは、緊急事態宣言に伴う外出や消費の自粛により交通需要等が落ち込む一方、テレワークやオンライン授業の広がりで在宅時間が長くなり、自宅でより多くのエネルギーを使うようになったことが影響したと見られます。
以下では、人や物の移動制限の影響を大きく受けた運輸部門と、エネルギー消費量が比較的大きい産業部門のうち製造業分野について、詳細に分析していきます。
【第131-2-2】各部門におけるエネルギー利用の変化
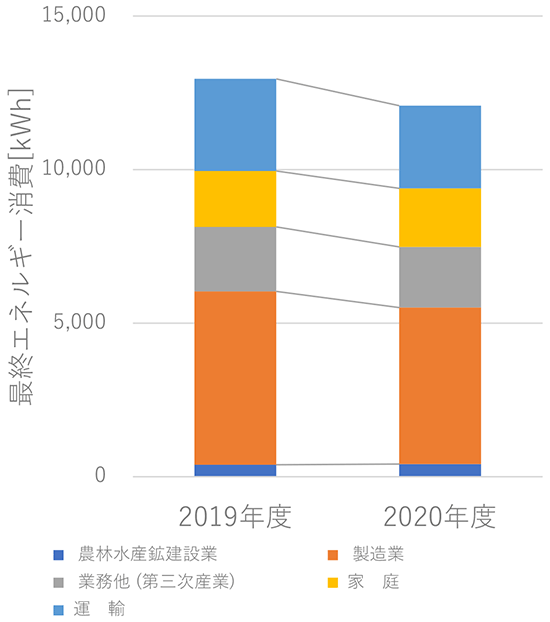
【第131-2-2】各部門におけるエネルギー利用の変化(xls/xlsx形式57KB)
- 資料:
- 総合エネルギー統計(2020年度)より経済産業省作成
①運輸部門の動向
2020年度の運輸部門の最終エネルギー消費は2019年度比で約10%減少しましたが、その内訳を見ると、旅客部門では約15%減少する一方で、貨物部門では約5%減にとどまるなど、影響度合いは異なりました。これは、海外からの出入国者を含む人の移動が厳しく制限されたことで航空燃料の需要が約70%減少した一方で、経済活動が縮小する中でも在宅時の宅配需要が増加したことで、軽油需要が約10%減に抑えられたことなどが影響したと考えられます。
【第131-2-3】運輸分野におけるエネルギー利用の変化
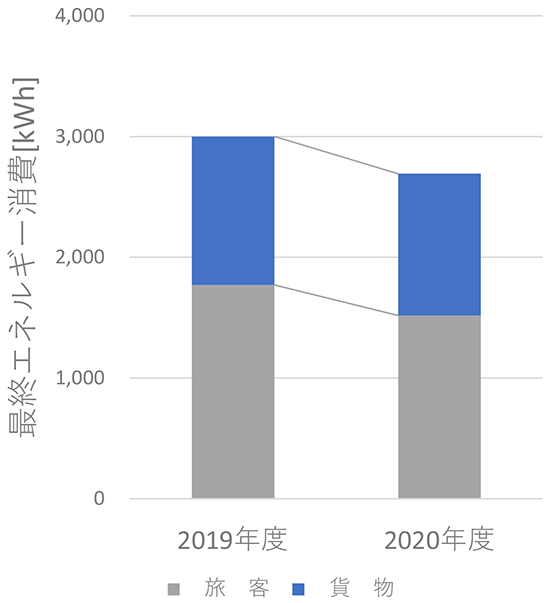
【第131-2-3】運輸分野におけるエネルギー利用の変化(xls/xlsx形式57KB)
- 資料:
- 総合エネルギー統計2020年度確報より経済産業省作成
②産業部門(製造業)の動向
2020年度の産業部門のうち、製造業の最終エネルギー消費は2019年度比で9.5%減少しました。その内訳を見ると、全ての分野でエネルギー消費量が減少していますが、特に製造業全体のエネルギー消費のうち25%を占める鉄鋼分野で15.6%減と大きく落ち込んだことや、40%を占める化学分野で9.3%落ち込んだことなどが影響しました(第131-2-4)。
【第131-2-4】製造分野におけるエネルギー利用の変化
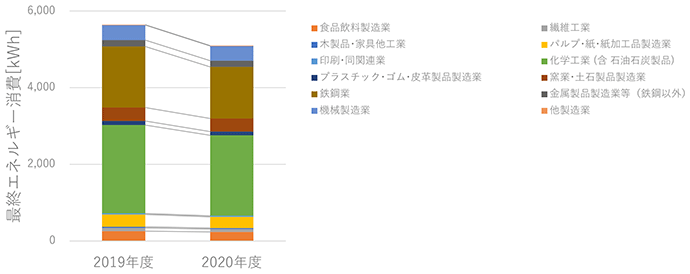
- 資料:
- 総合エネルギー統計2020年度より経済産業省作成
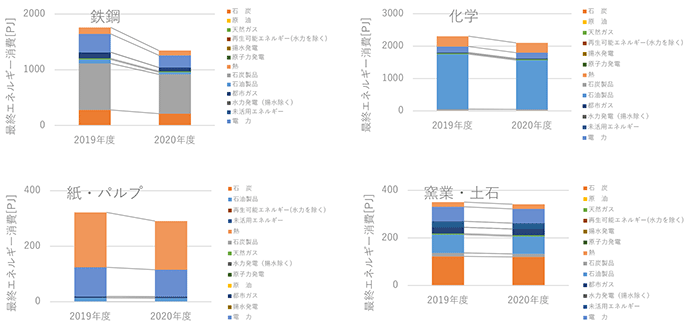
【第131-2-4】製造分野におけるエネルギー利用の変化(xls/xlsx形式129KB)
- 資料:
- 総合エネルギー統計2020年度確報より経済産業省作成
鉄鋼分野のエネルギー消費の内訳を見ると、電力、熱需要に加え、高炉による製鉄で材料となる石炭製品(コークス)や、燃料として用いる一般炭の使用量が大きく減少しました。これは、鉄鋼産業の主要な供給先である自動車の生産量が減少したり、建設工事の工期が延長することで、主力製品である高性能鉄板の需要が減少し、高炉による生産量が減少したことが原因と考えられます。
化学分野のエネルギー消費の内訳を見ると、電力、熱需要よりも、最終製品の原料となる石油製品(ナフサ)の使用量が大きく減少しました。これは、化学産業の主要な供給先である自動車の生産量減少に伴って、塗料や部品需要が減少したことで、石油化学分野の生産量が減少したことが原因と考えられます。他方、鉄鋼や化学と同じく製品一単位当たりに占めるエネルギー消費量が多い紙パルプ分野や窯業・土石分野のエネルギー消費を見ると、それぞれ9.1%減、5.3%減となっていますが、その内訳に大きな変化はありませんでした。紙パルプ分野では、テレワークに伴うペーパーレス化や、外出制限によるイベント・娯楽の中止に伴う紙需要の落ち込みがあった一方で、ペーパータオルといった衛生用品や通販用の段ボールの需要増加があった結果、鉄鋼ほどの落ち込みがなかったものと考えられます。窯業・土石分野については、電力、熱需要と比較して、セメントやガラスの製造過程で必要となる石炭製品、石油製品の使用量の減少が見られました。
(3)産業別に見た生産量とエネルギー消費量の関係
新型コロナに起因する人や物の移動・接触制限等によって、消費者の行動様式にも様々な変化が生じています。2020年度の日本のエネルギー消費量は、経済活動の量的縮小に伴って2019年度比で10%の減少となりましたが、この落ち込みは一時的なものであって経済活動が回復すればエネルギー消費も元通りに回復するという見方がある一方で、リモートワークやオンライン消費の拡大に伴う構造的な人的移動の縮小や、国際物流の停止によるサプライチェーンの組替え等の質的変化を伴うものであって、エネルギー消費のあり方が中長期的に変わっていく可能性がある、という見方もあります。いずれの場合においても、エネルギーの消費構造の特性を踏まえた政策を講じていく必要があります。
以下では、まず産業、業務他、運輸部門について生産量とエネルギー消費量の関係を概観した後、日本の最終エネルギー消費全体の約4割を占める製造業の中でも特にエネルギー使用量の多い鉄鋼産業と化学産業について、鉱工業生産指数と石油等消費動態統計を用いて2021年末までデータを延長した上で、2019年同月比で産業分野ごとの生産量とエネルギー消費量の関係を見てみます。
①産業部門、業務他部門、運輸部門における生産量とエネルギー使用量の関係
まず、日本の産業全体について、2019年度と2020年度で、生産量とエネルギー使用量がそれぞれどう変わったのかについて見ていきます。横軸に2019年度から2020年度への生産量の変化率をとり、縦軸に同じく最終エネルギー消費量の変化率をとり、各分野の実績をプロットすると、全産業において生産量の減少に伴って最終エネルギー消費が減少していますが、その内訳を見ると、ほぼ1:1で減っている鉄鋼、化学、貨物といった分野もあれば、生産量の落ち込みほどにはエネルギー消費が減らない機械製造業や旅客といった分野もあるなど、その影響度合いは一様ではありません(第131-2-5)。
【第131-2-5】製造業、業務他(第三次産業)、運輸の各部門における生産量と最終エネルギー消費の変化率
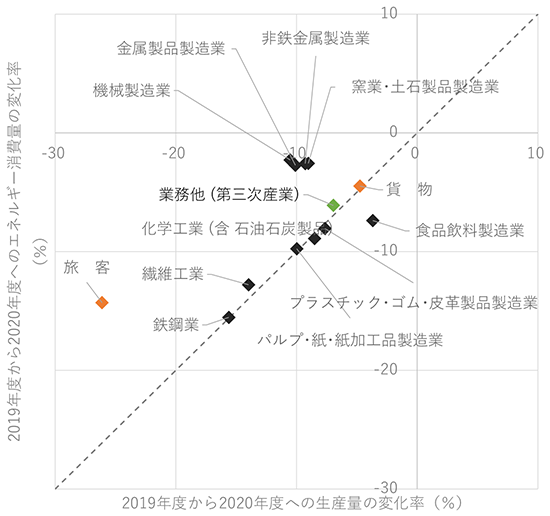
【第131-2-5】製造業、業務他(第三次産業)、運輸の各部門における生産量と最終エネルギー消費の変化率(xls/xlsx形式94KB)
- 資料:
- 総合エネルギー統計、鉱工業指数等より経済産業省作成
②産業部門のうち、鉄鋼・化学分野における生産量とエネルギー使用量の関係の時系列分析
次に、日本のエネルギー消費全体の約4割を占める製造業の中でも特にエネルギー使用量の多い鉄鋼産業と化学産業について、鉱工業生産指数と石油等消費動態統計を用いて2021年12月までデータを延長した上で、各月の生産量とエネルギー消費量について、新型コロナ拡大前の2019年同月比で比較していきます。
鉄鋼について、2020年の動向を見ると、2020年1月以降、生産量の落ち込みにほぼ1:1対応してエネルギー消費量が減少していき、緊急事態宣言解除後の6月にそれぞれ30%以上の減で底を打つと、2020年末にかけて急速に回復したことが読み取れます。2021年の動向を見ると、同じく6月頃に底を打った後に年末にかけて2019年の水準にほぼ戻していますが、エネルギー消費については5%程度の減少で終わっていることがわかります。
化学について、2020年の動向を見ると、鉄鋼ほど強い1:1の関係とはなっていませんが、2020年1月以降、生産量の落ち込みとエネルギー消費量がともに減少し、緊急事態宣言が解除された5月にそれぞれ20%前後の減で底を打つと、2020年末にかけて緩やかに回復していることが読み取れます。その結果、2019年の水準には戻らず、それぞれ10%減となったことや、鉄鋼ほどの落ち込みが生じなかったことが読み取れます。2021年の動向を見ると、6月頃に底を打った後に年末にかけて2019年の水準にほぼ戻していますが、エネルギー消費については5%程度の減少で終わっていることが分かります。2
鉄鋼、化学分野においては、2020年の変動に対し2021年の変動幅は相対的に小さくなっています。また、2020年には緊急事態宣言は二度、2021年には三度発令されましたが、個人消費や人流・物流が大きく抑制されたのは一度目の緊急事態宣言が出された2020年の4〜6月期であり、2021年は2020年と比べると緊急事態宣言下でも人の流れや経済活動の落ち込みが相対的に小さかったことから、その結果として鉄鋼、化学の両分野における生産量、エネルギー消費量の落ち込みも少なかったと考えられます。
【第131-2-6】鉄鋼業、化学業における新型コロナ前後の生産量及び最終エネルギー消費の関係
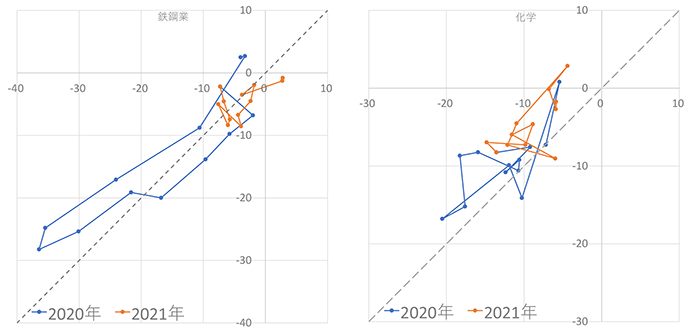
【第131-2-6】鉄鋼業、化学業における新型コロナ前後の生産量及び最終エネルギー消費の関係(xls/xlsx形式82KB)
- 資料:
- 特定業種石油等消費統計調査、鉱工業指数より経済産業省作成
(4)家庭、業務他(第三次産業)、産業部門の電力消費動向に関する詳細な分析
①分析の手法
ここでは、スマートメーターから取得した30分ごとの電力使用量のデータを用いて、新型コロナによる家庭部門、業務他(第三次産業)部門、産業部門の電力消費量が2019年、2020年、2021年でどう変わったのかについて詳細な分析を行います。
具体的には、スマートメーターの設置が進んでいる東京電力3管内から、夜間人口の多い都市(住宅エリア)、昼間人口や飲食店の多い都市(商業エリア)、製造業出荷額の多い都市(工業エリア)のデータを集計します。新型コロナ前の2019年と、新型コロナ拡大後の2020年及び2021年を比較して電力消費パターンに影響があったかを、主に最初の緊急事態宣言の影響に着目するため各年の4月のデータを中心に用いて分析します。なお、空調需要を左右する気象条件(天気、気温、湿度)と、曜日の影響を極力取り除くため、それらの条件が類似している日を選択した上で比較4しました。5,6
【第131-2-7】分析の前提となる条件
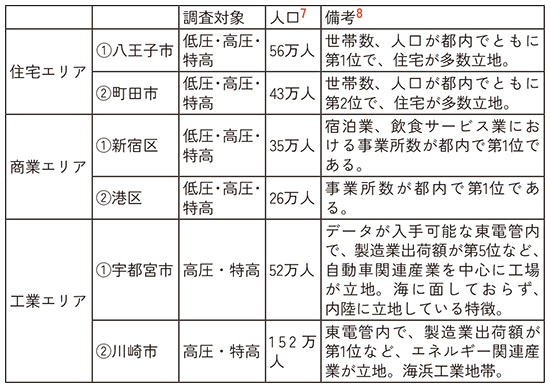
②低圧(家庭や商店)の動向
電力は、発電所で作られてから変電所を経由して送電線によって送られていますが、効率化のため変電所で変電して送電されています。低圧は、主に一般家庭や商店向けに使用される送電電圧の規格の1つで、100ボルトまたは200ボルトで供給されます。低圧の動向を見ることで、家庭や商店の動向を推察することができます。
2020年4月の緊急事態宣言期間外及び宣言期間中と、それぞれの2019年・2021年同時期の電力需要を比較すると、住宅エリア、商業エリアともにいずれの時間帯においてもおおむね2019年に比べ2020年・2021年の電力需要が増加しています。これは、宣言期間中に住民が外出を控え、自宅での電力消費が増えたことが影響していると考えられます。
(a)住宅エリアの低圧の動向
住宅エリアにおける低圧電力の動向を見ると、2020年・2021年では2019年に比べて、主に朝6時頃から夜21時頃にかけて電力需要が増加しています。これは、2020年以降に人々が外出を自粛するようになった影響が出ていると考えられます。さらに、2019年に特徴的であった朝の電力需要ですが、2020年・2021年は需要のピークが1時間程度後ろ倒しになっています。テレワークが浸透し通勤が不要になった結果、通勤前の準備などの朝の需要の一部が遅い時間帯に使われるようになったことを示唆しています。
また、2020年に発令された最初の緊急事態宣言前後を比較すると、発令後において、特に朝6時頃から夜21時頃にかけての電力需要の増加が顕著です。緊急事態宣言による外出自粛の影響が強く出ていることが推察されます。
2021年の電力需要は、2019年と2020年の中間あたりの値で推移しており人流や経済活動の抑制が回復していることを示唆していますが、回復の程度は地区ごとに差が生じている状況も推察されます。
(b)商業エリアの低圧の動向
商業エリアにおける低圧電力の動向を見ると、2020年の宣言期間外を基準とした同期間比較においては、2019年に比べ2020年・2021年の夜間にかけて電力需要が減少しており、客足の減少や店舗等の営業形態変化が影響していると考えられます。
【第131-2-8】低圧・住宅エリアにおける、通常時と緊急事態宣言期間中の1日の電力使用量の推移の比較
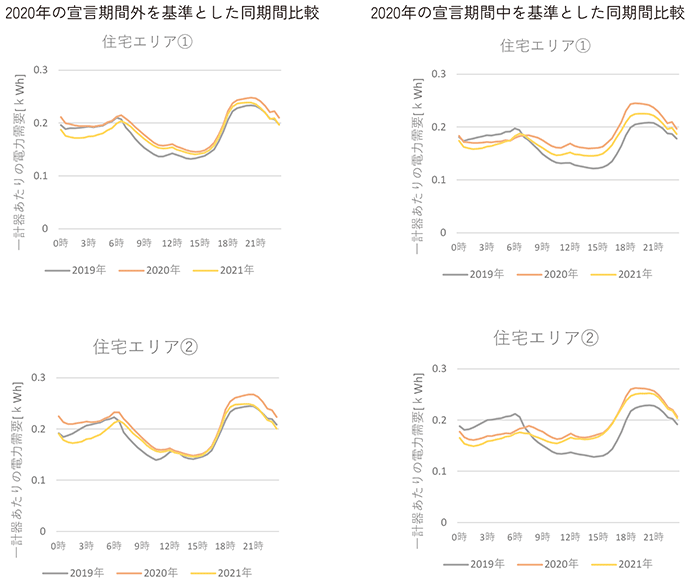
【第131-2-8】低圧・住宅エリアにおける、通常時と緊急事態宣言期間中の1日の電力使用量の推移の比較(xls/xlsx形式55KB)
- 備考:
- データ分析手法の詳細は脚注4参照
- 資料:
- グリッドデータバンク・ラボ有限責任事業組合「電力使用量データを基にした行動変容等の分析」より経済産業省作成
【第131-2-9】低圧・商業エリアにおける、通常時と緊急事態宣言期間中の1日の電力使用量の推移の比較
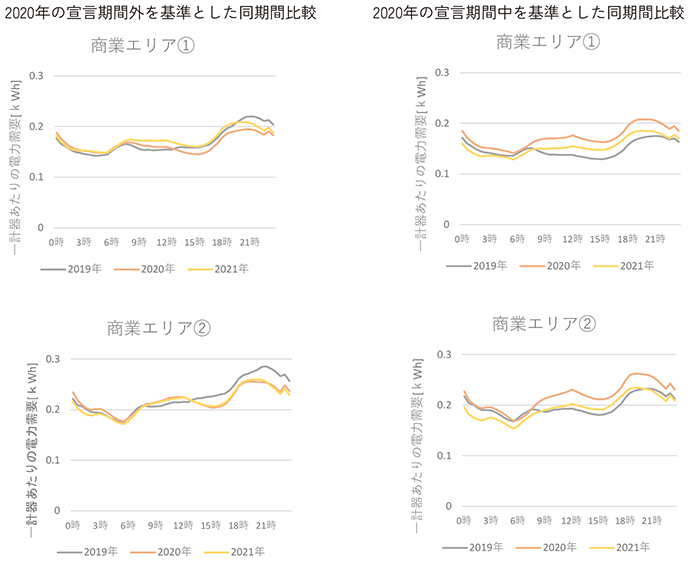
【第131-2-9】低圧・商業エリアにおける、通常時と緊急事態宣言期間中の1日の電力使用量の推移の比較(xls/xlsx形式56KB)
- 備考:
- データ分析手法の詳細は脚注4参照
- 資料:
- グリッドデータバンク・ラボ有限責任事業組合「電力使用量データを基にした行動変容等の分析」より経済産業省作成
他方、2020年の宣言期間中を基準とした同期間比較においては、2020年・2021年において昼間から夜間にかけての電力需要が増加しています。この時期に見られた外出自粛による家庭における電力需要の増加の影響が、外出自粛や店舗等の業態変化による需要の落ち込みを上回っていることを示唆しています。
③高圧(産業、業務他部門)の動向
高圧は、主に工場や商業施設において使用される送電電圧の規格の1つで、6,000ボルトで供給されます。高圧の動向を見ることで、工場や商業施設の動向を推察することができます。
(a)住宅エリアにおける高圧の動向
住宅エリアにおける高圧の動向を見ると、2019年に比べて、2020年・2021年は昼間から特に夜間にかけて電力需要が落ち込んでいる傾向が見られました。これは、飲食店等の時短営業や営業自粛の影響と考えられます。
また、2020年の最初の緊急事態宣言前後を比較すると、発令後の電力需要の減少が顕著に出ており、緊急事態宣言による外出自粛、飲食店等の時短営業や営業自粛の影響が強く出ていることが推察されます。
2021年の電力需要は、2019年と2020年の中間あたりの値で推移しており、人流や経済活動の抑制が回復していることを示唆していますが、回復の程度に地域差がある状況も推察されます。
なお、住宅エリアにおける高圧の電力需要カーブには、日中の電力消費量が急激に立ち上がり、その後夕方以降に落ち込む傾向が見られました。また、工場が活動を休止すると考えられる12時台には、一時的に電力需要が落ち込む傾向も見られます。
(b)商業エリアにおける高圧の動向
商業エリアにおける高圧の動向を見ると、住宅エリア同様に、緊急事態宣言の有無にかかわらず、2019年、2020年、2021年ともに、日中の電力消費量が急激に立ち上がり、その後夕方以降に落ち込む傾向が見られました。なお、商業エリアの高圧は、住宅エリアよりもオフィスビルや飲食店が占める比率が高いこともあり、工場のお昼休み等に伴って需要が落ち込んだ住宅エリアとは異なり、昼の時間帯に需要の落ち込みは見られません。
2019年に比べ、2020年は昼間から夜間にかけて電力需要が減少しています。これは、テレワークの浸透によりオフィスビルの活動が低下したことや、飲食店等の時短営業や営業自粛の影響が出ていると考えられます。また、2020年の電力需要の動向を緊急事態宣言期間外と期間中で比較すると、宣言期間中は日中から夜間にかけて大きく電力需要が減少しています。
(c)工業エリアにおける高圧の動向
工業エリアにおける高圧の動向を見ると、2019年に比べて、2020年・2021年は昼間から夜間にかけて電力需要が落ち込んでいる傾向が見られ、工場等の生産活動の影響が出ていると考えられます。
また、2019年、2020年、2021年ともに、日中の電力消費量が急激に立ち上がり、その後夕方以降に落ち込む傾向が見られました。また、工場が活動を休止する12時台には、一時的に電力需要が落ち込む傾向も見られます。
2021年については、電力消費量が落ち込んだ2020年とほぼ同水準で推移しており、経済活動の落ち込みが継続している可能性が考えられます。
④特別高圧(特高)の動向
特別高圧(特高)とは、直流・交流ともに7,000V超の電圧のことで、大規模な工場など、大量の電力を使用する施設で用いられます。特別高圧の動向を見ることで、大規模工場等の動向を推察することができます。なお、特高の産業用スマートメーターについては、低圧や高圧に比べ計器数が少ないため、生産計画や定期点検、自家発の稼働状況等によって大きく変動する電力需要について、今回の分析結果のみをもって新型コロナの影響かどうか判定することが難しい点に留意が必要です。
(a)工業エリアにおける特高の動向
工業エリア①においては、2020年は、2019年に比べ全時間帯で電力需要が下落しており、その下落幅は緊急事態宣言による経済活動の制限がなされていた時期の方が大きいことが分かります。一方、2021年については、新型コロナ前の2019年の水準にほぼ回復しています。
また、工業エリア②については、2019年に比べ2020年・2021年の夜間の電力需要が大きく減少しています。これは、一部の工場の夜間操業を停止した影響が出ていると考えられます。
(b)商業エリアにおける特高の動向
商業エリアにおける特高の動向を見ると、2019年に比べて、2020年・2021年は昼間から夜間にかけて電力需要が落ち込んでいる傾向が見られました。また、2020年の緊急事態宣言期間外と期間中を比べると、期間中のほうが大きく電力需要が落ち込んでいます。2020年・2021年には、ビルのテナント(商店・飲食店等)の営業自粛等により昼間から夜間にかけての電力需要が減少している影響が出ていると考えられます。
(c)住宅エリアにおける特高の動向9
住宅エリアにおける特高の動向を見ると、2019年に比べて、2020年・2021年は昼間から夜間にかけて電力需要が落ち込んでいる傾向が見られました。また、2020年の緊急事態宣言期間外と期間中を比べると、期間中のほうが大きく電力需要が落ち込んでいます。特高には公共施設等が含まれていることもあり、2020年の宣言期間中の電力需要が大きく減少していると推察されます。
【第131-2-10】高圧・住宅エリアにおける、通常時と緊急事態宣言期間中の1日の電力使用量の推移の比較
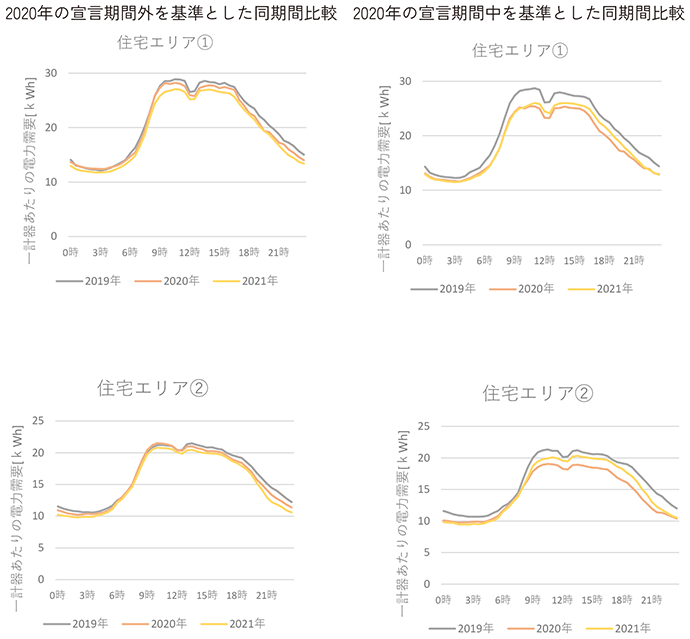
【第131-2-10】高圧・住宅エリアにおける、通常時と緊急事態宣言期間中の1日の電力使用量の推移の比較(xls/xlsx形式65KB)
- 備考:
- データ分析手法の詳細は脚注4参照
- 資料:
- グリッドデータバンク・ラボ有限責任事業組合「電力使用量データを基にした行動変容等の分析」より経済産業省作成
【第131-2-11】高圧・商業エリアにおける、通常時と緊急事態宣言期間中の1日の電力使用量の推移の比較
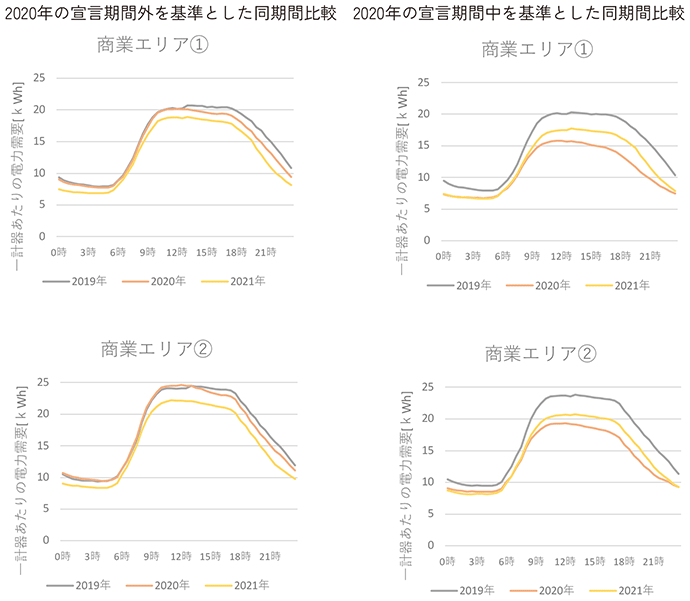
【第131-2-11】高圧・商業エリアにおける、通常時と緊急事態宣言期間中の1日の電力使用量の推移の比較(xls/xlsx形式:66KB)
- 備考:
- データ分析手法の詳細は脚注4参照
- 資料:
- グリッドデータバンク・ラボ有限責任事業組合「電力使用量データを基にした行動変容等の分析」より経済産業省作成
【第131-2-12】高圧・工業エリアにおける、通常時と緊急事態宣言期間中の1日の電力使用量の推移の比較
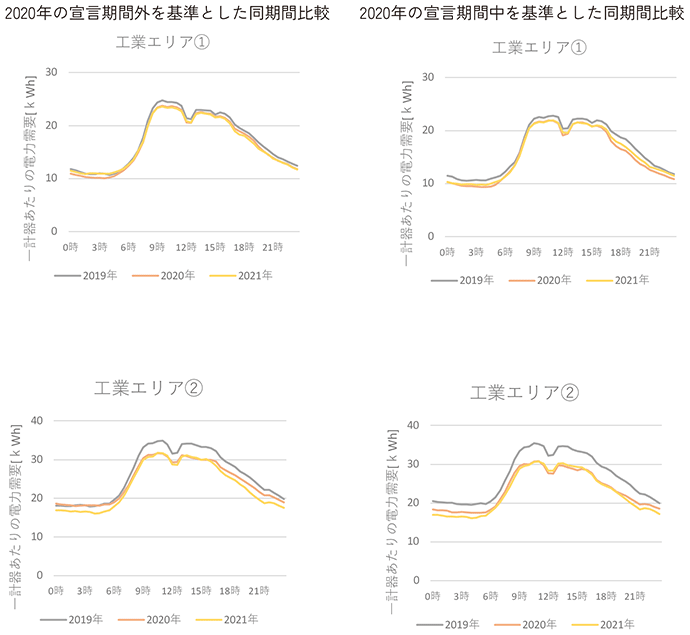
【第131-2-12】高圧・工業エリアにおける、通常時と緊急事態宣言期間中の1日の電力使用量の推移の比較(xls/xlsx形式65KB)
- 備考:
- データ分析手法の詳細は脚注4参照
- 資料:
- グリッドデータバンク・ラボ有限責任事業組合「電力使用量データを基にした行動変容等の分析」より経済産業省作成
【第131-2-13】特高・工業エリアにおける、通常時と緊急事態宣言期間中の1日の電力使用量の推移の比較
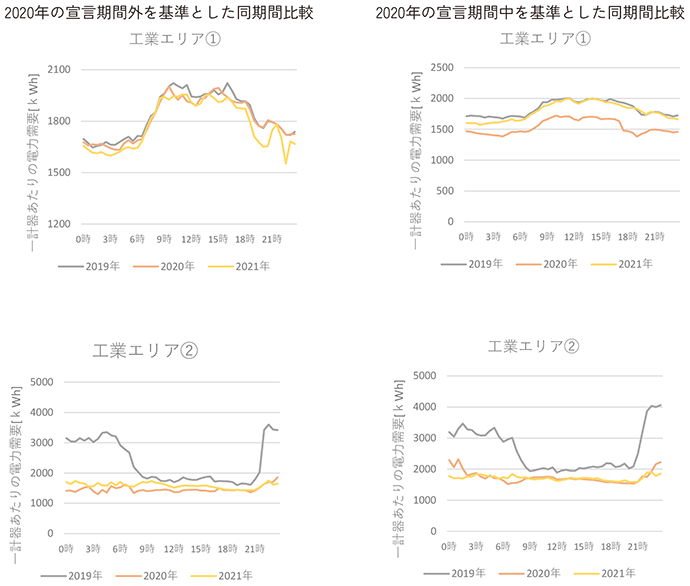
【第131-2-13】特高・工業エリアにおける、通常時と緊急事態宣言期間中の1日の電力使用量の推移の比較(xls/xlsx形式58KB)
- 備考:
- データ分析手法の詳細は脚注4参照
- 資料:
- グリッドデータバンク・ラボ有限責任事業組合「電力使用量データを基にした行動変容等の分析」より経済産業省作成
【第131-2-14】特高・商業エリアにおける、通常時と緊急事態宣言期間中の1日の電力使用量の推移の比較
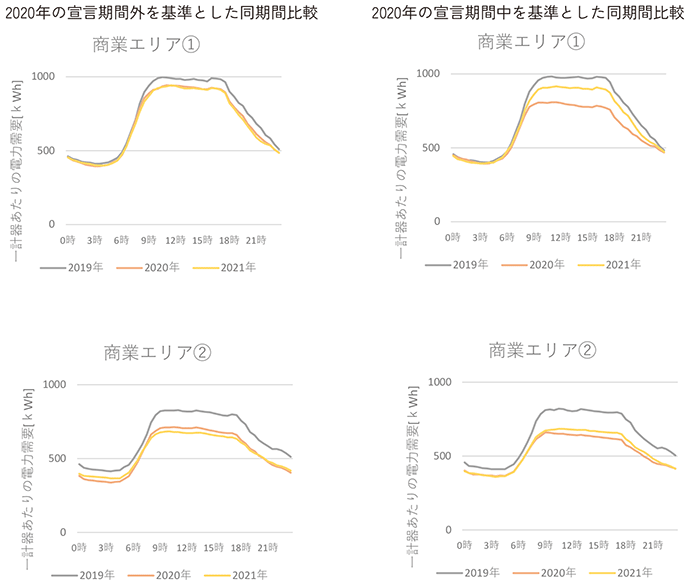
【第131-2-14】特高・商業エリアにおける、通常時と緊急事態宣言期間中の1日の電力使用量の推移の比較(xls/xlsx形式60KB)
- 備考:
- データ分析手法の詳細は脚注4参照
- 資料:
- グリッドデータバンク・ラボ有限責任事業組合「電力使用量データを基にした行動変容等の分析」より経済産業省作成
【第131-2-15】特高・住宅エリアにおける、通常時と緊急事態宣言期間中の1日の電力使用量の推移の比較
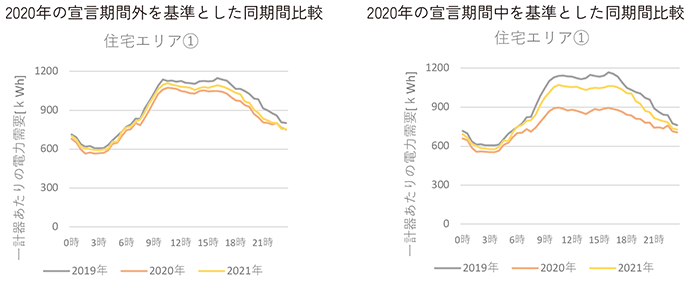
【第131-2-15】特高・住宅エリアにおける、通常時と緊急事態宣言期間中の1日の電力使用量の推移の比較(xls/xlsx形式46KB)
- 備考:
- データ分析手法の詳細は脚注4参照
- 資料:
- グリッドデータバンク・ラボ有限責任事業組合「電力使用量データを基にした行動変容等の分析」より経済産業省作成
3.国内外の分析から得られる示唆
本節では、いまだに影響が続く新型コロナが日本のエネルギー分野に及ぼす影響について、主に需要側に焦点を当ててデータに基づいて分析・考察を加え、いくつかの示唆を得ました。新型コロナは経済活動を収縮させることを通じ、2020年には産業分野、運輸分野を中心にエネルギー消費を減少させた一方、家庭分野ではエネルギー消費が増加する等、分野や地域によって異なるエネルギー消費の変化を生じさせました。多くの分野でエネルギー消費についてはコロナ前の水準に戻りつつありますが、2021年時点ではコロナ前の水準まで戻りきっていない分野もあります。エネルギー分野におけるコロナの影響は一時的なものに止まる可能性もありますが、他方、テレワークやオンライン授業、eコマースの拡大に伴う活動拠点の分散化等を通じ、分野間のエネルギー消費比率が変わるなど、構造的な変化が生じている可能性もあり、これを明らかにするには、今後継続的に分析を行う必要があります。
エネルギーをとりまく不確実性はますます高まっています。省エネの更なる強化や、エネルギー源と調達先の一層の多様化・分散化等により、エネルギー需給構造を質と量の両面で強靱化していく必要があります。世界各国で政府が新型コロナへの対応等に取り組んでいる中、日本においても、第208回国会に提出した「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案」や「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」、「クリーンエネルギー戦略」に基づく施策など、あらゆる政策手段を総動員して取り組んでいく必要があります。
- 1
- (2)では、特段の記載がない限り、IEA「Global Energy Review 2021」に基づいています。
- 2
- 石油化学部門については、生産量・エネルギー消費ともにプラントの定期修理の影響も考えられるなど、新型コロナ要因以外の影響についても注意が必要です。
- 3
- 東京電力パワーグリッド社によると、同社サービスエリア内において、2019年時点で2000万台(約70%)、2022年3月時点で2840万台(一部取り換え作業が困難な場所などを除くすべての世帯・事業所)の電力量計をスマートメーターに切り替えています(東京電力パワーグリッド株式会社「スマートメーターの設置状況について」(2021年5月発表))
- 4
- 首都圏に緊急事態宣言が発令された2020年4月7日を基準日とし、発令前の3週間(3月17日〜4月6日)を「宣言期間外」、発令後の3週間(4月7日〜27日)を「宣言期間中」と定義します。「宣言期間外」と「宣言期間中」のそれぞれにおいて、2019年と2021年の双方に気温や湿度、天気の面で条件が近くなる平日が存在する日を対象とし、曜日は平日のみを対象としました。上記の条件をすべて満たした日の電力需要データを採用し、期間別に平均して分析に用いました。
- 5
- 本稿では、特定地域の分析ではなく、エリアごとの特色を示すことを目的としているため、以後「住宅エリア①」と表記します。
- 6
- 選定した類似日について、2019年は緊急事態宣言、まん延防止期間中ではないが、2021年については一部まん延防止期間中の日も含んでいることに注意が必要です。
- 7
- 総務省 住民基本台帳に基づく令和3年1月1日時点の人口、人口動態及び世帯数に基づいています。
- 8
- 各項目の利用可能な最新の政府統計(総務省・経済産業省 経済センサス‐活動調査、経産省 工業統計調査等)参照。
- 9
- エリア②における特別高圧については、対象地域で十分な計器数が確保できなかったため、分析の対象外としました。