第1節 脱炭素を巡る世界の動向
1.脱炭素に向けた潮流
脱炭素に向けた動きは、世界的に加速しています。COP26が終了した2021年11月時点で、154カ国・1地域が2050年等の年限を区切ったカーボンニュートラルの実現を表明しています(第121-1-1)。これらの国におけるCO2排出量とGDPが世界全体に占める割合は、それぞれ79%、90%に達しました1。COP26では、パリ協定第6条に基づく「市場メカニズム」2の実施指針が長年の交渉の末に合意され、パリ協定のルールブックが完成したり、インドが2070年カーボンニュートラルを宣言する等3、脱炭素に向けた国際的なルール作りや機運の醸成に進展が見られました。
金融面では、世界のESG投資額が2020年に35.3兆ドルまで増加するとともに、気候変動に関する情報開示を企業に求める動きが世界的に広がっています。英国では、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言に基づく情報開示を、1,300社を超える上場企業及び大企業に対し義務づける法改正が行われ、2022年4月から適用が開始されています。世界のESG4投資の過半が集まる米国では、証券取引委員会(SEC)がTCFD提言に基づく気候変動に関する情報開示規則の案を2022年3月21日に示しました。今後外部の意見公募等を経て、最終規則がまとまれば、2024年にも情報開示が必要になります。日本でも、東京証券取引所のプライム市場上場企業はTCFD又はそれと同等の国際的枠組みに基づく開示を求められます5。こうした各国の動きに加えて、2021年11月にはIFRS財団により「国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)」が設立され、2022年末までにESG情報の開示に関する統一的な国際基準を策定しようという議論も進んでいます(第121-1-2)。
産業界でも、国内外で、取引先まで含めたサプライチェーン全体の脱炭素化やそれに伴う経営全体の変容(グリーントランスフォーメーション(GX))が加速しており、デジタル技術を活用し、サプライチェーン上のCO2排出量を算定し、可視化するサービスも活発になっています。
【第121-1-1】年限付きのカーボンニュートラルを表明した国・地域
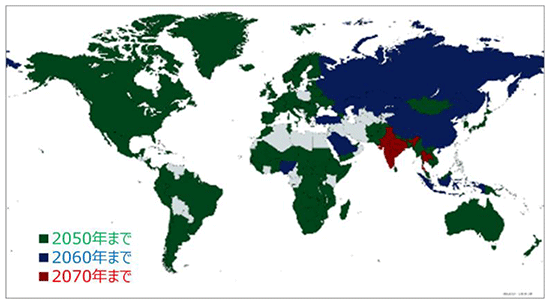
- 資料:
- 経済産業省作成
【第121-1-2】日米欧のESG投資の合計額の推移
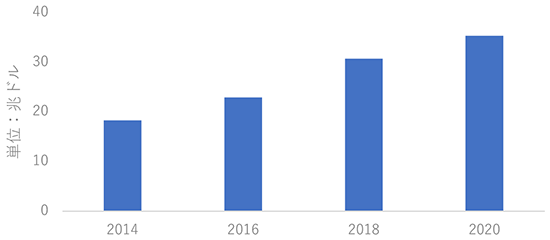
【第121-1-2】日米欧のESG投資の合計額の推移(xls/xlsx形式16KB)
- 資料:
- GSIA「Grobal Sustainable Investment Review 2020」より経済産業省作成
2.脱炭素実現に向けた諸外国の政策動向
カーボンニュートラルについては、各国の表明内容は様々ですが、いずれの国もカーボンニュートラルに至る単一の道筋にコミットすることはなく、ビジョンとして複数のシナリオを掲げて取り組んでいます。また、カーボンニュートラル実現に向けて、電化、水素化、CCUSの活用を進めていくことや、革新的なイノベーションが欠かせないといった共通項があることから、取り組む政策の方向性は世界各国で一致しています(第121-2-1)。
【第121-2-1】カーボンニュートラルに向けた各国の政策の方向性
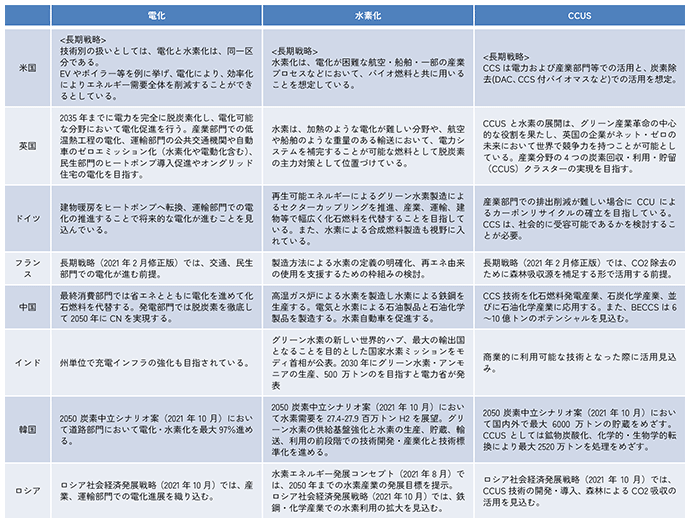
- 資料:
- 各国政府資料等から経済産業省作成
一方、2030年の野心的な温室効果ガス削減目標を実現しようとすれば、わずか8年で温室効果ガス排出量を大幅に減らす必要があることから、各部門でメリハリを付けながら既存の技術を最大限活用することが求められます。最終的な到達点が同じだとしても、足下で現実的に実行可能な具体策は、各国のエネルギーを巡る情勢や現状の産業構造に左右され、施策の強度、順序、時間軸は大きく異なってきます。
例えば、各国について、IEA「World Energy Outlook 2021」における「公表政策シナリオ(STEPS)」とNDCや長期削減目標等を反映した「表明公約シナリオ(APS)」の差分を見て、追加的に講じる必要がある政策のインパクトを部門別に比較すると、国によって様相が大きく異なることが分かります。具体的には、製造業が盛んな中国や日本では、CO2排出削減量の大きさが産業、運輸、民生の順になっており、産業の脱炭素化に向けた政策に重点が置かれています。一方、国土が広く自動車大国である米国では、CO2排出削減量の大きさは運輸、民生、産業の順で、運輸部門の脱炭素化が鍵となることが分かります。一方、欧州はCO2排出削減量の大きさは産業、運輸、民生であるものの、他国と比較すると特徴として民生部門の割合が高いことが分かり、EUの施策を見ていくと、既築の住宅やビル等の省エネ改修を促す規制・制度や資金支援の取組が見られます(第121-2-2)。
各国とも、現状の産業構造を出発点として、必要な部分に重点的に追加的政策を講じようとしています。以下では、米国、英国、ドイツ、フランス、中国、インドについて、2050年と2030年の取組状況を整理します。あわせて、2050年のエネルギー構造に必須となる水素や金属鉱物の動向についても紹介します。
【第121-2-2】各国の2050年目標達成に追加的に必要なCO2削減量の部門別比率(非電力)
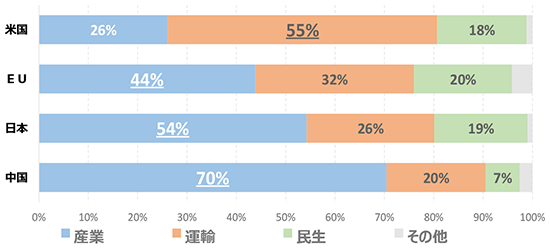
- 資料:
- IEA「World Energy Outlook 2021」より経済産業省作成
①米国
米国では、2021年10月に長期戦略を国連に提出しました。この中で、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、電力部門の2035年脱炭素化、産業分野は電化を進め、電化が難しい分野は水素化、航空分野等は持続可能な航空燃料(SAF)等に置き換えるとしています。また、新築・既築建物や家電の省エネを進めるとともに、世界全体でメタンを2030年に少なくとも30%削減し、CO2除去技術についても取組を拡大していくことにしています。
その具体策として、2021年11月15日に成立した超党派インフラ投資雇用法に基づき、今後5年で5500億ドルを支出する中で、気候変動に関しては、EVインフラ(EV充電設備、75億ドル)、電気バス等(ゼロエミスクールバス、フェリーの導入支援75億ドル)、電力インフラ(送電線の建設・研究開発、革新炉実証、CCUS、クリーン水素等の実証等)等に予算を措置するとしており、運輸部門に重点が置かれていることが分かります。
米国は、部門別にも様々な計画を発表しています。産業部門では、クリーン水素の活用等を含む製造業の脱炭素化計画を打ち出し、エネルギー転換部門ではハイドロフルオロカーボン(HFC)や石油ガス開発時のメタン等の排出規制を策定しています。金融部門では、大手銀行を対象とした気候リスクマネジメントの指針案を公表するともに、企業の情報開示のあり方についてもTCFD提言に基づく規則案を2022年3月に公表しました。
運輸部門では、EV等のクリーン自動車の普及に力を入れています。2021年8月には、2030年に新車販売の50%をクリーン自動車とする大統領令に署名し、乗用車などの燃費・排ガス規制を強化しました。また、EV充電インフラについては、2030年までに50万基の整備に向けて、超党派インフラ投資雇用法に基づく75億ドルのうち、50億ドル分に相当するEV充電プログラム予算の執行に2022年2月から着手し始めています6。さらに、航空部門については2021年11月に燃料転換等により2050年にゼロ・エミッションとする行動計画を公表し、100%のSAF化に加え、エンジンの燃費改善に向けた研究開発や航空設備の低炭素化等を進めるとしています7。
民生部門では、建物のエネルギーや家電等のエネルギー効率基準を見直しています。2021年12月に連邦政府全体を2050年にカーボンニュートラルとする大統領令に署名し、政府機関の建築物の省エネ基準を初めて策定するとともに、低炭素製品の普及を後押しするために政府調達のクリーン化を打ち出しました。また、既存住宅向けに電気機器のエネルギー効率基準の見直しや、低所得者層向けの既存住宅のエネルギー効率向上支援の規模を拡大することにしています。
一方、再生可能エネルギーやEV、原子力、CCSなど、多岐にわたるクリーン技術に対する税額控除の拡大等の気候変動対策(0.55兆ドル)を含む総額1.7兆ドル規模の歳出法(Build Back Better Act)は、2021年11月に下院を通過した後、2022年5月時点では上院での審議が進んでおらず、成立に至っていません。
②EU
EUでは、2050年と2030年の温室効果ガス削減目標に関する「欧州気候法案」を欧州理事会で2021年7月に採択・法定化するとともに、欧州委員会が2050年と2030年の目標を達成していくための政策パッケージ「Fit for 55」8を提案しました。この中で、①排出量取引の強化(2030年の削減目標の引上げ(2005年比43%→61%)、炭素国境調整メカニズム適用による産業部門への無償割当の段階的な削減、無償割当ベンチマークの全般的な見直し、運輸・建物暖房部門の追加)、②再エネの導入目標引上げ(最終エネルギー消費に占める割合を32%から40%へ)、③エネルギー効率化目標の引上げ(1990年比32.5%→36-39%)、公共部門でのエネルギー効率向上の数値目標強化、④2035年以降のガソリン車の新車販売禁止、⑤充電インフラや水素インフラの整備、⑥持続可能な航空・海運燃料供給、⑦エネルギー税を数量ベースから熱量ベースに変更、⑧炭素国境調整措置の導入(鉄、セメント、肥料、アルミ、電力等の輸入事業者に対して証書購入を義務付け)等を示しています。
さらに、2021年12月15日には、「Fit for 55パッケージ第2段」を発表し、①欧州内のガスを天然ガスから水素やバイオガスに移行するためのルール改正や域内ガス市場の共通ルール指令改正案、②エネルギー部門から排出されるメタンガス削減の新規則案、③建物エネルギー性能指令の改正案(2020年10月のリノベーションウェーブ戦略で掲げた大規模改装の推進のために2030年までのZEB義務化や省エネ性能評価の共通化、低性能建物の省エネ改修の義務化)、④DACCS等のCO2除去技術を認証する制度構築等、対策の更なる深掘りを進めています。
特に、建物のエネルギー効率指令改正案は、EUが推し進めるグリーンディールの一つの柱として位置付けられている、建物のエネルギー効率を一層高めるための省エネ改修投資を促すことで経済成長と気候変動対策を両立させることを目指すリノベーションウェーブとして重要視される政策の一つです。EUは、2030年の排出削減目標の達成や2050年のカーボンニュートラルのためには、既築を含めて建築物を、エネルギー効率が高く、再生可能エネルギーと高度に統合されたものにすることが求められます。
COLUMN
EUタクソノミーの動向
EUは2050年に域内のカーボンニュートラルを達成するために必要となる資金を、公的機関だけでなく民間金融機関などからも振り向けられるようにし、気候変動に起因するリスク等を管理しやすくするための枠組みの中核として、経済活動を一定の基準によって分類する規則の策定を進めてきました。2020年6月にEUタクソノミー規則が施行され、気候変動緩和(削減)、気候変動適応等の6つの環境目的のいずれかに貢献し、他の環境目的に重大な害を与えない(DNSH: Do No Significant Harm)持続可能な経済活動を定める技術スクリーニング基準を採択する権限を欧州委員会に委任しました。原子力発電については意見の隔たりが大きいため、欧州委員会共同研究センターでライフサイクルでの評価が行われることとなりました。2020年11月に欧州委員会が技術スクリーニング基準を定める委任規則案を公表しましたが、ガス火力発電については加盟国間・欧州議会内の意見の隔たりが大きいため、それを除外した委任規則が採択・施行されました。ガス火力発電については継続的に検討されることになりました。
その後、原子力発電についての欧州委員会共同研究センターによる評価、加盟国間での議論などを踏まえて、2022年2月2日に欧州委員会が原子力発電とガス火力発電を一定の条件の下で持続可能と分類する委任規則案9を発表しました。この中で、原子力発電は、放射性廃棄物の処分や資金確保に関する計画が整っていること、新規建設の場合、2045年までに建設許可を得ること等を条件としています。また、ガス火力発電は、GHG排出量が270g-CO2e/kWh未満であること、2030年末までに建設許可を得ること、2035年までに低炭素ガスに切り替えることなどが条件となっています。今後、欧州議会及びEU理事会との最長6ヵ月の協議が行われ、2023年1月から適用開始となります。
③英国
英国は、2019年に「2050年までの温室効果ガスのネットゼロ排出」を法制化しました。2021年6月には、2050年カーボンニュートラルに至る道程として、2035年までに1990年比78%削減を含むカーボンバジェットを設定し、10月に長期戦略を国連に提出しています。英国は、脱炭素の電力による経済社会の電化を進めつつ、EV化、省エネの推進、低炭素燃料への転換、CO2回収・固定技術などに取り組むことにしています。また、建築物については、ほぼ全ての建物に省エネ基準の適合を義務づけ、住宅用は2020年4月から、非住宅用は2023年4月から省エネ率の低い物件の賃貸を禁止するなど規制の強化を進めています。
2050年、2030年の削減目標を着実に実現するため、2021年10月にはビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)が「Net Zero Strategy: Build Back Greener」を公表しました。この中で、電力部門については2035年に脱炭素化し、2030年に5GWの水素発電を進めることにしています。産業部門については、同部門から600万トンのCO2を回収・利活用することにしています。また、2021年10月に、BEISが国内大型原発新設支援のための資金調達枠組みとしてRABモデル導入を目指した原子力資金調達法案を検討立案しています10。
④ドイツ
ドイツでは、2021年6月25日に改正気候保護法が成立し、カーボンニュートラルの達成期限を2050年から2045年に前倒ししました。あわせて、2030年のGHG削減目標を1990年比55%減から65%減に引き上げるとともに、2040年に1990年比88%減とする中間目標を新たに導入し、各年の削減目標も明確化しました。さらに、エネルギー、製造業、建築、交通、農業、廃棄物その他の計6分野について、2030年までのGHG排出目標を定めました。さらに、森林や湿地などのCO2吸収源の保全・再生による産業分野のCO2除去に関する目標も新たに盛り込みました。
電力部門について、ドイツにおける再エネ比率は2021年に42%強に達しましたが、連邦政府は、3党連立協定書に基づき、2030年までに同比率を現状の2倍以上となる80%に高めるべく、再エネの拡大を抜本的に加速させていくとしています。例えば、陸上風力発電については、発電所と住宅との最小距離に関する規制などで設置可能面積が2020年末時点で国土の0.5%にとどまるため、法整備を進めて設置可能面積を国土の2%まで広げたり、営農型太陽光発電設備の導入を支援するなどにより、100GWを目指すとしているほか、州や自治体との協力も深めることにしています。また、2030年までに商業用施設などの新築時に太陽光パネルの設置を義務化し、それ以外の民間用施設などの新築時にも太陽光パネル設置を原則とすることで、太陽光発電の容量を現在の3倍以上となる200GWに増やしていくことにしています。さらに、消費者の負担軽減のため、再生可能エネルギー賦課金(EEG賦課金)を2023年に廃止し、その分を連邦財政で賄うことにより、電力価格を引き下げる方針です。さらに、発電に利用する天然ガスの使用量を徐々に減らし、一部をグリーン水素に代替させるため、2030年までに電解槽の拡大目標を現在の2倍となる10GWに増加させることを目指し、2022年中に「国家水素戦略」を改正し、追加的な支援プログラムを開始することにしています。
民生部門については、建築物エネルギー法を改正し、既存建築物に対する省エネ改修や、再生可能エネルギーの利用拡大、ヒートポンプの導入をこれまで以上に拡大する方向です。
運輸部門については、2030年にEVを1500万台普及させることや、2025年までに10万ヵ所の公共充電設備の設置を盛り込んでいます。さらに、EUでは2035年以降のカーボンニュートラルではない自動車は登録禁止となることが議論されていますが、ドイツでは合成燃料の活用も念頭に置きつつ、その時期を前倒しに向けた検討を進めています。
連邦政府は2022年4月に気候変動対策に関する法改正をまとめた「イースターパッケージ」を決定し、今後ドイツ連邦議会で審議される見通しです11。
⑤フランス
フランスでは、2019年9月に、2050年のカーボンニュートラルを目指し、そのための具体的な目標を定める「エネルギー・気候法」が議会で可決されました。具体的には、電力部門について、2030年までに化石燃料消費を40%削減する一方、再エネの利用を全体の33%まで拡大する等の目標を定めました。
フランスでは、民生部門における排出削減に特に力を入れており、エネルギー効率の改善に向けた様々な取組が実施されてきました。具体的には、省エネ機器の導入に関する優遇税制(低温ボイラ、圧縮ボイラ、断熱材などの設備、エネルギー制御管理システム、スマートメーター、再エネ等の導入費用を控除)、公営住宅へのエネルギー効率改善のための優遇金利の適用(既存建築に対して、エネルギー消費の抑制を伴う改修費用について、貸出金利を0%で、最長10年間、最高30,000ユーロを貸し付ける制度)等の取組です。
また、2030年に最終エネルギー消費量を2012年比で20%削減するとともに、低所得者向けの既築の賃貸住宅の省エネを進めるための規制や貸出金利の免除措置等の資金的支援策が導入されています。運輸部門については、EVの購入補助金を提供しているほか、航空機の利用を控え、鉄道の利用を促す取組が行われています。
2021年10月には、マクロン大統領が産業競争力強化のための「フランス2030」を発表し、年間300億ユーロの投資のうち80億ユーロを原子力・水素エネルギーを使ったクリーン電力への転換や製造業の脱炭素化を進めることにしています。水素産業振興には、19億ユーロ追加支援を表明しました12。
また、2022年2月10日には、マクロン大統領がフランス国内のGEの工場を訪問し、2050年カーボンニュートラルに向けた政策を発表しました。具体的には、今後、最大6割の低炭素電力増産が必要となることから、再エネと原子力の二本立てで供給を増やすこととし、原子力は、安全が確保された原発について40年から運転延長をするほか、50年の安全基準も審査を開始することにしています。また、6基のEPR建設と、8基のEPR2追加新設を検討し、うち1基は2028年着工、2035年運転開始を目指す方向です。これに関連して、フランス電力公社(EDF)がGEの低速蒸気タービン事業を一部買収する等の動きも出てきています13。さらに、SMR等の革新炉開発については、2030年までに10億ユーロを投じて取り組むことにしています。再エネについては、太陽光発電を現在の10倍の100GWにするとともに、洋上風力発電については2050年までに50ヵ所、計40GWの導入を目指すことにしています。一方、陸上風力については住民の反対があることを踏まえて目標を下方修正し、2050年までに2021年末時点の18.5GWを倍増。次世代浮体式洋上風力についても、研究開発に10億ユーロ投資することにしています。
⑥中国
中国では、2020年9月に習近平国家主席が国連総会で「2060年までにカーボンニュートラルを達成するよう努力する」との目標を表明し、2020年10月には長期戦略を国連に提出しました。その後、2021年3月の全国人民代表大会で「国民経済・社会発展第14次5カ年計画」が採択され、この中で積極的に気候変動に対応することが明記されました。
カーボンニュートラルに向けた具体的な行動計画も策定され始めています。例えば、2021年10月に国務院は「2030年前カーボンピークアウト目標達成に関する行動計画」を公表し、石炭の消費を段階的に削減し、風力・太陽光発電所の建設を加速し、水力発電所の増設、原子力発電所の建設も進める方針を示した上、10大行動分野を定め、例えば、産業部門の対策として、産業構造の最適化、遅れた生産能力の廃止、戦略的新興産業の開発などを主な対策とし、電力の需要側管理を強化し、産業の電気化、デジタル化、グリーン化を促進する方針を示しました。
さらに、2021年11月に工業情報部は「第14次5カ年計画工業のグリーン発展計画」を発表し、2025年までに鉄鋼、建材等の産業でCO2の排出量を減らし、脱炭素化を後押しする具体的な計画を示しました。加えて、2022年1月に国務院は「14次5カ年計画の省エネ・炭素排出削減方針14」を発表し、GDP当たりエネルギー消費量を2025年までに、2020年比で13.5%削減するほか、鉄鋼、アルミ、セメント、板ガラス等の重点産業の生産について、2025年までにエネルギー効率のベンチマーク水準を満たすものの比率が30%を超えるようにするとしました15。
中国は、電気自動車(EV)の普及を気候変動対策の柱の一つとして位置づけており、消費者への購入助成措置や自動車メーカーへの導入割当制度等がEVの急速な普及をもたらしました。2021年、中国のEV販売台数は291万台に達し、前年比2.6倍に増加したほか、新車市場でのシェアも2割を超えました。今後の普及方針として、2035年に新車の電動化率を100%とし、うちEVを新車販売の半分程度、約2000万台に拡大する目標としています。
上記「行動計画」では、ピークアウト目標の実現のための重点政策として、省エネ対策の方針と内容を再エネの推進政策以上に具体的に記述しました。全国的に省エネ管理と監視能力を向上する制度設計、都市部における建築物や運輸、照明、熱供給等のインフラの省エネ革新、発電産業や鉄鋼・建材等のエネルギー多消費産業の省エネ推進、モーターやボイラなどエネルギー消費設備の効率向上プロジェクトの推進、さらに主要な工業部門について重点省エネ技術ごとの推進方針等を定めました。今後、省エネの取組が一層強化される見通しです。また、既存住宅や公共建築物に対しては省エネリノベーションを加速し、新築建築物に対しては2025年までグリーン建築基準に全面的に適合する方針を示しました。
⑦インド
インドは、2021年11月のCOP26世界リーダーズ・サミットにおいて、2070年カーボンニュートラルを宣言し、2030年までに500GWを非化石燃料由来とすることにしました。これに関し、モディ首相は、2030年までにグリーン水素の年間生産量を500万トンにまで増やすことを目標とした「国家水素ミッション」の策定を2021年8月に発表し、これを具体化するものとして、2022年2月17日に、「グリーン水素・アンモニア政策」を発表しました。この中で、再エネの優先購入や州をまたぐ電力融通料金の25年間の減免などの支援策を列挙しています16。
産業部門の対策については、省エネ法のもと、省エネ目標に向けて、一種の排出権取引のような仕組みが2012年から活用されています。著しい都市化や水道網の整備等の様々な開発目標の策定や、住環境の整備、温暖化対策がとられています。
【第121-2-3】インドの諸目標
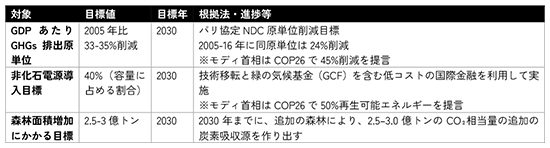
- 資料:
- インド政府「NDC」、インド政府「気候変動枠組条約第3次隔年報告書」、モディ首相COP26演説を基に作成
⑧ロシア
2020年11月、ロシアはNDCを国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)事務局に提出し、温室効果ガスを2030年までに1990年比で30%削減という目標を掲げています。なお、ロシアは長期戦略を提出していません(2022年3月現在)。NDCでは、気候変動対策の一つとして、全ての部門におけるエネルギー効率向上を掲げています。「省エネルギー・エネルギー効率法」(2009年制定、2010年発効)が基盤となり、高効率設備の導入、メーター設置、省エネマークの規定、新規建築物のエネルギー効率規定等が導入されています。電気自動車の普及についてはNDCでの言及はありませんが、2021年8月、経済発展省が電気自動車の購入補助制度の導入を発表しました。
2021年10月、プーチン大統領は、「ロシアは実際に、経済のカーボンニュートラル化を目指していく。遅くとも2060年までにというベンチマークを設定した。」と発表し、ロシアもカーボンニュートラルを宣言しました。2021年10月、ロシア政府は、2050年までの温室効果ガス排出削減を伴うロシア社会経済発展戦略を発表しました。目標シナリオでは、GHGネット排出量を2050年に2019年比60%削減(1990年比80%削減)とし、このシナリオを継続することで2060年カーボンニュートラルを達成する計画です。排出量削減に向けて、石炭火力発電・産業部門への低炭素技術の導入やエネルギーリサイクルの促進、低炭素電源(ガス火力・原子力・水力・再生可能エネルギー)への転換、より厳しい環境基準や経済インセンティブの導入、鉄鋼・化学産業における水素利用の拡大、電気自動車利用の増加ペースの加速、GHG回収などに取り組む方針を示しています。また、技術導入やリサイクルに加え、森林など生態系による温室効果ガスの吸収量を増加させる方針です。
COLUMN
水素、金属鉱物について
電化・水素化を進めようとすれば、必要となる金属鉱物(クリティカル・ミネラル17)や水素は必須となる戦略物資です。IEAによれば、2050年には、化石燃料の貿易量よりもこれらの物資の貿易が重要になり、地政学も変わり得るとしています。クリティカル・ミネラルは、加工の半分以上を中国が占めることから、輸入元を多様化していく取組の必要があります。また、水素は、日本・韓国など東アジアとEUが需要国・地域となり、中東・北アフリカやオーストラリアが供給国となり、化石燃料と同様の構造となる可能性があります。
【第121-2-4】クリティカル・ミネラル製造の上位3ヵ国のシェア
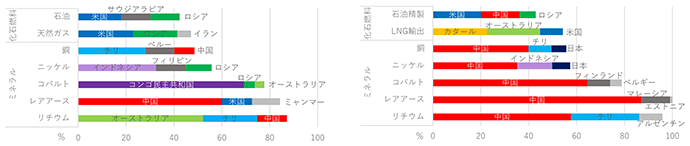
【第121-2-4】クリティカル・ミネラル製造の上位3ヵ国のシェア(xls/xlsx形式29KB)
- 資料:
- IEA「The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions: World Energy Outlook Special Report」
- 1
- ①Climate Ambition Allianceへの参加国、②国連への長期戦略の提出による2050年CN表明国、2021年4月の気候サミット・COP26等における2050年CN表明国等をカウントし、経済産業省作成(2021年11月9日時点)。また、CO2排出量は、IEA(2020), CO2 Emissions from Fuel Combustionを基にカウントし、エネルギー起源CO2のみ対象。GDPは、World BankのWorld Development IndicatorsのGDP(constant 2015 US$)を基にカウント。
- 2
- 市場メカニズムとは、温室効果ガスの排出について、海外で削減した分を自国の削減としてカウントし、目標達成に計上する仕組みのこと。例えば、省エネやCO2排出量を減らすための技術などがすでに導入されていて排出量削減の余地が少ない国が、まだまだ削減ポテンシャルが高い国に対して技術を提供して排出削減し、その削減量の一部を自国の削減量としてカウントすることにより、世界の排出削減を効率的に進めることができます。
- 3
- COP26では、上記の他に、各国取組の報告様式の統一、2025年以降の新たな途上国支援の数値目標の議論開始等が合意されました。また、COP26でのインドの2070年カーボンニュートラル表明や、世界のメタン削減目標などを織り込んだ2021年11月時点のIEAのレポートによると、今世紀末までに地球の気温上昇を1.8℃に抑えることができるとされています。地球温暖化を2℃以下に抑える(さらに1.5℃に抑える努力を追求する)のに十分な野心的目標を各国政府が示したのは初となります。
- 4
- 環境(Environment)、社会(Society)、ガバナンス(Governance)を考慮した投資のこと。
- 5
- 日米英の他、EUで気候変動を含む開示基準案を22年半ばに提案、シンガポールで22年度から上場企業にTCFD開示を要請、23年度以降義務化、ニュージーランドで主要約200社にTCFD開示を義務化、23年度から開示、スイスで大手上場企業などにTCFD開示を要請、23年度以降順次義務化。香港で25年までにTCFD開示を関連業種に義務化等の動きがあります。
- 6
- Federal Highway Administration「The National Electric Vehicle Infrastucture(NEVI)Formula Program Guidance」(2022年2月発表)
- 7
- Federal Aviation Administration「Aviation Climate Action Plan」(2021年9月発表)
- 8
- European Council「Fit for 55」Webサイト(https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/)
- 9
- European Commission Webサイト(https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-631_en.pdf)
- 10
- BEIS「Future Funding for nuclear plants An explanation of the Regulated Asset Base(RAB)model option」(2021年10月)
- 11
- 連邦経済・気候保護省(BMWK)Webサイト(https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2022/04/20220406-federal-minister-robert-habeck-says-easter-package-is-accelerator-for-renewable-energy.html)
- 12
- 経済・財務・復興省「Discours de Bruno Le Maire - Présentation des 15 projets français sélectionnés pour le PIIEC hydrogène」(2022年3月発表)
- 13
- EDF「EDF signe un accord d’exclusivité pour l’acquisition d’une partie de l’activité nucléaire de GE Steam Power」(2022年2月プレスリリース)
- 14
- 国務院「国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知」(2022年1月発表)
- 15
- 国家発展改革委員会「高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)」(2021年11月発表)
- 16
- Ministry of Power「Ministry of Power notifies Green Hydrogen/ Green Ammonia Policy A Major Policy Enabler by Government for production of Green Hydrogen/ Green Ammonia using Renewable sources of energy A step forward towards National Hydrogen Mission」(2022年2月発表)
- 17
- IEA「The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions」(2021年5月公表)では、銅、コバルト、ニッケル、リチウム、亜鉛、アルミニウムなど、クリーンエネルギー技術に必要な金属鉱物を「Critical Mineral」と称している。