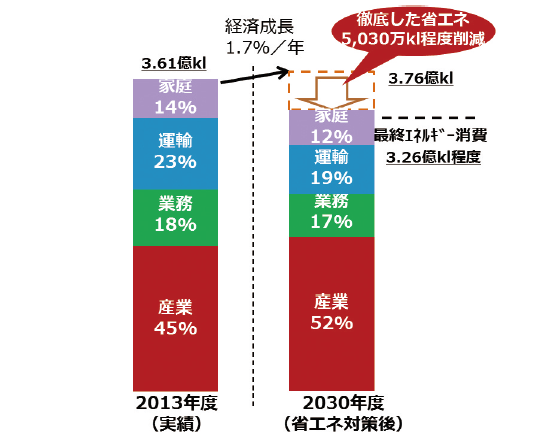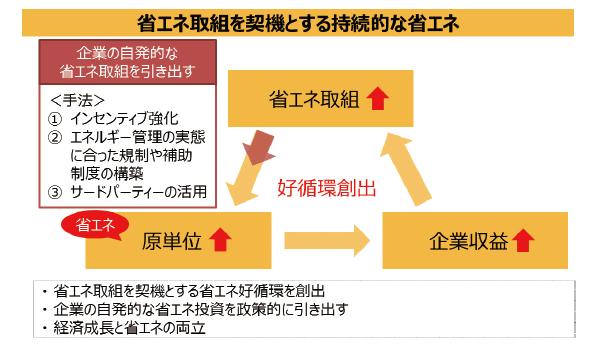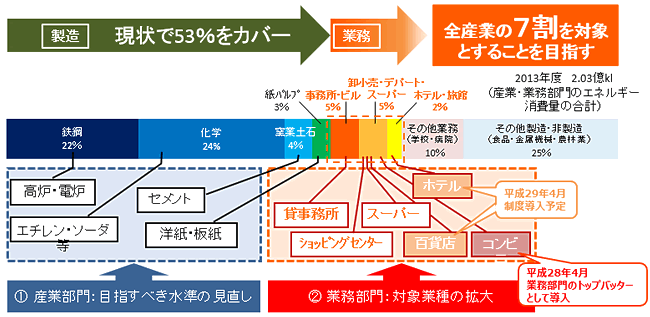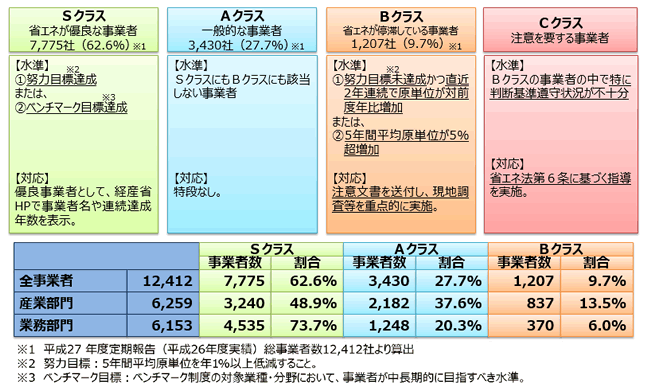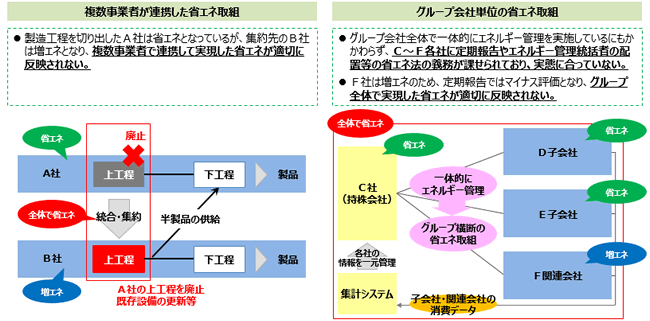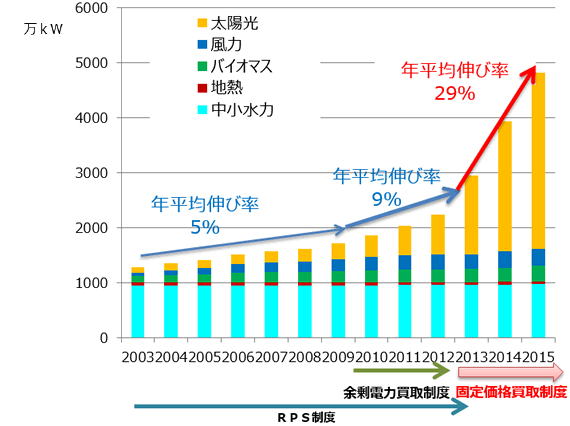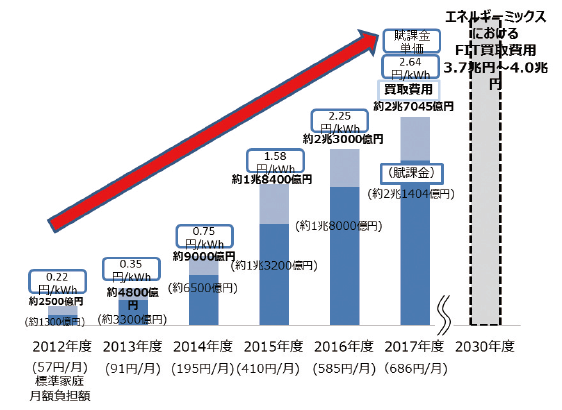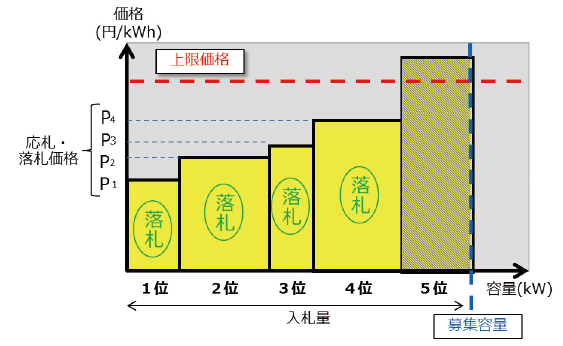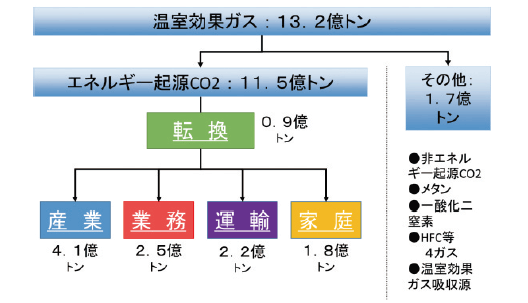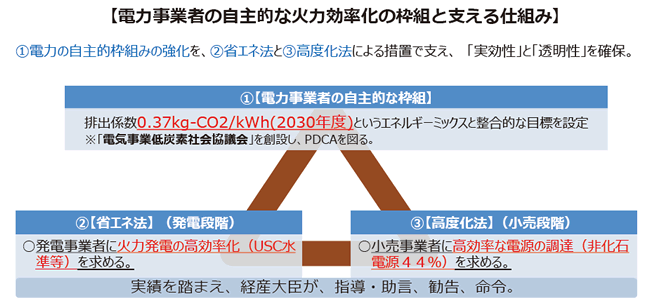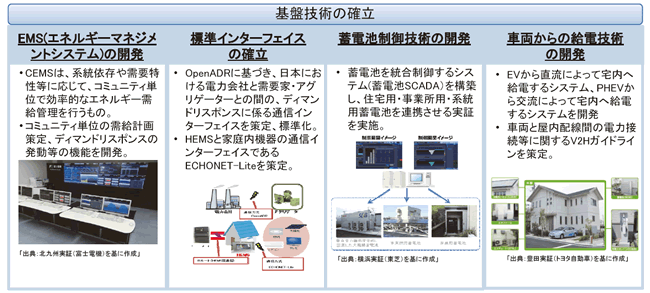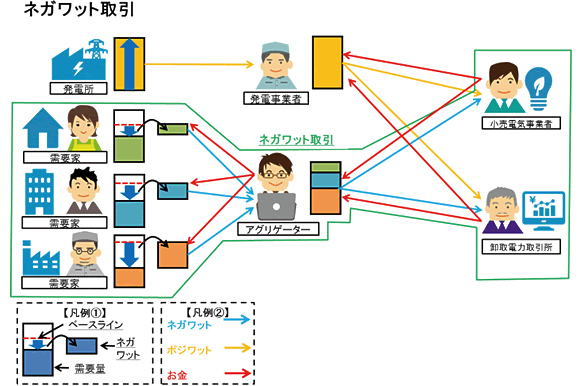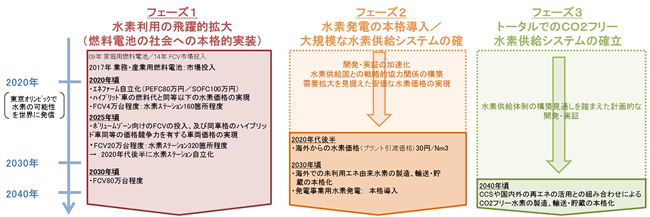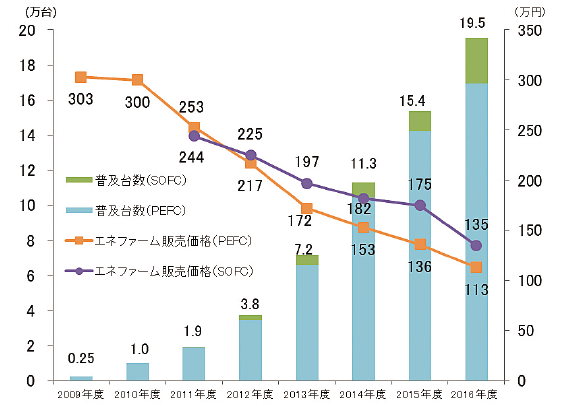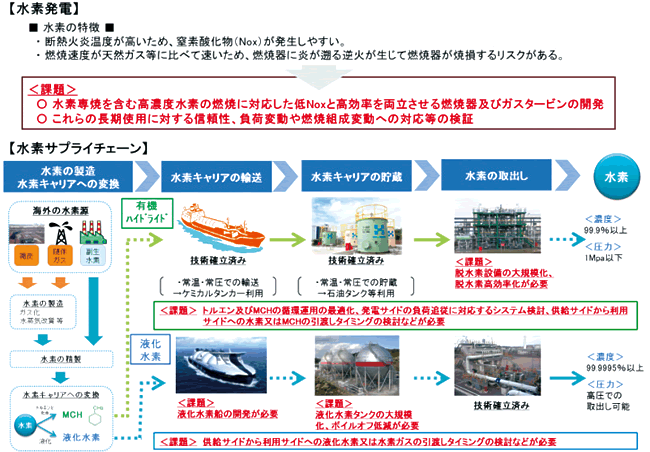第2節 環境制約と成長を両立する省エネルギー・再生可能エネルギー政策
はじめに
2014年6月に閣議決定された「エネルギー基本計画」及び2015年7月に策定された「長期エネルギー需給見通し(エネルギーミックス)」の実現に向けて、徹底した省エネルギー(以下「省エネ」という。)の推進、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入と国民負担抑制の両立、火力発電の高効率化、安全性の確認された原発の再稼働などを進めていくこととしています。
省エネについては、年1.7%の経済成長を前提に、2012年度から2030年度までの約20年間に、エネルギー消費効率(=最終エネルギー消費量/実質GDP)を35%程度改善することを見込んでいます。そのため、省エネポテンシャルを最大限深堀りするため、事業者単位で自発的に省エネへの取組が進むための事業者のインセンティブの強化、事業者単位を超えて複数事業者が連携した省エネへの取組の促進、省エネノウハウを有する民間企業の省エネビジネスを活用した省エネ等、徹底した省エネと経済成長の両立に向けた取組を紹介します。
また、再エネは、資源の乏しい我が国のエネルギー自給率の向上や化石燃料輸入の削減に寄与し、温室効果ガスを排出しないエネルギー源であり、その役割は非常に重要です。固定価格買取制度の見直しをはじめ、系統整備や系統運用ルールの整備、発電設備の高効率化・低コスト化や系統運用の高度化等に向けた技術開発など、エネルギーミックスにおいて示された2030年度における再エネの導入水準(22 ~24%)の実現に向けた取組を紹介します。
加えて、本節では、強い経済とCO2抑制の両立に資する、徹底した省エネを推進するための制度、再エネを最大限導入するための制度や、環境性やエネルギー安全保障から将来の二次エネルギーの中心的役割を担うことが期待されている水素を活用する社会の実現に向けた取組を紹介します。
1.徹底した省エネと経済成長の両立
「エネルギー基本計画」の考え方を踏まえ、エネルギーミックスにおいては、年1.7%の経済成長を前提に、徹底した省エネへの取組を積み重ねることで、2030年度に原油換算で5,030万kl程度、最終エネルギー消費を削減する目標を設定しました。これは、2030年度までの約20年間にエネルギー消費効率を35%程度改善することに相当し、1970年代のオイルショック後の20年間に我が国が達成したエネルギー消費効率の改善率に匹敵する、野心的な目標です。しかし、我が国のエネルギー消費効率は現在でも世界最高水準ですが、1990年代以降は改善のペースは鈍化しています。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
【第122-1-2】エネルギー消費効率改善
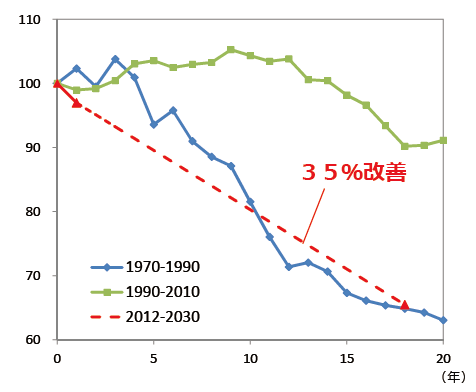
縦軸は1970年、1990年、2012年のエネルギー消費効率を100とした場合の各年のエネルギー消費効率
- 出典:
- 資源エネルギー庁
この状況下でエネルギーミックスを実現するためには、産業・業務・家庭・運輸の各部門にて、徹底した省エネと経済成長を両立させ、さらに省エネを深掘りする必要があります。そのために、2016年4月に経済産業省が決定した「エネルギー革新戦略」における省エネ対策では、事業者が自主的に省エネ投資を行うことでエネルギー消費効率を改善し、それが生産性向上やコスト削減を通じて競争力の強化・収益拡大につながることで、さらなる省エネ投資が実現する好循環を創出することを目指しています。具体的には、①事業者単位で自発的な省エネへの取組を促進するため、事業者に対する省エネインセンティブの強化、②新たな生産・流通プロセスの導入の進展等により変化するエネルギー管理の実態等のもとで、企業の経営方針に沿って省エネに取り組むことができる制度の構築、そして、③省エネノウハウが不足する中小企業や家庭等の省エネポテンシャルを掘り起こす環境整備をするためのネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(以下「ZEH」という。)ビルダーやエネルギーマネジメント(以下「エネマネ」という。)事業者等の省エネノウハウを有する民間企業の活用の促進の3点について、制度と支援の両面から必要な施策を順次検討し、実施していきます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
(1)事業者単位での省エネインセンティブの強化
我が国では、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)による各部門に対する規制とエネルギー使用合理化等事業者支援補助金(以下「省エネ補助金」という。)等による支援の両輪により、事業者の省エネへの取組を促してきました。省エネ法では、エネルギーを使用する事業者に対して、エネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るために必要な判断の基準となるべき事項(以下「判断基準」という。)に示された取組の実施と、エネルギー消費効率の改善に関する目標の達成に向けた努力を促しており、事業者の省エネへの取組を後押しする支援策との連携により、我が国の省エネを進めてきました。
省エネ法により事業者の自主的な取組を一層促す観点から、より実効性の高い制度となるよう、2016年度は、産業トップランナー制度(以下「ベンチマーク制度」という。)のさらなる拡大に向けた検討を行うとともに、2016年度から事業者クラス分け評価制度(SABC評価制度)の運用を開始しました。
①産業トップランナー制度(ベンチマーク制度)
省エネ法では判断基準において、特定事業者(事業者単位で年度あたり原油換算1,500kl以上エネルギーを使用する事業者)に対し、エネルギー消費原単位の年平均1%以上の低減を努力目標として定め、エネルギー消費原単位の低減率などを踏まえ、特定事業者の省エネへの取組を評価しています。
エネルギー消費原単位とは、エネルギー使用量を、生産数量又は建物延床面積その他のエネルギー使用量と密接な関係をもつ値で除した値です。分母のエネルギー使用量と密接な関係を持つ値を事業者が自ら設定することで、事業者のエネルギー消費実態に合わせて省エネへの取組を経年的に評価・把握することができます。
他方、エネルギー消費原単位は同業他社でも異なる場合があり、これを活用しても同業他社との省エネへの取組の比較は難しく、自社の省エネへの取組の相対的な立ち位置が分かりにくい側面もあります。
そこで、事業者の省エネへの取組を相対的に比較できるよう、2008年にベンチマーク制度を導入しました。判断基準の目標として、特定事業者に対し、従来の「エネルギー消費原単位の年平均1%以上低減」に加え、業界ごとの状況を考慮した新たな指標を設定し、事業者に業界における客観的な位置付けに基づいた取組を促しています。
ベンチマーク制度は、これまで製造業を中心に導入が進められており、製造業のエネルギー消費量の約80%をカバーしており、全産業のエネルギー消費の53%をカバーしています。「日本再興戦略2016」(2016年6月閣議決定)に示された、「3年以内(2018年度中)に全産業のエネルギー消費の7割に拡大」するとの方針に沿って、現在進めている流通・サービス業への拡大については、2016年4月に導入されたコンビニエンスストア業に続き、2017年4月から、ホテル・百貨店にも導入されることとなります。今後も、食料品スーパー、貸事務所、ショッピングセンター等への導入を検討していきます。
②事業者クラス分け評価制度(SABC評価制度)
2016年度から開始されたSABC評価制度は、優良事業者と停滞事業者を中心に、事業者全体の省エネへの取組に対する意欲を向上させることを目的としています。2016年度は12,412事業者のうち、7,775事業者をSクラスと位置付け、経済産業省HPで公表しました。2016年度の実施結果のフォローアップを踏まえ、今後、事業者の自主的な省エネへの取組をさらに促進するためのSABC評価制度の活用を検討していきます。
また、停滞事業者に対しては、2016年度は5月末に1,207事業者に対して注意喚起文書を送付するとともに、370事業所に対して現地調査を実施しました。これらの事業者について、省エネが停滞する理由を詳細に把握・分析し、事業者の実情を踏まえた支援を強化するとともに、必要があれば省エネ法に基づく追加的な措置も検討することで、本制度により、事業者の省エネへの取組を一層促進します。
なお、事業者の自主的な省エネへの取組を促すためには、省エネへの取組の水準を業界内・地域内等で自己診断できるようにすることも肝要です。そのため、各企業から提出された定期報告データを業種・規模・地域等の観点から整理して公表するなど、省エネ関連データのオープン化を通じて、事業者による自主的な省エネへの取組を促進するための検討も今後進めていきます。
- 出典:
- (一財)日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧2015」
- 出典:
- 資源エネルギー庁
- 出典:
- 資源エネルギー庁
(2)エネルギー管理の実態に合った規制や補助制度の構築
経済成長と両立する省エネを積極的に推進していくためには、新しいビジネスのあり方の下で、エネルギー管理の実態と企業の経営方針を踏まえた規制や補助制度の構築が不可欠です。エネルギー管理の変化として、今後IoT等を活用した新しい生産・流通プロセスの導入が進展していくことから、省エネの取組も、個々の事業者の枠を越え、業界、サプライチェーン、グループ単位等の複数事業者が連携した取組に拡大していくことが予想されます。
複数事業者が連携した省エネへの取組として、複数の事業者が協力し、工程の一部を特定の事業者に集約することで、全体の生産性を向上させ、全体として省エネを実現する事例があります。また、個々の事業者では小規模にとどまるエネルギー需要を、調整者が複数の事業者について束ね、大型で高効率なコージェネレーションシステムを導入する事例、さらに、これまで個々の事業者ごとに行っていた貨物輸配送を共同で行う事例などがあります。このように、複数事業者が連携した省エネへの取組には様々なケースが想定されており、事業者単独では実現できない省エネポテンシャルを引き出すことに繋がることが期待されます。
また、企業経営が多様化する中で、持株会社傘下のグループ会社全体で一体的にエネルギー管理を行う事例も生まれています。このようなエネルギー管理は、省エネ法が求める個々の事業者ごとのエネルギー管理の枠を越え、さらなる省エネポテンシャルの掘り起こしに繋がることが期待されます。
さらに、産業政策と一体化した省エネへの取組を業界で促進する観点から、データ取得およびネットワーク接続が可能な射出成型機を活用した生産効率化の取組や、自動車産業で取組が進んでいるシミュレーション技術を活用した開発プロセスの省エネなど、IoT等新たな生産プロセスを活用した先進的な省エネへの取組を進めることも重要であり、省エネ法の業種別告示に2017年度から位置付け、こうした取組により、業界単位での省エネを促進していきます。
エネルギーミックスの野心的な目標に向けて、個々の事業者単位の省エネへの取組に加えて、このような複数事業者が連携した省エネへの取組を新たな省エネの手法として積極的に推進するため、省エネ法における複数事業者が連携した省エネへの取組の評価制度のあり方や支援策について、見直しを進めていきます。
(3)省エネノウハウを有する民間企業を活用した省エネポテンシャルの深掘り
中小企業や家庭等、省エネノウハウを必ずしも有しない主体の省エネへの取組を促進するためには、省エネノウハウを有し、これら主体に働きかけることができる民間企業の省エネビジネスや企業活動を活性化することも重要です。そのため、省エネノウハウを有する民間企業に働きかけを促す適切な動機を与えるとともに、支援策の充実やオープンデータの提供等を含め、これをビジネスとして成長させる仕組みづくりの検討を進めていきます。具体的な事例としては、以下の通りです。
【第122-1-7】省エネノウハウを有する民間企業の活用例
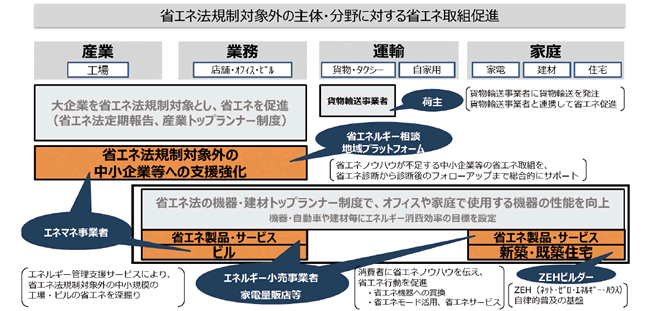
- 出典:
- 資源エネルギー庁
①我が国では、住宅の省エネ化を進めるため、ZEHの普及を進めています。ZEHとは、大幅な省エネを実現した上で、再エネにより、年間で消費するエネルギー量をまかなうことを目指した住宅であり、2020年までに標準的な新築住宅で、2030年までにほぼすべての新築住宅でZEHの実現を目指すことを政府目標として掲げています。ZEHの自律的普及を図るため、建築主(消費者)を対象とする補助制度を設けていますが、 ZEHの自立的普及の基盤として、ZEHの建築を消費者に働きかけるハウスメーカーや工務店、設計事務所が全国で増加する必要があります。そこで、これらハウスメーカー等について省エネノウハウを有する民間企業と捉え、ZEHの販売目標や販売実績を公表して積極的に取り組むハウスメーカー等を「ZEHビルダー」と位置付け、その活用を補助金交付の要件とすることで、ハウスメーカー等の取組を促し、ZEHの普及を進めています。実際、2017年2月の時点で、ZEHビルダーは既に約4,500事業者に達し、ZEHの普及に必要な体制が整いつつあります。
②省エネ補助金において、エネルギーマネジメントシステム(以下「EMS」という。)を導入し、エネルギー管理支援サービスによって他の事業者の工場等の省エネ対策等を支援する者をエネマネ事業者として位置付け、エネマネ事業者を活用する事業については、活用しない事業と比べて補助率を優遇しています。このようなインセンティブを与えることで、エネマネ事業者による工場等への働きかけを後押しし、省エネへの取組の掘り起こしや深掘りに繋げています。
③全国19か所に設置されている省エネルギー相談地域プラットフォームは、中小企業等の省エネを支援する事業者が、地域の専門家(商工会議所や自治体、コンサル及び金融機関等)と協力する省エネ支援の連携体です。省エネ診断から診断後のフォローアップまで中小企業等の省エネへの取組を総合的に支援しています。今後は「日本再興戦略 2016」の方針を踏まえ、省エネルギー相談地域プラットフォームを拡大し、2017年度までに全国に省エネへの取組に関する支援窓口を構築することなどを通じて、中小企業の経営課題の解決に向けた一手段として、中小企業の省エネ投資や設備の運用改善に向けた支援を強化します。
④電力ガス小売全面自由化の中で、多様な製品・サービスが登場し、需要家のエネルギーの使い方は大きく変化すると考えられます。そこで、効果的な情報提供やサービスの展開を通じて、自由化環境下においても需要家が適切に省エネに取り組める環境整備を進めるため、需要家と直接の接点を持ち、省エネ法で情報提供の努力義務が求められているエネルギー小売事業者を省エネノウハウを有する民間企業と捉え、需要家の省エネに資する情報提供等のあり方の検討を進めています。
⑤2005年の省エネ法改正で運輸部門が新たに省エネ法の規制対象となった際、貨物運送事業者とともに荷主も対象となりました。荷主自身は輸送に関してエネルギーを消費しませんが、貨物輸送事業者に発注する立場であり、輸送に関わる省エネノウハウを有する民間企業として捉えられます。実際、省エネ法では、判断基準において、特定荷主(事業者単位で自らの貨物輸送量が年度あたり3,000万トンキロ以上になる事業者)に対して、貨物輸送事業者との連携等による省エネ努力を求めています。近年、Eコマース等の発展に伴い、運輸部門のエネルギー消費の構造には変化が見られ、小口輸送・再配達の増加により、エネルギー消費の増大が懸念されています。これに対し、貨物の所有権を前提として運用されている省エネ法の荷主(現行の省エネ法の特定荷主の約8割は製造業)の定義では捕捉できない荷主が存在することに留意して、貨物輸送事業者と荷主の連携促進に向けた対応を検討しています。
2. 再エネの最大限導入と国民負担抑制の両立
2015年7月に策定されたエネルギーミックスでは、2030年度の再エネの導入水準を電源構成の22~ 24%、その場合の固定価格買取制度(以下「FIT」という。)における買取費用総額を3.7 ~ 4兆円程度と見込んでいます。FIT開始後の4年で再エネの導入量は2.5倍となるなど、同制度は再エネ推進の原動力となっています。一方で、FITでは、再エネ由来の電気の買取に要した費用の一部を、賦課金として電気料金に上乗せする形で国民が負担することになっており、2016年度には買取費用の総額が2.3兆円に達するなど、国民負担増大への懸念等の課題が生じています(なお、2017年度は買取費用総額が2.7兆円に達する見込み)。このため、再エネの最大限導入と国民負担の抑制の両立を目指し、2016年5月に電気事業者による再エネ電気の調達に関する特別措置法の改正(以下「改正FIT法」という。)により、制度の見直しを行いました。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
- 出典:
- 資源エネルギー庁
(1)新認定制度創設による未稼働案件の排除と適切な事業実施の確保
FITでは、認定の取得だけを行い、再エネの運転開始が未稼働のまま設備価格の低下を待っている案件や、運転開始をしないで認定の権利が転売される案件も存在していました。こうした未稼働案件の滞留は、系統制約が顕在化する中で、系統枠の空押さえにより後発の高性能・低価格の事業の参入の妨げとなり、潜在的な国民負担の増大をもたらす恐れがあります。こうした状況を解決するため、改正FIT法の施行日前である2017年3月31日までに電力会社と接続契約(連系承諾および工事費負担金契約)を締結していない過去FITの認定を受けた事業者については、FIT法に基づく認定(FIT認定)を原則失効することとしました。一方で、同日までに既に接続契約締結済み(発電開始済みを含む)の事業者については、改正FIT法下において創設された新しい認定制度において認定を受けたものとみなします(みなし認定)。
併せて、太陽光発電については、新たな未稼働案件の防止の観点から、認定取得後、早期に運転を開始するインセンティブを与え、各種手続きや工事着手が遅延することがないように、運転開始までに一定の期限を付しました。具体的には10kW未満の太陽光発電については認定から1年(1年を経過したものは認定が失効)、10kW以上の太陽光発電については認定から3年という期限を設定することとしています(3年を経過したものは経過した期日分だけ買取期間が短縮)。
また、再エネが我が国の重要な安定電源となるためには、再エネの発電事業者が長期にわたり安定的に発電を継続していくことが重要です。そこで、改正FIT法における新しい認定制度では、従来の「設備認定」から事業者の長期的な事業の実施内容に着目した「事業計画認定」に変更しました。その事業計画の認定にあたっては、新たな認定基準として、事業の適切な実施の確認のために接続契約を求めることや、事業実施中の点検・保守や事業終了後の設備撤去等の遵守を求めるなど、再エネの長期安定電源化に向けて適切な事業実施を確保する仕組みとしました。
また、再エネの普及拡大にあたっては、地域社会の理解を得て長期安定的な発電を継続し、地域社会と共生した形で導入を図っていくことが不可欠です。そのため、改正FIT法では、FITの適用を受ける事業を運営するにあたって必要な他法令の遵守を求めると共に、当該関係法令に違反した事案について、当該法律の罰則等の措置のみならず、FIT法においても改善命令を行い、場合によってはFITの認定の取消を行うことが出来る仕組みとしています。また、自治体が各地域での再エネ発電事業において、地域トラブルへの対応を的確に行うことができるよう、2016年4月から自治体に認定情報を提供するシステムの運用を開始しています。
このように、改正FIT法の下では、再エネの発電事業者が、責任ある形で地域とも共生をしながら長期安定的に発電をしていくことを求めています。
(2)大規模太陽光に対する入札制度実施による価格抑制
再エネの最大限導入と国民負担抑制の両立のためには、コストを下げながら、多くの再エネを導入していく、コスト効率的な導入が重要です。現行の固定価格買取制度では、「通常要する費用」を基礎に調達価格を算定しているため、コスト効率的な導入をさらに進めるにあたっては、競争的な仕組みが不可欠です。そのため、今般の改正FIT法では入札制度を導入しました。改正FIT法上、入札制度について、経済産業大臣は、①買取単価について入札を行うことが国民負担の軽減につながる際に、②入札対象の電源区分等を指定することができ、その際には、③入札実施指針を策定することとしています。
具体的には、コストベースで買取価格を決定する方式から、事業者間の競争を通じて買取価格を決定する方式とし、買取価格が決まった後は従来のFITと同様、固定価格で一定期間FIT電気の買い取りを行います。今回、入札制度の対象は、導入が進んでいる大規模な事業用太陽光(2MW以上)とし、応札額を調達価格として採用する方式(pay as bid方式)にて今後2年間で計3回、合計1 ~ 1.5GWを入札量として募集し、試行的に入札制度を実施することとなっています。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
(3)中長期的な価格目標の設定
改正FIT法では、将来の買取価格の予見可能性を向上させるとともに、その目標に向けた事業者の努力やイノベーションによるコスト低減を促す観点から、電源(買取区分)毎に中長期的な買取価格の目標を経済産業大臣が設定することとしました。従来、買取価格は、「通常要する費用」を基礎として、利潤や供給の量の状況等を勘案したコストベースに基づいて算定してきましたが、今後はこの中長期的な価格目標も勘案した上で算定することとなります。各電源毎の価格目標は次の通りです。
①太陽光
- FITからの自立を目指し、以下の水準を達成。
- 非住宅用太陽光:
2020年に発電コスト14円/kWh
2030年に発電コスト7円/kWh - 住宅用太陽光:
2019年に調達価格が家庭用電気料金並み
2020年以降、早期に売電価格が電力市場価格並み
②風力
- 20kW以上陸上風力:2030年までに、発電コスト8~9円/kWhを実現。FITから自立した形での導入を目指す。
- 20kW未満の小型風力発電:導入動向を見極めながら、コスト低減を促し、FITからの中長期的な自立化を図る。
- 洋上風力発電:導入環境整備を進めつつ、FITからの中長期的な自立化を図る。
③地熱
- 当面は、FITに加え、地元理解促進や環境影響評価手続の迅速化等により、大規模案件の開発を円滑化。
- 中長期的には、技術開発等により開発リスク・コストを低減し、 FITからの自立化を図る。
④中小水力
- 一度新規に地点開発を行った後は、調達期間終了後も必要な修繕を行っていくことにより、低コストで長期的な発電を行うことが可能。
- 当面はFITに加え、流量調査等によるリスク低減を進め、新規地点開発を促進すると共に、技術開発によるコスト低減等を進め、FITからの中長期的な自立化を図る。
⑤バイオマス
- 燃料の集材の効率化等の政策と連携を進めながら、FITからの中長期的な自立化を図る。
3. 電力市場への新規参入と CO2排出抑制の両立
ここでは、強い経済とCO2抑制の両立に資する省エネや再エネを最大限導入するための制度や電力業界の自主的枠組みとそれを後押しする制度について紹介します。
(1)0.37kg-CO2/kWhに向けた高度化法、省エネ法の整備
エネルギー起源CO2は我が国の温室効果ガスの9割を占め、そのうちの転換部門、特に電力部門は、自らの事業所から排出するCO2の抑制に加えて、提供する電力の低炭素化によって、電力使用者のCO2排出抑制に貢献するなど、大きな役割を果たしています。
このような観点から、電力業界では、京都議定書の第一約束期間におけるCO2排出削減の自主目標として、1990年度比で20%程度削減のCO2排出係数0.34kg-CO2/kWhを掲げ、他国と比べても低いCO2排出係数を維持しておりました。しかしながら、震災後の原子力発電所の停止等の影響により、CO2排出係数は大幅に増加しています。
- 出典:
- 経済産業省
【第122-3-2】各国のCO2排出係数実績と日本の2030年度目標
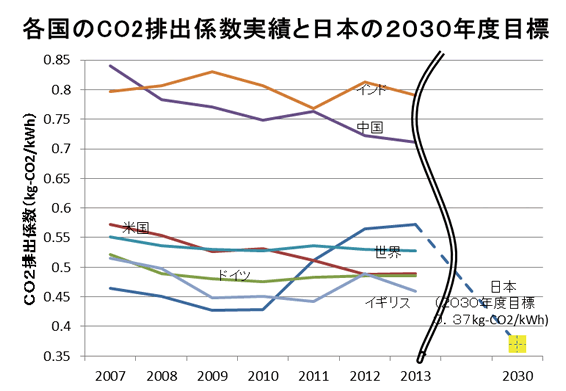
各国の火力発電効率と比較しても、日本の火力発電効率は最上級であるが、エネルギーミックスを達成するためにはさらなる高効率化や低炭素化を進める必要がある。
- 出典:
- CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION 2015より、資源エネルギー庁作成
その後、エネルギーミックスにおいて2030年度の電力需給構造が示され、これに合わせて、2015年7月に主要な事業者が参加する電力業界の自主的枠組み(国のエネルギーミックス及びCO2削減目標とも整合する二酸化炭素排出係数0.37kg-CO2/kWhを目標)が発表されました。2016年2月には、電気事業低炭素社会協議会が発足し、個社の削減計画を策定し、業界全体を含めてPDCAを行う等の仕組みやルールが発表されたところです。
この自主的枠組みの目標達成に向けた取組を促すため、省エネ法及びエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(以下「高度化法」という。)に基づく政策的対応を行うことにより、電力自由化の下で、電力業界全体の取組の実効性を確保していくこととしています。
省エネ法は石油危機を契機に制定された、エネルギー需要サイドの化石燃料の使用の合理化を求める法律です。省エネ法においてこれまでも火力発電設備の性能に関するベンチマーク指標が設けられてきましたが、エネルギーミックスの実現に向けて、これを実際の運転時の発電効率を評価できる厳しい指標に見直すこととしました。これによって、発電段階で、エネルギーミックスと整合的な発電効率の向上を求めていきます。
具体的には、省エネ法に基づき、発電事業者に、新設の発電設備について、発電設備単位で、エネルギーミックスで想定する発電効率の基準を満たすこと(石炭42.0%以上、LNG50.5%以上、石油等39.0%以上)を求めます。既設の発電設備については、発電事業者単位で、エネルギーミックスで想定する発電実績の効率(火力発電効率A指標:目指すべき水準を1.00以上(発電効率の目標値が石炭41%、LNG48%、石油等39% (いずれも発電端・HHV)が前提)、火力発電効率B指標:目指すべき水準を44.3%(発電端・HHV)以上)の基準を満たすことを求めます。
また、高度化法は、エネルギー供給サイドにおける非化石エネルギー利用等を促してきた法律です。これをエネルギーミックスの改訂にあわせて、小売電気事業者に非化石電源比率44%を求めることとします。これによって、小売段階で、エネルギーミックスと整合的な販売電力の低炭素化を進めていきます。その際、小売電気事業者の非化石電源調達目標の達成を後押しするための措置として、第3節にて後述する非化石価値取引市場を創設することとしています。
(2)ネガワット取引市場とバーチャルパワープラントの構築に向けた取組
再エネの拡大や、東日本大震災により生じた電力不足により、既存の大規模集中型の電力システムの脆弱性が明らかとなったことを受け、需要家側のエネルギーリソース(蓄電池や各種需要設備など)を電力系統の安定化などに有効に活用する、新たなエネルギーシステムの構築が課題となっています。経済産業省では、これまで、「スマートコミュニティ」に関する様々な実証事業を実施し、需要家側のエネルギーリソースの活用に向けた基盤的技術の開発・実証を行ってきました。こうした技術の進展と、一連の電力システム改革を踏まえ、経済産業省では、ネガワット取引市場の創設とバーチャルパワープラントの構築に向けた取組を進めています。
①ネガワット取引市場の創設
ネガワット取引とは、電力の需要家が、本来であれば使用する予定であった電力量(ベースライン)より、実際に使用する電力量を抑制(節電)することにより生じた電力量の差分(いわゆるネガワット)を、発電所で生み出す電力量(いわゆるポジワット)と同等とみなし、アグリゲーターと呼ばれる事業者を介して電力会社に提供することで、節電の対価として報酬を得る取引です。ネガワット取引は、発電所の建設などと比較して、大規模・長期の投資をすることなく、電力量の確保が可能であることから、より柔軟な電力システムを実現する上で有用であるとされ、電力自由化が進む諸外国においても、その活用が進んでいます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
- 出典:
- 資源エネルギー庁
- 出典:
- 資源エネルギー庁
2015年6月に公布された電気事業法等の一部を改正する等の法律(第3弾)では、ネガワット取引の円滑化に向けた制度が法定されました。また、2015年11月の第3回「未来投資に向けた官民対話」では、安倍総理から、需要家の節電のインセンティブを抜本的に高めるべく、ネガワット取引市場を2017年までに創設するよう、経済産業省に対して指示がなされました。これを受け、経済産業省では、2015年度から2016年度にかけて、より高度なネガワット取引の実証事業を実施するとともに、こうした実証の知見も踏まえつつ、ネガワット取引に関する事業者間取引ルールの策定や、関連する制度の整備等を行いました。また、電力会社などにおいても、ネガワット取引に対応したシステムの整備等が進められた結果、2017年4月には、ネガワット取引市場が創設されました。これにより、小売電気事業者が自社の供給力を確保するために市場を通じてネガワットを調達することが可能となりました。また、並行して、一般送配電事業者が確保する調整力の公募の際、ネガワットがポジワットと比較して差別的な取扱いを受けることのないよう、公募条件などについて検討を進めました。その結果、2016年度に実施された2017年度分の調整力公募においては、全国で、約100万kWのネガワットが落札されました。こうしたネガワット取引の社会への浸透を図るべく、経済産業省では、「ディマンドリスポンス(ネガワット取引)ハンドブック」を作成し、ネガワット取引に関する普及啓発を行っています。
②バーチャルパワープラントの構築
今後、再エネ設備や蓄電池などの需要家側のエネルギーリソースの拡大がより一層進むと考えられています。一方で、特に蓄電池などは、常時利用されているわけではないため、こうした未利用となっているエネルギーリソースを電力系統の安定化などに有効活用するビジネス(アグリゲーションビジネス)を創出できれば、電力システムの合理化に貢献するだけでなく、設置する需要家の経済的メリットが増加すると考えられます。
【第122-3-6】バーチャルパワープラントのイメージ
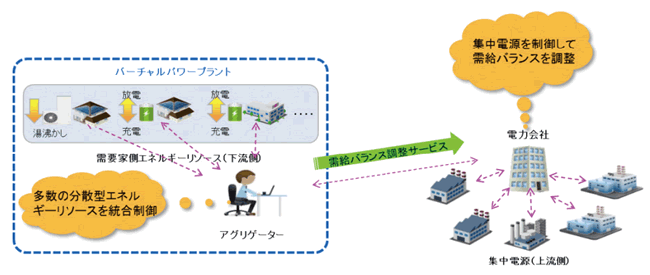
- 出典:
- 資源エネルギー庁
このため、2016年1月には、民間主体でアグリゲーションビジネスを推進するための合意形成の場として、関連する企業のトップマネジメント層をメンバーとする「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス・フォーラム」が創設されました。また、同月、経済産業省は、「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス検討会」を立ち上げ、通信規格の整備やサイバーセキュリティなど、アグリゲーションビジネスの振興に向けた様々な課題について、議論を開始しました。また、2016年度からは、需要家側のエネルギーリソースを、高度なエネルギーマネジメント技術により遠隔・統合制御し、あたかも一つの発電所のように機能させることで、電力の需給調整に活用する「バーチャルパワープラント」の構築に向けた実証事業を開始するなど、取組を加速しています。
4.水素エネルギー利用の意義と水素社会の実現に向けた取組の方向性
水素は、利用時にCO2を排出せず、燃料電池において活用することで大幅な省エネを実現するといった優れた特長を持ちます。また、水素の製造時にCCS(Carbon Capture and Storage: 二酸化炭素回収・貯留技術)を組み合わせる、又は再エネから水素を製造するといった水素の製造方法次第では、CO2排出量を大幅に削減、更にはCO2フリーのエネルギー源として水素を活用し得ると考えられることから、将来のクリーンエネルギーとして期待されています。また、エネルギー安全保障上も重要な役割が期待されており、「エネルギー基本計画」においても、「将来の二次エネルギーの中心的役割を担うことが期待される」としています。加えて、我が国では、通商産業省の「ムーンライト計画」の下、1981年から燃料電池の開発を進めており、燃料電池分野での特許出願件数が世界一位であるなど、産業政策の観点からも、水素エネルギー利用を進める意義は大きいと言えます。
- 出典:
- 水素・燃料電池戦略協議会「水素・燃料電池戦略ロードマップ」を基に作成
そこで、産官学の関係者からなる「水素・燃料電池戦略協議会」において、水素社会の実現に向けた官民のアクションプランである「水素・燃料電池戦略ロードマップ」(2014年6月策定、2016年3月改訂)を策定しました。このロードマップでは、水素社会の実現に向けて、技術面、コスト面、制度面、インフラ面で様々な課題があることを踏まえ、「主として技術的課題の克服と経済性の確保に要する期間の長短に着目し」、「ステップ・バイ・ステップで、水素社会の実現を目指す」としています。以下では、水素社会の実現に向けた3つのフェーズについて、最新の取組を紹介します。
(1)水素社会の実現に向けた3つのフェーズに関する取組
①水素利用の飛躍的拡大(フェーズ1)
フェーズ1では、足下で実現しつつある定置用燃料電池や燃料電池自動車(FCV)の利用を大きく広げ、我が国が世界に先行する水素・燃料電池分野の世界市場を獲得することを目指します。
定置用燃料電池としては、2009年から世界に先駆けて市場投入された家庭用燃料電池エネファームが、2017年度までに、累計で約20万台が普及しています。ロードマップでは、2016年3月の改訂により、2030年530万台の普及とともに、新たに価格低減目標(2019年度80万円(PEFC:固体高分子形燃料電池)及び2021年度100万円(SOFC:固体酸化物形燃料電池))を設定しましたが、2016年度末時点で、PEFCについては113万円、SOFCについては135万円と、順調に価格低減が進んでいます。また、業務・産業用SOFCについても、ロードマップの目標どおり、2017年の市場投入が見込まれており、今後普及が期待されます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
運輸分野では、2014年にFCVが市場投入され、それに先行する形で水素ステーションの整備が進められてきました。FCVについては、2016年3月に国内2車種目となる車両が発売され、累計約1800台(2017年3月末)が普及しています。また、商用水素ステーションについては、全国90箇所で開所(2017年3月末)し、比較的規模の小さな、再エネ由来の水素を活用するステーションについても、全国8箇所が開所(2017年3月末)するなど、世界に先駆けた整備が進んでいます。
FCVと水素ステーションは、FCVが普及しなければ水素ステーションの経営が困難であり、水素ステーションが普及しなければFCVの普及が困難であるという、いわゆる「鶏と卵」の関係にあるため、両者のバランスを取りながら普及を進めることが必要となります。このため、ロードマップでは、それぞれについて、中期的な普及目標を定めました。具体的には、FCVについては、2020年4万台程度、2025年20万台程度、2030年80万台程度を目指し、水素ステーションについては、2020年度160箇所程度、2025年度320箇所程度の整備を目指すとともに、2020年代後半の自立化を目指すこととしています。
こうした目標の達成に向けては、FCVや水素ステーションの整備・運営コストの低コスト化が欠かせません。このため、経済産業省では、FCVや水素ステーションの低コスト化に向けた研究開発を進めるとともに、累次の規制改革実施計画に基づき、様々な規制見直しを実施してきました。今後も、こうした取組を着実に進めることで、FCVや水素ステーションの普及を進めていきます。
②水素発電の本格導入と大規模な水素供給システムの確立(フェーズ2)
フェーズ2では、フェーズ1からさらに水素の用途を拡大し、水素発電の本格導入を目指します。また、水素発電では、水素を大量に消費することになるため、大規模な国際的水素サプラチェーンの構築も同時に目指します。
水素発電は、ガスタービン等で水素を燃焼させることによって行う発電です。水素発電の段階ではCO2を排出しないため、水素の製造時にCCS等を組み合わせ、又は再エネ由来の水素を活用することで、クリーンな発電が可能となります。また、海外の副生水素、原油随伴ガス、褐炭等の未利用エネルギーを水素源とすることが可能であり、我が国の電源構成に新たな選択肢を提供できる可能性があります。
【第122-4-3】水素ステーションの低コスト化に向けた研究開発の例
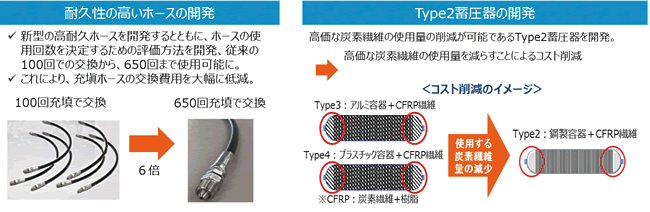
- 出典:
- 資源エネルギー庁
【第122-4-4】規制改革実施計画(平成27年6月に掲げられた規制見直し事項)
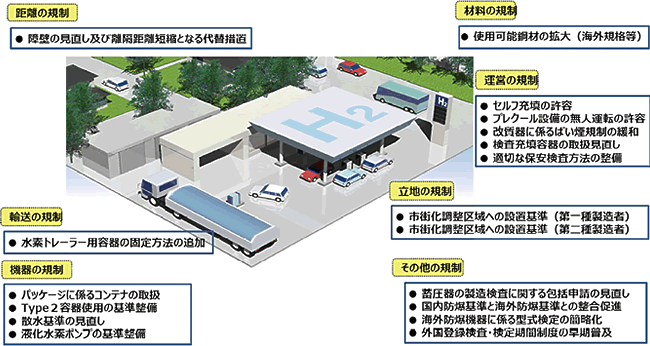
- 出典:
- 資源エネルギー庁
一方で、水素発電の実現により、安定的かつ大規模な水素需要が生じることとなるため、これに対応する大規模水素サプライチェーンが必要となります。大規模水素サプライチェーンを実現すれば、スケールメリット等により水素の価格低減が期待でき、フェーズ1で導入された燃料電池の経済性がより向上すると考えられます。
水素発電の基本原理は火力発電と同じであり、一部の設備(燃焼器など)の改造で水素混焼が可能です。このため、水素発電の導入に当たっては、①まずは、小規模な電源(コージェネレーションなど)で水素を活用しつつ、②既設の火力発電所の改造により水素混焼発電を実現し、③大規模水素サプライチェーンの構築と合わせ、水素専焼発電を導入する、というシナリオが考えられます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
【第122-4-6】有機ハイドライド(メチルシクロヘキサン)による水素サプライチェーンのイメージ
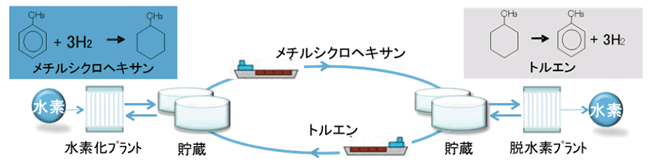
【第122-4-6】有機ハイドライド(メチルシクロヘキサン)による水素サプライチェーンのイメージ(ppt/pptx形式:125KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
一方、水素発電や水素サプライチェーンの実現に向けては、技術的な課題があるため、経済産業省では、その解決に向け、様々な研究開発・技術実証を行っています。具体的には、水素を活用した小規模(1千kW級)のコージェネレーション(大林組・川崎重工業)のオンサイトでの実証や、大規模(50万kW級)の水素混焼発電用の燃焼器等の技術実証(三菱日立パワーシステムズ・三菱重工業)、さらには、水素専焼発電に関する研究開発(川崎重工業、三菱日立パワーシステムズ・三菱重工業)を実施しています。小規模のコージェネレーションの実証については、2017年度中に試運転を開始し、世界初となる水素ガスタービンによる地域への電力・熱供給を行う予定です。また、水素サプライチェーンの実現に向けては、液化水素により水素を輸送する「豪州褐炭水素プロジェクト」のほか、有機ハイドライドにより水素を輸送するプロジェクト(千代田化工建設)も実施しています。
③トータルでのCO2フリー水素供給システムの確立(フェーズ3)
フェーズ3では、利用時だけではなく、製造時にもCO2を排出しない、トータルでのCO2フリー水素供給システムの確立を目指します。
現段階では、化石燃料由来の水素が主に用いられており、水素の製造段階でCO2が発生することから、地球規模の問題である地球温暖化への対応を考えた場合には、必ずしも十分ではないと言えます。したがって、将来的にはCCSや再エネの活用により、よりCO2の排出が少ない水素供給構造を実現していくことが必要となります。水素製造方法の一つである水の電気分解(水電解)技術を活用し、再エネ電気を水素に転換するPower-to-Gas(以下「P2G」という。)については、電力貯蔵技術としても注目されています。水素は、他のエネルギー貯蔵手段と比較すると、長期間・大容量のエネルギー貯蔵に優位性を持ち、また、ガスパイプラインなどにより、電力系統を経ずにエネルギーを輸送可能です。こうした特長をいかし、季節を越えた再エネの変動吸収や、再エネの地域偏在性の解消など、系統安定化対策やさらなる再エネ導入促進策としての水素の利活用が期待されています。諸外国(ドイツやフランスなど)でも、水素によるP2Gに関する実証が行われています。
【第122-4-7】水電解の方式
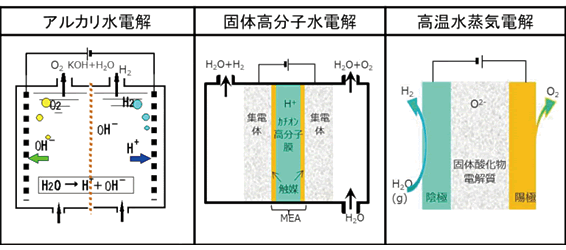
- 出典:
- 旭化成提供
【第122-4-8】様々な蓄エネルギー技術の優位性比較
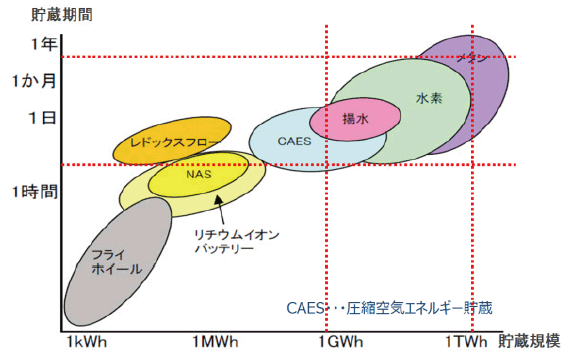
- 出典:
- Energieträger der Zukunft資料を基に資源エネルギー庁作成
【第122-4-9】Power-to-gas技術の様々な活用方法
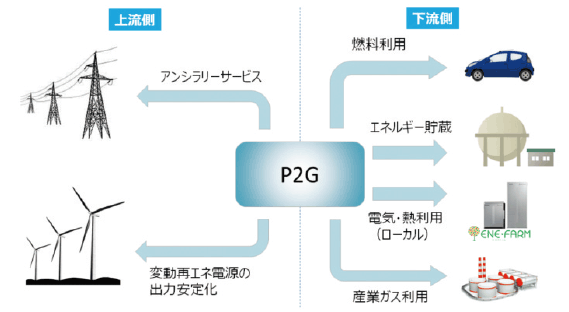
- 出典:
- 資源エネルギー庁
一方で、水電解による水素製造は、①水電解装置の大規模化が困難、②投入した電気エネルギーに対し、水素エネルギーとして得られる効率が約7割程度である、という課題に加え、投入する電気エネルギーを太陽光発電や風力発電などの変動電源で賄う場合には、③電流の変動が水電解装置のセルに悪影響を与え、損耗が激しくなる、④投入する再エネ自体が高コストであるため、水素の製造コストが上昇してしまう、という課題があります。
こうした課題に対し、経済産業省では、これまで、水電解に関する技術開発を実施し、その解決を図ってきました。また、福島新エネ社会構想では、こうした取組をさらに一歩進め、水素の大規模製造実証を実施することとしています。
また、トータルでのCO2フリー水素供給システムの実現には、技術的な課題とともに、経済性や制度の面でも課題があります。そこで、水素・燃料電池戦略協議会の下に「CO2フリー水素ワーキンググループ」を開催し、CO2フリー水素の普及拡大に関する課題の整理及び今後の取組の方向性について取りまとめました(2017年3月)。また、並行して、経済産業省では、P2Gに関する研究開発や技術実証を行っています。
【第122-4-10】水電解装置の一例と研究開発の取組
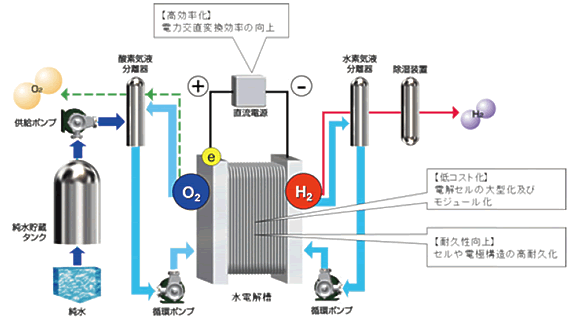
- 出典:
- 日立造船資料を基に経済産業省作成
C O L U M N
再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議
2017年4月11日、「第1回再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議」が開催されました。会議では、安倍政権の重要課題である再生可能エネルギーの導入拡大や水素社会の実現に向けて、関係閣僚間で議論しました。
再生可能エネルギーに関しては、その導入促進に向けた取組を強力に進めるため、関係府省庁が連携して取り組む施策をまとめた「再生可能エネルギー導入拡大に向けた関係府省庁連携アクションプラン」を決定しました。このアクションプランでは、今後5年を目処に以下のような12のプロジェクトを関係省庁が連携して推進することとしています。
第1回再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議の様子

- 出典:
- 首相官邸ホームページ
再生可能エネルギー導入拡大に向けた関係府省庁連携アクションプラン 概要
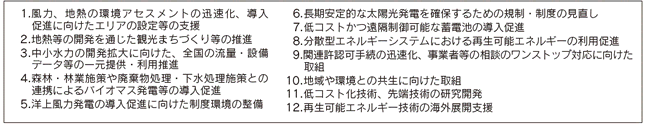
また、水素社会の実現に向けて、2017年内に政府一体となって水素社会の実現に取り組むための基本戦略を策定するよう安倍総理から指示がありました。これを踏まえ、今後水素ステーションの整備を加速させる仕組みを作るとともに、規制の合理化に向けた総点検をしていきます。加えて、国際的な水素サプライチェーンの構築と水素発電の本格導入に向けて、多様な関係者の連携の基礎となる共通シナリオを策定します。
~「再生可能エネルギー等関係閣僚会議」から「再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議」へ~
2014年に策定された第4次エネルギー基本計画に基づき、再生可能エネルギー等の推進に関する事項について各省連携を強化することを目的として、同年4月に内閣官房長官が主宰する「再生可能エネルギー等関係閣僚会議」が設置されました。
以後、「再生可能エネルギー等関係閣僚会議」は2016年3月の会議まで全3回が開催されましたが、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた取組に加えて、エネルギー安全保障と地球温暖化対策の切り札である水素の活用を強力に推進し、水素社会を実現するために、水素発電の実現や規制の見直しなど様々な省庁が連携して取り組むべき課題に政府を挙げて対応するべく、2017年4月「再生可能エネルギー等関係閣僚会議」は「再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議」に改組されました。
「再生可能エネルギー等関係閣僚会議」、「再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議」の経緯
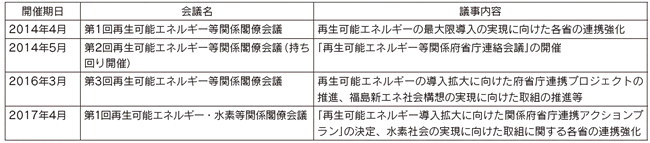
- 出典:
- 資源エネルギー庁