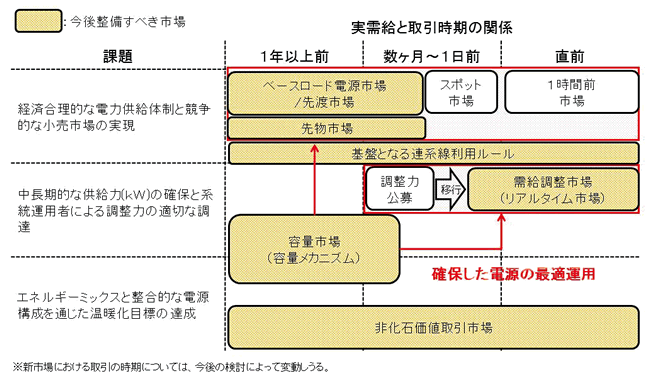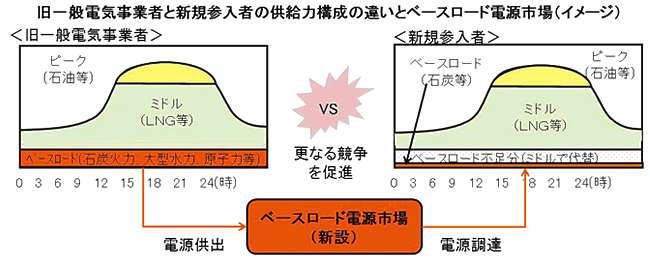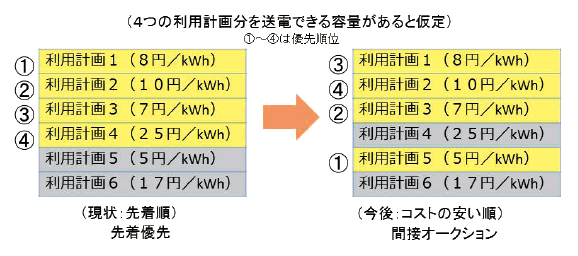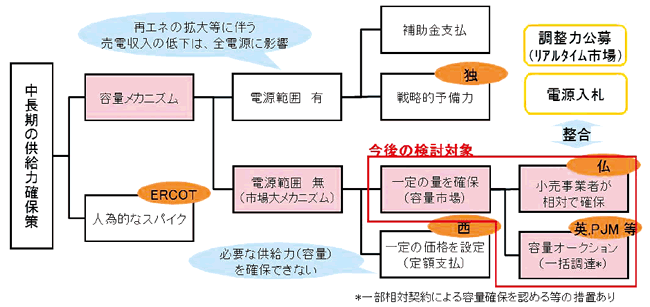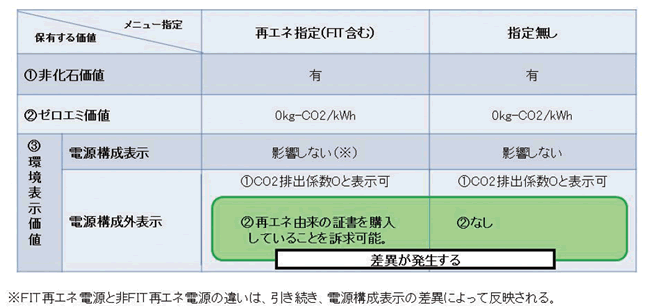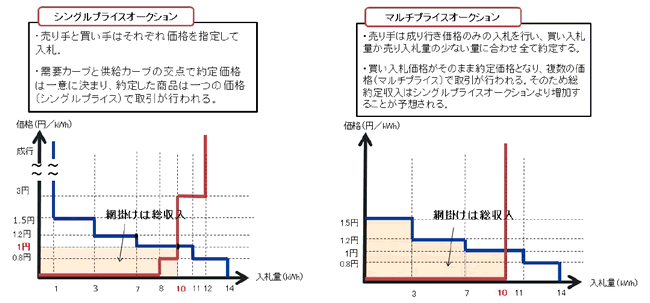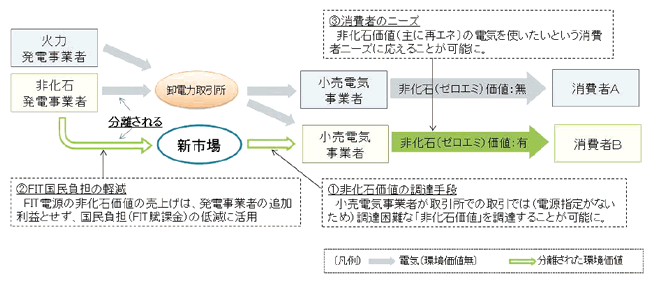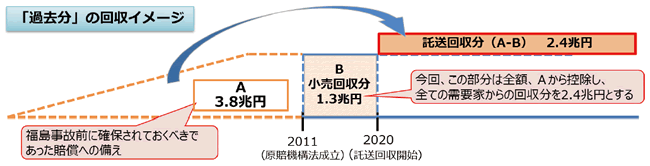第3節 競争活性化と自由化の下での公益的課題への対応
はじめに
戦後60年余り続いた我が国の電気事業制度は、東日本大震災やその後の電力需給のひっ迫を契機に、広域融通の限界や料金水準の高騰といった課題が浮き彫りとなりました。こうした課題を克服しつつ、電力やガス、あるいは供給区域といった市場の垣根を越えた競争が可能となるエネルギー市場を形成すべく、岩盤規制打破に向けたアベノミクスの改革の柱の1つとして、①安定供給の確保、②電気料金の最大限の抑制、③事業者の事業機会及び需要家の選択肢の拡大を目的とする電力システム改革のための電気事業法等の抜本改正が2013年から3段階に分けて行われました。
改革の第3弾となる2020年の発送電分離に向けて、さらなる競争の活性化が期待される中で、今後とも競争を通じ、電気料金の抑制や選択肢の拡大を通じて電力システム改革の果実を国民に広く還元するためには、公正・公平な競争環境を整備することが必要不可欠であり、同時に、市場原理のみでは解決が困難な公益的課題の克服を図る必要があります。そこで、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会に「電力システム改革貫徹のための政策小委員会(貫徹小委員会)」を設置し、競争活性化の方策と競争の中でも公益的課題への対応を促す仕組みの具体化に向け審議を依頼し、2016年12月に中間とりまとめを行いました。
また、2017年4月1日から、ガスの小売全面自由化が開始されました。これにより、各地域の一般ガス事業者からしかガスの供給を受けることができなかった一般家庭等が、他事業者からもガスの供給を受けることができるようになりました。
今般のガスシステム改革では、電力システム改革同様、①安定供給を確保すること、②ガス料金を最大限抑制すること、③需要家の選択肢や企業の事業機会を拡大すること、の3つを主要な目的に据えました。より具体的には、①安定供給については、一般ガス導管事業者に対して導管網の建設・保守、最終保障サービスを義務付けることや、導管網の整備・相互接続を促進することで、安定供給の確保を目指すこととしています。②ガス料金については、事業者間の競争や、他業種・他地域からの参入を促し、創意工夫や経営努力を引き出すことで、ガス料金を最大限抑制することとしました。③選択肢・事業機会については、新しい発想を持つ事業者の参入を促し、一般家庭や企業を含めた全てのガスの利用者が自由に供給者を選択できるようにするとともに、導管網の整備・相互接続を促進することで選択肢・事業機会を拡大することを目指すこととしています。
本節では、エネルギーシステム改革の下における、競争活性化の方策と競争の中でも公益的課題への対応を促す仕組みの整備について紹介します。
1.電力システム改革の貫徹
(1)さらなる競争活性化等に向けた市場・ルールの整備
電力システム改革貫徹に向けた課題への対応に際しては、市場メカニズムを有効に活用しつつ、3E+S(安定供給、経済効率、環境適合、安全)の実現を目指すことが重要です。そのため、卸電力市場をはじめとした既存の市場の流動性を高めるとともに、容量市場や非化石価値取引市場など、これまでになかった新たな市場を創設することにより、新たな価値を顕在化・流動化させていくことが適当です。こうした考え方に基づき、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革貫徹のための政策小委員会の下に「市場整備ワーキンググループ」を設置し、①ベースロード電源市場、②連系線利用ルール、③容量メカニズム、④非化石価値取引市場の4つの制度に関して、その意義と基本的な考え方、今後さらなる検討を進める上での留意事項等について議論を行い、結果を取りまとめました。
①ベースロード電源市場の創設
卸電力市場の活性化は、広域メリットオーダーの実現や、小売電気事業者の電源調達の円滑化、透明性・客観性の高い電力価格指標の形成等を通じて、事業者間の健全な競争を促し、競争の果実を、電気料金の抑制、選択肢の拡大といった形で需要家に還元する上で非常に重要な役割を果たしています。
そのため、政府は小売全面自由化以前から、余剰電源の市場投入や常時バックアップの運用見直し、卸電気事業者であった電源開発の売電先多様化等の取組を旧一般電気事業者に対して求めてきました。
しかしながら、こうした取組にも関わらず、小売全面自由化後の卸電力市場の流動性は、依然として、活発な競争が行われている自由化先進国と比して低い水準に留まっています。特に、石炭や大型水力、原子力等の安価なベースロード電源については、旧一般電気事業者がその大部分を保有または長期契約で調達しているため、新規参入者のアクセスが限定的であり、このことが競争をさらに活性化させるための障壁なってきました。具体的には、新規参入者はベースロード電源へ十分アクセスできていないため、ミドル電源でその不足分を代替しており、結果として、負荷変動の小さい産業用等の分野において、十分な競争力を有しない結果となっております。
したがって、新規参入者もベースロード電源へのアクセスを容易とするための新たな市場として、ベースロード電源市場を創設し、実効的な仕組みを導入することで、旧一般電気事業者と新規参入者のベースロード電源へのアクセス環境のイコールフッティングを図るとともに、卸電力市場の活性化を通じたさらなる小売競争の活性化を図ることが貫徹小委員会において適当とされました。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
- 出典:
- 資源エネルギー庁
具体的な制度設計については、今後の詳細な検討を経て決定していくこととなりますが、ベースロード電源は、主に中長期断面で見た需要家のベース需要に対応する、安定的な供給力として位置付けられており、小売電気事業者は、実需給の一定期間前の段階で確保することを志向するため、ベースロード電源市場については、先渡市場の一種として位置付け、ある程度の長い期間、一定の電力量を受け渡す標準化された商品を取り扱うこととし、商品数については、昼夜や季節を問わず安定的に発電を行うベースロード電源の特性や、事業者のニーズなどを踏まえつつ、卸電力市場の流動性を高めていく観点から検討していくこととしております。また、市場の取引方式は、小規模事業者を含むアクセスの公平性等を確保する観点から、オークション方式とし、年間複数回実施することも視野に、今後さらなる検討を進めてまいります。加えて、こうした商品に対して、現行の常時バックアップと同様、燃料費調整制度や買取オプションなどの機能を付与することも考えられますが、事業者の創意工夫を促し、卸電力市場全体の価格指標性を高める観点からも、こうした機能は極力排除し、原則としてリスク管理は市場を介して行うべきとの議論がなされています。市場に供出可能な電源種については、限定をしてしまうと、その電源の特性(立地の偏在性、電源脱落リスク等)が供出量や価格に大きく影響を及ぼすため、事業者が適切にリスクを評価・平準化することを可能とするため、同市場に供出することができる電源種は基本的には限定しない方向で検討が進められています。
また、これまでの自主的取組を通じて、旧一般電気事業者は、自社で保有する限界費用の高い電源を中心に、卸電力取引所等に投入してきました。しかし、限界費用の安いベースロード電源については、経済合理的な判断の下、専ら自社で利用してきたため、自主的取組の一環である電源開発が保有する電源(以下「電発電源」という。)の切り出しについては、これまであまり進んできませんでした。そのため、ベースロード電源市場における取引の実効性を確保する観点から、旧一般電気事業者等が保有するベースロード電源により発電された電気の一部を、適正な価格でベースロード電源市場に供出することを制度的に措置することが検討されていくこととなりました。
②連系線利用ルールの見直し
地域間(エリア間)連系線の利用は、「先着優先」と「空おさえの禁止」を原則として、電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」という。)によって利用計画が管理されています。近年、発電設備を設置しようとする者からの地域間(エリア間)連系線の利用・増強ニーズが高まっている中で、一部の連系線で設備増強のための計画策定プロセスが開始されていますが、現行の先着優先ルールを継続する場合、一刻一秒を争って申し込み順位を争うといった競争が生じるおそれがあります。さらに、我が国の電力需要の今後の大きな伸びが期待できない中で、単に設備増強を行うこととすれば、設備利用率が低くなり、結果として、託送料金や電気料金の上昇につながるおそれがあります。加えて、2016年4月から計画値同時同量制が導入されたことで、託送制度上、自由に電源の差し替えができるようになり、連系線の利用計画も特定電源との紐付きが不要となり、このため、先着優先によって連系線容量を確保している事業者は、それを用いて自身にとって最も経済効率的になるよう電気の調達先を差し替えることが可能となる一方、新規参入者は、既存事業者によって連系線が占用されている場合、連系線を活用して電源を差し替えることができず、既存事業者が極めて有利な権利又は地位を有することになるといった新たな問題も生じています。
こうした状況も踏まえ、先着優先によって確保されている連系線容量を原則開放し、卸電力市場を介して、コストの安い電源順に送電させるようなルール(間接オークション)を導入し、公正な競争環境の下で送電線の利用を促すことによって、卸電力市場の活性化、より広域的かつ効率的な電源活用を通じ、電気料金を最大限抑制し、事業者の事業機会の拡大を実現していくことが適当です。
そうした中で、2016年2月の「再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会 報告書」では、効率的な形での電力の取引・流通の実現を通じた再エネの導入拡大に結びつけていくために、計画的な広域系統整備・運用が必要であり、連系線の利用計画等の見直しについて、引き続き検討を進めていくべきとされました。また同年5月の第6回電力基本政策小委員会では、連系線利用ルールの見直しも含めた検討をするべきとの提言等を受けて、連系線利用ルールの見直しについて、同年9月より「電力システム改革貫徹のための政策小委員会」において議論を行いました。
なお、間接オークションを導入した場合、卸電力市場を介した地域間(エリア間)電力取引の活性化が期待されますが、当該取引が地域間(エリア間)連系線の空き容量を超える場合には、現行の卸電力取引市場の処理方法と同様、地域間(エリア間)の市場分断が発生し、各エリア内で売買を成立させる処理が行われることになります。その結果、分断されたエリア間で値差が生じることになりますが、こうした事象は間接オークション導入に伴う卸電力市場での取引量の増加に伴い、より多くの事業者に、より大きな影響が及ぶことになります。そのため、このようなエリア間値差リスクをヘッジできる仕組みについても、併せて検討を進めていく必要があります。
連系線利用ルールの見直しに伴う間接オークションの導入時期については、2019年に北海道・本州間連系設備の増強が予定されていることにより、遅くともそれまでに導入する必要があるため、2018年度の早い段階での導入を目指しています。また、エリア間値差ヘッジ商品については、ベースロード電源市場創設による卸電力市場(先渡市場)活性化を見据え、同市場創設までに導入を目指して検討を進めていきます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
③容量メカニズムの導入
2016年4月の小売全面自由化以降、家庭や商店も含む全ての消費者が、電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになり、ライフスタイルや価値観に合わせて電気の売り手やサービスを自由に選べるようになりました。
一方で、発電投資については、これまでは総括原価方式の下で、規制料金を通じて投資回収がなされてきましたが、小売全面自由化以降は、原則として、市場での取引を通じて、または、卸電力市場価格を指標とした取引を通じて投資回収がなされていくようになり、電源の投資回収の予見性は、これまでと比較して低下する蓋然性があります。
また、FIT等を通じて、再エネの導入が拡大すれば、電源稼働率の低下や市場価格の低下に伴い、売電収入が低下し、事業者の発電投資意欲をさらに減退させる可能性があります。
仮に今後、発電投資が適切なタイミングで行われなければ、電源の新設や更新が十分になされないまま、老朽化した既存の電源が閉鎖されていくことになります。その結果、中長期的に電気の供給力が不足し、電源の開発には一定のリードタイムを要することから、需給がひっ迫する期間にわたって電気料金が高止まりする問題や、電気の調整力が不足し、再エネ導入拡大の妨げになる問題が生じる蓋然性があります。
そのため、我が国全体で中長期的に必要となる供給力を確保するために、単に卸電力市場等に調整機能を委ねるだけでなく、一定の投資回収の予見性を確保する施策を追加で講じていくことが適当です。
他の自由化先進国でも、一定の投資回収の予見性を確保する施策が導入されていますが、その具体的な手法については、各国の個別事情に鑑み、それぞれ大きく異なっています。したがって、我が国において新たな施策を導入する場合、我が国固有の事情も鑑みた上で、電源の新陳代謝が市場原理を通じて効率的に行われるようにし、できる限り国民負担を最小化する仕組みとすることが必要です。
こうした観点から、我が国では、電力システム改革専門委員会報告書(2013年2月公表)において、早い段階で将来の供給力を市場で確保することを可能とする機能、価格指標の形成機能、実需給より手前で投資コストの回収を可能とする機能が必要となるが、これらを実現するための仕組みとして、将来発電することの出来る能力を系統運用者、小売電気事業者等が取引する市場(容量市場)を創設することが適当とされました。その後、2016年9月より貫徹小委員会において議論を行い、容量市場は、①予め必要な供給力を確実に確保することができること、②卸電力市場価格の安定化を実現することで、電気事業者の安定した事業運営を可能とするとともに、電気料金の安定化により消費者にもメリットがもたらされること、③再エネの導入拡大に伴う売電収入の低下は全電源に影響していることを踏まえると、最も効率的に中長期的に必要な供給力を確保するための手段であるとされました。
なお、小売電気事業者については、供給力確保義務として安定供給上の一定の役割を果たすことが求められていますが、将来の供給力を早い段階から確保するための容量市場においても、ディマンドリスポンスの活用によるピーク需要削減等も含め、事業者の創意工夫を最大限活用することが可能です。
そのため、新規参入を過度に抑制しないよう留意しつつも、中長期的に必要な供給力を確保するための費用負担を小売電気事業者に対して求めていくこととなります。なお、こうした措置は、投資回収の予見性を高めるためのものであり、理論上、必要な電源投資等のための総コストは変わらないため、中長期的に見た小売電気事業者全体としての負担は増加しません。
容量市場には、必要な供給力を市場管理者等が一括で調達する集中型と、小売電気事業者が相対や取引所取引等の市場取引を通じて自社に必要な供給力を確保する分散型という2つの類型が存在しますが、①市場管理者等が一括で調達するため、容量確保の実効性が高いことや、②市場支配的な事業者の影響力行使に対する対応の容易さ等に鑑み、分散型の可能性を完全に排除するものではありませんが、今後は集中型を軸に詳細な検討を進めていくこととしています。
また、容量市場の運営にあたっては、①全電気事業者が加入する中立機関であること、②供給計画の取りまとめを行い、全国大での供給予備力評価等に知見があることから、広域機関が市場管理者等として、一定の役割を果たすことが適当とされました。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
容量市場の導入時期については、2020年度を目安として、必要な供給力(容量)の取引を開始することを目指して検討を進めていきます。
④非化石価値取引市場の創設
高度化法により、小売電気事業者は、自ら調達する電気の非化石電源比率を2030年度に44%以上にすることが求められています。
しかし、卸電力取引所では、非化石電源と化石電源の区別がされないため、非化石電源の持つ価値が埋没し、非化石電源比率を高める手段として活用ができません。結果、取引所取引の割合が比較的高い新規参入者にとっては特に、非化石電源を調達する手段が限定される状況になっており、高度化法の目標達成が困難な面があります。
また、FIT電気(固定価格買取制度に基づき買い取られた電気)の持つ環境価値(非化石価値を含む)については、現状、賦課金負担に応じて全需要家に均等に帰属するものと整理されており、国民負担の軽減を図る観点から、その価値を顕在化するような制度設計の在り方についての更なる検討が求められているところです。
このような状況を踏まえ、新たな市場である非化石価値取引市場を創設することによって非化石価値を顕在化し、取引を可能とすることで、小売電気事業者の非化石電源調達目標の達成を後押しするとともに、需要家にとっての選択肢を拡大しつつ、FITによる国民負担の軽減を促します。
また、本市場の創設に当たっては、上記の制度趣旨を踏まえ、非化石価値を顕在化し、その価値に適切に評価を与えることができるよう、以下の主要な論点について基本的な考え方を整理しました。
(ア)非化石価値の分離と二重計上防止
非化石価値を顕在化するに当たり、非化石価値とその実電気を一体で取引する方法も考えられますが、実電気のみに対する需要や、実電気と分離された非化石価値に価格がつくことによって確実に非化石価値の顕在化を実現できる点などに鑑み、非化石価値を証書化し、実電気とは分けて取引するものとします。
また、非化石価値が分離された実電気から二重に非化石価値が計上される状況が発生しないよう、相対取引も含め、発電段階で全ての非化石電源の非化石価値を分離し、全ての非化石電源を一律に証書発行の対象とします。
なお、非化石証書を発行する際に必要となる、その証書が非化石電源由来であることを認証する作業については、FIT電源は費用負担調整機関が担うこととし、非FIT非化石電源の認証手段についても、今後速やかに検討を進めます。
(イ)非化石価値以外の環境価値
電気の持つ環境価値としてはいくつかの概念が考えられますが、①非化石価値(高度化法上の非化石比率算定時に非化石電源として計上できる価値)以外に、②ゼロエミ価値(CO2排出係数が0kg-CO2 /kWhであることの価値)や③環境表示価値(小売電気事業者が需要家に対しその付加価値を表示・主張する権利)が主なものとして挙げられます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
ゼロエミ価値については、そもそも全ての非化石電源はCO2排出量がゼロであることに鑑み、非化石価値と同時にゼロエミ価値が移転されるものと整理します。
環境表示価値については、非化石証書によって加算された非化石比率やオフセットされた排出係数に関しては、その付加価値を需要家に訴求することは可能とします。ただし、電源構成表示に関しては、実際に受電した電源の構成を表示するとの整理がなされており、非化石証書を購入しても電源構成は変わらない点に留意が必要です。他方、再エネ由来の証書に関しては、電源構成外にて「実質再生可能エネルギー100%」等の表示を許容することも考えられ、こうした表示に関する具体的な規定は、電力・ガス取引監視等委員会において別途検討することとします。
(ウ)非化石証書の種類
非化石証書に関して、その由来する非化石電源種は再エネ、原子力が考えられますが、再エネ由来の証書に関しては、どの非化石電源種由来の証書か区別せず販売するか、「再生可能エネルギー由来証書」として販売するか、売り手が選択できることとします。なお、証書を電源毎にさらに細分化するか等は事業者のニーズを踏まえ、今後引き続き検討します。
(エ)市場の担い手
当該市場が高度化法の非化石電源比率達成の手段であることに鑑み、非化石証書の買い手は、原則として小売電気事業者とし、証書を購入した者に非化石価値がすべて帰属することとします。証書の売り手は、FIT電源は費用負担調整機関、非FIT非化石電源は発電事業者とします。なお、証書の流動性の観点から、小売電気事業者間での証書の転売も認めることとします。また、市場の設置場所については、これまでの卸取引所取引の業務経験や、既存の市場との関連性に鑑み、日本卸電力取引所の下に創設します。
(オ)市場の価格決定方式
取引所での価格決定方式としては、制度導入当初の取引所取引においてはFIT由来の証書流通量が多くを占めることが予想されることから、FITによる国民負担の軽減を最大限に図る観点から、当面はマルチプライスオークション方式を採用します。
(カ)需要家の選択肢の拡大
上記の結果として、証書を購入した小売電気事業者は、非化石価値(再エネ由来の価値)を電気とともに需要家に販売することが可能となります。したがって、例えば、再エネの推進に貢献したいと考える需要家は、数ある料金メニューから、こうした小売電気事業者が提供する再エネ価値付きのメニューを選択することで、実際に貢献することが可能となります。需要家のニーズが高ければ、非化石価値取引市場が積極的に活用され、小売電気事業者のサービス多様化が図られることが期待されます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
- 出典:
- 資源エネルギー庁
(2)自由化の下での財務会計面での課題
電気事業は、その特性として、安定供給確保のため、発電及び送配電に巨額の設備投資が必要であり、かつ、投下資本の回収期間が長期に及ぶという点が挙げられます。このため、電気の低廉かつ安定的な供給確保を達成するため、戦後約半世紀にわたり、地域独占・垂直一貫・総括原価方式による料金規制の下、確実な費用回収が制度的に担保される環境下において事業が営まれてきました。一方で、総括原価方式による料金規制の下では、認められた費用等以上に料金収入を得ることが制限されていた点に大きな特徴を有しています。総括原価方式の下で営まれてきた電気事業においては、一般の事業と異なり、将来的な費用増大リスクを見込んだ自由な価格設定を行うことはできず、制度的に認められた費用以外を料金原価に算入することは認められていませんでした。
2016年4月の小売全面自由化以降、総括原価方式による料金規制の撤廃に伴い、電気事業の財務・会計上の特性にも変化が生じました。このため、電力分野の自由化を進めるに当たっては、これら制度変更に伴う課題として、一般の事業においては問題とならないような、例えば、制度変更により事後的に費用が増大する場合の対応費用をどのように回収するかが課題となり得ます。このため、財務・会計制度や負担の在り方について、具体的な措置の検討・審議を行うため、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革貫徹のための政策小委員会の下に「財務会計ワーキンググループ」を設置し、小売全面自由化の下での原子力事故に係る賠償への備えに関する負担や廃炉に係る会計制度の在り方に関する議論を行いました。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
①原子力事故に係る賠償への備えに関する負担の在り方
東京電力福島第一原子力発電所(以下「1F」という。)の事故後、原子力事故に係る賠償への備えとして、従前から存在していた原子力損害賠償法に加えて新たに原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下「原賠機構法」という。)が制定され、現在、同法に基づき、原子力事業者が毎年一定額の一般負担金を原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「原賠・廃炉機構」という。)に納付しています。原子力損害賠償法の趣旨に鑑みれば、本来、こうした万一の際の賠償への備えは、1F事故以前から確保されておくべきでしたが、政府は何ら制度的な措置を講じておらず(=制度の不備)、事業者がそうした費用を料金原価に算入することもありませんでした。従来、総括原価方式の下で営まれてきた電気事業においては、一般の事業と異なり、将来的な費用増大リスクを見込んだ自由な価格設定を行うことはできず、料金の算定時点で合理的に見積もられた費用以外を料金原価に算入することは認められていませんでした。これは、規制料金の下では、全ての需要家から均等に費用を回収することとなるため、同じ電気を利用した需要家間では不公平は生じないということを前提として、その電気を利用した時点で現に要した費用(合理的に見積もられた費用)のみ料金原価への算入を認めるという考え方に基づいています。
しかし、2016年4月に小売が全面自由化され、新電力への契約切替えにより一般負担金を負担しない需要家が増加していることを踏まえ、賠償の備えを小売料金のみで回収するとした場合、過去に安価な電気を等しく利用してきたにもかかわらず、原子力事業者から契約を切り替えた需要家は負担せず、引き続き原子事業者から電気の供給を受ける需要家のみが全てを負担していくこととなります。こうした需要家間の格差を解消し、公平性を確保するためには、全需要家が等しく受益していた賠償の備えについて、全ての需要家が公平に負担することが適当であり、また、そうした措置を講ずることが、福島の復興にも資するものとの考えに立ち、負担の在り方についての検討を進めました。
回収する金額の規模は、現行の一般負担金の算定方法を前提とすることが適当と考えられ、現在の一般負担金の水準をベースに、1kWあたりの単価を算定した上で、これを前提に、2010年度までの我が国の原子力発電所の毎年度の設備容量等を用いて算出した金額から、回収が始まる前の2019年度末時点までに納付した又は納付することになると見込まれる一般負担金の合計額を控除した約2.4兆円としました。
回収方法については、電源構成に占める原子力の割合は供給区域ごとに異なる一方で、過去分の負担は、過去の原子力の電気の利用に応じて行うべきものであることや、現状、一般負担金は小売規制料金に含まれ、供給区域ごとに異なる水準となっていること等を踏まえると、過去分を国民全体で負担するに当たっては、特定の供給区域内の全ての需要家に一律に負担を求める託送料金の仕組みを利用することが適当と考えられました。
なお、留意点として、本来、発電部門の原価として回収されるべき過去分について、託送料金の仕組みを通じて広く全需要家に負担を求めるに当たっては、その額の妥当性を担保する措置を講ずるとともに、個々の需要家が自らの負担を明確に認識できるよう、指針等を通じ、小売電気事業者に対し、需要家の負担の内容を料金明細票等に明記する措置を講じることとされました。また、原子力に関する費用について、託送料金の仕組みを通じた回収を認めることは、結果として、原子力事業者に対し、他の事業者に比べて相対的な負担の減少をもたらすものであり、競争上の公平性を確保する観点から、原子力事業者に対しては、例えば、原子力発電から得られる電気の一定量を小売電気事業者が広く調達できるようにするなど、一定の制度的措置を講じることとしています。
②福島第一原子力発電所の廃炉の資金管理・確保の在り方
小売全面自由化の中にあっても事故収束や福島復興の歩みが滞ることがあってはならず、東京電力の非連続の経営改革を具体化していくための検討を行う「東京電力改革・1F問題委員会(東電委員会)」が2016年9月に設置されました。東電委員会から国に対しては、同年10月、1Fの廃炉に必要な資金については、東京電力が負担することが原則であり、東京電力にグループ全体で総力を挙げて捻出させる必要があるとの考え方の下、「国民負担増とならない形で廃炉に係る資金を東電に確保させる制度」について、検討要請がなされました。本委員会においては、この要請を踏まえ、1Fの廃炉の円滑かつ着実な実施を担保するため、長期間にわたり必要となる巨額の資金の適切な管理を担保する制度と、発電・送配電・小売に分社化されている東電において、自由化の下でもグループ全体で総力を挙げて捻出する資金が確実に廃炉に充てられるための制度について、検討を行いました。
(ア)確実な資金管理の方策
1Fの廃炉に必要な資金については、東京電力(燃料火力、送配電、小売を含むグループ全体)が負担することが原則です。他方で、世界に前例を見ない1Fの廃炉に必要となる資金は巨額であり、かつ、その支出は長期間にわたることが見込まれます。2016年12月に閣議決定された「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針について」において、廃炉・汚染水対策については、東京電力グループ全体で総力を挙げて責任を果たしていくことが必要であり、国はそれに必要な制度整備等を行うこととされたこと等を踏まえ、事故炉廃炉の確実な実施を確保するため、事故炉の廃炉を行う原子力事業者(事故事業者)に対して、廃炉に必要な資金を機構に積み立てることを義務づける等の措置を講ずることを内容とする「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律案」が2017年2月に閣議決定され、第193回通常国会に提出されています。
(イ)送配電事業の合理化分の充当
東京電力によるグループ全体での総力を挙げた経営合理化等で必要な資金を捻出させるに当たり、総括原価方式の料金規制下にある東京電力パワーグリッド(送配電部門、以下「東電PG」という。)においては、例えば、託送収支の超過利潤が一定の水準に達した場合、電気事業法の規定に基づき託送料金の値下げを求められることがあり、合理化努力による利益を自由に廃炉資金に充てることはできません。したがって、東電PGにおける経営合理化分を確実に1F廃炉に充てられるようにするため、毎年度行われる託送収支の事後評価の例外として、東電 PGの合理化分のうち、東電PGが親会社(東京電力ホールディングス)に対して支払う1F廃炉費用相当分について、(i)超過利潤と扱われないように費用側に整理して取り扱われるようにする制度的措置、(ii)乖離率の計算に際して実績単価の費用の内数として扱われるようにする制度的措置を講ずることが適当とされました。
しかし、上記措置を講ずるに当たっては、(i)東電PGの託送料金の値下げ機会が不当に損なわれないよう、東電PG自体の超過利潤・乖離率の代わりに、他の一般送配電事業者の効率化達成状況によって値下げ命令の要否を判断する、(ii)東電グループ全体の中で東電PGの負担が過大なものとならないよう、例えば収益性や資産状況を参考に、グループ各社との負担の程度を比較し、著しく不適当な分担となっていないかどうかを確認するといった措置を併せて講ずる必要があります。
③廃炉に関する会計制度の扱い
(ア)廃炉会計制度について
従前の電気事業会計制度の下では、廃炉に伴う資産の残存簿価の減損等により、一時に巨額の費用が生じることで、(i)事業者が合理的な意思決定ができず廃炉判断を躊躇する、(ii)事業者の廃炉の円滑な実施に支障を来す、との懸念がありました。このため、2013年と2015年に、設備の残存簿価等を廃炉後も分割して償却(=負担の総額は変わらないが、負担の水準を平準化)する会計制度が措置されました。こうした制度整備を受けて、2015年に5基、2016年に1基の原子炉について、廃炉決定が行われています。
廃炉会計制度は、計上した資産の償却費が廃炉後も着実に回収される料金上の仕組みが併せて措置されることを前提としており、現在は小売規制料金により費用回収することが認められています。したがって、現在経過的に措置されている小売規制料金が原則2020年に撤廃されることを見据えた場合、今後も制度を継続するには、着実な費用回収を担保する措置を講ずることが不可欠です。この点、2015年3月の廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループ報告書(「原発依存度低減に向けて廃炉を円滑に進めるための会計関連制度について」)においては、競争が進展した環境下においても制度を継続させるためには、「着実な費用回収を担保する仕組み」として、総括原価方式の料金規制が残る送配電部門の託送料金の仕組みを利用することとされていました。
制度創設の経緯・趣旨を踏まえれば、廃炉会計制度は、原発依存度低減というエネルギー政策の基本方針に沿って措置されたものとして、本制度を継続することが適当であるとされました。本制度を継続するために必要となる着実な費用回収の仕組みについては、小売規制料金が原則2020年に撤廃されることから、自由化の下でも規制料金として残る託送料金の仕組みを利用することが妥当と考えられます。ただし、発電、送配電、小売の各事業が峻別された自由化の環境下で、発電に係る費用の回収に託送料金の仕組みを利用することは、原発依存度低減や廃炉の円滑な実施等のエネルギー政策の目的を達成するために講ずる例外的な措置と位置付けられるべきです。
また、現行の廃炉会計制度においては、事故炉の廃炉を円滑に進めるとの観点から、2013年に措置された廃止措置資産については事故炉を対象から除外していませんが、様々な事象を総合的に勘案し、1Fの1~6号機については、新たに講じられる制度的措置の下で円滑に廃炉が行われることを前提に、原則として託送料金の仕組みを利用した廃炉会計制度の対象から除外すべきと位置付けています。
(イ)原子力発電施設解体引当金について
原子炉の運転期間中に廃炉に必要な費用を着実に積み立てるため、原子力事業者は、毎年度、原子力発電所一基ごとの廃止措置に要する総見積額を算定し、経済産業大臣の承認を得た上で、各原子炉の発電実績に応じて原子力発電施設解体引当金として積み立てることが義務付けられています。解体引当金は、1F事故以降、原子力発電所の長期にわたる稼働停止が続き、従来の生産高比例法では引当が進まないといった課題が生じたことから、2013年、引当方法を定額法に、引当期間を運転期間40年に廃炉後の安全貯蔵期間10年を加えた原則50年に変更する制度改正が行われ、今後、競争が進展した環境下でも本制度を継続し、廃炉後の安全貯蔵期間中も引当を継続させるためには、廃炉会計制度と同様、費用回収が着実に行われる仕組みが必要となっています。
その引当期間については、事業者が負担するという原則に立てば、着実な費用回収が前提となる安全貯蔵期間に入る前、すなわち、廃炉前に引当を完了していることが廃炉を円滑に実施する観点からより適切な制度の在り方であり、原則50年としている引当期間を原則40年に短縮することが適当とされました。
引当期間の見直しを行った場合、現在、解体引当金の残額を10年間に分割して引当を行っている、2013年の制度改正以降に廃炉決定したものや、今後早期廃炉するものについては、当該原子炉の解体引当金の未引当分を一括して引き当てる必要が生じますが、制度の事後的な変更によって、事業者の財務に影響を与えることは適当でないことに加え、こうした費用の発生が早期廃炉を志向する事業者の判断を歪めるようなことがあれば、廃炉会計制度の趣旨にも反します。したがって、2013年の制度改正以降に廃炉決定したものや今後早期廃炉するものに限り、廃炉に伴い一括して計上することが必要となる費用を廃炉会計制度の対象とすることで、一括して発生する費用を分割して計上する仕組みとすることが適当とされました。
解体引当金の基礎となる原発の解体に必要な費用は、1985年及び1999年の総合資源エネルギー調査会原子力部会において示された算定式に基づき、毎年度、物価変動や廃棄物量の変動を加味し、炉ごとに総額(=総見積額)を算定しています。この算定式は、原子力部会において技術的な検討を行った結果として導き出されたものであり、その前提に大きな変更はないことから、現時点で合理的に見積もることのできる費用が不足なく含まれているものと評価できます。一方で、この算定式は、モデルとなるプラントの廃炉工程を前提としたものであるため、今後、個々のプラントにおいて廃止措置を実施していく過程等で、例えば、多数の炉が設置されている原子力発電所では、設備の共有等による効率化などにより、総見積額の見直しが必要となり得ます。こうしたことを踏まえ、自由化の下でも廃炉に必要な費用があらかじめ確実に確保されるよう、個別の炉・発電所ごとに固有の事情(規制変更などにより算定式の前提を大幅に変更する必要がある場合を除く)が生じた場合に、当該事象を速やかに総見積額に反映させることが可能な仕組みを導入することが必要と考えらます。ただし、総見積額の妥当性を確保するため、これまでと同様に、総見積額を経済産業大臣が承認する仕組みとすることが適当とされました。
(3)原子力事業者による安全性向上の取組・防災連携の加速
①原子力政策が直面する課題
福島第一原発事故後に策定された「エネルギー基本計画」では、安全の確保を大前提に、原子力を重要なベースロード電源と位置づけ、原子力規制委員会によって新規制基準に適合すると認められた原発のみ、その判断を尊重し、地元の理解を得ながら、再稼働を進めることとしています。
こうした方針の下、現在までに、複数の原発が、原子力規制委員会の規制基準を満たすと認められ、再稼働が進められています。しかしながら、今なお、国民の中には原子力の安全に対する不安の声があります。政府や原子力事業者はまず、こうした声に正面から向き合う必要があります。原子力をエネルギーの選択肢の一つとして活用していく上では、不断の努力でさらなる安全性を追及し、併せて、万が一事故が起きてしまった場合の備えを充実させ、国民の声に応え、原子力の社会的な信頼を取り戻していかなければなりません。
さらに、今後、電力自由化が進み、経済効率性の追求を目指した競争環境の進展が図られることになります。こうした状況下においても、事業者を含めた原子力の関係者が、安全規制に受け身で対応するのではなく、自らの意思で常により安全を高めていく、こうしたことが自律的・継続的に行われる仕組みを構築していくことが必要となります。
②安全性向上の好循環を生み出す「継続的な原子力の安全性向上のための自律的システム」の構築
原子力事業者の安全性向上に向けた取組については、これまでも、福島第一原発事故の教訓を踏まえ、規制基準さえ満たせば原発のリスクがないとする「安全神話」と決別するため、国は総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会自主的安全性向上・技術・人材ワーキンググループにおいて、二度にわたり原子力の自主的安全性向上に係る提言を行ってきました。
また、一義的に安全の責任を負う原子力事業者も、確率論的リスク評価(PRA)に関する取組の推進や、自主規制をするための組織を設置する等、自主的安全性向上へ向けた取組を進めています。
このうち、PRAに関する取組については、今後のリスク評価のさらなる高度化に向けて、2014年10月に原子力リスク研究センター(NRRC)が設立され、既存プラントを対象とした発電所ごとのPRA手法の開発が実施されています。今後、リスク情報活用のプロセスを体系的に構築していくためのロードマップの策定や、海外への知見の展開及び海外からの知見の取り入れ、PRA手法に対するピアレビュー、PRAの結果を安全対策に活かす際の手法を確立していくことが求められます。
自主規制に関する取組については、2012年11月、原子力安全推進協会(JANSI)が設立され、発電所のマネジメント体制向上のためのピアレビュー等の取組が行われてきました。今後は、レビューの結果を具体的な取組に結びつけるインセンティブの仕組みの構築等、より実効的な体制の構築が必要となります。
今後、こうした安全性向上の取組が継続的・自律的に機能するためには、安全確保活動の指針となる目標や安全文化の醸成について議論を深めることが必要となります。また、その目標を頂点として、規制機関はもとより、原子力事業者やメーカー、原子力関係省庁など原子力に関わる全ての関係者が、それぞれの立場で原発の安全性向上を追及しながら、相互に指摘をし合うことで、さらなる高みを目指す「継続的な原子力の安全性向上のための自律的システム」を構築する必要があります。併せて、自律的システムの重要な要素である、研究開発、学協会規格の積極的な活用、人材育成、住民・社会とのコミュニケーションの在り方、国際機関との関係の構築についても、さらなる検討が求められます。
こうした諸課題について、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会自主的安全性向上・技術・人材ワーキンググループにおいてさらに議論を深め、自律的システム構築に取り組んでいきます。
③事故に備えた原子力防災対策の充実に向けた防災連携の加速
上記のとおり、原発の利用に当たっては、不断の努力でその安全性向上を目指していきますが、原子力利用に「絶対安全」はなく、事故に備えた原子力災害対策の充実も取り組んでいくことが大切です。
地域防災計画・避難計画自体は、地域の事情に精通した自治体が策定することになっていますが、発災事業者たる原子力事業者は、事故収束活動に責任をもって取り組むことはもとより、住民支援等の被災者支援活動等に誠意をもって対応することが必要です。その際、原子力発電所において事故が起きた場合の影響は、一事業者の枠内に留まるものではないため、原子力災害対策の充実に向けては各社のきめ細やかな地域への支援に加え、地域性を考慮した各社連携や、全原子力事業者の協力によるリソースの確保が期待されます。
このような観点から、実際に各社の連携も始まっています。具体的には、西日本5社による相互協力協定、中部電力・北陸電力・東京電力ホールディングスによる「原子力安全向上にかかる相互技術協力定」、東北電力・東京電力ホールディングスによる相互協力協定、さらには、北海道電力・東北電力による「原子力災害時における相互協力に関する基本合意」などが、2016年度には取組として進んでいます。
今後、電力自由化が進み、さらなる競争が促される中にあっても、原子力災害対策の充実に当たっては、事業者が一丸となって取り組むことでその対策の実効性を向上させ、こうした体制を整えることによって、結果として、原子力事業への国民の信頼回復が促されることが期待されます。
2.ガスシステム改革の実行
(1)ガスシステム改革の2つの柱
①安定供給を確保すること、②ガス料金を最大限抑制すること、③需要家の選択肢や企業の事業機会を拡大すること、の三つの目的を達成するため、ガスシステム改革は、小売参入の全面自由化、導管部門の一層の中立化の2つを段階的に行うこととしています。
①小売の全面自由化(2017年4月)
一般ガス事業者にしか認められていなかった家庭等へのガスの供給について、2017年4月から小売の地域独占を撤廃し、登録を受けた事業者であればガスの小売事業への参入が可能となりました。これにより、家庭を含めた全てのガスの利用者がガス供給者を選択できるようになりました。これを実現するため、まず一般ガス事業、ガス導管事業、大口ガス事業等といった事業類型に代わるものとして、ガス小売事業(登録制)、一般ガス導管事業(許可制)、特定ガス導管事業(届出制)、ガス製造事業(届出制)という事業類型を設け、それぞれに対し必要な規制を課すこととしました。具体的には、自由化後もガスの安定供給を確保し、需要家保護を図るため、以下のような様々な措置を講じています。
(ア)ガスの安定供給を確保するための措置
一般ガス導管事業者に対しては、導管網の建設・保守、最終保障サービスを義務付けるとともに、これらを着実に実施できるよう、地域独占と総括原価方式の託送料金規則(認可制)を措置することとしました。
また、現在、都市ガス導管網が敷設されている一般ガス事業者の供給区域は国土全体の6%弱にすぎず、ガスの小売全面自由化後、供給安定性を向上させるとともに、ガス小売事業者間の競争を促すためには、都市ガス導管網の一層の整備が必要であることから、都市ガス需要の調査や開拓に係る費用を託送料金原価に算入することを認めるなどの措置を講ずることとしました。
(イ)需要家保護を図るための措置
小売全面自由化と同時に、小売料金規制は原則として撤廃されることとなります。ただし、需要家保護の観点から、競争が不十分な地域には規制料金メニューの提供を経過措置として義務付けることとしています。大手3社(東京ガス・大阪ガス・東邦ガス)を含む12社が対象となります。
また、ガスの小売全面自由化後に、どのガス小売事業者とも契約を結べず、ガスの供給を受けられなくなることのないよう、セーフティネットとして最終的なガスの供給を行うよう一般ガス導管事業者に義務づけています。
さらに、ガス小売事業者に対しては、小売電気事業者と同様に、需要家保護のための規制として、消費者への契約条件の説明義務や、書面交付義務、消費者からの苦情や問い合わせへの対応義務を課すこととしました。
このように様々な措置を講じることで、ガスの小売全面自由化後の消費者の保護を図ることとしています。
②導管部門の法的分離(2022年4月)
ガス市場における活発な競争を実現するためには、導管部門を中立化し、適正な対価を支払った上で、誰でも自由かつ公平・平等にガス導管ネットワークを利用できるようにすることが必須となります。そこで、導管部門の中立性の一層の確保を図るため、導管総距離の長い大手3社を対象に、ガス製造事業・ガス小売事業と一般ガス導管事業の兼業を原則禁止し(法的分離)、大手3社を含めたガス事業者については、会計分離を維持することを予定しています。なお、導管会社がグループ内の小売会社を優遇して、小売競争の中立性・公平性を損なうことのないよう、人事などについても適切な「行為規制」を講ずることとしています。
(2)ガス小売全面自由化の現状
ガス事業については、1995年、1999年、2004年及び2007年の4度にわたる制度改革が行われています。1995年の制度改革においては、従来の一般ガス事業者による地域独占を見直し、大口需要家を対象としたガスの小売部分自由化等を実施しました。この制度改革により、年間契約ガス使用量200万㎥以上の大口需要家は、ガスの供給者を選ぶことが可能となりました。
1999年の制度改革においては、小売自由化範囲の拡大(年間契約ガス使用量100万㎥以上に拡大)、接続供給(託送)制度の法定化、料金規制の見直し(供給約款料金の引き下げについて認可制から届出制へ移行)等を実施しました。また、公正・有効な競争を確保するという観点から、2000年3月、「適正なガス取引についての指針」が制定されました。
2004年の制度改革においては、新たに、ガス導管事業をガス事業法において位置付け、全ての一般ガス事業者及びガス導管事業者に託送供給義務を課すとともに、小売自由化範囲を年間契約ガス使用量50万㎥以上まで拡大しました。
2007年の制度改革においては、小売自由化範囲を年間契約ガス使用量10万㎥以上まで拡大しました。
これまでの4度にわたる制度改革により、ガス販売量の64%が自由化されているところ、本年4月からは家庭などの小口についても自由化が実施されることにより、ガスの小売全面自由化が果たされることとなりました。ガスの小売全面自由化により、一般ガス事業者が独占的に供給していた約2.4兆円の市場(需要家数は約2600万件)が開放されることとなります。この結果、既に自由化されている市場と合わせて、合計約5兆円のガス市場が開放されることになります。このような巨大市場が誕生したことにより、より多様な事業者の新規参入を促し、事業者間での競争がこれまで以上に促進されることが期待されています。
ガスの小売事業への参入者が増えることで競争が活性化し、様々な料金メニュー・サービスが登場することが期待されます。具体的には、電力、通信など他事業分野との連携によるセット割引や、見守りサービス、住宅リフォームサービス等の登場が期待されます。
ガスの小売全面自由化に先立って、2016年8月からガス小売事業者の事前登録受付を開始し、順次審査を行ってきました。2017年4月1日現在において、ガス小売事業45件の申請を受け付け、審査の結果、全件が登録されました。
法律や省令に則り、資源エネルギー庁が、最大需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みやガス小売事業を適正かつ確実に遂行できる見込みがあるか、電力・ガス取引監視等委員会が、「ガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者」に該当しないか、それぞれ審査を行っています。
また、資源エネルギー庁では、一般ガス事業者から契約変更申込件数の報告を徴収し、その情報を基に、地域別のスイッチング申込件数をまとめており、2017年5月5日時点のスイッチング申込件数は、約19万件となっています。
【第123-2-1】ガス小売自由化の歴史
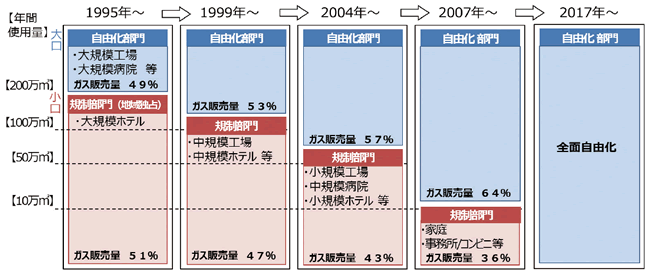
- (注1)
- 小売全面自由化後も、需要家保護の観点から、競争が進展していない地域においては、経過措置として小売料金規制を存続させる。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
(3)今後の展望
今後、ガスシステム改革を契機として、我が国のエネルギー企業は、各エネルギー種の垣根を超えた総合エネルギー企業に進化する可能性があります。これまでは、資源国から石油、電力、ガスとエネルギー種ごとに調達し、石油会社、電力会社、ガス会社といったエネルギー種会社から各ユーザーに供給していました。しかし、より競争的となるべく、今後は、各エネルギー種を一括調達し、エネルギー種のユーザーごとに、それに合ったエネルギーを供給するという総合エネルギー企業が出現してくることが期待されます。