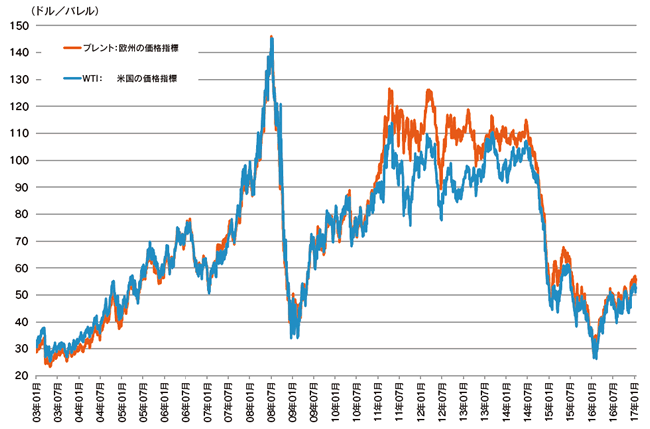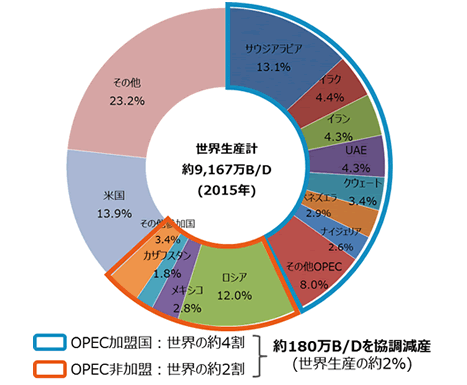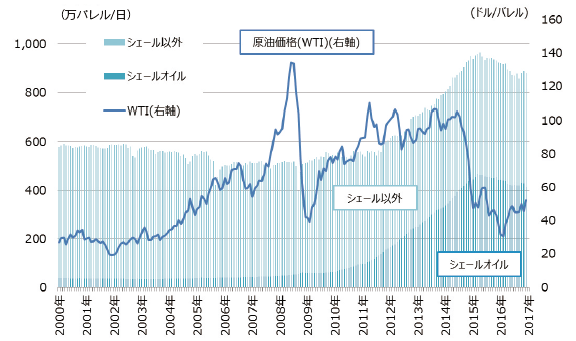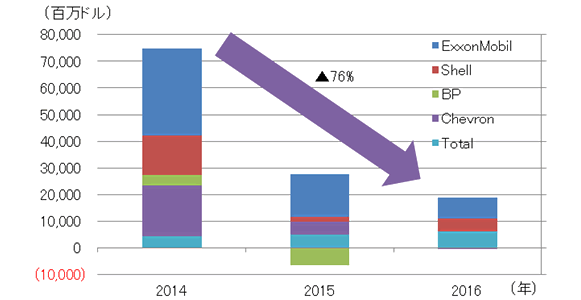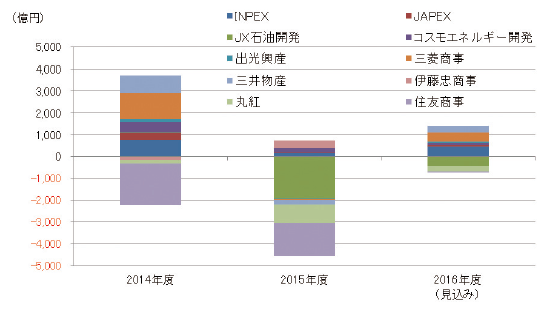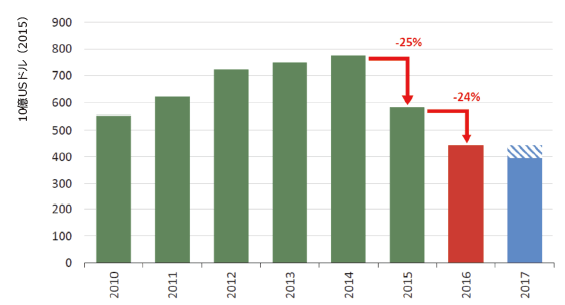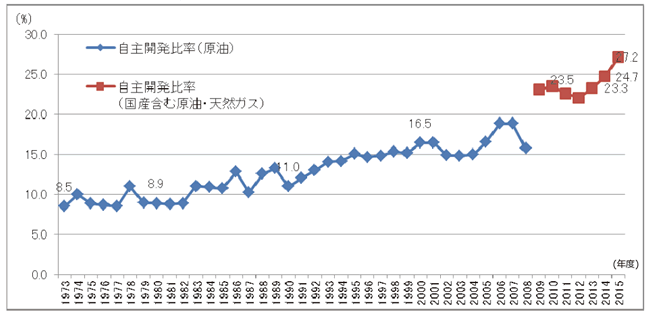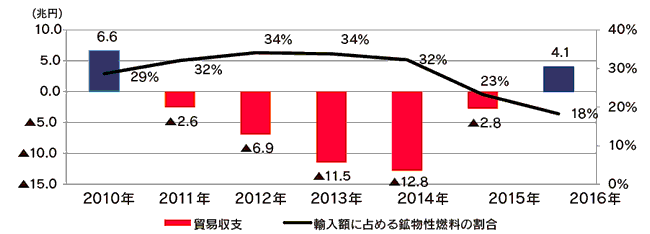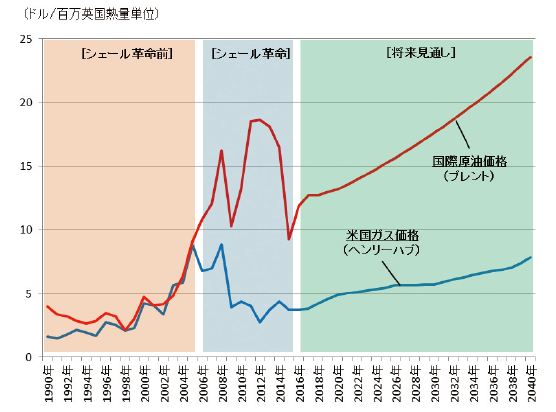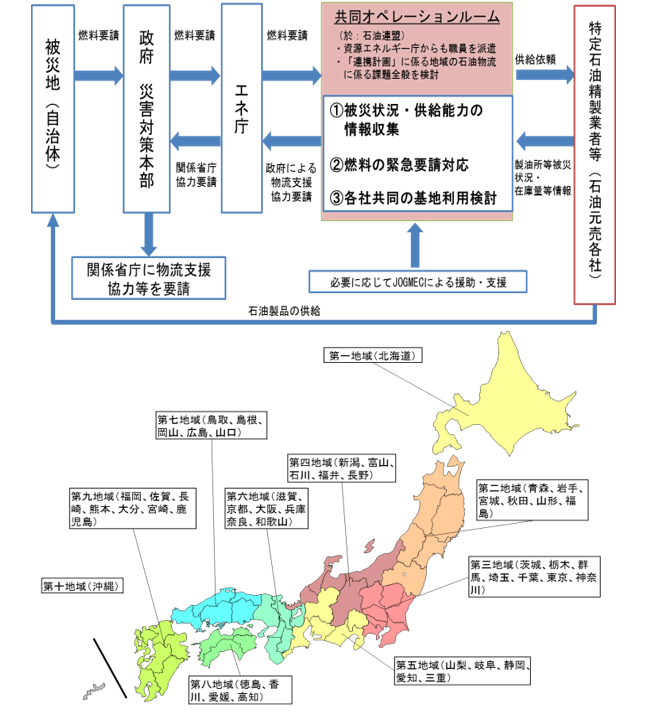第1節 エネルギーセキュリティの強化
はじめに
海外からの資源に対する依存度が高い我が国にとって、国際情勢の変化に対する対応力を高めるため、再生可能エネルギーや原子力などを戦略的に活用していくための取組とともに、ほぼ全量を海外からの輸入に頼っている化石燃料を安定的かつ低廉に調達し、エネルギーの安定供給を確保していくことは、我が国のエネルギー戦略及び国民生活や経済活動の観点から、重要な課題の一つです。
本節では、エネルギーの安定供給確保に向けたエネルギーセキュリティの強化として、①資源開発の動向、②流動性の高いLNG市場の実現、③防災対応の強化について紹介します。
①資源開発の動向では、近年の油価低迷、石油輸出国機構(OPEC)や非OPECによる協調減産の合意等の国際原油市場の動向、2014年後半からの原油価格の低迷による上流開発への影響、加えて、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)法の改正による我が国上流開発体制の強化について紹介します。②流動性の高いLNG市場の実現の取組では、原油価格に連動する価格決定方式や自由な転売を規制する仕向地条項などのLNG取引の現状と課題、世界の天然ガス・LNG取引環境の変革とLNG価格形成の拠点(ハブ)整備に向けた取組、さらに、流動性の高いLNG市場の実現に向けた課題と官民の対応について紹介します。③防災対応の強化としては、東日本大震災の教訓を踏まえた熊本地震対応、熊本地震で明らかになったさらなる課題と今後の取組について紹介します。
1. 資源開発の動向
(1)国際原油市場の動向
国際的な原油価格は1986年に急落して以来、1990年代にかけて20ドル/バレルで安定していましたが、2004年以降は新興国での需要急増などを背景に上昇を続け、2008年7月には147.27ドル/バレル(West Texas Intermediate=WTI、終値ベース、以下同じ)という史上最高値を付けました。その後は、リーマン・ショックの影響で一旦急落しましたが、中国などの新興国の石油需要の急拡大、「アラブの春」による混乱や、イラン核問題といった中東地域での地政学的リスクなどを背景に再び上昇に転じ、2011年以降は100ドル/バレル前後で高止まりしてきました。
しかし、2014年後半以降、原油価格は大幅な下落に転じました。新興国の景気減速などによる需要の伸び悩みや、米国でのシェールオイル増産OPECをはじめとした主要産油国の高水準生産を受けた供給過剰感などから、原油価格は値下がりを続け、2016年2月には2003年以来の安値水準となる26.21ドル/バレルまで下落しました。
従来、原油の生産目標を公表し、世界の石油需給の調整を図ってきたOPECは、今般の供給過剰感を背景とした原油価格下落に対し、2014年11月に行われた総会で生産目標を据え置いて減産を行わないことを決定し、また、2015年12月に行われた総会では生産目標の発表自体を見送りました。これらの動きは、サウジアラビアを中心に石油市場の需給調整役を担ってきたとされるOPECが、生産量が急拡大した米国のシェールオイルに対抗するために、市場シェアの維持を図るための戦略に転じたとされ、石油市場における供給過剰感が継続する要因の一つになったとされます。
- 出典:
- NYMEX、ICE公表の数値を基に資源エネルギー庁作成
2016年2月以降は、OPEC加盟国やロシアをはじめとする非OPECの一部産油国において、原油価格低迷の要因である供給過剰解消に向けた生産調整を図る動きが表面化しました。これに伴い、2016年春以降は、原油価格も上昇基調に転じました。しかしながら、サウジアラビアやイランなど主要産油国の生産調整に対するスタンスの違いなどもあり、なかなか生産調整に関する合意に至らなかったことから、原油価格も春から秋にかけては、40ドル台/バレルで推移しました。
その後も主要産油国による生産調整の議論は継続され、2016年11月のOPEC総会において、2008年の金融危機以来、約8年ぶりとなるOPEC加盟国による減産が合意されました。また、12月には、OPECとの協議を継続してきたロシアなど非OPECの一部産油国も、協調減産を行うことで合意しました。OPECと非OPECの産油国による協調減産合意は、2001年の米国同時多発テロを受けた需要の落ち込みへの対応以来、約15年ぶりとなります。今回の協調減産に合意したOPEC及び非OPECの一部産油国の世界の石油生産量に占めるシェアは約6割に達し、今回の合意は、世界の石油生産量の約2%の減産を行うという規模になります。
これまでもOPECをはじめとする主要産油国が減産合意に至ったことはありましたが、遵守率が高くなかったこともあり、今回の減産合意についても実効性を疑問視する見方もあります。一方で、減産合意に至ったOPEC、非OPECの主要産油国は、減産合意の遵守状況に関する監視委員会を設立し、減産状況を確認していくこととしています。2017年5月下旬に開催予定のOPEC総会では、監視委員会から状況報告が行われた上で、減産の延長が検討される予定とされています。市場では、各産油国の生産動向が注目されていますが、特に、増産が認められたイラン、減産適用除外とされたリビアやナイジェリア、また非OPECの産油国の中でも、特に大きな生産量を占めるロシアなどの動向が注目されています。
- 出典:
- BP統計2016年版を基に資源エネルギー庁作成
一方、主要産油国で協調減産が合意されたことを受け、石油市場に供給過剰をもたらしたもう一つの要因とされる、米国のシェールオイルの生産動向にも注目が集まっています。シェールオイル生産は、投資決定から回収までの期間が在来型原油と比較して短く、原油価格の変化による生産量の変動が顕著とされています。2012年以降、シェールオイルの増産により米国の原油生産量は大幅に増加しましたが、2015年には、原油価格の急落に伴い、米国内の石油掘削リグの稼働数は大幅に減少し、原油生産量も減少に転じました。しかしながら、直近では、上述の主要産油国による生産調整に向けた動きなどにより原油価格が上昇に転じたことを受け、米国内の石油掘削リグの稼働数は増加に転じており、米国の原油生産量にも回復の兆候が見られています。また、シェールオイルについては、生産コストの削減も進んでいるとされ、米国の原油生産量が再び増加
に転じることで、原油価格の上値を抑えるとの見方もあります。
- 出典:
- 米エネルギー情報局の統計データを基に資源エネルギー庁作成
主要産油国による減産合意を受け、原油価格はやや上昇しましたが、直近では50ドル/バレル前後で推移しています(2017年3月現在)。減産合意が遵守されれば、原油価格低迷の要因となってきた供給過剰の解消につながるとの期待感がさらなる原油価格上昇につながるとの見方もありますが、上述のとおり、減産合意の遵守状況や米国のシェールオイルの生産動向次第では原油価格が下落に転じる可能性も指摘されており、今後の先行きは依然として不透明な状況が続いています。また、原油価格は需給バランスに加え、世界経済や金融市場の動向にも影響を受けることから、これらの周辺環境についても注視をしていく必要があります。
(2)原油価格の低迷による上流開発への影響
2014年後半からの原油価格の低迷は、国内外の石油・天然ガス田を開発する、いわゆる上流開発企業の経営に大きな打撃を与えました。「スーパーメジャー」と呼ばれる国際的な石油・天然ガス開発企業上位5社においては、2016年の純利益は2014年比で約76%、額にして約560億ドル減少しました。この傾向は、我が国の石油・天然ガス開発企業においても例外ではなく、2016年の主要企業の純利益の総額は2014年比で約55%の減少となっています。こうした企業体力の減退の結果、世界的に上流開発投資が縮小しています。国際エネルギー機関(IEA)によると、世界全体の石油・天然ガス上流開発への投資額は、2014年から2年間で約43%、額にして約3,000億ドルの減少になると見込まれています。これは、リーマン・ショック後の投資減少額を上回る規模であり、2年連続の投資額の減少は史上初めてとなる未曾有の事態です。足下の上流開発投資の減退は、当然に将来の石油・天然ガスの供給ひっ迫を誘引します。これは、中長期的にはさらなる原油価格の高騰に繋がるものであり、世界経済の不安定化の一つのリスク要因にもなり得るため、上流開発投資の促進は全世界的な課題となっています。
- (注)
- 米国会計基準。
- 出典:
- 出典:各社決算情報を基に資源エネルギー庁試算
- (注1)
- コスモエネルギー開発は経常利益。出光興産は営業利益。
- (注2)
- 出光興産は石油開発部門、商社5社はエネルギー部門の数値。
- 出典:
- 各社決算情報を基に資源エネルギー庁試算
- (注)
- 2016年(見込み)、2017年(予想)
- 出典:
- IEA 「World Energy Investment 2016」
原油価格の低迷は、世界の投資環境に変化を与えました。財政面で極めて厳しい状況に直面したメジャーは、投資額を削減するとともに、非戦略的資産を売却する動きを見せています。例えば、5大メジャーの1つであるロイヤル・ダッチ・シェル(英/蘭)は、2016年から2018年までの3年間で総額300億ドルの資産売却を計画しており、2016年も米国メキシコ湾やカナダのシェール資産などの売却を立て続けに発表しました。また、原油の売却収入が財政に大きな影響を与える産油国及びその国営石油企業においては、原油価格の低迷による財政悪化の影響もあり、増産に向けて上流資産を外資に開放する動きを見せており、世界最大の石油生産者であるサウジアラビアの国営石油企業・サウジアラムコの株式上場が計画されているほか、ロシアの国営企業の政府保有株の売却や、ペトロブラス(ブラジル)の資産売却が進められています。さらに、米国でシェール開発を行う独立系企業を始めとする中堅・中小企業は、メジャーや産油国以上に厳しい財政状況に立たされ、原油価格の低迷に伴い時価総額を大きく低下させました。
こうした動きの中、2016年初頭、原油価格は20ドル台中盤で底を打ち、同年末にはOPEC加盟国・非加盟国による減産合意が実現する等、将来の原油価格上昇への期待から、欧米メジャーや、中国・インドの政府及び国営石油企業を中心として、権益獲得や企業買収が2016年以降再び活発化してきました。2016年2月に、ロイヤル・ダッチ・シェルが英国のガス企業BGを約700億ドルで買収し、世界1位のエクソンモービル(米)に迫るまで生産規模を拡大したことは、こうした一連の投資環境の変化の代表例の一つであるといえます。
自国資源に乏しい我が国では、国産を含む石油・天然ガスの自主開発比率1を2030年に40%以上とする目標を掲げていますが、現在の世界の投資環境は、優良資産を効率的に獲得するとともに、非戦略的資産の売却・処分や企業買収等の思い切った投資判断を通じて、自主開発比率を飛躍的に向上させ、エネルギー安全保障を強化する絶好の機会です。この好機に立ち遅れることなく、我が国上流開発企業の国際競争力強化を支援していくことが求められています。
【第121-1-7】各国企業等の資産売却の動き
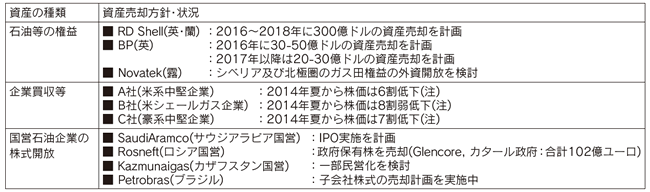
- (注)
- 2017年3月1日時点で比較。
- 出典:
- 報道を基に資源エネルギー庁試算
- (注)
- 1973年度から2008年度まで石油のみを対象とし、自主開発比率を算出してきたが、「エネルギー基本計画」(平成19年3月閣議決定)により定義を見直し、平成21年度(2009年度)以降は石油と天然ガスを合算して、自主開発比率を算出。
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
(3)我が国の上流開発体制の強化
2016年5月、我が国が8年ぶりに議長国を務めたG7首脳会議が三重県・伊勢志摩で開催されました。首脳会議では、現在のエネルギー価格の下落と乱高下が、世界経済の将来の成長に対するリスクとなり得る点を共有し、上流開発投資の促進に主導的な役割を果たすことを首脳間でコミットしました。議長国であり、自国資源に乏しく、石油・天然ガスの自主開発比率の向上を目指す我が国が、世界の上流開発投資の促進を主導していく必要があります。こうした背景から、2016年の臨時国会において、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案(JOGMEC法改正法案)」を提出し、2016年11月に可決・成立、同月に公布・施行されました。今回の改正では、JOGMECによるリスクマネー供給機能を大幅に拡充し、我が国上流開発企業への支援体制を強化しました。具体的には、①JOGMECの出資支援の対象を拡充し、(ア)石油ガス田の個別権益の取得のみならず、我が国企業が行う海外の資源会社の買収や資本提携に対する支援、(イ)我が国企業が探鉱を手掛けた油田の開発に対する支援を可能とするほか、②民間企業では実施困難な、海外の国営石油企業の株式の取得をJOGMECが直接行うことが可能になりました。また、今般の法改正に関連する財源措置として、平成28年度第2次補正予算において124億円、財政投融資計画において1,500億円を措置しました。
【第121-1-9】独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(JOGMEC法)改正の概要
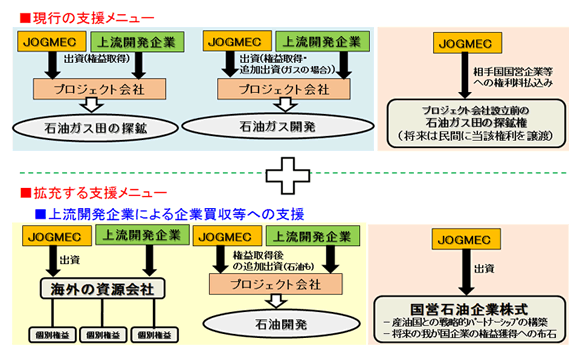
【第121-1-9】独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(JOGMEC法)改正の概要(ppt/pptx形式:134KB)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
これにより、資産売却や企業買収が活発化している現在の局面において、我が国企業が効率的に優良権益を獲得できるほか、企業買収や資本提携によって、パートナーたる海外企業を通じたノウハウの獲得・国際競争力の強化が期待できます。また、JOGMEC による国営石油企業の株式取得は、産油国との戦略的なパートナーシップを構築し、将来の我が国企業の権益獲得への布石となり得ます。今後ますます国際的な資源獲得競争が激化していく中で、我が国上流開発企業の国際競争力の強化に資する今回の法改正は、極めて意義深いものといえます。
これまで、我が国の石油・天然ガス上流開発は、① JOGMEC によるリスクマネー供給等支援、②中核的企業による効率的な権益獲得、③政府による積極的な資源外交の三位一体での取組が重要とされてきました。今回の法改正は、JOGMEC のリスクマネー供給機能を強化するのみならず、我が国の上流開発を牽引する中核的企業の育成にも資するものといえます。現在、我が国の上流開発企業においては、日量約50 万バレルの生産量を有する国際石油開発帝石(INPEX) が最大規模であり、日量100 万バレル以上の生産量を誇る欧米メジャーや準メジャーと呼ばれる世界の上流開発企業と比べて大きく劣後しています。小規模な企業が複数存立している我が国の業界構造の下では、資金・技術・人材等の限られた資源の効率的活用や、海外での現場経験の蓄積を図り、世界の上流開発企業と肩を並べ、我が国の上流開発を牽引する中核的企業を創出していくことが必要です。当面は、日量100 万バレル規模の生産量を有する企業を創出することを目指し、JOGMECによるリスクマネー供給などの政策資源を戦略的かつ重点的に投入していくことが重要となります。このため、政府としては、我が国企業がオペレーターとして参画する案件、相当規模の埋蔵量が期待できる案件、企業間での経営資源の連携・集約化に資する案件に支援を重点化する等により、我が国上流開発産業全体での国際競争力強化や資源価格の変動にも耐えうる財務基盤の強化に努めていくこととしています。
【第121-1-10】世界の石油・天然ガス開発企業(国営企業含む)の生産規模の比較(2015年)
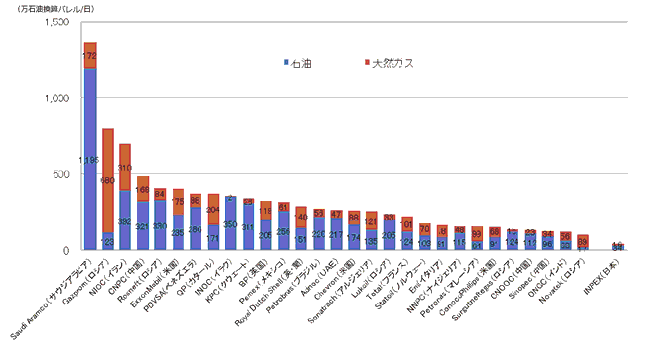
【第121-1-10】世界の石油・天然ガス開発企業(国営企業含む)の生産規模の比較(2015年)(ppt/pptx形式:113KB)
- 出典:
- Energy Intelligence(PIW 2016/11)を基に資源エネルギー庁作成
2.流動性の高いLNG市場の実現
(1)LNG取引の動向と課題
我が国はLNGを約8,300万トン輸入する世界最大のLNG消費国です。これまでのLNGの調達に際しては、特に長期契約においては、原油価格に連動する価格体系が主流でした。このため、高油価局面では我が国のLNG輸入価格が高くなるなど、天然ガスの需給が輸入価格に適切に反映されづらい構造になっています。東日本大震災後には、原子力発電所の稼働停止等によるLNG火力の稼働率上昇に伴い、大量のLNGをスポット取引等により追加的に輸入しましたが、当時の原油高の影響を受けた事に加え、LNG需要の急増による市況のタイト化により、結果として我が国は欧米諸国に比べて高値の天然ガスを輸入せざるを得ず、震災前に6.6兆円の黒字であった経常収支が、2011年には2.6兆円の赤字に転落する等、貿易・経常収支の大幅悪化を引き起こす結果となりました。足下では油価の低下に伴い、我が国のLNG輸入価格は低下し、これも一因となって2016年の貿易収支は再びプラスに転じていますが、LNG価格の決定方法の基本的な構造は変わっておらず、今後の健全なLNG市場育成のためには多くの課題があります。
- 出典:
- 貿易統計を基に資源エネルギー庁作成
また、日本が輸入しているLNG売買契約の多くには、いわゆる「仕向地条項」が付けられています。仕向地が制限されていると、荷揚場所(仕向地)が固定され、第三国や他の事業者への転売が認められなくなります。生産国からみれば、仕向地を固定することで需要国側の引取りを確実にすることができ、また副次的には、スポット市場に出回る天然ガスのボリュームを抑えることができるため国ごとの供給量を一定程度コントロールできるというメリットがありますが、需要国にとっては、長期契約により購入したLNGに余剰が出た場合に、その余剰分のLNGを転売することができないため、長期契約を結ぶリスクが高まることになります。また、仕向地条項により共同調達やスワップ取引等による効率的な調達が難しくなります。その結果、スポット市場への供給が大幅に制約されることから、地域間の価格裁定、ユーザー間の価格裁定が働かず、ひいてはLNG需給を反映した価格形成が阻害されることにも繋がり、引き続き我が国が高値のガスを輸入せざるを得ないというリスクが残ります。
またLNGは、天然ガスから不純物を取り除いた上で零下162度まで冷却・液化したものであり、その取り扱いには専用の設備が必要となるほか、LNGタンカーによる輸送を行うため、気体状態の天然ガスと異なり、取引をカーゴ単位で行うことが通例であり、他のエネルギー商品に比べ取引規模が大きくなります。さらに、液化プラントの建設や、専用の輸送船を必要とするなど、LNG取引に際しては原油に比べ巨額の投資が必要となり、これを回収するため、売主は買主に対し、LNGの転売を制限する仕向地条項を伴う長期契約を求めてきました。これは、一方では、売手と買手が双方とも一定の量を安定的に確保できる面がある反面、転売等によるスポット取引が限定されるため、その取引時点での需給の変化を適時に価格に織り込めないことや、流動性が不十分なために取引の機会が限られ、競争が十分に働きにくい等の課題があります。こうしたこともあり、LNG市場は、石油市場に比べ、スポット取引や先物市場が発達していません。
(2)LNG取引環境の変革
シェール革命や電力・ガスシステム改革等を受け、LNGを巡る内外の市場環境は、まさに今、変革期にあります。2000年代後半に生じたシェール革命の影響は、米国のエネルギー需給の変動を通じて世界全体に波及しつつあります。特にシェール開発の相次ぐ技術革新により、生産性は継続的に上昇しており、米国のガス価格は原油価格と比して将来的にも低位に推移するとする予測もあります。2016年2月の米国本土からのLNGの輸出開始は、こうしたシェール革命の影響が本格的に世界のガス市場に波及することにつながるものです。日本としてもLNG取引の適正化を通じ、原油価格とガス価格が乖離していく環境変化の果実を取り込むことが期待されます。
- 出典:
- BP統計
また、2016年4月から開始された電力市場の小売全面自由化と2017年4月から開始されたガス市場の小売全面自由化は、世界最大の買い手である我が国の電力・ガス企業の調達行動に大きな変化を促すことが予測されます。具体的には、不透明化する自社のエネルギー需要見通しの下で、より柔軟かつ多様なLNG調達の選択肢(例:調達先、調達期間、価格フォーミュラ等)を求めることとなります。加えて、再生可能エネルギー電源の導入拡大等により、発電向けのLNG需要についてはさらに不確実性が高まります。さらに、自由化した電力市場やガス市場では、LNG調達価格が競争力に直結します。こうした変化に適応するため、我が国の企業は、調達量・調達価格の適切な管理や価格ヘッジの手段として、「流動性の高い市場」の活用をより強く指向するようになってきています。さらに、長期契約でコミットした調達量が需要を上回るケースが発生し、一部の買い手がスポットの売り手となってLNGを国内外へ転売するケースが増える可能性もあります。その結果、多様なプレーヤーが「市場」から短期・スポットでの調達を行うことと組み合わせた新たなモデルへと移行していく可能性が高まっています。
この変革期を世界最大のLNG輸入国である我が国がグローバルな市場形成を主導していくチャンスと捉え、経済産業省は2016年5月に「LNG市場戦略」を発表しました。透明かつ柔軟性の高い国際LNG市場の実現を目指すと同時に、2020年代前半までに、LNG取引の集積や価格の形成・発信の面で国際的に認知された「ハブ」となることを目指します。これにより需給調整や価格裁定を行い易くなり、国全体としての調達安定性や価格交渉力の向上も期待できます。
(3)LNG市場の実現に向けた課題と官民の対応
経済産業省は、2016年5月に発表した「LNG市場戦略」において、LNGの流動性の向上や取引ハブの実現のためには、「LNGの取引の容易性(Tradability)」、「適切な価格発見メカニズムの構築(Price Discovery)」、「オープンかつ十分なインフラ(Open Infrastructure)」の3つの要素を備えることが重要であるとしています。
①LNGの取引の容易性の向上
LNGの物理的・商業的な制約をできる限り取り払い、一定の「クリティカル・マス」を超える水準まで取引参加者や取引量、取引頻度を増加させていくことが重要になります。LNGの転売を制限する仕向地制限の撤廃に向けては、消費国間の連携強化などを通じた買主側の交渉力の強化が重要です。そのため、政府としても、主要な国際会議において仕向地制限の撤廃を含むLNG市場の創設に向けた働き掛けを実施しています。例えば、2016年5月に三重県・伊勢志摩で開催されたG7サミットにおいては、より良く機能し、透明かつ競争的な天然ガス市場の実現に向けて各国が取り組むことがG7加盟国の首脳間で確認されました。
②適切な価格発見メカニズムの構築
近年では、プラッツ、アーガス、リム情報開発等のいわゆる価格報告機関によるLNGスポット価格のアセスメント情報が公表されており、スワップ取引等の実績を拡大しつつあるものも見られます。ただし、現状では、LNGのスポット取引の頻度が十分でないこと等から、いずれの価格指標も広く市場参加者に受容されているとは言い難い状況です。価格報告機関によるスポット価格アセスメントの信頼性向上には、価格報告機関の間での競争促進のほか、市場参加者による協力も重要です。政府としては、2016年11月に開催した「LNG産消会議」において、LNGの価格指標に関するセッションを開催しました。このセッションでは、主要な価格報告機関等の代表者が登壇し、価格アセスメントの信頼性向上に向けた価格報告機関の取組等が紹介されました。このほか、民間では、東京商品取引所がLNG取引の活性化に向けた取組を進めており、2016年11月には価格報告機関のプラッツや、シンガポール取引所との間で、取引活性化や価格指標形成等に向けた協力に関する覚書を締結しています。また、指標の信頼性、透明性向上を目指して、2017年4月にはLNG現物市場が東京商品取引所で開設されました。
③オープンかつ十分なインフラの整備
LNGの流動性を高め、我が国がそのハブの地位を獲得するために、新規プレーヤーの参画を促すとともに、事業者間の相互融通や季節間裁定などの柔軟なLNG取引を可能とすることも重要です。例えば、LNG受入基地への自由なアクセスが可能となれば、基地を受け渡し場所とする現物・先物の取引や、LNGのタンク内での取引等が想定されます。LNGのリロード(再輸出)設備により、さらに多様なLNG取引が可能となる場合もあり得ます。さらに、ガスパイプラインが国内で接続され、枯渇ガス田等の地下貯蔵施設の利用が可能となれば、日本全体のLNGの需給調整機能が強化され、LNG取引のボリュームの一層の拡大が期待されます。また、LNG基地への第三者アクセスについては、2015年6月に成立した改正ガス事業法に基づき、いわゆるLNG基地の第三者利用制度が2017年4月より開始されました。
これらの3つの要素を着実に実現していくためにも、LNG市場の「厚み」を増していくことが必要です。具体的には、潜在的なLNG需要やガス需要を日本内外で発掘し、新規プレーヤーの参画を促す必要があります。経済産業省においては、国内ではコージェネレーション等の導入の促進に取り組みます。また近年、国際的な船舶の排出ガス規制の強化が進展し、今後、LNGを燃料とする船舶の増大が見込まれています。国土交通省は国際コンテナ戦略港湾であり、LNG基地が立地する横浜港をモデルケースとし、我が国初となるLNGバンカリング(船舶への燃料供給)拠点の整備方策を検討するため、「横浜港LNGバンカリング拠点整備方策検討会」を2016年に開催し、同年12月にLNGバンカリング拠点の整備計画の策定や実現に向けて取り組むべき課題の整理を行う等、LNG燃料船の普及やLNGバンカリング拠点の整備に取り組んでいます。
また、今後、アジアを中心とした地域において天然ガスの需要拡大が期待されています。政府としては、2016年9月に開催された東アジアサミットエネルギー大臣会合(EASエネルギー大臣会合)において、各国がオープンで透明かつ競争力があり、強靭な天然ガス市場の拡大を促進すること、また新規ガス利用技術を促進していくことを目的として、政府が、開かれた、透明、競争的かつ強靭な天然ガス市場の発展を促し、かつ、貯蔵のための新技術及びこのクリーンエネルギー源の効率的な使用を促進することができる方法に関して、EAS国間で協力と議論を促進することを提案し、これが歓迎されました。今後、2017年に開催予定の、EASエネルギー協力タスクフォース(ECTF)に向けて、ガス市場が効率的に作用することを確保するための市場親和性のある政策オプションの形成に取り組みます。
3.防災対応の強化
(1)東日本大震災の教訓を踏まえた対策
2011年3月11日に発生した東日本大震災では、東北地方から関東地方までの広範囲にわたり、製油所・油槽所等の石油供給インフラのほか、道路・鉄道・港湾等の物流インフラ、タンクローリー・タンカー等の物流手段、サービス・ステーション(SS)等の販売拠点が損壊・滅失しました。また、発災後、緊急車両に対する給油需要が増加する一方で、停電の影響により、SSでの給油が困難になる事態が生じました。さらに、東日本大震災発生当時は、政府、石油業界等が一体となって石油供給の連携や支援を行うための体制が確立しておらず、緊急供給体制の構築に時間を要したため、被災地等への迅速な石油供給に支障が生じました。
こうした経験の反省を踏まえ、今後懸念される首都直下地震・南海トラフ地震等の大規模災害に備えた石油供給体制を早急に確立するため、政府では、地方公共団体や関係業界等と協力しながら、災害時に被災地に対して石油製品を確実に届けることを可能とするために必要な、様々な対策を講じてきました。
東日本大震災当時、我が国における緊急時石油供給体制は、海外からの石油供給途絶リスクを想定したものとなっており、国内災害時の対応を想定した体制が整備されていませんでした。このため、まずは法制度の整備のため、2012年に「石油の備蓄の確保等に関する法律」(以下「石油備蓄法」という。)を改正し、国内自然災害を理由とした国家石油備蓄の放出を可能とするとともに、これまで原油を中心に蔵置を行っていた国家石油備蓄について、全国需要の約4日分に相当する石油製品(ガソリン・軽油・灯油・A重油)の備蓄を増強することとしました。また、同法では、石油元売各社に対して、災害時に石油元売会社が相互に連携して石油供給に対応することができるよう、「災害時石油供給連携計画」の作成を義務付けました。また、一定の設備を備えたSSを災害時の供給拠点として位置付けました。こうした法制度面での整備に加え、資源エネルギー庁では、石油元売各社に対して、製油所・油槽所からの物流プロセス、SSに至るまでの石油サプライチェーン全体の業務継続計画である「系列BCP(事業継続計画)」の策定を要請しました。これを踏まえ、石油元売各社は、被災製油所において24時間以内に1/2の供給能力を回復することを目標とした系列BCPを策定し、資源エネルギー庁では、毎年、各社が策定したBCPの内容やそれに基づく訓練の取組状況について格付け審査を行うことにより、石油業界の危機対応能力向上を促しています。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
災害時における被災地への石油供給を円滑に実施するためには、石油業界の取組のみならず、関係省庁や地方公共団体との協力も不可欠であることから、関係機関との連携を通じた取組も進めています。
まず、燃料の物流を担うタンカー、タンクローリーによる輸送の円滑化を図る取組としては、「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画」(中央防災会議幹事会2015年3月)及び「首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画」(同会2016年3月)において、災害時には、製油所・油槽所のアクセス道路・航路を速やかに啓開することを確認しています。また、2015年4月に災害対策基本法上の「指定公共機関」として石油元売各社を追加指定し、タンクローリーの緊急通行車両確認標章の事前届出を推進しています。
また、これまで整備してきた官民協力による石油供給体制の実効性を向上させるべく、国、地方公共団体、石油業界等が一体となって燃料供給に係る訓練に毎年度取り組んでいます。また、民間のタンクローリー等による燃料輸送が困難な状況や、自衛隊の活動用燃料の確保が困難な状況を想定し、地方経済産業局、自衛隊、地方公共団体等が連携した燃料供給の実働訓練を、全国各地域において実施しています。
以上のようなソフト面での対策のみならず、石油供給の拠点となる施設が災害時においても機能するよう、ハード面での対策も進めています。具体的には、製油所・油槽所が、地震や津波の発生時においても供給拠点としての機能を維持できるよう、非常用電源の増強や耐震強化や液状化対策、製油所間での供給機能バックアップ強化など、石油コンビナートの強靭化を推進しています。
また、自家発電設備や大型タンク等を備え、災害時に緊急車両への優先給油を実施する災害対応型中核給油所(いわゆる「中核SS」)を全国約1,600か所整備しました。なお、LPガスにおいても同様に、自家発電機を備え、災害時にも稼働可能な中核充填所を全国約340か所整備しました。
(2)熊本地震で明らかになったさらなる課題点
2016年4月には熊本地震が発生しました。政府、地方公共団体、石油業界では、東日本大震災後に整備してきた制度・体制を活かし、製油所、油槽所、SS等の石油供給インフラの被災状況把握、被災地からの燃料供給要請への対応、石油供給網の回復等に取り組みました。
具体的には、2016年4月16日の地震の発生後被災地への燃料供給に万全を期するため、経済産業大臣が石油元売会社に対して、「災害時石油供給連携計画」の実施を勧告しました。石油元売各社では、直ちに同計画を発動し、石油インフラの被災状況等の現地情報収集を開始し、被災地からの燃料供給要請に対して迅速に対応する体制を整えました。
また、被災地においては、中核SSが発災後速やかに営業を再開し、警察・消防等の緊急車両や災害復旧車両に対する優先的な石油供給が発災後の10日間で延べ1,600回行われるとともに、現地での燃料供給が途絶えることがないよう、石油元売各社は、被災地におけるタンクローリーを増強し、中核SSへの燃料在庫の補充を優先的に行いました。
【第121-3-2】被災地からの燃料供給要請に対する石油連盟における会合の様子

- 出典:
- 石油連盟
以上のような取組により、熊本地震においては概ね円滑に燃料が供給されました。他方で、熊本地震の経験からも、新たに取り組むべき課題も確認されました。
まず、タンクローリー等の燃料輸送車両の「長大トンネル等」の通行可否の問題です。平時には危険物を積載したタンクローリーの通行は長大トンネル等では規制されておりますが、陸路の寸断や渋滞により、緊急的に長大トンネルをタンクローリーが通行する必要性が生じました。結果的には通行せずに燃料輸送を実現することができましたが、こうした事態を想定した対応として、タンクローリーの長大トンネル等の通行を災害時に特例的に認める措置を、関係省庁において早急に検討することの必要性が確認されました。
また、燃料の供給拠点となるSSでは、発災後、熊本市内などの都市部において、一部SSの営業停止や渋滞による配送遅延の影響で、パニック・バイのような事態が発生しました。そのため、経済産業省と石油元売会社及び農協・商社等のHPにおいて、被災地のSSの営業状況を公表する対応を行い、被災者の不安の解消を図りました。このような事態もあり、災害時に被災者の不安を解消し、パニック・バイのような事態を防止するためにも、緊急車両へ優先給油を行う「中核SS」以外に、災害時に地域住民の燃料供給拠点となる「住民拠点SS」の整備や、災害発生直後から迅速にSSの稼働状況等の把握や被災者への情報発信の体制整備が急務となりました。
以上のような供給側の課題に加え、需要家側でも備えを強化していく必要性が確認されました。病院・避難所等の重要施設において、非常用発電機向け燃料(自衛的備蓄)が不足する事態が発生しました。緊急時に重要施設が機能を継続するためには、平時から非常用発電機の燃料を十分に確保し、機器や燃料のメンテナンスを継続的に実施することが重要です。また、地方公共団体において、地域内の重要施設の把握や国に対する燃料供給要請の方法について十分に認識されておらず、地方公共団体等に対する災害対応の重要性の啓蒙の必要性を改めて認識しました。
そのほか、熊本地震においては、医療機関、福祉施設、避難所等の早期に通電を復旧させるべき施設等に対し、電源車による臨時の電力供給を行う対応が実施されました。また、送電鉄塔が傾斜したこと等により停電が長期化した阿蘇地域に対し、九州電力が全国の電力会社から応援を受け多くの電源車を配備し、24時間体制での送電を実施しました。この電源車に対して、発電用燃料を継続的に給油する必要があったため、九州電力、地元のSS事業者や経済産業省、全国石油商業組合連合会、石油連盟、ドラム缶工業会等が協力し、電源車を配備した地点への大量のドラム缶配備、周辺地域から集めたミニローリーによるSS・小口配送拠点とのピストン運送等、円滑な供給に必要な体制を業界の垣根を越えて急遽調整し構築しました。ガスについても同様に、供給停止した地域において、西部ガスや日本ガス協会が、移動式ガス発生設備による医療機関等への臨時供給などの応急対策を実施しました。
今後、熊本地震と同様に、多くの電源車に対して大量の石油の継続供給を行う事態が発生することを想定し、事前に経済産業省、石油業界、電力業界等における連絡体制の整備や事前の情報共有、さらには訓練を進める必要性が確認されました。
(3)今後の取組
熊本地震で浮き彫りになったさらなる課題を踏まえ、国、地方公共団体、石油事業者、需要家のそれぞれの観点から必要となる対策を検討し、次なる災害に備えて速やかに実行していくことが必要です。
足元の取組として、まず輸送路に関しては、2016年8月26日付けで、石油等を輸送するタンクローリーについて、前後に誘導車を配置するなど通行の安全を確保する場合には、長大トンネル等の通行を可能とするよう、国土交通省から各道路管理者に対して通知がなされました。今後、長大トンネル等を管理する各道路管理者における必要な手続きが整い次第、通行規制が緩和されることになります。
また、災害時においても避難者・被災者の生活を支えるため、自家発電機を備え、災害時に地域住民の燃料供給拠点となる「住民拠点SS」を2019年度頃までに全国8,000カ所整備するとともに、災害時には迅速にSSの稼働状況等を把握し、公表できるシステム構築を進めています。
さらに、需要家側での備えを強化するための取組として、資源エネルギー庁において、災害時の燃料供給に関して都道府県等が行うべき役割についてまとめたマニュアルを作成し、都道府県等向けの説明会を全国各地域において実施しました。また、周知にとどまらず定着を図るための取組として、2016年9月に南海トラフ地震主要被災想定県10県、同年11月にそれ以外の全国の都道府県を対象として、燃料要請対応を行う訓練を行い、こうした取組を通じ、災害時にも、国民への燃料供給を円滑に実施出来るよう努めています。
これらの取組に加え、熊本地震の際に発生した事案である電源車に対する燃料供給について、将来の災害時に迅速に体制構築できるよう、現在、電気事業連合会と全国石油商業組合連合会、石油連盟、経済産業省において、災害時の役割分担や連絡手法等について協議を進めております。また、関係機関の連携による電源車への燃料供給訓練にも取り組んでいます。具体的には、2016年11月の大阪府、堺市、近畿地方整備局、高石市、陸上自衛隊中部方面隊、近畿経済産業局等が連携する訓練において、製油所から電源車が配備された公園まで、自衛隊トラックにて石油製品をドラム缶形態で輸送し給油する内容の訓練を実施しました。また、災害時において、電気・ガスの臨時供給をスムーズに実施する体制を早期に構築することを目指し、今後、自治体、電気事業者、ガス事業者等とで連携し、災害時の電源車、移動式ガス発生設備等の展開を想定した訓練を実施していきます。
熊本地震で明らかとなった課題については、引き続き対策を促進させるとともに、構築した枠組みについて維持・定着を図ることができるよう、関係者間で連携して取り組んでいきます。
【第121-3-3】災害発生時のSSにおける自家発電機稼働の様子
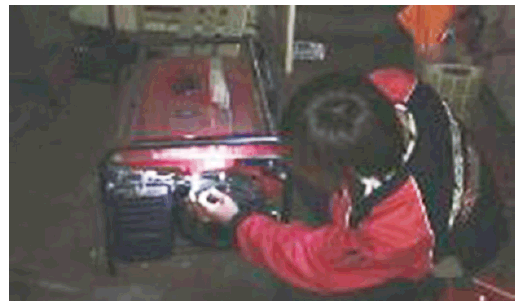
【第121-3-4】電源車への燃料供給の様子
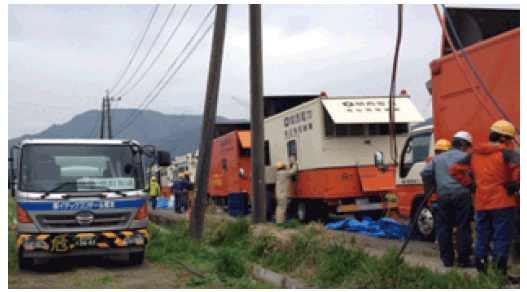
- 出典:
- 資源エネルギー庁
COLUMN
エネルギー安全保障に資する水素エネルギー ~豪州褐炭水素プロジェクトの推進~
水素エネルギーは、高い環境性から、クリーンエネルギーとして期待されるだけでなく、様々な方法で製造することができ、また、気体、液体、固体(水素吸蔵合金の活用など)という様々な形態での輸送・貯蔵が可能であるという特性から、エネルギー安全保障上も重要な役割を果たすことが期待される次世代のエネルギーです。
水素社会の実現に向けては、大規模な水素サプライチェーンの構築が必要となります。政府では、この実現に向け、エネルギー調達先の多様化を実現する大規模な水素サプライチェーンの構築を目指す技術実証の支援に取り組んでいます。以下では、その一つとして、「豪州褐炭水素プロジェクト」を紹介します。
水素エネルギーの資源開発に当たっては、①大量かつ安定的に水素を得ることができるか、②いかに地政学的リスクの低い地域からの調達ができるか、③将来的な大規模サプライチェーンの構築の際、十分経済的に水素の調達が可能となるか、の3点が重要となります。これらの条件を検討の上、川崎重工業株式会社などは、2015年度から、オーストラリアからの大規模水素調達に向けた技術実証プロジェクトを進めています。
オーストラリアのビクトリア州には、石炭の中でも、水分などを多く含む低品位炭である「褐炭」が大量に埋蔵されています。この褐炭は、非常に豊富な埋蔵量を誇る資源である一方、乾燥すると発火しやすく、輸送が困難、といった特徴を有します。このため、現在は、現地において、採掘後すぐに石炭火力発電所の燃料として活用されるに留まっています。また、水分を多く含むため、燃焼の際に、水分の蒸発に多量のエネルギーを要し、得られる電気エネルギーに対してCO2排出量が多いという課題も抱えています。
そこで、豪州褐炭水素プロジェクトでは、石炭のガス化技術(石炭と高温水蒸気を反応させ、水素を製造する技術)を活用し、褐炭から製造した水素を、マイナス253℃の極低温で液化し、液化水素運搬船により日本に輸送する技術について、2020年度までに実証を行い、2030年頃の大規模水素サプライチェーンの確立につなげていくことを目指しています。なお、褐炭のガス化の際に発生するCO2については、豪州連邦政府、ビクトリア州などが取り組むCCS(Carbon Capture and Storage: 二酸化炭素回収・貯留技術)のプロジェクトと連携し、将来的には、CO2を地下に貯留することを見据えています。
世界の褐炭埋蔵量
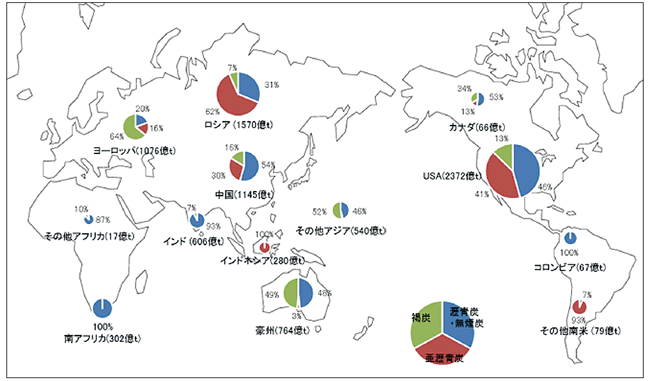
- 出典:
- WEC2013 Survey of Energy Resources 2013
液化水素運搬船のイメージ
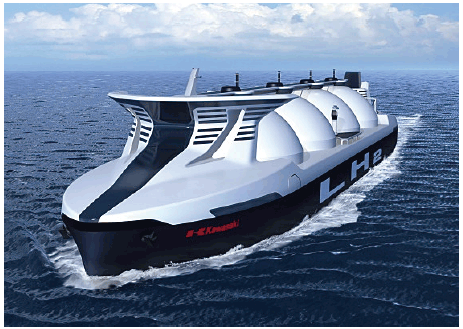
- 出典:
- 川崎重工業提供
本プロジェクトは、当初、船舶建造やプラント建設の知見を有する川崎重工業、水素の取り扱いの知見を有する岩谷産業、石炭ガス化技術の知見を有する電源開発の3社が共同で取り組んできましたが、取組を加速するべく、これら3社に、船舶の国際基準や運航の知見を有するシェルジャパンを加えた4社により、「技術研究組合 CO2フリー水素サプライチェーン推進機構」(HySTRA)が設立され(2016年2月)、現在は、HySTRAにより実証事業が行われています。
政府は、このプロジェクトに対し、技術実証予算による支援だけでなく、液化水素運搬船に関する安全基準の国際合意に向けた支援を行っています。具体的には、国土交通省が、液化水素運搬船の安全要件の策定に関する国際海事機関(IMO)における多国間の議論を主導し、2016年11月には、IMOにおいて、暫定的な安全要件が採択されました。2017年1月には、液化水素運搬船の安全基準について、日豪二国間の協議を終了し、液化水素運搬船の建造着手が可能となりました。
また、2015年12月の安倍総理とターンブル豪州首相の会談の際には、両首脳による共同声明において、本プロジェクトに対する支持が表明されました。2017年1月には、安倍総理大臣の訪豪に合わせ、経済産業省とオーストラリアの産業・イノベーション・科学省との間で、本プロジェクトを含む複数のイノベーションプロジェクトの推進を両国で進めていく旨などを明記した日豪イノベーション協力の覚書が署名されるなど、政府間での連携の動きも加速しています。
- 1
- 自主開発比率は、石油及び天然ガスの輸入量及び国内生産量の合計に占める、我が国企業の権益下にある石油・天然ガスの引取量(国産を含む)の割合と定義されます。