ISO50001導入事例紹介
| 事例1 | エネルギー供給業 | 株式会社東京エネルギーサービス |
| 事例2 | 内装施工・ビルメンテナンス業 | 株式会社パルコスペースシステムズ |
| 事例3 | 鋳物製造業 | 鍋屋バイテック株式会社 |
| 事例4 | 装置設計製作業 | 大村技研株式会社 |
| 事例5 | ビル管理業 | 株式会社オーエンス |
| 事例6 | 産業廃棄物処分業 | オーエム通商株式会社 |
| 事例7 | インフラシステム設計製造業 | 株式会社日立製作所おおみか事業所 |
| 事例8 | 空調・給排水設備設計・施工業 | 栗田工業株式会社 |
| 事例9 | ビル管理事業 | 三幸株式会社 |
| 事例10 | ビル管理事業 | 三井不動産ファシリティーズ株式会社 |
| 事例11 | 建物総合管理業 | 株式会社トーリツ |
| 事例12 | 金属プレス加工業 | 株式会社サイベックコーポレーション |
| 事例13 | 自動車部品製造業 | 株式会社エフテック |
| 事例14 | 小売業 | イオン株式会社 |
| 事例15 | スマートエネルギーサービス業 | 株式会社ファミリーネット・ジャパン |
| 事例16 | 空調機製造業 | ダイキン工業株式会社 |
| 事例17 | 学校教育 | 千葉大学 |
事例7 株式会社日立製作所おおみか事業所

| 1 | 業種 | インフラシステム設計製造業 |
| 2 | 指定・認証 | 省エネ法エネルギー管理指定工場等、ISO14001、ISO9001 |
| 3 | トップマネジメント | 事業所長 |
| 4 | エネルギー方針 | 従業員に配布 |
| 5 | エネルギー目標 | エネルギー消費原単位の1%削減 |
| 6 | エネルギーパフォーマンス指標 | CO2排出量原単位(事業所全体ベース) |
| 7 | 活動 | エネルギーマニュアル文書センサーとイントラを活用した電力使用量の見える化、 太陽光発電設備・蓄電池設備・FEMS(空調制御)の導入、運用規準の改訂 |
| 8 | 成果 | 電力コスト13%削減達成(前期比) |
(1)事業者の概要
(株)日立製作所の情報制御システムを設計製造する大みか事業所は、敷地面積20万m2にサイト人員 約4,000人。2012年7月にISO50001を認証取得。既存マネジメントシステムの認証取得はISO9001を1994年、ISO14001を1996年に取得済。
ほかに2007年にISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)認証を取得。省エネ法の第一種エネルギー管理指定工場。


(2)EnMS導入の経緯
2010年のCO2排出量削減のさらなる推進を契機に、スマートな次世代ファクトリー計画を提案。2011年6月に事業所のBCP対応、太陽光・蓄電池など分散型エネルギーマネジメントシステム社内実証において、①社会インフラ事業のグローバル展開、②マネジメントシステムの国際標準化、③エネルギー使用効率の向上を図る仕組み作りの観点から、大みか事業所をマザー工場として国内・グローバルの展開を図るツールとしてISO50001認証取得を目指した。
ISO50001技術講座に参加して規格の要求事項の解釈の理解から始め、ISO14001取得時の認証登録機関とも取得に向けて検討を開始。既にEMSの運用経験があり、マネジメントシステムの基盤は構築済みであったため、外部コンサルの参画はなかった。
(3)EnMS適用範囲
対象となる組織は、日立製作所インフラシステム社の製造拠点である大みか事業所のみが対象。今後、会社全体や協力会社への拡大も想定。
(4)推進体制
トップマネジメント(EnMS経営責任者)は大みか事業所長。推進主体は大みか事業所長を筆頭に環境管理センター長(EnMS管理責任者)、事業所のエネルギー管理者で構成したエネルギー委員会。エネルギー委員会の下位組織にISO14001と兼務の地球温暖化防止分科会、著しいエネルギーを使用する生産設備WG、試験設備WG、各部門の代表から構成するエネルギー管理委員会の4つのマネジメントチームを編成。
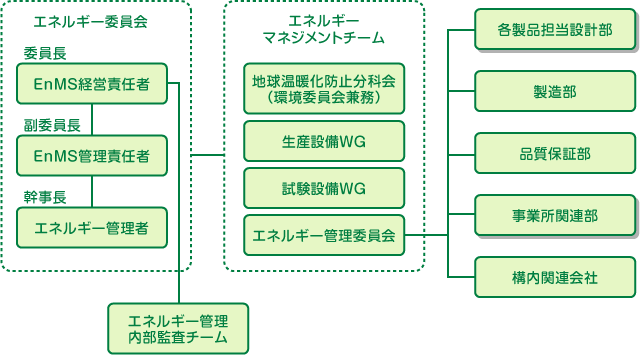
図 EnMS構築・推進体制
(5)エネルギー方針
エネルギー方針は、エネルギーパフォーマンス向上をめざした事業活動を推進することを明確に宣言し、組織の事業内容に照らして、製品やサービスに関してもエネルギーパフォーマンスの向上を目指すことを強調。事業所内ではエネルギー方針をしたためた携帯カードを全従業員に配布、携帯させている。
表 エネルギー方針
スローガン:次世代へクリーンな地球を
2012年5月30日 |
(6)エネルギー目的・目標・行動計画
エネルギーパフォーマンス指標(EnPIs)の選定
エネルギー計画のエネルギーレビューでは、場内の電気・ガス・灯油のエネルギーフローを作成した。
電力は建屋単位の受電電力量のみしか把握できていなかったため、スマートメーターやマルチメーターを約900カ所に取り付けを実施。エネルギーパフォーマンスは床面積当たりの電力原単位を共通指標とし、平均の原単位を上回っている部門(製造部門、品証部門)を‘著しいエネルギーの使用の領域’と特定。
2012年度には、 改善の機会として以下のような対策を実施。
- 太陽光発電設備(940kWh)の導入
- 蓄電池設備の導入(4.2MWh)の導入
- FEMS(電力可視化、空調制御)の導入
さらに、灯油ボイラーのガスボイラー化と、需要場所に対する設置場所の最短化を2012年度中に実施予定。
2012年度以降は、継続的に実施している空調機の高効率化、照明設備Hfインバータ化、照明のLED化等を計画。
中期計画
中期計画として5年間の複数年度で計画を策定。計画では、CO2排出量を2015年までに2010年度比26%減を達成することを目標に設定。単年度目標として、本年度は年間エネルギー消費量原単位1%削減を目指す。マネジメントレビューの中で、 適切なEnPIsの形や変数の選択を検討する予定。
(7)活動の工夫
要求事項の理解
要求事項にある「エネルギーパフォーマンスを確実に検証するための方法を記述する」部分については、データの計測と電力、都市ガス、灯油の各支払伝票の数値と合致していることと捉えて対応することとした。
電力の見える化
これまで電力使用状況を見える化していたイントラホームページに、太陽光発電量、蓄電池充放電量等の最新情報を追加拡充した。
データ収集と分析にともなう関係者の負担感は、分散型エネルギーマネジメントシステム社内実証とISO50001認証取得が同じタイミングで進んだことでEnMS構築の負担感を取り除けた。実証のために組み込まれた約900カ所のセンサー設置は、省エネの必須アイテムと位置付け‘見える化’を推進。
エネルギー使用量の違いが部署ごとに横並びで見えるようになったことで、原単位削減に向けた部門間の省エネ意欲が働き、結果的に省エネが進んだ。また、見える化のシステム作り(設計)は、「お客さまに提案する前に、まず、自ら事業所の中で実証する」ことが重要であるとの視点に基づく取組。
部門ごとの原単位指標の採用
事業所全体では、売上高あたりのCO2排出量原単位をエネルギーパフォーマンスの指標としているが、事業所内で行われる業務が広範であることを考慮して、各部署が自ら最適な原単位指標を設定し、改善を目指すことができるようにした。採用された原単位指標の影響変数には、フロア面積、サーバー設置台数、製作面数、作業時間等があげられている。
運用規準の確立
運用規準として省エネ法「管理標準」の改訂では、番号体系の見直しとともに、環境マネジメントで要求される点検とエネルギーマネジメントで要求される点検を合わせて行うなど、効率的な運用が実現できるよう工夫。例えば、ISO14001の活動として行っていたボイラーのばい煙等測定時に、エネルギー効率に関連する空気比の確認も実施するよう改訂。
エネルギーマネジメントシステム文書
エネルギーマニュアル等の文書化については、内部監査や文書管理の要求事項はISO14001と大きな違いがないと判断。できるだけ新たな文書化による負担がかからないように、ISO14001の文書システムに追加し、合わせて運用ができるように工夫。1996年からISO14001を運用していることから、文書管理の負担や抵抗感は無し。むしろ、第三者認証を通して外部から運用の適合性を担保してもらうことをメリットと考えた。
従業員への周知・理解
エネルギー方針ポスターを各部に掲示。環境小冊子・携帯カードを従業員に配布。電力使用状況のリアルタイム監視と従業員への公開を通じて全員参加型の節電の取組につなげている。
(8)EnMSの構築・認証に必要とした資源
資金・人材等の確保・配分
規格の要求事項「トップマネジメントは必要な資源(人・技能・技術・資金)を用意する」への対応として、認証推進タスクを組織化し、分散型エネルギーマネジメントシステム社内実証と合わせて、ISO50001認証取得を進め、投資と必要な資源を用意。
取得に要した費用
準備から取得までの期間は1年を要した。研修費用としてはECCJのISO50001技術講座に参加。また内部監査員研修を2012年9月に実施した。
2012年1月に事業所長の承認、2月にエネルギーマニュアルの作成を開始。5月に認証登録機関の初回審査を受審。
(9)活動の成果
目標達成の程度
分散型エネルギーマネジメントシステム社内実証とISO50001認証取得が同じタイミングで進めたことは、設備投資及び作業の負担感の軽減などの面で恩恵あり。実際に、センサーの設置によるリアルタイムのエネルギー使用状況の見える化は、日常業務にエネルギー使用量又はエネルギー効率という意識付けが根付いた。エネルギー使用が上限に近付くと、経営陣からの状況確認が入るなど、経営トップから現場の作業者まで共通の課題意識を持って業務に当たることが可能になった。
エネルギーコスト削減費用
2011年下期比、2012年上期電力コスト約13%削減。
その他副次的効果、グループ会社・協力会社へのマネジメントシステム取得の影響
ISO50001を取得している企業が国内でしっかりブランド力として認知され、省エネ活動が優遇されるようになっていくものとの信念。マザー事業所として原単位指標を確立し、グローバルに他事業所にもはめ込んでいく予定。ISO14001でとどまらず、敢えてISO50001にチャレンジした理由として、エネルギーパフォーマンスを改善するという組織の強い意気込みがあった。ISO50001というツールを通して、部署を限定せず事業所全員参加の取組を推進しようとした。特に分散型エネルギーマネジメントシステム社内実証プロジェクトは担当設計やエネルギー関連部署だけが関わるものであるのに対し、ISO50001は組織全体で日々の活動に広げる側面がある。結果、環境というキーワードで事業所全体のベクトルを合わせるのが狙い。また、ISO50001取得を事業所の省エネ取組みのブランド力としていく。
今後の改善の取組み
事業・製品戦略上のステータス向上に関して、事業所のBCP対応(事業継続計画対応)、太陽光・蓄電池など分散型エネルギーマネジメントシステム社内実証とエネルギーマネジメントシステムをパッケージにして投資認可を受けスタートした。本活動は、ISO50001認証のプロセスを生かし、新規製品(サービス)開発のためのインキュベーションとして活用できることを想定し、継続的に推進していく。