ISO50001導入事例紹介
| 事例1 | エネルギー供給業 | 株式会社東京エネルギーサービス |
| 事例2 | 内装施工・ビルメンテナンス業 | 株式会社パルコスペースシステムズ |
| 事例3 | 鋳物製造業 | 鍋屋バイテック株式会社 |
| 事例4 | 装置設計製作業 | 大村技研株式会社 |
| 事例5 | ビル管理業 | 株式会社オーエンス |
| 事例6 | 産業廃棄物処分業 | オーエム通商株式会社 |
| 事例7 | インフラシステム設計製造業 | 株式会社日立製作所おおみか事業所 |
| 事例8 | 空調・給排水設備設計・施工業 | 栗田工業株式会社 |
| 事例9 | ビル管理事業 | 三幸株式会社 |
| 事例10 | ビル管理事業 | 三井不動産ファシリティーズ株式会社 |
| 事例11 | 建物総合管理業 | 株式会社トーリツ |
| 事例12 | 金属プレス加工業 | 株式会社サイベックコーポレーション |
| 事例13 | 自動車部品製造業 | 株式会社エフテック |
| 事例14 | 小売業 | イオン株式会社 |
| 事例15 | スマートエネルギーサービス業 | 株式会社ファミリーネット・ジャパン |
| 事例16 | 空調機製造業 | ダイキン工業株式会社 |
| 事例17 | 学校教育 | 千葉大学 |
事例4 大村技研株式会社
| 1 | 業種 | 装置設計製作業 |
| 2 | 指定・認証 | ISO14001,ISO9001 |
| 3 | トップマネジメント | 社長 |
| 4 | エネルギー方針 | 公開予定(品質方針・環境方針公開済) |
| 5 | エネルギー目標 | 電力量を500kWh/月 削減 |
| 6 | エネルギーパフォーマンス指標 | 月毎のエネルギー使用量(kWh) |
| 7 | 改善対策・活動 | エネルギー消費データ分析の重視,空調温度の適正化, 照明のLED化,昼休み消灯,中間期の外気導入量の削減, 環境・エネルギーマネジメントマニュアル文書, EMS/QMS経験のある内部審査員の活用 |
| 8 | 成果 | 電力量を500kWh/月 を削減達成 |
(1)事業者の概要
半導体製造装置、液晶関連装置、LED関連装置等及び付帯設備の設計、製作、据え付け及び保守・メンテナンスなどの事業が主。資本金2,000万円、従業員数96名。本社、メカニカルセンター他、美浦(茨城県)、熊本、宮崎、会津に営業所を所有。
本社(43名)及びメカニカルセンター(39名)ではISO50001以外のマネジメントシステムはISO9001が夫々2007年と2002年に、またISO14001が夫々2009年と2010年に取得運用している。省エネ法届出対象外。

(2)EnMS導入の経緯
ISO50001導入の経緯は、以下のとおり。
- 2011年3月の東日本大震災の影響によるエネルギー供給不足の懸念から、エコプロジェクトとして節電活動を推進(~同年9月)
- 本社、メカニカルセンターともに主なエネルギー源は電力。メカニカルセンターでは、手洗い場の湯沸しに都市ガスを使用しているが、使用量はごく僅かであり、エネルギー使用量の分析などからは除外した。
- 本社における電力の使用量は、約22万kWh/年~24万kWh/年と安定している。メカニカルセンターでは、設備の稼働試験を行う際のクリーンルームにおけるエネルギーの使用量が多いため、エネルギー使用量はクリーンルームの稼働状況に大きく影響を受ける。そのため、ここ数年のエネルギー使用量は13万kWh/年~約27万kWh/年と稼働率に依存して大きな変動が発生。
- 年間のエネルギー使用量は、年毎の変動はあるものの、最も多い年においても事業者全体で50万kWh/年に満たず、省エネ法による特定事業者には該当しない。
同年10月、エコプロジェクトの成果を社内に定着するため、ISO50001の内部審査員研修をきっかけにISO50001の導入、認証の取得を決断。
(3)EnMS適用範囲
今回ISO 50001の適用範囲は、本社及びメカニカルセンターの2か所。営業所は遠隔であること、エネルギーの使用量も僅かであることから、ISO50001の適用からは除外。本社及びメカニカルセンターにおいては、ISO9001及びISO14001が導入運用されているが、4営業所は適用の対象外。(4)推進体制
EnMSの構築・推進体制は下図のとおり。
ISO9001及びISO14001の推進・運用の組織であるISO 推進委員をISO 50001の構築・推進メンバーに位置付け、EnMSの構築及び運用を推進。
ISO推進メンバーは、各部署から選任され、兼務ながら全員が品質保証部に所属するという推進体制。品質保証部の部長は、社長が兼務。
EnMSの管理責任者は、本社及びメカニカルセンターの推進メンバー(品質保証部)各1名をそれぞれ充てている。
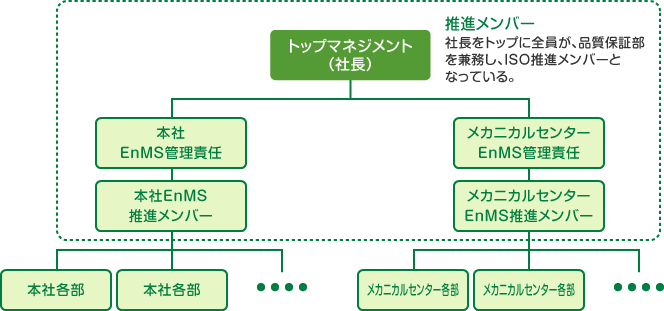
図 ISO50001構築・推進体制
(5)エネルギー方針
既に運用されている環境マネジメントシステムの環境方針に当社におけるエネルギーの使用の特徴、エネルギーマネジメントの目的などを追加し、「環境・エネルギー方針」として整理。エネルギー方針は環境方針と共に外部にウェブページで近日公表の予定(環境方針は公開済)。
(6)エネルギー目的・目標・行動計画
エネルギーベースラインに対して、本社、メカニカルセンターそれぞれに500kWh/月 削減することをエネルギー目標に設定している。この削減目標としたエネルギー消費量は、全社の2.6%に相当する。
この調査時点では、本社、メカニカルセンターともにこの目標を達成しているが、メカニカルセンターのエネルギー使用量が減少している原因が、エネルギーマネジメントの成果よりも、むしろクリーンルームの稼働率の低下にあることを事業者は認識。
エネルギーパフォーマンスの改善の機会は(ハードの投資ではなく)まずは運用改善を中心として対策案を検討。本社の空調は28℃設定としたが、メカニカルセンターはそれでは人間の発汗など作業性が悪く25℃以下とせざるを得なかった。メカニカルセンターでは照明のLED化を進め、昼休み消灯、中間期の外気導入量の削減を実施。
(7)活動の工夫
エネルギーレビュー
本社及びメカニカルセンターそれぞれで、月毎のエネルギー使用(総量)を分析している。本社は、外気温14℃を基準とした回帰モデルによる分析が試みられ、空調によるエネルギー使用量が最も大きいことを把握(このため、空調を‘著しいエネルギーの使用’に特定)。メカニカルセンターは、クリーンルームの稼働がエネルギー使用量に最も大きく影響することが把握されているが、有効な分析の手法については、まだ試行錯誤の段階である。電気使用量は年間247、000kWh(=原油換算64kL)。エネルギーベースライン及びエネルギーパフォーマンス指標
本社、メカニカルセンターそれぞれに2008年から2010年の月毎のエネルギー使用量(総量)の平均を求め、エネルギーベースラインとしている。エネルギーベースラインとエネルギーパフォーマンスを比較するための指標としては、月毎のエネルギー使用量(総量kWh)を使用。本社は14℃を基準温度として回帰モデルによる補正方法を検討。ソーラー電力と買電のデータを区分していないので分析に限界も生じている。
EnPIsやベースラインの決定では、メカニカルセンターは過去3期分の電力量平均値としているが半導体製造装置の入荷時のみエネルギーを多量に使用する傾向にあり、稼働率の影響を受けて値の安定性に課題があった。このため、クリーンルームの稼働状況を補正する原単位指標について開発の段階にある。
エネルギーマネジメントシステム文書
環境マネジメントシステムマニュアルと統合化して、環境・エネルギーマネジメントマニュアルを作成。また、このエネルギーマネジメントのために、「設備管理規程」、「クリーンルーム管理規程」を新たに作成。認証登録機関による登録(認証)の審査は、ISO50001単独で実施されたが、今後はISO14001と時期を統一して実施することを予定。
マネジメントレビューのアウトプット
マネジメントレビューでは、社員全員へのエネルギーマネジメントの教育を完了すること、及び運用面における細かい指示(節電のためにコンセントを抜くことを検討すること、機器の設置の見直し等の指示)が実施されており、トップマネジメント自らが積極的にエネルギーマネジメントに関与。
EnMSの運用における工夫
- ISO9001、ISO14001と統合化した運用体制の構築
ISO推進メンバーの職制化(ISOの推進活動を委員会的な活動ではなく、兼務ながら品質保証部という会社組織に位置付け、通常の業務と完全に融合化した活動の展開を図っている。)
ISO50001の導入
事業者は、ISO50001の導入において以下の点に課題を感じている。
- 用語の理解
エネルギーベースライン、エネルギーパフォーマンス指標等の用語の概念を理解し、組織に適用するのが難しかった。 - ISO14001と要求事項の構成(箇条の番号)が異なること
事業者は、ISO14001に基づく環境マネジメントシステムマニュアルにISO50001の要求事項を追加し、環境及びエネルギーマネジメントシステムマニュアルとしてEMS及びEnMSの運用を図っていたが、要求事項(箇条)の構成が異なることから統合化されたマニュアルの文書化に労力を要した。
エネルギーマネジメントシステムの運用
事業者は、ISO50001に基づくEnMSの構築後、その運用において以下の点に課題を感じている。- エネルギーマネジメントの成果を的確に把握する指標の設定
前述のように、メカニカルセンターでは、試験、評価のために使用されるクリーンルームにおけるエネルギーの使用が最も大きいが、試験設備の稼働状況、評価の対象となる装置も様々であり、エネルギーマネジメントの成果を把握することが困難な状況。
(8)EnMSの構築・認証に必要とした資源
ISO50001及びEnMSの運用に関する知識等を修得するための研修など
- EnMSに関する基本的な知識の習得
事前知識の習得のために、推進メンバーが、審査機関の行ったマーケティングセミナー(半日)に参加し、その情報を社内に展開することによってISO50001の基本的な知識を習得。 - EnMS構築のための研修
ISO 50001の構築に先立ち、推進メンバー全員は、審査機関の行った2時間程度の研修を受講。この研修は、審査機関から講師を社内に招聘する形で実施。 - 内部監査員研修
審査登録機関から講師を招聘し、1日のEnMS内部監査員研修を受講。受講者は、ISO9001、ISO14001の内部監査員経験者を対象としている。
初回審査前に行う規格要求事項と現状のギャップアナリシスより、5月に取得するまで約6か月かかった。取得にかかった工数としては5名×毎週1回×1日×3カ月(=延べ500時間)くらい。
認証取得の費用など
ISO9001及びISO14001の認証を行なっている認証登録機関にISO50001の認証を依頼。ISO14001の認証・運用の実績を踏まえ、認証登録機関へは初年度60万円程度を要した。
(9)活動の成果
ISO50001の導入による成果
事業者は、ISO50001の導入のメリットとして以下を認識。
- エネルギーレビューの実施により、メカニカルセンターのクリーンルームにおいて多量のエネルギーを消費していることがデータ分析を通じて明らかになり関係者で共有できたこと。(EnMSの導入前には、この点は意識されていなかった。)
- 設備投資など大きな投資が望めない企業の場合でも運用による省エネ改善のほか、マネジメント活動を通じて社員のエネルギー管理に関する意識の向上が図れた。
今後の改善の取組み
EnMSに関連する今後の改善、計画は以下のとおり。
- メカニカルセンターにおける有効なエネルギーパフォーマンス指標及びエネルギーベースラインの開発。
- ISO9001及びISO14001と審査の時期を合わせた統合審査への切り替え。
- ISO22301に基づく事業継続マネジメントシステムの導入。