第1節 東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故への取組
1.中長期ロードマップ
廃炉・汚染水・処理水対策は、2019年に改訂された「東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ4」(2019年12月27日 廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議決定。以下「中長期ロードマップ」という。)に基づいて進められています。この改訂では、リスクの早期低減・安全確保を最優先に進める「復興と廃炉の両立」を改めて大原則として位置づけました。この大原則に基づき、個別の対策についても見直しを行っています(第111-1-1)。
【第111-1-1】中長期ロードマップ(2019年12月改訂)の概要
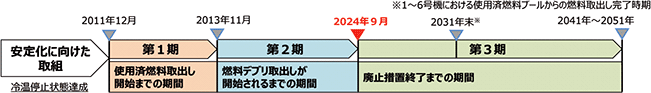
【第111-1-1】中長期ロードマップ(2019年12月改訂)の概要(pptx形式:49KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
2024年9月には、2号機での燃料デブリの試験的取出しの着手をもって、中長期ロードマップにおける第3期に移行しました。引き続き、国も前面に立って、東京電力福島第一原子力発電所の現場状況や廃炉に関する研究開発成果等を踏まえ、中長期ロードマップに継続的な検証を加えつつ、必要な対応を安全かつ着実に進めていきます。
2.汚染水対策
原子炉建屋内には、原子力発電所事故により溶けた燃料が構造物と混ざりながら固まった「燃料デブリ」が残っており、水をかけて冷却を続けることで、低温での安定状態を維持していますが、燃料デブリに触れた水は、高い濃度の放射性物質を含んだ「汚染水」になります。この水が建屋に流入した地下水等と混ざり合うことで、日々新たな汚染水が発生しています。2013年9月には、原子力災害対策本部において「汚染水問題に関する基本方針」が決定され、①汚染源に水を「近づけない」、②汚染水を「漏らさない」、③汚染源を「取り除く」という3つの基本方針に沿って、予防的・重層的に対策を進めています(第111-2-1、第111-2-2)。
【第111-2-1】汚染水対策の3つの基本方針と対応状況
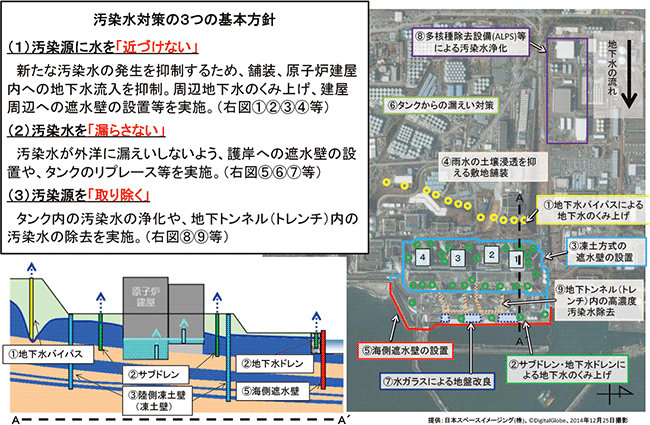
【第111-2-1】汚染水対策の3つの基本方針と対応状況(pptx形式:1,528KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
【第111-2-2】汚染水対策の進捗
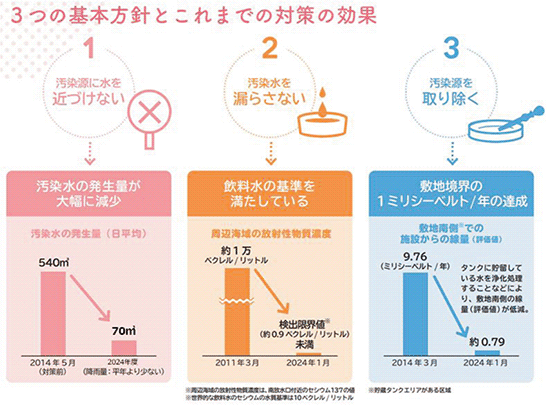
【第111-2-2】汚染水対策の進捗(pptx形式:260KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
汚染源に水を「近づけない」対策は、汚染水発生量の低減を目的としており、建屋への地下水流入を抑制するための多様な対策を組み合わせて進めています。具体的には、建屋の山側で地下水を汲み上げて海に排出する地下水バイパスや、建屋近傍の地下水位を管理するサブドレン、陸側遮水壁(凍土壁)を運用しています。加えて、雨水の土壌浸透を防ぐための敷地舗装(フェーシング)は2025年3月末時点で施工予定箇所の約97%のエリアで工事を完了しています。これらの対策により、汚染水発生量は、対策実施前(2014年5月)の540㎥/日程度から、2024年度には平均で70㎥/日程度まで低減されました。平年雨量相当であったとしても約80㎥/日程度と評価されたことから、中長期ロードマップに記載されている「2025年内に100㎥/日以下に抑制する」という目標を前倒しで達成しました。今後、更なる地下水の流入抑制のため、局所的な建屋止水等を進めていきます(第111-2-3)。
【第111-2-3】凍土壁
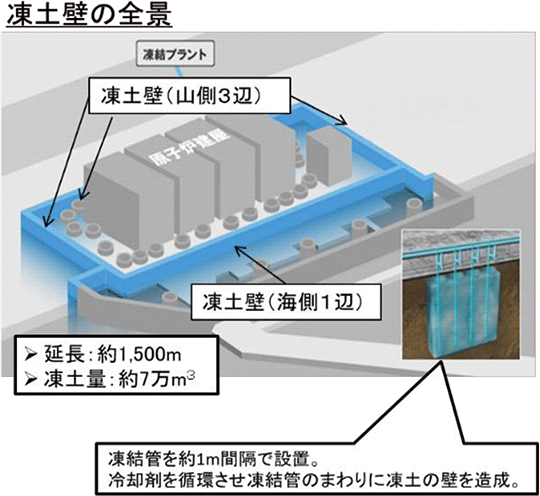
- 資料:
- 経済産業省作成
汚染水を「漏らさない」対策としては、海側遮水壁やタンク周囲への二重堰の設置に加え、1日複数回のパトロールを実施し、海洋へ放射性物質が流出するリスクを低減しています。
汚染源を「取り除く」対策としては、ALPSをはじめ、ストロンチウム除去装置等の複数の浄化設備により、汚染水の浄化を行っています。また、原子炉建屋の海側の地下トンネル(海水配管トレンチ)に溜まっていた高濃度汚染水については、ポンプによる抜き取りと、トレンチ内を充塡・閉塞する作業を全て完了しています。また、建屋内滞留水の除去や浄化についても、1~3号機原子炉建屋、プロセス主建屋、高温焼却炉建屋を除き完了しています。今後は、プロセス主建屋、高温焼却炉建屋の建屋内滞留水処理を進めていく予定です。
さらに、大規模自然災害に対する対策にも取り組んでいます。津波対策としては、切迫性が高いとされている千島海溝津波に対する防潮堤の設置(2020年9月工事完了)に加え、2020年4月に内閣府が発表した日本海溝津波に対する防潮堤の設置を2024年3月に完了しました。また、近年国内で相次ぐ大規模な降雨に備え、浸水解析に基づき、排水路を改良しました(2022年8月供用開始)。こうした予防的・重層的な取組により、汚染水対策は大きく進んできています。
今後は、雨水対策として、建屋周辺の舗装や、破損している1号機屋根のカバー等の対策を進めることで、汚染水発生量は2028年度までに約50~70㎥/日に低減される見通しです。
3.ALPS処理水の海洋放出等
ALPS処理水とは、東京電力福島第一原子力発電所の原子炉建屋内にある放射性物質を含む水について、トリチウム以外の放射性物質を、規制基準を満たすまで浄化した水のことを指します。ALPS処理水は、東京電力福島第一原子力発電所の敷地内で、巨大なタンクの中に貯蔵されています。この巨大なタンクの数は、これからより本格化する廃炉作業を安全に進める上で必要な施設を建設するためのスペースを圧迫するおそれがありました。そのため、ALPS処理水を処分し、タンクの数を減らしていくことは、復興の前提となる安全かつ着実な廃炉に向けて不可欠な作業です。
ALPS処理水の取扱いについては、6年以上にわたる有識者の検討等を経た上で、2021年4月の第5回廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議において、「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」(以下「ALPS処理水の処分に関する基本方針」という。)を決定し、安全性を確保し政府を挙げて風評対策を徹底することを前提に、ALPS処理水を海洋放出する方針を公表しました。
ALPS処理水の処分に関する基本方針の決定以降、「ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた行動計画」(2021年12月28日第3回ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議決定)を策定し、対策の実施状況を継続的に確認して、状況に応じ随時、追加・見直しを行うこととしました。
2023年8月、第6回廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議、第6回ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議(合同開催)において、安全確保と、風評対策・なりわい継続支援に政府としてALPS処理水の処分が完了するまで全責任を持って取り組むことを確認し、2023年8月24日に海洋放出が開始されました。
ALPS処理水の海洋放出に当たっては、トリチウム以外の放射性物質について、規制基準を確実に下回るまで浄化されていることを確認し、取り除くことが困難なトリチウムについても、規制基準を十分に満たす濃度(1,500ベクレル/リットル未満)まで海水で大幅に希釈した上で、処分を行っています。
また、規制基準を満たしていることについては、東京電力のみならず、客観性・透明性を確保するために、第三者機関である国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(JAEA)も分析を実施し、確認しています。
2024年8月30日には、第7回廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議、第7回ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議(合同開催)において、「政府としてALPS処理水の処分が完了するまで全責任を持って取り組む」という方針に変わりはなく、①安全確保、説明・情報発信、②風評影響対応、なりわい継続支援、③将来技術の検討等を引き続き実施することを確認しました。
ALPS処理水の海洋放出は、2023年8月24日の海洋放出開始以降、2023年度中に4回、2024年度中に7回の計11回実施されました。ALPS処理水は、トリチウム濃度が規制基準の40分の1に当たる1,500ベクレル/リットルを下回るレベルまで海水で大幅に希釈して放出されています。その上で、東京電力に加え、水産庁や環境省、原子力規制委員会、福島県等が定期的にモニタリングを実施し、ALPS処理水の海洋放出の前後で、海水や魚類等の放射性物質濃度に大きな変化が発生していないか確認しています。モニタリングの結果や国際原子力機関(IAEA)の評価から、ALPS処理水の海洋放出は人や環境への影響がなく、安全であることが確認されています。また、こうしたモニタリングの結果については、一目でわかるマーク形式でモニタリングの結果を表示するウェブサイト5や、関係機関による測定結果をまとめたウェブサイト等により、国内外に対して、透明性高く、わかりやすい情報発信を継続しています(第111-3-1、第111-3-2)。
【第111-3-1】経済産業省ホームページ 「ALPS処理水に係るモニタリング」二次元コード

【第111-3-1】経済産業省ホームページ 「ALPS処理水に係るモニタリング」二次元コード(pptx形式:42KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
【第111-3-2】包括的海域モニタリング閲覧システム(ORBS)での海域モニタリング結果の情報発信例
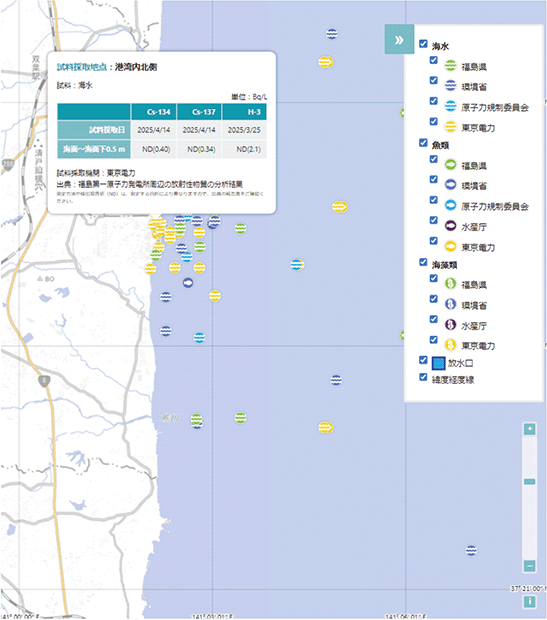
【第111-3-2】包括的海域モニタリング閲覧システム(ORBS)での海域モニタリング結果の情報発信例(pptx形式:292KB)
- 資料:
- 東京電力ホールディングス「包括的海域モニタリング閲覧システム6
加えて、ALPS処理水の海洋放出に伴い、2025年2月より、ALPS処理水を貯蔵していたタンクの解体に着手しました。今後ALPS処理水の貯蔵に使用しないタンクについては、計画的に解体を行います。
また、ALPS処理水に係る取組については、2021年7月に日本政府とIAEAが署名したALPS処理水の取扱いに係る協力の枠組みに関する付託事項(TOR)に基づき、IAEAが安全性に係るレビューを実施してきました。IAEA職員及び国際専門家が繰り返し来日し、東京電力の計画及び日本政府の対応について、科学的根拠に基づき厳しく確認するとともに、その結果については、国内外に高い透明性を持って発信されています。
2023年7月にIAEAから公表された「東京電力福島第一原発におけるALPS処理水の安全性レビューに関する包括報告書」では、ALPS処理水の海洋放出は、関連する国際安全基準に合致し、人及び環境に対する放射線影響は無視できるほどであると結論づけられました。また、海洋放出開始後も、IAEAによる安全性レビューミッションが3回(2023年10月、2024年4月及び同年12月)実施されており(第111-3-3)、放出開始後1回目から3回目までのレビューミッションの報告書(2024年1月、同年7月及び2025年3月に公表)では、日本の取組について、関連する国際安全基準の要求事項と合致しないいかなる点も確認されなかったと結論づけられています。
【第111-3-3】IAEAによるALPS処理水の海洋放出に関する安全性レビューミッション(2024年12月)

左:IAEAタスクフォース(経済産業省及び東京電力ホールディングスとの議論)、右:測定・確認用タンク(K4タンク群)の確認
【第111-3-3】IAEAによるALPS処理水の海洋放出に関する安全性レビューミッション(2024年12月)(pptx形式:6,906KB)
- 資料:
- 経済産業省ニュースリリース
2024年9月20日、日本政府とIAEAは、関係国の関心を踏まえ、IAEAの枠組みの下で現行のモニタリングを拡充することで一致しました。同年10月15日には、このIAEAの枠組みの下での追加的モニタリングの一環として、IAEA及び第三国分析機関(韓国、スイス、中国)の関係者による海水の採水が初めて実施されました。続けて、IAEAの枠組みの下での追加的モニタリングの一環として、2025年2月には、IAEAの枠組みの下でIAEA及び第三国分析機関(韓国、スイス、中国)の関係者による海水の採水、水産物の選定が実施されるとともに、IAEA及び第三国分析機関(韓国、スイス、中国、フランス)の関係者による測定・確認用タンクから海水で希釈する前のALPS処理水の採水が実施されました。さらに、2025年4月には、IAEA及び第三国分析機関(韓国、スイス、中国、ロシア)の関係者による海洋放出前に海水で希釈した後のALPS処理水の採水が実施されました。日本政府は、引き続き、IAEAのレビューを通じて国際的な安全基準に従った対策を講じ続け、安全確保に万全を期していきます。
加えて、原子力規制委員会は、海洋放出設備が使用開始後も必要な機能を有していること及び認可した福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画に基づき設備の運用が適切に行われていることを継続して確認していくとともに、東京電力に対しては、安全に係る法令等の遵守に加え、緊張感を持った対応を求めることとしています。
また、風評影響を抑制する観点からも、こうした安全性の確保等に関する説明や情報発信について継続して取り組むとともに、国内水産物の消費拡大に向けて、様々なイベントやキャンペーン等を通じ、その安全性や魅力の積極的な発信にも継続して取り組んでいます。
2022年12月には、「三陸・常磐もの」の消費拡大を図る官民連携の枠組みとして、「魅力発見!三陸・常磐ものネットワーク」が設立されました。本ネットワークには、2025年3月末時点で、1,200以上の企業、全国の自治体、政府関係機関等が参加しています。2024年10月1日から11月4日には、「三陸・常磐ウィークス(第4弾)」と称して、本ネットワーク参加企業等における社食や弁当の購入等を通じて、約42万食の「三陸・常磐もの」が提供されました。
また、三陸常磐エリアの豊潤な海の幸を多くの方に知っていただき、味わっていただくための施策として、「ごひいき!三陸常磐キャンペーン」を2022年10月から実施しています。全国各地のスーパーマーケット等と連携し、販促キャンペーンを拡大するとともに、各種イベントを実施しており、その模様については、全国地上波のテレビや地方紙、全国紙等で紹介されています。2024年8月に東京ビッグサイトで開催された日本最大級の水産見本市「ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」において、本キャンペーンの下、一画に「三陸・常磐エリア」を設け、三陸・常磐地方の事業者の方々の出展をサポートする等、流通・小売関係事業者等に向けて魅力を発信しました。また、2025年3月には、コンビニ・スーパーマーケット・外食チェーンと連携した「三陸常磐食べようフェア」を開催し、各店舗において三陸常磐ものを使用したオリジナル商品を販売しました(第111-3-4)。
【第111-3-4】国内水産物の消費拡大に向けた取組例

【第111-3-4】国内水産物の消費拡大に向けた取組例(pptx形式:3,448KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
ALPS処理水の海洋放出については、欧州や米国、アジア、太平洋諸国等、幅広い国・地域において理解が広がっています。中国との間では、2024年9月20日、「日中間の共有された認識」を発表し、中国側は、IAEAの枠組みの下での長期的かつ国際的なモニタリングに有効に参加し、参加国による独立したサンプリング等のモニタリング活動を実施後、科学的証拠に基づき、日本産水産物の輸入規制措置の調整に着手し、基準に合致した日本産水産物の輸入を着実に回復させることとなりました。2025年3月の第6回日中ハイレベル経済対話では、双方は、2024年9月に発表した「日中間の共有された認識」が着実に履行されていることを共に評価し、日本側から、日本産水産物の輸入を近く再開するよう求めました。双方は、IAEAの枠組みの下で追加的モニタリングを引き続き実施していくことを確認し、分析結果に異常がないことを前提に、日本産水産物の輸入再開に向けて、関連の協議を推進していくことで一致しました。
引き続き、あらゆる機会を通じて日本の取組を丁寧に説明し、一部の国・地域による科学的根拠に基づかない輸入規制措置の即時撤廃を求めていきます。
また、前述の輸入規制を踏まえ、「水産業を守る」政策パッケージ等により支援策を措置したところです。さらに、令和6年度補正予算の措置として、ホタテ等の一時買取・保管や国内外の新規需要開拓支援、国内加工体制の強化に向けた機器導入等の支援を実施しており、引き続き、全国の水産業の支援に万全を期していきます。
4.使用済燃料プールからの燃料取出し
2011年に決定された中長期ロードマップの初版において、当面の最優先課題とされていた4号機使用済燃料プールからの燃料取出しについては、2014年12月に、燃料1,535体全てを共用プール等へ移送しました。3号機については、2019年4月から燃料の取出しを開始し、2021年2月に燃料566体全ての取出しを完了しました。1号機については、2021年6月から原子炉建屋を覆う大型カバーの設置に向けた作業を実施しています(第111-4-1)。2号機については、2021年8月からオペレーティングフロアの線量低減作業を実施するとともに、2022年6月に燃料取出し用構台の設置に向けた工事を開始しました。
【第111-4-1】1号機大型カバーの設置
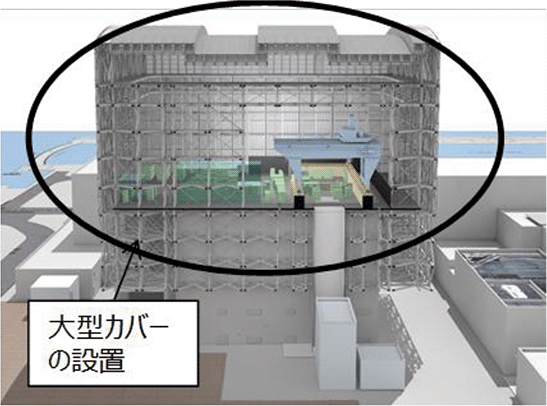
【第111-4-1】1号機大型カバーの設置(pptx形式:231KB)
- 資料:
- 東京電力ホールディングスの図を基に経済産業省作成
引き続き、2031年内に全号機で燃料取出しを完了することを目標に、安全を最優先に、燃料取出しに向けた準備作業を進めていきます(第111-4-2)。
【第111-4-2】東京電力福島第一原子力発電所1~4号機の状況
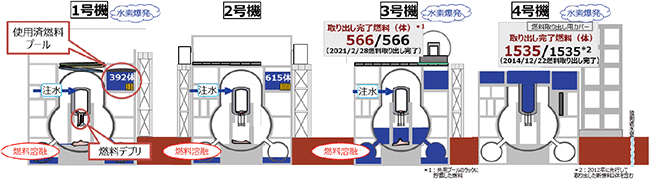
【第111-4-2】東京電力福島第一原子力発電所1~4号機の状況(pptx形式:177KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
5.燃料デブリの取出し
(1)燃料デブリの取出しに向けた原子炉格納容器内の調査
原子力発電所事故により溶けた燃料が構造物と混ざりながら固まった「燃料デブリ」のある1~3号機の原子炉建屋内は放射線量が高く、容易に人が近づける環境ではないため、遠隔操作機器・装置等による除染や原子炉内の調査を進めています(第111-5-1)。
【第111-5-1】原子力発電所の構造
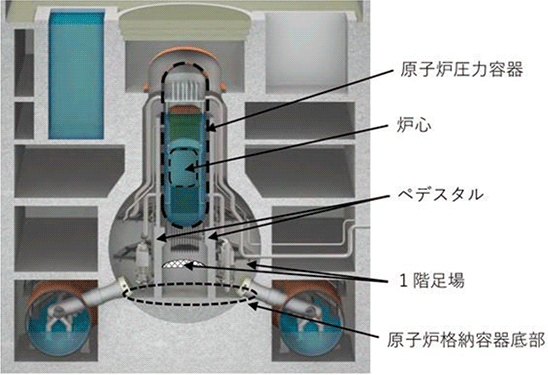
【第111-5-1】原子力発電所の構造(pptx形式:381KB)
- 資料:
- 技術研究組合 国際廃炉研究開発機構の図を基に経済産業省作成
1号機では、2024年2月から3月にかけて、小型ドローンを用いた原子炉格納容器内の調査を実施しました。調査の結果、ペデスタル内壁や構造物、制御棒駆動機構(CRD)ハウジングの落下状況を確認しました。CRD交換用開口部付近では、つらら状の物体、塊状の物体が確認されましたが、ペデスタル内壁のコンクリートに大きな損傷は見られませんでした。狭隘かつ暗所での調査における小型ドローンの有用性が確認されました(第111-5-2)。
【第111-5-2】原子炉格納容器内部調査装置(小型ドローン)及び調査画像
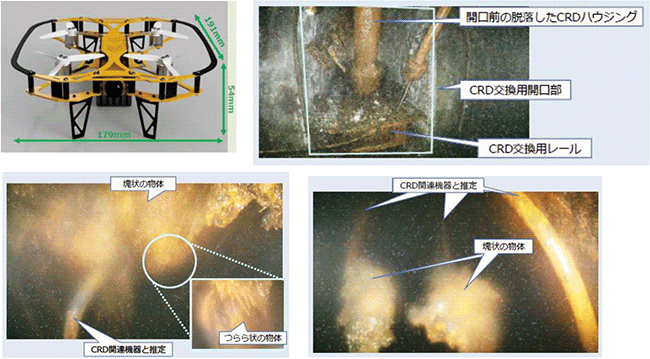
【第111-5-2】原子炉格納容器内部調査装置(小型ドローン)及び調査画像(pptx形式:873KB)
- 資料:
- 東京電力ホールディングス
2号機では、数グラムの燃料デブリを採取する「試験的取出し」に向け、2023年10月に原子炉格納容器内につながる貫通孔のハッチを開放し、2024年1月からは貫通孔内の堆積物の除去作業を開始し、同年5月に除去作業を完了しました。
2024年9月に、テレスコ式装置による燃料デブリの試験的取出し作業に着手し、同年11月に試験的取出しに成功しました(第111-5-3、第111-5-4)。取り出した燃料デブリは、現在JAEA等の分析施設で分析を進めています(第111-5-5)。さらに、燃料デブリのサンプル数を増やし知見を拡充するため、テレスコ式装置を使用し、2025年4月に2回目の試験的取出しに成功しました。2回目に取り出した燃料デブリも同様に分析を進めていきます。
【第111-5-3】テレスコ式装置による試験的取出しイメージ
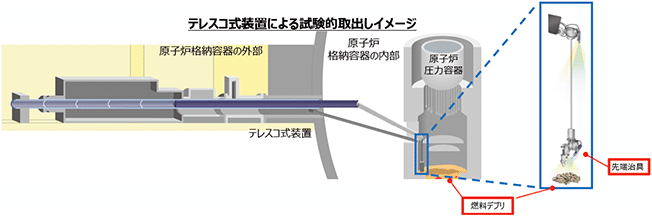
【第111-5-3】テレスコ式装置による試験的取出しイメージ(pptx形式:134KB)
- 資料:
- 東京電力ホールディングス資料を基に経済産業省作成
【第111-5-4】燃料デブリを運搬用ボックスに回収する様子(2024年11月)
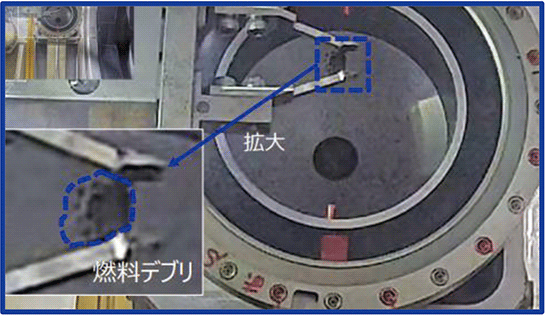
【第111-5-4】燃料デブリを運搬用ボックスに回収する様子(2024年11月)(pptx形式:744KB)
- 資料:
- 東京電力ホールディングス
【第111-5-5】2号機原子炉格納容器内部から採取した燃料デブリ
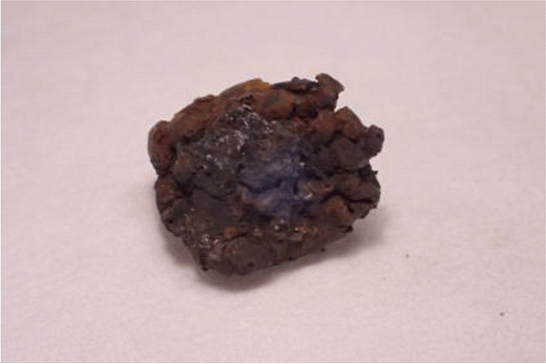
【第111-5-5】2号機原子炉格納容器内部から採取した燃料デブリ(pptx形式:3,055KB)
- 資料:
- JAEA
また、2022年2月より、JAEAの楢葉遠隔技術開発センターにおいて、取出し用のロボットアームのモックアップ試験により貫通孔の通過性や障害物除去等の性能確認を実施しています。試験中に経年劣化箇所が確認されたことを踏まえ、現在、性能確認のための試験を実施しています(第111-5-6)。
【第111-5-6】ロボットアームのモックアップ試験の様子
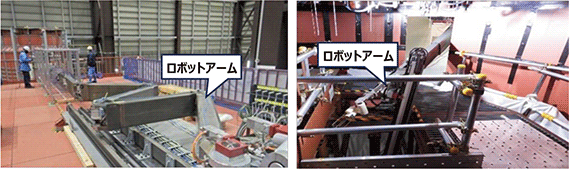
【第111-5-6】ロボットアームのモックアップ試験の様子(pptx形式:967KB)
- 資料:
- 東京電力ホールディングス資料を基に経済産業省作成
なお、いずれの調査においても、周辺環境に影響は生じておらず、放射線モニタリングデータに有意な変動は見られていません。
2023年3月から、原子力損害賠償・廃炉等支援機構が設置した小委員会において、3号機における将来の大規模な取出しに向けた工法について、本格的な検討を開始しました。従来議論されている工法(気中工法、冠水工法)に加え、新たな工法(充塡材で固化・安定化して取り出す工法。気中工法オプション)についても検討し、2024年3月に、当該委員会の報告書を原子力損害賠償・廃炉等支援機構が公表しました(第111-5-7)。現在、東京電力が報告書の提言に基づき、気中工法と気中工法オプション(充塡固化工法)の組み合わせによる具体的な設計検討を進めています。
【第111-5-7】燃料デブリの大規模な取出しに向けた工法
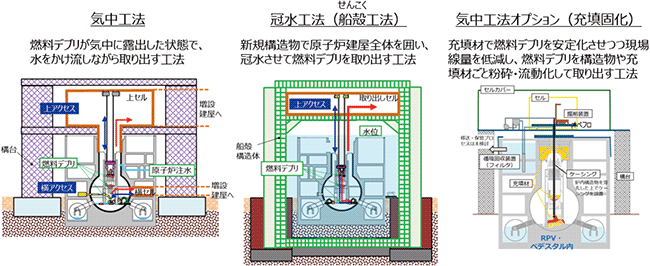
【第111-5-7】燃料デブリの大規模な取出しに向けた工法(pptx形式:408KB)
- 資料:
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構資料を基に経済産業省作成
(2)廃炉に向けた研究開発
廃炉に関する技術基盤を確立するための拠点整備も進めており、2016年4月には、楢葉町において、遠隔操作機器・装置の開発・実証施設(モックアップ施設)であるJAEAの「楢葉遠隔技術開発センター」が、本格運用を開始しました(第111-5-8)。
【第111-5-8】モックアップ施設である楢葉遠隔技術開発センターと試験設備
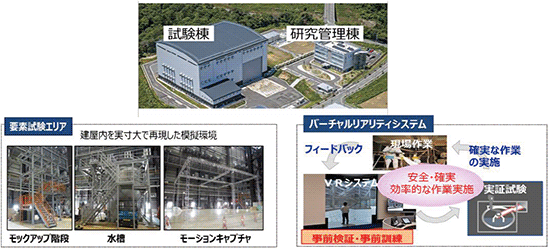
【第111-5-8】モックアップ施設である楢葉遠隔技術開発センターと試験設備(pptx形式:796KB)
- 資料:
- 技術研究組合 国際廃炉研究開発機構
2017年4月からは、富岡町において、廃炉に係る基礎的・基盤的な研究開発や人材育成に取り組む拠点として、「廃炉国際共同研究センター(現:廃炉環境国際共同研究センター)国際共同研究棟」を運用しています。
2018年3月には、大熊町において、燃料デブリや放射性廃棄物等の分析手法、性状把握、処理・処分技術の開発等を行うJAEAの「大熊分析・研究センター」の一部施設が運用を開始しました。さらに、2022年6月には、放射性廃棄物等の分析を行う第1棟が竣工し、現在は、燃料デブリ等の分析を行う第2棟の建設工事を進めています(第111-5-9)。
【第111-5-9】燃料デブリや放射性廃棄物等の処理・処分技術の開発等を行う大熊分析・研究センター
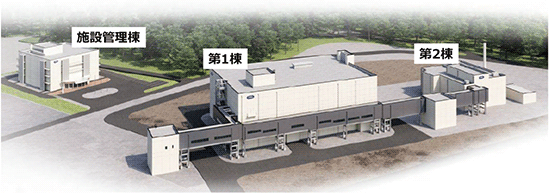
【第111-5-9】燃料デブリや放射性廃棄物等の処理・処分技術の開発等を行う大熊分析・研究センター(pptx形式:1,011KB)
- 資料:
- JAEA
6.廃棄物対策
東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に伴い発生する固体廃棄物は、物量が膨大かつ多種多様な性状を有しているため、安全かつ合理的な保管・管理を徹底することが求められます。
固体廃棄物の適切な保管・管理を行うため、東京電力は、2016年3月に、今後10年程度の廃棄物の発生量を予測した「東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の固体廃棄物の保管管理計画」(以下「保管管理計画」という。)を策定し、進捗状況等に応じて、毎年度改訂しながら、固体廃棄物貯蔵施設・減容施設の整備や焼却炉による減容処理等、廃炉工程を進める上で増加する廃棄物を適切に保管・管理するための取組を進めています。2024年12月に改訂された保管管理計画においては、中長期ロードマップの目標である「2028年度内までに、水処理二次廃棄物及び再利用・再使用対象を除く全ての固体廃棄物(伐採木、ガレキ類、汚染土、使用済保護衣等)の屋外での保管を解消し、作業員の被ばく等のリスク低減を図る」ために必要な取組等が定められています。
また、廃棄物の処理・処分の検討を進めていくためには、廃棄物の核種組成、放射能濃度等を分析することが必要ですが、事故炉である東京電力福島第一原子力発電所は、廃棄物の物量が多く、核種組成も多様であることから、分析試料数の増加に対応しながら、分析を進めていくことが重要であり、廃棄物の分析体制の強化は重要な課題の1つです。東京電力は、今後の廃炉を効率的に進めるために必要な分析対象物と分析数を年度ごとに見積もった「東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた固体廃棄物の分析計画」を、2023年3月に公表し、毎年度更新しながら、適切に分析を進めるための取組を進めています。この分析計画を着実に実行していくため、政府、東京電力、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、JAEA等の関係機関の連携の下、必要となる「分析人材の育成・確保」「施設の整備」「分析を着実に実施していくための枠組みの整備」等、分析体制の強化のための取組を進めています。この分析計画及び分析体制整備に必要な対応については、今後の分析作業の進捗や得られたデータに基づく検討を踏まえ、不断に見直しを行っていく予定です。
7.労働環境の改善
長期にわたる東京電力福島第一原子力発電所の廃炉作業を円滑に進めていくためには、作業に従事するあらゆる方々が安心して働くことができる環境を整備することが重要です。
事故の直後には、発電所構内全域において全面マスクと防護服の着用が必要であり、全面マスクについては、装着すると息苦しい、作業時に同僚の声が聞こえづらいといった課題が、防護服については、動きづらい、通気性がなく熱がこもるといった課題がありました。これらは、作業時の大きな負担になるとともに、安全確保に当たっての課題にもなっていました。また、食事については、十分な休憩スペースもなかったことから、冷えたお弁当を床に座って食べるというような環境でした。
そのため、東京電力は、発電所内の労働環境改善に継続的に取り組んできました。例えば、除染・フェーシング作業による環境線量低減対策を行うことで、全面マスクと防護服の着用が不要なエリアは、構内面積全体の96%まで拡大しました。1~4号機を俯瞰する高台については、マスクなしでの視察が可能となる運用を開始しています。また、ヘリポートを設置して搬送時間を短縮したことで緊急時の医療体制を強化する等、健康管理対策についても充実させてきました。さらに、食堂、売店、シャワー室を備え、一度に約1,200人を収容可能な大型休憩所を設置しました。食堂では、発電所が立地する大熊町内の大川原地区に設置した福島給食センターにおいて地元福島県産の食材を用いて調理した、温かくておいしい食事を提供しています。長期にわたる廃炉作業を着実に進めていくため、今後も引き続き、安全でより良い労働環境の整備に努めていきます(第111-7-1)。
【第111-7-1】構内面積96%まで拡大した一般作業服等エリアと1,200人を収容可能な大型休憩所
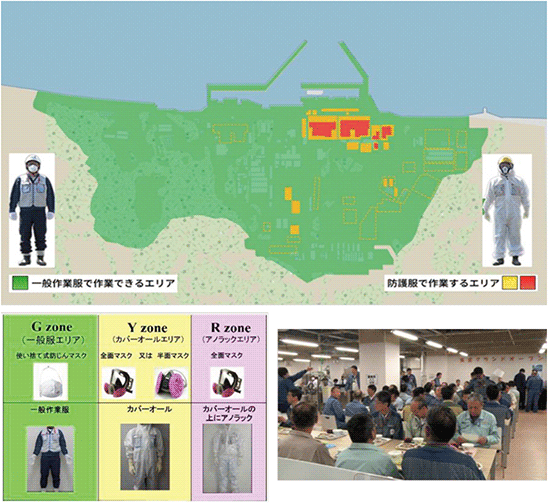
【第111-7-1】構内面積96%まで拡大した一般作業服等エリアと1,200人を収容可能な大型休憩所(pptx形式:1,053KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
8.国内外への情報発信
長期にわたる廃炉作業は、帰還・復興が進展する周辺地域において、住民の安心・安全に深く関わるものです。また、風評を生じさせないためにも、国内外に対して東京電力福島第一原子力発電所の現状についてわかりやすく正確な情報を発信するとともに、地域・社会の不安や疑問に答えていくことが重要です。
地元を中心とする国内への情報発信としては、周辺地域の首長や関係団体等が参加する「廃炉・汚染水・処理水対策福島評議会」を開催し、廃炉・汚染水・処理水対策の進捗をお伝えしているほか、対策の進捗をわかりやすく伝え、様々な不安や疑問にお答えしていく動画・パンフレットの作成等にも取り組んでいます(第111-8-1)。また、情報発信に際しては、双方向のコミュニケーションを意識しており、住民に東京電力福島第一原子力発電所を視察いただき、その中で感じた疑問に直接お答えする視察・座談会の取組や、地元でのイベントへの廃炉関連ブースの出展、コンテンツ制作における地元の方々の意見の事前聴取・内容への反映等の取組を進めています。東京電力も、2018年11月に、「東京電力廃炉資料館」を富岡町において開館し、事故当時の状況や廃炉・汚染水・処理水対策に関する情報発信を行っています。
【第111-8-1】動画やパンフレット等のコンテンツ
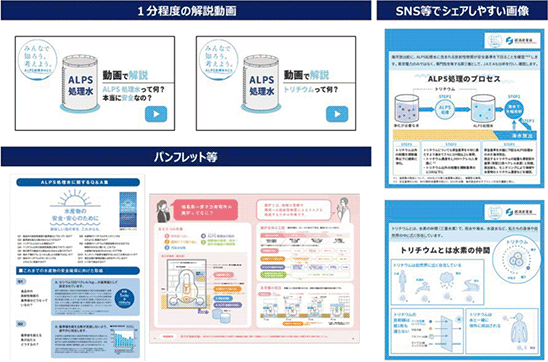
【第111-8-1】動画やパンフレット等のコンテンツ(pptx形式:728KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
国際社会への発信として、多国間の枠組みでは、例えばオーストリア・ウィーンで開催されるIAEA総会において、直近では、2024年9月に、経済産業省、東京電力、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、環境省から、福島県における復興の現状、東京電力福島第一原子力発電所における廃炉の現状、燃料デブリの取出し、オフサイトにおける取組を紹介し、参加者に対し、理解の促進を図りました。二国間の枠組みでも、継続的に情報提供や意見交換を行っています。また、在京外交団等や特に関心を有する国・地域に対しては、廃炉・汚染水・処理水対策の現状及びALPS処理水の海洋放出に係る対策の進捗、IAEAによる評価等について、累次にわたって説明する機会を設けています。加えて、様々な国際会議における説明、政府のホームページにおける情報提供、国内外の報道関係者に対する説明等を実施しています。
- 4
- 本ロードマップは、2011年に決定された「東京電力(株)福島第一原子力発電所1~4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(2011年12月21日 原子力災害対策本部 政府・東京電力中長期対策会議決定)を継続的に見直しているものです。