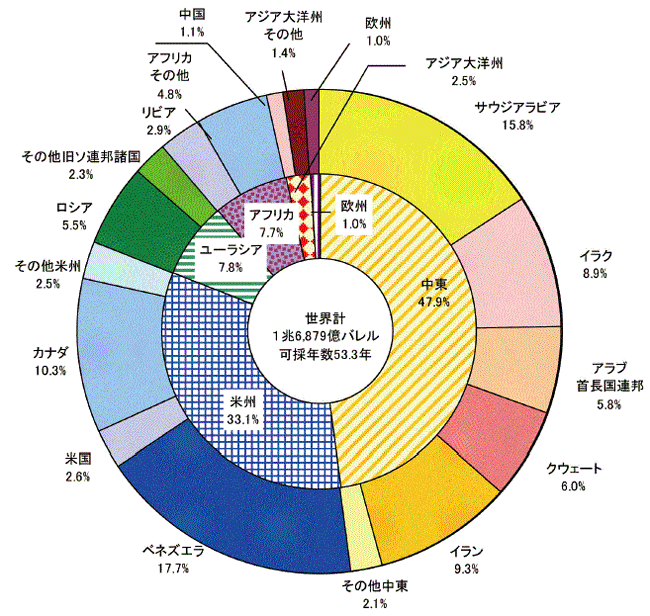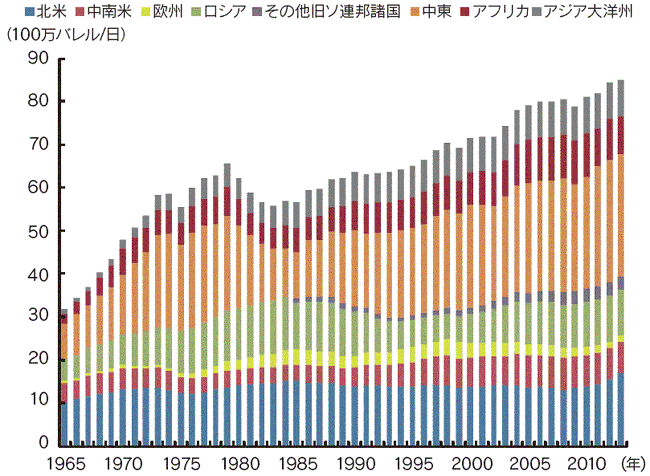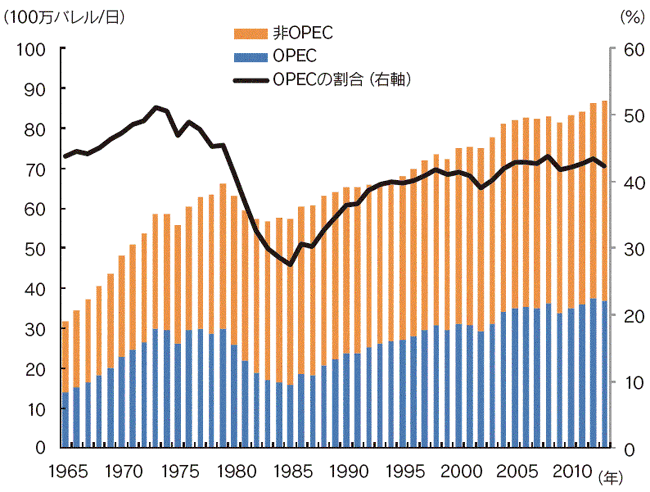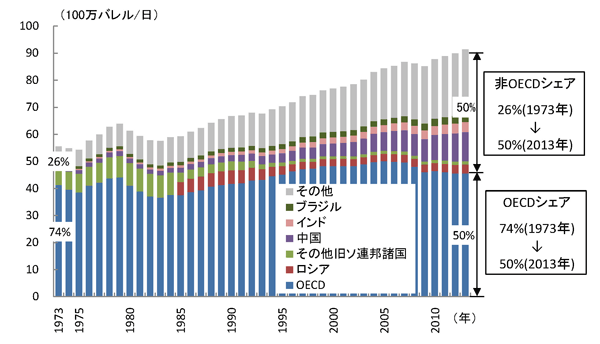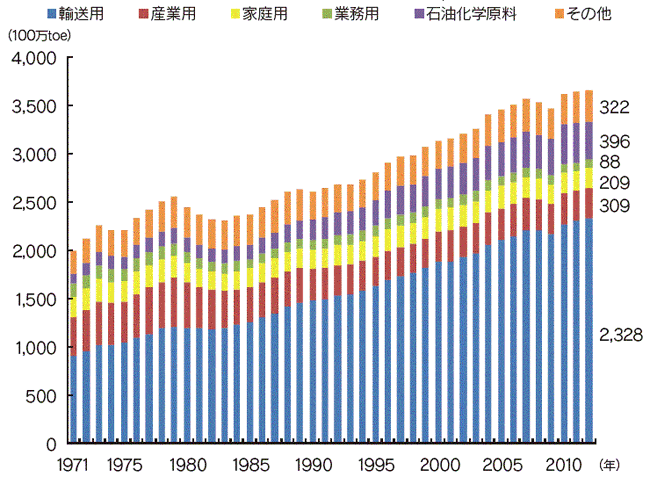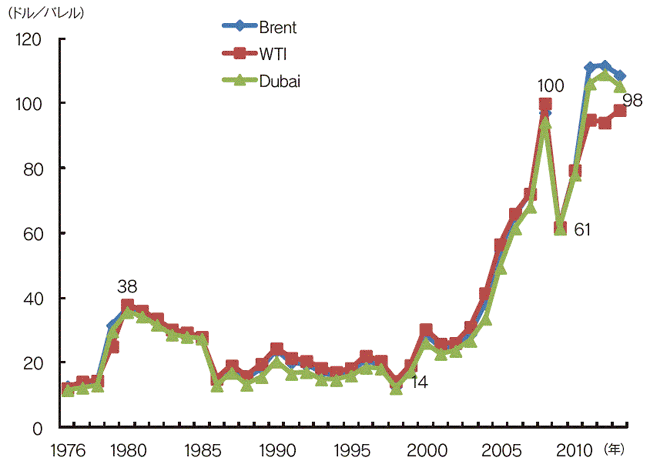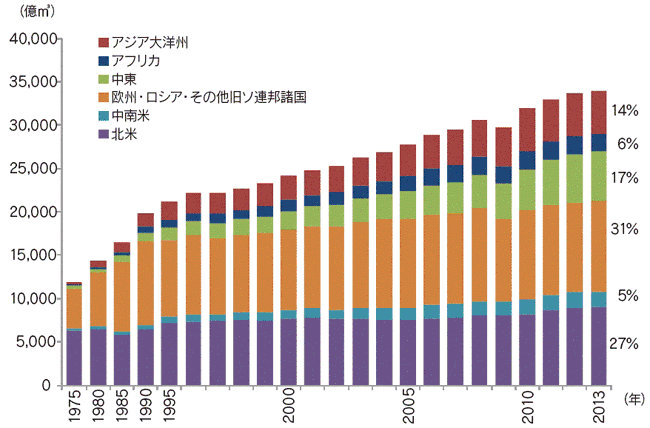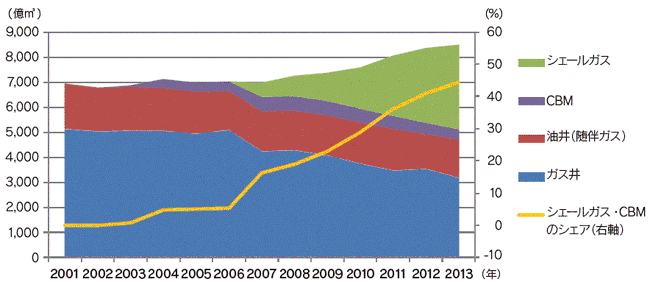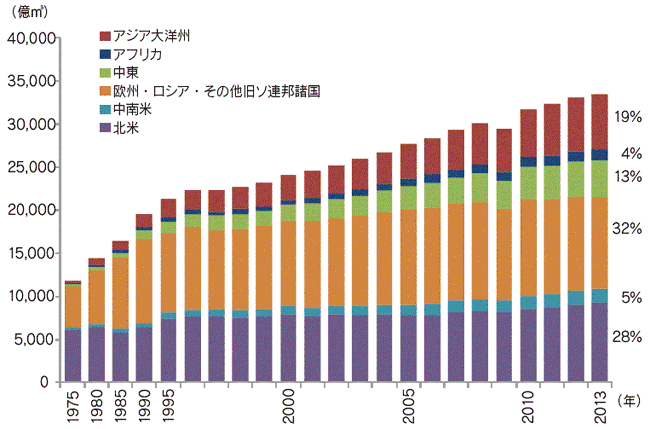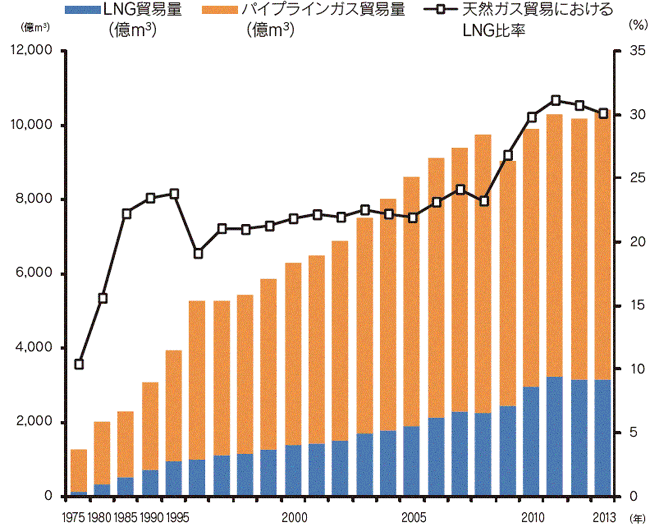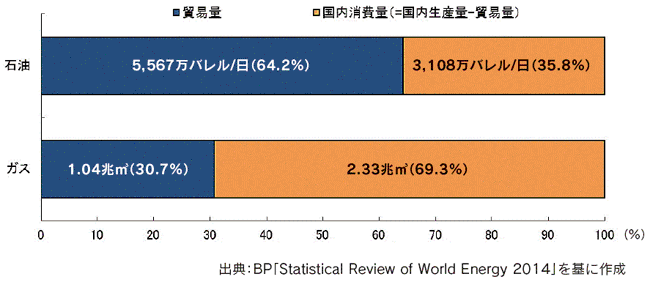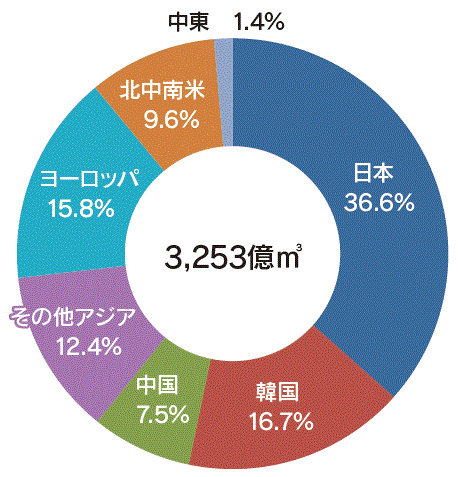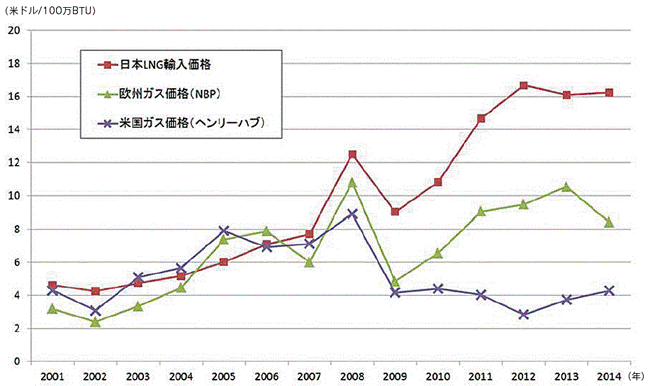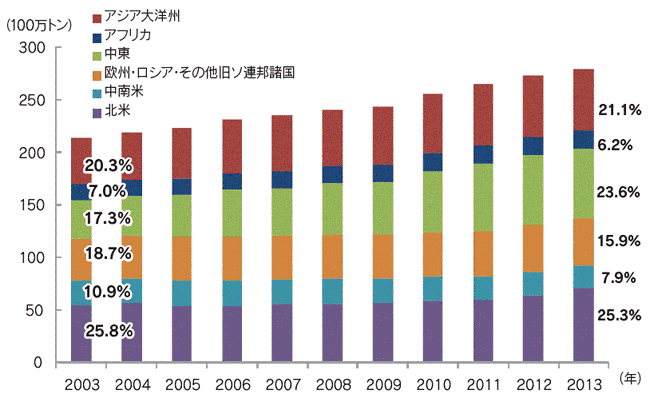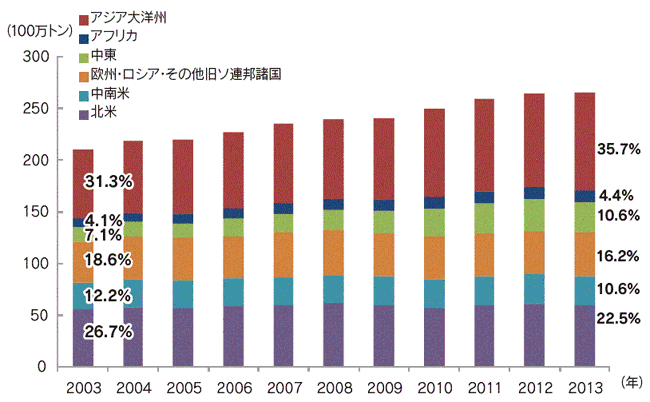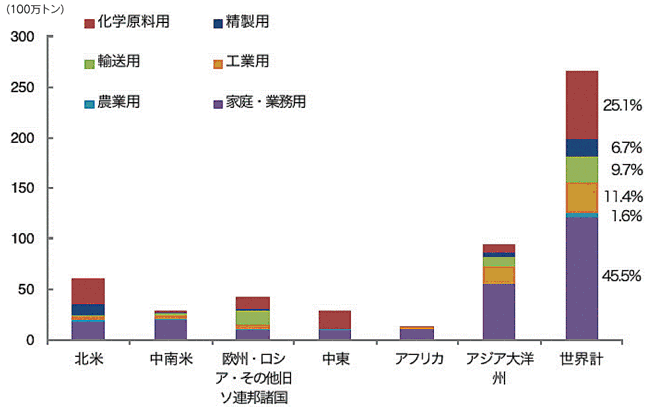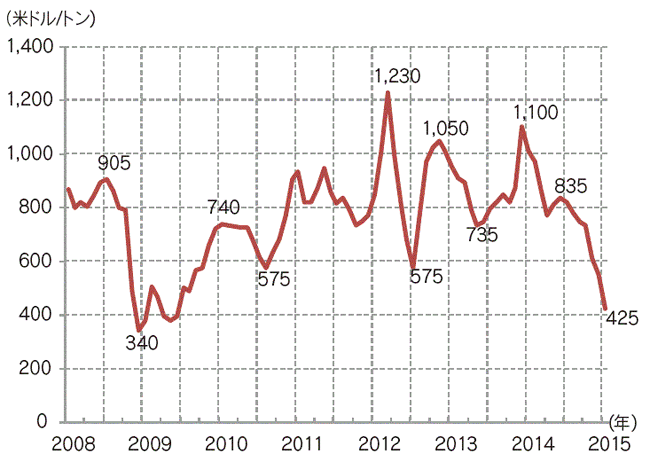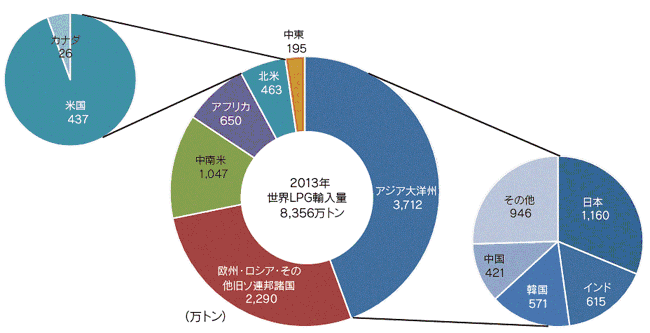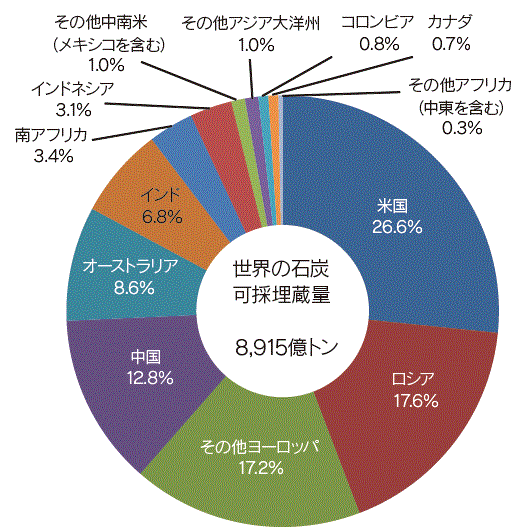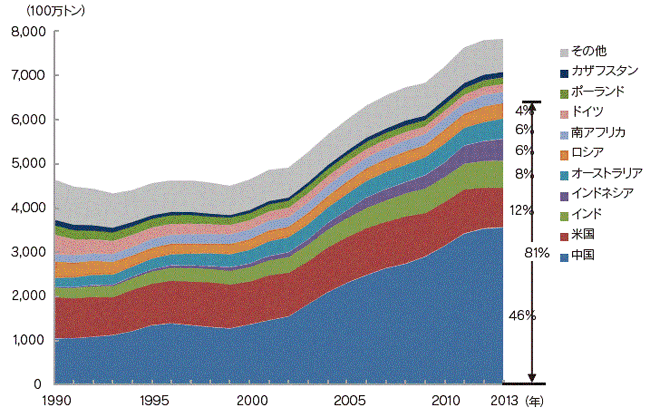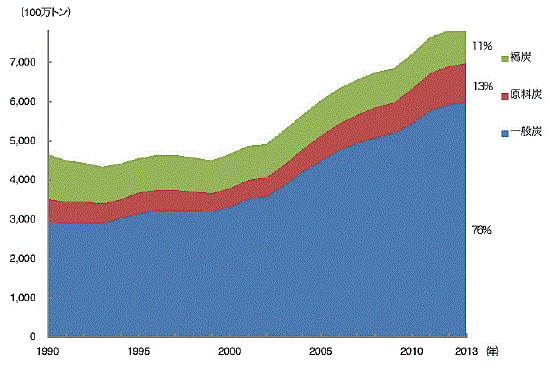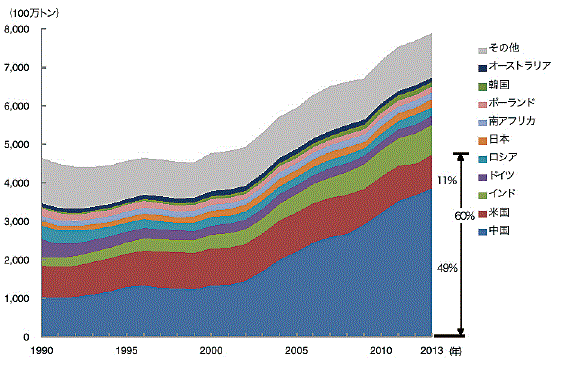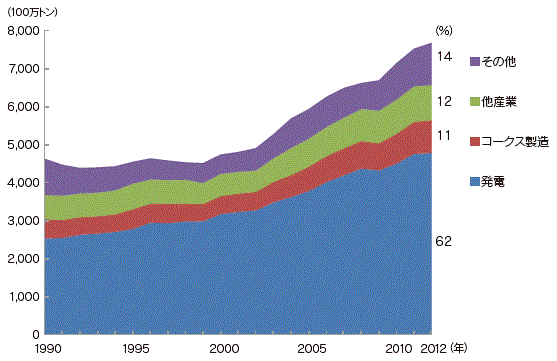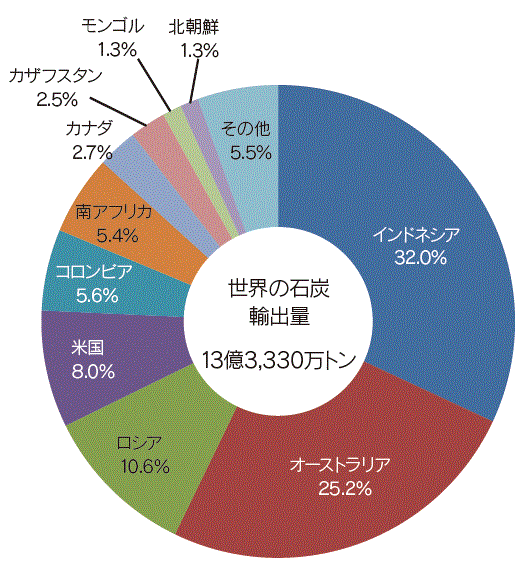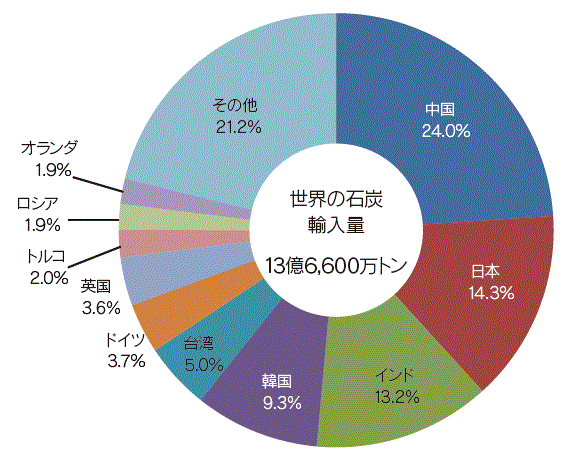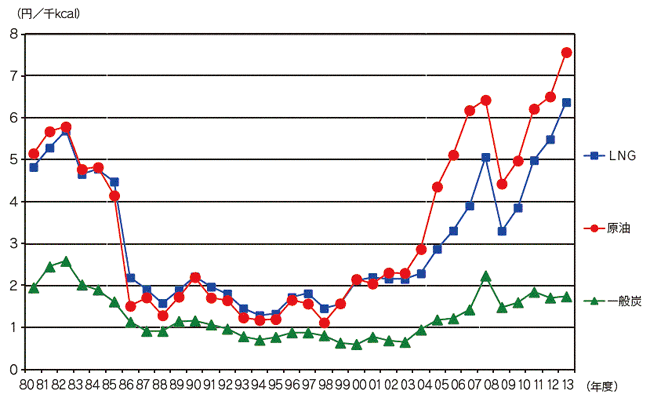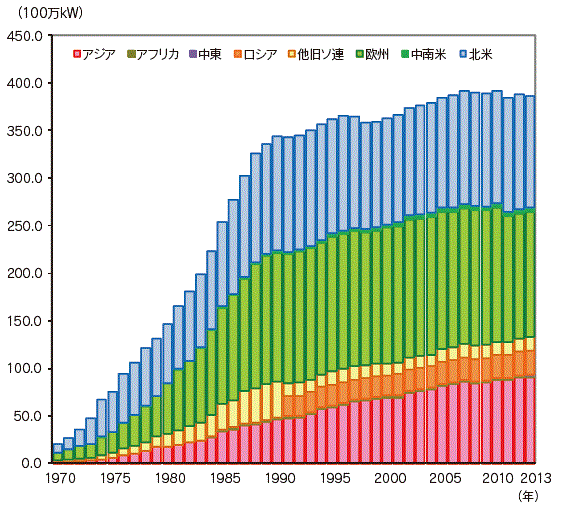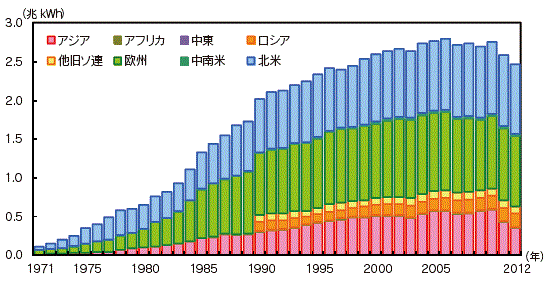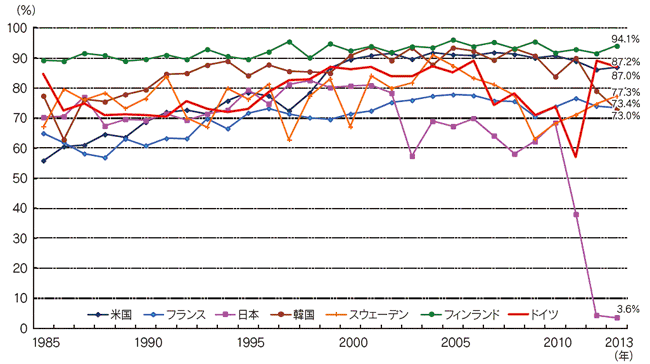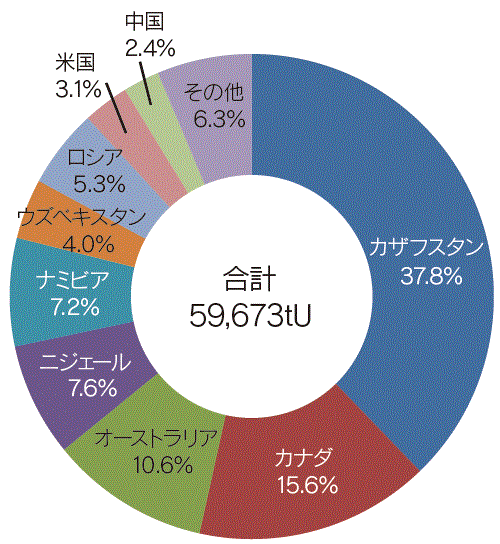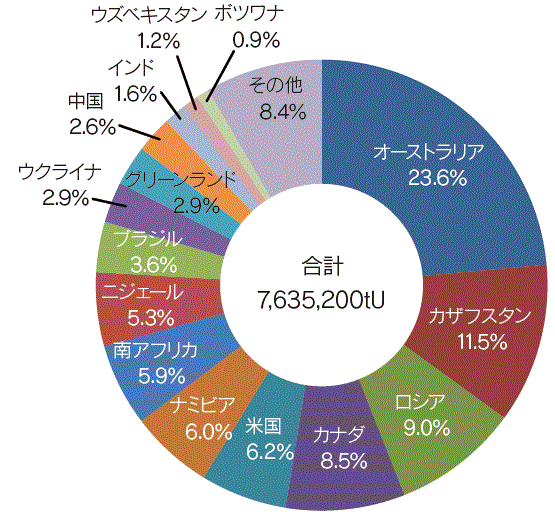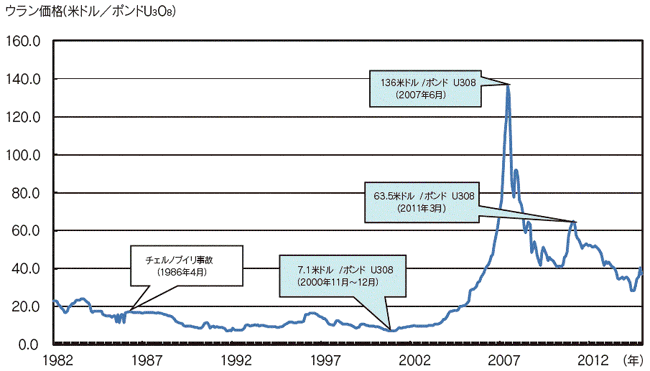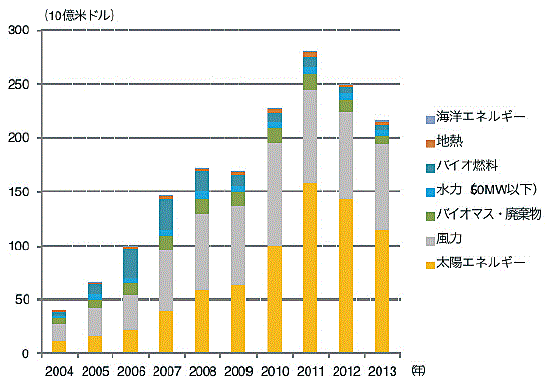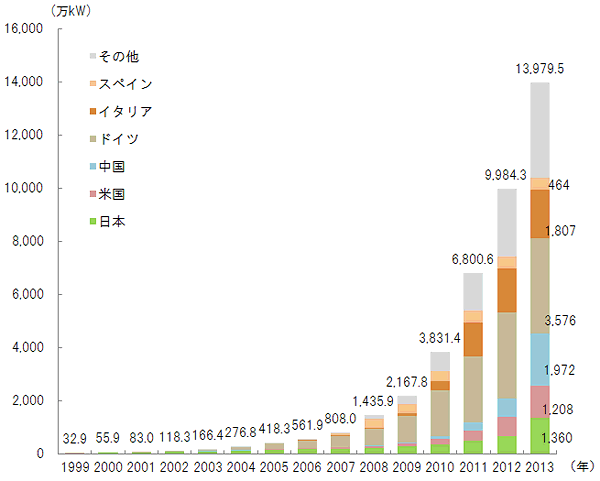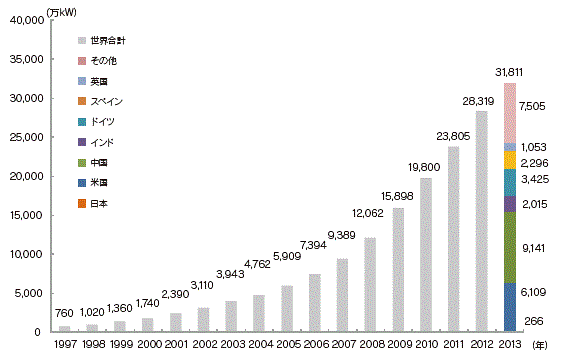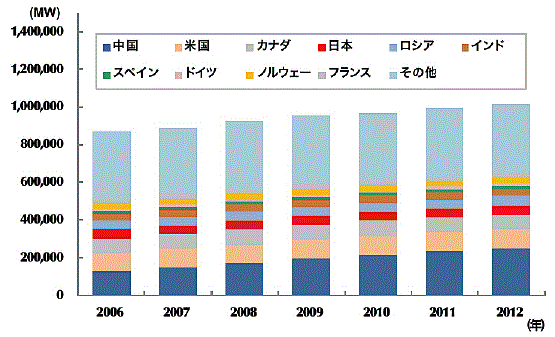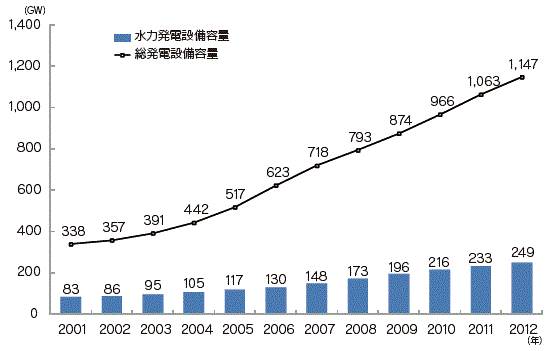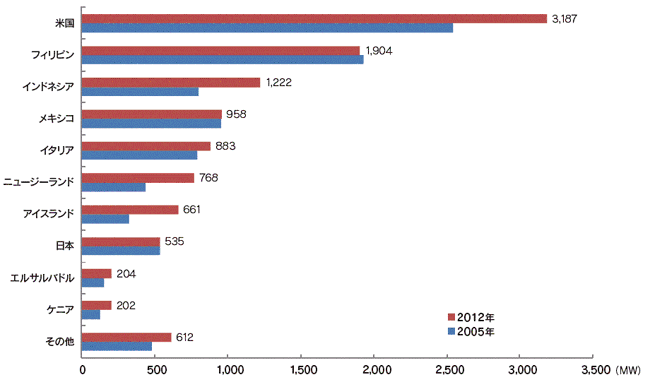第2節 一次エネルギーの動向
1.化石エネルギーの動向
(1)石油
①資源の分布
世界の石油確認埋蔵量は2013年末時点で1兆6,879億バレル(オイルサンドを除く)であり、これを2013年の石油生産量で除した可採年数は53.3年となりました。1970年代の石油ショック時には石油資源の枯渇問題も深刻に懸念されましたが、回収率の向上や追加的な石油資源の発見・確認によって、1980年代以降、可採年数はほぼ40年程度の水準を維持し続けてきました。最近では、ベネズエラやカナダにおける超重質油の埋蔵量が拡大していることもあり、可採年数はむしろ増加傾向にあります。
2013年末時点では、世界最大の確認埋蔵量を保有しているのはベネズエラであり、長らく1位の座を保っていたサウジアラビアは、2010年以降は2位となっています。ベネズエラの確認埋蔵量は2,983億バレルと世界全体の約18%のシェアを占めています。サウジアラビアの確認埋蔵量は2,659億バレルで世界シェアは約16%、以下、カナダ(1,743億バレル、シェア約10%)が3番目に大きく、その次はイラン(1,570億バレル、シェア約9%)、イラク(1,500億バレル、約9%)、クウェート(1,015億バレル、約6%)、アラブ首長国連邦(978億バレル、約6%)と中東産油国が続きます。中東諸国だけで、世界全体の原油確認埋蔵量の約半分を占めています(第222-1-1)。
- (出典)
- BP「Statistical Review of World Energy 2014」を基に作成
最近では、これまでの在来型の石油とは異なった生産手法を用いて生産されるシェールオイル(タイトオイル)に対する関心が高まってきています。2013年6月に米国のエネルギー省情報局(EIA)が発表した資料では、世界のシェールオイルの可採資源量は3,450億バレルと推定されており、主なシェールオイルの資源保有国は、ロシア、米国、中国などとなっています。(第222-1-2)。
【第222-1-2】EIAによるシェールオイル・シェールガス資源量評価マップ(2013年)
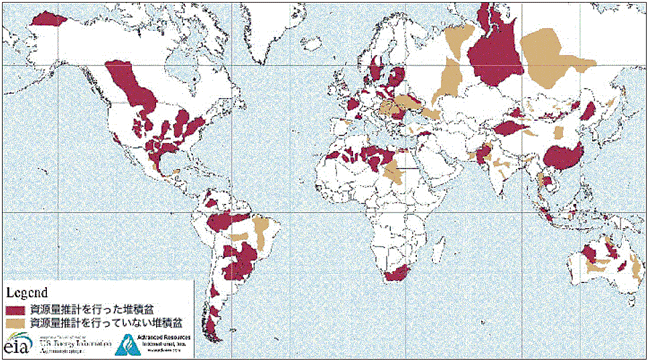
- (注)
- 「可採資源量」とは、技術的に生産することができる石油資源量を表したもので、経済性やその存在の確からしさなどを厳密に考慮していないという点で、「埋蔵量」よりは広い範囲の資源量を表す。
- (出典)
- EIA「Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources」(2013年6月)を基に作成
②原油生産の動向
世界の原油生産量は、石油消費の増大とともに増加し、1973年の5,846万バレル/日から2013年には8,681万バレル/日と、この40年間で約1.5倍になりました。地域別に見ると、2000年以降では欧州での減産が進む一方で、アジア大洋州とアフリカ、中南米の石油生産量はほぼ横ばいで、ロシア、中東、北米の生産量が堅調に伸びてきています(第222-1-3)。
OPEC産油国の生産は、1970年代までの大幅増産の後、高油価を背景に非OPEC産油国の生産が増加してきたことや、1980年代前半は世界の石油消費が低迷したことを受けて1980年代前半を通じて減少しましたが、その後1980年代後半からは緩やかに回復してきています。この結果、世界の原油生産に占めるOPEC産油国のシェアは、1970年代前半の5割強から1980年代半ばには3割を割り込んだものの、その後再び上昇し、2000年代以降は4割程度で安定的に推移しています。
非OPEC産油国全体(旧ソ連邦諸国、米国、メキシコ、カナダ、英国、ノルウェー、中国、マレーシア等)の生産は1965年以降、堅調に増加を続けており、1965年の1,788万バレル/日から、2013年には4,998万バレル/日に達しています。その増産の内訳は、年代によって異なっており、1970年代から1980年代にかけては、北米や中南米、旧ソ連邦がけん引し、1990年代はアフリカ、また2000年代に入ってからは再び旧ソ連邦地域の生産量が非OPEC産油国の増産を主導しています。最近では、シェール革命の進展で急速に生産量が増加しつつある米国の動向が注目されています。(第222-1-4)。
米国の生産量が近年、急速に伸びている最大の要因が、技術革新によってシェールオイルの生産量が伸びているためです。特に原油価格が高止まりを続けた2011年以降は、毎年100万バレル/日以上の生産量の増加が見られました。(第222-1-5)。
- (注)
- 1984年までのロシアには、その他旧ソ連邦諸国を含む。
- (出典)
- BP「Statistical Review of World Energy 2014」を基に作成
- (注)
- 上図の非OPECにはロシア及び旧ソ連邦諸国を含む。
- (出典)
- BP「Statistical Review of World Energy 2014」を基に作成
【第222-1-5】米国のシェールオイルの生産量
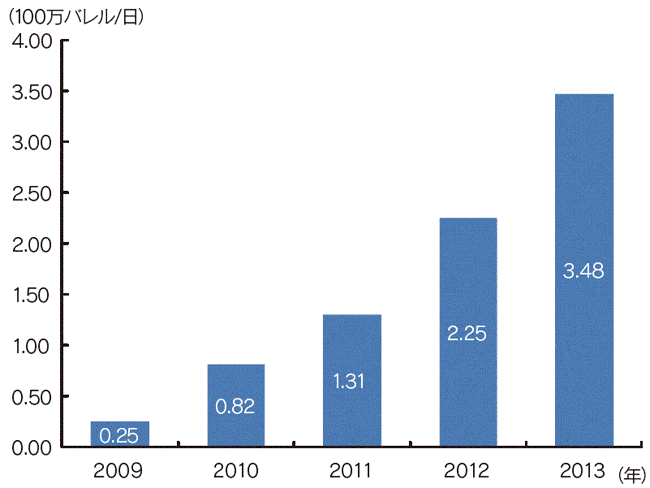
- (出典)
- 米国エネルギー情報局「Annual Energy Outlook」 2011年~2014年版を基に作成
③石油消費の動向
世界の石油消費は、経済活動の活発化とともに増加傾向をたどってきました。1973年には5,572万バレル/日であった世界の石油消費は2013年には9,133万バレル/日まで増加しました(年率平均1.3%増)。
先進国(OECD諸国)では、1973年の4,132万バレル/日の消費から1970年代後半にかけて増加傾向を示したものの、二度の石油ショック後の世界経済の低迷に加え、原子力、天然ガス等の石油代替エネルギー導入促進を受けて1980年代には石油消費が減少しました。その後、1980年代後半以降、経済の拡大とともに緩やかに石油消費が増加しましたが、近年の自動車燃費の改善や石油価格高騰を背景に、2005年以降は減少傾向を見せており、直近の2013年の需要も前年比0.4%減の4,556万バレル/日となりました。
一方、近年著しい石油消費の増加を示しているのが開発途上国(非OECD諸国)です。開発途上国の石油消費は堅調な経済成長に伴い、1973年の1,425万バレル/日から年平均3.0%で増加し、2013年には4,577万バレル/日となりました。その結果、世界の石油消費に占める開発途上国のシェアは1973年の26%から2013年には50%となり、逆に同期間内の先進国(OECD諸国)のシェアは74%から50%にまで低下してきました(第222-1-6)。
石油製品は様々な用途において利用されています。1970年代には産業用においても石油製品が使われており、1971年には産業用エネルギー需要の28%が石油でしたが、最近では天然ガスなどの他の燃料への代替が進み、2012年時点での石油のシェアは12%となっています。一方、輸送用と石油化学原料用の需要は堅調に伸びてきています(第222-1-7)。
- (出典)
- BP「Statistical Review of World Energy 2014」を基に作成
- (出典)
- IEA「Energy Balances of non-OECD Countries」(2014年版)を基に作成
④石油貿易の動向
世界の石油貿易は、石油消費の増加とともに着実に増大してきました。2013年の世界全体の石油貿易量は5,648万バレル/日となっており、そのうち日米欧3大市場による輸入量が合計で2,696万バレル/日と全体の48%を占めました。一方、輸出サイドで見ると、中東からの輸出量が1,960万バレル/日と最大で、全貿易量の35%を占めました。以下、ロシア及びその他旧ソ連邦諸国(905万バレル/日)、西アフリカ(446万バレル/日)、中南米(371万バレル/日)等が主要石油輸出地域となっています。
仕向地別では中東からの石油輸出のうち、10%(201万バレル/日)が米国向け、11%(207万バレル/日)が欧州向け、76%(1,491万バレル/日)がアジア大洋州地域向けとなっており、中東地域にとってアジア大洋州市場が最大の販路となっています(第222-1-8)。
なお、アジア地域の中東依存度は、その域内需要の増加に伴い、1990年代以降、常に欧米より大幅に高い水準で推移しています。
【第222-1-8】世界の石油の主な移動(2013年)
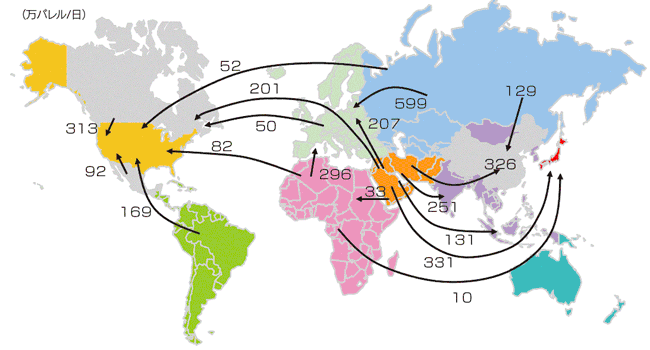
- (注)
- 上図の数値には石油製品の移動も含む。
- (出典)
- BP「Statistical Review of World Energy 2014」を基に作成
⑤原油価格の動向
国際原油価格は、これまでも大きな変動を繰り返してきました。最近では、2000年代の半ば以降、中国を始めとする新興国における石油需要が急速に増加したことを受け上昇を続けましたが、2008年に米国の大手証券会社の経営破たんを契機に発生した経済危機(リーマンショック)によって急速に下落しました。その後は、再び新興国を始めとする世界経済が回復を見せたこと、またサウジアラビアを始めとするOPEC産油国が協調減産を行ったことで、価格は上昇に転じ、2011年1月〜2014年6月までの月間平均価格は、ブレント原油で1バレル96ドルから125ドル、WTI原油で86ドルから110ドルの範囲で推移してきました(第222-1-9)。
2014年の夏以降は、高い原油価格によって米国のシェールオイルを始めとする非OPEC産油国の供給が増加していたこと、新興国経済の成長とその石油需要の伸びが鈍化し始めたこと、そうした状況によって発生した需給の緩和に対し、OPEC産油国が市場におけるシェア確保を重視したことで原油価格は再び急速に下落しています。
- (注)
- 図中価格の数字はWTIの数字
- (出典)
- BP「Statistical Review of World Energy 2014」を基に作成
(2)ガス体エネルギー
①天然ガス
(ア)資源の分布
世界の天然ガスの確認埋蔵量は、2013年末で約186兆㎥でした。中東のシェアが約43%と高く、欧州・ロシア及びその他旧ソ連邦諸国が約30.5%で続きました(第222-1-10)。
石油埋蔵量の約47.8%が中東に存在していることと比べますと、天然ガス埋蔵量の地域的な偏りは小さいと言えます。また、天然ガスの可採年数は2013年末時点で54.8年でした。
近年は、シェールガスや炭層メタンガス(CBM)といった非在来型天然ガスの開発が進展しており、特にシェールガスは大きな資源量が見込まれています。2013年7月に公表された米国エネルギー省情報局(EIA)の評価レポートによると、シェールガスの技術的回収可能資源量は、評価対象国合計で206.6兆㎥とされており、在来型天然ガスの確認埋蔵量よりも多いと推計されています。また、地域的な賦存では、北米以外にも、中国、アルゼンチン、アルジェリア等に多くのシェールガス資源が存在すると報告されています(第222-1-11)。
【第222-1-10】地域別天然ガス埋蔵量(2013年末)
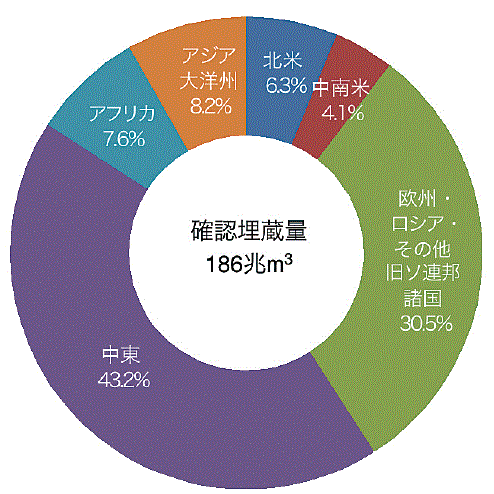
- (注)
- 端数処理の関係で合計が100%にならない場合がある。
- (出典)
- BP「 Statistical Review of World Energy 2014」を基に作成
【第222-1-11】EIAによるシェールオイル・シェールガス資源量評価マップ(2013年)【再掲】
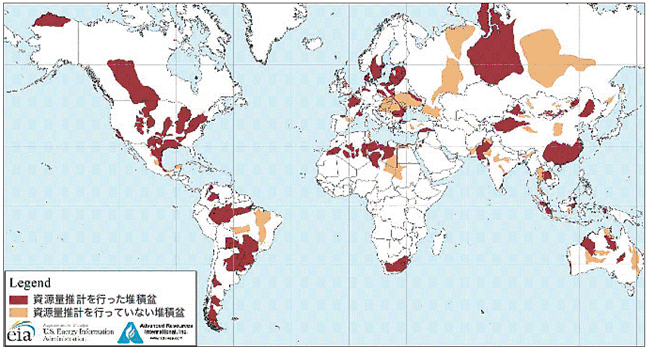
- (出典)
- EIA「Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources」(2013年6月)を基に作成
(イ)天然ガス生産の動向
2013年の天然ガス生産量は3.4兆㎥でした。2003年から2013年までの間で、石油の生産量の年平均伸び率が1.1%であったのに比べ、天然ガスは2.6%の伸びを記録しました。ただし、2009年の生産量は需要の減少に伴って若干落ち込みました。
地域別には、2013年時点では北米が世界の生産量の27%、欧州・ロシア及び旧ソ連邦諸国が31%を占めました(第222-1-12)。
中東の天然ガス埋蔵量は世界の43%を占めているにもかかわらず、その生産量は17%に過ぎません。これは、天然ガス輸送に莫大な投資が必要であることに加えて、中東ではこれまで石油開発投資が主に行われており、天然ガス開発投資は、その埋蔵量に比べ比較的少なかったことによります。したがって、中東から大消費地へのパイプラインが、ロシアと西欧間のように敷設されることもありませんでした。中東各国で生産された天然ガスの多くは中東地域内で消費され、残りは液化してLNGとして輸出されてきました。世界的な天然ガス消費の伸びに対応するため、欧米メジャー各社や産油国等による大規模な天然ガス資源開発が進められてきました。特に、LNG消費の伸びを背景に、LNGの新規プロジェクトが多数計画されています(第222-1-13)。
- (出典)
- BP「Statistical Review of World Energy 2014」を基に作成
【第222-1-13】世界の主要なLNGプロジェクト
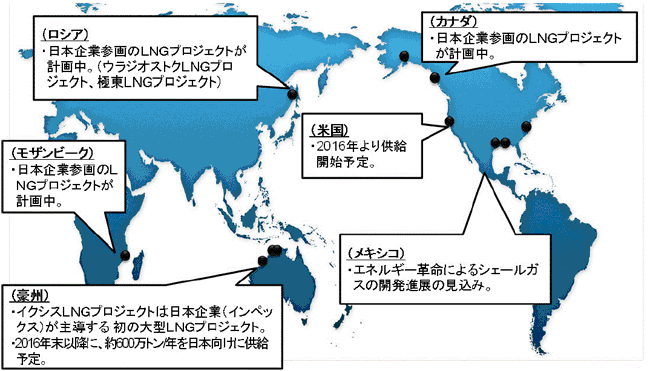
- (出典)
- 企業からのヒアリング等を基に作成
さらにGTL(Gas to Liquids)1やDME(Di-MethylEther)2等、天然ガスの新たな利用可能性を広げる技術について研究開発が進展しており、一部では既に商業生産が行われています。
また、世界各国でシェールガスやCBMの開発計画が立てられており、特に米国におけるシェールガス増産が顕著です。EIAは、2003年からCBMの生産量を、2007年からシェールガスの生産量を発表しており、それによるとCBMの生産量は2003年の53億㎥から2008年には572億㎥へと10倍に増加しましたが、それ以降減産し、2013年は404億㎥となっております。それに対して、シェールガスの生産量は2007年から右肩上がりに急増し、2013年には3,367億㎥に達しています(第222-1-14)。
- (出典)
- EIA「Natural Gas Data」を基に作成
(ウ)天然ガス消費の動向
天然ガス消費は北米、欧州・ロシア及びその他旧ソ連邦諸国で世界の60%を占めました(第222-1-15)。
- (出典)
- BP「Statistical Review of World Energy 2014」を基に作成
この理由としては、これらの地域内で豊富に天然ガスが生産されており、天然ガスの利用が進んでいること、既にパイプライン・インフラが整備されており、天然ガスを気体のまま大量に輸送して利用することが可能であることが挙げられます。アジアでは天然ガスの消費はまだ少ないですが、近年増大してきました。
2003〜2013年の間、世界の天然ガス消費は年率2.6%で増加してきました。2009年の需要は世界的な景気後退により若干減少しましたが、近年の消費増加の主な理由の一つとして、発電用燃料としての消費が伸びていることが挙げられます。これは、天然ガスは他の化石燃料に比べて環境負荷が低いこと、コンバインドサイクル発電3等の技術進歩により、発電燃料として天然ガスの経済的優位性が高まったこと等によります。
2012年の一次エネルギー総供給量に占める天然ガスの割合は、米国28%、OECD欧州24%に対して、日本もほぼ近い23%となっています。以前は、日本の一次エネルギー供給に占める天然ガスの比率は米国や欧州と比較して低いものでした。これは、欧米では自国もしくは周辺国で天然ガスが豊富に生産されるため天然ガスの利用が進んできた一方、我が国は、天然ガスの他のエネルギーに対する競争力が十分でないためでした。しかし、東日本大震災後に停止した原子力発電の多くを天然ガス火力発電で代替したことが影響し、2010年の17%から6ポイント上昇しました(第222-1-16)。
天然ガスの用途を見ても我が国と欧米とでは大きな差異があります。我が国では発電用としての利用の割合が全体の68%を占めており、産業用は8%、民生・その他用は24%に過ぎません。これに対して、米国、OECD欧州では発電用としての利用の割合がそれぞれ38%、31%と日本よりも低く、その分、民生・その他用や産業用としての利用の割合が高くなっています(第222-1-17)。
このように利用形態が異なっている主な理由としては、割高であった我が国の天然ガス輸入価格に加え、①LNG輸入という形態でしか天然ガスが導入できなかったこと、②このため、需要が集積しやすい発電用や一定規模以上の大手都市ガス会社による利用を中心に導入されたという経緯があります。この結果、天然ガスの需要がある地域にLNG基地が順次立地し、LNG基地から、需要に応じてパイプラインが徐々に延伸するという我が国特有のインフラ発展形態となりました。発電用と比べて需要が地理的に分散している民生用や産業用では、天然ガス利用は相対的に遅れています。
一方、欧米では、民生用と産業用への天然ガス利用が先に進みました。しかし、発電燃料としての天然ガスの優位性が高まっていることにより、近年、米国においても、発電用としての利用が増加しています(第222-1-17)。
【第222-1-16】日本・米国・OECD欧州の一次エネルギー構成(2012年)
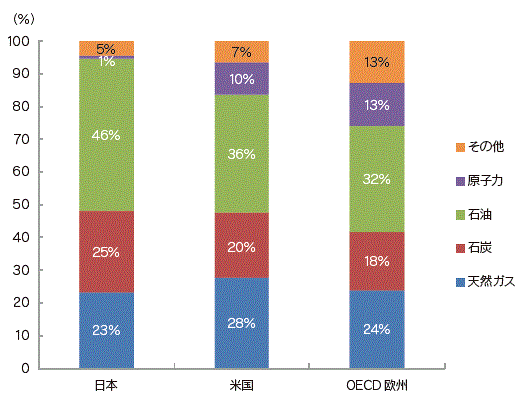
- (注)
- 端数処理の関係で合計が100%にならない場合がある。
- (出典)
- IEA「Energy Balances of OECD Countries 2014」を基に作成
【第222-1-17】日本・米国・OECD欧州における用途別天然ガス利用状況(2012年)
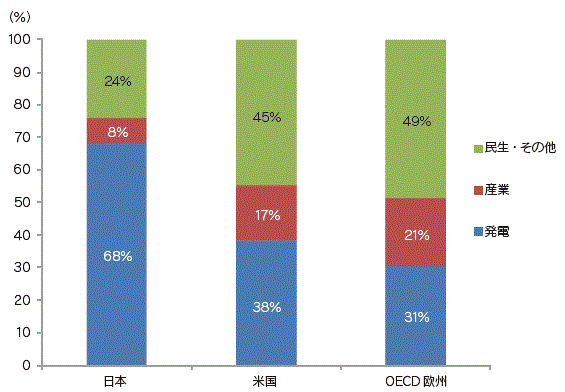
- (注)
- 端数処理の関係で合計が100%にならない場合がある。
- (出典)
- IEA「Energy Balances of OECD Countries 2014」を基に作成
(エ)天然ガス貿易の動向
2013年の一年間で取引された天然ガスの貿易量1兆395億㎥のうち、パイプラインにより取引された量は7,264億㎥(貿易量全体の70%)、LNGによる取引は3,131億㎥(同30%)でした(第222-1-18)。
2013年の世界全体の天然ガス生産量の30.7%が生産国では消費されずに、他国へ輸出されました(第222-1-19)。天然ガスの貿易量は増加しているものの、その割合は、生産量の64.2%が輸出される石油ほどではありませんでした。
主な輸入国は米国、欧州、北東アジアの3地域でした。輸送手段別には、パイプラインによる主な輸出国はロシア、カナダ等、輸入国は米国、ドイツ等でした。LNG貿易はアジア向け輸出を中心として拡大し、2013年のLNG貿易量の36.6%は日本向け(アジア全体で73.2%)でした。輸出国もアジア大洋州地域が中心ですが、近年、中東諸国からの輸出も増加してきました(第222-1-20)、(第222-1-21)。
また、米国ではこれまで天然ガス消費の伸びに対して、その主たる供給源である国内生産とカナダからのパイプラインガス輸入の伸びが追いついておらず、LNG輸入の計画が進められていました。しかし、探査・生産技術の進展により、これまでは開発が難しかった非在来型天然ガス(シェールガス)の生産が米国国内で急激に拡大してきました。これによって、米国の輸入量は減少しましたが、主としてアジア向けに多くのLNG輸出プロジェクトが計画されるようになっています。
- (出典)
- Cedigaz「Natural Gas in the World 2014」、 BP「Statistical Review of World Energy 2014」を基に作成
- (出典)
- BP「Statistical Review of World Energy 2014」を基に作成
【第222-1-20】世界の主な天然ガス貿易(2013年)
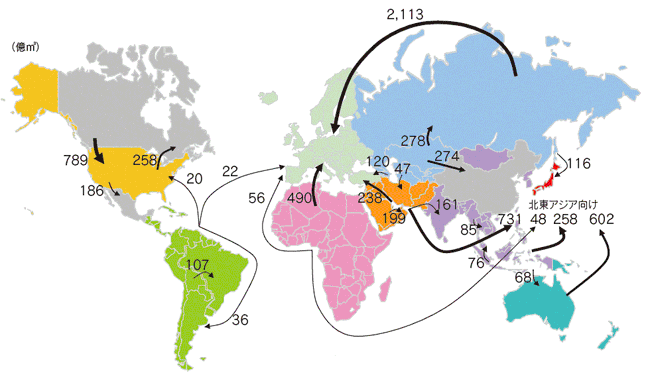
- (出典)
- Cedigaz「Natural Gas in the World 2014」、BP「Statistical Review of World Energy 2014」を基に作成
- (注)
- 再輸出分を含むため、第222-1-18に示す本文のLNG取引総量と一致しない。
- (出典)
- BP「Statistical Review of World Energy 2014」を基に作成
(オ)価格の動向
日本向けの天然ガス(LNG)価格(CIF)は、1990年代に、3 ~ 4ドル/百万BTUで推移していました。2000 〜2005年は4 ~ 6ドル/百万BTUで推移しましたが、その後は原油価格に連動して上昇し、2013年時点では、日本向けのLNG平均価格(CIF)は16.17ドル/百万BTUとなっており、米国国内の天然ガス価格3.71ドル/百万BTU(Henry Hub4スポット価格)や英国内の天然ガス価格10.63ドル/百万BTUと比べて割高でした(第222-1-22)。これは、日本向けのLNG価格が原油価格の水準を参照して決められるものが多く、原油価格の影響を大きく受けたためです。
なお、2013年のLNGのスポット及び短期取引の世界のLNG取引全体に占める割合は27%との報告があります(第222-1-23)。
- (出典)
- 財務省「貿易統計」、「ICE」(英ICEフューチャーズ)、「CME」(シカゴ・マーカンタイル取引所)等のデータを基に作成
【第222-1-23】世界のLNG取引全体に占めるスポット及び短期取引の割合(2013年)
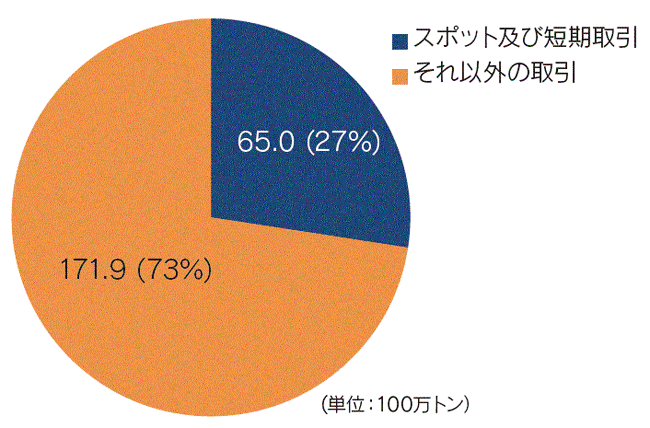
【第222-1-23】世界のLNG取引全体に占めるスポット及び短期取引の割合(2013年)(xls/xlsx形式:565KB)
- (注)
- スポット取引は1年未満の取引、短期取引は契約期間が4年未満の取引を指す。
- (出典)
- GIIGNL「The LNG Industry」を基に作成
②LPガス
(ア)生産の動向
2013年の世界のLPガス生産量は約2.8億トンで、2003年以降、年率2.7%のペースで増加しました。
このうち、ガス田及び油田の随伴ガスから60%、製油所から40%が生産されました。
地域別に見ると、2013年は中東に替わり北米が25.3%と最大のシェアを占めており、シェールオイル・シェールガス由来のLPガス生産量が増えています(第222-1-24)。今後はオーストラリアやロシア等で大型のLNGプロジェクトの稼働開始が計画されているため、それらのプロジェクトから生産されるLPガスも増加すると考えられます。
- (注)
- 端数処理の関係で合計が100%にならない場合がある。
- (出典)
- World LP Gas Association「Statistical Review of Global LP Gas 2014」を基に作成
(イ)消費の動向
2013年の世界のLPガス消費は約2.7億トンで、2003年以降年率2.4%のペースで増加してきました。
地域別に見ると、最大消費地域であるアジア大洋州地域が2003年の31%から、2013年には36%とシェアが上昇しました(第222-1-25)。
2013年の消費を用途別に見ると、家庭・業務用が46%、化学原料用が25%、工業用が11%、輸送用が10%となりました。さらに、これを地域別に見ると、中東地域と北米地域は化学原料用のシェアが一番高く(それぞれ63%と43%)、アジア大洋州地域では家庭・業務用のシェア(58%)が高くなりました(第222-1-26)。
- (出典)
- World LP Gas Association「Statistical Review of Global LP Gas 2014」を基に作成
- (出典)
- World LP Gas Association「Statistical Review of Global LP Gas 2014」を基に作成
(ウ)価格の動向
世界のLPガスの価格は、原油価格の動向に大きく影響を受けて形成されています。主要な価格を形成する市場地域としては、①米州(米国テキサス州のモント・ベルビュー市場を中核にした地域)、②欧州(北海のBP公定価格、及びアルジェリア・ソナトラック公定価格をベースにした北西欧・地中海等を中核にした地域)、③スエズ以東(サウジアラビア・アラムコの公定契約価格(CP)をベースにした中東・アジア大洋州地域を中核にした地域)の3つのゾーンに大別されています。それぞれの価格形成市場地域の価格差を埋めるように裁定取引が発生することにより、需給調整がなされています。
我が国のLPガス輸入指標となるサウジアラビアの公定契約価格は、ある程度スポット市場の値動きが反映されていますが、基本的にはサウジ側から一方的に通告される価格であり、我が国を含む消費国においては、価格決定プロセスの不透明性が指摘されてきました。ただし、シェールオイル及びシェールガス開発に伴って、今後米国でのLPガス増産が見込まれることから、サウジアラビアのLPガス価格支配力に変化が生じるのではないかとみられています。
原油価格の高騰とともに、3つのゾーンとも2000年から2008年7月までLPガス価格は上昇基調を続けてきました。その後、2008年12月には、プロパン価格(FOB価格5)が、サウジアラビア産(サウジアラムコCP)で340ドル/トン、北海産(ANSI)で296ドル/トンまで低下しました。原油価格が回復するにつれてLPガス価格も上昇しましたが、2014年1月以降再び価格低下に転じ2015年1月にはサウジアラムコCPは、425ドル/トンとなっています(第222-1-27)。
- (出典)
- 石油情報センター「LPG価格の動向」を基に作成
(エ)貿易の動向
最大の輸出地域は中東地域で、2013年には3,818万トンの輸出実績がありました。また、最大の輸出国はカタールで1,100万トンでした。中東地域に続く輸出地域は、欧州・ロシア及びその他旧ソ連邦諸国(1,912万トン)、アフリカ地域(1,065万トン)となりました。
一方、輸入面ではアジア地域が最大の輸入地域で、同年の輸入量は3,712万トンでした。アジア地域に続く輸入地域は、欧州・ロシア及びその他旧ソ連邦諸国で2,290万トンとなりました。最大の輸入国は我が国で輸入量は1,160万トン、続いてインド(615万トン)、韓国(571万トン)、米国(437万トン)、中国(421万トン)となりました。米国は世界最大のLPガス消費国ですが、自給率が高いため貿易量はそれほど多くありませんでした(第222-1-28)。
世界のLPガス貿易市場は、(ウ)価格の動向において既述のとおり、大きく3地域(米州地域、欧州地域、アジア地域)に分割されており、従来は、基本的にこの各域内で貿易取引が行われていました。しかし、1999年を境にそれまで余剰であったアジア市場が一転して不足状態となり、スエズ以西からLPガスが流入するようになりました。
- (出典)
- World LP Gas Association「Statistical Review of Global LP Gas 2014」を基に作成
(3)石炭
①資源の分布
石炭の可採埋蔵量は8,915億トンで、国別には、米国(26.6%)及びロシア(17.6%)、次いで中国(12.8%)に多く埋蔵されています(第222-1-29)。他方、石炭の炭種別には、瀝青炭と無煙炭が4,032億トン、亜瀝青炭と褐炭で4,883億トンです。
石炭の持つメリットとしては、石油、天然ガスに比べ地域的な偏りが少なく、世界に広く賦存していることが挙げられます。また、可採年数(可採埋蔵量/年産量)が113年(BP統計2014年版)と石油等のエネルギーよりも長いのも特徴です6。
- (注)
- BP統計では、World Energy Counc「il Survey of EnergyResources 2013」(2011年末のデータ)を引用。
- (出典)
- BP「Statistical Review of World Energy June 2014」を基に作成
②石炭生産の動向
世界の石炭生産は2000年代に入り、急速な拡大を遂げました。2003年から2013年の10年間で生産量は52億5,800万トンから78億2,282万トンと約25億6,500万トン拡大しましたが、その68%に相当する約17億4,800万トンは中国によるものでした。
2013年の石炭生産量を国別シェアで見ると、中国(約46%)と米国(約12%)の2か国で世界の生産量の半数以上となる約57%を占めました。さらに、インド、インドネシア、オーストラリア、ロシアまでの上位6か国の生産量を合計するとそのシェアは約81%でした。また、2013年において石炭生産量が1億トンを超える上位10か国(上述の6か国に、南アフリカ、ドイツ、ポーランド、カザフスタンを加える)のうち、2003年と2013年を比較して石炭生産量が減少しているのは米国、ドイツ、ポーランドの3か国で、他の7か国では増加しました。米国の生産量の減少はシェールガスの生産増加により天然ガス価格が低下し、その結果、電力分野での石炭消費が減少したことが一番の要因と考えられ、ドイツ、ポーランドの減少は国内消費が減少傾向にあるのに加え、国内炭より価格の安い輸入炭が増加傾向にあるためです(第222-1-30)。
- (注)
- 2013年データは見込み値。
- (出典)
- IEA「Coal Information 2014」を基に作成
石炭生産量が世界第1位の中国は1996年をピークに需要量が減少し、減産傾向にありましたが、これは中国政府が石炭需給バランスの確保と石炭価格の安定を目的に、小規模炭鉱を中心に違法な採掘を行っている炭鉱や赤字の炭鉱を閉山したためでした。しかし、2001年以降、電力分野を中心に急拡大する国内消費に応えるため、生産量を大幅に伸ばしています。第2位の米国は石炭を石油に次ぐ重要なエネルギーと位置付けてきており、2000年代前半までは石炭火力発電が発電電力量の50%以上を担ってきました。しかし、環境問題、天然ガス火力発電所の増加等により発電電力量に占める石炭火力発電の比率は次第に下がり、更には上述のとおり競合する天然ガス価格の急落によって2012年には一時期30%近くまで落ち込み、発電分野での石炭消費量は減少しました。その結果、石炭生産量も減少することとなりました。旧東ドイツでは、国産褐炭に一次エネルギーの約70%を依存していましたが、1990年の両ドイツ統合後、効率が悪く環境負荷の高い褐炭の生産量が減少しました。
インドネシアでは、国営炭鉱と採掘権を持つ中小炭鉱により、小規模な生産が行われていましたが、1980年代初めに生産分与方式が導入されたことにより炭鉱開発に外国資本が参入し、1990年代に入り生産と輸出が拡大してきました。2000年代に入り、我が国を始めとして、韓国、台湾、中国、インド等アジア域内各国・地域への石炭輸出を拡大し、2011年に世界最大の石炭輸出国になりました。
2013年の世界の石炭生産量(褐炭を含む)は78億2,282万トンと推計されていますが、このうち76%に相当する59億7,930万トンは発電用燃料や一般産業で利用される一般炭でした。一般炭の生産量は2000年代に入り急速に増加しました。コークス製造に用いられる原料炭も2000年代に入り生産量が倍増していますが、2013年における原料炭の生産量は総生産量の約13%に相当する10億346万トンでした。熱量が低く、生産地での発電燃料など用途の限られる褐炭は2000年代を通して生産量は8億トン台で推移しています(第222-1-31)。
- (注)
- 2013年データは見込み値。
- (出典)
- IEA「Coal Information 2014」を基に作成
③石炭消費の動向
2013年の世界の石炭消費量(褐炭を含む)は78億7,556万トンと推計されており(対前年比2.5%増)、そのうち、中国の消費量は総消費量の49%に相当する38億8,059万トンでした。つまり中国だけで世界のほぼ半分を消費していることになります。また、中国に米国、インド、ドイツ、ロシアを加えた5か国で世界の60%を消費しています。
2013年の石炭消費の国別シェアは、中国(49%)、米国(11%)の2か国で世界の石炭消費量の半数以上(60%)を占めました。中国は1990年代後半から2000年代初頭にかけて石炭消費量の伸びが停滞しましたが、それ以後、石炭消費量を急激に増加させ、2013年の消費量は38億8,059万トンまで増加しました。我が国の2013年の石炭消費量は1億9,559万トンで、インド、ロシア、ドイツ、南アフリカに続き世界第7位(褐炭を除くと中国、米国、インドに続き世界第4位)でした(第222-1-32)。
- (注)
- 2013年データは見込み値。
- (出典)
- IEA「Coal Information 2014」を基に作成
2012年の世界の石炭消費量を用途別にみると、発電用に62%、鉄鋼生産に用いるコークス製造用に11%、製紙・パルプや窯業を始めとする産業用に12%が消費されています(第222-1-33)。
- (注1)
- その他には誤差値が含まれる。
- (注2)
- 用途別の内訳は2012年までしか公表されていない。
- (出典)
- IEA「 Coal Information 2014」を基に作成
④石炭貿易の動向
2013年の世界の石炭輸出量(褐炭を含む)は13億3,330万トンと推計されました。インドネシアは2011年にオーストラリアを抜き世界最大の輸出国になり、2013年は世界の輸出量の32.0%を占めました。第2位のオーストラリアは世界の輸出量の25.2%を占め、次いでロシアが10.6%と続き、以下、米国、コロンビア、南アフリカの順となりました。この上位6か国で世界の石炭輸出量の87%を占めました(第222-1-34)。中国は2003年には世界第2位の輸出国でしたが、国内消費の急拡大により需給がひっ迫したことから2004年以降に輸出量が急減し、2013年の輸出量は731万トン(世界第14位)まで減少しました。
一般炭と原料炭の輸出量について見ると、2013年の一般炭輸出量は10億2,782万トン、原料炭輸出量は3億69万トンと推計されました。輸出国別では、インドネシアが一般炭の最大の輸出国で、世界の一般炭輸出量の39.5%を占め、次いでオーストラリアが17.7%、ロシアが11.4%、コロンビアが7.1%、南アフリカが7.6%と続きました。一方、原料炭の最大の輸出国はオーストラリアで、世界の原料炭輸出量の51.3%を占め、次いで米国19.8%、カナダ11.0%、ロシア7.2%と続き、これら4か国で全体の89%を占めました。
インドネシアからの輸出が急拡大している理由としては、石炭需要が拡大しているインドや東南アジア諸国、また中国や韓国など東アジアに地理的に近いこと、発熱量の低い石炭を安く購入できること等が挙げられます。一方、オーストラリアが多くの石炭を輸出している理由としては、高品質の石炭が豊富に賦存すること、石炭の生産地が積出港の近くにあること、鉄道や石炭ターミナルのインフラが他の輸出国と比較して整備されていることが挙げられます。
- (注)
- 【 第222-1-35】の輸入統計と本輸出統計では、出典データが異なるため合計値が一致しない。
- (出典)
- IEA「Coal Information 2014」を基に作成
一方、輸入国としては2011年には中国が日本を抜いて最大の輸入国になりました。2013年の中国の輸入量は3億2,722万トン(褐炭を含む世界の総石炭輸入量の24.0%)と推計されました。我が国の輸入量は1億9,559万トン(14.3%)、以下、インドが1億7,995万トン(13.2%)、韓国が1億2,651万トン(9.3%)、台湾6,804万トン(5.0%)と続きました(第222-1-35)。
近年、中国、インド等アジア諸国では電力消費の増加に伴い石炭火力発電所での石炭消費が増加し、2013年には日本、中国、韓国、インド、台湾の合計で8億9,731万トン(褐炭を含む世界の総石炭輸入量の65.7%)の輸入が推計されました。特に、石炭消費の拡大が著しい中国では、2009年に輸入量が1億トンを超え、輸入量が輸出量を上回る純輸入国に転じました。
一般炭と原料炭の別に2013年について輸入国を見ると、一般炭は中国が最大の輸入国で、以下、インド、日本、韓国と続きました。原料炭についても中国が最大の輸入国で、以下、日本、インド、韓国、ウクライナ、ブラジル、ドイツと続きました。
2013年の世界の主な石炭貿易フロー(褐炭を除く)を見ると、石炭が中国と我が国を中心とするアジア地域と欧州地域へ流れており、石炭市場はアジア市場と欧州市場の二つに大きく分かれていること
が分かります(第222-1-36)。
- (注)
- 【第222-1-34】の輸出統計と本輸入統計では、出典データが異なるため合計値が一致しない。
- (出典)
- IEA「Coal Information 2014」を基に作成
【第222-1-36】世界の主な石炭貿易(2013年見込み)
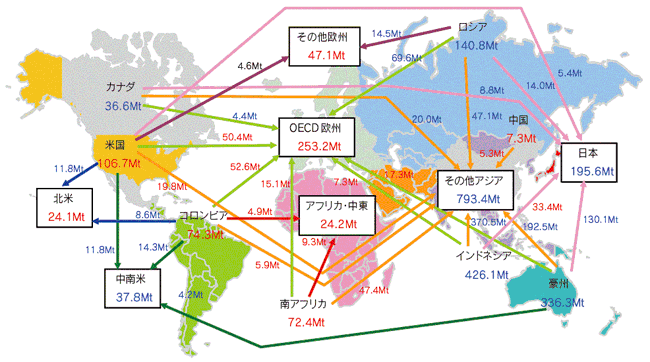
- (注)
- 褐炭を除く。400万トン未満のフローは記載しておらず、青字は対前年比増、赤字は対前年比減、黒字は増減なしを示している。輸入側の「北米」には、メキシコを含む。中国の輸入量は「その他アジア」に含む。
- (出典)
- IEA「Coal Information 2014」を基に作成
⑤石炭価格の推移
石炭取引における価格交渉では、いわゆるベンチマーク価格が、1980年代後半以降、世界的に参照価格として広く採用されてきました。これは最大の輸出国であるオーストラリアの石炭シッパー7と最大の輸入国である我が国の鉄鋼会社や電力会社との協議により決定される年間協定価格です。ベンチマーク価格方式では、代表的銘柄についてFOB価格を決め、その他の銘柄のFOB価格はベンチマーク価格を基準に品位の変動幅にスライドして決めていました(なお、一般炭については、熱量以外の品質差は基本的に加味しない、いわゆる熱量等価方式8でした)。
しかし、1996年度に入ると我が国の電力業界における規制緩和が一段と進んだため、電力事業者のコスト削減の一環として一般炭の競争入札が展開されるようになりました。その結果、一般炭のベンチマーク価格取引のウェイトは減少傾向に向かい始め、中部電力とオーストラリアの石炭シッパーの間で合意された1997年度価格が実質的に一般炭最後のベンチマーク価格となりました。1998年度以降、電力各社は各石炭シッパーと個別に交渉し、ベンチマーク価格に替わって独自の契約価格を設定するようになりました。
一方、原料炭は1996年度の価格交渉から、従来のベンチマーク方式からシッパー別、銘柄別に価格決定が行われることになり、さらに2001年度からは鉄鋼各社が各石炭シッパーと相対交渉するようになりました。
なお、1995年度までは、強粘結炭9についてはBHP社(現BHP Billiton Mitsubishi Alliance(BMA)社)のグニエラ炭の価格がベンチマークとされ、他銘柄もグニエラ炭の価格に合わせる仕組みでした。
2003年度以降は、いわゆるベンチマーク価格に代わり日本の電力向けの一般炭(長期契約ベース)FOB価格(以下、石炭価格については米ドル/トンをドルと表示する)がリファレンス価格として参考にされるようになりました。2003年夏以降の世界的な石炭需給ひっ迫を受け2003年末から一般炭スポット価格が急騰し、その後も高止まりしたことから、2004年度、2005年度と上昇しました。さらに2007年夏に世界最大の石炭輸出国であるオーストラリア、ニューサウスウェールズ州の石炭積出港を嵐が襲い、供給が滞ったことを発端に、スポット価格が上昇を続け、2008年度の価格は前年度を大幅に上回りました。2009年度の価格は一転して世界同時不況の影響を受け、前年度を大幅に下回りましたが、2010年度は経済情勢の回復を反映して、一般炭の価格は上昇に転じ、中国やインドが輸入を増やす中、2011年度には130ドルに迫る高値を記録しました。2012年度の価格は輸出国の供給力が増加しているのに対して、欧州の経済不安等から世界的に需要の伸びが鈍化し、値を戻しました。その後も石炭供給力が需要を上回る状況が続き、2013年度から2014年度にかけて価格は引き続き下落を続けています(第222-1-37)。従来、長期契約ベースの一般炭価格の改定は、日本の会計年度に合わせて4月を契約開始日として1年間の固定価格で契約(複数年契約では2年目以降4月に価格の改定を実施)されていました。しかし、2000年頃からサプライヤー、ユーザー双方にスポット価格の変動によるリスクを回避する意識が働き、契約開始日を4月ではなく、7月、10月、1月といったようにずらす契約を行うほか、ターム固定価格のみならず市場連動価格を盛り込むようになってきました。また1年契約、取引毎に価格を決めるスポット契約も行っています。
【第222-1-37】我が国の輸入炭FOB価格の推移
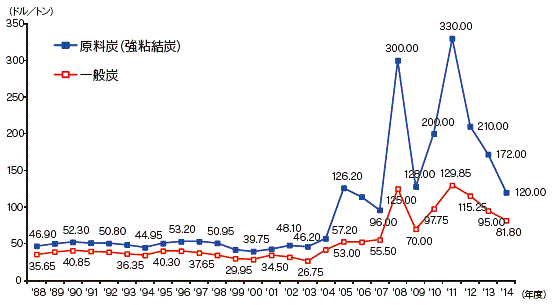
- (注)
- オーストラリア産日本向け長期契約ベースの石炭価格。
- 原料炭(強粘結炭):グニエラ炭などの強粘結炭の契約価格で代表させた。2010年度以降は年度始(各年4月)における改定価格。
- 一般炭:1997年度までがベンチマーク価格、1998年度から2002年度が参考価格、2003年度が東北電力(株)の長契更新価格、2004年度以降は電力各社の契約更新価格。
- (出典)
- 2005年度まではBarlow Jonker(現Energy Publishing Inc)「Coal 2005」、2006年度以降は各種情報を基に作成
一方、原料炭価格も世界的な石炭需給のひっ迫、豪州を襲った豪雨による影響を受け、2005年度、2008年度、2010年度、2011年度に急上昇しました。2008年度においては、2008年1月から2月にかけて原料炭の輸出地であるオーストラリアのクィーンズランド州を襲った記録的な集中豪雨による炭鉱の冠水等のために生産や出荷が滞り、前年度比で3倍以上となる300ドルまで急上昇しました。一般炭と同様に、2009年度は世界同時不況の影響を受けて大幅に下落しましたが、2010年度は経済情勢の回復を反映し、原料炭価格も上昇に転じました。2011年度はクィーンズランド州を再度記録的な集中豪雨が襲い生産や出荷が滞ったことと輸入需要の高まりを背景に300ドルを超える最高値を更新しました。しかし、欧州の経済不安、さらに中国、インドでの経済成長の減速等から世界的に原料炭需要が停滞したため、2012年度以降3年連続して価格の下落が続いており、2014年度は2009年度のレベルまで戻りました。なお、2010年度からはオーストラリアの原料炭シッパーの要望を受けて、長期契約ベースの原料炭価格を四半期ごとに見直すようになりました。
一般炭スポット価格は、市場原理に基づき決定され、ベンチマーク価格、その後の電力向け年度契約FOB価格を先行する形で推移してきました(第222-1-38)。なお、電力用以外の一般炭の取引では、年度契約あるいは取引毎に価格を取り決めるスポット契約が一般的です。
【第222-1-38】スポット価格とベンチマーク価格の関係
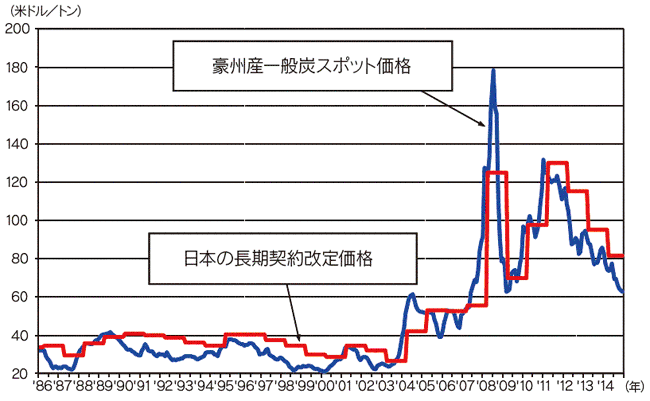
- (注)
- 長期契約改定価格:年度毎に更新されるオーストラリア産日本向け一般炭の長期契約をベースとしたFOB価格(4月改定価格)。豪州産一般炭スポット価格:Energy Publishing Incが集計・発表するオーストラリア・ニューカッスル港出し一般炭スポットFOB価格(NEX Spot Index)の月平均。
- (出典)
- Barlow Jonker(現Energy Publishing Inc)「Coal 2005」、「Australian Coal Report」等を基に作成
石炭の価格と他の化石エネルギーの価格を同一の発熱量(1,000kcal)当たりのCIF価格11で比較すると、石炭の価格が原油、LNG、LPガスの価格よりも低廉かつ安定的に推移していることが分かります(第222-1-39)。1980年代前半では石炭(一般炭)の価格優位性は非常に高いものでしたが、1986年度以降はその価格差が縮小しました。しかし、1999年度以降再び価格差は増大し、石炭の優位性が増してきました。また、2004年度以降、原油価格の上昇に合わせて他の化石エネルギーの価格も上昇していますが、発熱量当たりのCIF価格で比較すると、石炭の上昇幅は他の化石エネルギーよりも小さくなりました。2012年度は上述したように石炭価格が下落したことから発熱量当たりのCIF価格は低下しました。
- (出典)
- 日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧2015」を基に作成
2.非化石エネルギーの動向
(1)原子力
①世界の原子力発電の推移
1951年、世界初の原子力発電が米国で開始されて以来、二度の石油ショックを契機として世界各国で原子力発電の開発が積極的に進められてきましたが、1980年代後半からは世界的に原子力発電設備容量の伸びが低くなりました(第222-2-1)。
しかし、化石燃料資源の獲得を巡る国際競争の緩和や地球温暖化対策のため、特にアジア地域では、原子力発電設備容量が着実に増加してきました。2011年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて日本の原子力発電電力量が減ったため、アジア地域の原子力発電電力量は減少しています。(第222-2-2)。
一方、欧米地域においては、原子力発電所の新規建設が少ないものの、出力増強や設備利用率の向上によって、発電電力量は増加傾向となってきました。設備利用率で見ると、例えば、米国ではスリーマイル島事故後の自主的な安全性向上の取組によって官民による稼働率向上・出力向上の取組を進めた結果、近年では設備利用率9割前後で推移しています。逆に、東日本大震災後長期稼働停止している日本では設備利用率が下落しています(第222-2-3)。またエネルギー需要が急増する新興国を中心に、原子力発電所の導入もしくは増設の検討が進められています。
- (出典)
- 日本原子力産業協会「世界の原子力発電開発の動向2014年版」を基に作成
- (出典)
- IEA「Energy Balance 2014」を基に作成
- (出典)
- IAEA「Power Reactor Information System(PRIS)」を基に作成
②各国の現状
ここでは、各国・地域の現状について説明します(第222-2-4)。
【第222-2-4】各国・地域の現状一覧
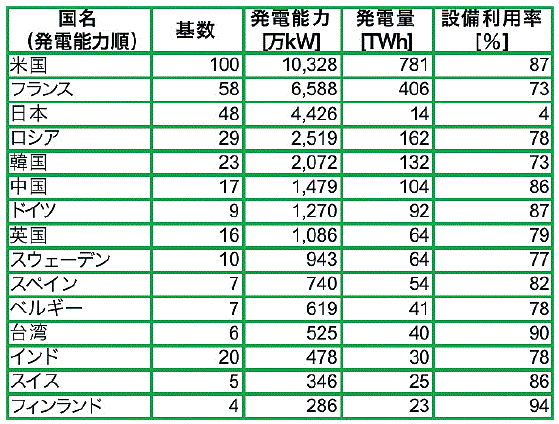
- (注)
- 基数・発電能力は2014年1月1日時点。発電量・設備利用率は2013年時点(年ベース)。
- (出典)
- 基数・発電能力:日本原子力産業協会「世界の原子力発電開発の動向2014年版」、発電量・設備利用率:IAEA「Power Reactor Information System(PRIS)」を基に作成
(ア)米国
米国では運転中の原子力発電所の基数が100基(合計出力1億328万kW)あり、その規模は世界一で、原子力発電により発電電力量の約19%を賄っていました(2013年)。また、平均設備利用率が87%(2013年)と順調な運転を続けてきました。2015年1月時点で7割程度の原子力発電所について、運転期間(認可)を60年とする延長が認められており、更に2割程度の原子力発電所について延長の申請が提出されています。さらに、エンタジー社、エクセロン社等が、小規模な原子力発電所所有会社のプラントを買収する等、原子力発電所所有会社の再編が急速に進んできました。
2005年8月に成立した、原子力発電所の新規建設を支援するプログラムを含む「2005年エネルギー政策法」に基づいて、建設遅延に対する政府保険、発電量に応じた一定の税額控除、政府による債務保証制度が整備されました。そのようなインセンティブ措置の導入を受け、原子力発電所の新規建設に向けて、2007 〜2014年現在に至るまで18件の建設・運転一体認可(COL)申請が米国原子力規制委員会(NRC)に提出されました(認可2件、審査中8件、審査一時停止6件、申請取下げ2件)。
東京電力福島第一原子力発電所事故直後の2011年3月14日、エネルギー省は、前月に発表した2012会計年度のエネルギー省予算のうち、原子力発電所新設支援のための融資保証枠360億ドルは変更しないと発表し、原子力政策の維持を表明しました。さらに3月30日にオバマ大統領はエネルギー政策に関する演説を行い、そこで原子力の重要性に言及しました。
この方針に沿って2012年2月9日にNRCはサザン社等によるジョージア州ボーグル発電所における新規原子炉建設計画の承認を決定し、同月13日にはエネルギー省が同計画への83億ドルの融資保証実施を決定しました。また、同年3月30日には、サウスカロライナ電力・ガス社等によるサウスカロライナ州V.C.サマー発電所に2基の原子炉を建設する計画がNRCにより承認されました。
他方で、米国内でシェールガス開発が進み天然ガス価格が下落している等の要因を含む経済性の観点から、原子力発電所の閉鎖も発表されています。2012年10月にはドミニオン社のキウォーニー原子力発電所、2013年2月にはデュークエナジー社のクリスタルリバー3号機、同年8月にはエンタジー社のバーモントヤンキー原子力発電所の閉鎖が発表されました。なお、サザンカリフォルニアエジソン社のサンオノフレ原子力発電所についても、停止中の原子炉の再稼働が見込めないことから、同年6月に閉鎖が決定されました。
(イ)欧州
(a)英国
英国では、16基の原子力発電所が運転中で、発電電力量の約20%を賄っています(2013年)。2007年7月、英国政府は、新しいエネルギー白書「EnergyWhite Paper: meeting the energy challenge」を発表し、この中で、原子力発電所の新規建設に向けた政策面での支援方針を表明しました。さらに2008年1月には、原子力発電所新規建設に向けた体制整備やスケジュール等を盛り込んだ原子力白書を発表しました。2011年7月には、英国下院において8か所の原子炉新設候補サイトが示された原子力に関する国家政策声明書が承認されました。2013年12月に成立したエネルギー法では、原子力発電への適用を含んだ差額決済方式を用いた低炭素発電電力の固定価格買取制度(FIT-CfD:Feed-in Tariff with Contracts for Difference)を実施することが規定されています。このFIT-CfDについては、EDFエナジー社のヒンクリー・ポイントCにおける原発新設案件への適用について、欧州委員会よりEUの国家補助(State Aid)規則に違反する可能性につき調査が行われましたが、2014年10月に同規則に違反しないとの判断が下されました。2015年1月現在、英国内ではEDFエナジー社のヒンクリー・ポイントC発電所計画及びサイズウェルC発電所計画、(株)日立製作所が100%出資するホライズン・ニュークリア・パワー社のウィルファ・ニューウィッド発電所計画及びオールドベリーB発電所計画、(株)東芝が60%出資することで合意したニュージェネレーション社のムーアサイド発電所計画等の新設計画が進められています。このうち、ヒンクリー・ポイントC発電所計画では、2013年10月に英国政府と事業者の間で、具体的な固定買取価格(ストライク・プライス)、中国資本を受け入れること等について合意に至ったことが発表されています。
(b)フランス
フランスは、原子力発電所の基数が58基と米国に次ぐ世界第2位の原子力発電規模を有しており、発電電力量の約74%を賄っていました(2013年)。発電設備が国内需要を上回っているという状況から、新規原子力発電所の建設は行われてきませんでした。しかし、2005年7月に制定された「エネルギー政策指針法」において、2015年頃までに既存原子力発電所の代替となる新規原子力発電所を利用可能とするため、原子力発電オプションの維持が明記されたこともあり、フランス電力公社(EDF)は2006年5月、新規原子力発電所としてフラマンビル3号機(EPR)を建設することを決定しました。EDFはこのフラマンビル3号機について、2007年12月に着工しました。東京電力福島第一原子力発電所事故後の2011年3月以降、原子力政策堅持の姿勢を崩しませんでした。2012年5月の大統領選挙で新たに就任したオランド大統領は、2025年には原子力比率を現状の75%から50%まで低減するといった公約を掲げました。2014年6月にはオランド大統領率いる社会党政権が、原子力発電の発電量について、2025年までに50%まで割合を引き下げ、現行の発電容量(63.2GW)を上限とする内容の「エネルギー転換法案」を発表しました。本法案は、2014年10月に下院で可決されましたが、上院においては、2025年までの原子力発電比率引き下げは困難であるとして、“2025年”という達成年限を“最終的に”との文言に置き換える修正と、原子力発電の発電容量の上限値を現状の発電容量に建設中のフラマンビル3号機の発電容量を含めた、64.85GWに引き上げる修正が可決されました。今後、両院の合同協議会における協議が開始される予定です。
(c)ドイツ
ドイツでは、2002年2月に成立した改正原子力法に基づき、当時運転中であった国内19基の原子炉を、2020年頃までに全廃する予定としていましたが、2009年9月の連邦議会総選挙において、「脱原子力政策」が見直され、2010年9月、原子力発電所の運転延長を認める法案が閣議決定され、電力会社は経営判断に基づき既設炉の運転延長を判断することができるようになりました。しかし、東京電力福島第一原子力発電所事故直後の2011年3月27日に行われた州議会選挙で、脱原子力発電を公約とした緑の党が躍進したことや、大都市で原子力発電所の運転停止を求めるデモが相次いだこと等により、連立政権も同年4月には脱原子力を推進する立場へと転換しました。その後、国内17基の原子炉を段階的に廃止し、再生可能エネルギーとエネルギー効率改善により代替していくための法案が、同年6月30日に下院で、7月8日に上院で可決し、7月31日の大統領署名を経て、8月1日から施行となりました。この政策変更により、8基の原子炉が即時閉鎖となりました(2011年においては、原子力発電所の基数が9基で発電電力量の約18%を賄っていました)。また、残り9基の原子炉については、2022年までに順次閉鎖されることになりました。
(d)その他の欧州
スウェーデンで10基(発電電力量の約43%)、スペインで7基(同20%)、ベルギーで7基(同52%)、チェコで6基(同33%)、スイスで5基(同38%)、フィンランドで4基(同33%)オランダで1基(同4%)の原子力発電所が運転中です(基数:2014年1月時点。発電力量シェア:2013年時点)。
このうちスウェーデンでは、1980年の国民投票の結果を踏まえて、原子力発電所を段階的に廃止することとされ、1997年には新設禁止を定めた原子力法が制定されました。それに基づき1999年12月にバーセベック1号機を、2005年5月に同2号機を閉鎖しました。しかしその後、原子力発電所廃止見直しの機運が高まり、2010年6月、新設禁止を定めた原子力法を改正し、国内10基の既設原子炉のリプレースを可能とする法案が議会で可決されました。これにより新規建設は法律上可能となりました。これまでは、電気事業者は既設発電所の出力向上に優先的に注力しており、正式な建設計画は提出されていませんでしたが、2012年7月、電気事業者よりリプレースのための調査を行うとの発表があり、規制当局に対してリプレース計画が申請されました。2014年10月に発足したローベン新首相率いる新政権では、長期的には電力の全てを再生可能エネルギーで賄うことを目指すという目標の下、原子力発電については安全性を強化し、廃棄物処分のための費用をより多く事業者が負担することを定めています。
ベルギーでは、2003年1月、脱原子力発電法が成立し、これに基づき、国内7基の原子炉は、建設から40年を経たものから順次閉鎖する予定となりました。一方2008年3月に発足した前・連立政権時には、専門家による検討を踏まえ、2009年10月に原子炉3基の運転期間を10年延長することを決定する等の動きも見られましたが、2011年10月末、新政権設立を目指す政党間で、2003年の脱原子力発電法の基本方針を踏襲すること、運転期間の10年延長は撤回されることで合意されました。2012年7月4日、ベルギー政府は建設から40年を経たものから順次閉鎖との基本方針を踏襲し、ドール1号機、2号機を2015年に廃炉にすることを決定する一方で、国内最古の原子力発電所の一つであるチアンジュ1号機については10年延長(2025年まで運転)することを決定しました。
チェコでは、2011年10月、CEZ社がテメリン原子力発電所の増設のための入札を開始し、東芝・ウエスチングハウス、ロスアトム、アレバの3社から入札を受けました。2014年4月、CEZ社は現状の制度の下では投資回収が見込めないことを理由に入札を中断しましたが、チェコは、引き続き2040年のエネルギー計画として原子力発電の割合を51%に拡充する方針を示しており、原子力推進のための包括的原子力計画の策定が進められています。
フィンランドでは、2003年12月、TVO社が同国5基目の原子炉としてアレバ社のEPR(160万kW級PWR)を選定し、オルキルオト3号機として2005年12月に着工しました(計画遅延により2018年以降運転開始の見込み)。2010年7月には、議会がTVO社とフェンノボイマ社の新規建設(各1基)を承認しました。それを受け、TVO社は、2012年3月にオルキルオト4号機建設の入札手続が開始され、2013年1月末にTVO社は5社(アレバ、GE日立、韓国水力原子力、三菱重工、東芝)から入札を受けました。また、フェンノボイマ社は2012年1月にピュハヨキ1号機建設の入札を行い、2013年12月、ロスアトム社が選ばれました。
リトアニアでは、2011年7月、ビサギナス原子力発電所の建設のために、日立が戦略的投資家(発電所建設の出資者)として優先交渉企業に選定されました。2012年10月には、国政選挙と併せて実施された国民投票で6割強が原発建設に反対し、政権も交代したためプロジェクトは停滞しましたが、2014年3月にはウクライナ情勢を受けてエネルギー安全保障への関心が高まり与野党間で再度プロジェクト推進の合意がなされました。2014年7月には、リトアニア・エネルギー省と日立の間で、事業会社の設立に向けたMOUが署名されました。
(ウ)アジア地域
(a)中国
中国では、17基の原子力発電所が運転中であり、発電電力量の約2%を原子力発電で賄っています(基数:2014年1月時点。発電力量シェア:2012年時点)。2007年の原子力発電中長期発展規則では、2020年までに40GWまで拡大する計画とされています。また、2011年3月に安全確保を前提条件としてより効率的な原子力開発を行う方針を示した「国民経済と社会発展第12次5か年計画」を採択しました。この全体計画に基づき、2013年1月には「エネルギー発展第12次5か年計画」が公表され、2020年の原子力発電所設備容量を58GW(2013年時点では15GW)とするとの目標が示されました。この目標は、2014年11月に公表された「エネルギー発展戦略行動計画2014-2020」にも引き継がれています。
(b)台湾
台湾では、6基の原子力発電所が運転中であり、発電電力量の約16%を原子力発電で賄っています(基数:2014年1月時点。発電力量シェア:2012年時点)。2005年の「全国エネルギー会議」では、既存の3か所のサイトでの原子力発電の運転と現在の建設プロジェクトの継続が確認されましたが、それ以降は原子力発電所の新規建設は行わず、既存炉が40年間運転した後、2018 ~ 2024年に廃炉するとの方針が示されました。東京電力福島第一原子力発電所事故後の2011年11月に明らかにされた原子力政策の方向性でも、その方針に変更はありません。2014年4月、野党や住民による原子力発電反対の声が高まったことを受け、政府は立法院国民大会において、現在の建設プロジェクトを凍結し、当該原子力発電所の稼働の可否については、必ず国民投票を通じて決定することを決議しました。
(c)韓国
韓国では、23基の原子力発電所が運転中であり、発電電力量の約26%を原子力発電で賄っています(基数:2014年1月時点。発電力量シェア:2013年時点)。また5基が建設中です。2014年1月、韓国政府は官民を交えた議論を経て、第2次国家エネルギー基本計画を閣議決定し、2035年の原子力発電比率を29%とすることが決定されました。同計画では、電力需要が年平均2.5%拡大すると想定されており、現在の原子力発電比率を維持するだけでも2,000万kW以上の新規建設が必要とされています。また、2014年1月には、新設2基の建設計画が承認されました。
(d)インド
インドでは、20基の原子力発電所が運転中であり、発電電力量の約3%を原子力発電で賄っています(基数:2014年1月時点。発電力量シェア:2012年時点)。電力需要が増大する中、原子力に対する期待が高まっています。2005年7月、米印両国政府は民生用原子力協力に関する合意に至り、2007年7月には両国間の民生用原子力協力に関する二国間協定交渉が実質合意に至りました。同協定は、原子力供給国グループ(Nuclear Suppliers Group: NSG)におけるインドへの原子力協力の例外化(インドによる核実験モラトリアム等の「約束と行動」を前提に、核不拡散条約未加盟のインドと例外的に原子力協力を行うこと)の決定や国際原子力機関(IAEA)による保障措置協定の承認、米印両国議会による承認等を経て、2008年10月に発効しました。この原子力供給国グループによる例外化の決定以来、インドは、米国の他、ロシア、フランス、カザフスタン、ナミビア、アルゼンチン、カナダ、英国、韓国といった国々と民生分野で原子力協力協定を締結しています。また、東京電力福島第一原子力発電所事故以降も、電力需給のひっ迫が続くインドでは、原子力発電の利用を拡大するとの方針に変化は見られません。
(エ)ロシア
ロシアでは1986年のチェルノブイリ原子力発電所(現在のウクライナに所在)事故以降、新規建設が途絶えていましたが、積極的に推進するようになり、2001年に新たな原子力発電所が運転を開始し、2015年5月現在34基を運転中であるとともに、9基を建設中です。
2011年3月、ロスアトム社キリエンコ総裁及びシュマトコ エネルギー大臣は、東京電力福島第一原子力発電所事故の如何に関わらず、原子力発電開発をスローダウンする意向はないと表明しています。
ロシア政府は、2007年に連邦原子力庁「ロスアトム」を国営公社ロスアトム社へ再編し、同社がロシアの原子力の平和利用と軍事利用及び安全保障を一体的に運営することになりました。この結果、ウラン探鉱・採掘、燃料加工、発電、国内外での原子炉建設等民生原子力利用に関して国が経営権を完全に握っていたアトムエネルゴプロムも、ロスアトム社の傘下に入ることとなりました。2009年11月に政府により承認された「2030年までを対象期間とする長期エネルギー戦略(2030年戦略)」では、原子力が総発電量に占めるシェアが2008年の16%弱から2030年には20%近くまで引き上げられ、発電量は2.2~ 2.7倍に増大することを想定しています。2014年1月、エネルギー省は「2035年までを対象期間とする長期エネルギー戦略(2035年戦略)」の草案を発表し、2015年1月現在も検討が続けられています。
③核燃料サイクルの現状
(ア)ウラン資源
ウラン資源は世界に広く分布しており、2013年時点では、カナダ、オーストラリア、カザフスタン等が埋蔵量、生産量ともに上位を占めています(第222-2-5、第222-2-6)。
- (出典)
- 世界原子力協会(WNA)ホームページ
- (注1)
- ウラン確認埋蔵量とは260米ドル/kgU以下のコストで回収可能な確認埋蔵量。
- (注2)
- 世界のウラン需要量は約10.96万トンU(2012年)。
- (出典)
- OECD/NEA-IAEA, 「URANIUM2014」を基に作成
ウラン価格(スポット価格)は、1970年代、特に第一次石油ショック後の原子力発電計画の拡大を受けて上昇しましたが、スリーマイル島事故、チェルノブイリ事故を受けて新規原子力発電建設が低迷したことから下落し、低価格で推移してきました。近年、ウラン価格は再び上昇を見せており、一時2007年には136ドル/lbU3O8まで上昇し、2011年3月時点でも60ドル/lbU3O8を超える高値となりました。これは解体核高濃縮ウランや民間在庫取り崩し等の二次供給の減少や、中国等によるウラン精鉱の大量購入等から需給ひっ迫が懸念され、世界的なウラン獲得競争が激化したことと、投機的資金の一部がウランスポット取引市場に流入したことに起因したと考えられています。東京電力福島第一原子力発電所事故後、若干の下落傾向を見せたものの、比較的安定した価格で推移しています(第222-2-7)。
- (出典)
- International Monetary Fund「IMF Primary Commodity Prices」を基に作成
(イ)ウラン濃縮
世界のウラン濃縮事業は、2014年時点で、ロシアのTENEX、フランスのアレバ、英国・オランダ・ドイツの共同事業体URENCO、米国のUSECの4社で90%以上のシェアを占めています。
我が国のウラン濃縮事業は遠心分離法を採用しており、その許可上の設備規模は、2014年時点で、年間1,050トンSWUでした。
(ウ)再処理
フランス及び英国では、自国内で発生する使用済燃料の再処理を実施するとともに、海外からの委託再処理も実施してきました。フランスAREVA NC社(旧COGEMA社)は、海外からの委託再処理を行うためのUP3(処理能力:1,000トン・ウラン/年、操業開始:1989年)及びフランス国内の使用済燃料の再処理を受け持つUP2-800(処理能力:1,000トン・ウラン/年、操業開始:1994年)の再処理工場をラ・アーグに有しています(ただし、UP3及びUP2-800における処理能力の合計は、1,700トンHM/年に制限されています)。
英国原子力廃止措置機関(NDA)はセラフィールド施設及び海外からの委託再処理を行うためTHORP(処理能力:900トン・ウラン/年、操業開始:1994年)の再処理工場をセラフィールドに有しています。
(エ)プルサーマル
海外では既に相当数の実績があり、1970年代からフランス、ドイツ、米国、スイスなどの9か国で、58基の発電プラントにおいて、MOX燃料の装荷体数で7,112体が使用されました。例えばフランスでは、3,738体、ドイツでは2,494体のMOX燃料が軽水炉で利用されました(2011年末現在)。また、MOX燃料加工施設は、フランス、ベルギー、英国で既に稼働しています。
(オ)高レベル放射性廃棄物の処分
海外の高レベル放射性廃棄物の処分については、各国の政策により、使用済燃料を直接処分する国と、使用済燃料の再処理を実施し、ガラス固化体として処分する国があります。高レベル放射性廃棄物は処分方法を決定している国としては、すべての国で深地層に処分する方針が採られており、処分の実施主体の設立、処分のための資金確保等の法制度が整備されるとともに、処分地の選定、必要な研究開発が積極的に進められてきました(第222-2-8)。
【第222-2-8】高レベル放射性廃棄物処分に関する状況
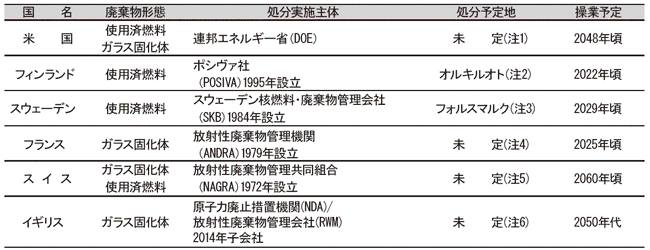
- (注1)
- 2002年7月に処分地として決定したが、現政権は計画を中止する方針。2013年1月、DOEは「使用済燃料及び高レベル放射性廃棄物の管理・処分戦略」を公表し、2048年までに地層処分場を操業開始する等の新たな処分戦略を策定している。
- (注2)
- 2001年5月に処分地として決定。
- (注3)
- SKB社が2011年3月に提出した使用済燃料処分場の立地・建設許可申請書に記載した建設予定地。今後の許可発給によって正式決定となる。
- (注4)
- ビュール地下研究所近傍より選定される予定。
- (注5)
- 処分場のサイト選定は、原子力令に従って策定された特別計画「地層処分場」に基づいて3段階で進められている(期間は2008年から2027年頃までを予定)。その第1段階として、2011年11月末に高レベル放射性廃棄物の処分場の「地質学的候補エリア」3か所が正式に選定された(低中レベル放射性廃棄物を合わせると計6か所)。引き続き、第2段階として「地質学的候補エリア」の絞り込みが行われており、NAGRAは2015年1月に「チューリッヒ北東部」と「ジュラ東部」を提案した。NAGRAはこれら2か所が低中レベル放射性廃棄物、高レベル放射性廃棄物の地層処分場のいずれにも適しているとしている。
- (注6)
- カンブリア州と同州内の2市がサイト選定プロセスへの関心表明を行っていたが、2013年1月にカンブリア州議会がサイト選定プロセスからの撤退を議決。2市の議会はプロセスへの継続参加に賛成していたが、州と市の両方のレベルでの合意を必要としていたため、1州2市はプロセスから撤退することとなった。2014年7月に、英国政府は地層処分施設の新たなサイト選定プロセス等を示した白書を公表。
- (出典)
- 資源エネルギー庁「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について(2015年版)」(2015年2月)を基に作成
(a)米国
1987年の放射性廃棄物政策修正法により、ネバダ州ユッカマウンテンが唯一の処分候補地として選定されました。米国エネルギー省(DOE)によって、処分場に適しているかどうかを判断するための調査が1988年から実施され、2001年に報告書がまとめられました。2002年には、エネルギー長官が大統領にユッカマウンテンを処分サイトとして推薦。大統領はこれを承認し、連邦議会に推薦しました。ネバダ州知事が連邦議会に不承認通知を提出しましたが、ユッカマウンテンを処分場に指定する立地承認決議案が連邦議会上院・下院で可決され、大統領がこれに署名して法律として成立することにより、ユッカマウンテンが処分地として選定されました。2008年6月にDOEは、2020年の処分場操業開始を目途とし、処分場の建設認可のための許認可申請書を原子力規制委員会(NRC)へ提出しました。
その後、2009年2月にオバマ政権が示した予算方針において、ユッカマウンテン関連予算は許認可手続のみに必要な程度に削減し、高レベル放射性廃棄物処分の新たな戦略を検討する方針が示されました。2010年3月、DOEは許認可申請の取下げ申請書をNRCに提出しましたが、NRCの原子力安全・許認可委員会(ASLB)は取下げを認めない決定を行いました。その後、NRCはASLBの決定が有効であるとした上で、2011年9月に、ユッカマウンテン処分場の建設認可に係る許認可申請書の審査手続について、一時停止することを指示しました。しかし、2013年8月、連邦控訴裁判所がNRCに対して許認可申請書の審査を再開するよう命じました。この連邦控訴裁判所の判決を受け、2013年11月にNRCは、安全性評価報告(SER)の完成等を優先して行うことを決定し、2015年1月までにSERの全5分冊を公表しています。高レベル放射性廃棄物処分を巡っては、2013年11月に連邦控訴裁判所からDOEに対して、放射性廃棄物基金への拠出金を実質的に徴収しないように命じる判決を下しており、エネルギー長官はこの判決を受けて、2014年1月に、放射性廃棄物基金への拠出金額をゼロに変更する提案を連邦議会に提出し、2014年5月に本提案が有効となりました。
また、DOEは、代替方策を検討するため、ブルーリボン委員会(米国の原子力の将来に関するブルーリボン委員会)を設置(2010年1月)して検討を行いました。本委員会においては、2012年1月に最終報告書が公表され、8つの勧告が示されました。2013年1月には、DOEが「使用済燃料及び高レベル放射性廃棄物の管理・処分戦略」を公表しており、ブルーリボン委員会の最終報告書で示された基本的な考え方に沿った実施可能な枠組みが示されています。具体的には、2021年までにパイロット規模の使用済燃料の中間貯蔵施設の操業を開始し、2025年までにより大規模な中間貯蔵施設を建設、2048年までに処分場を操業開始できるように処分場のサイト選定とサイト特性調査を進めるというものです。
(b)フィンランド
フィンランドでは、1983年よりサイト選定が開始され、1999年に処分実施主体であるポシヴァ社がオルキルオトを処分予定地として選定し、法律に基づく「原則決定」の申請書を政府に提出しました。2000年に地元が最終処分地の受け入れを承認し、その結果を受け、政府がオルキルオトを処分地とする原則決定を行い、翌2001年に国会が承認しました。2012年12月28日、ポシヴァ社は政府へ最終処分場の建設許可申請書を提出しました。放射線・原子力安全センター(STUK)は、建設許可申請書に係る安全審査を完了し、2015年2月11日に、キャニスタ封入施設及び地層処分を安全に建設することができるとする審査意見書を雇用経済省に提出しました。現在、政府による処分場の建設許可発給に向けて、雇用経済省による許可発給に関する検討が行われています。処分場の建設許可が発給された場合、次の段階として政府による操業許可の発給が必要となります。
(c)スウェーデン
スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(SKB社)が、1993年から公募及び申し入れにより8自治体を対象にフィージビリティ調査を行い、2000年11月にサイト調査の対象として3自治体(エストハンマル、オスカーシャム、ティーエルプ)を選定しました。このうち、サイト調査の実施について、自治体議会の承認が得られたエストハンマル自治体とオスカーシャム自治体でボーリング調査を含むサイト調査が行われました。その結果から、SKB社は、2009年6月に地質条件を主たる理由(①処分場深度の岩盤が乾燥しており亀裂がほとんどないこと、②処分場に必要となる地下空間が小さいことなど)としてエストハンマル自治体のフォルスマルクを最終処分場予定地として選定し、2011年3月に使用済燃料処分場の立地・建設の許可申請を行いました。この許可申請の際に提出された安全評価書「SR-Site」について、スウェーデン政府の要請に基づいて経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)が行った国際ピアレビューの報告書が2012年6月に公表されており、SKB社による処分場閉鎖後の安全評価は十分かつ信頼ができるとの見解が示されました。処分場の立地・建設の許可申請については、安全規制当局である放射線安全機関(SSM)が安全審査を行っているところであり、2017年に許可発給権をもつ政府に審査意見書を提出する予定です。
使用済燃料の集中貯蔵施設「CLAB」がオスカーシャム自治体にあり、SKB社が1985年から操業しています。SKB社は、使用済燃料の処分に向けて新たに建設するキャニスタ封入施設をCLABに併設してCLINKと呼ぶ一体の施設にする計画であり、CLINKと使用済燃料処分場の申請書の安全審査が並行して進められています。SKB社は2015年3月に、CLABにおける使用済燃料の貯蔵容量を、現行の8,000トンから11,000トンへ引き上げる追加の許可申請を行っています。
(d)フランス
フランスでは、1991年に「放射性廃棄物管理研究法」が制定され、地層処分、核種分離・変換、長期地上貯蔵の3つの高レベル放射性廃棄物に関する管理方法の研究が15年間を期限として実施されました。地層処分については、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)が、カロボ・オックスフォーディアン粘土層のあるビュールにおいて、2000年8月から立坑の掘削を開始して地下研究所を建設し、研究を行いました。法律に基づいて設置された国家評価委員会(CNE)は、2006年に3つの管理方法に関する研究成果を総合的に評価しました。これらを基に2006年6月には可逆性のある地層処分の実施に向けて「放射性廃棄物等管理計画法」が制定され、2015年に処分場の設置許可申請、2025年に処分場の操業を開始すること、設置許可申請は地下研究所による研究対象となった地層に限定することが定められました。ANDRAは、ビュール地下研究所周辺の250㎢の区域から30㎢の候補サイト区域を政府に提案し、2010年3月の政府の了承を経て、同区域の詳細調査を実施しました。2013年7月から翌年1月にかけて地層処分の設置に関する公開討論会及び市民会議が実施され、これらの総括報告書及び市民会議の見解書が、2014年2月に公開されました。この報告書等を受けて、ANDRAは地層処分場プロジェクトの継続に関する方針を決定し、2014年5月に今後のプロジェクト継続計画を公表しました。ANDRAはこの計画の中で2017年までに処分場の設置許可申請を提出し、当初の目標である2025年の操業開始を維持することを検討しています。
(2)再生可能エネルギー
再生可能エネルギーの利用拡大は、近年多くの国・地域が取り組んでいます。再生可能エネルギーの促進策については、研究開発・実証、設備導入補助のほか、日本でも実施されている固定価格買取制度(FIT:Feed-in-Tariff)や、再生可能エネルギー導入量割当制度(RPS:Renewables Portfolio Standards)が多くの国で導入されています。一般的に、FITは優遇的な買取価格を設定する施策であり、RPSは政府が義務的な導入量を事業者に割り当てる施策で、大規模発電はRPS、小規模発電はFITといった形で、両制度を併せて実施するケースもあります(第222-2-9)。
こうした施策を通じ、再生可能エネルギーへの投資は2000年代半ば以降飛躍的に増大し、2011年には約2,800億米ドルにのぼる投資が行われました。エネルギー源別に見ると、近年の投資は太陽エネルギー及び風力に集中しています。近年は、特に太陽光発電に対するFITの買取費用がかさみ電力料金の上昇をもたらす等の課題が顕在化していることから、促進策の抜本的な見直しに着手する国も出ています。こうしたことを受けて、投資が鈍化する傾向も見られます(第222-2-10)。
【第222-2-9】主要国・地域の再生可能エネルギー促進施策の導入状況
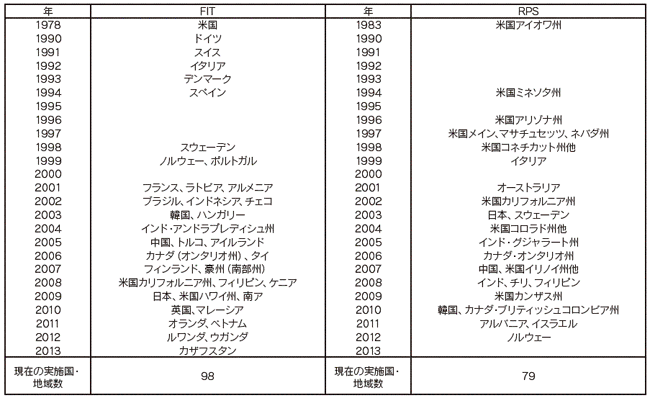
- (注)
- 廃止例を含む。
- (出典)
- REN21「Renewables 2014 Global Status Report」を基に作成
- (出典)
- REN21「Renewables 2014 Global Status Report」を基に作成
①太陽光発電
世界の主要国における太陽光発電の導入量は2000年代後半から増加が加速し、2013年の累積導入量は約1.4億kWに達しました13。導入の拡大は、2000年前後に欧州で導入された固定価格買取制度(FIT)による効果が大きく、太陽光発電の買取価格が高額に設定されたこと等によりドイツ、イタリア、スペイン等で顕著な伸びを示しました。日本でもFITが2012年7月に導入されたことにより、導入が大幅に拡大しました。IEA諸国を中心に太陽光発電市場が大きく拡大したことで、太陽光発電の導入コストが低下し、近年は中国を始めとする新興諸国にも導入が広がっています。2013年の累積導入量で見ると、世界第1位ドイツ(3,576万kW)、第2位中国(1,972万kW)、第3位イタリア(1,807万kW)となっており、日本はこれに次いで第4位(1,360万kW)となっています(第222-2-11)。
- (出典)
- IEA 「PVPS TRENDS 2014」を基に作成
こうした太陽光発電の導入拡大の経済的な波及効果として雇用創出等が期待されますが、他方で、FITによる買取費用は最終的に消費者に転嫁される仕組みとなっていることから、費用負担の増大も懸念されています。ドイツでは、電気料金に課金されるFITの費用は、2015年はkWh当たり6.17ユーロセントとされ、標準家庭における月額負担は約3,030円と推計されます。
②風力発電
世界の風力発電設備容量は近年急速に増加し、3億1,810万kW(2013年)に達しました(第222-2-12)
- (出典)
- Global Wind Energy Council(GWEC)資料を基に作成
2013年時点で導入量が最も多いのは中国で、世界の28.7%を占め、次いで米国(19.22%)、ドイツ(10.8%)となっています。これら3か国で世界の風力発電設備容量の約6割を占めています。
また近年は、洋上風力発電の市場も急速に拡大しています。ただし、現時点では世界の洋上風力発電の90%が欧州北部の沖合(北海、バルト海、アイルランド沖、イギリス海峡等)に集中しています。2012年までに世界で合計542万kWが設置されています。とりわけ、洋上風力に注力しているのは英国で、累積導入量の54.4%を占めています。この他に、中国は2015年中に洋上風力発電を500万kW導入する計画を掲げており、事業入札を開始する等しています。
③バイオマス
バイオマスは、発電燃料としての利用の他、輸送用燃料としても用いられています。また、開発途上国のバイオマス利用には薪や炭といったものが含まれています。これらの国では、経済の成長に伴って灯油、電気、都市ガスといった商業的に供給されるエネルギーの利用が増え、バイオマスの比率は低下することが考えられます。世界全体では、2012年時点で一次エネルギー総供給の約10%と大きな割合を占め、先進国(OECD諸国)平均では4.8%、開発途上国(非OECD諸国)平均では13.6%となっています。米国や欧州等の先進国では、気候変動問題への対応といった観点からバイオマス導入を政策的に推進する国が多くなってきました。(第222-2-13)。
【第222-2-13】世界各地域のバイオマス利用状況(2012 年)
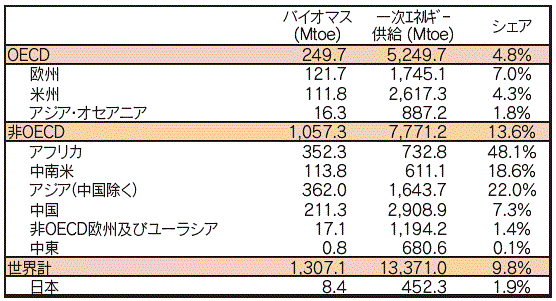
- (注)
- 中国の値は香港を含む。
- (出典)
- IEA「Extended Energy Balances of OECD Countries 2014」及び「Extended Energy Balances of Non-OECD Countries 2014」を基に作成
利用拡大という面では、特に交通部門における石油依存の軽減及び、温室効果ガス排出の抑制を目指した政策が打ち出されています。例えばEUでは、2020年までに交通部門における燃料利用のうち10%程度をバイオ燃料(及び再生可能エネルギー利用電気等)とする目標を掲げました。しかしながら、バイオ燃料の主たる原料は、サトウキビやトウモロコシといった食料であるため、バイオ燃料利用の急激な増大は、食料価格の高騰など、深刻な影響を与える可能性が指摘されました。さらに、バイオ燃料生産のために、森林や熱帯雨林を伐採して耕地とする動きが拡大しかねないとの見方もありました。このため、バイオ燃料の生産・消費による自然環境や食料市場への影響を抑えるための持続可能性基準(LCAでの温室効果ガス削減効果等)の策定や国際会議での検討が進められてきました。また、食料以外の原料(稲わらや木材等のセルロース系原料、藻類等)を用いたバイオ燃料開発への取組が進められてきました。近年は、世界の石油メジャーも次世代バイオ燃料の開発に力を入れており、米国のシェブロン等が藻類のバイオ燃料開発に関するベンチャー企業に投資する等の活動を行っています。
④水力
世界の水力発電設備は2012年時点でおよそ10.1億kWであり、世界の総発電設備の約2割を占めています。水力による発電設備が最も多い国は中国で、世界の水力発電設備容量の67.7%を占めています。国内の総発電設備に対する割合は、中国は約22%、日本は約17%、米国は8.5%等となっていますが、ノルウェーのように、約94%(2011年)と極めて高いシェアを持つ国もあります(第222-2-14)。
- (注)
- カナダ、インド及びノルウェーは2011年が最新の値であるため、2012年は2011年の値を代用。
- (出典)
- 海外電力調査会「海外電気事業統計」2008年版~ 2014年版を基に作成
先進国においては、大規模ダム開発は頭打ちとなっている一方、中国では、水力発電の設備容量は過去10年間で約3倍程度に増大しました(第222-2-15)。中国の揚子江中流(湖北省)に建設された三峡ダム発電所は2009年2月に完成し、世界最大規模の水力発電所(2,250万kW)となっています。
- (出典)
- 海外電力調査会「海外電気事業統計2014年版」を基に作成
⑤地熱
地熱による発電は、世界で1,122.4万kWが導入されてきました(2012年)。設備容量が最も大きいのは米国で、合計318.7万kWが設置されました。次に高い設備容量を有するのがフィリピンで、国内の発電設備総量(2011年)の14.4%を占めました。インドネシア、ニュージーランド及びアイスランドでは、2005年以降、設備容量が大幅に増大しました(第222-2-16)。また、アイスランド及びグアテマラでは、国内の発電設備に占める地熱発電の割合が2割以上となりました。日本ではおよそ50万kWが設置されましたが、過去5年間の設備容量はほとんど変化していません。一方、欧州では地熱を利用できる地域が少なく、イタリアやポルトガルの一部等に限られています。
- (出典)
- 国際地熱協会(International Geothermal Association)
- 1
- GTL(Gas to Liquid)とは、天然ガスを化学反応によって常温で液体の炭化水素製品に転換したものを指します。主に輸送用の燃料として用いられます。
- 2
- DME(Di-Methyl Ether)とは、GTL同様、天然ガスを原料として生産される炭化水素製品ですが、常温では気体です。ただし、比較的低い圧力で液化するので液化石油ガ ス(LPG)などと同様に扱われます。現在はスプレー用のガスとして用いられることが多いですが、今後輸送用の燃料としても用いられることが期待されてい ます。
- 3
- コンバインドサイクル発電とは、ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせた発電方式です。
- 4
- 米国国内のガス取引価格の指標となっている、ルイジアナ州にある天然ガスのパイプラインの接続地点(ハブ)の呼び名。ヘンリーハブ価格を元に日本のLNG輸入価格との比較を行う場合には、天然ガスの液化・再ガス化コストやLNG船舶輸送コスト等を考慮する必要がある。
- 5
- Free On Board価格の略称で積地引渡し価格を指します。
- 6
- 石炭の根源植物が石炭に変質する過程を一般に石炭化作用と呼び、この進行度合を石炭化度と言います。石炭は、石炭化度により無煙炭、瀝青炭、亜瀝青炭、褐炭、亜炭、泥炭に分類されますが、日本では一般に無煙炭から褐炭までを石炭と呼んでいます。
- 7
- 石炭シッパー:石炭出荷主のこと。
- 8
- 熱量等価方式:基準とする発熱量の一般炭の価格をベースに、取り引きされる一般炭の発熱量に応じて、その価格を定める。
- 9
- 強粘結炭:強固なコークスを作る際に必要な石炭。原料炭の一種。
- 11
- CIF価格:CIFは、Cost, Insurance and Freightの略。積荷である石炭の積出し地での価格に、運賃や船荷保険料を加えた価格。
- 12
- U3O8(三酸化ウラン):ウラン鉱石を精錬したもので、ウラン精鉱。イエローケーキとも呼ばれる。
- 13
- IEA「 PVPS TRENDS 2014」による。