第3節 2050年カーボンニュートラルに向けた我が国の課題と取組
1. 2050年カーボンニュートラル宣言と現状の評価
菅内閣総理大臣は2020年10月26日の所信表明演説において、我が国が2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。加えて、2021年4月には、菅内閣総理大臣は、地球温暖化対策推進本部及び米国主催の気候サミットにおいて、「2050年目標と整合的で、野心的な目標として、2030年度に、温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す。さらに、50%の高みに向けて、挑戦を続けていく」ことを表明しました。
日本が排出する温室効果ガスのうち約9割がCO2であり、CO2の排出量の約4割が電力部門、残りの約6割が産業や運輸、家庭などの非電力部門からの排出となっています(第123-1-1)。ここでは、電力部門と非電力部門に分けて、現状とカーボンニュートラルに向けた課題について整理します。
【第123-1-1】世界の温室効果ガス排出量(2018年)
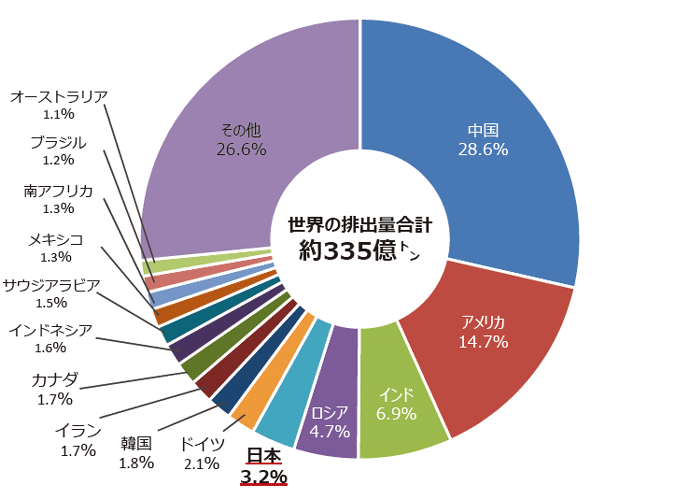
【第123-1-1】世界の温室効果ガス排出量(2018年)(ppt/pptx形式:71KB)
- 出典:
- 国立環境研究所「温室効果ガスインベントリオフィス」より経済産業省作成
【第123-1-2】日本の部門別のCO2排出量(2019年度)
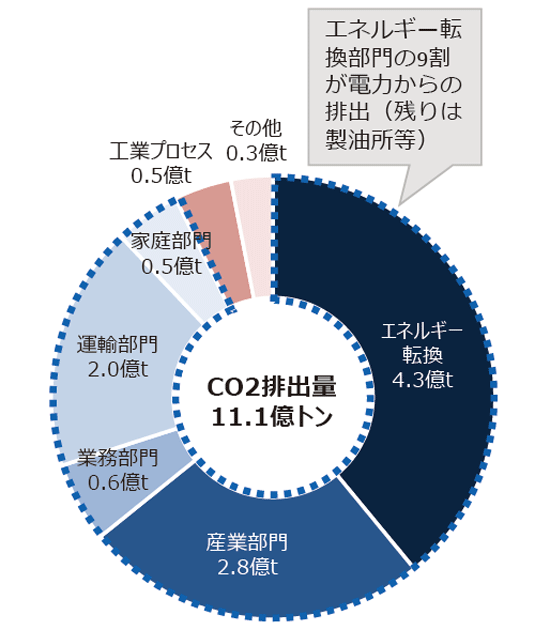
【第123-1-2】日本の部門別のCO2排出量(2019年度)(ppt/pptx形式:47KB)
- 出典:
- 国立環境研究所「温室効果ガスインベントリオフィス」より経済産業省作成
(1)電力部門の現状
電力部門のCO2排出量の大半を占めるのが火力発電所からのCO2排出であり、2050年までにカーボンニュートラルを実現するためには、火力発電所からのCO2排出量を削減していく必要があります。
火力発電はCO2を多く排出しますが、一方で、太陽光発電や風力発電など出力が変動する再生可能エネルギーの導入拡大を支える機能も持っています。太陽光発電や風力発電は、①天候等の自然条件によって出力が変動する、②日照量や風況などの適地と電力の需要地が必ずしも一致しておらず、送電網の整備が必要であること、③災害等により電源が脱落した際の系統の安定性を保つ機能(慣性力等)を有していないこと、④自然制約(太陽光発電に適した平地や風力発電に適した遠浅の海などが我が国は少ないこと)や社会制約(農業や漁業等の他の利用との調和や地域との調整が必要であること)がある中での案件形成、⑤以上の諸課題を克服していくために大規模な投資が必要であり、適地不足により今後コストが上昇するおそれがある等の課題があります31。こうした課題に対して、火力発電は、①安定して大きな供給力持ち、②電力の需要と、太陽光発電や風力発電等により変動する電力供給を一致させる上での重要な調整力(需要に合わせて供給量を調整できること)であること、③系統で突発的なトラブルで生じた場合でも、周波数を維持し、ブラックアウトを防ぐなど、重要な役割を果たしています32(第123-1-4)。今後、脱炭素電源、特に再生可能エネルギーを主力電源化していく中で、火力発電が担ってきた役割を、水素・アンモニア等のCO2フリー電源、CO2の貯留・利用(CCUS)、蓄電池等の技術を組み合わせながら代替していく必要があります。
【第123-1-3】電源別のライフサイクルCO2排出量の比較
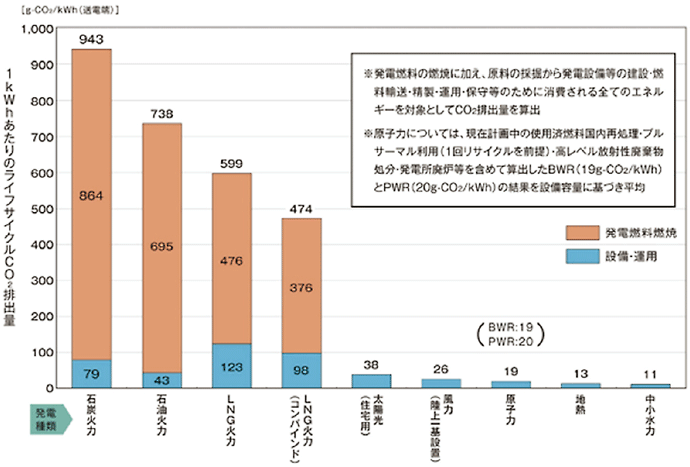
【第123-1-3】電源別のライフサイクルCO2排出量の比較(ppt/pptx形式:146KB)
- 出典:
- 一般財団法人電力中央研究所「日本における発電技術のライフサイクルCO2排出量総合評価(2016.7)」より電気事業連合会作成
【第123-1-4】火力発電の特性と再エネ拡大に当たっての課題
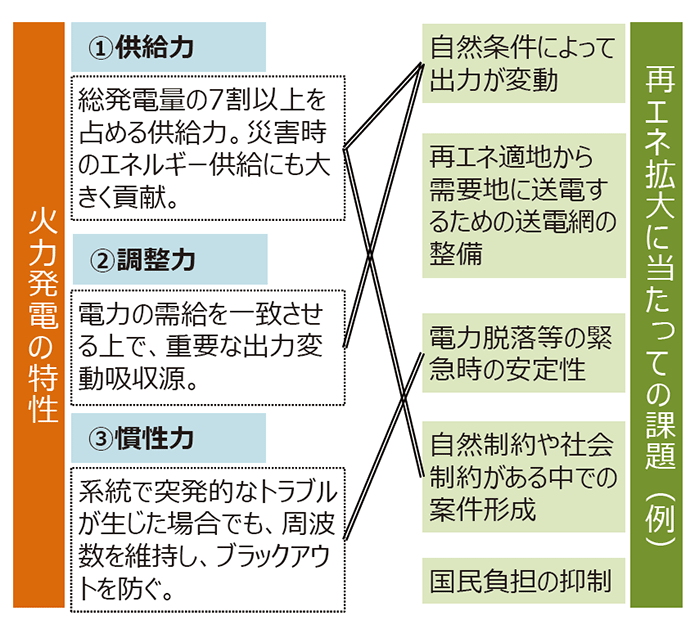
【第123-1-4】火力発電の特性と再エネ拡大に当たっての課題(ppt/pptx形式:22KB)
- 出典:
- 経済産業省作成
COLUMN
非効率石炭火力発電のフェードアウト
2020年7月、梶山経済産業大臣は、第5次エネルギー基本計画において明記された非効率石炭火力のフェードアウトについて、より実効性のある新たな仕組みを導入するべく、検討を開始することを表明し、総合資源エネルギー調査会電力・ガス分科電力・ガス基本政策小委員会を中心に検討が行われました。
2018年度において、石炭火力発電による発電量は、総発電量の32%を占め、その内訳は、高効率の石炭火力発電33が総発電量の13%(計26基34)、非効率の石炭火力発電35が総発電量の16%(計114基)、自家発・自家消費分が総発電量の3%となっています(第123-1-5)。
こうした中で、経済産業省は、非効率石炭火力のフェードアウトを着実に進めるため、①省エネ法上で石炭火力の発電効率目標を最新鋭のUSC(超々臨界)の水準に設定する規制的措置、②容量市場により安定供給に必要となる供給力を確保しつつ、稼働抑制に対するインセンティブを付与することにより発電量(kWh)削減を促進する誘導措置、に加え、事業者の取組を確認・担保するためにフェードアウトに向けた計画の提出を求めることで、安定供給を確保しつつフェードアウトを進めていく方針を示しました。(第123-1-6)
【第123-1-5】非効率石炭火力の全火力発電所に占める割合
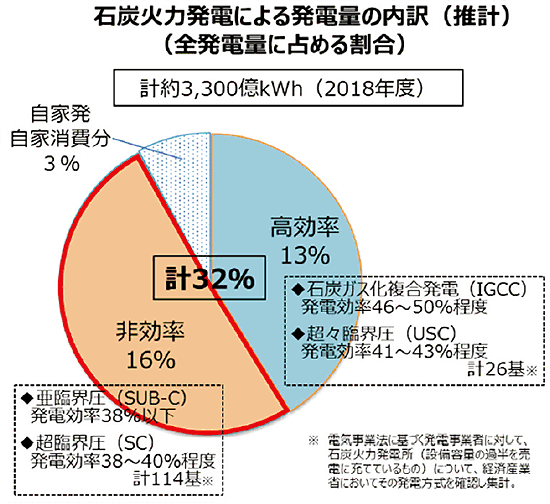
【第123-1-5】非効率石炭火力の全火力発電所に占める割合(ppt/pptx形式:123KB)
- 出典:
- 総合資源エネルギー調査会電力・ガス基本政策小委員会(第26回)(2020年7月13日)資料より抜粋
【第123-1-6】非効率石炭火力フェードアウトに向けた対応の方向性
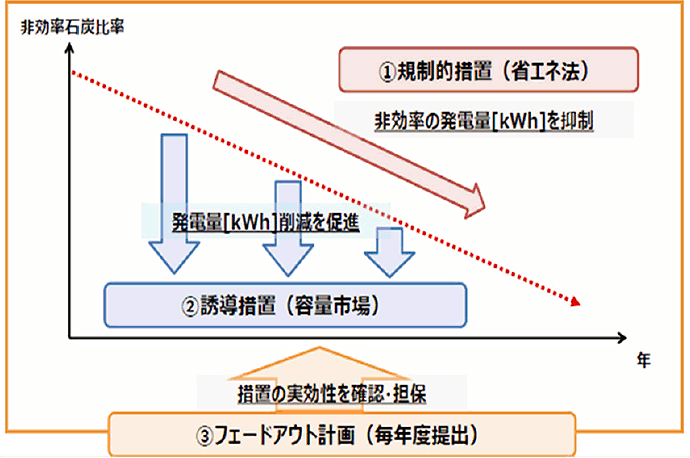
【第123-1-6】非効率石炭火力フェードアウトに向けた対応の方向性(ppt/pptx形式:162KB)
- 出典:
- 総合資源エネルギー調査改電力・ガス基本政策小委員会(第32回)(2021年3月26日)資料より抜粋
(2)非電力部門の現状
非電力部門のCO2排出量は省エネ化等により減少を続けています(第123-1-7)。カーボンニュートラル実現のためには、①電化、②熱需要の水素の利用、③CCUSが必要ですが、電化では賄えないのが、製造プロセス上で大量の熱エネルギーを必要とする産業(例:パルプ・紙・紙加工業)や、化学反応においてCO2が発生する産業(例:鉄鋼業、化学工業、セメント業)です。
【第123-1-7】非電力部門のCO2排出量の推移(2019年度)
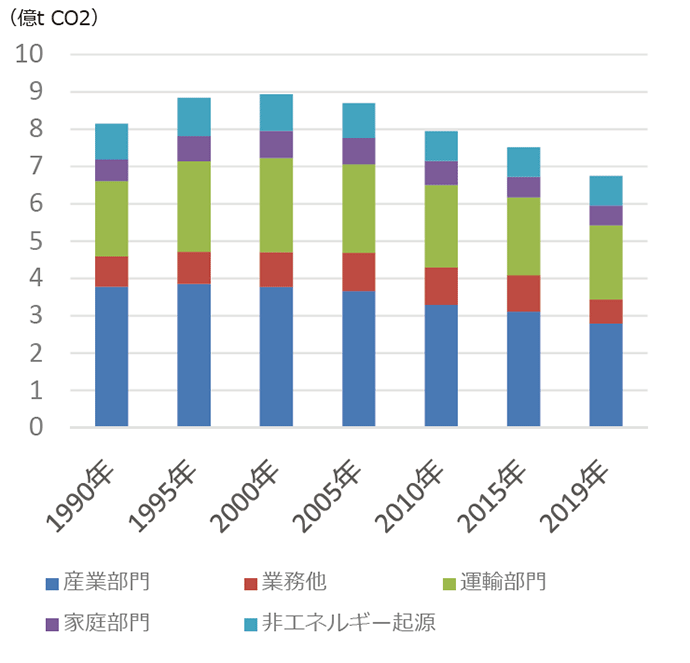
【第123-1-7】非電力部門のCO2排出量の推移(2019年度)(ppt/pptx形式:35KB)
- 出典:
- 国立環境研究所「温室効果ガスインベントリオフィス」より経済産業省作成
【第123-1-8】産業部門のCO2排出量の内訳(2019年度)
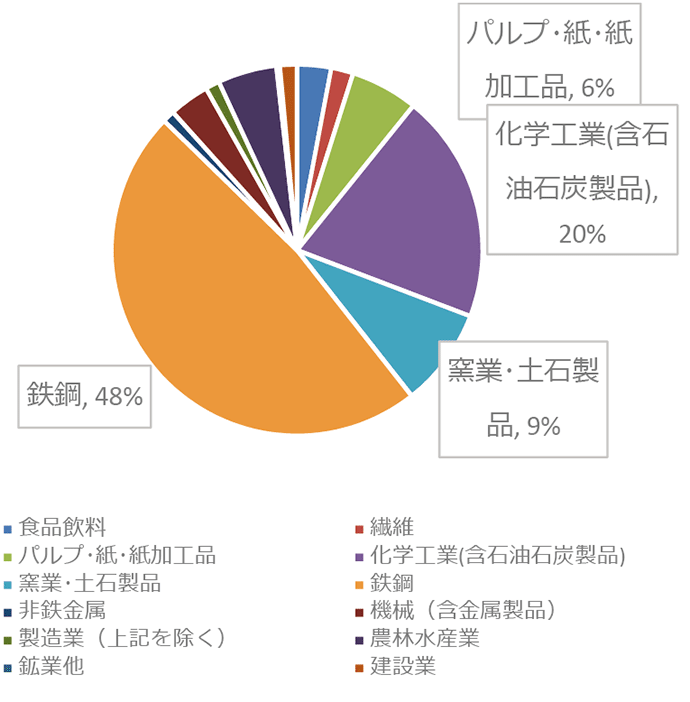
【第123-1-8】産業部門のCO2排出量の内訳(2019年度)(ppt/pptx形式:36KB)
- 出典:
- 国立環境研究所「温室効果ガスインベントリオフィス」より経済産業省作成
①鉄鋼
鉄鋼業は産業部門のCO2排出の約5割を占める最大の排出産業です。高炉による鉄鋼生産では、鉄鉱石から石炭を用いた還元反応を利用して鉄を精製していますが、この還元反応において、大量のCO2が発生します。鉄鋼生産のカーボンニュートラル化を図るため、石炭ではなく水素を用いた還元反応により鉄を取り出す水素還元製鉄などの技術開発が必要になっています。
②化学
化学産業では、主に原料となるナフサを高温で熱分解しエチレンやプロピレンなどの基礎化学品を製造しています。現在は化石燃料などを燃焼させて熱エネルギーを得ており、この過程でCO2が発生します。他方で、化学産業は炭素を原料利用できる産業でもあるため、発生するCO2を回収し、水から光触媒により取り出した水素を使ってプラスチック原料を製造する人工光合成などのカーボンリサイクル技術の開発が必要になっています。
③セメント
セメントの主原料である石灰石は、炭酸カルシウム(CaCO3)を成分としており、これを焼成してクリンカ(CaO)と呼ばれる中間製品を生成し、それに石こう等を添加してセメントを作っていますが、石灰石の焼成過程での脱炭酸反応によりCO2が発生します。このように、セメント製造では、焼成の熱源と化学反応の両方でCO2を排出していることから、製造過程で発生するCO2を回収するための技術開発等が必要になっています。
④パルプ・紙・紙加工品
紙の原材料は、木材チップや古紙が中心となっており、これらをパルプにし、水中に分散したパルプから水を蒸発させることで紙を作っています。現在は化石燃料や一部バイオ燃料などを燃焼させて熱エネルギーを得て乾燥させていますが、大量の熱エネルギーを必要とし、このプロセスの電化は現時点では困難とされています。カーボンニュートラルに向け、省エネルギー化やバイオ燃料の混焼割合を引き上げる技術開発等を進めるとともに、植林や廃材の利用等を組み合わせ、ライフサイクルでのCO2排出量を削減する取組が行われています。
また、日本の企業数の99.7%を占める中小企業における脱炭素化の取組も重要です。大企業に比べ投資余力の小さい中小企業が脱炭素化に向けた取組を進められるような環境整備も求められます。
COLUMN
カーボンプライシングの動向
温室効果ガス排出削減のための手法としては、規制的手法(法令による統制や目標達成の義務付けなど)や経済的手法(経済的インセンティブの付与を通じた合理的な行動への誘導)、自主的取組手法(事業者等の自主的な努力目標の設定、対策の実施など)などが存在します。カーボンプライシングは、炭素への価格付けを通じて、民間事業者や消費者等の脱炭素への行動変容を促す経済的手法の一つであり、カーボンニュートラルを実現するための手法として注目を集めています。
カーボンプライシングの中にも様々な類型が存在します。CO2の排出量に比例した課税を行う炭素税や、企業ごとに排出量の上限を決め、その超過分・余剰分を売買する国内排出量取引、CO2削減価値を証書化・クレジット化して取引を行うクレジット取引が代表的です。特にクレジット取引は、欧米等の取引先からエネルギーの脱炭素化を求められている我が国の産業界を始め世界的にニーズが高まっており、近年取引量が増大しています(第123-1-9)。これらに加えて、国際的な市場メカニズムの整備や、企業内でCO2排出に対して価格を付けて投資判断等に活用するインターナルカーボンプライシングといった手法も存在します。
【第123-1-9】クレジット取引量(世界)の推移(2019年度)
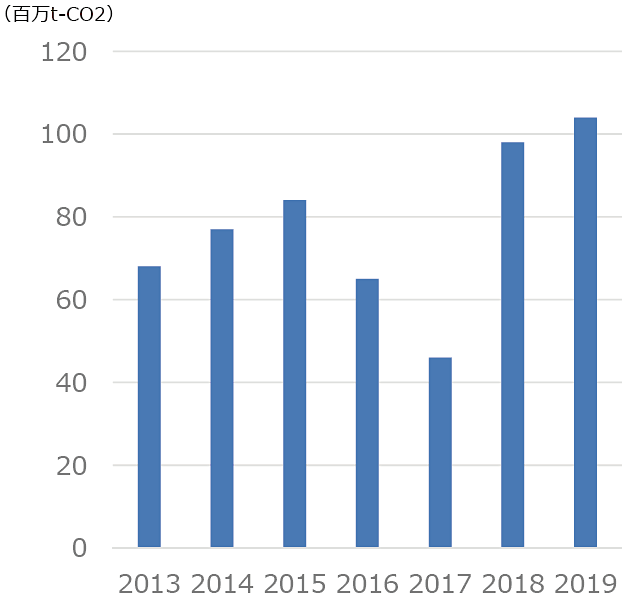
【第123-1-9】クレジット取引量(世界)の推移(2019年度)(ppt/pptx形式:34KB)
- 出典:
- Forest Trends「State of the Voluntary Carbon Markets 2020」より経済産業省作成
国内でCO2に対する価格付けを行い排出量削減の誘導を行った結果、CO2の価格が低い又は規制の弱い国に企業が移転してしまうと、結果として、世界全体のCO2排出量が増大してしまう(いわゆる「カーボンリーケージ」)とともに、国内産業に大きな影響を与えることになります。このため、CO2価格差等を国境で調整する仕組みとしての「炭素国境調整措置」について、EUでは具体的な制度の検討が行われています。
現在政府では、成長に資するカーボンプライシングの検討に取り組んでいます。検討に当たっては、成長戦略の趣旨に則った制度を設計しうるかについて、マクロ経済・気候変動対策の状況や脱炭素化に向けた代替技術の開発状況等を考慮した適切な時間軸を設定する観点、国際的な動向や多くの企業が脱炭素化に意欲的に取り組んでいることも含めた我が国の事情、企業の研究開発や設備投資への影響も含めた産業の国際競争力への影響等を踏まえることが必要です。企業が排出削減に向けた投資にメリットを感じ、具体的な投資を行うような制度となるよう、専門的・技術的な議論を進めていきます。
このように、カーボンプライシングを成長に資するものとするためには、炭素国境調整措置等を通じて国際的に公正な競争条件を確保すること、産業競争力強化やイノベーション、投資促進につながること、国内で適切に還流・再配分されること等の観点を踏まえながら、脱炭素化の段階に応じて政策手法を組み合わせることが必要となります。
【第123-1-10】カーボンプライシングの類型
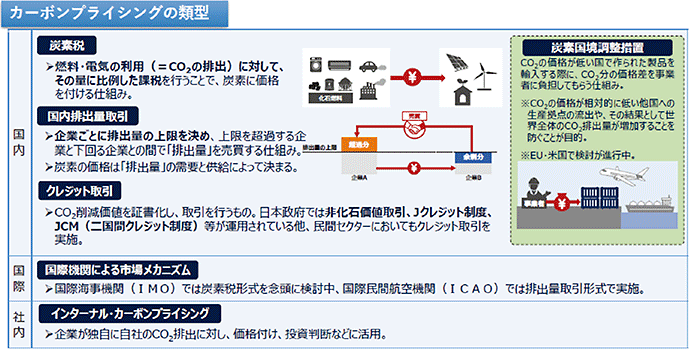
【第123-1-10】カーボンプライシングの類型(ppt/pptx形式:153KB)
- 出典:
- 経済産業省・環境省作成
2. 2050年カーボンニュートラルに向けた道筋
(1) 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略
2020年12月、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略(以下「グリーン成長戦略」という。)」が公表されました。国として、可能な限り具体的な見通しを示し、高い目標を掲げて、民間企業の前向きな挑戦を応援し、大胆な投資とイノベーションを促す環境を作ることを目的としたものです。
【第123-2-1】グリーン成長戦略の枠組み
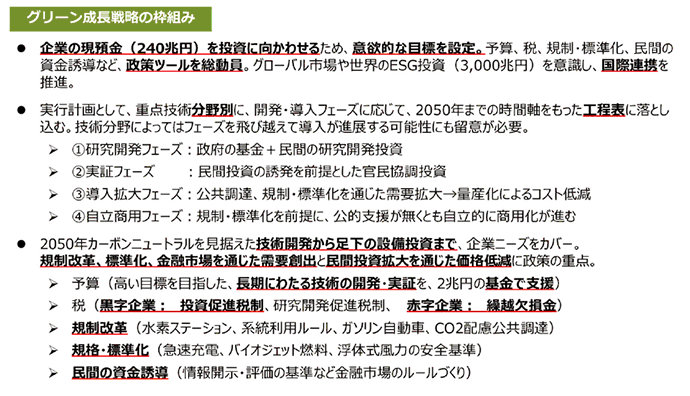
- 出典:
- 成長戦略会議(第6回)(2020年12月25日)資料より抜粋
グリーン成長戦略では、2050年カーボンニュートラルに向けた道筋として、電力部門では脱炭素電源の拡大、産業・民生・運輸(非電力)部門(燃料利用・熱利用)においては、脱炭素化された電力による電化、水素化、メタネーション、合成燃料等を通じた脱炭素化を進めることが必要としています。こうした電源や燃料の転換を行ってもなお排出されるCO2については、植林やDACCS(Dirct Air Carbon Capture and Storage:炭素直接空気回収・貯留)などを用いて、実質ゼロを実現していくこととしています(第123-2-2)。
また、グリーン成長戦略では、2050年カーボンニュートラルを実現する上で不可欠な重点分野ごとに、①年限を明確化した目標、②研究開発・実証、③規制改革・標準化などの制度整備、④国際連携などを盛り込んだ「実行計画」を策定し、合わせて2050年までの時間軸を持った工程表を提示しています。足下から2030年にかけて市場が立ち上がるものから、2050年にかけて市場が立ち上がってくるものまで、時間軸が異なる14分野を取り上げられています。
政府としては、2兆円のグリーンイノベーション基金をはじめ、税、規制改革・標準化、国際連携などあらゆる政策を総動員して、グリーン成長戦略を実行し、企業の前向きな挑戦を全力で後押しします。
【第123-2-2】2050年カーボンニュートラルへの転換イメージ
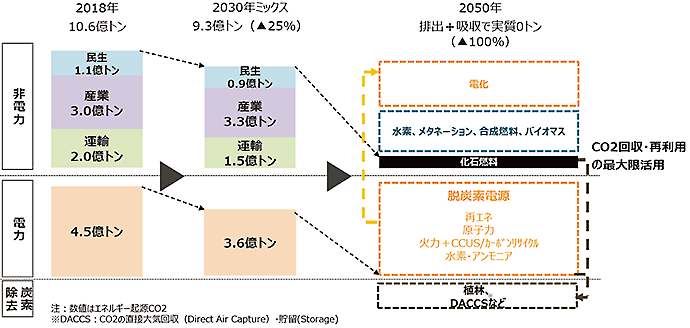
【第123-2-2】2050年カーボンニュートラルへの転換イメージ(ppt/pptx形式:30KB)
- 出典:
- 成長戦略会議(第6回)(2020年12月25日)資料を一部加工
【第123-2-3】グリーン成長戦略の重点14分野
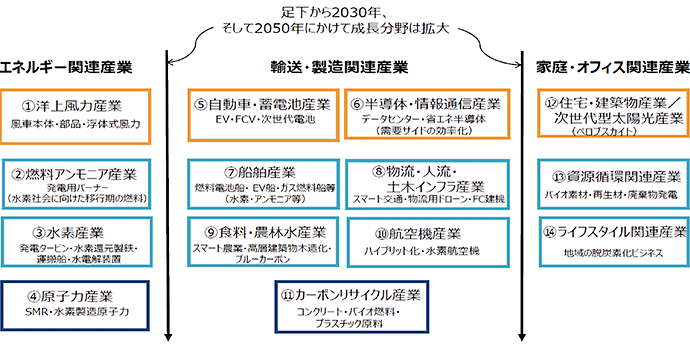
【第123-2-3】グリーン成長戦略の重点14分野(ppt/pptx形式:187KB)
- 出典:
- 成長戦略会議(第6回)(2020年12月25日)資料より抜粋
COLUMN
脱炭素関連技術の日本の知財競争力
2050年カーボンニュートラル実現は、地球温暖化対策として、成長戦略として取り組む必要があります。グリーン成長戦略で取り上げられた14分野について、知財競争力を主要国と比較しました。
具体的には、知財競争力を代表する指標として、他社からの注目度(他社閲覧回数、情報提供回数など)や他社への脅威度(他社拒絶査定引用回数、無効審判請求回数など)等を評価し、それを各特許の残存年数等と掛け合わせ、国・地域ごとに集計をした指標(トータルパテントアセット)を用いています。過去10年(2010年から2019年)に、日本、米国、中国、韓国、台湾、英国、ドイツ、フランスの8か国に出願された特許を分析の対象としています。
日本は、「水素」、「自動車・蓄電池」、「半導体・情報通信」、「食料・農林水産」の4分野で首位、他の6分野(洋上風力、燃料アンモニア、船舶、カーボンリサイクル、住宅・建築物/次世代型太陽光、ライフスタイル)でも世界第2位又は第3位となっており、比較的高い知財競争力を保有していると言えます(第123-2-4)。
日本が首位になっている分野について、個別に概観すると、「水素」と「自動車・蓄電池」は、日本が他国と比較して強い分野と言えますが、両分野において日本の自動車メーカー・自動車部品メーカーが高い知財競争力を持ち、他国企業を大きく離していることが要因となっています。「半導体・情報通信」については、上位50社中19社を日本企業が占めており、半導体の素材から製造装置、情報通信機器・システムまで幅広い企業が上位に入っています。「食料・農林水産」では、日本の農業用機械の特許が強く、欧米の化学メーカーを抑え上位に入っています。
今回の分析は、知財競争力のあくまで一面を評価したものですが、日本が持つ知財競争力を、今後の社会実装の段階で産業競争力に変えていくことが重要です。そのためには、例えばカーボンニュートラルポート36をはじめ、インフラの側面からも社会実装を支援すること、あるいは、燃料アンモニアの国際標準化の推進といった国際ルール形成の中で社会実装を支援することなど、環境整備を行うことが重要です。
【第123-2-4】14分野の知財競争第力の国別比較
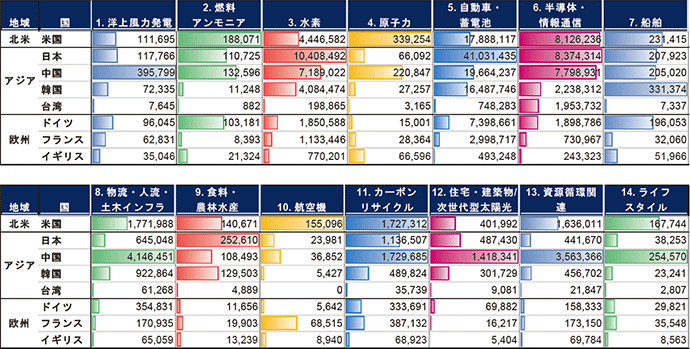
- 出典:
- アスタミューゼ(株)「令和2年度エネルギーに関する年次報告書に係る脱炭素関連技術の日本の競争力に関する分析作業等」等の分析結果より経済産業省作成
【第123-2-5】各分野の分析結果の特徴
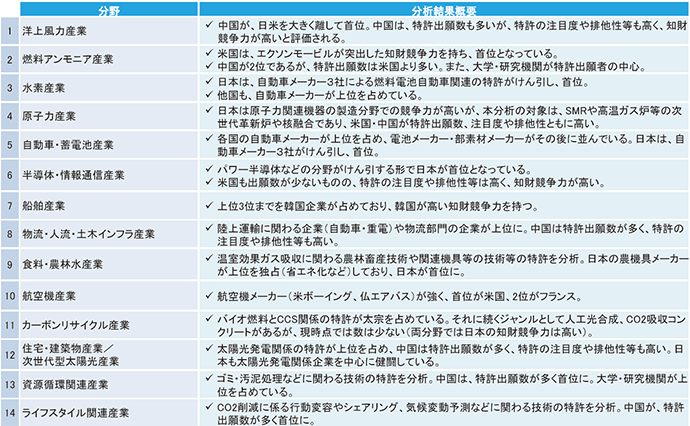
【第123-2-5】各分野の分析結果の特徴(ppt/pptx形式:37KB)
- 出典:
- アスタミューゼ(株)「令和2年度エネルギーに関する年次報告書に係る脱炭素関連技術の日本の競争力に関する分析作業等」等の分析結果より経済産業省作成
(2)CO2を資源として利用する「カーボンリサイクル」
実行計画に取り上げられた分野のうち、「CO2排出源の代替技術への置き換え」ではなく、「CO2を資源として有効活用」する技術である「カーボンリサイクル」は、今後、日本が技術面・産業面で世界をリードしていくことが期待されている分野の一つです。「カーボンリサイクル」により、火力発電所等から排出されたCO2や大気中から直接回収したCO2を、鉱物化(コンクリートの材料として利用)や水素と組み合わせて化学製品など新たな素材を作ることが可能になります。
【第123-2-6】カーボンリサイクルの概念図
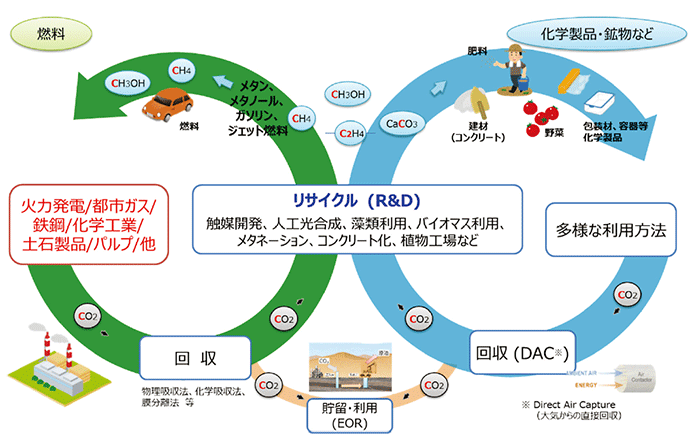
【第123-2-6】カーボンリサイクルの概念図(ppt/pptx形式:290KB)
- 出典:
- 経済産業省HPより抜粋
【第123-2-7】カーボンリサイクルの技術ロードマップ
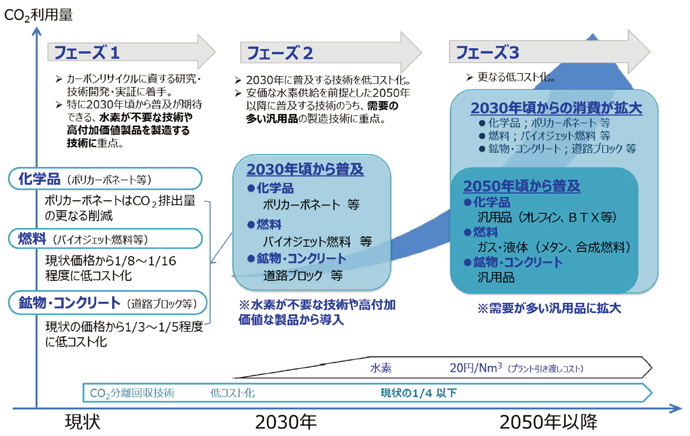
【第123-2-7】カーボンリサイクルの技術ロードマップ(ppt/pptx形式:309KB)
- 出典:
- 経済産業省HPより抜粋
2019年6月にカーボンリサイクル技術ロードマップが、経済産業省の取りまとめの下、内閣府、文部科学省、環境省の協力を得て策定されました。当該ロードマップでは、カーボンリサイクル技術を社会に実装していくに当たって、3段階で進めていくこととしています。
第1段階(フェーズ1)では、カーボンリサイクルに資する研究や技術開発、実証に着手することし、特に2030年頃から普及が期待できる、水素が不要な技術や高付加価値製品を製造する技術に重点を置くこととしています。第2段階(フェーズ2)では、2030年に普及する技術を低コスト化していくとともに、安価な水素供給を前提とした2050年以降に普及する技術のうち、需要の多い汎用品の製造技術に重点を置くこととしています。第3段階(フェーズ3)では、カーボンリサイクルによる製造技術・製品のさらなる低コスト化を図り、社会実装を進めていくこととしています。
このように、カーボンリサイクルは技術開発を伴って多くの製品に展開されていくことが期待されていますが、既に製品化されているものもあります。
CO2吸収型コンクリート
新たに開発された混和材を、セメントを一部代替する形でコンクリートに用いたものがCO2吸収型コンクリートです。混和材がCO2を吸収するとともに、セメント使用量を減らすことでセメント製造時のCO2を削減することができます。しかし、CO2吸収型コンクリートは鉄筋が錆びやすいため、現状、鉄筋構造物には使用できず、用途は道路・舗装ブロックやパネル等に限定されています。また、コストが通常のコンクリート製品に比べて3 ~ 5倍であることが課題とされており、用途拡大・低コスト化を図るための技術開発が行われています。
CO2を原料とした化学素材(ポリカーボネート)
ポリカーボネート樹脂は自動車のヘッドライトカバーやパソコンの外装、CDやDVDなどに幅広く使われている素材です。従来のポリカーボネート製造技術は、有毒性が高いホスゲンを使用していましたが、新たな製造法では、ホスゲンを使用せずに、アルコール、CO2、フェノールを原料として、ポリカーボネートを製造することが可能となっており、CO2の有効活用と有毒物質の使用削減の両面で意義のあるものとなっています。
CO2を原料とした化粧品用プラスチック容器
フランスの大手化粧品メーカーが、フランスの石油化学会社と米国のスタートアップと共同で、排気ガス中のCO2を再利用するカーボンリサイクル技術を活用して、化粧品用ポリエチレン容器を開発しています。
人工光合成によるプラスチック原料
人工光合成では、水とCO2を原料とし、太陽エネルギーを用いてプラスチック原料を製造することができます。現状では、太陽エネルギーを用いて水から水素を製造する光触媒の変換効率が低く、また製造コストが高いため、大規模実証の実施には技術的課題があります。そのため変換効率の高い光触媒等の開発が行われています。
【第123-2-8】カーボンリサイクルの実用化事例
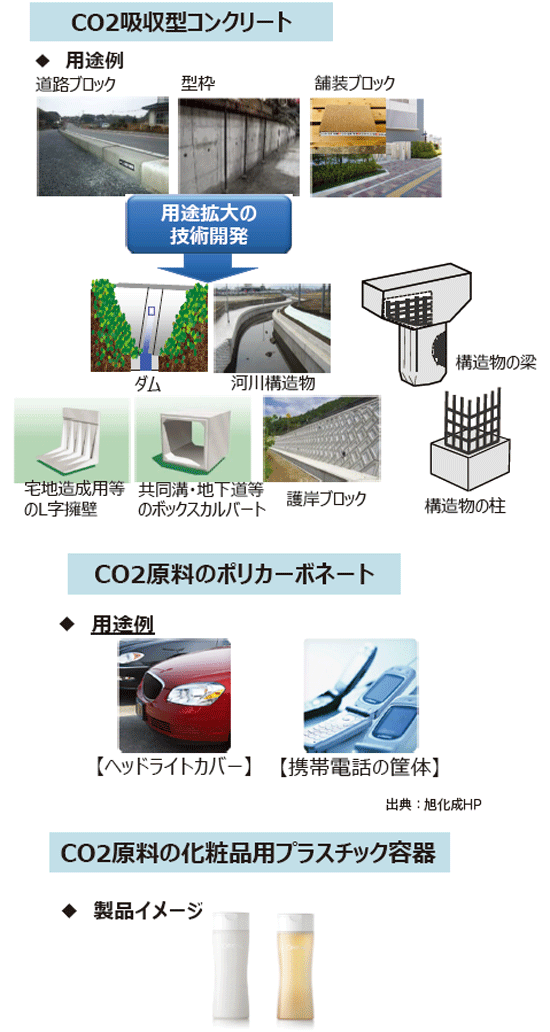
【第123-2-8】カーボンリサイクルの実用化事例(ppt/pptx形式:341KB)
- 出典:
- 提供:日本ロレアル(株)より提供
COLUMN
カーボンリサイクルに関する知財競争力
グリーン成長戦略の14分野に関する知財競争力の分析(第123-2-5)において、カーボンリサイクルについても分析をしましたが、この分析では、CO2の分離・回収技術や、燃料に転換するバイオ燃料の特許が上位を占めており、日本は、中国、米国に次ぐ第3位となっています。一方で、燃料以外の素材や製品に転換する部分では日本が強みを発揮しています。例えば、太陽光エネルギーを使って水から水素を作り出したり、CO2を化学品に変換したりする「人工光合成」の分野では、日本の知財競争力の数値は他国を圧倒しており(第123-2-9)、企業別に見ても、上位を日本企業が独占する結果となっています。
【第123-2-9】人工光合成の知財競争力の国別比較
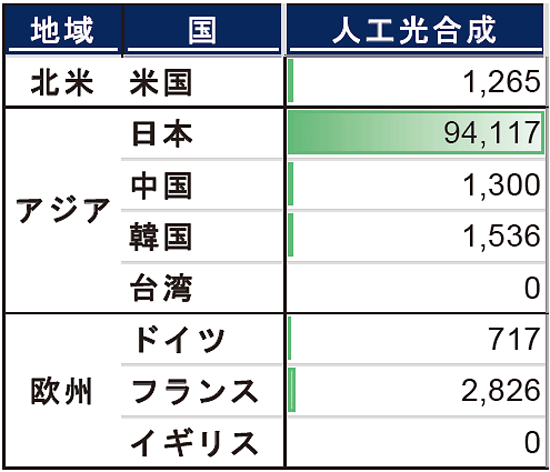
- 出典:
- アスタミューゼ(株)「令和2年度エネルギーに関する年次報告書に係る脱炭素関連技術の日本の競争力に関する分析作業等」等の分析結果より経済産業省作成
- 注:
- 知財競争力とは、他社からの注目度(他社閲覧回数、情報提供回数など)や他社への脅威度(他社拒絶査定引用回数、無効審判請求回数など)等を評価し、それを各特許の残存年数等と掛け合わせ、国・地域ごとに集計をした指標
アスタミューゼ社が保有する日本の科学研究費や米国の国立衛生研究所・国立科学財団等、世界25か国、約90兆円の研究投資情報のデータベースから、2010年以降に実施された「人工光合成」に関する研究テーマを、配布額が大きい順に上位20件をランキング化すると、20件のうち、米国が12件で最多(計9500万米ドル)、次いで英国と日本が3件ずつ(それぞれ計2300万米ドル、1700万米ドル)となっています。各国が公的な研究開発支出を増加させており、人工光合成分野における国際的な開発競争が激しくなることは予想されます。
- 31
- 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会(第33回会合)(2020年11月17日開催)資料を参照
- 32
- 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会(第35回会合)(2020年12月21日開催)資料を参照
- 33
- ここでは石炭ガス化複合発電(IGCC)と超々臨界圧(USC)を指す。
- 34
- 電気事業法に基づく発電事業者に対して、石炭火力発電所(設備容量の過半を売電に充てているもの)について、経済産業省においてその方式を確認し、集計。非効率石炭火力についても同様。
- 35
- ここでは亜臨界圧(SUB-C)と超臨界圧(SC)を指す。
- 36
- 国際物流の結節点・産業拠点となる港湾において、水素・燃料アンモニア等の次世代エネルギーの大量・安定・安価な輸入や貯蔵等を可能とする受入環境の整備や、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等を通じて温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを目指すもの。