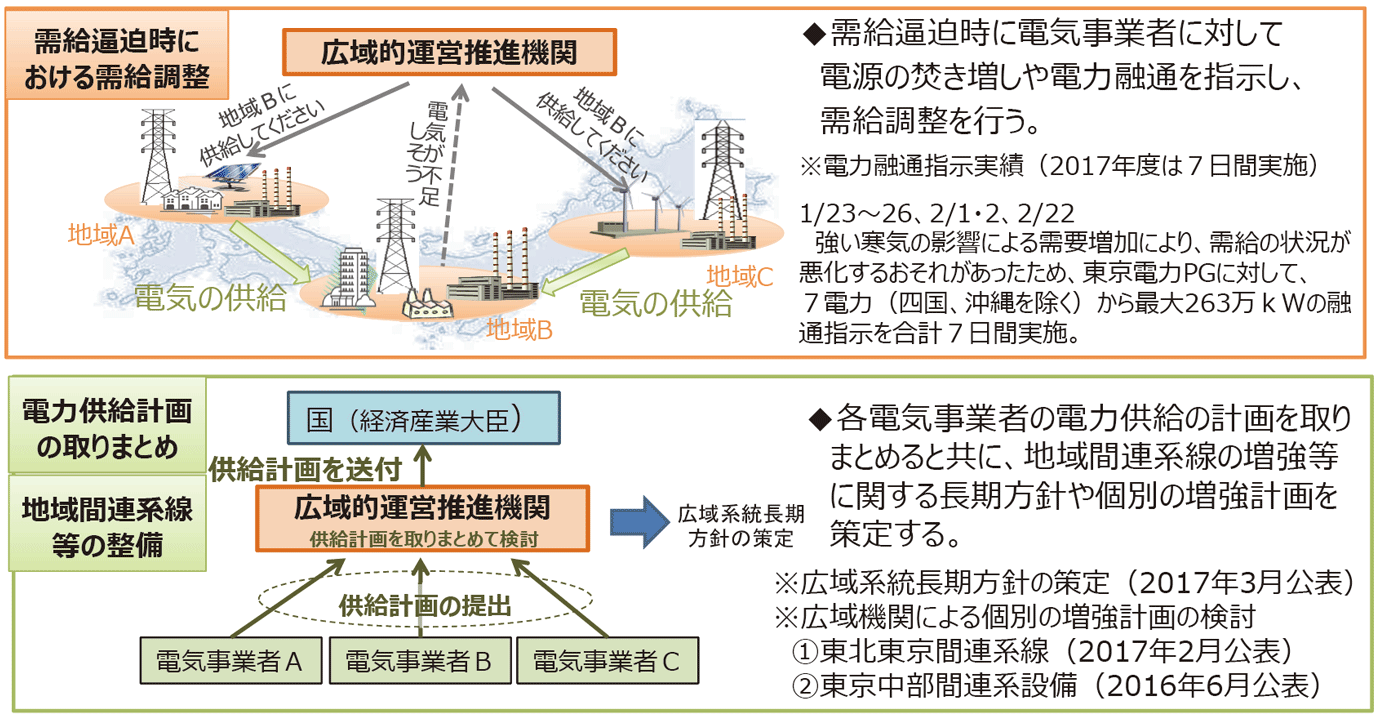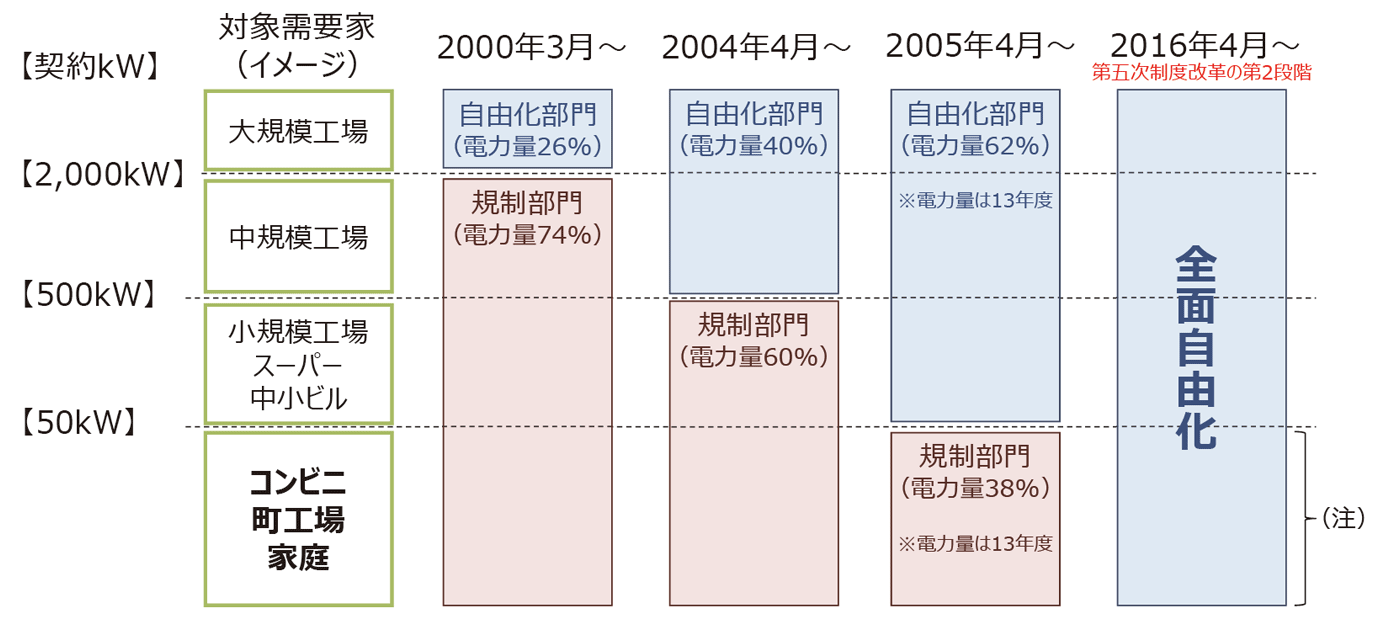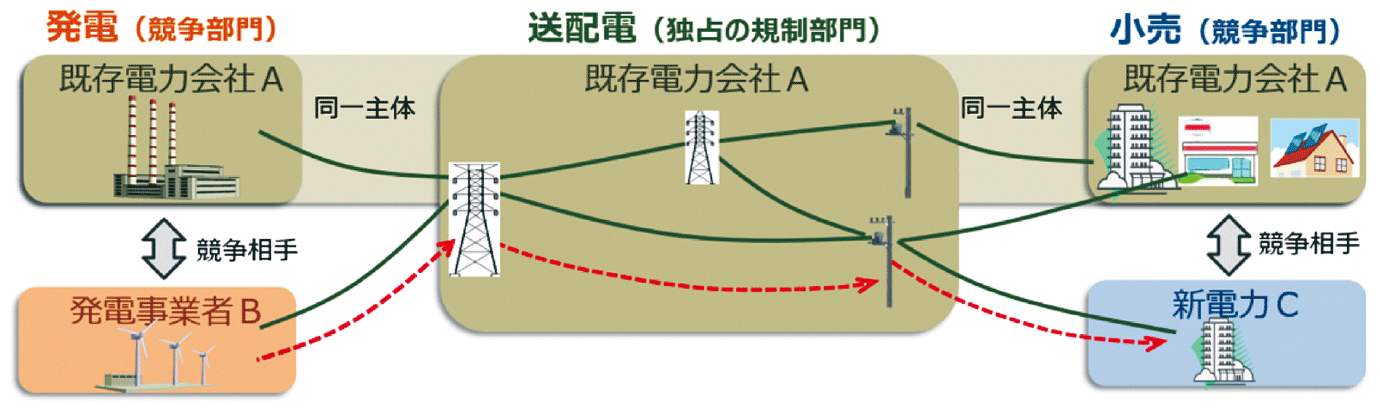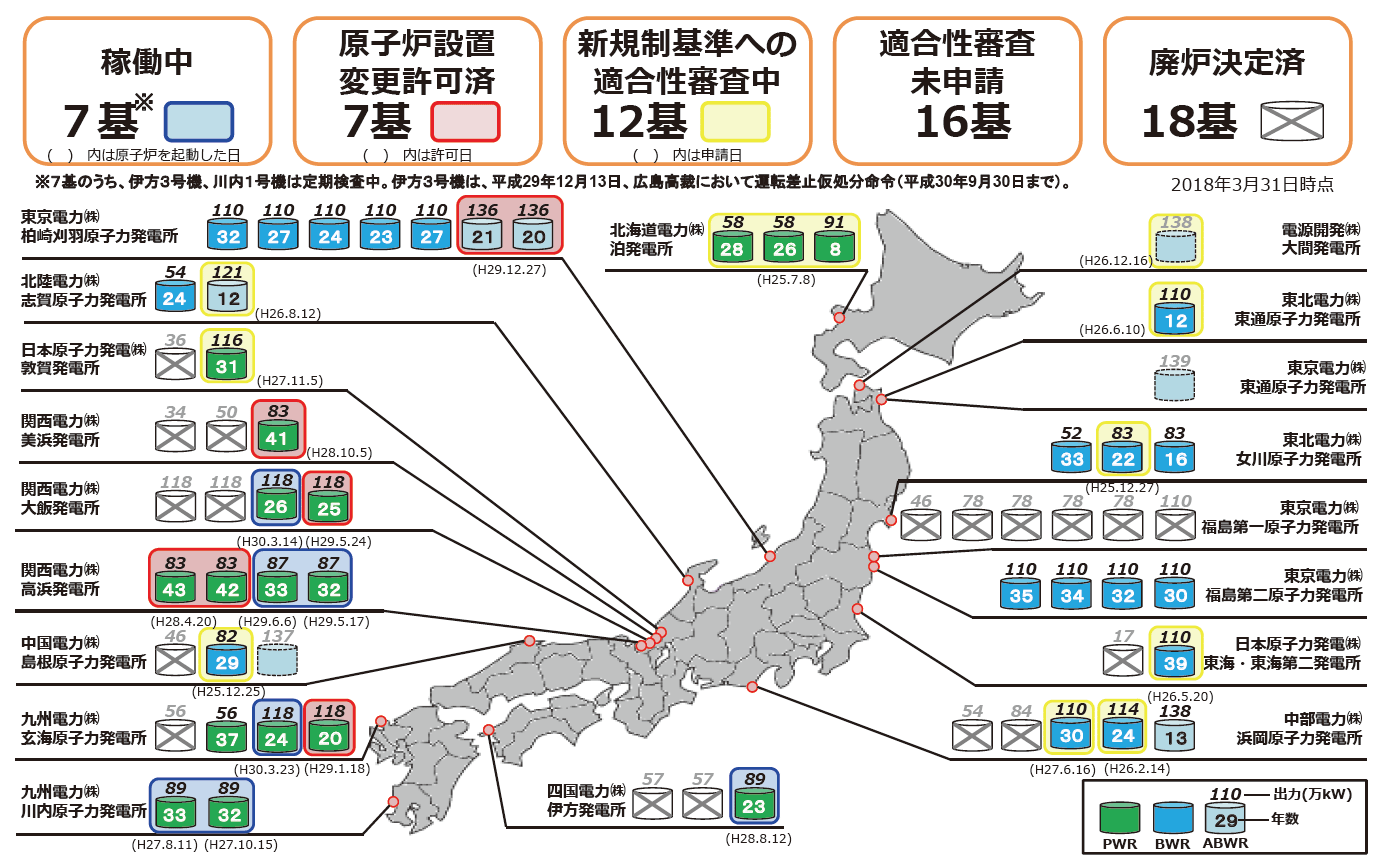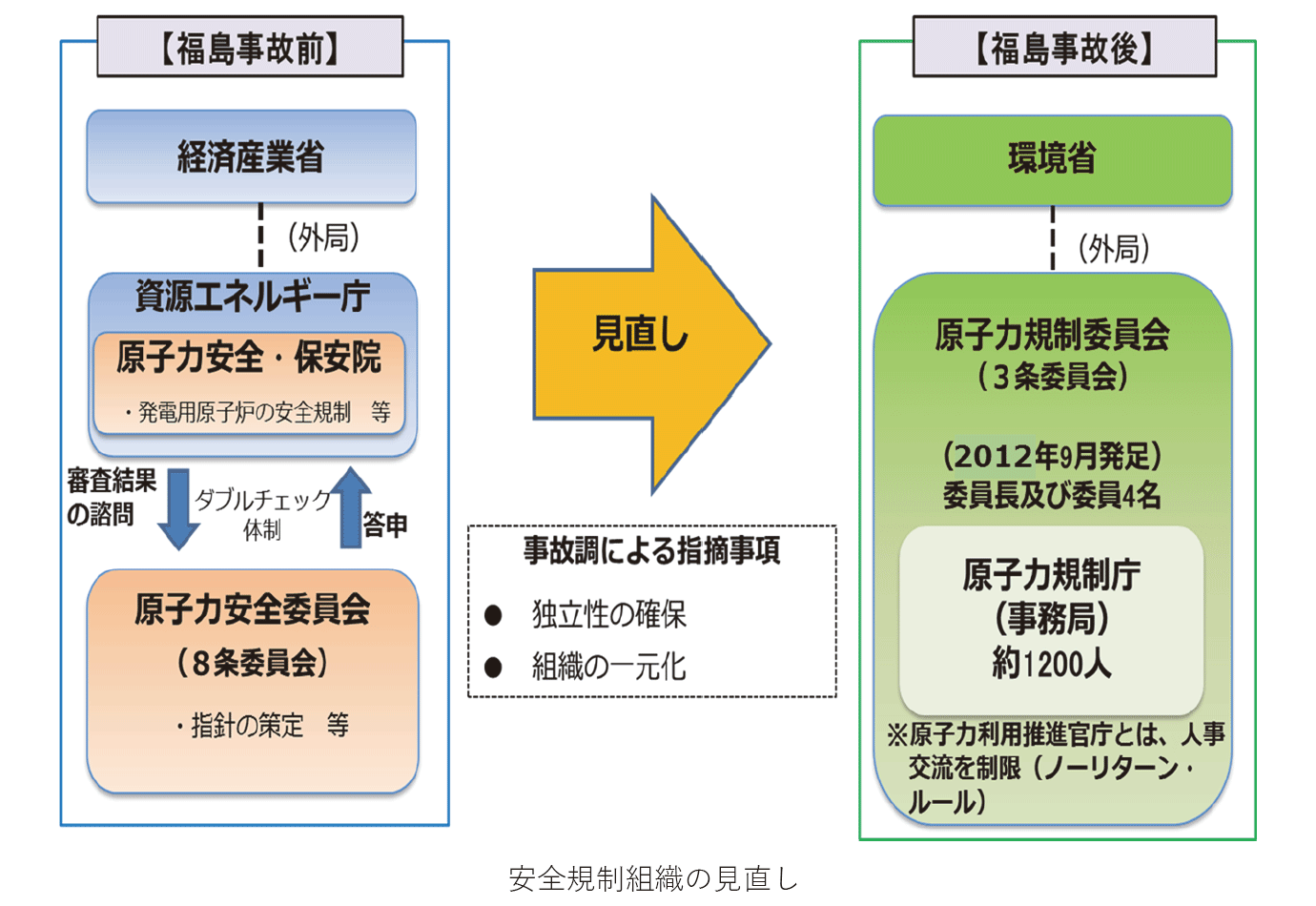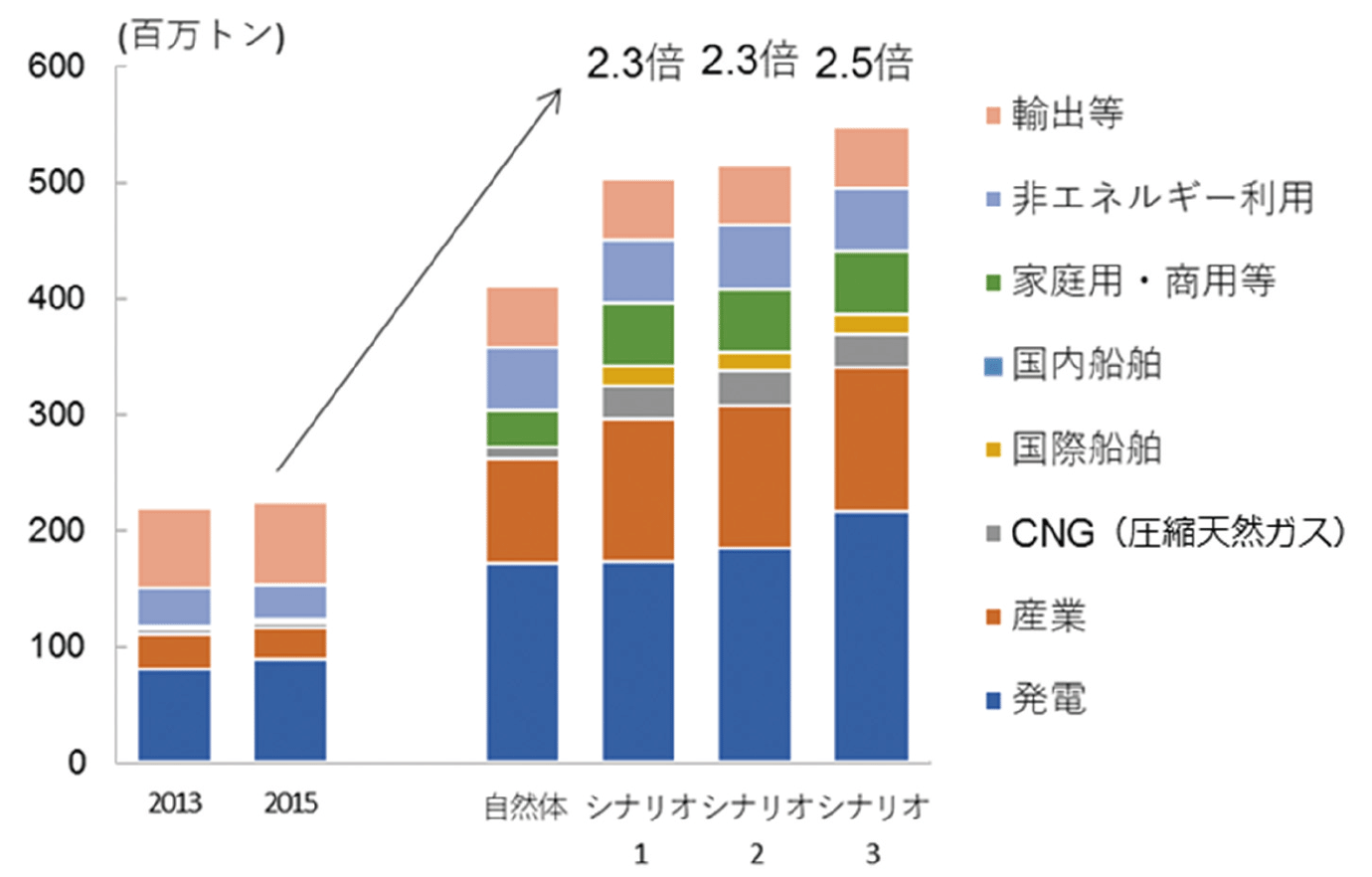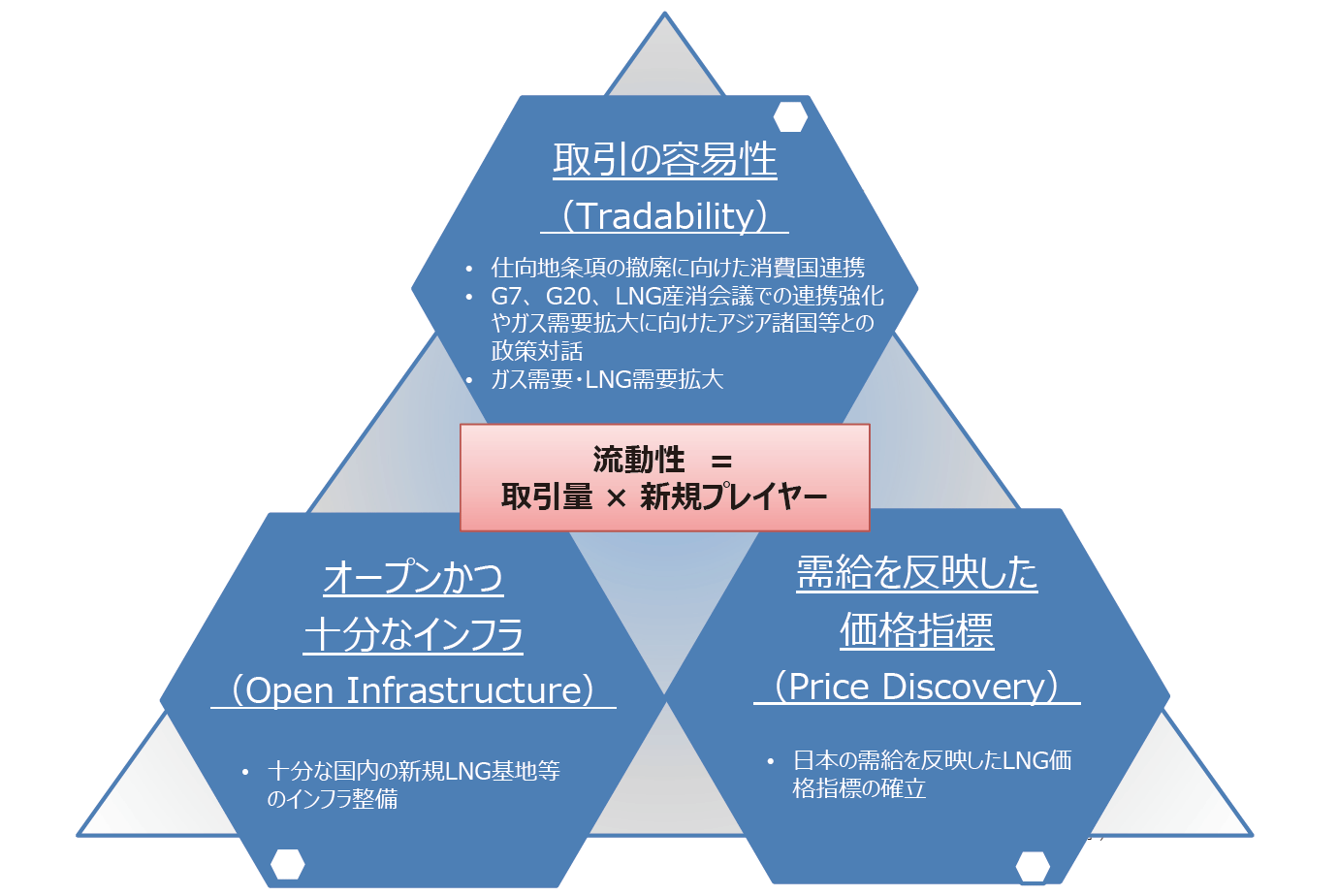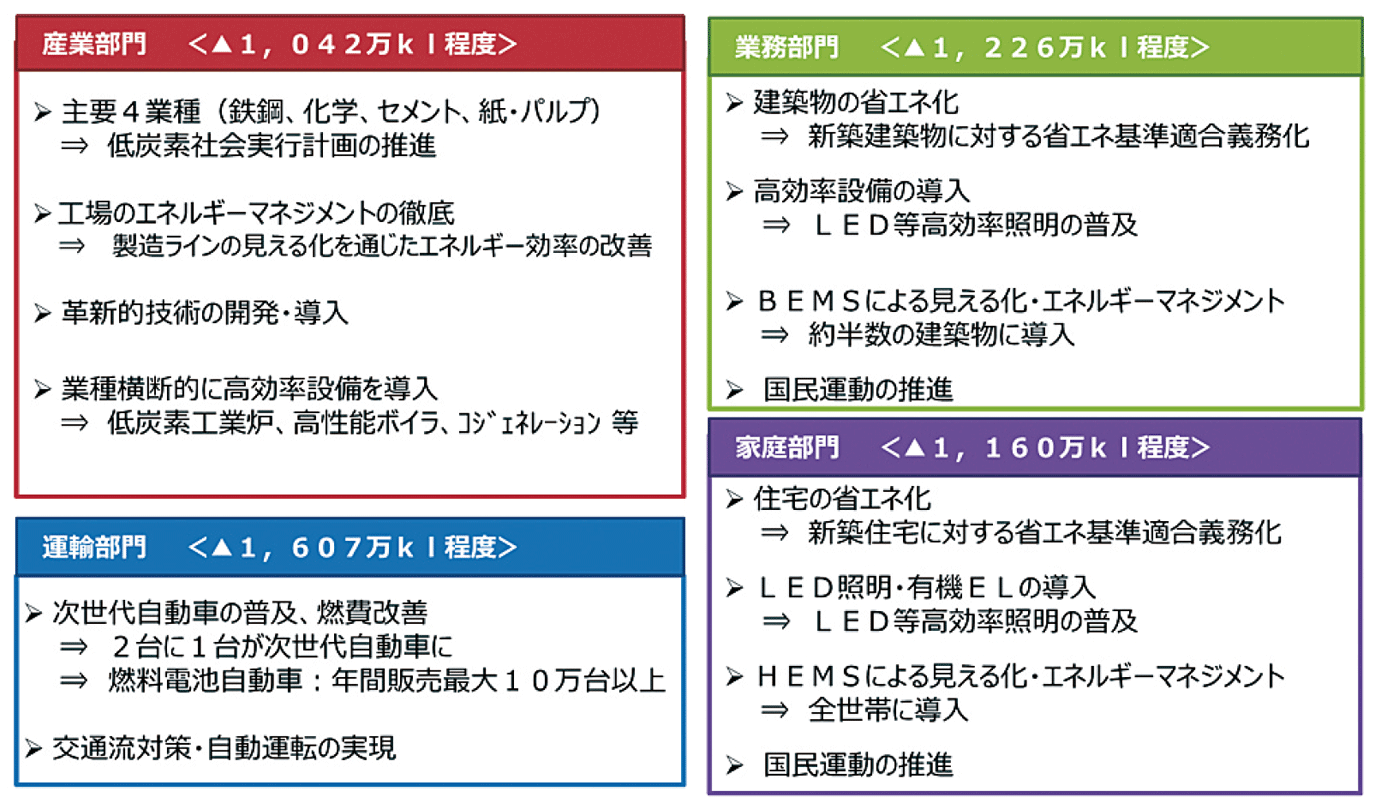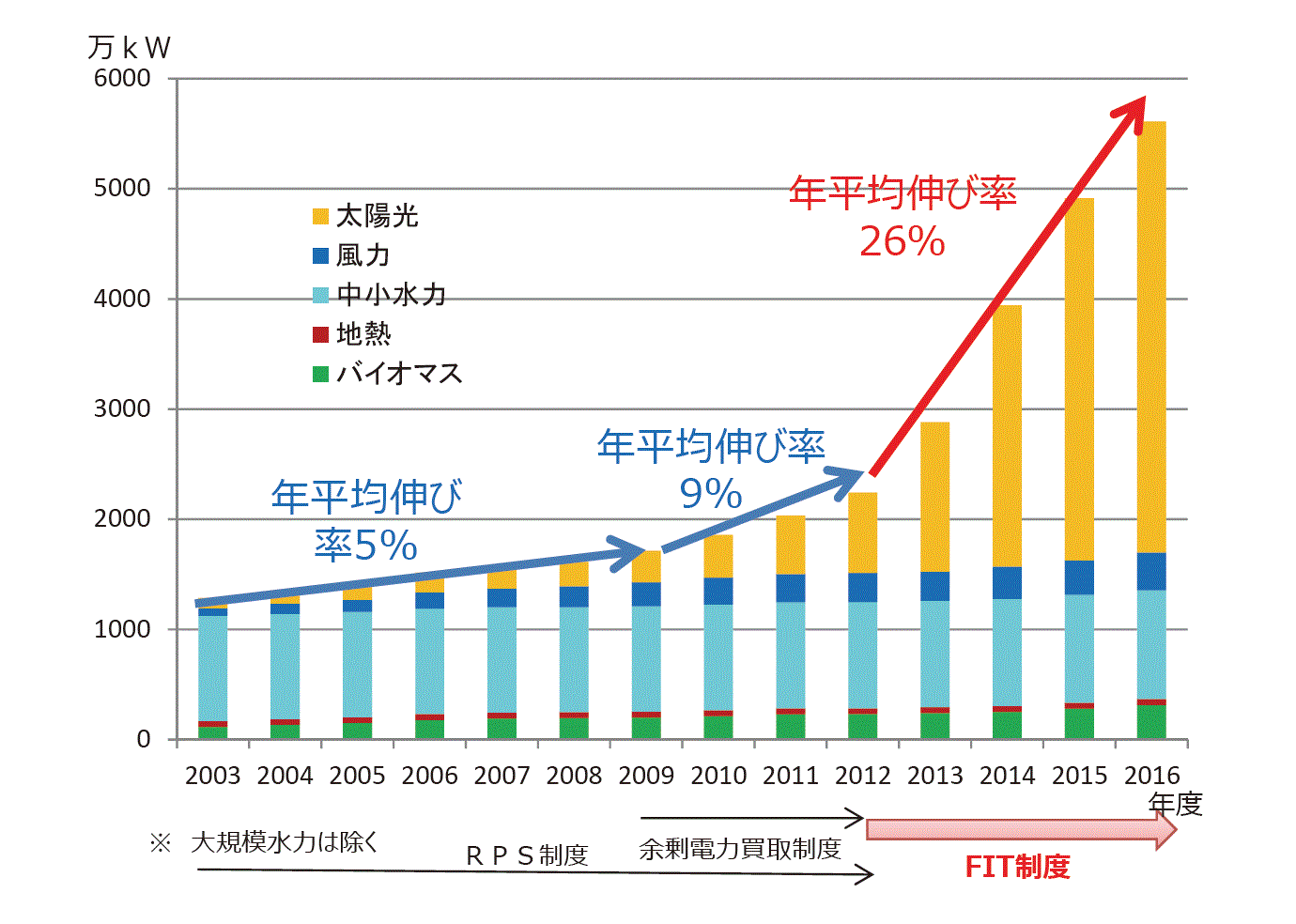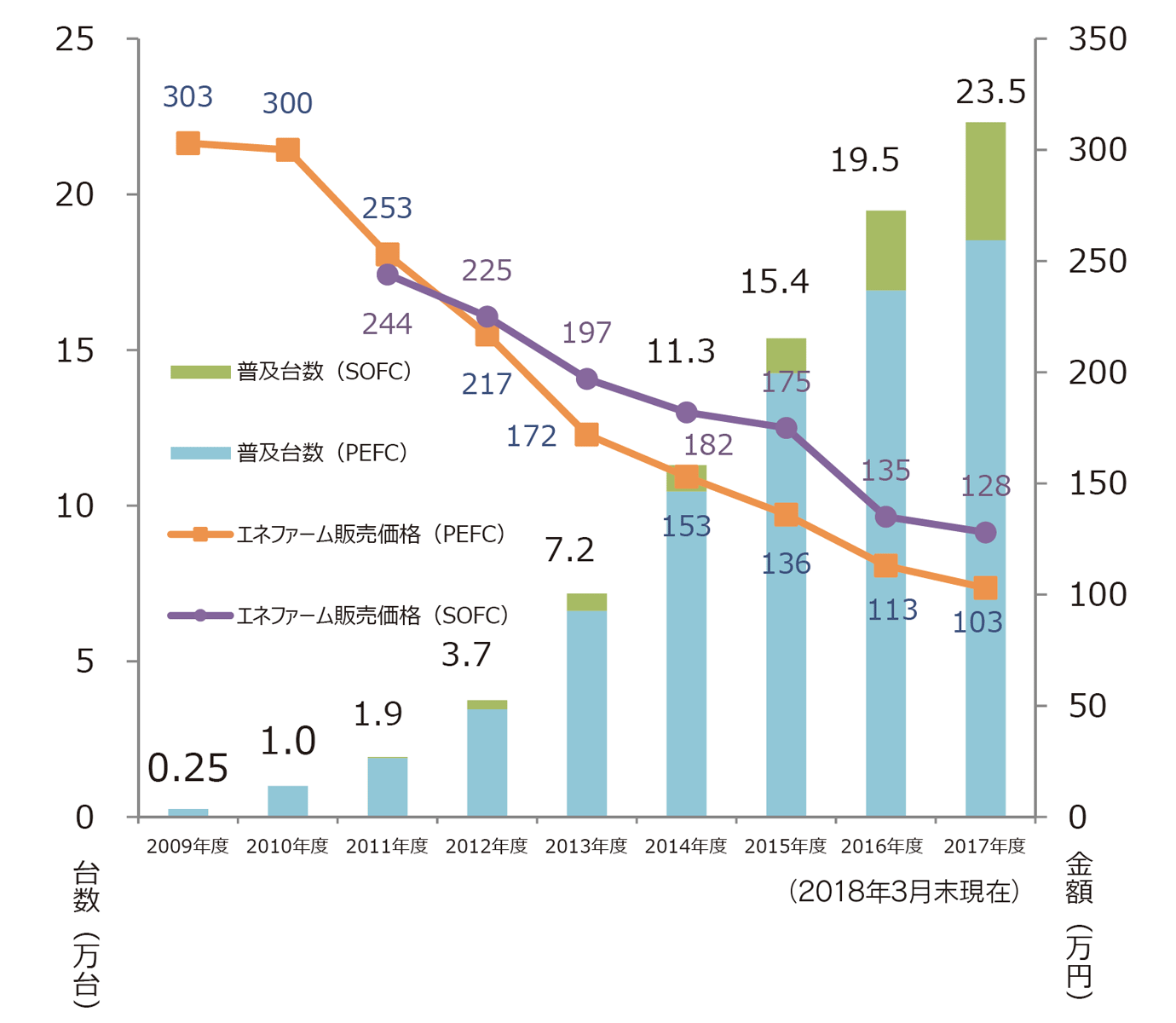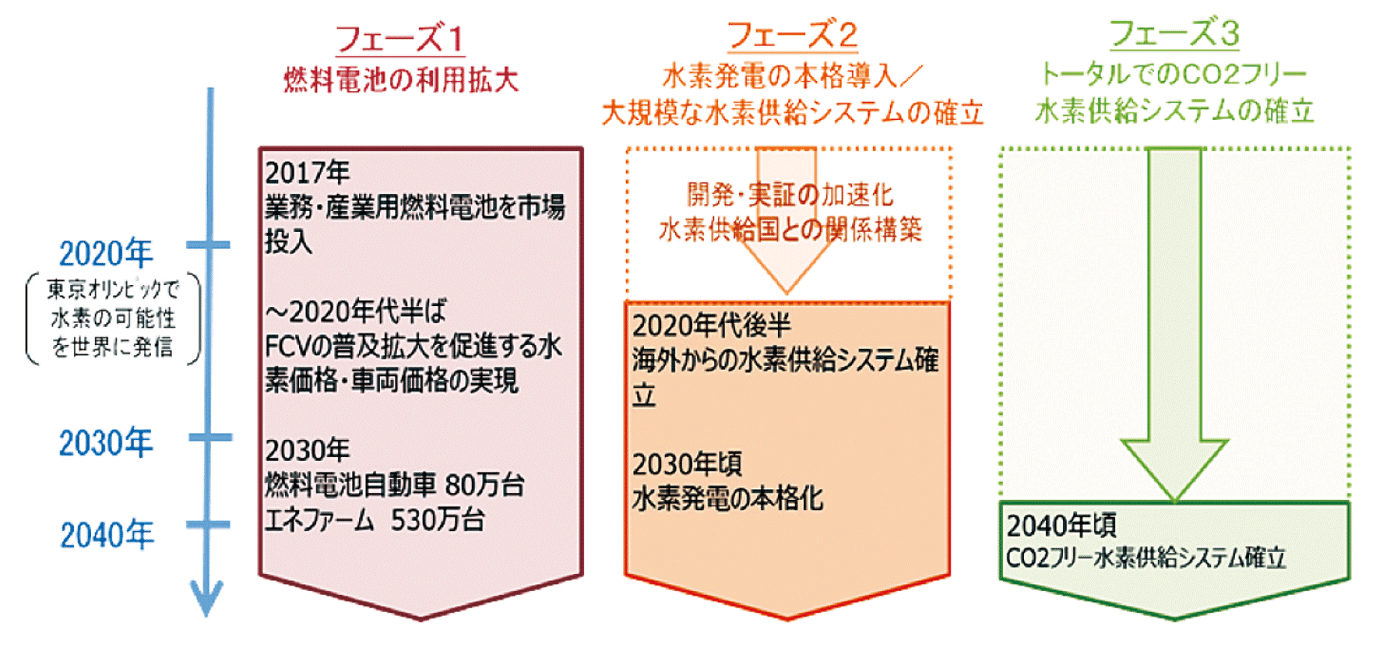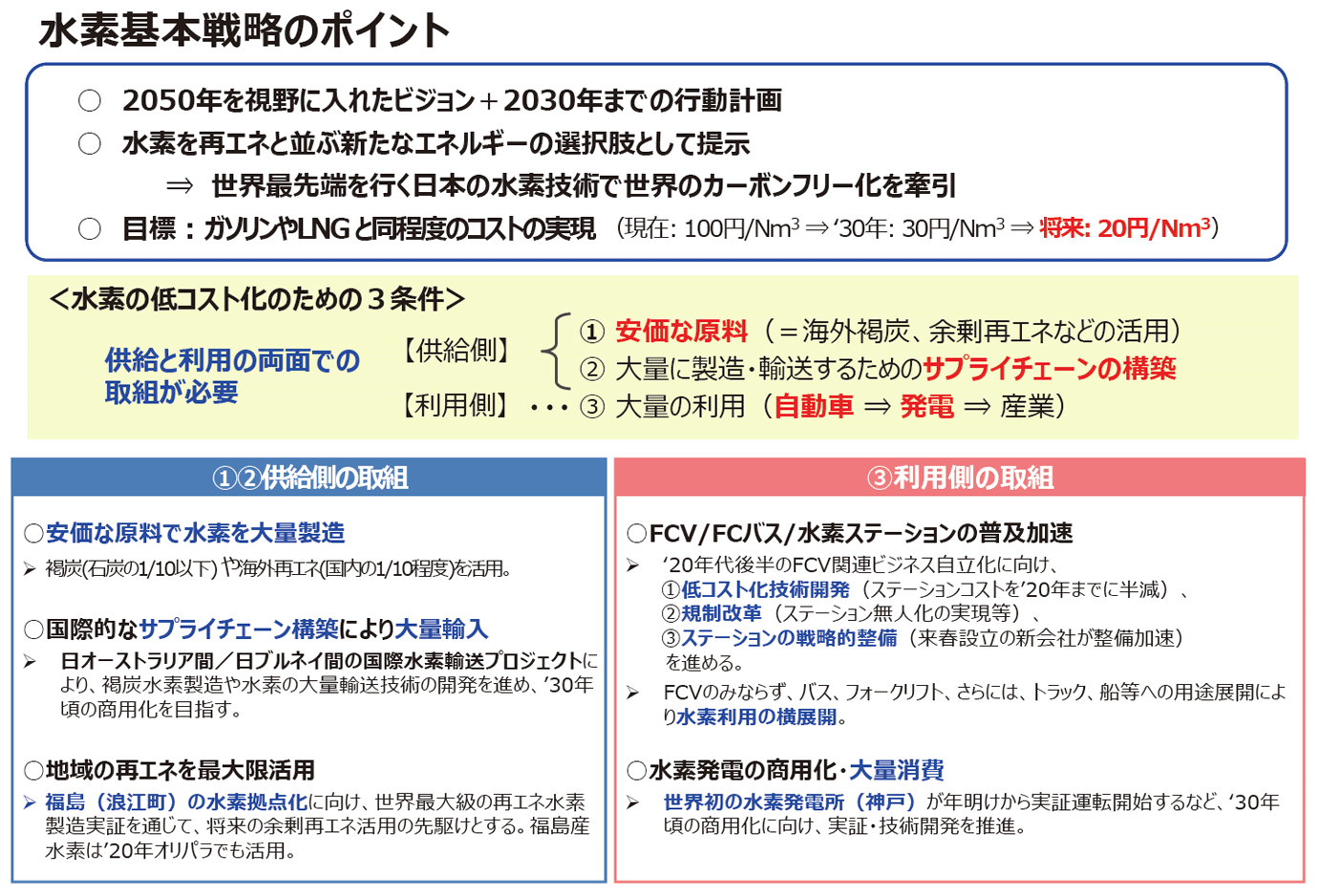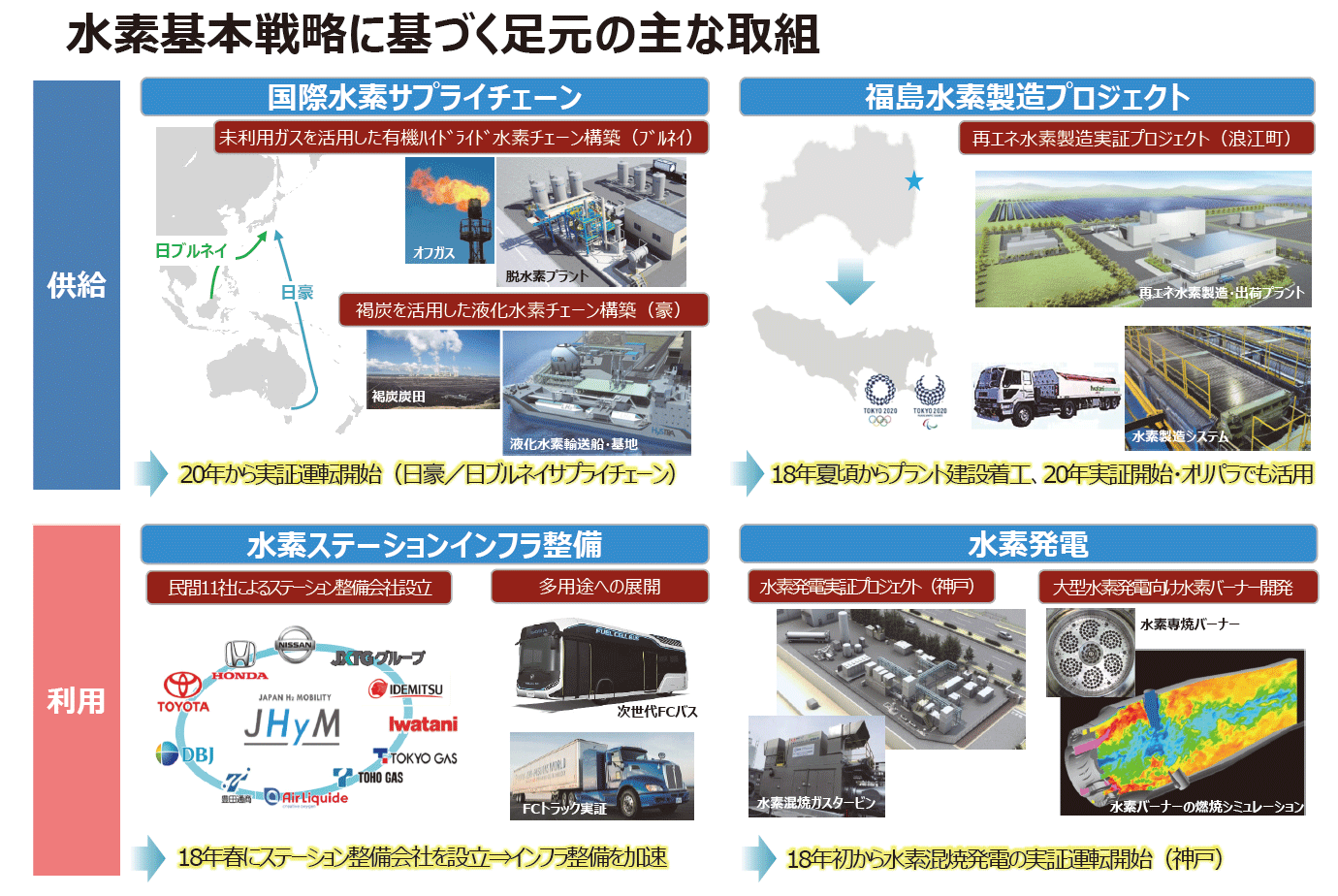第6節 2010年頃~
2011年、我が国のエネルギー政策転換の契機となる東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故が起きました。その後、2014年4月に閣議決定されたエネルギー基本計画(以下、「第四次エネルギー基本計画」)は、我が国の全ての原子力発電所が停止し、化石燃料への海外依存度の増加、エネルギーコストの上昇、CO2排出量の増大等、我が国のエネルギーを取り巻く環境が厳しい中で、こうした問題に適切に対応しつつ、中長期的に我が国の需給構造に関する脆弱性の解決を図っていくための、エネルギー政策の方向性を示したものです。
第四次エネルギー基本計画では、我が国が抱える構造的課題と東京電力福島第一原子力発電所事故及びその前後から顕在化してきた課題を抽出した上で、エネルギー政策の基本方針として、これまでの「3E(Energy Security、 Economic Efficiency、Environment)」という基本的視点に、安全性の確保「S(Safety)」の重要性、国際的な視点の重要性、経済成長の視点の重要性について加味しています。
さらに、第四次エネルギー基本計画を踏まえ、2015年7月、経済産業省として、長期エネルギー需給見通し(以下、「エネルギーミックス」という。)を決定しました。エネルギーミックスは、安全性、安定供給、経済効率性、環境適合(3E+S)について達成すべき政策目標を想定した上で、施策を講じたときに実現されるであろう将来のエネルギー需給構造の見通しであり、あるべき姿を示すものです。エネルギーミックスの実現に向けて、徹底した省エネルギー、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担抑制の両立、火力発電の高効率化、安全性の確認された原発の再稼働などを進めています。
1.電力・ガスシステム改革
(1)電力システム改革
2015年度からの第五次制度改革(電力システム改革)の第1段階として、改正電気事業法に基づき広域的運営推進機関(認可法人)が創設され、全電気事業者の加入が義務付けられました。同機関を司令塔として、地域を超えた電気のやりとりを容易にし、災害時等に停電を起こりにくくすること、また、全国規模での需給調整機能の強化等により、出力変動の大きい電源の導入拡大等に対応することなどが行われています。
また、同年9月には、電力市場において健全な競争が促されるよう、電力市場の監視機能を強化するため、経済産業大臣直属の組織として、電力取引監視等委員会(2016年4月に電力・ガス取引監視等委員会に改組)が設立されました。同委員会において、適正な取引が行われているか厳正な監視が行われているほか、必要なルール作りなどに関して経済産業大臣に対し意見・建議が行われています。
2000年度以降、段階的に電力の小売自由化が実施されてきましたが、第五次制度改革の第2段階として、2016年4月からは全面的な小売自由化が実施され、一般家庭を含むすべての需要家が電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになりました。
そして、今後、電力市場における活発な競争を実現するうえで、送配電ネットワーク部門を中立化し、適正な対価(託送料金)を支払ったうえで、誰もが自由かつ公平・平等に送配電ネットワークを利用できるようにすることが必須です。他方現行の会計分離では、発電と送配電間の社内でのやりとりが法人間の契約として明確にならず、外部からの検証が難しいことや託送ルールが適用されない等の問題があるため、第五次制度改革の第3段階として、2020年には送配電の法的分離が行われ、送配電部門の中立性を高めていくなどの改革が行われます。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
- (注)
- 需要家保護のため、経過措置として、少なくとも2020年まで料金規制を残す(需要家は規制料金も選択可能)。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
- 出典:
- 資源エネルギー庁
(2)ガスシステム改革
① ガスシステム改革の4つの目的
今般のガスシステム改革では、(i)天然ガスの安定供給の確保、(ii)ガス料金の最大限抑制、(iii)利用メニューの多様化と事業機会拡大、(iv)天然ガス利用方法の拡大、の4つを主要な目的に据えました。
具体的には、(i)天然ガスの安定供給の確保については、一般ガス導管事業者に対して導管網の建設・保守、最終保障サービスを義務付けることや、導管網の整備・相互接続を促進することで、安定供給を確保することを目指すこととしています。(ii)ガス料金の最大限抑制については、事業者間の競争や、他業種・他地域からの参入を促し、創意工夫や経営努力を引き出すことで、ガス料金を最大限抑制することとしました。(iii)利用メニューの多様化と事業機会拡大については、新しい発想を持つ事業者の参入を促し、一般家庭や企業を含めた全てのガスの利用者が自由に供給者を選択できるようにするとともに、導管網の整備・相互接続を促進することで選択肢・事業機会を拡大することを目指すこととしています。(iv)天然ガス利用方法の拡大については、潜在的なニーズを引き出すサービス、燃料電池やコージェネレーションなど新たな利用方法を提案できる事業者の参入を促進すること等で、天然ガス利用方法の拡大を図っていきます。
② ガスシステム改革のスケジュール
上記の4つの目的を達成するため、ガスシステム改革は、小売参入の全面自由化、導管部門の一層の中立化の2つを段階的に行うこととしています。
旧一般ガス事業者25にしか認められていなかった家庭等へのガスの供給について、2017年4月から小売の地域独占を撤廃し、登録を受けた事業者であればガスの小売事業への参入が可能となりました。これにより、家庭を含めた全てのガスの利用者がガス供給者を選択できるようになりました。
また、ガス市場における活発な競争を実現するためには、導管部門を中立化し、適正な対価を支払った上で、誰でも自由かつ公平・平等にガス導管ネットワークを利用できるようにすることが必須となります。そこで、導管部門の中立性の一層の確保を図るため、2022年4月以降、導管総距離の長い大手3社(東京ガス、大阪ガス、東邦ガス)を対象に、ガス製造事業・ガス小売事業と一般ガス導管事業の兼業を原則禁止することを予定しています。なお、導管会社がグループ内の小売会社を優遇して、小売競争の中立性・公平性を損なうことのないよう、人事などについても適切な「行為規制」を講ずることとしています。
2.東京電力福島第一原子力発電所事故の反省と原子力政策の再構築
2011年、東日本大震災にともなう東京電力福島第一原子力発電所の事故が発生し、深刻な被害をもたらすことになりました。
いわゆる「安全神話」に陥って、このような悲惨な事態を防ぐことができなかったことへの深い反省に立ち、政府は、福島の復興・再生を全力で成し遂げ、震災前に描いてきたエネルギー戦略を白紙から見直しました。責任あるエネルギー政策を構築するため、総合資源エネルギー調査会における議論と、パブリックコメントを通じていただいた国民の御意見等を踏まえ、2014年4月には、「第四次エネルギー基本計画」を閣議決定しました。同計画では、「原発依存度を可能な限り低減すること」「安全を最優先した上で再稼働する」ことを謳っています。
このような動きと前後して、①原発依存度の低減、②安全・災害対策、③使用済み燃料対策、④福島復興と廃炉・汚染水対策、といった諸課題について、原子力関係閣僚会議、最終処分関係閣僚会議を開催し、政府一体となってこれらを解決していくという姿勢を明確にしました。
また、2012年9月には、東京電力(株)福島第一原子力発電所事故を踏まえ、原子力利用の推進と規制を分離し、原子力安全に関する規制を一元化した上で、専門的な知見に基づき中立公正な立場から原子力安全規制に関する職務を担う独立した機関として原子力規制委員会が設置されました。
こうした中、2017年度末において、震災後に一度全ての原発が停止して以来、再稼働を果たした原発は7基あり、新規制基準に適合することが認められた原発が14基、原子力規制委員会の審査中の原発が12基になります(2018年3月31日時点)。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
- 出典:
- 資源エネルギー庁
3.震災発生を契機とした災害対応能力の強化~製油所等の強じん化と中核SSの整備開始~
(1)東日本大震災の発生とエネルギー供給の脆弱性の露呈
2011年3月11日に発生した東日本大震災は、国内観測史上最大規模の地震であり、大規模な津波を伴って、東北地方を中心に我が国に未曽有の大災害をもたらしました。東日本大震災の発生は、災害時における我が国のエネルギー供給の脆弱性を露呈させ、根本的なエネルギー政策の見直しの必要性を認識させることとなりました。
石油関連施設については、東北地方唯一の製油所であるJX日鉱日石エネルギー株式会社の仙台製油所をはじめとする6製油所が被災するとともに、東北太平洋岸の油槽所のほとんどが出荷不能に陥りました。このため、石油製品の在庫は十分あったにもかかわらず、港湾や道路の損壊といった社会インフラの麻痺やタンクローリーの被災と相まって、被災地域への石油供給に大きな支障を来しました。また、サービスステーション(SS)についても津波の影響で給油設備が被害を受けたこと等により、東北地方を中心とする多くの地域において、SSが営業を停止せざるを得ない状況となりました。
(2)東日本大震災の教訓を踏まえた災害対応能力の強化
こうした東日本大震災の教訓を踏まえ、災害時においても石油の安定供給を確保することができるよう、石油備蓄法の改正や製油所・油槽所、SSの強靭化等による災害対応能力の強化を行っています。
① 石油備蓄法の改正
東日本大震災では、石油供給網が広範囲にわたって被災し、石油の安定供給に支障を来しましたが、改正前の石油備蓄法は、国内災害の発生による石油の供給不足に対応できる枠組みとなっていませんでした。このため、2012年に石油備蓄法を改正し、国内災害の発生による特定地域への石油の供給不足時にも対応できるよう、備蓄放出の発動要件を見直すとともに、災害時に石油元売り各社が系列の枠を超え、連携して石油供給を行う「災害時石油供給連携計画」の届出制度の導入等の措置を行いました。
② 製油所・油槽所の強靭化
2013年に実施した石油コンビナート敷地全体における地盤の液状化や設備等の耐震性能等を調査した「コンビナート耐性総点検」の結果等を踏まえ、首都直下地震等の大規模災害が発生した場合でも、適切な石油の供給が確保されるよう、①設備の耐震・液状化対策等や、②設備の安全停止対策、③他地域の製油所とのバックアップ供給に必要な入出荷設備の増強対策等を支援しています。
③ 中核SSの整備
東日本大震災では、停電等で多くのSSが稼働停止に追い込まれたことから、石油製品の供給に支障が生じ、救援活動や復旧活動等に影響を与えました。この東日本大震災の教訓を踏まえ、全国的な防災、減災の観点から、地域における石油製品の供給体制の災害対応力を強化していくことが重要とされました。そのため、自家発電機を備え、災害発生時にはパトカー、救急車といった緊急車両等に優先給油を行う中核SSを全国に約1,600か所整備しました。
(3)熊本地震の発生と対応
2016年4月に発生した熊本地震では、東日本大震災後に整備した制度を活用し、製油所、油槽所、SS等の石油供給インフラの被災状況把握、被災地からの燃料供給要請への対応、石油供給網の回復等に取り組みました。具体的には、被災地への燃料供給に万全を期するため、経済産業大臣が石油元売会社に対して、制度の導入後初となる「災害時石油供給連携計画」の実施を勧告しました。石油元売各社では、直ちに石油インフラの被災状況等の現地情報収集を開始し、被災地からの燃料供給要請に対して迅速に対応する体制を整えました。また、被災地においては、中核SSが発災後速やかに営業を再開し、警察・消防等の緊急車両や災害復旧車両に対する優先的な石油供給が行われるとともに、石油元売各社は、タンクローリーを増強し、中核SSへの燃料供給を優先的に行いました。こうした取組によって、熊本地震においては概ね石油供給が円滑になされました。他方で、一部のSSでは、発災後、熊本市内など都市部において、SSの営業停止や渋滞による配送遅延の影響で、パニックバイのような事態が発生しました。このため、災害時に地域住民の燃料供給拠点となる「住民拠点SS」の整備や災害発生後から迅速にSSの稼働状況等の把握や被災者への情報発信を行う体制整備が必要となり、現在、その整備を行っているところです。
4.LNG取引の柔軟性向上に向けて~シェールガス革命の進展等によるLNG市場の拡大~
(1)我が国におけるLNGの重要性
1969年、アラスカから初めて我が国にLNG(液化天然ガス)の輸入が実現されてから50年弱が経過し、我が国は今なお、年間8,000万トン超を輸入する世界最大のLNG輸入国です。LNGは、石油に比べて調達における地政学的リスクも相対的に低く、また温室効果ガスの排出が最も少ない化石燃料でもあり、我が国の中心的な発電燃料として位置づけられてきました。
特に、2011年の東日本大震災以降は、原子力発電所の稼働停止等により、LNG火力発電所の稼働率が上昇し、その役割の重要性がますます高まりました。震災直後は大量のLNGをスポット取引等により追加的に輸入しましたが、当時の原油高の影響を受けた事に加え、LNG需要の急増による市況のタイト化により、結果として我が国は欧米諸国に比べて高値の天然ガスを輸入せざるを得ず、震災前に6.6兆円の黒字であった通関ベースでの貿易収支が、2011年には2.6兆円の赤字に転落する等、結果として経常収支の大幅悪化につながりました。
(2)LNG取引を巡る国内外の環境変化
他方、2000年以降、LNGを巡る国際環境は大きく変化しています。
2000年代後半に米国で生じたシェール革命は、米国のエネルギー需給の変動を引き起こし、米国をエネルギー輸入国から輸出国へと転換させるインパクトをもたらしました。2016年から米国からシェールガス由来のLNGの輸出が開始され、我が国にも2017年に初めて輸入されました。これまでのLNG供給の担い手は、東南アジアや中東の国営企業の存在感が大きかったものの、今後こうした国々からの輸出は減少または横ばいとなる見通しであり、米国や豪州といった新たなLNG供給国からの輸出が拡大し、こうした国々の市場指向型の企業が国際的なプレゼンスを高めていく見込みです。
一方、世界的に地球温暖化対策に対する関心が高まる中、比較的クリーンな発電燃料であるLNGの重要性が高まっており、グローバルなLNG需要も今後拡大する見込みです。世界のLNG需要は、現状の約2.5億トンから2020年までに約45%増加し、3.5億トンに迫ることが見込まれています。特に、インドや中国の旺盛な需要が続き、マレーシアやインドネシアといった伝統的な輸出国も輸入国に転じるなど、アジアが世界の需要拡大をけん引すると見込まれています。また、欧州や中東、中南米等の輸入も今後増加する見込みです。
我が国においても、2016年4月から開始された電力市場の小売全面自由化と2017年4月から開始されたガス市場の小売全面自由化は、世界最大の買い手である我が国の電力・ガス企業の調達行動に大きな変化を促すことが予測されます。具体的には、不透明化する自社のエネルギー需要見通しの下で、より柔軟かつ多様なLNG調達の選択肢(例:調達先、調達期間、価格フォーミュラ等)を求めることとなります。加えて、再生可能エネルギー電源の導入拡大等により、発電向けのLNG需要についてはさらに不確実性が高まります。さらに、自由化した電力市場やガス市場では、LNG調達価格が競争力に直結します。こうした変化に適応するため、我が国の企業は、調達量・調達価格の適切な管理や価格ヘッジの手段として、「流動性の高い市場」の活用をより強く指向するようになってきています。また、長期契約でコミットした調達量が需要を上回るケースが発生し、一部の買い手がスポットの売り手となってLNGを国内外へ転売するケースが増える可能性もあります。その結果、多様なプレーヤーが「市場」から短期・スポットでの調達を行うことと組み合わせた新たなモデルへと移行していく可能性が高まっています。
- ※
- シナリオ1:新規火力に占めるガス比率15%、シナリオ2:同30%、シナリオ3:同60%
- 出典:
- ERIA資料を基に資源エネルギー庁作成
(3)LNG市場戦略
2016年5月、経済産業省は「LNG市場戦略」を策定し、柔軟かつ透明性の高い国際的なLNG取引市場の実現に向けた取組方針を発表しました。この中で、LNGの流動性の向上のためには、「LNGの取引の容易性(Tradability)」、「適切な価格発見メカニズムの構築(Price Discovery)」、「オープンかつ十分なインフラ(Open Infrastructure)」の3つの要素を備えることが重要であり、官民が協力してこの実現に取り組むべきとの方向性が示されています。
これに基づき、例えば、主要な国際会議における仕向地制限26の撤廃等に関する働き掛け、「LNG産消会議」における価格アセスメントの信頼性向上に向けた価格報告機関の取組等の紹介、LNG基地の第三者利用制度の開始等に取り組んでいます。特に、アジア地域におけるLNG需要を拡大する観点から、2017年10月に開催したLNG産消会議において、世耕経済産業大臣より、①官民で100億ドル規模のLNG関連インフラ整備のためのファイナンスを我が国が用意することや、②今後5年間で500人規模のLNGに関する人材育成の機会を提供することを発表しました。
また、指標の信頼性、透明性向上を目指して、2017年4月にLNG現物市場が東京商品取引所で開設されました。さらに、2017年6月、公正取引委員会は液化天然ガスの取引実態に関する調査報告書をまとめ、一定の場合には仕向地制限等が独占禁止法上問題となるおそれがある、との見解を発表しました。柔軟かつ透明性の高いLNG市場の構築に向けた取組は、省庁間の垣根を越え、また官民双方の努力により、着々と進展しています。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
5.徹底した省エネの推進~震災後の対応やパリ協定に係る新たな地球温暖化対策に向けた課題~
(1)エネルギー基本計画とエネルギーミックス
2011年の東日本大震災以降、我が国は、①電力供給における海外からの化石燃料への依存度の増加、②原子力発電所停止等による燃料費の増加、③電気料金の上昇、④CO2排出量の増加など、エネルギーを巡る様々な制約や課題に直面しました。こうした環境変化に対応するため、安定的で社会の負担の少ないエネルギー供給を実現するエネルギー需給構造を実現するための方策が検討されました。
省エネについては、まず、東日本大震災以降の電力需給の状況を踏まえ、エネルギー消費効率の向上だけでなく、蓄電池やエネルギー管理システムの活用など、需要側による電力ピーク対策を円滑化する措置を講じることが重要となりました。
そこで、2013年に省エネ法を改正し、電力ピーク時間帯における電力使用量を低減する取組を適正に評価できる措置(電気需要平準化に関する措置)を新たに導入しました。また、民生部門の省エネ対策を一層進めるため、トップランナー制度の対象を建築材料に拡大しました。
また、2014年には、震災後初のエネルギー基本計画として、第四次エネルギー基本計画が閣議決定され、省エネについては、省エネ法の規制体系に基づき、部門ごとに効果的な方法によって省エネ取組をさらに加速していくことで、より合理的なエネルギー需給構造の実現と温室効果ガスの排出抑制を同時に進め、徹底した省エネルギー社会を実現するとの基本的な方向性が掲げられました。
翌2015年には、第四次エネルギー基本計画を踏まえ、エネルギーミックスが策定され、省エネについては、2013年度実績から2030年度まで年1.7%の経済成長等によるエネルギー需要の増加を見込みながら、具体的な裏付けのある対策・施策、技術の積み上げに基づく徹底した省エネ対策により、年間最終エネルギー消費を対策前に比べ原油換算5,030万kl程度、13%削減することとされています。これは、2013年から2030年度までに、エネルギー消費効率(=最終エネルギー消費量/実質GDP)を35%程度改善することに相当し、石油危機後の20年間に我が国が実現した省エネと同程度のエネルギー消費効率の改善が必要となります。
この省エネ対策は、2015年のCOP21におけるパリ協定の締結を控え、国際的な地球温暖化対策をリードすべく、欧米と遜色ない温室効果ガス削減目標を掲げることも見据えた野心的な対策としており、2016年に発効した「パリ協定」における日本の中期削減目標(2030年度に対2013年度比でCO2排出量を26%削減)とも整合的な対策としています。
(2)エネルギーミックスで掲げる2030年度の省エネ見通しの実現に向けて
エネルギーミックスの実現に向けて、エネルギー投資の拡大を通じた経済成長とCO2排出抑制を両立させるため、「技術の革新」「プレーヤーの革新」「仕組みの革新」を新たな視点として的確に捉えつつ、省エネ、再エネをはじめとする関連制度を一体的に整備する「エネルギー革新戦略」を2016年に策定するとともに、具体的な検討を、審議会(総合資源エネルギー調査会 省エネルギー小委員会)において進め、2017年8月に提言(「省エネルギー小委員会 意見」)が取りまとめられました。
当該提言を踏まえつつ、エネルギーミックスで掲げる省エネ見通しの実現に向けて、製造業や貨物輸送等の省エネを進めるための課題に対応するため、①同業種やサプライチェーン上の複数企業の連携による省エネの推進、②ネット小売事業者を省エネ法の荷主規制の対象に確実に位置づける、等を柱とした省エネ法の改正法案(エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律案)を2018年3月9日に閣議決定し、同日、第196回国会に提出しました(第1部第3章参照)。
また、製造業や貨物輸送以外の、足下では比較的順調に省エネが進んでいる事務所・オフィスや家庭についても、エネルギーミックスの実現にはさらなる省エネ取組が必要となります。そこで、引き続き、①業種ごとにエネルギー消費効率の目標を定めて省エネを促す産業トップランナー制度の流通業・サービス業への拡大、②省エネ法のトップランナー制度等による家電や自動車等のさらなる機器効率の向上、③住宅・建築物のゼロ・エネルギー化、などの取組を進めていきます。
エネルギー資源の大部分を海外に頼る我が国は、限られた燃料資源の有効な利用を図ることが不可欠です。引き続き、省エネ法による制度措置と補助金や税などの支援措置の両輪で、エネルギーミックスにおける野心的な省エネ対策の実現によるエネルギー消費効率の改善に向けて、着実に取り組んでいきます。
【第116-5-1】エネルギーミックスにおける最終エネルギー需要と効率改善の見通し
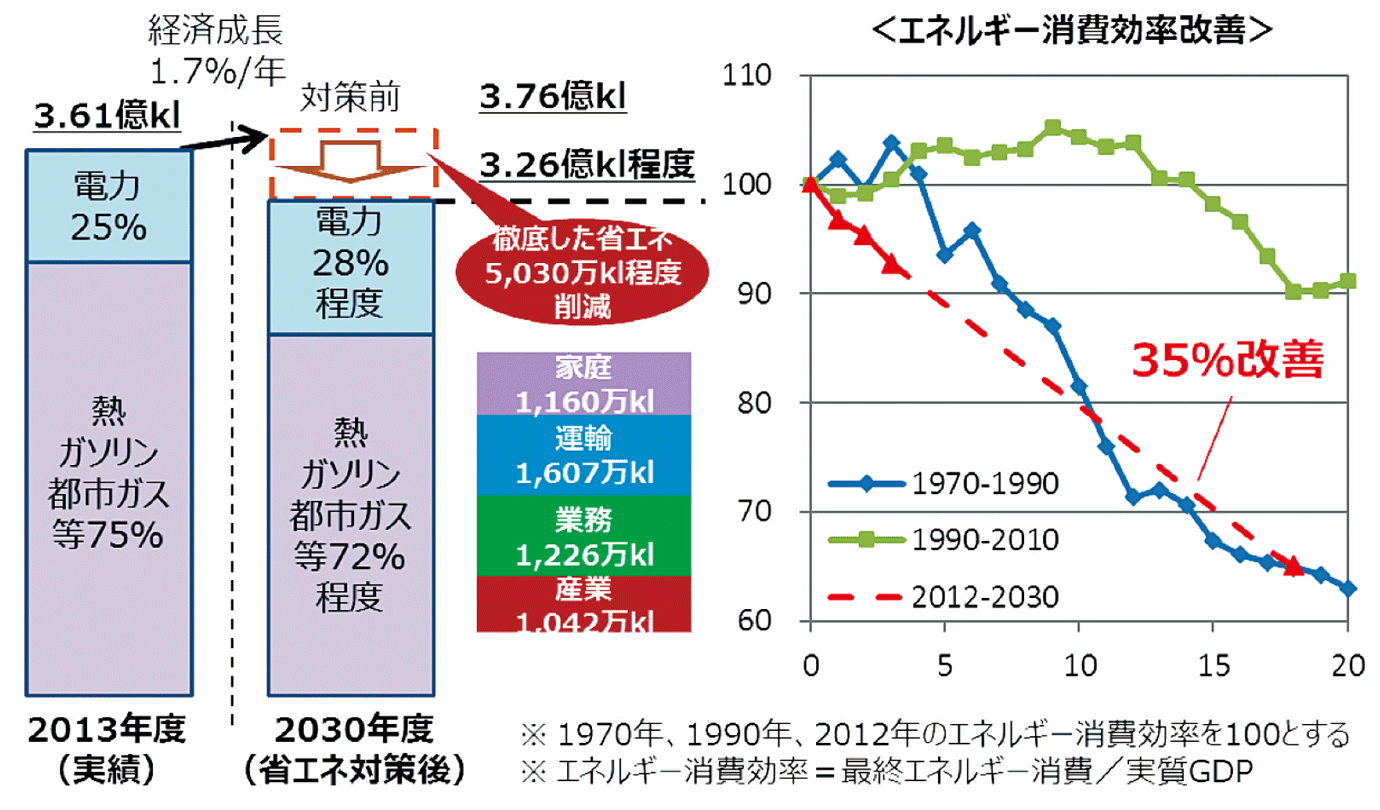
- 出典:
- 資源エネルギー庁
- 出典:
- 資源エネルギー庁
6.再生可能エネルギーの導入の加速~固定価格買取制度の開始~
(1)固定価格買取制度の開始
2000年代も半ばを過ぎると、環境問題への関心の高まりもあり、世界各国の再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)技術開発や導入拡大の取組が加速します。再エネの導入拡大を加速させた代表例はドイツです。ドイツは2000年代半ばに太陽光導入量で日本を追い抜き世界一になったのちも再エネ導入拡大を続け、2016年には水力を除いた再エネの電源構成に占める割合は27.7%に達しています。ドイツの再エネ導入拡大の一要因として挙げられるのが、世界にさきがけて1990年より導入をはじめた固定価格買取制度(FIT制度)です。FIT制度は、再エネ(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)によって発電された電気を、国が定める一定の期間にわたって、国が定める一定の価格で電気事業者が調達することを義務づけるものです。電気事業者が調達した再生可能エネルギー電気は、電気事業者の送電網を通じて広く利用されるため、調達に要する費用は、再生可能エネルギー発電促進賦課金により電気料金の一部として、電気の使用者が負担します。本制度により、再生可能エネルギー発電設備を設置する者のコスト回収の見通しが立ちやすくなるとともに、普及が進むことで、スケールメリットによるコストダウンが期待されるのです。FIT制度はドイツの取組をうけて2005年以降世界各国で導入が進み、2010年までに少なくとも60か国が導入しています。
日本でも2000年代後半から検討を開始し、2009年には太陽光の余剰電力に限定して導入を開始しました。さらに、2010年のエネルギー基本計画では、FIT制度が世界各国で再エネ導入拡大に寄与している点を指摘し、実用化されている全エネルギー(太陽光、風力、中小水力、地熱、バイオマス)を対象に日本でも制度を構築すると明記しました。そして、2012年に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)」に基づいて「FIT制度」が開始されました。
本制度は、調達価格と調達期間については、国会の同意を得た上で任命される委員から構成される調達価格等算定委員会の意見に基づき、関係大臣(農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣、消費者担当大臣)への協議等を経た上で、経済産業大臣が毎年度告示することが定められました。
【第116-6-1】「長期エネルギー需給見通し」(2015年度)における2030年電源構成
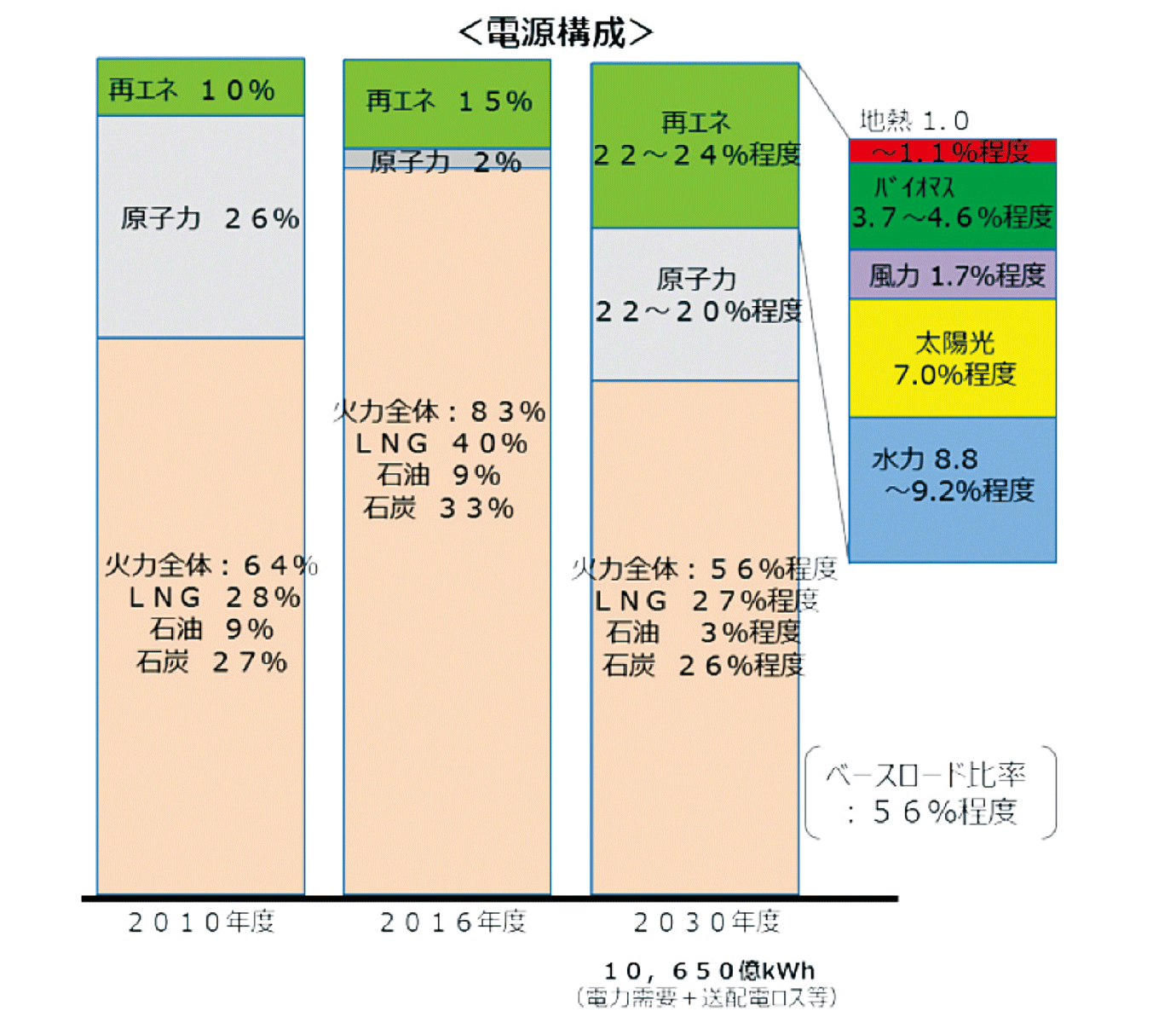
- 出典:
- 資源エネルギー庁
(2)エネルギー基本計画での位置づけ
東日本大震災を経て、内閣総理大臣指示の下エネルギー・環境戦略のゼロベースでの見直しが行われ、2014年度にエネルギー基本計画が閣議決定されました。同計画では、「再エネは温室効果ガスを排出せず、国内で生産できることから、エネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、重要な低炭素の国産エネルギー源」と位置付けられ、再エネの「導入を最大限加速」することが明記されました。また、同計画をふまえて2015年度に策定された「長期エネルギー需給見通し」では2030年度再エネ水準22~24%が設定され、官民で共有されるようになりました。さらに、目標達成にむけて政府全体の司令塔機能を強化するために2014年に再生可能エネルギー等関係閣僚会議が設置され、2017年には今後5年間の具体的なアクションプランがとりまとめられました。
(3)FIT法の改正と再エネ大量導入時代の幕開け
FIT制度については、2030年度導入水準達成に向けて最大限の導入と国民負担の両立の観点から、2016年に改正を行いました。改正FIT法においては、①新認定制度の創設、②中長期的な価格目標の設定や入札制度等コスト効率的な再生可能エネルギーの導入を促す仕組みの導入、③リードタイムの長い電源の導入拡大のための複数年買取価格の設定、④減免制度の見直し、⑤送配電買取への移行等を盛り込みました。こうした制度改正を伴いつつも、制度開始から約5年で再エネ導入量は2.7倍に拡大し、着実に再エネ導入拡大に寄与しています。
また2017年には「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」を設置するなど、再エネの大量導入に伴い顕在化し始めた系統制約や調整力確保等の新たな課題の解決に向けた議論も本格化し、再エネ大量導入時代の幕があけています。
- 出典:
- 資源エネルギー庁(JPEA出荷統計、NEDOの風力発電設備実績統計、包蔵水力調査、地熱発電の現状と動向、PRS制度・固定価格買取制度認定実績等より資源エネルギー庁作成)
7.”水素社会”の実現に向けた取組の加速~ロードマップ・基本戦略の策定~
家庭用燃料電池(エネファーム)・燃料電池自動車(FCV)の商用化とその後の普及拡大によって水素技術普及への道が開けました。家庭用燃料電池については、技術開発によるコスト低減や性能向上、導入支援による普及初期の市場の確立などを通じて、2018年3月には約23.5万台が普及しました。また、2013年から燃料電池自動車の市場投入に向けた水素ステーションの先行整備が開始され、2018年3月末までに約100か所の水素ステーションが開所しました。さらに、2014年12月に国内初の燃料電池自動車の市販が開始されたことに続き、2016年3月には2車種目の燃料電池自動車の販売が開始され、我が国では世界に先駆けて市場展開が進んでいます。
こうした中、2014年の第四次エネルギー基本計画において「水素社会の実現に向けた取組を加速する」旨が明記されました。
2014年には、第四次エネルギー基本計画に基づき、水素製造、貯蔵・輸送、利用に関わる様々な要素を包含した官民のアクションプランである「水素・燃料電池戦略ロードマップ」を策定しました。その後、様々な取組が進展している最新の状況を踏まえて、2016年3月にロードマップの内容を改訂し、新たな目標設定や取組の具体化を行いました。
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
2017年には、ロードマップの内容を内包しつつ、水素を脱炭素化エネルギーの新たな選択肢として位置づけ、政府全体として施策を展開していくための方針として、「水素基本戦略」を決定しました。同戦略では、水素供給側の取組としては国際的なサプライチェーン構築や再エネ水素製造等について、水素利用側の取組としてはFCV・FCバス・水素ステーションの普及加速や水素発電の商用化等を掲げています。(第3部第8章第3節参照)
- 出典:
- 水素・燃料電池戦略ロードマップ(2016年3月22日改訂)
- 出典:
- 資源エネルギー庁
- 出典:
- 資源エネルギー庁