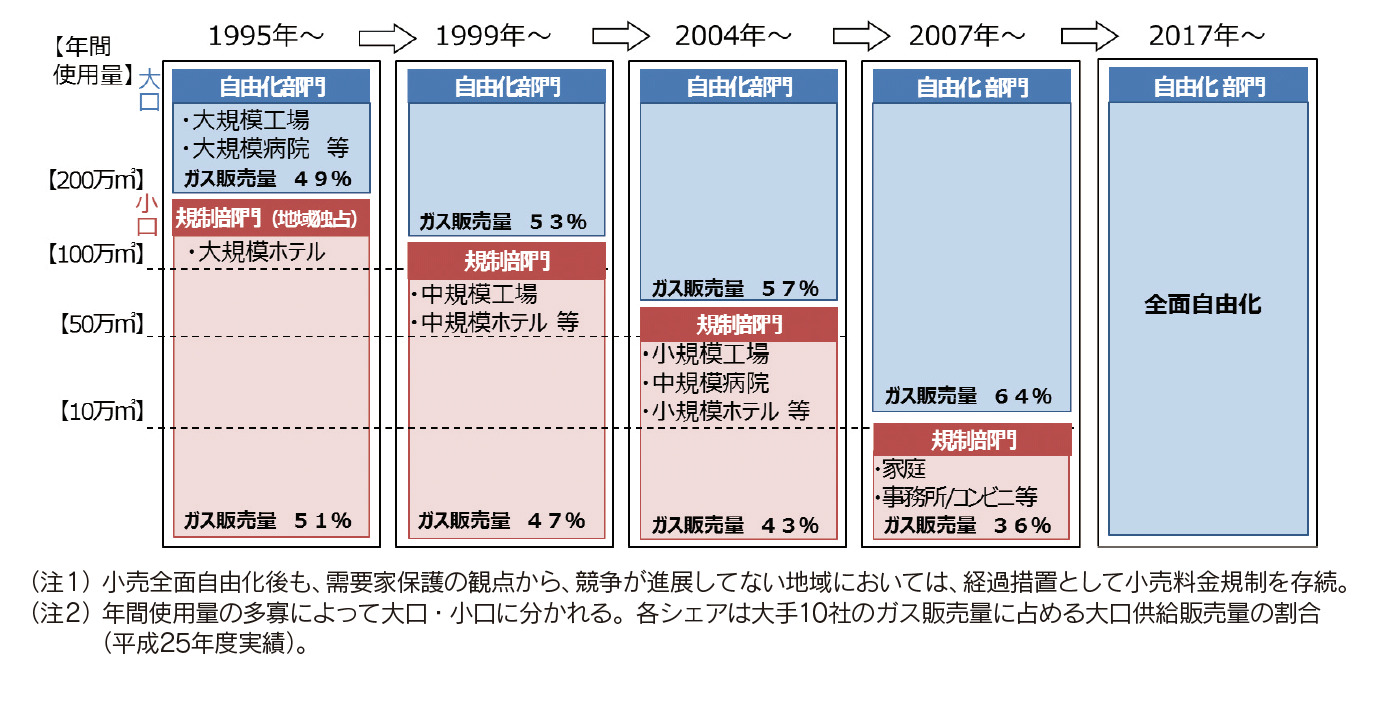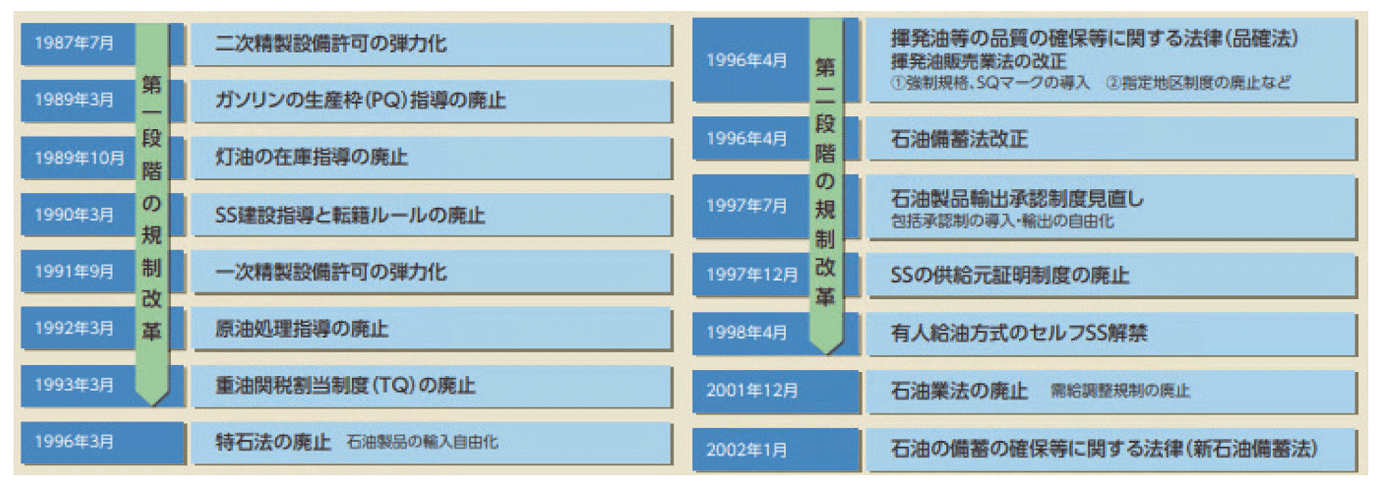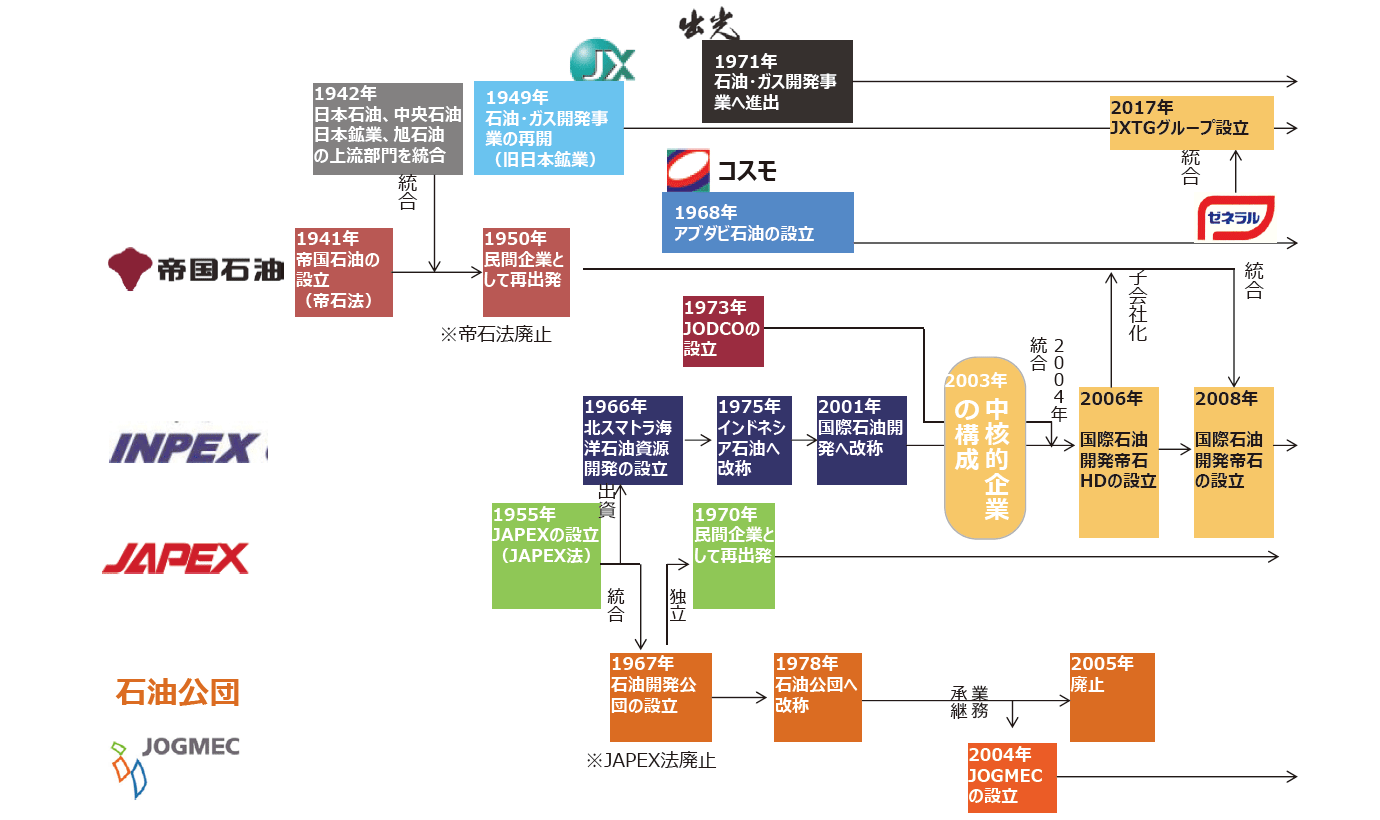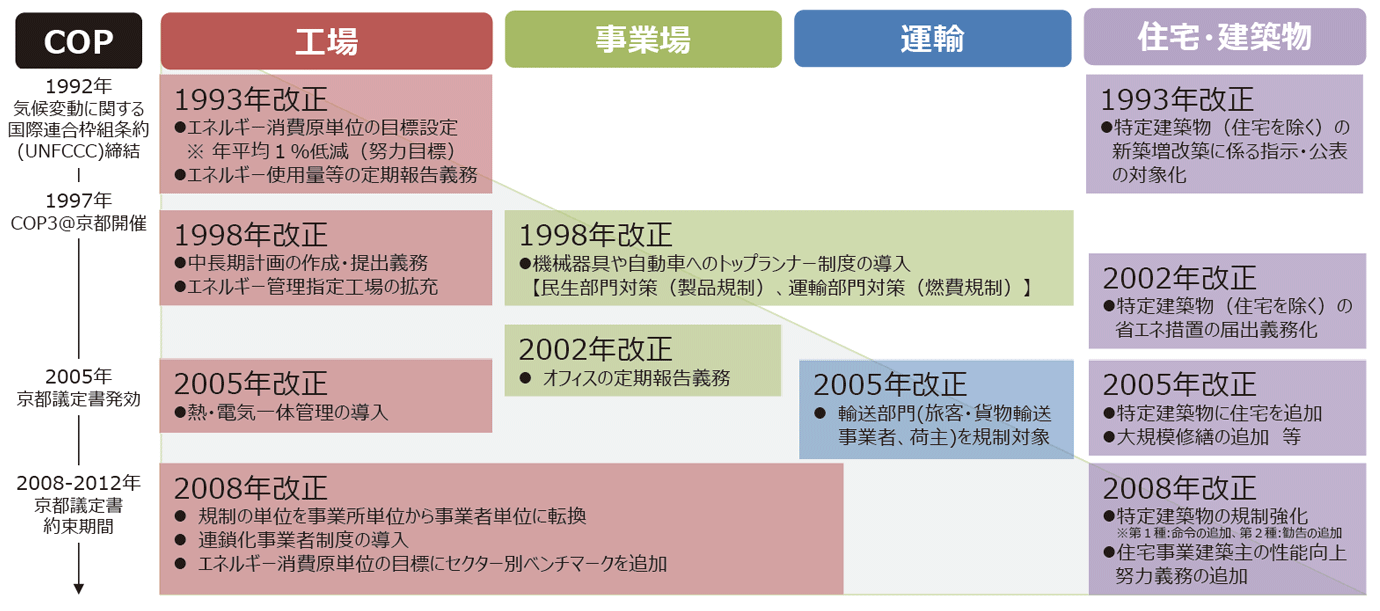第5節 1990年頃~
1.大口部門の段階的な自由化
(1)電気
電気事業制度については、1995年度以降、数度にわたり改革が行われてきました。
1995年度の第一次制度改革では、電力の卸供給を行う独立発電事業者(IPP)制度の導入と電源入札制度の創設、電力会社の料金メニューの多様化(選択約款の導入)等が、1999年度の第二次制度改革では、特別高圧需要家(大規模工場、デパート等)を対象にした自由化の実施や電力会社の料金引下げに係る規制緩和(許可制⇒届出制)等が行われました。
2003年度の第三次制度改革では、卸電力取引市場の整備や高圧需要家(中規模、スーパー等)を自由化対象にするなどが行われました。これにより、我が国の販売電力量の約6割が自由化対象となりました。
2008年度の第四次制度改革では、卸電力取引活性化のための時間前市場の創設、託送料金におけるストック管理制度(超過利潤累積額が一定の水準を超えた場合で、翌々事業開始年度開始日までに値下げ届出がなされない場合には、託送供給約款(料金)に対する変更命令を発動する仕組み)の導入等が行われました。
【第115-1-1】電気事業の段階的な自由化
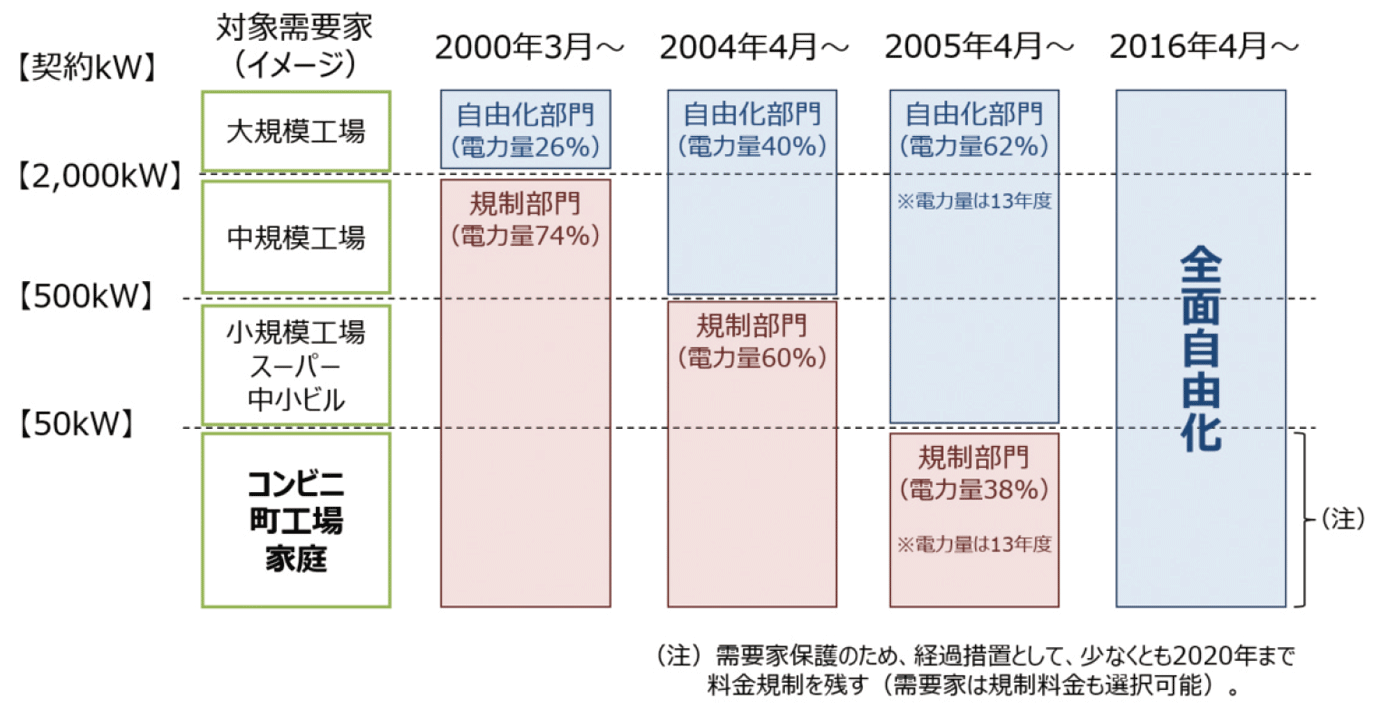
- 出典:
- 資源エネルギー庁
(2)ガス
ガス事業については、1995年、1999年、2004年及び2007年の4度にわたる制度改革が行われています。
1995年の制度改革においては、従来の一般ガス事業者による地域独占を見直し、大口需要家を対象としたガスの小売部分自由化等を実施しました。この制度改革により、年間契約ガス使用量200万m3以上の大口需要家は、ガスの供給者を選ぶことが可能となりました。
1999年の制度改革においては、小売自由化範囲の拡大(年間契約ガス使用量100万m3以上に拡大)、接続供給(託送)制度の法定化、料金規制の見直し(供給約款料金の引き下げについて認可制から届出制へ移行)等を実施しました。また、公正・有効な競争を確保するという観点から、2000年3月、「適正なガス取引についての指針」が制定されました。
2004年の制度改革においては、新たに、ガス導管事業をガス事業法において位置付け、全ての一般ガス事業者及びガス導管事業者に託送供給義務を課すとともに、小売自由化範囲を年間契約ガス使用量50万m3以上まで拡大しました。
2007年の制度改革においては、小売自由化範囲を年間契約ガス使用量10万m3以上まで拡大しました。
これまでの4度にわたる制度改革により、ガス販売量の64%が自由化されていますところ、2017年4月からは家庭などの小口についても自由化が実施されることにより、ガスの小売全面自由化が実現しました。
- (注1)
- 小売全面自由化後も、需要家保護の観点から、競争が進展してない地域においては、経過措置として小売料金規制を存続。
- (注2)
- 年間使用量の多寡によって大口・小口に分かれる。各シェアは大手10社のガス販売量に占める大口供給販売量の割合(平成25年度実績)。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
2.石油の安定的かつ効率的な供給へ~石油産業の規制緩和とエネルギー供給構造高度化法の制定~
(1)第一次規制緩和
1985年12月、一定の秩序の下で特定石油製品(ガソリン・灯油・軽油)の輸入を促進することを目的として、「特定石油製品輸入暫定措置法」が制定されました。一方、特定石油製品の輸入を行う場合には、通商産業大臣の登録を受けることが必要とされており、常圧蒸留装置等の精製設備等の保有を要件としていたことから、実質的に石油精製業者に限定する意味合いをもっていました。
しかし、1980年代後半に入ると、世界的な規制緩和の流れが、石油産業にも及ぶようになってきました。1986年11月、石油審議会石油部会に「石油産業基本問題委員会」を設置し、翌1987年6月に「1990年代に向けての石油産業、石油政策のあり方について」と題する報告書がまとめられ、これに基づき、いわゆる第一次規制緩和が行われました。具体的には、1987年7月の二次精製設備許可の弾力化を皮切りに、ガソリンの生産枠指導の廃止、灯油の在庫指導の廃止、サービスステーション(以下、「SS」という。)建設指導と転籍ルールの廃止、一次精製設備許可の弾力化、原油処理枠指導の廃止、重油関税割当制度の廃止など措置が順次行われました。この第一次規制緩和のプロセスでは、石油業法や揮発油販売業法などが、運用上、平常時においても石油精製・販売活動を競争制限的に規制した点について、一定の見直しが図られました。
(2)第二次規制緩和
第一次規制緩和を経て、石油精製・販売活動においてはある程度競争が活発化されましたが、輸入に関する規制は依然として残されていました。特に、ガソリン、灯油、軽油の輸入については、実質的に、石油精製業者に限定されたままとなっていたことから、石油精製・販売だけでなく、輸入分野にまで競争原理の導入を拡張するため、いわゆる第二次規制緩和が行われました。
1990年代の半ばになると、バブル経済の崩壊や円高の進行などの経済情勢の変化を受けて、公正な競争原理を確保しつつ、安定供給と効率性のバランスのとれた石油製品の供給を実現することがいっそう求められるようになっていきました。こうした中、1993年12月の経済改革研究会において、「石油にかかわる規制は必要最小限のものとし、可能な場合は『平常時自由、緊急時制限』方式を導入する」との提言がなされました。これを受けて、翌年12月の石油審議会において「今後の石油製品供給のあり方について」という報告書が取りまとめられ、1995年4月、特定石油製品輸入暫定措置法の廃止を盛り込んだ「石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。同時に、揮発油販売業法から「揮発油等の品質の確保等に関する法律」へと改正され、石油製品の輸入の自由化に伴う市場環境下においても、石油製品の品質が確保されるよう、揮発油販売業者の登録制度や規格に適合しない燃料油の販売規制などが定められました。その後、さらなる規制緩和が推し進められ、石油製品輸出承認制度の見直しやSSの供給元証明制度の廃止、監視員が常駐する有人給油方式によるセルフ給油が解禁されることとなりました。
さらに、1998年6月の石油審議会石油部会基本小委員会の報告書において、石油政策の基本的な考え方として、市場が機能しない場合に備えた政策展開の必要性を指摘しつつも、国際石油市場の機能を評価し、平時における石油精製業の需給調整機能を廃止することが提言され、これに基づき、2001年12月に石油業法が廃止され、我が国の石油産業における自由化が完成されました。
- 出典:
- 石油連盟「今日の石油産業2017」
(3)エネルギー供給構造高度化法に基づく国内精製設備の最適化
こうした一連の規制緩和が実施される一方、人口減少や省エネの取組等を背景として、1999年をピークに国内石油需要が減少を続けています。このような状況の中、原油一単位あたりから精製されるガソリン等石油製品の得率を向上させ、余すところなく原油を利用する(原油の有効利用)体制を強化すべく、「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(エネルギー供給構造高度化法)」に基づき、原油の有効利用を促すため、石油精製業者に対する判断基準(以下「告示」という。)を策定し、国内精製設備の最適化の促進がなされました。
具体的には、2010年7月に施行した一次告示により、我が国製油所全体の「重質油分解装置の装備率」の装備率の向上が義務付けられ、対象となる各石油精製業者は常圧蒸留装置の能力削減及び重質油分解装置の新設・増強の組み合わせで対応しました。これにより、我が国製油所全体で重質油分解装置の装備率は10%程度(告示制定時)から13%程度(2013年度末)へと改善され、国内の精製能力は過去10年間の最大である489万バレル/日から約2割削減しました。
また、2014年7月に施行した二次告示では、さらなる原油の有効利用を進める観点から、我が国全体の「残油処理装置の装備率」の向上を義務付け、各石油精製業者は常圧蒸留装置の廃棄または公称能力の削減及び残油処理装置の新設・増強の組み合わせで対応しました。これにより、我が国全体の残油処理装置の平均装備率は45%程度(告示制定時)から50.5%程度(2016年度末)へと改善し、国内の精製能力は二次告示開始当時の395万バレル/日から約1割削減しました。
こうした取組により、国内製油所の重質油分解装置等の装備率は世界的に高い水準を実現した一方、実際の分解能力の活用は十分ではなく、国際競争力の高い他国の製油所と比較して多くの残渣油を生産しているとの指摘があります。そのため、2017年10月、さらなる原油の有効利用や製油所の国際競争力強化に向けて、重質油分解装置等のさらなる有効利用を目的とする、新たな告示(三次告示)が施行されました。
3.上流開発・権益確保の促進~積極的な資源外交の展開~
(1)石油公団の設立と自主開発原油の獲得
1967年の総合エネルギー調査会答申に、1985年度において我が国が必要とする原油の30%を海外自主開発原油で賄うべきであり、この実現のため、国の積極的な財政措置の下、公団形態の総合的推進母体の設立が必要であるとの政策提言がなされました。これを受け、同年制定された「石油開発公団法」に基づき、石油開発公団が設立され、長年提言されてきた海外での石油開発を促進するための国家機関が創設されることとなりました。
石油開発公団は当初は海外における石油の探鉱のための出融資、探鉱・開発のための債務保証、石油探鉱機械の貸付け、技術指導及び国内地質構造調査を所掌業務としており、その後天然ガスの探鉱への出融資や探鉱権の直接取得等の業務が追加されて機能を拡充し、1978年には国家石油備蓄関係業務が追加されて名称を石油公団に改称しています。19
石油開発公団を通じた支援のみならず、政府としても積極的な支援を実施しています。前述のサウジアラビアにおける石油権益の獲得等に外交面での貢献を行ったほか、1965年には鉱業所得に対する課税の特例として減耗控除制度を創設するなど、様々な助成策を講じました。
政府や石油開発公団の支援により、石油開発事業を目的とする企業の設立が相次ぎ、自主開発原油輸入量は増加を続けました。具体的には、インドネシアのマハカム沖油田(北スマトラ海洋石油資源開発)、UAEのアブダビ海上油田(ジャパン石油開発)、ロシアのサハリン1(サハリン石油開発協力(現・サハリン石油ガス開発))等の自主開発権益の獲得が実現されました。
(2)二度の石油危機による石油調達形態の変化
1973年10月の第四次中東戦争に端を発した第一次石油危機、1978年のイランでの政変に端を発した第二次石油危機は、国際的な石油市場の構造変化を促しただけでなく、我が国の石油政策にも影響を与えました。1977年の総合エネルギー調査会石油部会の中間取りまとめ「今後の石油政策の方向」において、原油の安定供給の確保策として、メジャーズ20経由の原油確保に努めるとともに、政策原油(自主開発原油、政府間の交渉に基づくいわゆるGG21原油など)の規模を、1990年度までに我が国需要の3分の1程度以上にすることを目指すことが望ましい旨、提言されました。
これにより、1973年度は74%あったメジャーズからの輸入比率は、1983年度には33%まで低下しました。代わりに、産油国国営企業からのGG原油及びDD原油22の輸入比率は、1983年度には54%にまで達しています。また、従来は長期契約によるものが主流でしたが、石油危機を契機に価格面で弾力性のあるスポット原油輸入が増加し、1983年度は19%近くまで達しました。
(3)JOGMECの設立と自主開発の推進
1997年の衆議院決算委員会における「石油開発に関する問題」についての集中審議をはじめとして、石油公団の事業運営のあり方、石油公団及び出融資先企業の経営・財務状況等に関し、様々な問題が指摘され始めました。特に、1998年に堀内通商産業大臣よりなされた、石油公団が出融資先企業に対して抱える多額の不良債権等に関する指摘以降は、通商産業省内外で様々な分析・検討がなされました。2001年に閣議決定された「特殊法人等整理合理化計画」において、石油公団の廃止が決定し、2004年に設立された独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)においては、リスクマネーの供給は出資に限定され(融資業務は廃止)、その支援割合は5割以下とされました。こうした中、2006年に策定された「新・国家エネルギー戦略」において初めて自主開発比率23を2030年までに40%程度とするという数値目標が定められ、新たな体制による海外での資源開発への支援がますます推進されることになります。
また、2003年に公表された総合資源エネルギー調査会石油分科会開発部会石油公団資産評価・整理検討小委員会報告書「石油公団が保有する開発関連資産の処理に関する方針」に基づき、国際石油開発(旧北スマトラ海洋石油資源開発)は、アブダビ海上油田権益等、石油公団が保有する優良資産を承継するとともに、2006年に帝国石油と経営統合し国際石油開発帝石ホールディングスを設立、2008年にはホールディングス及び傘下の国際石油開発と帝国石油の3社が完全統合し、国際石油開発帝石が誕生しました。同社は、2015年に世界最大級の規模を誇るアブダビの陸上油田の権益をアジア企業として初めて獲得し、また豪州でオペレーターとして大型LNGプロジェクトに取り組むなど、積極的な開発活動を続けています。
政府としても、2010年の「エネルギー基本計画」策定以降、石油・天然ガスの自主開発比率を2030年に40%以上に引き上げることを目指し、戦略的な資源外交を展開するほか、JOGMECを通じたリスクマネー供給等により、我が国企業の石油・天然ガス開発を支援しています。
【第115-3-2】アブダビ陸上油田
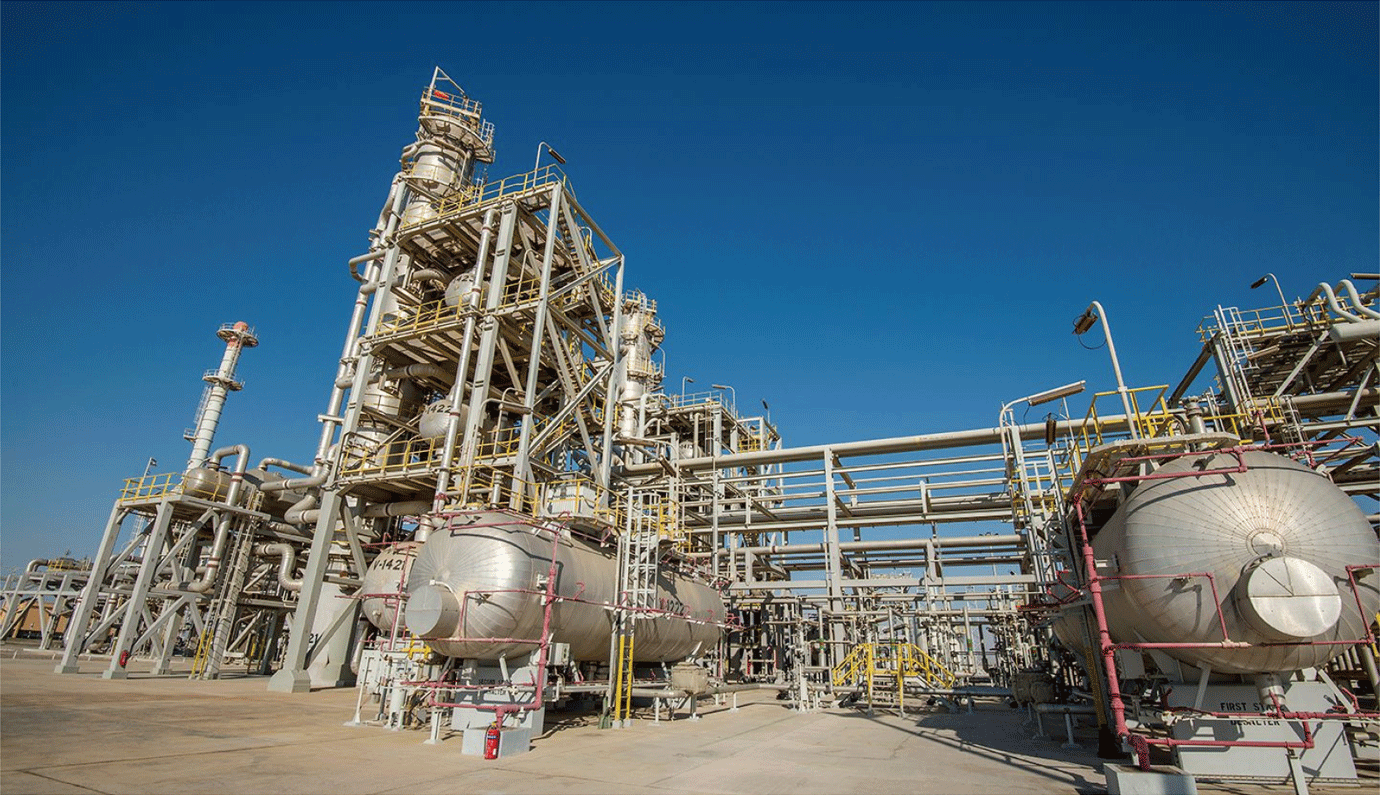
- 出典:
- 国際石油開発帝石ホームページ
- 出典:
- 各種資料を基に資源エネルギー庁作成
4.省エネ法の対象拡大~京都議定書などの地球温暖化対策への対応~
(1)地球温暖化対策に向けた世界的な機運の高まり
1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国連会議」において、気候変動に関する国際連合枠組条約(UNFCCC、1992年採択、1994年発効)が採択されて以降、地球温暖化防止に向けた世界的な機運が高まりました。UNFCCCでは、「気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガス濃度を安定化させる」という究極的な目標な目標に向けて、各国が取り組むべき行動として、温室効果ガス排出量の実態把握や温暖化対策の計画の策定、そして技術開発や調査研究の協力等が掲げられました。
UNFCCC発効翌年の1995年から毎年開催されることとなった締約国会議において、CO2の排出量削減行動も含めた各国の取るべき行動を促進するための枠組みの議論が始まりました。1995年にドイツのベルリンで開催された第1回締約国会議(COP1)では、2000年以降の先進国の数量化された温室効果ガスの排出抑制・削減目標及び政策と措置を定めた議定書をCOP3で採択することが決議されました。これが後の京都議定書(Kyoto Protocol)です。
京都議定書は、UNFCCCにおける温暖化防止行動をより具体的なものとし、2008年から2012年までの第1約束期間において、温室効果ガスの排出量を先進国全体で1990年レベルと比べて少なくとも5%削減するため、附属書I国(先進国及び市場経済移行国)の温室効果ガスの排出量について、法的拘束力のある数値目標を各国毎に設定したものです。1997年に京都で開かれたCOP3で採択され、2005年2月に発効しました。
(2)日本の取組
地球温暖化対策に向けたこうした世界的な機運の高まりを受け、我が国においても1980年代以降から地球温暖化対策が検討されるようになりました。日本のCO2排出量のうち約9割は化石燃料などエネルギー起源であるため、省エネ取組は地球温暖化対策としても重要なものです。そこで、部門ごとの省エネ対策を一層強化するため、省エネ法を計5回改正して法規制の対象を順次拡大するとともに、省エネルギー設備・機器の普及支援策を講じるなど、規制と支援の両輪で、省エネ取組や地球温暖化対策を推進してきました。
① 1993年改正(1993年4月施行)
1992年にUNFCCCが発効されたことや、1990年に地球環境保全に関する関係閣僚会議において決定された「地球温暖化防止行動計画」(日本初の包括的な温暖化対策。CO2排出総量が2000年以降概ね1990年レベルで安定するよう努めることを目標に設定。)の着実な実施を担保するため1993年に省エネ法が改正されました。主な改正のポイントは以下の3点です。
(ア)事業者が省エネ取組を実施する際の目安となるべき「判断基準」中に、エネルギー消費原単位の年平均1%低減を努力目標として設定。
(イ)原単位改善に向けた事業者の取組状況を国が把握し、必要に応じて指導や助言を行うため、エネルギー使用量等の定期報告義務を創設。
(ウ)特定建築物(住宅を除く。)について、新築増改築に係る指示・公表の対象に。
② 1998年改正(1999年4月施行)
1997年に採択された京都議定書を踏まえて1998年に策定された、我が国が取り組むべき包括的な温暖化対策を掲げた「地球温暖化対策推進大綱」において、今後エネルギー消費の大幅な伸びが見込まれる業務部門を含む幅広い業種で徹底した省エネを図ることが必要とされたことを踏まえ、1998年に省エネ法を改正し、省エネ法の規制対象を工場からオフィスや運輸部門にも拡大しました。主な改正のポイントは以下の3点です。
(ア)年平均1%の努力目標達成に向けた計画的な省エネ取組の履行を求めるため、「中長期計画」の作成・提出義務を創設。
(イ)エネルギー管理義務が課される「エネルギー管理指定工場」の指定をオフィスにも拡大。
(ウ)機械器具や自動車へのトップランナー制度を導入。
③ 2002年改正(2003年4月施行)
2002年6月に我が国が京都議定書を締結することを踏まえ、京都議定書におけるCO2排出量削減目標の達成に向けた取組として、業務部門や住宅・建築物の省エネ対策を強化するため、2002年に省エネ法を改正しました。主な改正のポイントは以下の2点です。
(ア)オフィス系事務所の定期報告義務の創設。
(イ)特定建築物(住宅を除く)の省エネ措置の届出を義務化。
④ 2005年改正(2006年4月施行)
2005年2月に京都議定書が発効することを踏まえ、「地球温暖化対策推進大綱」に掲げられている運輸部門の省エネ対策を抜本的に強化するため、2005年に省エネ法を改正しました。主な改正のポイントは以下の2点です。
(ア)旅客輸送事業者・貨物輸送事業者、荷主(輸送事業者に自らの貨物を輸送させる事業者)を省エネ法の規制対象に。
(イ)特定建築物に住宅を追加し、省エネ措置の届出義務の対象に。
⑤ 2008年改正(2009年4月施行)
京都議定書の第一約束期間が2008年に開始することを踏まえ、産業部門・業務部門及び住宅・建築物に関する最適な省エネ取組を促進すべく、事業者単位で最適な省エネ取組を求める規制体系を導入するとともに、業務部門のカバー率を1割から4割へと大幅に引き上げるため、2008年に省エネ法を改正しました。主な改正のポイントは以下の4点です。
(ア)規制の単位を事業所単位から事業者単位に転換。
(イ)連鎖化事業者制度24の導入。
(ウ)産業部門において、業種単位でエネルギー消費効率を高めるため、産業トップランナー制度を創設。
(エ)特定建築物の規制強化(命令又は勧告の追加)及び住宅事業建築主の性能向上努力義務の追加。
こうした5回の改正の結果、現行省エネ法の規制体系は以下のとおりとなっています。
(i)工場等の設置者、輸送事業者・荷主に対し、省エネ取組を実施する際の目安となるべき判断基準(設備管理の基準やエネルギー消費効率改善の目標(年1%)等)を示すとともに、一定規模以上の事業者(例:工場等の設置者の場合、年度で1,500kl以上エネルギーを使用する事業者。約12,000者。)にはエネルギーの使用状況等を報告させ、取組が不十分な場合には指導・助言や合理化計画の作成指示等を行う。
(ii)特定エネルギー消費機器等(自動車・家電製品等)の製造事業者等(生産量等が一定以上の者)に対し、機器のエネルギー消費効率の目標を示して達成を求めるとともに、効率向上が不十分な場合には勧告等を行う。
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
【第115-4-2】省エネ法の概要
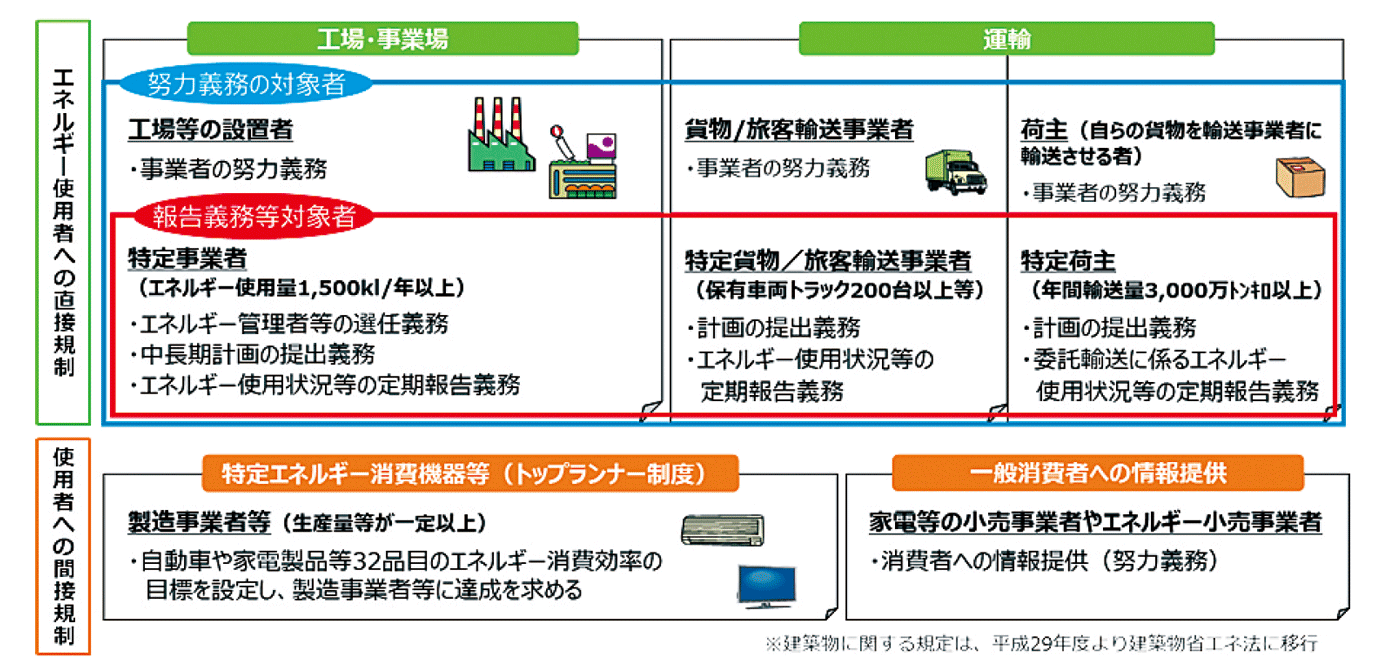
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
5.再生可能エネルギーの導入の拡大~技術開発・法制度整備・利用拡大策の展開~
90年代に入ると、地球温暖化問題対策への機運が高まり、石油代替エネルギーに関する取組みは、温室効果ガスを削減する効果もあることから、環境問題に対しても有効だとみなされました。その潮流の中で、技術開発・法制度や計画の策定・利用量拡大策といった再生可能エネルギーに関わる施策は一層強化されていきます。
(1)<技術開発支援>ニューサンシャイン計画(1993~2000年)の開始
「サンシャイン計画」は「ムーンライト計画」と統合され、1993年から「ニューサンシャイン計画」が開始されます。「サンシャイン計画」に引き続き、太陽光・地熱・風力などに関する技術開発が推進されました。
2001年の中央省庁再編に伴い、「ニューサンシャイン計画」の研究開発テーマは、以後「研究開発プログラム方式」によって実施されることとなりました。この「研究開発プログラム方式」は、産業界、学界等の意見を国(経済産業省)が研究開発のプログラムに反映させ、これに基づいて研究開発を行うものであり、その成果について厳しくチェック&レビューを行うものです。
【第115-5-1】ニューサンシャイン計画のプロジェクト
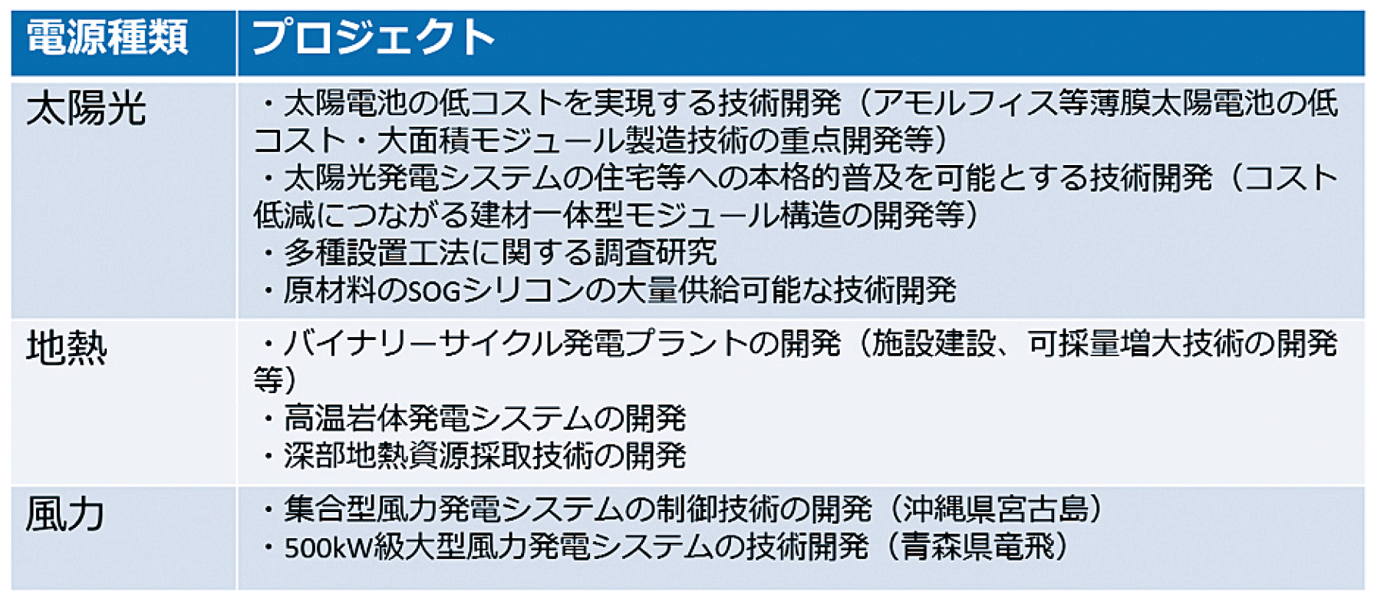
- 出典:
- 新エネルギー便覧 平成10年度版、「ニューサンシャインハンドブック」
(2)<法制度・計画>新エネルギーの導入拡大方針を定める法律や大綱の策定
1990年代、石油価格が低位安定的に推移している中で経済性に劣る新エネルギーの積極的導入を図るためには、中長期的観点に立った導入のための基本方針の策定とそれに基づく効果的な施策展開が必要とされ、法律や大綱などの策定が進められました。
1994年、新エネルギー導入に向けた初の国全体の基本方針である「新エネルギー導入大綱」が策定されました。「新エネルギー導入大綱」においては、新エネルギーの導入を促進するために通商産業省だけでなく関係省庁の諸施策も活用しつつ総合的な対策を講じることとし、また政府の取組とあわせて地方公共団体を中心とする地域レベルの取組みの活発化や、民間事業者、国民の理解と協力を求めるなど、中央と地方、官側と民間が一体となって加速的な導入促進を図るとしました。
1997年には、「新エネルギー導入大綱」に基づき、「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(新エネ法)」が制定されました。新エネ法により、国や地方公共団体、事業者、国民等の各主体の役割を明確化する基本方針の策定や新エネルギー利用等を行う事業者に対する金融上の支援措置等が定められ、新エネルギー導入促進の取組が一層加速しました。
さらに2002年には、「地球温暖化対策推進大綱」において新エネルギーの2010年度における導入目標1910万klが設定され、地球温暖化対策の観点からも新エネルギー導入を一層強力に推進していくことが政府の方針として明記されました。
(3)<利用量拡大策>「RPS法」や「太陽光発電の余剰電力買取制度」の開始
技術開発によってコストは着実に低下しているものの、他の電源に比べて依然として経済性に劣る再生可能エネルギーの導入拡大のためには、再エネ利用を促進する政策的措置が必要であり、1990年代2000年代を通じて様々な取組が官民でなされました。
まず1992年に太陽光発電による余剰電力の販売価格での買電制度が、電力会社による自主的な取り組みとして始まりました。本制度では、太陽光発電が需要を上回って発電した場合に、余った電力を一般家庭向けの電力販売価格と同じ値段で電力会社が買い取ります。余剰電力を売ることができれば、太陽光発電設置にかかったコストをより早く回収できる可能性があることから、太陽光発電設置の促進につながりました。
2003年に、太陽光以外も含む新エネルギーの利用促進を目的として、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法)」が制定されました。RPS法は、電気事業者に対し、毎年の販売電力量に応じた一定割合以上の新エネルギー等の利用を義務付ける制度です。新エネルギー利用目標は経済産業大臣が4年ごとに8年分の目標値を定めるとされ、例えば2005年度に義務対象電気事業者(38社)に課された利用義務量の総量は約38億kWh(総電気供給量の0.44%)でした。RPS法施行後3年間で新エネルギー供給量は87%増大しました。
2009年からは「太陽光発電の余剰電力買取制度」が開始されました。本制度では、太陽光発電で作られた電気のうち、余剰電力を電力会社が従来の倍程度の価格で10年間買い取ることを義務付けます。買取に要した費用は、「太陽光発電促進賦課金(太陽光サーチャージ)」として、電気の使用量に応じて、電気を使用する全ての需要家の電気料金に上乗せされます。事業者の投資回収期間を短縮し、一層事業予見性を高めることにつながりました。
以上の取組の結果、1990年代・2000年代を通じて再生可能エネルギー、中でも技術開発による低コスト化や利用量拡大策、補助金などの設備設置支援策の効果が大きかった太陽光発電の導入量は着実に増大し続け、2000年代半ば頃まで導入量・生産量シェアで世界一の水準を達成しました。
【第115-5-2】太陽光発電の国内導入量とシステム価格の推移
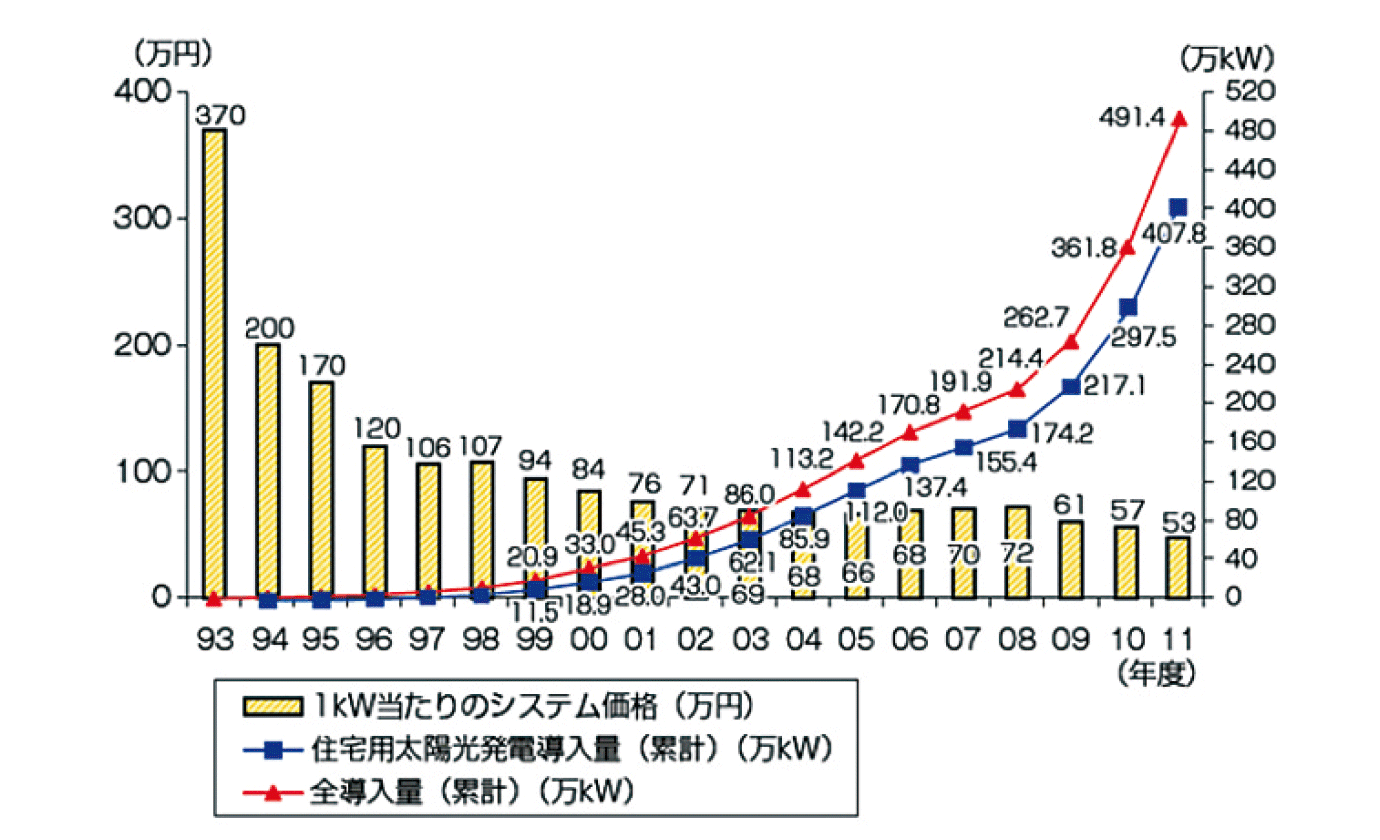
- 出典:
- エネルギー白書2013
6.水素エネルギー導入に向けた機運~世界に先駆けた水素技術の商用化の実現~
水素は無尽蔵に存在する水や多様な一次エネルギー源から様々な方法で製造することができ、利用方法次第では高いエネルギー効率、低い環境負荷等の効果が期待されるエネルギーです。
水素のエネルギーとしての利活用を目的とした国の施策の始まりは、1970年代から開始された「サンシャイン計画」と「ムーンライト計画」における水素の製造・輸送・貯蔵システムや燃料電池の技術開発です。1993年より開始された「ニューサンシャイン計画」でも引き続き水素・燃料電池の技術開発は進められ、これらの基礎研究の蓄積が家庭用燃料電池(エネファーム)や燃料電池自動車(FCV)の開発に活用されていきました。
1990年代に入ると地球温暖化対策への世界的な機運の高まりを背景に、国内メーカーにおけるエネファームやFCVの技術開発も本格化し、燃料電池の開発・実証を継続的に行った結果、2009年にはエネファームが、また2014年にはFCVが、それぞれ市場投入されました。
【第115-6-1】水素の様々な製造方法
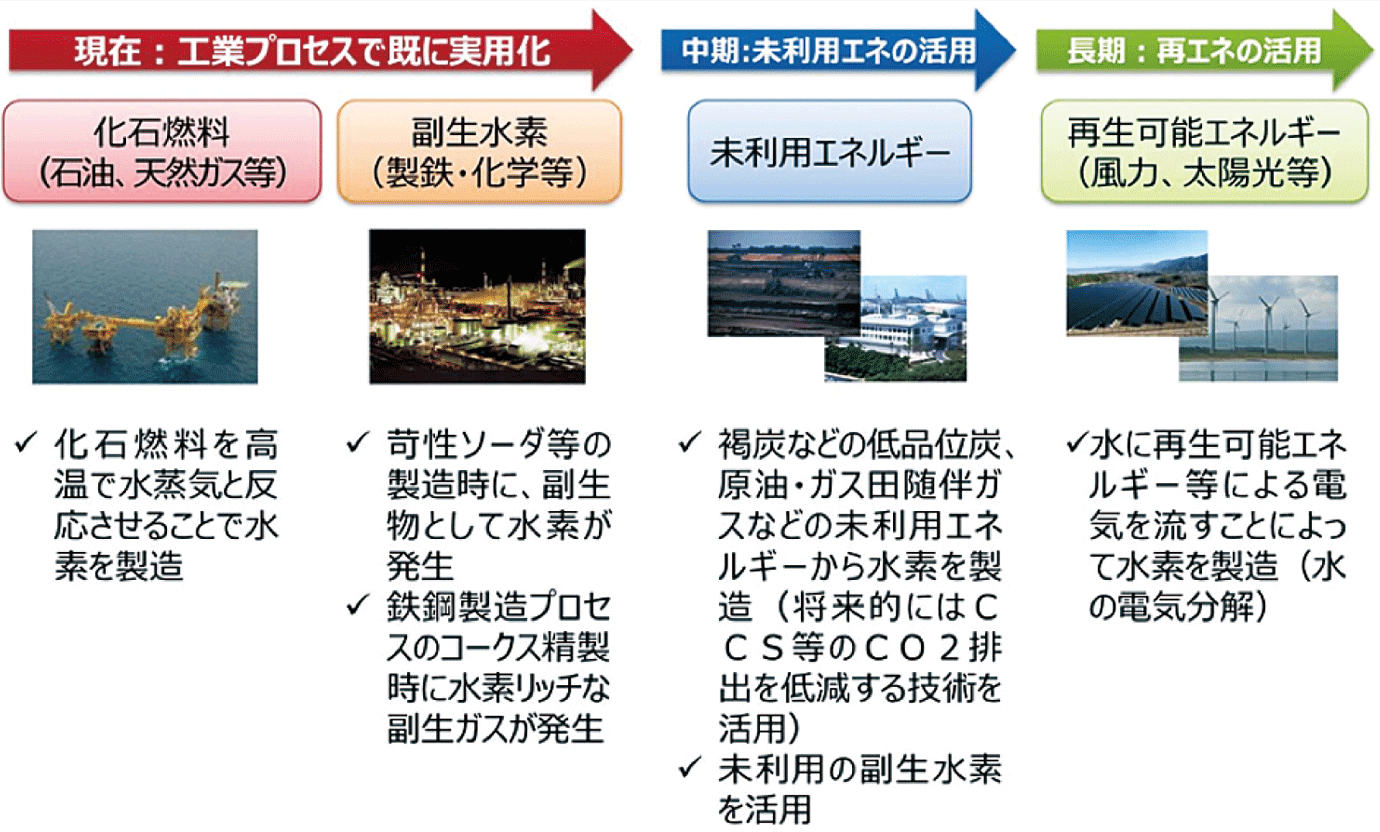
- 出典:
- 水素・燃料電池戦略ロードマップ(2016年3月22日改訂)
【第115-6-2】水素エネルギーの利活用の形態

- 出典:
- 水素・燃料電池戦略ロードマップ(2016年3月22日改訂)
【第115-6-3】水素・燃料電池の技術開発の歴史
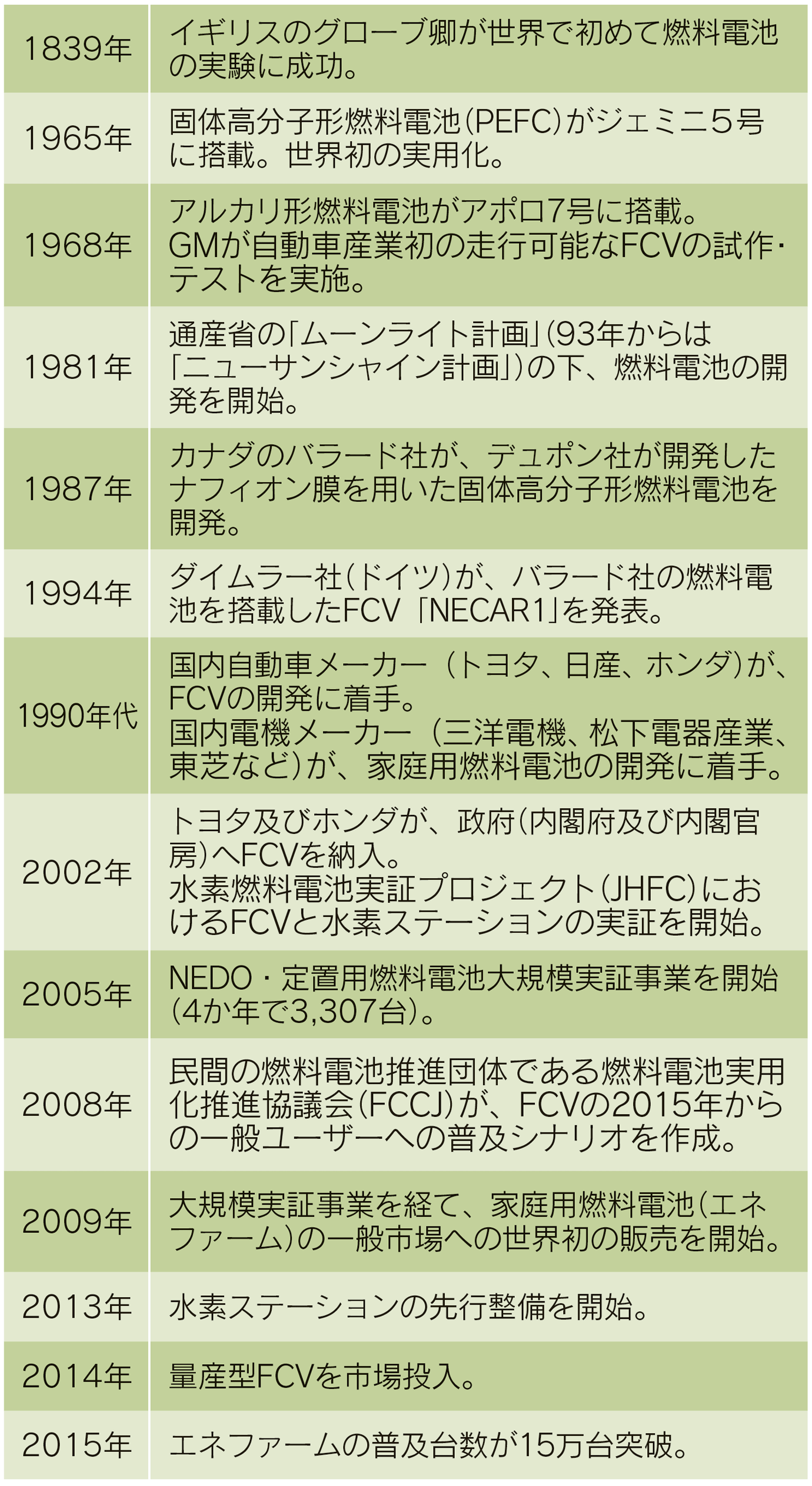
- 出典:
- 水素・燃料電池戦略ロードマップ(2016年3月22日改訂)
- 19
- 石油公団「石油公団史」2005年を参考に記載。
- 20
- 当時世界の主要石油資源を独占していた国際石油企業を指し、エクソン、モービル、テキサコ、スタンダード・オイル・オブ・カリフォルニア、ガルフ・オイル(以上米)、シェル(蘭)、BP(英)の7社を総称して「セブン・シスターズ」とも呼ばれる。
- 21
- 政府間の取決めに基づき、産油国が国際石油企業を経由せず、直接消費国に輸出する原油。日本では1975年にイラクから輸入した原油が最初。
- 22
- 産油国が国際石油企業を経由せず、直接消費国の石油会社などに販売する原油。
- 23
- 当時は「我が国の原油輸入量に占める我が国企業の権益下にある原油引取量の割合」と定義されていた。
- 24
- フランチャイズチェーン事業を営む本部が、その事業の加盟店に対して、エネルギー使用の条件に関する事項を約款等で定めている場合には、フランチャイズチェーン事業の本部に対して、加盟店を含めて省エネ取組を求めるとともに、加盟者を含めたフランチャイズチェーン事業全体の年度のエネルギー使用料が原油換算で1,500kl以上の場合には、エネルギー使用の状況や省エネ取組状況等について、フランチャイズチェーン事業の本部が国に定期報告等を行わなければならない制度です。