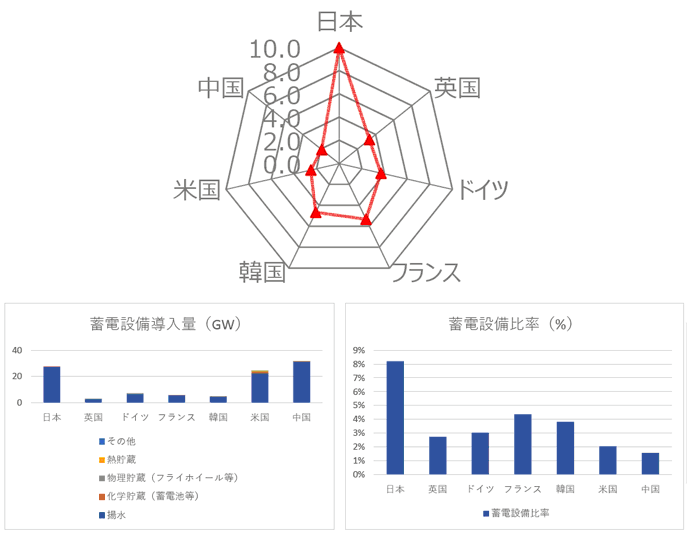第3節 構造変化を踏まえたエネルギーセキュリティの評価
1.エネルギーセキュリティを構成する要素
① エネルギーセキュリティの定量評価に関する国際的な動向
経済協力開発機構(以下、「OECD」という。)が2018年に発行した「The Full Costs of Electricity Provision」では、エネルギーセキュリティを構成する要素を、外的要素と内的要素の2側面に分けて整理しています。外的要素とは、一次エネルギーに伴う地政学的な要素を指します。内的要素は、その国における経済、財政、技術的な要素を指します。
こうした整理を念頭に、エネルギーセキュリティを定量的に評価しようという試みは、国際機関でも行われてきました。OECDの専門機関である原子力機関(以下、「OECD/NEA」という。)が2010年に公表した「The simplified supply and demand index」(以下、「SSDI」という。)が一つの例です。これは、IEAのエネルギー統計を基に、エネルギー需要・社会インフラ・エネルギー多様性・輸入先多様化・省エネルギー性等を考慮した統合した指標となっています(第133-1-1)。
SSDIは「各項目のウェイトを各国の好みにアレンジでき、透明性の高い手法だ9」とされていますが、同時に「過去10年間のエネルギー需給構造の変化を考慮しておらず、水力以外の、太陽光や風力発電等の再生可能エネルギー源が含まれていない。(今後のエネルギーセキュリティの評価には)自然変動電源が電力システムに与える影響を考慮する必要がある」という限界があるとされています。
【第133-1-1】SSDIを構成する要素
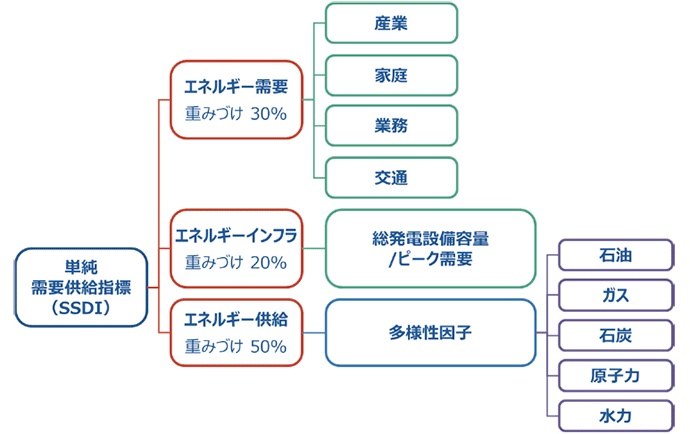
【第133-1-1】SSDIを構成する要素(ppt/pptx形式:124KB)
- 出典:
- OECD(2018) 「The Full Costs of Electricity Provision」より経済産業省作成
② 我が国におけるエネルギーセキュリティの定量評価の試み
これまでのエネルギー白書においても、エネルギーセキュリティの定量評価に取り組んできています。
例えば、「エネルギー白書2010」では、エネルギーセキュリティを「国民生活、経済・社会活動、国防等に必要な量のエネルギーを受容可能な価格で確保できること」と定義した上で、独自の定量評価指標(以下、「エネルギー安全保障の定量評価指標」という。)を示しています。エネルギー安全保障の定量評価指標では、エネルギーセキュリティを構成する要素を「国外からの資源調達」、「国内供給」、「国内消費」の三段階に分けて考えるとともに、サプライチェーン全体を支える要素として「供給途絶への対策」についても評価しています。
また「エネルギー白書2015」では、米国のいわゆる「シェール革命」によって世界のエネルギー情勢が大きく変化したことを踏まえ、「エネルギー白書2010」で示した「エネルギー安全保障の定量評価指標」を用いて、世界各国のエネルギーセキュリティの定量評価結果を更新して示しました。
2020年は、世界が脱炭素に向けて一斉に動き出し、世界のエネルギー情勢が再び大きく動いた年でした。このため、「エネルギー白書2010」で示した「エネルギー安全保障の定量評価指標」を用い、一部指標について見直しを行った上で、各国のエネルギーセキュリティの定量評価を試みます。
評価項目としては、「一次エネルギー自給率(外的要素)」、「エネルギー輸入先多様化(輸入相手国の分散度)(外的要素)」、「エネルギー源多様度(外的要素)」、「チョークポイントリスクの低減度(中東依存度)(外的要素)」、「電力の安定供給能力(停電時間)(内的要素)」、「エネルギー消費のGDP原単位(内的要素)」、「化石燃料供給途絶への対応能力(石油備蓄)(外的要素)」の7項目を設定しました。
調査対象国としては、「エネルギー白書2010」、「エネルギー白書2015」との比較可能性を確保する観点から、引き続き日本、米国、英国、フランス、ドイツ、中国、韓国の7か国を設定しました。ただし、一部の国については、上記した7つの評価項目のうちデータが入手できないものがあり、その場合は、その国を除外して評価しました。
評価は10点満点で行い、項目ごとに評価の対象となる数値(評価数値)を算出した上で、最も評価数値の良い調査対象国を10点とします。項目によって評価数値が最も大きい国が10点になる場合と、最も小さい国が10点になる場合があります。他の国の点数は、その国の評価数値を、最も評価数値の良い国と比較して算出します。評価数値が大きい方が良い評価となる場合と、小さい方が良い評価となる場合とで算出の仕方が異なりますので、例を挙げながら説明します。
【第133-1-2】点数化の方法(評価数値が大きいほど良い評価となる項目)
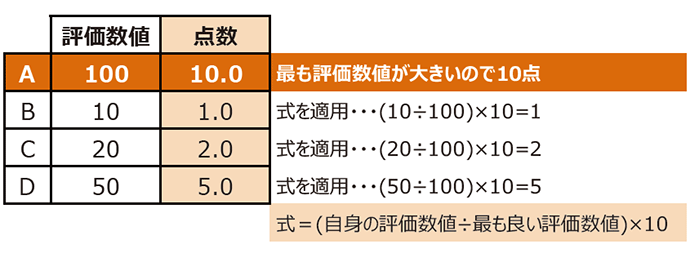
評価数値が大きい方が良い評価となる場合、上の表の中で評価数値が最も大きいAが10点となります。Bの評価数値は10で、最も大きいAの評価数値100と比べると、10分の1となります。これにより、Bの評価はAの10分の1となります。Aの点数は10点なのでBの点数はその10分の1の1点となります。これを数式にすると、「(自身の評価数値÷最も良い評価数値)×10」となります。C、Dについても、この式を用いると、それぞれ2点、5点が点数となります。
下の表のA ~ Dの評価数値は【第133-1-2】と全く同じですが、評価数値が小さい方が良い評価となる場合には、Bが10点となります。Aの評価数値は100で、最も小さいBの評価数値10と比べると、10倍となります。これはAがBの10倍評価が低いということになるので、Aの評価はBの10分の1と考えます。Bの点数は10点なので、Aの点数はその10分の1の1点となります。
【第133-1-3】点数化の方法(評価数値が大きいほど良い評価となる項目)
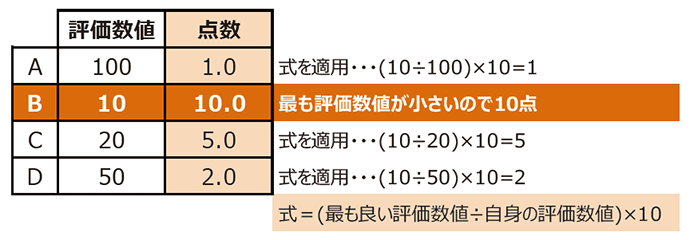
これを数式にすると、「(最も良い評価数値÷自身の評価数値)×10」となります。C、Dについても、この式を用いると、それぞれ5点、2点が点数となります。この手法に基づき、各項目につき調査対象国の直近での定量評価・点数化を行いました10。
エネルギーセキュリティは時代とともに変化する動的なものです。点数は調査対象国の中で最も良い点数の国との相対評価で決まることから、最も良い国の点数が大きく変化した場合、日本単独で見ると変化が無いのに、日本の点数が大きく動く場合があることには注意が必要です。
2. エネルギーセキュリティ指標日本の経年評価
現在入手可能な最新のデータ(【第133-2-1】のデータ参照年を参考)を用いて指標を更新し、日本の経年変化を図にしたものを以下に示します。
【第133-2-1】日本のエネルギーセキュリティ指標の変化
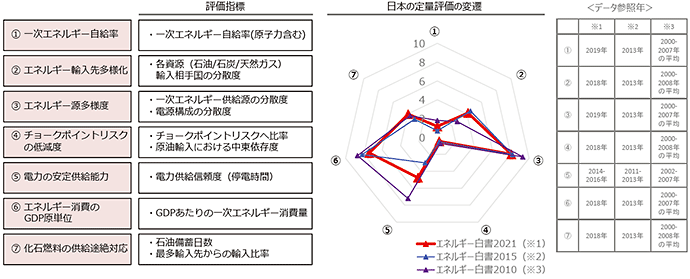
【第133-2-1】日本のエネルギーセキュリティ指標の変化(ppt/pptx形式:495KB)
- 出所:
- 過去のエネルギー⽩書を基に経済産業省作成
エネルギーセキュリティにおいて①一次エネルギー自給率、④チョークポイントリスクの低減度、⑦化石燃料の供給途絶対応能力の3点は、諸外国と比較して一貫して低い評価点に留まっています。特に一次エネルギー自給率は、原子力発電所停止の影響で大きく下がっており、再生可能エネルギーの導入等の影響で改善はしているものの、引き続き化石燃料の安定調達は、日本のエネルギーセキュリティにとって重要な命題となることが見て取れます。
「エネルギー白書2010」、「エネルギー白書2015」での評価と比較して大きく変化しているのが、②エネルギー輸入多様化と⑤電力の安定供給能力(停電時間の短さ)の指標です。②エネルギー輸入多様化については、LNG輸入元の多様化が進んだことで輸入途絶のリスクが減少し、大きく改善しています。⑤電力の安定供給能力(停電時間の短さ)は、東日本大震災の影響によって「エネルギー白書2010」から「エネルギー白書2015」で大きく低下しました。同指標の数値は改善しているものの、「エネルギー白書2010」の水準には戻っていません。カーボンニュートラルを進めれば、エネルギーの電化率は今後一層上昇し、電力安定供給能力(停電時間の短さ)は引き続き重要です。電力系統の強靭化等の災害への備えをさらに進める必要があります。
3. エネルギーセキュリティ指標の各国比較
(1)一次エネルギー自給率
本項では、国際エネルギー機関(IEA)が公表する各国の一次エネルギー自給率を評価数値として点数化しています。自給率が高いほどエネルギーを安価・安定的に確保しやすいことから、自給率が高いほど良い評価となります(なお、IEAは原子力を「準国産エネルギー」と位置付け、一次エネルギー自給率に含めています。)。
日本の一次エネルギー自給率を各国と比較すると、2010年、2015年に続き、2020年も低い評価に留まっています。なお、諸外国のうち、大きな動きがあったのが中国です。中国は、2015年時点では最も高い評価を得ていましたが、経済成長に伴うエネルギー需要増で、燃料の海外依存度が上昇し、2020年には大きく点数を落としています。なお、いわゆる「シェール革命」で2015年に大幅に点数を高めた米国や、同じく北海油田の生産量衰退に伴い2015年に大幅に点数を下げた英国は、2020年の評価でも大きな変化は見られませんでした(第133-3-1)。
【第133-3-1】一次エネルギー自給率(点数)の変化
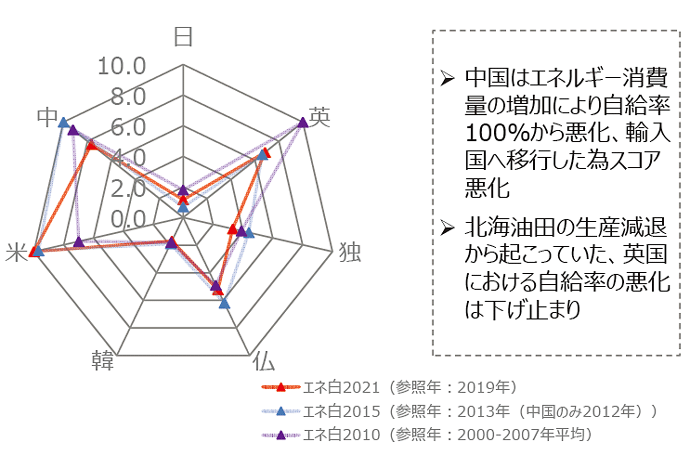
【第133-3-1】一次エネルギー自給率(点数)の変化(ppt/pptx形式:475KB)
(2)エネルギー輸入先多様化
特定の国・地域へのエネルギー依存を低減させることは、エネルギー安全保障の強化に資すると考えられます。ただし、カントリーリスクの高い国・地域へ輸入先を分散していくことは、かえってリスクを高める可能性があります。
本項では、原油・天然ガス・石炭の3種のエネルギー源それぞれにつき、評価対象国における輸入先の寡占度を、OECDの輸出与信データによるカントリーリスクを加味した上で算出しています(通常の寡占度は各国の輸入シェア(%)の2乗を合計しますが、本項の寡占度は過去のエネルギー白書2010、エネルギー白書2015での算出方法に倣い、カントリーリスクの高い国の輸入シェアが実際より高くなるように輸出与信データによるカントリーリスクに+1を補正して調整しています)。
日本は2010年以降、豪州やロシアからの天然ガス輸入量を増やしており、輸入先の多様化が進んだことで、エネルギー白書2010での評価と比べて数値が大きく改善しています。また、英国は石炭への依存度が低減したことから、総合評価において点数が改善しています(第133-3-2)。
【第133-3-2】エネルギー輸入先多様化(点数)の変化
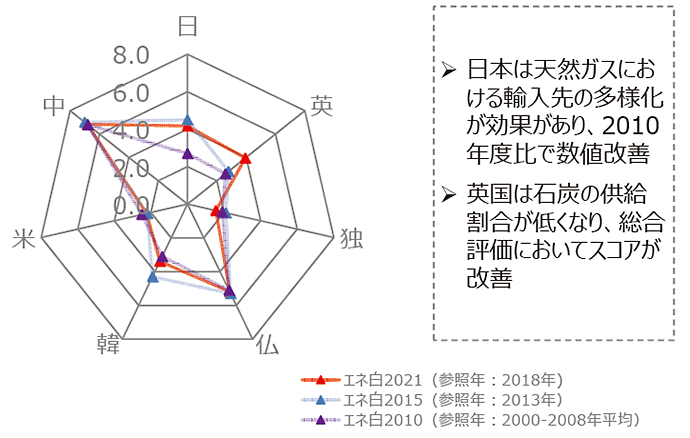
【第133-3-2】エネルギー輸入先多様化(点数)の変化(ppt/pptx形式:464KB)
(3)エネルギー源多様化
特定のエネルギーへの依存を減らすことは、エネルギー供給途絶時の悪影響を低減し、エネルギー安全保障の強化に寄与することになります。本項では、各国の「一次エネルギー供給量」及び「発電電力量」の2つのデータについて、エネルギー源ごとに各エネルギー源のシェア(%)の2乗を合計した値(ハーフィンダール・ハーシュマン指数)をその国の特定エネルギー源への依存度として算出し、それを評価数値として点数化しています。特定エネルギー源への依存度が低いほど良い評価となります。
エネルギー源の多様化において、日本は諸外国と遜色ない評価となっています。諸外国の動きとしては、米国は天然ガスによる発電量の増加によって寡占度が高まり、点数が悪化しているのが分かります。また、英国は石炭の供給割合が低下し、他のエネルギー源に集中することで点数が悪化しています(第133-3-3)。
【第133-3-3】エネルギー源多様化(点数)の変化
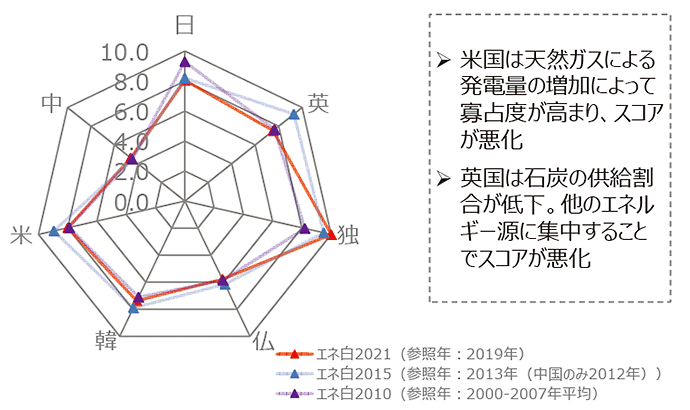
【第133-3-3】エネルギー源多様化(点数)の変化(ppt/pptx形式:475KB)
(4)チョークポイントリスクの低減度
チョークポイントとは、物資輸送ルートとして広く使われている狭い海峡11を指しますが、原油やLNGなど大量のエネルギー輸送に際しても利用されることから、その安全確保、あるいはそこに依存しない輸送ルートの確保はエネルギー安全保障にとって非常に重要な要素となります。
本項では、各国が輸入する原油が、ホルムズ海峡、マラッカ海峡、バル・エル・マンデブ海峡(イエメンとアフリカ大陸の間にあり、紅海とアデン湾を隔てる海峡)、スエズ運河、トルコ海峡、デンマーク海、パナマ運河、喜望峰の8つのチョークポイントを通過することをリスクと捉え、評価を行いました。
原油総輸入量に対するチョークポイントを通過する各国の輸入原油の数量の割合をチョークポイント比率とし、これを評価数値として点数化しています。チョークポイントを複数回通過する場合は数量を都度計上するため、チョークポイント比率は100%を超えることもあります。
チョークポイント比率が低いほど、チョークポイントを通過せずに輸入できる原油が多いということになるため、良い評価となります。日本は中東依存率が高く、多くのチョークポイントを通るため、評価点が低い状況が続いています。特徴的なのは英国で、北海からの石油、天然ガス調達が可能でチョークポイントを一切通らないで済むため、スコアが突出しています。エネルギー白書2015から大きな変化を見せているのは米国で、中東からの輸入量減少に伴い、スコアが改善しています(第133-3-4)。
【第133-3-4】チョークポイントリスクの低減度(点数)の変化
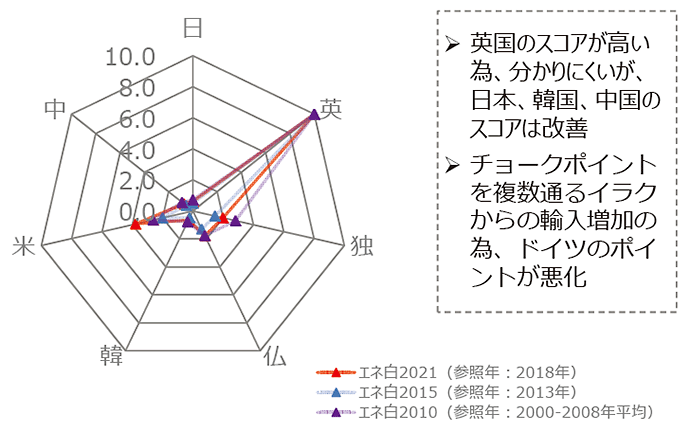
【第133-3-4】チョークポイントリスクの低減度(点数)の変化(ppt/pptx形式:43KB)
(5)電力の安定供給能力(停電時間)
国内のエネルギー供給の安定度を測るには、電力や燃料、資源等の各エネルギーについて、国内における供給ネットワークが安定的に構築されているかを総合的に検証する必要がありますが、本項では、そのうち今後役割の向上が見込まれる電力を取り上げます。その供給信頼度を測る指標の一つとして、1世帯当たりの年間停電時間(停電が発生してから復旧するまでの時間)を評価数値として点数化します。評価数値が低いほど良い評価となります。
日本は、東日本大震災の影響を受けて、「エネルギー白書2010」での評価と比較して、「エネルギー白書2015」での評価は大きく低下していますが、近年では回復しています(第133-3-5)。
【第133-3-5】電力の安定供給能力(点数)の変化
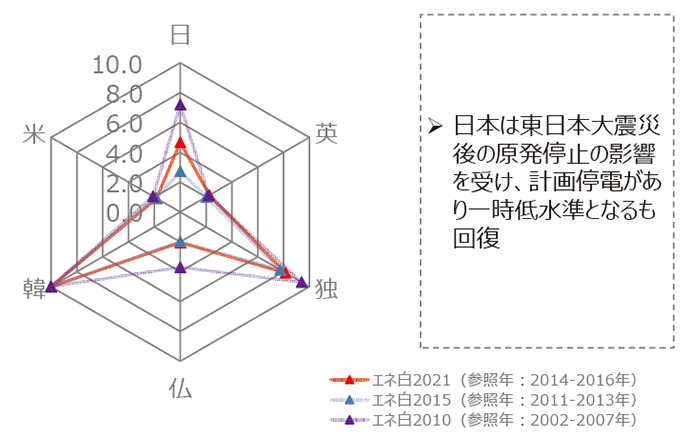
【第133-3-5】電力の安定供給能力(点数)の変化(ppt/pptx形式:463KB)
(6)エネルギー消費のGDP原単位
エネルギーの消費を抑制することも、必要なエネルギー供給量の削減につながるため、エネルギー安全保障を強化する上で効果的と言えます。ただし、エネルギー消費量を単純に減らすだけでは、経済活動や国民生活の水準を損なう可能性があります。機器等のエネルギー消費効率の改善や、産業界や国民の行動変容を通じたエネルギーの使い方の効率化などにより、エネルギー消費の抑制と、経済成長や国民生活の水準の維持・向上を両立していくことが不可欠です。
産業構造や気候等が異なる各国とのエネルギー効率の単純な比較は難しいですが、相対的な比較を示す1つの指標として、本項では、各国のGDPあたりの一次エネルギー消費量を評価数値として点数化します。GDPあたりの一次エネルギー消費量が低いほど良い評価となります。
日本のエネルギー消費のGDP原単位は、英独仏に及ばないものの、米中韓よりも高い評価点を維持しています。英国では、主に産業部門(鉄鋼・化学・自動車)での省エネルギー化が進み高い点数を維持しているのが見て取れます。また、中国は、11次5ヵ年計画に基づき、2005年から省エネルギー技術や再生可能エネルギー技術開発に取り組み始めており、これまで諸外国と比較して低かったエネルギー効率が近年改善しています。他方、1980年台から省エネルギー化や再生可能エネルギー技術開発に取り組む欧米や日本に比較すれば、依然低いスコアであり、引き続き、エネルギー効率の向上の余地があると考えられます(第133-3-6)
【第133-3-6】エネルギー消費のGDP原単位(点数)の変化
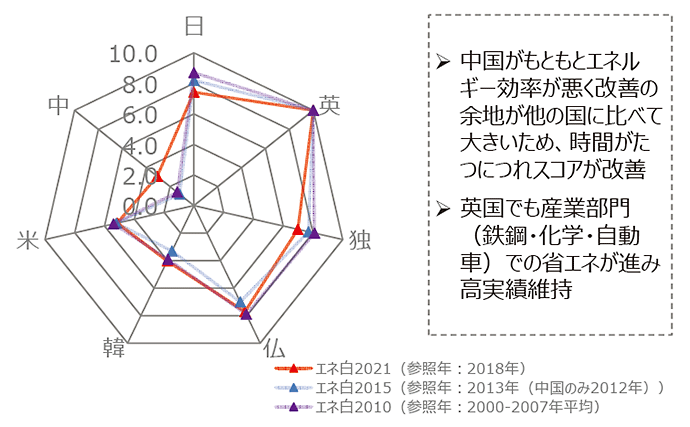
【第133-3-6】エネルギー消費のGDP原単位(点数)の変化(ppt/pptx形式:475KB)
(7)化石燃料の供給途絶対応能力(石油備蓄)
エネルギー資源の供給が一時的に途絶した場合を想定した備えは、エネルギー安全保障の強化において大きな対応能力になります。
本項では、国際比較が可能な石油の陸上備蓄量をベースとして、仮に各国の最多輸入先(地域)からの原油供給が途絶した場合、その備蓄によって対応可能な日数を評価数値として点数化します。対応可能日数が多いほど良い評価となります。
日本・韓国は備蓄日数・輸入地域の構成に大きな変化なく、対応日数の変動は軽微となっています。米国は、カナダへの依存度高まったことから、対応日数が悪化していますが、依然首位を維持しています(第133-3-7)。
【第133-3-7】化石燃料の供給途絶対応能力(点数)の変化
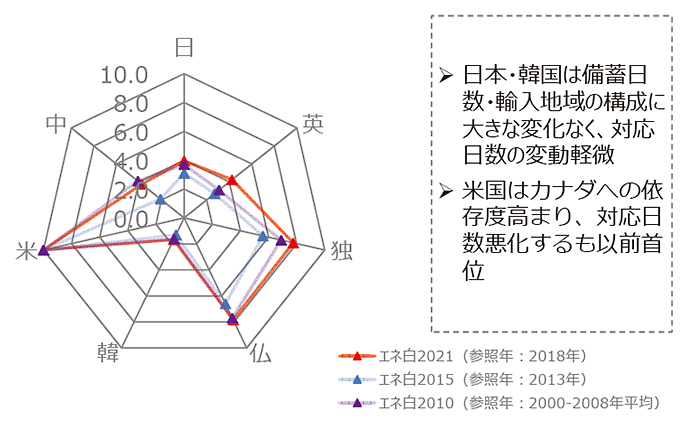
【第133-3-7】化石燃料の供給途絶対応能力(点数)の変化(ppt/pptx形式:475KB)
4. エネルギーセキュリティの変化を踏まえた定量評価
第2節で概観したとおり、2050年カーボンニュートラルに向けた気候変動対策の強化や太陽光や風力発電等の自然変動電源の大量導入など、エネルギーをめぐる情勢はこれまで以上に大きく変わろうとしています。IEAの「World Energy Outlook」のエグゼクティブ・サマリーからも読み取れるように、エネルギーセキュリティの観点から重視すべき項目は、時代を経て拡大してきています。「エネルギー白書2010」で示した従来型のエネルギーシステムの基策定された7つの指標だけでは、我が国のエネルギーセキュリティを十分に評価することは難しくなってきていると考えられます。
そこで、本項では、上記の①~③、それぞれの観点から新たに導入すべき指標を検討します。第133-4-1の左側に示されているのが、従来の7つの指標であり、右側が①~③に相当する追加指標の案となります。指標としての妥当性、取得可能なデータ信頼度等を基に検討した結果、今回は、①は蓄電能力、②はサイバーセキュリティ対応度を定量評価することとしました12。なお、③の指標案としては、例えば、水素やアンモニアにおけるサプライチェーン強靭性が考えられますが、水素やアンモニアが現段階で大量に輸送される状況になく、データ取得できないことから、今回は定量評価を行いませんでしたが、今後、エネルギー源としての水素やアンモニアの普及が進み、データの取得等が可能になった段階で評価を行うことが有用であると考えられます13(第133-4-1)。
【第133-4-1】エネルギーセキュリティの変化を踏まえた定量評価
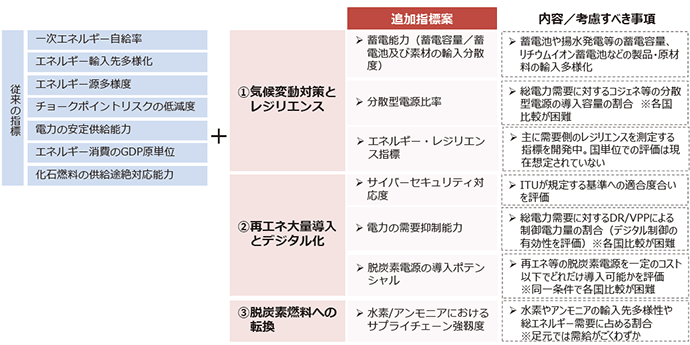
【第133-4-1】エネルギーセキュリティの変化を踏まえた定量評価(ppt/pptx形式:48KB)
5.追加指標における評価と分析
(1)蓄電能力
電力システムの柔軟性を図る指標として、蓄電能力を新たに導入しました。国内の発電容量に対する蓄電容量の比率と、今後重要性が急速に高まる蓄電池及び蓄電池素材の輸入分散度の指標を組み合わせて「蓄電能力」の指標としています(第133-5-1)。
【第133-5-1】蓄電能力
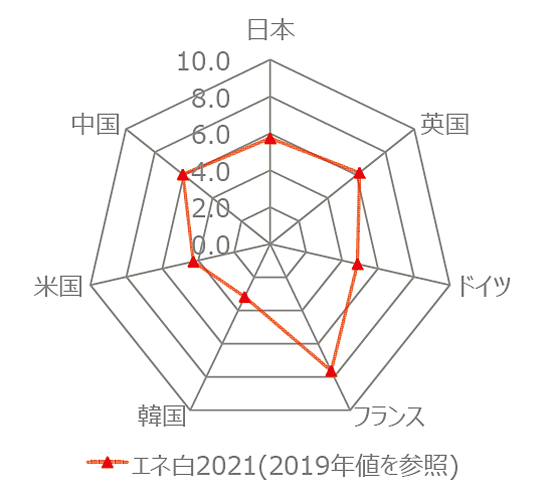
【第133-5-1】蓄電能力(ppt/pptx形式:453KB)
日本は、蓄電容量について揚水発電設備の保有量が、中国に次いで世界2位となっており、その結果、発電設備容量に対する揚水発電設備の比率で規定した「蓄電能力」の指標は、日本が突出する結果となっています(第133-5-2)。
日本では、現在、蓄電容量の大部分を揚水発電設備が占めていますが、今後、揚水発電容量を大きく拡大していくことは困難です。再生可能エネルギーの大量導入に伴い蓄電能力の拡大が必要になりますが、これを可能とする蓄電池及び蓄電池素材の安定調達が今後は重要な指標になるものと考えられます。
フランスは、蓄電池の主要輸入先が中国以外(ポーランド)にも存在し、蓄電池の輸入分散度の指標において、高い点数を有しています(第133-5-3)。
【第133-5-3】蓄電能力(蓄電容量/蓄電池及び素材の輸入分散度)
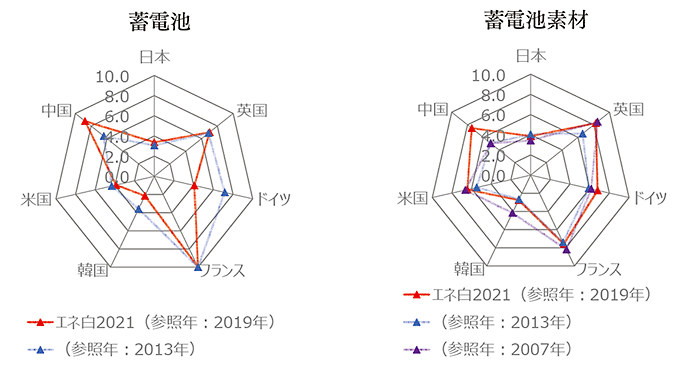
【第133-5-3】蓄電能力(蓄電容量/蓄電池及び素材の輸入分散度)(ppt/pptx形式:426KB)
(2)電力のサイバーセキュリティ
デジタル化の進展に伴い、主要インフラであるエネルギーにおけるサイバーセキュリティの重要性は増加していくことから、新たにサイバーセキュリティ指標を設けます。国際電気通信連合(ITU)が設定している、5つの指標14を基に各国のサイバーセキュリティを評価しており、指標化しています。調査対象国は、いずれも高い点数を示しています(第133-5-4)。ITUが設定した5指標は、国家間での比較を容易にするため、国家レベルでの制度や組織の整備状況に着目し評価を行っており、各国の政府や民間企業等における実際のサイバーセキュリティに係る取組状況(データの保管方法やサイバー攻撃への対策状況等)については評価の対象となっていません。今後、こうした実際のサイバーセキュリティに係る取組状況なども指標として評価ができるよう検討を行う必要があります。
【第133-5-4】電力のサイバーセキュリティ
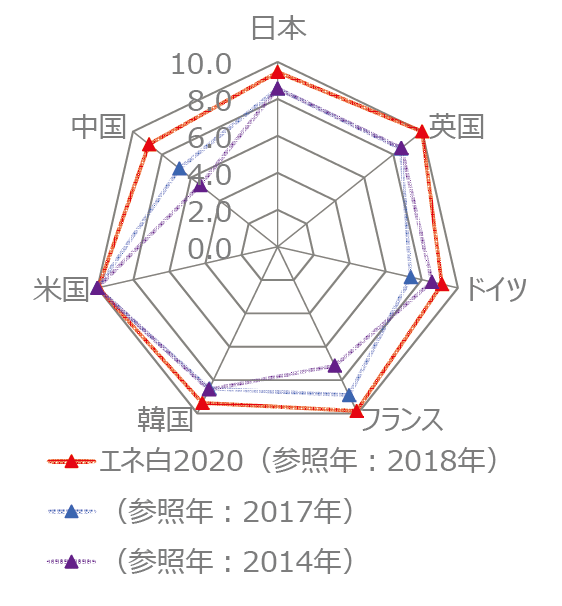
【第133-5-4】電力のサイバーセキュリティ(ppt/pptx形式:291KB)
(3) エネルギーセキュリティの変化を踏まえた定量評価結果(9指標による評価)
今回追加した指標は、脱炭素における主力技術である再生可能エネルギーに重きを置いたものとなっています。「エネルギー白書2010」から使用している「エネルギー安全保障の定量評価指標」の7指標については外的要素についての評価が多かったですが、今回追加で指標化した「蓄電能力」と「電力のサイバーセキュリティ」についてはどちらも国内における電力システムに関連する「内的な要素」となっており、日本においても外的要素だけでなく、内的な要素についても検討する必要があり、エネルギーセキュリティを評価する際にも意識しなければならないことが増えています(第133-5-5)。
【第133-5-5】エネルギーセキュリティの変化を踏まえた定量評価(最新実績)
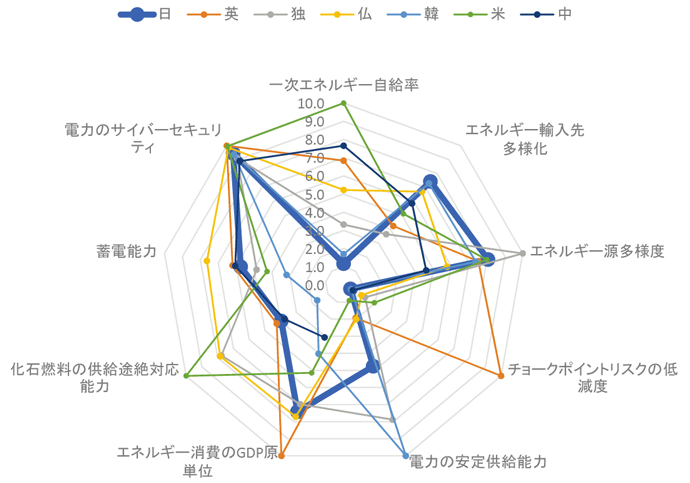
- 9
- OECD(2018)「The Full Costs of Electricity Provision」
- 10
- 「エネルギー輸入先多様化」や「エネルギー源多様化」のように多様性がエネルギーセキュリティの評価に繋がるものについては、ハーフィンダール・ハーシュマン指数を適用し評価している。この指数は市場の独占度合いを測定する指標の一つで、各国が市場で有するシェアを自乗し、それを加算して算出する。ハーフィンダール・ハーシュマン指数はシェアを自乗して加算するので、シェアの大きな国のシェア変動が大きく影響する。逆に小さな国のシェア変動の影響は小さい。小規模な国の情報を欠いても、指標の有効性が損なわれにくい特徴がある。
- 11
- チョークポイントについては、米国エネルギー省エネルギー情報局(EIA)が示したレポートにあるチョークポイント8カ所、すなわちホルムズ海峡、マラッカ海峡、バル・エブ・マンデブ海峡、スエズ運河、トルコ海峡、パナマ運河、デンマーク海峡、喜望峰を使用しています。
- 12
- 今回の追加指標は、OECDが指摘したSSDIの限界(太陽光や風力発電等の再生可能エネルギー源が含まれていない。(今後のエネルギーセキュリティの評価には)自然変動電源が電力システムに与える影響を考慮する必要がある)とも整合しています。
- 13
- 2021年3月31日、国際エネルギー機関(IEA)及び英国が共催する「IEA-COP26ネットゼロサミット」がテレビ会議形式で開催され、日本からは、梶山経済産業大臣が参加し、「全体セッション」の冒頭で、「クリーンエネルギー・トランジションにおけるエネルギー安全保障の役割」についてスピーチ。カーボンニュートラルは、途上国も含め国際社会全体で取り組むべき課題であり、各国の状況に応じて「全てのエネルギー、全ての技術」を活用した現実的かつ多様なアプローチが重要であること、エネルギーの安定供給は社会の基盤であり、移行の プロセスにおいて、変動電源の導入拡大、自然災害、サイバー攻撃等のエネルギー安全保障上の新たな脅威に対し、ハード・ソフト両面での「強靱性」の担保や投資の確保、アンモニアや水素の活用も含めた多様な電源の活用が重要であることを強調しました。
- 14
- ① Lega(l サイバー犯罪やサイバーセキュリティ等に関する法制の整備状況)、②Technical Measures(サイバーセキュリティ情報の共有、技術的支援組織の整備、基準の策定等)、③Organizational Measures(国家レベルのサイバーセキュリティ戦略の整備や責任官庁の設置等)、④Capacity Building Measures(サイバーセキュリティ専門人材の育成、資格の整備等)、⑤Cooperation Measures(国際的なサイバーセキュリティ協力の実施等)