第2節 エネルギーセキュリティの構造変化
1. 国際的なエネルギーセキュリティの重点の変遷
石油危機を契機に1974年にIEAが設立されて以来、エネルギーセキュリティはIEAの主要課題の一つであり続けています。設立してしばらくは化石燃料を中心としたエネルギーセキュリティの議論が進められましたが、その後の世界情勢の変化を受け、IEAがエネルギーセキュリティの文脈で議論するテーマは順次、広がってきています。
こうした変遷が端的に表れているのが、IEAが毎年発行する「World Energy Outlook」(以下「WEO」という。)冒頭のエグゼクティブ・サマリーです。WEOは1977年に創刊されたIEAの代表的な刊行物であり、エネルギーの需給や技術開発に関する見通しなどを示しています。WEOのエグゼクティブ・サマリーには、IEAがその年のWEOで特に強調する内容が要約されています。
化石燃料中心の議論が転換し始めたのが、2008年以降です2。WEO2008では気候変動対策の必要性を強く主張し、WEO2010では、2009年第15回気候変動枠組締約国会議(COP15)におけるコペンハーゲン合意3を失敗と断じ、天然ガスと電力(特に再生可能エネルギー)による低炭素化加速の重要性を強調しています。WEO2012になると、「水力の順調な増加と風力・太陽光の急増がエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの位置をゆるぎないものにした」とするなど再生可能エネルギーの拡大を好意的に記載しています。しかし、WEO2016になると、太陽光や風力等の自然変動電源の大量導入時には系統増強やバックアップ電源が必要となるなど課題が指摘され始め、各国で進む自然変動電源の導入拡大に伴う電力システムの脆弱性も認識されるようになりました。2008年から2015年頃は、化石燃料の安定調達を中心としたエネルギーセキュリティの議論から、気候変動対策や、自然変動電源の導入拡大に伴う電力システム全体での安定性の確保など多様な要素を含むエネルギーセキュリティの議論へと認識が徐々に広まっていった時期と見ることができます。
WEO2017では、2016年に史上初めて電力投資額が石油・ガス投資額を上回ったことを取り上げ、電力セキュリティの重要性の高まりが強調されています。あわせて、太陽光・風力等の自然変動電源の導入増加に伴い、電力システムの安定性を確保するための系統増強やバックアップ電源の必要性が強調されています。あわせて、経済のデジタル化が電力部門において進めば柔軟性を効率的に調達できるようになるとする一方で、デジタル化に伴って新たな電力システムの脆弱性が生じ得るとも述べています。こうした問題意識から、IEAは2017年以降、エネルギーセクターのデジタル化にも焦点を当てるようになっています。
WEO2019では、エネルギーの脱炭素化や、電力以外のあらゆるセクターを巻き込んだエネルギーシステム全体の抜本的な転換が論じられるようになってきました。脱炭素化は、単一手段では達成できず、省エネルギー、電化の促進、原子力の活用を含む電力の脱炭素化、熱需要の水素化、それでも残るCO2については分離回収をする(Carbon Capture,Utilization & Storage: CCUS)など、あらゆるエネルギー源とエネルギー技術を総動員することが重要である旨が強調されています。WEO2020では、「10年以内に石油成長の時代は終わりを迎える」とし、エネルギーの脱炭素化に関する記載が厚みを増しています。また2020年には世界の100以上の国・地域が2050年のカーボンニュートラル実現を宣言したことなどから、2050年に世界全体で脱炭素社会を実現する「Net Zero Emissions by 2050 case」が複数シナリオの一つとして新設されていることも特徴の一つです(第132-1-1)。
このような国際的なエネルギーセキュリティの議論は、我が国にも当てはまるところが大きく、我が国のエネルギーセキュリティの議論を深めていくに当たっても示唆に富むものと言えます。
【第132-1-1】エネルギーセキュリティの重点の変遷(IEA)
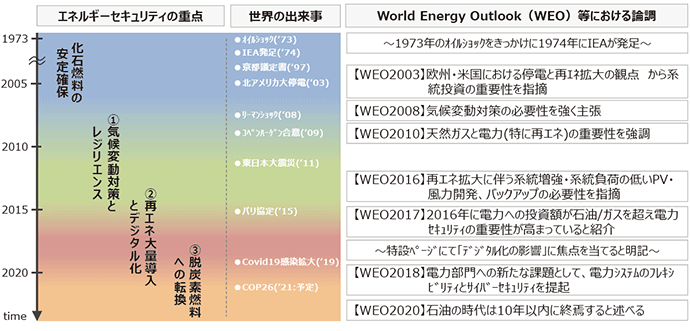
【第132-1-1】エネルギーセキュリティの重点の変遷(IEA)(ppt/pptx形式:50KB)
- 出典:
- IEA「World Energy Outlook 2003-2020」より経済産業省作成
2. 気候変動・レジリエンスの観点からみたエネルギーセキュリティ
自然変動電源の導入が世界的に拡大する中、電力システムの安定性を確保するには、エネルギーシステムの分散化や、電力融通能力の強化につながる系統整備の促進、短時間で出力を調整できる柔軟性のある電源や水素・蓄電池等の蓄電能力の強化等がますます重要になってきます。
また、台風や地震等、自然災害の激甚化傾向を踏まえ、災害によるダメージを最小化し、なるべく短期間で復旧、復興するための取組も重要であり、世界で議論が活発化してきています。
(1) 自然変動電源の導入拡大に伴い求められる電力セキュリティの重要要素
①送配電部門での対応
電力システムのうち、特に送配電部門において、IEAは、静的信頼性(Adequacy)、動的信頼性(OperationalSecurity)、強靱性(Resilience)の3点を電力セキュリティの重要要素として示しています。まず、静的信頼性とは、通常時において、適切な供給予備力を有するとともに、送電余力を確保できており、全ての電力需要を問題なく供給可能な状態を示します。次に、動的信頼性は、電力システムが通常時に問題なく稼働し続け、また、落雷など、様々な突発的な事象が発生した際に、可能な限り早く通常の状態に戻る能力を有する状態を示します。最後に、強靱性は、電力システム及びその構成要素が、短期の負荷変動や長期的な電源構成の変化等に耐え得る状態を示します(第132-2-1)。
【第132-2-1】IEAが定義する送配電に関するエネルギーセキュリティ上の重要要素
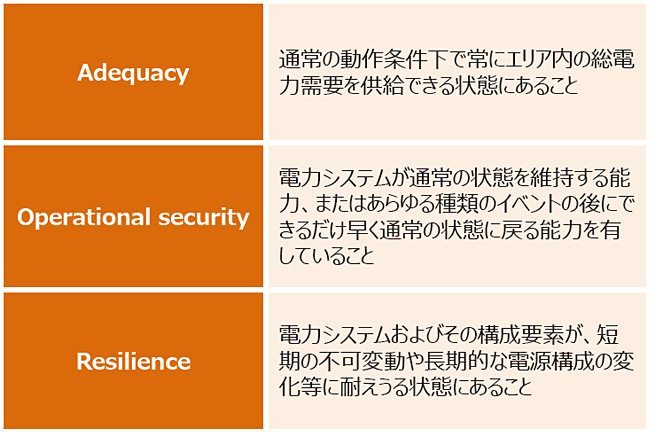
- 出典:
- IEA「Power Systems in Transition」より経済産業省作成
②蓄電技術や需要側での対応
太陽光や風力等の自然変動電源が電力システム全体に占める比率が高まると、これを補う調整力の重要性が飛躍的に高まります。当面はガス火力・揚水発電等を活用しつつ、中長期的には系統増強による地域間の電力融通の促進や、蓄電池やEVの導入やディマンドリスポンスの活用等の需要側への働きかけ等が重要になります。
さらなる蓄電能力の強化には、次世代蓄電池や、合成燃料、水素、アンモニア等を活用した電力貯蔵技術が有望ですが、これらの技術は様々な理由から現時点ではまだまだコスト高です。こうした技術が社会実装されるには、研究開発と実証が進展し、既存の蓄電技術等と同程度までコスト低減が進むことが必要です。政府としては、グリーンイノベーション基金等も活用しながら、強力に後押しをしていきます(第132-2-2、第132-2-3、第132-2-4)。
【第132-2-2】各国の運用上のフェーズの変化
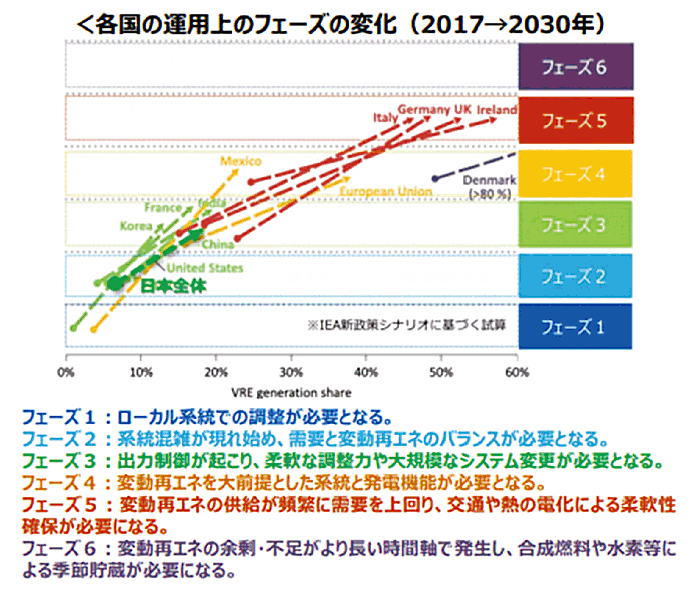
【第132-2-2】各国の運用上のフェーズの変化(ppt/pptx形式:1030KB)
- 出典:
- IEA「World Energy Outlook 2018」より経済産業省作成
【第132-2-3】電力貯蔵技術の各方式の出力・放電時間
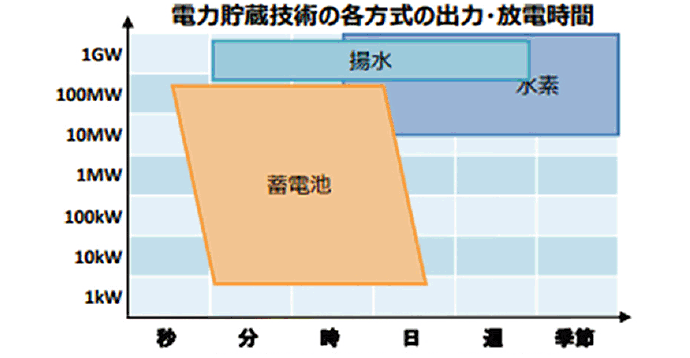
【第132-2-3】電力貯蔵技術の各方式の出力・放電時間(ppt/pptx形式:1026KB)
- 出典:
- IEA「Technology Roadmap Hydrogen and Fuel Cells」より経済産業省作成
【第132-2-4】各調整力に必要な出力・放電時間
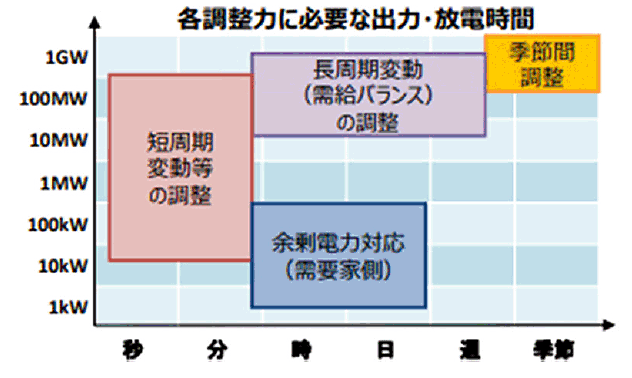
【第132-2-4】各調整力に必要な出力・放電時間(ppt/pptx形式:1026KB)
- 出典:
- IEA「Technology Roadmap Hydrogen and Fuel Cells」より経済産業省作成
COLUMN
カリフォルニア州の大規模停電について(2020年8月)
2020年8月、カリフォルニア州で計画停電が実施されました。同州デスバレーにおいて、当時世界で過去3番目の記録となる華氏130度(摂氏54.4度)を記録するなど、歴史的猛暑により西部地帯一帯で電力需要の増加が見られました。同州は太陽光発電の導入を進めており、以前より、太陽光発電の発電量が減少する日没に実需要(需要から太陽光発電の発電量を差し引いたもの)が急激に立ち上がる現象がダックカーブ現象として課題視されていました。実需要の曲線がアヒルの姿のように見えることから名づけられたこの現象は、急激な需要の立ち上がりに対応できるだけの応答性の高い発電設備を必要とします。計画停電はいずれも実需要がピークの時に発生しており、猛暑から来る大きな電力需要に対応できなかったことが要因の一つとして考えられています。(第132-2-5)。
また、別の要因として、卸電力市場の一部機能不備が指摘されています。域内の需要計画が過小に見積もられ、「前日市場」への需要入札量が不足する事態が発生したのです。これにより、市場システムにおいて、域内需要が少ないと誤認された結果、域外に電力を輸出するための需要入札が約定する結果となりました。そのため、域内は需給ひっ迫の状況にあるにも関わらず、一部の電力が域外に輸出されることとなったのです。
カリフォルニア州の大きな特徴として、州外からの電力輸入に依存している点、再生可能エネルギーの比率が急速に上昇している点、小売事業者が自社の供給する需要量に対して一定量の発電能力を調達する容量メカニズムが複数併存している点が挙げられます。輸入に依存していることから、例えば今回のように隣の州でも同じように電力需要が増加した場合、同州の需給はひっ迫することとなります。同州の場合、高い比率で導入されている再生可能エネルギー発電設備の多くが、太陽電池や風力といった発電量が天候に左右される発電設備のため、それらの出力が低いタイミングが需要ピークに重なると、更に需給ひっ迫することとなります。このような性質を持つ地域で、安定的に電力を供給するためには、十分な予備力が求められることが分かります。
【第132-2-5】需要及び実需要(2020/8/14 ~2020/8/15)
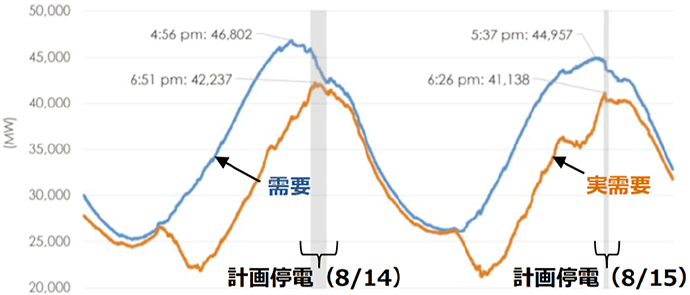
【第132-2-5】需要及び実需要(2020/8/14 ~2020/8/15)(ppt/pptx形式:1159KB)
- 出典:
- Preliminary Root Cause Analysis Mid-August 2020 Heat Storm(Oct.6, 2020)より経済産業省作成
(3)世界で進むエネルギーレジリエンスの議論
エネルギーシステム強靱化の必要性は、日本だけでなく、広く世界に共通するものです。
例えば、アジア太平洋地域の21の国と地域(エコノミー)が参加する経済協力の枠組みであるAPEC(アジア太平洋経済協力)では、持続可能な成長と繁栄のため、過去数年にわたり、エネルギーレジリエンスに関する議論がされてきました。2014年のAPEC首脳宣言の付属文書である「2015-2025年APEC連結性ブループリント」を受けて、2015年のエネルギー大臣会合ではエネルギーレジリエンスが主要テーマとされ、エネルギー安全保障と持続可能な発展を推進する上で、エネルギーレジリエンスを高めることが重要との認識が共有され、成果文書として「セブ宣言」が公表されました。セブ宣言に基づき、エネルギーワーキンググループの下にエネルギーレジリエンスタスクフォースが新たに設置され、2015年12月以降、エネルギーレジリエンスに関する取組や知見の共有とともに議論が進められ、2020年8月、エネルギーレジリエンス原則が国際合意となりました。エネルギーレジリエンス原則では、「国ごとによってエネルギー事情は多様であり、エネルギーレジリエンスのために取るべき措置は、多様性を踏まえ各国がそれぞれ判断すべき」との原則のもと、ステークホルダーやエネルギーレジリエンスに資する取組の特定、これを実現する技術に投資が回る仕組み作りの必要性に触れています。エネルギーレジリエンスに資する取組として、電源や燃料調達先の多様化、系統の強化・分散化などが考えられ、このような取組を具体化したガイドラインの作成が今後進められる予定です。
アジアに加え、欧州を始めとした世界でもエネルギーレジリエンスへの関心が高まっています。例えば、毎年スイスのダボスで年次総会を開催している世界経済フォーラム(World Economic Forum)では保険会社・機関投資家による「Insurance & Asset Management Industry Group」が組織され、2021年4月からエネルギーを含むレジリエンスについて本格的な議論が始まっており、レジリエンスを定量評価するための「Resilience Index」策定に向けた取組が活発化しています4。また、日米欧の再保険会社や金融機関、電力会社、学術機関の有志が集まって「Energy Resilience Study Group」を組織し、2021年3月にエネルギーレジリエンスの重要性に関する報告書を発出しています5。
COLUMN
エネルギーレジリエンスの定量評価の取組
自然災害の激甚化が進む中、災害による損害を極小化するとともに、早期の復旧・復興につなげ、以前よりも強靱性を高める(Build Back Better)ための仕組みや能力が必要です。とりわけ、エネルギーはあらゆる産業活動や国民生活の基盤であることから、電力、ガス、石油や水道等の公共インフラの頑健性向上や、こうしたインフラが被災した場合に早期復旧・復興するための仕組みの整備が、住民生活と企業活動の双方にとって重要です。
日本は、台風による風水害や地震など様々な災害対応の経験と知見を有しています。例えば、大手損害保険会社等は、ビッグデータやAIを活用し、自然災害による被害を地域ごとに精度高く予測し、自治体や企業等に備えを促しています。また、電力・ガス・石油等のエネルギー企業は、風水害や地震等に強い供給網の構築や、災害対応のために自治体や他の事業者と円滑に連携するための事前の枠組み作り等に多角的に取り組んできています。
しかしながら、自然災害による被害の最小化と早期の復旧・復興を確実なものとするためには、エネルギー供給側の取組だけでは十分ではなく、エネルギーを利用する側である企業等における取組の更なる強化が必要です。これまでも個別企業による自社の事業継続計画(BCP)の策定が進められてきていますが、こうしたBCPは、地域における災害ごとの発生頻度や、企業活動における電力、ガス、石油等の利用状況、地域のエネルギーインフラの特性を踏まえたものとなっていないことも多く、実際の被災時には必ずしも有効に機能しないなど、改善の余地が大いにあります。ある企業では受電設備の耐震化を進め、比較的地震の影響が少ないという理由で受電設備を地下に設置していたため、予想を超える豪雨で浸水が生じた際には受電設備が完全に水没し、電力会社による電力供給は途絶えていないにもかかわらず、受電できないために生産活動が停止したという例もあります。
ただし、想定し得る全ての災害に備えることは多額の費用が必要となるため、経済的に現実的ではありません。地域における災害ごとの発生頻度や、企業活動における電力、ガス、石油等の利用状況、地域のエネルギーインフラの特性を踏まえ、優先順位を付けて対応していくことが必要になります。また、こうした取組に円滑に資金が供給されるためにも、エネルギーレジリエンス向上が災害対応力に止まらず平時も含む企業経営全般にとってプラスになることを定量的に示し、金融面でも適切に評価されるようにすることが重要であり、そのためにはエネルギーレジリエンスを概念だけでなく具体的・定量的に捉えていく必要があります。
こうした考えの下、2020年にエネルギーの需要家(IT産業や不動産業)、エネルギー産業、金融業、アカデミアを中心とした「エネルギーレジリエンス協議会」が発足し、日本経済団体連合会を始めとした関連団体や金融庁、経済産業省等の関係省庁も参加して議論が進められており、2020年11月にはエネルギーレジリエンスの定量評価の重要項目を明確化した「エネルギーレジリエンスフレームワーク」が取りまとめられました6(第132-2-6、第132-2-7、第132-2-8)。
【第132-2-6】エネルギーレジリエンス定量評価指標のフレームワーク
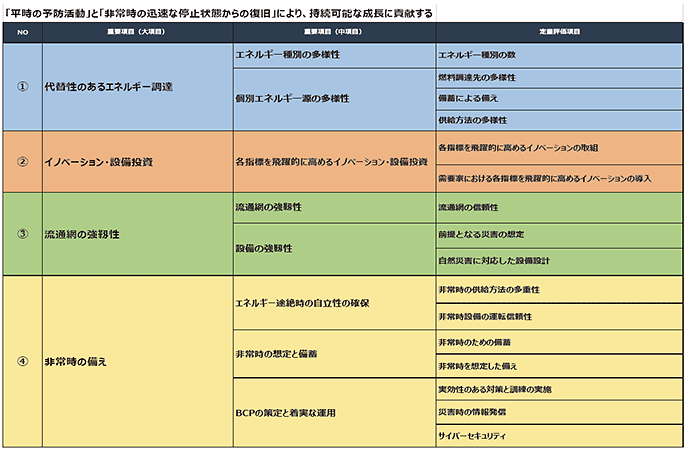
【第132-2-6】エネルギーレジリエンス定量評価指標のフレームワーク(ppt/pptx形式:44KB)
- 出典:
- 第2回 エネルギーレジリエンス協議会資料より抜粋
【第132-2-7】エネルギーレジリエンススコアの考え方
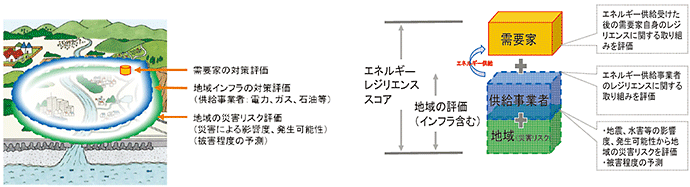
【第132-2-7】エネルギーレジリエンススコアの考え方(ppt/pptx形式:443KB)
- 出典:
- 第2回 エネルギーレジリエンス協議会資料より抜粋
【第132-2-8】エネルギーレジリエンス評価指標一覧
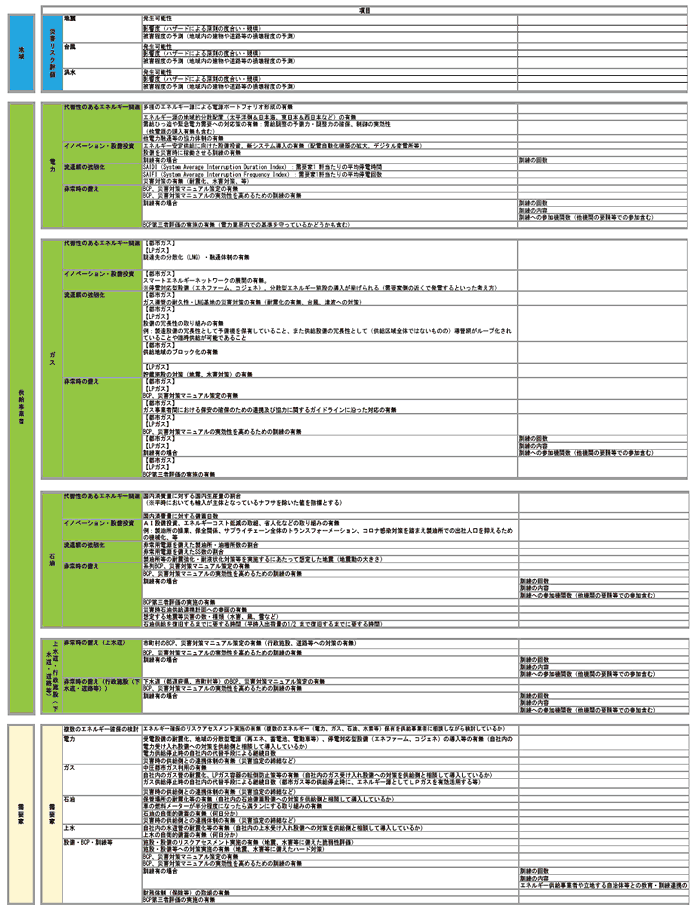
【第132-2-8】エネルギーレジリエンス評価指標一覧(xls/xlsx形式18KB)
- 出典:
- 第2回 エネルギーレジリエンス協議会資料より抜粋
3. 再生可能エネルギーの大量導入とデジタル化による影響
(1)電力システムに対するサイバー攻撃の増加
電力システムのデジタル化により、効率性の向上とコストの削減、停電時間の短縮など、エネルギーシステム全体にとって大きな便益が生まれる可能性があります。特に、系統運用のデジタル化が進めば、需給調整の高度化を通じて、従来ならば出力抑制していた太陽光・風力等を活用していくことも可能になります。
一方で、電源や系統、EVを含む蓄電池がデジタル制御され、つながることにより、電力システム全体が潜在的なサイバー攻撃リスクを背負うことになることにも十分な留意が必要です。実際に、2010年には20件であった電力システムに対するサイバー攻撃の件数は、デジタル化が進展した2017年以降急増し、2019年に100件を超えるなど、過去10年で5倍以上に急増しており、十分な備えが必要です(第132-3-1)。
【第132-3-1】電力システムに対するサイバー攻撃の件数推移
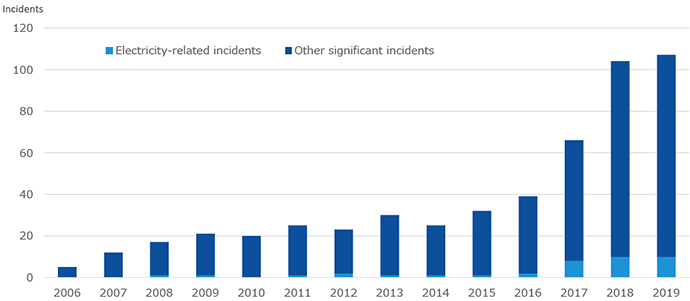
【第132-3-1】電力システムに対するサイバー攻撃の件数推移(ppt/pptx形式:60KB)
- 出典:
- IEA「Power Systems in Transition」
(2)電力システムに対するサイバー攻撃の質の変化
電力システムに対するサイバー攻撃の事例を見ると、企業や国家の情報窃取等を目的とした攻撃に止まらず、電力供給途絶を招くような深刻な攻撃も見られるようになってきています。大規模停電に至れば、国民の生命・財産を脅かしかねません。我が国においても、国民の安全に責任を持つ政府と、電力の安定供給に責任を持つ事業者が連携し、サイバー攻撃対策に積極的に取り組む必要があります(第132-3-2)。
【第132-3-2】近年発生した電力分野の主要なセキュリティインシデント
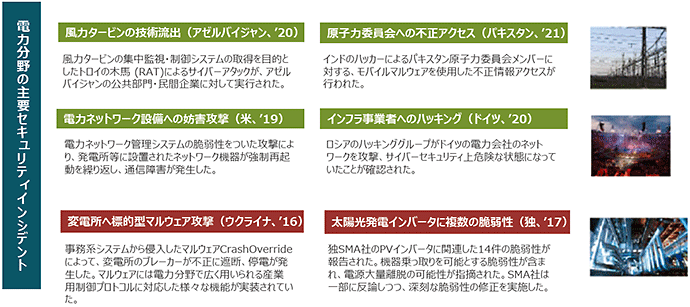
【第132-3-2】近年発生した電力分野の主要なセキュリティインシデント(ppt/pptx形式:87KB)
- 出典:
- CSIS「Significant Cyber Incidents Since 2006」より経済産業省作成
4. 脱炭素化とエネルギーセキュリティの両立
(1)次世代燃料の可能性
カーボンニュートラル実現時のエネルギー需給構造の在り方については複数の可能性がありますが、IEAの予測によれば、世界全体の電化率は、カーボンニュートラル実現段階でも47%に止まり、残り53%は熱に対する需要だとされています7(第132-4-1)。熱需要のうち、特に大きな割合を占めるのが鉄鋼や化学等の産業部門における高温の熱需要です。
こうした熱需要の脱炭素化に貢献すると期待されているのが、水素やアンモニアといった次世代の脱炭素燃料であり、我が国のみならず、欧州を始め世界中で実用化に向けた研究開発や実証が精力的に進められています。水素やアンモニアの製造方法は複数存在しますが、脱炭素燃料として製造する場合には、再生可能エネルギーによる水の電気分解や、化石燃料の改質とCO2の分離回収(CCUS)を組み合わせた手法が有力です(第132-4-2)。
日本では、世界に先駆けて「水素社会」を実現するべく取り組んでいますが、大量の水素を安価、安定的に調達するには、国内における水電解装置等による水素製造に加えて、再生可能エネルギーやCCUSのコストが安い海外で水素を製造し、大量に輸送することも有力な選択肢となります。水素を大量に貯蔵し、長距離を輸送する技術も複数存在し、液化水素、有機ハイドライド、アンモニアの3つが有力とされますが、それぞれに長所・短所があり、社会実装に向けた研究開発・実証段階にあります。再生可能エネルギーが豊富なドイツなども、将来必要となる水素を自国でまかなうのみならず海外から輸入することに関心を示しています。このような中、我が国の脱炭素化はもちろん、産業競争力の強化にもつなげるため、水素を「つくる」「はこぶ」「つかう」技術を我が国が早期に確立・商用化していくことが重要です。政府としては、グリーンイノベーション基金等も活用しながら、民間企業の取組を強力に後押ししていきます(第132-4-2)。
【第132-4-1】温室効果ガス排出量ネットゼロ段階 での世界の電化率見通し
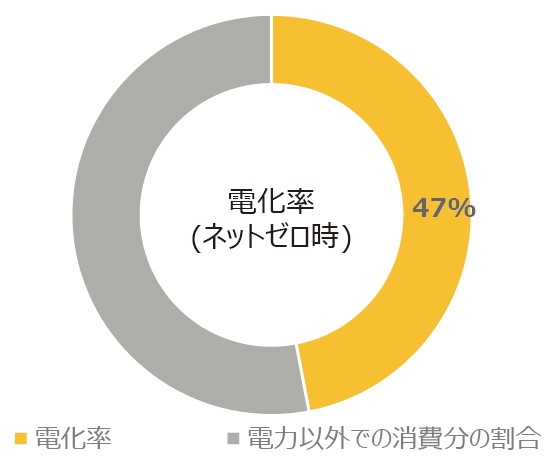
(注)グラフはIEA「World Energy Outlook 2020」SDSシナリオベース
(注)電化率=最終エネルギー消費に占める電?消費の割合
【第132-4-1】温室効果ガス排出量ネットゼロ段階 での世界の電化率見通し(ppt/pptx形式:41KB)
- 出典:
- IEA「Energy Technology Purspectives 2020」より経済産業省作成
【第132-4-2】次世代燃料のセキュリティ
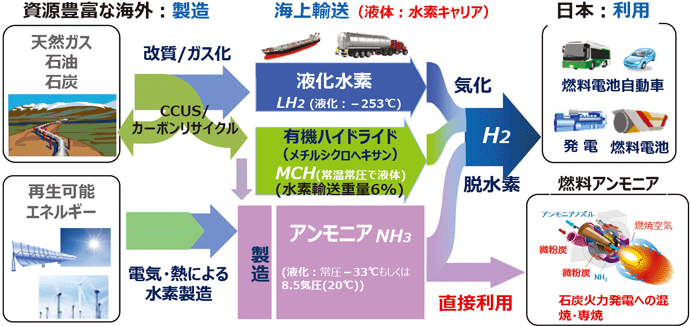
【第132-4-2】次世代燃料のセキュリティ(ppt/pptx形式:394KB)
- 出典:
- 総合資源エネルギー調査会第35回基本政策分科会資料より抜粋
COLUMN
諸外国のエネルギー政策文書等から見るエネルギーセキュリティの重点の変遷
諸外国(英・米・仏・独・中・韓)について、政府文書等におけるエネルギーセキュリティに関する記載を抜き出し、重点的に記載されている内容を時系列で整理すると、その国が自国に化石燃料資源を豊富に有するかどうかによって、エネルギーをめぐる情勢変化への対応が分かれることが見えてきます。
例えば、石油危機後の1970年代には、国内に化石燃料資源を有する米国や英国では、まずは国内資源開発を通じてエネルギー安全保障の強化に取り組んでいますが、資源に乏しいフランスやドイツでは、石油危機を契機に原子力開発を加速させています。また、同じく小資源国の韓国も1978年の古里原子力発電所運転開始を皮切りに、1980年代・1990年代にわたり、原子力発電所の建設を積極的に進めることになります。
1980年代半ば以降は資源価格が下落し、規制緩和が進み、市場原理の導入に力点が置かれていましたが、2000年代に入ると、資源価格の高騰に伴って再びエネルギー安全保障が重視されるようになります。国内に化石燃料資源を有する米国では再び国内資源開発が進みましたが、エネルギー安全保障に加えて気候変動対策への意識も高まっていた欧州では、その両方に資する再生可能エネルギーの開発が資源国・非資源国問わず、進められることとなりました(第132-4-3)。
【第132-4-3】諸外国の政策文章等から見るエネルギーセキュリティの重点の変遷
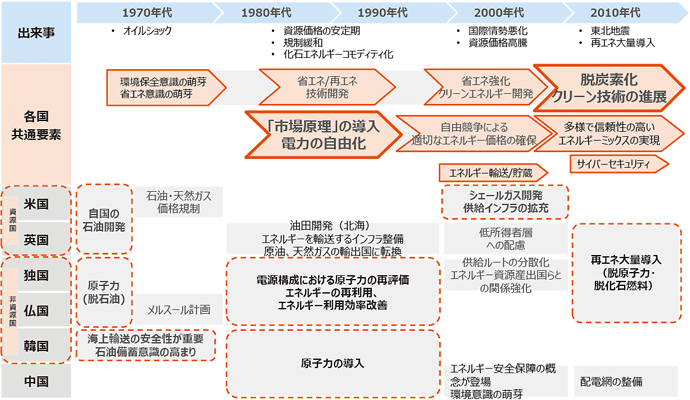
【第132-4-3】諸外国の政策文章等から見るエネルギーセキュリティの重点の変遷(ppt/pptx形式:204KB)
- 出典:
- (株)日本総合研究所「令和2年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等委託事業(エネルギーに影響を与える国内外の経 済社会動向に関する調査)」(2021年3月)
COLUMN
スーパーメジャー各社における脱炭素時代の事業戦略
原油の探鉱・開発・生産・輸送・精製・販売までを一貫してグローバルかつ大規模に展開してきたスーパーメジャー8も、昨今の世界的なカーボンニュートラルの流れや拡大するESG投資の動向を受けて、事業戦略の転換を進めており、伝統的に事業の柱であった化石燃料に関する投資額の削減や、電力小売、再エネ、水素等への新分野への進出等を目標として掲げる企業が出てきています(第132-4-4)。
ただし、現在のスーパーメジャーの収益の中心は、依然として原油事業であることから、目標の実現には抜本的な事業転換が必要となります。具体的に各社がどのように対応しようとしているのか、それぞれの投資動向を分析すると、各社のアプローチは大きく異なっていることが見て取れます。
例えば、天然ガス・LNG事業に強みを有する英蘭Shellと仏TOTALは、脱炭素社会への「移行」期間に稼ぐことを念頭に、石油から天然ガス・LNG事業等へのポートフォリオ転換を進めています。天然ガス・LNGは、化石燃料の中では比較的二酸化炭素の排出量が少なく、証書を活用したカーボンニュートラルLNGの販売も始まっています。また天然ガス・LNG発電は柔軟性が高いために天候に左右される太陽光や風力発電のバックアップ電源として機能するなど、カーボンニュートラルに向けた「移行」期間においては引き続き一定の存在感を有する資源になると見込まれています。一方で、英BPは脱石油ビジネスと再エネへの事業転換を他社以上急速に進めています。対照的に、米Chevronは、長期的な石油・天然ガスの世界需要は拡大するという見立てから、CCSやバイオ燃料に投資しながらも、引き続き上流開発を強化しようとしています。
世界全体のカーボンニュートラルに向けた取組と石油需要の縮小がどのくらいの速度で進むのかによって、スーパーメジャー各社間の今後の相対的な優位性が大きく変化することになりそうです。
【第132-4-4】スーパーメジャー各社における脱炭素時代の事業戦略の概要
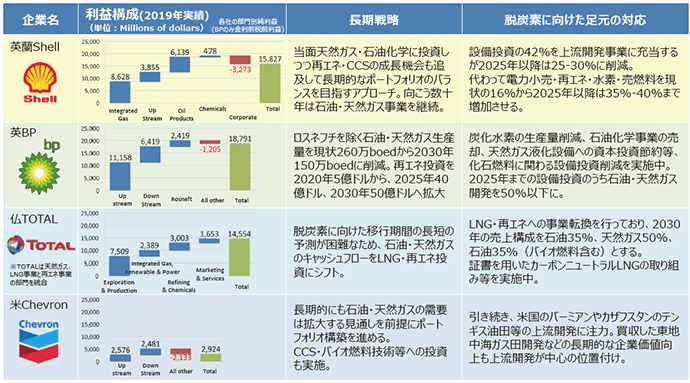
【第132-4-4】スーパーメジャー各社における脱炭素時代の事業戦略の概要(ppt/pptx形式:106KB)
- 出典:
- JOGMEC「メジャー企業2020年第3四半期決算とエネルギートランジション戦略について」と各種公表情報より経済産業省作成
- 2
- 北米大停電が発生した2003年にも、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた系統投資の重要性が指摘されましたが、ただ、この年のWEOの中心に据えられたのは引き続き「石油の安定調達」でした。
- 3
- 京都議定書に続く、温暖化対策の国際的なルール(次期枠組)を決めることを目的とした合意内容でしたが、数カ国が合意の採択に反対したため、拘束力のある数値目標など、新たな仕組みを決定する最終合意に至ることはできませんでした。
- 4
- Allianz、AXA、Zurich Insurance Group等の保険会社、アセットマネジメント会社が参加し、議論が進められています。
- 5
- Munich Re, Munich、Swiss Re、Stanford University等の保険会社や金融機関、学術機関の参加を得て議論を進めています。
- 6
- 代表幹事である東京大学小宮山涼一准教授に加え、金融界から荻野零児・三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) シニアアナリスト、木村彰宏・損害保険ジャパン(株)ビジネスデザイン戦略部長、竹田達哉・(株)三井住友銀行 サステナビリティ推進室長、蛭間芳樹・(株)日本政策投資銀行 産業調査部 調査役、産業界から坂梨興・大阪ガス(株)執行役員・企画部長、鈴木眞吾・三井不動産(株)執行役員ビルディング本部副本部長、岸野寛・東京ガス(株)専務執行役員 総合企画担当、谷口直行・NTTアノードエナジー(株)取締役スマートエネルギー事業部長、中原俊也・ENEOS(株)常務執行役員、長﨑桃子・東京電力ホールディングス(株) 常務執行役、渡部正治・三菱重工業(株)シニアフェロー・パワードメイン技師長、工藤拓毅・日本エネルギー経済研究所 理事、安部大介・(株)ウェザーニューズ 執行役員 サービス統括主責任者、高須芳彦・リンナイ(株)海外事業本部 副本部長、オブザーバーとして長谷川雅巳・(一社)日本経済団体連合会 環境エネルギー本部長、宮田卓・電気事業連合会立地環境部長、須藤 幸郎・石油連盟企画部長、深野行義・(一社)日本ガス協会企画ユニット環境部長、池田賢志・金融庁 総合政策局 チーフサステナブルファイナンスオフィサーの参加を得て議論を進めています(2021年3月31日時点)。
- 7
- 最終エネルギー消費に占める電力消費の割合を示します。
- 8
- 米ExxonMobil、英蘭Shell、英BP、米ConocoPhillips、米Chevron、仏Totalの6 社を指します