第1節 化石資源に係るエネルギーセキュリティ
1. 一次エネルギー自給率の現状
1973年、1979年の二度の石油危機で、エネルギーの大半を政情が不安定な中東からの輸入に頼ることのリスクが顕在化し、脱石油依存の観点から、原子力・石炭・天然ガスの開発が進められました。1980年代以降高まったエネルギー自給率は2010年には20.3%に至りましたが、2011年に東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故を契機とした原子力発電量の減少に伴い、約6%まで低下しました。足下では「固定価格買取制度(FIT)」の導入による再生可能エネルギー発電量の増加や、原子力発電所の再稼働、省エネルギー化のさらなる進展などによってエネルギー自給率は2018年に11.8%に回復してきているものの、東日本大震災前の2010年の水準には遠く及びません(第131-1-1)。世界のエネルギー動向に目を転じると、過去10年で、最も特徴的な変化を見せたのがシェール革命を起こした米国です。元々先進国の中では自給率の高かった米国ですが、シェールガス・シェールオイルの生産により自給率が向上しています。同じく近年自給率を上昇させているのが英国で、洋上風力・原子力に牽引される形で自給率を伸ばしています。電力に占める原子力の割合が高いフランスも高水準の自給率を維持しており、ドイツのエネルギー自給率は、長期的に低下傾向にあるものの、高い再生可能エネルギー普及率、石炭の国内生産、原子力発電の利用によって、日本の倍以上の自給率を維持しています。
【第131-1-1】各国の一次エネルギー自給率の推移
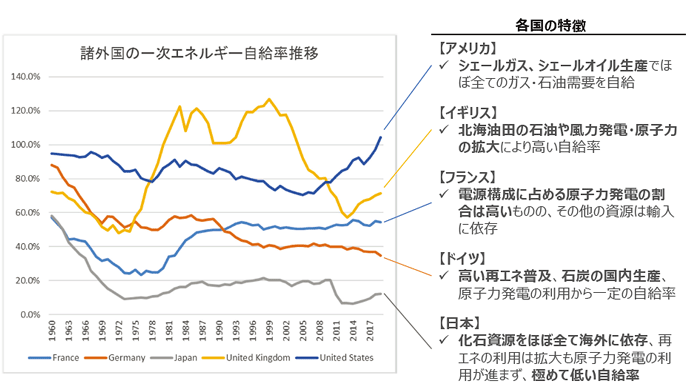
【第131-1-1】各国の一次エネルギー自給率の推移(ppt/pptx形式:102KB)
- 出典:
- 総合資源エネルギー調査会第38回基本政策分科会資料より抜粋
2. 化石燃料の調達先多角化と権益確保の状況
一次エネルギーの約9割を輸入に頼る我が国にとって、化石燃料の安価で安定的な確保はエネルギーセキュリティ上重要なテーマです。エネルギーセキュリティ向上のためには、燃料種の多様化と調達先の多角化、チョークポイント1リスクの低減等の取組が必要になります。例えば原油に関しては、チョークポイントを通過せずに輸入が可能なロシア産を確保することで、中東依存度の低下を図り、天然ガスについてはロシア・アフリカ・東南アジア・豪州・北米と、世界各地に調達先を広げることで、リスクの分散を図っています。積極的な資源外交やJOGMECを通じた海外プロジェクトへのリスクマネー供給等を通じ、更なる海外権益の確保を進める必要があります(第131-2-1)。
【第131-2-1】化石燃料の調達先多角化と権益確保の状況
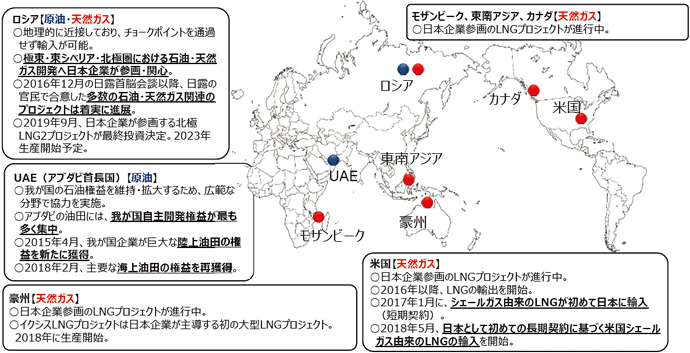
【第131-2-1】化石燃料の調達先多角化と権益確保の状況(ppt/pptx形式:141KB)
- 出典:
- 総合資源エネルギー調査会第38回基本政策分科会資料より抜粋
3.天然ガス・LNG市場価格の推移
天然ガス・LNGは、化石燃料の中で相対的に二酸化炭素の排出量が少なく、天候等に発電量が左右される太陽光・風力等の導入拡大に不可欠な柔軟性(フレキシビリティ)を供給することに優れており、特にカーボンニュートラルに向けた「移行」を後押しする技術として、重要性が増しています。天然ガス・LNGの市場価格は、アジア市場の需給状況に加え、原油価格の水準に連動して変化するものが多く、価格の変動幅が大きいという特徴があります。エネルギーセキュリティ向上の観点からは、大幅な価格上昇が起きた場合にも小売価格が高騰しないよう、金融的手法等を講じて対応する必要があります(第131-3-1)。
【第131-3-1】天然ガス・LNG市場価格の推移
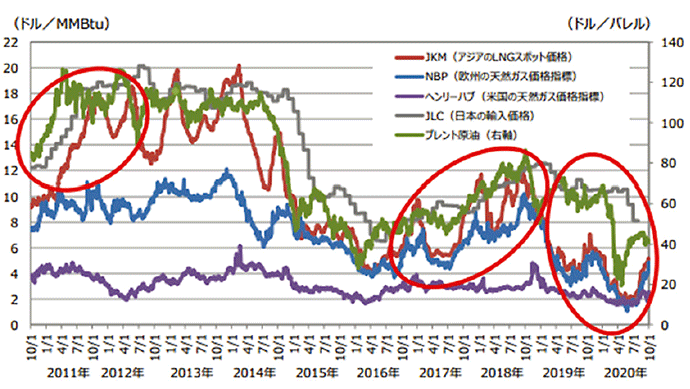
【第131-3-1】天然ガス・LNG市場価格の推移(ppt/pptx形式:115KB)
- 出典:
- S&P Global Platts, and others
COLUMN
2020年度冬期の日本の電力需給ひっ迫とスポット市場価格高騰をめぐる対策
2020年12月中旬以降、日本では、断続的な寒波による電力需要増加とLNGの在庫減少によるLNG火力発電の稼働抑制などにより、電力需給ひっ迫とそれに伴うスポット市場(以下「市場」という。)価格高騰が発生しました。まず12月中旬に、一部のエリアにおいて電力需給が厳しい時期が生じ、LNGの燃料消費が進みました。また、市場価格は比較的落ち着いて推移していたものの、平時よりは高値水準となりました。その後12月下旬は需要も比較的落ち着き、供給力も向上したものの、石炭火力発電所のトラブル停止やLNG火力の燃料制約実施に伴い、市場への売り玉が切れるようになり、市場価格がかなりの高値を付け始めました。1月上旬になると、全国にわたって10年に一度の需要が発生した日が複数生じるなど、最も厳しい需給状況となり、市場価格が高騰しました。1月中旬には、需要が例年までに落ち着き、供給力も増加しましたが、売り切れ状態・市場価格高騰は継続したままでした。その後、インバランス料金の上限価格の導入や燃料在庫が増加傾向となってきたことにより、徐々に市場価格も落ち着き、1月25日の週には、事象はおおむね沈静化しました(第131-3-2)。
【第131-3-2】2020年度冬期の需給ひっ迫・市場高騰をめぐる時系列整理
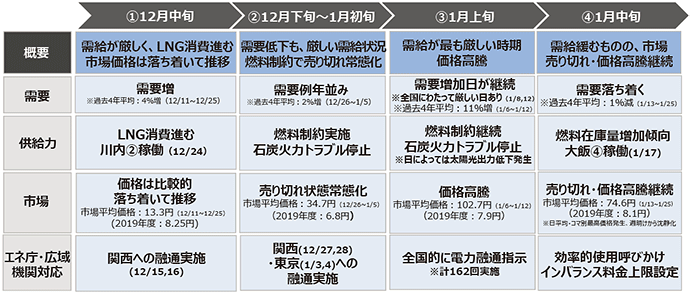
【第131-3-2】2020年度冬期の需給ひっ迫・市場高騰をめぐる時系列整理(ppt/pptx形式:62KB)
- 出典:
- 総合資源エネルギー調査会第34回電力・ガス基本政策小委員会資料より抜粋
これを受け、資源エネルギー庁の審議会や電力・ガス取引監視等委員会において、原因究明や検証を行いました。2020年度冬期の電力需給ひっ迫は、断続的な寒波による電力需要の大幅な増加とLNG供給設備のトラブル等に起因したLNG在庫減少によるLNG火力の稼働抑制が主因だったと考えられます。さらに、石炭火力のトラブル停止や渇水による水力の利用率低下、太陽光の発電量変動といった事象が重なったことで、LNG火力等への依存度が高まり、需給ひっ迫が増幅される結果となりました。こうした需給ひっ迫の背景には、石油火力の休廃止や稼働中原発の減少という構造的事象も存在しています。また、市場においては、これまでに入手したデータ等に基づく監視・分析によれば、相場を変動させることを目的とした売惜しみ等の問題となる行為は確認されませんでしたが、燃料不足の懸念による供給力の減少と寒波による需要増などにより売り切れ状態が継続的に発生し、スパイラル的に買い入札価格が上昇した結果、市場価格が高騰しておりました。
こうした検証を踏まえ、2020年度冬期の教訓を最大限に活かせるよう、電力需給のひっ迫やそれに伴う市場での売り札切れ継続を前もって防ぐための「予防対策」、電力量(kWh)不足が懸念されたり、差し迫ったりした際の対応の整理やセーフティネットの措置といった「警戒時・緊急時対策」、さらには、安定供給とカーボンニュートラルの両立に向けた供給力の確保や新規投資を促すための措置など自由化の進展や脱炭素の流れを踏まえた電気事業の構造的変化を受けて今から対応・検討していくべき「構造的対策」について、取りまとめ(案)を公表し、国民の皆様の御意見を頂いているところです(第131-3-3)。
これらの対策を通じて、今後、同様の事象が生じないように取り組むとともに、持続可能な電力システムの構築に向けて引き続き検討を行っていきます。
【第131-3-3】電力需給ひっ迫・市場価格高騰に係る事象要因と対策のポイント
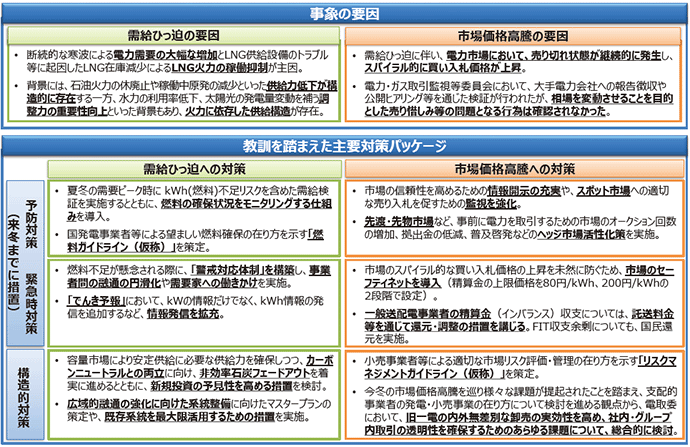
- 出典:
- 総合資源エネルギー調査会第34回電⼒・ガス基本政策⼩委員会資料より抜粋・⼀部修正
- 1
- 物資輸送ルートとして広く使われている狭い海峡のことで、米国エネルギー省エネルギー情報局(EIA)が示したレポートにあるチョークポイント8 カ所、すなわちホルムズ海峡、マラッカ海峡、バル・エブ・マンデブ海峡、スエズ運河、トルコ海峡、パナマ運河、デンマーク海峡、喜望峰を指します。