第3節 世界的なエネルギー価格の高騰が日本に与える影響
第3章第2節で概観したように、2021年以降、複合的な要因でエネルギーの価格が世界的に高騰し、各国の輸入物価や消費者物価にも影響を与えています。資源を輸入に頼る日本は世界的なエネルギー価格高騰の影響を受けやすいことから、その影響の把握は重要です。本項では、資源価格の影響を大きく受けると考えられるエネルギー多消費産業を中心に、資源価格の変動が産業の投入・産出価格に及ぼす影響について分析します。
1.世界的なエネルギー価格の変動と日本における輸入物価と消費者物価の動向
原油価格等の上昇を受け、日本の企業物価は2021年2月に前年同月比9.3%増と、第二次石油危機の1980年12月(10.4%)以来の歴史的な上昇率を記録するとともに、輸入物価(円ベース)も同34.0%増と、リーマンショック直前の2008年8月以来の高い水準を記録しました。一方で、消費者物価は、石油危機当時と異なりほぼ横ばいで推移しており、国際市況上昇の消費者物価への波及は限られています(第133-1-1)。
【第133-1-1】原油価格、輸入物価指数、国内企業物価指数、消費者物価指数の推移
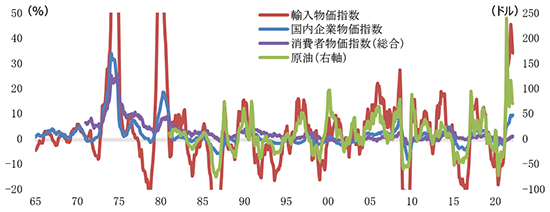
企業物価の分野別内訳を見ると、いわゆるウッドショック19の起こった木材・木製品が2015年比で6割も上昇したほか、鉄鋼、非鉄金属、石油・石炭製品で同じく4割上昇する一方で、輸送用機器や生産用機器などについてはほぼ横ばいで推移しました。鉄鋼、非鉄金属、石油・石炭製品といったエネルギー多消費産業は、エネルギー価格上昇の影響を大きく受けて投入物価が上昇したと考えられますが、素材産業から加工組立産業を経て消費者に届くまでの間に、価格上昇がサプライチェーンの各段階で転嫁できずに吸収されていったと考えられます(第133-1-2)。
【第133-1-2】素材分野及び組立加工業における企業物価指数の推移
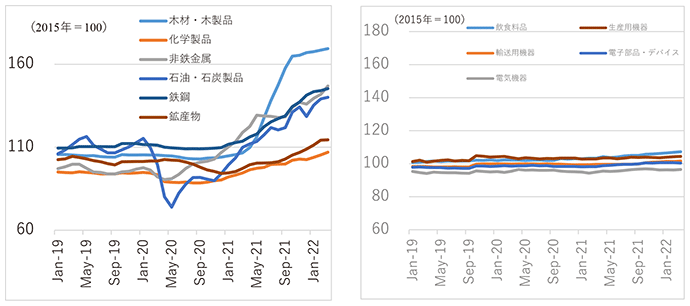
【第133-1-2】素材分野及び組立加工業における企業物価指数の推移(xls/xlsx形式737KB)
2.各産業における国内生産額に占めるエネルギーの割合
鉄鋼、非鉄金属、石油・石炭製品といったエネルギー多消費産業の間でも、各産業における国内生産額に占めるエネルギー投入額の割合が高いほど、その影響は大きくなります。そこで、産業連関表から国内生産額に占めるエネルギーの割合を見ると、2015年時点で、例えば鉄鋼業(銑鉄28.3%)、化学分野(石油化学基礎製品81.0%)、紙・パルプ分野(パルプ業12.8%)、窯業・土石業(セメント32.0%)の4業種で特に高くなっています。これらの業種では、製造プロセスで大量の電力や熱を使用するほか、鉄鋼・化学等では原料として石炭や石油を用いることも要因となっています。
上記の素材系の4業種を中心に、エネルギー価格の変動がどのように製品価格に転嫁されるのか、といった分析を行いました。
【第133-2-1】エネルギー多消費産業における主なエネルギーの用途
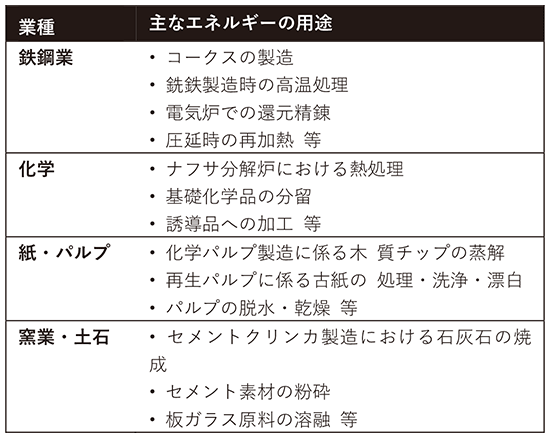
【第133-2-2】各業種の生産額に占めるエネルギーコストの割合20
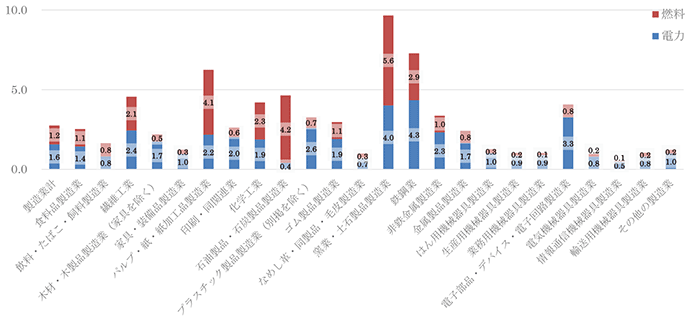
3.各産業における転嫁の進み具合
鉄鋼、化学製品、パルプ・紙・木製品、窯業・土石製品(セメント)等の製造業は、幅広い製品の基礎的な部素材として活用されているほか、日本国内で大きな付加価値と良質な雇用を創出するなど、日本経済の根幹を支える産業です。今般のエネルギー価格高騰のように投入財の大きな価格変動が生じると、その影響がサプライチェーン上で適切に配分されず、一部の事業者・消費者に過度にしわ寄せが行ってしまう可能性があります。
本項では、各産業における投入物価と産出物価を比較し、それぞれどの程度転嫁が進んでいるかを分析します。分析に当たっては、実際の産出物価と、投入物価の上昇が産出物価に全て同月中に転嫁され、付加価値(中間投入以外)の価格が一定であったと仮定した場合の産出物価の推計値との比較を行うことで、各産業の価格転嫁の進み具合を機械的に試算しました。なお、後に見るように、足下の価格変動要因の大部分はエネルギーであるため、本分析はおおむねエネルギー価格の転嫁を示している考えることができます21。最後に、エネルギー価格上昇に大きな影響を受ける消費者向けの財・サービスについて、実際にどの程度影響を受けているのか分析します。
まず、第133-3-1を見ると、多くの産業はおおむね価格転嫁が100%行われている45度線上に位置していますが、鉄鋼、化学製品、非鉄金属、パルプ・紙・木製品等の素材系業種でも、実際の産出物価がおおむね推計値と近い水準になっており、転嫁が進みやすくなっていることが分かります。他方、輸送用機械や情報機器など加工度が高い分野は、実際の産出物価が推計値の水準を下回っており、転嫁が進みにくい状況です。一方、素材系業種でも窯業・土石製品では、産出物価が推計値の水準を大きく下回っており、業界の商慣習などの影響が出ていると推察されます。
全体として見ると、素材系業種では比較的価格転嫁をしやすい一方、加工組立型業種では転嫁が進みにくい大まかな傾向が見られます。ただし、加工度や商慣行によって産業ごとに転嫁の進み具合に違いが見られることには留意が必要です。
【第133-3-1】各産業における産出物価と産出物価の推計値の関係22
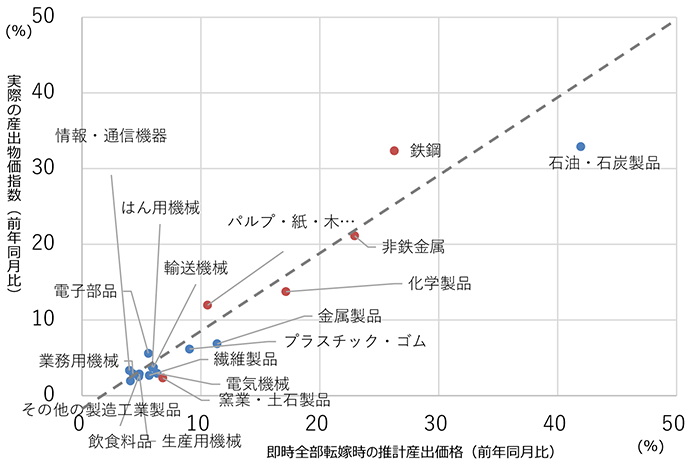
【第133-3-1】各産業における産出物価と産出物価の推計値の関係(xls/xlsx形式294KB)
- 資料:
- 日本銀行「製造業部門別投入・産出物価指数」、総務省「産業連関表」
【第133-3-2】各産業の推計産出物価/実際の産出物価
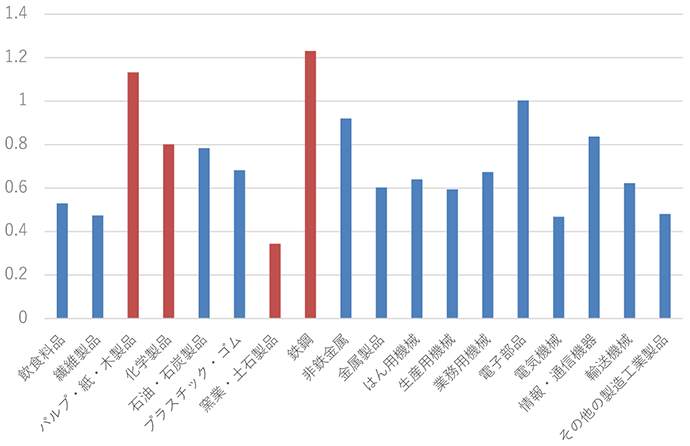
【第133-3-2】各産業の推計産出物価/実際の産出物価(xls/xlsx形式292KB)
(2)物価の変動に対するエネルギーの寄与度23
価格転嫁に要する時間は産業ごとに異なるため、一時点での比較のみではなく、時系列で投入物価と産出物価の時間差を考慮した評価をしていくことも重要です。本項では、時系列のデータを用いて、投入物価上昇率を寄与度分解して足下の投入物価の上昇の主因がエネルギーであることを確認する(自己部門については脚注21を参照)とともに、投入物価の上昇が全て同月中に産出物価に転嫁されたと仮定した場合の産出物価の推計値を、実際の産出物価と併せて示すことで、価格の転嫁のピーク同士の比較や転嫁に要した時間を分析します。
①鉄鋼
鉄鋼では、投入物価の変動に、鉱業、石油・石炭製品が大きく寄与しており、鉄の原料となる鉄鉱石(鉱業)に加え、高炉で多量の熱を発生させる一般炭(鉱業)や、鉄を還元する際に必要となる原料炭(鉱業)、コークス(石油・石炭製品)が、鉄鋼の投入物価全体に大きく影響していることが分かります。また、産出物価の推計値と産出物価の実績値の推移を比較すると、散布図の近似曲線の傾きが1を超えており、決定係数も非常に高いことからも、おおむね産出物価の実績値と産出物価の推計値が連動しており、相当程度、時間を置かずに転嫁が進んでいると考えられます。
【第133-3-3】エネルギー投入物価の寄与度分解と、産出物価の推計値と実績値の関係(鉄鋼)
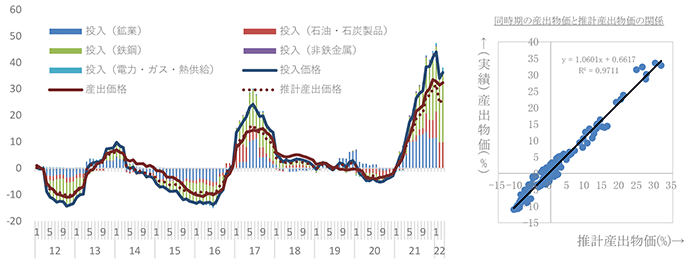
【第133-3-3】エネルギー投入物価の寄与度分解と、産出物価の推計値と実績値の関係(鉄鋼)(xls/xlsx形式210KB)
- 資料:
- 日本銀行「企業物価指数」より経済産業省作成。
②化学工業
化学工業では、自己部門を除くと石油・石炭製品の寄与度が大きく、ナフサ(石油・石炭製品)等の寄与が化学製品の投入物価に大きく影響していることが分かります。また、推計産出物価と、実際の産出物価の推移を比較すると、散布図の傾きも0.85と1に近く、決定係数も高いため、ある程度転嫁が進んでいる状況です。
【第133-3-4】エネルギー投入物価の寄与度分解と、産出物価の推計値と実績値の関係(化学製品)
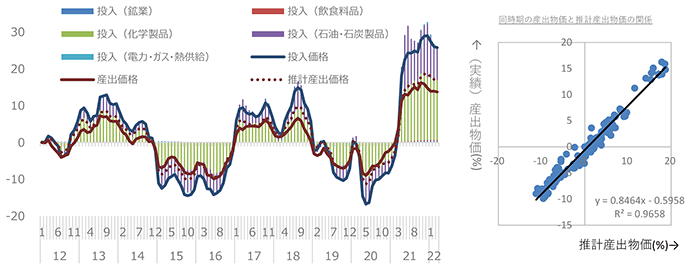
【第133-3-4】エネルギー投入物価の寄与度分解と、産出物価の推計値と実績値の関係(化学製品)(xls/xlsx形式224KB)
- 資料:
- 日本銀行「企業物価指数」より経済産業省作成
③パルプ・紙・木製品
紙・パルプ・木製品では、自己部門を除くと農林水産業、鉱業、化学製品、石油・石炭製品の寄与度が大きいことが分かります。ウッドショック(脚注19参照)により丸太(農林水産業)が木製品に与える影響が大きいですが、本稿で念頭に置いているパルプ・紙についても、乾燥工程で必要とされる一般炭(鉱業)や塗料(化学)等のエネルギーもパルプ・紙の投入物価の上昇に寄与していることが分かります。また、推計産出物価と、実際の産出物価の推移を比較すると、散布図の傾きも0.82と1に近く決定係数も高いため、ある程度転嫁が進んでいると言えます。また、推計産出物価が高い(つまり投入物価が高い)ときほど実際の産出物価が高くなっていることもこの業種の特徴です。
【第133-3-5】エネルギー投入物価の寄与度分解と、産出物価の推計値と実績値の関係(紙・パルプ・木製品)
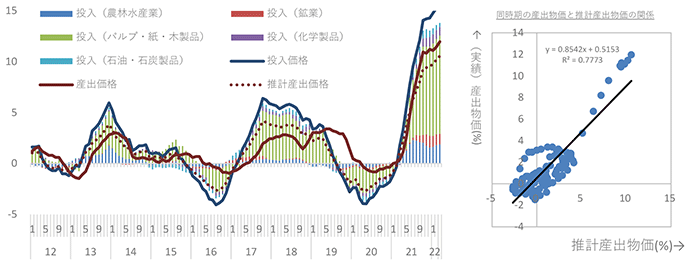
【第133-3-5】エネルギー投入物価の寄与度分解と、産出物価の推計値と実績値の関係(紙・パルプ・木製品)(xls/xlsx形式251KB)
- 資料:
- 日本銀行「企業物価指数」より経済産業省作成
④窯業・土石製品
窯業・土石製品では、鉱業、石油・石炭製品、化学製品、電力・ガス・熱供給の寄与度が大きく、セメント製造時の焼成プロセスで用いる一般炭(鉱業)やコークス等の寄与が窯業・土石製品の投入物価に大きく影響していることが分かります。推計産出物価と、実際の産出物価の推移を比較すると、推移の図ではあまり連動しているように見えず、散布図の決定係数が低く、第2象限、第4象限にも点が散らばっており、転嫁が進みづらい業種であることが推察されます。特に足下では、推計産出価格の上昇に実際の産出価格が追い付いていない状況です。
【第133-3-6】エネルギー投入物価の寄与度分解と、産出物価の推計値と実績値の関係(窯業・土石製品)
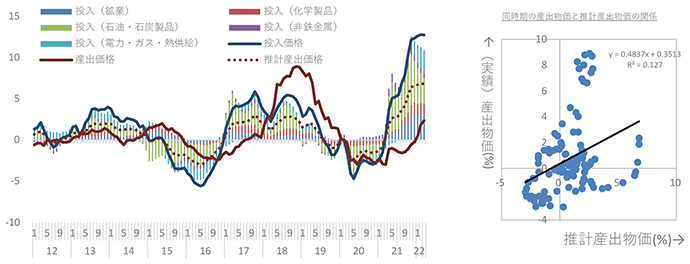
【第133-3-6】エネルギー投入物価の寄与度分解と、産出物価の推計値と実績値の関係(窯業・土石製品)(xls/xlsx形式251KB)
- 資料:
- 日本銀行「企業物価指数」より経済産業省作成
⑤輸送機械
ここまで素材型業種を見てきましたが、ここでは加工組立型業種の代表例として輸送機械を見ていきます。自動車等の部品として供給される金属製品(鉄鋼、非鉄金属)や塗料(化学工業)等が上昇要因として寄与しているほか、電力・ガス・熱供給も上昇要因となっています。電力・ガス・熱供給自体は大きな寄与度ではありませんが、金属製品や塗料等の価格上昇を通じて、エネルギーが輸送機械の投入価格の上昇に寄与していると考えられます。実際の産出物価とその推計値の関係性を見ていくと、2016年以降はほぼ一貫して実際の産出物価が推計産出価格よりも低く、転嫁が進みづらい状況が続いていることが分かります。
【第133-3-7】エネルギー投入物価の寄与度分解と、産出物価の推計値と実績値の関係(輸送機械)
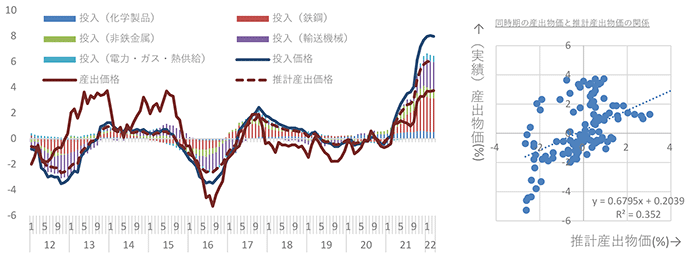
【第133-3-7】エネルギー投入物価の寄与度分解と、産出物価の推計値と実績値の関係(輸送機械)(xls/xlsx形式256KB)
- 資料:
- 日本銀行「企業物価指数」より経済産業省作成
⑥エネルギー分野
次に、エネルギーに関連の大きな財の消費者物価を見ていきます。まず、エネルギーそのものの消費者物価から確認します。
エネルギーの消費者価格は、2021年5月にプラスに転じ、その後ほぼ一貫して上昇を続けて、足下では22.2%になっています。2021年5月時点でプラスに寄与していたのは主にガソリンでした。ガソリンは、2021年3月にプラスに転じて以来、継続的にエネルギー価格を押し上げてきました。足下では電力や都市ガスもプラスに寄与しています。ただし、電力・都市ガスはそれぞれ燃料費調整制度と原料費調整制度により価格の反映にラグが生じるため、2021年8月、2021年10月にプラスに転じました。
【第133-3-8】エネルギーの消費者物価の推移(前年同月比)
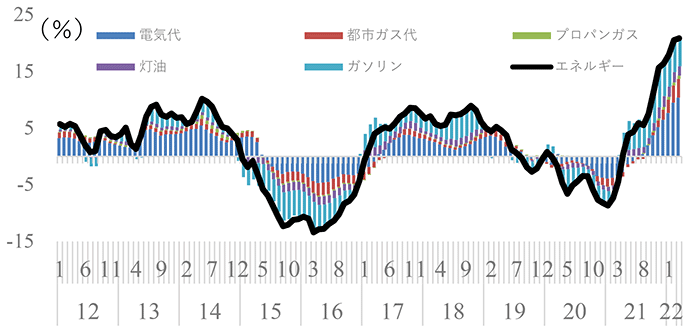
【第133-3-8】エネルギーの消費者物価の推移(前年同月比)(xls/xlsx形式238KB)
- 資料:
- 総務省「消費者物価指数」より経済産業省作成
⑦運輸
次に、コスト構造上、エネルギー価格上昇の影響を大きく受ける運輸の状況を確認します。足下でガソリン価格や電力料金が大きく上昇している一方、交通の消費者物価はほとんど変動していません。航空運賃は比較的変動しており、足下では上昇していますが、特にJR、路線バス、タクシーはほとんど価格が動いていない状況です。これは料金を変更する場合には事業法に基づく認可等が必要であるため、エネルギー価格の上昇を消費価格に転嫁しきれていない状況であると推察されます。
足下のエネルギーの価格上昇は、輸入物価を通じ、川上の素材産業から川下の加工組立型業種を経て、消費者価格に中長期的に影響を及ぼしていくと考えられます。ここでは、素材型業種のうち窯業・土石製品のように製品分野によっては価格転嫁が進んでいない状況があることをデータで確認しました。また、消費者価格については、消費者のマインドの影響を受けるほか、価格変更に政府の認可が必要な業種があることから、エネルギー価格の上昇が製品価格に反映されづらいということや、反映される場合でも時間を要することを確認しました。
今後、ロシアのウクライナ侵略が長引いてエネルギー価格が高止まりしたり、脱炭素に向けた取組を進めるための新規投資等を拡大させていくと、価格・量の両面からエネルギーコストが上昇していくことが予想されます。個社で考えれば、個別企業にとってはコストの上昇につながるため、いずれかの段階で販売価格を引き上げていく必要が生じます。ただし、本項で確認したように、全ての業種で適時に販売価格を引き上げることは困難です。このため、日本経済全体としては、エネルギー源の多角化や調達先の多様化等を通じてエネルギーの輸入価格を抑えながら、エネルギー生産性を向上させることを第一として、それでも補いきれない場合には、企業・消費者の間でエネルギー価格の上昇をどのように負担するのか、議論を深めていくことが重要です。
【第133-3-9】運輸の消費者物価とエネルギーの企業物価の推移
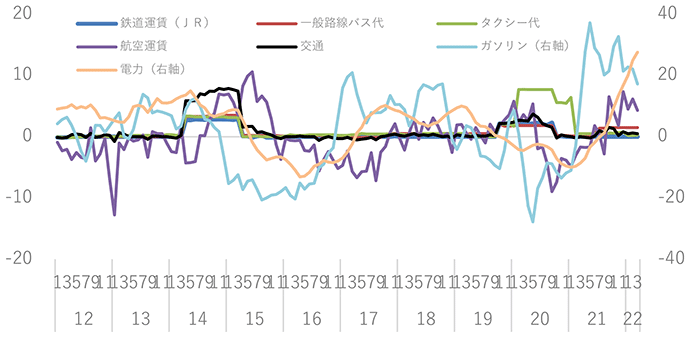
【第133-3-9】運輸の消費者物価とエネルギーの企業物価の推移(xls/xlsx形式89KB)
- 資料:
- 総務省「消費者物価指数」、日本銀行「企業物価指数」より経済産業省作成
- 19
- 2021年以降、米国における住宅着工戸数の急増、中国の木材需要増大や世界的なコンテナ不足による運送コストの増大等により木材価格が世界的に高騰し、国産材の製品価格も上昇しました。
- 20
- 総務省・経済産業省「工業統計調査」産業別統計表より作成。原材料使用額の内訳として公表されている燃料使用額及び購入電力使用額を生産額で除した割合を、それぞれ燃料及び電力の生産額に占めるエネルギーコストとみなしています。
- 21
- 自己部門(例えば産出が鉄鋼の場合、投入部門としての鉄鋼)の投入価格も大きく寄与していますが、中間投入としての鉄鋼の価格上昇は元を辿ればより上流の他部門、すなわちエネルギーや資源の価格上昇の影響を受けているため、自己部門の価格変動は他部門で按分して考えることも可能です。ここでは按分はせず、自己部門の価格上昇もエネルギー等の価格上昇によるものとして解釈して分析しています。
- 22
- 日銀の投入物価、産出物価の前年同月比を用い、2022年2月時点のデータを使用。
- 23
- 日銀の投入物価、産出物価の前年同月比を用い、2012年4月〜2021年3月のデータを使用。投入物価のうち、足下におけるウエイトが高い5分野について、投入物価への寄与度を積み上げグラフで表示しました。また、産出物価のうち、エネルギー関連の寄与度のみが変化した場合に、どの程度産出物価が変化するか、という値を産出物価の理論値として定義し、産出物価の理論値と実際の産出物価の一致を見て転嫁の進み具合と定義しています。