第2節 世界的なエネルギー価格の高騰とロシアのウクライナ侵略
2021年は新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)からの経済回復に伴ってエネルギー需要が急拡大する一方で、世界的な天候不順や災害、化石資源への構造的な投資不足、地政学的緊張等の複合的な要因によってエネルギー供給が世界的に拡大せず、エネルギーの需給がひっ迫し、2021年後半以降、歴史的なエネルギー価格の高騰が生じています。エネルギーは国民生活や企業の生産活動に欠かせないものであり、エネルギー価格が継続的に高い水準で推移すれば、製品価格の上昇と購買力の低下等を通じて、各国の経済活動の大きな足かせになるのみならず、政治・経済・社会に更なる悪影響を及ぼしかねません。
2022年に入ると、2月にはロシアがウクライナに侵略し、世界のエネルギー情勢は混迷を深め、エネルギー価格の上昇は一過性のものにとどまらない可能性があります。各国政府は、中長期的な脱炭素の流れを認識しながらも、安定・安価なエネルギー供給を最優先に、価格抑制策や低所得者等への支援策や、産油国・産ガス国への増産要請、備蓄の強化、調達先の多様化等の政策を展開しています。
本節では、2021年の世界のエネルギー需給と価格の動向やその背景を概観した上で、各国別の影響や政策的な対応状況を整理します。その上で、世界的な資源価格の上昇が各国の輸入物価や消費者物価に及ぼす影響について概観します。
1.エネルギー価格の高騰
(1)天然ガス
まず、2020年に世界の一次エネルギー源として重要度を高めた天然ガスについて見ていきます。
2021年12月には、欧州のTTFで天然ガス価格が高騰を始め、年初来約8倍となる60ドル/MMBtuを記録しました。需要期の冬を前に値上がりすることは異例です。この背景は、次項で詳しく見ていきます。さらに、2022年2月になるとロシアがウクライナに侵略し、欧州がロシア産ガスからの脱却を目指したことで短期的な需給バランスが大きく崩れた結果、2022年3月には、天然ガス価格は欧州のみならずアジアのLNG市場でも史上最高値を付けました(欧州TTFで72ドル/MMBtu10・アジアJKMで85ドル/MMBtu11)(第132-1-1)。
【第132-1-1】天然ガス・LNG価格の推移
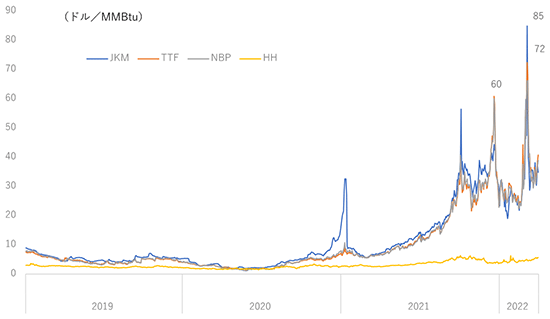
【第132-1-1】天然ガス・LNG価格の推移(xls/xlsx形式108KB)
- 資料:
- S&P Global Platts, ICE, CMEより経済産業省作成
(2)石油
原油価格も様々な要因から足下で大きく変動しています。米国の指標価格であるWTIは、新型コロナの感染拡大に伴う需要縮小の中で、2020年3月にOPECプラスの減産交渉が決裂すると、2020年4月20日12にはマイナス38ドル/バレルになりました。2021年には新型コロナからの回復に伴う需要増に加え、2020年後半にはガス価格の高騰により、ガスに比べて割安になった原油を発電用燃料として使う動きが欧州やアジアで広がったことで、原油価格の上昇が進みました。2022年2月にロシアがウクライナに侵略し、ロシア産原油の禁輸が議論されると、原油価格は100ドル/バレルを超え、3月にはWTIに加え、欧州の指標価格であるブレントともに取引時間中に130ドル/バレルを超えるとともに、アジアの指標価格であるドバイも引き続き高い水準で推移しています(第132-1-2)。
【第132-1-2】原油価格の推移
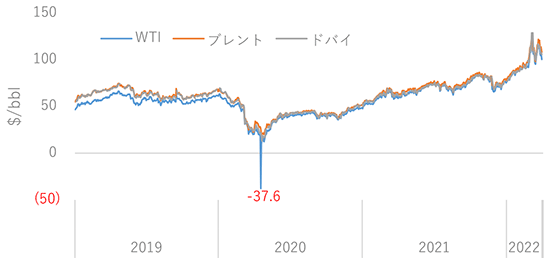
【第132-1-2】原油価格の推移(xls/xlsx形式74KB)
- 資料:
- Chicago Mercantile Exchageより経済産業省作成
(3)石炭
2021年には石炭価格が世界各地で上昇しました。これは、2021年の天候不順で欧州の風力発電(欧州の電源構成の13%)の設備利用率が低下し、ガス火力とともに石炭火力の需要が高まったこと、それにも関わらず2020年に新型コロナによる電力需要減で発電事業者が発電設備の供給量を拡大していなかったこと、また豪州の石炭の積出し機材の不具合等が背景にあげられます。その後、2022年に入って以降は、新型コロナの影響に加え、ロシアによるウクライナ侵略を始めとする国際情勢の不安定化、エネルギー・資源価格の高騰・高止まり懸念等、エネルギー安全保障が憂慮される状況となっていることを背景に、一旦落ち込んだ石炭価格は再び急騰しています。石炭輸入国はロシアからの石炭輸入の代替策を模索していますが、インドネシアや豪州等、石炭の主要輸出国では、輸出拡大は困難な状況です。インドネシアでは、国内の石炭需給がひっ迫し、政府は国内向けの石炭供給を確保するために、2022年1月1日から石炭の海外輸出を一時制限しました。また豪州では、新型コロナのオミクロン株の感染拡大の影響から、炭鉱の人員不足に陥り、更に3月には豪州東部を襲った記録的な豪雨により、炭鉱や輸出インフラの操業に支障が出る等しています。そうした中で、一般炭価格は3月上旬に一時400米ドル/t超まで高騰しました(第132-1-3)。
【第132-1-3】石炭(豪州一般炭)価格の推移
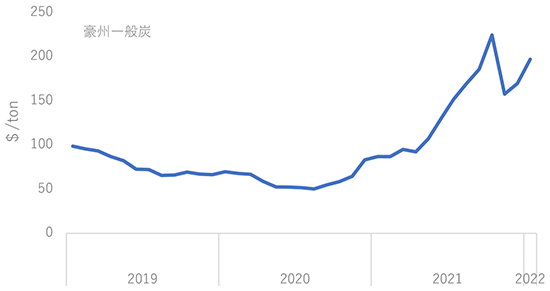
【第132-1-3】石炭(豪州一般炭)価格の推移(xls/xlsx形式31KB)
- 資料:
- The World Bank「Commodity Markets」より経済産業省作成
欧州では、これまで石炭火力発電及び炭鉱を廃止する脱石炭政策が急速に進められてきましたが、世界的な天然ガス価格の高騰に加え、風力発電の不調等により、2021年は卸電力価格が高騰しました。EUは、温室効果ガスの排出削減策の一環である排出量取引制度により、電気事業者等は排出権の購入を義務付けられていますが、石炭及び排出権の価格が高騰する中でも、ガス火力発電と比較し、石炭火力発電の方が安価状況です。ロシアによるウクライナ侵略により事態は加速しており、ドイツを始めとする各国で、少なくとも短期的には脱石炭を含むエネルギー政策の見直しが始まりつつあります。
2.エネルギー価格高騰の背景(構造要因)
(1)上流投資不足
世界の化石資源開発への投資は、資源価格の下落を受けて2015年頃から減少し、その後も脱炭素の流れもあって停滞しています。パリ協定合意前の2014年に8,000億ドル近くあった投資額は2021年にはほぼ半減し、足下で4,000億ドルに届かない見通しです(図132-2-1)。
【第132-2-1】上流開発投資額と上流開発企業の投資額の推移
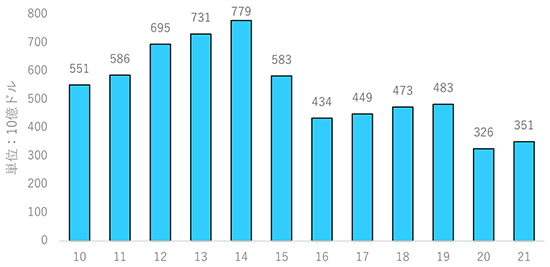
【第132-2-1】上流開発投資額と上流開発企業の投資額の推移(xls/xlsx形式16KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Investment 2021」より経済産業省作成
(2)エネルギー消費量の回復
2020年、新型コロナの拡大による世界的な経済活動の縮小により、世界の一次エネルギー消費量は第二次世界大戦後では最大となる4.5%の減少を記録しました。減少分の4分の3は石油であり、天然ガスは前年比で2.3%減にとどまりましたが、この結果、一次エネルギーに占める天然ガスの割合が25%に上昇し、エネルギー供給における天然ガスへの依存度が高まりました(第132-2-2)。また、IEAのGrobal Energy Review 202113によると、2021年には経済活動の回復を受けてエネルギー需要は4.6%の増加が見込まれています。エネルギー源別にみると、2019年水準から石炭需要は4.5%、天然ガス需要は1.3%の増加が予測されています。主としてアジアにおける石炭火力発電の拡大が石炭需要の回復を支え、天然ガス需要は中国を始めアジアで拡大するとしていますが、米国ではガス価格の高騰によって2020年水準を維持するとされています。
【第132-2-2】世界のエネルギー源別の消費量(左グラフ)と2019年、2020年におけるエネルギー源別シェア(右グラフ)
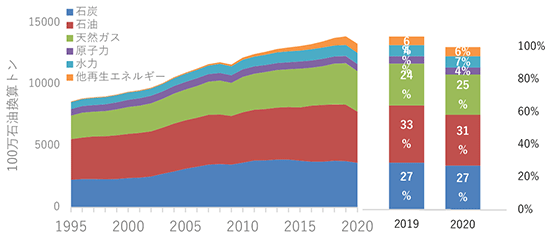
【第132-2-2】世界のエネルギー源別の消費量(左グラフ)と2019年、2020年におけるエネルギー源別シェア(右グラフ)(xls/xlsx形式36KB)
- 資料:
- BP統計より経済産業省作成
(3)電力供給構造の変化
二次エネルギーである電力の需要は、2020年には2019年比で0.5%減にとどまりました。供給側の変化の内訳をみると、減少分の過半は出力調整が可能な石炭火力でした。一方、出力調整ができない太陽光、風力等の自然変動電源は、2020年にも発電量を増やしました。この結果、世界の電力供給に占める自然変動電源比率は29%に上昇し、エネルギー供給における自然変動電源への依存度が高まりました。
2021年には経済活動の拡大に伴い、2020年比で電力需要は4.5%増となる見込みです。供給側を項目ごとに見ると、最も大きく伸びるのは石炭火力ですが、自然変動電源も同様に伸びるため、世界の電力供給に占める自然変動電源比率は30%(想定)と、2020年よりも更に依存度を高める見通しです(第132-2-3)。
【第132-2-3】世界の電力供給の電源別の動向(2019年と2020年、2021年の比較)
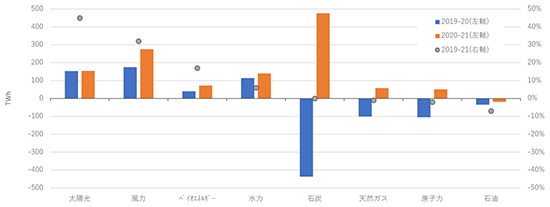
【第132-2-3】世界の電力供給の電源別の動向(2019年と2020年、2021年の比較)(xls/xlsx形式17KB)
- 資料:
- IEA「Global Energy Review 2021」より経済産業省作成
(4)各国の電力需給ひっ迫
2021年1月には、日本で寒波に伴う需要増により燃料不足や需給ひっ迫でLNGと卸電力前日のスポット価格が高騰しました。2月には米国テキサス州では寒波で多くのガス供給設備が停止し、大規模な輪番停電が実施されました。夏になると西部地域全体で猛暑となりカリフォルニア州で度々節電要請が出されました。8月にはハリケーンの「アイダ」の影響によりルイジアナ州などで大規模停電が起こりました。欧州でも熱波の到来によりギリシャで節電要請が出され、トルコでは停電が発生しました。南半球のニュージーランドでは寒波で輪番停電が実施されました。ブラジルでは干ばつによる渇水で節電要請が出されました。9月には石炭不足で中国において電力不足となると共にインドでも10月に石炭不足で電力不足が起こりました。欧州では9月頃から天然ガス価格の高騰により卸電力価格が高騰し、小売会社の撤退や電気料金の急激な上昇が続いています。年が明けた2月24日にはロシアがウクライナに侵略し、エネルギー価格の高騰が続いています(第132-2-4)。
【第132-2-4】2021年の主な大規模停電・需給ひっ迫状況
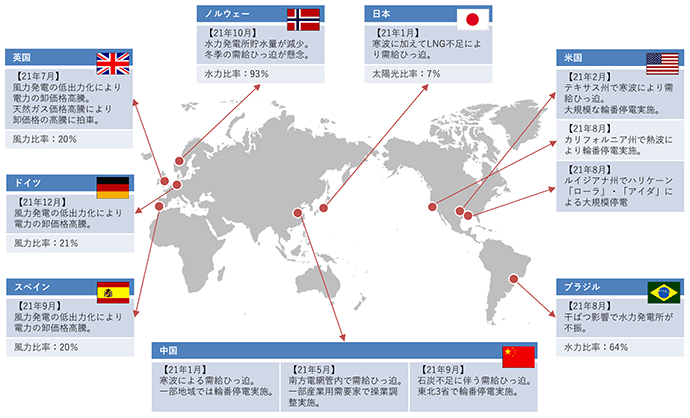
【第132-2-4】2021年の主な大規模停電・需給ひっ迫状況(ppt/pptx形式:194KB)
- 資料:
- IEA、エネルギー社会経済研究所より経済産業省作成
(5)欧州の天然ガス貯蔵量減少
欧州には、枯渇ガス田を転用した地下ガス貯蔵設備が各国に設置されており、仮に天然ガス・LNGの生産・供給が完全に停止した場合、冬期でも2ヵ月程度は耐えられる在庫が確保されています。2021年はこの在庫が、例年と比べ2割程度低い状態となっていました(第132-2-5)。
【第132-2-5】欧州天然ガス貯蔵量(直近2年)
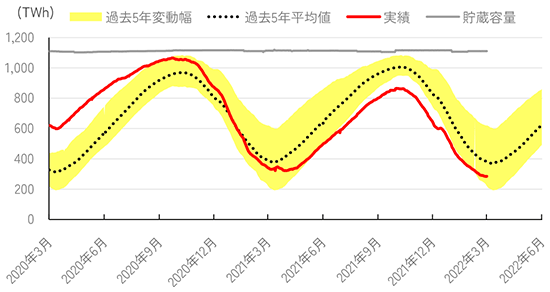
- 資料:
- AGSIデータからJOGMEC作成
欧州では、太陽光や風力等の自然変動電源の比率を近年拡大してきていますが、これらの電源は天候や時間帯で発電量が大きく上下します。この上下動を補い、エネルギーの安定供給を担保するためには、石炭火力、原子力、天然ガス火力等を調整電源として活用する必要がありますが、欧州では天然ガス火力への依存度が大きくなっていました。こうした中、2021年後半にロシアが欧州向けの天然ガス供給を絞り、2022年2月にロシアがウクライナを侵略した後は、天然ガス供給が世界的に絞られました。こうした結果、天然ガス火力が期待通りに活用できなくなり、欧州のエネルギー安全保障にも大きな影響を及ぼすことになりました。
天然ガス火力のみに頼る状況で、そのバッファーを失った欧州のエネルギーセキュリティは、ロシア産パイラインガスの供給変動に対する抵抗力が低下を表しており、この構造は今後も設備の増強等がない限りは基本的に継続すると考えられます14。
3.エネルギー価格高騰の背景(ロシアのウクライナ侵略要因)
(1)原油・天然ガス・石炭における各国のロシア依存度
ロシアのウクライナ侵略が各国のエネルギー情勢に与える影響は、各国の原油・天然ガス・石炭のロシアへの依存度によって大きく異なります。資源別のロシア依存度を見ると、各資源ともに欧州各国では依存度が高いことが分かります。ドイツが天然ガスの4割以上をロシアに依存し、原油・石炭もロシアが輸入シェア1位となっているほか、オランダが原油のほぼ全量をロシア依存している等、エネルギー安全保障上のリスクが高い状況になっていました(第132-3-1)。欧州各国が自国で一次エネルギーを賄うことができていないことに加え、特に天然ガスについてはロシアからの輸入にパイプラインを使っていることが、ロシア依存度を高めていると考えられます。
【第132-3-1】主要国におけるロシア産・原油・天然ガス・石炭の依存率(2020年)
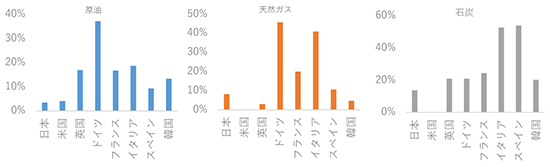
【第132-3-1】主要国におけるロシア産・原油・天然ガス・石炭の依存率(2020年)(xls/xlsx形式29KB)
- 資料:
- IEA「Reliance on Russian Fossil Fuels in OECD and EU Countries」より経済産業省作成
(2)ガスプロム社のデータから見る欧州向けガス輸出量推移
次に、世界最大のガス会社であるロシアのガスプロム社の公開情報から、主な取引先となる欧州に対してどのような供給が行われてきたのかについて見ていきましょう。
図132-3-2に示す通り、ガスプロム社の欧州(EU)向けの月別天然ガス輸出量の推移を見ると、2021年の秋から輸出量が減少しています(第132-3-2)。輸出量減少の要因として、スポット販売に相当するガスプロム社のESP(電子販売プラットフォーム)における販売量の減少も要因の一つとして考えられます。事実、ガスプロム社は2021年10月14日以降にESPでの販売入札を実施していません(第132-3-3)。
【第132-3-2】ガスプロムの欧州向け天然ガス輸出量の推移
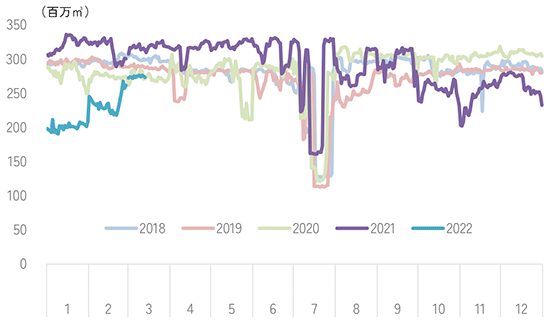
- 資料:
- ガスプロム社ウェブサイト、エネルギー経済社会研究所より経済産業省作成
【第132-3-3】ガスプロム社のESP販売量の推移
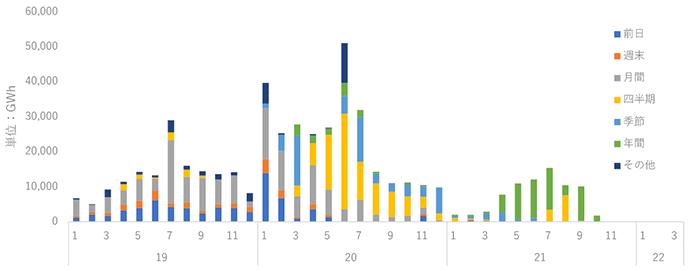
【第132-3-3】ガスプロム社のESP販売量の推移(xls/xlsx形式20KB)
- 備考:
- ESP(電子商取引プラットフォーム)はガスプロム社の販売窓口であり、欧州向けにのスポット販売を行う
- 資料:
- ガスプロム社ウェブサイト、エネルギー経済社会研究所より経済産業省作成
(3)ガスプロム社の天然ガス販売価格ポートフォリオ
また、ガスプロム社の販売価格ポートフォリオを見てみると、欧州天然ガス市場の価格が急騰したことの一因が分かります。日本ではLNG長期契約の価格フォーミュラについては受け渡し3ヵ月前の原油価格連動が一般的とされていますが、ガスプロム社の天然ガス販売価格ポートフォリオのうち、約87%がプロンプト市場15または先物市場16の価格リンクとなっており、天然ガス自身の市場価格に連動して、販売価格が決定する仕組みになっています(図132-3-4)。このため、ガスプロムとの長期契約では、原油価格と比較して天然ガスが割高になっている状況で、天然ガス価格高騰の影響を直接的に受けることになります。
【図132-3-4】ガスプロムの天然ガス販売価格ポートフォリオ(2020年)
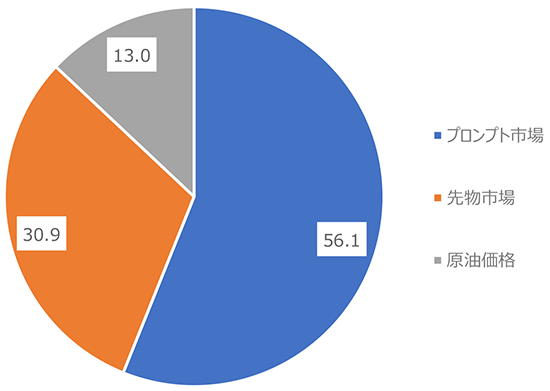
【図132-3-4】ガスプロムの天然ガス販売価格ポートフォリオ(2020年)(xls/xlsx形式15KB)
- 資料:
- ガスプロム社Webサイトより経済産業省作成
【第132-3-5】原油価格と天然ガス価格の比較
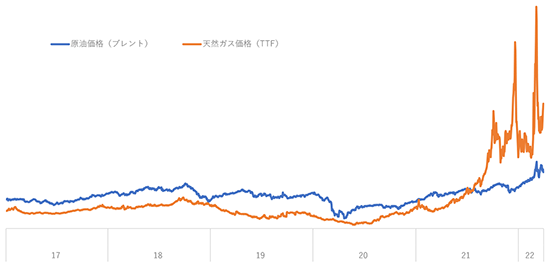
【第132-3-5】原油価格と天然ガス価格の比較(xls/xlsx形式208KB)
- 資料:
- Chicago Mercantile Exchage, ICEより経済産業省作成
(4)各国のロシアに対する制裁
2022年2月24日にロシアがウクライナに侵略したことにより、世界のエネルギー情勢は更に混迷を深め不確実性が高まり、エネルギーの需給と価格にも大きな影響を及ぼしています(第132-3-6)。
【第132-3-6】エネルギー分野におけるロシアへの制裁措置(2022年3月末時点)
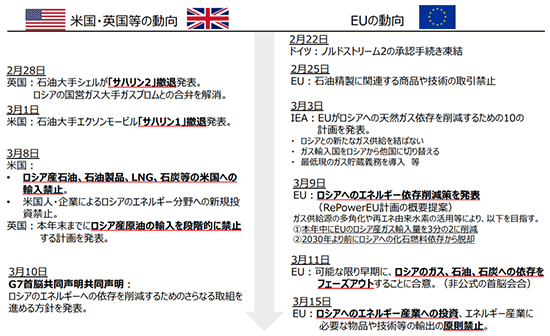
- 資料:
- 経済産業省作成
COLUMN
日本におけるサハリン1・2プロジェクトの重要性
日本は、原油及びLNGの輸入のほぼ全量を海外からの輸入に依存しており、エネルギー安定供給の観点から供給源の多角化を進めてきました。特に、原油は91.7%を中東に依存しており、LNGも豪州やマレーシア、カタールといった特定の産ガス国の依存度が高いことから、調達先の多角化が急務となっています。
こうした日本の脆弱なエネルギー供給構造の中で、ロシアからの原油及びLNGの輸入は、それぞれ日本の輸入量全体の3.6%、8.8%であり、この太宗を占めるサハリン1・2は、日本にとって重要な供給元となっています。また、サハリンからのエネルギー輸送は、中東を始めとする他の国や地域と比べて、日本との距離が非常に近く、輸送日数やコストを低く抑えられ、マラッカ海峡やホルムズ海峡といったチョークポイントを通過する必要がないため、安全かつ安定的な供給が可能となっています。
【第132-3-7】日本の原油・LNG・石炭輸入におけるロシアのシェア(2021年速報値)
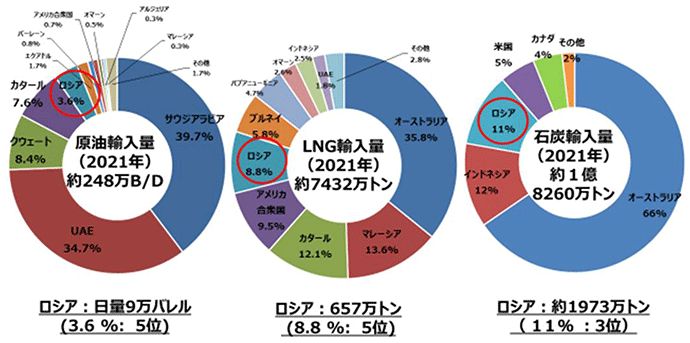
- 資料:
- 財務省貿易統計
しかしながら、今般のロシアによるウクライナ侵略を受けて、G7を始めとする欧米各国は、ロシアに対し、エネルギー分野を含む様々な制裁措置を講じてきました。2022年3月11日のG7首脳声明では、秩序立った形で、世界が持続可能な代替供給のための時間を確保しつつ、ロシアのエネルギーへの依存を削減するため更なる取組を進めていくことで一致しています。一次エネルギー自給率の高い、米国、カナダ、英国は、ロシアからの原油輸入の禁止を決めたほか、LNGや石油製品等についても禁輸を発表しています。フランス、ドイツ、イタリアは、ロシアへのエネルギー依存度が高く、EUとしては、2030年までにロシア産化石燃料からの脱却を目指す計画(「REPowerEU」)を発表し、自国へのエネルギー安定供給を確保すべく検討を進める発言をしています。
【第132-3-8】G7各国の一次エネルギー自給率とロシアへの依存度
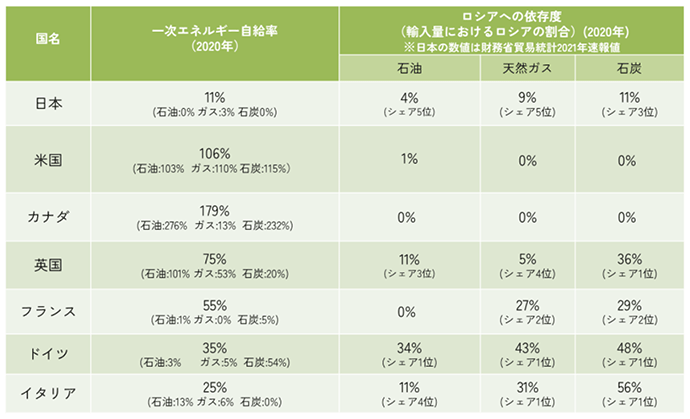
- 資料:
- World Economy Balances 2020(自給率)、BP統計、EIA Oil Information、Cedigaz統計、Coal Information(依存度)
このように、国によってエネルギー需給構造が異なるものの、ロシアが無辜の民間人の殺害を始め、断じて許されない国際法違反を繰り返したこと等を受けて、2022年5月8日のG7首脳声明では、「我々は、ロシアの石油の輸入のフェーズアウト又は禁止等を通じて、ロシアのエネルギーへの依存状態をフェーズアウトすることをコミットする。我々は、適時にかつ秩序立った形で、また、世界が代替供給を確保するための時間を提供する形で、これを行うことを確保する。」と記載されました。日本としても、G7首脳声明も踏まえ、エネルギー資源の太宗を輸入に頼っている日本としては大変厳しい決断ではあったものの、G7の結束が何よりも重要な時であり、ロシア産石油の原則禁輸という措置をとることとしています。ただし、日本として、今すぐにロシア産石油を禁輸できるわけではなく、一定の時間軸の中で秩序立った形で代替エネルギーを確保しながら、ロシアのエネルギーへの依存状態から徐々に脱却していくこととしています。また、日本が有する権益からの石油輸入については、エネルギーの長期的かつ安価な安定供給に貢献していること等を踏まえ、国民生活や事業活動への悪影響を最小化する方法で、時間をかけてフェーズアウトのステップをとっていくこととしています。
ロシアにおける日本の原油及びLNGプロジェクトであるサハリン1・2については、サハリン1は原油輸入の約9割を中東に依存する日本にとって貴重な中東以外からの原油調達先であり、また、サハリン2は、LNG輸入の約9%を供給し、発電電力量の約3%に相当するなど、日本の電力・ガス供給に不可欠なエネルギー源となっています。いずれも自国で権益を有し、長期的な資源の引取権が確保されており、また、現状のようなエネルギー価格高騰時は、市場価格よりも安価に調達できることから、エネルギー安全保障上、極めて重要なプロジェクトです。
2022年2月28日、シェル(英)がサハリン2からの撤退を表明し、2022年3月2日にはエクソンモービル(米)もサハリン1からの撤退を表明しましたが、仮に、日本がサハリン1・2から撤退し、日本の権益をロシアや第三国が取得する場合、ロシアを逆に利したり、日本のエネルギー安全保障を害することとなり、有効な制裁とならない可能性があります。より具体的には、仮にロシアに権益が渡ることになった場合は、ロシアはより高価格で当該権益からの生産物を第三国や市場で売却することで、より多くの外貨を稼ぐことになります。制裁に参加しない第三国に権益が渡る場合も、同様に彼らを利することになります。その一方で、日本企業は、足下ではより高い対価で石油や天然ガスを市場から調達せざるを得なくなる、あるいは、代替調達先を確保できなければ、国民生活や経済活動が多大な犠牲を強いられる恐れがあります。こうした、対ロ制裁の実効性及び長期的なエネルギー安定供給確保の観点から、岸田内閣総理大臣はサハリン1・2の権益は維持する方針を示しています。
ロシアのウクライナ侵略に対して、G7を始めとする国際社会が連携して、対ロ制裁を強化する中、ロシア側も対抗する措置を講じている現状を踏まえれば、不測の事態に備え、万全の対策をとる必要があります。とりわけLNGの安定供給については、既に電力・ガス会社が2〜3週間程度のLNG在庫を有していますが、今後、様々な不測の事態が発生する可能性もあります。ロシア以外のLNG生産国やスポット市場からの代替調達が世界中で加速していることから、見通しは厳しいものの、事業者間の融通に加えて、電力システム全体での機動的な電力の広域融通に向けて取組が進められています。
日本としては、G7首脳声明に沿って、①再生可能エネルギーや原子力も含めたエネルギー源の多様化、②LNGへの投資等によるロシア以外での供給源の多角化、③主要消費国とも連携した生産国への増産働きかけ等を通じて、ロシアへのエネルギー依存の低減に取り組んでいきます。
4.エネルギー価格高騰の影響
(1)エネルギー輸入物価の推移
資源輸出国と価格変動リスクをヘッジできるようなフォーミュラで長期契約等を結んでいる国では、原油・天然ガス・石炭の市場価格が高騰しても、それが即座に各国の輸入価格の高騰につながるわけではありません。
そこで、主要国における原油・天然ガス・石炭の輸入価格の推移を各国の貿易統計に基づき集計・整理(以下、2019年1月の数値を基準(100)として、グラフデータの計算をしています)すると、2021年天候不順に伴って風力発電が順調に発電しなかった欧州で、天然ガスをスポットで大量に調達した影響で、英国で3.56(2022年3月)、オランダで3.46(2022年1月)、ドイツで2.26(2022年2月)まで上昇していますが、2022年3月に約8倍まで高騰した天然ガス(TTF)の市場価格よりは上昇幅が抑えられています(第132-4-1)。これに比べ、日本の輸入価格は欧州と比較して低く抑えられていることが分かります。
【第132-4-1】主要国における原油、天然ガス、石炭の輸入物価の推移(2019年1月を100としている)
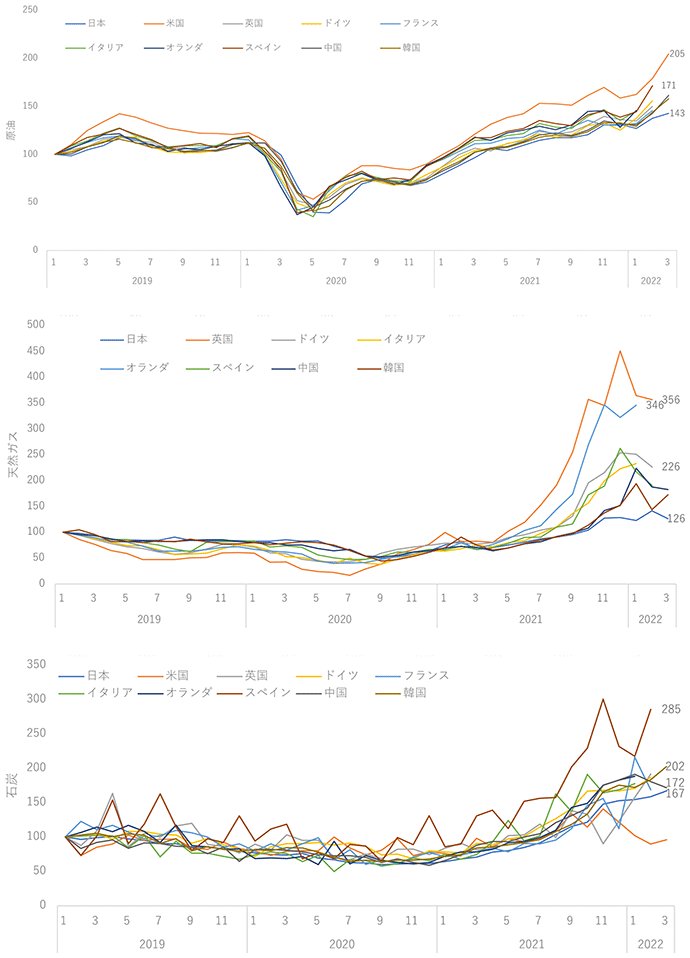
【第132-4-1】主要国における原油、天然ガス、石炭の輸入物価の推移(2019年1月を100としている)(xls/xlsx形式65KB)
- 資料:
- Global Trade Atlasより経済産業省作成
(2)欧州における電力卸価格の高騰と小売電気事業者の経営破綻
欧州では送電線により国境を越えた電力融通が行われていますが、欧州における卸電力価格は、新型コロナによって落ち込んでいた2020年から一転して、2021年後半には大幅に上昇しました。背景には、前述のように、欧州における天候不順によって風力発電が低迷し、天然ガスを中心に火力発電の燃料の需給がひっ迫して価格が高騰したこと等が影響したと考えられます(第132-4-3)。
【第132-4-3】欧州における卸電力価格の推移(2021年)
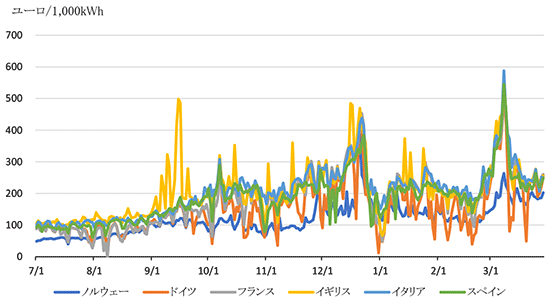
【第132-4-3】欧州における卸電力価格の推移(2021年)(xls/xlsx形式296KB)
- 備考:
- ノルウェーはオスロゾーンの価格
- 資料:
- ノルウェー、ドイツ、フランス及び英国はNord Poolウェブサイト、イタリアはGMEウェブサイト、スペインはOMIEウェッブサイトより経済産業省作成
電力の調達価格の上昇を小売価格に転嫁しきれなかったため、欧州では2021年から2022年3月にかけて、英国、オランダ、ドイツ、チェコ、ベルギー、フィンランドで多数の小売エネルギー事業者が経営破綻しました(第132-4-4)。特に英国では、29社が経営破綻し、うち1社は170万世帯の顧客を抱える企業(Bulb Energy)であり特別公的管理へと移行されました。
【第132-4-4】欧州における小売エネルギー事業者経営破綻の状況
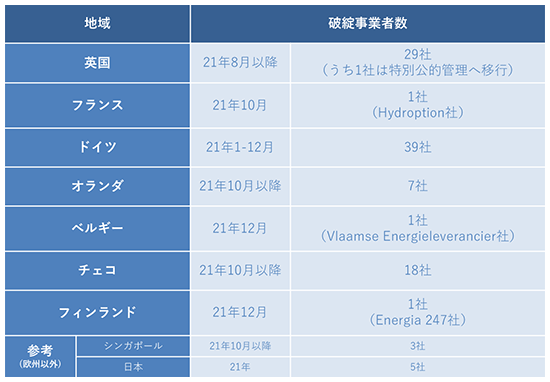
【第132-4-4】欧州における小売エネルギー事業者経営破綻の状況(ppt/pptx形式:35KB)
- 資料:
- エネルギー経済社会研究所作成資料
(3)エネルギーに関する消費者物価指数の推移
次に、電気・ガス・ガソリン等について、日米欧の消費者が直面する価格がどうなっているかについて見ていきます(以下、2019年1月の数値を基準(100)として、グラフデータの計算をしています)。まず電気料金は、イタリアが1.77と突出して上昇しています。一方、英国やフランスでは、卸電力価格がイタリアと同水準まで高騰したにも関わらず電力料金は1.3〜1.4程度の変化に収まっています。イタリアは、英国やフランスと違い、電源構成に占めるガス火力発電の割合が相対的に高かったために天然ガス価格の高騰に伴って電気代も急激に上がったものと考えられます。ガス料金は、イタリアが1.47と最大の値上がりを見せていますが、フランス、ドイツ、米国も1.3程度まで上がっています。ガソリン等17料金は、英国、ドイツ、米国、フランスの順で1.88、1.85、1.82、1.76と値上がりしています。この中で、米国は該当期間を通じて高めに推移していますが、これは米国の石油製品価格の動きは国際的な原油価格指標であるブレント価格に連動する傾向があることに加え、2019年1月の水準が例外的に安かったことが影響しています。例えば2019年のピークである2019年4月を基準(100)とした場合には、他国と同様の推移となります。
なお、全体の指標を通じて日本は電気で1.10、ガスは1.11、ガソリンは1.29と相対的に抑えられています。本来、資源輸入国である日本は、世界的な資源価格高騰の影響を直接受けやすい状況にありますが、電力・ガス事業者における油価連動を中心とした長期契約比率が相対的に高いことによって輸入価格が比較的安価に抑えられていることと、電気・ガスに関する燃料費調整制度18やガソリンの激変緩和措置等によって小売価格まで転嫁されていないこと等が要因であると考えられます(第132-4-5)。
【第132-4-5】主要国における消費者物価指数(エネルギー価格)の推移(2019年1月を100としている)
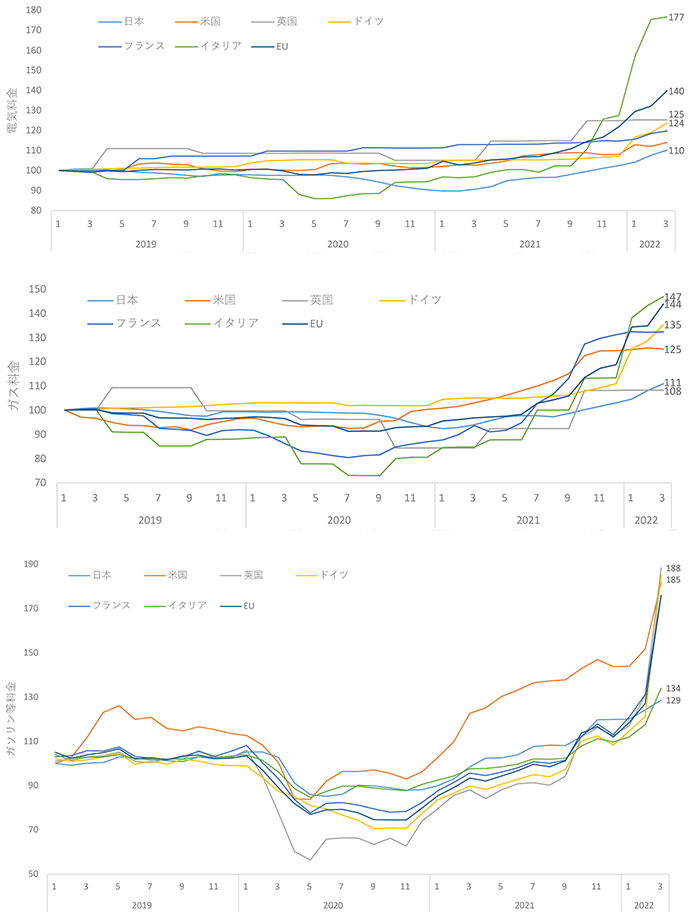
【第132-4-5】主要国における消費者物価指数(エネルギー価格)の推移(2019年1月を100としている)(xls/xlsx形式552KB)
- 資料:
- 各国政府統計より経済産業省作成
5.エネルギー価格高騰に対する各国の政策対応
エネルギー価格高騰を受けた各国の短期的な対応は、①需要家保護と②小売事業者保護の大きく二つに分かれますが、小売料金上限の引上げ/引下げのように、片方にとって便益となる内容が、もう片方にとっては損失となるケースも存在します。そのため、①のうち、特に困窮する需要家の保護を優先させつつ、国の資金も注入しながら、需要家保護と小売事業者保護を両立させるケースが多く見られます。
中長期的な対応としては、③エネルギーセキュリティの向上が主な対応方針となっており、原子力や石炭を含む化石資源に対する評価が見直される傾向にあります。
(1)英国
英国は、①の需要家保護として、困窮世帯救済に従来から実施している電気・ガス料金の割引等に加えて、5億ポンドの基金を用いた支援を行っています。また、規制当局であるOfgemが、小売事業者が破産した場合にも需要家が安定して電気・ガス供給を受けられるよう代わりの電力・ガス小売事業者を指定したり、小売事業者の監視を強めたりしています。困窮世帯以外を含む全世帯に対しても350ポンドの支援を行う一方、②の小売事業者保護として小売電気・ガス料金上限の引上げを行い、燃料高騰の影響を価格転嫁できる措置を講じています。
③のエネルギーセキュリティ向上への取組としては、原子力の資金調達を支援する枠組として規制資産ベースモデル(RABモデル)を検討しています。これは、建設と操業に係るリスクを消費者と分け合うことで資金調達のハードルを下げるもので、ロンドンの下水道プロジェクトやヒースロー空港の第5ターミナル建設において導入実績があります。
(2)ドイツ
ドイツは、①の需要家保護として再エネ賦課金の減額や低所得者世帯に対して一度きりの補助金支給を行っています。また、③のエネルギーセキュリティの向上について、2030年終了を目標に置いていた石炭火力を2030年以降も継続することで、ロシア産エネルギーへの依存度を低減する検討を開始しています。
(3)フランス
フランスは、①の需要家保護について、電気では電気料金に係る税を引き下げることによる規制料金引上げの制限、ガソリンでは自動車利用の多い個人、法人に対して補助金を導入しています。また、エネルギーと直接的な関係はありませんが、低所得者世帯に対する補助金・月収2,000ユーロ未満の個人へのインフレ手当を実施しています。②の小売事業者保護については、新規小売電気事業者に対してEDFが供給する原子力発電の電力量の一部を比較的安価な規制価格で販売する既存の制度について、例外的・一時的な措置として電力販売量を増加させる措置を取っています。
また、③のエネルギーセキュリティについて、フランスはロシアによるウクライナ侵略を受けて原子力発電の拡大を検討しています。2050年までに最大14基の原子力発電所が新設される可能性があり、建設は早ければ2028年に開始する予定とされています。
(4)スペイン
スペインでは、①の需要家保護について、電気料金に係る付加価値税の時限的な減税や困窮者に対しては追加的な割引措置を講じています。②の小売事業者向けにも大手発電事業者はオークションを通じて自社の原子力及び水力発電の電力量の25%を小売電気事業者及び大口需要家に提供する強制ベースロードオークションを展開しています。
(5)EU
欧州委員会は2022年3月にエネルギー政策の包括案を発表し、域内のエネルギー事業者に対して一定の天然ガスの貯蔵を実施するよう義務づけることや、再生可能エネルギー等の普及や家計及び企業支援の財源として、価格高騰で利益を得たエネルギー企業に臨時の増税をすることも加盟国に提案しました。欧州委員会はこれらの対策を実行すれば2022年内にロシアに対するガス依存度を現状の1/3程度にできるとしています。ガス備蓄についてはEUの共通政策として、最低限の備蓄量を設定するガス貯蔵に関する規則案を発表しました。同規則案は、加盟国に対して、2022年11月1日までに自国に設置されたガス貯蔵施設の備蓄上限の8割の備蓄を義務付けるもので、年間を通じた複数の中間目標を設定するとともに、2023年11月以降は、備蓄義務を9割以上に引き上げる内容となっています。
その他のEU加盟国では、ベルギーが2022年3月に2025年までに閉鎖を予定していた2基の原子力発電所の稼働を10年間延長することを決定し、電気料金上昇による消費者負担を抑え、ロシア依存からの脱却を急ぐ取組を展開しています。
本項では、資源高によって各国がどのような影響を受けているのかについて、定量的に示しました。化石資源はどこからでも採掘できる訳ではなく、一次エネルギーを完全に自給できる国は非常に限られます。カーボンニュートラルの実現に向けては、再エネの大量導入に対応するための調整電源として、天然ガスをスポット(又は短期)契約で輸入することで、燃料供給過多による市場価格低迷時に経済的メリットを享受できることがありますが、今般のような事象が一度発生すると、国の地理的制約や制度、民間企業の契約形態によってはたちまち消費者価格に反映されてしまい、国民生活に多大な影響を及ぼしかねないということが明らかになりました。エネルギー政策の大原則であるS+3Eの1つであるエネルギー安定供給について、化石資源開発から消費者へのエネルギー供給までのバリューチェーンを最適化していくことの重要性を踏まえ、改めて各種の制度設計を検討していく必要があります。
COLUMN
2022年3月の東日本における電力需給ひっ迫について
3月22日の東日本における電力需給ひっ迫の要因の一つには、3月16日に生じた地震の影響がありました。16日23時36分に福島沖を震源とする地震(最大震度6強)が発生し、計14基・647.9万kWの火力発電所が停止しました。地震による火力発電の停止に伴って、電力システムを保護するために一定の需要を自動停止するUFRの発動等により、東京電力管内で最大約210万戸、東北電力管内で最大約16万戸の停電が発生しましたが、運転中の火力発電所の出力増加や被害を受けた配電・送変電設備の改修等を行い、停電は解消されました。また、東北電力管内においては、17日の間、他エリアからの電力融通を受けることで、安定供給に最低限必要な予備率3%を確保しました。
3月18日は、16日の福島沖地震の影響で、引き続き東北・東京電力管内の火力発電所7基(計約440万kW)が停止していたほか、新たに電源の計画外停止が生じました。一方で、需要は朝から高水準で推移したため、追加供給力対策を終日実施していました。需要ピーク時を過ぎ、夜間になっても需要の減少が見られず、21〜22時頃に揚水発電が枯渇し、需給ひっ迫に陥る恐れが生じたため、東京電力パワーグリッドにおいて、急遽、節電の呼びかけを行いました。
19日からの3連休を経て、連休明けとなる22日の東京電力管内の想定電力需要は、3月19日夜時点で、4,300万kWでした。その後、20日、21日と天気予報が悪化。最高・最低気温ともに大きく下がり、都心でも雪が混じる予報となりました。前日21日夕方の時点での22日の想定最大需要は、こうした天候の予測の変化を反映し、約4,840万kWと大幅に増加しました。これは、今冬の電力需給見通しにおける、10年で一度の厳しい寒さを想定した場合の3月の最大需要を約300万kW上回る極めて高い水準でした。そのため、経済産業省は、21日夜に需給ひっ迫警報(第1報)を出し、国民の皆様に節電をお願いすることとなりました。
22日当日は、東北電力管内でも天候が悪化しました。福島市や仙台市においては気温が急激に低下し、暖房による電力需要が大きく増加した結果、電力使用率が100%(速報値)に届く等、電力需給が極めて厳しい状況となりました。このため、需給ひっ迫警報(第2報)において、東北電力管内も対象とし、最大限の節電への協力を呼びかけました。
電力需給ひっ迫警報を受けた各所での節電の取組として、産業界や商業施設等において、消灯、暖房の設定温度抑制、自家発電の最大限活用等の節電対応が行われました。また、経済産業省としても、地方経済産業局や他省庁等と連携し、業界団体・主要企業・自治体等に対する需給ひっ迫警報の周知や節電の依頼、庁舎における節電対策(ロビー・廊下・エレベーターホール等の照明5割消灯、エレベーターの5割間引き運転等、不要不急な電気製品の使用停止の呼びかけ等、を行いました。
22日当日の節電量の実績について、東京電力管内の電力需要は、午前中までは高水準で推移し、目標とする節電量を大きく下回っていましたが、15時以降は節電量が急速に拡大しました。これにより、1日を通じて、目標とする節電量の約7割を達成しました。また、東北電力管内では、需給ひっ迫警報発令後、想定需要よりも大幅に減少して推移しました。結果として、両エリアにおいて、不測の大規模停電を回避することができました。
今回の電力需給ひっ迫を受け、当日の一連の対応について、資源エネルギー庁の審議会(電力・ガス基本政策小委員会)においてを行ってきました。その中で、電源や需要抑制の対策の在り方、燃料の確保策等についての重要性が改めて確認され、今後、供給力と需要の両面から対策を講じていくこととしました。
- 10
- ”Title Transfer Facility”の略であり、欧州のガス取引の価格指標。
- 11
- ”Japan Korea Marker”の略であり、S&P Global Platts社による価格指標。
- 12
- 新型コロナの拡大により世界の経済が減速し、石油需要が短期間のうちに大幅に減少しました。当時、OPECはこの状況に対処しようと2020年3月に非OPECに追加減産を提案しましたが、ロシアがこれを拒否したことで協調減産そのものが決裂・崩壊しました。この結果を受けたサウジアラビアは、これまで協調減産をリードしてきた態度を一変し、増産に踏み切ることを表明しました。市場は価格競争に突入するとの見方から、原油価格が急落、この急落から2020年4月にOPECプラスは再び協調減産に合意しましたが、都市封鎖(ロックダウン)等で世界の石油需要は急減し、また原油の貯蔵能力の限界を超えるとの見方から、一時WTI原油はマイナス価格を記録しました。
- 13
- 2021年4月発行のため、実績ではありません。
- 14
- 白川裕「天然ガス・LNG最新動向 ─欧州発ガス・スポットLNG高騰からの教訓と脱炭素ネットゼロエミッションへのミッシングリンク─」(2021年12月24日発表)
- 15
- 短期取引市場、即ち当日・前日・週間・月間取引を指しますが、ガスプロムでは前日・月間市場と定義しています。
- 16
- ここでは四半期・季節(夏季・冬季)・年間契約を指します。
- 17
- 他に軽油・灯油等を含む。
- 18
- 事業者の効率化努力の及ばない燃料価格や為替レートの影響を外部化することにより、事業者の経営効率化の成果を明確にし、経済情勢の変化をできる限り迅速に料金に反映させると同時に、事業者の経営環境の安定を図ることを目的とし、平成8年1月に導入された制度のことで、平成28年4月以降は、旧一般電気事業者の小売部門(みなし小売電気事業者)の特定小売供給約款における契約種別ごとの料金に適用することとなっています。