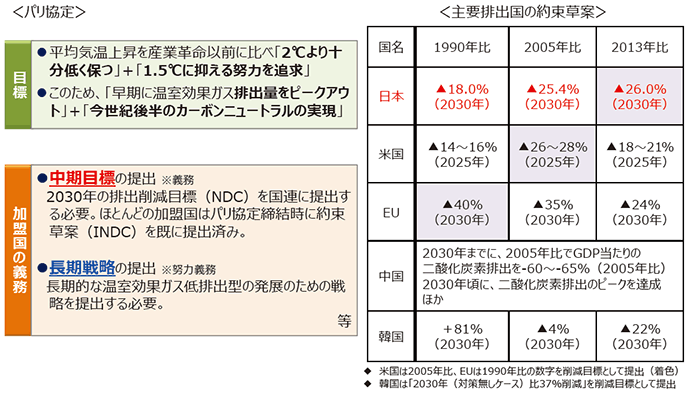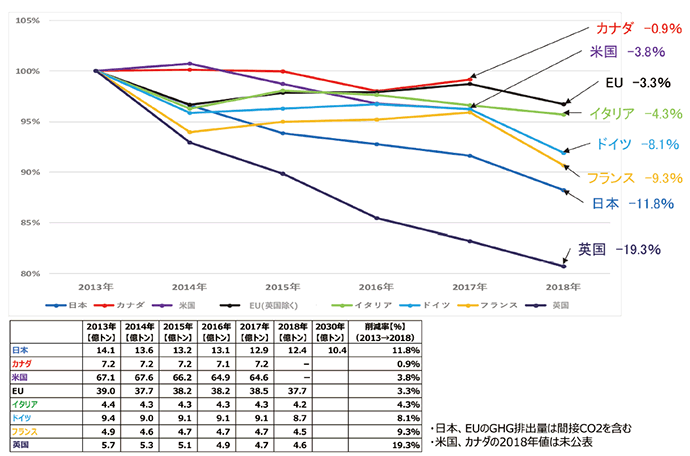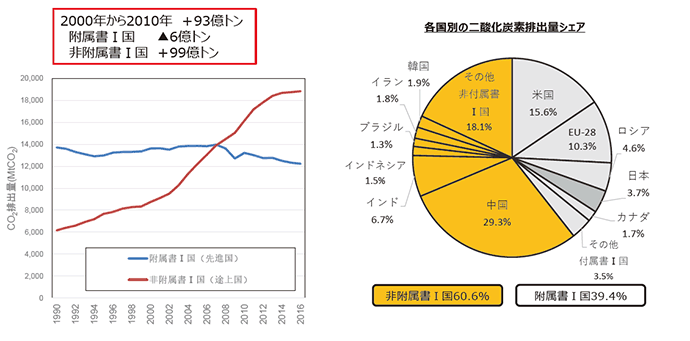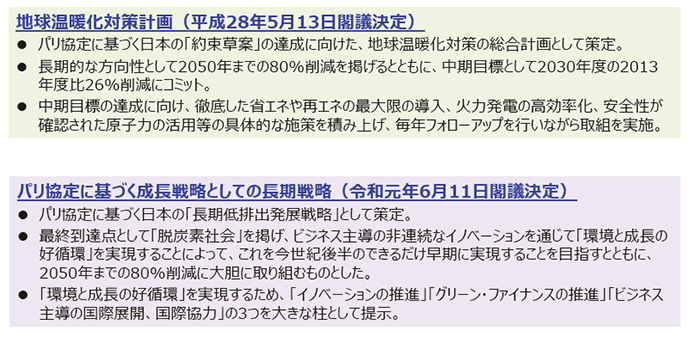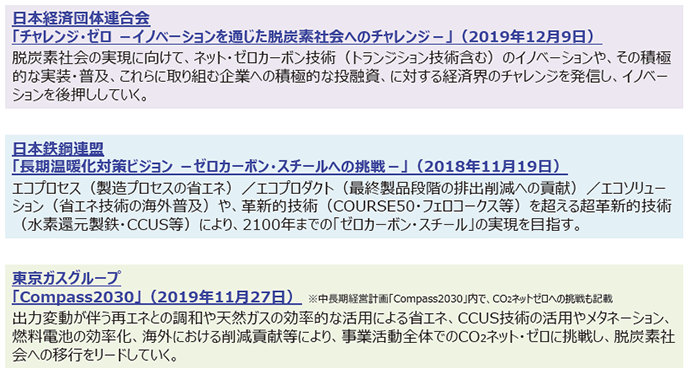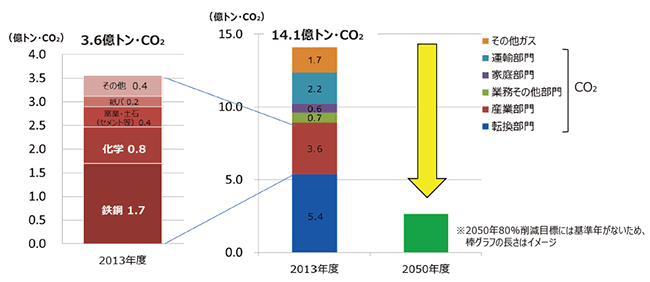第1節 温暖化をめぐる動き
1.温暖化対策の状況
(1)日本政府の方針(パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略と「国が決定する貢献(NDC)」)
パリ協定は、2015年12月の第21回気候変動枠組条約締約国会議(COP21)で採択され、2016年11月に発効し、2020年から本格的に運用が開始されます。
パリ協定では、世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べ2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑えるよう努力を続けることを目的に掲げています(パリ協定第2条)。また、各国は温室効果ガス(以下、「GHG」という。)削減に向けた「国が決定する貢献」(Nationally Determined Contribution、以下、「NDC」という。)を定め、GHGの排出削減や吸収に関する国内措置を取り、今世紀後半にGHGの人為的な発生源による排出と吸収源による除去量を均衡させるよう取り組むことが求められています。NDCは、5年ごとに提出・更新することとされています(パリ協定第3条、第4条)。
2013年のCOP19における合意で、全ての国に対して、2020年以降の削減目標を、2015年12月のCOP21に十分先立って作成することが招請されていました。日本はパリ協定合意に先立つ2015年7月に、裏付けのある対策や技術の積み上げによる実行可能な削減目標として、2030年度にGHG排出量を2013年度に比べ26%削減する目標を掲げた「日本の約束草案」(Intended Nationally DeterminedContribution、以下、「INDC」という。)を地球温暖化対策本部で決定し、国連気候変動枠組条約事務局に提出しており、これがそのままパリ協定のNDCとなりました。
また、2020年3月には、日本のNDCを地球温暖化対策推進本部で決定し、国連気候変動枠組条約事務局に提出しました。これは、パリ協定の目標の達成により野心的に貢献する観点から提出したものであり、我が国の積極的なメッセージとして以下の3点を国内外に発信しました。
①2030年度26%目標を確実に達成することを目指すとともに、この水準にとどまることなくさらなる削減努力を追求していくこと
②これに基づき、「地球温暖化対策計画」の見直しに着手し、計画見直し後に追加情報を国連へ提出すること
③その後の削減目標の検討は、エネルギーミックスの改定と整合的にさらなる野心的な削減努力を反映した意欲的な数値を目指し、パリ協定の5年ごとの期限を待つことなく実施すること
さらに、各国は、NDCとは別に、長期的なGHGの低排出型の発展のための戦略を作成し、通報するよう努力すべきとされています(パリ協定第4条19)。G7諸国は、長期戦略を2020年より十分先立って提出することとし1、これに基づき、日本も、2019年6月に「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略(以下、「長期戦略」という。)」を閣議決定し、国連に提出しました。
長期戦略では、「最終到達点として『脱炭素社会』」を掲げ、それを野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目指すとともに、地球温暖化対策と経済成長を両立させながら、2050年までに80%のGHG排出削減という長期的目標を掲げており2、その実現に向けて大胆に施策に取り組むこととしています。
日本は、2014年度以降5年連続でGHG排出量を削減しており、既に2013年度比約12%削減しています。これはG7では英国に次ぐ水準です。理念を掲げるだけでなく、毎年、着実にGHGの排出量を削減しながら、技術開発も進めることで、実効的なGHG削減に取り組んでいくことが重要です。
【第131-1-1】パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略の概要
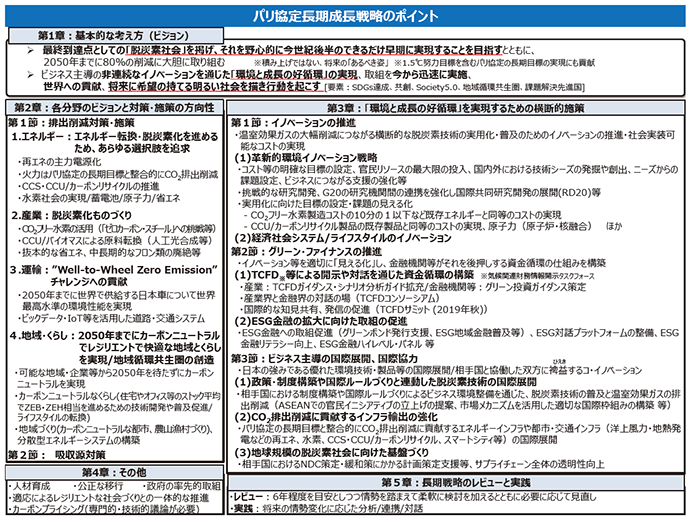
- 出典:
- 経済産業省・環境省・外務省作成
- 出典:
- 経済産業省「環境イノベーションに向けたファイナンスのあり方研究会(第1回)」より抜粋
(2)新興国等を含む世界全体のGHG削減の必要性
先進国では着実にGHG排出削減が進んでいますが、それだけでは、地球温暖化を止めることはできません。世界全体のGHG排出量の3分の2は新興国等が占めており、新興国の排出削減なくしてパリ協定の目標の達成はあり得ません。
しかし、国連気候アクションサミットなどで、2050年のカーボンニュートラルにコミットした新興国であっても、そのほとんどが国連に長期的な排出量削減目標を提出しておらず、カーボンニュートラル実現への道筋は見えていません。一方、国際エネルギー機関(IEA)等の見通しによれば、新興国のGHG排出量は、経済成長にともなって今後も増えていく見込みです。世界では、電力を利用できない人々が2017年でも8.4億人存在し、特にアジア・アフリカでは、安価で手に入れやすい石炭から電力を得ようとする国が多いという現実もあります。
気候変動との戦いと、新興国の電力アクセスによる生活の向上を両立するような非連続のイノベーションが、これまで以上に求められるようになっています。そのための具体的な筋道をつけていくことが必要なのです。
- 出典:
- Greenhouse Gas Inventory Data(UNFCCC)、The EEA’s annual report on EU approximated GHG inventory for 2018(EEA)を基に作成
- 出典:
- 経済産業省「環境イノベーションに向けたファイナンスのあり方研究会(第1回)」より抜粋
- 出典:
- 経済産業省「環境イノベーションに向けたファイナンスのあり方研究会(第1回)」より抜粋
【第131-1-5】電力アクセスの現状
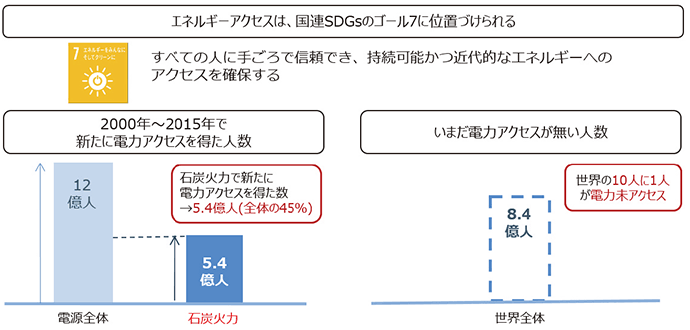
- 出所:
- (左)国際エネルギー機関(IEA)「Energy Access Outlook2017」
- 出所:
- (右)国連「SDGs Report 2019」(2017年)
- 出典:
- IEA「Energy Access Outlook2017」及び国連「The Sustainable Development Goals Report 2019」より経済産業省作成
COLUMN
グローバル・バリューチェーンを通じた排出削減の必要性
世界全体のGHG削減には、各国内の低炭素化・脱炭素化を進めるだけでなく、各国がグローバル・バリューチェーンにおいて果たす役割を踏まえ、それぞれの特性に応じた低炭素化の取組を進めることも重要です。
例えば、先進国では着実にGHG排出減が進んでいますが、これは、各国の努力の結果だけでなく、産業構造の変化(経済のサービス化等)に伴い炭素集約製品を新興国等からの輸入に頼っている影響が大きく、本来先進国に帰属すべきGHGが新興国に帰属しているだけとの研究もあります3。
現行のCO2排出量推計方法では、製品・サービスの「生産国」でCO2を計上していますが、これを製品・サービスの「消費国」での計上に変えると、欧州の削減率は縮小する一方、日本はG7で削減率1位になります(2013年比、2015年時点4)。このように、計上方法で帰属先国が変わるCO2の量は、世界排出量の1~2割にも相当するとされています5。これは、最大約60億トンと、EUの2018年のCO2排出量の2倍にもなる大きな量です。
【第131-1-6】CO2排出量の国別推計(自動車の国際サプライチェーンのイメージ):生産国計上(現行手法)と、消費国計上の比較
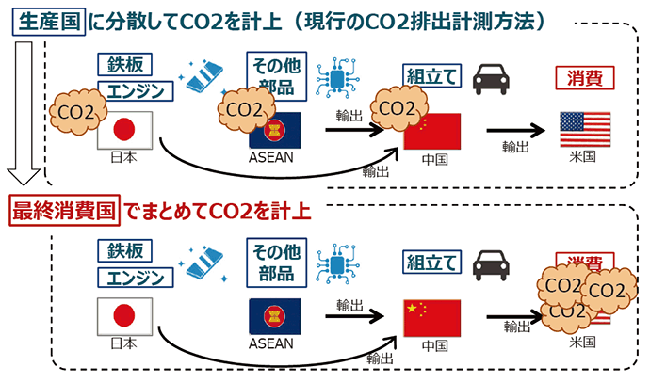
【第131-1-6】CO2排出量の国別推計(自動車の国際サプライチェーンのイメージ):生産国計上(現行手法)と、消費国計上の比較(ppt/pptx形式:87KB)
- 出典:
- OECD「CO2 emissions embodied in consumption」より経済産業省作成
【第 131-1-7】 主要国のCO2排出削減率:生産国計上(現行手法)と消費国計上の比較
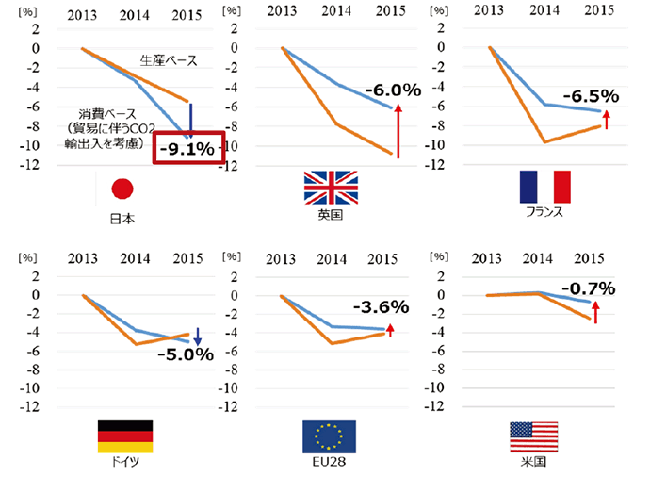
【第 131-1-7】 主要国のCO2排出削減率:生産国計上(現行手法)と消費国計上の比較(ppt/pptx形式:129KB)
- 出典:
- OECD「CO2 emissions embodied in international trade 2019」より経済産業省作成
先進国が消費する炭素集約製品の製造を担う新興国が、CO2排出も肩代わりしているとも言えますが、国際的な産業配置はCO2だけでなく、天然資源の賦存状況、労働力、市場との近接性など様々な要素によって経路依存的に定まったものであり、短期的に変えることは困難です。また、世界全体で鉄鋼や化学等の炭素集約製品の利用を直ちに止めることも、現実的ではありません。世界の実効的なCO2排出削減を進めるために、まずは国際的な産業構造配置の在り方を前提にしつつ、輸入元である新興国等の低炭素化をどのように進めるかが鍵となります。そのためには、現行のCO2計上方法や国際ルールでは十分に実態を捉えていないため、新たな計上方法や国際ルールづくりが必要になります。長期的には、非連続なイノベーションによって製品の製造方法そのものを低炭素化・脱炭素化していくことが欠かせません。日本は、革新的環境イノベーション戦略(第3章第3節)の着実な実行により、高効率・低炭素技術やカーボンリサイクル等のイノベーションを新興国等に展開し、世界の実効的な排出削減に貢献していきます。
2. 非連続なイノベーションの実現等による世界への貢献
(1)政府の取組
気候変動問題への対応は、従来の取組の延長では解決が困難であり、非連続なイノベーションが不可欠です。その実現には、巨大な資金、技術力を有するビジネスの力を最大限活用することが重要です。日本の温暖化対策は、長期戦略において、「環境と成長の好循環」とのコンセプトの下、成長戦略として位置づけられており、これを具体化するために、①イノベーションの推進、②グリーン・ファイナンスの推進、③ビジネス主導の国際展開・国際協力の3つの施策を進めていきます。「環境と成長の好循環」のコンセプトは、2019年に軽井沢で開催されたG20エネルギー大臣・環境大臣合同会合で確認され6、さらにG20大阪サミット首脳宣言に盛り込まれ、日本だけでなくG20リーダーの共通認識となっています7。日本政府は、2016年に閣議決定した「地球温暖化対策計画」や、前述の長期戦略の中で、中長期の時間軸のそれぞれを見据え、様々な政策的手段を組み合わせて温暖化対策に取り組んでいます。
(2)産業界の取組
日本では産業界による自主的な温暖化対策も進んでいます。115業種(2020年3月末時点)が業界ごとに「低炭素社会実行計画」を策定し、2020年度、2030年度の削減目標を掲げ、毎年PDCAサイクルを回しながら取組を進めています。また、日本経済団体連合会(経団連)は、2019年12月に「チャレンジ・ネット・ゼロカーボン・イノベーション(チャレンジ・ゼロ)」構想を発表し、トランジション技術を含むネット・ゼロカーボン技術のイノベーション等に関する企業の取組を集約・整理し、国内外に発信するとしています。日本鉄鋼連盟では、水素還元製鉄等によるゼロカーボン・スチールの実現を2018年11月に宣言したほか、東京ガスグループは2030年までに事業活動全体でCO2ネットゼロを目指すことを2019年11月の中期経営計画に盛り込むなどの動きが出てきています。
- 出典:
- 経済産業省「環境イノベーションに向けたファイナンスのあり方研究会(第1回)」より抜粋
- 出典:
- 経済産業省「環境イノベーションに向けたファイナンスのあり方研究会(第1回)」より抜粋
COLUMN
CO2排出削減に必要なのは「イノベーション」と「ファイナンス」
日本は、「2050年までに80%のGHGの排出削減を目指す」、「今世紀後半のできるだけ早期に脱炭素社会を実現することを目指す」という目標を掲げています。この目標を実現するためには、極めて野心的な取組が必要となります。日本のGHGの排出源別に見て見ると、「エネルギー転換部門」(石油などの一次エネルギーを電気・ガソリンなどの二次エネルギーに転換して使用する部門)「産業部門」「家庭・業務部門」「運輸部門」などからGHGをCO2換算で14.1億トン排出しています(2013年度確報値)。「80%削減」は、長期的なビジョンとして掲げているものであり、基準年が設定されているわけではありませんが、たとえば2013年を基準に考えてみると、80%の削減目標を達成するには、以下の取組が必要となります。
- 業務用や家庭用などすべての社会インフラをオール電化または水素利用などのエネルギーに入れ替えること
- 運輸部門(自動車・電車・航空機・船舶など)のエネルギーをすべてゼロエミッションにすること
- 発電を100%非化石にすること
- 出典:
- 経済産業省「環境イノベーションに向けたファイナンスのあり方研究会(第1回)」より抜粋
現在社会に導入されている技術やその延長線の取組では、「80%削減」や「脱炭素社会の実現」の実現には大きな困難が伴います。このため、非連続なイノベーションを起こし、現在社会に導入されているものとまったく異なる、新しい技術を実現・普及していくことが欠かせないのです。
- 1
- 伊勢志摩サミット首脳宣言(http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000160267.pdf)。長期戦略の通報期限は、パリ協定ではなくCOP21決定(1/CP21)パラグラフ35で「2020年まで」とされている。
- 2
- 地球温暖化対策基本計画(2016年5月13日閣議決定)
- 3
- (公財)地球環境産業技術研究機構(RITE)推計(経済産業省 第1回「環境イノベーションに向けたファイナンスのあり方研究会」秋元圭吾委員資料)
- 4
- OECD「CO2 emissions embodied in international trade 2019」より経済産業省が作成。なお「消費国」でのCO2計上には国際産業連関表を用いる必要があり、OECD 国際産業連関表でデータ取得可能な最新時点である2015年について分析しました。
- 5
- 既存の研究では、22%(Peters, G. P. et al.,“ A synthesis of carbon in international trade”, Biogeosciences, 9, 3247?3276,2012)や7%(OECD,“ CO2 emissions embodied in international trade”, 2019)とするものがあります。
- 6
- 2019年6月G20持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合開催結果(https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190618008/20190618008.html)