第4節 エネルギーレジリエンスの強化
1. エネルギー供給強靱化法案の閣議決定
国際資源情勢の変化や地政学的リスクの高まりや自然災害の頻発・被害の甚大化を踏まえた電力インフラのレジリエンス向上の必要性がこれまでになく高まるとともに、長期的な脱炭素化も見据えながら、国民負担を最小限に抑制しながら再エネの主力電源化を達成していくことも必要となってきています。
これまで紹介してきた総合資源エネルギー調査会の各分科会や小委員会等における議論を踏まえ、エネルギー供給のレジリエンス向上に向け、災害時の迅速な電力復旧や送配電網への投資の促進、再エネの導入拡大等に向けた必要な措置を講じるため、2020年2月に「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」(エネルギー供給強靱化法案)を閣議決定しました。
同法案では、①災害時の送配電事業者の連携強化やプッシュ型ネットワーク整備計画などによる送配電網の強靱化、②災害に強い分散型電力システムの整備、③FITに代わるFIP制度の創設、④JOGMECによるリスクマネー供給支援などを通じた燃料等の安定供給の確保など、強靱かつ持続可能なエネルギー供給体制を確立するための措置を講じることとしています。
強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案(エネルギー供給強靱化法案)の概要
(1)電気事業法
①災害時の連携強化
災害時に迅速かつ効率的に対応できるよう、送配電事業者に、共同して、相互の連携に関する事項等を記載した災害時連携計画を策定することを義務づける。経済産業大臣の求めに応じ、災害復旧時に送配電事業者が自治体等に対して、高齢者の安否確認等に必要な戸別の通電状況等の情報提供を義務づける等の措置を講ずる。
②送配電網の強靱化
レジリエンス強化の観点から、プッシュ型のネットワーク整備計画(広域系統整備計画)の策定業務を電力広域機関の業務に追加するとともに、送配電事業者に既存設備の計画的な更新を実現するための義務を課す。送配電網の強靱化等の実現のため、経産大臣が事業者の投資計画等を踏まえて収入上限を定期的に承認し、その枠内でコスト効率化を促す託送料金制度を創設する。
③災害に強い分散型電力システム
新たに参入する事業者が、特定エリア内で分散小型の電源等を含む配電網を運営しつつ、緊急時にも独立したネットワークとして機能できるよう、配電事業を位置付ける等の措置を講ずる。
(2)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)
①市場連動型の導入支援
再エネ発電事業者の投資予見可能性を確保しつつ、市場を意識した行動を促すため、固定価格での買取りに加えて、新たに、市場価格に一定のプレミアムを上乗せして交付する制度(FIP制度)を創設する。
②再エネポテンシャルを活かす系統増強
これまで地域の送配電事業者が負担していた、再エネの導入拡大に必要な地域間連系線等の系統増強の費用の一部を、賦課金方式で全国から回収し送配電事業者に交付する制度を創設する。
③再エネ発電設備の適切な廃棄
太陽光発電が適切に廃棄されない懸念に対応するため、発電事業者に対し、廃棄のための費用に関する外部積立て義務を課す。
(3)独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(JOGMEC法)
①LNGの調達先の多様化や金属鉱物の安定的な供給を確保するため、JOGMECに天然ガスの積替・貯蔵基地や金属鉱物の採掘・製錬事業に対する出資等業務を追加する。
②緊急時に経産大臣からの要請によりLNG等の発電用燃料をJOGMECが調達する業務を創設する。
2.エネルギーレジリエンスに関する国際的な議論の動向
これまで、エネルギーレジリエンスの強化に向けた最近の日本の議論について紹介してきましたが、自然災害の多発・激甚化は日本だけの事象ではなく、国際的にも、災害対応やエネルギーレジリエンスに関する議論や取組が活発に行われています。
以下では、災害対応やエネルギーレジリエンスに関する国際的な議論を概観した上で、従来はコストと見なされ必ずしも十分に投資がなされてこなかったエネルギーレジリエンスを金融面でも積極的に評価し、必要な投資を確保していくための取組について紹介します。
(1)国連防災会議における議論
災害対応時には各国や国際機関がそれぞれの分野毎の緊急支援を行っていますが、それらが効率的に行われるための全体調整を国連人道問題調整事務所(OCHA:Office for Coordination of HumanitarianAffairs)が担っています。
国連を中心に1990年代に進められた「国際防災の10年」活動では、数多くの災害の経験から得られた知見を活かした日本が、主導的な役割を果たしてきました。具体的には、10か年の国連防災計画の中間年にあたる1994年、2005年、2015年に、それぞれ横浜、神戸、仙台に国連防災会議を誘致・開催し、国際防災戦略の基本文書として「兵庫行動枠組み2005-2015」及び「仙台防災枠組み2015-2030」を採択しています。
「仙台防災枠組み」では、地方、国、地域、グローバルレベルで災害リスク削減の取組を強化し、新たな開発アジェンダや気候変動枠組に防災の視点が取り込まれることを目的として、4つの優先行動として、①災害リスクの理解、②災害リスクを管理する災害リスク・ガバナンスの強化、③レジリエンスのための災害リスク削減への投資、④効果的な災害対応への備えの向上と、復旧・復興過程における「より良い復興(BBB: Build Back Better)」が規定されるとともに、これらを着実に進捗させるために、7つのターゲットが示されました。具体的には、2030年までに(ア)死亡者数、(イ)被災者数、(ウ)直接的経済損失、(エ)重要インフラの損害を大幅に減少させること、(オ)2020年までに防災戦略採用国を大幅に増加させること、(カ)2030年までに開発途上国への国際協力を大幅に増加させること、(キ)早期警戒及び災害リスク情報へのアクセスを大幅に増加させることとなっています。
国連における防災の議論では、事後の復旧活動に比べ、事前の防災投資を通じたレジリエンス向上の費用対効果が優れているといった点や、より良い復興と多様な主体の参画を得たガバナンスが重要である点などが盛り込まれています。こうした点は、日本が過去の知見や経験を活かして従来から主張してきた視点であり、日本は、この分野の国際的な議論をリードしています。
(2)APECにおける議論
エネルギーシステムの強靱化の必要性もまた、災害対応と同様に、日本だけでなく、広くアジアに共通するものです。
アジア太平洋地域の21の国と地域(エコノミー)が参加する経済協力の枠組みであるAPEC(アジア太平洋経済協力)では、持続可能な成長と繁栄のため、過去数年にわたり、エネルギーレジリエンスに関する議論がされてきました。2014年のAPEC首脳宣言の付属文書である「2015-2025年APEC連結性ブループリント」を受けて、2015年のエネルギー大臣会合ではエネルギーレジリエンスが主要テーマとされ、エネルギー安全保障と持続可能な発展を推進する上で、エネルギーレジリエンスを高めることが重要との認識が共有され、成果文書として「セブ宣言」が公表されました。
セブ宣言に基づき、エネルギーワーキンググループの下にエネルギーレジリエンスタスクフォースが新たに設置され、2015年12月以降、エネルギーレジリエンスに関する取組や知見の共有とともに、「APECエネルギーレジリエンス原則」の取りまとめに向けた議論を進めています。
自然災害に対応したエネルギーレジリエンスの在り方については、各国・地域を取り巻く事情は多様であり、従って取組も多様であるべきことや、エネルギーサプライチェーン全体の取組が重要であることを前提として、平時・災害時の双方でエネルギーの安定供給に必要な取組を政府、産業界、需要家、金融業界などの関係機関ごとに整理することが重要であることなど様々な観点から検討しており、今後APECでは、より詳細な取組の指針づくりが進んでいく見通しです。
(3)世界のエネルギーシステム強靱化に必要な投資額
エネルギーインフラの強靱化には、巨額の投資が必要です。例えば、一般財団法人日本エネルギー経済研究所の試算では、世界の需要拡大に対応しエネルギー安定供給を実現するために世界全体で必要な投資額は、2018年~2050年までの累積で7,620兆円(230兆円/年。それぞれ1ドル=100円で換算)にもなります。パリ協定の実現に向けた低炭素・脱炭素技術とは別に、エネルギーの安定供給のためにも、巨額の資金が必要であり、これを集めていくことも大きな課題です。
【第124-2-1】2050年のエネルギー安定供給を実現するために必要な累積投資額
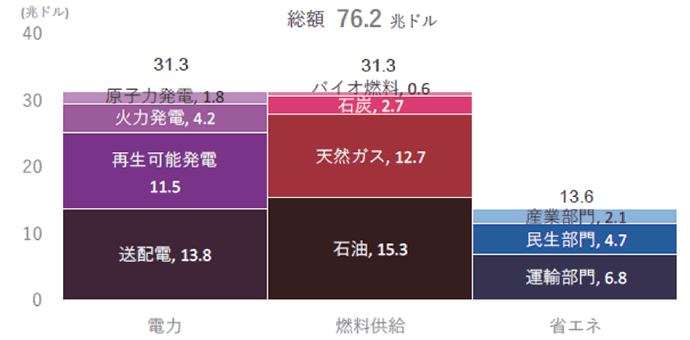
- 出典:
- (一財)日本エネルギー経済研究所「IEEJ Outlook 2020」より
(4)エネルギーシステム強靱化に向けた資金供給の円滑化の取組
エネルギー供給の強靱化のための投資は、従来はコストと見なされ、必ずしも十分な資金供給がなされてきませんでした。しかし、自然災害の多発化・激甚化に伴い、エネルギー供給の途絶に伴うサプライチェーンの途絶が国民生活や企業経営にも大きな影響を及ぼすようになっています。
エネルギーレジリエンス向上の取組に円滑に資金が供給されるために重要になるのが、エネルギー供給の強靱化が企業経営にとってもプラスになるとの認識の下、金融面でも適切に評価されるようになることであり、そのためにはエネルギーレジリエンスを概念だけでなく具体的・定量的に捉えていくことが重要です。
日本では、台風15号や台風19号等の経験から、自然災害等でエネルギーが途絶しない建物への入居を求める動きが一部で見られ、エネルギーレジリエンスの確保がサイバーセキュリティと並ぶような企業活動の根幹をなす必須条件となっていく可能性があります。
エネルギーレジリエンス重視の萌芽を的確に捉え、今後政府や産業界、金融界が取るべき対応を検討するため、経済産業省では2020年2月から「エネルギーレジリエンスの定量評価に向けた専門家委員会」を開催し、先進的な取組を行う企業や金融機関による議論を進めています。5
【第124-2-2】エネルギーレジリエンスが企業経営に与える影響①
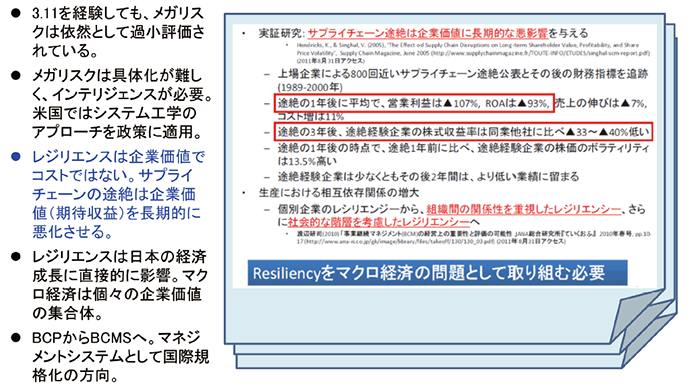
- (出所)
- 保井俊之「事業継続へのシステムズ・アプローチ」、産業競争力懇談会(COCN)レジリエントエコノミー研究会小委員会「レジリエントエコノミー研究会発表資料(2011年9月13日)」等より作成
- 出典:
- (一財)日本エネルギー経済研究所「エネルギーレジリエンスの定量評価に向けた専門委員会(第1回)」より
【第124-2-3】エネルギーレジリエンスが企業経営に与える影響②
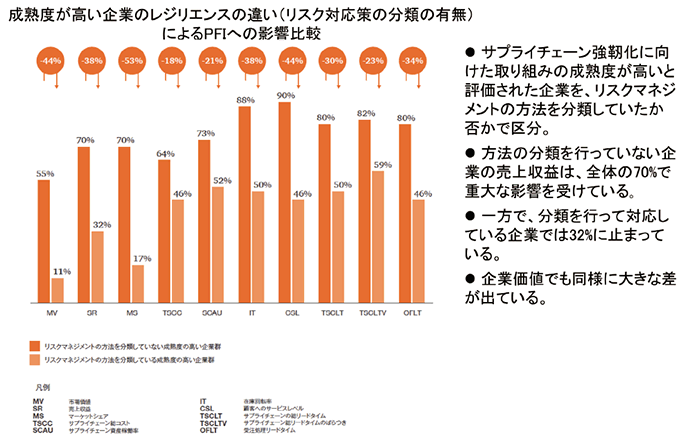
- (注)
- リスクマネジメントの方法の分類の有無により、サプライチェーンの寸断による「重大な影響」が出た成熟度の高い企業の割合を比較している。
- 出典:
- (一財)日本エネルギー経済研究所「エネルギーレジリエンスの定量評価に向けた専門委員会(第1回)」より
- 5
- 座長である東京大学小宮山涼一准教授に加え、金融界から荻野零児・三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)シニアアナリスト、木村彰宏・損害保険ジャパン(株)ビジネスデザイン戦略部長、末廣孝信・(株)三井住友銀行 サステナビリティ推進室長、蛭間芳樹・(株)日本政策投資銀行 サステナビリティ企画部BCM格付主幹、産業界から井上雅之・大阪ガス(株)執行役員・企画部長、鈴木眞吾・三井不動産(株)執行役員ビルディング本部副本部長、笹山晋一・東京ガス(株)常務執行役員、谷口直行・NTTアノードエナジー(株)取締役スマートエネルギー事業部長、中原俊也・JXTGエネルギー(株)取締役・常務執行役員、守谷誠二・東京電力ホールディングス(株)代表執行役副社長、渡部正治・三菱重工業(株)シニアフェロー・パワードメイン技師長が委員として参加するとともに、(一社)日本経済団体連合会、電気事業連合会、石油連盟、(一社)日本ガス協会がオブザーバーとして参加し、議論を進めています。