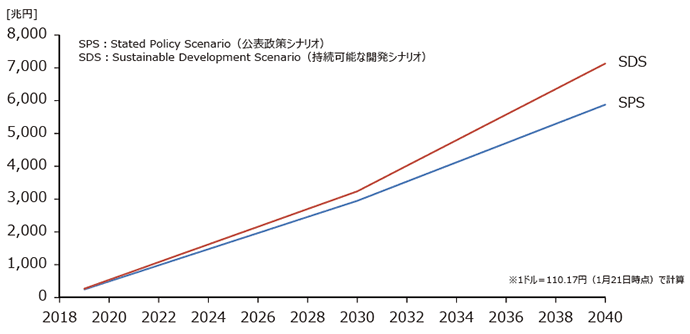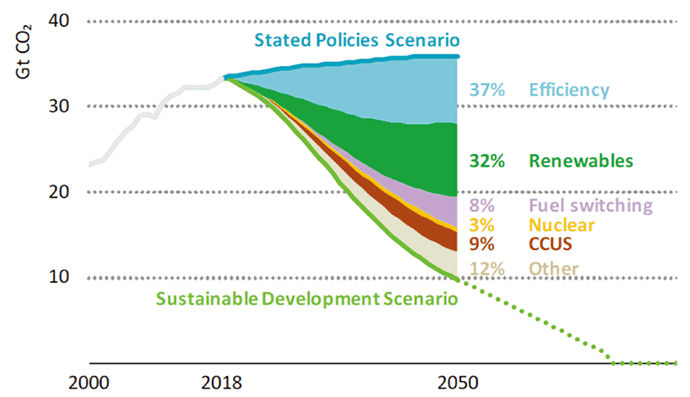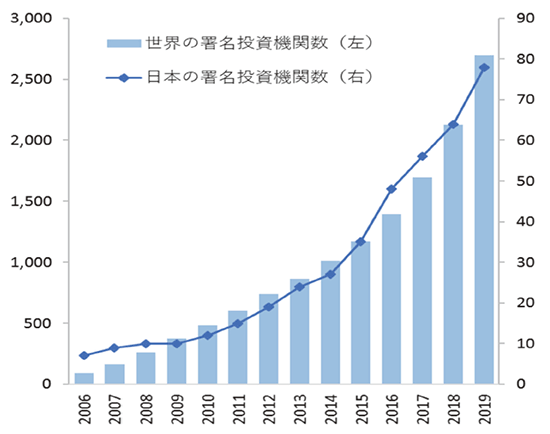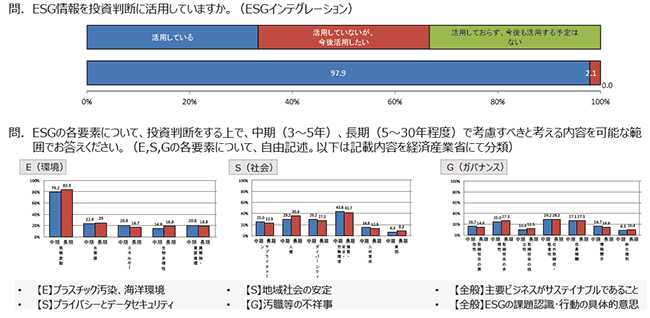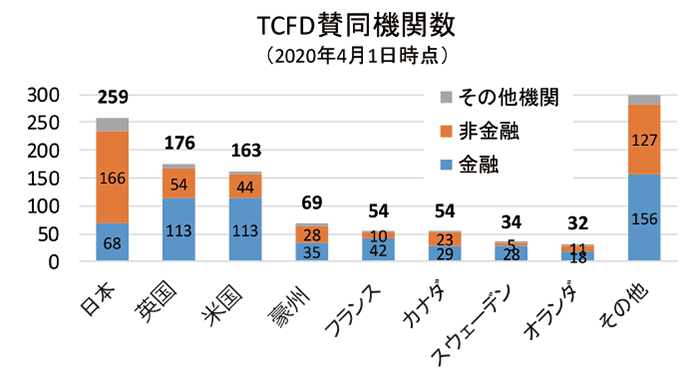第2節 エネルギーファイナンスをめぐる動き
1.パリ協定実現に必要な資金の供給
パリ協定が目指す社会の実現には、技術・経済・社会システムのイノベーションが欠かせません。気候変動対策やイノベーションの実現に取り組む企業に対し、資金を集中する必要があります。国際エネルギー機関(IEA)によれば、パリ協定の実現に必要な資金は2040年までの累積で6,470兆円~ 7,860兆円にもなり、その投資先は、省エネ、再エネ、燃料転換、原子力、カーボンリサイクル等、あらゆる方策を全て模索すべきとしています8 。これだけの巨額の資金は、到底政府だけでまかなえるものではなく、これをどのように供給していくかが課題です。
- 出典:
- 経済産業省「環境イノベーションに向けたファイナンスのあり方研究会(第1回)」より抜粋
- 出典:
- IEA「World Energy Outlook 2019」より抜粋
2.ESG投資等による環境分野への資金供給の活発化
(1)国際的なESG投資等の流れ
2006年に国連の提唱で「責任投資原則(PRI:PrinciplesforResponsibleInvestment)」が策定され、環境・社会・ガバナンス要素を投資判断に組み込む「ESG投資」の考え方が打ち出されました。その後、2008年のリーマン・ショックにより、財務情報に限らず非財務情報が企業価値に及ぼし得る影響に注目が集まり、2006年に100機関で始まったPRIへの署名機関数も2019年には2,400機関以上へと増加してきています。
2015年には、国連で「持続可能な開発目標(SDGs)9」が採択されるとともにパリ協定が採択され、これらの達成のためにもイノベーションが不可欠なことから、中長期的な企業価値向上を志向するESG投資の果たす役割が期待されています。
ESGを考慮する動きは投資のみならず金融全体に広がりつつあります。投資以外の保険、銀行分野でも、2012年には「持続可能な保険原則(PSI:PrinciplesforSustainableInsurance)」が、2019年には「責任銀行原則(PRB:PrinciplesforResponsibleBanking)」が国連で策定されています。
日本では、世界最大規模10の機関投資家である年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2015年にPRIに署名するなど、ESG投資への関心が高まりました。また、機関投資家の行動規範とも言うべき「日本版スチュワードシップ・コード」11が2020年に改訂され、ESG要素を考慮すべき旨が明示されました。
世界のESG投資額は2018年に30.7兆ドルに拡大し12、投資市場全体の約3分の1を占めるに至っています。その中で、日本は欧州、米国に続く世界第3位のESG投資残高国となっています。
- 出典:
- PRI「責任投資原則」より経済産業省作成
【第132-2-2】投資市場全体に占めるESG(サステナブル)投資額の推移(兆ドル)
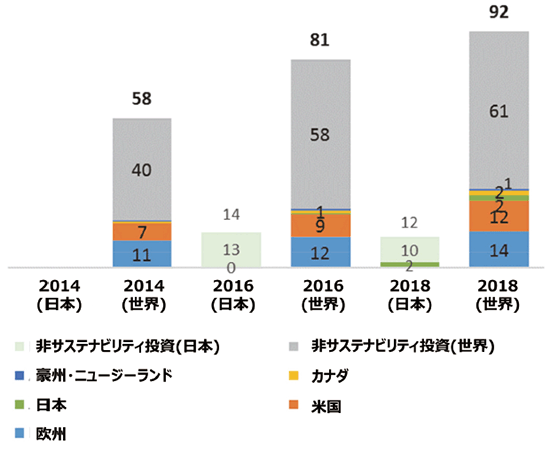
- 出典:
- GSIA「Global Sustainable Investment Review 2016、2018」より経済産業省作成
COLUMN
主要な資産運用機関はESGをどのくらい考慮しているのか
経済産業省が国内外の主要運用機関に行ったアンケート調査(調査対象機関は63、回答は48、総運用残高約3,998兆円)によれば、98%の運用機関がESG要素を投資判断に活用していると回答しました。また、約80%の運用機関が、E(環境)のうち、特に気候変動を最も重視していると回答しました。
- 出典:
- 経済産業省「ESG投資に関する運用機関向けアンケート調査」より抜粋
その一方で、「企業のESGに関する情報開示が不十分」とする意見が85.4%を占め、また「ESG投資の適切な評価方法が確立できていない」とする意見も56.3%を占めており、ESGを投資判断などにおいて考慮する際の障害があります。これらを解決し、よりESG投資が促進される環境を整備することが求められています。
【第132-2-4】ESGを投資判断やエンゲージメントにおいて考慮する上での障害
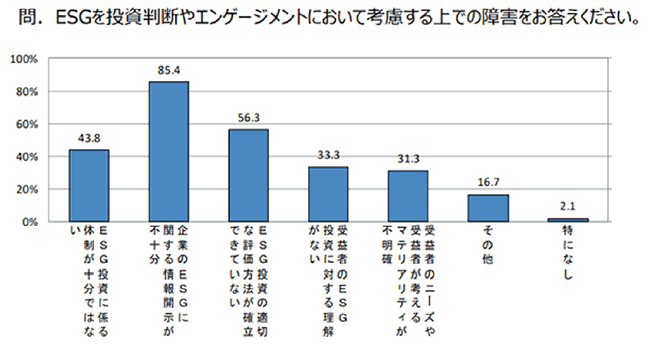
- 出典:
- 経済産業省「ESG投資に関する運用機関向けアンケート調査」より抜粋
(2)気候変動に関する情報開示の進展
ESG要素の中で最も投資家の関心が高いテーマの一つである気候変動については、企業の気候変動に対する取組の情報開示を求める動きが高まっています。G20の意向を受けた金融安定理事会(FSB)により2015年に設置された「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」は、2017年に最終報告書(以下、「TCFD提言」という。)を公表し、企業の気候関連情報の開示に関するフレームワークを提示しました。TCFD提言では、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標・目標の4項目について、自社への財務的影響のある気候関連情報を開示するよう勧めています。
こうした動きを受け、日本企業の情報開示の取組を後押しするために、経済産業省は2018年12月に「気候関連財務情報開示に関するガイダンス(TCFDガイダンス)」を政府として世界で初めて策定しました。同ガイダンスでは、情報開示の方法や進め方などに加え、業種ごとにどのように戦略を示し、情報開示に取り組んでいけばよいかを解説しています。
また、TCFDに賛同する企業・機関は世界で1,163企業・機関に上っており、その中で日本は259企業・機関と世界最多になっています(2020年4月1日時点)。こうしたTCFDに対する機運の高まりを受け、2019年5月には民間主導でTCFDへの対応を推進していくための組織として「TCFDコンソーシアム」が設立され、企業の効果的な情報開示や、開示された情報を金融機関等の適切な投資判断に繋げるための取組等についての議論が行われています。
2019年10月には、経済産業省が主催、TCFDコンソーシアム、持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)が共催という形で、世界の産業界や金融界のトップが一堂に会する世界初の「TCFDサミット」を東京で開催し、投資家が企業の開示情報を評価する際の視点を解説した「グリーン投資ガイダンス」を公表しました。TCFDサミットでは、「気候変動はリスクではなく事業機会と捉えるべき」、「金融機関は投資引揚げ(ダイベストメント)ではなく企業への建設的対話(エンゲージメント)を強化すべき」、「アジアにおいて継続的な経済発展を促進し、低炭素社会への円滑な移行を後押しすることが必要」等のメッセージを世界へ発信しました。また、環境省では、2019年度は12社に対してTCFDに対応したシナリオ分析の支援を行い、当該事業で得られた事例を踏まえ、2020年3月に「シナリオ分析実践ガイドver2.0」を公表しています。
- 出典:
- TCFD「Supporters」等より経済産業省作成
3.グリーンな産業活動を定義する国際的な動き
(1)欧州等の動き
パリ協定の実現に向け、気候変動を考慮する金融市場の機運を高め、実質的にGHG排出を削減する取組に資金を動員するため、「グリーンな活動」を定義する動きが出てきています。欧州では「持続可能な金融推進のためのアクションプラン」の一環として、「グリーンな経済活動に関するEUタクソノミー」13を定め、これをグリーンボンドの発行等に幅広く活用しようという動きがあります。また、中国でも発展改革委員会、中国人民銀行等の7つの公的機関が共通で用いる「持続可能な経済活動の定義」として「グリーン産業ガイダンス・カタログ」14が策定されています。
【第132-3-1】「二元論」的な定義ではなく、低炭素化やイノベーションを後押しするような定義の必要性について(国際的な意見)
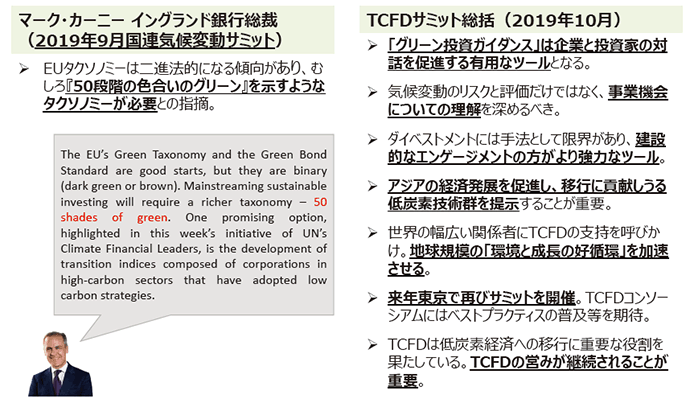
【第132-3-1】「二元論」的な定義ではなく、低炭素化やイノベーションを後押しするような定義の必要性について(国際的な意見)(ppt/pptx形式:60KB)
- 出典:
- 経済産業省「環境イノベーションに向けたファイナンスのあり方研究会(第1回)」より抜粋
(2)「二元論」的でなく、効率改善やイノベーションにつながるより柔軟な定義の必要性
こうした取組は、民間資金の供給を円滑化し得る一方で、二元論的なグリーン基準は、企業による効率改善やイノベーションの取組を適正に評価できないなどの課題を指摘する声もあります。
例えば、前イングランド銀行総裁のマーク・カーニー氏は「EUタクソノミーは二元論的だが、むしろ『50段階の色合いのグリーン』を示すようなタクソノミーが必要」15と指摘しています。また、2019年10月に開催されたTCFDサミット総括においても、アジアの経済発展を促進しながら、低排出型の経済構造への「移行(トランジション)」に貢献し得る低炭素技術群を提示することが重要である旨等が確認されました。
同様に、国内でも、日本経済団体連合会(経団連)が、絶対的な基準や閾値で線引きせず地域・業種の事情を踏まえた実効的な温暖化対策を評価すべきであり、そのために幅広い技術や設備への投資やイノベーションを促す枠組みにすべきこと、個別技術を分類・定義する場合には製品のライフサイクルやバリューチェーン全体を勘案すべき旨を意見表明しています。また、全国銀行協会(全銀協)も、過度に詳細で規則的なタクソノミーはイノベーションを阻害しかねず、民間の創意工夫を後押しするべく、柔軟で時流に即した見直しが出来る形にすべきである旨を意見表明しています。
(3)低炭素経済に向けた「改善」や「移行」(トランジション)を評価し、促す国内外の動き
技術や事業がグリーンか否かの二元論的な分類ではなく、GHG排出削減の改善幅や低炭素経済への移行(トランジション)に資するかどうかを評価し、低排出に向けた適切な取組や改善の行われている分野に資金を供給しようという動きが世界的に進み始めています。
例えば、フランスの資産運用会社アクサ・インベストメント・マネージャーズ(AXAIM)は、2019年6月に発表した「トランジションボンドガイドライン」において、現段階では、技術的・経済的に脱炭素化が困難な産業分野が、低炭素化を進めていく移行の取組について、分野別に資金使途を示しています。具体的には、エネルギー分野ではガスコージェネレーション、CCS(CarbondioxideCaptureandStorage)、石炭からガスへの転換、ガス輸送インフラの燃料転換、廃棄物のエネルギー転換等、輸送分野ではガス燃料船舶、航空機向け代替燃料、製造分野では、セメント・金属・ガラス製造におけるエネルギー効率向上に向けた投資を挙げています。また、カナダ政府は、2019年6月に発表した「サステナブル・ファイナンス専門家パネル最終報告書:持続可能な成長のための資金動員」の提言において、「カナダのグリーン債券市場を拡大し、トランジション志向のファイナンスのための国際標準を設定する」としており、トランジション・ファイナンスに関するルール整備に向けた議論を進めています。このような動きがあるなか、国内でも、経済産業省において、気候変動対策のための着実な移行(トランジション)やCO2大幅削減に向けたイノベーションに取り組む企業への資金供給を促進させるために、有識者、金融関係者、産業界関係者等の委員及び金融庁、環境省等のオブザーバーから構成される「環境イノベーションへ向けたファイナンスのあり方研究会」を開催し、2020年3月には、「クライメート・トランジション・ファイナンスの考え方」16を取りまとめて公表し、国際的に発信しています。
【第132-3-2】低炭素経済への移行(トランジション)に関する国際的な議論
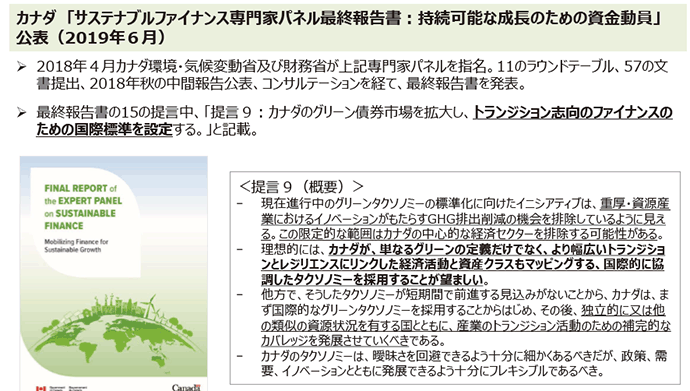
- 出典:
- 経済産業省「環境イノベ・ファイナンス研究会(第2回)
- 8
- IEAは「World Energy Outlook2019」の中で、最も起こる蓋然性が高い「公表政策シナリオ」と、パリ協定遵守ベースの「持続可能な開発 シナリオ」の間に大きなCO2ギャップがあり、これを埋めるには省エネ、再エネ、燃料転換、原子力、CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)等、あらゆる方策を組み合わせることが必須としています。
- 9
- SDGs(持続可能な開発目標):2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで策定された 「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標のことです。持続可能な世界を実現する ための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として残さない(leave no one behind)ことなどを謳っています。特 徴として、①普遍性、②包摂性、③参画型、④統合性、⑤透明性の5点が挙げられます。
- 10
- GPIFは特定業種に限らず、世界中の資産を幅広く保有しているユニバーサルオーナーであり、2019年12月時点で約170兆円を運用し ています。国内では、TOPIXをベンチマークに2,300社以上の日本企業(東証一部全社プラスアルファ)を保有しています(小森博司「GPIF のインベストメントチェーンとESGの取組みについて」)。
- 11
- 2008年のリーマン・ショックを受け、英国では「ウォーカー・レビュー」が取りまとめられました。機関投資家が短期収益志向に陥った ことで、金融機関の株主としてガバナンスを機能させられなかったとし、企業や機関投資家のガバナンス改革を提言しました。これを受 け、英国の財務報告協議会が企業の長期的な成功を促進するため、「スチュワードシップ・コード」を2010年に策定しました。日本でも 2014年に「日本版スチュワードシップ・コード」を策定しました。円高・デフレからの脱却を目指して成長戦略の一つとして位置づけられ、 投融資先企業の持続的な成長を目指しています。
- 12
- Global Sustainable Investment Alliance「Global Sustainable Investment Review 2018」
- 13
- 欧州委員会がEUタクソノミー規則案を欧州議会・理事会に提案し、2019年12月に合意に至りました。2021年末までに詳細を正式決定し、 運用が始まる予定です。EUタクソノミーの基準案の例は以下の通りです。①自動車:2025年まではテールパイプエミッションが50gCO2/ km以下の車であれば適格。2026年以降はテールパイプエミッションがゼロの車のみが適格。②ガス発電:ライフサイクルで100gCO2/ kWhであれば適格。また、化石燃料の運搬や関連建物の新築・改修等は(個別の閾値を満たしていたとしても、化石燃料を扱っていることか ら)不適格とされています。
- 14
- 掲載されている具体的な産業の例:新エネルギー・クリーンエネルギー(風力・太陽光等)、原子力エネルギー、新エネルギー自動車、クリー ンな石炭生産・利用 等。
- 15
- 2019年9月の国連気候サミットでの発言。
- 16
- クライメート・トランジション・ファイナンスの考え方」は、世界全体でGHGの排出量を着実に削減していく観点から、再生可能エネルギー等の既に脱炭素化・低炭素化の水準にある活動へのファイナンスを促進していくことと併せて、GHG排出産業部門が脱炭素化・低炭素化を進めていく移行の取組(トランジション)へのファイナンスについても、同様に、気候変動対策に資するクライメート・ファイナンスの一つとして位置づけ、促進していくことが重要であり、国際資本市場協会(ICMA)における議論など国際的にもトランジション・ファイナンスに関する議論が進んでいる中、「環境イノベーションに向けたファイナンスのあり方研究会」として、その在り方について、我が国が発信すべき考え方を取りまとめたものです。