第1節 電力システム改革の推進
1.電力の小売全面自由化の進捗状況
2025年3月末時点で、761者を小売電気事業者として登録しています。
登録された小売電気事業者の内訳を見ると、過去より高圧の小売電気事業を行っていた新電力事業者(PPS)に加え、LPガスや都市ガス、石油、通信、放送、鉄道関係の事業者等、非常に多岐にわたります。また、異業種の事業者間の連携や地域の枠を超えた事業統合等も始まっており、事業者の事業機会の拡大も進んでいます。
なお、電力取引報によると、2024年12月時点における電力市場全体の販売電力量に占める新電力のシェアは、約17%となっています。
新電力の提供する料金メニューを見ると、全体的な傾向としては、基本料金と従量料金の二部料金制からなる既存の料金メニューに準じたものが多く見られます。他方で、一部では、完全従量料金メニューや定額料金メニュー、市場連動型料金メニュー、時間帯や季節に応じて料金単価が変更になるメニュー、指定された時間帯における節電状況に応じた割引メニュー、セットプラン等、新しい料金メニューも提供されるようになっています。
また、再エネ等の電源構成や地産地消型の電気であることを訴求ポイントとして、顧客の獲得を試みる小売電気事業者の参入も見られ、中には、需要家が発電所を選んで電力を購入できる等、特色のある小売電気事業者も存在しています。さらに、電力消費の見える化(電気の使用状況の可視化)や、電気の使用状況等の情報を利用した家庭の見守りサービス等も提供され始めています。その他にも、応援するスポーツチームとのつながりや里山の景観保存等、需要家の好みや価値観に訴求するサービスも始まっています。
加えて、需要家側の取組として、電力コストの削減といった観点から、同種の事業者間における電気の共同調達や、地域を問わない事業グループ全体としての電気の一括調達等の動きも見られています。
2.電力小売市場・卸売市場に関する取組
(1)小売取引の監視等
①各種相談への対応
電力・ガス取引監視等委員会は、相談窓口を設置し、需要家等から寄せられた相談に対応し、質問への回答やアドバイス等を行っており、2024年度における相談件数は2,624件でした。不適切な営業活動等に係る情報があった場合には、事実関係を確認し、必要な場合には小売電気事業者に対する指導等を行いました(第261-2-1)。
【第261-2-1】相談窓口への相談件数(電気)の推移
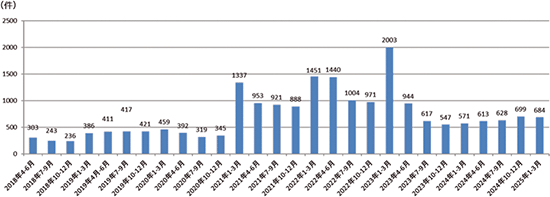
【第261-2-1】相談窓口への相談件数(電気)の推移(pptx形式:97KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
また、消費者庁及び独立行政法人国民生活センターと連名で電気の契約トラブルに関する注意喚起を行ったほか、経済産業省のXを活用し、電気・ガスの契約前後の注意点を周知する等、消費者に対して情報提供を4件行いました。
②小売電気事業者に対する勧告等
(ア)勧告
●ハルエネに対する勧告(2024年4月)
2023年1月から同年8月までの間にハルエネが受け付けた自社の需要家からの契約番号の提供依頼のうち、提供依頼後に3週間以上の期間を経過してから契約番号の提供が行われていた事例が606件確認されました。
契約番号は需要家がスイッチングをするために必須の情報であるため、需要家に対して速やかに契約番号の提供が行われないことは、円滑なスイッチング及びこれに伴う小売供給契約の解除等を阻害しうるものです。
このため、電力・ガス取引監視等委員会は、ハルエネに対し、業務改善勧告を行いました。
(イ)指導の例
●A社に対する指導(2024年10月)
A社は、提供する料金プラン名について、電話で小売供給契約を締結する需要家に対して、旧一般電気事業者と誤認させるおそれがある情報提供を行っていました。これは需要家の誤認に基づく選択を招きかねず、小売電気事業者間の公正な競争を阻害するおそれがあります。
また、A社は、需要家と小売供給契約を締結する際に必要となる書面を電磁的方法により提供する際に、法令上認められていない、電話等において需要家が承諾した旨を録音する方法により当該承諾を取得していました。
このため、電力・ガス取引監視等委員会は、A社に対し、所要の改善措置を実施するように指導を行いました。
●B社に対する指導(2025年1月)
B社は、小売供給契約を締結する際に必要な書面を準備して交付する必要があるところ、一部の営業担当者の知識不足や認識の誤りがあったこと等により、必要な書面を交付していませんでした。
契約締結時の書面交付は、小売電気事業者と需要家との間のトラブルを未然に防止する上で重要です。
このため、電力・ガス取引監視等委員会は、B社に対し、所要の改善措置を実施するように指導を行いました。
③関西電力、中部電力ミライズ、中国電力、九州電力及び九電みらいエナジーに対する業務改善命令後のフォローアップ
関西電力、中部電力ミライズ、中国電力、九州電力及び九電みらいエナジーがカルテル及びこれに類する競争制限的な行為を行ったこと等について、2023年7月に経済産業大臣が業務改善命令を行いました。電力・ガス取引監視等委員会は、業務改善命令を受けて各事業者が取り組んでいる再発防止策の状況について、フォローアップを行っています。2024年度は、第99回制度設計専門会合(2024年7月開催)において、教育・研修の実効性及び役職員の行動の変化等のフォローアップ結果を報告するとともに、第1回制度設計・監視専門会合(2024年9月開催)において、フォローアップの最終報告を行いました。同会合では、業務改善命令の対象となった各事業者が改善計画に基づき、改善に向けた取組を着実に実施していること、また、再発防止に向けた実効的な取組を継続して行っていくことなどの表明をしていることを確認しました。
④小売市場重点モニタリング
電力・ガス取引監視等委員会は、一定の価格水準を下回る小売供給契約について、競争者からの申告や公共入札の状況を踏まえ、取引条件等を含む実態を重点的に把握する「小売市場重点モニタリング」を実施しており、2023年度に締結された小売供給契約については、問題となる事例は認められなかった旨を第1回制度設計・監視専門会合(2024年9月開催)において報告し、その調査結果を公表しました。
⑤規制料金に係る審査・監査・事後監視
(ア)規制料金の改定申請に対する審査
電力・ガス取引監視等委員会は、2023年5月に規制料金の値上げが認可されたみなし小売電気事業者7社(北海道電力、東北電力、東京電力エナジーパートナー、北陸電力、中国電力、四国電力及び沖縄電力)について、調達コストの効率化に向けたロードマップに織り込まれた効率化施策の進捗状況や修繕費等の費目の合計額の推移を確認し、第63回料金制度専門会合(2024年11月開催)において報告・公表等を行いました。
(イ)みなし小売電気事業者に対する監査
電力・ガス取引監視等委員会は、電気事業法に基づき、みなし小売電気事業者(10社)に対して実施した2023年度監査の結果を第515回電力・ガス取引監視等委員会(2024年5月開催)に報告しました。監査の結果、部門別収支について、1事業者に対し指導を行いました。
(ウ)経過措置が講じられている規制料金に係る原価算定期間終了後の事後評価
2024年11月に、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣からの意見聴取を受けて、第63回料金制度専門会合(2024年11月開催)において、原価算定期間が終了している中部電力ミライズ、関西電力及び九州電力の各規制料金について事後評価を行い、現行料金に関する値下げ認可申請の必要があるとは認められませんでしたので、経済産業大臣に対し、その旨を回答しました。
⑥小売電気事業者に関する今後の対応(電気関係報告規則の改正に係る建議)
電力・ガス取引監視等委員会は、電気関係報告規則に基づく定期報告に関する事項について、2024年7月に、料金メニューの回答形式の変更や報告対象の拡大等、所要の制度的措置を図るよう、経済産業大臣に建議し、2025年1月に必要な省令改正が行われました。
(2)電力の卸取引の監視
①スポット市場の監視
電力・ガス取引監視等委員会では、卸電力取引所が実施するスポット市場に対して日々監視を実施しています。その結果、2024年11月12日には、JERAが出力を絞って運転できたはずの発電機を完全停止させ、供出可能な電力を市場に供出しなかった行為について相場操縦に該当するものと判断し、同社に対して業務改善勧告を行いました。同委員会は、2024年12月27日から2025年12月26日までの1年間を同社の集中改善期間として設定し、重点的に確認・指導しています。
②ベースロード市場の監視
電力・ガス取引監視等委員会は、2024年度に実施されたベースロード市場のオークションに関する取引内容について監視を行い、全ての大規模発電事業者における供出量と供出上限価格について、問題となる行為は確認されませんでした。
また、2023年度に受渡が行われた2022年度のベースロード市場について事後的な監視を行い、その結果、一部の大規模発電事業者が、本来含めるべきではない費用を発電コストに含めていたことを確認したため、当該事業者に対して注意喚起を行いました。
(3)容量市場の運用・監視
①容量市場の運用
発電事業者の投資回収の予見性を高め、将来必要となる供給力を確保するための仕組みとして2020年度に創設された容量市場については、2024年10月に、2028年度における必要供給力を確保するための第5回メインオークションが実施されました。また、2024年5月には、2025年度における供給力を追加で調達するための追加オークションが初めて実施されました。
また、2050年カーボンニュートラル実現と安定供給を両立するため、電源への新規投資を促進するための仕組みとして2023年度に創設された長期脱炭素電源オークションは、初回入札が2024年1月に行われ、脱炭素電源は募集量400万kWに対して401万kWが落札し、LNG火力電源は募集量600万kWに対して575万kWが落札されました。2025年1月には第2回入札が行われました(第261-2-2)。
【第261-2-2】長期脱炭素電源オークションの概要
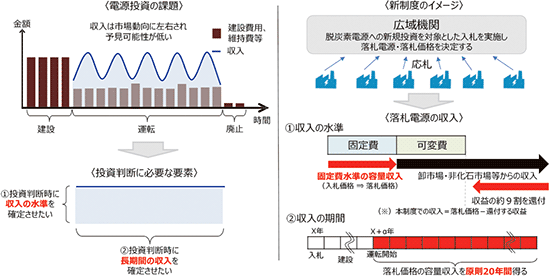
【第261-2-2】長期脱炭素電源オークションの概要(pptx形式:60KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
②容量市場の監視
電力・ガス取引監視等委員会による2024年度メインオークション(対象実需給年度:2028年度)における売り惜しみの事前監視において、容量市場に参加しない正当な理由に該当するものと認められなかった1電源について応札を求め、当該1電源が実際に応札されていることを確認しました。
(4)非化石価値取引市場の創設・運用・監視
①非化石価値取引市場の創設・運用
高度化法により、小売電気事業者には、自らが調達する電気の非化石電源比率を2030年度に44%以上とすることが求められています。このような状況を踏まえ、新たな市場である「非化石価値取引市場」を2017年に創設し、非化石価値を顕在化し、取引を可能とすることで小売電気事業者の非化石電源の調達目標の達成を後押ししています。
2024年度には、国際的な環境意識の高まりなどを背景とした需要家のニーズ増大を受けて制度を見直し、非FIT非化石証書を含む全ての非化石証書に発電所情報等が付与されることとなりました(全量トラッキング)。さらに、非FIT非化石証書は、一定の条件を満たす非FIT電源やFIP電源、卒FIT電源について、発電者と需要家間の直接取引を認めていたところ、新たにFIP電源については、運転開始日の制限を設けず、直接取引が可能となりました。
②非化石価値取引市場の監視
2024年度に電力・ガス取引監視等委員会が実施した監視(2023年度第3回オークションから2024年度第2回オークションまで)では、問題となる事例は認められませんでした。
(5)発電・小売間の不当な内部補助の防止策
電力・ガス取引監視等委員会は、内外無差別に卸売を行うこと等へのコミットメントに対する旧一般電気事業者各社の取組状況を確認するため、2024年度には、制度設計専門会合において2023年度に交渉・締結した卸契約について確認し、その結果、北海道、北陸、関西、中国、四国、九州及び沖縄の各エリアについては、内外無差別な卸売を行っていると評価されました。また、2024年度に各社が交渉・締結予定の卸売契約についても中間的な確認を行い、多くの事業者がこれまでの同会合における指摘を踏まえて対応策を措置済み又は検討中であることを確認しました。
あわせて、2024年度には、これまで同会合で整理された内外無差別な卸売等のコミットメントに基づく評価の考え方について、パブリックコメントを経て、取りまとめました。また、内外無差別な卸売の対象電源の考え方についても議論がなされ、旧一般電気事業者の子会社が保有する電源については、自家消費用電源、FIT電源、経過措置電源及び規模僅少電源に該当するものを除き、原則、内外無差別な卸売の対象電源として整理されました。さらに、第84回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2024年12月開催)における議論を受けて、同会合において、エリア内供給制限を付与する場合の評価の考え方等について整理されました。
(6)電力先物市場の活性化
電力先物市場について、東京商品取引所(TOCOM)が、2019年8月に電力先物の試験上場(3年間の時限的な上場)の認可を取得し、同年9月から取引を開始し、2022年4月に本上場しました。その後、電力先物の取引高は増加しており、電力先物は、価格変動リスクヘッジ手段等として認識されています。また、TOCOMのほか、欧州エネルギー取引所(EEX)、インターコンチネンタル取引所(ICE)、第二種特定商品市場類似施設における取引、相対での店頭商品デリバティブ取引等を含め、電力先物市場は活性化しつつあります。
こうした状況を踏まえて、電力先物の現状整理及び更なる取引の活性化を目的に「電力先物の活性化に向けた検討会」を開催し、2024年4月に取りまとめを行いました(第261-2-3)。また、電力先物を活用したヘッジを日本の会計基準上どのように扱うべきか検討するため、TOCOMを事務局として2024年7月に「電力先物におけるヘッジ会計適用に向けた検討会」を開催しました。発電事業者や小売電気事業者、金融機関、有識者等に加えて会計士を交え、電力先物におけるヘッジ会計適用における課題等に関して議論を行い、ヘッジ会計に関する現行の日本の会計基準を前提に、ヘッジ会計を適用する際の課題と対応等について2025年2月に取りまとめを行いました。
【第261-2-3】「電力先物の活性化に向けた検討会」取りまとめ
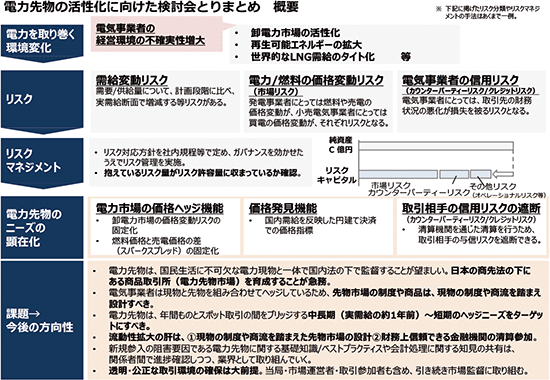
【第261-2-3】「電力先物の活性化に向けた検討会」取りまとめ(pptx形式:64KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
3.送配電分野に関する取組
(1)送配電事業の監視
①一般送配電事業者等に対する監査
電力・ガス取引監視等委員会は、電気事業法に基づき、一般送配電事業者及び送電事業者13社に対して実施した2023年度監査の結果を第515回電力・ガス取引監視等委員会(2024年5月開催)に報告しました。
具体的には、重点監査項目として、託送供給等収支に係る誤算定等の事案についての再発防止策の実施状況等、非公開情報を取り扱うシステムへのアクセスに必要となるID・パスワードの管理状況やログ記録の保存状況、事業者におけるログの解析結果、ある日時のアクセスログを指定した上でアクセス権限のない者が利用していないことなどを報告しました。
監査の結果、経済産業大臣への勧告を行うべき事項は認められませんでしたが、約款の運用等及び託送供給等収支について、5事業者に対し合計7件の指導を行いました。
②一般送配電事業者等の業務実施状況の監視
電力・ガス取引監視等委員会は、必要に応じ、電気事業法に基づく報告徴収を行い、一般送配電事業者、送電事業者及び特定送配電事業者の業務実施状況を把握・分析するとともに、問題となる行為等が見られた場合には、その是正や再発防止を図るよう指導しています。
また、2022年度以降に一般送配電事業者が発生させたインバランス料金の再精算の事案についての再発防止策の実施状況や、一般送配電事業者全体の横断的な取組として誤算定を発生させないための今後の対応について確認しました。
③一般送配電事業者による非公開情報の漏えい事案への対応
一般送配電事業者8社において特定関係事業者の従業員が非公開情報を閲覧し業務に利用していた事案に関し、電力・ガス取引監視等委員会は業務改善計画の提出日から1年間を集中改善期間と位置づけ、その実施状況、計画の取組の十分性及び実効性が担保されているかを確認するためモニタリングを実施しました。その後、モニタリングにより確認した各社の再発防止に向けた取組状況を採点し、2024年6月25日に、採点結果を公表しました。
また、東京電力パワーグリッドにおいて、非公開情報が特定関係事業者において閲覧可能となっており、東京電力リニューアブルパワーが非公開情報を業務に利用していたことが判明しました。これを受け、電力・ガス取引監視等委員会は2024年6月20日に、東京電力パワーグリッドに対して業務改善勧告を行い、東京電力リニューアブルパワーに対して業務改善指導を行いました。電力・ガス取引監視等委員会は、業務改善計画の提出日から1年間を集中改善期間と位置づけ、再発防止に向けた取組状況についてモニタリングを実施しています。
これらの事案を受け、電力・ガス取引監視等委員会は、2024年3月28日に、一連の事案への再発防止策としての制度的措置として、一般送配電事業者の従業者が兼職することを禁止されている特定関係事業者の従業者の対象範囲に、組織的に非公開情報の業務利用を実施させうる従業者を追加すべき旨を、経済産業大臣に対して建議し、建議を受けて、2025年1月31日に必要な省令改正等が行われました。
(2)調整力の調達・運用状況の監視及びより効率的な確保等に関する検討
①一般送配電事業者が行う調整力の公募等の結果の確認
電力・ガス取引監視等委員会は、一般送配電事業者が行った調整力の公募調達等の結果を分析し、発電事業者の入札行動に問題となる点がないか、監視を行いました。また、一般送配電事業者による調整力の運用が、経済合理的に適切に運用されているか等について、監視を行いました。
②需給調整市場の創設・運用
再エネの導入が進む中、調整力を効率的に確保していくことが重要です。効率的に調整力を調達するためには、エリアを超えて広域的に調整力を確保することも課題とされました。
こうした背景の下、「総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会」(以下「制度検討作業部会」という。)や広域機関の委員会において、需給調整市場(第261-3-1)の詳細設計が進められ、2025年4月現在、全調整力商品(一次調整力、二次調整力①、二次調整力②、三次調整力①、三次調整力②)が需給調整市場にて取引されています。
【第261-3-1】需給調整市場の概要
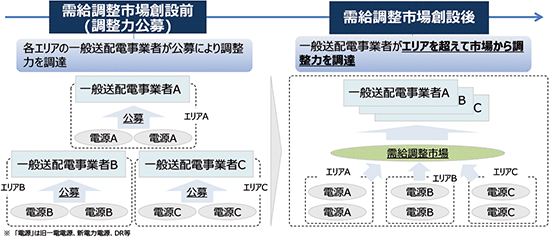
【第261-3-1】需給調整市場の概要(pptx形式:65KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
しかし、2024年度以降、募集量に対する約定不足・調達単価の高騰といった課題が発生しています。こうした課題に対して、市場の競争環境を高めるべく市場での募集量削減などの対応策を講じています。このように、市場取引の課題に対する適切な施策検討を継続的に進めています。
③需給調整市場の監視及び価格規律の在り方の検討
2024年4月より、需給調整市場において全商品の取引が開始されましたが、多くの商品及びエリアにおいて、募集量に対して応札量が少ない状況が継続し、市場競争が十分に機能していないという課題が生じています。また、市場競争が十分に機能していないことにより、約定価格が高値で推移するなど、調達価格の高騰についても対応が必要となっています。
こうした課題について、電力・ガス取引監視等委員会は、制度設計専門会合及び制度設計・監視専門会合において、応札量の増加を促進するとともに事業者の適切な入札を促す観点から、入札価格の規律等について検討を行い、その結果を踏まえ2024年12月に需給調整市場ガイドラインの改定について経済産業大臣に建議し、2025年3月にガイドラインの改定が行われました。
(3)インバランス料金制度の運用状況の監視等
電力・ガス取引監視等委員会では、インバランス料金の動きを監視し、その動きが合理的でない可能性がある場合には、その原因等を分析しました。また、一般送配電事業者におけるインバランス料金単価の誤算定事案については、再発防止策を着実に実施するよう、指導を行いました。
また、制度設計・監視専門会合において、需給ひっ迫時の補正インバランス料金の上限値に関して議論を行い、2025年度は暫定的な措置として200円/kWhを継続することとし、見直し等については2026年度からの実施を目指して検討を継続することとしました。
(4)託送料金制度に係る制度等の運用・検討
①レベニューキャップ制度の運用
レベニューキャップ制度においては、各事業者が作成した規制期間5年間の事業計画について、着実に実行がなされるよう実施状況をフォローアップしていくことが必要であるため、電力・ガス取引監視等委員会では2023年度の各事業者の取組状況について2024年度の料金制度専門会合で確認(期中評価)を行いました。
あわせて、送配電効率化・計画進捗確認ワーキンググループを開催し、送電、変電、配電の各部門や主要設備ごとの効率化の取組やモデルケースを用いた各工事の費用分析等について議論を行いました。また、送配電ネットワークの形成に関わる関係企業等へのヒアリングも実施しました。
②発電側課金の導入
発電側課金は、託送料金について発電事業者にも一部の負担を求め、公平な費用負担とするため、2024年度より導入されました。その運用においては、発電事業者から小売電気事業者に適切に転嫁が行われ、「相対契約における発電側課金の転嫁に関する指針」の趣旨に沿った契約交渉・情報開示等がなされているかを把握するため、アンケート・ヒアリング調査を当面の間は、年に1回実施することとされました。
各小売電気事業者及び発電事業者に対して行った2024年度の調査において、「小売側が転嫁に応じない」といった事案は確認されず、調査結果を制度設計・監視専門会合に報告しました。
4.電力システム改革の検証
2015年に成立した第3弾の改正電気事業法(電気事業法等の一部を改正する等の法律)の附則においては、事後検証を行う旨の規定が設けられています。2025年3月末までに行うこととされている法的分離後の検証の時期を迎えるに当たり、「総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会」において、2023年12月から2025年3月にかけて全体にわたる検証を行い、2025年3月に検証結果を取りまとめました。
検証を進めるに当たっては、専門的な観点及び実務的な観点を十分に踏まえることが重要であることから、2024年1月から2024年6月まで、電力・ガス基本政策小委員会において、30を超える有識者・実務者からのヒアリングを行いました。
(1)これまでの改革の評価と今後目指すべき方向性
①電力システム改革の目的に照らした現状の検証
2013年4月2日に閣議決定された「電力システムに関する改革方針」では、「安定供給を確保する」「電気料金を最大限抑制する」「需要家の選択肢や事業者の事業機会を拡大する」という3点を電力システム改革の目的として掲げていました。これからの電力システムが目指すべき方向性を検討するに当たり、まず、これらの目的と照らして、現状の電力システムはどのように評価できるかについて検証を行いました。
安定供給を確保する
送配電網の広域運用の司令塔として、2015年に広域機関が創設され、災害等の不測の事態も含めて広域融通を300回以上実施し、連系線の増強も進展するなど、広域的な電力需給・送配電ネットワーク整備については目標を一定程度達成できたと評価できます。一方、供給力については、再エネの導入に伴う火力発電の稼働率・収益性の低下により、電源の休廃止が進展し、2020年以降は断続的に需給ひっ迫を経験しました。今後は電力需要の増加も見込まれますが、事業者による電源の新設・リプレース投資は容易ではない状況であり、安定供給に必要な供給力の維持・確保を進めていくことが必要です。
電気料金を最大限抑制する
2016年の小売全面自由化以降、競争が進む中、小売電気事業者は供給力をより安く調達すべく、卸電力取引所からの調達量を増やす動きが活発化しました。こうした動きは、2022年に国際的な燃料価格の高騰の影響が出るまで家庭向け自由料金を押し下げる方向に働き、自由料金はおおむね経過措置料金よりも安価な水準で推移してきました。一方、火力発電が大宗を占める中、燃料価格高騰時には電気料金が高騰しました。また、小売電気事業者の経営状況の悪化は、需要家との契約解除や事業撤退、託送料金の不払い等につながりました。
需要家の選択肢や事業者の事業機会を拡大する
700を超える事業者が小売電気事業に参入し、再エネに特化したメニュー等、料金メニューも多様化しました。需要家の選択肢の拡大については、目指してきた方向性で取組が進んでいると評価できます。一方、実際には電気の供給を行っていない小売電気事業者が約200者存在するほか、国際的な燃料価格の高騰時には経営悪化による退出等で一定の負担や混乱の引き金となった事業者もおり、需要家保護等の観点から課題があります。
②電力システムを取り巻く経済社会環境の変化
加えて、電力システム改革が行われたこの約10年の間に、電力システムを取り巻く経済社会環境がどのように変化したかも整理されました。国際的なDXやカーボンニュートラルへの対応が加速化し、排出削減と経済成長をともに実現するGXに向けた大規模な投資競争が激化しています。また、AIの進展による計算量の増大に伴い、将来的な電力需要は増加する見込みです。また、地政学的な環境の変化に伴う国際的な燃料価格の高騰等へのリスクが高まりつつあり、海外調達先の多角化、徹底した省エネの推進、エネルギー自給率の向上等の対応が求められています。LNGは長期契約による調達が多いため、2022年の国際的な燃料価格高騰のピーク時にも欧州の天然ガスやアジアのLNGほどの急騰は避けられましたが、LNGスポット価格の上昇の影響等で発電用の一般炭が未曾有の高水準に高騰しました。さらに、世界全体でエネルギー・食糧価格や賃金の上昇を背景としたインフレが進行しており、物価高騰等の電気料金の上昇要因への対応といった課題にも直面しています。
③これからの電力システムが目指すべき方向性
こうした、電力システム改革の目的に照らした現状の検証と、電力システムを取り巻く経済社会環境の変化を踏まえ、これからの電力システムが目指すべき方向性が整理されました(第261-4-1)。
【第261-4-1】これからの電力システムが目指すべき方向性
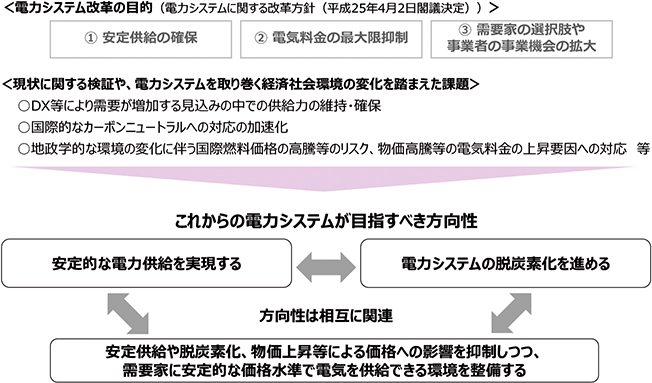
【第261-4-1】これからの電力システムが目指すべき方向性(pptx形式:48KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
(2)電力システムが直面する課題と対応方針
電力・ガス基本政策小委員会におけるヒアリングでいただいた意見等を踏まえ、電力システムが直面する課題と対応方針が、以下の①~③のとおり整理されました。その他、電源・系統への投資に対するファイナンス及び電力システムにおける公的役割を担う機関の体制強化について、共通する課題も整理されました。
①安定供給確保を大前提とした、電源の脱炭素化の推進
世界的な脱炭素化の流れや、20年ぶりの電力需要増が見込まれる中で、安定供給と脱炭素化の両立に向けて、長期的かつ継続的に必要な電源投資が行われ、安定的に電源の運用ができるような仕組みを構築することが必要です。このため、主に以下の事項について検討を進めていきます。
- 事業期間中の市場環境の変化等に伴う収入・費用の変動に対応できるような制度措置や市場環境を整備する。
- 水素・アンモニア、CCUS等を活用した火力の脱炭素化について、技術開発やコストなどを踏まえた時間軸や排出量にも留意しつつ、長期脱炭素電源オークション等を通じ、事業者の予見可能性を確保しながら進める。
- 燃料の安定的確保の見通しや供給力を提供する事業者の実態確認等、発電事業者に求められる機能や役割を整理する。
②電源の効率的な活用に向けた系統整備・立地誘導と柔軟な需給運用の仕組み構築
再エネの更なる導入拡大と電力の安定供給を実現するためには、電源と需要の状況を踏まえた系統の効率的な整備、供給力や調整力の確保、短期の需給運用の効率的な実施等が必要です。このため、主に以下の事項について検討を進めていきます。
- 地域間連系線の整備について、マスタープランの見直し等の検討を進めるとともに、大規模系統整備に係る託送料金制度における費用回収の在り方等、制度的な対応を含めた資金調達環境の整備について検討する。
- 地内基幹系統等について、一般送配電事業者等が効率的・計画的に整備を進めるための仕組みを検討する。
- データセンター等の系統接続申込の規律の確保や、大規模需要の効率的な系統整備の観点での適地への誘導、適地における先行的・計画的な系統整備を進めるための枠組みを検討する。
- 系統制約を考慮しつつ、供給力と調整力を同時に約定させる同時市場の導入に向けた検討を本格的に進める。
③市場を通じた、安定的な価格での需要家への供給に向けた小売事業の環境整備
スポット市場には一定の厚みが確保されましたが、燃料価格の高騰など市場環境が厳しい局面においては、小売電気事業者の退出、電気料金の急激な変動など、需要家に一定の負担や混乱を生じさせ、国民経済に大きな影響を与えました。需要家に対する安定的な水準の価格による電力供給を実現するためには、小売事業の環境整備が必要です。このため、主に以下の事項について検討を進めていきます。
- 電源調達手段をより多様化するため、長期取引を含めた相対取引やブローカー経由の取引等の活用、先物市場・先渡市場・ベースロード市場などの市場を含む取引制度の拡充・再整備等を検討する。
- 需要家の脱炭素化に向けた取組ニーズや発電・小売電気事業者の創意工夫がいかされるよう、内外無差別な卸売の考え方を整理する。
- 現行制度も踏まえつつ、量的な供給能力(kWh)の確保に関し、小売電気事業者に求める責任・役割やその遵守を促す規律、それを前提とした市場や卸取引を含む制度措置の必要性等について検討を深め、必要な措置を実施する。
- 経過措置料金は、解除が妥当な状況と評価された地域はなく、引き続き競争状況の確認を継続する。その上で、経過措置料金の実体的な役割の是非や今後の制度的な対応の必要性、低圧需要家に対するセーフティネットの在り方・必要性等について改めて検討する。
(3)事業者に期待される役割・取組の方向性~将来の電力産業の在り方~
電力システムが目指すべき方向性を実現することは、日本の産業が持続的な発展を実現する上で不可欠です。電力システムが直面する課題の解決に当たって中心的な役割を担うのは、電気事業者、さらには新規参入者を含めた電気事業に関連する電力産業です。持続可能な次世代の電力システムを構築するには、こうした新たなプレイヤーを含む電力産業の一層の活躍が期待されます。このような認識の下、電力システムの担い手である電気事業者・電力産業に期待される役割と責任、これを果たすために必要となる取組について整理されました(第261-4-2)。
【第261-4-2】事業者・電力産業に期待される役割・責任と必要な取組のイメージ
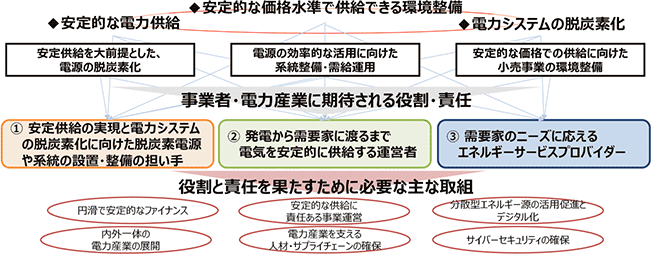
【第261-4-2】事業者・電力産業に期待される役割・責任と必要な取組のイメージ(pptx形式:50KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
(4)検証の結果を踏まえた将来の電力システムを支える取引市場の全体像
電力システム改革では、従来、垂直一貫体制、地域独占、総括原価方式によって実現しようとしてきた「安定的な電力供給」を、事業者や需要家の「選択」や「競争」を通じた創意工夫によって実現することを目指してきました。その中で、供給力の確保など様々な課題に直面しています。このため、今後、「供給力を確保するための取引市場・制度」、「量・価格両面で安定的な調達を可能とする中長期取引市場」、「効率的な広域メリットオーダー実現のための短期取引市場」の3つの取引市場等を整備し、これらを最大限効率的に活用していきます(第261-4-3)。
【第261-4-3】今後整理していく電力システムに関する取引市場等の全体像
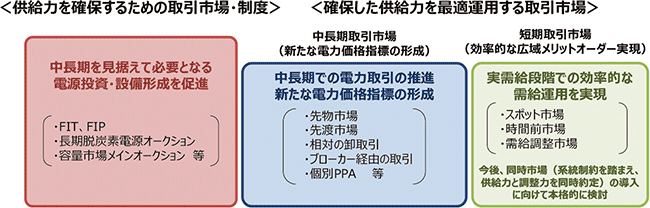
【第261-4-3】今後整理していく電力システムに関する取引市場等の全体像(pptx形式:44KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
電力システム改革の次のフェーズに向けて、こうした取引市場の整備により、事業者の創意工夫を最大限活用しつつ、安定供給の確保・脱炭素化・安定的な水準の価格による電気の供給を実現し、電力システムを進化させていきます。