第3節 カーボンニュートラル実現に向けた次世代エネルギー革新技術の動向
日本がエネルギー安定供給・経済成長・脱炭素を同時に実現することにより、2050年カーボンニュートラル実現を目指していくためには、日本企業が有する次世代エネルギー革新技術について、非連続的なイノベーションに取り組み、ビジネスにつなげていくことが不可欠です。
本節では、光電融合技術、ペロブスカイト太陽電池、浮体式洋上風力発電、次世代型地熱発電、次世代革新炉、水素等を中心に、次世代エネルギー革新技術の動向について、(1)日本の取組と世界における競争力、(2)国内企業の戦略と今後の展望、の2つの観点から確認していきます。
1.光電融合技術
(1)日本の取組と世界における競争力
光電融合技術は、従来の電気信号と比較してエネルギー消費や処理遅延が大幅に小さい光信号を、データ処理や通信に活用する技術です(第123-1-1)。DXの進展や、AI技術の進化・普及に伴い、情報処理を担うデータセンターの電力需要が増大しており、日本全体の電力需要も増加に転じることが見込まれている中、データセンターにおける消費電力の大幅な削減が期待できる光電融合技術は、デジタル化と脱炭素化の両立を支える技術として期待されています。NTTが提唱する「IOWN構想」においても、光電融合技術を活用してネットワークシステム全体の処理を電気通信から光信号に置き換えることで省エネ化(電力消費1/100)・大容量化(125倍)・低遅延化(1/200)を目指すとしており、次世代の通信インフラの中核を担う技術としても注目されています。
【第123-1-1】光電融合技術の開発イメージ
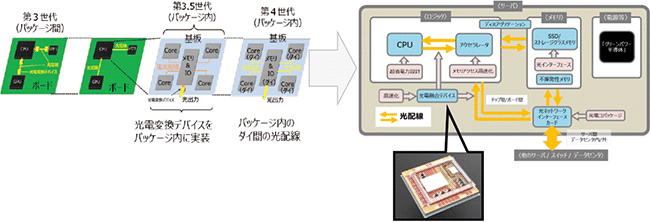
【第123-1-1】光電融合技術の開発イメージ(pptx形式:775KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
近年、米国・中国を中心に光電融合技術の開発競争が激化している中、国内においても、データセンター内のデータ処理や通信に光信号を活用できるようにする「光電融合デバイス」の開発が進められています。例えば、アイオーコア社は2023年、海外製の光電融合デバイスと比較して約1.5倍の最高動作環境温度となる105℃の環境下でも動作する、データセンター内における光配線の導入を可能とする光電融合デバイスの開発に成功し、大手半導体メーカーのインテル、大手ネットワーク機器メーカーのCisco等に対して、高温耐性や長期信頼性の点で優位性を築いています。また、IOWN構想を掲げるNTTは、データセンター内のラック間・ボード間のデータ処理や通信に光信号を活用する技術開発を完了しており、現在は、半導体チップ内の通信に光信号を活用する技術(パッケージ内光配線技術)の開発に取り組んでいます。
(2)国内企業の戦略と今後の展望
光電融合技術の実用化に向けては、低消費電力化を実現する集積回路(ICチップ)の開発、デバイス数の爆発的増加に対応する量産体制の構築等が必要です。
国内では例えば、アイオーコア社は、2030年までに、2023年時点で普及しているデータセンターと比較して40%以上の省エネに貢献する光電融合デバイスの開発を目指しています。また、NTTは、2025年度以降、前述のとおり技術開発が完了したラック間・ボード間の光化を実用化(電力消費1/8~1/13)するとともに、2028年度以降のCPIやメモリといったチップ間接続の光化、2032年度以降のチップ内光化と商用化(電力消費1/100)を目指しており、これに向けてNTTは、光電融合デバイスの試作ラインを2025年度に稼働させ、2029年度頃を目途に光電融合デバイスの量産開始を目指すとしています。
光電融合デバイスの高温耐性、IOWN構想との連携によるネットワークシステム全体への光電融合技術の実装等、日本ならではの強みをいかしながら、世界に先駆けた量産体制を構築することで、早期に市場を獲得することが期待されます。
2.ペロブスカイト太陽電池
(1)日本の取組と世界における競争力
ペロブスカイト太陽電池は、従来のシリコン型太陽電池と比較して、軽量で柔軟といった特長をもつ、日本発の次世代型太陽電池です。日本では、既に太陽光発電を導入できる適地の制約が生じており、従来設置が困難であった耐荷重性の小さい屋根や壁面等にも導入できるペロブスカイト太陽電池には、再エネ導入拡大と地域共生を両立する役割が期待されています(第123-2-1)。
【第123-2-1】ペロブスカイト太陽電池の種類

【第123-2-1】ペロブスカイト太陽電池の種類(pptx形式:887KB)
- 資料:
- フィルム型(積水化学工業提供)、ガラス型(パナソニックHD提供)、タンデム型(カネカ提供)
近年では、特に中国や欧州などを中心に、ペロブスカイト太陽電池の開発競争が激化しており、2024年11月現在、従来のシリコン太陽電池の発電効率(20%程度)を上回る27%程度まで、ペロブスカイト太陽電池の発電効率が向上した例もあります。中国では、多数の企業や大学が自国内の特許取得を進めており、各社で量産化に向けた動きが見られます。また欧州でも、独立系メーカーを中心に開発が進められており、同様に量産化に向けた動きが見られます。
そのような中、日本は特にフィルム型ペロブスカイト太陽電池の開発において、製品化のカギとなる耐久性や大型化等の面で技術的に世界をリードしています。例えば、積水化学工業は、セルを全工程ロール状に製造する「ロールtoロールプロセス」で、耐久性10年相当/30cm幅のフィルム型ペロブスカイト太陽電池を効率的に作製できる工程を確立しています。
(2)国内企業の戦略と今後の展望
このように、フィルム型ペロブスカイト太陽電池は、日本企業に一定の技術的な強みがあり、今後、世界をリードすることが期待される分野です。引き続き、耐久性や大型化、発電効率の向上に向けた技術開発を進めるとともに、世界に引けを取らない規模とスピードで投資を進め、量産技術を構築し、生産体制の拡大を図ることが不可欠です。
例えば、フィルム型ペロブスカイト太陽電池の量産化に向けた取組を進めている積水化学工業は、まず、2025年度までにペロブスカイト太陽電池の製造を開始した上で、2027年中の100MW規模の製造ラインの稼働を目指して、今後、設備投資を行うとしています。さらには、海外展開も視野に、段階的に製造ラインの増強投資を行い、2030年度にはGW級の製造ラインを構築することを目指すとしています。
各国がペロブスカイト太陽電池の量産体制の構築を進める中、日本はまずは、フィルム型ペロブスカイト太陽電池の技術開発を進めるとともに、世界に引けを取らない規模とスピードで量産体制を構築し、製品の差別化を図りながら、国内外の需要を先んじて獲得していくことが重要です。
3.浮体式洋上風力
(1)日本の取組と世界における競争力
浮体式洋上風力は、風車を海底に固定するのではなく、洋上の浮体構造物に設置する発電方法です。着床式は水深が約50m未満の海域に適している一方、浮体式は水深が約50m以上の海域に適しており、水深の深い沖合でも導入が可能なため、今後の洋上風力の導入拡大に欠かせない技術です(第123-3-1)。
【第123-3-1】浮体式洋上風力の形式と要素技術
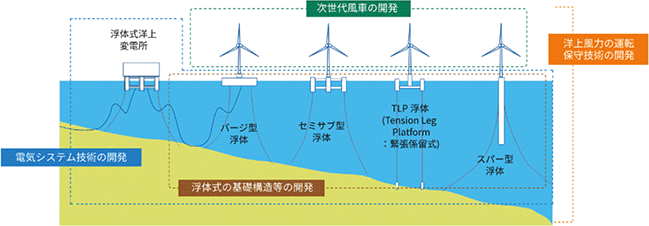
【第123-3-1】浮体式洋上風力の形式と要素技術(pptx形式:115KB)
- 資料:
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構提供
浮体式洋上風力は、欧州を中心としてバージ型、セミサブ型、TLP型、スパー型それぞれについて、10MW以下の風車数基~10基程度の規模によるプロジェクトが進展しており、現在はとりわけ、耐候性に優れており、設置場所に柔軟性がある等の理由から、セミサブ型が多く開発されています。例えば、セミサブ型は、英国・ポーランドでプロジェクトが進展しており、水深100m程度の海域で2011年から実証が始まり、2022年には9.5MW級の風車5基から構成されるプロジェクトが稼働しました。また、スパー型は、英国・ノルウェーでプロジェクトが進展しており、水深100~300m程度の海域で2009年から実証が始まり、2023年には8.6MW級の風車11基から構成されるプロジェクトが稼働しました。TLP型についても、近年フランスにおいてプロジェクトが進められています。
日本においても、経済産業省の委託事業として2011年度から、丸紅、三菱重工業、東京大学等が組成した「福島洋上風力コンソーシアム」により、浮体式洋上ウィンドファームの実証研究事業が福島県の沖合において実施されました。この事業では、現在多く開発されているセミサブ型を当時世界で初めて複数基採用するともに、2025年3月時点でもなお世界で導入実績のない浮体式洋上変電所を設置しました。欧州と異なり遠浅の海域が少なく、台風等の気象条件を有する日本に適合した設備の構築をはじめ、港湾等のインフラ整備や事業を支えるサプライチェーンの形成など、この実証を通じて浮体式洋上風力を日本で進めるための課題を整理してきました。
(2)国内企業の戦略と今後の展望
今後、国内企業の競争力を強化し、浮体式洋上風力を低コストに普及拡大していくためには、要素技術を統合した早期の技術確立に加え、グローバル展開を視野に、欧州等の諸機関との連携を通じて、風車・浮体一体システムの最適設計手法の開発や量産化技術の確立、さらには規格の策定・標準化といった共通基盤の開発に取り組んでいく必要があります。
そのため、グリーンイノベーション基金事業において、早期の技術確立や低コスト開発に向け、10MW超の大型風車を用いた浮体式洋上風力発電の実証を進めています。さらに、発電事業者による協調体制である浮体式洋上風力技術研究組合(FLOWRA)において共通基盤開発を進めています。欧州等との連携では、2025年3月に、FLOWRAと英国の研究機関との間で協力覚書が締結されました。
また、日本が強みを有する造船技術等を活用することで、浮体基礎の量産化等が見込まれます。具体的には、大島造船所や日鉄エンジニアリングが浮体基礎について、ナロックが係留ロープについて、それぞれ量産化に向けた設備投資を進めているとともに、世界でも数社しか製造していない係留チェーンのメーカーが日本に存在するなど、浮体式洋上風力の製造において世界をリードしていくことが期待されます。
こうした産業の強みもいかしつつ、世界に引けを取らないスピードで技術開発を進め、グローバルに需要を獲得していく必要があります。
4.次世代型地熱発電
(1)日本の取組と世界における競争力
次世代型地熱発電と称される技術には、「クローズドループ方式」「超臨界地熱発電」などがあります。「クローズドループ方式」は、地下の高温の地層に人工的にループを掘削・設置し、内部に水等を流し込み、発生した蒸気でタービンを回して発電する地熱発電の方法です。高温の地層があれば発電できるため、従来技術では開発が困難だった場所での電源開発を可能にする技術として注目されています。
また「超臨界地熱発電」は、地下深部(3~6km以上)の超高温・高圧の地熱流体を利用することで、従来よりも高出力での地熱発電が可能となり、また、発電効率の向上も期待される技術です(第123-4-1)。
【第123-4-1】次世代型地熱発電(クローズドループ・超臨界地熱発電)
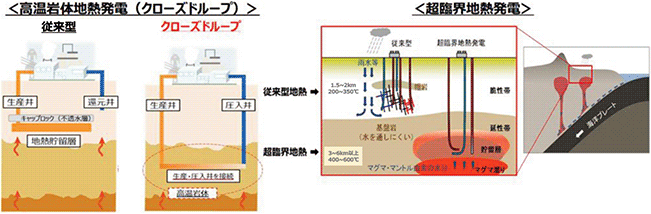
【第123-4-1】次世代型地熱発電(クローズドループ・超臨界地熱発電)(pptx形式:415KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
「クローズドループ方式」は、カナダのスタートアップEavor社が技術開発と商用化において世界をリードしており、カナダにおいて実証施設「エバーライト(Eavor Lite)」を2019年から稼働させています。また現在は、ドイツのミュンヘン郊外ゲレツリードにおいて世界初の商用のクローズドループ発電施設(出力約8.2MW)の建設を進めており、2025年頃の商用運転開始を目指しています。そのような状況の中、国内企業では中部電力・鹿島などがEavor社に出資し、地熱発電事業に関する知見やクローズドループ技術の取得に取り組んでいます。
また、「超臨界地熱発電」は、日本を含め、世界各国で技術開発が進められている段階です。日本では、NEDOが2020年までに実施した調査により超臨界地熱資源が存在する可能性が高いエリアを選定しており、2021年度以降、超臨界地熱資源の存在が期待される国内4地点(岩手県2地点、秋田県1地点、大分県1地点)において、シミュレーションにより資源量評価を行うとともに、超臨界地熱発電の事業化に必要な研究開発・技術開発・事業モデルなどについて、調査を実施しています。
(2)国内企業の戦略と今後の展望
「クローズドループ方式」については、前述のとおり、現時点ではその技術開発で先行する国外企業との連携によって、ノウハウを蓄積する段階にありますが、並行して日本国内でも「クローズドループ方式」の実証実験を積み重ねていく必要があります。現在、国内では三井物産が米国の石油大手シェブロンと連携し、2023年から北海道のニセコ地域で実証実験を行っています。
また、「超臨界地熱発電」については、2050年頃の商用発電の実現に向けて、NEDOがこれまで実施した調査の結果を踏まえ、調査井の掘削や実証実験に引き続き取り組んでいくとしています。
次世代型地熱発電については、国外でも実証事例や商用化事例が少ない今だからこそ、海外の先行企業とも連携しながら実証プロジェクトを加速化し、世界に先駆けた商用化のノウハウを確立することで、日本の地熱発電のポテンシャルの最大限活用を図っていくことが重要です。
5.次世代革新炉(革新軽水炉・小型軽水炉(SMR)・高速炉・高温ガス炉・フュージョンエネルギー)
(1)日本の取組と世界における競争力
次世代革新炉は、安全性向上はもとより、脱炭素の電力供給に留まらず、廃棄物の減容化・有害度低減、カーボンフリーな水素・熱供給など、炉型ごとに特長を有しており、実用化に向けた取組を進めています(第123-5-1)。
【第123-5-1】次世代革新炉
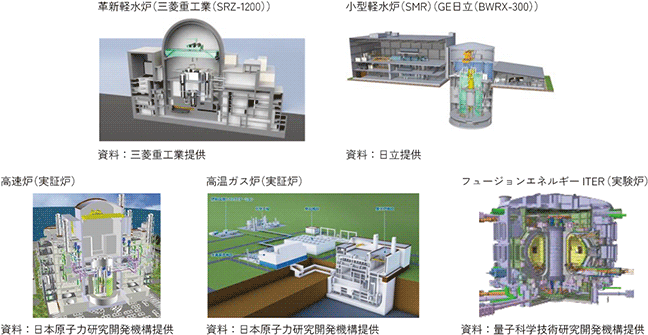
【第123-5-1】次世代革新炉(pptx形式:1,213KB)
革新軽水炉については、設計段階から新たな安全メカニズムを組み込むことにより、万が一の事故があった場合にも放射性物質の放出を回避・抑制するための機能を強化することで、より安全なものとなるよう実用化に向けた開発を進めています。大型鍛造品や蒸気発生器・タービンなど海外市場で一定の競争力を有するサプライヤが国内に存在しており、サプライチェーンの競争力を更に高めるため、技術開発を促進しています。
小型軽水炉(SMR)は、小出力をいかした自然循環により、冷却ポンプや外部電源なしで炉心冷却を可能とするシステムを目指しています。米国やカナダ等の国外では、データセンターをはじめとする電力多消費設備への脱炭素・安定電源としてのニーズが高まっています。海外の実機プロジェクトへの日本企業の参画も進んでおり、相手国に不足するサプライチェーンを補い、重要部品の製造面での事業展開が期待されます。
高速炉は、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減や資源の有効利用等に資する核燃料サイクルの効果をより高めることが期待されるとともに、安全性が高い設計が可能です。日本は、実験炉「常陽」、原型炉「もんじゅ」の建設・運転経験を通じて培われた技術・ノウハウといった強みをいかし、国際連携も活用しながら、国内でも実証炉開発に取り組んでいます。
高温ガス炉については、高温熱をいかした準国産のカーボンフリーの水素や熱の供給により、製鉄や化学などの素材産業の脱炭素化への貢献が期待されています。高温工学試験研究炉(HTTR)では、カーボンフリーの水素製造に活用し得る950℃の高温熱の生成を世界で初めて達成するとともに、2024年3月には、原子炉出力100%の運転中に原子炉を冷却できない状況を引き起こしても、自然に原子炉出力が低下し、安定な状態を維持することを確認する実証試験にも世界で初めて成功しました。
元素同士を結合させて膨大なエネルギーを生み出すフュージョンエネルギーは、高レベル放射性廃棄物を排出しないというメリットがありますが、核融合反応の連続化や、投入したエネルギー量を超えるエネルギーの回収など、その実現に向けて解決すべき課題は数多くあります。フュージョンエネルギーの早期実現に向けて、国際約束に基づいて、核融合実験炉の建設・運転を行う国際熱核融合実験炉(ITER)計画において、日本は高い技術が必要な超伝導コイルや加熱機器などの機器製作を担当しています。また、ITER計画と並行して日本と欧州が共同で実施するJT-60SA計画においては、日本はトカマク型超伝導プラズマ実験装置JT-60SAを建設する優れた技術力を有しています。海外では、米国の核融合スタートアップ企業を中心に2030年前後での核融合実用化を掲げ、多様な炉型(トカマク型、レーザー型、ヘリカル型等)の技術開発が進められています。
(2)国内企業の戦略と今後の展望
革新軽水炉については、更なる安全性向上を目的に、革新軽水炉に組み込まれる新たな安全メカニズム等と規制基準との関係性の整理に向けて、事業者が規制当局と積極的な意見交換等を行っており、共通理解の醸成を図っています。引き続き、地震・津波対策の向上、シビアアクシデント対策設備の多重化等による信頼性向上、事故時の更なる信頼性向上等、新しい安全対策に係る技術開発を促進し、実用化を加速していきます。
小型軽水炉(SMR)については、日本のIHIと日揮は、米国ペンシルバニア州やオハイオ州のデータセンターへの電力源として、最速で2029年頃の運転開始を目指して小型軽水炉(SMR)の開発を手掛けているNuScale社と連携し、モジュール工法の技術実証などに取り組んでいます。また、2025年5月、カナダのオンタリオ州営電力会社(OPG社)の所有者であるオンタリオ州政府が、BWRX-300の初号機プロジェクトとなる、オンタリオ州ダーリントンサイトのOPG社の建設プロジェクト(1号機)に対して、建設開始を承認しました。日本の日立GEは主要機器を提供予定であり、最速で2030年末までの運転開始を目指しています。日本における将来ニーズを念頭に置いた選択肢を確保する観点から、日本の技術をいかした日本企業の海外プロジェクトへの参画や研究開発を引き続き支援していきます。
高速炉については、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(JAEA)、原子力事業者及び中核企業の技術者が集結する研究開発統合組織の統括の下、安全設計方針の在り方や必要な技術開発、基本設計段階以降を見据えた事業運営体制の構築など、中長期を見据えた課題への対応を産学官で進めていきます。
高温ガス炉については、これまで積み上げられてきた高温ガス炉の研究開発の成果を基礎として、HTTRを活用した水素製造試験に向け、規制審査プロセスに進むとともに、英国との国際連携も活用し、産業界との幅広い連携により、実証炉開発を産学官で進めていきます。
フュージョンエネルギーについては、2023年4月に策定された「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」(2023年4月14日統合イノベーション戦略推進会議決定)において、発電実証時期をできるだけ早く明確化するとともに、研究開発の加速により原型炉を早期に実現すること等が示されています。今後、当該戦略を踏まえ、早期実現と産業化を目指し、ITER、トカマク型超伝導プラズマ実験装置JT-60SA等で培った技術や人材を最大限活用し、技術成熟度を高めるべく、スタートアップを含めた官民の研究開発力強化に取り組んでいきます。
6.水素等(水素・アンモニア・合成燃料・合成メタン)
(1)日本の取組と世界における競争力
水素は、アンモニアや合成燃料、合成メタンの基盤となる材料であり、これら水素等は幅広い分野(鉄鋼・化学・モビリティ分野・産業熱・発電など)のカーボンニュートラル化に寄与する次世代燃料として期待されています。水素は、水などの身近な化合物から製造できるメリットがあります。一方、アンモニアや合成燃料、合成メタンは、輸送や貯蔵インフラなどに従来の設備を活用できるメリットがあります。
近年、ロシアによるウクライナ侵攻などによるエネルギー構造変化の影響を受け、水素社会の実現に向けた動きが世界的に加速しています。こうした中、各国ではカーボンニュートラルを見据え、水素等の活用拡大に向けた取組が、「製造」「輸送・貯蔵」「利用」それぞれの段階で進められています。
「製造」については、水電解装置の大規模化の点で欧米が世界に先行しており、各地でMW規模の水電解装置の大規模化に向けた実証や、大規模な水電解装置の商用化が進められています。日本は、膜・触媒など、水電解装置に用いられる要素部材の強みを武器に、効率、耐熱性・耐圧性、コスト等の面で優位性があり、海外企業に多く採用されています。
「輸送・貯蔵」「利用」については、日本が、海上輸送技術と燃焼技術で世界をリードしています。水素の海上輸送技術については、2022年2月、川崎重工業が建造した世界初の液化水素運搬船(すいそふろんてぃあ)を用いて、豪州から日本に水素(約75トン)を海上輸送することに成功しました。燃焼技術については、2023年に三菱重工業が世界初の水素10%(熱量ベース)の混合燃料を用いた大型ガスタービンの発電実証に成功し、2024年には川崎重工業が、世界初の5MW以上の大型ガスエンジンにおいて水素だけを燃料として安定した燃焼を実現する技術を開発しました。また、アンモニア発電技術については、2024年にJERAとIHIが、大型の商用石炭火力発電所(100万kW)では世界初となる、アンモニア20%(熱量ベース)の混合燃料を用いた発電の実証に成功しました(第123-6-1)。
【第123-6-1】海上輸送技術と水素・アンモニア発電技術
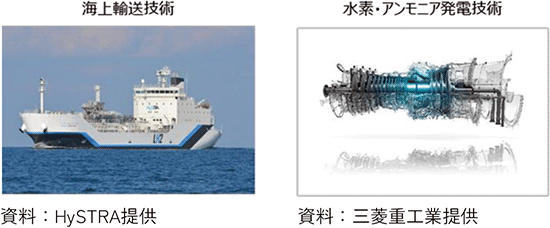
【第123-6-1】海上輸送技術と水素・アンモニア発電技術(pptx形式:323KB)
(2)国内企業の戦略と今後の展望
2050年を見据えて、中長期的に水素等の利活用を拡大していくためには、「製造」「輸送・貯蔵」「利用」の各段階において、革新的技術の開発を進めて競争力を磨くとともに、世界の市場拡大も見据え、供給コスト低減と需要拡大に寄与する大規模サプライチェーンを確立するために先行的な設備投資を進めていくことが不可欠です。
「製造」については、例えば、旭化成とカナデビアが、水電解システムの大型化・モジュール化の技術開発に取り組んでおり、今後、工場熱需要の脱炭素化やアンモニアなどの基礎化学品の製造過程において、本技術によって製造された水素の利活用実証を行い、2030年頃の商用化を目指しています。
「輸送・貯蔵」については、例えば、川崎重工業は、上記の実証実験に成功した小型の液化水素運搬船の約32倍の液化水素を運搬できる中型の液化水素運搬船を今後建造し、2030年代に複数の液化水素サプライチェーンを立ち上げ、世界の液化水素市場に参入することを目指しています。
「利用」については、水素等への大規模な需要を国内で創出するため、水素・アンモニアを発電で利用するための技術開発が先行して進められています。例えば、水素については、三菱重工業は、大型ガスタービンに水素だけを燃焼させて発電するための燃焼器の開発を進めており、2025年度の開発完了を目指しています。アンモニアについては、IHIと三菱重工業がアンモニアだけを燃焼させて発電するための専焼ガスタービンの開発を進めており、IHIは、2026年度を目途にアンモニア専焼ガスタービンの商用運転を開始した上で、2030年までに一般の火力発電の出力に匹敵する数万~数十万kW級の専焼技術を開発する方針を掲げています。あわせて、三菱重工業やIHIは、インドネシアやシンガポール、タイ、マレーシアの火力発電において水素やアンモニアの混焼発電を行うための実現可能性調査(FS)を開始するなど、既存の火力発電の脱炭素化を志向する東南アジア諸国への参入も進めています。
また、水素等は、製造プロセスに必要な高温の熱源としても期待されています。水素還元製鉄などの製造プロセスの大規模転換や、水素バーナー・ボイラー等の技術開発・実証を引き続き進めていくことが重要です。
前述のとおり、日本は水素製造や輸送技術、燃焼技術など複数分野における技術で世界を先導しています。引き続き、日本が強みを有する分野を中心に技術開発を進めるとともに、そうした技術をいち早く商用化し、水素等の需要の拡大が見込まれる国内外の市場に早期参入することで、他国に先駆けて各国の水素等の市場における優位性を築くことが期待されます。
7.その他の技術
これまで確認してきた技術以外にも、エネルギー技術として、様々な技術が着目されています。例えば、メタンハイドレート等の国内資源開発は、地政学リスクや為替の影響に左右されずに安定的なエネルギー供給の確保に資するものであり、民間企業が事業化する際に必要となる技術、制度等を確立するための技術開発等を推進していきます。また、太陽熱、地中熱、雪氷熱、温泉熱、海水熱、河川熱、下水熱等の自然由来の再生可能エネルギー熱は、地域性の高い重要なエネルギー源です。経済性や地域の特性に応じて取組を進め、再生可能エネルギー熱の導入拡大を図ることが重要です。また、波力・潮力等の海洋エネルギーをはじめとする革新的な技術について、低コスト化・高効率化や多様な用途の開拓に資する研究開発を推進していきます。
加えて、蓄電池やコージェネ等の分散型エネルギーリソースを活用したDR(ディマンドリスポンス)、大気から直接CO2を分離・回収するCDR5などの技術についても、イノベーションに取り組んでいくことが重要です。
- 5
- CDRとは、Carbon Dioxide Removalの略称であり、大気中のCO2を除去する技術や手法を指します。