第2節 DX・GXを踏まえたエネルギー・産業政策
1.DX・GXを踏まえたエネルギー・産業政策の重要性(電力と通信の連携を通じたデータセンター等の国内立地加速)
2025年2月に閣議決定された「GX2040ビジョン」では、DXや電化等のGXの進展による電力需要の増加が見込まれる等、将来の見通しに対する不確実性が高まる中、エネルギー安定供給・経済成長・脱炭素の同時実現に向けてGX投資の予見可能性を高めるため、エネルギー・GX産業立地・GX産業構造・GX市場創造について総合的に検討が進められ、より長期的なGXの取組の方向性が示されました。
GX産業立地については、脱炭素電源等の活用を見据えて、クリーンエネルギーを活用する産業の集積を加速する方針が示されており、エネルギー・GX産業立地政策を通して目指す姿として、脱炭素電力等のクリーンエネルギーの供給拠点には一般的に地域偏在性があることから、「エネルギー供給に合わせた需要の集積」という大胆な発想が必要である旨が示されています。GX産業への転換が求められるこのタイミングで、脱炭素電源などのクリーンエネルギーが豊富な地域に企業の投資を呼び込み、新たな産業集積を構築すべく、効率的・効果的にスピード感をもって「新たな産業用地の整備」と「脱炭素電源の整備」を進めるとともに、こうした動きを地方創生と経済成長につなげていくことを目指していきます。
「GX2040ビジョン」では、産業構造の高度化に不可欠なAIにも活用されるデータセンターの国内立地を加速するため、効率的な電力・通信インフラの整備を通じた電力と通信の効率的な連携を進めていく「ワット・ビット連携」が打ち出されました。本節では、こうした議論の背景や、「ワット・ビット連携」の今後の検討の方向性を確認していきます。
2.データセンターや脱炭素電源の立地状況等
(1)データセンターの立地の現状
AIを活用した再エネ需給の最適化技術、CO2削減効果の高い効率的な新素材開発など、AI活用を通じたDXの加速は、成長と脱炭素の同時実現を目指すGXの効果を最大化させる可能性があります。データセンターはこうしたデジタル技術を最大限活用する上で重要であり、データセンターの国内整備が必要不可欠です。
データセンターの立地に際しては、データの需要地からの距離や、電力・通信ネットワークの充実等が重視されています。国内におけるデータセンターの立地状況を見ると、2023年時点で日本全国のデータセンターの約90%(面積換算)が、大規模需要地に近い東京圏と大阪圏に集中しています。当面はこうした傾向が続くと想定されますが、大規模災害時等にもデジタルインフラを維持していく観点や、土地や産業用水、そして系統運用に余裕がある地域のインフラを有効に活用していく観点から、地域分散を進めていくことが重要です(第122-2-1)。
【第122-2-1】データセンターの立地状況
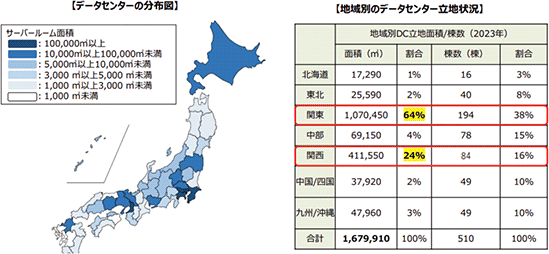
【第122-2-1】データセンターの立地状況(pptx形式:190KB)
- 資料:
- 「デジタルインフラ(DC等)整備に関する有識者会合(第7回事務局説明資料)」
(2)脱炭素電源の立地状況
前述のとおり(第1部第2章第1節参照)、DXやGXなどの進展に伴い電力需要が増加に転じると見込まれており、データセンターや半導体工場を中心に、脱炭素電源を求める動きが今後ますます増えていくと想定されることから、脱炭素電源の供給力の確保が重要となっています。しかし、日本で再エネや原子力などの脱炭素電源比率が4割を超える地域は、北海道、九州、関西エリアとなっており、脱炭素電源の供給は地域ごとに偏在性があります(第122-2-2)。
【第122-2-2】脱炭素電源の立地状況・規模
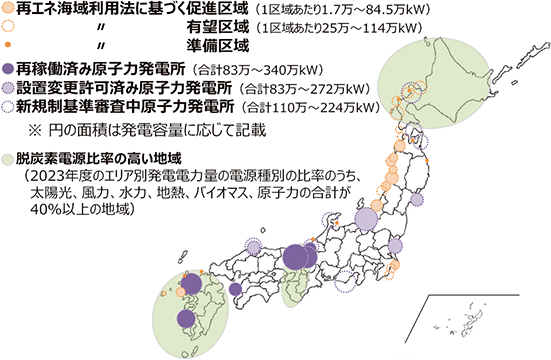
【第122-2-2】脱炭素電源の立地状況・規模(pptx形式:254KB)
- 資料:
- GX実行会議第11回「我が国のグリーントランスフォーメーションの加速に向けて」を基に経済産業省作成
DXやGXなどを進展させていくに当たって、十分な脱炭素電源の供給を求める需要側と、地域ごとに偏在性がある脱炭素電源の供給側との間に、今後ギャップが生じるおそれがあります。
(3)データセンターと脱炭素電源の整備のリードタイム
こうした局地的な脱炭素電源に対する大規模な需要と脱炭素電源の立地場所とのギャップに対応するためには、まずは、データセンターや半導体工場などの稼働に必要となる脱炭素電源を整備し、供給量の拡大を図ることが重要です。
しかし、一般に、電源の方がデータセンターよりも建設のリードタイムが長くなる傾向があります。例えば、IEAのレポートによると、データセンターの建設期間は1~2年程度の一方、脱炭素電源の建設期間は1~15年程度必要になります(第122-2-3)。
【第122-2-3】データセンターと脱炭素電源の建設期間

【第122-2-3】データセンターと脱炭素電源の建設期間(pptx形式:41KB)
- 資料:
- IEA「Energy and AI」(2025)より経済産業省作成
とりわけ、DXやGXなどの取組を今後進展させていくタイミングでは、脱炭素電源への需要の規模や需要が顕在化するタイミングに不確実性が伴うことから、脱炭素電源の需要と供給にギャップがより生まれやすい状況です。このため、産業競争力強化を目指し、需給一体型で計画的に脱炭素電源の利用や整備を進めていく観点が重要となります。
(4)データセンターの立地と電力インフラの整合的な整備促進
前述のとおり、日本においてデータセンターは一部のエリアに局地的に立地する傾向があるため、立地に際して、変電所の新増設を含めた大規模な系統整備が必要になる場合があります。このため、系統運用に余裕がある変電所の近接地点にデータセンターの立地を誘導することや、データセンターの立地適地において系統整備を先行的・計画的に進めていくことが必要です。
まずは足下では、新規需要に応じて脱炭素電力を迅速に供給していくため、新たな大規模送電線の建設が不要であり、一般送配電事業者が早期に電力供給を開始できる場所を示した「ウェルカムゾーンマップ」の全国展開などの取組を通じて、地方を含めて、送配電設備の整備状況を踏まえた適地にデータセンターの立地を促していくことが重要です。ただし、「ウェルカムゾーンマップ」を活用した情報開示の取組においては、供給側の情報提供が限定的であるといった課題もあります。また、データセンター等の大規模な需要については、各種検討・工事が長期化し、系統接続までに時間を要するといった課題もあります。これらの課題に対して、中長期的には、効率的に系統整備を行う観点から適切な場所にデータセンターの立地を集約するための仕組みや、当該立地地域における先行的・計画的な系統整備の枠組みも重要になります。
海外を見ると、データセンターによる膨大なエネルギーの使用が国の気候目標や電力網に与える影響を考慮し、データセンターの建設に対する監視や規制を行う事例が生まれています。データセンター需要が伸びているアイルランドでは、公益事業規制委員会(CRU)が、大都市圏での新規データセンター設置に規制を課すことが決定されています。アイルランドの他にも、ドイツ、シンガポール、中国、米国、オランダの一部都市などでデータセンターの新設に関する規制がなされるなど、電力に関する問題がDX・GXの産業拡大の障壁となっています。
十分な脱炭素電源が確保できなかったが故に、国内においてデータセンターや半導体工場などの投資機会が失われ、日本の経済成長や産業競争力強化の機会が失われないようにしていく必要があります。
3.効率的なデータセンターの整備促進
こうした課題に対応し、産業構造の高度化に不可欠なAIにも活用されるデータセンターの国内立地を加速していくためには、脱炭素電源の発電設備や電力系統などの電力インフラの整備、データセンターの立地、通信インフラの整備など、全体最適を考慮して、効率的に電力・通信インフラを整備し、電力と通信を効果的に連携させていくことが必要になります。この構想が、「ワット・ビット連携」です。
前述のとおり、脱炭素電源の立地場所と、大量の脱炭素電源を必要とするデータセンターの立地場所には乖離があります。例えば、東京電力エリアを見ると、データセンターの立地はデータの消費場所である都心などの人口密集地(おおむね、大手町から50km圏内)に集中している一方で、太陽光を中心とする再エネの立地は、データセンターの立地場所の外側への立地が進展しています(第122-3-1)。しかし、電力の需要地と供給地が離れると、送電網などの系統整備に多大なコストや時間が必要になります。
【第122-3-1】東京電力エリアにおけるデータセンターと太陽光の導入状況
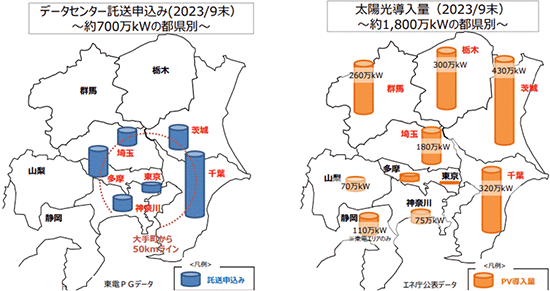
【第122-3-1】東京電力エリアにおけるデータセンターと太陽光の導入状況(pptx形式:267KB)
- 資料:
- 東京電力パワーグリッド「GX・DXの同時達成に向けた電力システムの役割と課題」
「ワット・ビット連携」構想では、足下でデータセンター需要が増えていることも踏まえ、データセンターの立地場所、すなわち脱炭素電源の需要場所に合わせて脱炭素電源の整備や送配電網の増強を進めるのではなく、電力インフラから見て望ましい場所や地域にデータセンターの立地を促進するとともに、光ケーブルを伸ばしてデータの需要地に情報を伝送することで、脱炭素電源とエネルギー需要地の空間的な制約を解消することを目指しています。
このようにデータセンター側の立地を変える理由は、送電線の整備よりも通信を担う光ケーブルを整備する方が、準備期間が短くコストが安価となることに加え、次世代情報通信基盤として2030年代に実装が予定されている「オール光ネットワーク」(APN:All Photonics Network)を活用することで、ネットワークを含めたICTシステム全体の省エネ性能が抜本的に高められるだけでなく、低遅延性により、通信遅延に由来するデータセンターの需要地からの距離制約が緩和されることによります。現在は大都市周辺に集中するデータセンターの更なる分散立地が可能になり、脱炭素電源が豊富で系統運用に余裕がある変電所の近接地点等へのデータセンターの立地誘導を更に推し進めることができるようになります4。
まずは、電力インフラから見て望ましい場所や地域へのデータセンターの立地を促進させ、その際必要となる次世代の通信基盤や国際海底ケーブルを含む通信インフラの整備についても整合性を図ることにより、効率的な電力・通信インフラの整備を通じた電力と通信の効果的な連携(ワット・ビット連携)を進めていきます。
「ワット・ビット連携」を実現するためには、電力系統や通信情報の見える化に加えて、政策的手段や市場メカニズムを活用し、脱炭素電源の近傍など系統面で有利な地域へ次世代産業(データセンター・半導体工場等)の誘致を促進することが必要です。その際、一般送配電事業者と通信事業者の協業が求められるため、官民連携による電力網と通信網の一体整備を推進する必要があります。
4.「ワット・ビット連携官民懇談会」
「ワット・ビット連携」は、2025年2月に閣議決定された「GX2040ビジョン」において構想が打ち出された後、同月20日に開催された「デジタル行財政改革会議(第9回)」において、石破総理から、地方創生2.0の実現に向け、速やかに官民一体で議論する協議会を立ち上げ、今後の取組の方向性を2025年の6月を目途に具体化する旨の指示が出されました。
これを受けて、2025年3月、経済産業省と総務省は、「ワット・ビット連携官民懇談会」を立ち上げ、同月21日、第1回会合を開催しました。「ワット・ビット連携官民懇談会」は、今後のデータセンターの整備を見据え、効率的な電力・通信インフラの整備を通した電力と通信の効果的な連携(ワット・ビット連携)に向けた、官民の関係者における連携・協調の場になります。関係事業者におけるインフラの整備状況・整備計画やデータセンターの立地意向の共有、データセンターの立地に必要な諸条件・課題の整理等、ワット・ビット連携に向けた効果的な方策の検討が行われ、2025年6月の今後の検討の方向性の取りまとめに向けて議論が進められました。
5.脱炭素電力の利活用・確保に関する官民一体の取組
これまで見てきたようなデータセンターを含め、今後脱炭素電力などのクリーンエネルギーを利用した製品・サービスが付加価値を創出する時代になることが予想されます。特に、電子機器をはじめとした製造業における国内外のバリューチェーン下流企業が、自社サプライヤに対してカーボンニュートラル化を求める動きなどもあり、下流顧客の脱炭素化ニーズに対応することが企業価値向上や国際競争力強化につながります。こうした点を踏まえ、送配電設備の整備状況を踏まえた適地への企業の誘導や当該エリアにおける先行的・計画的な系統整備とともに、需要家自らが脱炭素電力を利活用・確保する動きを加速化させるためのインセンティブ措置を検討していきます。
- 4
- 「デジタルインフラ(DC等)整備に関する有識者会合 中間とりまとめ 3.0」(経済産業省・総務省、2024年)においても、低消費電力・大容量・低遅延の通信が可能なAPNの整備に伴い、電力消費の分散化を進め、日本全体での最適立地、エネルギーの地産地消とともに脱炭素の実現にも貢献することが、2030年代の目指すべき姿として描かれています。