第3節 二次エネルギーの動向
1.電力
(1)消費の動向
世界の電力消費は、これまでほぼ一貫して増加してきました。その大きな要因となったのは、途上国を多く抱えるアジア、中東、中南米等の地域でした。特にアジアは、1994年に電力消費で西欧を上回り、2004年以降は北米をも上回るようになりました(第223-1-1)。
【第223-1-1】世界の電力消費量の推移(地域別)
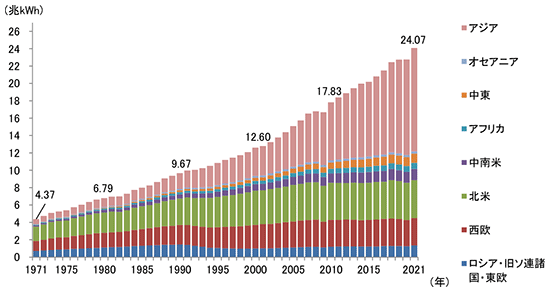
【第223-1-1】世界の電力消費量の推移(地域別)(xls/xlsx形式:36KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023 Edition」を基に作成
一方、アジアや中南米、アフリカ等は、北米や西欧に比べ、1人当たりの電力消費量が低い水準となっています。例えば、2021年時点のアジアの1人当たり電力消費量は、北米の2割強に過ぎませんでした(第223-1-2)。
【第223-1-2】1人当たりの電力消費量(地域別、2021年)
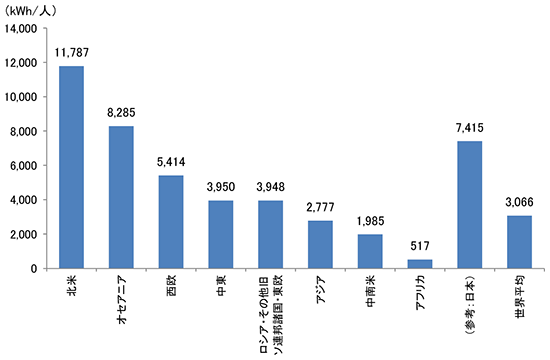
【第223-1-2】1人当たりの電力消費量(地域別、2021年)(xls/xlsx形式:19KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023 Edition」及び世界銀行「World Development Indicators」を基に作成
また、電力化率(最終エネルギー消費全体に占める電力消費の割合)は、世界全体で見ると1980年の11.0%から2021年には20.6%へと上昇しました。世界全体で電化製品等の普及が目覚ましかったこと等が大きな要因です(第223-1-3)。
【第223-1-3】電力化率の推移(地域別)
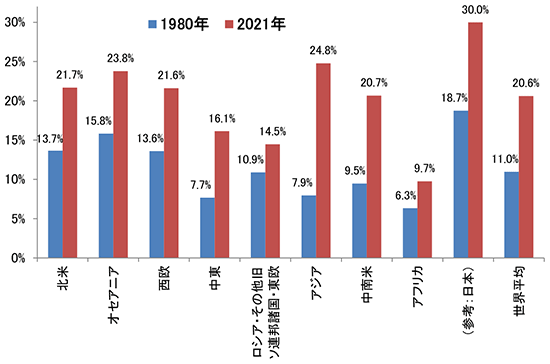
(注)「電力化率」とは最終エネルギー消費全体に占める電力消費の割合を指す。
【第223-1-3】電力化率の推移(地域別)(xls/xlsx形式:22KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023 Edition」を基に作成
世界的に電力化率が上昇している一方、2022年時点で、世界の総人口の約1割、日本の人口の約6倍にもなる7.6億人もの人々が、電力供給を受けていない状況となっています。その多くは、サブサハラアフリカやアジアに存在しています。アジアでは、2000年以降、新たに12億人が電力にアクセスできるようになりました。そのうちの3分の2をインドが占めており、2019年には、人口の99%が電力にアクセスできるようになったとインド政府から発表がありました。一方、サブサハラアフリカにおける未電化人口は、2022年時点で6.0億人であり、世界全体の未電化人口の約8割を占めています。こうした地域では、電力アクセスの実現が大きな政策課題となっており、その実現のためには、電力供給インフラに対する大規模な投資が必要とされています(第223-1-4)。
【第223-1-4】世界の未電化人口(地域別、2022年)
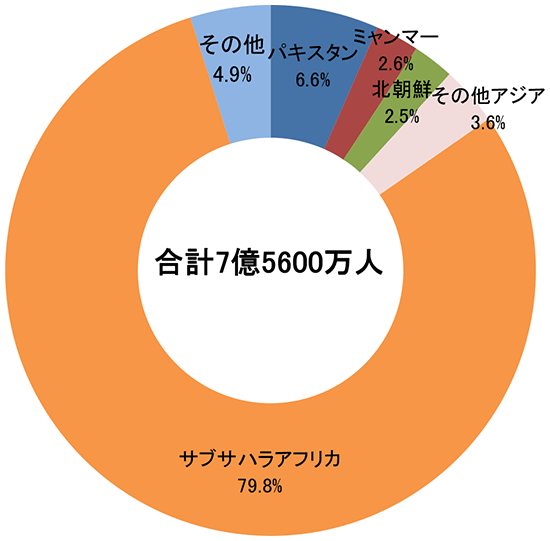
【第223-1-4】世界の未電化人口(地域別、2022年)(xls/xlsx形式:168KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Outlook 2023」を基に作成
(2)供給の動向
世界の発電設備容量は右肩上がりで増加しています。2021年の世界の発電設備容量は、80.1億kWとなりました。これを電源別に見ると、化石エネルギーの割合が55.4%を占めており、主力電源の役割を果たしていることがわかります。次いで再エネが23.0%を占めています。再エネは気候変動対策の高まりを背景に、近年急速に導入が進んでいます。次に大きな割合を占めるのは水力ですが、新規開発が難しくなってきていることから、近年の伸び率は低い水準にあります。原子力は、1970年代の二度のオイルショックを契機に石油代替エネルギーとして開発が促進され、1980年代には高い伸び率を示しましたが、先進国での原子力開発が鈍化した結果、1990年代以降の伸び率は低い水準となっています(第223-1-5)。
【第223-1-5】世界の発電設備容量の推移(電源別)
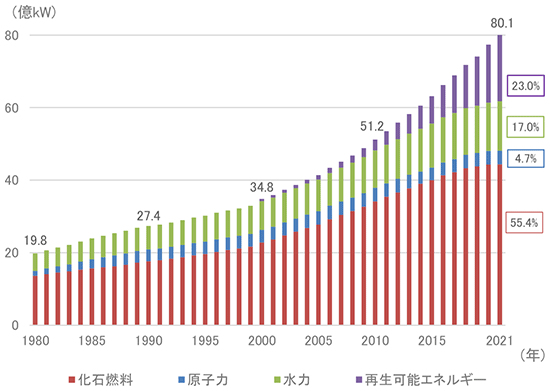
【第223-1-5】世界の発電設備容量の推移(電源別)(xls/xlsx形式:36KB)
- 資料:
- EIA「International Energy Statistics」を基に作成
世界の発電電力量もほぼ一貫して増加しています。2021年の世界の発電電力量は、28.4兆kWhでした。これを電源別に見ると、最も大きな割合を占めているのが火力(石炭火力、石油火力、天然ガス火力)であり、全体の61.7%を占めています。次いで水力、再エネ、原子力が続いています。近年では、政策的な支援を受けた再エネの増加傾向が顕著となっています。
火力による発電電力量を燃料別に見ると、石炭火力は1970年代以降、増加傾向にありましたが、2010年代からは気候変動対策の高まりや再エネの導入拡大もあり、概ね横ばいで推移しています。石油火力は、1970年代には堅調に増加していましたが、オイルショックを契機に石油代替エネルギーへ転換された結果、1980年代以降は減少傾向に転じています。天然ガス火力は、石炭や石油と比べて発電時のCO2の排出が少ないことから、近年に至るまで増加傾向にあります(第223-1-6)。
【第223-1-6】世界の発電電力量の推移(電源別)
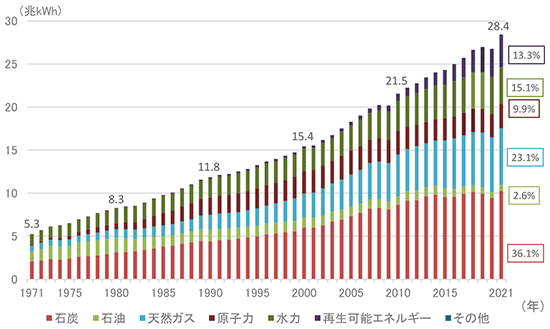
【第223-1-6】世界の発電電力量の推移(電源別)(xls/xlsx形式:45KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023 Edition」を基に作成
次に、2021年における主要国の電源構成を見ていきます。米国は、シェールガス生産の増加に伴い、ガス火力の割合が増加しており、2021年には全体の37.5%を占めました。他方で、石炭火力の割合が減少傾向にあります。英国は、国内に石炭が豊富に存在することから、かつては石炭火力が主力電源の役割を担っていましたが、北海ガス田の開発や電力自由化に伴って、ガス火力の割合が増加した後、政策的なCO2価格の引き上げにより、石炭火力の割合は2.4%まで低下しています。フランスは、東京電力福島第一原子力発電所事故以降、電源の多様化を進める政策を取っており、原子力の割合が、2011年の79.4%から2021年には68.9%まで低下しました。ドイツは、再エネの導入を積極的に進めており、原子力や石炭火力のシェアが低下しています。イタリアは、石炭火力の割合が減少する一方、ガス火力の割合が増加しています。中国は、経済発展とともに発電電力量も著しく増加していますが、石炭火力の割合が非常に高く、気候変動問題への対応が課題となっています。韓国は、石炭火力の割合が34.3%、原子力の割合が26.0%と高くなっています(第223-1-7)。
【第223-1-7】主要国の発電電力量と発電電力量に占める各電源の割合(2021年)
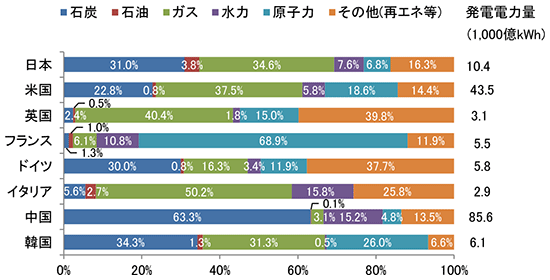
【第223-1-7】主要国の発電電力量と発電電力量に占める各電源の割合(2021年)(xls/xlsx形式:42KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2023 Edition」を基に作成
なお、欧州や北米では、国境を越えて送電線網が整備されており、電力の輸出入が活発に行われています(第223-1-8)。
【第223-1-8】欧州の電力輸出入の状況(2021年のフランスの例)
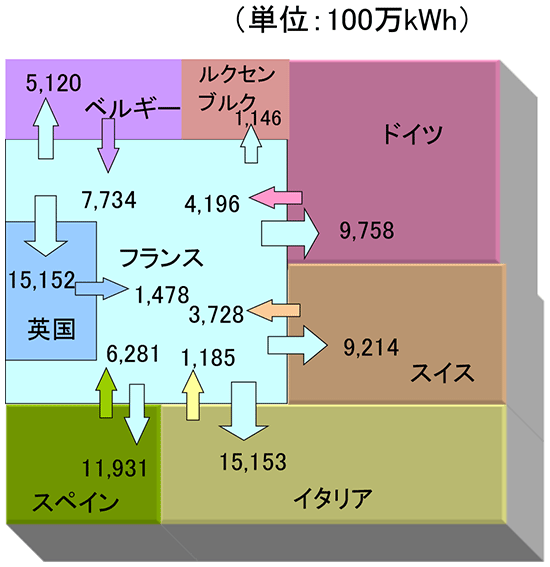
(注1)数値は、物理的な電力量の推移を示したもの。
(注2)電力が他の国を回って元の国に戻ってきた場合や、電力がある国を通過した場合には、輸出量と輸入量の両方でカウントしている。
【第223-1-8】欧州の電力輸出入の状況(2021年のフランスの例)(xls/xlsx形式:22KB)
- 資料:
- IEA「Electricity Information 2023 edition」を基に作成
2.ガス
欧米におけるガス事業の状況を見ると、かつて欧州では、上流のガス生産・輸入から、国内でのガス輸送・配給、販売までを、国営企業が一元的に行うケースが主流でしたが、1980年代からは、英国等において、国営企業の民営化やガス市場の自由化が進められました。その後、1998年の「第一次EUガス指令」、2003年の「第二次EUガス指令」、2009年7月の「第三次エネルギーパッケージ」によって、EU全体でガス市場の自由化が進められ、現在では、小売市場の全面自由化や輸送部門の所有権分離もしくは機能分離が実施されています。米国では、特に1985年以降、連邦規制により州をまたぐパイプラインの第三者利用、ガスの輸送機能・販売機能の分離が進められました。また、州レベルにおいても、家庭用も含めた自由化の拡大及びガス配給会社(LDC)による託送サービスの提供を制度化する州が登場しており、2022年末時点では、計23州において自由化を実施済です。自由化プログラムに参加した需要家数は、有資格者全体の18%となっています28。
2021年における主要国の都市ガスの消費量を比較すると、米国では30,187PJ、ドイツでは3,695PJ、英国では2,897PJ、イタリアは2,834PJで、日本は1,723PJでした。パイプラインについては、米国の輸送パイプラインの総延長が485千km、配給パイプラインの総延長が2,158千kmとなりました。日本では、電気事業者や国産天然ガス事業者等によって整備されている輸送パイプラインの総延長が3千km、一般ガス導管事業者によって整備されている配給パイプラインの総延長が268千kmとなりました(第223-2-1)。
【第223-2-1】世界の都市ガス消費量、パイプライン延長(2021年)
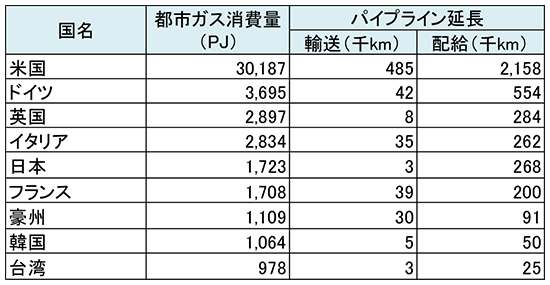
(注)英国の配給パイプラインの延長は2016年のデータ、イタリアの輸送パイプラインの延長は2022年、配給パイプラインの延長は2017年のデータ、豪州のパイプラインの延長は2015年のデータ。
【第223-2-1】世界の都市ガス消費量、パイプライン延長(2021年)(ppt/pptx形式:46KB)
- 資料:
- 日本ガス協会「ガス事業便覧 2023年版」を基に作成
3.熱供給
熱供給は、一般的に「地域冷暖房」とも呼ばれていますが、その始まりは19世紀にまで遡ります。オイルショック以降は、特に欧州において飛躍的に発展しました。熱源として、化石エネルギーだけでなく、再エネや廃棄物、工場排熱等が利用できることに加え、熱電併給29も適用できることから、石油依存度の低減やエネルギー自給率の向上、環境保護といった観点から、有効性が注目されてきました。
熱供給の主たる燃料は国によって様々です。英国では天然ガスが約9割を占めていますが、北欧諸国では再エネや廃棄物の利用割合が比較的高いという特徴があり、例えばスウェーデンでは、熱供給に占めるバイオマスや廃棄物の利用割合が約8割30となっています。
地域単位で空調用の熱をまとめて製造・供給する地域熱供給設備は、広大な寒冷地を抱えており、暖房需要の大きい中国等で大規模に普及しています。他にも、北欧や中東欧、韓国等においても普及が進んでいます。熱を伝えるための導管ネットワークの長さで比較すると、こうした国々の導管ネットワークの長さは、いずれも日本と比べてはるかに大きな値となっていることがわかります(第223-3-1)。
【第223-3-1】世界の地域熱供給の状況(2019年)
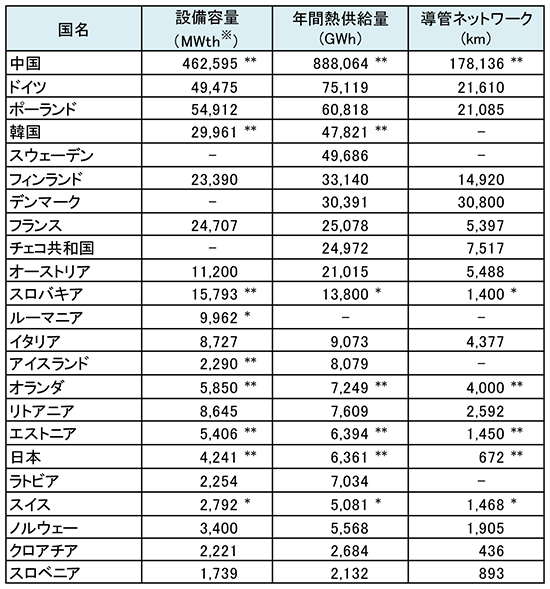
(注1)「MWth」はMega Watts thermalの略で、熱源容量のこと。
(注2)「*」は2015年の値、「**」は2013年の値、「-」はデータなし。
【第223-3-1】世界の地域熱供給の状況(2019年)(ppt/pptx形式:46KB)
- 資料:
- Euroheat & Power「District Heating and Cooling: Country by Country」各年版を基に作成
4.石油製品
世界の石油製品の消費は、1965年から2022年にかけて3倍以上に拡大しました。特に、中国を含むアジアや中東における消費の拡大が顕著となっています。2022年における石油製品の消費の地域別シェアは、中国を含むアジアが36.3%を占めており、次いで北米、欧州が続きました(第223-4-1)。
【第223-4-1】世界の石油製品の消費の推移(地域別)
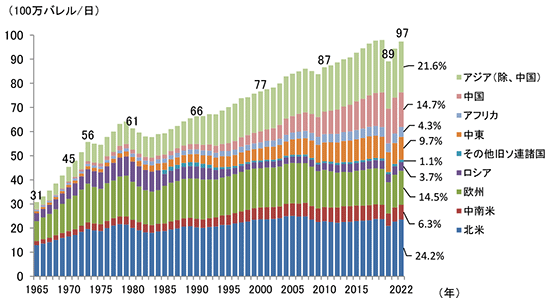
(注)1984年以前の「ロシア」には、その他旧ソビエト連邦諸国を含む。
【第223-4-1】世界の石油製品の消費の推移(地域別)(xls/xlsx形式:40KB)
- 資料:
- Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2023」を基に作成
このデータを製品別に見ると、新型コロナ禍からの経済回復もあり、2022年はいずれの製品についても前年から増加しました。長期的に見ると、ガソリンや灯油、軽油等の軽質油の消費が堅調に増加してきた一方で、重油の消費が低下傾向にありましたが、2021年以降は重油も増加に転じています(第223-4-2)。
【第223-4-2】世界の石油製品の消費の推移(製品別)
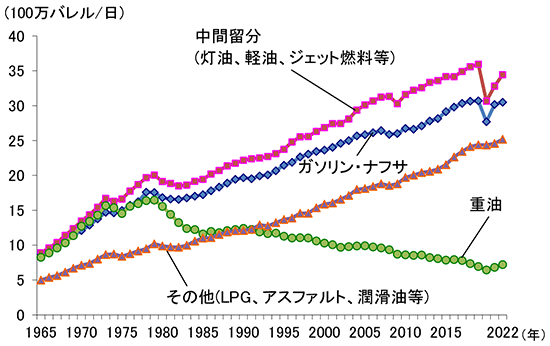
【第223-4-2】世界の石油製品の消費の推移(製品別)(xls/xlsx形式:28KB)
- 資料:
- Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2023」を基に作成