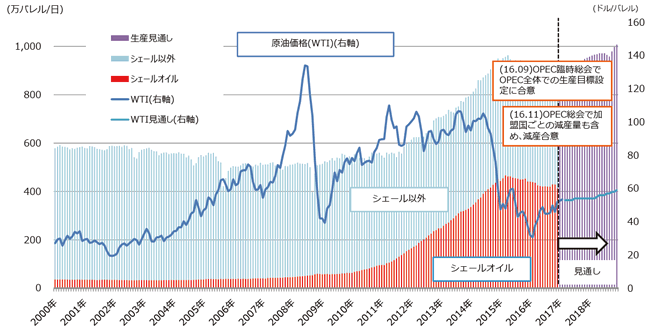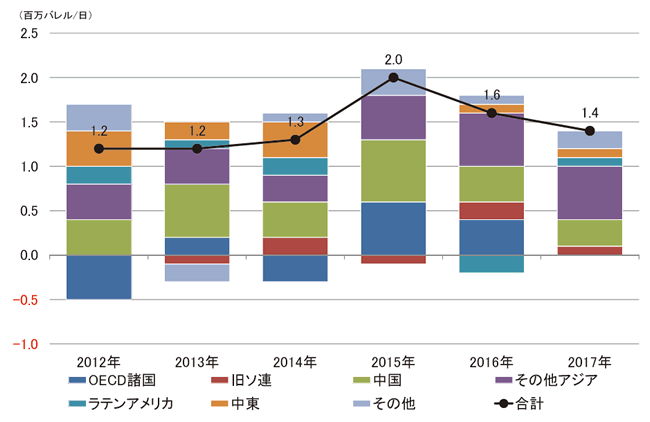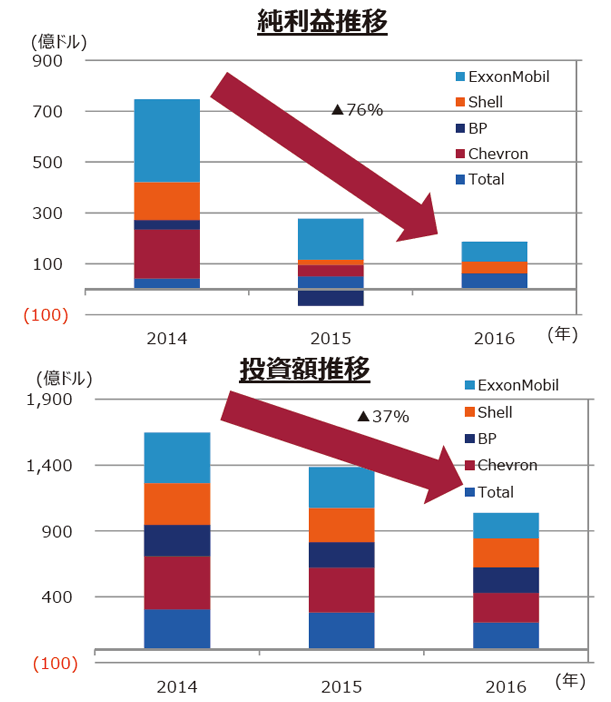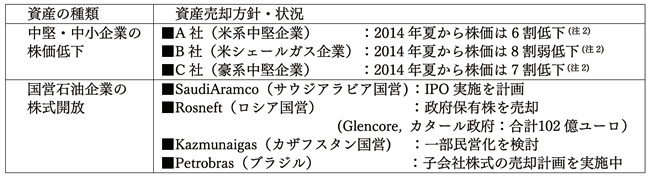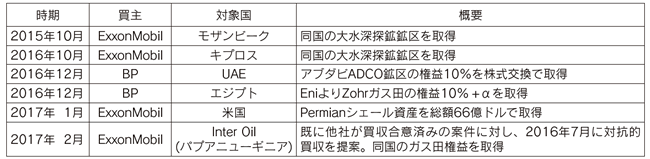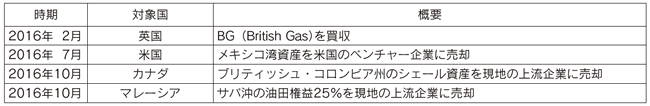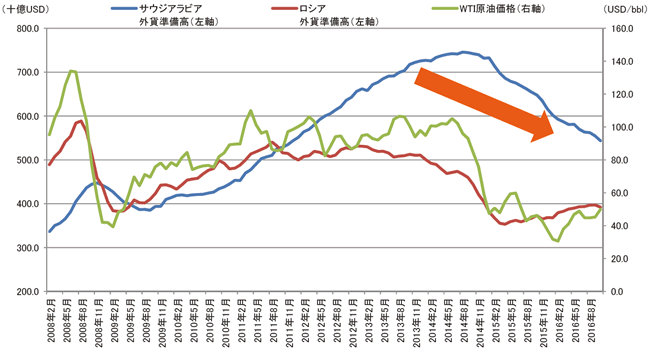第3節 国内外の石油産業の動向
1. オイルメジャーをはじめとした石油産業の動向
(1)石油開発を取り巻く環境変化
国際的な原油価格は、リーマン・ショックの影響により2009年前後に一時的な急落を見せたものの、2004年以降は一貫して上昇基調にありました。しかし、2014年後半以降、原油価格は大幅な下落に転じます。理由は様々あげられますが、中国などの新興国の成長率減速などによる需要の伸び悩み、米国での大幅なシェールオイル増産、石油輸出国機構(OPEC)をはじめとする主要産油国の高水準生産など、全世界的な供給過剰感が背景と言われています。当初はすぐに価格が上昇に転じるとの見方もあったものの、OPECによる減産合意の見送り等もあり、価格は下落を続け、2016年2月には2003年以来の安値水準となる26.21ドル/バレル(WTIベース)まで下落しました。これ以降は、OPEC加盟国を含む産油国による生産調整の動きが表面化し、2016年11月には8年ぶりとなるOPEC加盟国による減産合意、同年12月にはOPEC非加盟国である一部産油国とも協調減産を行うことで合意されました。その後、50ドル/バレル台まで上昇した原油価格ですが、米国におけるシェールオイル生産がなお堅調な動きを見せていることから、市場は再び慎重姿勢を見せており、2017年3月には3か月ぶりに40ドル/バレル台に下落しています。今後の原油価格の見通しについては、依然不透明であるといえます。
こうした原油価格の低迷は、世界中の石油・天然ガス開発企業に大きな打撃を与えました。「スーパーメジャー」と呼ばれる世界を代表する5社(ExxonMobil、Shell、BP、Chevron、Total)の石油・天然ガス開発企業においても、2016年の純利益は2014年比で約76%、投資額は約37%減少しています。中堅・中小企業においても、既存事業における投資を維持することができず、保有資産を放出する動きが見られ、株価を5割以上減少させた企業もあります。国家財政の大半を石油収入に依存する産油国への影響はさらに大きく、国内鉱区を外国資本に開放し、国営石油会社の株式の売却を進める動きなどがみられます。石油開発産業にとって、今回の原油価格低迷は、リーマン・ショックを超える大きな環境の変化に直面した出来事であったといえます。
- 出典:
- Baker Hughes、EIAを基に資源エネルギー庁作成
- 出典:
- IEA「Oil Market Report」を基に資源エネルギー庁作成
- (注)
- 米国会計基準。投資額は上流部門以外を含む。
- 出典:
- 各社決算情報を基に資源エネルギー庁作成
- (注1)
- 米国会計基準。投資額は上流部門以外を含む。
- (注2)
- 2017年3月1日時点で比較。
- 出典:
- 各社決算情報、報道等を基に資源エネルギー庁作成
(2)オイルメジャー等の上流開発投資動向の変化
2000年前後、石油開発産業は今以上の超低油価時代を経験しました。きっかけは、1997年にタイで始まったアジア通貨危機だと言われています。欧米の為替政策によりアジア各国の通貨価格が急落し、アジアだけでなく世界経済全体が停滞しているにもかかわらず、1997年11月のOPEC総会での増産合意により、石油需要の減少と供給過剰から、原油価格は急落しました。1998年の年間平均は、実質価格において18ドル/バレル台と、現在の水準の2分の1から3分の1程度の水準でした。
また、この時期は、市場環境や事業環境においても大きな転換点にありました。米国の代表的な株価指数であるS&P500が1985年から2000年にかけて7倍強に拡大するなど、株式市場が著しく発達しました。成熟産業とみなされていた石油産業は、株主からより強い圧力に晒され、利益率向上のための経営合理化を迫られました。上流事業においては、民間企業が容易にアクセスできる在来型の大油田が成熟し、プロジェクトの巨額化や天然ガスへのエネルギーシフト等が進んだことで、もはや既存のビジネスモデルによる企業規模の拡大が難しくなっていました。
こうした背景から、オイルメジャーは2000年前後に大規模な再編期を迎えることとなります。1998年8月のBP(イギリス)によるアムコ(アメリカ)の合併を皮切りに、エクソン(アメリカ)とモービル(アメリカ)の合併等、2001年まで毎年100億ドル以上の大型再編が続き、かつてない巨大な企業規模の「スーパーメジャー」を誕生させました。こうした企業買収により、オイルメジャーは資金力、技術力、交渉力等の経営基盤を強化し、変わりゆく環境への対応と生き残りを図りました。
2014年以降の低油価は、この2000年前後の超低油価に並ぶ水準で、世界の石油開発産業に打撃を与えています。むしろ、2000年前後の低油価はOPEC加盟国や非OPEC産油国の取組により比較的速やかに回復に向かったのに対し、現在の低油価は、2016年末のOPEC加盟国及び非加盟国による減産合意にもかかわらず、米国シェールオイルの生産拡大が上値を抑え、長期化の様相を呈しています。IEAによれば、世界全体の石油・天然ガス上流開発への投資額は2年連続で縮小しており、オイルメジャーを含む各国石油開発産業の財務状況の悪化が窺えます。
【第133-1-5】スーパーメジャーの変遷
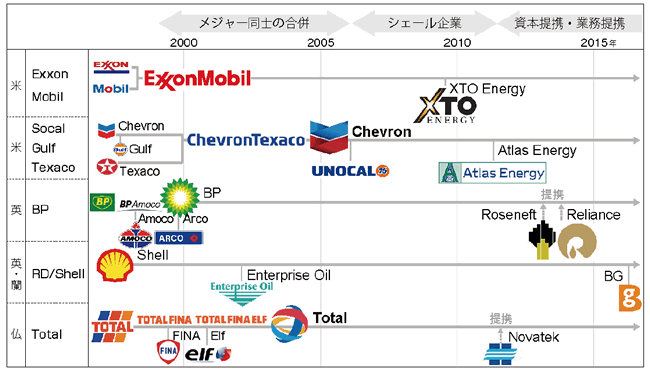
- 出典:
- JOGMECレポート
こうした低油価時においても、オイルメジャーは共通して株主への利益還元を重要視しており、株主配当の継続を約束し、低油価の長期化に備え財務体力を維持する姿勢を明確にしています。その代わり、操業コスト(OPEX)、資本支出(CAPEX)の削減を含む徹底的なコスト削減によって早急に収支の改善を図るとともに、事業の効率化のため、優良資産・不良資産の入替を通じた投資の「選択」と「集中」を図る方針がみてとれます。各社ごとに戦略の差はありますが、主としてLNGプロジェクト、大水深油ガス田開発、経済性が見込める既存事業・既発見未開発資産の買収や、自社のコアエリアでの資本増強の動きが目立ちます。
例えばエクソン・モービル(アメリカ)は、2017年2月にパプアニューギニアのLNG生産者であるインター・オイル社を買収したほか、既にガスの埋蔵が確認されているモザンビーク沖合やキプロス海域の大水深探鉱鉱区の取得も行いました。また、ロイヤル・ダッチ・シェル(イギリス/オランダ)は2016年2月にイギリスのガスメジャーとも称されるBGを買収し、オーストラリアのLNG資産や同社のコアエリアであるブラジルの大水深油田権益を獲得しました。BPにおいては、2016年12月にUAE(アブダビ)の陸上鉱区権益や、エジプトのガス田権益など、同社の既参画エリア周辺のポートフォリオを増強させています。
こうした選択的・戦略的な資産買収・企業買収と併せて、オイルメジャー各社は非戦略に分類される資産の売却を進める意向を示しています。特に、BGと合併したロイヤル・ダッチ・シェルにおいては、最適なポートフォリオバランスを再構築すべく、2016年から2018年の3年間で300億ドル規模の売却を計画しています。すでにカナダのシェール資産を72.5億ドルで、米国メキシコ湾資産を4.25億ドルで売却するといった発表がされたほか、イラクの油田権益やノルウェーの上流資産について売却可能性があるとの報道がなされており、今後他のオイルメジャーによる資産売却も含めて、相当程度の資産放出が見込まれます。
- 出典:
- 各社公表資料等を基に資源エネルギー庁作成
- 出典:
- 各社公表資料等を基に資源エネルギー庁作成
(3) オイルメジャー等の下流投資動向の変化
欧米やオーストラリアといった先進国地域においては、2000年代に入り、石油製品の需要が減少に転じました。これを製品別に見ると、例えば欧州においては、ガソリンの需要が減少している一方で、ディーゼル車の普及により軽油需要が増加の傾向にあるなど、用途別・製品別に需要動向の違いが生じています。このような石油製品の需要動向の変化により、これらの地域においては、従来の精製設備では効率的に供給することができなくなるという需給のミスマッチが顕在化しました。このため、同地域に多くの製油所を保有していたオイルメジャー等の企業は対策を講じる必要に迫られました。
これらの企業は、同地域において石油製品需要が減少している状況を踏まえ、既存の製油所の選択と集中を進め、生産性の高い一部製油所のみに投資を行う一方で、多くの製油所を閉鎖し、供給能力が不足する分については自社が他地域に保有する製油所等からの輸入により補う、という対応を行いました。その結果、イギリスやオーストラリアなどにおいては、メジャーによる製油所の売却・閉鎖が相次ぎ、国内の供給力が需要を下回るようになりました。
【第133-1-8】世界地域別の石油製品需要の見通し(単位:百万バレル/日)
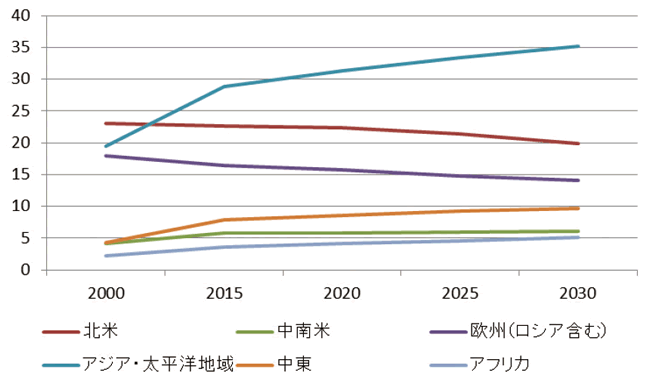
- 出典:
- IEA、World Energy Outlook 2016を基に資源エネルギー庁作成
【第133-1-9】世界の石油製品需要の増減推移と見通し
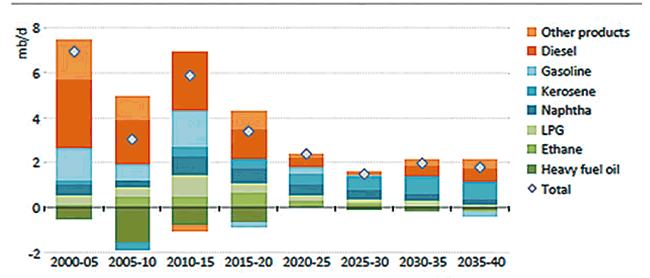
- 出典:
- IEA、World Energy Outlook 2016
このように、オイルメジャーでは、需要減少が見込まれる先進国地域での下流事業、特に石油精製事業を縮小し、今後の経済成長に伴う需要増加が見込まれるアジア地域等へ資本の移転を進め、石油製品のトレーディングを通じて全体の需給バランスを最適化することにより、収益の最大化を追求する対応を進めています。
また、同様に、2007年頃に国内のガソリン需要が頭打ちになったアメリカ市場においては、いわゆるオイルメジャーに属さない石油精製専業企業であるバレロなどが、既存の複数の国内製油所を買収し、その選択と集中を進めるとともに、近隣国等への商圏拡大を図る動きを進めています。バレロは、2000年代半ばまではオイルメジャー等の既存製油所の買収を繰り返すことにより事業規模を拡大してきました。その後、国内ガソリン需要の減少を踏まえ、自社が保有する製油所のうち不採算なものの売却や操業停止を進めるなど、製油所の選択と集中を進める一方で、2011年にシェブロンからイギリスPembroke製油所を取得するなど、北米から欧州、アフリカなどへの事業拡大を進め、大西洋市場全体での需給最適化に取り組んでいます。
こうした先進国地域における企業とは別に、これまで上流分野での国外投資に積極的であった中国の国営石油企業においても、下流分野での国外進出、とりわけ、今後成長が見込まれるミャンマー、カンボジア、シンガポールなどアジア地域における製油所の取得等の投資が進められています。また、シノペックがサウジアラビア等においてサウジアラムコとの合弁による製油所を新設し、ペトロチャイナがイギリスやフランスなどにおいて製油所を取得するなど、アジア地域以外への進出の動きも見られます。こうした動きを通じて、世界規模で最適な石油供給ネットワークを構築しようとする取組が進められています。
(4)国営石油企業の改革
原油価格低迷の影響を受けているのは、中東をはじめとする産油国の国営石油企業においてももちろん例外ではありません。国家の財政収入の大半を石油収入に依存している産油国においては、原油・天然ガス価格の下落は国家財政を直撃しており、国民に対して補助金の撤廃や国内投資の削減等の緊縮策を打ち出しています。また、こういった政策に加え、石油産業からの収入確保に向け、国営石油企業の改革、政府保有株の放出、外国石油企業に対する新規ライセンス付与等の施策が表明されているところです。
- 出典:
- サウディ通貨庁、ロシア中央銀行、EIA等
象徴的であるのが、サウジアラビアの社会・経済改革策「ビジョン2030」であり、その具体策の一つが、世界最大規模を誇るサウジアラビアの国営石油会社サウジ・アラムコの株式上場計画です。2016年5月に、全体あるいは一部を切り出して子会社化し2018年頃を目途に上場すると発表しました。サウジ・アラムコはこれまで国内資源を一元的に操業管理し、外国石油企業との共同事業化を行っておらず、石油・天然ガスの可採埋蔵量・生産量、石油精製量・精製能力・輸出量・販売量等は一部部分的に開示されているものの、具体的な投資規模や財務諸表等については一切公開されていません。具体的な上場方法については明らかにされていませんが、この上場により、外部投資家からの資金調達にとどまらず、一企業としての投資戦略の明確化や事業運営の効率化、さらには、国外の上流事業に進出する可能性等があります。
また、ロシアにおいては、政府が国営企業の民営化プログラムを策定しており、国営石油企業においても政府保有株式が放出されています。2016年12月、国営石油企業であるロスネフチの政府保有株式19.5%が、スイスのトレーディング会社のグレンコアとカタール投資庁に売却された取引は、2016年最大の取引となりました。また、ロスネフチは、インドやインドネシアの国営石油企業に対して油田権益の一部売却を行うなど、積極的に外国資金の獲得を進めていると言えます。
この他、ブラジルの国営石油企業・ペトロブラスは、1999年からすでに外国企業に対し鉱区の開放を行い、大油田の開発を順次進めていたところですが、2014年に汚職問題と油価低迷が重なり、投資計画の抜本的な変更に追い込まれています。また、ペトロブラスは2016年には国内のエネルギー関連企業の株式売却や、小規模油ガス田の売却に着手しており、今後も上流資産の売却が見込まれています。
2. 我が国石油関連市場の環境変化と産業の動向
(1)環境変化概説(国内需要の減少)
我が国においては、戦後の高度経済成長に合わせて石炭から石油へとエネルギー転換が進展し、石油の需要は増加していきました。我が国の石油製品需要は、2度にわたる石油危機の後、1980年代には産業用燃料・原料である重油とナフサを中心に減少したものの、その他の油種は1990年代まで増加を続けてきました。しかし、2000年代に入り、石油製品需要は全体として減少傾向に転じいます。IEAによれば、我が国の石油製品需要は、2000年の5.1百万バレル/日から2015年には3.9百万バレル/日まで減少し、今後2030年までには、さらに2.6百万バレル/日まで減少することが見込まれています。こうした変化の構造的要因としては、主に、①脱石油シフトを目指した産業、民生用の燃料転換の進展、②少子高齢化や人口減少という社会構造の変化、③CO2排出量の少ないエネルギーへの転換や自動車の燃費改善、エネルギー消費効率向上による石油消費量の削減等が挙げられます。
【第133-2-1】国内石油製品需要の動向(単位:百万バレル/日)
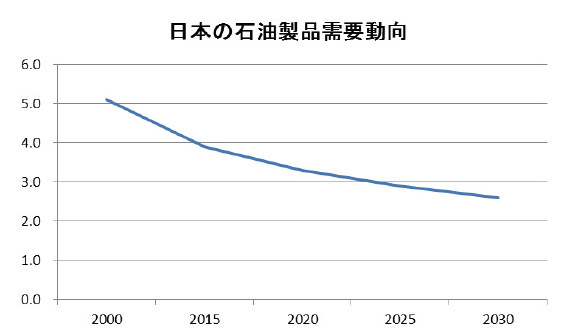
- 出典:
- IEA,World Energy Outlook2016
一方で、中国や東南アジア等のアジア地域においては、将来の経済発展に伴い需要が増加していくことが見込まれています。IEAによれば、中国の国内需要は2015年の11百万バレル/日から2030年には14.3万バレル/日、東南アジア諸国全体の需要は2015年の4.8百万バレル/日から2030年には6百万バレル/日に、それぞれ増加していく見通しです。これらの地域では、石油需要の増加を見据え製油所の新設等が計画されており、供給力が拡大していくことが予想されます。
また、これらの国々では、今後、環境規制の強化が進むことが予想されます。特に、中国においては、既に2017年からガソリンや軽油の硫黄分規制が10ppm以下と、先進国並の規制が導入されております。こうした動きにより、将来的には、先進国と途上国の石油製品の品質差が縮小し、石油製品の国際取引がさらに活発化する可能性があります。
こうした状況に鑑みれば、我が国の石油製品市場も、輸出・輸入の両面でアジア地域内の石油製品の流通の影響を受けることは避けられない状況です。
【第133-2-2】世界の地域別の石油製品取引量(単位:百万バレル/日)
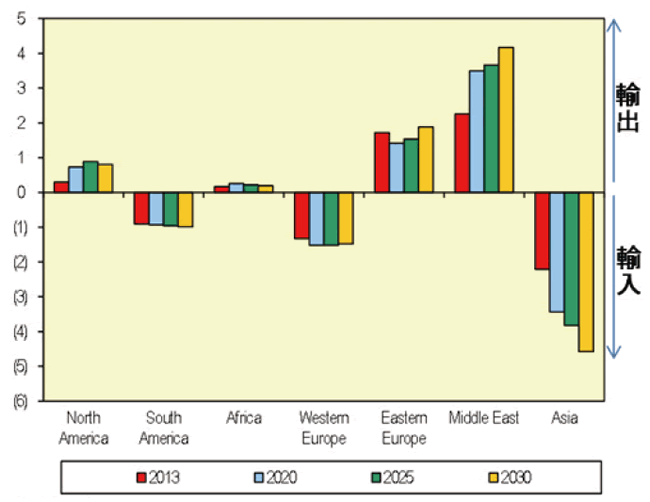
- 出典:
- Nexant資料(2014)
【第133-2-3】アジアにおけるガソリンの硫黄分規制
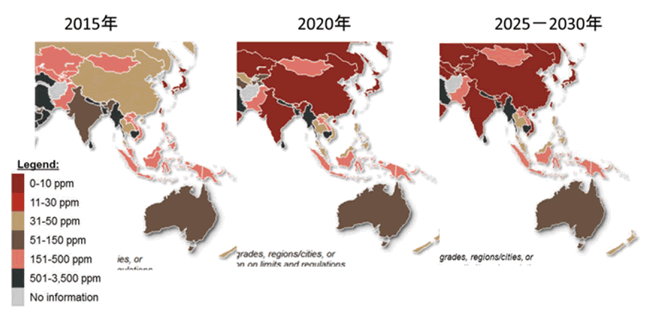
- 出典:
- Nexant資料(2014)
(2)国内石油産業の動向(石油・天然ガス上流開発の体制)
我が国の石油・天然ガス上流開発の体制は、2001年の「特殊法人等整理合理化計画」を受けた石油公団の廃止と石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)の設立によって大きく転換しました。1967年に設立された石油公団は、自主開発を推進するため、国内企業に対する資金面、技術面での支援を行い、石油・天然ガスの安定的な供給に一定の貢献を果たしてきたものの、5,000億円を超える多額の欠損金を計上し、解散を余儀なくされました。その理由の一つとして挙げられるのが、政府、石油公団、石油・天然ガス開発企業のそれぞれが、主体性に欠け、責任の所在が必ずしも明確でなかった点です。政府及び石油公団は、量的確保を最大の目標に掲げるあまり、資金面や企業による事業の進め方に関する効率性という視点を欠いていました。また、開発企業は、政策案件への協力との名目の下、事業資金の多くを公的制度に依存するなど、事業遂行における主体性を欠いていました。この結果、我が国では、自らが様々な権益を保有して自立した経営を行う資源開発企業ではなく、油ガス田ごとにその事業のみを行う小規模のプロジェクト企業が乱立し、国際競争力を有する自立的な企業体が育ちにくい環境にあったといえます。
これらの反省を踏まえ、2004年に設立したJOGMECによるリスクマネー供給支援においては、「民間主導の原則」の下、融資は行わず出資に限った上で、支援割合については5割を上限とすることとされました。また、新たな石油・天然ガス開発体制の中心として、欧米のオイルメジャーに伍する「中核的企業」を形成することが必要であるとされました。石油公団の解散に当たり、中核的企業として位置づけられた国際石油開発は、石油公団が保有するUAE(アブダビ)等の優良資産等を承継し、その規模の拡大を図ったほか、2006年には帝国石油を子会社化して国際石油開発帝石ホールディングスを設立、2008年には帝国石油を吸収合併し、現在の国際石油開発帝石(INPEX)が設立されました。
このように、2000年前後の欧米オイルメジャーの大規模な企業合併・買収から少し遅れる形で、我が国でも中核的企業の形成という目的の下、一定の企業規模の拡大を図ってきました。しかしながら、我が国では未だに中核的企業と呼びうる企業は現れていません。国際的に活躍する世界の石油・天然ガス開発企業の生産規模は、概ね日量100万バレルを超えていますが、我が国においては、最も生産規模の大きい石油・天然ガス開発企業である国際石油開発帝石においても、2015年度の生産量は日量51.4万バレルに留まっています。欧米のオイルメジャーに伍する中核的企業となるためには、まずはメジャー級といえる生産規模の拡大が不可欠です。
2014年以降の原油価格の低迷は、世界の石油・天然ガス開発企業の経営に甚大な影響を与えました。一方で、欧米のオイルメジャーにとっては自社の経営戦略の見直しの契機となり、将来の開発事業に向けたポートフォリオの再構築という観点から、資金不足の産油国や中堅・中小企業が放出する保有資産を対象として、企業買収・資産買収の動きを加速化させています。我が国の石油・天然ガス開発企業にとっても、企業買収・資産買収等を通じて、企業規模を拡大させる絶好の機会であるともいえます。
我が国では、2016年11月、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(JOGMEC法)を改正し、企業買収・資本提携を行う我が国の石油・天然ガス開発企業に対しても出資等による支援を行えるように制度を拡充させました。新たに拡充した支援制度を活用し、我が国企業においても、欧米オイルメジャーと同様に、戦略的かつ効率的なポートフォリオを構築すべく、企業買収・資産買収等の取組を加速化させ、石油公団解散以降の目標である、中核的企業の形成に、官民で連携して本格的に取り組んでいくべきであると考えられます。
【第133-2-4】日本の石油・天然ガス開発企業の変遷
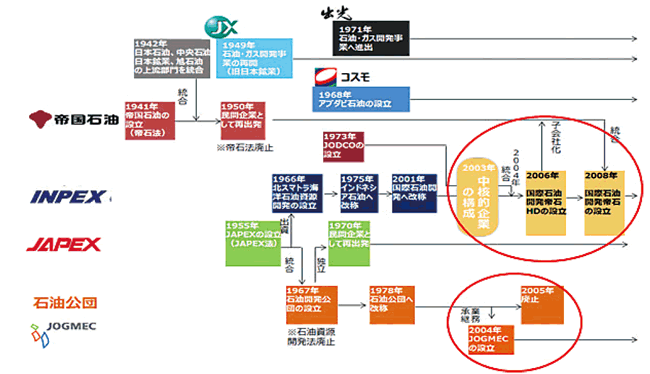
- 出典:
- 各種資料を基に資源エネルギー庁作成
(3)国内石油精製事業の今後の見通し
我が国の石油精製・元売企業は、1990年代に石油業法の廃止等の規制緩和が進められ、国内市場の自由化が進展したことに伴い、国内市場における激しい価格競争に直面してきました。さらに、2000年代に入ってからは、国内の石油製品需要の減少が進むなど厳しい経営環境が続いています。こうした状況を乗り越えるため、国内の石油精製・元売企業では、製油所の統廃合や物流の合理化など、既存事業の選択と集中による事業再編が進められてきました。2015年には、出光興産・昭和シェル石油、JXグループ・東燃ゼネラル石油が相次いで経営統合を発表し、2017年4月には、JXグループと東燃ゼネラル石油の統合会社であるJXTGグループが誕生するなど、企業統合も含めた国内需給最適化の取組が進められています。
今後も国内需要がさらに減少することや、国際市場における石油製品取引の活発化等により、石油産業間の国際競争が激化することが見込まれる中で、国内の石油精製・元売企業が将来にわたりエネルギー安定供給の担い手としての役割を果たしていくためには、持続的な成長を志向し、安定的な経営基盤を確保していくことが必要です。とりわけ、これらの企業は、国内の石油製品市場に売上や利益の大半を依存しているため、縮小する国内市場における過当競争状態からの脱却、拡大する市場へのポートフォリオの変更を進めていく必要があります。
このため、国内の石油精製・元売企業では、事業再編による既存事業の合理化や石油化学との連携等を通じた国内製油所の国際競争力強化といった取組の他、国外市場や他のエネルギーへの事業展開といった取組が進められています。
国内石油精製・元売企業による国外への進出の代表例としては、出光興産がベトナムにおいて、三井化学株式会社やクウェート国際石油、現地の国営石油会社であるペトロベトナムと共同で製油所建設が進められています。同製油所では2017年中にも、商用運転が開始される予定です。また、精製事業以外でも、JXエネルギーやコスモ石油が韓国において現地企業と連携した石油化学事業を、東燃ゼネラル石油が豪州において石油製品ターミナルを取得・運営し石油製品の卸売事業を、それぞれ進めているなど、各社において成長する国外市場に商圏を拡大する取組が進められています。
【第133-2-5】石油業界俯瞰図
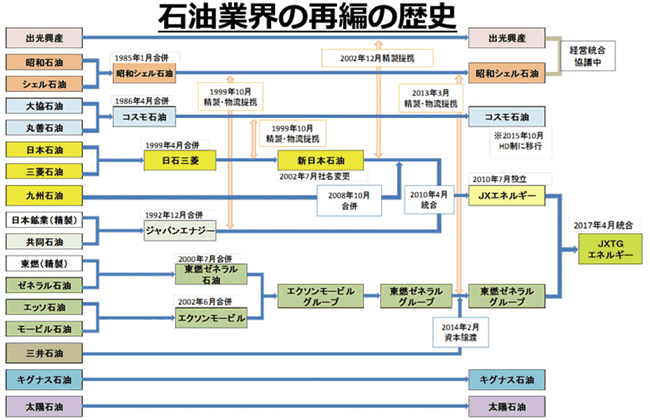
- 出典:
- 石油連盟作成
先述のとおり、オイルメジャーや中国などの国外企業においても、アジア市場への積極的な進出がなされている中、国内の石油精製・元売企業がその競争に参加していくためには、国内の企業再編による統合効果が見込まれる数年の間に、市場獲得に向けた取組を加速化することが期待されます。