まとめ
これまで紹介してきた事例からもわかるように、自由化や環境適合への要請などの制度的な変化に先行して直面した欧米の企業は、こうした変化に対して、日進月歩で進化する技術を迅速に取り込みながら、海外展開や異分野への進出、新サービスの創出など、各社の戦略にあわせて、大きく事業の姿を変えてきています。
我が国に今後生じるであろう変化は、過去に欧米で起きたものと同じものであるとは限りませんが、どんな変化であったとしても、その変化に対して、できるだけ的確に、そして迅速に、事業の形を変えていくことが必要になっていくと考えられます。政府としての取組は、第1部第2章や第3部において御紹介しているとおりですが、我が国のエネルギー事業者が、世界規模での事業環境の変化の中にあっても、高い競争力を維持・強化させながら、我が国のエネルギーの3E+Sが実現できるよう、官民が一体となった取組が求められると考えています。
C O L U M N
NEDOによるハワイ州マウイ島での系統電力安定化のためのデマンドサイドマネジメントの実証
太陽光発電システムや蓄電池のコスト低減と、その普及の進展が好循環を生み出し、再生可能エネルギーの導入・普及が世界的に加速しています。その結果、太陽光発電システムの普及に対するインセンティブを見直したり、取りやめたりする地域が出てきたりしている一方、こうした再生可能エネルギーのさらなる普及を実現するための政策や需要家のニーズの高まりを受けて、新しいエネルギーシステムへの転換を推し進める動きがあります。
新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)では、国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業の一環として、2009年より、スマートコミュニティに関する実証事業を海外で行うことを通じ、こうした海外の動きに触れ、日本の技術やシステムで、その課題に挑む取組を進めて来ました。ここでは、その中でも、積極的な再生可能エネルギーの導入が進む米国ハワイ州マウイ島で取り組むプロジェクトについて紹介します。
1. マウイ島のエネルギー事情と課題
マウイ島を含むハワイ州では、エネルギー源の多くを化石燃料に依存し、エネルギーコストが高く、米本土と比べ約2.5倍程高い電気料金を住民が負担してきました。そのため、ハワイ州では、2045年までに電力需要の100%を再生可能エネルギーで賄う目標を掲げて、ハワイ州の抱えるエネルギー問題に取り組んでいます。マウイ島では、ピーク需要が約19万kWに対して、 既に風力発電7万2千kW、太陽光発電 約9万3千kWが稼働し、2016年12月時点で発電量に占める割合は約36.9%に達しています。
化石燃料からの脱却やエネルギーコスト低減に向けた取り組みを行う一方で、再生可能エネルギー大量導入に伴い、2015年後期頃から再生可能エネルギーの出力抑制が日常的に行われるとともに、島全体の電力系統の安定化(周波数維持)や、配電網の安定化(電圧維持、系統設備の保護)などが課題となっています。とりわけ、太陽光発電の影響は大きく、昼間の電力システム側の供給量がへこみ、朝夕の急速な変化が大きくなり、世界各国でその対策が検討され始めているダックカーブ問題が既に発生しています。
マウイ島におけるダックカーブ問題(注)
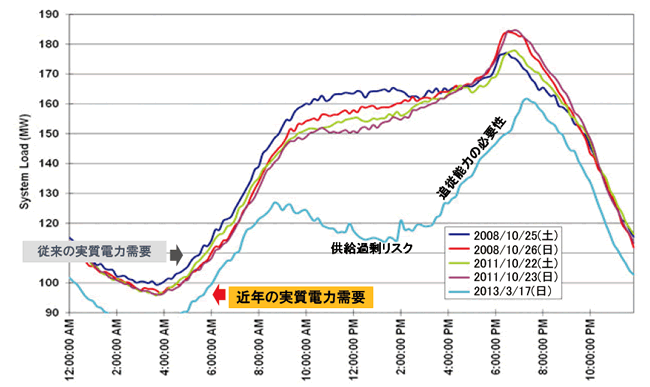
- (注)
- 夕方4時ごろから7時頃にかけて、電力需要は増加するが、太陽光発電の発電量は減少するため、火力の出力の急激な増加が必要となる。この需要曲線がアヒルの背中の形状に似ていることから、ダックカーブと呼ばれている。
- 出典:
- マウイ電力
2. プロジェクトの概要
上記のような課題解決に対し、日本の技術・システムにより貢献するため、NEDOは、ハワイ州及びマウイ郡との協定の下、現地の電力会社や大学などと協力し、日立製作所、みずほ銀行、サイバーディフェンス研究所を実施者として選定の上で、JUMPSmartmauiプロジェクトと称して、2011年11月から2017年2月までプロジェクトを実施しました。マウイ島では、従来の内燃機関の自動車に比べて、走行に必要な経費が少なくて済む電気自動車(以下「EVという。」)の普及が進んでいます(EV:約800台、シェア約0.5%/ 2017年2月時点)。そこで、EVの蓄電機能を活用し、ディマンドレスポンス(以下「DR」という。)やヴァーチャルパワープラント(以下「VPP」という。)を始めとする、再生可能エネルギーの大量導入に伴う電力システムの安定化に貢献する取組を行うことにしました。
JUMPSmartmauiプロジェクトの全体像
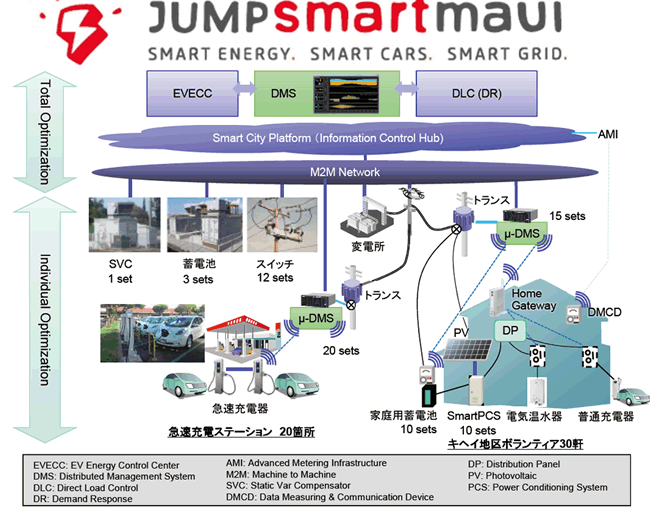
- 出典:
- NEDO
プロジェクトには、200世帯以上のEV利用者が参加し、各家庭にはEV充電器を設置しています。また、キヘイ地区の一部の家庭には、EV充電器および給湯器を遠隔遮断することができる機器(Home Gateway)、太陽光発電の出力を制御する機器(SmartPCS)、家庭用蓄電池も設置しています。
電力系統側には、これら需要家の機器を低圧変圧器単位で制御できる機器(μDMS)や系統蓄電池等の設備を設置しています。これらのフィールド機器はそれ自体が自律制御運転を行うことができます。さらにこれらフィールド機器を統合的に制御する装置として、電力会社のコントロール室に統合DMS(Integrated Distribution Management System)を設置し、電力会社が運転する全島レベルでの電力需給バランスを制御するエネルギーマネジメントシステムと連携して運転しています。
3.主な成果
(1)再生可能エネルギーの最大限の利用
EV利用者の協力を得て、当プロジェクトのシステムを用いて、EV充電開始時刻を遠隔で集中制御を行い、EV充電の時間帯を、電力ピーク時間帯と重なる夜7~8時頃から、夜10~11時頃にシフトすることが出来ました。夜間を中心に行われている風力発電の出力抑制を将来的に減らすことができると期待されています。
EV充電開始時刻の制御結果
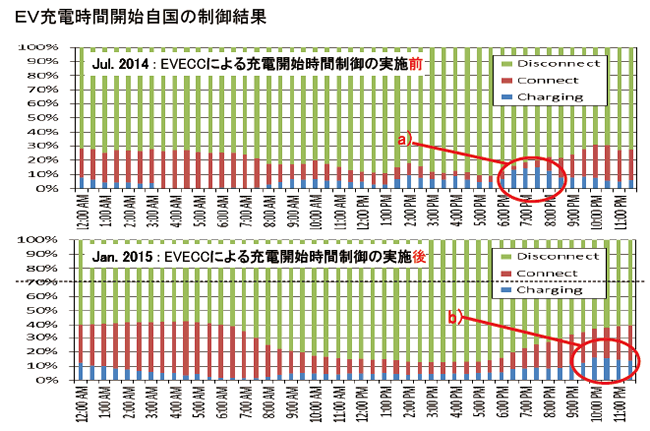
- 出典:
- NEDO
a)普通充電器が充電開始されるピーク時刻は午後7~8時で、一般の需要とピークが重なっていた(職場等、外出先からの帰宅後にプラグを接続して充電開始するユーザが多い)。
b)EVECC(EV Energy Control Center)の制御によって、プラグが接続されてから充電が開始されるまでの時間を、夜10~11時頃にシフト(深夜時間は、風力発電量が増加するため、風力発電の余剰電力を吸収することに寄与)することが可能となった。
(2)島全体の系統安定化(周波数維持)
キヘイ地区の一部世帯の協力を得て、宅内に設置したHome Gatewayを用いて電力消費の大きい各家庭内のEV充電器、給湯器の負荷については、一時的に電力供給を遮断しても支障がないため、一時的な直接負荷制御(Direct Load Control)を行う実験を実施しました。島全体の系統が予測に反して不安定になった場合に、できるだけ需要家の生活の利便性を損うことなく、DRの一環としてこの仕組みを発動することにより、その安定化に貢献できる可能性を確認できました。
(3)配電系統の安定化(電圧維持、系統設備の保護)
キヘイ地区の一部世帯の協力を得て、各家庭内に設置したSmartPCSを電力会社のコントロール室から制御し、逆潮流が引き起こす配電線の電圧上昇を回避できることを確認しました。また、低圧変圧器に設置したμDMSとSmartPCSを連携させ、系統設備の過負荷時に、SmartPCSに出力抑制指令を行って系統設備の保護を図る仕組みの可能性を確認できました。
(4)ダックカーブ問題の改善(昼間需要の創出とピークカット)
一部のEV利用者には、充放電対応のEV充電器を設置し、VPP(Virtual Power Plant)システムを構築、職場などで昼間太陽光発電の発電量が多い時にEV充電し、帰宅後の電力ピーク時にはEVから放電する実験を行い、将来的に島全体のダックカーブ問題の解決に貢献する可能性を確認できました。
下図に示すように、電力ピーク前後の夜6~9時頃は、赤線で示されている実証前(2016年9月平均の手動による充電)と比べて、濃い青棒で示されている実証後のEVの充電(2016年10月~ 2017年1月平均のシステム制御による充電)が抑制され、さらにオレンジ色で示されているようにEVからの放電(2016年~2017年1月平均のシステム制御による放電)が行われています。これにより、夕方に急激な電力需要が立ち上がるダックカーブ問題の緩和に貢献できることを示しています。
また、この実験では、充放電対応のEV充電器を主に住宅地に設置したため、風力発電の余剰が生じている深夜12~6時頃に、充電時間帯をシフトする制御を行い、この時間帯に出力抑制が行われている風力発電を有効に活用できる可能性を確認(赤線と濃い青棒の差分)していますが、今後、EV利用者が日中EVを駐車する職場などにEV充電器の設置が進めば、太陽光発電の発電量が多い時にEV充電の時間帯をシフトすることも可能です。
EVを活用したダックカーブ問題への対策(EV80台による充電/放電実績)
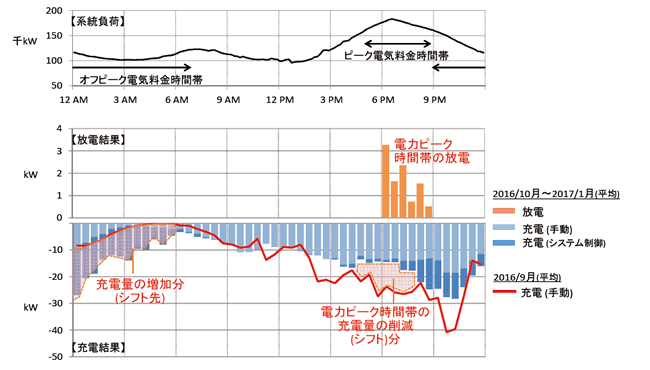
- 出典:
- NEDO
3. 今後の展望
風力発電や太陽光発電のような、天候に左右されやすい再生可能エネルギーの割合を増やすと、その調整のために火力発電の効率が落ちたり、増設する必要が発生して、かえって化石燃料の使用量が増えたりする事例報告がありますが、ハワイ州では、調整力としてのDRを現地電力会社が既に調達しているなど、先駆的な取り組みを始めています。しかしながら、その多くは、大口需要家の協力に依るものです。今後、さらに再生可能エネルギーの割合を増やしていくためには、小口需要家の協力も必要になると考えており、JUMPSmartmauiプロジェクトは、その実現可能性を示すことが出来ました。
JUMPSmartmauiプロジェクトでは、小口需要家の協力を得るために、現地の関係機関の多大な努力がありました。マウイ郡長自ら、JUMPSmartmauiプロジェクトの意義、重要性を市民に周知するとともに、学校教育の現場でも、理解促進が図られ、その結果として、EVを利用して、プログラムに参加することが、島の営み全体に良い貢献ができるという意識が根付きました。
こうしたコミュニティレベルでの意識高揚の重要性と並んで重要なのが、需要家の選択肢の幅を広げることです。JUMPSmartmauiプロジェクトに限らず、太陽光発電システム、家庭用蓄電システム、EVなどのシステムの統合化の動きが活発化しています。しかしながら、それぞれの製品寿命が異なる一方で、相互の動作保証は製造事業者間で確認されたものに限られるのが現状です。今後は、需要家が、こうした個々の機器を少ない制約のもとで選択できるようになることに加え、DRやVPP事業者を選択する際の選択肢の幅を広げるためにも、こうした分散エネルギー資源の統合化に寄与する標準などのプラットフォーム整備が重要になってくると考えられています。
JUMP Smart mauiプロジェクトを学ぶ子供たち
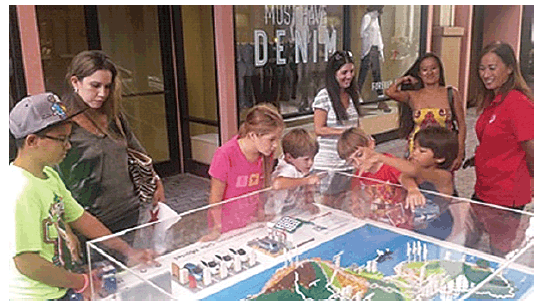
- 出典:
- NEDO