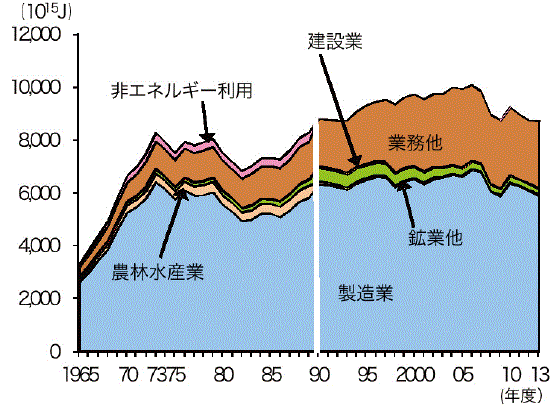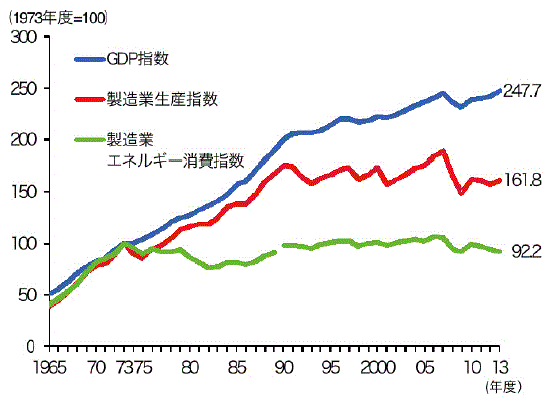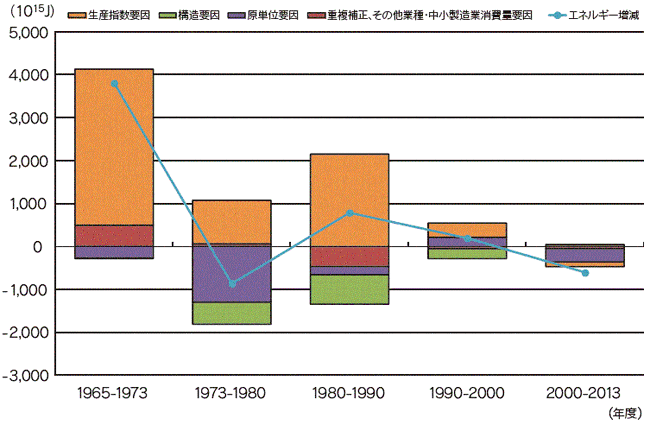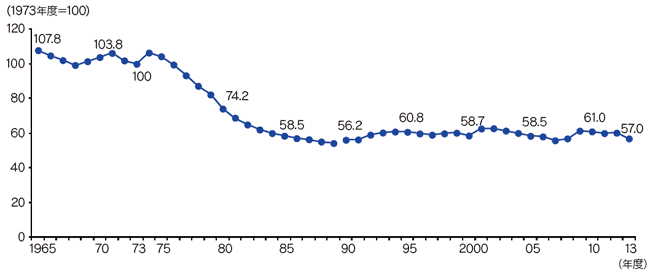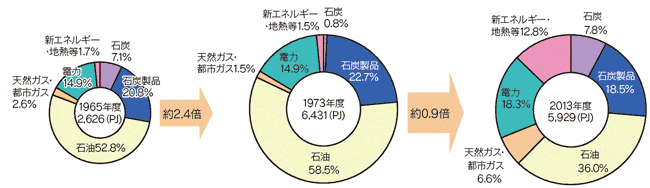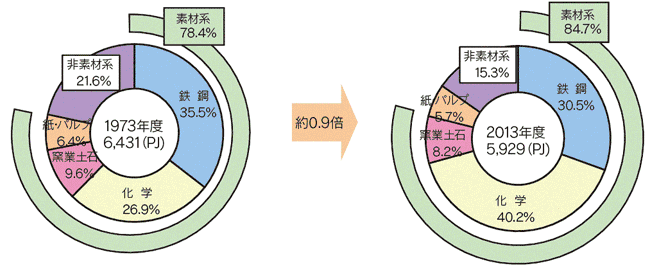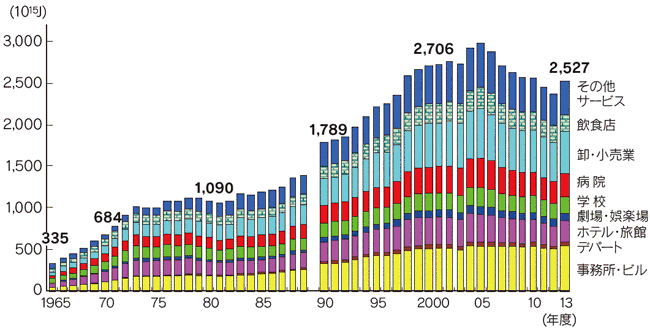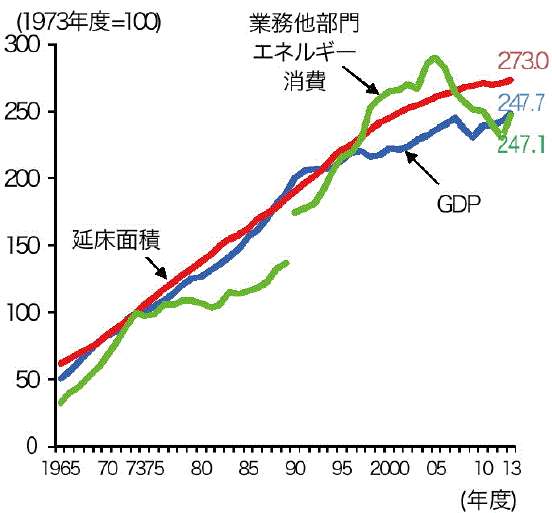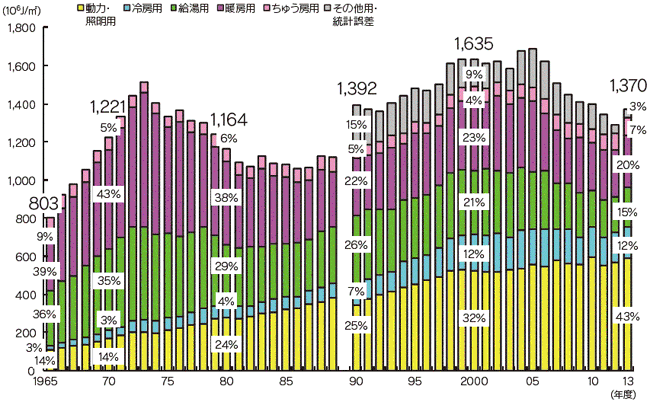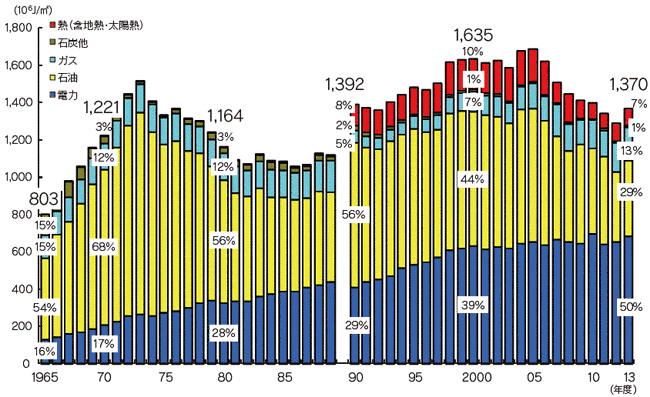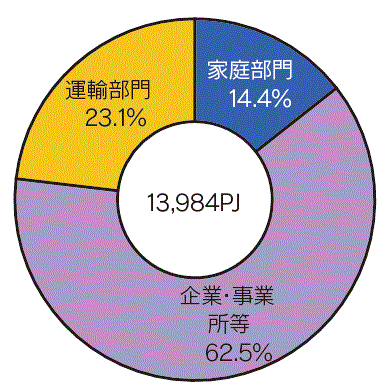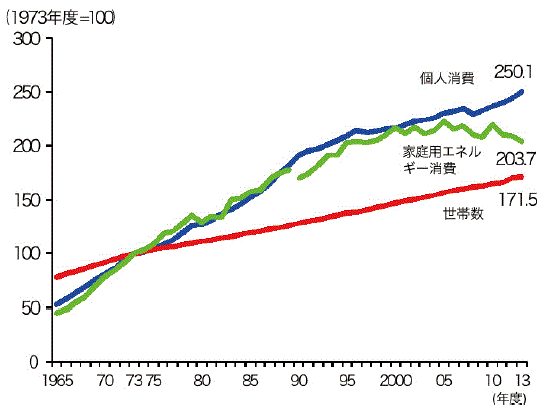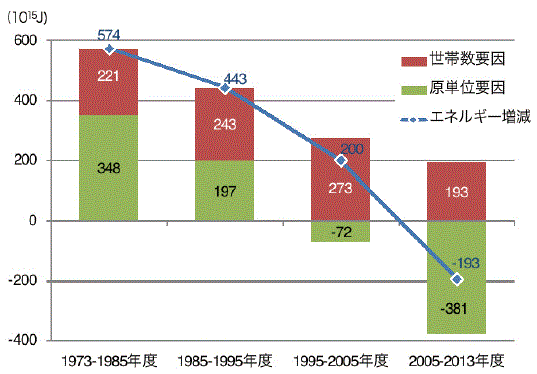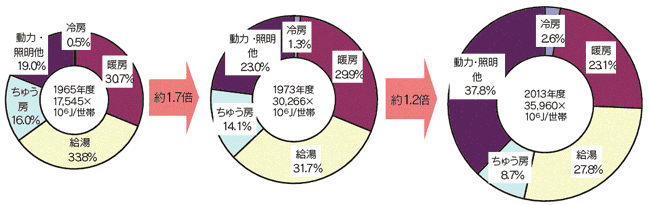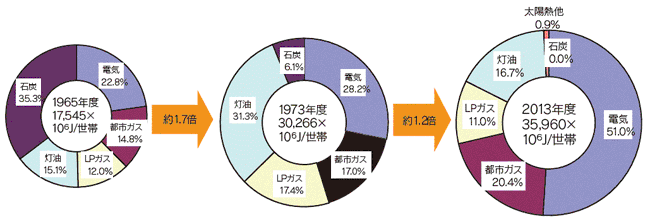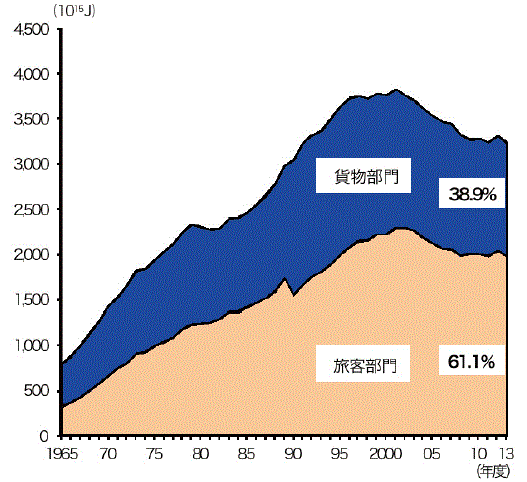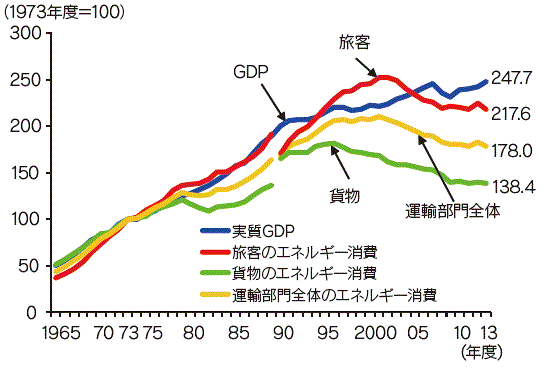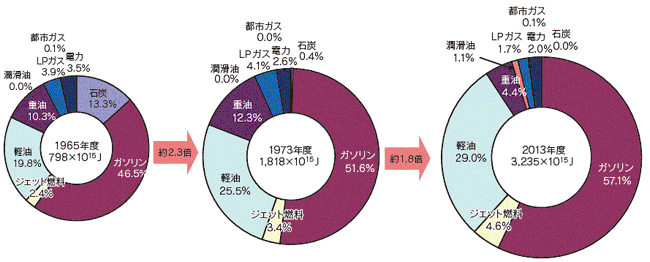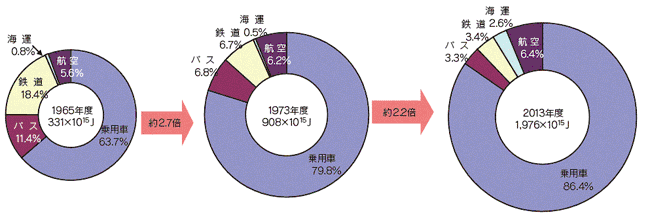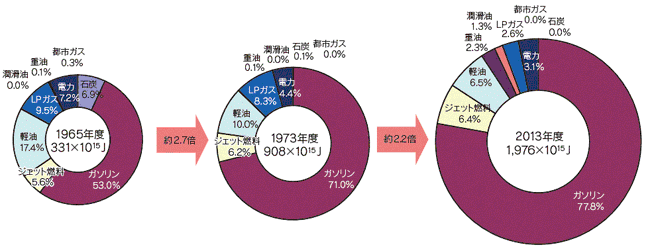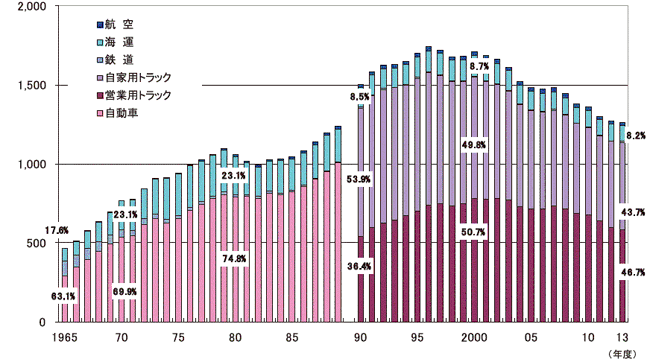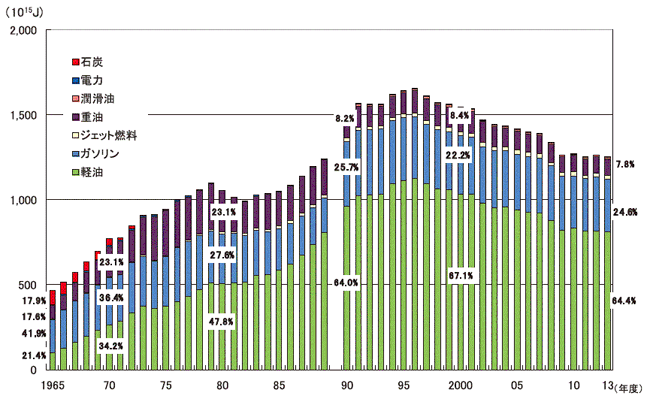第2節 部門別エネルギー消費の動向
1.企業・事業所他部門のエネルギー消費の動向
(1)企業・事業所他部門のエネルギー消費の動向
企業・事業所他部門とは、製造業4、農林水産鉱建設業、業務他(第三次産業)5の合計であり、1965年度から2013年度までの全期間で最終エネルギー消費で最大のシェアを占める部門です。2013年度は企業・事業所他部門が最終エネルギー消費全体の62.5%を占めました。1965年度から2013年度まで企業・事業所他部門の中では製造業が最大のシェアを占め、2013年度には67.9%を製造業が占めました(第212-1-1)。
- (注)
- 「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている6。非エネルギー利用分については、1990年度以降は各業種の消費量の内数となっている。
- (出典)
- 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成
(2)製造業のエネルギー消費の動向
製造業のエネルギー消費は第一次石油ショック前の1965年度から1973年度まで年平均11.8%で増加し、GDPの伸び率を上回りました。その後、1973年の第一次石油ショック以降では減少傾向を示し、1973年度から1983年度までの10年間ではGDPが増加する一方で、エネルギー消費は年平均2.5%減少しました。しかし、1987年度から再び増加に転じ、1995年度には1973年度を上回りました。2008年度以降は世界的な経済の低迷や東日本大震災などが影響して、製造業のエネルギー消費は1973年度の水準を下回っています。2013年度はGDP及び製造業生産指数が前年度から増加しましたが、製造業のエネルギー消費は前年度比で2.4%減少しました。1973年度と2013年度を比較すると、経済規模は2.5倍になり、製造業全体の生産も1.6倍に増加していますが、製造業のエネルギー消費は0.9倍と引き続き1973年度を下回る水準となりました(第212-1-2)。
- (注1)
- 「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。
- (注2)
- 1979年度以前のGDPは日本エネルギー経済研究所推計。1980年度から1993年度の値は内閣府「平成17年基準支出系列簡易遡及」を使用。
- (出典)
- 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、経済産業省「鉱工業指数」、日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」を基に作成
このように石油ショック以降、製造業において生産量が増加した中でエネルギー消費が抑制された主な要因となったのは、省エネルギーの進展(原単位要因)及び素材産業から加工組立型産業へのシフト(構造要因)が考えられます(第212-1-3)。
製造業は、生産コスト低減の観点から、エネルギー効率向上に対する関心が高い業種です。2013年度では生産1単位当たりに必要なエネルギー消費を表す「IIP(鉱工業生産指数)7当たりのエネルギー消費原単位」は1973年度に比べて43.0%縮小するなど、省エネルギーに積極的に取り組みました(第212-1-4)しかしながら、1990年代を見ると、IIP当たりのエネルギー消費原単位に若干の上昇傾向が見られます。これは、日本経済の低迷により設備稼働率が低下したことなどが影響していると考えられます。2000年代半ば以降になると、上昇傾向にあった原単位はほぼ横ばいとなっています。製造業のエネルギー消費は、依然として最終エネルギー消費全体の4割を占めていることからも、引き続き省エネルギー対策が必要とされています。
- (注1)
- 1998年に一次統計の調査対象の見直しが行われたため、1997年度と1998年度の数値に不連続が生じている。
- (注2)
- 「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。
- (注3)
- 生産指数要因は生産指数の変化による要因で、生産指数の増加がエネルギー消費の増加要因となる。構造要因は産業構造の変化による要因で、エネルギー多消費型産業に移る場合はエネルギー消費の増加要因、素材産業から加工組立型産業に移る場合はエネルギー消費の減少要因となる。原単位要因は生産量の単位当たりのエネルギー消費量の変化による要因であり、省エネが進めばエネルギー消費の減少要因となる。
- (出典)
- 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、経済産業省「鉱工業指数」、日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」を基に作成
- (注1)
- 原単位は製造業IIP(付加価値ウェイト)1単位当たりの最終エネルギー消費量で、1973年度を100とした場合の指数である。
- (注2)
- このグラフでは完全に評価されていないが、製造業では廃熱回収などの省エネルギー努力も行われた。
- (注3)
- 「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。
- (出典)
- 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、経済産業省「鉱工業指数」、日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」を基に作成
次に製造業で消費されるエネルギー源を見ると、1973年度の第一次石油ショックまでは石油の消費の伸びが顕著でしたが、その後は素材系産業を中心に石炭などへの燃料転換が進み、石油からの代替が進展しました(第212-1-5)。さらに、第二次石油ショック以降には、都市ガスの消費も増加しています。また、電力消費量は産業構造の高度化や製造工程の自動化などにより、この40年間で13%増加しました。
製造業は素材系産業と非素材(加工組立型)系産業に大別できます。前者の素材系産業とは、鉄鋼、化学、窯業土石(セメントなど)及び紙パルプの素材物資を生産する産業を指し、エネルギーを比較的多く消費する産業です。一方、後者の非素材系産業とは、それ以外の食品煙草、繊維、金属、機械、その他の製造業(プラスチック製造業など)を指しています。エネルギー消費の構成を見ると、素材系産業である前述の4つの業種が製造業全体のエネルギー消費の8割を占めました(第212-1-6)。
- (注1)
- 「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。
- (注2)
- 石油は原油と石油製品の合計を表す。
- (出典)
- 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成
- (注1)
- 「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。
- (注2)
- 化学のエネルギー消費には、ナフサなどの石油化学製品製造用原料を含む。
- (出典)
- 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成
- (注)
- 「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。
- (出典)
- 日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」、資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成
- (注1)
- 「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。
- (注2)
- 1979年度以前のGDPは日本エネルギー経済研究所推計。1980年度から1993年度の値は内閣府「平成17年基準支出系列簡易遡及」を使用。
- (出典)
- 内閣府「国民経済計算」、日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」、資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成
(3)業務他部門のエネルギー消費の動向
業務他部門は、事務所・ビル、デパート、卸小売業、飲食店、学校、ホテル・旅館、病院、劇場・娯楽場、その他サービス(福祉施設など)の9業種に大別されます。これら9業種のエネルギー消費を見ると、1975年度までホテル・旅館のエネルギー消費が最大シェアを占めていましたが、1976年度以降、事務所・ビルが最も大きなシェアを占め、1979年度から卸・小売業のシェアが2位に上がりました。2000年度から2006年度まで、卸・小売業のシェアは一時的に事務所・ビルを抜き、最大となりなしたが、その後また2位に転じました(第212-1-7)。
業務他部門のエネルギー消費量は、「延床面積当たりエネルギー消費原単位×延床面積」で表すことができます。そのエネルギー消費の推移を見ますと、1965年度から1973年度までは、高度経済成長を背景に年率15%増と顕著に伸びましたが、第一次石油ショックを契機とした省エネルギーの進展により、その後しばらくエネルギー消費はほぼ横ばいで推移してきました。しかしながら、1980年代後半からのバブル経済期には再び増加傾向が強まりました。その後は2000年代後半からのエネルギー価格の高騰や2008年の世界金融危機を背景に、業務他部門のエネルギー消費量は減少傾向に転じたが、2013年度には回復の様子が現れました(第212-1-8)。
業務他部門のエネルギー消費を用途別に見た場合、暖房、冷房、給湯、ちゅう房、動力・照明の5用途に分けられます。用途別の延床面積当たりエネルギー消費原単位の推移を見ると、動力・照明用のエネルギー消費原単位は、OA化などを反映して高い伸びを示しました。その結果、動力・照明用の業務他部門のエネルギー消費全体に占める割合は、2013年度では43%に達しました。一方、冷房用のエネルギー消費原単位は、第一次石油ショックまでは年率15%を超える勢いで伸びていましたが、それ以降は省エネルギーの進展や、空調機器導入が一巡したことなどから増加は鈍化したものの、2013年度の割合は12%となりました。また、暖房用のエネルギー消費原単位は、ビルの断熱対策が進んだことや「ウォームビズ」に代表される様々な省エネルギー対策が進展したことなどから減少傾向で推移し、2005年度から2013年度の8年間で年平均3.9%の減少を示しました(第212-1-9)。
また、業務他部門のエネルギー源では、電力の割合が増加傾向にあります。ガスを使って発電すると同時に、排熱を給湯や空調に利用するガスコージェネレーションシステムなどの普及拡大に伴いガスも増加傾向になりました。一方、主として暖房用に利用される石油は減少傾向になりました(第212-1-10)。
業務他部門における省エネルギーを実現するためには、建物の断熱強化や冷暖房効率の向上、照明などの機器の効率化を行うとともに、更なるエネルギー管理の徹底が必要であるといえます。
- (注)
- 「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。
- (出典)
- 日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」、資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成
- (注)
- 「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。ガスは天然ガス、都市ガス、LPGの合計である。
- (出典)
- 日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」、資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成
2.家庭部門のエネルギー消費の動向
家庭部門は、自家用自動車などの運輸関係を除く家庭でのエネルギー消費8を対象とし、2013年度の最終エネルギー消費全体に占める家庭部門の比率は14.4%となります。(第212-2-1)。
- (注)
- 構成比は端数処理(四捨五入)の関係で合計が100%とならないことがある。
- (出典)
- 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成
- (注)
- 1979年度以前の個人消費は日本エネルギー経済研究所推計。「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。
- (出典)
- 内閣府「国民経済計算」、日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」、資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、総務省「住民基本台帳」を基に作成
- (注)
- 「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。
- (出典)
- 内閣府「国民経済計算」、日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」、資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、総務省「住民基本台帳」を基に作成
家庭部門のエネルギー消費は、生活の利便性・快適性を追求する国民のライフスタイルの変化、世帯数増加などの社会構造変化の影響を受け、個人消費の伸びとともに、著しく増加しました。第一次石油ショックのあった1973年度の家庭部門のエネルギー消費量を100とすると、2000年度には216.9まで拡大しました。その後省エネルギー技術の普及と国民の環境保護意識の高揚に従って家庭部門のエネルギー消費量は、2005年度以外は時系列的に低下傾向となり、2013年度には203.7まで低下しました(第212-2-2)。
家庭部門のエネルギー消費量は、「世帯当たり消費量×世帯数」で表すことができます。したがって、世帯当たり消費量の増減(原単位要因)及び世帯数の増減(世帯数要因)が、家庭部門のエネルギー消費の増減に影響を与えます。世帯当たりの消費量は、エネルギー消費機器の保有状況・効率、所得、エネルギー価格、世帯人員、省エネルギー行動などに左右されるほか、短期的には気温変動の影響も大きく受けます。1973年度から2005年度までのエネルギー消費増減の合計は1,217×1015Jであり、そのうち世帯数要因によるものは737×1015J、原単位要因は474×1015J(残りは交絡項)となり、世帯数の増加と家電製品などの普及による世帯当たり消費量が共に増加に寄与していました。一方、2005年度から2013年度の間はエネルギー消費増減の合計は-193×1015Jであり、そのうち世帯数要因によるものは193×1015J、原単位要因は-381×1015Jでした。省エネ技術の普及や世帯人員の減少などに加え震災後には省エネルギーへの取込の強化が、増加し続ける世帯数の増加寄与を上回り、家庭のエネルギー消費量を抑えたことが分かります(第212-2-3)。
用途別に見ますと、家庭用エネルギー消費は、冷房、暖房、給湯、ちゅう房、動力・照明他(家電機器の使用等)の5用途に分類することができます。
1965年度におけるシェアは、給湯(33.8%)、暖房(30.7%)、動力・照明他(19.0%)、ちゅう房(16.0%)、冷房(0.5%)の順でしたが、家電機器の普及・大型化・多様化や生活様式の変化などに伴い、動力・照明他用のシェアが増加しました。またエアコンの普及などにより冷房用が増加し、相対的に暖房用・ちゅう房用・給湯用が減少しました。この結果、2013年度におけるシェアは動力・照明他(37.8%)、給湯(27.8%)、暖房(23.1%)、ちゅう房(8.7%)、冷房(2.6%)の順となりました(第212-2-4)。
我が国の高度経済成長が始まったとされる1965年度頃までは家庭部門のエネルギー消費の3分の1以上を石炭が占めていましたが、その後主に灯油に代替され、1973年度には石炭はわずか6%程度になりました。この時点では、灯油、電力、ガス(都市ガス及びLPガス)がそれぞれ約3分の1のシェアでしたが、その後の新たな家電製品の普及、大型化・多機能化などによって電気のシェアは大幅に増加しました。また、オール電化住宅の普及拡大もあり、2009年度には電気のシェアは50%を超え、2013年度には51.0%となりました(第212-2-5)。
なお、家庭において電力を多く消費しているのはエアコンなどの空調機器で、冷蔵庫や洗濯機などを動かすための動力や照明器具、テレビなどの電力消費も増加しました。2012年度の調査によると家庭における世帯当たり待機時消費電力量9は、家庭の世帯当たり全消費電力の5.1%を占めました10。
- (注1)
- 「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。
- (注2)
- 構成比は端数処理(四捨五入)の関係で合計が100%とならないことがある。
- (出典)
- 日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」、資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、総務省「住民基本台帳」を基に作成
- (注)
- 構成比は端数処理(四捨五入)の関係で合計が100%とならないことがある。
- (出典)
- 日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」、資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、総務省「住民基本台帳」を基に作成
3.運輸部門のエネルギー消費の動向
(1)運輸部門のエネルギー消費の動向
運輸部門は、乗用車やバスなどの旅客部門と、陸運や海運、航空貨物などの貨物部門に大別されます。2013年度、運輸部門は、エネルギー最終消費全体の23.1%を占めており、このうち、旅客部門のエネルギー消費量が運輸部門全体の61.1%、貨物部門が38.9%を占めました(第212-3-1)。
- (注)
- 「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。
- (出典)
- 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成
- (注1)
- 「総合エネルギー統計」は、1990年度以降の数値について算出方法が変更されている。GDPは2005年基準。
- (注2)
- 1979年度以前のGDPは日本エネルギー経済研究所推計。1980年度から1993年度の値は内閣府「平成17年基準支出系列簡易遡及」を使用。
- (出典)
- 内閣府「国民経済計算」、資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成
旅客部門のエネルギー消費量は、GDPの伸び率を上回る伸びで増加してきましたが、2001年度をピークに下降傾向に転じました。また、旅客部門のエネルギー消費量の伸びは、貨物部門を上回って推移しました(第212-3-2)。
1965年度における運輸部門のエネルギー消費量は約800×1015J(最終エネルギー消費全体の18%)であり、その構成は、旅客部門が41.5%、貨物部門が58.5 % でした。1965年度から1973年度の8年間にエネルギー消費量は運輸部門全体で2.3倍(年率10.8%増)となり、二度の石油ショックを経て伸び率は鈍化したものの、1973年度から2013年度の40年間で更に1.8倍(年率1.5%増)に拡大しました。2013年度のエネルギー消費は1965年度から48年間で見ると4.1倍、年率3.0%の増加となりました。このうち旅客部門は6.0倍(年率3.8%増)、貨物部門は2.7倍(年率2.1%増)と、旅客部門は貨物部門の増加を上回る勢いで増加しており、1974年度にそのシェアは逆転しました。2013年度の運輸部門におけるエネルギー源別の構成比を見ますと、ガソリン、軽油、LPガス、潤滑油などの石油系エネルギーが97.9%を占め、電力のシェアは2.0%になりました(第212-3-3)。
- (注)
- 「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。
- (出典)
- 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成
(2)旅客部門のエネルギー消費の動向
旅客部門のエネルギー消費は1965年度から1973年度まで年平均伸び率で13.4%の伸びを示し、2.7倍に増加しましたが、1973年度以降は伸び率が2.0%に鈍化しました。その結果、2013年度のエネルギー消費は1965年度比で6.0倍となりました。その内訳を見ますと、乗用車は、保有台数の増加などにより、1965年度から2013年度まで年平均4.5%増と旅客部門全体の伸び率3.8%を上回る増加を示しました。また、旅客部門全体のエネルギー消費量に占める乗用車の割合は、1965年度の63.7%から2013年度では86.4%へと上昇しました。逆に、同期間のエネルギー消費量に占める公共交通機関の割合は、バスが11.4%から3.3%へ、鉄道が18.4%から3.4%へとそれぞれ低下しました(第212-3-4)。
旅客部門におけるエネルギー源別の構成比の変化を見ますと、主として乗用車に使われるガソリンの割合が1965年度の53.0%から2013年度では77.8%に上昇した一方、主として鉄道に使われる電力の割合は1965年度の7.2%から2013年度には3.1%に低下しました(第212-3-5)。
- (注1)
- 2013年度は、グラフに示していない輸送機関内訳推計誤差が存在するため、構成比の合計は100%にならない。
- (注2)
- 「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。
- (出典)
- 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」を基に作成
- (注)
- 「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。
- (出典)
- 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成
(3)貨物部門のエネルギー消費の動向
貨物部門のエネルギー消費量は、第二次石油ショック後の1980年度から1982年度、バブル経済崩壊後の1992年度に前年度実績を割り込むことがあったものの基本的に拡大し続け、1996年度にピークに達しました。それ以降は、減少に転じ、2013年度にはピーク期に比べて24%縮小しました。貨物部門は経済情勢、価格の変動、産業構造の変化及び省エネルギー技術の普及などに影響されやすく、そのエネルギー消費量は旅客部門に比べ、伸びが穏やかですが、より早い時期に減少局面に転じ、その減少幅がより大きいのが特徴でした。貨物部門のエネルギー消費の内訳を見ますと、そのほとんどが自動車で占められていました。特に、自家用トラックのエネルギー消費は大きく、後で述べる輸送量と比較すると、大量のエネルギーを消費したことが分かります。ただし、自家用トラックは1993年度より、営業用トラックは2003年度以降エネルギー消費が共に減少しています。
船舶のエネルギー消費は、高度経済成長期を通じて増加したものの、1980年度から減少に転じました。そして、1990年代ではほぼ横ばいか、やや増加傾向にありましたが、2002年度から再び減少傾向に転じました。航空のエネルギー消費量は、輸送能力の増大や輸送コストの低廉化などによって1990年代半ばまで急速に伸びましたが、その後、経済の停滞とともに伸び悩みました。鉄道のエネルギー消費は、1987年度まで急速に縮小しましたが、その後ほぼ横ばいで推移しました(第212-3-6)。
2013年度の貨物輸送のエネルギー源は64.4%が主として大型トラックで消費される軽油、24.6%が主として配送用の小型貨物車で消費されるガソリン、残りが主として船舶に使われる重油や航空用のジェット燃料などとなっていました(第212-3-7)。
- (注1)
- 輸送機関内訳推計誤差を除く。
- (注2)
- 「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。また、それまで1つであった自動車によるエネルギー消費量は1990年度以降、自家用トラックによるものと営業用トラックによるものの2つに区分されている。
- (注3)
- 自家用トラックとは事業者が自社の貨物を輸送する目的で保有するもの、営業用トラックとは事業者などから依頼された貨物を輸送する目的で保有するものをいう。
- (出典)
- 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成
- (注)
- 「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。
- (出典)
- 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成
- 4
- 石炭・石油産業などのエネルギー産業は転換部門に含まれます。
- 5
- ここでの第三次産業は運輸関係事業、エネルギー転換事業を除きます。
- 6
- 旧総合エネルギー統計は、「エネルギー生産・需給統計」を中心に販売側の統計に基づいた算出が行われていましたが、政府統計の整理合理化対策の一環として石炭・石油製品の販売統計調査が2000年を最後に廃止されたことなどから、継続して作成することができなくなりました。このようなことから、新しい総合エネルギー統計では、石油等消費動態統計・家計調査報告や自動車燃料消費調査などの消費側の各種統計調査を中心とする算出方法に変更されています。
- 7
- IIP(鉱工業生産指数:Indices of Industrial Production)は、鉱工業全体の生産水準の動きを示す代表的な指数であり、ある時点への鉱業・製造業の生産量について、基準年の生産量と付加価値額を基準に指数化したものです。
- 8
- 家庭でのエネルギー消費の用途には冷房、暖房、給油、ちゅう房、動力・照明などがあります。
- 9
- 待機消費電力とは、リモコンやマイコンなどを組み込んだ家電機器が、その機器を使っていないときでもコンセントにつながっていることで消費される電力のことをいいます。
- 10
- 資源エネルギー庁省エネルギー対策課「平成24年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業(待機時消費電力調査)報告書概要」によると、全体の消費量4,432kWh /年のうち228kWh /年が待機電力であり、電力消費の5.1%を占めています。